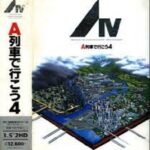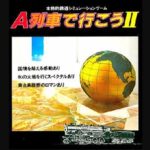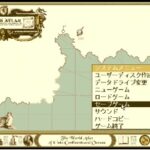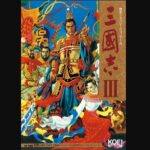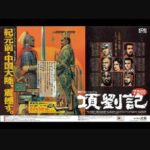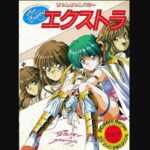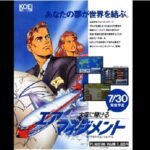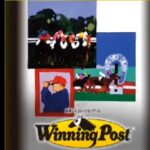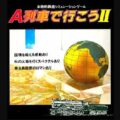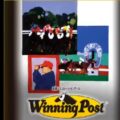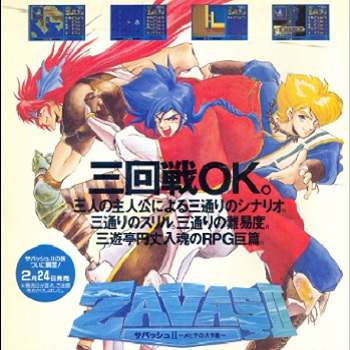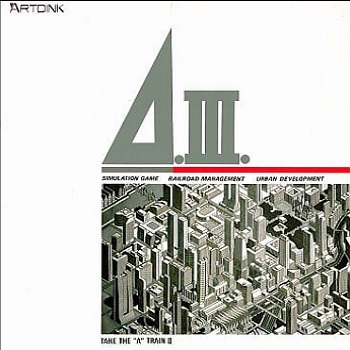
ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 インテル Core i5-13450HX メモリ 32GB SSD 512GB 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Blu..
【発売】:アートディンク
【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS、X68000、Windows
【発売日】:1990年12月
【ジャンル】:シミュレーションゲーム
■ 概要
● シリーズの転換点となった第三作
1990年12月、アートディンクが送り出した『A列車で行こうIII』は、同社が手掛ける都市構築型経営シミュレーションシリーズの中で、極めて重要な分岐点となった作品である。対応機種はPC-9801、FM TOWNS、X68000をはじめ、後年にはWindows95/98対応版も登場。発売当初は国産パソコン市場におけるシミュレーションゲームの可能性を大きく押し広げたタイトルとして話題を呼んだ。
本作は、単に線路を敷いて列車を走らせるという枠を越え、「都市経営」というテーマを中心に据えた点が革新的であった。プレイヤーは一鉄道会社の経営者として、列車の運行だけでなく都市開発や子会社の経営にまで踏み込み、街そのものの発展を見守るという、まさに“経済シミュレーション”の醍醐味を体現する内容になっている。
● 前作までとの決定的な違い
前作『A列車で行こうII』までは、どちらかといえばパズル的な要素が強く、目的地まで効率的に線路をつなぐことが主目的だった。しかし『III』では、その発想を根本から改め、列車運行を軸に「街を育て、企業を拡大する」という長期的視点のゲームシステムに変化した。 この転換により、プレイヤーの役割は単なる線路設計者から、一企業の総帥へと昇華している。
街の発展は鉄道網の整備状況や人口動態、子会社の経営状況など、多くの要因が複雑に絡み合って進行する。そのため短期的な利益追求ではなく、10年、20年といった長いスパンでの戦略が必要になった。この構造は後に『A列車で行こうIV』以降のシリーズにも受け継がれ、現在に至る「A列車」シリーズの基本設計がこの第3作で確立されたといえる。
● 視点の進化とビジュアル表現
『A列車で行こうIII』でまず目を引くのは、シリーズで初めて導入された“クォータービュー”の斜め見下ろし型マップである。これにより、従来のトップビュー(真上視点)では表現できなかった立体感と奥行きが生まれ、プレイヤーはまるで模型都市を眺めているような感覚を味わうことができた。
当時のPC-9801やFM TOWNSといったハードウェア性能を最大限に活かしたグラフィック表現は、当時のプレイヤーに強い印象を残した。列車が街を抜け、駅に停まり、夜には街灯が灯る——この“ミニチュア都市の時間の流れ”を感じられる演出は、1990年当時としては非常に先進的であった。
都市の成長に応じて高層ビルやホテルが立ち並び、郊外には住宅地や工場が広がる。すべてが鉄道ネットワークと連動して動的に変化していくことで、画面全体に「都市の呼吸」が宿るような臨場感を演出している。
● インターフェースの革新
もうひとつ特筆すべきは、マルチウィンドウ型のインターフェースの採用である。当時のMS-DOS系ゲームでは、メニュー画面を切り替える方式が一般的だったが、本作では複数のウィンドウを同時に開き、財務情報や列車運行状況、子会社経営などを並行して管理できた。
このUI設計は、後のWindows時代を先取りしたような直感的操作を可能にしており、ユーザーにとっても「経営者のデスクで複数の資料を見比べながら意思決定する」というリアルな没入感をもたらしている。
鉄道運行のスケジュール設定、子会社の建設、株式の運用といった操作をスムーズに行えるこの仕組みは、今なお“完成度の高いインターフェース”として評価され続けている。
● 経営システムの深化
『A列車で行こうIII』の最大の魅力は、鉄道事業だけでなく、多様な子会社経営を通じて収益構造を多角化できる点にある。 プレイヤーは鉄道会社を中心に、沿線開発を促進するための不動産事業や観光業にも進出できる。駅前にホテルを建てれば観光客が増え、商業施設を設ければ乗客が増加し、結果的に鉄道の収益も向上する。こうした“相乗効果”の連鎖を戦略的に構築することが、本作の醍醐味といえる。
また、経営が悪化すれば赤字転落もあり得る。資金繰りや株価の変動、景気の循環などがリアルタイムで反映されるため、経済的センスが求められる難易度の高い設計となっている。まさに「都市の成長と企業の経営が一体化した経済シミュレーション」としての完成度を誇る作品である。
● 多様化する列車の種類
初期シリーズでは、客車列車・貨物列車・A列車・大統領専用列車といった限定的なラインナップしか存在しなかったが、『III』以降は実在する多様な車両がゲーム内に登場するようになった。これにより、プレイヤーは列車の特性に応じてダイヤを組み、輸送効率や旅客需要に合わせた柔軟な経営戦略を立てられるようになった。
特急・通勤・観光列車など、運用目的の異なる車両が存在することで、ゲーム内の鉄道経営はより現実味を帯びたものとなり、プレイヤーは“鉄道の面白さ”と“経済のロジック”を同時に味わえるようになった。
● 派生版と移植展開
FM TOWNS版には『A.III マップコンストラクション』という地形編集ツールが同梱されており、プレイヤーが自由に地形を作り替えて独自の都市を設計できる仕様となっていた。 また、同年にはスーパーファミコン向けに『A列車で行こうIII スーパーバージョン(A3SV)』が登場。より家庭向けにアレンジされた内容で、グラフィックや操作系統が再構成されていた点も興味深い。
その後、2000年にはWindows対応版が発売され、2014年にはPC-9801版がプロジェクトEGGで配信、2020年にはPCエンジン版が同サービスで配信されるなど、長期にわたって愛されるタイトルとなっている。
● シリーズ史における意義
『A列車で行こうIII』は、単なる“続編”ではなく、シリーズの“新章”を開いた作品である。鉄道を都市経済の中心に据えたデザイン思想は、以後の『A列車で行こうIV』や『A列車で行こう7』などにも受け継がれ、都市開発シミュレーションというジャンルそのものの方向性を決定づけた。
本作が提示した「経営×都市構築×鉄道」の三位一体構造は、シミュレーションゲームの歴史の中でも極めて独自性が高く、今日に至るまで国内外のクリエイターに影響を与え続けている。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● 自分の都市を創り上げる“経営者体験”
『A列車で行こうIII』最大の魅力は、プレイヤー自身が都市経済の舵を取る“経営者”としての体験にある。線路を敷き、列車を走らせるだけでは終わらない。そこから派生する人の流れ、街の発展、産業の拡大、そして企業の収益構造の変化までもがプレイヤーの判断次第で姿を変えていく。
ゲーム開始時に静かだった田園風景が、数十年の経営を経るうちに高層ビルが立ち並ぶ大都市へと変貌していく様子は、単なるシミュレーションを超えて“創造の快感”そのものだ。自分の描いた都市像が、列車の音とともに現実化していく瞬間——この感覚こそが『A列車で行こうIII』の核心的な面白さといえる。
● 鉄道と都市のシナジーを体感
都市の発展が鉄道の発展を支え、鉄道の拡充が再び都市を拡大させる。この相互作用の循環が見事にゲーム内で表現されている。 駅を新設すればその周辺に人が集まり、住宅や商業施設が次々に建設される。新たな需要が生まれれば列車の増便が必要となり、それに伴ってさらなる開発が進む。
この「鉄道網=都市の血管」という設計思想が、ゲーム全体を貫く美しい構造となっている。プレイヤーはまるで都市の鼓動を操る神経のように、路線を敷くたびに街の命が脈打つ感覚を味わうことができるのだ。
● “経済シミュレーション”としての完成度
単なる鉄道ゲームでは終わらないのが『A列車で行こうIII』の真骨頂だ。 会社の財務状況は常に変動し、投資・建設・運行コストのバランスを見極めることが求められる。 景気の波や人口の推移など、マクロ経済的な要素もプレイヤーの経営に影響を与えるため、短絡的な戦略では長期的な成功を収めることはできない。
こうした“リアルな経済の動き”を取り入れた設計は、当時としては非常に斬新で、鉄道を中心に据えた都市経済モデルをゲームの中で体験できる貴重な存在となった。まさに「遊びながら経済を学べる」知的エンターテインメントといえる。
● クォータービューが生み出す没入感
斜め見下ろしのクォータービューによって、プレイヤーは自らの手で築いた都市をまるで模型のように鑑賞できる。 列車が住宅街を抜けて山間部を走り抜け、夕暮れには街の灯りがともる。 その光と影の変化が時間経過によって繊細に描かれることで、まるで実在する都市を眺めているような没入感を味わえる。
当時のハード性能を超えたグラフィックの美しさは多くのプレイヤーを驚かせた。とくにFM TOWNS版ではサウンド面の強化もあり、BGMや環境音がプレイヤーの感情を引き込み、都市の“息づかい”をよりリアルに感じさせてくれた。
● ユーザーインターフェースの快適さ
経営シミュレーションは複雑なデータを扱うため、操作性が悪いとストレスになりがちだ。しかし『A列車で行こうIII』のUIは非常に洗練されており、複数のウィンドウを並べながら直感的に操作できる。
マップウィンドウで鉄道網を確認しつつ、財務ウィンドウで経営状況をモニタリング、同時にダイヤ設定ウィンドウで列車のスケジュールを調整する——まさに経営デスクに座る社長のような気分だ。
こうした操作感の快適さが、シリーズ初の長時間プレイでも飽きさせないリズムを作り出している。
● 音楽と時間の流れの演出
BGMもまた、このゲームの魅力を語る上で欠かせない。 静かな朝の音楽、賑やかな昼の旋律、そして夜に響く落ち着いたメロディ——時間の経過とともに変化する音楽が、都市の一日のリズムを感じさせてくれる。
プレイヤーは鉄道会社の経営者でありながら、同時に“街の住人”でもあるような感覚を味わえる。音と景観の融合によって、ただの数値シミュレーションではなく、ひとつの“生きる街”を見守る感動がそこにある。
● 豊富なプレイスタイル
本作の優れている点は、明確な「クリア条件」を強制しない自由度にある。 利益重視で最短経路を構築するもよし、芸術的に美しい都市を目指すもよし、山岳鉄道や海岸線を活かした観光路線を作るのも面白い。
プレイヤーによって街の姿がまったく異なるため、何度プレイしても新しい発見がある。
「最適解がない」という設計が、本作を長く遊ばせる最大の理由となっている。
● 子会社経営の戦略性
鉄道だけでなく、沿線開発を推進するための子会社経営が戦略性をさらに深める。 商業ビル、ホテル、工場などを建設して収益源を多様化することで、鉄道事業が一時的に赤字になっても会社を支える仕組みができる。
どのタイミングでどの子会社に投資するかという判断が、プレイヤーのセンスを試す。
これにより、鉄道を“都市経済の核”とするプレイスタイルだけでなく、グループ企業全体で街を支配する“総合企業型”経営の楽しさも味わえる。
● 都市発展を眺める長期的満足感
このゲームの面白さは、短時間で結果を求めるタイプのシミュレーションとは異なり、じっくり腰を据えてプレイすることで得られる“成熟の快感”にある。 最初は単線の小さな鉄道会社でも、数十年後には複数路線を持つ大企業へと成長し、都市は光の海となる。
そうした変化を何十時間もかけて見届ける体験は、他のどんなゲームにもない“自分だけの都市史”を作る喜びだ。
プレイヤーの一手一手が都市の未来を形づくる——その手応えこそが、『A列車で行こうIII』の最大の魅力である。
■ ゲームの攻略など
● 序盤攻略:まずは安定した路線作りから
『A列車で行こうIII』の序盤は、限られた資金の中で効率よく利益を上げるための計画性がカギとなる。最初に行うべきは、都市中心部と郊外を結ぶ短距離の路線を構築し、需要の高い区間で確実な運行収益を確保することだ。 いきなり長距離路線を敷設したり、複雑なダイヤを組むのは資金を圧迫するリスクが高い。まずは1~2駅間で確実に黒字を出せるシンプルな往復運転を行い、資金を貯めることが鉄則である。
加えて、駅周辺の土地価格や発展傾向を観察することも重要だ。住宅地の近くに駅を設けると人口増加が見込め、結果的に乗客数が増える。最初の一手が、その後の都市発展を大きく左右する点を常に意識しよう。
● 中盤攻略:都市開発と子会社経営の両立
資金が安定してきたら、次のステップは“沿線開発”と“子会社経営”のバランスだ。駅周辺の土地を買収して商業施設やホテルを建てると、旅客需要が増加し、鉄道利用率が向上する。 また、工場などの産業施設を郊外に設置することで、通勤・輸送の動きが生まれる。この需要循環が軌道に乗ると、都市全体の人口が自然と増えていく。
ただし、子会社を建てすぎると維持費がかさみ、鉄道事業の利益を圧迫することがある。収益性の高い施設を優先し、定期的に損益を確認して赤字企業は整理するなど、企業グループとしての健全な財務体制を意識しよう。
● 資金運用:借入と返済のバランス感覚
このゲームでは金融機関からの借入も可能だが、金利が高く設定されているため、安易な借金は破綻のもと。とはいえ、適切なタイミングでの借入は都市発展を加速させる強力な手段にもなる。 攻略のコツは、「投資のリターンが明確に見える案件にだけ借入を行う」こと。たとえば、既存路線に新駅を増設し、その周辺に商業ビルを建設するなど、利益が回収できる確信がある場合に限って活用すると良い。
資金繰りが安定している時期は積極的に借金を返済し、余剰資金を株式投資や新路線開発に回す。鉄道会社としての信用度を高めることが、後の大型プロジェクトの成功へとつながっていく。
● ダイヤ設定:運行効率を最大化する鍵
列車ダイヤの設定は、『A列車で行こうIII』の中でも特に戦略性が高い要素のひとつだ。 運行間隔を狭めすぎると過剰投資となり、逆に広げすぎると乗客が減少して収益が落ちる。最適なダイヤを組むには、駅の利用者数を観察し、時間帯によって列車本数を変える柔軟さが求められる。
また、貨物列車の運行にも注目したい。工場地帯や港湾エリアと都市部を結ぶ貨物ルートを構築することで、乗客需要が少ない時間帯にも安定収益を得られる。旅客と貨物のバランスをとった運行計画が、持続的な黒字経営への近道となる。
● 都市計画:地形と発展方向を見極める
マップは単なる背景ではなく、地形そのものが攻略の一部だ。 山岳地帯を貫くトンネル建設や、河川に橋をかけるなど、地形をどう活かすかによって鉄道運行の効率や開発コストが大きく変わる。 さらに、都市発展は地形の制約に影響を受けるため、山を背にした街では工場を設置しやすく、海沿いの街では観光地開発が有利になるなど、立地戦略を意識することが求められる。
プレイヤーは地形を“敵”ではなく“資源”と見なし、地形の個性を活かした都市設計を行うと良い。これは単なる攻略テクニックではなく、『A列車で行こうIII』が持つ“都市を読む力”を試す知的要素のひとつでもある。
● 経済循環を意識した発展戦略
本作では、鉄道の発展が都市の経済活動を刺激し、その経済活動が再び鉄道の需要を生むという循環構造が設計されている。 したがって、攻略の基本方針は「輸送と経済の両立」に尽きる。輸送効率を上げるだけでなく、乗客が集まる場所=消費が発生する場所を設計することが肝心だ。 駅周辺に住宅地と商業地を共存させ、昼夜を問わず人の流れが途絶えない都市構造を作ることで、自然と鉄道収益も安定する。
こうした“都市経済の呼吸”を読む感覚が身につけば、『A列車で行こうIII』の攻略は一段階上の深みを帯びてくる。
● 景気変動とリスクマネジメント
シリーズの中でも『III』は経済変動の影響が大きい。好景気の時期には投資を拡大し、景気が悪化すると収益が減少するため、過剰投資を控える必要がある。 そのため、攻略の鍵は「好況時に備えて資金を蓄え、不況時に備える」こと。短期的な利益よりも長期的な安定経営を重視しよう。
また、複数路線を持つ場合は、それぞれの採算性を定期的に確認すること。赤字路線を放置すると全体の収益を圧迫するため、場合によっては路線廃止や縮小も決断しなければならない。経営者としての“勇気ある撤退”も攻略の一部だ。
● マップコンストラクションの活用
FM TOWNS版などに同梱された『マップコンストラクション』は、攻略において非常に有用なツールである。 このモードを使えば、自分だけの地形を設計し、鉄道路線を最適化した仮想都市を事前にシミュレーションすることができる。 たとえば、山脈の位置を変えて都市間を短縮したり、川の流れを調整して港湾地区を発展させるなど、実験的な都市デザインを通じて“理想の攻略マップ”を構築できる。
この自由度の高さが、プレイヤーの創造力をさらに刺激し、単なるゲーム攻略を超えた“都市づくりの研究”を楽しめる要素となっている。
● 長期プレイにおける成功の秘訣
『A列車で行こうIII』は短時間で完結しない。むしろ何十年にも及ぶ都市経営を通じて、持続的な発展を実現するゲームである。 攻略の本質は、「早く成長する都市」ではなく「ゆっくりと強く育つ都市」を目指すこと。安定した輸送網、無理のない財務管理、そしてバランスの取れた地域開発が、最終的に巨大な成功を生む。
途中で停滞しても焦らず、都市の動向を分析しながら戦略を調整する冷静さが重要だ。まさに、経営者の視点と都市計画者の目を併せ持つことが、このゲームを制する最大の鍵なのである。
■■■■ 感想や評判
● 発売当時のプレイヤーの驚きと感動
1990年当時、『A列車で行こうIII』が発売された際、多くのプレイヤーはその圧倒的な進化に衝撃を受けた。前作からの変化は単なるバージョンアップではなく、“別次元の体験”と評されたほどである。 鉄道を中心とした都市経営シミュレーションという概念は当時まだ珍しく、ゲーム雑誌のレビューでも「まるで本当に街が呼吸しているようだ」「鉄道会社を動かす喜びを初めて体験した」といった感想が多数寄せられた。
また、シリーズ初のクォータービュー表現による美しい街並みや、時間の経過とともに変化する風景は、当時のパソコンユーザーにとってまさに新時代のグラフィック体験であった。プレイヤーたちは、画面上で刻々と発展していく都市の姿に見入り、自らの手で作り上げた街が“生きている”と感じたと語っている。
● 難易度の高さと“経営の奥深さ”に対する賛辞
本作はシミュレーションゲームの中でも特に難易度が高く、安易なプレイでは赤字経営に陥る。だが、そこにこそプレイヤーたちは魅力を感じた。 「数字と地形の裏に、確かに街の命がある」と多くのファンが述べており、利益を上げるための試行錯誤が、ゲームを進めるモチベーションとなっていた。
失敗しては再挑戦し、より効率的な鉄道網や収益構造を探る過程は、ビジネスシミュレーションとしてのリアルさを際立たせていた。単なる遊びではなく“学び”の要素を含むゲームであったため、当時の社会人プレイヤーや経済学を学ぶ学生にも高く評価された。
● 雑誌・メディアによる評価
『ログイン』『コンプティーク』『ベーマガ』といった当時のPCゲーム誌では、『A列車で行こうIII』は常に高得点を記録していた。 特に評価されたのは「都市の時間変化の美しさ」と「鉄道運行システムの完成度」であり、シミュレーションゲーム部門の年間ベストにも選出されている。
また、専門誌のコラムでは「日本的都市開発の美学を最もリアルに描いた作品」として紹介され、同時期に発売された海外製の経営シムと比較しても完成度の高さが際立っていた。アートディンクという開発会社の独自の哲学が評価され、以後“都市と鉄道の融合を描くスタジオ”として確固たるブランドを築くきっかけとなった。
● 長期プレイで生まれる愛着と没入感
プレイヤーの多くが共通して挙げる魅力は、“長く遊ぶほどに愛着が湧く”点である。 序盤こそ資金繰りに苦労するが、やがて街が発展し、自らの設計した路線網に列車が走る光景を見ると、達成感とともに深い没入感が得られる。 SNSや掲示板がなかった時代にも、プレイヤー同士がハガキ投稿や雑誌の読者コーナーで「自分の都市の発展記録」を語り合うなど、コミュニティ的な盛り上がりを見せていた。
とくに、「一晩中街を眺めてしまった」という声が多く、都市の夜景や列車のライトアップに癒やされるという感想も少なくなかった。経営ゲームでありながら“観賞用ゲーム”としても成立する稀有な存在だった。
● プレイヤー層の広がりと教育的側面
当初は鉄道ファンを中心に支持されたが、発売後は建築・都市設計・経済学などに興味を持つプレイヤー層にも広がった。 「経済の流れを実感できる教材のようだ」「都市計画の感覚が身につく」といった意見が多く、実際に学習目的でプレイした学生や教師も存在した。
後年、教育機関で“都市成長モデル”を扱う際に『A列車で行こうIII』が参考事例として取り上げられることもあり、単なる娯楽を超えた社会的意義を持つ作品となった。
この点が、ほかの娯楽寄りのシミュレーション作品との差別化に成功した理由でもある。
● 批評的視点:テンポと操作性への意見
もちろん、すべての評価が肯定的というわけではない。 当時の一部プレイヤーからは「ゲームテンポが遅い」「資金回収までが長い」「メニュー操作が煩雑」といった指摘もあった。特にマウス操作が一般的でなかった時代のPC版では、キーボード中心の操作体系に慣れるまで時間がかかったという意見も多い。
しかし、こうした点も「現実的な経営シミュレーションとしてのリアルさ」と受け取るプレイヤーも多く、テンポの遅さが“都市の呼吸を感じる時間”として逆に評価されることもあった。結果的にこのゲームの“じっくり遊ぶ”設計思想は、シリーズの個性として定着していく。
● ファンによる創作とリプレイ文化
熱心なプレイヤーの中には、プレイ結果を地図化して自作の都市誌や路線図を描く者も現れた。 当時の同人誌やパソコン通信の掲示板(NIFTY-Serveなど)では、自作マップや経営記録を共有する文化が生まれ、『A列車で行こうIII』を通じて都市づくりの想像力を競い合う場となっていた。
「この作品がきっかけで都市計画の仕事を目指した」という声もあり、ゲームを超えた“創作の土台”として後世に影響を与えたことは間違いない。
これらのファン活動は、シリーズの根強い人気を支え、後のリメイク版発売の原動力ともなった。
● 現代における再評価
近年では、プロジェクトEGGなどで配信された復刻版を通じて再び注目が集まっている。 現代のゲーマーがプレイしても、その設計思想の確かさと、システムの緻密さに驚かされるという。 「グラフィックはレトロだが内容は今でも新しい」「30年以上前にこのレベルの経営シミュレーションが存在したことに驚いた」といったレビューがSNSやブログなどに寄せられており、いまなお“時代を超える完成度”として語り継がれている。
とくにPCエンジン版やWindows版のリリースによって、当時遊べなかった若い世代が新たに参入し、“自分の街を作る喜び”を改めて体感している点も興味深い。
● 総評:静かに街を見守る喜び
『A列車で行こうIII』がこれほど長く愛される理由は、派手な演出や明確な勝敗ではなく、“都市が生きる過程そのものを見守る”という静かな感動にある。 経営、都市、美観、音楽、時間——それらが穏やかに調和し、プレイヤーに“自分の世界”を創造する楽しさを与えてくれる。
シリーズの中でもっとも“哲学的”と評されるこの作品は、単なるゲームではなく、“都市と人の関係を考えさせるアート作品”と呼ぶにふさわしい。
鉄道を通して描かれた街の成長と衰退、そして再生——その全てを見届ける体験こそが、『A列車で行こうIII』の普遍的な魅力である。
■ 良かったところ
● 鉄道経営と都市発展の一体化が生むリアリティ
『A列車で行こうIII』の最大の魅力として多くのプレイヤーが挙げるのが、鉄道経営と都市発展が見事に結びついている点だ。 単に線路を敷いて列車を走らせるだけではなく、その結果として街が発展し、建物が増え、人口が動く。その全ての変化が“自分の手で動かしている”という実感とともに味わえる。 例えば新駅を開設した瞬間、周囲に商業施設が建ち始め、時間とともに住宅が増え、ついにはビル群が立ち並ぶ。そうした“変化の連鎖”を目の前で観察できるリアルさこそが、多くのファンを魅了した。
鉄道が経済の血流として機能し、それに合わせて街が呼吸を始める。これは他の経営シミュレーションでは体験できない、“都市と鉄道の生命循環”の美学といえる。
● クォータービューによる美しい街並み表現
従来のトップビューを脱し、斜めから街を見下ろすクォータービューを採用したことは、シリーズにおける大きな進化だった。 この視点によって、建物や線路の立体感が生まれ、まるでジオラマを眺めているかのような温かみのある都市描写が実現した。 特に列車が街の中をすり抜ける瞬間や、夕暮れ時にライトが灯るシーンは、多くのプレイヤーが“いつまでも眺めていたい”と語るほど印象的である。
また、時間帯によって色合いが変化し、朝焼けや夜景が再現される演出は、1990年当時のPCゲームとしては驚異的な完成度だった。
このビジュアルの魅力は、のちのシリーズ作品にも受け継がれ、“A列車”といえば美しい都市景観、というブランドイメージを確立する要素になった。
● 経営の手応えと試行錯誤の楽しさ
本作のもう一つの良点は、経営シミュレーションとしての“手応え”である。 収益が思うように上がらない時期もあれば、投資のタイミングを誤って赤字に転落することもある。しかしその一つひとつが学びとなり、再挑戦することで経営感覚が磨かれていく。
プレイヤーが自らのミスを糧に次の戦略を立てていくプロセスは、他のゲームでは得られない深い満足感をもたらす。
単に勝つ・負けるという二元的な結果ではなく、「どのように成功へ導くか」という思考の過程そのものが楽しい——それが『A列車で行こうIII』の真価だといえる。
● サウンドと時間演出の調和
昼夜の移り変わりと連動して変化するBGMや環境音も、本作を語る上で欠かせない要素だ。 朝には軽やかなメロディが流れ、昼には活気ある音楽、夜には穏やかで静かな旋律が流れる。音と時間の変化が融合することで、プレイヤーはまるで実際の都市の中にいるような錯覚を覚える。
さらに、列車の走行音や駅のアナウンスなども環境として組み込まれており、鉄道ファンにとっては臨場感あふれる演出だった。
このサウンドデザインがもたらす没入感は、グラフィックだけでは表現しきれない“街の空気”を補完している。
● 子会社経営の面白さと経済の広がり
鉄道経営だけでなく、子会社を設立して多角的に収益を上げられるシステムは、当時として非常に斬新だった。 ホテル、商業施設、オフィスビル、工場など、様々な事業を展開できることで、プレイヤーは単なる鉄道会社の社長から“都市経営者”へと進化する。
また、子会社が街の発展に直接影響を与える点も秀逸だ。
商業施設を建てれば旅客が増え、工場を設置すれば通勤需要が発生する。経済活動が相互に絡み合う構造は、まさに現実社会の縮図であり、このリアルな連携性がシリーズの中でも特に高く評価された部分である。
● マルチウィンドウUIの快適さ
当時としては画期的だったマルチウィンドウ形式のインターフェースは、操作性の良さと視認性の高さでプレイヤーから高く評価された。 複数の情報を同時に参照しながら操作できるため、経営データを分析しつつ、マップの変化をリアルタイムで観察することができる。
とくにPC-9801版やX68000版のUIはレスポンスがよく、慣れると非常に快適に操作できた。
こうした“ユーザーの視点に立った設計”は、アートディンク作品全般の強みであり、後のシリーズでも継承されていく要素となった。
● プレイヤーの創造性を刺激する自由度
本作は明確なゴールを設けず、プレイヤーの発想次第で無限に遊び方が広がる構成になっている。 都市を効率的に拡張することに専念するもよし、風景の美しさを追求するもよし、あるいは観光都市・工業都市といったテーマで街を作り分けることもできる。
この自由度の高さがプレイヤーの創造意欲を掻き立て、“自分だけの都市を持つ”という感覚を強く印象づけた。
現代で言う「サンドボックス的シミュレーション」の原型ともいえる存在であり、後年の都市開発ゲームに多大な影響を与えた点は特筆に値する。
● 長期プレイの持続性と愛着
『A列車で行こうIII』は、一度完成した街をただ眺めるだけでも楽しめるほど、長期プレイへの耐久性が高い。 時間の経過とともに変化する風景や人口動態を観察していると、まるで自分の作り上げた世界を“見守る”ような感覚に包まれる。
「今日は何も開発しないで、ただ列車の運行を見ていた」と語るプレイヤーも多く、都市を眺めること自体が癒しとなっていた。
この“静かに楽しむプレイ体験”は、他のどんなゲームにもない独自の価値として、多くのファンの心に残っている。
● 他機種版による進化と拡張性
FM TOWNS版に付属した『A.III.マップコンストラクション』を活用すれば、自分の思い通りの地形を設計し、オリジナルマップで新たな都市を創造できる。 これにより、攻略・観賞・創作といった複数の遊び方が融合し、単一作品でありながら“無限に続くゲーム体験”が実現した。
また、後年に発売されたWindows版では操作系統が現代的に改善され、グラフィックや動作速度も向上。
古き良きシステムを残しながら、快適さが増したことで、“懐かしさと新しさが共存する名作”として再び評価を高めた。
● シリーズ全体への影響力
『A列車で行こうIII』が確立した経営+都市構築の構造は、以降の作品すべての原点となった。 『IV』以降で導入された株式システムや3D都市表現も、この第三作で培われた設計思想が基礎にある。
シリーズファンの中では、「A列車の魂はIIIで完成した」と語る者も多く、のちの作品がどれだけ進化しても、この時代のバランス感覚こそが“理想のA列車”だという意見も根強い。
その完成度と安定感は、今なおファンの間で語り継がれている。
● 総括:静かな満足感をもたらす“完成された体験”
『A列車で行こうIII』の良さは、即時的な刺激ではなく、時間をかけてじっくりと熟成する満足感にある。 派手な演出よりも、都市の成長を静かに見守る過程そのものが楽しく、経営という行為が“街を育てる物語”として昇華している。 一見地味だが、深く触れるほどに心地よい余韻が残る——そんな“静かな名作”として、多くのユーザーに記憶されている。
この作品を体験した人の多くが、「A列車の原点はここにある」と口を揃えるのも頷ける。
『A列車で行こうIII』は、まさに“完成されたシミュレーションゲーム”の一つとして、日本のPCゲーム史に確かな足跡を残した。
■ 悪かったところ
● 全体的なテンポの遅さと進行スピードの問題
『A列車で行こうIII』において最も多く指摘された点のひとつが、「ゲームのテンポが非常にゆっくりしている」という点だった。 鉄道経営と都市開発が現実的な時間軸で進行するため、建設の効果や人口増加が目に見える形で表れるまでに相当な時間がかかる。 その結果、序盤から中盤にかけての進行が遅く、特に初めてプレイする人にとっては「なかなか街が発展しない」「成果が出るまでが長い」と感じることが多かった。
もちろん、長期的な都市成長を観察することが本作の醍醐味ではあるのだが、当時のプレイヤーの中には“スピード感のある展開”を求める層も少なくなかった。
テンポの遅さはシミュレーションのリアリティを支える一方で、“遊びやすさ”という観点では賛否が分かれた部分である。
● 操作体系の複雑さと学習コストの高さ
もう一つの課題として、多くのプレイヤーが挙げたのが操作の難しさだ。 マウスが一般的ではなかった1990年代初期のPC環境において、キーボード中心の操作体系は直感的とは言いがたかった。 メニューを呼び出してウィンドウを切り替え、さらにサブメニューから細かい設定を行うという流れは、慣れるまでに相当な時間を要した。
マニュアルを読み込まなければ理解しづらいシステムも多く、「取っつきにくい」「最初の壁が高い」という意見も散見された。
この点は、初心者層の参入をやや妨げる要因となっており、当時のゲーム誌レビューでも「慣れるまでが本当に大変だが、慣れると病みつきになる」と評価されている。
いわば“上級者向けの作り”であり、そこが本作の魅力であると同時に、入り口の狭さでもあった。
● 資金バランスの厳しさと序盤の難易度
経営シミュレーションとしてのリアルさを追求した結果、序盤の資金繰りが非常にシビアであった。 駅をひとつ建設するだけでも莫大なコストがかかり、列車を増備すればすぐに資金が底を突く。 しかも、路線を延ばしても利用者が増えるまでに時間がかかるため、黒字化までの道のりは長い。
このバランスの厳しさは“現実的すぎる”とも評され、特に初見プレイヤーが序盤で経営破綻するケースが多発した。
攻略情報が乏しかった当時は「どうすれば黒字になるのかわからない」という声も多く、経営初心者にとっては非常にハードルの高いゲームだったといえる。
● 都市発展の演出面での単調さ
街の発展を観察する楽しさは本作の醍醐味である一方で、その変化がやや淡白であるという指摘もあった。 建物のバリエーションは当時としては多いものの、発展段階が進むと似たようなビルが増え、景観の変化が単調に感じられる。 また、建設アニメーションがなく、建物が“いきなり現れる”演出も没入感を損ねる要因とされた。
これらの要素はハードウェアの制約上仕方のない部分ではあったが、プレイヤーからは「都市の成長をもっと視覚的に楽しみたかった」という意見が少なくなかった。
後のシリーズ作品で導入される“建設過程の可視化”や“発展ステージの段階的変化”は、この時期の課題を受けて改善されたものと言える。
● 情報量の多さによる混乱
マルチウィンドウで複数のデータを同時に確認できる仕組みは革新的であったが、その反面、情報量が多すぎて混乱するという声もあった。 財務状況、列車の運行状態、人口動態、子会社の収支など、同時に管理すべき項目が多岐にわたるため、慣れないうちは“どこを見ればよいのかわからない”状態になりがちだった。
また、画面上に開いたウィンドウ同士が重なりやすく、重要なデータが隠れてしまうこともあった。
この点は後年のWindows版で改善されていくが、当時のDOS環境ではハード的制限もあり、インターフェースの煩雑さは避けがたかった。
● 視覚的派手さに欠ける印象
当時のプレイヤーの中には、「派手なイベントやアクションが少ない」という理由で物足りなさを感じた人もいた。 他社のゲームが戦略イベントやアニメーション演出を積極的に導入していた時期に、本作はあくまで“静かに都市が成長する”ことを主題としており、ダイナミックな展開を期待していた層からは「地味すぎる」と見られることもあった。
特に、プレイヤーの行動が即座に結果に結びつかない設計は、“ゲーム的な爽快感”を求める人にとっては不向きだったかもしれない。
しかし、そうした静的な構成こそが『A列車』シリーズの哲学的な魅力でもあり、この点は好みがはっきり分かれる部分だった。
● 時代背景による技術的制約
1990年という時代を考慮すると、本作のプログラムやグラフィック表現は非常に野心的であったが、それでもハードウェアの制限による制約は大きかった。 描画速度が遅く、都市が拡張するほど動作が重くなる現象が発生し、長時間プレイ時には処理落ちを感じることもあった。 特にX68000版では比較的スムーズだったものの、PC-9801版や初期DOS版ではフレーム更新が遅く、プレイヤーから「もっさりしている」と評されたこともある。
このような技術的問題は、後の『A列車で行こうIV』で最適化が図られることになるが、IIIでは「理想の構想にマシンが追いついていなかった」と言われることも多かった。
● 初心者向けチュートリアルの欠如
現代のゲームに比べると、チュートリアルや説明の少なさも不親切に感じられた部分だ。 ゲームの冒頭で明確なガイドがなく、何をどうすれば発展するのかが直感的に分からないため、試行錯誤を強いられる。 「最初の一時間で挫折した」という声もあり、マニュアルを熟読しなければ理解できない設計は、初心者にはやや厳しい仕様だった。
ただし、そうした“自由すぎる導入”を魅力と捉えるベテランプレイヤーも多く、「自分で気づいて成長する楽しさがある」という肯定的な意見も存在した。
このように、本作は“遊ぶ人を選ぶ”ゲームであり、その点が長く語り継がれる一因にもなっている。
● 一部の経営要素の単調さ
経営のリアリティが高い一方で、子会社経営や財務操作のバリエーションはやや少なめで、後半になると似たような作業が続く印象もあった。 特に、建設可能な施設が限られており、街の成熟段階を超えると発展の伸びしろが感じにくくなることがある。 また、株価変動や市場競争といった要素は導入されておらず、経営の“外部リスク”が少ないため、終盤は安定しすぎてしまう。
これにより「序盤の緊張感はあるが、終盤が単調になる」という声も見られた。
しかし、この安定感を“理想的な都市経営の完成”と見るプレイヤーもおり、最終的にはプレイスタイルによって印象が分かれる点でもあった。
● 総括:挑戦的設計ゆえの“不親切さ”
『A列車で行こうIII』の“悪かったところ”は、同時に“挑戦的だったところ”でもある。 開発陣がリアルな経済と都市成長を追求した結果、テンポや難易度、操作性などの面でプレイヤーに高い理解力と忍耐を要求する作品になった。 しかし、それは単なる欠点ではなく、本作の“骨太な個性”の裏返しでもある。
万人向けではないが、深く遊び込むほどに見えてくる設計の緻密さや、リアルな経済構造の再現性は、他の作品にはない価値を持っていた。
まさに、“分かる人にはたまらない”硬派なシミュレーションゲームだったと言える。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
● 『A列車で行こうIII』における“キャラクター”の概念
『A列車で行こうIII』は、いわゆる“登場人物”が明確に存在するストーリーゲームではない。 しかし、プレイヤーを支える経営アシスタント、銀行担当、都市住民のメッセージウィンドウ、そして各種システムウィンドウの案内役など、プレイヤーの想像力の中で“人格を持った存在”として機能するキャラクター的要素が散りばめられている。
さらに本作では、列車や建物そのものに個性が宿っており、プレイヤーが長期にわたって街を育てる過程で、それぞれの車両や施設に“愛着”を感じるようになる。
つまり『A列車で行こうIII』の“キャラクター”とは、人間ではなく“街を形づくる存在すべて”であり、プレイヤーにとっては自ら育てた都市の一部がキャラクターのように感じられるのだ。
● 鉄道会社の経営者=プレイヤー自身という主人公像
多くのファンが「最も好きなキャラクター」として挙げるのは、他ならぬプレイヤー自身——すなわち鉄道会社の経営者である。 本作では名前も性別も年齢も自由。背景設定も語られない。 だが、それゆえにプレイヤーは完全に自分を投影し、自分自身の意志で都市を導く主人公として没入できる。
経営判断のすべてが街の未来を左右し、成功すれば栄光を手にし、失敗すれば破綻という現実が待つ。
その緊張感の中で少しずつ会社を成長させていく過程は、まさに“物語の主人公”としての成長譚である。
「数字の中に自分の意志が宿る」「都市の姿が自分の性格を映しているようだ」というプレイヤーの声が多く、キャラクター性のない主人公こそ、最もキャラクター性を持っていたとも言える。
● 銀行担当やシステムメッセージの“冷たい温もり”
シリーズを通して登場する銀行担当者の存在は、地味ながら印象的だ。 『III』では資金を借りる際や返済を行う際に淡々としたメッセージが表示されるが、その文章の冷静さが逆に“経営の厳しさ”を感じさせた。 「利率を確認の上でお申し込みください」という一言が、プレイヤーに現実の経営感覚を植え付ける瞬間でもある。
また、システムメッセージの中には時折ユーモラスな表現もあり、プレイヤーが破産寸前になると皮肉めいたコメントをすることもある。
このようなテキストの“人間味”が、数字とデータに囲まれたゲーム空間にささやかな温もりを添えていた。
多くのファンが「冷たいのに優しい」と評した独特の文体は、まるで無口な秘書のようなキャラクター性を感じさせる。
● プレイヤーの分身“列車たち”
『A列車で行こうIII』における最も象徴的な存在といえば、やはり“列車”だろう。 このゲームでは列車一つひとつに名前を付けることができ、運行ルートもプレイヤー自身が設計する。 朝の通勤列車、夜行特急、貨物列車——それぞれの役割を担う車両たちは、まさにプレイヤーの意志を体現する“動くキャラクター”である。
中でも多くのファンが愛着を持ったのが「A列車」と名付けられた特別列車だ。
シリーズの顔ともいえる存在で、運行する姿を見守るだけでも満足感がある。
路線を延ばし、街を結ぶたびに彼らが走り抜けていく姿は、都市の成長と経営者の努力を象徴するものであり、“A列車が主人公”と言われる所以でもある。
● ビルやホテルなどの子会社施設にも宿る“個性”
建設できる子会社施設にも、それぞれ固有の“性格”があると感じるプレイヤーは多い。 オフィスビルは堅実で信頼性があり、ホテルは華やかで観光地の象徴。 一方で工場は実直に都市を支える裏方のような存在だ。 こうした施設群が経営の柱として息づき、それぞれが都市という舞台で個性を発揮していく様は、まるでキャラクター同士の共演のようでもある。
プレイヤーによって「お気に入りの施設」が異なり、中には“駅前ホテルマニア”や“ビル街特化派”など、自分の経営哲学を施設選びで表現する者もいた。
『A列車で行こうIII』は、数字の裏に確かに“人格的要素”を持たせる設計で、プレイヤーの感情移入を自然に引き出していたのである。
● 都市そのものがキャラクターとして成長する
本作の中で最も“キャラクター的”な存在は、実は街そのものである。 プレイヤーが線路を敷き、ビルを建て、時間をかけて育てた都市は、それぞれが独自の個性を持つようになる。 産業中心の都市、観光都市、住宅都市——同じマップでもプレイヤーの判断次第でまったく異なる性格を持つ。
時間が経つほど街の景色が変わり、人口構成が変化し、列車の運行パターンも進化していく。
まるで街自身が意志を持って成長しているように感じられる瞬間がある。
この“都市=キャラクター”という発想は、後のシリーズでより明確に意識されていくが、その原点はこの『III』にあったと言えるだろう。
● プレイヤーと街の“関係性”が生む感情
他のゲームではキャラクターがプレイヤーに語りかけるが、『A列車で行こうIII』では街そのものが語りかけてくる。 「列車の通る音」「人の流れ」「灯りの増減」——それらが無言の会話となり、都市とプレイヤーの間に“絆”のようなものが生まれる。
プレイヤーが不採算路線を廃止すると、街が静まり返る。
新駅を作ると、再び人の流れが生まれ、街が息を吹き返す。
この“感情的反応”が積み重なることで、プレイヤーは都市をまるで生きたパートナーのように感じる。
「街が自分に微笑みかけているようだ」という感想は、当時のファンの間でよく語られた言葉だった。
● 想像の余地を残した“無名の登場人物たち”
『A列車で行こうIII』では、ゲーム内に登場する市民や通勤者の顔は描かれない。 しかし、その“見えない人々”こそがプレイヤーの想像を刺激した。 駅に集う群衆、ビルに灯る光、車窓を走る列車の明かり——それらが人々の生活を象徴し、プレイヤーの頭の中に“物語”を生み出していく。
あるプレイヤーは「この街にはきっとこんな人が住んでいる」と想像し、
ある人は「夜景に灯る光は社員たちの努力の証だ」と語る。
キャラクターが存在しないからこそ、プレイヤー一人ひとりが自分の物語を紡げる。
その“余白の美学”こそが、本作におけるキャラクター表現の本質だった。
● 総括:無言のキャラクターが語りかける都市ドラマ
『A列車で行こうIII』に明確なキャラクターはいない。 だが、そこには確かに“人格”がある。列車が走り、街が呼吸し、企業が成長していく過程そのものが、ひとつの壮大なドラマを形づくっている。 プレイヤーはその世界の中で指揮を執り、時に見守り、時に支え、街とともに成長していく。
つまり、この作品における「好きなキャラクター」とは、プレイヤー自身と、その手で築いた都市そのものである。
『A列車で行こうIII』は、キャラクターを“人”ではなく“世界”として描いた稀有なゲームであり、そこにこそシリーズが長く愛される理由がある。
[game-7]
● 対応パソコンによる違いなど
● 同じタイトルでも異なる“個性”を持つ各機種版
『A列車で行こうIII』は、1990年当時としては非常に幅広いプラットフォームに対応していた。 PC-9801、FM TOWNS、X68000、そして後にリリースされたWindows対応版など、同じタイトルでありながら、それぞれのハードウェア性能や特性を最大限に活かすよう設計が異なっていた。 当時の日本のパソコン市場は、機種ごとにCPUやグラフィックチップ、サウンド機能が大きく異なっており、ユーザー間では「どの版が一番リアルか」「どれが遊びやすいか」といった議論も盛んに行われていた。
それぞれの機種は、“同じゲームの別の顔”を持っており、プレイヤーがどの環境で遊ぶかによって体験そのものが変化する。
以下では、代表的な各プラットフォームごとの特徴を掘り下げて紹介していこう。
● PC-9801版 ― シリーズの基礎を支えた安定型
日本のビジネス市場を席巻していたPC-9801シリーズ向けにリリースされたバージョンは、もっとも多くのプレイヤーに触れられた定番モデルだった。 グラフィックは当時の16色表示ながらも、アートディンク独自の美しいドットアートで都市の雰囲気を見事に描き出している。 特に、光の使い方が秀逸で、夜景時の窓明かりや街灯の点滅が、限られた色数の中で驚くほど繊細に表現されていた。
動作は安定しており、同時期の他タイトルに比べてクラッシュも少なかったため、シリーズファンからは「最も堅実なA列車」として高く評価されている。
CPUの性能上、スクロール速度はやや遅めだったが、長期プレイ時の安定感は抜群で、経営データの読み込みも安定していた。
まさに「堅実でバランスの取れたA列車」と呼ぶにふさわしいバージョンだった。
● X68000版 ― 高解像度と処理性能が生む快適さ
当時“グラフィック最強機”として知られたX68000版は、その性能を存分に活かしたクオリティの高さで多くのプレイヤーを唸らせた。 高解像度表示によってマップの細部までくっきりと描写され、列車の車両デザインや建物の質感が一段とリアルに感じられる。 また、動作速度が速く、スクロールやウィンドウ切り替えがスムーズだったことから、快適なプレイ体験を求める上級者の間で特に人気が高かった。
さらに、X68000特有のサウンド機能「FM音源+ADPCM」の組み合わせによって、環境音やBGMの臨場感が際立っていた。
工場エリアでの低音や、列車が走り抜ける金属的な響きなど、音の表現力は他機種版より一段上。
当時の雑誌レビューでは「A列車シリーズの理想形はX68版」と称され、後のWindowsリメイク版の基準的存在ともなった。
● FM TOWNS版 ― サウンドと拡張性で人気を博した特別版
FM TOWNS版は、シリーズの中でも特別な存在として語られる。 何より特徴的なのは、本体同梱の『A.III. マップコンストラクション』の存在である。 これを使えば、プレイヤーが自分で地形をデザインし、完全オリジナルの都市を構築できた。 当時としては画期的なユーザークリエイション機能であり、都市づくりを単なる経営シミュレーションから“創作体験”へと拡張していた。
また、FM TOWNSはCD-ROM搭載機として音質が圧倒的に優れており、BGMの再生品質が他機種とは別格だった。
ジャズ調やアンビエントな曲調が高音質で流れることで、まるで映画のような空気感を演出していた。
このサウンド体験は、シリーズ全体の“音楽美”を象徴する原点として、今もファンの間で語り継がれている。
● Windows版 ― 2000年代への架け橋となった再構築版
2000年に発売されたWindows 95/98対応版『A列車で行こうIII』は、単なる復刻ではなく、現代風に再設計されたリメイク的存在である。 グラフィックは滑らかになり、インターフェースもマウス操作に最適化。 かつてのキーボード中心の煩雑さが解消され、初心者でも扱いやすくなっていた。
このWindows版の登場によって、本作は再び脚光を浴び、多くの新規プレイヤーが参入した。
特に当時のレビューでは「懐かしさと快適さが共存する名移植」と評され、シリーズ初期三部作の中で最も再評価が進んだバージョンとなった。
また、データの保存形式も近代化され、安定した長期プレイが可能になった点も高く評価された。
● PCエンジン版 ― コンソール向けアレンジの実験作
後年、PCエンジン版としても移植された『A列車で行こうIII』は、当時の家庭用ゲーム市場における“本格経営シミュレーションの挑戦”として注目を集めた。 グラフィックやインターフェースは大幅に簡略化されていたものの、コントローラー操作でも十分遊べるよう調整されていた点が画期的だった。 ただし、システムの一部が省略されており、PC版と比べるとややカジュアル寄りの内容となっていた。
とはいえ、テレビ画面で街を俯瞰しながら列車が走る光景を眺められる体験は新鮮で、シリーズを家庭用ユーザーへ広める橋渡し的役割を果たした。
この移植の成功が、後のスーパーファミコン版「A列車で行こうIII スーパーバージョン(A3SV)」開発につながったと言われている。
● 比較して見えてくる“機種ごとの方向性”
同じ『A列車で行こうIII』でありながら、各機種ごとに表現された世界観には明確な個性がある。 PC-9801版は堅実で落ち着いたビジネス志向、X68000版は映像美と快適性、FM TOWNS版は音楽と創造性、Windows版はモダンな利便性を重視している。 まるで同じ楽譜を異なる楽器で奏でているように、どのバージョンも同じ旋律を持ちながら、それぞれの響きが異なる。
プレイヤーの間では「どのA列車IIIが本命か」という議論がいまだに交わされており、それぞれの版に熱烈なファンが存在する。
この“多様性の中の一体感”こそが、本作の長寿命を支えてきた最大の理由ともいえる。
● 現代における復刻と保存の意義
現在では、プロジェクトEGGによってPC-9801版(2014年)、PCエンジン版(2020年)が配信され、現代の環境でもプレイ可能となっている。 これにより、かつての機種ごとの違いを比較しながら遊ぶ楽しみが再び注目されている。 ゲーム保存の観点からも、『A列車で行こうIII』のように複数の機種で異なる文化を持つ作品がデジタル配信されることは非常に意義深い。
アートディンクの“マルチプラットフォーム哲学”が実を結んだ形であり、それぞれの機種が残した違いは、単なる技術差ではなく、日本のPCゲーム史そのものの記録でもある。
ハードの制約を超え、今なお愛され続ける『A列車で行こうIII』は、まさに時代とともに走り続ける“ゲームの鉄道”と言えるだろう。
[game-10]
● 同時期に発売されたゲームなど
● 1990年前後――パソコンゲーム黄金期の転換点
『A列車で行こうIII』が発売された1990年は、日本のパソコンゲームが大きく変化した時代だった。 PC-9801やX68000、FM TOWNSなど高性能機が普及し、グラフィックや音楽の表現力が飛躍的に向上していく一方で、開発者たちはゲームを“娯楽”から“文化”へと昇華させようとしていた。 経営シミュレーション、ノベル、アクション、RPGといった多様なジャンルが成熟期を迎え、各メーカーが自社の強みを発揮していたのもこの頃である。
『A列車で行こうIII』はその中で、“知的な経営シミュレーション”という新しい方向性を確立した作品であったが、同時期には他にも名作が数多く誕生している。
ここでは、1990年前後に発売された代表的なパソコンゲーム10作品を挙げ、それぞれの特徴や背景を詳しく見ていこう。
★『シムシティ』(マクシス/1990年/価格:9,800円)
都市開発シミュレーションの代名詞とも言える本作は、『A列車で行こうIII』と比較されることが多い。 プレイヤーが市長となり、インフラや税金、災害対策を通して街を育てていくという発想は、当時としては非常に斬新だった。 『A列車』が鉄道と企業経営を中心に据えたのに対し、『シムシティ』は市民の幸福と都市機能の維持を重視しており、社会構造のシミュレーションとして人気を博した。 両作は“都市の発展”を題材にしながらもアプローチが異なり、1990年はまさに「都市シミュレーション元年」と呼べる年となった。
★『プリンセスメーカー』(ガイナックス/1991年/価格:8,800円)
プレイヤーが“娘”を育てるという独創的なテーマで話題を呼んだ育成シミュレーション。 アニメ的なキャラクター描写と経済要素の融合が新鮮で、特にFM TOWNSやPC-9801版では美麗なグラフィックが高く評価された。 『A列車で行こうIII』が「都市の成長」を描いたのに対し、本作は「人間の成長」を描き、プレイヤーの感情を強く揺さぶるゲーム体験を実現している。 経営要素と育成要素の両立という設計思想は、その後のシミュレーションゲーム全般に大きな影響を与えた。
★『大戦略II』(システムソフト/1990年/価格:9,800円)
日本製ストラテジーゲームの金字塔。 ターン制による軍事戦略システムを採用し、複雑な兵器の運用と地形戦術を高度に再現した。 戦術・経営・地形把握といった思考要素のバランスが取れており、知的なシミュレーションとして『A列車』と同じ層のユーザーから支持を集めた。 また、マップエディタ機能を搭載しており、ユーザーがオリジナル戦場を作成できる点も画期的だった。
★『ポートピア連続殺人事件』(エニックス/PC移植版:1990年)
堀井雄二が手掛けたアドベンチャーの名作。1983年のオリジナル版から数年を経て、PC-9801向けに再構築された。 ビジュアルの高解像度化と共に、プレイヤーの入力操作がよりスムーズになり、物語性を重視した体験が強化された。 この頃のプレイヤーは、『A列車で行こうIII』のような経営型ゲームと並行して、物語重視型のタイトルを楽しんでおり、“知的遊び”の多様化が進んでいた。
★『ルナティックドーン』(アートディンク/1990年/価格:8,800円)
同じくアートディンクが手掛けた自由度の高い冒険RPG。 職業や行動がすべてプレイヤーの自由に委ねられており、「人生をシミュレーションするRPG」として注目を集めた。 『A列車で行こうIII』と同様、“システムの中で自分の物語を紡ぐ”という思想が根底に流れており、アートディンクの多様なシミュレーション哲学を象徴する作品といえる。
この二作が同時期に存在したことで、アートディンクは“創造型シミュレーションメーカー”として確固たる地位を築いた。
★『信長の野望・戦国群雄伝』(光栄/1989年/価格:12,800円)
戦国時代を舞台にした歴史シミュレーションの定番。 『A列車で行こうIII』と同じく、長期的な戦略思考と資金・人材の管理が要求されるため、知的ゲーム愛好家から高い支持を得ていた。 光栄(現コーエーテクモ)はこの頃、“歴史を経営する”というテーマを確立し、アートディンクが“都市を経営する”方向に進む中で、日本のシミュレーション文化を二分していく。 いずれも、現代に至るまで続くロングシリーズの礎を築いた作品群である。
★『ソーサリアン』(日本ファルコム/1989年PC-98版/価格:9,800円)
アクションRPGとシナリオ制を融合させた革新的な作品。 追加シナリオを次々に発売する“拡張ディスク”の手法は、のちのDLC文化の先駆けとされている。 この時期のファルコム作品は、グラフィック・音楽・操作性すべてにおいて高品質で、 『A列車で行こうIII』のように長期的に遊べる構造の作品として、ユーザーから同様の支持を集めた。
★『レミングス』(DMA Design/輸入版1990年)
海外から輸入されたパズルアクションだが、日本のパソコンユーザーの間でも大ヒットを記録した。 多数の小さなキャラクターを誘導してゴールへ導くというゲーム性は、 シミュレーションと戦略を融合した思考型作品として高く評価された。 『A列車で行こうIII』と同様、プレイヤーが直接的な操作よりも“環境を整えることで結果を導く”という設計思想を持っており、 その間接的な操作性が知的プレイヤー層に強く支持された。
★『ハイドライド3』(T&Eソフト/1989年/価格:8,800円)
リアルタイムRPGとして人気を博したシリーズの第3作。 この時代のT&Eソフトは、独自の世界観と物理演算的なアクションで注目を集めていた。 『A列車で行こうIII』が“現実の経済”を模したのに対し、『ハイドライド3』は“現実的な物理”を取り込んだファンタジー作品であり、 どちらも当時のPCユーザーが“リアリティ”を求め始めた潮流を象徴している。
★『大航海時代』(光栄/1990年/価格:12,800円)
世界を舞台にした貿易・探検シミュレーション。 プレイヤーが商人として航海し、交易や海戦を通じて富を築くという構成は、 『A列車で行こうIII』と同様に“経済を通じて世界を動かす”というテーマを持っていた。 特に資金繰りやリスク管理の要素は共通しており、鉄道会社経営を海上貿易に置き換えたような構造といえる。 この2作は日本における“経営シミュレーション”の東西二大代表作として、長く比較され続けた。
● 当時の潮流と『A列車で行こうIII』の位置づけ
1990年前後のパソコンゲーム界は、ジャンルの成熟と多様化が同時に進行していた。 アクションやRPGの中にも経営要素やシミュレーション思考が導入され、 一方でシミュレーションゲームは物語性や演出を重視する方向へと進化していく。 『A列車で行こうIII』は、そんな時代の“境界線”に立つ作品だった。
それは単に鉄道経営を扱うゲームではなく、“人の営みそのもの”を描こうとする意志を感じさせた。
同時期の他作品が戦い・冒険・育成を通してドラマを描いたのに対し、
本作は街の灯りや列車の音といった“日常のドラマ”をテーマにした点で異彩を放っている。
つまり、『A列車で行こうIII』は1990年代初頭における「静の名作」として、華やかな時代の中で独自の存在感を確立したのだ。
● 総括:多様な名作が共鳴した創造の時代
『A列車で行こうIII』と同時期に登場したこれらの名作群は、それぞれ異なる方向から「プレイヤーの思考と想像力」を刺激した。 経営のリアルを追求したアートディンク、戦略を磨いたシステムソフト、物語を深化させたエニックス、感情と世界観を結びつけたガイナックス。 1990年前後のPCゲーム界は、まさに“知と創造の黄金時代”であった。
その中で『A列車で行こうIII』は、鉄道を通じて“社会の縮図”を描いた唯一無二の存在として輝きを放っていた。
30年以上を経た今もなお、その思想はシリーズ作品に脈々と受け継がれており、
“都市が生きることの美しさ”を教えてくれる象徴的な作品として語り継がれている。


![【新品】【NS2】A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10880000/10884115.jpg?_ex=128x128)


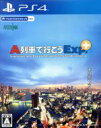

![【中古】[PS] A5 A列車で行こう5 アートディンク (19971204)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271015.jpg?_ex=128x128)
![A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[Nintendo Switch 2] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2128/nxs-p-ayayf.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[3DS] A列車で行こう3D(A3D) アートディンク (20140213)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1022/0/cg10220344.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS] A.IV. EVOLUTION(A4エボリューション) A列車で行こう4 アートディンク (19941203)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270004.jpg?_ex=128x128)