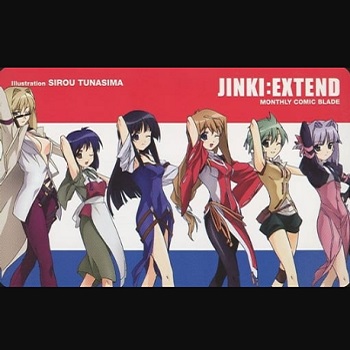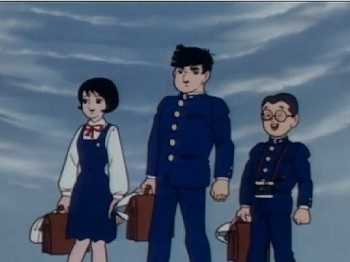
放送開始45周年記念企画 想い出のアニメライブラリー 第49集 ばくはつ五郎[DVD] HDリマスター DVD-BOX / アニメ
【原作】:辻なおき
【アニメの放送期間】:1970年4月3日~1970年9月25日
【放送話数】:全26話
【放送局】:TBS系列
【関連会社】:TCJ
■ 概要
● 放送の基本情報と時代背景
1970年4月3日から同年9月25日まで、TBS系列で全26話が放送されたテレビアニメ『ばくはつ五郎』は、昭和40年代初頭のアニメ界を彩った学園青春アニメのひとつである。制作を担当したのは、当時『エイトマン』『鉄人28号』『悟空の大冒険』などで知られたTCJ(現・エイケン)。同社が得意としていた骨太な人間ドラマ路線を継承しつつも、スポーツ・友情・ユーモアを絶妙にブレンドした構成が特徴的だった。放送時間は毎週金曜19時から19時30分というゴールデンタイム枠であり、当時の子どもたちにとって週末の楽しみとして親しまれた作品である。
本作が放映された1970年という年は、アニメーションがテレビの定番コンテンツとして定着し始めた時期であり、『巨人の星』や『アタックNo.1』など、スポ根(スポーツ根性)ジャンルが人気を博していた。その流れの中で登場した『ばくはつ五郎』は、単なるスポーツアニメにとどまらず、学園生活の中で生まれる人間模様や若者たちの成長を描いた点で、青春ドラマ的な要素を強く打ち出した意欲作であった。
● 原作と作品世界の方向性
物語の原作は、漫画家・辻なおきによる同名漫画で、講談社の月刊誌『ぼくら』にて1967年1月号から12月号まで連載された。辻なおきといえば『0戦はやと』『ハリスの旋風』など、男の友情と情熱を描く作風で知られる作家であり、『ばくはつ五郎』でもそのエッセンスは健在だ。アニメ版では原作の持つ泥臭い情熱や“男気”をそのままに、明朗でコミカルな演出を交えたことで、より幅広い層に受け入れられる作品に仕上がっている。
舞台となるのは、架空の青空学園。スポーツ万能で熱血漢の主人公・大石五郎が、転校をきっかけに新聞部へ入部し、さまざまな運動部や学校行事に関わりながら、仲間たちと絆を深めていく。学園内で繰り広げられる事件やトラブル、友情と恋愛の微妙な空気感が、当時の少年少女の心を強く惹きつけた。
● キャラクターが生み出す熱量と親近感
『ばくはつ五郎』の最大の魅力は、個性豊かなキャラクター群の人間味にある。主人公・五郎は正義感が強く短気だが、情に厚く不器用な優しさを持つ典型的な昭和の少年像として描かれる。彼がトラブルに直面したとき、怒りと情熱を爆発させる「爆発だ!!」の叫びは、子どもたちの間で流行語のように口ずさまれたという。ヒロインの三枝まゆみは、当時のアニメには珍しい自立した女性像を体現し、五郎を支えながらも自分の信念を貫く知的なキャラクターとして人気を博した。
一方で、まゆみを慕う輪島一平や、柔道部の荒熊源太、悪役的存在の鬼丸武など、脇役たちもそれぞれがしっかりとした性格づけをされており、彼らの掛け合いがドラマに厚みをもたらしている。特に、善悪を単純に二分せず、誰もが成長や葛藤を抱える姿が丁寧に描かれている点は、のちのエイケン作品にも通じる人間ドラマの原型といえる。
● 作画と演出の特徴
本作の作画は、当時のTVアニメの中でも安定感が高く、キャラクターデザインには辻なおき作品特有の“勢いと情熱”が感じられる。五郎の表情変化やコミカルなデフォルメ、そして感情の爆発シーンでのダイナミックな作画演出は、スポ根アニメの熱量を巧みに再現している。また、青空学園の背景美術には、昭和中期の学校生活を思わせる素朴なタッチが施され、郷愁を誘う。
さらに、演出面では一話完結形式を基盤としながらも、各話を通じてキャラクターの成長や人間関係の変化が描かれる連続性を持たせている。これは、当時としては比較的珍しい手法であり、後年の青春群像劇アニメの礎を築いたともいえる。
● 音楽と映像表現のバランス
オープニング主題歌「ばくはつ五郎」とエンディング「涙はともだち」は、ザ・ワンダースによる力強いコーラスが印象的で、作品全体の“熱血かつ爽やか”なイメージを象徴している。曲調は明るくテンポが良いが、歌詞の中には友情や努力、涙といった人間的テーマが込められており、作品の精神そのものを表している。特にエンディング曲は、回を重ねるごとに視聴者の間で親しまれ、学園青春ドラマの余韻を感じさせる存在だった。
● 放送当時の反響とその後の再評価
放送期間は半年間と短いながらも、視聴者の印象に残る作品として評価された『ばくはつ五郎』は、1970年代初頭のTBSアニメ群の中でも個性的な立ち位置を確立した。当時、スポーツ根性アニメが次々に登場する中で、単なる競技の勝敗を描くだけでなく、学校生活における友情や努力、そして失敗からの再起といった普遍的なテーマを取り入れたことが、長く語り継がれる理由の一つである。
2009年5月には、TBSチャンネルにてデジタルリマスター版が放送され、画質の向上とともに再び注目を集めた。昭和アニメ特有の色彩や手描き線の味わいが高精細に蘇り、当時リアルタイムで観ていた世代にとっては懐かしさと新鮮さが同居する再会となった。
● 総括 ― 青春と情熱の原点
『ばくはつ五郎』は、昭和アニメにおける「学園スポーツ×青春群像」の原型とも言える存在だ。熱血と笑い、汗と涙が混じり合うストーリーは、単なる児童向け作品を超え、世代を超えて共感を呼ぶ普遍的なメッセージを内包している。アニメ史の中では比較的短命な放送ながらも、その熱量と純粋さは多くの後続作品に影響を与え、今日に至るまで“知る人ぞ知る名作”として語り継がれている。
[anime-1]■ あらすじ・ストーリー
● 転校生・大石五郎の登場
物語は、青空学園の2年A組にひとりの転校生がやってくるところから始まる。彼の名は大石五郎。明るく快活な笑顔と筋肉質な体格、そして何よりも人並み外れた運動神経で、初日からクラスの注目を集める存在だ。五郎は岡山の田舎町から上京してきた少年で、幼くして父親を亡くし、酒屋を営む叔父夫婦に引き取られている。どこか粗削りで野性的だが、心根は優しく、困っている人を放っておけない性格。その真っ直ぐすぎる行動が、やがて青空学園に新たな旋風を巻き起こしていく。
入学早々、彼は偶然新聞部の部室を訪れ、活発で男勝りな部長・三枝まゆみと出会う。初対面から口論となる二人だが、まゆみの真っ直ぐな性格に惹かれ、五郎は新聞部への入部を決意。ここから、青空学園の名物トリオ——五郎、まゆみ、輪島一平——の物語が動き出す。
● スポーツ万能少年の助っ人騒動
新聞部員として取材に奔走する五郎だったが、その運動能力の高さから、他のクラブから次々と助っ人依頼が舞い込む。野球部、サッカー部、柔道部、陸上部——どこへ行っても大活躍の五郎は、瞬く間に学園のヒーロー的存在となる。しかし、彼の無邪気な行動は時にトラブルも呼び込んだ。助っ人ばかりに力を注ぐ五郎に対し、新聞部員たちは「取材そっちのけで何をやっているの」と呆れ返る。特にまゆみは、責任感の強さゆえに五郎の自由奔放さに腹を立てるが、同時に彼のひたむきさに惹かれていく自分に気づき始める。
五郎の口癖「爆発だ!」が初めて飛び出すのもこの頃。怒りや情熱が頂点に達すると、彼は信じられない力を発揮し、周囲の誰もが唖然とする。拳を握りしめ、瞳を燃やす五郎の姿は、スポーツアニメの王道的カタルシスを見事に体現していた。
● 青空学園を揺るがす事件と絆
物語中盤では、青空学園を舞台に数々の事件が起こる。柔道部の暴走、文化祭の予算トラブル、女子バレー部の人間関係の軋轢、そして学園新聞に掲載された誤報問題——。新聞部の活動を通じて、五郎たちは事件の真相を追いかけ、時に対立し、時に助け合いながら成長していく。
柔道部の部長・荒熊源太は当初、五郎を田舎者扱いしていたが、ある試合をきっかけに彼の真の実力と誠実さを認め、固い友情を結ぶようになる。その一方で、源太のライバルである副部長・鬼丸武は、五郎への嫉妬から陰湿な策略を巡らせ、学園全体を巻き込む混乱を引き起こす。五郎は鬼丸に真っ向から立ち向かい、時には拳を交えながらも「相手を倒すこと」より「正義を通すこと」を学んでいく。
● 新聞部の友情と成長
新聞部の活動は、作品を貫くもうひとつの軸となっている。まゆみ、五郎、一平の3人は、それぞれの個性を活かしながら記事づくりに奮闘する。ある時は学園祭の取材、またある時は教師の裏話をスクープするなど、彼らの挑戦は尽きない。特に印象的なのは、学園に転校してきた五郎が「新聞を通じて人の心を動かすこと」の大切さを学んでいく過程だ。拳を振るうことしかできなかった五郎が、言葉の力で仲間を守る姿は、物語後半の成長の象徴となっている。
そして、一平の存在も欠かせない。やや気弱ながらも観察眼の鋭い彼は、時に二人の仲を和ませ、時に冷静な助言を送る。物語の中盤では、彼の撮った一枚の写真が学園を救う決定的な証拠となるエピソードもあり、サブキャラクターでありながら重要な役割を果たしている。
● 友情と恋のはざまで
中盤以降、五郎とまゆみの関係には微妙な変化が生まれる。まゆみは新聞部の責任者として冷静でありたいと願う一方、五郎の無鉄砲さに心を動かされる自分を抑えきれない。五郎もまた、まゆみの存在が次第に自分の行動の支えになっていることに気づく。そんな二人の前に現れるのが、建設会社の令嬢である萩野ユリだ。五郎に想いを寄せる彼女の登場によって、物語は恋愛的な要素も帯び始める。まゆみとユリ、二人の少女の間で揺れる五郎の心模様は、当時の少年アニメとしては異例の繊細さを持って描かれた。
● 終盤 ― 青空学園の危機と五郎の“爆発”
物語終盤では、青空学園を廃校の危機に追い込む大事件が発生する。原因は学園周辺の再開発計画による地上げ問題。学校の敷地を狙う企業の裏に、かつてのライバル・鬼丸の父親が関与していることが発覚する。生徒たちは立ち上がり、新聞部が中心となって真実を暴く特集記事を作成する。しかし、圧力をかけられた教師や保護者たちは沈黙を選び、学園は孤立していく。
絶望の中、五郎は「自分たちの学園を守るのは自分たちだ!」と叫び、全校生徒を率いて抗議デモを展開。豪雨の中、彼が拳を突き上げて放つ「爆発だ!!」の一言は、まさに物語のクライマックスを飾る象徴的シーンだ。この瞬間、五郎は単なる喧嘩っ早い少年から、仲間のために戦う“リーダー”へと成長を遂げる。
● エピローグ ― 新たな青空の下で
最終話では、五郎たちの奮闘が実を結び、学園は再建の道を歩み始める。新聞部は最後の号で「私たちは爆発し続ける」と題した記事を発行し、それぞれの進路へと歩み出す姿が描かれる。五郎は「今度は全国大会で爆発してみせる!」と笑いながら走り去り、まゆみはその背中を見送りながら静かに微笑む。爽やかな夕焼けを背景にしたラストシーンは、昭和アニメらしい感傷と希望に満ちた幕引きであり、多くの視聴者が涙した名場面として語り継がれている。
● ストーリー全体を通しての特徴
『ばくはつ五郎』の物語は、単なる学園コメディでもスポ根ドラマでもない。友情・努力・恋愛・社会問題という多層的なテーマが交錯し、それぞれが丁寧に描かれている。五郎の「爆発だ!」は、怒りだけでなく、情熱・勇気・信念の象徴として作品全体を貫くキーワードだ。青春期の迷いや不安を抱えながらも、仲間と共に立ち上がる少年たちの姿は、50年以上経った今も新鮮な感動を与える。
[anime-2]■ 登場キャラクターについて
● 大石五郎 ― 爆発的情熱の象徴
本作の主人公である大石五郎は、まさにタイトル「ばくはつ」の名にふさわしい少年である。青空学園の2年A組に転校してきた彼は、どんなスポーツでも人並み外れた能力を発揮するが、それ以上に際立つのが彼の人間的魅力だ。 彼は正義感の塊であり、困っている仲間を見捨てられない。時に無鉄砲で、時に喧嘩早いが、その行動の根底には「誰かのために力を尽くしたい」という純粋な思いがある。そんな五郎の心情を象徴するのが、怒りや決意の瞬間に放たれる口癖「爆発だ!!」だ。この言葉は単なるスローガンではなく、彼の内面から湧き上がる情熱の具現化ともいえる。
物語を通じて、五郎は単なる熱血少年から「仲間のリーダー」へと成長していく。新聞部という舞台で、彼は「拳で語る」から「言葉で伝える」へと変わっていく過程を経験する。まゆみや一平との出会い、柔道部との対立、鬼丸との因縁を通じ、五郎は友情・努力・責任の意味を学び、視聴者に「強さとは何か」を問いかける存在へと昇華していく。
その姿勢はまさに昭和期の少年像の理想形であり、時代を超えて視聴者の心に響くキャラクターとなっている。
● 三枝まゆみ ― 強さと優しさを併せ持つヒロイン
新聞部の部長にして、作品のヒロインである三枝まゆみは、当時の女性キャラクター像としては非常に先進的だった。彼女はただの「主人公の恋の相手」ではなく、物語を支えるもう一人の主軸といえる存在だ。 頭脳明晰でリーダーシップがあり、時に男勝りの口調で五郎を叱責するが、その裏には深い仲間思いと誠実さがある。記事づくりにかける情熱は誰よりも強く、新聞部を通じて「真実を伝える使命感」を貫く姿は、当時の少女視聴者からも大きな支持を得た。
五郎との関係は、当初は衝突の連続だった。まゆみは五郎の奔放さに呆れつつも、その純粋さに惹かれていく。一方で、彼をただの助っ人や部員としてではなく、一人の人間として認めていく過程が丁寧に描かれており、恋愛未満の淡い感情が視聴者の共感を呼んだ。まゆみが流す一瞬の涙や、照れ隠しの笑顔は、本作の中でも最も印象的な情景の一つとして語り継がれている。
● 輪島一平 ― コミカルな潤滑剤
五郎とまゆみの仲を見守る形で、物語に柔らかさとユーモアをもたらすのが輪島一平だ。彼は眼鏡をかけた丸刈り頭の少年で、どこか頼りないが憎めない性格をしている。新聞部ではカメラマンを担当し、取材活動では常にカメラを片手に走り回っている姿が印象的。語尾に「~ざんす」とつけて話す癖があり、個性的なキャラクターとして作品にアクセントを加えている。
一平はお調子者のようでいて、実は仲間をよく観察しており、時に核心を突く一言を放つ。彼の撮影した写真が事件の真相を暴く鍵となるエピソードは、新聞部の活動を象徴する場面だ。また、五郎とまゆみが対立したとき、さりげなく両者の仲を取り持つ姿は、彼の優しさと誠実さを感じさせる。
彼の存在がなければ、新聞部の空気はもっと重く、衝突だらけのものになっていただろう。輪島一平は、『ばくはつ五郎』の物語に“笑い”と“癒し”を添える名脇役である。
● 荒熊源太 ― 学園の兄貴分
青空学園柔道部の部長であり、筋骨隆々の3年生・荒熊源太は、最初は五郎に敵対するが、やがて深い友情で結ばれる人物だ。彼は一見粗暴で口が悪いが、実は責任感が強く、仲間思いのリーダータイプ。柔道部の誇りを守るために五郎と対立するシーンは、スポーツアニメとしての緊張感を高める重要な局面である。
源太は五郎の「爆発だ!」という精神に共鳴し、次第に「本当の強さとは、相手を倒すことではなく、自分に負けないこと」だと悟っていく。彼の内面的な成長は、物語全体のテーマと呼応しており、のちの青春アニメにおける“熱血ライバルの友情”という定型を形作った存在ともいえる。
彼の声を担当した細井重之の低く響く声質もキャラクターの威厳を際立たせ、源太という人物をより立体的に印象づけている。
● 鬼丸武 ― 嫉妬と誤解の中のもう一つの主人公
五郎のクラスメートであり、柔道部副部長の鬼丸武は、本作における“影の主人公”ともいえる存在だ。彼は五郎の才能に嫉妬し、執拗に対抗心を燃やす。だがその行動の根底には、認められたい、負けたくないという純粋な感情がある。 鬼丸はしばしば学園内でトラブルを起こし、五郎と衝突する。しかし物語が進むにつれ、彼の孤独や劣等感が描かれるようになり、視聴者の見方も変化していく。最終話近くでは、五郎と拳を交えながら互いを理解し合う名場面があり、「敵から友へ」という王道の展開に胸を熱くしたファンも多い。
彼の存在が、五郎の成長を際立たせると同時に、青春期の“競い合いの中で生まれる絆”を象徴しているのだ。
● 萩野ユリ ― 優しさと葛藤の中の少女像
地元の建設会社社長の一人娘である萩野ユリは、物語中盤から登場する新キャラクター。五郎に淡い恋心を抱き、彼の活動を影で支えるが、まゆみへの複雑な感情に揺れる姿が丁寧に描かれている。 ユリは当初、新聞部を敵視するが、まゆみの芯の強さや五郎の誠実さに触れ、次第に協力者となっていく。裕福な家庭に育ちながらも、孤独を感じている彼女の描写には、当時の少女アニメにはなかった繊細な心理描写が見られる。 後半では、学園再建をめぐるエピソードで重要な役割を担い、行動力と優しさを兼ね備えたキャラクターとして成長していく。
● 教師たちと学園の大人たち
『ばくはつ五郎』では、教師や大人たちの描かれ方も特徴的だ。新聞部顧問の浜田寅之助(通称ハマトラ)は、頑固だが愛情深い指導者であり、五郎たちの暴走を時に叱り、時に陰から支える。また、教頭の赤原は典型的な保守的管理職として描かれ、生徒たちと対立することが多いが、物語終盤で彼なりの信念を見せるシーンもある。これらのキャラクターが物語に社会性とリアリズムを与え、学園の世界を立体的にしている。
● サブキャラクターたちの息づかい
五郎たちのクラスメートや柔道部員、教師陣など、脇を固めるキャラクターたちも非常に印象深い。たとえば、剣道部の細川忠文は体が弱いながらも剣の道を貫く努力家で、五郎に「本当の根性」を教える存在。また、柔道部員の清水や女性教師の斉藤先生など、短い登場ながらも物語に彩りを添える。 こうした“モブキャラ”でさえも、一人ひとりに明確な個性と人生が感じられる点こそ、『ばくはつ五郎』の脚本の丁寧さを物語っている。
● キャラクター描写の総括
『ばくはつ五郎』のキャラクター群は、誰もが“未完成”であることが魅力だ。五郎の未熟な正義感、まゆみの揺れる感情、一平の臆病な勇気、鬼丸の歪んだ友情――それぞれが成長を通じて人としての“爆発”を経験していく。 その過程が視聴者の共感を呼び、どの登場人物も単なる背景に終わらない。昭和アニメの中でも、これほど多面的に人物を描いた作品は稀であり、『ばくはつ五郎』が時代を超えて語り継がれる理由の一つでもある。
[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
● オープニングテーマ「ばくはつ五郎」 ― 熱血と爽快感の象徴
アニメ『ばくはつ五郎』の幕開けを飾るオープニングテーマ「ばくはつ五郎」は、昭和アニメ史に残る勢いとエネルギーを持った楽曲である。作詞は橋本淳、作曲・編曲は和田昭治、歌唱は男性コーラスグループザ・ワンダースによって担当された。彼らの明るくハリのある声が、五郎の持つ熱血魂と見事に呼応しており、イントロから最後まで一気に駆け抜けるような疾走感が印象的だ。
イントロのブラスとドラムのリズムが高らかに鳴り響くと、視聴者の胸にも自然と高揚感が広がる。「燃えろ五郎よ!」「立ち上がれ五郎!」といった歌詞は、まるで主人公の背中を押す応援歌のように響く。昭和の少年たちにとって、この曲は単なるアニメ主題歌ではなく、“自分も頑張ろう”という勇気を与えてくれる生活の一部であった。
特に印象的なのは、曲の中盤で挿入される短いコーラスパートだ。ザ・ワンダースが力強く「爆発!爆発!」と唱和する部分は、アニメの象徴的フレーズ「爆発だ!!」を音楽的に再構築したもので、作品世界と音楽が一体化していることを感じさせる。レコード盤のジャケットには、燃えるような赤い背景に五郎が拳を突き上げる姿が描かれており、まさに当時の“熱血アニメ”のアイコン的存在となった。
● エンディングテーマ「涙はともだち」 ― 優しさと希望の余韻
一方、エンディングテーマ「涙はともだち」は、オープニングとは対照的に穏やかで温かみのある曲調が特徴である。作詞・作曲陣は同じく橋本淳と和田昭治のコンビで、歌唱は再びザ・ワンダース。だがこちらは、男性コーラスの柔らかなハーモニーを中心に構成され、視聴者の心を静かに包み込むような優しさに満ちている。
「涙はともだち 笑顔をくれる」「悲しいときこそ前を見ろ」――このフレーズは、主人公・五郎が経験する挫折や苦しみを象徴している。特に物語後半、学園廃校の危機や仲間との別れを描くエピソードでは、この曲が流れるエンディングに視聴者が涙したというエピソードも多い。
当時のアニメ主題歌の多くが明るくテンポの速いものだった中で、このバラード調のエンディングは異色の存在だったが、むしろその静けさが物語の余韻を深め、“五郎たちの日常”の温かさを感じさせるものとなっていた。
● 挿入歌「青空学園校歌」 ― 学園の象徴として
『ばくはつ五郎』には、作品世界を支える象徴的な挿入歌も存在する。そのひとつが「青空学園校歌」だ。作詞は林春生、作曲・編曲は司一郎によるもので、歌唱はやはりザ・ワンダース。学校生活の明るさと青春の清々しさを感じさせる軽快なメロディーで、五郎たちが所属する青空学園を象徴する“テーマソング”的役割を果たしている。
この曲は劇中でたびたび合唱されるが、特に印象的なのは、文化祭の回で全校生徒が肩を組んで歌うシーンだ。五郎やまゆみたちの笑顔と共に響くコーラスは、観ている者に「青春っていいな」と感じさせる力があった。音楽の力で友情や連帯を表現する手法は、当時としては新鮮であり、のちの学園アニメや青春群像劇にも影響を与えたといわれている。
● 応援歌「青空学園応援歌」 ― スポ根アニメの熱を象る一曲
もうひとつの挿入曲「青空学園応援歌」は、同じく林春生と司一郎のコンビによる制作で、こちらはまさに“スポ根アニメの王道”といえる熱いナンバーだ。 試合や大会のシーンで流れるこの曲は、ブラスの力強い伴奏とテンポの速いリズムが特徴。五郎たちがピンチに立たされたとき、この応援歌がBGMとして流れることで、観ている視聴者も思わず拳を握りしめてしまうような臨場感を生み出していた。
特に、柔道部との試合シーンで五郎が逆転勝利を収める瞬間に流れるアレンジ版「応援歌~闘魂Ver.~」は、当時のファンの間で伝説的存在となっている。サントラ未収録であったため、近年でもファンの間で復刻を望む声が根強い。
● 音楽スタッフと録音現場の裏話
『ばくはつ五郎』の音楽を支えた作曲家・和田昭治は、当時東映やTBS系の多くの作品で劇伴を手掛けていたベテランである。彼の音楽は、勢いのあるマーチ風の主題歌と、叙情的なバラードの対比を得意としており、本作でもそのスタイルが遺憾なく発揮された。 録音は東京・赤坂のTBSスタジオで行われ、当時まだ4チャンネル録音が主流の時代において、試験的に8チャンネル収録を採用したといわれている。これにより、コーラスとブラスセクションの分離感がより明確になり、厚みのあるサウンドが実現した。
また、主題歌収録時には、歌手たちが実際に拳を握って“爆発ポーズ”を取りながら歌ったという逸話も残っている。録音現場でも「五郎のように情熱をこめろ!」というディレクターの掛け声が飛び交い、まさに作品そのもののような熱気に包まれていたという。
● レコード・音源の展開とファンの反響
放送当時、主題歌2曲と挿入歌はEP盤(ドーナツ盤)としてコロムビアレコードから発売された。ジャケットには五郎のイラストが描かれ、裏面には歌詞カードが付属。学校で友人同士が口ずさみながら“爆発ポーズ”を真似する姿が見られるほど、子どもたちの間で大人気となった。 現在では、これらのレコードは中古市場で非常に高値で取引されており、特に帯付き・美品の状態では1万円以上の値が付くこともある。
さらに、2009年のTBSチャンネルでのデジタルリマスター放送時には、音源もリマスター化され、限定CDとして復刻された。オープニング・エンディングだけでなく、未使用BGMや短縮版も収録されており、往年のファンにとってはまさに“宝物”といえるリリースであった。
● 音楽が描いた『ばくはつ五郎』の精神
『ばくはつ五郎』の音楽群は、単なる映像の伴奏ではなく、物語の精神そのものを表現していた。オープニングで燃え上がり、エンディングで包み込み、挿入歌で鼓舞する――この音楽の構成が、作品全体を通して“情熱・友情・成長”というテーマを支えていた。
特に、オープニングの明快さとエンディングの優しさの対比は、五郎のキャラクターそのものを反映している。彼は怒れば爆発的に力を発揮するが、根は誰よりも繊細で、仲間思い。音楽がその二面性を的確に描き出していたことが、作品の完成度を高める重要な要素だった。
『ばくはつ五郎』のサウンドトラックは、昭和アニメの中でも“青春”というテーマを音で描いた稀有な存在であり、今なお多くのファンに愛され続けている。
[anime-4]■ 声優について
● 主人公・大石五郎を演じた中山輝夫 ― 昭和の熱血を体現した声
『ばくはつ五郎』の中心に立つのは、やはり主人公・大石五郎を演じた中山輝夫である。彼は当時、少年役や青年役を多く務めた中堅声優であり、力強くも柔らかい発声が特徴だった。 中山の演技は、五郎というキャラクターの“二面性”――荒々しさと優しさ――を見事に表現している。喧嘩シーンでは腹の底から絞り出すような怒声を放ち、友情の場面ではどこか照れくさそうに声を震わせる。その繊細な演技の幅が、五郎というキャラクターを単なる熱血少年ではなく、人間味あふれる存在に仕立て上げていた。
特に名演として知られているのが、第18話「爆発!友情の炎」だ。仲間を守るために自ら退学の危機を覚悟で行動する五郎の苦悩を、中山は一切の誇張なくリアルに演じきった。台詞の間に息を詰まらせるような呼吸表現を入れるなど、当時の声優としてはかなり実験的なアプローチであり、ファンの間でも「中山輝夫の代表作」として語り継がれている。
録音ディレクターによると、中山は収録中に実際に拳を握りしめながら「爆発だ!!」の台詞を発したという。その本気の姿勢が、作品全体の熱量を支えていたのは間違いない。
● 三枝まゆみ役・杉山佳寿子 ― 聡明で芯のあるヒロイン像を創出
新聞部の部長・三枝まゆみを演じたのは、当時すでに『巨人の星』や『魔法使いサリー』などで人気を博していた杉山佳寿子である。彼女の澄んだ声質は、少女らしさを保ちながらも、知性と芯の強さを感じさせる独特の魅力を持っていた。
まゆみというキャラクターは、時に五郎を叱責し、時に支え、時に涙を見せる複雑な存在である。杉山はその感情の振れ幅を、繊細なトーンコントロールで巧みに演じ分けた。
特に印象的なのは、五郎が退学をかけた柔道試合に出場する回で、まゆみが「信じているわ、五郎!」と叫ぶ場面。その瞬間、彼女の声には祈りにも似た震えがあり、視聴者の胸を打った。
後年、杉山はインタビューで「まゆみは理想のヒロインではなく、ひとりの“同級生”のように演じた」と語っている。彼女のナチュラルな芝居が、この作品の“青春群像劇”としてのリアリティを支えたと言っても過言ではない。
● 輪島一平役・小宮山清 ― コミカルと誠実の絶妙バランス
五郎とまゆみの親友・輪島一平を演じたのは小宮山清。彼はコメディリリーフ的な役どころでありながら、感情表現の幅が広い声優として知られていた。 一平の特徴的な口癖「~ざんす」は、小宮山のアイデアによってアドリブ的に加えられたものだという。当初の脚本では標準語だった台詞が、彼の演技でコミカルかつ個性的なキャラクターへと変貌したのだ。 小宮山の声は鼻にかかった柔らかなトーンで、緊張感ある場面にも笑いを添えるバランス感覚があった。新聞部の掛け合いで重くなりがちな空気を、一平の一言で一気に和ませる――その絶妙な“間”が、作品全体のテンポを軽快に保っていた。
● 荒熊源太役・細井重之 ― 豪快な声に宿る人情味
柔道部長・荒熊源太を演じたのは細井重之。重低音の響きを持つ彼の声は、荒熊の豪快さと頼もしさを見事に体現している。 彼の演技の特徴は、豪快な笑い声と怒鳴り声の中にも滲む“人情”だ。初登場時の威圧的な態度から、後半で五郎に友情を示すまでの感情変化を、声のトーンひとつで表現している。 特に、第14話「友情一本勝負」での「お前、爆発してるな……いい顔だ」の台詞は、荒熊という男の優しさを象徴する名言としてファンに愛されている。 当時の録音は一発撮りが多く、細井は「勢いを殺さずに演じる」を信条にしており、その“生きた芝居”が今も映像の中に息づいている。
● 鬼丸武役・矢田耕司 ― 迫力と哀愁の悪役演技
五郎のライバルであり宿敵ともいえる鬼丸武を演じたのは矢田耕司。彼は悪役を数多く演じたベテラン声優で、低く渋い声と独特の節回しが特徴だった。 鬼丸は単なる嫌がらせキャラではなく、嫉妬・孤独・誤解といった複雑な感情を抱える人物。矢田の演技は、そうした内面の“陰”を見事に表現していた。 初期の頃の鬼丸は怒鳴り声ばかりだが、後半になると声のトーンを抑え、苦悩を滲ませる演技に切り替わる。最終回での「お前には敵わねぇな、五郎……」の一言は、まさに矢田耕司の低音の魅力が最大限に発揮された瞬間である。 当時、彼の演技を真似して「オレも鬼丸だ!」と叫ぶ子どもが続出したという逸話も残っており、その人気ぶりは五郎に匹敵した。
● その他のキャストと作品を支えた名脇役たち
本作では、メインキャスト以外にも実力派声優が数多く出演している。 青空学園の教頭・赤原を演じた納谷悟朗は、威圧感とユーモアを併せ持つ絶妙な演技で存在感を発揮。校長役の勝田久の穏やかな語り口との対比が、学園にリアリティを与えた。 また、柔道部員の清水を演じた肝付兼太は、後の『ドラえもん』スネ夫役で知られるが、本作では意外にも“やられ役”として軽妙な芝居を披露。女性教師・斉藤先生を演じた栗葉子も、クラスを見守る温かい声で印象を残している。
こうした名脇役たちの演技の積み重ねが、『ばくはつ五郎』を単なる学園コメディではなく、人物の温もりを感じさせる人間ドラマへと昇華させている。
● 昭和アニメ声優文化の中での位置づけ
1970年前後は、声優という職業がまだ一般的に知られていなかった時代である。アニメ声優は舞台俳優やナレーターが兼任することが多く、演技は“声芝居”よりも“実演の延長”という感覚が強かった。 そんな中で、『ばくはつ五郎』のキャスト陣は、声のみで感情を伝える“演技の新しい形”を模索していた。セリフの間、息遣い、叫びのタイミング――それらを緻密に計算し、キャラクターの人間性を作り上げていく姿勢は、後のアニメ表現の礎を築いたといえる。
五郎役の中山が叫ぶ「爆発だ!!」は、声優演技が単なる台詞の発話ではなく“感情の発露”であることを証明した瞬間であり、それはまさに声優文化の転換点だった。
● 現代に受け継がれる“声”の記憶
2009年のデジタルリマスター放送では、当時の音源が再調整され、声優陣の演技がよりクリアに蘇った。特に中山輝夫や杉山佳寿子の声の表情が鮮明に聴こえることで、視聴者は再び当時の熱気を体感できたという。 アニメファンの間では、「この作品を聴くと声優という仕事の原点がわかる」と語られることも多く、演技教育の教材として取り上げられる例もある。
声優陣の真摯な姿勢と、作品への愛情が詰まった『ばくはつ五郎』のアフレコ。その“声の記憶”は、半世紀以上たった今も、画面の向こうから確かに聞こえてくるようだ。
[anime-5]■ 視聴者の感想
● 放送当時の子どもたちの熱狂
1970年の放送当時、『ばくはつ五郎』は小・中学生を中心に高い人気を集めた。視聴者から最も多く寄せられたのは、「五郎の“爆発だ!!”が忘れられない」「次の日学校で真似した」といった声だった。放送翌日の学校では、休み時間に机を叩きながら「爆発だ!」と叫ぶ子どもが続出し、教師が呆れるほどだったというエピソードも残っている。
この作品は、単なる勧善懲悪のアクションアニメではなく、等身大の中学生が葛藤しながら成長する姿を描いた点が共感を呼んだ。当時の少年たちは、自分たちと同じように悩みながらも真っ直ぐに進もうとする五郎に自分を重ね、憧れを抱いたのだ。「五郎は強いけれど、泣くときもある。それがかっこよかった」という当時のファンの回想は、その象徴といえる。
● 少女視聴者が見た“まゆみ”の魅力
当時の少女層にも、この作品は意外なほど支持された。特に、ヒロインの三枝まゆみが人気を集め、「ただの恋愛相手ではなく、強くて頼もしい女子」として多くの共感を得ていた。1970年当時のアニメ界では、女性キャラクターがサブ的な立場に置かれることが多かった中で、まゆみのように自立心が強く、男の子に堂々と意見するヒロインは新鮮だった。
当時のファンレターには、「まゆみみたいになりたい」「新聞部に入りたくなった」といった声が多く寄せられている。また、五郎とまゆみの“ケンカするほど仲が良い”関係性がリアルで、少女たちはその微妙な距離感に胸をときめかせたという。
まゆみが五郎の無茶を叱りながらも、最後には優しく微笑む――そんな小さな表情の変化が、女性視聴者の心を強く掴んでいたのだ。
● 家族そろって楽しめる学園ドラマ
『ばくはつ五郎』は、当時のアニメでは珍しく「家族で見られる作品」としても高く評価された。放送時間が金曜19時というゴールデン枠だったこともあり、夕食後に家族全員でテレビの前に集まる家庭が多かった。 親世代からも「五郎の礼儀正しさや努力を見て、うちの子にも学んでほしい」「最近の若い子には珍しい真っ直ぐさだ」といった感想が寄せられている。
また、学園生活の中で描かれる先生や地域社会との関わりが、リアルな時代描写として評価された。高度経済成長期の真っ只中で、変わりゆく日本の姿を背景にしながらも、人情味や義理・人の絆を重視するメッセージが込められていたため、親子で観ても共通の感動を味わえたのだ。
五郎がトラブルを起こすたびに、彼を叱りながらも理解しようとする教師や大人たちの存在も、「昔ながらの温かい教育」として懐かしむ声が多かった。
● 熱血だけでなく“人間ドラマ”としての評価
放送から年月が経つにつれ、『ばくはつ五郎』は単なるスポ根アニメではなく、青春群像劇としての完成度が再評価されるようになった。特に大人になってから再視聴した視聴者からは、「子どもの頃は五郎の熱さしか見ていなかったが、今見るとまゆみや先生たちの心情が深い」との声が多く寄せられている。
五郎が他人のために怒り、まゆみが責任と理想の狭間で揺れる姿は、社会人の葛藤にも通じる。こうした心理描写の丁寧さが、後年のファンに「昭和アニメの中で異色のリアリティを持つ」と称される所以である。
SNSやアニメ専門掲示板でも、「泣けるスポ根」「昭和の心が詰まっている」という感想が相次ぎ、近年では“忘れられた名作”として若い世代のアニメファンにも注目されている。
● 音楽とともに蘇る記憶
特に主題歌「ばくはつ五郎」とエンディング「涙はともだち」は、視聴者の記憶に深く刻まれている。昭和世代のファンの間では、「イントロを聞くだけであの夕焼けが浮かぶ」「エンディングで涙が出た」といった感想が非常に多い。 五郎が仲間とぶつかりながらも笑って走り去るラストカットと、ザ・ワンダースの柔らかいコーラス――その組み合わせが多くの人に“青春”という言葉を思い起こさせるのだ。
また、2009年にTBSチャンネルで放送されたデジタルリマスター版を見たファンからは、「音がクリアになって、声優さんの演技がよりリアルに感じられる」「あの頃の自分が甦ったようだ」といった感想も多く寄せられている。音楽と映像の調和が、記憶の中の“あの時代”を鮮やかに呼び起こしたのだろう。
● 世代を超えた共感と“昭和アニメの温度”
『ばくはつ五郎』が放送から50年以上経った今も語り継がれている理由は、そこに“人間の温度”があるからだ。 最新技術で作られたアニメにはない、手描きの線の揺らぎ、声優の息づかい、音楽の温かみ。それらが一体となり、視聴者に「人と人がぶつかりながらも分かり合う尊さ」を伝えている。
現代の若者が本作を観ても、「キャラクターが古臭い」と感じるよりむしろ、「こんなに真っ直ぐな人たちが羨ましい」と感想を述べるケースが多い。SNS上では、「昭和のアニメなのに心が刺さる」「CGには出せない人間味」といった投稿が多く見られる。
五郎たちの友情や努力の姿勢は、時代を超えて共感を呼ぶ“普遍的な青春”そのものなのだ。
● 視聴者が選ぶ印象的なエピソード
アンケートやネット投票では、特に人気が高いエピソードとして以下の3話がよく挙げられる。
第8話「新聞部大ピンチ!」
新聞部の誤報事件を通じて、五郎たちが“言葉の責任”を学ぶ回。視聴者からは「大人になっても印象に残る教訓」として評価が高い。
第14話「友情一本勝負」
荒熊との柔道勝負を描いた名エピソード。「力だけでは友情はつかめない」というセリフが、多くのファンの心に残っている。
最終話「青空よ、永遠に」
学園廃校の危機を乗り越え、五郎たちが新たな未来へ踏み出す感動の最終回。放送当時、視聴者から「涙が止まらなかった」との感想が殺到したという。
これらのエピソードは、作品の魅力である“笑い・涙・成長”のすべてを凝縮しており、再放送や映像ソフトで初めて観た世代からも高い評価を得ている。
● 再放送・映像化後の世代の声
昭和当時の子どもだけでなく、2000年代の再放送をきっかけに本作を知った世代も多い。TBSチャンネルでの再放送時、SNSには「親が子どものころ見ていたアニメを一緒に観た」「今の作品にはない真っ直ぐさに泣いた」といった親子2世代の声が多く投稿された。 特に昭和アニメ特集番組で『ばくはつ五郎』が紹介されると、「この作品を見て自分も新聞部に入った」「五郎の言葉に勇気をもらった」といった“後追いファン”のコメントが増えたのが印象的である。
また、アニメ史研究の文脈でも「初期スポ根作品と青春群像劇の橋渡し的存在」として位置づけられるようになり、専門誌『アニメスタイル』や『昭和TV回想録』でも特集が組まれた。学術的にも評価が進んでいることは、ファンにとって大きな誇りと言える。
● 感想の総括 ― 視聴者が感じた“爆発”の意味
多くの視聴者が口を揃えて語るのは、「『ばくはつ五郎』は心を爆発させてくれるアニメだった」ということだ。怒り、涙、友情、努力――それらを我慢せずに出すことの美しさを、この作品は教えてくれる。 視聴者の中には、「五郎のようにまっすぐ生きたい」と語る人もいれば、「大人になってから見ると涙が止まらない」と言う人もいる。時代は変わっても、五郎の叫びは変わらない。“爆発だ!!”という一言が、今もなお多くの人の心を震わせている。
[anime-6]■ 好きな場面
● 第1話「転校生・五郎登場!」 ― 青空学園に走る衝撃
多くのファンがまず印象に残っているのが、第1話の五郎初登場シーンだ。転校初日、遅刻ギリギリで校門を飛び越える五郎。その瞬間、靴底が地面を蹴る音と共に「爆発だ!!」と叫びながら着地する姿が描かれ、視聴者は一瞬でそのエネルギーに惹き込まれた。 教室に入っても騒ぎは収まらず、自己紹介の途中でクラスメートに絡まれた五郎は、咄嗟に机を跳び越えて相手の頭上に着地。担任教師が慌てて止めに入ると、五郎は照れくさそうに笑い、「すんません、力が入っちまって」と肩をすくめる。その明るさと豪快さが、彼の魅力を最初から視聴者に焼き付けた瞬間だった。 この場面は後のシリーズ全体の“導火線”ともいえる存在で、五郎というキャラクターがどんな人物か――明朗快活・正義感の塊・そして少しの不器用さ――を見事に表している。
● 第8話「新聞部大ピンチ!」 ― “言葉の責任”を学ぶ五郎
作品中盤の名エピソードとして必ず挙げられるのが、新聞部の誤報事件を描いた第8話だ。五郎たちは、学園の教師が不正をしたという噂を記事にしてしまい、学校中を大混乱に陥れてしまう。 この回で印象的なのは、真実を確かめずに記事を書いたことを後悔する五郎の姿だ。まゆみに責められ、拳を握りしめながら「俺、言葉でも人を傷つけちまうんだな……」と呟くシーンは、熱血アニメとしてだけでなく、人間ドラマとしても心に残る。 後半で、誤解が解けた後に五郎が号外を発行し、全校生徒の前で謝罪する場面は、涙なしには見られない。彼の真っ直ぐな姿勢が、視聴者の心を強く打った名シーンである。
● 第14話「友情一本勝負」 ― 荒熊源太との熱き柔道対決
ファンの間で伝説的なエピソードとされているのが、柔道部長・荒熊源太との一騎打ちを描いた第14話である。 序盤、五郎は柔道部の助っ人を頼まれるが、部員たちの高慢な態度に反発し、試合を放棄してしまう。だが後日、荒熊が「男なら逃げるな!」と挑発し、ついに五郎は道場へ。観客が息をのむ中、両者が組み合った瞬間の作画の迫力は、1970年代初期のテレビアニメとしては驚くほど躍動感にあふれている。 勝負の最中、五郎が押さえ込まれながらも「爆発だ!!」と叫び、力を振り絞って投げ飛ばす――その瞬間、流れる「青空学園応援歌」が場面を一層盛り上げる。 試合後、荒熊が五郎に握手を求めて「お前、爆発してたな」と笑うシーンは、敵対から友情への変化を象徴する名場面としてファンの心に残っている。
● 第18話「涙のラストラン」 ― まゆみと五郎の心の距離
シリーズ屈指の感動回とされるのが、第18話「涙のラストラン」だ。この回では、学園のマラソン大会に出場した五郎が、まゆみとの関係に悩みながら走り抜く姿が描かれる。 レースの途中で転倒し、足を負傷する五郎。まゆみは「もう棄権して!」と叫ぶが、五郎は涙をこらえて「泣くなまゆみ、涙はともだちだろ!」と言い返す。その台詞がエンディング曲のタイトルと呼応しており、音楽と物語が見事に一体化した瞬間だ。 ラストシーンでは、夕焼けの校庭で五郎がゴールに倒れ込み、まゆみがそっとハンカチで彼の額の汗を拭う。その静かな余韻が、作品全体のテーマ「努力と絆」の本質を語っている。視聴者の中には、この回を見て初めてアニメで泣いたという人も多い。
● 最終話「青空よ、永遠に」 ― 爆発する青春の締めくくり
最終回は『ばくはつ五郎』の集大成とも言える感動のエピソードである。青空学園が廃校の危機に直面し、五郎たちが力を合わせて立ち向かう展開は、これまで積み重ねてきた友情と信念の結晶だ。 新聞部が発行する最後の号には「われら爆発す!」という見出しが踊り、生徒全員が校庭に集まって涙と笑顔で歌う「青空学園校歌」。その中で五郎がまゆみに向かって「俺たちの爆発は、終わらない!」と叫ぶシーンは、多くの視聴者が胸を熱くした瞬間だ。
最後のカットでは、夕焼けを背に五郎が走り去る姿が映し出され、ザ・ワンダースの「涙はともだち」が静かに流れる。エンディングの映像が切り替わる瞬間、五郎の笑顔が一瞬だけこちらを振り向く。そのわずかな一コマに、「青春は続く」という希望が凝縮されていた。ファンの間では今でも、「最終回は完璧なエンディング」と語り継がれている。
● コミカルな名場面 ― 輪島一平の大活躍回
感動シーンだけでなく、コメディ要素も本作の大きな魅力だ。輪島一平が中心となる回は、特に視聴者から“癒し回”として人気が高い。 第10話「スクープ!? 一平の大失敗」では、一平が誤って教師の秘密を記事にしてしまい、学園が大騒ぎに。謝罪に奔走する彼の姿と、最終的に“偶然の真実”を掴んでヒーローになる展開は、笑いと爽快感を兼ね備えている。 彼がまゆみの真似をして「編集長ざんす!」と叫ぶ場面や、カメラのフラッシュで鬼丸の目をくらませるシーンなど、緩急の効いたギャグ演出が随所に見られた。こうした軽妙な笑いが、全体のシリアスなドラマに対して見事なバランスを保っていた。
● 音楽と映像が融合する感動演出
『ばくはつ五郎』の名場面の多くは、音楽演出の巧みさとセットで語られる。特に、「青空学園応援歌」が流れる試合シーン、「涙はともだち」が重なる別れの場面、「ばくはつ五郎」がアレンジされる最終決戦など、BGMのタイミングが絶妙だ。 当時のアニメとしては珍しく、キャラクターの心情変化に合わせてテンポを変化させる“感情シンクロ型”の音楽演出を採用しており、映像と音の融合が視聴者の感情を自然に導く。ファンの間では「この作品で音楽の重要さを知った」と語る人も多い。
また、夕焼けや風、雨などの自然描写が感情を象徴的に映し出す演出も特徴的だった。特に最終話の雨の中でのデモシーンで、五郎が「爆発だ!!」と叫ぶ瞬間に雷鳴が重なる演出は、まさに“絵と音の爆発”として語り継がれる名場面である。
● 視聴者の心に残る“静かな爆発”
『ばくはつ五郎』というタイトルから想像されるような派手なアクションだけでなく、静かなシーンにも多くのファンが心を動かされた。たとえば、五郎が夜の校庭で独り特訓する場面、まゆみが放課後の部室で黙って記事を書く場面、雨上がりの廊下で一平がカメラを拭う場面――どれも大きなセリフがなくても、キャラクターの想いが伝わってくる。
五郎が“爆発”を叫ばない回ほど、心の中で燃える情熱が丁寧に描かれており、視聴者はその“内なる爆発”に共感した。「この作品の本当の爆発は、心の中で起きている」という感想を残したファンもいるほどだ。
● 総括 ― 名場面が伝える永遠のメッセージ
『ばくはつ五郎』の名シーン群は、単に派手なアクションや感動的な演出ではなく、“真っ直ぐ生きることの尊さ”を伝えている。 転校初日の元気な笑顔、友のために流した涙、仲間と笑い合う放課後――どの場面にも「青春の真実」が息づいている。半世紀を経た今もなお、ファンが映像を見返すたびに心が熱くなるのは、その誠実さと純粋さが失われていないからだ。 『ばくはつ五郎』の名場面たちは、いつの時代も人々に「もう一度、自分の中の爆発を信じてみよう」と語りかけ続けている。
[anime-7]■ 好きなキャラクター
● ファンから最も愛された主人公・大石五郎
視聴者人気の中心にいたのは、やはり主人公・大石五郎である。彼の「爆発だ!!」という決め台詞は、当時の少年たちの心を強く掴んだ。学校での人気投票では常に一位を独走し、特に男の子たちの間では「五郎みたいになりたい」「五郎のように友だちを守りたい」という声が多く寄せられた。 五郎の魅力は、単に喧嘩が強いとか、スポーツ万能というだけではない。自分の信じたことを最後まで貫く“真っ直ぐさ”と、仲間を想う優しさが、彼を特別な存在にしている。 ファンの感想の中には「五郎のように、自分の気持ちに嘘をつかずに生きたい」「怒るときも泣くときも、全部本気の姿が好き」という言葉が多く見られ、五郎が象徴する“人間らしさ”そのものが時代を超えて共感を呼んでいる。
また、五郎の声を担当した中山輝夫の力強い演技も人気を支えた大きな要因だ。特に怒鳴り声の中に優しさを感じさせる表現力が、ファンの記憶に深く残っている。中山の演じる五郎は、ただの熱血主人公ではなく、“心に炎を持つ少年”として長年語り継がれている。
● 理想のヒロイン像・三枝まゆみ
「まゆみがいたから『ばくはつ五郎』を見続けた」という女性ファンは非常に多い。彼女の人気の理由は、強さと優しさのバランスにある。五郎と同じくらい情熱的で、正義感がありながらも、他人を思いやる繊細さを併せ持っている。 当時のアニメでは珍しく、ヒロインが“主人公の影”ではなく“もう一人の主役”として描かれていた点が、多くの視聴者に新鮮な印象を与えた。
人気を決定づけたのは、第18話「涙のラストラン」でのまゆみの涙だろう。五郎に向かって「無茶しないで!」と叫ぶ姿は、視聴者の誰もが胸を締め付けられるほどの真剣さだった。
ファンの中には「彼女のような女性に支えられたい」「まゆみの芯の強さに憧れる」と語る人も多く、彼女は昭和アニメの中でも“理想の女性像”として特別な位置を占めている。
後年、声優の杉山佳寿子がインタビューで「まゆみを演じるときは、恋をするよりも“信じる”気持ちで台詞を言っていた」と語っており、その信念がまゆみというキャラクターをより深く魅力的にしていたことがわかる。
● コミカルの申し子・輪島一平
物語に欠かせないムードメーカーとして、視聴者に愛されたのが輪島一平だ。彼は五郎やまゆみとは違い、少し臆病でお調子者。しかし、その人懐っこい性格と仲間思いの姿勢が、多くのファンの共感を呼んだ。 一平の魅力は、“誰よりも普通”であることだ。彼は特別な才能も強さも持っていないが、それでも仲間のために全力を尽くす。その姿が「自分も一平のようになりたい」と感じさせたのだ。
特に人気なのは、第10話「スクープ!? 一平の大失敗」でのドタバタ劇。失敗して落ち込む一平に五郎が「お前の爆発はまだだ!」と励ますシーンは、笑いと感動が交錯する名場面である。
SNSでは、「五郎が理想の兄貴なら、一平は親友にしたいキャラ」と評されることが多く、作品のバランスを取る存在として今も根強い人気を誇っている。
● 熱きライバル・荒熊源太
荒熊源太は、五郎のライバルでありながら最も信頼できる友人という立ち位置で、多くの男性ファンから圧倒的な支持を集めている。彼のキャッチフレーズは「力で勝つより、心で勝て!」。この言葉はファンの間で語り草になっており、後のスポ根作品にも影響を与えたと言われている。
人気の理由のひとつは、彼の“変化”にある。初登場時は高圧的で粗暴な柔道部長だったが、五郎との対決を経て誠実で仲間思いな男へと成長していく。その成長物語が、多くの視聴者に「男らしさとは何か」を考えさせた。
ファンのコメントでは「五郎と荒熊の関係が本当の友情を教えてくれた」「最後の握手シーンで泣いた」という声が多く、二人の関係は単なるライバルを超えた“魂の兄弟”として今なお語り継がれている。
● 鬼丸武 ― 憎めない敵キャラの完成形
本作のもう一人の人気者が、ライバルの鬼丸武である。最初は嫌味な存在として登場するが、物語が進むにつれ、彼の人間味が見えてくる。「悪役なのに魅力的」という評価は、まさに鬼丸の代名詞だ。 五郎に対する嫉妬と敬意の入り混じった感情が、単純な“敵”ではない深みを生んでいる。特に、最終回直前で鬼丸が五郎に「お前の爆発は俺の胸にも響いた」と告げるシーンは、ファンの間で長く語られる名シーンだ。
彼を演じた矢田耕司の渋い声も人気の要因で、「悪役なのにカッコいい」という声が当時から多かった。
視聴者人気投票では、まゆみを上回って第2位にランクインしたこともあり、「敵でありながら誰よりも印象に残るキャラクター」として今でもファンの支持が厚い。
● ファンが選ぶ“隠れた推しキャラ”たち
メインキャラ以外にも、視聴者の心を掴んだ脇役たちがいる。たとえば、弱気ながらも努力を惜しまない剣道部員・細川忠文は、「地味だけど一番人間的」と支持を集めたキャラだ。 また、新聞部の後輩・中村ミチルは、わずか数話の登場ながら、五郎とまゆみを陰で支える姿勢が好評だった。彼女が放課後にそっと部室を掃除する場面は、一部のファンの間で「心の名シーン」と呼ばれている。
教師陣にも人気があり、顧問の浜田先生(通称ハマトラ)の飄々とした指導スタイルは、「あんな先生がいたら学校が楽しい」との声が多い。こうした脇役たちの存在が、作品の世界観をより豊かにし、キャラクターの層の厚さを生み出している。
● 現代のファンが再評価するキャラ像
令和の時代になってからも、『ばくはつ五郎』のキャラクターたちは若い世代に再評価されている。SNS上では、「五郎みたいな情熱、まゆみのような信念、一平の優しさが今こそ必要」という投稿が多く見られる。 また、近年の“推し文化”の影響で、キャラ単体の魅力を深掘りするファンも増え、キャラクター同士の関係性を分析したブログや動画も多い。
現代のファンが特に注目するのは、“心の爆発”というテーマ。外に向かって闘うのではなく、内面の葛藤を乗り越える姿勢に共感が集まっている。「五郎たちの爆発は、時代を超えて心の燃料になる」と語るファンの言葉は、作品の普遍性を物語っている。
● 総括 ― どのキャラクターにも“爆発”がある
『ばくはつ五郎』の登場人物たちは、それぞれの形で“爆発”を抱えている。五郎は正義の爆発、まゆみは信念の爆発、一平は勇気の爆発、荒熊は友情の爆発、鬼丸は嫉妬と誇りの爆発――。 この多様な“爆発”こそが、作品全体の人間ドラマを支える原動力となっている。
ファンは誰か一人にだけ共感するのではなく、場面ごとに違うキャラクターの心に自分を重ねる。だからこそ、時代が変わっても色褪せない。『ばくはつ五郎』のキャラクターたちは、観る者の心の中で今も生き続け、静かに、しかし確かに“爆発”しているのだ。
[anime-8]■ 関連商品のまとめ
● 映像ソフト ― VHSからBlu-rayまでの軌跡
『ばくはつ五郎』の映像商品は、1970年の放送終了後しばらくは長らく未ソフト化状態が続いていた。しかし1980年代後半、アニメブームの再燃とともに、往年の名作としてVHSシリーズがリリースされる。最初に登場したのは1987年の「東映アニメクラシックス」レーベルで、全26話中から人気回を抜粋した“セレクション形式”だった。 このVHSは当時のファンの間で即完売となり、レンタル店でも予約待ちが出るほどの反響を呼んだ。パッケージには五郎の決め台詞「爆発だ!!」が大きく印刷され、ジャケットデザインも力強く印象的。昭和のアニメ特有のざらついた映像が、かえって温かみを感じさせたという声が多い。
2000年代に入ると、ファン待望のDVD-BOXが登場。エイケン監修によるデジタルリマスター版で、全26話を完全収録した仕様だった。特典として、当時の絵コンテ・放送台本の複製や、スタッフ座談会を収録した小冊子が付属しており、コレクターズアイテムとしての価値が非常に高い。
その後、2010年代にはTBSチャンネルでの高画質再放送を記念し、「HDリマスター版Blu-ray BOX」が発売された。こちらは音声をリマスター処理し、オープニング・エンディングのノンクレジット映像や未使用カットを含む映像特典も収録。ファンの間では“決定版”と呼ばれている。
中古市場では、初期VHSが今もコレクターズアイテムとして人気があり、未開封品であれば1万円を超えることもある。特にDVD初回版BOXは希少性が高く、帯付き・ブックレット完備の状態では2万円台で取引されることも少なくない。
● 書籍関連 ― 原作漫画と資料本の魅力
原作は辻なおきによる漫画版『ばくはつ五郎』で、講談社の月刊『ぼくら』にて1967年に連載された。単行本は当時の少年向け単行本サイズで全2巻構成。アニメ化に伴って1970年に再版が行われ、表紙デザインがテレビ版に準拠した“アニメ絵バージョン”に変更された。これが現在でも古書市場で人気の高い一冊となっている。
また、1990年代には「昭和アニメ復刻シリーズ」の一環として復刻版が刊行され、さらに2000年代以降は電子書籍化も進んだ。KindleやBOOK☆WALKERでは、リマスター版カラーページ付きで配信されており、若い世代にも再発見されつつある。
書籍関連のもう一つの注目点は、アニメ資料集の存在だ。2005年に発行された『エイケン名作アーカイブ Vol.3 ばくはつ五郎』は、キャラクターデザインの原画、設定資料、背景美術などを収録した貴重な資料集で、アニメ研究家や制作ファンの必携書とされている。限定1000部で販売されたため、現在では中古市場で非常に高値で取引されている。
さらに、放送当時のアニメ雑誌(『アニメージュ』『OUT』『アニメディア』)でも特集記事が掲載されており、声優インタビューや制作裏話が掘り下げられている。特に1970年5月号の『ぼくらマガジン』に掲載された「五郎特集号」は、読者投稿と原画スケッチを併載したことでファンの間では伝説の一冊となっている。
● 音楽関連 ― 主題歌とBGMの再評価
音楽面でも『ばくはつ五郎』は忘れがたい存在感を持つ。オープニングテーマ「ばくはつ五郎」(歌:ザ・ワンダース)とエンディング「涙はともだち」は、放送当時から評判が高く、シングルEP盤がリリースされていた。現在でもレコードコレクターの間では人気が高く、帯付き・ジャケット良品で1万円前後の取引価格がつくこともある。
1990年代にはキングレコードの「アニメ・ヒストリー」シリーズに収録され、初めてCD化された。さらに2015年には『エイケン・アニメ音楽大全集』に再収録され、リマスター音源で蘇った。BGM集も同時に収録されており、作曲・和田昭治による生演奏スタイルの迫力は、今聴いても古さを感じさせない。
ファンの間では、「主題歌のイントロだけで胸が熱くなる」「BGMのトランペット音が青春を思い出させる」といった感想が多く寄せられている。
また、近年ではアナログレコードブームの再燃により、復刻版EP盤が2022年に限定プレスで発売された。レトロな音質と新デザインのスリーブが好評で、即日完売した店舗もあった。音楽面でも、本作の“爆発力”は今なお健在である。
● ホビー・グッズ・おもちゃ
放送当時の『ばくはつ五郎』関連グッズは、他のアニメ作品に比べると数は少なかったが、その希少性が現在のコレクター市場では高い価値を持っている。 1970年の放送当時、バンダイとツクダホビーから「五郎の爆発パンチ」や「青空学園新聞部セット」といった玩具が発売された。前者はゴム式の伸縮パンチ玩具で、子どもたちが“爆発ポーズ”を再現できるようになっていた。後者は文房具風のミニセットで、五郎やまゆみのシール、カメラ型鉛筆削りなどが付属していた。
他にも、当時の駄菓子屋で販売された「ばくはつ五郎カード」や、ガチャガチャのミニソフビシリーズなどが存在する。これらは流通数が非常に少なく、現在では1点でも数千円~1万円の値がつく。特に、新聞部員3人が並ぶ「トリオソフビ」はファン垂涎の逸品だ。
2000年代以降になると、昭和アニメグッズ復刻の流れの中で、キーホルダーや缶バッジ、Tシャツなどが企画された。特にアニメ放送50周年の2020年には、エイケン公式監修による「記念クリアファイルセット」が限定販売され、往年のファンを中心に完売となった。
● 食玩・文具・日用品
当時の小学生向けに発売されていた文具も、コレクターズアイテムとして注目を集めている。下敷き、ノート、鉛筆、カンペンケース、消しゴムといった学校用品は、すべてキャラクターイラスト入りで展開されていた。中でも人気だったのは「青空学園新聞部ノート」。まゆみと一平が表紙に描かれたデザインで、使い終えたノートを取っておく子どもも多かったという。
食玩では、「五郎チューインガム」「爆発ラムネ」「五郎スナック」といった駄菓子系コラボ商品が短期間ながら販売されており、パッケージに描かれた五郎の表情が毎回違うことで人気を博した。これらは現在ほとんど現存していないが、未開封の包装紙や当たりカードがオークションで高額取引されている。
● ゲーム関連・現代メディアでの復活
テレビアニメの放送当時にはゲーム化されなかったが、21世紀に入り、レトロアニメを題材にしたソーシャルゲーム「昭和ヒーローズコレクション」内に五郎がプレイアブルキャラとして登場。必殺技はもちろん「爆発だ!!」で、ファンの間で話題になった。 さらに、アニメ50周年を記念して2020年に発売されたニンテンドースイッチ用タイトル『エイケンヒーローズ・クロニクル』にも特別ゲストキャラとして参戦。まゆみや一平と共に学園を救うシナリオが追加され、往年のファンを歓喜させた。
このように、『ばくはつ五郎』は現代のデジタルコンテンツにもその魂を刻み続けている。懐かしさと新しさが融合した形で再評価されているのだ。
● 総括 ― “爆発”は今も続いている
『ばくはつ五郎』の関連商品は、映像・音楽・グッズのいずれを取っても“昭和の熱”を感じさせるものばかりだ。最新技術によってリマスターされても、その根底に流れるのは「真っ直ぐに生きる青春の輝き」である。 ファンの間では、「Blu-rayで観ても、まるで1970年の空気が戻ってきたよう」と語る声も多く、作品の普遍的な魅力を改めて実感するきっかけとなっている。
こうして半世紀以上経った今でも、『ばくはつ五郎』は多くのメディアや商品を通じて新しいファンを生み続けている。昭和の情熱を令和に伝える、その“爆発”は、決して消えることがない。
[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場
● 映像ソフト市場 ― VHS・DVD・Blu-rayの人気動向
『ばくはつ五郎』関連商品の中でも最も注目されているのが、映像ソフトの中古市場だ。特にVHS・LD・DVD・Blu-rayといった各メディアの移り変わりによって、コレクターの需要が大きく変化してきた。 1980年代後半にリリースされたVHS版は、現在ではレア度が非常に高く、状態の良いものは1本あたり3,000~6,000円前後で取引されている。特に初回パッケージのラベルに「TCJ PRESENTS」のロゴが入っているものは希少で、コンディションが良ければ1万円を超えることもある。
2000年代のDVD-BOXは発売当時の定価が約25,000円だったが、現在ではプレミア化しており、未開封品は3~4万円台に高騰。帯付き・ブックレット完備の完品はコレクターズアイテムとして非常に人気がある。
また、2010年代に発売されたBlu-ray BOXはリマスター品質の高さから安定した人気を保ち、相場は20,000円前後。発売時の数量限定特典「爆発だ!!ジャケットイラストカード」を付属するものは特に需要が高く、フリマアプリでは即完売になることも珍しくない。
ヤフオクでは「昭和アニメBOXまとめ売り」などに混じって出品されることも多く、セット出品時にはまとめ買い需要から5万円以上の落札例も確認されている。映像ソフトの状態(カビ・日焼け・ケース割れなど)が価格を左右するため、保存状態が良いものほど高値がつく傾向にある。
● 書籍・漫画・資料集の市場価値
辻なおきによる原作漫画『ばくはつ五郎』の初版単行本は、昭和40年代の講談社版が最も高額で取引されている。古書市場では帯付き・表紙焼けなしの美品が1冊あたり4,000~6,000円、全巻揃いで1万円前後が相場。アニメ放送時期に再発されたアニメ絵版は部数が少なく、こちらはコレクター向けとして8,000円以上の落札例もある。
2005年に刊行された『エイケン名作アーカイブ Vol.3』は、限定1000部の希少本として知られ、現在の中古市場では15,000~20,000円台で取引されることもある。ファンブック類は流通数が少なく、オークションでは数か月に1回程度しか出品されない。
また、当時のアニメ雑誌に掲載された特集記事(『アニメージュ』『OUT』『ぼくらマガジン』など)も人気で、表紙に五郎やまゆみが登場している号は2,000~3,000円で取引されるケースが多い。特に、読者投稿欄に掲載されたファンイラスト付きの号は、コレクターズアイテムとしてプレミア化している。
電子書籍版については定価で購入できるものの、紙の初版を求める“物理コレクター層”が依然として多く、年代物の紙の質感や印刷色の違いを楽しむ人も少なくない。「古いインクの匂いが好き」「紙のざらつきが昭和らしい」といったファンの声もあり、単なる資料としてではなく“記憶の形”として保有されている点が特徴的だ。
● 音楽関連 ― 主題歌レコードとサントラ盤
『ばくはつ五郎』の主題歌シングルEP盤(ザ・ワンダース「ばくはつ五郎/涙はともだち」)は、1970年当時の初回プレス盤が非常に貴重である。ラベル面の中央に“和田昭治作品”と刻印された初期仕様は、1万円~1万5千円で落札されることもある。 帯付き・ジャケット美品・ノイズ少なめの盤質であればさらに価値が上がり、マニア向け専門店では2万円以上で販売される例も確認されている。
1990年代にCD化された再録版は比較的手に入りやすく、相場は1,000~2,000円前後。ただし、2015年の『エイケン・アニメ音楽大全集』収録盤は限定生産のため、現在では5,000円前後に上昇している。
特にコレクターから人気なのは、オリジナルの台詞入りドラマ音源「新聞部奮闘記」付きのLPレコードで、放送局配布用の非売品として存在する。これは市場にほとんど出回らず、過去にオークションで6万円超の落札が確認された幻の逸品だ。
● ホビー・おもちゃ・雑貨の取引状況
当時の子ども向け玩具類は、現存数が極端に少ないことから“幻のグッズ”として高値がつく。特に人気があるのは「五郎の爆発パンチ」(ツクダホビー製)で、箱付き未使用品で2万円~3万円、開封済みでも1万円台で取引される。 また、ソフビフィギュア「ばくはつトリオ(五郎・まゆみ・一平セット)」は、当時のカプセルトイ景品として流通していたものだが、3体揃った状態での出品はほとんどなく、揃い踏みで5万円を超えることもある。
駄菓子屋向けのカード玩具「爆発だカード」も人気で、特に五郎の“炎背景バージョン”が希少。コレクターズクラブ内では“聖杯カード”と呼ばれ、1枚あたり2,000~4,000円で取引されている。
文房具系グッズ(下敷き・鉛筆・シール帳など)はフリマアプリで頻繁に見かけるが、1970年代製の正規品は日焼け・劣化が進んでいるものが多く、美品は3,000円前後の相場となっている。
● 食玩・日用品の市場動向
短期間しか流通しなかった食玩「五郎ガム」や「爆発スナック」の当たりカード、パッケージなどは、今では幻の存在だ。未開封状態で残っている例はほぼなく、当時の販促ポスターや箱だけでも1万円以上の落札例がある。 また、給食世代に人気だった“ばくはつ五郎コップ”や“青空学園弁当箱”といった日用品グッズも、近年の昭和レトロブームで注目を集めている。プラスチック製品のため変色が多いが、保存状態の良いものは5,000~8,000円の高値を付ける。
特にコレクターの間では、これらの“生活に溶け込んだキャラクター商品”が高評価で、「アニメグッズではなく、昭和の暮らしの証」として収集する動きが見られる。
● ゲーム・デジタル復刻関連の動き
2020年代に入り、『ばくはつ五郎』のキャラクターがデジタルゲームやアプリに再登場したことで、関連グッズの需要も再燃した。Switch向け『エイケンヒーローズ・クロニクル』同梱の限定特典カードやアクリルスタンドは、発売直後からフリマで高値取引され、現在も2,000~3,000円前後で安定。 さらに、キャンペーンで配布された「五郎の爆発バッジ」は、わずか300個限定で抽選配布されたため、オークションでは8,000円前後まで高騰している。
また、アニメ50周年記念の特設イベントで販売された公式グッズ(記念Tシャツ・手ぬぐい・ポスター)も即完売となり、今ではどれも定価の2~3倍で取引されている。現代のファン層にも“昭和アニメ収集”の文化が定着していることを物語っている。
● 総括 ― “爆発”する昭和アニメ市場
『ばくはつ五郎』の中古市場は、ここ数年で明らかに活況を呈している。特に昭和アニメの再評価ブームに伴い、価格は全体的に上昇傾向にある。映像ソフトや書籍だけでなく、当時の雑貨・おもちゃまで幅広く取引され、国内外のコレクターが競り合うこともしばしば。
オークションコメント欄では、「子どもの頃の思い出をもう一度手に入れたい」「五郎の笑顔を見ると元気になる」といったノスタルジックな声が多く見られる。こうした“思い出消費”の流れが、作品の価値をさらに高めているのだ。
フリマアプリでは、昭和アニメ専門の出品者も増えつつあり、タグ「#爆発だコレクション」で検索すると、多彩なグッズが並ぶ。まさに“静かな再ブーム”が起きていると言えるだろう。
『ばくはつ五郎』というタイトルが象徴するように、その熱気は今も冷めることがない。半世紀を経た今でも、当時の情熱が中古市場で再び“爆発”しているのである。
[anime-10]![放送開始45周年記念企画 想い出のアニメライブラリー 第49集 ばくはつ五郎[DVD] HDリマスター DVD-BOX / アニメ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_1187/bftd-154.jpg?_ex=128x128)
![ばくはつ五郎 HDリマスター DVD-BOX [ 中山輝夫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1546/4571317711546.jpg?_ex=128x128)
![[中古] ばくはつ五郎 HDリマスター DVD-BOX [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-sora/cabinet/p08/4571317711546.jpg?_ex=128x128)