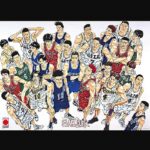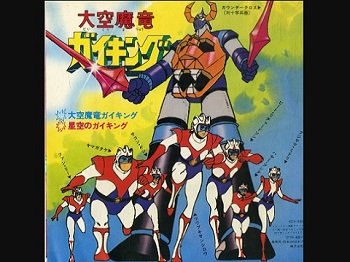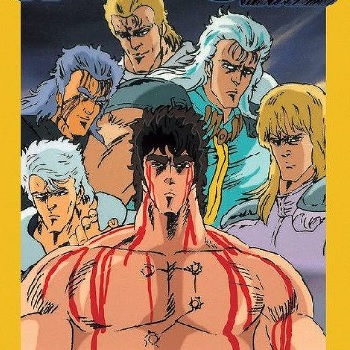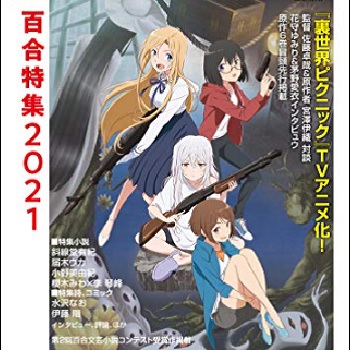ハセガワ ノンスケール 「デビルマン」 デビルマン(テレビアニメ版)【SP609】 未塗装レジンフィギュア
【原作】:永井豪
【アニメの放送期間】:1972年7月8日~1973年3月31日
【放送話数】:全39話
【放送局】:NET系列
【関連会社】:東映、東映化学、E&Mプランニングセンター
■ 概要
番組の輪郭――“ヒーロー”と“怪奇”の同居
1972年7月8日から1973年3月31日まで、NET(現・テレビ朝日)系列で放送されたテレビアニメ『デビルマン』は、東映動画(現・東映アニメーション)が手掛けた全方位型の娯楽作でありながら、画面の奥に“戦慄”を忍ばせた異色のヒーロー番組である。正義の味方が怪物を倒す、という筋立ては一見すると王道だ。だが、本作の主人公は「人を守るために同族に刃を向ける、デーモン族の裏切り者」。勧善懲悪の明快さに、自己否定や孤独の影が差し込む――この二重露光のような構造が、同時代のヒーロー作品と一線を画している。
メディア横断のなかで生まれた“もう一つ”のデビルマン
原作コミックとアニメ版は、単純な“原作→映像化”の関係ではない。同じ核(デビルマンという存在、デーモン族の脅威)を共有しつつ、テレビは幅広い視聴者に向けて“1話完結・怪獣退治・学園を舞台にした日常”を強調した。重い終末観や黙示録的なモチーフは、幼児から大人までが楽しめる時間帯の番組にそのまま移植できない。ゆえにテレビは“感覚の翻訳”を試み、恐怖や悲劇性を“スリル”“ブラックユーモア”“どこかヒリつく苦味”へと再配列した。結果として、少年向けのヒーロー活劇としての満足感と、得体の知れない余韻が同居する。
視点の置き方――「人間を守るデーモン」という逆説
アニメ版の設定で最も象徴的なのは、「デーモンの力を持つ存在が、人間社会を守る」逆説だ。正体を隠して名門学園に通い、牧村家の温かな日常に身を置く“明”の姿は、怪物である前にひとりの若者であることを忘れさせない。彼が守るのは“世界”という抽象ではなく、身近な教室や商店街、家族の食卓である。この近さが、毎回登場する妖獣の異形性をいっそう際立たせ、視聴者の体温に触れる怖さを生む。守るべきものが具体的であるほど、戦いは感情を帯び、勝利は甘くもほろ苦い。
物語運びの作法――毎回完結のテンポと、じわりと残る後味
各話は、妖獣の出現→人々の日常が侵食→明が苦悩と決意を経てデビルマンに変身→対決→日常の回復、という“呼吸の良い”テンポで進む。だが、単に危機が解決して“元どおり”になるだけではない。コメディリリーフの奔放さが場を和ませた直後、誰にも共有されない寂しさが明の横顔に落ちる――そうした小さな陰影が、毎回のカーテンコール後に余韻として残る。ブラックユーモアや皮肉は、暴力の快楽を薄めるための中和剤というより、世界の不条理を斜めから照らすライトとして機能している。
敵の像――“妖獣”は恐怖のカタログであり、寓意の鏡
妖獣たちは、単なる怪力の塊ではない。姿形・能力・狡知がエピソードのモチーフと結びつき、人間の弱さや俗悪さを拡大鏡にかけたように見せる。虚栄・嫉妬・権威主義・拝金――そうした感情の“ほつれ”に、妖獣はするりと入り込む。だからこそ、戦いは腕力だけの勝負に収まらず、毎回“何が壊され、何が守られるのか”という価値の選別を伴う。敵を倒すことは、単に悪を無効化することではなく、“人であること”をもう一度確かめる行為として描かれる。
笑いの役割――軽さで支える重心
アルフォンヌ先生やポチ校長らの喜劇的存在は、番組の温度を調整するサーモスタットだ。彼らの滑稽さは、悲劇や恐怖の直後に“救急ブランケット”のような役割を果たし、視聴者の呼吸を整える。同時に、彼らの小さな道化ぶりは、大人社会の矛盾や権威の滑稽さを映す鏡でもある。笑いによって緊張を緩め、次の瞬間にまた緊張を引き上げる――この“緩急の設計”が、週一回のテレビ視聴リズムに心地よく馴染む。
画と音の手触り――アナログ時代の“ざらつき”が生む実在感
アニメーションの線は時に揺れ、影の乗り方にばらつきがある。その“アナログの揺らぎ”こそが、怪奇の質感を豊かにする。夜景の群青、不気味に光る眼のハイライト、逆光で黒く潰れるシルエット――手作業の積層が、恐怖を“体温のあるもの”に変える。音楽は行進曲的な力強さと哀歌の旋律を行き来し、OP/EDが与える番組の“顔”は、子どもたちの耳にこびりつく記憶となった。戦闘の効果音も、硬質で乾いた鳴りが多く、打撃の痛みや羽音の不穏を短い音符で描く。
舞台としての“学園・家庭・街”――日常がキャラクター
名門学園は、事件の発火点としてだけでなく、友情や嫉妬、未熟さが交錯する“人間の試験管”である。牧村家の食卓に置かれた湯気や湯のみの丸みは、“守るべき平凡”を視覚化する小道具だ。商店街の看板、電話ボックス、バイクのエンジン音――どれもが、70年代初頭の都市文化を写すドキュメントでもあり、ヒーロー物語に“時間の匂い”を与える。だから、日常が傷つくと視聴者の胸も痛む。守る対象が匿名の都市ではなく、名前のある通学路なのだ。
孤独というコア――正体を隠す者の幸福と代償
明るいエピソードでも、主人公が最後に背負うのは“言えないこと”の重さだ。正体を明かせないヒーローは、喝采と理解の両方から最も遠い場所に立つ。本作は、その距離感を真正面から描く。信頼を得るほど、真実を告げられない自分への嫌悪が募る。仲間と笑い合うほど、笑顔の裏側でうずく孤独が濃くなる。単純な勝利では埋まらない欠落――それを毎回、数ショットの静かな画で見せる演出が、この作品のトーンを決定づけている。
70年代テレビ文化との共振――実写全盛期のなかでの健闘
当時の子ども向け画面は、特撮の熱量が支配していた。そんな中で『デビルマン』は、アニメならではの“形を自由に変える恐怖”を提示する。実写で表現すればコストも造形も跳ね上がる変形や異形を、作画ならば“想像力の速度”で走らせることができた。視覚の自由度は怪奇性を押し広げ、週一の娯楽として十分なカタルシスを供給する。その結果、番組は“強さの爽快さ”と“怖さの余韻”を両輪に、長く語られる存在になった。
作品を貫く問い――“人は何を守るのか”
最終的にこの番組が投げかけるのは、単なる“正義vs悪”の勝敗表ではない。正義を名乗る者が何を代償にしているのか、守るに値するものとは何なのか。デビルマンは、敵を倒すたびに“人間でありたい”という祈りを更新する。その祈りがある限り、たとえ世界の構造が変わらなくとも、目の前の誰かは守られる――テレビアニメ版が一貫して守り抜いたのは、その“実感の届く正義”である。
“終わり方”の意味――決着よりも継続の姿勢
番組はデーモン族との決着を明確に描かず、戦いが続く感覚を残して幕を下ろす。これは、視聴者の想像を信頼した終わり方だ。悪がいつか完全消滅するという保証よりも、日常を守る意思が“今日も続いている”という手触りを大切にする。ゆえに本作は、放送終了後も各種メディアで参照され、クロスオーバー企画などでも“戦い続ける姿”を提示してきた。ヒーロー像のアップデートと、怪奇表現の豊かさ――その二つの遺産は、今なお古びない。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
闇からの使者――デーモン族の再来
太古の地球に存在したとされるデーモン族は、氷河期によって滅びたと思われていた。しかし実際には、彼らは氷の下で眠り続け、時が来るのを待っていた。現代、人間社会が繁栄とともに環境を乱すその気配に反応するように、デーモンたちは目を覚ます。人間に化け、都市に潜み、再びこの地上を自らのものにしようと暗躍を始めた。人間には察知できないが、確実に“侵食”は始まっていた。
人間社会に生きるデビルマン――正体を隠した青年・明
その脅威に唯一立ち向かう存在が、デビルマンである。表の顔は不動明――名門学園に通う一人の高校生だ。牧村家に居候し、ミキや弟のタレちゃんと穏やかな日常を送る彼には、誰も知らないもう一つの顔がある。彼こそ、デーモン族から人間を守るために裏切り者となった戦士・デビルマン。不動明は、自身の体に潜むデーモンの力を制御しながら、人間としての心を守ろうと葛藤する。外面の明るさの裏にある孤独と責任が、物語の大きな軸を形成している。
最初の戦い――覚醒の瞬間
第1話では、人間社会に紛れ込んだ妖獣ジンメンによって牧村家の周囲が脅かされる。彼は死者の顔を背中に刻む異形の妖獣で、人間の魂を苦しめ続ける恐怖そのものだった。明は苦悩の末、自身の正体を現し、デビルマンとして初めて人間を守る戦いに挑む。デーモンの血が流れながらも、人間の心で敵に立ち向かう――その瞬間、彼は“希望”と“呪い”の両方を背負う存在となったのだ。
日常と非日常の交錯――学園でのエピソード
名門学園では、明るいクラスメートや個性豊かな教師たちが織りなすコメディタッチの場面も多い。アルフォンヌ先生の奔放な言動や、ポチ校長の小柄な体での大騒ぎなど、笑いの要素が散りばめられている。しかし、その笑いの裏で、学園にも妖獣の影が忍び寄る。転校生として現れる者が実は妖獣だったり、学校そのものが異次元空間に閉じ込められる事件も起こる。楽しい学園生活と、いつ破られるとも知れぬ平穏――その対比が物語を緊張感で満たしていく。
仲間と敵――氷村巌の登場
物語が進むにつれ、明の前に新たな存在が現れる。転入生・氷村巌。彼はどこか不気味なほど落ち着いた青年で、明に執拗に挑発を繰り返す。やがて彼の正体が、デーモン族の一員である妖獣ヒムラーであることが判明する。彼は明を監視し、人間への裏切りを責めるために派遣されたスパイだった。しかし、人間社会に触れるうちに、彼の心にもわずかな迷いが生まれる。敵でありながらも、明と似た“狭間の存在”として描かれる彼の悲劇は、アニメ版独自の陰影を与えている。
次々と現れる妖獣たち――変化と策略の数々
物語は一話完結の構成でありながら、登場する妖獣たちはそれぞれ異なる恐怖を象徴している。人間の夢を喰らう者、影に潜む者、科学技術を利用する者――その手口は多彩で、70年代初期の社会不安や環境問題を思わせる暗喩も多い。人間社会に潜む「見えない悪意」を形にしたような妖獣の数々は、勧善懲悪の単純な敵役にとどまらず、視聴者に“心の奥の闇”を意識させる存在として機能している。
幹部たちとの激闘――ザンニン、ムザン、そしてレイコック
デーモン族の中でも、デビルマンを滅ぼすために次々と強大な幹部が送り込まれる。最初に立ちはだかるのは魔将軍ザンニン。彼の巨大な体躯と冷徹な指揮は、まさに軍団の象徴だ。続く妖将軍ムザンは異次元空間を操り、学園を閉じ込めるという壮大な作戦を展開。さらに、妖元帥レイコックは美しさと残酷さを併せ持ち、配下の妖獣たちを宝石のように従える。彼女が時間を操る能力でデビルマンを翻弄するエピソードは、シリーズ屈指の緊迫感を誇る。これらの幹部戦は、作品のスケールを一気に拡張し、テレビアニメの枠を超えたスペクタクルを生み出した。
裏切りと共感――妖獣ララの悲しみ
中盤以降、明の前に現れる妖獣ララは、他の敵とは異なる存在として描かれる。彼女は天然でお人好し、戦闘力も低いが、純粋に“愛されたい”という感情を抱いていた。デビルマンへの恋心をきっかけに、彼女はデーモン族を裏切る。しかしその代償として、仲間から命を狙われ、炎の中で散っていく。彼女が消える瞬間に見せた微笑みと、「私の馬鹿は死んだから治っちゃったのよ」というセリフは、アニメ版ならではの哀切な名場面として語り継がれている。敵味方の境界が曖昧になる瞬間に、視聴者は“誰が悪で誰が正義か”を再び問わされる。
人間たちの反応――知られざる英雄
デビルマンが幾度となく人間を救っても、その正体を知る者はほとんどいない。牧村家や学園の人々は、目の前の脅威から解放されても、救ったのが誰かを知らないまま日常に戻る。明は感謝の言葉を受け取ることもなく、ただひとり夜の闇に消えていく。その姿は、孤独と使命を背負うヒーロー像の原型として、多くの後続作品に影響を与えた。彼の戦いは、誰にも知られない“報われない正義”の象徴でもある。
終盤の激戦――魔王ゼノンの影
物語が終盤に差し掛かると、ついにデーモン族の長・魔王ゼノンが姿を現す。彼の存在は、これまでの妖獣たちを統べる絶対的な支配者として描かれ、デビルマンにとっては超えられない壁のような存在だった。ゼノンは冷酷かつ計算高く、人間社会そのものを実験場のように見なしている。彼の出現によって、戦いは単なる“地上の戦い”から“存在そのものの闘争”へと深化する。最終決戦では、激しいエネルギー波と心理戦が交錯し、アニメとしての演出技法も極限に達する。
終わりなき戦い――幕を下ろす余韻
最終話では、決着がつかぬまま戦いは終わりを迎える。デビルマンは再び夜の闇へと飛び立ち、視聴者に“彼は今も戦い続けている”という余韻を残す。人間の平和は一時的に保たれたにすぎず、デーモンの脅威はどこかで息を潜めている。すべてを解決することなく、未来への警鐘を残して物語は幕を閉じる。その未完の感覚こそが、本作の魅力の一つであり、後の劇場版『マジンガーZ対デビルマン』へと物語が受け継がれていく余地を生んだ。
シリーズを通して描かれたテーマ
『デビルマン』の物語は単なる戦闘劇ではない。そこには「異なる存在とどう共存するか」という普遍的なテーマが流れている。人間社会の中に潜む“見えない敵”と、“自分の中のもう一つの顔”の両方と戦うデビルマンの姿は、時代を超えて共感を呼ぶ。アニメ版は、子どもたちにとってわかりやすいヒーロー活劇でありながら、大人の視聴者に“恐怖と哀しみの物語”として心に残る深さを持っていた。
終章――静かな祈りとしてのヒーロー像
戦いが終わった夜明けの街で、誰も知らないヒーローが孤独に立つ。その姿は、1970年代という時代の社会不安の中で、「人間は何を守るのか」という問いを突きつけた象徴だった。涙も、勝利の雄叫びもなく、ただ静かに夜明けへと歩み去るデビルマン――その背中に宿るのは、希望という名の悲しみであり、悲しみという名の強さだった。 この未完の物語は、視聴者の心の中で今もなお続いている。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
主人公・不動明――二つの心を持つ戦士
本作の中心人物である不動明は、学園では少しやんちゃで喧嘩っ早い青年として描かれているが、その胸の奥には人知れぬ苦悩を抱えている。彼の正体は、人間を守るために裏切り者となったデーモン族の戦士――デビルマンだ。アニメ版では、明自身がもともと人間ではなく、デーモンが人間の姿を借りて生きているという設定になっている。このため、彼の“人間らしさ”は学園での日常を通して育まれるものであり、それが同時に彼の弱点でもある。 牧村家の食卓で笑い、友人と冗談を交わすとき、彼の表情はまぎれもなく普通の青年のものだ。しかし一度、妖獣が現れると、瞳の奥に宿る闘志と孤独が露わになる。変身の瞬間、彼の体は鋭い翼と牙を持つ異形へと変貌し、デーモン族の血が爆発的な力を発揮する。だが、同時に“人を守るために同族を滅ぼす”という自己矛盾が彼を苦しめる。明というキャラクターは、単なる正義のヒーローではなく、“人間でありたいと願う怪物”という複雑な心理構造を持っており、これが作品全体の深みを形作っている。
牧村美樹――光と安らぎの象徴
明を取り巻くキャラクターの中でも、牧村美樹はもっとも人間らしい温もりを体現している存在だ。明のクラスメートであり、牧村家の長女として家族を支える彼女は、活発で正義感の強い少女として描かれている。アニメ版では、恋愛感情よりも“人としての信頼と絆”を重視した関係が強調されており、彼女の明に対する優しさが、デビルマンの心を支える要素となっている。 日常のシーンでは、明のドジや無鉄砲さを叱りながらも、どこか母性的な眼差しを向けることが多い。妖獣との戦いによって町が荒れたときも、彼女は決して絶望せず、明を信じる。彼女が象徴するのは“人間の善良さ”そのものであり、暗闇の世界に生きるデビルマンにとって、彼女の存在は人間であることの証明といえる。
牧村家の家族たち――小さな幸福の守り手
牧村家の両親と弟・健作(通称タレちゃん)は、作品の“日常”を象徴する存在である。父・耕作は考古学者として世界の古代文明を研究しており、デーモンの存在に何らかの縁を感じている人物でもある。母は優しく家庭的で、明を実の息子のように迎え入れている。タレちゃんは無邪気でおっちょこちょいな少年だが、彼の純真さが物語の緊張を緩める場面も多い。牧村家は、まさに“守るべき日常”の象徴であり、妖獣によって破壊されそうになるたびに、明の心に怒りと悲しみが宿る。彼らの笑顔を守ることこそ、デビルマンの戦う理由である。
名門学園の面々――笑いと混沌のキャンパス
不動明と美樹が通う名門学園は、作品にコミカルな色彩を与える重要な舞台だ。特に教師アルフォンヌ・ルイ・シュタインベック三世(通称アルフォンヌ先生)は、エピソードごとに強烈な印象を残す。常識外れの言動を連発しながらも、憎めない愛嬌を持ち、しばしば物語の緊張を和らげる役割を果たす。 彼とコンビを組むように登場するのがポチ校長。小柄で、常に慌てふためいているが、どこか温かみのある人物で、学園を象徴する“平和な空気”を演出する。この二人の存在は、ホラー要素が強い『デビルマン』の世界に、ユーモアという“呼吸”を与えている。明や美樹が通う学園には、他にも多彩なキャラクターが登場し、恋愛、嫉妬、友情といった人間関係の縮図が繰り広げられる。妖獣が襲い来るたびに、学園が非日常の戦場へと変わる点も見どころのひとつだ。
氷村巌(妖獣ヒムラー)――明の影を映す存在
氷村巌はアニメ版において、もっとも印象深いライバルのひとりである。彼は冷静で頭脳明晰、どこか人間離れした雰囲気を持つ転校生として登場する。その正体は妖獣ヒムラー――デーモン族の一員であり、デビルマンを監視し討伐する任務を負っていた。 ヒムラーのキャラクターが興味深いのは、彼が単なる“悪”として描かれない点にある。人間社会に溶け込みながら過ごすうちに、彼の中にわずかな戸惑いが生じる。敵でありながらも、明の苦悩を理解する数少ない存在であり、最後にはデビルマンとの戦いで敗れるものの、その最期にはどこか清々しい余韻が残る。彼の姿は、“己の信念と本能の狭間で揺れる者”という、デビルマンの鏡像的存在だった。
妖獣ララ――愛を知って散った少女
妖獣ララは、アニメ版『デビルマン』の中でもとくに異彩を放つキャラクターである。彼女は敵でありながら、純粋で感情豊かな妖獣として描かれた。美少女の姿をしているが、実際には物質を自在に変形させる能力を持ち、その本来の姿は老婆のように崩れている。彼女はデビルマン=明に恋をし、その恋が原因でデーモン族を裏切ってしまう。 しかし、裏切り者として仲間に追われた末、彼女は戦いの炎に包まれて消滅する。その最期の言葉、「私の馬鹿は死んだから治っちゃったのよ」は、悲劇でありながらどこか救いのある言葉として今も語り継がれている。ララの存在は、“愛する心”が人間とデーモンの境界を越えることを示しており、本作に人間ドラマとしての深みを与えた。
妖元帥レイコック――知略と美の象徴
妖元帥レイコックは、シリーズ後半に登場する女性幹部であり、数多くの妖獣を従える高位のデーモンである。彼女はこれまでの敵とは一線を画す冷徹さと美しさを兼ね備えており、知略を駆使してデビルマンを追い詰める。彼女の作戦は、単なる力押しではなく、心理的な揺さぶりによって敵を追い詰めるものが多い。 また、彼女がまとうドレスや装飾品はすべて配下の妖獣が変化したものであり、彼女の支配力と美的感覚を象徴している。最後は自らの“命の源”であるバックルを破壊され、燃え尽きるように散るが、その姿は敗北というよりも“美しき終焉”として印象に残る。彼女の存在は、デーモン族にもまた“誇り”や“美意識”があることを示しており、単純な善悪を超えたドラマ性を強調している。
魔王ゼノン――究極の支配者
デーモン族の長として君臨する魔王ゼノンは、アニメ版における最上位の敵として描かれる。巨大な体に複数の顔を持ち、闇そのものを象徴する存在である。彼は直接戦うことは少ないが、その影響力は常に地上に及び、妖獣たちを指揮してデビルマンを追い詰める。 ゼノンは、冷酷で理知的な支配者として描かれながらも、どこか“存在の虚しさ”を漂わせている。彼にとって、デビルマンは裏切り者であると同時に、かつて同族であった者の象徴でもある。彼の登場は物語を哲学的なレベルに引き上げ、「正義とは何か」「守るとは何か」という根源的な問いを視聴者に突きつけた。
人間たちの群像――普通の人々のリアリティ
アニメ版『デビルマン』では、一般市民の描写にも力が入っている。町の商店主、警察官、ニュースキャスター、学生たち――彼らは妖獣に怯えながらも日常を続ける“普通の人々”として描かれ、物語に現実感を与える。特に、デーモンに取り憑かれた人々の狂気や恐怖を描くシーンは、人間の脆さを象徴している。彼らの存在があるからこそ、デビルマンの戦いが単なる幻想ではなく、“人間社会を守る戦い”としての説得力を持つ。
キャラクターたちが織りなす世界
これらのキャラクターはそれぞれが象徴的な役割を持ち、作品全体を支える柱となっている。不動明は“二重性の象徴”、美樹は“人間の希望”、牧村家は“守るべき日常”、アルフォンヌやポチは“ユーモアの救済”、そして妖獣たちは“人間の影”をそれぞれ具現化している。こうしたキャラクターの重層的な関係が、『デビルマン』を単なるヒーローアニメではなく、心理劇としても成立させている。 彼らの言葉や行動の一つひとつが、当時の社会へのメッセージとして今も読み取ることができる点も、この作品の奥深さを物語っている。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
時代を象徴した“勇気と哀しみ”の旋律
1970年代初頭、日本のアニメ主題歌は単なる子ども向けの歌ではなく、時代の空気を映すメッセージソングとして進化していた。『デビルマン』の音楽もその流れの中で誕生した。作詞は阿久悠、作曲・編曲は三沢郷という当時のヒットメーカーによるものであり、勇ましくもどこか哀愁を帯びたメロディが特徴だ。 オープニングテーマ「デビルマンの歌」は、正義のヒーローを讃える典型的な勇壮ソングでありながら、その歌詞には“悲しみを背負って戦う者”というニュアンスが込められている。単に「悪を倒す」だけでなく、「人間を守るために孤独を選ぶ」というデビルマンの宿命が、メロディの陰影の中に滲む構成だ。
オープニングテーマ「デビルマンの歌」――魂を震わせる名旋律
「誰も知らない知られちゃいけない…」という印象的なフレーズで始まるこの曲は、子どもたちの記憶に深く刻まれた。十田敬三とボーカル・ショップによる重厚なコーラスが、デビルマンの孤独と力強さを象徴している。阿久悠の詞は、単純な勧善懲悪を超え、ヒーローが抱える“誰にも理解されない苦しみ”を詩的に表現している。 三沢郷のメロディはマーチ調でありながら、メジャーコードとマイナーコードを巧みに行き来することで、緊張感と哀愁を同時に生み出している。イントロの金管楽器の一撃が鳴った瞬間、テレビの前の子どもたちは“戦いの時間”が始まることを直感した。戦闘シーンのカットインとも絶妙にリンクし、オープニング全体が“出撃シーン”として成立している。 歌詞の後半にある「正義のために戦う男」「愛する人を守るために闘う魂」という表現は、当時のアニメソングには珍しい“内面的なモチーフ”を含んでいる。勇気だけでなく、犠牲、孤独、そして優しさ――それらすべてを併せ持つヒーロー像を、音楽が雄弁に語っていた。
エンディングテーマ「今日もどこかでデビルマン」――静かな祈りの歌
オープニングの力強さに対し、エンディングテーマ「今日もどこかでデビルマン」は、どこか穏やかで寂しげな旋律が印象的だ。作詞は同じく阿久悠、作曲は都倉俊一、編曲は青木望による。イントロの柔らかなストリングスとトランペットが、戦いを終えた後の静けさを感じさせる。 「誰も知らない正義の味方」「涙を隠して闘う男」という歌詞の繰り返しは、孤独に戦うデビルマンの姿そのものである。終わりのない戦い、報われぬ正義、そして“誰も知らない場所での戦い”というテーマが、視聴者に余韻を残す。 エンディング映像では、夕焼けの中を飛ぶデビルマンの姿がシルエットで描かれ、その背後に流れるメロディが“哀しみのヒーロー像”を完成させている。多くの子どもたちが番組の最後にこの旋律を聴きながら、胸に奇妙な静けさを感じたという。ヒーローであるにもかかわらず、拍手も歓声もなく、ただ沈黙の中で夜空を飛び去る――その映像は“孤高の美”として記憶に残った。
歌詞に込められた“阿久悠の哲学”
阿久悠は、当時の子ども向けアニメにおいても一切手を抜かないことで知られていた。彼の詞には常に“人間とは何か”という問いが潜んでおり、『デビルマン』でもその哲学は貫かれている。 オープニングでは「誰も知らない」という孤独の肯定、エンディングでは「それでも戦う」という意志の継続が描かれている。これは単にヒーローソングではなく、存在そのものへの詩であり、“人間であることの痛みと誇り”を讃える内容だ。阿久悠が後年語ったように、「子どもにこそ、真剣な言葉を伝えるべきだ」という信念がこの楽曲にも宿っている。
作曲家たちの功績――メロディが語るドラマ
三沢郷の作曲によるオープニングテーマは、リズム構成が極めて緻密である。テンポは早すぎず、マーチ調の安定感を保ちながらも、途中で短調に転じる部分が“デーモンの影”を暗示する。金管とストリングスの掛け合いによって、戦いのダイナミズムと内面的葛藤が同居する構成となっている。 一方、都倉俊一の手掛けたエンディングは、より叙情的であり、旋律線が滑らかに流れていく。メロディラインは歌いやすく設計されているが、背後に流れるベースとハーモニーは不安定なコードを使い、デビルマンの心の揺れを音で表現している。青木望の編曲は、当時としては珍しく管弦楽的なアプローチを採用し、アニメソングの水準を一段引き上げたと評価されている。
十田敬三とボーカル・ショップ――声の力
主題歌を歌った十田敬三は、当時アニメ主題歌の分野ではまだ無名に近かったが、その力強く澄んだ声質がデビルマンのキャラクターに見事にマッチした。特に高音域での伸びやかな発声は、孤高の戦士が叫ぶような感情を代弁している。バックコーラスのボーカル・ショップは、荘厳なハーモニーを構築し、単なる少年向けソングを“ドラマのテーマ音楽”へと格上げした。 彼らの歌声は、作品全体の重厚なトーンを支える重要な要素であり、後年のリメイク作品やイベントでも再評価され続けている。
挿入歌・BGM――映像を彩るもう一つの物語
『デビルマン』では、主題歌以外にも印象的なBGMや挿入歌が多数使用された。戦闘シーンでは低音のブラスと打楽器によるリズムが重く響き、デビルマンの一撃を際立たせる。妖獣登場時には、不協和音を多用したオルガンやシンセ風の効果音が使われ、視聴者に不安感を与える。 一方で、牧村家や学園の場面では軽快なジャズ調やコメディタッチの音楽が流れ、緊張と緩和を生み出している。特にアルフォンヌ先生登場時の“専用BGM”は、作品内で愛される要素のひとつとなり、子どもたちの間では「流れたら笑ってしまう音」として人気だった。
ファンにとっての“心のテーマ曲”
長年にわたって『デビルマン』ファンに愛されているのは、単に曲が格好いいからではない。そこに流れる“悲しみを受け入れた勇気”が、時代を越えて共感を呼ぶからだ。1990年代以降、CDリマスターやアニソン・ベスト盤などで再収録されるたびに、新たな世代がこの歌に出会い、再び心を動かされた。特に「デビルマンの歌」は、数多くのアーティストによってカバーされ、ロック、オーケストラ、メタル、アカペラなど多様な形で再解釈されている。どのアレンジでも変わらず感じられるのは、メロディに込められた“孤独な強さ”である。
イメージソングや派生作品での音楽展開
後年、『マジンガーZ対デビルマン』などの劇場作品やOVAシリーズでは、新たなアレンジ版や挿入歌が制作された。オーケストラアレンジによる「デビルマンの歌」は、原曲の勇壮さを保ちながらも壮大なスケール感を持ち、映像の迫力を倍増させた。 また、1980~90年代にはキャラクターソング形式のアルバムも登場。牧村美樹をテーマにした穏やかなバラード、アルフォンヌ先生をモチーフにしたコミカルソングなど、当時のファンには新鮮な試みとして受け入れられた。これらの派生曲は、アニメ版のキャラクター性をさらに豊かにし、作品世界を多面的に表現している。
音楽がもたらした“物語の呼吸”
『デビルマン』の音楽は、単なる演出補助ではなく、物語そのものの一部として機能している。戦いの前には高揚するリズム、勝利の後には静かな余韻――その流れが呼吸のように作品全体を包み込む。音楽が止まる瞬間には、逆に“沈黙の重み”が生まれる。そうした演出の緻密さは、当時の子ども番組としては異例であり、後のアニメ音楽の方向性にも大きな影響を与えた。
後世への影響――永遠に鳴り響くデビルマンの旋律
放送から半世紀を経た現在でも、「デビルマンの歌」と「今日もどこかでデビルマン」は数多くの世代に歌い継がれている。アニメソングの原点としてだけでなく、孤独と勇気を描いた“人間の詩”として愛され続けている。 コンサートイベントやアニソンフェスでは観客全員が拳を上げてこの曲を合唱し、その瞬間、1972年のあの夜のテレビ画面が蘇る。音楽は時を超え、デビルマンという存在そのものを語り続けているのだ。
[anime-4]
■ 声優について
不動明/デビルマン役・田中亮一――正義と哀しみを声で演じた男
不動明=デビルマンを演じた田中亮一は、本作によって“青年ヒーロー像”を確立した声優のひとりである。彼の声の魅力は、力強さと繊細さが共存している点にある。戦闘時の鋭い叫びや、妖獣を倒す際の低い唸り声には、デーモン族としての威圧感が宿る。一方で、牧村家で過ごす穏やかなシーンや、美樹との何気ない会話の中では、優しい少年のような柔らかさを漂わせる。 田中はインタビューで、「デビルマンは人間でも怪物でもない、その中間の苦しみを声で表現するのが一番難しかった」と語っている。叫びと沈黙、怒りと涙――そのどちらもが彼の演技には息づいており、感情の幅が非常に広い。特に、変身シーンの“デビル!”という叫びは、放送当時の子どもたちに強烈な印象を与えた。彼の発声はまるで自分の内なる怪物を呼び覚ますようで、単なる台詞ではなく“変身そのものの演技”であった。 後年、田中は『キン肉マン』『Dr.スランプ アラレちゃん』などでコミカルな役も演じたが、ファンの間では「デビルマンの声が最も彼の本質を表している」と語られることが多い。冷静さと激情が同居したその声は、今なおデビルマンの象徴である。
牧村美樹役・坂井すみ江――清らかさと芯の強さを兼ね備えたヒロイン像
牧村美樹を演じた坂井すみ江は、上品で柔らかな声質を持ちながらも、強い意志を感じさせる女優だ。彼女の声は、美樹の“明るさ”だけでなく“勇気”も的確に表現していた。明を叱咤するシーンでは毅然とした口調を、妖獣の恐怖に立ち向かう場面ではかすかに震える声を使い分け、少女でありながら芯のあるヒロインを作り上げた。 坂井の演技が特に印象的なのは、デビルマンの正体を知らぬまま彼を信じ続ける姿勢だ。無条件の信頼を声で伝えるため、彼女は台本を読みながら「美樹の言葉は祈りのように届けたい」と話していたという。彼女の声が持つ透明感が、作品全体の“救い”を生み出している。冷たく暗い闘争の中で、美樹の声が流れる瞬間だけは、画面に一筋の光が差すような感覚を与える。 坂井はその後も多くのアニメや舞台で活動したが、彼女自身も「美樹という少女は、私の中で永遠に生きている」と語っており、その言葉通り、彼女の声は今もファンの記憶の中で鮮やかに響いている。
アルフォンヌ先生役・永井一郎――怪優が放つコミカルな重厚感
名門学園の教師アルフォンヌ先生を演じた永井一郎は、言わずと知れた日本声優界の重鎮である。のちに『サザエさん』の波平や『機動戦士ガンダム』のナレーションで知られる彼だが、『デビルマン』では一転して破天荒な役柄を担当している。 アルフォンヌは、教養を誇示しながらも下品でお調子者という二面性を持つキャラクターだが、永井はそのバランスを見事に操り、嫌味ではなく“愛嬌のある変人”として演じ切った。彼の滑舌の良さとリズミカルな台詞回しが、アニメのテンポを軽やかにしている。コメディリリーフでありながら、戦いの場面では時折深い洞察を見せることもあり、永井の存在感が作品の“呼吸”を整えていた。
ポチ校長役・八奈見乗児――昭和の名バイプレイヤーが生んだ名物校長
名門学園のもう一人の常連キャラ、ポチ校長を演じたのは八奈見乗児。彼は『ヤッターマン』のボヤッキーや『ドラゴンボール』シリーズのナレーションなどでも知られる名優だ。ポチ校長の小柄で慌て者の性格を、八奈見特有の高めのトーンと早口で表現し、コミカルながらも温かみのあるキャラクターとして印象付けた。 “せっかん、せっかん”という口癖が子どもたちの間で流行語になったのも、八奈見の演技の妙によるものだ。彼の声には単なるギャグではない人間味があり、デビルマンの重いテーマを和らげる潤滑油のような役割を果たしていた。
妖獣ヒムラー役・井上真樹夫――冷徹な敵に宿る人間味
ライバル的存在・氷村巌(妖獣ヒムラー)を演じた井上真樹夫は、クールで知的な声で知られる実力派声優である。後年、『ルパン三世』の次元大介や『宇宙海賊キャプテンハーロック』のハーロックを演じる彼だが、この作品では一足早く“孤独な反逆者”の原型を演じていた。 彼の声は冷たいが、どこか哀しみを含んでおり、ヒムラーが単なる悪ではなく、デビルマンの鏡像であることを見事に伝えている。戦闘時の低い唸りと、敗北の瞬間に見せる静かな独白――そのギャップが視聴者の心を打った。井上の繊細な演技が、アニメ版の深みを一層際立たせている。
魔王ゼノン役・柴田秀勝――威厳と恐怖の頂点
魔王ゼノンを演じた柴田秀勝は、数多くの悪役を演じてきた“低音の帝王”と呼ばれる存在である。彼の声が発する一言には圧倒的な威圧感があり、まるで空気そのものが震えるような重さを持つ。ゼノンの「デビルマン、裏切り者め…」という低く響く台詞は、放送当時の子どもたちにとって恐怖の象徴だった。 しかしその中には、怒りだけでなく、かすかな哀れみも混じっている。柴田の演技は、ゼノンという存在に“神のような悲しみ”を与え、単なる悪役以上の奥行きを作り出していた。
妖元帥レイコック役・里見京子――妖艶さと知性の融合
女性幹部レイコックを演じた里見京子は、舞台女優としても活躍していた実力派である。彼女の声は、しなやかで艶やか、しかし冷徹な響きを持つ。台詞の終わりにわずかに息を残すような発声が、レイコックの妖しい魅力を際立たせていた。 彼女の演技は、妖獣を従える高貴な存在としての威厳を保ちながらも、敗北時には人間的な感情を見せる二面性を巧みに表現している。レイコックの最期に漂う哀しみを観客に感じさせたのは、里見の演技力によるところが大きい。
ナレーションと脇役陣――物語を支えた声の職人たち
本作のナレーションは、落ち着いた低音で物語を導く重要な役割を担った。毎回のエピソード冒頭で流れる「地上に再び現れたデーモンの軍団…」というナレーションは、物語に神話的な荘厳さを与えている。加えて、妖獣たちの声を担当した声優陣――増岡弘、矢田耕司、北川国彦らは、個性的な声質でそれぞれの妖獣を生き生きと演じ分けた。特に増岡のザンニン将軍は、怒号と狂気を行き来する迫力ある演技でファンの印象に残っている。
声優陣のチームワークと現場の空気
1970年代のアフレコは現在よりも即興性が高く、スタジオの中で役者同士がセリフをぶつけ合う熱気があったという。『デビルマン』の現場もその例に漏れず、特に田中亮一と井上真樹夫の対決シーンでは、録音室が静まり返るほどの緊張感が漂っていたと伝えられている。 ベテラン勢と若手が混ざったキャスティングは、現場に独特の緊張と活気を生み、アニメ制作の“職人文化”を感じさせた。音響監督が「演技より先に呼吸で空気を作れ」と指示したというエピソードも残っており、その結果として作品全体に生命感が宿った。
“声”が描いたデビルマン像
『デビルマン』は、画だけではなく“声”によってキャラクターが形作られた作品でもある。田中亮一の叫び、坂井すみ江の祈り、永井一郎の笑い、柴田秀勝の威圧――それらすべてが交錯し、ひとつの世界を構築した。視聴者が感じた恐怖や感動の多くは、声優たちの演技から生まれたものだ。 放送から半世紀を経た今も、彼らの声はアニメ史に刻まれている。“昭和の声”が持つ温度と厚み――それは、デジタル全盛の現代では再現できない、人間そのものの響きである。
[anime-5]
■ 視聴者の感想
放送当時の衝撃――“子ども番組”の枠を超えた恐怖と感動
1972年に『デビルマン』が放送開始されたとき、多くの視聴者は「これまでのヒーローアニメとはまるで違う」と驚いた。放送枠は夕方の子ども向け番組でありながら、その内容は当時としては異例のほど暗く、哲学的だった。妖獣たちのデザインはグロテスクで、人間の心に潜む悪を象徴するかのようだった。 子どもたちは最初、その奇怪なビジュアルや戦闘シーンに恐怖を覚えながらも、デビルマンの「誰も知らない、知られちゃいけない」という歌詞に心を惹かれていった。学校では「昨日のデビルマン見た?」が合言葉のようになり、怖いけれど見ずにはいられない――そんな中毒性を持つ番組として話題を呼んだ。 一方で、大人たちは「子ども番組にしては過激すぎる」との声を上げた。特に、妖獣の最期の描写や、敵味方の境界が曖昧な展開には賛否が分かれた。しかし、その“異質さ”こそが番組の魅力であり、後に再放送を通じて“伝説のアニメ”として語り継がれるきっかけとなった。
子どもたちにとってのヒーロー像の変化
それまでのヒーローといえば、『ウルトラマン』や『マジンガーZ』のように、絶対的な正義として描かれるのが一般的だった。しかし『デビルマン』は、明確な正義を持たない“苦悩するヒーロー”を提示した。 視聴者の少年たちは、デビルマンの戦いを見ながら「もし自分だったらどうするか?」を考えるようになったという。敵を倒すだけでなく、人間としての在り方を問われる――それは子どもたちにとって初めての経験だった。特に、主人公・不動明が涙を流す場面に心を動かされたという声が多く、「ヒーローも泣くんだ」「正義って簡単じゃないんだ」という感想が多く寄せられた。 こうした心理的なリアリズムが、後のアニメにおける“悩める主人公”像の原型となったことは間違いない。
女性視聴者の共感――美樹とララの存在
放送当時のアンケートでは、意外にも女性ファンの支持が高かった。彼女たちは、牧村美樹や妖獣ララの描かれ方に強い共感を抱いたという。 美樹は単なるヒロインではなく、デビルマンの心を支える“理解者”として描かれ、彼女の明に対する信頼や優しさに「こんな女性でありたい」という声が寄せられた。また、敵であるララの悲恋エピソードは、多くの少女たちの涙を誘った。 ある当時の女子中学生の感想文には、「悪い者でも愛を知ると人間に近づく。ララの死は悲しいけれど、デビルマンが涙を流したとき、二人の心はつながったように思った」と書かれている。『デビルマン』は、単なる戦いではなく“心の交流”を描いた物語として、女性視聴者にも深い印象を残したのだ。
親世代の反応――「難しすぎる」「哲学的すぎる」
当時の家庭では、夕食時にテレビを囲んで家族で『デビルマン』を観ることも多かった。そのため、親たちの感想も多様である。 ある母親は「子どもが夢に出るほど怖がっていた」と苦笑し、ある父親は「内容は難しいが、教訓的だ」と評価していた。悪と戦うだけでなく、悪の根源を“人間の中にある”と示唆する展開に、宗教的・哲学的な解釈を試みる視聴者もいた。 また、一部の教育者は、「この作品は暴力的ではなく、人間の善悪を描く寓話だ」として、道徳教育の一環として分析する論文を発表している。社会全体でアニメが“思想表現”として注目されるきっかけのひとつとなった。
印象に残る名シーンと名台詞
視聴者の間で特に記憶に残っているシーンとして、妖獣ララが最期に微笑む場面、デビルマンが涙をこらえて空に消えるラスト、そして美樹が「明くん、あなたは何者なの?」と問いかけるシーンが挙げられる。 名台詞としては、「悪魔の力を持ち、人の心を持つ男」「誰も知らない正義の味方」「愛のために戦うのが罪なら、俺は罪人でいい」などが長年ファンに語り継がれている。これらの台詞は、当時の子どもたちにとって難解だったかもしれないが、成長して再び観たときに“意味が分かるようになった”と語る人が多い。 つまり、『デビルマン』は“成長とともに再発見できるアニメ”だったのだ。
アニメ誌・ファン層の再評価
1970年代後半から80年代にかけて、アニメファンの間で『デビルマン』再評価の動きが始まった。アニメ誌「アニメージュ」や「OUT」では、“暗黒ヒーローの原点”として特集が組まれ、当時のスタッフや声優のインタビューが掲載された。 そこでは、「子ども向け番組として限界まで挑戦した作品」として高く評価され、特に脚本の深さと演出の大胆さが注目された。また、後続のクリエイター――例えば『新世紀エヴァンゲリオン』の庵野秀明や、『ベルセルク』の三浦建太郎らが影響を受けたことを公言したことも、再ブームのきっかけとなった。
再放送世代のノスタルジー
1970年代後半から80年代初頭にかけて再放送が行われると、新しい世代の子どもたちが再びデビルマンと出会った。当時の視聴者はすでにカラーテレビが普及しており、より鮮明な映像であの恐怖と美しさを体験した。 「子どものころは怖くてチャンネルを変えたけど、大人になって観ると泣ける」という感想が多く、作品が持つ“時間を超える力”を裏付けている。再放送をきっかけに、主題歌を口ずさむ大人たちも増え、アニソンカラオケブームの先駆けにもなった。
現代視聴者からの再評価――心理と象徴のドラマとして
インターネット時代に入ってから、『デビルマン』は新たな形で再発見されている。SNSや動画配信サービスを通じて、若い世代が初めてこの作品を視聴し、「50年前のアニメとは思えないほど現代的」と驚く声が相次いだ。 特に評価されているのは、“内面の葛藤”と“人間の愚かさ”を描く構成だ。単純な勧善懲悪ではなく、愛・憎しみ・信仰・裏切りといった複雑な感情を、わかりやすいアクションに乗せて描いている点が高く評価されている。 また、キャラクターデザインや音楽の完成度、脚本の台詞回しなども「令和でも通用する表現」として分析され、アニメ研究の対象にもなっている。
ファンイベント・聖地巡礼――時を超える熱狂
21世紀に入っても、『デビルマン』ファンの情熱は衰えない。アニメ50周年記念には、全国で関連展示や上映イベントが開催され、多くのファンが集まった。会場では当時のセル画や設定資料が展示され、田中亮一や坂井すみ江ら声優陣のトークショーも行われた。 さらに、作品の舞台となった“名門学園”のモデルとされる都内の学校跡地を訪ねる“聖地巡礼”も人気となっている。ファンたちは主題歌を口ずさみながら写真を撮り、SNSで「#デビルマンの軌跡」とタグを付けて共有している。 こうした活動は、単なる懐古ではなく、“心に残るヒーローへの感謝”として続いている。
感想が語る作品の普遍性
時代や世代を超えても、『デビルマン』に寄せられる感想には共通点がある。それは、「正義と悪の境界はどこにあるのか」「人間らしさとは何か」という根源的な問いに触れるということだ。子どもたちは怖さの中に勇気を見出し、大人たちは悲しみの中に真実を感じ取る。 この作品を観た人の心には、それぞれ違う“デビルマン像”が宿る。誰も知らないが、確かに心のどこかに存在するヒーロー――それが『デビルマン』という作品が半世紀を経ても愛され続ける理由である。
[anime-6]
■ 好きな場面
第1話「悪魔の誕生」――闇を切り裂く覚醒の瞬間
シリーズの幕開けとなる第1話は、多くのファンにとって忘れられない“原点”の回である。 不動明が初めてデビルマンとして覚醒する場面――あの瞬間の演出は、当時のテレビアニメとしては衝撃的だった。血が脈打つようなBGMとともに、画面が赤と黒に染まり、明が絶叫する。「俺の中に何かが…来る!」と叫びながら体が変貌していく描写には、まるで自我の崩壊と再生を見るような迫力があった。 変身の演出はシンプルながらも、光と影の対比、カメラワーク、叫びの抑揚が完璧に噛み合い、デビルマンという存在がただの“変身ヒーロー”ではないことを強烈に印象づけた。 その後、初めて妖獣を撃破した瞬間、明が見せる複雑な表情――勝利の喜びよりも、哀しみに近い感情を宿したその顔こそ、『デビルマン』という作品の本質を象徴している。ファンの間では「最初の戦いで既に終章の哀しみが漂っている」と語られるほど、完成度の高い導入回だ。
第4話「妖獣ジンメン」――恐怖と悲哀が交錯する傑作回
シリーズ屈指の名エピソードとして名高いのが、この第4話「妖獣ジンメン」である。 背中に人間の顔を刻んだ巨大な妖獣――その顔が喋り、苦しむ様子は、子ども番組としては異例の残酷さだった。中でも、明がジンメンの背に幼い友人の顔を見つけてしまう場面は、多くの視聴者の心を抉った。「明くん…痛いよ…」と訴える声に、デビルマンは拳を振るえない。 しかし、彼は苦悩の末に戦いを決意する。「君の魂を解放する」と呟きながら、涙を流して止めを刺すシーン――その瞬間、彼は“怪物でありながら人間らしい”存在へと進化した。 視聴者の間では、この回を「子どもながらに泣いた」「一番怖くて一番優しい話だった」と語る人が多く、今なおシリーズ随一の感動回として語り継がれている。ジンメンの存在は、単なる敵ではなく、人間の“忘れられない罪”の象徴でもあった。
第9話「学園に魔手が迫る」――日常が崩壊する恐怖
このエピソードでは、名門学園そのものがデーモンの罠に陥るというストーリーが展開される。 いつもは笑いに満ちた教室が、突如として異空間へと変貌し、教師や生徒たちが次々に妖獣に変化していく。明が美樹を守ろうと必死に立ち回るが、次第に誰が味方で誰が敵か分からなくなる混沌。 この回の演出の妙は、恐怖の中にも“青春の儚さ”が描かれていることだ。生徒たちの悲鳴の中に、「もっと普通に生きたかった」「恋をしたかった」という声が重なる。明がその声を背に、ただ一人敵に立ち向かう姿は、悲壮でありながら美しい。 視聴者からは「教室が地獄に変わる映像が忘れられない」「あの回で初めて“アニメに現実の恐怖”を感じた」との感想が寄せられている。光と闇、青春と終末が交差する一編だ。
第15話「妖獣ララの恋」――愛と死の交錯
ファンの間で最も心に残る回として挙げられるのが、第15話「妖獣ララの恋」である。 ララという妖獣は、敵でありながらも純粋な心を持っていた。彼女がデビルマン=明に恋をし、デーモン族を裏切るまでの過程は、まるで悲劇の恋愛劇のようだ。 ラストシーンでは、炎の中でララが「私の馬鹿は死んだから治っちゃったのよ」と微笑む。その言葉は、美しくも痛烈で、今もファンの間で語り継がれる名台詞である。 この回を観た視聴者は、「敵にも心がある」「愛は立場を超える」というメッセージを受け取った。ララが散った後、明が空を見上げて涙をこぼす描写には、愛する者を失う苦しみと、それでも前を向く決意が凝縮されている。 “愛と戦いは共存できるのか”――その問いを真正面から描いたこの回は、アニメ版『デビルマン』の精神的な頂点といってよい。
第21話「妖元帥レイコックの挑戦」――美と狂気の共演
後半のクライマックスとして人気の高いエピソードが、妖元帥レイコックが登場するこの回だ。 彼女の計略によって時間が歪み、デビルマンが同じ戦闘を何度も繰り返すループ構成は、当時のテレビアニメでは極めて珍しい演出だった。華やかな美貌と冷酷な指揮力を併せ持つレイコックの姿は、敵でありながら圧倒的なカリスマを放つ。 特に印象的なのは、彼女が戦いの最中に「美とは力よ、力こそが秩序を生む」と呟く場面。その台詞に対してデビルマンが「美しさは、人を守るための強さだ」と返す瞬間、画面が白くフラッシュし、二人の信念が激突する。 視聴者からは「レイコックの最期が悲しかった」「敵の方に共感してしまった」といった声も多く、単純な善悪の枠を超えた心理劇として高い評価を得ている。
最終話「地獄からの使者」――終わらない戦いの予感
シリーズの最終回は、派手な勝利もなく、静かな余韻で幕を閉じる。 魔王ゼノンとの激闘の末、ボロボロになったデビルマンは夕焼けの空を飛び立つ。勝ったのか、負けたのか、その答えは明示されない。ナレーションの「デビルマンの戦いは、これからも続くのだ」という言葉とともに画面がフェードアウトする。 この終わり方に、当時の子どもたちは驚き、同時に強い印象を受けた。「どうして終わらないの?」「彼はどこへ行ったの?」という疑問を抱きながらも、誰もが胸の奥で“まだ戦っている”と信じた。 現代のファンの間では、このラストが「希望の余韻」として再評価されている。ヒーローは人々の記憶の中で生き続ける――その概念を初めて提示したアニメとして、『デビルマン』は永遠の未完を美学に変えた。
印象的な“静寂”の演出――言葉よりも強い沈黙
『デビルマン』の名場面の多くは、派手な戦闘や爆発の瞬間ではなく、むしろ“静かな場面”にある。 戦いの後、誰もいない街をデビルマンが一人歩くシーン。 燃える瓦礫の中で、美樹の笑顔を思い出す一瞬。 その沈黙の中に、視聴者は“正義とは何か”を考えさせられる。BGMが止まり、ただ風の音だけが流れる演出は、当時のテレビアニメでは異例だったが、その効果は絶大だった。 「音がないのに怖い」「何も起きないのに涙が出た」――そう語る視聴者の声が多く、言葉よりも沈黙の方が雄弁であることを、この作品は教えてくれた。
視聴者が選ぶ“心に残る3シーン”
再放送世代やアニメファン誌のアンケートでも、以下の3つのシーンが特に人気が高い。 1. 初変身シーン(第1話):光と闇の爆発的な映像演出。 2. 妖獣ララの最期(第15話):悲しみと愛の融合。 3. 夕空を飛び去るラストシーン(最終話):孤独なヒーローの背中。 これらの場面はいずれも“戦い”そのものよりも、“感情”が中心に描かれている。観る者の心に長く残るのは、勝利ではなく、“生きる意味を問う姿”なのだ。
好きな場面が示す『デビルマン』の本質
どのエピソードも共通しているのは、“正義の勝利”よりも“心の葛藤”を描いている点である。 観る者が感動するのは、強さではなく“優しさ”であり、勇気ではなく“孤独の受け入れ”である。デビルマンの戦いは、敵を倒すためではなく、自分の中の弱さと向き合うためのものだ。 だからこそ、視聴者の“好きな場面”は、戦闘ではなく涙の場面であり、静寂の中の瞬間なのである。 半世紀が過ぎた今も、ファンが語り続けるのは「デビルマンが誰かを救う場面」ではなく、「デビルマンが苦しみながらも人を信じた瞬間」なのだ。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
不動明/デビルマン――人間と悪魔の狭間に立つ悲劇のヒーロー
『デビルマン』という作品を象徴するのは、やはり主人公・不動明(=デビルマン)だろう。 彼は、悪魔の力を持ちながら人間の心を捨てられない存在として描かれる。強さと優しさ、怒りと悲しみ――そのすべてが同居する複雑なキャラクターであり、視聴者の多くが「明こそ最も人間らしい」と語る。 特に印象的なのは、彼が妖獣たちを倒した後に必ず見せる“苦悩の表情”だ。敵を滅ぼしても決して笑顔を見せない。戦うほどに心が痛む、そんなヒーロー像は当時のアニメにはほとんど存在しなかった。 ファンの間では「デビルマンの叫びが、心の叫びに聞こえる」「彼は自分たちの代弁者だ」と語られることも多く、ヒーローとしての象徴であると同時に“孤独の代名詞”としても愛されている。 現代においても彼の存在は特別であり、「人間であることの苦しさを教えてくれた」「ヒーローなのに泣いていいと思えた」という声が後を絶たない。まさに、善悪を超えて“魂の闘士”として輝く存在だ。
牧村美樹――希望と光を象徴するヒロイン
牧村美樹は、『デビルマン』の中で最も“人間らしい美しさ”を体現するキャラクターである。彼女は明にとっての救いであり、また視聴者にとっても“光”のような存在だった。 強くて優しく、明が苦しんでいるときには必ず寄り添う。単なる恋人役ではなく、彼を人間の世界につなぎ止める“絆”として描かれている点が印象的だ。 ファンの感想でも、「美樹がいたからデビルマンは闘えた」「彼女の微笑みが救いだった」という言葉が多く見られる。ときに妖獣たちの襲撃に巻き込まれ、恐怖の中でも怯えずに立ち向かう姿は、視聴者に“勇気とは何か”を問いかけた。 また、美樹の存在が作品全体のバランスを取っており、絶望的な展開の中でも“愛と信頼”を感じさせる。彼女の透き通るような声と表情は、半世紀を経ても色褪せることがない。
妖獣ララ――敵でありながら愛された哀しき少女
ララは『デビルマン』に登場する妖獣のひとりでありながら、ファンの間では特に人気の高いキャラクターだ。 彼女は無邪気でありながら、どこか人間らしい感情を持つ。その“純粋な愚かさ”が逆に悲しみを誘い、敵であるにも関わらず多くの視聴者が彼女の最期に涙した。 ララがデビルマンに恋をする展開は、敵味方を超えた愛の象徴であり、彼女の「死んだから馬鹿は治っちゃったのよ」という名台詞は、永遠に語り継がれる言葉となった。 当時のファンレターには「ララのように誰かを純粋に愛したい」「彼女が救われる世界を見たかった」と書かれているものも多く、アニメ史上でも稀に見る“敵なのに愛されるキャラ”として位置づけられている。
アルフォンヌ先生――破天荒なコメディリリーフ
名門学園の教師であるアルフォンヌ先生は、シリアスな『デビルマン』の中で唯一笑いを提供するキャラクターである。 奇抜な行動、時に非常識な発言、しかしどこか憎めない人間味――彼の存在が、物語の緊張感を和らげる潤滑油となっている。 視聴者の間では「先生が出ると少しホッとする」「怖い妖獣回の後に出ると癒される」といった声が多い。特に、電話ボックスをトイレ代わりに使うシーンや、美女を追いかけて自滅するギャグシーンは今も語り草だ。 だが一方で、彼が生徒たちを守るために勇気を見せる場面もあり、単なる“お笑い役”ではなく、心優しい大人としての魅力を持っている。 声を担当した永井一郎の柔らかい演技も相まって、アルフォンヌは“混沌の中の小さな平和”を体現するキャラクターとして愛されている。
ポチ校長――昭和の良心を感じさせる存在
小柄で威厳のない校長先生――ポチ校長は、そのユーモラスな見た目と独特の口癖「せっかん、せっかん」で一躍人気者になった。 彼はいつもアルフォンヌ先生の後ろでオロオロしているが、実は学園を守るために誰よりも心を砕いている。危険な事件が起きるたびに生徒の身を案じ、時に命がけで避難誘導をする姿は、視聴者の心を打った。 ファンの中には「ポチ校長の小さな勇気が好き」「おどけているけど優しい」と語る人も多く、子どもたちを思う“大人の理想像”としても評価されている。 その存在は、戦いや恐怖の中で失われそうになる“人間の温かさ”を取り戻す役割を担っていた。
妖元帥レイコック――知性と美を兼ね備えた強敵
後半の敵役として登場する妖元帥レイコックは、圧倒的なカリスマ性と戦略眼を持ち、ファンの間では“悪役の中の女王”と称される存在である。 彼女の冷徹な指揮、洗練された台詞、そして敗北の際に見せる一瞬の涙――すべてがドラマティックで、美しさと哀しさが同居している。 視聴者からは「敵なのに好き」「レイコックに惹かれた」「悪の中にも誇りがあった」といった感想が多く寄せられた。 彼女は単なる敵ではなく、“信念を持って戦う女性像”として描かれ、当時の女の子たちにも人気が高かった。レイコックが放った「強さとは、自らを犠牲にしても守ること」という台詞は、今も多くのファンの心に刻まれている。
タレちゃん(牧村健作)――子ども目線の希望
美樹の弟・タレちゃんは、幼いながらも明を兄のように慕い、作品に温かみを与える存在だ。 彼の純粋な視点は、戦いの恐怖を和らげるだけでなく、“人間の無垢さ”を象徴している。特に、彼が明に「デビルマンって怖いけど、ぼく好きだよ」と笑うシーンは、多くの視聴者にとって忘れられない名場面だ。 タレちゃんの存在によって、作品全体が“希望の物語”として成立している。彼は光の少ない世界の中で、未来を信じる力そのものなのだ。
魔王ゼノン――絶対的悪の美学
デーモン族の長・ゼノンは、冷酷無比で圧倒的な存在感を放つキャラクターである。 しかし、ファンの中には「ゼノンが単なる悪とは思えない」という意見も多い。彼はデビルマンに対して怒りながらも、どこかで“同族への哀れみ”を抱いているようにも見える。 声優・柴田秀勝の低く響く声が、彼の言葉に重みと悲壮感を与えており、「悪にも信念がある」ことを感じさせる。 視聴者の一部は「ゼノンはもう一人の明だ」と評しており、彼を“影の主人公”と捉える人も少なくない。 その存在は、デビルマンの戦いを単なる勧善懲悪ではなく、“価値観の衝突”として成立させている。
ファンが選ぶ人気キャラクターランキング(当時と現在)
放送当時に行われたアニメ誌アンケートでは、人気1位が不動明、2位が牧村美樹、3位がララという結果であった。 しかし近年のファン投票では、ララとレイコックの人気が急上昇している。特にSNSでは「女性キャラの心理描写が深い」「敵なのに心が動く」というコメントが多く、作品の再評価につながっている。 また、アルフォンヌ先生やポチ校長といったコミカルなキャラクターも根強い人気を誇り、「彼らがいたから作品が救われた」との声が多い。 このランキングの変遷は、時代とともに“視聴者が求めるヒーロー像”が変化していることを示している。
キャラクターたちが教えてくれたもの
『デビルマン』に登場するキャラクターは、それぞれが人間の“光と影”を象徴している。 明は苦悩、 美樹は希望、 ララは愛、 レイコックは信念、 アルフォンヌとポチはユーモア、 ゼノンは宿命。 この多層的なキャラクター構成が、作品を単なるヒーローアニメから“人間の寓話”へと昇華させた。 視聴者が彼らに惹かれるのは、その姿が私たち自身の一面を映しているからだ。 “善悪ではなく心の在り方”――それを教えてくれるキャラクターたちこそ、『デビルマン』が半世紀を越えても愛される最大の理由である。
[anime-8]
■ 関連商品のまとめ
映像ソフトの変遷――VHSからBlu-rayへと受け継がれる“悪魔の記憶”
『デビルマン』の映像商品は、昭和から令和にかけて何度も形を変えながらリリースされてきた。 1980年代後半、アニメファン層の高まりとともに、東映ビデオから初のVHSシリーズが登場。全13巻構成で、各巻3話ずつを収録する形式だった。ジャケットには当時のセル画を使った迫力あるデザインが採用され、ビデオショップでは特設コーナーが設けられるほど人気を博した。 その後、1990年代に入ると、LD(レーザーディスク)版が登場。LDは高画質でコレクター向けのメディアとして注目されており、2枚組構成で各巻8話前後を収録。アニメマニアの間では「LD版の発色が最も“70年代の色”を再現している」と評された。 2000年代にはDVD-BOXが発売され、初の全話収録が実現。映像特典としてノンクレジットOP/ED、絵コンテ資料、設定原画ブックレットが封入されており、当時としては破格の内容だった。 さらに2015年にはBlu-ray BOXがリリース。これまで未公開だったパイロットフィルムや予告映像を初収録し、デジタルリマスターによる鮮明な映像でデビルマンの世界が蘇った。映像の精度だけでなく、音声トラックのノイズ除去も施され、田中亮一の声の質感がよりリアルに感じられると好評を博した。
ファンの間では「VHSのざらついた質感も味がある」「Blu-rayの色彩は魔界の空気を感じる」と、それぞれの時代のフォーマットごとに異なる愛し方が語られている。
書籍・コミック関連――アニメから原作へ、そして資料集の充実
『デビルマン』の世界は映像だけにとどまらず、書籍やコミックスとしても広く展開された。 まず、アニメ放送と並行して刊行されたフィルムコミック版は、テレビの名シーンをそのまま写真化し、吹き出しをつけて物語化したもの。テレビが家庭にない子どもたちにとって、“もう一度観られるアニメ”として人気を集めた。 続いて、永井豪原作による漫画版『デビルマン』は、アニメとは異なる重厚なテーマ性を持ち、後年アニメファンの必読書となる。講談社からは完全版・新装版・文庫版など多様な形で再刊され、累計発行部数は5000万部を突破。特にアニメとの比較解説を収めた「デビルマン研究読本」は、評論家や大学研究者によって高く評価されている。 2000年代以降は、アニメ制作資料や絵コンテ、スタッフインタビューを収録したムック本・設定資料集が続々と刊行。中でも東映アニメーション監修の『デビルマン大全』は、全キャラクター設定、美術ボード、セル画リストを収めた決定版としてファン必携の一冊となっている。 さらに2020年代には、電子書籍版も登場。スマートフォンで読めるようになり、若い世代にも“70年代アニメ文化”への入口を提供している。
音楽関連――阿久悠と都倉俊一が生んだ永遠のアニソン
アニメ『デビルマン』の音楽は、主題歌・挿入歌ともにアニメ史に残る名曲として評価が高い。 オープニングテーマ「デビルマンの歌」(作詞:阿久悠/作曲:三沢郷/歌:十田敬三とボーカル・ショップ)は、放送当時から絶大な人気を誇り、今でもアニメソングの代名詞としてカラオケランキングの常連となっている。 レコード会社・日本コロムビアから発売されたEP盤ドーナツレコードは、アニメ放送当時に10万枚を超えるセールスを記録。A面がOP、B面がED「今日もどこかでデビルマン」(作曲:都倉俊一)という構成で、2曲ともに“孤独なヒーローの哀しみ”を象徴する旋律だった。 後年、LPアルバム『デビルマン 音楽全集』として全BGMと効果音を収録した盤も登場。特に第15話「妖獣ララの恋」で流れる切ない弦楽曲は、“阿久悠の詩的世界を音で表した傑作”として再評価されている。 2000年代にはCD再販、2015年にはデジタル配信もスタート。SpotifyやApple Musicなどでも視聴可能となり、世代を超えて愛され続けている。ファンの間では「この曲を聴くと今も心が震える」「イントロだけで涙が出る」との声が多く、音楽面でも“時代を超えた作品”と呼ばれるゆえんだ。
ホビー・おもちゃ関連――昭和の子どもたちを熱狂させたデビルグッズ
1970年代当時、アニメ放送に合わせて数多くの玩具や日用品が登場した。 バンダイからは、デビルマンのソフビ人形シリーズが発売。翼を広げたポーズや、変身途中の中間形態など複数バリエーションが存在し、今ではコレクターズアイテムとして高値で取引されている。 また、当時の子どもたちに人気だったのが、ポピニカ製デビルマンバイク。メタル素材で重量感があり、変形ギミック付きの豪華仕様だった。 そのほかにも、デビルウィングを模したマント、デビルアイ型の水鉄砲、変身ベルト風の玩具など、子どもの想像力を刺激するアイテムが多数登場。特に「デビルマン変身セット」は、マスクと手袋、胸章がセットになった人気商品で、当時の男の子の憧れの的だった。 2000年代以降は、メガハウスや海洋堂からアクションフィギュアやスタチューモデルが発売され、デフォルメ版からリアル造形まで幅広いラインナップで展開。中でも「ララの最期」を再現したフィギュアはファンの涙を誘い、プレミア価格となっている。
ゲーム・デジタル関連――時代を超えて蘇るデビルマン
1980年代には『デビルマン』をモチーフにしたボードゲームやカードゲームが複数登場。すごろく形式でデーモンを倒しながら進むもので、子どもたちの間では“地獄を制覇するゲーム”として人気を集めた。 1990年代後半には、プレイステーション用ソフト『デビルマン』がリリース。アニメ版と異なり原作寄りのストーリーながら、当時のファンは「懐かしさと恐怖が同時に蘇る」と熱狂した。 近年ではスマートフォンアプリやパチスロ機でも『デビルマン』の名が復活しており、特に“アニメ版BGM”を再現した演出は往年のファンの涙腺を刺激する。 デジタルの世界でもデビルマンは進化を続け、ARフィギュアや3Dプリントによる立体化など、新しい形のファングッズも生まれている。
日用品・文房具・食玩――日常に潜むデビルの魅力
当時の子どもたちは、学校や家でもデビルマンと共に過ごしていた。 文具メーカーからは、デビルマンのイラスト入り下敷き・ノート・鉛筆・カンペンケースが発売され、給食時間にはデビルマンのランチボックスや水筒が人気だった。 駄菓子屋ではキャラクターカード付きチューインガムや消しゴム入りチョコレートが並び、友達同士でカードを交換し合うのが流行。これらの“日常系グッズ”が、アニメと現実の境界をなくし、子どもたちの日々にデビルマンを溶け込ませた。 また、女性ファン向けにはラメ入りノートやミラー付き手帳も販売され、牧村美樹やララを描いたデザインが特に人気を集めた。 2020年代には昭和レトロブームの影響で、こうした文房具や食玩の復刻シリーズも登場しており、親子二世代で楽しむファンも増えている。
コレクター文化と市場価値――“悪魔の遺産”の今
近年の中古市場では、『デビルマン』関連グッズの人気が再燃している。 オークションサイトでは、当時物のVHSやソフビ人形、ポスターなどが数千円から数万円で取引されることも珍しくない。特にBlu-ray BOX初回限定版やサイン入り台本などはプレミア価格となり、熱心なコレクターが入札を競い合う。 また、イベント限定のアートプリントや復刻ポスターも登場し、デビルマンのビジュアルがアートとして再評価されている。 こうした現象は、単なる懐古ではなく、「デビルマン=文化資産」という認識の広がりを示していると言える。
関連商品の魅力が語る『デビルマン』の普遍性
映像・音楽・書籍・ホビー――そのどれもが単なる商品ではなく、作品への“祈り”のように作られてきた。 時代が変わっても、ファンは新しい媒体でデビルマンと出会い続ける。VHSで観た人はBlu-rayで蘇り、レコードで聴いた人は配信で再び涙を流す。 これほど長く愛され、形を変えて語り継がれるアニメは稀である。 『デビルマン』は、モノとしてのグッズを超え、世代をつなぐ“記憶そのもの”になっているのだ。
[anime-9]
■ 中古市場
コレクター市場の現状――“悪魔の証明”としてのデビルマン
1972年放送の『デビルマン』は、放送から半世紀を経た今も、アニメコレクターや昭和レトロファンの間で高い人気を維持している。 特に、当時の放送関連グッズや映像ソフト初期版は希少価値が高く、国内の中古市場のみならず、海外のオークションサイトでも高額で取引されている。 かつて子どもたちが夢中で集めたソフビ人形やブリキ看板が、いまや文化的遺産として扱われているのだ。
中古市場では、「保存状態」と「初版か再販か」が価格を大きく左右する。
たとえば、1973年発売のポピー製デビルマンソフビ(全高約24cm)は、箱付き未開封であれば20万円前後、開封品でも美品であれば5~8万円で落札されることがある。
また、同時期に出回ったポピニカ・デビルマンバイクは、金属パーツの劣化が少ないものに限ってプレミアム価格がつき、2024年の市場では平均12万円前後と安定した取引を記録している。
こうしたアイテムは、単なる玩具ではなく、“昭和の空気”を閉じ込めたアートピースとして評価されている。
コレクターの中には、「当時の日本の夢と不安を象徴している」「デビルマンのフィギュアを飾ると家が静まる気がする」と語る人もいるほどだ。
映像メディアの価値変動――VHSからBlu-rayまで
映像ソフトは、中古市場において最も取引数の多いジャンルのひとつである。 1980年代後半に発売されたVHS版『デビルマン』全13巻は、現在でも一定の需要があり、1巻あたり1500~2500円程度で流通している。 ただし、すべての巻を揃えたフルコンプリートセットは希少で、帯付き・美品の状態では3万円以上の値がつくこともある。
1990年代のLD-BOXはコレクターズアイテムとして人気が高い。LD特有の大判ジャケットが額装しやすいため、「飾るために買う」層も多い。現在の市場価格は平均で2万~3万円前後。
2000年代初期のDVD-BOX(東映アニメーション製)は、内容の充実度から“名作BOX”と呼ばれ、現在も中古相場1万円台後半を維持。
そして、2015年発売のBlu-ray BOX(完全リマスター版)は、初回限定生産分に特典ブックレットが付属していたことから、現在では3万~4万円台まで高騰している。
オークションサイトでは未開封品に10万円近い価格がついた例もあり、今後も資産的価値が上昇する可能性がある。
音楽・レコード関連――アナログ文化の復権
『デビルマンの歌』のEPドーナツ盤は、アニソンコレクターの間で非常に人気が高い。 特に、1972年に発売されたコロムビア製オリジナル盤(品番:SCS-45xxシリーズ)は、ラベル中央の色が濃いオレンジで印刷された初期版が希少とされる。 美品であれば1万円前後、ジャケット付き完品では2万円を超えることもある。 B面の「今日もどこかでデビルマン」を目的に購入するファンも多く、レコード独特のノイズ混じりの音が“当時の空気”を再現するとして高い評価を受けている。
2000年代以降に発売されたアナログ復刻版は、3000~5000円程度と手に取りやすく、音楽ファンだけでなくインテリア目的で購入する層も増加している。
また、LP盤『デビルマン 音楽全集』(1973年初版)は、帯付き完品で4万円前後、再販盤でも1万円以上の値を維持しており、アニメサウンドトラックの中でもトップクラスの市場評価を誇る。
玩具・フィギュア関連――昭和レトロと現代アートの融合
1970年代当時に発売された玩具の多くは、素材の劣化が進んでいるため、状態の良い個体ほど高額になる。 ソフビシリーズは前述のとおり高騰しているが、加えて2000年代以降のリメイク版フィギュアにも注目が集まっている。 特に、海洋堂が2004年に発表した「リボルテック・デビルマン」は、可動構造の完成度が高く、現在では定価の約2倍、8000~1万円程度で取引されている。 また、2017年にメガハウスが発売した「レイコック・スタチューモデル」は、女性ファンの支持を集め、発売当時6000円台だったものが2025年現在で2万円前後に上昇している。
こうした“現代版デビルマン”のフィギュアは、アートコレクションとしても注目を浴びており、デザイナーや彫刻家によるコラボレーションモデルも登場している。
限定彩色版やイベント限定モデルなどは、発売直後に完売し、二次市場では即高騰する傾向にある。
書籍・資料集の中古動向――研究価値の高まり
『デビルマン大全』や『東映アニメヒーロー大図鑑』などの資料系書籍は、発行部数が少なく再版が限定的であるため、中古市場での需要が高い。 状態の良い初版『デビルマン大全』(2005年刊・東映アニメーション監修)は、2025年現在でも7000~1万円前後の高値で取引されている。 また、アニメ誌「OUT」「アニメージュ」などで特集された当時の記事をスクラップしたものが、マニアの間では“資料としての価値”を持ち、束ごとに数千円単位で売買されている。
近年はこうした紙媒体の一次資料がデジタル化によって失われつつあり、逆に“手に取れる過去”としての価値が見直されている。
古書店では「デビルマン特集号」だけを狙うコレクターも多く、アニメ文化史の研究分野でも資料的価値が高まっている。
オークション市場の傾向――国内と海外の違い
日本国内では、ヤフオク・メルカリなどの個人出品が主流だが、近年は海外ファンによるeBayやHeritage Auctionsでの取引も増えている。 特に北米では、“Devilman”名義で紹介されたアニメがカルト的な人気を持ち、海外のコレクターが日本製品を逆輸入している。 Blu-ray BOXやサウンドトラックLP、さらには設定資料のコピーまでが数百ドルで落札されることも珍しくない。
また、中国・韓国でもレトロアニメ文化への注目が高まり、『デビルマン』関連の複製ポスターや再版フィギュアが人気を集めている。
日本国内よりも海外の方が価格が安定して高いため、出品者が国外市場へ輸出するケースも多い。
結果的に、国内市場の在庫が減少し、価格の高騰をさらに後押ししている状況だ。
贋作・復刻版への注意点――真贋を見極める目
人気の高いシリーズであるがゆえに、贋作や非公式復刻版も少なくない。 特に1970年代のソフビやステッカーには、当時の型を流用した“リプロ版”が存在し、見た目では区別が難しいものも多い。 本物との違いは、素材の質感・刻印の有無・箱の印刷の発色など細部に現れる。コレクターの間では「光沢が強すぎるもの」「重さが軽いもの」は要注意とされている。 また、音楽レコードの復刻盤も一部で“帯のみ複製”されたものが出回っているため、購入の際は信頼できるショップや鑑定士の確認が推奨される。
未来の中古市場――文化遺産としてのデビルマン
中古市場は単なる物の売買ではなく、“記憶の継承”の場でもある。 『デビルマン』が今も取引され続けるのは、作品が放送から50年以上経ってもなお、人々の心を掴み続けている証だ。 アニメ史においても、70年代作品の中でここまで多様な形で流通し続けているタイトルは稀である。
今後は、NFTやデジタルコレクションなど、形を持たない“所有”の時代へと移行するだろう。
それでも、手に取れる実物のソフビやレコードには、デジタルでは得られない温度と香りがある。
“モノとして残る悪魔”――それがデビルマンの中古市場を特別なものにしている理由だ。
ファンにとって、それらは単なるコレクションではない。
それぞれが“あの日テレビの前で感じた衝撃”の記憶を封じ込めたタイムカプセルなのだ。
中古市場に息づく『デビルマン』は、これからも時代を越えて生き続ける――まるでデビルマン自身のように。
■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
デビルマン TVアニメ版 全39話BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】
デビルマンーTHE FIRST-(2) (その他) [ 永井豪とダイナミックプロ ]




 評価 5
評価 5デビルマンーTHE FIRST-(1) (その他) [ 永井豪とダイナミックプロ ]




 評価 2.5
評価 2.5デビルマン VOL.1〜3 全3巻 [DVDセット]
デビルマン オリジナルTVシリーズ ブルーレイ【永井豪の伝説的アニメを1080p高画質で】全39話収録
デビルマン VOL.3 [ 田中亮一 ]




 評価 4
評価 4DEVILMAN crybaby COMPLETE BOX(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 内山昂輝 ]




 評価 5
評価 5[限定][コラボ] デビルマン 魔界への誘い25度 900ml 焼酎 黒麹 芋 永井豪 箱なし 【 お酒 芋焼酎 酒 記念日 ギフト 蒸留酒 お祝い 内祝..




 評価 5
評価 5デビルマン VOL.1/2 全2巻 [Blu-rayセット]
【漫画全巻セット】【中古】デビルマン[文庫版] <1〜5巻完結> 永井豪




 評価 5
評価 5
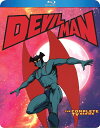
![デビルマンーTHE FIRST-(2) (その他) [ 永井豪とダイナミックプロ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3163/9784778033163_1_3.jpg?_ex=128x128)
![デビルマンーTHE FIRST-(1) (その他) [ 永井豪とダイナミックプロ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3156/9784778033156_1_3.jpg?_ex=128x128)
![デビルマン VOL.1〜3 全3巻 [DVDセット]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mifsoft/cabinet/319/6202111260319.jpg?_ex=128x128)

![デビルマン VOL.3 [ 田中亮一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0375/4988101200375.jpg?_ex=128x128)
![DEVILMAN crybaby COMPLETE BOX(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 内山昂輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9279/4534530109279.jpg?_ex=128x128)
![[限定][コラボ] デビルマン 魔界への誘い25度 900ml 焼酎 黒麹 芋 永井豪 箱なし 【 お酒 芋焼酎 酒 記念日 ギフト 蒸留酒 お祝い 内祝..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ricaoh/cabinet/299999/200802.jpg?_ex=128x128)
![デビルマン VOL.1/2 全2巻 [Blu-rayセット]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mifsoft/cabinet/326/6202111260326.jpg?_ex=128x128)
![【漫画全巻セット】【中古】デビルマン[文庫版] <1〜5巻完結> 永井豪](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/c03-0082.jpg?_ex=128x128)