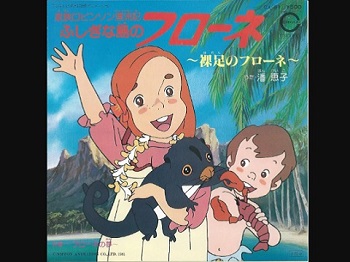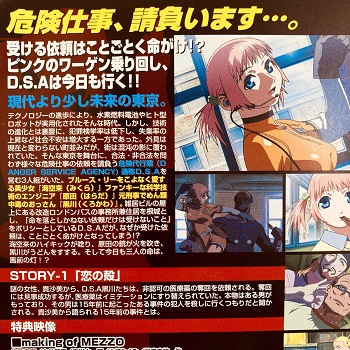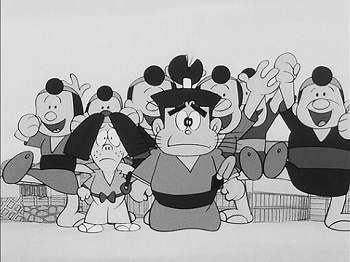【中古】フルタ 20世紀漫画家コレクション ~横山光輝の世界~「バビル二世」単品
【原作】:横山光輝
【アニメの放送期間】:1973年1月1日~1973年9月24日
【放送話数】:全39話
【放送局】:NETテレビ系列
【関連会社】:東映
■ 概要
● 作品の基本情報と放送時期
1973年1月1日から9月24日まで、NETテレビ(現・テレビ朝日)系列で放送されたテレビアニメ『バビル2世』は、横山光輝原作の同名漫画を基に制作された全39話の作品である。毎週月曜日の19時から19時30分というゴールデンタイムに放映され、少年層を中心に大きな人気を集めた。横山作品ならではの重厚なテーマと超能力アクション、さらに東映動画による丁寧なアニメーションが融合した本作は、1970年代初期のテレビアニメ史の中でも特に“正義の超能力者もの”というジャンルを確立させた存在といえる。作品の根幹にあるのは「孤高のヒーロー像」と「科学と神話の融合」という構図であり、当時の子どもたちにとっては未知の力を操る少年ヒーローの姿が強烈な印象を残した。
● 原作との関係と設定の特徴
原作漫画『バビル2世』は『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)で1971年から1973年にかけて連載された。宇宙人の血を引く少年が、人類の平和を守るために悪の超能力者と戦う――この壮大なテーマを、アニメ版はよりドラマチックにアレンジしている。原作ではややSF色が強く、哲学的な要素も多く含まれていたが、テレビアニメ版では視聴者層を意識して人間関係のドラマ性が前面に押し出された。特に主人公・浩一が「バビル2世」として覚醒した結果、育ての親である古見家と別れるという設定が追加され、家族愛と宿命の狭間で揺れる心理描写が深く描かれた点が特徴的である。この改変によって作品にはヒーロー物語でありながらヒューマンドラマ的な要素が加わり、当時の他のアクションアニメとは一線を画した。
● バビルの塔と三つのしもべ
作品の象徴的存在が「バビルの塔」である。荒れ果てた砂漠の中にそびえるこの塔は、超科学文明の遺産であり、バビル2世の力の源泉でもある。塔の内部には巨大なコンピューターやエネルギー装置が存在し、ロプロス・ロデム・ポセイドンという三体の“しもべ”を統率するシステムとして機能している。 ロプロスは鋼鉄の翼を持つ巨大怪鳥であり、空を飛び電撃を放つ能力を持つ。ロデムは黒豹に変身できる妖獣で、人間の姿にも変化可能な自在性を備える。そしてポセイドンは巨人のロボットで、海上・陸上を問わず圧倒的な破壊力を誇る。これら三体は単なる兵器ではなく、バビル2世の忠実な仲間であり、彼の心と意志を共有する存在として描かれる。アニメ版では、それぞれのキャラクターに個性が与えられ、ロデムの人間態での知的な助言や、ロプロスの戦闘時の雄叫びなど、細部まで演出が工夫されていた。これにより視聴者は単なるロボット・怪獣の戦闘ではなく、主人公と仲間たちの“共闘”としてドラマを楽しむことができた。
● 敵キャラクター・ヨミとの対立構造
主人公・バビル2世の宿敵となるのが、もう一人のバビル1世の末裔にして悪の超能力者・ヨミである。ヨミは人類支配を目的に世界各地で暗躍する存在で、冷徹な知略と圧倒的な超能力を武器に世界征服を企てる。彼は単なる“悪の権化”ではなく、自らの血筋と力を人類のために使うべきか、それとも支配に利用すべきかという葛藤を抱えた存在として描かれており、原作以上にアニメ版では複雑な人物像として表現された。彼の支配下にある兵器群やロボット軍団は、1970年代アニメに特有のスーパーロボット的要素を感じさせ、視覚的な迫力とともに視聴者を魅了した。バビル2世とヨミの対決は、単なる善悪の衝突ではなく、“同じ力を持ちながら違う道を選んだ者同士”の宿命的な戦いとして描かれている。
● アニメ版独自のドラマ展開
アニメ『バビル2世』は原作の基本設定を踏まえつつも、独自のエピソードを多く取り入れている。中盤以降は特に、主人公・浩一と従姉妹の由美子との再会をめぐるエピソードが感情的な軸として描かれた。由美子は浩一を探して各地を旅するが、いつもすれ違いに終わるという構成が繰り返される。この“再会できない悲しみ”は作品全体の叙情性を高め、超能力アクションにヒューマニズムを添える要素となった。さらに第27話以降では、舞台が北海道のワタリ牧場へと移り、浩一が平穏な日常を送る中で再び復活したヨミとの決戦に臨む展開となる。この構成変更によって物語に新鮮さが加わり、後半は牧場の人々との交流や自然描写など、アニメならではの演出が際立っていた。
● 制作背景と時代的意義
『バビル2世』のアニメ化は、当時の東映動画が持つ技術力と演出力を最大限に発揮した事例として知られる。監督・演出陣はSFアクションにリアリティを与えるため、背景美術やメカデザインに力を入れ、異国的な砂漠や塔の内部構造を緻密に描写した。また、音楽を担当した菊池俊輔による勇壮なテーマ曲は、後年まで語り継がれる名曲として評価が高い。特にオープニング「バビル2世」の力強いメロディは、視聴者に“未知への冒険”を感じさせ、物語全体の世界観を象徴する存在となった。 1970年代初期は『デビルマン』『マジンガーZ』など、強大な力を得た若者が葛藤しながら戦うヒーロー像がテレビを席巻していた時期であり、『バビル2世』もその潮流の中で位置づけられる。だが本作が特に異彩を放つのは、“科学”と“神話”を結びつけた点である。古代の遺産と未来の科学が融合する世界観は、後の日本アニメにおけるSFファンタジー表現の礎となった。
● 放送後の反響と再評価
放送当時から高い人気を誇った『バビル2世』は、特に少年層に圧倒的な支持を得た。再放送の回数も多く、1970年代後半には大阪を中心に「バビル2世ファンクラブ」が結成されるなど、長期的なファン層が形成された。放映終了後もその影響力は続き、1980年代以降のアニメや特撮作品において「超能力」「遺伝的宿命」「孤高のヒーロー」といったテーマが広く取り入れられるきっかけとなった。また、本作は1970年代東映動画の代表作として映像研究やアニメ史の文脈でも語られ、リメイクや続編作品が制作されるなど、長年にわたって文化的遺産として受け継がれている。2000年代に入ってからはDVDやBlu-rayの発売、音楽集の復刻なども行われ、新世代のアニメファンにも再評価される存在となった。
● 総評
『バビル2世』は、単なる少年向けアクションアニメの枠を超えた“孤独と使命の物語”である。主人公・浩一の成長、仲間との絆、そして宿敵ヨミとの永遠の対決――これらの要素が緻密に絡み合い、一つの壮大な神話世界を構築している。放送から半世紀を経た今なお、多くのファンに愛され続ける理由は、そこに描かれた普遍的なテーマと、時代を超えて響くドラマ性にあるといえる。
[anime-1]■ あらすじ・ストーリー
● 少年・古見浩一の運命の目覚め
物語は、一見どこにでもいる普通の少年・古見浩一が、ある夜から繰り返し見る奇妙な夢に悩まされるところから始まる。夢の中には、見たこともない巨大な塔と、呼びかけるような不思議な声が響く。浩一はそれが単なる夢ではないと感じていた。そしてある日、空を裂くように現れた巨大な怪鳥ロプロスが彼の前に降り立つ。その瞬間から彼の運命は動き始める。ロプロスに導かれた浩一は、砂漠の奥地にそびえる“バビルの塔”へとたどり着く。そこは太古の宇宙人・バビル1世が地球に遺した超科学の要塞であり、浩一は自らがその末裔、すなわち「バビル2世」であることを知らされる。
● バビル2世としての覚醒
塔の中心部で彼を待っていたのは、巨大コンピューターが映し出す幻影のようなバビル1世のメッセージだった。人類の進化と存続を見守るため、バビルの塔とその力を継ぐ者が必要であること、そして彼こそがその使命を受け継ぐ存在であることを告げられる。浩一はその日から、テレパシー、念動力、電磁波操作など、人間の限界を超えた超能力に目覚める。塔の守護者である三体のしもべ――ロプロス、ロデム、ポセイドン――も彼の指令に従い、地球を守る戦士としての人生が始まった。 だがその覚醒は同時に、彼がこれまで大切にしてきた“普通の生活”を失うことも意味していた。彼を育ててくれた古見家とは別れざるを得ず、特に従姉妹の由美子に別れを告げる場面は、作品の感情的な柱として強く印象に残る。少年がヒーローへと変わる瞬間、その裏には痛みと孤独があるというテーマが、この作品を単なる冒険譚ではなく深い人間ドラマへと昇華させている。
● 宿敵ヨミの登場と世界的陰謀
バビル2世の前に立ちはだかる最大の敵が、ヨミという超能力者である。彼もまたバビル1世の血を引く者だが、その思想は真逆だった。彼は「人類は未熟な存在であり、強者が支配すべき」と信じ、世界征服を計画する。ヨミは自らの本拠地を築き、各国の科学者や軍事力を掌握して超能力者軍団を組織。彼の冷酷な知略は国家をも脅かし、バビル2世との対決は世界規模の戦いとなっていく。 初期のエピソードでは、ヨミが各地で引き起こすテロや超能力犯罪をバビル2世が阻止していく形式で物語が進む。超能力対決に加え、社会問題や国際政治を意識した要素が描かれる点も特徴であり、1970年代のテレビアニメとしては異例のスケール感を持っていた。
● 由美子とのすれ違いと人間的葛藤
中盤以降の展開で印象的なのが、由美子の存在である。浩一を兄のように慕う従姉妹であり、彼が失踪した後も行方を追い続ける。由美子はバビル2世の正体を知らないまま、各地の事件を調査し、彼の姿を追いかけるが、いつもほんの少しの差で再会を逃す。アニメではこの“すれ違い”の描写が繰り返し挿入され、戦闘の合間に人間味と哀愁を添える構成となっている。 浩一もまた、彼女の存在を心の支えとしている。だが、世界を守る使命を背負う彼には、個人的な幸せを追う余裕はない。彼が塔に戻るたびに、由美子の笑顔が遠ざかる。正義のために戦うとは何か、力を持つ者の責任とは何か――このシリーズは、少年の成長物語であると同時に、“力と孤独”を描いた哲学的作品でもある。
● さまざまなエピソード構成
『バビル2世』の物語は1話完結型を基本としつつ、全体を貫くヨミとの戦いが軸になっている。各エピソードでは、ヨミの部下が送り込む怪物やロボットとの戦闘、あるいは人間社会に潜む陰謀を暴くといった形で進行する。時には科学兵器を利用した戦争阻止、またある時は超能力犯罪者の暴走など、多彩なテーマが扱われた。 特に印象深いのは、人間と超能力者の間にある“理解と恐怖”を描いた回である。超能力を恐れ排除しようとする人々と、守るために戦うバビル2世の姿は、単なる勧善懲悪ではなく「力の使い方」を問う寓話として描かれている。こうした社会的要素が子ども向け番組に織り込まれていた点が、本作の奥行きを支えている。
● 北海道編への転換と新たな仲間たち
物語後半、第27話以降では舞台が一新される。バビル2世は戦いに疲れ、北海道の「ワタリ牧場」で静かに暮らすようになる。ここで登場する牧場主・恒太郎や孫娘のユキ、牧童チー坊など、新しい登場人物たちとの交流が始まる。彼らは浩一の正体を知らず、普通の青年として接する。浩一は彼らとの穏やかな日々の中で“人としての温もり”を取り戻すが、そこにもヨミの魔の手は忍び寄っていた。 この牧場編は、戦い一辺倒だった前半とは異なり、自然と人間の関係、平和とは何かというテーマを描き出す。特に雪原の中で繰り広げられる戦闘シーンは映像的にも印象的で、白い大地に立つバビル2世と黒衣のヨミ軍団の対比は、まるで善と悪の象徴のように美しく構成されている。
● 最終決戦と“孤独な勝利”
クライマックスでは、再び復活したヨミとの全面対決が描かれる。ヨミは人類全体を掌握するため、超能力を拡張する装置を完成させ、地球規模の支配網を築こうとする。これに対し、バビル2世は三つのしもべを率い、決死の戦いに挑む。ロプロスの空戦、ポセイドンの地上突破、ロデムの潜入作戦――それぞれの戦闘が緻密に構成され、最終回に向けて緊迫感が高まっていく。 決戦の中で、浩一はヨミの本心を知る。彼もまた孤独な存在であり、自らの宿命に抗えなかった男であることを悟る。戦いの果てに勝利を収めたバビル2世だが、その表情には哀しみが宿っていた。塔に戻った彼は、再び孤独な守護者としての使命を果たすため、静かに砂漠へと姿を消す。派手な勝利宣言もなく、ただ風の音と共に幕を閉じるこのラストは、多くの視聴者に強い余韻を残した。
● 物語構成の魅力とテーマの深化
『バビル2世』のストーリーは、単なる超能力バトルを越えて、人間存在そのものを問う深いテーマを内包している。力を得た者が背負う孤独、運命に抗うことの難しさ、そして友情や愛情の儚さ――こうした普遍的な感情が随所に織り込まれている。アニメではバトルと感情描写のバランスが巧みに取られ、視聴者は毎回のエピソードを通して、主人公の精神的成長を感じ取ることができる。 また、ロプロス・ロデム・ポセイドンといった三体のしもべは、単なる兵器ではなく、主人公の内面を映す象徴として機能している。ロプロスは理性と勇気、ロデムは知性と迷い、ポセイドンは力と責任を表す存在として、それぞれの戦いが浩一の心理的変化と呼応している構成だ。このようにして、『バビル2世』は少年の覚醒から成長、そして孤高の使命へと至る壮大な物語として完成されたのである。
[anime-2]■ 登場キャラクターについて
● 主人公・バビル2世(古見浩一)
本作の中心人物であるバビル2世こと古見浩一は、物語の開始時点では普通の少年として暮らしていた。しかし、繰り返し見る不思議な夢をきっかけに、自分が“バビル1世”の末裔であること、そして人類の守護者としての使命を持つ存在であることを知る。浩一のキャラクター性は、単なるヒーロー像にとどまらず、どこか人間的な弱さを抱えた少年として描かれている点に大きな魅力がある。 彼は超能力を手に入れてからも万能ではなく、葛藤し、迷い、孤独と戦いながら正義を模索する。特に家族との別れや、従姉妹・由美子とのすれ違いのエピソードでは、“力を持つことの代償”というテーマが強調されている。アニメ版では、神谷明による声の演技が印象的で、少年らしい繊細さと、正義の戦士としての決意の両面を見事に表現していた。戦闘時の緊迫した叫びと、日常シーンでの穏やかな口調の対比がキャラクターをより立体的に見せ、視聴者の共感を得た。
● 宿敵・ヨミ
ヨミは物語全体の“影の主役”とも言える存在だ。彼もまたバビル1世の血を引く超能力者だが、その思想はバビル2世とは正反対である。彼は「人間は愚かであり、導くべきは力を持つ者」と考え、世界支配を企てる。冷酷で計算高い彼の行動は、単なる悪役の枠を超えており、理想と現実の狭間で苦悩する“もう一人のバビル2世”という側面を持っている。 アニメでは大塚周夫がその声を担当し、低く響く声と落ち着いた語り口によって、圧倒的な存在感を放った。彼の「人類の未来を支配によって救う」という信念は、主人公にとっての最大の試練であり、単なる善悪の対立ではなく“思想の衝突”として描かれている。特に最終盤で明らかになる、ヨミの孤独や宿命への苦悩は、敵でありながら人間的な哀しみを感じさせる描写で、多くの視聴者の心に残った。
● ロプロス ― 空を制する鋼鉄の怪鳥
ロプロスは、バビル2世に仕える三体のしもべの一体であり、空を象徴する存在である。鋼鉄の翼を持つ巨大な怪鳥で、最高速度はマッハ数倍に達するとも言われる。空を駆け、電撃を放つその姿は、まさにバビル2世の「目」と「爪」である。彼は主人公が危機に陥るたび、天を切り裂いて登場し、子どもたちの心を熱くさせた。 アニメ版ではロプロスの咆哮とともに空を飛ぶカットが毎回登場し、その圧倒的スケール感が作品の魅力を支えていた。ロプロスは単なる乗り物ではなく、バビル2世の意思を理解し、彼の命令を忠実に実行する“知性ある生物”として描かれている。空を舞うロプロスのシーンは、当時のアニメーション技術の限界を超える表現として評価が高く、のちにロボットアニメの空戦描写に大きな影響を与えたとされている。
● ロデム ― 変幻自在の黒豹
ロデムは、バビル2世のしもべの中でも最も神秘的な存在である。普段は漆黒の豹の姿をしているが、人間の姿にも変身できる能力を持つ。変身後の姿では冷静で知的な口調でバビル2世を補佐し、作戦立案や情報収集などの役割を果たす。アニメでは、獣態と人間態の両方に声優が配置されており、野田圭一と山口奈々によって異なる声の表現が行われた。 ロデムは単なる従者ではなく、しばしばバビル2世に対して意見を述べる“助言者”としての役割を担う。彼の冷静な判断力と高い知性は、激情的な主人公を支える存在でもあった。その反面、時折見せる悲しげな表情や意味深な台詞からは、彼自身にも“過去と感情”があることを感じさせる演出がなされており、ミステリアスな魅力で人気を博した。
● ポセイドン ― 海と陸を支配する巨人兵器
三体のしもべの中で最も巨大かつ力強いのがポセイドンである。全長数十メートルの巨体を誇り、海上・陸上を自在に移動できる万能戦闘マシンとして描かれている。腕部から発射されるミサイルや、足元の推進装置による突進攻撃など、まさに“バビル軍団の切り札”と言える存在だ。 ポセイドンは感情を持たない機械的な存在として描かれることが多いが、アニメ版では時折、バビル2世のピンチに反応するような動きを見せる場面があり、まるで魂が宿っているかのような印象を与える。巨大ロボットが登場するシーンでは特に作画に力が入っており、メカニカルな動きと重厚なサウンドエフェクトが融合し、視聴者に強烈なインパクトを残した。後のスーパーロボット作品における「巨大兵器の人格化」の原型としても注目されている。
● 古見由美子 ― 人間ドラマの象徴的存在
由美子は主人公・浩一の従姉妹であり、彼に密かな想いを寄せる少女として登場する。浩一が姿を消してからも彼を信じ、各地で彼の足跡を追いかける彼女の姿は、戦いの物語に“人間の温かさ”を与えている。再会を果たせないまま物語が進むという演出は、視聴者に切ない感情を呼び起こした。 由美子のキャラクターは“普通の人間”として描かれているが、だからこそ超能力者である浩一との対比が際立つ。人間らしい優しさと無力さ、そして彼女の純粋な思いが、作品全体のテーマである“孤独な力の代償”を際立たせている。声を担当した野村道子は、繊細で柔らかい声質で由美子の感情を丁寧に表現し、彼女を単なる恋愛要素ではなく、主人公の心の支柱として位置づけた。
● ワタリ牧場の人々 ― 平和な日常の象徴
物語後半に登場する恒太郎、孫娘ユキ、牧童チー坊といったワタリ牧場の面々は、戦いから離れた平和な日常を象徴する存在である。彼らは浩一の正体を知らずに接することで、ヒーローとしてではなく“ひとりの青年・浩一”の姿を引き出す。ユキの素朴な笑顔やチー坊の無邪気さは、戦いに疲れたバビル2世に安らぎを与える一方で、彼が再び戦いの渦へ戻る決意を固めるきっかけにもなる。 この牧場編におけるキャラクター描写は、アクション主体の序盤とは異なり、ヒューマンドラマとしての深みを増している。特にユキとの交流シーンでは、浩一の心の変化が静かに描かれ、戦士である前に“人間であること”を再認識する重要な要素となった。
● バビル1世とコンピューター
バビルの塔を統括する存在であり、バビル2世の精神的な導き手となるのがバビル1世の遺したコンピューターである。アニメでは矢田耕司の重厚な声によって、冷静かつ威厳に満ちた語りが響く。彼はしばしばバビル2世に助言を与えるが、同時に“感情ではなく理性に従え”と命じる姿勢を崩さない。その厳格さが、主人公を精神的に鍛える存在として描かれている。 この人工知能的存在は、当時としては非常に先進的な発想であり、“人と機械の共存”というテーマを先取りしたものだった。感情を持たないコンピューターが語る“使命”と、人間としての感情に悩むバビル2世との対比が、作品に哲学的な奥行きを与えている。
● キャラクターの多層性とドラマ性
『バビル2世』に登場するキャラクターは、単純な善悪の二元論で語れない複雑さを持っている。主人公は正義を貫くために孤独を受け入れ、敵であるヨミもまた自らの信念に殉じる。ロデムや由美子といった周囲の存在は、彼に人間らしさを思い出させる要素として機能している。これらのキャラクター群が絡み合うことで、作品は単なるアクションアニメではなく、深い心理劇として成立しているのである。 そして、それぞれの声優陣の演技がキャラクターをさらに際立たせた。神谷明、大塚周夫、野村道子という名優たちによる声の表現は、視覚を超えて感情を伝える力を持ち、放送から半世紀経った今でもファンの記憶に鮮明に残っている。
[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
● 音楽が作品に果たした役割
1970年代初期のテレビアニメにおいて、主題歌や挿入歌は単なるオープニング演出の一部ではなく、作品そのものの世界観を形づくる重要な要素だった。『バビル2世』も例外ではなく、音楽が持つ力が作品の印象を決定づけたといっても過言ではない。作曲を担当したのはアニメ音楽界の巨匠・菊池俊輔であり、彼の手によるメロディはヒーローアニメの枠を超えてドラマティックな深みを持っていた。 菊池俊輔が描いた旋律には、「孤独」「使命」「正義」といった『バビル2世』の根幹テーマが凝縮されている。勇壮でありながらもどこか哀しさを秘めたメロディラインは、主人公・浩一の宿命そのものを象徴しており、視聴者に強烈な印象を残した。特にオープニングとエンディングの楽曲は、放送から数十年経った今でもアニメファンの間で語り継がれる名曲として高い人気を誇っている。
● オープニングテーマ「バビル2世」
オープニングテーマ「バビル2世」は、水木一郎とコロムビアゆりかご会による力強い歌声が特徴的な一曲である。作詞は東映二、作曲・編曲は菊池俊輔によるもので、ヒーローソングとしての完成度が極めて高い。 曲の冒頭で響く「出でよロプロス、ポセイドン、ロデム!」という掛け声にも似た歌詞は、視聴者に鮮烈な印象を与えた。テンポは中速ながら、打ち鳴らされるドラムと金管のリズムが力強く、まるでバビルの塔の心臓が鼓動するかのような迫力を感じさせる。 歌詞には「地上の悪を打ち砕け」という明確なメッセージがあり、当時の少年たちにとって“正義の象徴”そのものであった。水木一郎の伸びやかな高音と、少年合唱団のコーラスが交互に重なり合う構成は、勇ましさの中にも清らかさを感じさせる絶妙なバランスを生み出している。 また、この楽曲は音楽的にも革新的で、ヒーローソングの中にマイナー調のメロディを組み込むことで、戦いの裏に潜む悲しみを表現している。これにより、単なる勝利賛歌ではなく「孤独な戦士の歌」としての奥行きを持たせることに成功した。
● エンディングテーマ「正義の超能力少年」
エンディングテーマ「正義の超能力少年」は、オープニングとは対照的に静けさと哀愁を基調とした曲調である。作詞・作曲・編曲を菊池俊輔が一貫して手がけ、水木一郎が独唱する形で構成されている。 この曲は、戦い終えたバビル2世の“心の内側”を描くような内容であり、ヒーローの強さだけでなく弱さや孤独をも感じさせる。リズムはスローテンポで、バックにはストリングスが柔らかく流れる。サビに入ると、静かな決意を込めた水木の声が響き、「明日も戦う ひとりの少年」というフレーズが観る者の胸に深く刺さる。 この楽曲は放送当時、子どもたちだけでなく大人からも評価され、アニメソングとしては珍しく“詩的な余韻”を残す作品として注目された。物語の締めくくりとしてこの曲が流れるたび、視聴者はバビル2世の孤独と使命を改めて感じ取ったのである。アニメ史上においても、これほどキャラクターの心理と密接に結びついたエンディングテーマは数少ない。
● イメージソングとキャラクターソング
『バビル2世』の放送期間中には、アニメの人気上昇に伴っていくつかのイメージソングが制作された。その中でも代表的なのが「愛はまぼろし」と「戦士ひとり」である。 「愛はまぼろし」は、水木一郎自身が作詞・作曲・歌唱を担当した楽曲で、主人公・浩一の内面にある“人間的な寂しさ”をテーマにしている。バビル2世という強大な力を持ちながら、決して人としての感情を失わない姿を、哀愁漂うメロディと共に表現している。ロデムや由美子との関係を暗示するような叙情的な歌詞が印象的で、まるでアニメ本編の外伝的な一曲として機能していた。 一方の「戦士ひとり」は、脚本家・辻真先による作詞で、水木一郎が力強く歌い上げる。こちらは孤高のヒーローとしての決意と誇りを象徴する楽曲であり、「友を持たずに立ち上がる者」という歌詞が物語の核心を突いている。アレンジには青木望が参加しており、勇壮でありながらも緻密なオーケストレーションが印象的だ。 これらのイメージソングは、番組内では使用されなかったものの、当時のレコードやイベントなどを通してファンの間で広く知られるようになった。現在ではこれらの楽曲がCD復刻版やデジタル配信で再び聴けるようになり、当時の熱気をそのまま感じ取ることができる。
● 菊池俊輔サウンドの魅力と功績
作曲家・菊池俊輔は、『バビル2世』を通じて、アニメ音楽に“重厚なストーリー性”を持ち込んだ第一人者のひとりである。彼の楽曲は単に主題歌を支えるものではなく、作品全体を統一する“音の物語”を構築していた。彼が手がけた劇伴(BGM)は、戦闘シーンでは金管を中心にした勇ましい曲調を採用し、静寂のシーンでは弦楽器やオルガンを使って神秘的な雰囲気を作り出すなど、シーンごとに緻密に設計されていた。 特に印象的なのは、バビルの塔内部の描写に使われる低音主体のテーマである。そこには古代文明と科学の融合を想起させる荘厳な響きがあり、視聴者に“人智を超えた力”を感じさせた。また、ロプロスやロデム登場時のテーマにはそれぞれ異なる旋律が用意されており、キャラクターごとに個別の音楽的個性が付与されていた点も画期的だった。 菊池俊輔の音楽は、ただの背景音ではなく、物語の感情を導くナレーターのような存在だった。その影響は後のアニメ作品――たとえば『ドラゴンボール』『タイガーマスク』『UFOロボ グレンダイザー』など――にも色濃く引き継がれている。
● 視聴者が感じた音楽の力
放送当時の視聴者たちは、これらの楽曲を通して“作品の一部としての音楽”を強く意識した。特に子どもたちの間では、放送時間になると主題歌を一緒に歌う光景が日常的だったという。水木一郎の堂々とした歌声は、少年たちにとって憧れそのものであり、彼の歌声を聞くだけで「バビル2世の世界」が立ち上がるような感覚を覚えたという証言も多い。 また、大人の視聴者からも「アニメ音楽とは思えないほど完成度が高い」という声が多く寄せられた。当時のレコード市場では主題歌シングルが子ども向け雑誌の付録やソノシート形式で発売され、家庭でも繰り返し聴かれるほどの人気を誇った。音楽はアニメの人気を後押しし、放送終了後も長く愛され続けた。
● 後年のリメイクと再評価
2000年代以降、『バビル2世』の主題歌はさまざまな形でリメイクやカバーが行われた。特に水木一郎自身が晩年までライブで歌い続けたことで、世代を超えた支持を得た。新録バージョンではオーケストラアレンジやデジタル音源を加え、原曲の力強さに壮大なスケール感が加わった。 また、2010年代にはアニメソング専門イベントで若手アーティストがこの楽曲をカバーし、新世代のファンが作品を知るきっかけとなった。オープニング「バビル2世」はもはや一つの文化的アイコンとして、1970年代アニメ音楽の象徴となっている。音楽を通じて作品が現代にも息づいていることは、アニメが単なる映像作品ではなく“総合芸術”であることを示す証でもある。
[anime-4]■ 声優について
● キャラクターに命を吹き込んだ声の力
1970年代のアニメーションにおいて、声優の存在はまだ一般には「裏方」としての印象が強かった。しかし、『バビル2世』は声の演技によってキャラクターを生き生きと立ち上げた作品のひとつである。台詞だけでなく、呼吸の間、感情の揺れ、戦闘時の叫び――すべてがドラマの構成要素として機能し、声優陣の表現力が物語の深みを決定づけた。 アニメ史においても、『バビル2世』のキャスティングは後世の多くの作品に影響を与えた。主演に若手ながら抜群の表現力を誇る神谷明、宿敵ヨミ役には重厚な存在感を持つ大塚周夫。この二人の対照的な声が作品全体を支える柱となった。さらに、ロデムや由美子といった脇役陣も当時の実力派声優が揃っており、群像劇としての完成度を高めている。
● 神谷明 ― バビル2世(古見浩一)役
主人公・バビル2世を演じた神谷明は、当時まだデビューから間もない若手であった。しかし、彼の声にはすでに確固たる個性があり、清涼感と芯の強さを兼ね備えていた。 神谷の演技の特徴は、感情の振れ幅の大きさにある。通常時の浩一では柔らかく穏やかなトーンを用い、由美子や古見家とのシーンでは人間的な優しさを滲ませる。一方で、バビル2世として戦闘に臨む際には声のトーンを低く、言葉を短く鋭く切り出す。まるで二つの人格が同居しているかのような演技で、彼が“少年から戦士へと変わる瞬間”を声だけで表現しているのが印象的だ。 また、神谷はアフレコ現場でも妥協を許さず、戦闘シーンでは実際に体を動かしながら声を出していたという逸話も残っている。その熱演がアニメに命を吹き込み、後の代表作『キン肉マン』や『シティーハンター』などへと続く彼のキャリアの基礎を築いた。『バビル2世』は、まさに神谷明が“真の主役声優”として開花した作品だった。
● 大塚周夫 ― ヨミ役
宿敵ヨミを演じた大塚周夫の存在感は、作品全体の空気を一変させるほどの重みを持っていた。彼の声は低く、静かな抑揚の中に不気味な威厳を宿しており、単なる悪役ではなく知性と哀愁を併せ持つ“哲学的な敵”としてヨミを際立たせている。 大塚の演技が際立つのは、怒りや憎しみを爆発させるのではなく、冷静な語りの中に狂気を滲ませる点だ。バビル2世との対話シーンでは、一見穏やかな声色で「人類を導くのは我々だ」と語るが、その裏に潜む支配欲と孤独を観る者に感じさせる。この“静かな恐怖”の演出こそ、大塚周夫の真骨頂であり、後年の『ルパン三世』シリーズのゼニガタ警部などとは異なる渋みを持つ演技であった。 また、アニメ後半で見せるヨミの悲哀や苦悩の表現も圧巻である。自らの宿命を悟りつつも滅びへ向かう男の声には、敵でありながらも共感を覚えさせる深さがあった。視聴者の多くが「ヨミは悪でありながら魅力的だった」と語るのは、大塚の演技力によるところが大きい。
● 野田圭一・山口奈々 ― ロデム役
変幻自在のしもべロデムは、獣態と人間態の二つの姿を持つ特異なキャラクターであるため、それぞれ別の声優が担当していた。獣態を担当したのは野田圭一、人間態を演じたのは山口奈々である。 野田圭一はロデムの獣形態において、低く響く声で威圧感と忠誠心を同時に表現した。咆哮や戦闘時の叫びには動物的な迫力があり、まるでロデムが生きているかのようなリアリティを与えている。一方の山口奈々は、人間態ロデムを知的で落ち着いた口調で演じ、戦略的な助言を与える存在としての品格を見事に表現した。 この男女二人による“二重表現”は、当時としては非常に珍しい試みであり、ロデムというキャラクターをより立体的に見せる効果をもたらした。視聴者からは「ロデムが話すシーンが怖いのに美しい」という声も多く、神秘性と人間味を併せ持つキャラクターとして高い人気を得た。
● 野村道子 ― 古見由美子役
由美子を演じた野村道子は、柔らかな声質と自然な演技で、物語の中に“癒し”と“現実”をもたらした。彼女の演技には誇張がなく、日常会話の中に真心が感じられる。そのため、戦闘や超能力といった非日常の要素が多い『バビル2世』の中で、彼女の声は視聴者を“人間の世界”へと引き戻す重要な役割を果たした。 特に印象的なのは、浩一を思って涙するシーンや、彼の行方を追う場面での独白である。野村の声には少女の純粋さと強さが同居しており、「逢いたいけれど逢えない」という複雑な感情を繊細に表現している。このキャラクターが単なる“恋する少女”に留まらなかったのは、野村道子の細やかな演技によるものである。
● サブキャラクターとベテラン陣の支え
『バビル2世』の魅力を支えたのは、主役だけではない。古見家の父母役には北川国彦と坪井章子、牧場主の恒太郎役には兼本新吾、孫娘ユキ役には田浦環、牧童チー坊役には山本圭子と、ベテラン・中堅声優が多数参加している。特に山本圭子の演じるチー坊は、明るく無邪気でありながらも時に鋭い洞察を見せるキャラクターで、物語後半の緊張を和らげる存在として視聴者に愛された。 さらに、バビル1世の声を担当した小山田宗徳、塔のコンピューターを演じた矢田耕司など、作品の神秘的側面を担う声も印象的であった。矢田の低く響くナレーション風の口調は、塔という存在に“知性と威厳”を与え、視聴者に畏怖を感じさせた。これら脇を固める声優陣の演技があってこそ、作品全体が厚みを持つ群像劇として成立している。
● アフレコ現場のエピソード
当時のアフレコは現在のように個別録音ではなく、声優たちが一斉にスタジオで収録する方式だった。そのため、チームワークや呼吸の合わせ方が重要であり、『バビル2世』のキャスト陣は撮影の合間でも互いの演技を確認し合っていたという。神谷明はインタビューで「大塚さんの台詞を聴いてから自分の間合いを決めていた」と語っており、ベテランと新人が刺激し合う理想的な環境が生まれていた。 また、ロデムの咆哮やポセイドンの効果音的台詞などは、声優自身が演出家と試行錯誤しながら収録したもので、当時の録音技術を最大限に活かしたチャレンジが行われた。こうした現場の熱意が、最終的に作品の臨場感を高めることにつながった。
● 声優陣が残した文化的影響
『バビル2世』の声優陣は、のちの日本アニメ文化における“声の演技”の礎を築いたといってよい。神谷明はその後、数々の主役を演じる国民的声優となり、大塚周夫は悪役・名脇役の名手として長く愛された。彼らの演技スタイルは次世代の声優たちに大きな影響を与え、「声で感情を語る演技」の重要性を再認識させた。 また、本作を通じて声優という職業そのものが注目されるようになり、アニメファンが声優名を覚え、雑誌などで特集を組む流れが生まれたのもこの時期である。『バビル2世』は、アニメ音楽とともに“声優文化”の黎明期を支えた作品のひとつとして記録されている。
● 総括 ― 声で築かれたもう一つの塔
『バビル2世』の物語は、映像の塔だけでなく“声の塔”によっても成り立っている。神谷明の情熱的な演技、大塚周夫の知的な静謐さ、そしてそれを支えた実力派キャストの共鳴が、作品全体に命を吹き込んだ。これらの声は時を超えて多くのファンの記憶に残り、今もなお再放送や音源復刻によって新たな世代に感動を与え続けている。 声優たちの演技が描き出した“音のドラマ”は、1970年代アニメの枠を超え、後の日本アニメーションの芸術的成熟を導いた原動力のひとつであった。
[anime-5]■ 視聴者の感想
● 放送当時の衝撃と新鮮さ
1973年当時、『バビル2世』がテレビに登場したとき、視聴者の多くがまず驚いたのはその“世界観の広がり”だった。少年が超能力を得て戦うというテーマは当時としては斬新であり、同時期に放送されていた『デビルマン』や『マジンガーZ』などの“超人もの”とも異なる静けさと知的な雰囲気を持っていた。 当時の子どもたちにとって、「テレパシー」や「超能力」という概念はほとんど未知のもので、テレビの画面で人の心を読む・物を動かすといった描写は、まさに未来の夢を見せてくれるものだった。アンケートや雑誌投稿欄では、「バビル2世が手を上げた瞬間に敵が吹き飛ぶのがカッコいい」「ロプロスに乗りたい」といった感想が多く寄せられ、少年層の憧れの的となった。 また、作品の持つ“静かな緊張感”は、親世代の視聴者にも評価された。当時のアニメには珍しく、単純な派手さよりも心理的な描写に重点を置いていたため、「子ども向けなのに哲学的だ」「人間の強さと弱さを考えさせられる」といった感想が新聞やアニメ雑誌に掲載されている。
● 孤独なヒーロー像への共感
視聴者の間で最も強く語られたテーマのひとつが、「孤独なヒーロー」という概念であった。バビル2世=浩一は、人類を守るという崇高な使命を持つ一方で、普通の少年としての生活を失う。友人も家族も遠ざかり、ただ一人塔に立つ姿は、幼いながらも“孤独を背負う強さ”を象徴していた。 子どもたちにとってそれは「悲しいけれどかっこいい」存在であり、同時に自分の中にある成長への憧れを重ねる対象だった。大人の視聴者からは「正義を貫くために犠牲を払う姿が美しい」「現代社会でも通じるストイックな生き方だ」との声が多く、ヒーロー像としての深さが高く評価された。 特に終盤の“北海道編”で見せる浩一の穏やかな表情や、再び戦いに戻る決意の場面は、多くの視聴者に涙を誘ったとされる。再放送世代のファンの中にも「この作品で初めて“孤独の美しさ”を知った」と語る人が少なくない。
● 女性視聴者が見た『バビル2世』
当時のアニメ視聴層は男性中心であったが、『バビル2世』は意外にも女性からの支持も多かった。特に従姉妹・由美子の存在が女性視聴者に強い印象を与えた。彼女の純粋な想い、そして再会できない悲恋的な展開は、ドラマ性を求める視聴者の心を捉えた。 女性雑誌やラジオ投稿でも「由美子がけなげで泣ける」「浩一と由美子の距離が切なくて好き」といった感想が寄せられ、恋愛要素を意識しないアクション作品でありながら、“人と人との絆”を感じさせる内容が評価された。 また、バビル2世自身が単なる暴力的ヒーローではなく、冷静で知的、そして優しさを併せ持つキャラクターだったことも、女性ファンを惹きつける要因となった。後年、神谷明が女性ファンの多い声優として人気を得るきっかけの一つが、この作品にあると語られることもある。
● 子どもたちを夢中にさせた“しもべたち”
ロプロス、ロデム、ポセイドン――この三体のしもべの存在は、視聴者の間で爆発的な人気を誇った。特にロプロスは「空を飛ぶ夢の象徴」として絶大な支持を受け、「自分もあの背中に乗りたい」「空を飛んで戦いたい」という声が当時の児童雑誌に多く寄せられている。 ロデムの神秘的な姿も人気が高く、変身能力や冷静な言葉遣いは多くのファンの憧れの的となった。一方のポセイドンは男の子たちにとって“最強のロボット”的存在であり、プラモデルやおもちゃとしても高い需要を生んだ。 こうしたキャラクター人気が作品を支え、放送終了後も“ロプロスごっこ”や“超能力ごっこ”が子どもたちの間で流行したと記録されている。キャラクターの魅力が物語を超えて生活文化にまで浸透したことは、この作品の社会的影響の大きさを物語っている。
● 音楽と演出への評価
視聴者の中には、音楽と演出に対して強い印象を語る人も多かった。オープニングテーマ「バビル2世」は放送当時から高い人気を誇り、水木一郎の力強い歌声が子どもたちの心を奮い立たせた。「歌を聴くと胸が熱くなる」「学校の朝礼で歌った」というエピソードもあり、主題歌が社会現象化していたことがうかがえる。 また、アニメの演出に関しても「静と動のコントラストが美しい」との声が多かった。戦闘シーンのスピード感と、塔内部の神秘的な静けさの対比が作品の独自性を強めており、特にバビルの塔のシーンでは「SF映画のような迫力」と評された。視聴者の中には、「毎週30分が映画のようだった」と述べる人もおり、当時のテレビアニメの水準を超える完成度を誇っていたことが分かる。
● 社会的背景と共鳴
1970年代初頭の日本社会は、高度経済成長の終盤にあり、技術革新と同時に“人間性の喪失”が問題視され始めていた。『バビル2世』の「科学と心の対立」「人間と超能力の距離感」といったテーマは、まさにその時代精神と共鳴していた。 当時の若者たちは、「科学の進歩が本当に人を幸せにするのか」という疑問を抱き始めており、その中で“科学を超える力=心の強さ”を体現するバビル2世は、希望と警鐘の両方を象徴する存在として映った。 新聞の視聴者コラムには、「バビル2世は超能力という形で“人間の進化”を描いている」「力を持つ者がどう生きるかは現代社会への問いかけだ」といった感想が寄せられ、子どもだけでなく大人の知的関心をも刺激していたことが分かる。
● 再放送世代・リバイバル世代の評価
1970年代後半から80年代にかけて『バビル2世』は各地で再放送され、そのたびに新しい世代のファンを獲得していった。特に1979年以降に結成された「バビル2世ファンクラブ」は、当時としては珍しい“アニメの世代間ファン組織”として注目を集めた。 再放送世代は、作品を懐かしさとともに“再発見”した世代でもあり、「子どもの頃は戦いが好きだったが、大人になって見ると孤独が胸に響く」「ヨミの言葉が今では理解できるようになった」といった感想が多く見られる。年齢を重ねるほどに異なる視点で楽しめる作品――それが『バビル2世』の最大の魅力であるともいえる。
● 現代のアニメファンによる再評価
インターネットや配信サービスの登場により、21世紀以降も『バビル2世』は新しいファン層に発見され続けている。SNS上では「1970年代のアニメにこんな完成度があったとは驚き」「構図や音楽が今見ても洗練されている」といった感想が多く見られる。 また、近年のアニメでは“孤独な少年が巨大な力を操る”というモチーフが再び注目されており、その源流として『バビル2世』を挙げる評論家も少なくない。若い視聴者からは「エヴァンゲリオンやコードギアスの原点を感じる」という声も上がっており、時代を超えて語り継がれる作品として位置づけられている。
● 総評 ― 視聴者が語り継ぐ“孤高の名作”
『バビル2世』に寄せられる視聴者の感想は、世代を超えて共通している。それは「寂しさの中にある強さ」への共感である。派手な必殺技や巨大ロボットに頼らず、心の力で戦う少年――このシンプルで普遍的なヒーロー像が、多くの人の記憶に残り続けている。 再放送やDVD化のたびに感想が新たに生まれ、世代を越えて共鳴する稀有なアニメ作品。それが『バビル2世』であり、その物語の深さと感情の余韻は、今もなおファンの間で語り継がれている。孤独と正義を描いたこのアニメは、昭和の枠を超えて“永遠のヒーロー像”を築いたといえるだろう。
[anime-6]■ 好きな場面
● 砂漠にそびえるバビルの塔との邂逅
『バビル2世』の中で多くの視聴者が印象深く語るのが、主人公・古見浩一が初めてバビルの塔に導かれる場面である。砂嵐が吹き荒れる荒野の中、巨大な翼を広げたロプロスが降り立ち、少年をその背に乗せて空へ舞い上がる。遠くに現れる不思議な光を放つ塔――その映像は、1970年代のアニメ技術を超えた壮大なスケール感で描かれていた。 塔の内部で響く重厚な電子音、そしてホログラムのように現れるバビル1世の幻影。このシーンでは、まるで神話と科学が交錯する瞬間のような神秘的な緊張感が漂う。視聴者の多くが「最初に塔が出た瞬間に鳥肌が立った」と語っており、作品全体の象徴ともいえる名場面である。 また、この場面でバビル2世が「私は誰なのか」と問いかける姿には、人間としての自己探求のテーマが凝縮されている。単なるヒーローの誕生ではなく、“存在の意味”を問う哲学的な導入として、このシーンを挙げるファンは非常に多い。
● ロプロス初出撃 ― 空を切り裂く電撃の翼
アクションシーンの中でも、特に人気が高いのがロプロスの初戦闘である。バビル2世の命令を受け、青空を裂くように飛び立つロプロス。そのスピード感、そして敵のメカを一瞬で撃ち落とす電撃攻撃の演出は、当時のアニメファンを驚嘆させた。 視聴者からは「空を飛ぶだけで感動した」「ロプロスの咆哮が頭から離れなかった」といった声が寄せられ、放送から数十年を経ても記憶に残る名場面として語り継がれている。特にBGMの重厚なブラスサウンドと、空を切る風の効果音が一体となって、映像的にも圧倒的な迫力を生んでいた。 この場面は単なる戦闘ではなく、「新しい力を得た少年が、初めて世界へ飛び立つ瞬間」を象徴している。つまり、ヒーローの覚醒を感情的に体感できるシーンであり、少年たちが“自分も強くなりたい”と感じたきっかけでもあった。
● ロデムの変身シーン ― 美と恐怖の境界
ロデムが黒豹から人間へと変身する場面は、シリーズを通してファンの間で特に印象的なシーンとして語られている。黒い影がゆらめき、光の粒子とともに人型へと変化していく映像表現は、当時としては非常に先進的だった。 この変身の瞬間に流れる低音のBGMと、山口奈々が演じる人間態ロデムの静かな声が重なることで、神秘と畏怖が同居するような雰囲気が生まれていた。子どもたちには「怖いけれどかっこいい」、大人には「人間と獣の狭間にある悲哀」として心に残る名場面である。 また、このシーンは単なる演出効果に留まらず、ロデムという存在の“二面性”を象徴している。人間のように理性を持ちながら、本能的な力に縛られる彼の姿は、バビル2世自身の葛藤を映す鏡でもあった。
● 由美子との再会未遂 ― すれ違う運命
物語の中で最も感情的なエピソードのひとつが、由美子が浩一を探して各地を旅する中で、再会寸前ですれ違ってしまう場面である。 列車のホーム、港町のカフェ、雪原の牧場――いずれのシーンでも、由美子はほんの数分の差で浩一を見失う。この“逢えそうで逢えない”演出が繰り返されるたび、視聴者の胸には切なさが募っていった。 特に北海道編での再会未遂は多くのファンが「シリーズ屈指の名シーン」と語る。雪の中で由美子が「浩一!」と叫ぶ声が空に吸い込まれ、遠くでロプロスの羽音が響く――その映像的対比が詩的であり、アクション中心の作品に深い情緒を与えている。由美子の涙は、バビル2世という存在の“人間的側面”を強く印象づける瞬間でもあった。
● 北海道編の夜明け ― 戦士の休息
後半に描かれるワタリ牧場での穏やかな夜明けの場面は、戦闘シーンとは対照的に静謐な美しさを持つ。雪に包まれた牧場を背景に、浩一が遠くの空を見つめる。ポセイドンの巨体が雪に覆われ、ロデムが静かにその傍らに佇む――この静かな映像は、まるで戦士たちの“休息”を象徴する詩のようだ。 この場面で流れる菊池俊輔による哀調を帯びたBGMが、心の奥に染み入る。戦いの合間に描かれるこの穏やかな時間こそ、視聴者にとっては“バビル2世が本当に人間らしく見える瞬間”であり、強さの裏にある優しさを再認識させてくれる。 このシーンを選ぶファンの多くは、「静けさが逆に力強い」「ヒーローがただ人として生きている姿が好き」と語る。派手なアクションよりも、心を映す描写こそが『バビル2世』の真骨頂だと感じる人が多いのだ。
● ヨミとの最終決戦 ― 宿命の終焉
シリーズのクライマックスであるバビル2世とヨミの最終決戦は、アニメ史に残る壮絶な名場面として語り継がれている。 暗雲立ち込める空の下、二人の超能力者が静かに対峙する。互いに手を上げ、無言のまま意志の力をぶつけ合う――その緊張感は画面から溢れ出るほどだ。激しい光と衝撃波の中、ロプロスとポセイドンが倒れ、ロデムが傷つく。最終的に勝利を収めるのはバビル2世だが、その顔には喜びよりも深い悲しみが浮かぶ。 この戦いの中で、ヨミが最後に呟く「我々は同じ血を引く者…」という言葉が視聴者の心に残る。悪役でありながら、彼もまた宿命に抗えなかった悲劇の存在であることが明らかになる瞬間だ。戦いの勝敗よりも“理解と別れ”が主題となるこの場面は、1970年代アニメの中でも特筆すべきドラマ性を持っている。
● エンディング ― 砂漠を歩く孤独な背中
最終話のエンディングシーンは、多くのファンが「忘れられない」と口を揃えて語る名場面である。全ての戦いを終えたバビル2世が、静かにバビルの塔へと歩いていく。夕陽に照らされる砂漠の地平線、彼の背中を見送る風――そこには一切の台詞がなく、ただ音楽だけが流れる。 この無言のエンディングは、力を持つ者の孤独と、使命を果たした者の静かな誇りを象徴している。戦いに勝っても人間社会には戻れない――そんな哀しみと美しさが同居する終幕は、視聴者に深い余韻を残した。 子どもたちは「ヒーローなのに寂しい」と感じ、大人は「本当の強さとは孤独を受け入れること」と受け止めた。この多層的な読み取りができるエンディングこそ、『バビル2世』が時代を超えて語り継がれる理由のひとつである。
● 総評 ― 見る者の心に残る詩的瞬間
『バビル2世』には派手な戦闘も多いが、視聴者が選ぶ「好きな場面」は意外にも“静かな時間”や“感情の機微”を描いたシーンが多い。それは、この作品が単なるアクションアニメではなく、人間の内面を丁寧に描いたドラマであることの証明でもある。 バビルの塔の荘厳さ、ロプロスの飛翔、ヨミの孤独、由美子の涙、そして沈黙のエンディング――どの瞬間も、アニメという枠を超えて“映像詩”として記憶に残る。視聴者それぞれが自分の心情や人生経験を重ねて見ることができる作品。まさに『バビル2世』の魅力は、視聴者一人ひとりの“好きな場面”の中に息づいているのだ。
[anime-7]■ 好きなキャラクター
● 永遠の主役 ― バビル2世(古見浩一)
『バビル2世』という作品を象徴するのは、やはり主人公・古見浩一その人だ。彼は単なるヒーローではなく、孤独を背負いながら使命を果たす“超能力者”という独自の存在として描かれている。視聴者の多くが彼に惹かれる理由は、力そのものよりも「その使い方の潔さ」にある。 バビル2世は超能力を持ちながらも、それを誇示せず、常に自らを律して生きる。その姿は当時の少年たちにとって、力と責任の意味を教えてくれる象徴だった。戦うときの厳しい表情、敵を倒しても決して笑わない沈黙、そして時折見せる人間的な優しさ――それらがすべて彼の魅力を形作っている。 ファンの間では「バビル2世は最も静かなヒーロー」と評されることが多い。彼は怒鳴らず、叫ばず、ただ必要なときに行動する。その冷静さが逆に“絶対的な強さ”として受け止められ、特に再放送世代からは「昭和の理想的ヒーロー像」として支持され続けている。
● 哀しき宿敵 ― ヨミ
ヨミは、悪の超能力者でありながら『バビル2世』における最も魅力的な人物の一人である。彼の冷徹な笑み、知略に満ちた発言、そして孤高のカリスマ性は、単なる“悪役”という枠をはるかに超えていた。 ファンの間では「ヨミがいなければ『バビル2世』は成り立たない」とまで言われており、彼の存在が物語に深みを与えている。彼はただ世界を征服したいわけではない。自分が持つ“力の宿命”を理解し、その運命を受け入れたうえで、世界を支配することで秩序を築こうとする。その信念の強さが、主人公と同等の説得力を持つのだ。 特に最終回近くでの「我々は同じ血を引く者」というセリフには、多くの視聴者が胸を打たれた。敵でありながらも、同じ孤独を抱えた存在――それがヨミである。ファンの中には「バビル2世よりもヨミに共感した」と語る者もおり、彼の“悪の中の人間味”が今なお愛される理由となっている。
● ロプロス ― 空を駆ける守護者
三つのしもべの中でも、最も人気が高いのが巨大な鳥型メカ・ロプロスだ。視聴者からは「ロプロスが出てくると安心する」「あの飛行シーンが最高」といった声が多く寄せられた。 ロプロスの魅力は、単なる乗り物ではなく、バビル2世の忠実な仲間として描かれている点にある。彼は命令に忠実でありながら、時に主人を守るために自ら危険を冒す行動をとる。その献身的な姿勢に、視聴者は“心を持つ機械”としての美しさを感じた。 また、ロプロスのデザインも印象的である。鋭い翼と金属的な質感、そして青空を裂くスピード感――この造形美は70年代アニメの中でも屈指の完成度を誇り、多くの子どもたちが“ロプロスごっこ”に夢中になった。現在でもフィギュアやプラモデルの人気が高く、彼はまさに「空を司る正義の象徴」として愛され続けている。
● ロデム ― 闇と理性を併せ持つ影
黒豹の姿をしたロデムは、三つのしもべの中でも特にファンから神秘的な存在として愛されている。暗闇を駆け抜ける漆黒の身体、静かに響く低い声、そして変身能力。どれもが妖しくも美しい。 ロデムの人気の理由は、ただ強いだけでなく“知的で寡黙”なキャラクター性にある。戦いの最中でも冷静に状況を分析し、バビル2世に助言を与える場面ではまるで参謀のような存在感を放つ。 人間態の姿もまた印象的で、男女どちらとも取れる中性的な美しさが描かれたことで、多くの視聴者に“神秘性の象徴”として記憶された。特に女性ファンの間では「ロデムは美しすぎる」「冷たいのに優しい」と語られ、後年のアニメにおける“クール系キャラ”の原型とされることもある。
● ポセイドン ― 寡黙なる巨人
陸・空に続き、海を支配する三体目のしもべ・ポセイドンは、その圧倒的な存在感で少年たちの心をつかんだ。巨大な鋼鉄の身体と静かな力強さは、いわば“沈黙の守護神”である。 ポセイドンの登場シーンでは、海面を割って現れる演出が印象的で、初登場回は視聴者の人気投票でも上位に挙げられていた。セリフはほとんどないが、その動作一つ一つに意思を感じる描写が多く、「無口なのに感情が伝わる」と評価された。 特に最終決戦でロプロスとともにヨミ軍の兵器を打ち破る場面は、ファンの間で“ポセイドン覚醒回”と呼ばれ、数十年経った今でも語り草となっている。彼の無言の忠誠と力強さは、まさに“静かなる正義”を体現している。
● 由美子 ― 儚くも強い少女
バビル2世を支える人間的存在として、由美子の存在は欠かせない。彼女は単なるヒロインではなく、浩一の人間性を映す鏡として描かれている。 視聴者からは「由美子の一途な想いが泣ける」「浩一との再会を信じて旅する姿が健気」といった感想が多く、特に女性ファンの共感を呼んだ。彼女は“守られるヒロイン”ではなく、“信じて待つヒロイン”である点が、他のアニメとは一線を画している。 また、彼女のセリフの中にたびたび現れる“人間らしい感情”――迷い、怒り、そして希望――が、作品全体のバランスを取っている。彼女がいなければ、バビル2世の世界はただの孤独な戦場になっていたに違いない。由美子の存在こそ、物語に温もりを与える光である。
● 古見家の人々 ― 人間社会の象徴
浩一を育てた古見夫妻やその家族は、物語の冒頭でしか登場しないにもかかわらず、多くのファンに深く印象を残した。 特に、浩一が超能力者として塔へ向かう際、彼を止めようとする叔父の叫びや、涙ながらに見送る叔母の姿は、視聴者に“家族の愛と別れ”を強く感じさせる。 彼らは普通の人間でありながら、超常的な運命を背負った少年を育てた存在として、作品の人間的側面を象徴している。戦いの場面とは異なるこの“静かな愛の描写”が、視聴者の心に深い余韻を残している。
● ファンの中で語り継がれる“もう一つの主役”たち
一部の熱心なファンの間では、「コンピューター」や「バビル1世の幻影」もまた“心の主役”として語られている。バビル1世の声が響く場面では、“神の声”とも“父の声”とも解釈できる神秘性があり、少年の心を導く存在として特別な印象を残した。 また、塔のコンピューターが冷静に状況を分析し、淡々と命令を下す声も、当時のファンの間で「不思議な安心感があった」「無機質なのに温かい」と語られている。こうした無機的なキャラクターへの感情移入は、当時のアニメとしては非常に先進的な体験だった。
● 総評 ― “静と熱”を併せ持つキャラクター群像
『バビル2世』のキャラクターは、それぞれが単なる善悪の枠を超えた存在として描かれている。バビル2世の冷静な強さ、ヨミの哀しい野心、ロプロスやロデムの忠義、由美子の優しさ――どのキャラクターも、それぞれの“信念”を持って生きている。 ファンが口をそろえて言うのは、「この作品の登場人物たちは“静かに燃えている”」ということだ。彼らは声を荒げず、感情を押し殺しながらも、心の奥では熱く戦っている。 それこそが『バビル2世』の魅力であり、50年以上経っても色あせない理由である。キャラクターたちの生き方そのものが、視聴者に“強く、優しく、孤独を恐れずに生きる”というメッセージを届け続けているのだ。
[anime-8]■ 関連商品のまとめ
● 映像関連 ― VHSからBlu-rayまで続く“蘇る塔”
『バビル2世』の映像商品展開は、昭和の終わりから平成、そして令和に至るまで、時代とともに形を変えながら続いている。 まず最初に登場したのは、1980年代後半に発売されたVHSシリーズである。当時はテレビ放送の録画が一般的ではなく、ファンにとって“自宅で好きな話を何度も観られる”というのは画期的な体験だった。VHS版は全39話の中から人気エピソードを抜粋収録した構成で、ジャケットには水木一郎が歌う主題歌の歌詞カードが同梱されていた。 その後、1990年代に入るとLD(レーザーディスク)版が登場し、より高画質・長時間収録が実現。コレクター向けに少数生産され、現在でも中古市場では希少なコレクターズアイテムとなっている。LD特有の大判ジャケットには、塔やロプロスを描いた新規アートが施され、所有欲をくすぐるデザインだった。 2000年代にはDVD-BOXが発売され、全39話を完全収録。映像をデジタルリマスター化したことで、当時のセル画の色味や線の繊細さが蘇った。このBOXには解説書や設定資料が付属し、声優・神谷明やスタッフのインタビューも掲載されている。さらに2010年代以降はBlu-ray化も進み、HDリマスター版が登場。映像の鮮明さはもちろん、音声もノイズ除去とリマスタリングでクリアに再現された。 現在では各種ストリーミングサービスでも配信されており、スマートフォンで手軽に視聴できるようになった。時代ごとの技術変化に合わせて、バビル2世は何度も“塔を蘇らせてきた”と言える。
● 書籍関連 ― 原作と資料が紡ぐ知的な魅力
横山光輝による原作漫画は、アニメ放送と同時期の『週刊少年チャンピオン』連載作品としても圧倒的な人気を誇った。全121話に及ぶ壮大な物語は単行本化され、1970年代当時は少年たちの必読書として書店に並んだ。 アニメ放送に合わせて発行された「アニメコミックス版 バビル2世」も高い人気を誇り、カラーのフィルムカットを用いた紙面構成が新鮮だった。読者は映像を“紙で再体験する”感覚を楽しみ、台詞や構図を覚えて模写するファンも多かった。 また、資料性の高い書籍としては「バビル2世設定資料集」「東映アニメーションヒーロー大全」「横山光輝アニメクロニクル」などが存在し、キャラクターデザイン・メカ設定・ストーリーボードなどが収録されている。とくにロプロスの飛行システムやポセイドンの装甲設計など、当時のスタッフが真剣に“科学的リアリティ”を追求していたことがわかる。 近年では、復刻版コミックスや「横山光輝大全」シリーズとしての再刊も続いており、オリジナル表紙を忠実に再現した限定版はコレクターズアイテムとして高い人気を持つ。書籍を通じて、『バビル2世』は単なるアニメではなく“知的なSF作品”として再評価されている。
● 音楽関連 ― 水木一郎が築いた“魂のテーマ”
『バビル2世』といえば、まず語られるのが水木一郎によるオープニングテーマだろう。「バビル2世!」という力強いコールと共に始まるこの曲は、昭和アニソン史を代表する名曲のひとつとして知られている。 EPレコードは1973年当時、コロムビアから発売され、子どもたちの間では“買ってもらった最初のレコード”として記憶に残る存在だった。B面にはエンディング曲「正義の超能力少年」が収録され、主題歌集LPでは挿入歌「愛はまぼろし」「戦士ひとり」なども聴くことができた。 1980~90年代にはCDアルバム『アニメ特撮ヒーロー大全』などのコンピレーションに収録され、カラオケでも定番曲として人気を保ち続けた。水木一郎自身もライブで何度もこの曲を披露しており、ファンの間では“アニキの象徴曲”として長く愛されている。 また、近年のBlu-ray特典として発売された「完全サウンドトラックCD」には、菊池俊輔による劇伴が収録されており、塔内部の静けさや戦闘シーンの緊迫感を支える音楽の魅力が改めて注目されている。音楽面においても、『バビル2世』は時代を超えた生命力を持ち続けている。
● ホビー・おもちゃ関連 ― 子どもたちの夢を形に
放送当時、玩具メーカー各社からはさまざまな関連商品が展開された。特に人気を集めたのは「ロプロス発進セット」や「ポセイドン合体モデル」など、当時の男児向けプラモデルシリーズである。バンダイやタカトクトイスが販売を手掛け、ゼンマイやゴム動力で羽ばたくギミックを備えたロプロスのモデルは、子どもたちの憧れの的だった。 また、食玩としてミニ消しゴムやカプセルトイも登場し、机の上でロプロスを飛ばしたりロデムを変身させる遊びが流行した。80年代にはソフビフィギュアやぬいぐるみも発売され、特に黒豹ロデムの柔らか素材ぬいぐるみは今でもコレクターの間で高値取引されている。 近年では超合金ブランドによる「超合金魂 GX-XX バビル2世&ロプロスセット」や、3Dプリントによる可動モデルなども登場し、往年のファンだけでなく若い層からも支持を集めている。アクションフィギュアでは各しもべにLED発光ギミックが搭載され、現代技術で“子どもの夢”を再現しているのが印象的だ。
● ゲーム関連 ― 電子の中のバビル
1980年代から90年代にかけて、『バビル2世』はボードゲームやカードゲームとしても展開された。特に「バビル2世 超能力すごろく」は人気が高く、各マスで超能力テストやヨミとのバトルが発生するルールで、子どもたちの間で大ヒットした。 また、MSX・ファミコン時代には非公式ながら同人風のアクションゲームが登場。後年、携帯アプリやPCブラウザゲームとしても復刻され、“ロプロスを操って空を飛ぶミニゲーム”などが登場している。 公式ライセンス商品としては、PlayStation 2時代に発売された「東映スーパーヒーローズ大全」内でバビル2世が登場し、他のヒーローたちと共演するクロスオーバー的な企画が話題を呼んだ。現在もレトロゲームコレクターの間で人気が高く、動作確認済みソフトはプレミア価格で取引されている。
● 文房具・雑貨・食玩 ― 日常に潜む“塔の影”
放送当時から子どもたちの日常を彩ったのが、文房具や食玩系グッズだ。バビル2世のイラストが描かれた下敷き・鉛筆・定規・ノートは、学用品として大人気で、特に“ロプロス飛翔デザイン”は学校で見せ合うほどの人気だった。 食玩では、キャラクターシール付きガムやカード入りウエハースなどが発売され、パッケージには水木一郎の似顔絵入りロゴが描かれていた。さらに、駄菓子屋限定の「超能力カードガム」シリーズは、当たり券を引くとバビル2世のステッカーがもらえる仕組みで、当時の子どもたちのコレクション熱を掻き立てた。 令和の現在でも、アニメ放送50周年を記念した「バビル2世アニバーサリーグッズ」が続々と登場。Tシャツ、アクリルスタンド、マグカップなど、現代的デザインに再解釈されたグッズはアニメ専門店やオンラインストアで販売され、往年のファンと新世代の両方から好評を得ている。
● 総評 ― “時を超える超能力”としての商品展開
『バビル2世』の関連商品は、単なる懐古的グッズではなく、“作品世界を再構築するメディア群”として存在してきた。映像、音楽、書籍、玩具――それぞれが異なる世代に異なる形でバビルの塔を再建してきたのだ。 特に注目すべきは、世代交代の中でファン層が途切れずに続いている点である。親世代がかつて買ったソフビを、今は子どもがリメイク版で手に入れる。アナログからデジタルへ、VHSから配信へ。『バビル2世』はその都度、新しい形で“再生”を果たしてきた。 関連商品の展開は、単に商業的な成功を超えて、作品そのものが“生き続ける証”であり、時代を超えた文化的遺産といえる。バビル2世が築いた塔は、今もアニメファンの心の中にそびえ続けているのだ。
[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場
● 映像関連 ― VHS・LD・DVDが示す“コレクターズアイテム化”の歴史
『バビル2世』の映像関連商品は、現在の中古市場でも根強い人気を誇っている。特に1980年代に発売されたVHSや1990年代のLD(レーザーディスク)は、当時のテレビ放送を忠実に収録しており、マニアの間では“時代の証拠品”として扱われている。 ヤフオクなどでは、初期のVHSソフト1本あたり2,000~4,000円程度で取引されることが多く、帯付き・未開封品となると1万円近い価格にまで高騰する場合がある。LDはさらに希少性が高く、特に全巻揃ったセットや解説書付き商品は6,000~10,000円前後で落札されている。 2000年代の「バビル2世 DVD-BOX」は、発売当時の定価(約25,000円)を超えてプレミア化しており、状態の良いものは現在でも3万円前後で取引されることがある。特にブックレットや特典ディスクが付属している完全版は人気が高く、再販版よりも初回限定版がコレクターから圧倒的に支持されている。 Blu-ray版も登場しているが、生産数が限られているため、プレミア価格化が進行中だ。中古相場では1万円を超えることも珍しくなく、「映像を残すためのコレクション」という観点で価値が高まっている。
● 書籍関連 ― 原作初版本・設定資料集の価値上昇
横山光輝原作の単行本は、初版帯付きのものが特に人気を集めている。1970年代の初版本は紙質の劣化が進みやすく、美品で残っているものが少ないため、完品状態のセットは1万円を超える価格で取引されることもある。 また、アニメ放送に合わせて出版された「バビル2世 アニメコミックス」や「設定資料集」などは、ファンアイテムとして需要が高い。設定資料集は状態によっては3,000~7,000円台で落札され、表紙の退色が少ないものや内部のカラーページが綺麗なものは特に人気だ。 さらに、近年刊行された「横山光輝大全」や復刻版コミックスも一部でプレミア化しており、限定版のケース入りセットなどは販売価格以上の値段で取引されている。 アニメ雑誌『アニメディア』や『OUT』などに掲載された当時の特集ページの切り抜きも人気で、ピンナップやポスター付きの号は1,500~3,000円程度の値が付く。特に神谷明インタビュー掲載号などはファンの間で“掘り出し物”として扱われる傾向がある。
● 音楽関連 ― アニソンコレクターの定番アイテム
水木一郎が歌う主題歌「バビル2世」は、1970年代アニソンの金字塔として、レコード市場でも根強い人気を維持している。EP(シングルレコード)は、当時の販売数が比較的少なかったため、状態の良いものは現在でも3,000~5,000円前後で取引されている。 特にレーベル面に初期型ロゴが印刷されている初版盤はコレクター垂涎の品であり、ジャケットが色あせていないものは1万円近い落札例もある。 また、LPアルバム『アニメ主題歌大全集』や『東映ヒーローソングコレクション』に収録された再録版も人気で、まとめ買いされることが多い。CD時代にリマスターされた「アニメ特撮ヒーロー伝説」シリーズや、Blu-ray特典として付属したサウンドトラックCDも中古市場で高値安定。 音楽グッズとしては、1970年代当時のソノシート(雑誌付録の薄型レコード)も注目されており、保存状態の良いものは1枚2,000円前後、複数枚セットでは5,000円を超えることもある。音楽メディアのコレクション需要は、年々上昇傾向にある。
● ホビー・おもちゃ関連 ― “昭和レトロ玩具”としての再評価
ホビー・玩具関連では、当時発売されたソフビフィギュアやプラモデルが中古市場で非常に高い人気を誇る。バンダイやタカトクトイス製の「ロプロス」「ポセイドン」「ロデム」などのソフビ人形は、状態次第で1体3,000~6,000円程度。未開封や箱付きのものは1万円超の落札も確認されている。 また、ゼンマイやスプリング駆動の「ロプロス発進モデル」や「ポセイドン出撃セット」などのギミックトイは希少性が高く、完品状態であれば2万円近くの値が付く。 ガチャガチャのミニフィギュアも人気が高く、特に“しもべ3体コンプリート”のセットは高額取引対象となる。これらの商品は、単なる玩具というよりも「昭和アニメ文化の象徴」として評価されている。 さらに、2010年代以降の再販商品「超合金魂シリーズ」や「アニメヒーローズコレクション」も、限定版はすでに中古市場で定価の2倍前後の価格をつけており、往年のファンと新規コレクターが市場を支えている。
● ゲーム関連 ― 幻のボードゲームと非公式ソフト
ゲーム関連では、1980年代に発売された「バビル2世 超能力ボードゲーム」が特に高値で取引されている。箱・駒・サイコロ・説明書が全て揃っている完品であれば、現在でも5,000~10,000円前後で落札されるケースがある。 また、当時の駄菓子屋で販売されたミニすごろくやトランプなども、未使用状態なら1,000~2,000円で取引される。珍しいものでは、食玩パッケージに封入されていた「バビル2世クイズカード」や「超能力判定ゲーム」なども人気が高い。 さらに、1990年代にPC向けに制作された同人風アクションゲームや携帯アプリの配布版がフリマアプリで出回ることがあり、非公式ながらも“幻のソフト”として3,000~5,000円の値がつくこともある。こうしたアイテムは、アニメの人気が根強く残っている証拠でもある。
● 文房具・日用品 ― 当時物グッズの希少価値
文房具や雑貨類も人気のジャンルだ。特に当時の「バビル2世 下敷き」「鉛筆」「消しゴム」などは、子ども時代の思い出とともにコレクターズアイテム化している。 ヤフオクやメルカリでは、未使用状態の鉛筆セットが2,000円前後、下敷きは1,500~3,000円程度で落札されることが多い。キャラクター柄が色褪せていないものは特に人気が高い。 また、駄菓子屋販促ポスターや当時のチョコレート・ガムのパッケージも収集対象となっており、保存状態が良ければ数千円単位で取引される。昭和レトロブームの影響で、“学校の記憶”を呼び覚ますグッズの価値は今後も上昇するとみられる。
● 総評 ― コレクター市場が映す“永遠の超能力ブーム”
『バビル2世』関連グッズの中古市場は、単なる懐古的な取引にとどまらず、“日本アニメ文化の記憶”を継承する場として成熟している。昭和のアニメ玩具やVHSが令和の今でも高値を維持しているのは、作品が持つ普遍的な魅力――孤独、力、正義、そして人間の強さ――が世代を超えて共鳴しているからだ。 オークションサイトやフリマアプリでは、世代の垣根を越えた取引が行われ、「父親が観ていたアニメのグッズを息子が落札した」というエピソードも珍しくない。 バビルの塔のように、時間を超えて再び姿を現す“記憶の遺産”として、『バビル2世』の関連商品は今なお生き続けている。中古市場は、単なる商業空間ではなく、作品を愛したファンたちの“継承の場”でもあるのだ。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
バビル2世 COMPLETE DVD BOOK vol.1(第1巻)
バビル2世 COMPLETE DVD BOOK vol.2
バビル2世(1) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]
ANIMEX1200 24::テレビオリジナルBGMコレクション バビル2世 [ (アニメーション) ]




 評価 3
評価 3【中古】バビル2世 【文庫版】 <全8巻セット> / 横山光輝(コミックセット)
[新品]バビル2世[新書版](1-12巻 全巻) 全巻セット
バビル2世 ザ・リターナー 5【電子書籍】[ 野口賢 ]
バビル2世(4) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]




 評価 5
評価 5バビル2世(7) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]




 評価 5
評価 5バビル2世(11) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]




 評価 5
評価 5


![バビル2世(1) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0373/9784253030373.jpg?_ex=128x128)
![ANIMEX1200 24::テレビオリジナルBGMコレクション バビル2世 [ (アニメーション) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/jan_4988001/4988001950332.jpg?_ex=128x128)

![[新品]バビル2世[新書版](1-12巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/m-comic/comic0002/ha-13.jpg?_ex=128x128)
![バビル2世 ザ・リターナー 5【電子書籍】[ 野口賢 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2327/2000000152327.jpg?_ex=128x128)
![バビル2世(4) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0403/9784253030403.jpg?_ex=128x128)
![バビル2世(7) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0434/9784253030434.jpg?_ex=128x128)
![バビル2世(11) (少年チャンピオンコミックス) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0472/9784253030472.jpg?_ex=128x128)