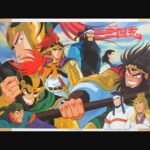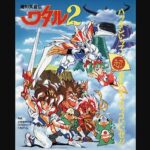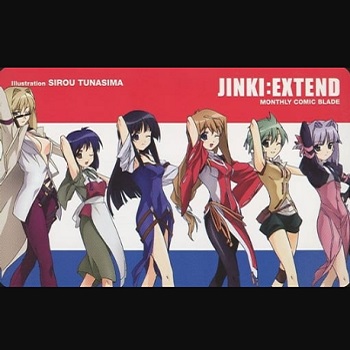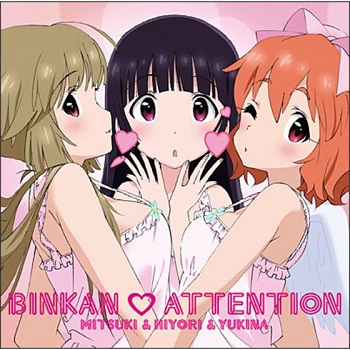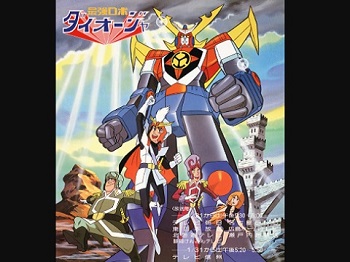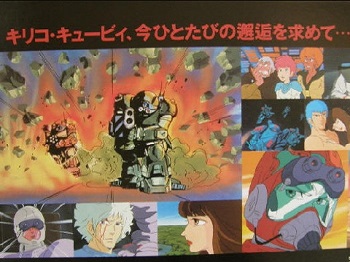世界名作劇場・完結版 七つの海のティコ [ 林原めぐみ ]




 評価 3.5
評価 3.5【原作】:広尾明
【アニメの放送期間】:1994年1月16日~1994年12月18日
【放送話数】:全38話
【放送局】:フジテレビ系列
【関連会社】:日本アニメーション
■ 概要
1990年代前半、日本のアニメ界は大きな転換点を迎えていました。ファミリー層に愛された安定のシリーズが求められる一方で、国際的な視野を持った新しい作品作りへの挑戦も始まっていたのです。そんな時代に1994年1月16日から同年12月18日まで、フジテレビ系列で放送された『七つの海のティコ』は登場しました。本作は「ハウス世界名作劇場」の20周年記念作品として企画されたものでありながら、それまでの名作劇場シリーズとは大きく趣を異にする“完全オリジナルストーリー”でした。
従来の世界名作劇場は『赤毛のアン』や『小公女セーラ』など、文学的古典を原作に据えて児童文学を映像化してきました。しかし『七つの海のティコ』にはそのような既存の原典が存在せず、企画段階から独自に練り上げられた設定・キャラクター・世界観を基盤として制作されています。これはシリーズ史上初の試みであり、同時に「時代を生きる子どもたちに現代的なテーマで物語を届ける」というスタッフの挑戦でもありました。
舞台は当時の“現代”そのもの、1990年代前半。海洋調査船ペペロンチーノ号に暮らす主人公ナナミと仲間たちが、世界中の海を舞台に冒険を繰り広げる物語です。特筆すべきは、主人公ナナミが日本人の母とアメリカ人の父を持つハーフの少女という設定。国際化が進みつつあった90年代の空気を反映し、多文化的な家族像をアニメの中心に据えた点は、当時の子どもたちに新鮮な驚きを与えました。さらに、日本の港町や観光地が直接描かれたのもシリーズ初。海外の名作文学を再現するのではなく、「私たちが生きている時代」を描いた作品だったのです。
制作を担ったのは『母をたずねて三千里』『小公女セーラ』などで知られる日本アニメーション。キャラクターデザインには森川聡子が選出されましたが、その裏では小松原一男や佐藤好春ら複数のアニメーターが候補に挙がっており、社内外で試行錯誤が続いた経緯があります。結果として森川の柔らかくも芯のあるデザインは、少女ナナミやシャチのティコを親しみやすく魅力的に描き出し、シリーズ全体のイメージを決定づけました。
また、企画当初は『未来少年コナン2』として準備されていた構想を部分的に引き継いだともいわれ、宮崎駿作品や『ふしぎの海のナディア』に通じる冒険譚やSF的要素が随所にちりばめられています。特に後半で展開される“異世界的な演出”や“環境破壊と科学技術の暴走”というテーマは、従来の名作劇場には見られなかったダイナミックなスケールを備えていました。
放送時間も変則的でした。当初は日曜19時30分から19時58分という枠でスタートしましたが、第30話以降は19時30分から20時ちょうどへと2分拡大され、視聴者層をより幅広く取り込む試みが行われました。ゴールデンタイムに家族そろって見られるアニメとして位置づけられた点も、本作の特徴のひとつです。
物語の核には「ヒカリクジラ」という伝説的存在が据えられています。科学の最先端を追い求める大人たちと、それに翻弄されながらも命の尊さを信じる子どもたちとの対比。この構図は90年代当時の社会問題――環境破壊、科学技術と倫理のせめぎ合い――をそのまま投影したものといえます。つまり『七つの海のティコ』は、児童文学の翻案という枠を越えて、“現代社会に生きる私たち自身”を映し出す作品だったのです。
視覚的にも挑戦が見られました。海を舞台とするため、当時としては高度な水中描写や群泳する魚群の表現が多用され、リアルな海洋ドキュメンタリー的雰囲気を演出。その一方で、ティコやナナミたちの感情表現には温かみのある作画を重ねることで、現実とファンタジーが溶け合うような世界観を創出しています。
そして、世界名作劇場としての通算20作目にして20周年記念作品でもある本作は、シリーズの節目を飾る存在でした。名作劇場の伝統を引き継ぎつつも、枠を飛び越えて“新しい時代の物語”を提示する。制作陣の意気込みは強く、結果として今なお「異色作」として語り継がれる地位を築きました。
このように『七つの海のティコ』は、90年代を生きた視聴者にとって「懐かしい日曜夜の思い出」であると同時に、環境問題や国際化という現代的テーマをいち早く取り入れた先進的アニメーション作品でもあったのです。大人になった今、改めて見返すことで、当時は気づかなかった深いメッセージを感じ取ることができるでしょう。
本作を語るうえで外せないのは、やはり「シリーズの中で唯一、完全オリジナルで制作された」という事実です。従来の世界名作劇場作品は「児童文学の古典を日本アニメーションがどう再構築するか」という点に醍醐味がありました。視聴者も、毎年どの作品が選ばれるのかを楽しみにしていたのです。しかし『七つの海のティコ』はそうした期待値をあえて裏切り、原作を持たない冒険ドラマとして生まれました。
制作側には「既存の名作をアニメ化するだけでは、若い世代にインパクトを与えられないのではないか」という危機感がありました。90年代に入ると、テレビアニメは『美少女戦士セーラームーン』や『スラムダンク』といった新機軸のヒット作が続々と登場し、従来型の文芸アニメはやや古風な印象を持たれつつありました。そこで生まれたのが「現代を舞台に、子どもたちが胸を躍らせる冒険を描こう」という挑戦でした。
興味深いのは、この作品が単なる娯楽に留まらず「環境問題」や「科学と人間の共生」という社会的テーマを物語の中心に据えていることです。90年代初頭、日本ではリオ地球サミット(1992年)の記憶が新しく、環境保護への意識が一般家庭にまで浸透し始めた時代でした。『七つの海のティコ』が扱った「ヒカリクジラ」という幻想的な存在は、自然界の神秘を象徴すると同時に、人類が科学技術を優先するあまり自然を犠牲にしてはいけないという警鐘の役割を果たしていました。視聴者にとっては冒険譚を楽しみながらも、どこか社会的な問題意識に触れるきっかけとなったのです。
また、作品の映像的特徴として“海”の描写は外せません。当時のアニメーション技術で、水の揺らぎやシャチの滑らかな泳ぎをリアルに表現するのは大変な挑戦でした。それでも制作陣は妥協せず、セル画とエフェクトを駆使して水面の反射や深海の神秘的な光を描き出しました。90年代の視聴者が「ティコの泳ぐ姿に癒やされた」と語るのは、単なる物語性だけでなく、この映像表現の質の高さに由来しているのです。
キャラクター造形も、従来の名作劇場の“健気で芯の強い少女”像を継承しながら、より現代的なアレンジが加えられていました。主人公ナナミは冒険心旺盛で少しお転婆、失敗しても前向きに突き進む性格。彼女の姿は、80年代に人気を博した宮崎駿作品のヒロイン像を思わせつつ、90年代的な「アクティブな女の子」の象徴でもありました。その相棒であるシャチのティコは、動物キャラクターでありながら人間に匹敵するほどの存在感を放ち、作品を通じて「仲間」や「家族」として描かれていきます。名作劇場の伝統的テーマである“絆”が、動物と人間の関係を通して新しい形で表現されていたのです。
放送当時、多くの子どもたちはナナミに自分を重ね、日曜の夕方に彼女と一緒に海を旅する感覚を味わっていました。一方で、大人たちはスコットやルコント博士といった研究者の葛藤に注目し、「科学の進歩と自然との関係」という現実的な問いを見て取ったのではないでしょうか。つまり『七つの海のティコ』は、世代を超えて異なる角度から楽しめる多層的な物語だったのです。
さらに、本作の終盤では「世界名作劇場らしからぬSF的演出」が展開されます。動物たちが集団で人間に襲いかかるサスペンス的なシーンや、異世界めいた空間の描写は、名作劇場を見慣れたファンにとって衝撃的でした。これまでのシリーズが持っていた牧歌的・文芸的な雰囲気を一歩踏み出し、90年代のアニメシーン全体が持つ「ジャンルの混交」「表現の多様化」に足を踏み入れたのです。
このような作品性から、『七つの海のティコ』は放送終了後も長くファンの記憶に残り続けています。DVD化やノベライズ化、さらにはゲームソフト化まで果たしたのは、その人気と影響力の証といえるでしょう。
『七つの海のティコ』の評価を語るうえで欠かせないのが、放送当時から展開された多彩なメディアミックスです。オープニング「Sea loves you」やエンディング「Twinkle Talk」を収録したシングルCDは、8センチCDという当時のスタンダードな形でリリースされました。さらにサウンドトラックやドラマCDまで制作され、音楽面でもファンの心を掴んでいます。主題歌を聴くと一瞬で90年代のテレビ前に戻れる、そんな人も多いのではないでしょうか。
映像商品も充実していました。レーザーディスクやVHSといった当時のフォーマットでのリリースが行われ、その後はDVD化されて新たな世代にも届きました。2000年代以降、DVD-BOXの発売によって「もう一度見たい」という大人のファン層に応えたことは大きな意味を持ちます。現在では配信サービスや中古市場でも手に入り、世代を越えて視聴可能になっている点も特徴的です。
書籍面ではノベライズ版が複数刊行されました。広尾明による小説版、草原ゆうみが手がけた文庫版など、同じ物語を異なる解釈で読むことができるのも魅力でした。特にテレビアニメでは語り切れなかった心理描写や背景設定が描かれ、当時のファンにとって“もう一つのティコ”を楽しめる入り口となったのです。
ゲーム分野でも存在感を放ちました。セガの子ども向けハード「ピコ」用ソフトの中に収録されたほか、Windows向けの教育・冒険ゲームとしても展開されました。これらは単にキャラクターを動かすだけでなく、海や自然環境をテーマにしており、作品本来のメッセージを子どもに体験させる試みでした。
シリーズ全体の歴史の中で見ると、『七つの海のティコ』は世界名作劇場第20作にあたります。つまり、70年代から続いた長い系譜の一区切りであり、なおかつ20周年記念作品という大役を担っていたわけです。その記念作が“古典文学の翻案ではなく、完全オリジナル作品”だったことは、シリーズの方向性が大きく変わるサインでもありました。実際、その後の名作劇場は『ロミオの青い空』を最後に新作が途絶えることになります。振り返れば『七つの海のティコ』は、シリーズの終盤にあって新しい可能性を探る挑戦作だったのです。
また、90年代のアニメ視聴環境という文脈も重要です。当時は家庭用ビデオデッキの普及で録画視聴が一般化し、アニメ雑誌が積極的に特集を組むなど、ファン文化が成熟していきました。その中で『七つの海のティコ』は“日曜夜の家族向けアニメ”であると同時に、“アニメファンが語り合う対象”にもなっていきました。作品の中に宮崎駿的要素やナディア的要素を見出す視聴者も多く、アニメ文化の中で比較や分析が盛んに行われたのです。
こうして見ていくと、『七つの海のティコ』はただの冒険活劇ではなく、世界名作劇場の伝統を守りつつ、新時代に向けて変化を模索した記念碑的作品であったといえるでしょう。シリーズファンにとっては「異色作」でありながらも、確かに“名作劇場らしい温もり”が宿っていた。その両面性が、本作をいまなお語り継がれる作品にしているのです。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
『七つの海のティコ』は、11歳の少女ナナミが父スコット、そして相棒のシャチ・ティコとともに海洋調査船ペペロンチーノ号で世界中を旅する物語です。全38話を通じて、彼らは伝説の存在「ヒカリクジラ」を追い求め、さまざまな人々や事件に出会いながら成長していきます。
物語の始まりはカリフォルニア近海。母を早くに亡くしたナナミは、父スコットの研究を手伝いながらティコと日々を過ごしていました。ナナミは海と自由を愛する少女ですが、まだ子どもらしい無鉄砲さも残しており、しばしば周囲を心配させる存在です。序盤では、彼女がティコや仲間たちと共に小さな冒険を繰り返し、やがて「ヒカリクジラ」という謎に巻き込まれていく布石が描かれます。
やがて物語は国際的な広がりを見せます。お嬢様大学生シェリルとその執事ジェームズが加わり、さらに天才少年トーマスも仲間入り。個性豊かな登場人物がそろったことで、物語は「家族のようなクルーの絆」を中心に展開していきます。中盤ではリオデジャネイロやアフリカ、シチリア、さらには日本の瀬戸内海といった各地を舞台に、環境問題や地域の事情が絡むエピソードが描かれました。これらの回は、単なる冒険譚に留まらず、社会性の強いエピソードとして視聴者の心に残りました。
物語の後半において大きな存在感を放つのが、巨大企業GMCと彼らが狙う「トロンチウム」という物質です。ヒカリクジラの体内にあるとされるこの物質は、人類の科学を飛躍させる可能性を秘めていますが、そのためにクジラを犠牲にすることは許されない。スコットと仲間たちは、自らの信念と命を懸けてGMCの思惑に立ち向かっていきます。
クライマックスでは、ティコの命をめぐる悲劇と希望が描かれます。ナナミにとってかけがえのない存在だったティコは仲間を救うために命を落とし、その後ティコジュニアが生まれるという大きな転機が訪れます。視聴者はナナミの涙と成長を通じて「命の循環」や「自然との共生」という作品のテーマを強く感じ取ることになりました。
最終盤でナナミたちはついにヒカリクジラに辿り着きます。そこでは単なる“幻の生物”ではなく、太古から命を見守る存在として描かれ、人間と自然の関係を根底から問いかける物語へと昇華します。このラストは多くの視聴者にとって予想外でありながら、シリーズの集大成として深い余韻を残しました。
結果として『七つの海のティコ』のストーリーは、冒険活劇であると同時に「自然と人間の関わり」を正面から描いた寓話ともいえるものになっています。子どもだった当時の視聴者が大人になって見返すと、その深いテーマ性に改めて驚かされるのです。
ここまでで「あらすじ・ストーリー」の冒頭部分をまとめました。
次はこの章をさらに膨らませて、序盤の具体的な冒険エピソード → 中盤の各国での出来事 → 後半のGMCとの対立 → クライマックスと結末をもう少し丁寧に肉付けしていきましょうか?
◆ 序盤:ナナミとティコの出航
物語の幕開けは、海を愛する少女ナナミと、彼女の相棒であるシャチのティコの絆から始まります。ナナミは父スコットの海洋研究を手伝いながら、ペペロンチーノ号で世界の海を巡る日々を送っています。序盤は彼女の好奇心旺盛な性格が際立ち、小さなトラブルや冒険が積み重ねられます。例えば、巨大なサメとの遭遇、沈没船をめぐる騒動、異国で出会った仲間との交流など、毎話が一つの冒険譚として描かれました。
ここで大きなテーマとして提示されるのが「ヒカリクジラ」の存在です。伝説の海洋生物として語られるそのクジラは、スコットの研究対象であり、ナナミにとっても夢の象徴。視聴者は、彼らがこれからどのように“幻の存在”に近づいていくのかに胸を躍らせました。
◆ 中盤:仲間との出会いと多彩な舞台
物語が進むにつれ、ペペロンチーノ号には新たな仲間が加わります。大財閥の令嬢シェリルは、冒険心を抑えきれず船に乗り込み、彼女に仕える執事ジェームズも一行に加わりました。さらにトーマスという天才少年も加わり、個性豊かなクルーがそろうことでドラマはより賑やかになります。
中盤ではリオデジャネイロ、アフリカの大地、シチリア島、さらには日本の瀬戸内海など、舞台は世界規模で広がっていきました。それぞれの土地で出会う人々との交流や文化的背景が描かれ、ただの冒険活劇にとどまらず“世界旅行記”的な楽しみがありました。90年代当時、海外旅行がまだ特別だった時代に、テレビの前で世界を巡る感覚を味わえたことは子どもたちにとって大きな魅力だったのです。
◆ 後半:GMCとの対立とティコの試練
物語が折り返しに入ると、物語は一気にシリアスな方向へ傾きます。巨大企業GMCが「ヒカリクジラ」から得られる物質“トロンチウム”を狙い、彼らは研究や捕獲を強行。科学の進歩を名目に自然を犠牲にしようとする姿勢に、スコットや仲間たちは強く反発します。
この頃からティコ自身にも試練が訪れます。仲間を救うために危険な海に飛び込み、時には命を賭してペペロンチーノ号を守る姿が描かれました。中でも視聴者に衝撃を与えたのは、ティコが北極の過酷な環境で仲間を助けるために命を落とすシーン。長年共に冒険してきたナナミにとって、最大の悲しみの瞬間でした。
◆ クライマックス:命の循環とヒカリクジラ
しかし物語はそこで終わりません。ティコの死を受けて誕生したティコジュニアが、新たな相棒としてナナミのそばに現れます。命が次の世代に受け継がれるという自然の摂理が、ナナミを再び前へ進ませる力となりました。
最終盤、ナナミたちはついにヒカリクジラと邂逅します。そこで描かれるのは単なる幻獣ではなく、太古から命を見守る存在としてのクジラの姿。人類の科学技術や欲望を超えたスケールで、自然と生命の神秘が語られました。ナナミは母やティコとの思い出を重ねながら、命の尊さと共存の意味を理解し、物語は大団円を迎えます。
このように『七つの海のティコ』は、冒険の楽しさと同時に“自然と科学の関係”“命の尊さ”という大人になっても忘れがたいテーマを残しました。子どもの頃には胸躍る冒険物語として楽しみ、大人になって見返すと深い哲学的問いを投げかけられる――その二重構造こそが、この作品が長く語り継がれる理由といえるでしょう。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
『七つの海のティコ』は、個性豊かなキャラクターたちが織りなす人間模様が物語の大きな魅力でした。主人公ナナミとシャチのティコを中心に、それぞれが欠かせない役割を担いながら、冒険の航海を彩っていきます。ここでは主要キャラクターとサブキャラクターを整理しつつ、彼らが作品全体でどのような存在感を放ったのかを振り返ってみましょう。
◆ ナナミ・シンプソン
物語の中心に立つ11歳の少女。アメリカ人の父と日本人の母を持つハーフで、名前は「七つの海」に由来します。彼女の明るさ、好奇心、そして無鉄砲な勇気は物語の推進力となりました。
ナナミは決して“完璧なヒロイン”ではなく、しばしば無茶をしてトラブルを招きます。しかしその行動力こそが仲間を救い、物語を動かす要因になっていました。90年代をリアルタイムで見ていた大人が今振り返ると、「自分の子どもの頃に重ね合わせて応援した」という声も少なくありません。
印象的なのは、ナナミとティコの絆。ナナミが海に向かってティコの名を呼ぶと、どこからともなくティコが姿を現す。その姿はまるで家族のようであり、ペット以上の存在。子どもの頃にペットや友達と過ごした思い出と重なる視聴者も多かったはずです。
◆ ティコ
全長8メートル、体重7トンのシャチ。推定18歳のメスで、物語のもうひとりの主人公といえる存在です。いたずら好きでありながら、仲間の危機には必ず駆けつける勇敢さを持ちます。
中盤でジュニアを出産し、母親としての姿を見せるティコは、単なる動物キャラクターを超えて「命の循環」の象徴として描かれました。そして北極で仲間を救うために命を落とす展開は、当時の視聴者に強烈な衝撃を与えています。大人になった今も「あのシーンで泣いた」と語るファンは多いでしょう。
◆ スコット・シンプソン
ナナミの父であり海洋生物学者。穏やかな知性と揺るぎない信念を持ち、作品全体で“理性と倫理”を体現する人物でした。
彼は「科学の進歩が生き物の犠牲の上に成り立つべきではない」という考えを貫き、GMCの非道な行為に立ち向かいます。ナナミの父としては時に厳しく、時に温かく娘を導く姿が描かれ、視聴者にとっては理想の父親像でもありました。90年代当時の大人視聴者には「親として共感した」という感想も多く残されています。
◆ アルフォンゾ・アンドレッティ(アル)
陽気で人懐っこいイタリア人。ペペロンチーノ号のムードメーカー的存在で、「オーキードーキー」が口癖。彼の発明した潜水球スクイドボールや機械いじりの腕は、物語の数々の危機を救いました。
失敗や失態も多く、しばしばナナミやスコットに呆れられますが、彼がいなければ船は回らない存在です。視聴者にとっては“コミカルで頼れる兄貴分”として印象深いキャラクターでした。
◆ シェリル・クリスティーナ・メルビル
財閥令嬢にして大学生。わがままで気の強い性格ながら、心根は優しく、仲間思いの一面もあります。ナナミにとっては頼れる姉のような存在であり、時に反発し合いながらも深い絆を育みました。
シェリルの魅力は「典型的なお嬢様」像を超えて、冒険に飛び込み、仲間を支え、成長していく姿にあります。当時、女性キャラクターに強さと優しさの両方を求める風潮が強まっていたことを考えると、まさに90年代的ヒロイン像を体現していたといえるでしょう。
◆ トーマス・ルコント
内気で嘘つきな面もあった少年ですが、旅を通じて成長し、自らを信じる力を得ていきます。ナナミと同世代だからこそ、彼の成長物語は子ども視聴者に近い目線を提供しました。特に「弱虫だった少年が勇気を得る」過程は、多くの子どもたちの共感を呼び、今もファンの心に残っています。
◆ ジェームズ・マッキンタイア
シェリルの執事であり、紳士的かつ忠実。お嬢様を諫めつつも陰で支える存在で、物語に安定感を与えました。ユーモラスな描写も多く、彼の存在は視聴者にとって“安心のキャラクター”でした。
この他にも、ルコント博士やGMCの幹部ベネックス、北極で出会う少女トゥピア、日本でナナミを支える親戚など、多彩な人物が登場します。それぞれが“旅の一コマ”を彩り、物語全体を豊かにしています。
キャラクター群を通じて描かれたのは「仲間」「家族」「命の絆」。これは名作劇場の伝統を受け継ぎながらも、90年代という新しい時代にふさわしいかたちで再提示されたテーマでした。
◆ GMC関係者と敵役たち
物語後半の緊張感を担ったのが、巨大企業GMCとその関係者たちです。科学技術の進歩を名目に「ヒカリクジラ」を捕獲しようとする姿は、子どもにも大人にも“分かりやすい悪役”として映りました。
ルコント博士
トーマスの父であり、スコットの大学時代の先輩。研究方針をめぐってスコットと袂を分かちますが、息子との関係や科学者としての誇りの間で揺れ動きます。GMCに協力しながらも、やがて彼らの非道なやり方に嫌気が差し、最終的にはスコット側に立つ。この複雑な立場が物語に深みを与え、単なる勧善懲悪ではない“現実感”を付け加えていました。
ナターリャ・カミンスカヤ・ベネックス
冷徹なGMCの幹部で、本作における象徴的な悪役です。彼女の目的は一貫してトロンチウムの確保と生物兵器開発。名作劇場シリーズの中でも珍しく「改心しない」「最後まで悪役に徹する」というキャラクターであり、その結末は衝撃的でした。多くの視聴者にとって「名作劇場にこんな冷酷な悪役が出るのか」と印象付けられた存在でした。
ゴロワ
GMCに所属する人物で、強欲で自己中心的な行動が目立ちました。北極での暴走は、仲間を危機にさらす愚行として描かれ、子どもでも「これはダメだ」と感じるキャラクター。物語上ではベネックスと対比的に「小物の悪」として配置され、物語をスリリングにする役割を果たしました。
これらの敵役たちは単なる対立構造を作るだけでなく、「科学技術の使い道」「倫理観の欠如がもたらす危機」を象徴する存在でした。90年代初頭、冷戦後の世界に広がる経済競争や技術革新の影を、子ども向け作品に落とし込んだ点は非常に挑戦的だったといえるでしょう。
◆ 各地で出会う人々
『七つの海のティコ』の魅力のひとつは、旅先ごとに個性豊かな人々との出会いが描かれる点です。
トゥピア
北極で登場する6歳のイヌイットの少女。犬ぞりを巧みに操る活発さと、幼いながらも過酷な自然環境で生き抜く逞しさを持ちます。ナナミやトーマスと同世代でありながら、彼らにとって新しい価値観を示す存在でした。トーマスと和解していく過程は、子ども視聴者に「友達の輪の広がり」を実感させるエピソードでした。
洋子(ナナミの母)と渚(叔母)
日本編で描かれるナナミのルーツ。亡き母・洋子の思い出や、叔母の渚との交流は、ナナミにとって“自分の半分は日本人である”ことを実感させる重要な物語でした。特に母が歌っていた「ブランコの歌」のエピソードは、視聴者の涙を誘った名場面として記憶されています。
ゲイル
アフリカ編に登場する青年。軽薄そうに見えても仲間を救う場面もあり、憎めないキャラクター。視聴者からは「シェリルとの掛け合いが楽しかった」と語られることが多い人物です。
アルの祖母ロザリンド
シチリア編で登場。豪快な性格と愛情深さでアルを叱りつける姿は、笑いと温かさを同時に届けました。伝統的な“世界名作劇場らしい母性的キャラ”を担いつつ、イタリアらしい陽気さも加えられた印象的な人物です。
◆ 動物キャラクター
忘れてはならないのが、動物たちの存在です。ティコ以外にも様々な動物が登場し、物語を豊かに彩りました。
ティコジュニア
ティコの子どもで、母の死後にナナミに寄り添う存在。最初はツンとした態度を見せながら、やがてナナミと心を通わせていく過程は「命が次へと受け継がれる」ことを体現しました。
ヒカリクジラ
物語全体を貫く伝説的存在。クジラでありながら「太古から命を見守る者」という神秘的な存在として描かれ、最終回の余韻を大きく残しました。子どもにとっては「幻想的なクジラ」、大人にとっては「自然と人類の関係の象徴」として心に刻まれました。
オウムのロロや犬のツピックなど
一見サブキャラながら物語を賑やかにし、時には大切な役割を果たしました。特にロロがリチャードの名前を繰り返し叫ぶ場面は、視聴者の記憶に強く残っています。
こうして見ていくと、キャラクターたちは単なる冒険の仲間や敵ではなく、ナナミの成長や「命と自然」というテーマを映し出す鏡でもあったことがわかります。90年代にこの作品を見た視聴者が大人になって振り返ると、それぞれのキャラが人生のどこかで出会った人々を思い起こさせ、懐かしさと同時に普遍的なメッセージを感じるのです。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
『七つの海のティコ』を思い出すとき、多くの人がまず口ずさむのはオープニングテーマ「Sea loves you」でしょう。篠塚満由美の透明感あふれる歌声は、海をテーマにした物語と見事にシンクロし、90年代のアニメソングらしい瑞々しさを放っていました。イントロの軽やかなリズムは、日曜夜のテレビ前に座った視聴者を一瞬で“旅の海”へと誘ったのです。
◆ オープニングテーマ「Sea loves you」
作詞は佐藤ありす、作曲は清岡千穂。90年代アニメ特有のシンセサウンドとアコースティックな要素が絶妙にブレンドされており、単なる子ども向け主題歌を超えて、当時の音楽シーンにも通じるポップス的な洗練がありました。歌詞には“海に抱かれながら旅を続ける勇気”が込められ、作品のテーマそのものをストレートに伝えています。子どもの頃は元気をもらえる歌、大人になって聴き返すと“海に託されたメッセージ”が胸に響く、そんな二重構造を持った楽曲です。
◆ エンディングテーマ「Twinkle Talk」
同じく篠塚満由美が歌うエンディングは、日常に戻る安らぎを感じさせる一曲。オープニングの開放感に対して、エンディングは「一日の冒険を振り返る小さなひととき」のような温かさがありました。画面に流れるエンディング映像では、キャラクターたちの何気ない表情や旅の風景が描かれ、視聴者にとっては物語の余韻を心地よく味わう時間となりました。
◆ 挿入歌
印象的なのは「海で会えるよ」と「ぶらんこの歌」です。
「海で会えるよ」 は旅の情景を思わせる優しい楽曲で、ナナミとティコの絆を象徴するように物語の節目で流れました。
「ぶらんこの歌」 はナナミの母・洋子の思い出として語られる曲。単なる挿入歌ではなく、“母の存在”を象徴する大切な要素であり、最終盤の感動を倍増させました。この曲が流れると視聴者は自然と涙を誘われ、作品のテーマ「命のつながり」を改めて実感したのです。
◆ キャラクターソング・イメージソング
公式には多くのキャラソンが展開されたわけではありませんが、ファンの間では主題歌や挿入歌をキャラクターに重ねて聴く楽しみ方が広がっていました。例えば「Sea loves you」はナナミそのものを象徴する歌として、「ぶらんこの歌」は母・洋子とナナミの絆を表現する歌として愛されました。
◆ 音楽の余韻とファンの記憶
90年代のアニメファンにとって、音楽は単なるBGMではなく作品体験の一部でした。CDを買って繰り返し聴いたり、カセットに録音して通学時に聴いたりと、日常に浸透していたのです。特に『七つの海のティコ』の楽曲群は、聴くだけで青く広い海や冒険の記憶を呼び覚ます“タイムカプセル”のような存在になっています。
[anime-4]
■ 声優について
『七つの海のティコ』のもう一つの魅力は、豪華で実力派揃いの声優陣です。90年代前半は声優人気が一般にも広まりつつあった時代で、本作のキャスティングはファンにとっても「安心して見られる布陣」でした。
◆ ナナミ・シンプソン(声:林原めぐみ)
主人公ナナミを演じたのは、90年代を代表する人気声優・林原めぐみ。当時すでに『らんま1/2』の女らんま役や『万能文化猫娘』などで注目されており、その快活で透明感のある声質はナナミのキャラクターと完璧に一致していました。
林原の声には子どもの無邪気さと芯の強さが同居しており、ナナミが冒険を通じて成長していく姿を自然に表現していました。当時のファンは「林原さんの声だからこそ、ナナミを最後まで応援できた」と語ることが多いです。
◆ スコット・シンプソン(声:池田秀一)
ナナミの父であり海洋学者スコットを演じたのは、クールで知的な役柄を得意とする池田秀一。代表作は『機動戦士ガンダム』のシャア・アズナブルであり、その落ち着いた声色はスコットの“知識と信念を持った父親”像にぴったりでした。
池田の演技があったからこそ、スコットは単なる学者ではなく「娘を守り、科学と倫理を貫く父親」として説得力を持ったのです。
◆ アルフォンゾ・アンドレッティ(声:緒方賢一)
アルを演じた緒方賢一は、ベテランならではのコミカルな演技で作品に明るさを添えました。陽気で失敗の多いアルのキャラクターは、緒方の柔らかくユーモラスな声によって一層魅力的に仕上がっています。
特に「オーキードーキー!」の口癖は当時の子どもたちの記憶に強く残り、学校で真似をする子どももいたほどです。
◆ シェリル・クリスティーナ・メルビル(声:水谷優子)
気の強いお嬢様シェリルを演じたのは水谷優子。『ちびまる子ちゃん』のお姉ちゃん役などで知られる彼女は、優雅さと可愛らしさをあわせ持った声質で、シェリルのキャラクターを豊かに彩りました。
シェリルのわがままさも、水谷の演技を通すと憎めない愛嬌に変わり、ナナミとの掛け合いに絶妙なテンポを生んでいました。
◆ トーマス・ルコント(声:松井摩味)
ナナミと同世代の少年トーマスを演じた松井摩味は、当時数多くの少年役を演じていた声優です。少し気弱な少年が冒険を通じて成長していく姿を、自然体の演技で表現しました。子ども視聴者にとっては「自分を重ねやすいキャラ」だったこともあり、松井の声がトーマスの魅力を大いに引き出しました。
◆ ジェームズ・マッキンタイア(声:増岡弘)
シェリルの執事ジェームズを演じたのは、『サザエさん』のマスオさんや『ドラえもん』のジャイアンのパパでお馴染みの増岡弘。温厚で誠実な声質は執事キャラにぴったりで、作品に落ち着きを与えました。子どもたちだけでなく大人視聴者からも信頼される存在感を持っていました。
◆ 敵役たちのキャスティング
ルコント博士を演じた納谷六朗、ベネックスを演じた川島千代子など、脇を固める声優陣も実力派揃い。特にベネックスの冷徹な声色は、シリーズにおいて珍しい「最後まで悪に徹するキャラクター」を際立たせ、名作劇場の歴史における特異点として強烈な印象を残しました。
こうした声優陣の活躍により、『七つの海のティコ』はキャラクターが生き生きと輝き、物語がより感情豊かに伝わりました。90年代アニメを支えた名優たちの演技が詰まった作品であることも、このアニメが今なお語られる理由のひとつです。
[anime-5]
■ 視聴者の感想
『七つの海のティコ』は1994年放送当時、幅広い世代に受け入れられました。日曜夜という家族でテレビを囲む時間帯に放送されていたこともあり、子どもだけでなく大人も一緒に視聴していた点が大きな特徴です。そのため「親子で見ていたアニメ」として記憶に残っている人も少なくありません。
◆ 子ども視聴者の感想
放送当時の小中学生にとって、ナナミとティコの冒険は憧れそのものでした。特に「シャチと一緒に海を泳ぐ少女」という設定は強烈に印象に残り、学校で「自分も海に潜ってみたい」と話題にしたという声が多くあります。
また、ナナミの無鉄砲な行動やシェリルのわがまま、アルのドジな姿は子どもたちにとって親しみやすい存在でした。視聴後の感想として「ナナミと一緒に旅をしている気分になれた」「ティコが出てくると安心した」と語る人も多く、キャラクターたちが友達のような存在になっていたことがうかがえます。
◆ 親世代・大人視聴者の感想
当時すでに大人だった視聴者からは「環境問題や倫理観を真剣に描いていて驚いた」という声が目立ちました。名作劇場シリーズはこれまでも児童文学を題材に道徳性を描いてきましたが、『七つの海のティコ』は完全オリジナル作品でありながら“現代の問題”を正面から取り上げた点が新鮮だったのです。
また、スコットの台詞や行動に「親として共感した」という感想も多く、親子の絆を再認識するきっかけになった家庭もありました。特にティコの死を描いた回では「子どもと一緒に泣いた」「生命の尊さを教える教材のようだった」という反響があり、教育的な意義も大きかったといえます。
◆ 大人になって振り返るファンの声
放送から30年近く経った今、改めて見直したファンの感想には「子どもの頃は冒険が楽しかったが、大人になってからはテーマの深さに気づいた」というものが多いです。
例えば、GMCとの対立は単なる勧善懲悪ではなく、「科学技術と自然の関係」という普遍的な問いを投げかけています。当時は悪役としてしか見えなかったベネックスも、今振り返ると“欲望にとらわれた人間の象徴”として捉え直せるのです。
また「ティコの死」のエピソードは、子どもの頃にはただ悲しかっただけなのに、大人になってからは“命のバトンを次世代に繋ぐ物語”として受け止められるようになった、という感想が多く寄せられています。
◆ 名作劇場ファンからの評価
シリーズ20周年記念作であることから、長年の名作劇場ファンも注目していました。当初は「原作がないオリジナル作品で大丈夫か?」と心配された声もありましたが、結果的には「現代を舞台にした挑戦作として成功した」と高く評価されています。従来の文学原作ではなくても“名作劇場らしい温かみとテーマ性”を十分に持ち合わせていたからです。
このように、『七つの海のティコ』は子どもに夢を与え、大人には社会的テーマを考えさせる二重の魅力を持った作品でした。その感想の幅広さこそが、今も語り継がれる理由といえるでしょう。
[anime-6]
■ 好きな場面
『七つの海のティコ』には、視聴者の記憶に深く刻まれた名シーンが数多く存在します。90年代当時にリアルタイムで観ていた子どもたちも、大人になってから見返したファンも、それぞれの人生の時期に響く「お気に入りの場面」を語っています。
◆ ナナミとティコの初期エピソード
序盤で描かれるナナミとティコの一体感は、多くの視聴者が「最初に心を掴まれた」と語るシーンです。ナナミが海に向かって名前を呼び、ティコが水面から飛び出して応える場面は、シンプルながら感動的で「これからの冒険が楽しみになる瞬間」でした。子どもにとっては「動物と心が通じ合う夢」、大人にとっては「純粋な絆の象徴」として心に残りました。
◆ シェリルとナナミの姉妹のような交流
普段は口喧嘩が絶えない二人ですが、ナナミが落ち込んだときにシェリルが優しく寄り添う場面は視聴者から高く評価されています。特に「ナナミは強い子よ」と声をかけるシェリルの姿は、彼女の成長を示すと同時に、女性キャラクター同士の温かい絆を描いた名場面として語り継がれています。
◆ ティコの出産と母性
中盤で描かれたティコの出産シーンは、命の神秘をストレートに描いたエピソードでした。海の中でジュニアを産み、母としてのティコが仲間を守る姿は、子どもにとっては「大きな感動」、大人にとっては「命をつなぐ物語」として印象に残っています。このエピソードをきっかけに「生命教育的な作品」として評価する親世代も多かったのです。
◆ ティコの最期
最も多くの視聴者が「忘れられない」と語るのは、ティコが北極で仲間を救い、命を落とす場面でしょう。ナナミが涙ながらに名前を呼び続ける姿は、90年代アニメ史に残る衝撃的な別れの場面です。当時子どもだった視聴者は「ショックで泣き止めなかった」と語り、大人になったファンは「命の尊さを改めて思い知らされた」と回想しています。
名作劇場シリーズの中でも、ここまで“死”を真正面から描いた作品は珍しく、そのため記憶に強烈に焼き付いているのです。
◆ ヒカリクジラとの邂逅
クライマックスでナナミたちがついにヒカリクジラと出会う場面は、幻想的な映像美と哲学的なメッセージが融合した名シーンです。青白く光るクジラの群れが海を漂い、ナナミが母やティコの存在を感じ取る場面は、ただの冒険物語を超えて「命と宇宙の神秘」に触れる瞬間でした。視聴者の多くが「このシーンだけで今でも鳥肌が立つ」と語っています。
◆ 日常の小さな場面
大きな冒険や感動的なシーンだけでなく、仲間たちが船上で夕食を囲むシーンや、アルの失敗に皆が大笑いする場面もファンのお気に入りです。特に「ジェームズの紅茶の時間」や「アルが一攫千金を狙って失敗するくだり」はコミカルで、物語全体のバランスを取る役割を果たしていました。こうした“息抜き”があったからこそ、シリアスな場面の重みが際立ったのです。
こうして振り返ると、『七つの海のティコ』の好きな場面は「大きな感動の瞬間」と「小さな日常の温もり」の両方に存在しています。その幅広さこそが、この作品を長く愛される理由といえるでしょう。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
『七つの海のティコ』を語る上で欠かせないのが、視聴者それぞれの“推しキャラ”です。放送当時の子どもたち、大人になってから改めて見返したファン、それぞれが異なるキャラクターに魅力を感じ、今も語り継がれています。
◆ ナナミ・シンプソン
圧倒的に人気が高かったのはやはり主人公ナナミです。彼女の無鉄砲さや元気さは子ども視聴者にとって憧れそのものでした。特に「怖がらずに飛び込む勇気」「仲間を守る強さ」に共感したファンは多く、「自分もナナミのようになりたかった」という声も多く残っています。
一方で、大人になってから見返した人々は「ナナミのわがままや突っ走る性格が人間らしくて愛しい」と感じるようになり、成長物語としての魅力を再発見しているのです。
◆ ティコ
動物キャラクターでありながら人間のキャラクター以上に人気を集めたのがティコ。彼女は「ただのマスコット」ではなく、仲間を守り導く存在でした。視聴者からは「ティコが出てくると安心する」「ティコの笑うような仕草が忘れられない」という声が寄せられています。
特にティコの最期は視聴者の心に深く刻まれており、「自分の好きなキャラクターが亡くなった経験は初めてだった」「ティコを通じて“命の尊さ”を学んだ」と語る人も少なくありません。
◆ シェリル・クリスティーナ・メルビル
シェリルは当時の女の子視聴者から強い支持を得ていました。お嬢様で気が強いけれど、本当は優しくて仲間思い。そのギャップに惹かれるファンが多かったのです。
また、大人になってから見返した人は「シェリルの人間らしさ」に魅力を再発見しています。プライドが高くて素直になれない姿は、現実の人間関係にも重なり、多くの視聴者にとって共感できるキャラクターでした。
◆ アルフォンゾ(アル)
コミカルな性格でムードメーカーのアルも人気者でした。彼がいることで物語にユーモアが加わり、緊張感のあるエピソードが和らぐのです。「ドジでお金に目がくらむけれど憎めない」という彼のキャラクターは、特に男の子視聴者から親しまれていました。
◆ スコット・シンプソン
大人視聴者の“推しキャラ”として挙げられることが多いのがスコットです。理知的で冷静、それでいて娘を大切に思う父親像は、視聴者に「理想の父」として強く印象づけられました。特に親世代からは「自分もこんな父でありたい」と共感を集めました。
◆ トーマス・ルコント
子どもたちの共感を集めたのがトーマス。最初は臆病で嘘つきな少年が、仲間との旅を経て成長する姿は「自分と同じような立場」だと感じる子どもが多かったのです。視聴者の中には「トーマスが成長する姿に勇気をもらった」と語る人もいます。
◆ サブキャラクターの人気
北極の少女トゥピアは「小さいのにたくましい」と特に女の子視聴者の心を掴みました。
アルの祖母ロザリンドは「豪快で愛情深いおばあちゃん」として、大人から人気が高かった存在です。
悪役のベネックスも、一部のファンから「名作劇場にあえて悪を持ち込んだ異色キャラ」として強い印象を残しました。
こうして見ると、視聴者の“好きなキャラ”は子どもの頃と大人になってからでは変化していることが多いのが特徴です。子どもの頃はナナミやティコの冒険に共感し、大人になるとスコットやシェリルの人間的な葛藤に惹かれる——この二重の楽しみ方ができるのも、『七つの海のティコ』ならではの魅力といえるでしょう。
[anime-8]
■ 関連商品のまとめ
『七つの海のティコ』は1994年放送当時から、映像ソフトや音楽CDを中心に多彩な関連商品が展開されました。名作劇場シリーズ20周年記念作品として特別に注目されたこともあり、ファンアイテムのバリエーションはシリーズの中でも豊富な部類に入ります。ここでは、当時のリリース状況やファンの受け止め方をまとめてみましょう。
◆ 映像関連
VHS・LD(レーザーディスク)
1990年代半ばに家庭向けにリリースされ、全巻を揃えたファンもいました。特にLD版は映像特典が収録され、コレクターズアイテムとして今も語られています。
DVD
2001年には全7巻のDVDソフトがバンダイビジュアルから発売。高画質で再視聴できる環境が整い、放送当時のファンが再び手に取るきっかけとなりました。レンタルでも展開されていたため、幅広い層に行き渡ったのが特徴です。
◆ 書籍関連
ノベライズ
原案者・広尾明による角川スニーカー文庫版、草原ゆうみによる竹書房文庫版が刊行されています。両者の内容には細かな違いがあり、ファンの間では「どちらを先に読むか」で話題になりました。竹書房版はテレビシリーズに近い構成で、角川版は独自解釈を交えたストーリー展開が特徴でした。
アニメ誌の特集
『アニメディア』や『ニュータイプ』といった雑誌では特集記事やピンナップが掲載され、放送当時のファンにとって貴重な資料となりました。
◆ 音楽関連
シングルCD
「Sea loves you」「Twinkle Talk」を収録したシングルは1994年に発売。8センチCDとして展開され、パッケージ形態が少し変わっていたためコレクション価値も高いです。
サウンドトラック
「Song Collection」「Music Collection」の2種類がリリースされ、劇中で流れたBGMや挿入歌を堪能できました。今でもファンの間では“聴くと情景が蘇る”と語られるアイテムです。
ドラマCD
「百万ドル争奪 ウルトラマリン・グレートレース」はスピンオフ的な要素もあり、キャラクターたちの新しい一面を知ることができました。
◆ ホビー・おもちゃ
名作劇場シリーズ全体を対象としたグッズ展開の一部として、キャラクターグッズやカプセルトイが販売されました。特にティコのぬいぐるみやマスコットは子どもに人気で、今でもオークションサイトで見かけると高値で取引されています。
◆ ゲーム関連
1995年、セガから「世界名作劇場」を題材にしたピコソフトが発売され、その中に『七つの海のティコ』も収録されました。アクション形式でキャラクターを操作し、ヒカリクジラを目指す内容で、教育的要素とゲーム性が融合したソフトとして知られています。
さらにPC向けには「Tico Treasure In Coast & Ocean」というソフトも登場し、当時としては珍しい“パソコンで遊べる名作劇場ゲーム”として一部のマニアに注目されました。
◆ 日用品・文具・食品コラボ
文房具やシール、下敷きなど定番アイテムも販売されました。さらに駄菓子や食玩といった商品も少数ながら展開されており、パッケージに描かれたナナミやティコのイラストを覚えている人も多いです。
このように、『七つの海のティコ』は映像・音楽・書籍を中心に幅広いグッズ展開が行われ、ファンの“作品を日常に持ち帰る手段”となっていました。とりわけ音楽CDやぬいぐるみは今も懐かしのアイテムとして語られ、コレクターズアイテムとして価値を持ち続けています。
[anime-9]
■ オークション・フリマなどの中古市場
『七つの海のティコ』は放送から30年近くが経った現在でも、中古市場で一定の需要があります。特にVHSやLDといった当時の映像ソフト、主題歌CD、ぬいぐるみや文具といったキャラクターグッズは、ヤフオクやメルカリなどで根強い人気を誇っています。ここではカテゴリごとに流通の傾向を見ていきましょう。
◆ 映像関連商品の市場傾向
VHS
セル版とレンタル落ちの両方が出品されています。単巻は1本1,000~2,500円前後が相場ですが、状態の良い初巻や最終巻は需要が高く、4,000円を超えることもあります。
LD(レーザーディスク)
マニア向けで、状態が良ければ1枚3,000~6,000円台。全巻揃いは2万円以上で落札されるケースも確認されています。
DVD
2001年発売の全7巻は今も比較的出回ります。単巻は1,500~2,500円程度、全巻セットは状態次第で12,000~20,000円前後。帯やブックレット付き完品はさらに高値がつきやすいです。
◆ 音楽関連の市場傾向
シングルCD「Sea loves you / Twinkle Talk」
当時の8cmシングルは入手が難しく、相場は2,000~4,000円。未開封品や歌詞カード付はプレミアがつきやすいです。
サントラCD「Song Collection」「Music Collection」
出品数は少ないものの、需要は高く1枚3,000~6,000円前後で安定。2枚セットだと1万円を超えることもあります。
ドラマCD
「百万ドル争奪 ウルトラマリン・グレートレース」は特に希少で、完品は8,000円以上の値が付くケースも。
◆ 書籍関連の市場傾向
ノベライズ(角川スニーカー文庫・竹書房文庫)
角川版は比較的出やすく1冊500~1,500円ほどですが、竹書房版は入手困難で2,000円前後。帯付きや初版はさらに高額。
アニメ雑誌の特集号
『アニメディア』『ニュータイプ』などでティコ特集が組まれた号はコレクター需要があり、1冊1,500~3,000円前後。ポスター付録付きは特に高値です。
◆ ホビー・おもちゃ関連
ぬいぐるみ・マスコット
ティコのぬいぐるみは中古市場で人気が高く、状態良好なものは5,000円を超えることも。小型のマスコットやキーホルダーも需要があり、1,500~3,000円前後で取引されています。
文房具・日用品
当時の下敷き、鉛筆、ノート、シールなどは数百円から1,500円程度。ただし未使用品やセット売りは高額になりやすく、まとめて出品されると5,000円を超えるケースもあります。
◆ ゲーム関連
セガ・ピコ版
『世界名作劇場』ソフトの中に収録されたティコ編は、ハードごとコレクションするファンが多く、出品数は少なめ。相場は4,000~8,000円。
PCソフト「Tico Treasure In Coast & Ocean」
流通量が非常に少なく、見かければ即落札されるレベルの希少アイテム。価格は1万円を超えることも。
◆ 中古市場での全体的な特徴
『七つの海のティコ』関連グッズは「出品数が少なくても必ず落札される」という傾向があります。つまりファンの数自体は多くなくても、根強いコレクター層が存在しているのです。特にティコのぬいぐるみやサントラCDは常に需要が高く、プレミアアイテム化しています。
また近年は「90年代アニメブーム」の影響で、メルカリなど若年層も利用するフリマアプリでの出品が増え、価格が全体的にやや上昇しています。
総じて、『七つの海のティコ』は“数は少ないが需要が安定している作品”であり、30年経った今も中古市場で確かな存在感を放ち続けています。ファンにとっては、あの時の感動を手元に置いておける貴重なコレクションとなっているのです。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
世界名作劇場・完結版 七つの海のティコ [ 林原めぐみ ]




 評価 3.5
評価 3.5【2/1限定! 最大P6倍 & 最大2000円OFFクーポン!!】七つの海のティコ 2 【DVD】
【2/1限定! 最大P6倍 & 最大2000円OFFクーポン!!】七つの海のティコ 1 【DVD】
七つの海のティコ (絵本アニメ世界名作劇場) [ 日本アニメーション株式会社 ]
七つの海のティコ 8 [ 高木淳 ]
ANIMEX1200 106::七つの海のティコ MUSIC COLLECTION [ (アニメーション) ]




 評価 4.5
評価 4.5![世界名作劇場・完結版 七つの海のティコ [ 林原めぐみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6386/4934569636386.jpg?_ex=128x128)
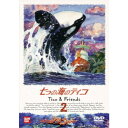
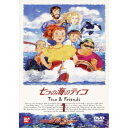
![七つの海のティコ (絵本アニメ世界名作劇場) [ 日本アニメーション株式会社 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3240/32406975.jpg?_ex=128x128)
![七つの海のティコ 8 [ 高木淳 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8642/4934569608642.jpg?_ex=128x128)
![ANIMEX1200 106::七つの海のティコ MUSIC COLLECTION [ (アニメーション) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/jan_4988001/4988001940555.jpg?_ex=128x128)
![七つの海のティコ[DVD] 3 / アニメ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_221/bcba-859.jpg?_ex=128x128)
![七つの海のティコ 3 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/598/bcba-859.jpg?_ex=128x128)

![七つの海のティコ 5 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/611/bcba-861.jpg?_ex=128x128)