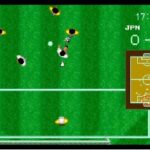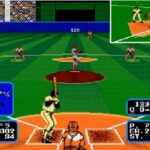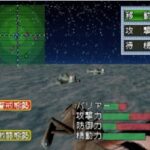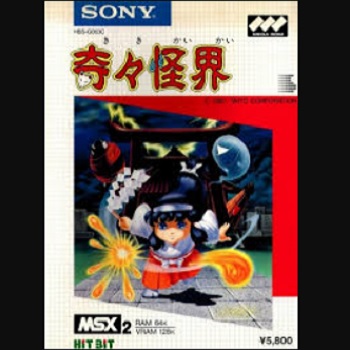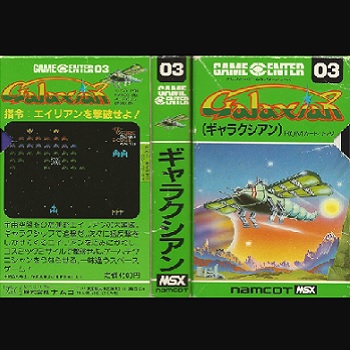【中古】【開封品】【2点セット】メガドライブソフト ファンタシースターII・III<レトロゲーム>(代引き不可)6558
【発売】:セガ
【発売日】:1989年3月21日
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
1989年3月21日、セガは自社の新型家庭用ゲーム機「メガドライブ」の普及を担う大作として『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』を発売した。本作は、1987年にセガ・マークIII(後のマスターシステム)で登場した『ファンタシースター』の続編にあたり、シリーズとしては第2作目にあたる。前作の冒険から実に千年後という壮大な時間軸を背景に据え、管理社会とテクノロジー、そして人間の宿命をテーマとした物語が展開される。SFとファンタジーを融合させた独特の世界観は、当時の他のRPG作品には見られない重厚さを放ち、現在でも語り継がれる伝説的作品として評価されている。
舞台となるのはアルゴル太陽系。人々は「マザーブレイン」と呼ばれる巨大コンピュータの制御下で繁栄を享受していた。あらゆる社会基盤がこの機械知性によって管理され、飢えも貧困もないユートピアのような世界。しかしその裏で、生態系に異変が生じ、各地に“バイオモンスター”と呼ばれる脅威が発生する。州政府の若きエージェントである主人公ユーシスは、その原因を探る任務を受け、義妹であり謎多き存在の少女ネイと共に調査の旅に出る。プレイヤーは彼らを操作し、惑星モタビアやデゾリスを巡りながら数々の困難を乗り越えていくことになる。
本作を語るうえで外せないのが、そのゲームデザインと難易度である。前作で採用されていた3D迷宮探索を廃し、代わりに広大かつ複雑な2Dダンジョンを導入。階段や落とし穴、入り組んだ通路が何層にも重なり、ちょっとした気の緩みで長時間迷うことも珍しくなかった。しかも敵の出現率は高く、序盤から全体攻撃を放つ敵が出現するため、油断すれば一瞬で全滅の危機に陥る。経験値の獲得バランスもシビアで、強敵を倒しても報酬が見合わないケースが多く、レベル上げには膨大な時間が必要とされた。そのため当時のプレイヤーの多くは度重なる挫折を経験し、「セガのRPGは骨が折れる」という印象を強く刻みつけられたのである。
制作の裏話も興味深い。本作は当初、前作同様にマークIII用として企画が進んでいた。しかしセガは新世代機としてメガドライブを投入し、本作をその目玉タイトルとして位置づけたため、急遽プラットフォームを変更。ハード変更の決定から完成までの期間はわずか半年間という苛烈なスケジュールで、シナリオやシステムの練り直し、デバッグまで行う必要があった。結果として難易度調整に粗さが残り、理不尽とすら感じられる部分もあったが、その反面で「手ごたえ」「達成感」というRPG本来の醍醐味を強烈に味わえる作品となった。
メガドライブという新ハードの性能を活かした点も注目すべきだ。グラフィックは当時の基準を大きく超える鮮明さを備え、戦闘シーンでは敵キャラクターがアニメーションする演出が加わり、動きのあるバトルが実現。味方の攻撃にもグラフィック演出が用意され、従来の「静止画で数値が動く戦闘」とは一線を画した迫力があった。背景にワイヤーフレームを採用した戦闘画面は、SF的な雰囲気を際立たせ、独特の没入感をプレイヤーに与えた。また音楽面でも、作曲家・上保徳彦氏による楽曲群が作品世界を彩り、後にシリーズを代表する名曲として語り継がれていくこととなる。
シナリオ面では、それまでのRPGに多かった「勇者が魔王を倒す」という王道展開から大きく外れ、暗く重いテーマに挑戦している。仲間の死や喪失、覆しようのない絶望、そして最後に突き付けられる虚無感――これらがストーリーの軸を成し、プレイヤーに深い余韻を残す。とりわけ義妹ネイに関する衝撃的な展開は、多くのファンにとって忘れられない体験となり、後のゲーム史においても“悲劇的イベントの象徴”のひとつとして語り草になっている。
また、本作のもうひとつの特徴は、プレイヤーが操作するキャラクターたちの多彩さだ。パーティは最大4人編成で、主人公とネイ以外は6人の仲間候補から自由に選ぶことができる。キャラクターごとに能力や特技に大きな個性があり、誰を選ぶかで戦術は大きく変化する。戦闘システムは基本的にターン制だが、攻撃対象を“種類単位”でしか指定できない仕様や、逃走確率の低さなど、現代のRPGに慣れたプレイヤーには独特な操作感がある。しかしそれが逆に“厳しい環境下での選択と工夫”を促し、戦略性を高める要因となっていた。
このように、『ファンタシースターII』はメガドライブ初期を代表するRPGとして、ゲーム史の中でも特異な位置を占めている。短期間での開発により荒削りな部分を残しつつも、シナリオの完成度や演出の斬新さは高く評価され、シリーズの方向性を決定づけた一作となった。初期のプレイヤーにとっては挫折と達成感の両方を与える“試練のRPG”であり、同時にセガというメーカーが持つ硬派で挑戦的な精神を体現した作品でもあった。
本記事では、この『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』について、その魅力、攻略のポイント、当時の反響や現在に至る評価、さらに中古市場での扱われ方に至るまで、多角的に掘り下げていく。レトロRPGを愛する読者に向けて、単なる思い出話にとどまらず、この作品がゲーム史において果たした役割をあらためて見つめ直していきたい。
■■■■ ゲームの魅力とは?
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』が今もなお強い存在感を放ち続けている理由は、その魅力が単に「面白いRPGだった」という枠に収まらないからだ。本作は、グラフィック、音楽、システム、物語、キャラクターといったあらゆる要素が、当時の限られた技術や開発期間の中で緊張感を持って結実しており、その独特の調和がプレイヤーを惹きつけてやまない。ここでは本作の魅力を多角的に掘り下げてみよう。
■ SFとファンタジーの融合が生んだ独自の世界観
まず特筆すべきは、舞台設定のユニークさだ。一般的なRPGが「中世風の剣と魔法の世界」を前提にしていた時代に、本作は「高度に管理されたコンピュータ社会」「宇宙を舞台とする惑星群」「遺伝子改造による生物兵器」という、まるでSF小説のような要素を大胆に導入した。剣や魔法に相当する武器や技(テクニック)も登場するが、それらは“科学技術が生んだ力”という文脈に組み込まれており、プレイヤーは「古典RPG的な冒険」と「未来社会のディストピア的な世界観」の両方を同時に体験できる。ファンタジーとサイエンスフィクションが違和感なく同居するこの空気感こそ、本作の大きな魅力のひとつだ。
■ キャラクターの個性と戦略性
プレイヤーが操作できる仲間たちは総勢8人。それぞれがはっきりとした役割や特技を持ち、誰を選ぶかによって冒険の難易度や戦術が大きく変化する。例えば、バイオモンスターに強いヒューイ、機械系の敵に特化したカインズ、安定した攻撃力を誇るルドガー、回復を担うアンヌ、素早さと器用さを武器にするシルカなど、各キャラクターの能力差は明確だ。現代のRPGでは“バランス型の仲間”が多いが、本作は極端な個性が際立っており、編成を間違えると即座に全滅するほどシビアだった。逆に言えば、プレイヤーはメンバーの特性を理解し、状況に合わせた最適解を導き出す喜びを得られる。
■ 戦闘演出とアニメーションの新しさ
戦闘シーンも当時としては非常に斬新だった。敵キャラクターは固定画像ではなくアニメーションで動き、攻撃や行動をするたびにそのグラフィックが生き生きと動いた。これによりプレイヤーは「ただ数値を削る」だけの戦闘ではなく、「動く敵と対峙している」感覚を味わえたのである。さらに味方側の攻撃にも専用演出が導入され、斬撃や銃撃、テクニック発動の動作がビジュアルで表現されたことは、プレイヤーに強烈な没入感を与えた。背景に採用されたワイヤーフレームのグリッドも、SF的な世界観と合致し、他のRPGにはない冷たい未来感を醸し出していた。
■ 音楽が描き出す世界の色彩
BGMの存在感も忘れてはならない。作曲を担当した上保徳彦氏による楽曲は、メガドライブ初期の音源の限界を押し広げ、電子的でありながらどこか人間味のある旋律を奏でていた。特に通常戦闘曲「Rise or Fall」は、シリーズを代表する名曲としてファンの間で高い人気を誇り、後年のアレンジ版でも度々使用されている。サウンド全体の特徴としてはドラムの強調が目立ち、悲劇的なシーンであってもリズムが力強く響くため、ある意味で“本作特有の癖”として記憶されている。結果的にそれが耳に残る要素となり、プレイヤーの思い出と強く結びついているのだ。
■ シナリオの深みと衝撃
RPGにおいて物語は重要だが、本作は従来作品と比較しても群を抜いて“暗さ”を前面に押し出した。冒険の途中で襲いかかる数々の悲劇、回避不能の喪失、そして最後に待ち受ける意外な真実――これらがプレイヤーの心に強烈な印象を残した。特にネイに関わるストーリー展開は、当時のプレイヤーに大きな衝撃を与え、後にゲーム史における“トラウマイベント”の代表例として語り継がれている。こうした悲劇性や絶望感は、単なる娯楽にとどまらず、物語体験としての深みをゲームにもたらした。
■ 「挑戦」を促す設計
理不尽とも評される難易度は、裏を返せば「徹底的に挑戦させる設計」とも言える。無数の分岐路を試行錯誤し、ようやく出口を見つけたときの達成感。全滅を繰り返しながら戦術を練り直し、勝利したときの解放感。これらは簡単にクリアできるゲームでは味わえないカタルシスであり、多くのプレイヤーが「乗り越えた者だけが知る喜び」として本作を記憶している。ゲームバランスの粗さが逆に作品の魅力を際立たせている点は、まさに“セガらしさ”を象徴している。
■ 時代を超えた評価
発売から数十年が経った現在でも、本作の魅力は色褪せない。リメイクや復刻版で再び触れたプレイヤーは、「あの理不尽さも含めてこそ、この作品の味わい」と再評価する声を上げている。ストーリーの重さや音楽の記憶、キャラクターへの愛着は、現代のライトなRPGファンにも新鮮に映る。単に“昔のゲーム”ではなく、“挑戦し続ける価値がある作品”として語られ続けていることこそが、本作の最大の魅力だといえるだろう。
■■■■ ゲームの攻略など
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』は、その高難度ゆえに攻略法を知っているかどうかで体験がまったく異なる作品である。発売当時、多くのプレイヤーが迷宮で立ち往生し、経験値稼ぎの過酷さに心折れた。しかし、しっかりと準備を整え、仲間の特性を活かし、敵の行動傾向を理解すれば、決して不可能なゲームではない。むしろ、手探りで突破した時の達成感こそが本作の醍醐味であり、攻略法を考える過程自体が「もうひとつの楽しみ方」と言えるだろう。ここではプレイを有利に進めるための知恵やコツを、段階を追って整理してみたい。
■ 序盤の資金繰りと装備の優先順位
冒険の始まりは惑星モタビアの州都パセオから。序盤で直面する最大の問題は「お金が足りない」ということだ。武器や防具は非常に高額に設定されており、最初の装備のままでは敵の攻撃に耐えきれない。ここで重要になるのは「装備の優先順位」だ。まずは主人公ユーシスとネイの防具を整えることが最優先。特にネイは耐久力が低いため、防具を早めに強化しておかないと戦闘不能に陥りやすい。攻撃力よりも防御を重視し、「倒されないこと」を第一に考えるのが攻略の基本となる。
■ ネイ離脱前の準備
物語序盤の大きな節目として、義妹ネイの離脱イベントがある。この展開を初めて体験したプレイヤーの多くは、強力な戦力を失うことで戦況が一変し、絶望感を味わった。攻略の観点では、ネイが離脱する前にできるだけ彼女を育成し、専用武器「ネイソード」を入手しておくことが鍵になる。ネイソードはその後の戦いでも重要な役割を果たすため、彼女が健在なうちに装備を整え、経験を積ませることが後々の難局を乗り越える助けとなる。
■ 仲間選びのポイント
ネイ以外の仲間はプレイヤーの選択によって決まるが、どの組み合わせも一長一短がある。序盤から中盤にかけては、安定した攻撃力を持つルドガーと、回復役のアンヌを加えるのが定番。これにより攻防のバランスがとれ、長期探索がしやすくなる。終盤に差し掛かると、素早さに優れるシルカや、高耐久力のアーミアが役立つ場面も多い。ヒューイやカインズといった“尖った能力”のキャラクターは、育成の手間はかかるが適材適所で爆発的な力を発揮する。重要なのは「誰を選んでも最後まで連れ歩く覚悟」を持つことだ。半端な育成では、終盤の苛烈な敵に太刀打ちできない。
■ ダンジョン突破の鉄則
本作のダンジョンは、単に広いだけでなく、階段や落とし穴が入り組み、出口にたどり着くまでに何度も迷わされる設計になっている。ここで役立つのが「地図を自作する」習慣だ。発売当時、攻略本のマップに誤植が多かったため、自分で方眼紙にマッピングすることが主流だった。通路を一歩ずつ確認し、階段の位置や宝箱の場所を記録することで、迷宮突破のスピードは格段に上がる。また、アイテム「トリメイト」や回復テクニックの備蓄を惜しまないことも大切。ダンジョンでは「いかに長く生き延びるか」が鍵となるため、準備を整えたうえで挑むのがセオリーである。
■ 敵の行動パターンを知る
敵の中には全体攻撃を連発するタイプや、状態異常を仕掛けてくる厄介な存在がいる。特に中盤以降に出現する「レムレス系」や「ギ・ル・ザーク」などは、対策を講じないと一瞬で壊滅しかねない。攻略のポイントは「どの敵を優先して倒すか」を明確に決めること。全体攻撃持ちを最優先で叩き、残りは回復を交えつつ削るのが定石だ。また、敵によっては経験値効率が悪いものも多いため、「戦っても得られるものが少ない敵」は可能な限り逃げる判断も重要になる。ただし逃走成功率は低く、失敗すると大ダメージを受ける危険がある。ここでのスリルこそ、本作独自の緊張感を形作っている。
■ 経験値稼ぎのコツ
レベル上げが苦行になりがちな本作だが、効率よく経験値を稼ぐ方法も存在する。比較的倒しやすいのに経験値効率の良い敵を見つけ、そこで集中的に戦うのが基本だ。例えば、デゾリス星に出現する特定の魔物は、攻撃力は高いが耐久力が低く、素早く処理すれば効率よく経験値を獲得できる。こうした「稼ぎポイント」を把握することで、プレイ全体のテンポが大きく改善される。
■ 裏技・小ネタ
発売当時はインターネットが普及していなかったため、口コミや雑誌で紹介された裏技がプレイヤーの間で話題となった。例えば特定の条件を満たすことでアイテムを増殖させたり、経験値を効率的に稼ぐ方法などが知られていた。また、ゲーム中に登場するNPCのセリフには開発スタッフの遊び心が込められており、さりげない会話からヒントを得ることもできる。こうした“小さな発見”を重ねていくのも攻略の醍醐味だった。
■ まとめ
本作の攻略は一筋縄ではいかない。しかしだからこそ、プレイヤーは自ら考え、試行錯誤し、失敗から学んで進むことになる。その過程で得られる「困難を乗り越えた達成感」こそ、『ファンタシースターII』が今なお多くのファンに語り継がれる理由のひとつだ。単なる作業としての攻略ではなく、「自分だけの冒険譚を築くための挑戦」として本作を捉えると、その難しさすらも魅力へと変わっていくのである。
■■■■ 感想や評判
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』は、1989年当時のプレイヤーやゲーム雑誌から「賛否両論に満ちた作品」として受け止められた。難易度の高さや迷宮構造の苛烈さから「投げ出してしまった」という声も少なくなかったが、一方で物語の衝撃や完成度、表現力の高さは強烈な印象を残し、ファンの記憶に深く刻まれている。ここでは、当時から現在に至るまでの評判を整理してみよう。
■ 発売当時のプレイヤーの反応
発売当初、多くのユーザーがまず驚いたのは「メガドライブでここまで表現できるのか」という点だった。戦闘シーンのアニメーションや鮮やかな色使い、BGMの存在感は、ファミコンに慣れた目と耳に強烈なインパクトを与えた。特に「Rise or Fall」をはじめとする楽曲は、当時のプレイヤーの間で「セガの音楽はかっこいい」という評価を定着させるきっかけとなった。
一方で、迷宮探索の難しさやエンカウント率の高さには悲鳴が上がった。雑誌のレビューでも「マッピング必須」「根気が試される」と記されるほどで、ゲームに不慣れな層は途中で挫折するケースも多かった。だが、それを“セガらしい硬派さ”として評価する声もあり、早くもプレイヤー間で二極化が進んでいったのである。
■ ゲーム雑誌での評価
当時のゲーム雑誌『Beep! メガドライブ』や『ファミコン通信』などでも取り上げられ、グラフィックと音楽、そして壮大なシナリオは高く評価された。特に「RPGの表現力を一段階引き上げた」という点は共通して指摘されている。一方で、「難易度調整が不十分」「攻略情報がなければ進めにくい」といった批判も少なくなく、点数評価では突出して高いというよりは「コア層向けの名作」といった扱いが多かった。
当時はRPG市場において任天堂のファミコンが圧倒的なシェアを持っており、ドラクエやFFといったビッグタイトルと比較されがちだった。その中で『ファンタシースターII』は“挑戦的で独自性の強いRPG”として、セガファンやコアゲーマーに熱狂的に支持された一方、ライト層からは敬遠される傾向が見られた。
■ プレイヤーの記憶に残る「ネイ」
評判を語る上で欠かせないのが、物語中盤で訪れるネイの悲劇だ。当時のプレイヤーの多くがこの展開に心を打たれ、ショックを受けた。「RPGで仲間が本当に死ぬ」という展開は当時としては衝撃的で、ゲーム誌の投稿欄やファンレターでも「涙が止まらなかった」「どうして救えないのか」という声が多数寄せられた。この出来事は本作の評価を「単なる高難度RPG」から「心に残る物語を持つ作品」へと格上げする役割を果たしたといえる。
■ 長期的な再評価
発売から数十年を経た今、本作の評価はむしろ上がっている。リメイクや復刻版で再プレイしたファンは、当時は苦痛に思えたダンジョン設計や戦闘バランスを「挑戦的な設計」「緊張感を生む仕組み」と捉え直している。特にストーリーの重さや終盤の衝撃的な展開は、現代のプレイヤーにも強い印象を残し、「時代を超えて語り継がれるシナリオ」として高い評価を受け続けている。
また、シリーズ全体を俯瞰すると、『II』は「ファンタシースターというブランドの方向性を決定づけた作品」として位置づけられることが多い。IIIやIVに受け継がれるテーマ性やキャラクターの描写は、本作で確立された部分が大きい。そうした意味でも、本作は単体としての完成度だけでなく“シリーズの礎”としても重要な意味を持っている。
■ ファンコミュニティでの語り草
インターネットが普及した90年代後半以降、ファンコミュニティや掲示板で語られる際にも、『II』は常に「難しいけど忘れられないゲーム」として挙げられる。とくに「ネイを救えない絶望」「マザーブレインの正体に直面したときの虚無感」といったテーマは、多くのプレイヤーが共感を込めて語り合う要素となっている。また、サウンドトラックやファンアート、同人小説といった二次創作の題材にも選ばれ続けている点からも、その根強い人気がうかがえる。
■ 総合的な評判
まとめると、『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』の評判は以下のように整理できる。
発売当時:グラフィック・音楽・シナリオは高評価、ただし難易度には批判多数
プレイヤー体験:ネイの悲劇的展開が強烈な印象を残し、賛否を超えて語り草に
現在の再評価:挑戦的デザインと物語性が高く評価され、シリーズの代表作とみなされる
結局のところ、本作は「万人に優しいRPG」ではなかったが、その硬派さと強烈な個性が、時を超えてファンを惹きつける要因となった。難しさに泣かされ、物語に心を揺さぶられ、それでも忘れられない――その矛盾こそが、『ファンタシースターII』の最大の魅力であり、評判の核心なのである。
■■■■ 良かったところ
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』は、その苛烈な難易度から「投げ出した」というプレイヤーも少なくないが、一方で“良かったところ”として語り継がれている要素は数多く存在する。むしろ、その長所が強烈に印象付けられたからこそ、本作は30年以上経った今でもファンの間で語り草になっているのだ。ここではプレイヤーやメディアが共通して評価してきた「良かったところ」を多角的に整理していこう。
■ グラフィック表現の進化と迫力
メガドライブの性能を最大限に活かしたグラフィックは、当時のプレイヤーにとって大きな驚きだった。戦闘画面では敵キャラクターがアニメーションで動き、ただの静止画に数値を当てる従来型RPGとは一線を画す臨場感を実現した。特に大型モンスターが繰り出す攻撃は迫力満点で、ファミコン世代のゲーマーからは「家庭用ゲーム機でもここまでできるのか」と驚きの声が上がった。背景に採用されたワイヤーフレームのグリッドは、近未来的でクールな雰囲気を演出し、本作特有のSF色をさらに強めている。
■ 音楽の印象とシリーズを象徴するBGM
BGMの完成度は「良かったところ」の代表格だ。作曲家・上保徳彦氏が手掛けた楽曲群は、メガドライブ音源の特性を活かし、力強くも哀愁漂う旋律を奏でている。通常戦闘曲「Rise or Fall」は、当時から“セガRPGを代表する名曲”として人気を集め、後のシリーズ作品でもアレンジが登場した。シーンごとに的確に感情を引き出すBGMは、悲劇的な展開や感動の瞬間をより強烈にプレイヤーの記憶に刻み込んでいる。ファンの中には「BGMを聴くと当時の冒険を思い出す」という声も多く、音楽が作品の評価を支える大きな柱となっている。
■ シナリオの重厚さと衝撃的な展開
シナリオ面も高評価を得ている。「仲間を失う悲劇」「覆しようのない結末」「希望よりも虚無を突きつけられるラスト」――これらは従来のRPGが描いてきた“勇者の勝利”という図式を大きく覆すものだった。特に義妹ネイの悲劇的な展開は、発売当時のプレイヤーに計り知れない衝撃を与え、ゲーム雑誌の投稿欄でも「涙が止まらなかった」との声が数多く寄せられた。こうした“心を揺さぶる体験”は、プレイヤーに深い余韻を残し、他作品にはない強烈な印象を与えている。
■ キャラクターの個性と多様性
パーティメンバーが8人という当時としては豊富な人数を誇り、それぞれが強い個性を持っていた点も評価されている。万能型のルドガー、回復役のアンヌ、俊敏なシルカ、特殊能力に特化したヒューイやカインズなど、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせて仲間を選択できた。特にキャラクターデザインがアニメタッチに刷新されたことで、男子プレイヤーを中心に好感を持たれやすくなり、キャラクター人気が飛躍的に高まった。後に「ゲーム図書館」で配信されたキャラクター短編ストーリーは、その人気を裏付けるエピソードだといえる。
■ “挑戦的”であることそのものが魅力
攻略本が不完全、ダンジョンが複雑、敵が強力――こうした要素は短所として語られる一方で、「挑戦のしがいがあった」という意味で長所とも捉えられている。簡単にクリアできないからこそ、乗り越えたときの達成感が際立ち、プレイヤーに強い思い出を残した。特にセガファンにとっては「他にはない骨太なRPG」として本作を誇りに思う声も多く、難しさが逆にブランドイメージを高める結果となった。
■ メガドライブ初期を代表する存在感
本作はメガドライブの初期ラインナップにおいて看板タイトル的な役割を担っていた。ハードの性能を示すデモンストレーション的な側面を持ちながらも、ただの技術見本ではなく、シナリオやシステムの完成度で「本格派RPG」として評価された。結果として、「セガはドラクエやFFに対抗できるRPGを持っている」とプレイヤーに印象付け、セガ陣営に強い誇りをもたらした。
■ 後世への影響
『ファンタシースターII』の良さは単なる同時代的な評価に留まらず、その後のRPGに与えた影響という形でも評価される。シリアスで重い物語展開、管理社会や人工知能をテーマに据えたSF要素、キャラクターごとの極端な個性付けは、後年のJRPGにも影響を与えた。結果的に「挑戦的なRPGの先駆け」として語られるようになり、シリーズを超えた意義を持つ作品となったのである。
■ 総合的に見た良さ
総じて、『ファンタシースターII』の“良かったところ”は、グラフィック・音楽・シナリオ・キャラクターといった「表現面の強さ」と、「難しさを含めた挑戦的なゲームデザイン」の両面に集約される。快適さや親切さよりも、“強烈な体験”を与えることを重視していたからこそ、多くのプレイヤーが「辛かったけど忘れられない」という評価を下すのである。ゲームとしての完成度だけでなく、人生の一場面として記憶に残るほどの力を持っている――それが、本作の真の魅力と言えるだろう。
■■■■ 悪かったところ
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』は、革新性や表現力の高さで多くのファンを魅了した一方で、同時に数々の「悪かったところ」も指摘されてきた。むしろ本作の評価は、長所と短所が強烈に並存しているからこそ際立っていると言える。ここでは、当時のプレイヤーや雑誌の批評、そして現代の再プレイ勢が口をそろえる不満点を丁寧に見ていこう。
■ ダンジョンの難易度が極端に高い
最もよく挙げられる欠点は、ダンジョンの複雑さだ。階段や落とし穴が入り組み、通路は無駄に長く、同じような景観が延々と続く。結果として「迷うために作られた」としか思えない構造が多く、方眼紙にマッピングしなければ進行できないレベルだった。攻略本に掲載された地図ですら誤植が多く、正しい情報を得られないこともしばしば。こうした要素はプレイヤーの根気を削ぎ、挫折を招いた最大の原因とされる。
■ 戦闘バランスの粗さ
戦闘における敵の強さと経験値の配分も問題点として語られる。倒すのに時間がかかる割に得られる報酬が少ない敵が多く、「苦労とリターンが釣り合わない」という不満が絶えなかった。また、敵が先制攻撃を仕掛けることはあっても、プレイヤー側が先制することはほとんどなく、不公平感を覚えるプレイヤーも多かった。さらに中盤以降は全体攻撃を使う敵が複数で出現し、先制されると即全滅という状況が頻発。これにより「理不尽」という評価が定着した。
■ 逃走確率の不親切さ
戦闘からの逃走成功率は敵固有の設定で決まっており、プレイヤーのレベルや素早さとは無関係だった。つまり、どれだけ鍛えても逃げられない敵は逃げられないまま。強敵から逃げつつ進むという戦略が成り立たないため、探索の自由度が大きく制限されていた。この仕様は挑戦的ではあるものの、「不親切」として批判されることが多かった。
■ 移動速度の遅さとストレス
広大なマップに対してキャラクターの移動速度が遅すぎるという点も、当時から大きな不満点だった。特にダンジョンでは、エンカウント率の高さと相まって、プレイ時間の大半を「移動と戦闘」に費やすことになる。後年の復刻版で移動速度が改善されたことからも、当時の仕様が多くのプレイヤーにとってストレスだったことは明らかだ。
■ 仲間加入のタイミングが不明瞭
他のRPGのようにイベントで自然に仲間が加入するのではなく、「新しい街に到着したらパセオの自宅に戻る」という仕様は、当時のプレイヤーを混乱させた。加入条件が曖昧でわかりにくく、「気づかないまま進めてしまった」という人も少なくない。さらに、仲間の能力バランスも極端で、一部のキャラクターは使いづらく、結局固定的な編成に落ち着いてしまう傾向が強かった。
■ ダークファルス戦の理不尽さ
シリーズの象徴的存在である「ダークファルス」戦も、理不尽な要素が多かった。仲間を「邪悪に染めて行動不能にする」特殊攻撃は、解除手段がネイソードのランダム効果しかなく、運が悪ければ何もできないまま全滅に追い込まれる。さらに通常攻撃も高威力の全体攻撃ばかりで、プレイヤーに有利な隙がほとんどない。緊張感を演出する意図は理解できるが、運要素に左右されすぎる点は批判され続けている。
■ 画面スクロールと視認性の悪さ
移動画面のスクロールがキャラ中心ではなく、画面端に近づくまで動かない仕様だったため、前方の視界が狭くなり、余計に迷いやすくなっていた。また、天井の配管や濃霧の演出が逆に視認性を下げ、プレイヤーのストレスを増幅させていた。これらの演出は雰囲気作りには一役買ったものの、快適性を犠牲にしてしまった点は否めない。
■ ダメージ数値が表示されない仕様
敵から受けたダメージ量が数値で表示されず、体感でしか判断できない仕様も、当時から不満の声が多かった。これは「緊張感を高める」意図だったとも推測されるが、実際には戦闘中の戦略判断を難しくし、不便さだけが目立ってしまった。
■ ストーリー進行上の不親切さ
物語の進行に必要なアイテムやイベントが、明確なヒントなしに配置されていることが多かった。例えば、重要アイテムを持つ宝箱が「正解ルートの途中にある」仕様自体は合理的だが、そのルートにたどり着くのが困難で、結果的に「ただ長時間さまよい歩かされる」印象が強かった。また、ダムやコントロールタワーの入口が背景と同化して分かりづらいなど、プレイヤーに不親切な点が随所に見られた。
■ 当時の評価と現代の視点
こうした「悪かったところ」は、発売当時の雑誌レビューでも繰り返し指摘されていた。現代の視点から見ても、快適性の低さや理不尽な難易度は否めない。しかし一方で、それらの欠点が逆に「挑戦的な作品」としての個性を際立たせ、長く語り継がれる要因になったことも事実だ。つまり、短所がそのまま「記憶に残る魅力」へと転じているのだ。
■ 総合的に見た欠点の意味
総じて『ファンタシースターII』の「悪かったところ」は、ゲームデザインの未熟さや開発スケジュールの過酷さに起因する部分が大きい。しかし、それらを含めて「骨のあるRPG」としてプレイヤーに深い印象を与えたのも事実である。快適さを求める現代のRPGとは真逆の設計だが、それゆえに本作は忘れがたい体験を残した。欠点を欠点のまま受け止めるのではなく、“当時のセガが挑んだ冒険の証”として捉えると、そこに独自の価値を見いだすことができるだろう。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
を約5000字級に肉付けしてご用意しますね。ここでは本作の主要キャラクター一人ひとりに触れ、プレイヤーが「なぜ好きになったのか」「どう心に残ったのか」を掘り下げます。
■ 好きなキャラクター
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』には、個性的で魅力的なキャラクターたちが多数登場する。彼らは単なる戦闘要員ではなく、それぞれが物語やシステム面において確かな存在感を放ち、プレイヤーの心に深く刻まれた。ファンの間では「誰をパーティに入れるか」「どのキャラクターに感情移入したか」といった話題が今も尽きない。ここでは代表的なキャラクターを取り上げ、それぞれの魅力と人気の理由を整理してみよう。
■ ユーシス(主人公)
本作の主人公であり、州政府のエージェントとして冒険の中心に立つ青年。名前を自由に設定できるため、プレイヤー自身の分身としての役割が強いキャラクターだ。彼の魅力は「ヒーローらしさ」よりも「苦悩と責任を背負う普通の人間」である点にある。ネイを守り、仲間を導き、最後には絶望的な真実に直面する姿は、プレイヤーに“共に旅をした”実感を与えた。ファンの間では「セガRPGの中で最も等身大の主人公」と評されることも多い。
■ ネイ
『II』の象徴的存在にして、シリーズ屈指の人気キャラクター。人間とバイオモンスターの間に生まれた存在であり、義兄ユーシスと共に冒険をするが、やがて運命的な悲劇に見舞われる。ネイの魅力は、その存在自体が物語のテーマを体現している点にある。優しさと孤独、希望と宿命の狭間で揺れる彼女の姿は、多くのプレイヤーの胸を打った。特に彼女が迎える運命は、当時のゲーマーに「ゲームで泣く」という体験を与えた初めての瞬間だったという声もある。ネイは本作の人気を超え、シリーズ全体を代表するキャラクターとして語り継がれている。
■ ルドガー
筋骨たくましいハンターであり、安定した攻撃力と耐久力を持つ“頼れる兄貴分”。どんな場面でも安定して活躍できるため、プレイヤーからの信頼は厚い。戦闘では堅実な火力要員として必須級の存在であり、シナリオ的には寡黙ながら仲間を支える影の立役者的ポジション。ファンの中には「ルドガーがいたから最後まで乗り越えられた」と語る者も少なくない。派手さはないが、まさに本作の“縁の下の力持ち”といえるキャラクターである。
■ アーミア
動物使いという独特のポジションを持つキャラクター。高い耐久力と特殊なスキルで、パーティを安定させる存在だ。彼女の魅力は「他では見ないユニークな役割」にあり、当時のRPGでは珍しい個性派キャラとして注目された。使いこなすのは難しいが、ハマれば非常に頼もしい戦力となり、ファンの間では「玄人好みのキャラ」として愛されている。
■ アンヌ
医療の専門家であり、回復役としてパーティの生命線を担う。彼女がいるだけで探索の安定感が段違いになるため、多くのプレイヤーにとって必須の仲間だった。アンヌの魅力は、その専門性と安心感にある。派手な必殺技や強烈な個性はないが、「いなくては困る存在」として地味ながら確かな人気を誇った。サポートに徹する姿勢は、仲間を支える温かさを象徴している。
■ シルカ
素早さに優れ、アイテム係として便利なキャラクター。盗賊的な立ち位置で、探索や戦闘における小回りの良さが光る。多くのRPGに登場する「スピード型キャラ」と同様、本作においても彼女の存在はユニークで、プレイヤーによっては「最後までシルカを使い続けた」という声もある。キャラクターデザインの魅力もあって、特に男性プレイヤーからの支持を集めた。
■ ヒューイ
バイオモンスターに強い科学者タイプ。序盤から中盤にかけては活躍の場が多いが、後半になると敵の種類が変わり、やや力不足になることもある。しかし「知識と技術で戦う」というキャラクター像はユニークで、ファンの中には「ヒューイのテクニック運用が好きだった」という声も少なくない。尖った性能ゆえに愛着を持たれる典型的な“玄人向けキャラ”である。
■ カインズ
機械系の敵に強いエンジニアタイプ。序盤ではやや使いづらいが、後半になると機械系の敵が多く登場するため一気に評価が上がる。成長させると非常に頼もしい存在となり、長期的な視野を持つプレイヤーからは高い支持を得た。特に「終盤の高耐久メカに対して、カインズがいなければ勝てなかった」という声は多い。時間をかけて育てたプレイヤーほど強い愛着を抱くキャラクターだ。
■ プレイヤーごとの「好き」が生まれる構造
本作の特徴は、キャラクター性能が極端に分かれているため、誰を選ぶかでプレイ体験が大きく変わることだ。そのため、プレイヤーごとに「自分にとっての好きなキャラクター」が自然と形成されていった。ある人はネイに感情移入し、ある人はルドガーの頼もしさに惹かれ、またある人は尖った性能のヒューイやカインズに愛着を持った。これほどキャラクターへの思い入れがプレイヤーごとに異なるRPGは、当時としても稀有な存在だった。
■ 総合的な人気の理由
総じて、『ファンタシースターII』のキャラクターたちが愛される理由は「物語とシステムの両面で強い印象を残した」ことにある。ネイの悲劇的な物語は感情を揺さぶり、他の仲間たちは性能の極端さでプレイヤーの選択を迫った。結果として誰もが「自分の好きなキャラ」を見つけ、そのキャラと共に困難を乗り越えた記憶が強烈な愛着へと変わったのだ。
[game-7]
■ 中古市場での現状
1989年に発売された『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』は、すでに30年以上の歳月が流れているにもかかわらず、中古市場において今もなお安定した需要を持つ作品である。単に「古いゲーム」という位置づけではなく、シリーズを象徴する名作であり、レトロRPGの研究対象やコレクションアイテムとして評価されているからだ。ここでは主要な中古販売チャネルにおける価格帯や流通状況を順に見ていこう。
■ ヤフオクでの取引状況
ヤフオクでは、メガドライブ版のカートリッジ単品から箱説付き、さらには未開封品まで幅広く出品されている。価格帯は状態によって大きく変動するが、カートリッジのみの場合は1,500円前後から、箱と説明書が揃っている美品では3,000円~4,000円程度で落札されることが多い。特に外箱の角の傷みが少なく、説明書に破れや書き込みがないものはコレクターからの人気が高く、入札が集中する。未開封新品はほとんど見られないが、稀に登場すると8,000円以上の高値がつくケースもあり、希少性の高さが際立っている。
■ メルカリでの販売動向
フリマアプリ・メルカリでは、ヤフオクよりもやや安価で取引される傾向がある。カートリッジのみで1,200円~2,000円程度、箱説付きで2,500円~3,500円が相場。写真の写りや出品者の説明の丁寧さによって売れ行きが大きく変わる点が特徴だ。また「送料無料」「即購入可」と記載された出品は人気が高く、状態が良いものは数日以内に売れる。時折、まとめ売りセットに含まれるケースもあり、そうした場合は相場より安く手に入る可能性がある。
■ Amazonマーケットプレイス
Amazonマーケットプレイスでは、他のフリマアプリやオークションよりもやや高値で安定している。中古品は3,000円~5,000円前後で出品されており、コンディション「非常に良い」と記載のあるものは特に高めに設定される傾向がある。Amazon倉庫発送の商品は信頼性が高い分、プレミア価格となることも珍しくない。逆に動作保証の記載がない商品は売れ残りやすい。Amazonは国際的な利用者も多いため、海外のセガファンが購入するケースも見られ、相場の底堅さにつながっている。
■ 楽天市場での取り扱い
楽天市場では、ゲームショップや中古専門店が出品していることが多く、価格帯は3,500円~6,000円前後。他の市場と比べて高めだが、ショップとしての保証やクリーニング済みの安心感を重視するユーザーに支持されている。特に「箱説付き・動作確認済み」の商品は安定して需要があり、在庫切れになることもある。楽天ポイントの利用を目的に購入されるケースも多く、価格の高さにもかかわらず一定の流通量が維持されている。
■ 駿河屋での状況
中古ゲームの大手ショップである駿河屋でも取り扱いが続いている。販売価格はおおむね2,500円~4,000円と比較的安定しており、状態によってはそれ以上の値がつくこともある。人気商品であるため在庫が切れることも珍しくなく、在庫復活時にはすぐに売れてしまうことも多い。駿河屋は査定基準が明確で、外箱や説明書の状態ランクを細かく提示しているため、コレクターからの信頼も厚い。
■ コレクションアイテムとしての価値
『ファンタシースターII』はシリーズを代表する作品であり、セガの歴史を語るうえでも重要なタイトルであるため、単なる「遊ぶための中古ソフト」以上の価値を持つ。特に初回版の外箱や説明書が綺麗な状態で残っているものは、コレクターズアイテムとして需要が高い。さらに、攻略本や関連グッズとセットで保存されている場合は価格が跳ね上がる傾向がある。
■ 復刻版の影響
本作は後年、セガサターンやPlayStation2の「セガエイジス」シリーズ、さらにはNintendo Switch向けの「セガエイジス」ダウンロード版など、さまざまな形で復刻されてきた。これにより「プレイするだけなら復刻版で十分」という層が増え、中古市場での価格高騰はある程度抑えられている。一方で「オリジナルのカートリッジを持ちたい」「当時のパッケージをコレクションしたい」という需要は根強く、安定した市場が形成され続けている。
■ 海外市場での評価
北米や欧州でも『Phantasy Star II』として発売されていたため、海外市場でも一定の人気がある。eBayなどでは30ドル~60ドル前後で取引されており、状態が良いものはさらに高値で落札される。特に海外版の箱やマニュアルはデザインが異なるため、国内外のコレクターから注目されるアイテムとなっている。
■ 総合的な現状
まとめると、『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』の中古市場は以下の特徴を持っている。
カートリッジのみなら2,000円前後から入手可能
箱説付き美品は3,000円~5,000円程度が主流
未開封品は稀少で高値(8,000円以上)
復刻版の存在で価格の高騰は抑えられているが、コレクター需要は根強い
海外でも安定した取引があり、世界規模で一定の価値を持ち続けている
つまり、本作は「今もなお安定して取引されるセガRPGの代表格」であり、単に懐古的な人気にとどまらず、コレクションとしての価値を確立した作品なのである。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
【中古】 ファンタシースターポータブル2 インフィニティ/PSP




 評価 4.33
評価 4.33【中古】[PS2] SEGA AGES 2500シリーズ Vol.1 PHANTASY STAR(ファンタシースター) generation:1 限定版 セガ (20030828)
【中古】 ファンタシースター ZERO/ニンテンドーDS




 評価 1
評価 1
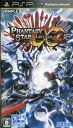
![【中古】[PS2] SEGA AGES 2500シリーズ Vol.1 PHANTASY STAR(ファンタシースター) generation:1 限定版 セガ (20030828)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/1/cg10401037.jpg?_ex=128x128)




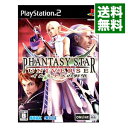
![【中古】[PSP] ファンタシースター ポータブル(PHANTASY STAR PORTABLE) セガゲームス (20080731)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1021/0/cg10210456.jpg?_ex=128x128)