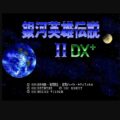【送料無料】【中古】PS プレイステーション 項劉記
【発売】:光栄
【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS、X68000、Windows
【発売日】:1993年7月21日
【ジャンル】:シミュレーションゲーム
■ 概要
●「楚漢戦争」を“二大勢力専用”に絞り込んだ、光栄らしい歴史SLG
『項劉記』は、古代中国で繰り広げられた楚漢戦争を題材に、項羽(楚)か劉邦(漢)のどちらかを選んで覇権を競う歴史シミュレーションゲームだ。初出はPC-9801版で、1993年7月21日に発売され、その後FM TOWNSやX68000にも移植されている。 いわゆる「群雄割拠」型ではなく、主役を最初から二人に固定することで、“勝ち筋の違い”を最初の一手から濃く感じられるのが特徴になる。 同じ光栄の歴史ものでも、『信長の野望』や『三國志』のように多数の勢力を渡り歩く感覚とは別物で、プレイヤーは「項羽の強さをどう維持するか」あるいは「劉邦の層の厚さをどう伸ばすか」という、対照的な課題に集中させられる。二大勢力だけのゲームだからこそ、序盤の小さな選択がそのまま数年後の戦線の形に直結し、史実の流れを“ゲームの手触り”として追体験しやすい。
●勢力の個性は「能力値」だけでなく“人材の集まり方”と“揺らぎ”で表現される
本作は、項羽と劉邦を単純に数値の強弱で差別化するのではなく、武将の集まり方、配下のまとまり、都市の空気感といった「運営のしやすさ/崩れやすさ」で個性を作っている。項羽は戦闘面で抜けた強さを持ち、正面衝突なら頼もしさが際立つ一方で、支配圏や友好関係が安定しにくく、“勝っているのに不穏”という感触がつきまとう。 対して劉邦は、本人が万能というより「任せられる人材が揃っていく」方向で強くなっていく。前線の軍団に戦闘を任せ、自分は外交や人材発掘に寄せる、といった役割分担が自然に成立しやすく、組織が育つほど運用が滑らかになる。さらに、武将ごとの好悪がはっきりしていて、登用が簡単な人物と難しい人物の差が大きい点も、史実の人材配置を感じさせる仕掛けになっている。 結果として「項羽は、強いが脆い」「劉邦は、地味だが伸びる」という物語的な輪郭が、数字ではなくプレイ感でにじむ。ここが『項劉記』が“二人しか選べないのに単調になりにくい”理由のひとつだ。
●ゲームの骨格は「軍団を動かして、補給で支えて、戦って押し切る」
内政で数字を積み上げるより、軍団(編成した部隊)をどう使い分けて戦線を作るかが中心になる。武将と兵をどの軍団に割り振り、どのルートで進軍させ、どの都市を補給拠点として使うか――この“行軍そのもの”が、作戦であり経営でもある。 ただし内政が不要というわけではなく、都市の支持率や君主の敬慕度といった値が低いままだと、支配が揺らいだり、登用が滞ったり、配下の離反が起きやすくなる。 だから本作の面白さは「前線を動かし続けたい欲」と「後方を整えないと崩れる現実」のせめぎ合いにある。戦闘軍団と後方軍団が自然に分かれ、後方が補給を回して前線を支える形ができあがると、楚漢戦争の“長い綱引き”らしさが立ち上がってくる。
●戦闘は“条件で手触りが変わる”方向に工夫されている
本作の戦闘は、ただ兵数をぶつけるだけにならないように、状況で効き方が変わる要素が用意されている。伏兵的な動きが絡む展開、部隊の向きによる守りの差、城砦への攻め方の選択、水攻めや夜襲といった「決まると一気に流れが変わる」手段など、戦闘の局面ごとに別の判断を迫ってくる。 ここで重要になるのが軍団編成で、同じタイプの武将を一箇所に固めるより、軍団ごとに得意分野を分散させたほうが戦線が滑らかに回る。万能型は扱いやすいが、尖った武将は「どこで尖らせるか」を決めた瞬間に戦術の色が出る。 戦闘そのものより、戦闘を成立させる準備(人材配置・補給線・拠点選び)に比重が置かれているのが『項劉記』らしさと言える。
●シナリオは4本。年を追うほど“史実通りに”空気が変わる
用意されているシナリオは4つで、どれからでも開始できる。 年代が進むにつれて項羽が不利、劉邦が有利になっていく流れが、ゲームの初期状況としてはっきり反映されているため、「同じ勢力でもシナリオで別ゲームになる」感覚を得やすい。 シナリオ名は、前206年「漢中王即位す」、前205年「項 義帝を弑す」、前204年「劉 項 広武に対す」、前203年「項 楚歌に涙す」。 この並び自体が“勝者が入れ替わっていく数年間”を示していて、プレイヤーは状況の悪化/好転を、開始画面の時点で覚悟させられる。特に後半ほど項羽側は厳しく、勝ちを狙うなら、短期で決める攻勢計画と、崩れやすい後方の立て直しを同時に求められる。
●スタッフワークが「重さ」と「華」を作る:シブサワ・コウ×長谷川智樹
開発・発売は光栄で、プロデューサーはシブサワ・コウ、音楽は長谷川智樹が担当している。 『項劉記』の雰囲気は、画面の色味や情報密度の“硬派さ”だけでなく、場面ごとに緊張感を押し上げる楽曲の存在感が大きい。戦線が動くときの高揚、拠点が崩れるときの不安、戦いが長引くときの焦れ――そうした感情の波が、操作の単調さを打ち消す方向に働く。 また、二大勢力の色を濃くした設計ゆえに、同じ地図を見ていても、項羽で遊ぶか劉邦で遊ぶかで“聞こえてくる音”まで違って感じる瞬間がある。史実を知っている人ほど、勝ち負け以上に「この局面に似合う空気」を想像してしまい、それがプレイを前に進める燃料になるだろう。
●復刻やWindows展開で、遊び直しの導線も残された
後年には復刻収録や、Windows向けの定番シリーズとしての展開も行われ、PC環境で触れ直す道が用意された。 当時の歴史SLGを「今の感覚で」再評価したい人にとって、こうした再展開はありがたいポイントで、特に二大勢力の緊張感や、補給・軍団運用の癖は、時代を越えて“独特な味”として残りやすい。 『項劉記』は、派手な演出で押す作品ではなく、地図と数字と人材の相互関係を噛みしめるタイプのゲームだ。その代わり、噛むほどに「項羽で勝つ難しさ」「劉邦で伸ばす楽しさ」が具体的な実感として積み上がり、短期決戦にも長期戦にも違う達成感を用意してくれる。発売から時間が経っても語られやすいのは、そうした“遊びの芯”が明確だからだと思う。
■■■■ ゲームの魅力とは?
●「二大勢力だけ」という潔さが、プレイの芯を太くする
『項劉記』のいちばん分かりやすい魅力は、最初から主役が「項羽(楚)」と「劉邦(漢)」の二択に固定されている点だ。群雄割拠のように多数の勢力から選んで“自分の好みの国づくり”を楽しむのではなく、歴史上の宿命として競り合う二者のどちらかに深く入り込み、「勝ち方の思想そのもの」を味わう方向に寄せている。だからプレイ開始直後から迷いが少ない。地図を見た瞬間に「この状況なら、項羽は何を急ぐべきか」「劉邦なら、どう伸ばすべきか」と問いが立ち、戦略が“物語の必然”として浮かび上がってくる。二勢力しかないのに薄味にならないのは、まさにこの設計の潔さのおかげで、勝つための技術と、歴史をなぞる手触りが同じ方向を向きやすい。
●項羽と劉邦が“強さの種類”からして違うので、同じマップが別ゲームに変わる
項羽は、前線で暴れられる豪胆さが魅力だ。戦闘面で頼りになる武将や兵の力で押し切りたくなる一方、支配が不安定になりやすい空気もまとわりつく。つまり「勝っているのに気が抜けない」。この緊張感が項羽プレイの面白さで、快進撃の最中でも後方のほころびが頭をよぎるから、攻勢と統治のバランスにセンスが問われる。 対して劉邦は、本人が何でもできる英雄というより、“人を使って伸びる”ことが強さになる。軍団を任せる人材を揃え、外交や登用で厚みを作り、戦線の噛み合わせを良くしていくほど、国家が滑らかに動くようになる。序盤は地味でも、積み上げが効いてくる中盤以降に「伸びた分だけ選択肢が増える」気持ちよさがある。結果として同じシナリオでも、項羽は短期決戦のスリル、劉邦は長期的な育成の手応えが強くなり、遊び比べるだけで“歴史SLGの別ジャンル”を二本買ったような満足感が生まれる。
●内政よりも「軍団運用と補給線」が主役。だから“前線が動く快感”が濃い
光栄の歴史SLGというと、都市の数値を上げたり、農業・商業を積み上げたりするイメージが強い人もいると思う。でも『項劉記』は、その快感を「軍団を組んで動かす」方向へ大胆に寄せている。武将と兵をどの軍団に配し、どのルートで進め、どの都市を補給基地にして前線を支えるか。戦いは“戦場の一局面”というより、行軍と補給を含む広い意味での作戦として描かれる。 ここが刺さる人にはとても刺さる。地図上で戦線を引き、補給の距離感を体で覚え、都市を「守る場所」ではなく「前線を支える装置」として扱うようになると、プレイの視点が一段上がる。勝利は戦闘の腕だけでは届かず、補給が切れた瞬間に強軍でもしぼむ。だからこそ、うまく回り始めたときの快感が大きい。「補給が続く限り、こちらは前に出られる」という確信が持てた瞬間、単なる戦術ではなく“戦争を動かしている”感覚が立ち上がる。
●“内政が軽い”のではなく、「放置すると崩れる」タイプの現実味がある
内政比重が相対的に低いとはいえ、完全に無視できるわけではないのが面白いところだ。都市の空気が悪いまま戦闘だけを続けると、支配の正当性が揺らぎ、武将の忠誠や登用のしやすさにも影響が出てくる。ここで要求されるのは、細かい数値最適化というより「最低限の手当てを、必要な場所に入れる」現場感覚だ。前線が忙しいほど後方が荒れ、後方が荒れるほど前線が不安定になる。この循環があるから、プレイヤーは“戦い続けたい欲”を抑え、時に踏みとどまって体勢を整える判断を迫られる。 そして、これが楚漢戦争という題材と相性がいい。いくら勝っても人心が離れれば瓦解するし、地味な積み上げが最後に効いてくる。ゲームのシステムが歴史のメッセージを自然に語ってくれるので、「史実を知っているほど納得できる」「史実を知らなくても、なぜこう動くべきかが体感で分かる」という二重の強みがある。
●軍団ごとに“適材適所”を作るのが楽しい。人材が単なる数値では終わらない
軍団単位でコマンドを回す設計だから、武将は「誰が強いか」だけでなく「どの軍団に置くと仕事が回るか」で価値が変わる。戦闘向きの人材を前線に、調略や交渉が得意そうな人材を後方や外交に、といった分担が自然に必要になる。万能型は扱いやすいが、万能型だけで固めると軍団同士の役割が曖昧になり、局面への対応力が下がりやすい。逆に尖った人材を“尖らせる場所”に置けると、軍団が道具として機能し始める。 この瞬間が『項劉記』の醍醐味のひとつで、強い武将を集める喜びだけでなく、「配置を組み替えたら、同じ戦線が急に滑らかに回り出した」という運用の快感がある。人材登用の難しさや、勢力による集まり方の違いも相まって、軍団編成は毎回同じ形に落ちにくい。結果としてリプレイ性が生まれ、「次はこの人を早めに確保できたら、違う勝ち筋が作れるかも」という再挑戦の動機につながる。
●戦闘は“決め手”が用意されていて、作戦がハマると一気に気持ちいい
戦闘そのものも単調にならないよう、局面で刺さる要素がいくつも用意されている。正面から殴るだけでなく、伏せるように動いたり、状況に応じた攻め方を選んだり、タイミングで勝負を決めにいく発想が生きる。こうした要素は、単純に派手な演出を見せるためというより、「補給・編成・進軍」で作った土台を、最後に戦闘で収穫するための仕掛けとして働く。準備が整っているときに決め手が通ると、勝利が“偶然”ではなく“設計の成果”として味わえる。 逆に準備が足りないと、どれだけ強そうな軍団でも息切れし、戦闘で勝っても追撃できず、戦線が伸び切らない。このシビアさがあるから、成功したときの達成感が大きい。「作戦が戦場で形になった」と感じられる瞬間が、歴史SLG好きの心を強く掴む。
●シナリオを追うほど空気が変わり、「同じ勢力でも別の難しさ」を味わえる
本作はシナリオの年代によって、両勢力の立ち位置が目に見えて変わる。早い年代では勢力差が小さく、手数の勝負になりやすいが、進むほど史実の流れが強く反映され、項羽は難度が上がり、劉邦は伸びやすくなる。この変化が「同じキャラクターでも、置かれた環境が違えば戦い方が変わる」という当たり前の事実を、ゲームとして分かりやすく提示してくれる。 とくに項羽側は、遅い年代ほど“勝つために必要な技術”が明確になる。攻勢の速度、後方の安定、離反を防ぐ手当て、決戦の作り方――それらを同時に要求されるからこそ、クリアしたときの満足が重い。一方で劉邦側は、年代が進むほど「組織を伸ばす喜び」が強くなり、戦線を押し上げる爽快感が増す。シナリオ選びが難易度調整だけでなく、楽しみの質の選択にもなっているのが良い。
●地味に見えて“熱量が上がるタイプ”の歴史SLG。噛むほど味が出る
第一印象は硬派で、派手な演出やキャラ推しの華やかさで引っ張るタイプではない。けれど、軍団が噛み合い、補給が通り、前線が伸び、相手の反撃を受け止め、そこから再び押し返す――この循環が回り始めると、画面の情報量そのものがドラマに見えてくる。勝ち負けだけではなく、「この局面はどこで止めるべきか」「どの都市を捨て、どの都市を守り抜くか」「誰を前線に置き、誰を後方に回すか」という判断の連続が、楚漢戦争の重さをプレイヤーの手に乗せてくれる。 そして最後には、項羽で勝てば“史実をねじ伏せた”気持ちよさ、劉邦で勝てば“積み上げが実った”納得感が残る。どちらの勝利も味が違うから、一本のゲームで二種類の達成感を持ち帰れる。『項劉記』の魅力は、そうした“噛むほど味が出る設計”にあると思う。
■■■■ ゲームの攻略など
●まず押さえるべき前提:このゲームは「前線の勝ち」より「戦線の維持」で決まる
『項劉記』の攻略で最初に意識したいのは、戦闘に勝った回数そのものより、勝ったあとに“戦線を保てるか”で結果が決まる点だ。軍団を動かして戦う仕組み上、勝利で得た土地や都市は、その瞬間から補給基地・中継点としての仕事を背負う。ここが整わないまま次の戦いに突っ込むと、たとえ局地戦で勝っても兵が減り、士気が落ち、行軍が鈍り、次の戦闘で押し返される流れになりやすい。 だから序盤は「一番強い軍団で敵を潰す」より、「勝った地点に補給の線が通っているか」「都市の支持が揺れないか」「軍団の役割分担が崩れていないか」を優先して、前へ進む速度を自分で調整することが重要になる。勢いに任せて一気に進軍したくなるゲームほど、あえて“止まる判断”が勝率を上げる。
●軍団編成の基本:尖った才能は分散、万能型は“穴埋め”に使う
攻略の土台は軍団編成だ。軍団単位でコマンドを回す以上、同じ軍団に似たタイプの武将を寄せすぎると、できることが偏って詰まりやすい。たとえば戦闘向きばかり集めた軍団は前線で強い反面、補給・調略・守備・立て直しが弱くなる。逆に政治向きばかりの軍団は安定するが、押し返す力が足りない。 おすすめは、主力軍団を2つ作り、それぞれに「戦闘の核」「機動・奇襲の核」「守備の核」を最低1枚ずつ置くこと。万能型の武将は“主力の穴”を埋める用途に回すと軍団が崩れにくい。さらに後方軍団を別に用意し、都市の維持や補給の回転、支持・敬慕の下支えを担当させると、前線の軍団が戦いに集中できる。 項羽側はとくに「強い武将を全部同じ軍団に詰めたくなる」誘惑があるが、そこをこらえて分散させると、戦線全体の勝ち筋が太くなる。
●補給管理のコツ:前線は“短い槍”、後方は“長い腕”で支える
行軍中心のゲームでは、補給は実質的な攻撃力だ。兵は戦闘で減るだけでなく、無理な行軍と長い滞在で疲弊し、立て直しが遅れる。ここを改善するコツは、前線軍団を「短い槍」として使うこと。つまり、補給が届く範囲で確実に勝ち、勝った地点を固定し、後方軍団(長い腕)で物資・兵の回転を作ってから次へ進む。 補給基地にする都市は、単に大きい都市より、前線への距離が短く、敵の反撃で奪われにくい位置を優先したい。もし敵が取り返しに来るなら、その都市は「攻撃対象」ではなく「罠」にできる。守備を厚くして待ち構え、敵軍団を消耗させてから反撃するほうが、結果的に兵の損が少なくなる。 逆に、補給が細いまま敵の奥へ踏み込むのは、勝ちを“借金”で買う行為になりがちだ。借金が返せなくなるタイミングが必ず来るので、序盤ほど慎重に線を太くする。
●支持・敬慕の維持:戦争だけしていると負ける「じわじわ型の危機」を潰す
本作では、都市の支持や君主への敬慕のような値が下がると、離反や登用難、配下の揺らぎにつながりやすい。攻略のポイントは、これを「起きてから直す」のではなく「起きる前に止める」ことだ。 具体的には、前線の主力軍団だけで全てを回さず、後方軍団に“治安維持・民心の手当て”を定期的に担当させる。前線が忙しいほど、後方に手を入れる回数は減りがちだが、そこで手を抜くと、数ターン後に都市が揺れ、補給線が断たれ、前線の勝ちが一気に無効化される。 項羽側はとくに支配の揺らぎが痛手になりやすいので、「勝っているのに負ける」事故を避けるためにも、支持の低い都市ほど早めに手当てし、同盟や友好の扱いも“短期の利益より長期の安定”を選びやすくしておきたい。
●登用と人材運用:欲張って全部取りに行かず、“役割が埋まる順”で揃える
武将は強いほど欲しくなるが、闇雲に名のある人物を追うと、時間と手数が溶けて前線が遅れる。おすすめは、軍団運用で必要な役割が先に埋まる順に人材を集めることだ。 優先度の高い順は、だいたい「主力軍団の戦闘核」「補給や立て直しを担う後方核」「外交や調略の核」「守備の核」「遊軍(臨時対応)」になる。主力軍団が2つ回る形を先に作ってしまえば、多少人材が豪華でなくても戦線は動く。そこから“不足している役割の穴”を埋める形で登用を進めるほうが、勝ち筋が安定する。 劉邦側は人材の厚みを作りやすい分、逆に「誰をどこへ置くか」で差が付く。万能型を前線に置き続けるより、尖った人材を軍団に散らし、万能型を調整役にするほうが伸びる。
●戦闘の実戦テク:奇襲・伏兵・夜襲は“勝つため”より“損を減らすため”に使う
戦闘で大事なのは、勝つことより“勝ったあとに残る兵力”だ。奇襲や伏兵、夜襲のような要素は、華々しい逆転のためだけでなく、損害を減らして次の戦いに備えるために使うと効率が上がる。 たとえば、敵軍団を全滅させるより、主力を崩して撤退させるだけで十分な局面もある。追撃で兵をすり減らすより、敵の補給線や拠点に圧力をかけて“次の戦闘を楽にする”ほうが、長期戦では勝率が上がる。 また、部隊の向きや地形的な要素が絡む場合は、「守りに入る形」を自分で作るのがコツだ。無理に攻めず、守備補正が効きやすい状況で敵を受け止めると、同じ兵力でも損が少ない。攻めるのは、敵が崩れた瞬間に限定する。これだけでも戦線の伸びが変わってくる。
●項羽プレイの攻略:短期で決めたいが、実は“後方の火消し”が最重要
項羽は攻めの破壊力が魅力だが、攻略上の敵は相手勢力だけではない。自勢力の揺らぎ、同盟の不安、都市の空気、配下の不満――こうした内部要因が敗因になりやすい。 基本方針は「主力で勝って、遊軍で穴を塞ぐ」。主力軍団は決戦のために温存し、無理な分進は避ける。代わりに遊軍(機動力のある小回りの利く軍団)を作り、支持が危ない都市や、敵の浸透に弱い地点に素早く対応させる。 もう一つのコツは、勝ちを急ぎすぎないこと。項羽は勝ちを急ぐほど内側が崩れやすい。前線を一段進めたら、必ず一呼吸入れて後方の整備をする。この“間”を作るだけで、終盤の失速がかなり減る。
●劉邦プレイの攻略:序盤は守って育て、中盤から「軍団の厚み」で押し返す
劉邦側は序盤の個の強さで押すより、組織を作って勝つのが気持ちいい。序盤は、守備と補給を優先して、無理な決戦を避けるのがセオリー。敵が強い局面ほど、こちらは「負けない戦い」を選び、兵を残し、登用と軍団整備で中盤の反撃に備える。 中盤以降は、軍団が2つ、3つと回り始めた時点で勝ち筋が一気に広がる。相手の主力を正面から受け止めつつ、別軍団で拠点を削り、補給基地を奪い、相手の戦線を細らせる。劉邦側は、この“広い勝ち方”ができるようになると、戦争が急に簡単に見えてくる。 ただし油断すると、攻勢に出た瞬間に補給が追いつかず失速する。伸びる勢力ほど、補給と後方整備の手当てを忘れないことが大切だ。
●難易度の感じ方:後半シナリオほど「項羽=修羅」「劉邦=爽快」になりやすい
シナリオが進むほど勢力差がつきやすいので、難易度体感も大きく変わる。項羽は後半ほど“逆風を技術でねじ伏せる”色が濃くなり、細かい失点が即死につながりやすい。一方で劉邦は後半ほど伸びやすく、軍団運用が噛み合った時の爽快感が増す。 どちらの勢力でも共通する攻略の鍵は、局地戦の勝敗より「戦線の太さ(補給・拠点・人材配置)」を維持すること。ここさえ守れば、多少の敗戦は取り返せる。逆にここを落とすと、勝っていても崩れる。 裏技的な派手な抜け道より、地道な“戦線の管理”がそのまま勝利に直結するゲームなので、負けたときは戦闘のミスではなく、補給線・支持・軍団の役割分担がどこで崩れたかを見直すと、次のプレイが劇的に安定する。
■■■■ 感想や評判
●全体の空気感:「硬派だけど、いつもの光栄より“入口が広い”」と言われやすいタイプ
『項劉記』の評判を一言でまとめるなら、「歴史SLGらしい硬派さは残しつつ、光栄作品の中では比較的“とっつきやすい側”」という見られ方をされやすいゲームだ。実際、海外タイトルの『Rise of the Phoenix』として触れた人のレビューでも、複雑さで知られる光栄の歴史シミュレーション群と比べて理解しやすく、入門向けとして遊べた、というニュアンスの評価が見られる。 一方で、ここがそのまま好みの分かれ目にもなる。「あの濃い内政や経済の詰め将棋こそ光栄」という層には、要点を絞った設計が“物足りなさ”として映ることがある。『項劉記』は万人受けを狙うというより、楚漢戦争を軸に「軍団運用と戦線管理」に寄せて手触りを作った作品なので、期待する“光栄らしさ”の方向が違うと印象が割れやすい。
●ポジティブ寄りの感想:二大勢力のドラマ性が濃く、プレイ後に“物語の余韻”が残る
良い感想として多いのは、まず題材の強さだ。楚漢戦争という「二人の英雄が最後にぶつかる」構図が、ゲームの選択肢そのもの(項羽か劉邦か)に直結しているので、プレイの最初から最後まで軸がブレにくい。さらに、勢力が二つに固定されているぶん、敵味方の戦力バランスや人材の偏りが“ドラマ”として理解しやすく、「史実のイメージ通りに苦しくなる」「史実の流れをねじ伏せられたときに達成感が大きい」といった語り方につながりやすい。 また、登場する人物や用語を掘り下げる書籍(用語・人物をまとめた辞典系)も出ており、遊んだ後に世界観を読み物として追いたくなるタイプのゲームでもある。 こうした周辺の盛り上がりは「ゲーム体験が歴史への興味に接続しやすい」ことの裏返しで、歴史SLGの良さが素直に出た部分と言える。
●システム面の評価:内政より“軍団を動かす面白さ”が前に出るのが好き嫌いの分岐点
『項劉記』は、内政を積み上げて国力差を作る快感より、軍団を動かして戦線を作る快感を太くした設計として語られやすい。結果として、遊びやすさ(取っつきやすさ)を評価する声がある一方で、従来の光栄作品にあった「内政の積み上げで勝つ」感覚を期待すると、やや肩透かしになることがある。海外メディアの言及でも、テンポがゆっくりな戦略ゲームである点を前提に、“このタイプが好きなら高評価、アクション好きには合いにくい”という方向で語られている。 さらに同じ文脈で、「簡略化によってカジュアルにも触りやすくなった反面、従来の濃厚な光栄ファンには物足りなく映り得る」という指摘も見られる。 つまり本作は“薄めた”というより“狙って絞った”作品で、刺さる人には深く刺さるが、期待の方向が違うと評価が伸びにくい。
●難しさの印象:シナリオ後半や項羽側は「歯ごたえが強い」と語られがち
難易度については、全体として「簡単」というより「やることが明確なぶん、失点の理由もはっきり出る」タイプとして受け止められやすい。特に項羽側は、勝っていても内部が揺らぐ・戦線が細ると崩れる、といった“じわじわ負け”が起こりやすいので、慣れていないと急に転ぶ感触になりやすい。 実際にプレイ感想を集めたレビュー系データベースでも、難しさを「難しい」とする評価が見られ、ゲーム性の好みが割れる様子が読み取れる。 ただ、ここは裏返すと「勝てたときの納得感が強い」部分でもある。負けた理由が、戦闘そのものより“戦線の維持”や“運用の詰め”にあると分かると、次の周回で改善しやすく、研究して上達するタイプの楽しさが立ち上がる。
●よく挙がる良い評価ポイント:選択がぶれにくい/戦略の焦点が絞られている
肯定的な声をもう少し具体化すると、次のような傾向に分けられる。 ・二大勢力制のおかげで、目的が常に明確(迷子になりにくい) ・軍団運用中心なので、戦線の設計と補給の通し方が“戦略そのもの”として味わえる ・歴史題材のドラマ性が強く、勝敗に意味が生まれやすい ・(海外版を含め)光栄の歴史SLGの中では比較的入りやすい、と感じる人がいる こうした評価は、長く遊ぶほど強くなりやすい。最初は地味でも、運用が噛み合ってくると「今の一手が、数か月後の戦局を作る」感触が見えてくるからだ。地図と軍団の動きが“戦争の形”として読めるようになった瞬間に、評価が一段上がるタイプのゲームと言える。
●よく挙がる不満ポイント:展開が単調に感じやすい/内政派には物足りない
一方で、不満として挙がりやすいのは「やることが見えすぎることで、展開が単調に感じる瞬間がある」という点だ。軍団を順に潰していく流れになりやすく、局面の変化が少ないと、作業感が顔を出す。レビューサイトでも“ゲーム性”を低く見る評価が存在し、キャラや設定は良いがゲーム部分は合わなかった、という切り分けが見える。 また、光栄作品の醍醐味として「都市経営・資金繰り・内政の最適化」を求めている人ほど、本作の絞り込みを“軽さ”として受け止めがちになる。海外の受け止めでも、インターフェースや管理要素が簡略化されている点が“手軽さ”になる一方で、従来ファンには不満になり得る、という方向で語られている。 つまり欠点というより、設計思想の副作用として「合わない人の理由が分かりやすい」ゲームになっている。
●メディア・コミュニティ側の反応:海外では“良作だが好みは選ぶ”という語られ方が残る
『Rise of the Phoenix』としてのSNES版に触れた海外側の記述では、戦略ゲームとしての質(選択肢の多さ、演出や音楽の良さなど)を評価する方向と、テンポや簡略化の方向性を好みで割る方向の、両面が併記されやすい。 また、現在でもレトロゲーム文脈で「今遊ぶ価値があるか」という切り口で語られることがあり、“後期のSNES作品で、いつもの光栄より取っつきやすい”という見方が出てくる。 こうした語られ方は、作品が“当時の文脈”だけで終わらず、入門用の光栄歴史SLGとして再発見されていることを示している。
●再発売・復刻への言及:Windows版は「当時の名作を触り直す入口」として名前が挙がる
評判を語るときに、再リリースの存在に触れられることも多い。PC-9801版がベースの移植として、Windows向けに「コーエー定番シリーズ 項劉記」が発売されており(2005年7月22日)、公式のラインナップページや流通情報でも日付・対応OSなどが確認できる。 この“触り直しの導線”があることで、「昔遊んだがうろ覚え」「楚漢戦争SLGを探していた」という層が再評価しやすくなり、評判も“懐古の語り”だけでなく“今遊ぶならどう?”という方向に広がりやすい。
●まとめ:評判が割れる理由が明快だからこそ、自分に合うか判断しやすい
『項劉記』は、二大勢力に絞った歴史ドラマ性と、軍団運用・戦線管理に焦点を当てた作りが長所として語られやすい一方、その絞り込みが「単調」「内政派には薄い」という不満にもつながりやすい。 だからこそ、評判を読むだけで向き不向きが判断しやすいタイプの作品でもある。 ・“前線を動かす戦略”が好きなら、噛むほど味が出る ・“内政の最適化”を期待すると、物足りない可能性がある この見立てが当たる人は多いはずだ。楚漢戦争という題材に惹かれるなら、なおさら一度触れてみる価値はある。
■■■■ 良かったところ
●「項羽と劉邦」だけに集中できるので、歴史のドラマがブレない
『項劉記』でまず挙がりやすい“良かった点”は、主役が二人に固定されていることで、プレイの焦点が最後まで揺れにくいところだ。群雄割拠型の作品だと、勢力が多いぶん状況判断の幅も広がる一方で、「今は何を目指すゲームなのか」がプレイヤーの経験値に依存しやすい。でも本作は、最初から「項羽が勝つか」「劉邦が勝つか」という一本の軸が通っている。 その結果、地図上の一都市の価値が単なる拠点以上の意味を持ちやすい。ここを取れば史実のこの局面に近づく、ここを守れなければ“楚歌”の影が濃くなる――そうした連想が自然に起きる。歴史を知っている人ほど、勝ち負けが単なるスコアではなく“物語の書き換え”として感じられるのが気持ちいい。二大勢力制は選択肢を減らす代わりに、体験の密度を上げる仕組みとして強く働いている。
●軍団運用が中心なので「戦争を動かしている」感覚が強い
良い点として多く語られるのが、内政の数値を積み上げる快感より、「軍団を編成して動かす」快感が前面に出ているところだ。軍団に武将と兵を割り振り、前線に出し、補給を回し、敵軍を削り、拠点を押さえ、戦線を維持する。この一連の流れが“戦争の手触り”として感じられる。 とくに、補給基地としての都市の使い方が見えてくると面白さが跳ね上がる。ただ奪うだけでなく、奪ったあとに守るのか、囮にするのか、捨てるのかを決めて、補給の線を太くする。ここが噛み合うと「勝ったから前へ進める」のではなく「進める状態を作ったから勝てる」という逆転した感覚になり、戦略ゲームとしての上達が気持ちよくなる。 この“上達の実感”が強いのは、良かった点としてかなり大きい。負けても理由が比較的はっきりしていて、次の周回で直すポイントが分かりやすいからだ。
●項羽プレイのスリルが高い:「勝っていても崩れる」緊張感がクセになる
項羽側で遊んだ人が良かったところとして挙げがちなのが、「強いのに安心できない」という独特のスリルだ。正面戦闘では頼もしさがある一方、支配の揺らぎや人心の不安が常に背景にあるため、“勝利の最中でも火消しが必要”という感触になる。 この緊張感は、よくある戦略ゲームの「勝ち始めたら消化試合」になりにくい強みでもある。勢いで押し切れそうな場面でも、補給が細かったり、後方の支持が低かったりすると、後から崩れる。だからこそ、勝ちを積み上げる過程に中だるみが出にくい。項羽で勝利できたときは、単なる勝利以上に「崩れやすいものを最後まで保った」という満足感が残る。これが項羽派の“刺さりポイント”になっている。
●劉邦プレイの気持ちよさ:「組織が育つほど戦略が広がる」伸びの快感
劉邦側で遊ぶと、“序盤の地味さ”が中盤以降に一気に報われるのが良さとして語られやすい。劉邦は本人が万能というより、任せられる人材を増やし、軍団を複数回せる体制にして、戦線を面で押し上げていく方向が強さになる。 これができた瞬間、戦争の見え方が変わる。敵の主力と正面で張り合う軍団、拠点を削る軍団、補給を回す軍団、臨時対応する遊軍――こうした役割分担が成立すると、戦場が“点の勝負”ではなく“面の勝負”になる。戦略が広がるほど操作の手応えも増し、「国家が回り始めた」という達成感が出る。劉邦プレイの良かった点は、まさにこの“伸びる気持ちよさ”に集約される。
●武将の役割がはっきりしていて、編成の工夫がそのまま強さになる
軍団単位で動かす設計のため、武将は単純な能力値の高さだけでなく「どこに置くと軍団が機能するか」で価値が変わる。尖った人材は尖った使い方をすると輝き、万能型は不足を補うと強い。こうした“編成ゲーム”としての面白さがあり、同じシナリオでも軍団の形が毎回違う手触りになりやすい。 良かった点としては、ここがプレイヤーの工夫を裏切りにくいことだ。適当に強い武将を固めるだけでも勝てる局面はあるが、分散して役割を作ると戦線が安定し、損害が減り、結果として勝利が近づく。工夫が結果に反映されるので、プレイの満足度が上がりやすい。
●戦闘に“決め手”があるので、作戦がハマると爽快感が出る
戦闘が完全な数値の殴り合いにならないように、局面で刺さる要素が用意されている点も良かったところとして挙がる。伏兵的な動き、タイミングで勝負を決める攻め方、守りの形を作って受け止める判断など、準備した作戦が戦場で形になると一気に流れが傾く。 この“ハマった感”が気持ちいい。補給や編成で作った土台が、戦闘の一手で収穫になるから、勝利が偶然ではなく「自分の設計の成果」として味わえる。結果として、ただ勝っただけでなく「勝ち方に納得できた」という満足が残る。
●雰囲気作り(音・世界観・題材)が硬派で、没入しやすい
良かった点として地味に大きいのが、ゲーム全体の空気感だ。楚漢戦争という題材の重み、硬派な画面構成、緊張感を作る音楽――こうした要素が合わさり、プレイしているうちに“当時の世界”に気分が寄っていく。派手な演出で盛り上げるのではなく、静かに戦局が動き続けることで熱量が上がっていくタイプの没入感がある。 とくに長期戦になるほど、地図上の前線の一本線が、だんだん“戦争の線”に見えてくる。ここを押せば相手が崩れる、ここを落とすと補給が切れる――そうした読みができるようになると、ゲームの緊張感がさらに増す。硬派な歴史SLGに求める“渋さ”がちゃんとある点は、良かったところとして強く残りやすい。
●「合う人には長く残る」タイプの設計。遊び直しでも味が変わる
最後に良かった点をまとめるなら、『項劉記』は“遊び方が固まるほど面白くなる”タイプだということだ。最初は地味でも、軍団運用と補給の感覚が身につくほど、無駄な損が減り、戦線が太くなり、戦略の自由度が上がる。項羽で短期決戦の精度を上げる楽しみ、劉邦で組織を伸ばす楽しみ――同じゲーム内に質の違う面白さが二つ入っているので、遊び直しの価値も高い。 結果として「一度クリアして終わり」ではなく、「次は別のシナリオ、別の勢力、別の軍団構成で試したい」という気持ちが残る。そういう意味で、良かったところは“設計の芯が太い”ことに尽きると思う。
■■■■ 悪かったところ
●展開が「軍団を潰して前へ進む」に寄りやすく、慣れると単調に感じる瞬間がある
『項劉記』で残念だった点として挙がりやすいのが、ゲームの流れがある程度見えてくると、どうしても「敵軍団を順に叩いて、補給を整えて、また叩いて……」というリズムに収束しやすいところだ。もちろんこれは“戦線運用のゲーム”としては筋が通っているのだけれど、局面の変化が少ないシナリオや、こちらの軍団運用が安定しすぎた周回では、作業感が顔を出しやすい。 特に、勝ちパターンが確立した後半は「次にやるべきこと」が明確で、ミスをしない限り淡々と進むことがある。その淡々さが“硬派で良い”と感じる人もいる一方で、演出やイベントで気分を切り替える要素が欲しくなる人も出る。二大勢力制はドラマ性を濃くする反面、第三勢力が割り込んで戦局を攪乱するような予想外の変化が起こりにくく、刺激が欲しい人には物足りなく映りやすい。
●内政の比重が軽く、光栄作品に期待する「国づくりの快感」が薄いと感じる人がいる
光栄の歴史SLGに「内政の積み上げ」「都市の育成」「資金繰りや国力差の構築」を期待している人ほど、本作の方向性には引っかかりやすい。『項劉記』は内政が不要というわけではなく、支持や敬慕の維持は重要になる。でも、それは“国づくりを伸ばして勝つ”というより“崩れないための手当て”としての内政だ。 この差が、人によっては「内政をやっている手応えが薄い」「数字を育てた達成感が小さい」という不満につながる。たとえば『信長の野望』系で城下を整えるのが好きな人や、『三國志』系で都市を肥やしてから一気に攻勢に出るのが好きな人だと、戦争が中心の手触りに寄っている分、“好きな部分が削られた”ように感じることがある。
●文官タイプが活躍しにくく、役割が戦闘寄りに偏って見えることがある
軍団運用が軸の設計では、どうしても戦闘や用兵に強い武将が主役になりやすい。後方支援や治安維持の重要性はあるのだけれど、プレイヤーの体感としては「前線で活躍しているのは武官」「政治だけ高い人は影が薄い」という印象になりやすい。 これは楚漢戦争という題材上、軍事の比重が高くなるのは自然ではある。だが、光栄作品の魅力のひとつである“文官の運用で国が回る感覚”を期待すると、やや物足りない。補給や後方管理の要として動かしているつもりでも、ゲーム画面に映る活躍の派手さはどうしても前線に寄るため、「活躍している実感」と「重要度」が一致しにくい瞬間がある。
●二大勢力制ゆえに、バランスが史実寄り=ゲーム的には理不尽に感じる場合がある
二大勢力制の最大の“副作用”は、バランスの偏りがそのままプレイ体験に出やすいことだ。史実通り、年代が進むほど項羽側が不利になり、劉邦側が有利になっていく設計は、歴史再現としては納得がある。しかしゲームとして見ると、後半シナリオの項羽は「なぜここまで苦しいのか」と感じるほど、失点が許されない戦いになることがある。 この難しさは“歯ごたえ”にもなるが、気軽に遊びたい人には“重すぎる”ともなる。特に、項羽側で勝ち筋を作るために必要な管理(支持の維持、離反対策、補給線の太さ、遊軍の運用)が噛み合わないと、「戦闘に勝っても負ける」現象が起きやすい。上級者には魅力でも、初見には理不尽に映りやすい部分だ。
●操作のテンポが合わないと、長期戦が“間延び”して感じることがある
戦線運用中心のゲームは、考える時間が面白さである反面、テンポ面で好みが分かれる。『項劉記』も、局面を読みながら軍団を動かし、補給を整え、戦闘を処理していく流れが基本になるため、短い時間で派手に盛り上がるタイプではない。 そのため、プレイヤーが「早く決着を見たい」「イベントで区切りが欲しい」と感じるタイプだと、長期戦ほど“間延び”が気になることがある。戦局が膠着したときに、打開策が「地道に補給を太くして押し返す」に寄りやすいので、派手な逆転劇を期待すると肩透かしになる場合がある。
●情報の見せ方が硬派で、慣れるまで“何が起きているか”を掴みにくいことがある
本作は硬派な画面構成で、状況が分かる人には整理されて見える一方、慣れていないと「どの数字を見ればいいのか」「どこが危険サインなのか」が掴みにくいことがある。とくに、支持や敬慕のような“すぐには爆発しないが、後から効いてくる値”は、初見だと軽視しやすい。 その結果、前線は勝っているのに突然都市が揺れたり、登用が滞ったり、配下が不安定になったりして、「なんで急に?」という印象になりやすい。これはゲーム側が悪いというより、プレイヤーが“後方の危機”を早期発見できるようになるまでの学習コストがある、という話だが、そこを苦痛に感じる人もいる。
●リプレイ性はあるが、イベント主導ではないため「周回の違い」を自分で作る必要がある
二つの勢力、四つのシナリオ、軍団編成の自由度――素材としてのリプレイ性は十分にある。ただし、周回ごとにイベントが大きく枝分かれして別の物語が展開するタイプではない。あくまで、軍団運用の工夫で別の勝ち筋を作り、別の難しさを味わうゲームだ。 だから「周回するたびに新しいイベントが見たい」「物語の変化で引っ張ってほしい」という人には、変化が地味に感じやすい。周回の楽しさを“自分のプレイ方針”で作れる人には向くが、ゲームが自動的に刺激を供給してくれるタイプではない点が、悪かったところとして挙がりやすい。
●まとめ:欠点は“設計の狙い”と表裏一体。合わない人の理由もはっきりしている
『項劉記』の悪かったところは、派手さ不足や単調さ、内政の薄さ、バランスの史実寄りといった点に集約されやすい。ただしこれらは、二大勢力に絞り、軍団運用と戦線管理に焦点を当てた設計の裏返しでもある。 ・戦線運用が好きなら、地味さは“渋さ”になる ・内政やイベントで盛り上がりたいなら、絞り込みは“物足りなさ”になる このように、欠点の指摘がそのまま“向き不向きの説明”として機能するゲームだ。だからこそ、自分が歴史SLGに何を求めるかが明確な人ほど、評価がはっきり割れる。合う人にとっては長く残るが、合わない人には早めに結論が出る――そういう性質も含めて、『項劉記』は印象に残りやすい作品だと思う。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
●項羽:圧倒的な“武の象徴”として、プレイ感そのものがキャラクターになる
『項劉記』で「好きなキャラクター」を語るとき、まず外せないのが項羽だ。史実でも“覇王”として語られる存在だが、本作ではそのイメージが、単なる設定文ではなくプレイ中の手触りとして伝わってくる。前線に立てば戦いが締まり、主力軍団の芯になる。いわば「この人がいる限り、こちらは勝負を作れる」という安心感がある。 ただし、項羽が好きだという人の多くは、強さだけでなく“危うさ”込みで惹かれている。勝てる力があるのに、勝ち続けるための土台が揺らぎやすい。だから項羽プレイは、英雄の強さを味わいながら、同時に「英雄だけでは国は保てない」という苦さを噛む体験になる。その両面がセットになっているから、クリアしたときには単なる勝利以上に「項羽という人物を動かした」実感が残りやすい。 好きな理由としては、「豪胆に押し切る快感」「逆風でも勝ち筋を作ったときの達成感」「史実の結末を覆せたときの高揚」が挙がりやすい。特に後半シナリオで勝てたときは、“史実の難しさ”を肌で理解したうえでの勝利になるので、項羽への愛着が強く残る。
●劉邦:派手さより“人を動かす強さ”が魅力。伸びるほど面白い主人公
劉邦を好きになる人は、「最初から完成された英雄」ではなく、「状況の中で勝ち方を作っていく主人公」としての魅力に惹かれやすい。項羽と比べると、最初の手触りは地味に見えることが多い。でも遊び込むほど、劉邦の強さが“本人の武力”ではなく“組織の伸びしろ”として現れるのが分かってくる。 軍団を複数回せるようになり、役割分担が成立し、補給が回り、人材が揃ってくると、国家が滑らかに動き出す。ここで感じるのは「一人の英雄が勝っている」のではなく「仕組みで勝っている」という快感だ。劉邦好きの人は、この“勝ち方の美しさ”に惹かれていることが多い。 好きな理由としては、「序盤の苦しさが中盤以降に報われる」「戦線を面で押し上げる爽快感」「人材配置が噛み合ったときの手応え」が挙がりやすい。とくに、項羽とは逆に“勝ちが積み上がるほど選択肢が増える”ので、プレイ中に成長の実感を得やすい主人公だ。
●韓信:劉邦側の“戦争の切り札”。編成が噛み合うと戦線の景色を変える
好きなキャラクターとして名前が挙がりやすいのが、韓信のような「戦局を動かせる将」だ。劉邦側の魅力は組織力だが、その組織が“勝ち筋”に変わる瞬間には、だいたい切り札級の武将がいる。韓信を主力軍団の核に据えると、単なる守りのゲームから「こちらが戦線を設計できるゲーム」に変わっていく感触が出やすい。 好きな理由としては、まず“使っていて気持ちいい”こと。軍団単位で動かすゲームでは、核になる武将をどこに置くかで軍団の価値が大きく変わる。韓信のような人物を「ここで使う」と決めた瞬間に、作戦の輪郭がくっきりする。結果として、戦争がぐっと立体的に見え、「軍団運用の面白さ」が一気に引き出される。そういう意味で、韓信はキャラクターであり、同時に攻略上の“スイッチ”にもなる存在だ。
●張良:派手さはなくても、戦いを“勝てる形”に整える参謀役が好きになる
派手な武功だけでなく、参謀や軍師タイプの人物が好きだという人も多い。張良のような存在は、前線で敵を倒すというより、戦いを勝てる形に整える役として魅力が出やすい。軍団運用中心のゲームでは、前線の勝利を支える“準備”が重要になるので、こうした人物を評価できるようになると、プレイそのものが一段深くなる。 好きな理由としては、「地味なのに重要」「勝利の陰で働いている感じが良い」「戦線が安定するほど存在感が増す」といったものが挙がりやすい。目立たないからこそ、上達したプレイヤーほど好きになるタイプだ。
●蕭何:後方支援の象徴。補給と維持の面白さに気づくと好きになる
『項劉記』の“好きなキャラクター”を語るうえで、このゲームらしさが出るのが蕭何のような後方型の人物だ。前線を動かすゲームだからこそ、補給と後方維持の重要性が刺さる。戦闘の勝ち負けより、補給線が太いか細いかで勝敗が決まる局面を経験すると、「前線の英雄より、後方の要が怖い」と感じ始める。 好きな理由は、「派手さはないのに勝利に直結する」「後方が回ると前線が強くなる」「補給と維持の重要さを体感させてくれる象徴」としての魅力だ。こういう人物を好きになってしまうのは、ある意味で『項劉記』にハマった証拠でもある。
●范増:項羽側の“知”としての魅力。うまく使うほど項羽プレイが締まる
項羽側で好きになりやすいのは、武の象徴だけでなく、それを支える知恵袋の存在だ。范増のような人物は、項羽プレイの「勝てるが崩れる」という弱点を補う方向で魅力が出やすい。項羽側はどうしても前線が強い分、勢いで押しすぎる事故が起きやすい。そこで、軍団を分け、後方を整え、外交や支持維持を意識するようになると、項羽プレイがぐっと“国家運営”らしくなる。 好きな理由としては、「項羽の危うさを締める存在」「単なる脳筋ではなく戦略のゲームになる」「史実の悲劇性を感じさせる」という語られ方になりやすい。項羽を好きな人ほど、こうした参謀役にも愛着が移りやすい。
●英布・彭越など“揺れる武将”が好き:登用と離反のドラマが刺さる
二大勢力制のゲームでは、第三の勢力として独立している人物が“揺れ”として面白さを作る。英布や彭越のように、歴史の中で立ち位置が揺れた人物は、ゲームでも登用・友好・離反のドラマとして印象に残りやすい。 好きな理由としては、「確保できたときの喜びが大きい」「相手に取られると厄介」「戦局が一気に変わる」という“読み合い”の面白さがあるからだ。こうした人物は単純な最強キャラではないが、戦線の形を変える存在として記憶に残る。
●まとめ:好きなキャラが「勝ち方の思想」と直結するゲーム
『項劉記』の面白いところは、好きなキャラクターが単なる好みで終わらず、そのままプレイヤーの勝ち方の思想に直結しやすい点だ。 ・項羽が好き=短期決戦の精度と、崩れやすさを制御する技術に惹かれる ・劉邦が好き=組織を育て、面で押す勝ち方に惹かれる ・韓信や張良、蕭何が好き=軍団運用と補給・参謀の重要性に気づいている こうした“好みの分岐”が、そのままプレイ体験の違いとして現れる。だからこそ、語るほどに面白いキャラクターが多く、歴史SLGとしての余韻も残りやすい。『項劉記』は、キャラクターの魅力が「数字の強さ」ではなく「戦争の形をどう作るか」という実感に結びつく、珍しくも渋いタイプの作品だと思う。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
●まず大前提:中身の“核”は同じでも、遊び心地はハードの個性で変わる
『項劉記』は、PC-9801版を起点にFM TOWNS版・X68000版へ移植され、その後Windows向けには「PC-9801版の移植」として復刻された流れがはっきりしている。 つまり、シナリオやゲームの骨格(軍団を編成して戦線を動かし、補給をつないで勝ち筋を作るという本質)は共通している一方で、「読み込み」「音の鳴り方」「画面の見やすさ」「操作環境」「保存のしやすさ」といった“体験の皮膚感”が、対応機種ごとに違ってくるタイプだ。ここでは、当時の各機種の得意分野と、本作の性格を噛み合わせたうえで、「どこが変わりやすいか」を整理していく。
●PC-9801版:基準になる“素の項劉記”。当時の空気を最も濃く味わえる
まずPC-9801版は、発売日が1993年7月21日で、ここがすべての基準点になる。 この版の良さは、言ってしまえば「当時の光栄のPC歴史SLGの手触りが、そのまま残っている」ことだ。コマンド入力のテンポ、画面の情報量、戦場とマップを眺めながら少しずつ決断を積み重ねる感覚――それらが“そのままの速度”で体に入ってくる。ゲームがプレイヤーを派手に煽らないぶん、こちらが局面を読む集中力が上がりやすく、じわじわと熱が乗る。 一方で、現代の感覚だと不便さが出やすいのもここだ。ディスク運用やセーブ管理、ロードの待ち時間など、プレイを中断・再開するときの摩擦が大きくなりやすい。だからPC-9801版は、環境が整っている人にとっては“最も濃い原液”だが、気軽さの面ではハードルがある。
●FM TOWNS版:CD-ROM化で“運用が軽くなる”方向。移植のうま味が出やすい
FM TOWNS版は1993年10月1日発売で、メディアがCD-ROMと明記されている。 CD-ROM化が何を変えるかというと、いちばん分かりやすいのは「取り回しの楽さ」だ。プレイ中のロードやデータ参照の感覚は、フロッピー主体の環境と比べて“引っかかり”が減りやすい。『項劉記』は、前線の状況を確認して、軍団を動かし、戦闘結果を受けて次の手を考える……という反復が多いゲームなので、細かな待ち時間が短くなるだけでテンポの印象が変わる。 また、FM TOWNSという機種そのものが「音やビジュアルを気持ちよく鳴らす」方向に強みを持つイメージがあるため、本作のBGMや効果音の“鳴り”に満足しやすい、という感想につながりやすい。ただし、ここは移植の方針によって差が出る部分でもあるので、「FM TOWNSだから必ず豪華」と決め打ちするより、「ロードや運用が軽くなって、プレイの集中を保ちやすい版」と捉えるほうが実感に近い。
●X68000版:操作の手触りが締まりやすく、“戦場の緊張感”が映える版
X68000版は1993年11月5日発売で、メディアは5インチフロッピー。 X68000で遊ぶ魅力は、同じゲームでも「画面の締まり」と「反応の良さ」によって、軍団運用の緊張感が立ちやすいところだ。『項劉記』は、戦闘そのものよりも“戦線を作る判断”が勝敗を左右しやすいので、マップ上の情報が見やすく、操作が小気味よいほど、プレイヤーの判断速度が上がって面白さが出やすい。 加えて、音の面でもX68000らしい鳴りを好む人が多く、BGMを「作品の雰囲気を固める重要要素」として評価する人ほど、この版に愛着を持ちやすい。実際、X68000版の音源(YM2151を中心にした構成)に触れて語られることもある。 ただし、メディアがフロッピーである以上、ロードや保存の扱いは環境に左右される。気軽さより“機種込みの味”を楽しむ方向の版、と考えると納得しやすい。
●Windows版:いちばん手軽に触り直せる“復刻窓口”。ただし中身はPC-98移植の味
Windows版について重要なのは、「PC-9801版の移植」と明記されている点だ。 つまり、Windows向けに新しく作り直して現代的に再設計したというより、“当時のPC-98の遊び心地を、Windowsで動かせる形に寄せた復刻”と捉えるのが近い。 発売日も確認でき、2005年7月22日リリースの「コーエー定番シリーズ 項劉記」が流通情報として残っている。 動作環境も、Windows98/Me/2000/XPを対象にし、解像度640×480・256色、CD-ROMドライブ必須など、当時の復刻PCゲームとしてはかなり割り切った仕様になっている。 この版の最大の良さは「手軽さ」だ。実機を揃えなくても、当時の歴史SLGのテンポや設計思想を体験できる。セーブデータの扱いも、物理ディスク中心の環境よりは管理がしやすくなる場合が多い。加えて、Windowsなら画面キャプチャやメモ書きなど、“研究しながら遊ぶ”行為がやりやすいのも利点だ。 一方で注意点もある。復刻系は環境依存が出やすく、対応OSやDirectX周りなど、当時の条件を前提にしている。 「今のPCなら何でも動く」とは限らないため、動かす手段を確保できる人ほど安心して選べる版でもある。
●結局どれが向いている?:目的別の選び方(“勝ち方”ではなく“遊び方”で選ぶ)
対応機種ごとの差は、性能差でマウントを取る話というより、「どんな気分で『項劉記』を味わいたいか」で決めるのがいちばん失敗しにくい。 ・当時の光栄PCゲームの原液を吸いたい、手間も含めて味だと思える → PC-9801版 ・ロードや運用の軽さでテンポ良く遊びたい、移植のメリットを感じたい → FM TOWNS版(CD-ROM) ・機種込みの手触り、音や操作の締まりで“戦争の緊張”を味わいたい → X68000版 ・実機に寄せた空気を、比較的手軽に触り直したい → Windows版(PC-98移植)
『項劉記』は「どの機種でも同じゲーム」になりやすい一方で、細かなテンポの差がそのまま没入感に響く作品でもある。軍団運用と補給の読み合いは、集中しているほど面白い。だからこそ、あなたのプレイ環境で“集中が途切れにくい版”を選ぶのが、いちばん賢い選択になると思う。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
★プリンセスメーカー2
・販売会社:ガイナックス ・販売された年:1993年 ・販売価格:16,280円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: “育成”という言葉がまだ今ほど一般的ではなかった時代に、「限られた年月の中で、ひとりの少女の人生をデザインする」というテーマを前面に押し出した作品。プレイヤーは父親役となり、学業・礼儀・武芸・芸術・社交・休養などの予定を月単位で組み、能力値・性格傾向・体調・ストレス・所持金といった複数の要素を同時に面倒を見る。面白いのは、数値の上げ下げが単なる強化では終わらず、「どう育ったか」がイベントの出方や周囲の反応を変え、最終的に“どんな大人になったか”として結末に反映されるところ。 この時期のPCゲームらしく、文章と絵で読ませる場面が多い一方で、遊びは極めてゲーム的だ。例えば、短期的に成績を伸ばすために詰め込むと体調が崩れやすくなり、逆に休ませすぎれば資金繰りが苦しくなる。バランスの乱れが、思わぬ病気や不機嫌、あるいは交友関係の変化として返ってくるので、プレイヤーは「効率」だけでなく「その子の機嫌」まで気にしはじめる。結果として、攻略手順をなぞるというより、家庭内マネジメントの“手触り”が残るタイプの名作になっている。
★ブランディッシュ2
・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1993年 ・販売価格:14,080円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: “見下ろし型のダンジョン探索”に、独特の「方向」というスパイスを混ぜ込んだアクションRPG。プレイヤーが操作する主人公は、迷宮内を歩き回り、扉を開け、罠を見抜き、敵と接触すれば即座に剣戟へ移る。ここで効いてくるのが、マップの向きや視点の感覚だ。単に通路を移動するだけでも、左右や上下の把握を狂わせるような構造が多く、慣れないうちは「今どこに向いているか」を意識し続けることになる。だからこそ、迷宮を“理解して支配する”感覚が強い。 戦闘は派手さよりも手堅さに寄っていて、回復・武器・防具の管理がじわじわ効く。勝てる相手でも、連戦すると回復資源が尽き、帰還の判断が遅れると一気に崩れる。探索・戦闘・帰還のリズムが固定されず、迷宮の嫌らしさがそのままテンポになるのが魅力だ。1990年代前半のPCユーザーが好んだ“骨太な探索感”を、かなり濃い味付けで提供している。
★A列車で行こう4(A-TRAIN Ⅳ)
・販売会社:アートディンク ・販売された年:1993年 ・販売価格:12,800円(税別の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 鉄道会社の経営者として、路線を引き、駅を置き、ダイヤや輸送力を整えながら、都市を“発展させていく”都市開発シミュレーション。特徴は、街づくりの主語が最初から「鉄道」であること。道路を敷いて街を作るのではなく、線路と駅が人の流れを生み、その流れに合わせて土地の価値や建物の密度が変わり、やがて街そのものが姿を変える。つまり、線路は移動手段であると同時に、都市の成長を誘導する“骨格”でもある。 当時のPCシミュレーションらしく、プレイヤーが得られる情報量は多い一方、何もしなければ何も進まない。路線の採算、列車の運行頻度、駅間距離、沿線の開発余地、競合交通の存在……それらを眺めながら「この一手で何が起こるか」を想像し続けるゲームだ。短期の利益を追うと渋滞や過密が発生し、長期の街づくりを狙うと資金が先に尽きる。うまく回り始めると、最初に敷いた一本の線路が、十年後には都市圏全体の形を決めていた、というような“時間の快感”が味わえる。
★超時空要塞マクロス リメンバー・ミー
・販売会社:ファミリーソフト ・販売された年:1993年 ・販売価格:10,780円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 人気アニメ作品の世界観を下敷きにしつつ、PCならではの“シミュレーション寄りの遊び”へ落とし込んだタイプのキャラクターゲーム。単純にアクションで撃ちまくるというより、状況を読み、装備や機体、作戦の組み立てで結果が変わる設計が持ち味になりやすい。マクロス題材らしく、戦闘だけでなくドラマ性や人物関係の雰囲気を感じさせる場面が差し込まれ、プレイヤーは「勝つための判断」と「物語を追う没入」の間を往復する。 この時期のPC作品は、演出のすべてを動きで見せるより、情報を整理して提示し、プレイヤーの想像で補完させる作りが多い。本作も、画面の切り替えやテキストの密度を通じて“当時のアニメゲームの作法”が伝わってくる。原作を知っているほどニヤリとでき、知らなくても「世界設定を読み解くSLG/ADV的な味」で楽しめる、という立ち位置の一本。
★ラスティ
・販売会社:シー・ラボ ・販売された年:1993年 ・販売価格:10,780円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: PC-98時代のRPG/アドベンチャーの空気を色濃くまとった作品で、探索・会話・イベント進行を積み重ねながら物語を前に進めるタイプ。派手なリアルタイム性より、行動の選択と情報収集が軸になりやすく、プレイヤーは「次にどこへ行くべきか」「誰に会うべきか」「何を手がかりにするか」をメモしながら進めることになる。 この手のゲームの魅力は、戦闘や謎解きの難度そのものより、“世界の断片がつながっていく感覚”だ。最初は意味不明だった台詞が、別の街の事件と結びついた瞬間に理解へ変わり、理解が次の行動を生む。そういう連鎖が気持ちよく、プレイヤーの頭の中に「自分だけの攻略地図」が育っていく。テンポは速くないが、浸るほどに面白さが増える――90年代PCゲームの良さが出やすい一本と言える。
★アルヴァリーク冒険記
・販売会社:グローディア ・販売された年:1993年 ・販売価格:12,980円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 冒険活劇の雰囲気を前面に出したRPG寄りの作品で、世界を歩き回りながら仲間や情報を集め、イベントを踏んで物語を解いていく“王道の手順”が気持ちよく回るタイプ。パッケージ内容としてドラマCD同梱が示されている点も、この時期らしい特色で、ゲーム外の要素で世界観を補強し、「作品としての没入」を高める狙いが見える。 ゲームの中身は、派手な瞬間芸よりも“旅の実感”が軸になりやすい。次の街へ行く、道中で危険に遭う、そこで得た報酬で装備を整える、会話から次の目的地を推理する。そういった手順が丁寧に積み上がり、プレイヤーが物語の住人になった気分を作っていく。万人向けに遊びやすく整えつつ、当時のPCユーザーが好む「文章と想像で広がる世界」も残しているのが強み。
★ファーランドストーリー
・販売会社:テイジイエル販売(販売元表記) ・販売された年:1993年 ・販売価格:9,800円(税別の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 90年代前半のPCで人気を伸ばした“シミュレーションRPG(SRPG)”の系譜にある作品で、マップ上のユニットを一手ずつ動かしながら戦況を組み立てていく。魅力は、戦闘が単なる数値比べになりにくいところ。地形の使い方、隊列の作り方、回復役の守り方、敵の射程管理など、初歩の工夫だけで勝率が変わる。だから、レベルを上げるだけではなく「戦い方が上手くなる」感覚が手に残る。 またSRPGは、戦闘の合間にキャラクター同士の関係性や小さなドラマを差し込むのが得意だ。本作も、戦いが続くほど“ただの駒”が“仲間”に変わっていき、損耗や撤退が重く感じられるようになる。その重みが、勝ったときの達成感につながる。1993年のPC-98ユーザーにとって、遊びごたえと物語性を両立した定番ジャンルを、手堅く楽しめる一本だった。
★三國志IV
・販売会社:光栄 ・販売された年:1994年 ・販売価格:16,280円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 三国時代の君主として中国統一を目指す歴史シミュレーションで、シリーズの中でも「戦闘表現」と「武将運用」の感触が変化した時期の作品。都市の取り合いだけではなく、戦場での判断や武将の特性が結果を左右しやすく、部隊の編成や人材配置の段階から勝敗が始まる。強い武将を集めるだけでなく、前線に誰を置き、内政や外交を誰に任せ、どのタイミングで攻勢に出るか――その筋道を作るのが面白い。 この作品が“同時期のPCゲーム”として象徴的なのは、プレイヤーに要求するのが反射神経ではなく「読み」と「準備」である点。忙しさはあるが焦らされはしない。そのかわり、判断を誤ると痛い目を見る。だから一手ごとに緊張感があり、戦局が動いたときの手応えが大きい。『項劉記』が楚漢戦争を題材に二大勢力の個性を立てたのに対し、『三國志IV』は群雄の多さで“人材の混沌”を描く、という違いもあって、同じ会社の歴史SLGでも遊後感が変わるのが面白い。
★ダンジョンマスターII スカルキープ
・販売会社:ビクターエンタテインメント(日本版の発売元として挙げられることが多い) ・販売された年:1994年(国内PC-98期) ・販売価格:12,800円(当時価格情報) ・具体的なゲーム内容: リアルタイム進行のダンジョン探索RPGで、「一歩進む」「振り向く」「扉を開ける」といった行為がそのまま緊張へ直結するタイプ。敵は待ってくれない。回復や補給のために立ち止まる行為自体がリスクになる。だからプレイヤーは、“迷宮の地形を理解する力”と同じくらい、“瞬間の判断”を鍛えられる。 面白さは、戦闘がコマンド選択ではなく、位置取りと手順で決まるところにある。通路での押し合い、視界外からの奇襲、パーティの並び替え、回復役の保護。慣れてくると、相手の速度や間合いを見て「この角で待ち、ここで一発入れて後退する」といった、身体感覚に近い攻略が可能になる。加えて、謎解きや仕掛けが探索のテンポを変え、単調な戦闘の連続になりにくい。1994年前後のPCで、硬派なダンジョンものを求める層に刺さりやすい一本だ。
★シムシティ2000(PC-9801版)
・販売会社:イマジニア ・販売された年:1994年(PC-98版の発売時期情報) ・販売価格:10,780円(当時の定価情報) ・具体的なゲーム内容: 都市運営シミュレーションの金字塔のひとつで、「街を作る」だけでなく「街を維持する」ことの難しさをゲームとして噛みしめられる作品。住宅・商業・工業のバランス、道路や鉄道など交通網の設計、電力・水道・ゴミ処理といったインフラ、治安や消防、教育、税率調整……やることは多いが、すべてがつながっている。税率を上げれば財政は楽になるが住民が減り、住民が減れば商業が死に、商業が死ねば雇用が落ち、雇用が落ちればさらに住民が減る。こうした連鎖が“生き物みたいに”動くのが醍醐味だ。 1994年前後のPCで遊ぶと、この作品は「画面の中の地図を眺め続けてしまう」中毒性として現れる。道路一本の位置で渋滞が変わり、区画ひとつの指定で税収が変わる。小さな変更が長期的に効くので、プレイヤーは短期の黒字より“十年後の都市像”を夢想し始める。『項劉記』が補給線で戦線を保つゲームなら、『シムシティ2000』はインフラで都市を保つゲーム――同じ“維持管理の面白さ”でも、題材が変わると快感の形が変わる。
[game-8]

![【中古】【箱説明書なし】[SFC] 項劉記(こうりゅうき) 光栄 (19940406)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005617.jpg?_ex=128x128)