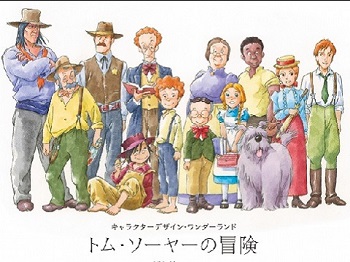【中古】 テレビアニメ スーパーヒストリー vol.8「けろっこデメタン」〜「新造人間キャシャーン」/(アニメーション)
【原作】:鳥海尽三
【アニメの放送期間】:1973年1月2日~1973年9月25日
【放送話数】:全39話
【放送局】:フジテレビ系列
【関連会社】:タツノコプロ
■ 概要
タツノコプロが描いた“もうひとつの水辺の寓話”
1973年1月2日から同年9月25日まで、フジテレビ系列で毎週火曜日の19時から19時30分にかけて放送された『けろっこデメタン』は、タツノコプロが制作した全39話のテレビアニメである。『ハクション大魔王』や『昆虫物語 みなしごハッチ』など、人間社会を投影した寓話的な作品群の流れを汲む一作として知られ、子ども向けの“かわいいカエルの物語”という外見の裏側に、社会の格差や抑圧、そして自由を求める個の勇気といった、重層的なテーマを内包していた。平均視聴率は10%前後と、当時の同時間帯としては安定した数字を記録しており、放送後も再放送や映像ソフトを通じて長く記憶されている。
物語は「虹のお池」と呼ばれる池を舞台に、貧しいアマガエルの少年・デメタンが、支配階級に属するトノサマガエルの娘・ラナタンと出会い、友情と愛情を育みながら成長していく姿を描く。表面的には動物たちの交流を通じた少年の成長物語だが、実際には社会の不平等や階級制度への風刺、そして弱者の立場から世界を見つめる痛切な視点をもつ作品である。
制作背景とタツノコ作品群における位置づけ
本作が制作された1973年当時のタツノコプロは、『科学忍者隊ガッチャマン』によってアクション路線を強化しつつも、同時に『昆虫物語 みなしごハッチ』や『樫の木モック』といった“感情劇・社会寓話路線”にも力を入れていた時期だった。『けろっこデメタン』はその流れの延長線上にあり、単なる子ども向け動物アニメの枠を超え、人間社会の縮図として“池”を描き出すことを狙った企画だったとされる。
制作スタッフには、後年『タイムボカンシリーズ』などで名を馳せる人材も多く参加しており、作画・美術面ではタツノコらしい滑らかで繊細なアニメーションが随所に見られる。特に水の描写や色彩設計の美しさは放送当時から高く評価され、湿度を帯びた情景表現や、夜明け・夕暮れなどの光の変化を繊細に表現する映像詩的な構成が特徴である。
また、劇伴を担当した越部信義による音楽も重要な要素である。オープニングの「けろっこデメタン」、エンディングの「まけるなデメタン」ともに、堀江美都子の澄んだ歌声が作品全体のトーンを象徴している。可憐さと哀しさを同時に抱く旋律は、当時の子どもたちに“優しさの中にある痛み”を印象づけた。
舞台設定と物語構造の特徴
『けろっこデメタン』の舞台である“虹のお池”は、カエルや魚、虫といった多様な生き物が共存する小さな社会として描かれる。そこでは“支配する者”と“支配される者”がはっきりと分かれており、池を仕切るトノサマガエルのギヤ太が圧政的な支配者として存在している。ギヤ太は名目上の権力者でありながら、実際には池の底に潜む巨大ナマズ“ナマズ入道”の操り人形にすぎず、最終的にその支配構造が崩壊するまでの物語は、まるで革命劇や階級闘争の寓話を見ているかのような印象を残す。
デメタンは庶民階級に生まれた少年で、両親の雨太郎・雨子と共に貧しい生活を送っている。一方のラナタンは、支配者層の娘でありながら純真で優しい心を持ち、社会の理不尽さに疑問を抱いている。二人の友情と恋の芽生えは、立場の違いがもたらす衝突の中で試されていく。まさに“水辺版ロミオとジュリエット”と呼ばれるゆえんである。
序盤は心温まる交流を中心に展開するが、物語が進むにつれ、池を覆う恐怖の正体=ナマズ入道の存在が浮かび上がる。ラナタンの父・ギヤ太はナマズ入道に従い、住民たちから貢ぎ物を徴収していたのだ。デメタンたち庶民は圧迫されながらも、勇気を持って立ち上がり、最後には池の仲間と共にこの支配構造を打ち破る。
主題の核心 ― “小さな者の勇気”と“優しさの力”
『けろっこデメタン』の中心にあるのは、“弱く小さな存在でも、理不尽な世界を変えられる”という信念である。デメタンは初めこそ泣き虫で臆病な少年だが、出会いと別れを繰り返す中で、痛みを知り、思いやりを覚え、やがて立ち上がる勇者へと成長していく。その成長過程は、1970年代初頭の社会風潮――高度経済成長の陰で広がっていた貧富格差や、個の尊厳の希薄化への警鐘としても読める。
また、作中で繰り返される“ケロケロ笛”の音色は、デメタンの純粋さと希望の象徴である。戦いや憎しみが渦巻く世界の中で、笛の優しい音が鳴り響くとき、そこには“争わずに生きる道”への願いが込められている。単なる子ども向け娯楽に留まらず、戦争や差別、自然破壊といったテーマに通じる普遍性を持つ点が、長く支持される理由でもある。
放送当時の反響と後年の再評価
放送当時、『けろっこデメタン』は一見して明るく可愛らしい作品でありながら、後半にかけてシリアスで悲劇的な展開を見せる点が特徴的だった。とくに最終話に至るまでの緊張感ある展開は、子どもたちだけでなく親世代にも強い印象を与え、「子ども番組の枠を超えた社会寓話」として語られた。
80年代に入ると、アニメ誌や映像ソフトの再発売を通じて“隠れた名作”として再評価が進んだ。のちに『みなしごハッチ』『てんとう虫の歌』などと並び、“タツノコ哀歌三部作”として言及されることも多い。近年ではDVDや配信サービスによる再視聴が容易になり、往年のファンだけでなく、新たな世代の視聴者にも「優しさの裏にある現実」を伝える作品として注目されている。
また、現代の視点から見ると、本作に描かれた“生態系の均衡”や“自然と共生する社会”というモチーフも環境教育的な意味を持ち、時代を超えて通用する普遍性を備えている。
まとめ ― 子どもの目を通して映す人間社会
『けろっこデメタン』は、かわいらしいキャラクターや牧歌的な映像表現の裏に、社会的メッセージと心理描写を巧みに織り込んだ作品である。貧富の差、権力と服従、勇気と愛、そして再生というテーマが、池という小さな世界の中に凝縮されている。タツノコプロらしいヒューマニズムと、当時の時代背景が融合したことで、今なお観る者の心を静かに揺さぶる名作として記憶されている。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
虹のお池にやって来た小さな旅人
物語は、アマガエルの少年・デメタンが両親とともに新天地を求めて旅をする場面から始まる。彼の故郷の池は、ある日イモリたちの襲撃によって壊滅してしまった。土砂崩れに巻き込まれて兄弟をすべて失い、悲しみに暮れるデメタン。そんな一家がようやく辿り着いたのが、豊かで美しい「虹のお池」だった。
しかしこの池は、表面こそ穏やかに見えるものの、実際は階級が厳然と存在する社会であった。トノサマガエルのギヤ太が池の支配者として君臨し、庶民の生き物たちはその庇護のもとで暮らすしかない。デメタンの父・雨太郎はおもちゃ作りの露天商で生計を立てるが、ギヤ太の取り巻きによる嫌がらせに苦しみ、貧しい生活を余儀なくされる。それでも家族は、明日への希望を失わずに生きていた。
ラナタンとの出会い ― 優しさが運命を変える
ある日、デメタンは虹のお池のほとりで、一人遊んでいた少女・ラナタンと出会う。彼女はトノサマガエルのギヤ太の娘で、身分の違いから本来は口をきくことも許されない存在だった。だが、ラナタンは生まれ育った特権的な環境に窮屈さを感じており、貧しくとも純粋に生きるデメタンの姿に心を惹かれる。
二人は池の秘密の場所で会うようになり、ラナタンは字を知らないデメタンに読み書きを教え、デメタンは代わりにケロケロ笛の吹き方を教える。小さな友情の芽は、やがて淡い恋へと変わっていく。しかし、その関係がギヤ太に知られると状況は一変する。身分を越えた交際を許さぬ父ギヤ太は激怒し、デメタン親子を池から追放しようとする。
それでもラナタンは諦めず、デメタンをかばい続ける。彼女の優しさは、やがて周囲の子どもたちにも影響を与え、池の中に少しずつ“違いを受け入れる心”が芽生え始める。
試練の連続 ― 不条理に立ち向かう少年
物語の中盤では、デメタンが様々な困難に直面する。父の仕事場がイボ吉たちの妨害で壊され、母が病に倒れる。さらに、池を荒らす外敵が現れ、デメタンたちは再び危機に陥る。だが、彼は逃げずに立ち向かうことを選ぶ。幼いながらも正義感に燃え、友のため、家族のために行動する姿は、単なる“弱者の象徴”ではなく、真の勇気を体現する存在として描かれる。
この頃からデメタンの笛の音は、池の生き物たちにとって“希望の音色”となる。戦いや憎しみの最中でも、笛の音が響けば誰もが一瞬立ち止まり、優しさを取り戻す。その音が、後に池の運命を変える重要な鍵となっていく。
支配者ギヤ太と巨大な影 ― ナマズ入道の正体
やがて、池の中で語られてきた“地獄ジャングルの主”という恐ろしい伝説が現実味を帯びてくる。実は、池の支配者ギヤ太の背後には、さらに巨大な存在――ナマズ入道が潜んでいた。池の底の洞窟に棲むこの大ナマズは、ギヤ太を操って貢ぎ物を集め、自らの食料としていたのである。
ナマズ入道は池の住民に恐れられながらも、その実態を知る者は少ない。デメタンも当初は彼を「池を守る神」と信じていた。だが、友人のエレ吉一家がナマズ入道に食べられてしまうという悲劇を目の当たりにし、真実を知る。そこから、少年の中に“怒り”と“正義”が芽生える。
ラナタンの父・ギヤ太もまた、ナマズ入道の支配から逃れられず苦悩していた。デメタンはそんなギヤ太をも救おうとし、敵であった者すら仲間として迎える強さを見せる。この過程こそ、彼の精神的成長のクライマックスである。
反逆と希望 ― 虹のお池の解放
物語の後半では、デメタンとラナタン、そして改心したギヤ太や他の仲間たちが団結し、ナマズ入道に立ち向かう壮絶な戦いが描かれる。力では到底敵わない彼らは、知恵と勇気で立ち向かう。エレ吉の電撃、デメタンの笛の音、仲間たちの連携――それぞれの小さな力が一つになり、ついにナマズ入道を撃退する。
この戦いの結末は、単なる勝利ではない。支配と恐怖に縛られていた池の住民たちが、自分たちの意志で新しい社会を築こうと立ち上がるきっかけとなる。ラナタンの涙とデメタンの笛の音が交わる場面は、まるで“再生”を象徴する祈りのようだ。
別れ、そして新たな始まり
戦いの後、虹のお池は静けさを取り戻す。デメタンは父母とともに平和な日々を迎え、ラナタンとも寄り添うように暮らす。だが、物語は甘い余韻だけでは終わらない。池の自然は再び季節とともに変わり、命の循環が続いていく。
最終話では、デメタンとラナタンが一緒に笛を吹く場面で幕を閉じる。かつて悲しみを癒やすために吹かれた笛が、今は“希望”と“未来”を奏でている。どこまでも静かなラストシーンには、タツノコプロ作品に共通する“優しさと切なさ”の美学が凝縮されている。
寓話としての余韻
『けろっこデメタン』は、単なるカエルの冒険譚ではなく、社会の不平等・環境問題・友情と愛・赦しと再生といったテーマを柔らかく包み込んだ、深い寓話である。人間社会の縮図でありながら、最終的には“誰もが分かり合える世界”への希望で終わる。
この物語が長く愛されるのは、デメタンの成長物語が、現実世界の私たち一人ひとりの人生と重なるからだろう。理不尽に立ち向かう勇気、他者を思う優しさ、そして過去を乗り越える強さ――それこそが、この作品の真の主題である。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
デメタン ― 優しさと勇気を兼ね備えた小さな主人公
本作の中心人物であるアマガエルの少年・デメタンは、外見も心もまだ幼いながら、非常に誠実で優しい心を持つキャラクターだ。貧しい家に生まれ、学校にも通えず、社会の片隅で生きている彼の姿は、当時の視聴者にとって“どこにでもいる普通の子ども”を象徴していた。 デメタンの最大の魅力は、「弱さを恥じない強さ」である。彼は決してヒーロー然とした存在ではなく、泣き、悩み、逃げ出しそうになりながらも、仲間や家族を守るために立ち上がる。ラナタンとの出会いを通じて成長し、やがて理不尽な社会に抗う勇気を身につける過程は、少年から大人への成長譚として描かれている。
彼が常に持ち歩く“ケロケロ笛”は、作品を象徴するアイテムだ。笛の音には仲間を勇気づけ、争いを鎮め、希望を呼び覚ます不思議な力がある。ときに武器として、ときに心の絆として、笛はデメタンの精神的支柱であり、視聴者にとっても印象的なシンボルとなった。
また、彼が時折見せる頑固さや怒りは、単なる善良さだけでなく、“本気で生きる”という強い意志の証でもある。最終話でラナタンと共に笛を吹くシーンは、デメタンの成長の到達点として語り継がれている。
ラナタン ― 階級の壁を越える純粋な心
ラナタンは、支配者ギヤ太の娘でありながら、貧しい庶民たちに優しく接する心優しい少女だ。彼女は生まれながらの特権を当然とせず、父の理不尽な命令に疑問を抱く。デメタンとの出会いは、ラナタンにとって“世界の広さ”を知るきっかけとなる。
当初、彼女は物語の中で唯一「教育を受けている存在」として描かれており、文字の読み書きや常識をデメタンに教える。その反面、社会的には“檻の中の姫”であり、自由に外の世界を見ることを禁じられていた。
ラナタンの成長は、デメタンとは異なる形の勇気で表現される。彼女は力ではなく、信念と優しさで立ち向かう。父に反抗し、弱き者を守るために立ち上がる姿は、視聴者の心に深い印象を残した。
また、ラナタンは作中でも特に情感豊かに描かれており、泣く・笑う・怒るといった表情の変化が非常に繊細だ。作画スタッフが力を注いだとされるその描写は、少女キャラとしての魅力と同時に、“人としての強さ”を際立たせている。デメタンとの関係は恋愛というよりも“魂の同志”に近く、彼女の存在がデメタンを変え、池の未来を変えていく。
雨太郎と雨子 ― 家族愛が生きる力を与える
デメタンの両親である雨太郎と雨子は、作品の土台を支える存在だ。雨太郎はおもちゃ職人として生計を立てており、どんな困難にも負けない強い意志を持つ。貧しいながらも正直に働き、息子に“誇り”を教える姿は、多くの大人視聴者に共感を呼んだ。
一方の雨子は、優しさと忍耐の象徴である。夫と息子を支え、理不尽な社会に抗う家族を明るく守る母親像として描かれた。特に彼女が病に倒れたエピソードでは、デメタンが初めて「守る」という責任を強く自覚する場面があり、物語全体の転機となる。
この親子の絆があるからこそ、デメタンの行動は単なる反抗や冒険ではなく、“家族の誇りを守る戦い”として成立している。
ギヤ太 ― 権力と弱さを併せ持つ支配者
虹のお池を支配するトノサマガエルのギヤ太は、表向きは威厳ある王のように振る舞うが、実際にはナマズ入道に操られた哀れな存在である。彼は支配者としての立場を保つために威圧的な態度をとり続けるが、内心では恐怖と劣等感に苛まれている。
ギヤ太の人物像は、単なる悪役ではなく「権力に縛られた被害者」としての側面も描かれる。娘のラナタンに対しては溺愛する一方で、支配者としての威厳を保とうとする不器用な愛情が悲劇を生む。物語後半で、ナマズ入道に逆らい池のために立ち上がる姿は、彼自身の“贖罪”でもあった。
彼の改心は、タツノコ作品らしい“悪役にも人間味を残す”演出であり、単純な勧善懲悪に終わらない奥行きを物語に与えている。最終的に彼がデメタンと共闘する展開は、視聴者に強いカタルシスを与えた。
イボ吉とキャール ― 滑稽さの中にある人間味
ギヤ太の腰巾着であるイボ吉とキャールは、物語にユーモアと現実味を与えるキャラクターである。彼らは悪役でありながら、どこか憎めない存在として描かれる。イボ吉はドジでお調子者だが、根は臆病で、上司の命令に逆らえない小心者。キャールはずる賢く、他人の陰に隠れて生き延びるタイプである。
二人の存在は、社会の中で“権力に従うしかない小市民”の象徴でもある。彼らは時に卑怯な手を使いながらも、最終的には恐怖よりも友情を選び、池の解放に協力する姿を見せる。その変化が、物語のメッセージ――「誰でも変わることができる」――を裏づけている。
エレ吉とその家族 ― 仲間と犠牲の象徴
電気ウナギのエレ吉は、デメタンの心強い友人であり、物語後半で重要な役割を果たすキャラクターだ。彼は陽気で快活な性格だが、仲間思いで、どんな危険にも身を投げ出す勇気を持っている。 彼の父親と弟たちは、ナマズ入道の餌食となってしまい、デメタンが“池を変える決意”を固める直接のきっかけとなる。エレ吉の放つ電撃は、単なる攻撃手段ではなく、“怒りと正義の象徴”として機能している。最終決戦で彼がナマズ入道に電撃を放つシーンは、シリーズ屈指の名場面の一つだ。
ナマズ入道 ― 恐怖と支配の具現
池の底に潜む巨大な存在、ナマズ入道は本作の最終的な敵であり、物語の象徴的な存在でもある。彼は単なる怪物ではなく、「恐怖による支配」「無知を利用する権力」の化身として描かれる。池の住民たちは彼の姿を見ることすら許されず、存在そのものを“伝説”として恐れてきた。
その実態は、食欲と支配欲に取り憑かれた老獣。だが、彼が人々を支配できたのは、彼自身の力ではなく、住民たちの“恐れ”だった。デメタンたちがその恐怖を乗り越えた瞬間、ナマズ入道の権力は崩壊する。
彼は物語の終盤で海に逃げ、最終的には人間の漁師に捕らえられる。これは自然界の摂理と、人間社会の無情さを対比させた象徴的なエンディングである。
脇役たちとナレーションの存在
作品には、タニシのおばあさん、沢五郎、ザリなど、多くの個性的な脇役たちが登場する。彼らは池の“民衆”として描かれ、時にはデメタンを支え、時には恐怖に屈する。その群像劇的な構成が、『けろっこデメタン』を単なる冒険物語ではなく、社会全体の縮図へと昇華させている。
また、ナレーションを担当した北浜晴子の穏やかな語り口は、作品全体を包み込むような温かさを持ち、視聴者を物語の世界へと優しく導いていく。
キャラクターたちが残したもの
『けろっこデメタン』のキャラクターたちは、善悪や身分に関係なく、それぞれが“変化する力”を持っている。小さな池の中で、支配、恐怖、友情、愛、赦しといった人間的なドラマを繰り広げる彼らの姿は、半世紀近く経った今でも鮮やかに心に残る。 特にデメタンとラナタンという二人の子どもの純粋さは、どんな時代の視聴者にとっても希望の象徴であり続けている。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
オープニングテーマ「けろっこデメタン」 ― 明るさの中に宿る哀しみ
『けろっこデメタン』のオープニングテーマ「けろっこデメタン」は、作詞・丘灯至夫、作曲および編曲・越部信義、そして歌唱を堀江美都子が担当している。この楽曲は一聴すると軽快で親しみやすいメロディを持ちながら、その奥には静かな哀愁が流れている。 堀江美都子の透明感ある声は、作品全体に通じる“優しさの中の切なさ”を体現しており、冒頭の歌詞「けろけろけろけろけろっこデメタン」で始まる陽気なフレーズが、子どもたちの記憶に深く刻まれた。
歌詞はデメタンの心情を象徴している。弱くても前を向き、仲間を信じて歩み続ける――そんなメッセージが、当時の子どもたちに“明るく生きる勇気”を与えた。特にサビ部分での「ぼくは負けない どんなに悲しくても」というフレーズは、物語後半でのデメタンの成長を暗示しており、作品全体のテーマを簡潔にまとめている。
また、曲調はワルツのような柔らかさと行進曲的なリズムを併せ持ち、池の生き物たちが跳ねるような軽やかさと、どこか胸に残る憂いを同時に感じさせる構成になっている。
この曲は放送当時、子ども番組の主題歌としては異例の完成度を誇り、アニメファンや音楽愛好家からも高い評価を受けた。のちに堀江美都子のベスト盤アルバムにも収録され、昭和アニメ主題歌の代表的存在のひとつとして語り継がれている。
エンディングテーマ「まけるなデメタン」 ― 希望への祈り
エンディングテーマ「まけるなデメタン」もまた、丘灯至夫と越部信義の黄金コンビによる作品で、歌唱はオープニングと同じく堀江美都子が担当している。 オープニングが“出発と希望”を描くのに対し、エンディングでは“試練と克服”がテーマとなっており、デメタンの心の叫びが優しくも力強く歌われている。
曲の冒頭から漂う静けさは、物語の余韻をそのまま引き継いでおり、視聴者が1話を見終えた後の感情を柔らかく包み込むように響く。歌詞の中では“涙”“風”“虹”といった自然のモチーフが頻繁に登場し、それらがデメタンの心情を象徴している。
特にラストの「まけるな デメタン 泣かないで デメタン」というリフレインは、単なる応援歌ではなく、“弱さを受け入れながらも立ち上がる”という作品全体のメッセージを代弁している。
越部信義の編曲はシンプルでありながら情感に富み、ストリングスとフルートの音色が池の静けさや夜明けの空気を連想させる。堀江美都子の優しい歌声がその旋律に溶け合うことで、視聴者に「また明日も頑張ろう」と思わせる温かい余韻を残す。
音楽担当・越部信義の作風と劇伴の魅力
越部信義は、1970年代のアニメ音楽を支えた作曲家の一人であり、彼の音楽は単なるBGMにとどまらず、登場人物の感情や自然の情景を音で表現することに長けていた。 『けろっこデメタン』でも、水の流れを感じさせるピアノのアルペジオや、草原の風のように柔らかな木管楽器のフレーズなど、自然と共鳴する音作りが徹底されている。
戦いのシーンで流れる勇壮なブラス曲も、派手さよりも“祈り”や“願い”を感じさせる抑制的な構成となっており、物語全体のトーン――つまり“静かな勇気”を音楽で支えている。
また、劇伴の多くは短いモチーフを組み合わせて場面転換をスムーズに演出しており、映像と音が一体化した“音響的演出”の完成度も非常に高かった。
越部の音楽は、同時期の『みなしごハッチ』や『てんとう虫の歌』とも共通する部分がある。いずれも“子ども向け”という枠を超えた深い感情表現が特徴で、視聴者の年齢を問わず心に訴えかける。
挿入歌 ― デメタンの心情を映す小さな詩
『けろっこデメタン』には、放送回によって異なる挿入歌がいくつか使用されている。これらはシングルカットされていないものも多く、現存する資料では一部しか確認されていないが、内容は非常に印象的だ。
たとえば、「虹の向こうに夢がある」では、デメタンが困難の中で希望を見出そうとする姿が歌われる。この曲は後年、一部のファンの間で“幻の主題歌”と呼ばれるほど人気を集めた。
また、「ケロケロ笛のうた」は、物語中でも繰り返し登場する笛のモチーフを歌詞に組み込み、仲間との絆や平和への祈りを表現している。明るいメロディの中に、どこか懐かしさと切なさが入り混じる。
こうした挿入歌は、ストーリーの転換点や感情の山場で流れることが多く、視聴者の涙を誘う演出の一端を担っていた。タツノコプロは音楽演出に特に力を入れており、本作でもその伝統が継承されている。
堀江美都子という声と“昭和アニメ音楽の象徴”
主題歌を歌った堀江美都子は、当時すでに『キャンディ・キャンディ』や『花の子ルンルン』などで知られる国民的アニソン歌手の地位を確立していたが、『けろっこデメタン』での彼女の歌唱はその中でも特に“素朴さと深み”が融合した名演とされている。
堀江の声には“子どもの純粋さ”と“大人の包容力”が同居しており、デメタンとラナタンの心情を代弁するかのような温度を持っている。彼女自身もインタビューで「この歌は優しいけれど泣ける歌。歌いながら自然に涙が出た」と語っている。
彼女の存在があったからこそ、『けろっこデメタン』は単なる児童アニメを超え、感情の深いドラマへと昇華されたと言っても過言ではない。
LP・EP・CD化と音楽の再評価
放送当時、主題歌シングルはEP盤(ドーナツ盤)として日本コロムビアから発売され、子どもたちの間で人気を博した。ジャケットにはデメタンとラナタンが寄り添うイラストが描かれ、その可愛らしいデザインもコレクターズアイテムとして人気である。
1980年代には一時的にLP版の「タツノコプロ主題歌大全集」に収録され、90年代以降はCD化も進んだ。特に2000年代にリリースされた「タツノコアニメ主題歌ベスト」や「堀江美都子アニソン・ヒストリー」などでは、高音質リマスター版として再収録されている。
ファンの間では、当時のアナログ音源特有の温かみと、堀江の声の柔らかさを楽しむためにEP盤を求める人も多く、オークションでも比較的高値で取引されている。
主題歌が伝え続けるメッセージ
『けろっこデメタン』の音楽は、ただのBGMやテーマソングではなく、作品そのものの魂を伝える媒体である。オープニングの希望、エンディングの祈り、そして挿入歌の哀しみ――それらが一体となって、視聴者の感情を揺さぶる。
半世紀が経った今でも、子どものころにこの歌を聴いた世代は、そのメロディを耳にすると一瞬であの水辺の風景を思い出す。音楽が“記憶の扉”を開く力を持つことを、この作品は見事に証明している。
そして、どんなに時代が変わっても「まけるな デメタン」という言葉は、人々の心の奥に優しく響き続けている。
[anime-4]
■ 声優について
主人公・デメタン役 ― 久松夕子の繊細な感情表現
デメタンの声を担当したのは久松夕子。彼女の柔らかく澄んだ声は、少年のあどけなさと心の強さを同時に伝える力を持っていた。当時のアニメでは男性子役が少年役を演じることも多かったが、本作では“女性声優による少年演技”の典型として高く評価されている。
久松の演技の魅力は、感情の起伏を極めて繊細にコントロールしている点にある。喜びの場面では少し高めのトーンで跳ねるように話し、悲しみや不安の場面では息を詰めるように低く抑える。その自然な変化が、デメタンの「普通の子どもらしさ」を見事に体現している。
特に注目されるのが、後半のエピソードで見せる“怒り”と“決意”の演技だ。ナマズ入道の真実を知ったデメタンが涙を流しながら叫ぶ場面では、久松の声に込められた震えが視聴者の心を強く揺さぶる。あのシーンは、彼女自身の感情が乗った瞬間とも言われ、当時の録音スタッフの間でも“神回”として語り継がれている。
彼女はこの役で、アニメファンのみならず、声優という職業に対する認識を広げた功績を残した。
ラナタン役 ― 岡本茉莉が奏でた少女の成長と慈愛
ラナタンを演じた岡本茉莉は、清楚で透明感のある声質が特徴で、物語のヒロインとしての存在感を確立した。彼女の演技は、単なる可憐な少女にとどまらず、次第に“意志を持つ女性”へと成長する過程を丁寧に描き出している。
初期のラナタンはおっとりして優しい少女として登場するが、物語が進むにつれ、父・ギヤ太の暴挙や社会の理不尽さに対して疑問を持ち、やがてそれに立ち向かう。岡本の演技は、ラナタンが弱さから強さへと変化していく“声の軌跡”そのものだ。
特に印象的なのは、デメタンを庇って父と対立するシーン。涙声でありながら毅然とした口調を保つその芝居は、多くのファンから「声だけで気高さを感じさせた」と絶賛された。
また、岡本茉莉は感情表現の幅広さに定評があり、笑いながら泣く、泣きながら微笑むといった微妙な表情の変化を声だけで伝えることに長けていた。その繊細な演技がラナタンというキャラクターに“人間らしさ”を与えたと言える。
ギヤ太役 ― 富田耕生の圧倒的存在感と深み
支配者ギヤ太を演じたのは、名優・富田耕生。彼の重厚で力強い声は、ギヤ太の威厳と恐怖を見事に表現している。富田の声は単なる“悪役ボイス”ではなく、権力者の中に潜む臆病さや苦悩まで感じさせるもので、キャラクターの多面性を浮き彫りにした。
特に印象的なのは、後半でギヤ太がナマズ入道の支配から逃れようと葛藤する場面だ。富田の低く震える声からは、恐怖と後悔、そして父親としての愛情が滲み出ており、ギヤ太というキャラクターを単なる“敵”から“悲劇の父”へと昇華させている。
また、ラナタンへの溺愛ぶりを見せるときの演技は一転してコミカルであり、彼の演技力の振り幅の広さを感じさせる。厳しさと滑稽さを行き来するその声の表現が、作品全体のドラマ性を深めた。
富田耕生は当時、タツノコ作品をはじめ多くのアニメで活躍しており、『タイムボカン』シリーズなどでも知られていた。彼の演技は作品の骨格を支えるものであり、“声の重み”という点でこの作品の精神的な支柱になっている。
雨太郎役 ― 北村弘一の誠実で温かい父親像
デメタンの父・雨太郎を演じた北村弘一は、穏やかで包み込むような声を持つベテラン声優である。彼の声は、厳しさの中にも優しさがあり、貧しくても誇り高く生きる父親像を見事に表現していた。
北村の演技の真骨頂は、静かなセリフの中に“信念”を込める点にある。ギヤ太に屈せず堂々と立ち向かうときのセリフ、「正しいことをやるのが、いちばんの力なんだ」という台詞には、父親としての強さと人間としての真摯さが宿っている。
また、デメタンを励ます場面では、感情を爆発させることなく、穏やかに語りかける。その抑制された演技が、かえって強い感動を生むのだ。視聴者の多くが「この父親がいたからこそ、デメタンは立派に成長できた」と語るほど、北村の演技は作品全体の信頼感を支えていた。
雨子役 ― 荘司美代子の母性あふれる包容力
デメタンの母・雨子を演じた荘司美代子は、落ち着きと温もりを兼ね備えた声で知られている。彼女の声が放つ柔らかさは、まるで陽だまりのように温かく、家庭の安心感を象徴していた。
荘司の演技は控えめでありながら非常に印象的で、特に病に伏した際のかすれ声や、デメタンを見守る優しい語り口には、母としての無償の愛が溢れている。
彼女は派手な感情表現を避け、息づかいで感情を伝えるタイプの演技を得意としており、そこにリアリティが宿っている。雨子の存在は、作品の中で“心の支え”として描かれ、視聴者の多くが彼女の優しさに涙した。
ナマズ入道役 ― 水島晋の威厳と不気味さ
巨大な支配者・ナマズ入道の声を担当したのは水島晋。その低く響く重厚な声は、まるで池の底から聞こえてくるような不気味さを持ち、作品に独特の恐怖と神秘性を与えた。
彼の声はただの悪役というより、“自然の摂理そのもの”のように感じられる。怒鳴り声ではなく、静かに語りかけるトーンで威圧する演技が特徴で、まるで催眠のように聞く者の心を縛る。
特に「お前たちは、わしのために生きておるのだ」という台詞は、彼の声の響きによって一層強烈な印象を残す。視聴者にとってナマズ入道は“声で恐怖を感じる存在”であり、音響面から見てもこの作品の完成度を支える重要な要素となっている。
イボ吉・キャール・沢五郎ほか脇役陣の演技の妙
イボ吉を演じた大竹宏、キャールを演じた八代駿など、個性派声優陣の掛け合いも作品の魅力の一つだ。特にこの二人のやり取りは、シリアスな物語の中に軽妙なテンポを与え、子どもたちが安心して見られるバランスを保っていた。 大竹宏の少し間の抜けたトーンと、八代駿の鼻にかかった声のコンビネーションは、まるで漫才のようでありながら、時折見せる“弱さの裏返し”が人間味を感じさせる。
また、ナレーションを担当した北浜晴子の存在も忘れてはならない。彼女の穏やかで品のある語りは、作品のトーンを優しく包み込み、物語全体を一本の詩のようにまとめ上げている。
声優陣が作り上げた“生きている池”
『けろっこデメタン』の声優たちは、単に台詞を読むだけでなく、“生き物としてのリアリティ”を声で表現している。登場キャラクターがカエルや魚であるにもかかわらず、どの声も自然で、観る者はいつの間にか「彼らが実在している」と感じてしまう。
この“生命感”こそが本作の最大の魅力であり、演技と音響が一体となったタツノコプロの職人技の賜物である。今見ても古びない温度と誠実さが、この声優陣の演技に息づいている。
[anime-5]
■ 視聴者の感想
放送当時の子どもたちに与えた印象 ― “泣けるアニメ”の衝撃
1973年の初回放送当時、『けろっこデメタン』をリアルタイムで見た子どもたちの多くは、そのストーリー展開に強い衝撃を受けたと語っている。 同時期に放送されていたアニメの多くが明るく楽しい冒険譚やギャグ要素を中心にしていたのに対し、『けろっこデメタン』は“泣けるアニメ”として際立っていたのだ。
特に序盤から、デメタンの兄弟がイモリの襲撃で全滅してしまうというショッキングな描写は、当時の子ども番組としては異例の重さだった。学校でのいじめや階級差といった現実的な問題を暗喩するエピソードも多く、「子ども心に怖かった」「でも目をそらせなかった」という感想が多く残されている。
一方で、デメタンとラナタンの純粋な友情や恋心、ケロケロ笛の優しい音色に癒されたという声も多く、涙と希望が入り混じった“感情のゆりかご”的作品として記憶されている。
当時のファンレターやアニメ雑誌の投稿欄には「デメタンのようにやさしくなりたい」「ラナタンのように友達を信じたい」といった言葉が並び、視聴者が物語に深く共感していたことがわかる。
大人たちの目に映った“社会寓話”としての側面
『けろっこデメタン』は、実は放送当時から大人の視聴者にも静かな人気を得ていた。家族で夕食後に観る時間帯であったため、子どもだけでなく親世代も自然と番組に触れていたのである。 彼らはこの作品に、単なる動物アニメ以上の“社会寓話”を見出していた。
ギヤ太による支配構造、ナマズ入道の恐怖政治、そして貧しいながらも正しく生きようとする庶民――それらは当時の高度経済成長期の日本社会に重ねて語られることが多かった。
「小さな池の中にも、現実の社会と同じ矛盾がある」「子どもにこそ、こうした正義と勇気の話を見せるべきだ」と評した新聞コラムも残っており、アニメが教育的価値を持つメディアとして注目され始めた時期でもあった。
また、家庭内で「デメタンのように我慢強くなろう」「ギヤ太のように威張っちゃいけない」といった会話が交わされたという証言もあり、作品が“親子の共通言語”となっていたことがうかがえる。
再放送世代の感想 ― ノスタルジーと再発見
1970年代後半から1980年代にかけて、『けろっこデメタン』は地方局やCSチャンネルで何度も再放送された。その再放送を見て育った世代の感想は、リアルタイム世代とは少し異なる。
彼らは、当時の映像技術や独特の演出に“昭和の香り”を感じつつも、物語のテーマの深さに驚いたという声が多い。「子どもの頃はただ可愛いと思っていたけれど、大人になって見直すととても重い内容だった」「あの頃わからなかった親の苦労や社会の仕組みが見える」といった再評価が多く寄せられた。
特に印象的なのが、インターネット掲示板やSNSなどで語られる「昭和アニメのトラウマ名作」としての側面である。『みなしごハッチ』や『フランダースの犬』などと並び、「悲しいけど優しい」「痛みを教えてくれた」と語られることが多い。
視聴者の多くが、成長してから再びデメタンの姿を思い出し、“自分もあの頃より少し強くなった”と感じている点に、この作品の普遍性がある。
音楽への共感と記憶の力
視聴者の感想の中で特に多いのが、主題歌・エンディング曲に対する愛着である。 「オープニングを聴くと自然に涙が出る」「“まけるなデメタン”は今でも自分の応援歌」という言葉が、世代を超えて寄せられている。
堀江美都子の澄んだ歌声は、子どもたちにとって“希望の音”として記憶に残り、50年近く経った今も「口ずさむと胸が熱くなる」という声が絶えない。音楽が単なる演出以上の役割を果たしていたことを、ファンの証言が裏づけている。
また、笛の音や挿入曲が流れるたびに感じた“切なさ”や“あたたかさ”は、作品の情緒と強く結びついており、感想の多くが「音が心を動かした」と語っているのも特徴的だ。
悲しみの中に光を見る ― 視聴者の心を掴んだ哲学性
視聴者が『けろっこデメタン』を愛した理由の一つに、“悲しみの描き方の誠実さ”がある。 多くのアニメが単純な勧善懲悪で終わる中、この作品では悪役にも動機があり、善人にも迷いがある。ギヤ太もナマズ入道も完全な悪ではなく、恐怖や無知から支配の連鎖に囚われている。 視聴者はその複雑な構造に“現実の苦さ”を見つけ、だからこそ最後の希望に深く共鳴した。
SNSやレビューサイトでは、「デメタンの優しさは時代を超えて心に残る」「争いをやめる勇気を子どもながらに学んだ」「何度見ても泣ける」といった声が今も多い。
また、「大人になってから見ると、あれは“社会を変える物語”だった」と評する意見も増えており、単なるノスタルジーではなく“思想的価値”として再評価されている。
現代のファンに受け継がれる“癒やしの名作”
21世紀に入り、DVDや配信サービスで気軽に視聴できるようになったことで、若い世代にも『けろっこデメタン』は静かな人気を得ている。 SNS上では「癒やされる昭和アニメ」「キャラがみんな優しい」「涙が出るほど美しい」といった感想が相次ぎ、特に環境問題や社会的格差が再び注目される現代において、そのメッセージが新たな意味を持ち始めている。
アニメ評論家の間でも、「環境と共生」「支配と自由」「命の尊厳」といったテーマを早くから描いた先駆的作品として評価されるようになった。
若いファンの中には、親世代や祖父母と一緒にDVDを観て感想を語り合うケースも多く、世代を超えた“共有の物語”としての役割を果たしている。
感想が示す普遍性 ― “やさしさ”という力
最終的に、視聴者の感想の多くは「やさしさ」に集約される。 デメタンの勇気も、ラナタンの純粋さも、雨太郎と雨子の愛情も、すべて“やさしさ”に根ざしている。それは決して弱さではなく、困難を乗り越えるための力であり、視聴者たちはそれを心に刻んでいる。
ある往年のファンはこう語っている――
「『けろっこデメタン』は、悲しいけれど、見終わったあとに心がきれいになるアニメだった。」
この一言こそ、多くの視聴者が半世紀経った今でもこの作品を愛し続ける理由であり、感想のすべてを要約していると言える。
[anime-6]
■ 好きな場面
第1話「虹のお池にデメタンが来た」 ― 世界の小ささと広さを知る出発点
作品の冒頭で描かれる、デメタンが「虹のお池」にたどり着くシーンは、多くの視聴者にとって忘れがたい名場面だ。 透明な水面の下に広がる色とりどりの生き物たち、風に揺れる水草、静かに流れるピアノの旋律――そのすべてが新しい世界の始まりを象徴している。
この場面の魅力は、“世界を見上げる視点”にある。デメタンの目には、虹のお池が広大で、美しく、そしてどこか恐ろしい。彼の心の中に芽生える「ここで生きたい」「でも怖い」という相反する感情は、誰もが経験する“未知への一歩”そのものだ。
演出上も巧みで、水面を透かして差し込む光の描写や、泡の動きまで丁寧に描き込まれており、まるで一枚の絵画のような美しさを放つ。視聴者はこのシーンを通じて、物語の舞台である池が“単なる自然の一部ではなく、社会の縮図”であることを直感的に理解する。
さらに、笛を吹くデメタンの姿に重なるオープニングテーマ「けろっこデメタン」が、希望と不安を優しく包み込む。この第一話の出会いの場面があるからこそ、後の数々の試練や別れの場面が一層心に響くのだ。
ラナタンとの初めての出会い ― 心の橋がかかる瞬間
デメタンとラナタンが初めて出会う場面も、視聴者の記憶に強く残るシーンの一つである。 高貴な身分に生まれたラナタンが、池の隅でいじめられていたデメタンにそっと手を差し伸べる――この一瞬に、作品全体のテーマが凝縮されている。
二人が交わす最初の会話は短く、ぎこちない。しかし、互いに立場の違いを意識しながらも、純粋に相手を思いやる眼差しがそこにはあった。
演出では、水面に映る二人の影が寄り添うように揺れる。セリフ以上に“距離が縮まる”瞬間を映像で語る演出が秀逸だ。
そして笛の音が二人の間に流れたとき、視聴者もまた“隔たりを越える希望”を感じる。
このシーンは、愛や友情というよりも、“理解の始まり”を描いた場面として特筆される。身分差や支配の構造を超えて、人と人が出会うことの尊さを、わずかなやり取りで表現している点で、昭和アニメ史の中でも屈指の名場面と言える。
雨太郎の教え ― 「正しいことをやるのが一番の力」
中盤で登場する父・雨太郎の言葉、「正しいことをやるのが一番の力なんだ」は、ファンの間で最も心に残る名セリフとして知られている。 このシーンは、ギヤ太の兵たちに理不尽に追われながらも、デメタンが父の教えを思い出す場面に挿入される。
演出上の特徴は、音の“静寂”だ。BGMがほとんど排され、デメタンの息づかいと心の声だけが響く。そこで流れる父の声が、まるで心の中の羅針盤のように聞こえる。
雨太郎は決して力で戦うことを教えなかった。彼が息子に残したのは「誠実に生きることこそが最大の武器」という、生涯変わらぬ信念だった。
この教えが、最終回に至るまでデメタンを導く精神の支柱となる。
視聴者の多くは、このシーンを「人生で初めて“正しさ”という言葉の重みを感じた瞬間」と語っており、子ども番組でありながら道徳的価値観を自然に伝えた秀逸な脚本構成だと再評価されている。
ラナタンの反抗 ― 愛と勇気の宣言
物語後半、ラナタンが父・ギヤ太に逆らい、庶民を守るために立ち上がる場面は、彼女の成長を象徴する名シーンだ。 「お父さま、もうこれ以上、みんなを苦しめないで!」というセリフにこめられた岡本茉莉の演技は、怒りと悲しみ、そして愛情が複雑に絡み合い、聞く者の胸を打つ。
この場面は“反抗”であると同時に、“赦し”の始まりでもある。ラナタンは父を憎んで立ち上がったのではなく、“正しいことを知ってしまった娘”として、父の苦しみを理解したうえで声を上げている。
映像的にも象徴的で、ラナタンの背後に差す光が水面を反射して揺れ、まるで新しい時代の夜明けを暗示するかのように演出されている。
このエピソードは視聴者に「優しさは勇気の形をしている」という印象を強く残した。単に可憐な少女ではなく、“意思あるヒロイン像”を早くから確立した名場面として、アニメ史の中でも語り継がれている。
ナマズ入道との最終決戦 ― 恐怖を越えて
最終話で描かれるナマズ入道との対決は、物語全体のクライマックスにして、視聴者の心に深く刻まれた場面である。 池を震わせるような轟音、濁流にのまれる仲間たち、そして恐怖に立ちすくむデメタン――そのすべてが“絶望の風景”として描かれる。
だが、デメタンは笛を手にし、静かに吹き始める。音楽は戦いのBGMではなく、祈りのような旋律。敵を倒すのではなく、“恐怖を鎮める”ための音色だ。
笛の音に呼応してラナタンや仲間たちが立ち上がり、ナマズ入道の支配が解けていく。巨大な影が崩れ、光が水面を照らす――この演出は、まるで“心の闇を祓う儀式”のようだ。
特筆すべきは、敵を討ち滅ぼすのではなく、“恐れを手放すことで勝利する”という構成である点だ。これは当時の児童アニメとして極めて珍しく、今なお哲学的深さを持つクライマックスとして高く評価されている。
エンディングの別れ ― 涙と再生の瞬間
最終話のラストシーン、デメタンとラナタンが虹の橋の下で静かに笛を吹く場面は、ファンの間で“アニメ史上屈指の名エンディング”と呼ばれている。 戦いが終わったあと、池は穏やかさを取り戻すが、彼らの心には消えない痛みが残る。 それでも、デメタンは涙をこらえて言う――「僕たちはきっと、また会えるよ。」
堀江美都子の歌う「まけるなデメタン」が重なる中、二人の姿が夕陽に照らされながら小さくなっていく。BGMと映像の融合、静寂と余韻のバランスが完璧で、多くの視聴者がこのシーンで涙を流した。
“悲しみの中に希望を見いだす”という本作のテーマが、このワンカットに凝縮されている。
ファンが選ぶ“忘れられない瞬間”
ファン投票やSNS上で語られる“好きな場面ランキング”では、上記のシーン以外にも「デメタンが仲間のために自分を犠牲にする場面」「エレ吉の最期」「池に虹がかかるエピローグ」などが頻繁に挙げられている。 それらに共通するのは、“悲しいけれど温かい”という感情の二重構造だ。視聴者は涙を流しながらも、心のどこかで“救われた”と感じる。それこそが『けろっこデメタン』が長く愛される理由であり、好きな場面がいつまでも語り継がれる所以でもある。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
デメタン ― 優しさが力に変わる象徴的主人公
ファンの間で最も多く“好きなキャラクター”として挙げられるのは、やはり主人公・デメタンである。 その理由は単純なヒーロー性ではなく、彼の“優しさの強さ”にある。彼は腕力も知恵も特別ではない。しかし、誰かの痛みを自分のことのように感じ、決して他人を見捨てない。そんな純粋な共感力が、最終的に大きな力へと変わっていくのだ。
子どものころの視聴者は、デメタンの泣き顔や小さな体に共感し、「自分もあんなふうに頑張りたい」と感じた。大人になって再び見ると、彼の行動が単なる善意ではなく、“信念”に裏づけられた勇気であったことに気づかされる。
つまり、デメタンというキャラクターは“成長の物語”そのものなのだ。
彼の魅力を象徴するのが“ケロケロ笛”である。笛を吹く姿は、一見すると弱々しい。しかしその音色は、仲間を励まし、争いを鎮める。彼が力ではなく音楽で世界を変えていく姿に、多くのファンが胸を打たれた。
SNSなどでも「デメタンのような優しさを持ちたい」「弱くてもいい、でも誠実でありたい」という感想が数多く見られ、50年経った今でも“理想の少年像”として語り継がれている。
ラナタン ― 美しさと芯の強さを兼ね備えた理想のヒロイン
ラナタンは、可憐で上品な外見だけでなく、心の美しさと意志の強さで圧倒的な人気を誇るヒロインである。 彼女の魅力は、デメタンを支える“天使的存在”でありながら、自らも社会の不条理と戦う勇気を持つ点にある。 序盤では父ギヤ太の庇護のもとで穏やかに暮らすが、貧しい者たちへの差別を目の当たりにして心を痛め、次第に支配の構造に疑問を抱く。ラナタンの内面の変化は、作品全体のテーマを象徴している。
また、ラナタンの声を演じた岡本茉莉の透明感ある声が、彼女の存在をより神秘的に引き立てている。
特に印象的なのは、ラナタンがデメタンを励ますときのセリフ――「あなたは小さいけれど、とても強い心を持っているのね」。この一言に、彼女の優しさと確信が詰まっている。
ラナタンは“憧れの存在”でありながら、“寄り添う友”でもある。その二面性が多くの視聴者を惹きつけた。
ファンの中には、「ラナタンの生き方に自分を重ねた」「彼女の微笑みに救われた」と語る人も多く、SNS上では今も“理想の昭和ヒロイン”として語り継がれている。
雨太郎 ― 誠実さの象徴であり父としての理想像
デメタンの父・雨太郎は、派手な登場ではないが、根強い人気を誇るキャラクターだ。 彼の魅力は、“強さとは何か”を静かに教える生き方にある。正直に働き、決して嘘をつかず、他者を傷つけない。その姿勢は、現代にも通じる普遍的な父親像として多くのファンの心に残っている。
彼が息子に語る「正しいことをやるのが一番の力なんだ」という言葉は、作品を超えて名言として引用されることが多い。
視聴者の中には、「自分の父親が雨太郎のようであってほしかった」「あのセリフで人生を見直した」という声もあるほどだ。
彼は時に厳しく、時に温かく、家族を支える土台のような存在であり、その静かな尊厳が物語を根底から支えている。
エレ吉 ― 明るさと友情の象徴
電気ウナギのエレ吉は、コミカルで陽気な性格の持ち主でありながら、仲間思いで勇敢なキャラクターとして多くのファンから愛されている。 彼の人気の理由は、どんな困難な状況でもユーモアを忘れず、仲間を励ますその姿勢だ。作品が全体的にシリアスな雰囲気を持つ中で、エレ吉の存在が絶妙な“光”となっている。
特に彼が命を懸けてデメタンを救う場面は、ファンの間で“涙なしには見られない名場面”として語り継がれている。
電撃を放ちながら「デメタン、行け! お前は生きて希望を伝えるんだ!」と叫ぶその声には、笑いながら生きた男の誇りが詰まっていた。
エレ吉の明るさは単なるキャラ付けではなく、“悲しみを乗り越える知恵”の象徴でもある。
ファンの中には「エレ吉みたいな友達が欲しい」「悲しいのに笑顔でいられる強さを教わった」と語る人も多く、彼の存在がいかに作品全体に“温度”を与えていたかが分かる。
ラナタンの父・ギヤ太 ― 悪役でありながら人間味ある存在
ギヤ太は当初、視聴者にとって明確な“敵”だった。 傲慢で権力を振りかざし、弱者を虐げる支配者。しかし物語が進むにつれ、彼が単なる悪人ではなく、“恐怖に支配された一人の父親”であることが明かされていく。
ファンの中には「最後に涙したのはギヤ太だった」という意見も多い。
彼が娘ラナタンへの愛情を失えず、ナマズ入道の命令に逆らって倒れる姿は、権力の呪縛から解放された“人間の再生”を象徴している。
声を演じた富田耕生の迫力ある演技が、ギヤ太の苦悩を深く掘り下げ、悪役でありながらも観る者の同情を誘った。
その結果、ギヤ太は“憎まれながら愛される悪役”として、昭和アニメ史の中でも特異な存在となった。彼を嫌いになれないという視聴者の声は今でも多い。
イボ吉とキャール ― コミカルな救いと人間味
ギヤ太の腰巾着であるイボ吉とキャールは、一見すると単なる滑稽な悪役コンビだが、ファンの間では“憎めない愛すべきキャラ”として人気が高い。 特に彼らが失敗して怒られる場面や、恐怖に震えながらもラナタンを助ける姿には、人間味があふれている。
視聴者の中には「イボ吉たちは、臆病だけど最後に正義を選んだ」「彼らの成長も地味に泣ける」と語る声もあり、脇役ながら物語の“救い”を担っていた。
彼らの存在があることで、作品全体の空気が重くなりすぎず、どこか温かい笑いが生まれている。
ファンが愛する“ケロケロ笛”という無言のキャラクター
意外に多くのファンが“好きなキャラクター”として挙げるのが、デメタンの持つ“ケロケロ笛”である。 この笛は単なる道具ではなく、デメタンの心そのものであり、物語を象徴するもう一人の“無言の登場人物”といえる。
彼が笛を吹くたびに流れる旋律は、希望、祈り、悲しみ、そして再生を表しており、ファンの中には「笛の音を聞くと泣いてしまう」「あの音があれば何でも頑張れそう」と語る人も多い。
アニメの中で“音”がここまでキャラクターとして機能する例は少なく、タツノコプロの演出力の高さを示している。
視聴者にとっての“自分を映すキャラクター”
『けろっこデメタン』の魅力は、どのキャラクターも単なる善悪の枠に収まらないことにある。 弱虫な者も勇気を出し、権力者も悔い改め、庶民も立ち上がる。だからこそ、視聴者は自分の人生のどこかを彼らに重ねる。
「子どもの頃はデメタンに共感したけど、大人になったら雨太郎やギヤ太の気持ちが分かるようになった」という感想が象徴的だ。
この作品のキャラクターたちは、時を経ても変わらない“人間の心の写し鏡”として、今も多くの人々に愛され続けている。
[anime-8]
■ 関連商品のまとめ
映像関連 ― VHSからBlu-rayまで、時代とともに形を変える名作
『けろっこデメタン』の映像ソフト展開は、1980年代後半のアニメ再評価ブームから始まった。 当時、テレビ放送を録画する手段が一般家庭に普及し始めたとはいえ、1970年代初期の作品は録画保存がほぼ不可能だった。そのため、公式VHSの登場はファンにとって“奇跡の再会”であった。
VHS版は一部のアニメ専門ショップや通信販売で限定的にリリースされ、全39話のうち代表的なエピソードを抜粋して収録。特に「虹のお池の出会い」「ナマズ入道との決戦」など、感動的な話を中心に構成されていた。
パッケージには当時のセル画をベースにした新イラストが使用され、柔らかな水彩タッチのデザインがファンの心を掴んだ。
1990年代にはLD(レーザーディスク)版が登場し、アニメコレクターの間で高値で取引されるようになる。LDボックスは豪華仕様で、解説ブックレットや絵コンテ資料、堀江美都子インタビューなどを収録。特に第1巻のジャケットに描かれた「笛を吹くデメタンとラナタン」は名デザインとして有名だ。
2000年代に入り、ついに全話収録のDVD-BOXが発売された。画質はデジタルリマスターされ、ノイズ除去と色彩補正によって当時の放送よりもクリアな映像が実現。ブックレットにはタツノコプロの当時の設定資料やスタッフ座談会が掲載され、昭和アニメ研究家にとって貴重な資料となっている。
2020年代にはBlu-ray化の動きも見られ、より高精細なマスターが一部のイベント限定版として登場。デジタル配信(Amazon Prime、U-NEXTなど)でも全話視聴が可能となり、半世紀を経ても“生きた名作”として新たな層に受け入れられている。
書籍関連 ― 絵本、アニメコミック、資料集としての復刻
放送当時、児童向け書籍として最初に登場したのは「けろっこデメタン 絵ばなしシリーズ」である。これは小学館やポプラ社の子ども向けアニメ絵本レーベルから発売されたもので、アニメのエピソードを簡略化し、美しいイラストとナレーション調の文章で構成された。 特に「デメタンとラナタンの虹」「なまず入道のまほう」は人気が高く、1970年代の子どもたちにとって“最初に出会う悲しくて優しい絵本”の一つとして記憶されている。
また、1980年代にはアニメ再評価の流れに合わせてフィルムコミック版(アニメのフィルムをコマ割りして再構成した書籍)が登場。セリフの一部が補完され、テレビ放送では見逃していた細かな表情や背景美術がじっくり楽しめる構成になっていた。
近年では、タツノコプロ公式監修の資料集『タツノコアーカイブス』シリーズにおいて『けろっこデメタン』が特集され、キャラクターデザイン原画・未公開設定スケッチ・色指定表などが初めて一般公開された。
ファンの中には、自分で絵本やスクラップブックを作る“自主再現派”も多く、ネット上には当時の雑誌付録や放送宣伝ポスターを復刻スキャンして共有するコミュニティも存在する。
“読むデメタン”の楽しみは、映像とは異なる形で今も受け継がれている。
音楽関連 ― 心に残る歌声と復刻の軌跡
『けろっこデメタン』を語る上で欠かせないのが音楽関連商品である。 オープニングテーマ「けろっこデメタン」とエンディング「まけるなデメタン」は、どちらも堀江美都子が歌い、作曲は越部信義。どちらの楽曲も“昭和アニメの抒情歌”として高い評価を受けている。
放送当時はドーナツ盤(EPレコード)として日本コロムビアから発売。アニメファンの間で人気を博し、堀江美都子が歌った中でも特に“泣ける主題歌”として語られている。
1990年代には『タツノコプロ主題歌全集』CDに収録され、2000年代にはリマスター版がアニメソングのコンピレーションアルバムに再収録された。
さらに、2020年代にはデジタル配信化が進み、Spotify・Apple Musicなどのプラットフォームでいつでも聴けるようになっている。アナログ派ファンのために限定LP盤も復刻され、ジャケットには1973年当時のセル画風デザインが再現された。
堀江美都子本人もライブでしばしば本曲を披露し、「今でも歌うと胸が熱くなる」と語っている。楽曲単体でも独立した価値を持つ名作主題歌である。
ホビー・おもちゃ ― 昭和レトロの宝物たち
当時のアニメ人気を支えたのは、子どもたちの手元にあったキャラクター玩具である。 『けろっこデメタン』も例外ではなく、1973年の放送時にバンダイ・タカトクなどから多様なグッズが発売された。
最も代表的なのが、デメタンとラナタンのソフビ人形セット。小型ながら精巧な塗装で、手足が動く仕様。現在では“昭和レトロ・ソフビコレクター”の間で高値で取引されている。
また、ゼンマイ仕掛けで泳ぐデメタンの“水中おもちゃ”や、ケロケロ笛を模した音が出る“デメタンの笛笛(ふえふえ)”も子どもたちに大人気だった。
文房具グッズでは、下敷き・ノート・鉛筆・定規など、学校生活に密着した商品が多く、特にラナタンのイラスト入りシリーズは女子児童に人気が高かった。
これらは“かわいいだけではなく癒される”と評判で、当時のキャラクターデザインがいかに普遍的だったかを物語っている。
現在では復刻グッズも登場しており、タツノコプロ公式ストアや昭和アニメ専門イベントで、復刻版ポスター・ピンズ・トートバッグなどが販売されている。ファンの間では「親子二代でデメタンを楽しめる時代になった」と喜びの声も上がっている。
食品・雑貨・日用品 ― 日常に溶け込むキャラクター
『けろっこデメタン』のキャラクター商品は、当時の駄菓子屋文化とも深く結びついていた。 “デメタンガム”“ラナタンクッキー”“けろっこラムネ”などの食玩商品が登場し、チューインガムには小さなシールが封入されていた。これらのシールを集めてアルバムに貼ることが、当時の子どもたちの定番の遊びだった。
また、プラカップ・お弁当箱・ティッシュケース・歯ブラシなどの生活雑貨も多数展開。ラナタンが描かれたピンク色のコップや、デメタンの笛をモチーフにしたペン立てなどは、今でもオークションで人気が高い。
昭和期の家庭用品に見られる“キャラクターを日常に取り入れる文化”を象徴するアイテム群と言える。
現代の復刻とコレクター市場
近年では、昭和アニメブームの再来とともに、『けろっこデメタン』グッズの再販・復刻が相次いでいる。 2023年にはタツノコプロ60周年記念として“デメタン&ラナタン アニバーサリーアクリルスタンド”が限定生産され、即日完売した。さらに、ファンアートを基にしたポストカードブックや、懐かしのエンディング映像をデザインしたTシャツもリリースされている。
中古市場でも人気が高く、オリジナルの1970年代ソフビやポスターは数万円単位で取引されることもある。とくに“初版VHSテープ”や“LDボックス”はコレクター垂涎のアイテムであり、保存状態が良いものはプレミア価格となっている。
こうした現象は、単なる懐古趣味にとどまらず、昭和アニメが“文化資産”として再評価されている証拠でもある。『けろっこデメタン』はその中でも、心の豊かさや優しさを象徴する存在として、令和の時代にも息づいている。
関連商品の魅力 ― 思い出を形にした温かさ
『けろっこデメタン』関連グッズの本質的な魅力は、“手に取ると心がやさしくなる”という点にある。 キャラクターの柔らかなデザイン、音楽のノスタルジー、そしてストーリーの普遍性が、グッズひとつひとつに宿っている。 ファンにとってそれは単なるコレクションではなく、“心の灯り”をもう一度手に入れる体験なのだ。
[anime-9]
■ オークション・フリマなどの中古市場
映像関連 ― 初期VHSとLDが高値安定、DVD-BOXはプレミア化
『けろっこデメタン』の中古市場において最も高値で取引されているジャンルは、やはり映像関連商品である。 1970年代当時は録画機器が普及していなかったため、後年に発売されたVHS・LD・DVDがコレクターズアイテムとして高い価値を持つ。
VHS版は1980年代末から1990年代初頭にかけて日本コロムビアや東映ビデオの系列で限定リリースされたもので、全巻セットは極めて入手困難。
1本あたりの落札価格は通常2,000~4,000円だが、未開封品や帯付き・ジャケット良好な状態のものは5,000円を超えるケースもある。
特に「第1巻(虹のお池の出会い編)」と「最終巻(ナマズ入道決戦編)」は人気が高く、単巻でもコレクター需要が集中している。
LD(レーザーディスク)版はさらに希少で、アニメコレクターの間では“タツノコLD三聖典”の一つに数えられるほど。
初回限定BOXには堀江美都子の特別インタビューやセル画ポストカードが付属しており、状態が良ければ1セット15,000~25,000円で取引されることもある。
近年ではLDプレイヤー自体の減少により視聴目的での需要は減ったが、アートワークやパッケージを目的に購入するファンが増加している。
DVD-BOXは2000年代初頭に発売されたリマスター版がプレミア化しており、中古市場では定価の2倍以上(15,000~20,000円前後)で取引されている。
ノンクレジットOP/ED、設定資料ブックレット付きの限定版は特に人気が高く、“昭和アニメ黄金期”を代表する収集対象として根強い需要を誇る。
書籍関連 ― 絵本・資料集・雑誌特集が人気の三本柱
書籍関連の中古流通では、1970年代当時の「アニメ絵ばなし」シリーズや「テレビえほん版」が特に高値で推移している。 表紙の色あせや破損があっても希少性が高く、状態次第では3,000円から8,000円近くまで値を上げる。
また、1980年代後半に刊行された「フィルムコミック版」は一時期再版されたが、初版帯付きは今でも1冊2,000~3,000円台を維持。
キャラクター紹介付きのムックや児童学習雑誌の付録ページも人気で、昭和レトロブームの中で「当時の紙質の風合い」に価値を見出すコレクターも多い。
特に注目されているのが、タツノコプロ公式資料集『タツノコ・アーカイブス』シリーズに掲載されたデメタン特集号。
すでに絶版状態であり、ヤフオクなどでは1冊6,000円以上で取引されることが多い。
復刻を望む声も多く、同人誌的に再編集した“自作設定資料集”を販売・交換するファンコミュニティも存在する。
音楽関連 ― EPレコードから復刻CDまで、音の温もりを求めるファン
音楽ソフトも中古市場では安定した人気を誇っている。 1973年発売のオープニング/エンディング主題歌ドーナツ盤(EP)は、アニメソングコレクターの間で定番中の定番。 オリジナル盤の相場は1,500~3,000円前後だが、帯付き・歌詞カード完備の美品は5,000円前後に高騰。堀江美都子の直筆サイン入り盤などは1万円を超える例もある。
LPアルバム『タツノコ・アニメ主題歌ベスト』シリーズに収録されたバージョンも人気で、状態が良ければ2,000円台後半から4,000円程度。
1990年代に発売されたCD版『タツノコプロ・メモリアルサウンドコレクション』は比較的流通量が少なく、現在もプレミア価格(4,000円前後)で取引されている。
また、2020年代に発売された復刻LP盤は、コレクターズレーベルから数量限定で生産され、瞬時に完売。再販を求める声がSNS上で多く上がっている。
音楽ジャンルでは「昭和アニメの情緒」を音で味わいたいというファン心理が強く、“聴くコレクション”としての価値が年々上昇している。
ホビー・おもちゃ関連 ― ソフビ、ミニフィギュア、ケロケロ笛が人気上位
『けろっこデメタン』関連グッズの中で特に市場価値が高いのが、1973年当時に発売されたソフビ人形だ。 デメタンとラナタンのペアフィギュアは、高さ約10cmほどのミニサイズながら、手彩色による繊細な表情が魅力である。 未使用・箱付き状態のものは非常に希少で、オークションでは1体4,000~8,000円、ペアセットで10,000円を超えることも珍しくない。
ケロケロ笛の玩具版(プラスチック製の笛)は現存数が少なく、動作確認済みの良品で5,000円前後。音が鳴らないものでも“展示用”として価値があり、近年は昭和雑貨店のディスプレイとしても人気が高い。
そのほか、ガチャガチャのカプセルフィギュア、メンコ、消しゴム、シールなどのミニアイテムも多数流通しており、特に“未開封ブリスター”はコレクター間で高値取引される。
おもちゃ市場の動向としては、「ノスタルジー+保存性」の二軸が価格を決定しており、状態が良ければ希少性よりも美観が重視される傾向にある。
ゲーム・ボード・文房具関連 ― 幻のすごろくが高額落札
『けろっこデメタン』にはファミコンなどの電子ゲーム化はされなかったが、当時のキャラクター人気に合わせて“すごろくボード”や“紙製ゲーム”が雑誌付録や市販玩具として登場している。 この「けろっこデメタン ぼうけんすごろく」は、タカトクトイスが発売した希少アイテムで、完全版は駒・サイコロ・ボード・説明書すべて揃っていれば10,000円を超えることもある。
文房具関連では、キャラクター下敷きやノートが現在でも人気。特にピンクとブルーの“ラナタン&デメタンのツインノート”は状態次第で3,000円前後。
シールブックや鉛筆、消しゴムセットも「昭和キャラ文具コレクション」として再注目されており、マニア向け市場が形成されつつある。
食玩・日用品 ― 懐かしさが価格を押し上げる
駄菓子屋で販売されていた「デメタンガム」や「けろっこクッキー」などのパッケージは、未開封で残っていれば驚くほどの価値を持つ。 とくにキャラクターカードやシール付きパッケージは、保存状態により3,000円以上の値が付く場合もある。 食品パッケージ系のコレクションは保存が難しいため、近年ますます希少性が高まっている。
また、生活雑貨では1970年代当時のマグカップ・コップ・ランチボックスが人気。
“デメタンとラナタンのハート型弁当箱”は非常にレアで、近年のオークションで8,000円を超える落札例が確認されている。
これらのグッズは単なる懐古品ではなく、“昭和の生活デザイン”を象徴するカルチャーアイテムとして再評価されている。
中古市場全体の傾向 ― ノスタルジーから文化遺産へ
近年の『けろっこデメタン』関連商品の取引傾向を見ると、単なる懐古ブームを越え、“昭和アニメ文化のアーカイブ的価値”として位置づけられつつある。 特に2020年代に入り、SNSや動画配信で若い世代がこの作品を知るようになり、「親から譲り受けたVHSをデジタル保存した」「祖父母のコレクションを整理して出品した」といった新しい流通も増加している。
中古相場は全体的に上昇傾向で、特に状態の良いもの・限定品・帯付きなど“完品”が重視される。
ファン層は40代以上が中心だったが、最近は20~30代の“昭和レトロファン”が加わり、需要の層が厚くなっている。
『けろっこデメタン』は単なるアニメではなく、“優しさを忘れない時代の記憶”として商品そのものが語り継がれている。
コレクターたちは口をそろえて言う――
「デメタンの笛の音を聞くと、あの頃の心が戻ってくる」と。
総括 ― 残るのは、ものではなく想い
中古市場で取引される一つひとつのグッズには、かつてそれを手に取った誰かの思い出が宿っている。 『けろっこデメタン』の人気が半世紀を越えても衰えない理由は、商品そのものが“心の記録”だからだ。
映像・音楽・書籍・玩具――どのジャンルを取っても、そこに流れているのは“優しさと郷愁”である。
そして今もオークションの画面越しに、誰かがその想いを受け継いでいる。
それこそが、『けろっこデメタン』が生き続ける証なのだ。




![【中古】けろっこデメタン セレクション1 [DVD] p706p5g](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/skymarketplus/cabinet/sm49/sm49-b000068w8m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】アニメ系トレカ/ノーマル/タツノコワールド1996 054[ノーマル]:けろっこデメタン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)


![【中古】けろっこデメタン セレクション2 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cocohouse/cabinet/mega01-2/b00006auuq.jpg?_ex=128x128)