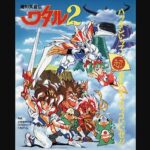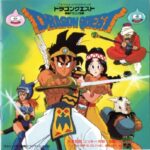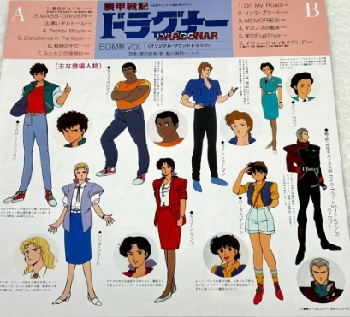CHUNITHM イロドリミドリ 箱部奈留 はこべなる★コスプレ衣装
【原作】:七条レタス、齊藤キャベツ
【アニメの放送期間】:2022年1月5日~2022年2月23日
【放送話数】:全8話
【放送局】:独立UHF局
【関連会社】:暁、SEGA、フロントウイング、イロドリミドリ新聞部
■ 概要
アーケードから生まれたガールズバンド・ストーリーのテレビ化
2022年1月5日から2月23日まで、独立UHF局を中心に放送されたテレビアニメ『イロドリミドリ』は、セガのアーケード音楽ゲーム『CHUNITHM(チュウニズム)』を原点とするメディアミックスプロジェクトの一環として制作された。もともとは2015年に始動した同タイトルの中で、ゲーム内楽曲として登場した女子高生バンド「イロドリミドリ」が人気を博し、そこから派生する形でラジオドラマ、コミックムービー、キャラクターCDなど多方面へ展開。その7年後、ついにTVアニメとしての映像化が実現した形だ。 “ゲーム内ユニットのアニメ化”という構図は、音楽ゲーム文化が成熟し、プレイヤー層が作品世界に深く共感するようになった2010年代後半の潮流を象徴している。リズムゲームの中に散りばめられたキャラクター性がアニメとして具現化することで、プレイヤーは「プレイする音楽」から「観る音楽」へと体験の幅を広げた。この作品はその典型例として、多くの音ゲーファンの記憶に残る存在となった。
放送フォーマットと構成の特徴
放送は全8話構成で、1話あたり約7分というショートアニメ形式が採用された。短尺ながらも、各話には確かなテンポ感と濃密なキャラクター描写が盛り込まれ、テンポよく笑いと情感を織り交ぜる構成となっている。TOKYO MXなどで放送されたほか、YouTubeや配信サイトでも順次公開され、リアルタイム視聴とネットアーカイブの双方で話題を呼んだ。 短い放送時間の中に、バンド活動や学園生活、音楽にかける情熱など、キャラクターたちの“いろとりどりの青春”を詰め込むことにより、物語としての起伏よりも日常の積み重ねやメンバー同士の掛け合いに焦点を当てた構成が特徴的だ。制作スタジオはトムス・エンタテインメントが担当し、同社の技術力を活かした鮮やかな色彩設計と軽快な動きの作画が印象的である。
物語の舞台と作品の世界観
物語の中心となるのは「舞ヶ原音楽大学附属舞ヶ原高等学校」。通称“まいまい”と呼ばれるこの学校は、全国から音楽の才能を持つ生徒たちが集まる名門校であり、劇中では「ライブパフォーマンスの完成度が成績評価に影響する」という独特のルールが存在する。音楽を“試験科目”として扱うという設定は、音楽ゲーム発の世界観をアニメ的に発展させたものであり、学園コメディと音楽アクションを融合させたユニークな舞台となっている。 主人公・明坂芹菜(あけさかせりな)は、単位の危機を救うために“バンドを結成してライブで好成績を取る”という半ば勢い任せの動機から活動を始めるが、仲間たちとの演奏を通じて次第に音楽そのものの楽しさや仲間の大切さを実感していく。この設定は、視聴者にとっても「音楽が人をつなぐ」ことを象徴的に表す仕掛けとなっている。
『イロドリミドリ』というバンドの成立と構造
アニメ内で描かれるバンド「イロドリミドリ」は、ボーカル兼ドラムの芹菜を中心に、ギター・ベース・キーボードなどを担当する仲間たちによって構成される。もともと5人編成としてスタートした彼女たちは、音楽への想いや互いの葛藤を重ねながら、次第に“7人バンド”として拡張されていく。 メンバーの名前が「春の七草」に由来していることも本作ならではの特徴で、彼女たちそれぞれが持つ個性の色合いを「七草=いろどり」に重ねることで、バンドの象徴的なテーマと一致させている。1月7日が“イロドリミドリの日”と定められている点も、ファンの間ではよく知られている。 アニメ版ではその設定を踏襲しつつ、個々のキャラクターがどのようにして“音楽”という共通言語を通して結びついていくのかを、ギャグ調のテンポとともに描いている。
音楽表現とアニメーション演出の融合
この作品の核は、やはり「音楽」。各話で披露されるライブシーンは、ショートアニメの制約を感じさせないクオリティで制作されており、アニメーションと実際の音楽映像が一体化する瞬間には、アーケードゲーム出身らしい高密度な演出が光る。 また、ゲーム『チュウニズム』や『maimai』、『オンゲキ』といった他タイトルで使用された楽曲群も随所に登場し、原作ファンにとっては“音楽的クロスオーバー”を体感できる構成となっている。各キャラの演奏シーンには楽器の動きやリズムの同期にも細やかなこだわりが見られ、実際の演奏経験者が見ても納得できるリアルな作画が特徴だ。音楽監修のセンスが随所に光り、サウンドそのものがキャラクター描写の一部として機能している点も高く評価された。
制作陣と作品のクリエイティブ指向
企画原案は七条レタスと齊藤キャベツという独自ユニットによるもの。キャラクターデザインはイラストレーターHisasiが担当し、個性的かつ華やかな色彩感覚がアニメの“鮮度”を強調している。脚本はシリーズ構成においてテンポとユーモアを重視し、アニメオリジナル要素としてキャラクター同士の会話の自然さ、そして“仲間の音を聴くこと”の重要性が丁寧に描かれている。 監督・演出陣も若手クリエイターが多く参加し、短尺ながらも緻密な構成力とテンポの良さが際立つ。全体として、原作ゲームの雰囲気を尊重しつつも、アニメとしての“軽やかなリズム”を持つ仕上がりとなっている。
ショートアニメならではのテンポと魅力
通常の30分枠アニメとは異なり、短い放送時間の中にギャグ・ライブ・キャラ紹介を詰め込む構成は、まるでミュージックビデオのようなテンポ感を生んでいる。視聴者は1話ごとに小さな笑いと高揚を得られ、繰り返し視聴にも適した設計だ。さらに、SNS時代に合わせて「1話完結型+ネット拡散向け映像」という現代的手法も採用され、アニメファン以外にも音楽ファンやゲーマー層からの注目を集めた。 作品全体には“音楽でつながる友情と成長”という普遍的なテーマがあり、短いながらも一貫した物語軸が感じられる点が魅力といえる。
多層的メディアミックスの中での役割
『イロドリミドリ』のアニメ版は単なる派生作品ではなく、音楽・漫画・ラジオといった他媒体との“ハブ”としての役割を果たしている。ゲームでキャラを知った人がアニメを通して人格を深く理解し、アニメから入った新規層がゲームに戻っていくという双方向的な流れを作り出している点が画期的であった。 また、アニメ化のタイミングが2022年という節目だったことも象徴的で、コロナ禍によってリアルライブが制限されていた時期に“映像で音楽の熱を感じられる”という新しい表現形態を提示した。
総括:作品としての意義と魅力
『イロドリミドリ』は、音楽ゲーム文化がアニメというフォーマットで一つの完成形を迎えた事例といえる。短尺ながらキャラクターの個性・演奏の魅力・友情の物語が丁寧に描かれ、ゲーム発のキャラクターたちが“生きた存在”として動き出した瞬間を体感できる。 音楽・青春・友情が交差するこの作品は、まさに“音で描く青春群像劇”。アーケード発の世界観をそのままテレビアニメとして成立させた稀有な例として、今も多くのファンの心に響き続けている。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
音楽の才能が集う学園・舞ヶ原高校
物語の舞台は、全国から音楽の才能を持つ若者たちが集う名門校「舞ヶ原音楽大学附属舞ヶ原高等学校」、通称“まいまい”。ここでは一般教養に加え、演奏・作曲・パフォーマンスといった音楽関連の専科が重視されている。特に注目すべきは、学園の独特な評価制度――「ライブパフォーマンスがすごければ単位がもらえる」という奇抜な噂である。 この設定が作品全体の原動力となる。単位が危うい生徒も、成績上位者も、最終的には“音で証明する”ことが求められる世界。学園という小さな舞台で、彼女たちは自分の居場所と仲間を見つけるために楽器を手に取り、音楽という言葉で自分を語ろうとするのだ。
芹菜、単位を賭けたバンド結成宣言
物語の中心となるのは、高校2年生の明坂芹菜(あけさかせりな)。元気で明るく、やや能天気な性格の彼女は、学業にはあまり熱心ではない。ある日、友人の天王洲なずなから「ライブでいい演奏をすれば単位がもらえるらしいよ」と聞いた芹菜は、半ば冗談のように「じゃあバンドを組もう!」と言い出す。 その瞬間から、学園の静かな日常が動き出す。単位のためとはいえ、音楽を愛する仲間が集まると、次第にその活動は“ただの課題対策”ではなく、“本気の青春”へと変わっていく。芹菜は自分の中に眠っていた情熱を見つけ、仲間たちとともに“イロドリミドリ”というバンドを立ち上げるのだった。
個性豊かなメンバーとの出会い
芹菜の誘いで集まったメンバーは、どれも個性の強い少女たちだ。 責任感が強く常識人の御形アリシアナ(おがたありしあな)、おっとりしているが意外に芯の強い天王洲なずな、頭脳明晰なキーボード担当小仏凪(こぼとけなぎ)、そして芹菜の年下の従妹であるベース担当箱部なる(はこべなる)。 それぞれの性格がぶつかり合い、衝突も起きるが、彼女たちは音楽という共通項を通して次第に絆を深めていく。練習のたびに笑いとドタバタが絶えず、真面目な話し合いも気づけば冗談に変わる。そんな“青春のにぎやかさ”がこの作品の大きな魅力だ。
日常に潜む小さな事件と笑い
アニメでは、1話ごとに小さなエピソードが展開される。楽器の練習中にケーブルを踏み抜いたり、衣装合わせで大騒ぎしたり、合宿中にカレーを焦がして全員で責任を押し付け合う――そんな他愛もない騒動が続く。 だが、その何気ない日々の中に、メンバーそれぞれの“音楽にかける思い”が滲み出る。特に芹菜の「やってみなきゃわからないじゃん!」という前向きな姿勢は、仲間の背中を押す原動力となり、彼女たちを本気の演奏へと導いていく。 全体のトーンは軽やかだが、その裏には“努力と情熱の積み重ね”という真剣なテーマが流れている。
学園フェスへの挑戦
物語のクライマックスは、舞ヶ原高校の一大イベント「学園フェス」。このフェスでは、各バンドがステージ上で演奏を披露し、審査員と観客から評価を受ける。これが芹菜たちの“単位をかけた勝負”の舞台となる。 最初は軽いノリで始まった活動も、フェスの近づくにつれて緊張感を帯びていく。練習時間の確保、機材トラブル、メンバーの衝突――様々な試練が彼女たちを襲う。特に、アリシアナの完璧主義と芹菜の感覚的な演奏スタイルの違いは、バンドを一時的に不協和音へと導く。だが最終的に、彼女たちは互いの違いを受け入れ、一つの音楽として調和させていく。その過程こそが、この作品が伝えたい“青春の和音”なのだ。
日常の中の成長譚
『イロドリミドリ』のストーリーは、大きなドラマやバトルではなく、“日常の積み重ね”を軸にしている。たとえば、ちょっとしたミスを笑いに変えたり、放課後のスタジオで練習を重ねたり――そんな小さな出来事がキャラクターの成長として積み上がっていく。 この日常描写の積み重ねが、短い話数にもかかわらず、視聴者に「確かな物語の厚み」を感じさせる理由だ。毎話の中でキャラクターの関係性が少しずつ変化し、最終話ではそれが一つの音となって結実する。言葉ではなく“音”で気持ちを伝えるという構成は、音楽アニメとして非常に完成度が高い。
最終話:音がつなぐ未来
最終話では、芹菜たちがついに学園フェスのステージへ立つ。練習ではミスを連発していたが、本番ではそれぞれの想いが一つになり、観客を圧倒する演奏を披露する。彼女たちの音は単なるメロディではなく、友情・努力・感謝の結晶だった。 演奏後、学園中が歓声に包まれる中で、芹菜が放つ一言――「やっぱり音楽って最高!」。その台詞が、彼女たちの青春のすべてを象徴している。 物語は特定の“終わり”を描かない。むしろ「彼女たちの音楽は、これからも続いていく」という余韻を残し、ゲーム・音楽・アニメを横断するプロジェクトとしての広がりを示して幕を閉じる。
軽やかで温かいトーンの物語
『イロドリミドリ』のストーリーには、重苦しい葛藤やシリアス展開はほとんど存在しない。代わりに描かれるのは、少女たちの“素の笑顔”と“音楽に夢中になる時間”だ。アニメ全体が軽快なテンポと優しい色調で統一されており、見ている側にもポジティブなエネルギーを与えてくれる。 短編形式だからこそ、一瞬一瞬の感情を切り取ることに集中でき、その“瞬間のきらめき”こそが作品の最大の魅力である。視聴後には、まるで放課後の部室にいるような温かさが心に残る。
“音で語る青春”の完成形
『イロドリミドリ』は、ストーリーそのものよりも“空気感”を楽しむタイプの作品だ。音楽を通じて育まれる友情、夢中で何かに打ち込む時間、そしてそれを共有する仲間たち――そうした普遍的な青春の姿が、短い時間にぎゅっと詰まっている。 彼女たちのステージは、決して大規模なものではない。しかし、その音には確かな輝きがある。見終えたあと、視聴者の多くが「明日も頑張ろう」と思えるような、そんなエネルギーを持った作品なのである。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
イロドリミドリ:七草が紡ぐ友情と音楽
『イロドリミドリ』の中心に立つのは、同名の女子高生バンド「イロドリミドリ」。彼女たちはそれぞれ“春の七草”にちなんだ名前を持ち、バンド活動を通して友情・努力・夢を共有する。7人のキャラクターが互いの個性をぶつけ合いながら成長していく姿は、本作の核となるテーマであり、音楽が彼女たちをひとつにする象徴的なモチーフでもある。
明坂芹菜 ― 天真爛漫なリーダー
バンドの発起人であり、ドラム兼ボーカル担当。彼女のエネルギッシュな性格は、物語の推進力そのものだ。勉強は苦手だが、誰よりも“音で語ること”に長けており、感情をそのままリズムに変えて叩き出すスタイルは、まさに彼女の生き方そのもの。 幼少期に父から贈られたスネアドラムを「すねちゃま」と呼び、楽器を擬人化して大切に扱うなど、音楽に対して人一倍の愛情を注ぐ。雷が苦手で泣き出すような子どもっぽさを残しながらも、バンドのピンチでは必ず中心に立つ頼もしさを見せる。実家の「カレー喫茶あけさか」を手伝う場面もあり、彼女の生活感が作品世界に温かみを与えている。
御形アリシアナ ― 才能と責任の狭間で
アリシアナはバンドのギター兼ボーカルで、作曲を担当する知性派。日本人の父とイギリス人の母を持ち、クラシカルな教養とロックへの情熱を併せ持つ。 完璧主義な性格が災いして芹菜と衝突することも多いが、それは常に“より良い音を目指す”ための真剣さからくるもの。普段は冷静で理論的だが、時折感情をあらわにする場面では視聴者の心を打つ。機械が苦手というギャップも魅力で、DTMを使いこなせず凪に助けを求める姿は微笑ましい。 ステージネームの「あーりん」は芹菜が名付けたもので、彼女の堅さをほぐす愛称としてすっかり定着している。
天王洲なずな ― 穏やかな調律者
ふわふわした雰囲気を漂わせながらも、メンバーの心の支えとなる存在。手先が器用で、ギターを自作するほどの技術を持つ。父がギタークラフト職人であり、幼い頃から木材の香りや弦の響きの中で育った。 彼女の穏やかさは、しばしばバンド内の緊張を和らげるクッションのように働く。発言は少ないが、一言ひとことに重みがあり、物語終盤では“イロドリミドリの母”的な役割を果たしている。 また、コミケで手芸作品を出すなどクリエイター気質も強く、音楽と手仕事の双方に“ものづくり”へのこだわりが表れている。
小仏凪 ― 静かなる天才
理論派で、編曲を担うキーボーディスト。幼少期からクラシック教育を受け、厳格な家庭に育ったため、感情表現が苦手。だが、音楽の中では最も自由で、ステージでは精密さと狂気が入り混じるようなパフォーマンスを見せる。 彼女の「正確さを愛する美学」はバンドに安定感を与える一方、感覚派の芹菜とはしばしば衝突する。しかし、衝突を経て相互理解に至るプロセスが作品の“友情描写”をよりリアルなものにしている。 ゲーム好きの一面を持ち、SNSでは意外なほど毒舌というギャップも人気だ。
箱部なる ― 野生と音楽の融合
最年少にして最もエネルギッシュな存在。天才肌のベーシストであり、理屈よりも感覚で音をつかむタイプ。髪を触られると音感が鈍るなどの奇妙な体質や、足でベースを弾くといった破天荒なプレイスタイルが印象的だ。 兄が有名なバンドマンという背景もあり、音楽に対しての嗅覚はずば抜けている。勉強は苦手だが、ライブ中の集中力と存在感は圧倒的。 無邪気で問題児的な一面を持ちながらも、凪との友情や信頼が描かれる場面では繊細な表情を見せる。作品を“躍動”させる象徴的キャラクターといえる。
月鈴那知&月鈴白奈 ― 姉妹の絆と才能
那知はプロのヴァイオリニストとして学園内でも別格の存在。小柄な体に似合わぬ強烈な個性を放ち、独特の語尾「~じゃ」が印象的。彼女の音楽に対する姿勢はストイックで、まるで修行僧のように妥協を許さない。卒業後は海外で活動しており、芹菜たちにとっては“到達点”のような存在である。 一方、妹の白奈は静かで内向的なチェロ奏者。天才姉へのコンプレックスを抱きながらも、自分なりの音楽を見つけようとする。その不器用な成長が、シリーズ後半で視聴者の心を大きく動かした。姉妹で奏でる二重奏シーンは、ファンの間で屈指の名場面とされている。
HaNaMiNa:新しい世代の情熱
「HaNaMiNa」は、舞ヶ原高校の軽音同好会を中心とした若い世代のバンドで、イロドリミドリの後輩にあたる。彼女たちは芹菜たちの活動に憧れ、音楽を通して自分たちの青春を描こうとする。メインの3人はどこか未熟で粗削りだが、そこにこそ“青春の原石”の輝きがある。
五十嵐撫子 ― 直情的なギターヒロイン
軽音部の会長で、学園フェスを見て音楽に目覚めた熱血ギタリスト。喜怒哀楽が激しく、まっすぐすぎて時に空回りするが、その真っ直ぐさこそが仲間を引き寄せる。中古ギターを自分の手で磨き上げて弾く姿は、努力家の象徴でもある。 彼女の“音楽に恋する瞬間”が随所に描かれ、視聴者が最も共感しやすいキャラクターでもある。
萩原七々瀬 ― 再び音を求めて
元軽音部の部長で、休学から戻ってきた復学生。落ち着いたトーンとミステリアスな雰囲気を持つ。過去の挫折を抱えながらも、撫子たちに導かれるように再びギターを手に取る。 その姿には「再出発」という大人びたテーマが込められており、若い世代との対比が美しく描かれる。
葛城華&小野美苗 ― 対照的な新人ペア
華は勝ち気で負けず嫌いな1年生。撫子へのライバル心を燃やしながらも、共に音を奏でるうちに理解し合っていく。家庭の厳しい教育方針から“自由な表現”を求めて軽音に飛び込むという設定が、彼女の反骨精神を表している。 一方の美苗はおとなしく控えめな性格。リズム感の良さを買われてドラムを担当する。決して派手ではないが、仲間を支える姿勢がファンから高く評価されている。
S.S.L.:電子の音を操るもう一つの舞ヶ原
S.S.L.(シンセ研究会)は、舞ヶ原高校の生徒会メンバーを中心としたテクノユニット。アコースティックなイロドリミドリやHaNaMiNaに対し、こちらは電子音とデジタルを駆使した“未来系サウンド”で学園を彩る。 彼女たちは物語の後半で登場し、音楽の多様性を象徴する存在として機能する。
芒崎奏 ― 完璧主義のリーダー
生徒会長であり、S.S.L.の中心人物。常に冷静で戦略的だが、内に秘めた情熱は誰よりも強い。彼女の演奏は構築的で、シンセの波形一つにも哲学を持つ。 音楽を“論理”として捉える彼女のスタンスは、イロドリミドリの“感情重視”とは対照的であり、作品全体に心地よい緊張感を与えている。
藤堂陽南袴&桔梗小夜曲 ― 言葉と音の化学反応
MC担当の陽南袴は、かつて子役として活動していた元芸能人。華やかな外見とは裏腹に、ラップを通じて内面を解放するスタイルが印象的。 一方、小夜曲(セレナーデ)は世界的なDJとしての腕を持ちながら、人見知りで控えめな少女。二人の関係性は“言葉と音の融合”として描かれ、ステージでは絶妙なコンビネーションを見せる。 彼女たちの楽曲は、アナログな感情とデジタルな冷たさを同居させたような独特の響きを持ち、シリーズ内でも異彩を放っている。
キャラクター群像としての魅力
『イロドリミドリ』の登場人物たちは、単なるバンドメンバー以上の存在である。彼女たち一人ひとりが“音楽を通して生きる”象徴であり、それぞれの個性が七色の音として物語を彩る。 リーダー格・努力家・天才肌・マイペース――性格も背景も異なる少女たちが、互いに影響を与えながら成長していく。その姿は、まさに青春そのもの。視聴者がどのキャラにも自分を投影できる、多層的な群像劇となっている。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
音楽が物語を導くアニメ『イロドリミドリ』
『イロドリミドリ』の魅力を語るうえで、音楽の存在を抜きにすることはできない。もともとセガのリズムゲーム『チュウニズム』から生まれたこのシリーズにおいて、楽曲は単なるBGMではなく「キャラクターの感情そのもの」を表すもう一つのセリフだ。 アニメ版では、各話ごとにエンディングテーマが変化する形式が採用されており、まるでミニアルバムを聴くような楽しさを提供している。それぞれの楽曲が登場人物の心情やストーリーのテーマと密接にリンクしており、短尺アニメながらも強い印象を残す構成となっている。音楽と映像が一体化した瞬間こそ、『イロドリミドリ』という作品の真骨頂である。
第1話エンディング「無敵We are one!!」
シリーズの幕開けを飾るこの楽曲は、タイトルの通り「私たちはひとつ!」というメッセージを全面に押し出した明快なバンドチューン。作詞・作曲・編曲はy0c1eが手掛けており、爽快感と疾走感を両立させたサウンドが特徴だ。 アニメ初回のエンディングで流れるこの曲は、まだ結成して間もないメンバーたちのぎこちない絆と、それでも一緒に音を鳴らす楽しさを象徴している。リズムは軽快だが、サビで一気に開放される高音が“青春のスタートライン”を感じさせ、視聴者に強い印象を残す。ライブシーンではキャラクターたちがカメラに向かって微笑みながらコーラスする演出が加わり、作品全体の明るいトーンを決定づけた。
第2話エンディング「brilliant better」
作詞は有里泉美、作曲は菊田大介、編曲は末益涼太と菊田大介という豪華布陣。タイトルの“brilliant”には「輝くように前へ進む」という意味が込められており、物語序盤で迷いながらも前進する芹菜たちの姿をそのまま音にしたような曲だ。 イントロのギターリフがきらめくように光り、続くメロディラインがキャラクターたちの内なる不安と希望を交錯させる。特に2番以降で展開されるコーラスの重なりは、バンドメンバーの心が少しずつ一つになっていく過程を象徴しており、アニメ演出では空に舞う光の粒として視覚的に表現されている。 「努力は報われる」と安易に言い切らない慎ましいポジティブさが、この曲の魅力だ。
第3話エンディング 「私の中の幻想的世界観及びその顕現を想起させたある現実での出来事に関する一考察」
タイトルからして一筋縄ではいかないこの楽曲は、シリーズ中でも最も異色な存在。作詞は七条レタス、作曲はコバヤシユウヤ&D.watt feat.まらしぃ、編曲はコバヤシユウヤという豪華コラボで制作された。 電子音とピアノの旋律が交錯する独特のサウンド構成で、幻想的な世界と現実を往復するようなリズム構成が特徴。なずなの内面を描く回で使用され、彼女の夢想的で掴みどころのない性格と、芯の強さを対比的に表現している。 歌詞には「形にならない想いが音になる」というフレーズがあり、それがまさにイロドリミドリというバンドの根幹を表している。視聴者の間でも「タイトルを覚えきれないがメロディが忘れられない」という声が多く、カルト的な人気を持つ曲となった。
第4話エンディング「フォルテシモBELL」
有里泉美による作詞、Elements Gardenの藤田淳平による作曲・編曲。劇中ではアリシアナが中心となるエピソードに使用され、クラシカルな旋律とロックサウンドを融合させた壮麗な一曲。 “フォルテシモ”という音楽用語が象徴するように、曲全体は情熱的で華やか。サビのヴァイオリンが鳴り響く瞬間、彼女の貴族的な生い立ちや音楽に対する誇りが一気に広がる。 アニメでは、彼女がステージ上で強いスポットライトに照らされながら微笑むシーンが印象的で、「音楽とは気品と情熱の両立」というメッセージが視覚的にも伝わるよう演出されている。
第5話エンディング「ハート・ビート」
MONACAの広川恵一が編曲を担当したこの曲は、芹菜となずなの友情を描いた穏やかなナンバー。テンポは落ち着いているが、リズムの“ドラムビート”がまるで心臓の鼓動のように鳴り続け、ふたりの心の距離が近づいていく様子を繊細に表現している。 映像では、夕焼けの屋上で二人が語り合う場面にこの曲が流れ、短いアニメでありながらも感情の余韻をたっぷりと残す構成となっている。特に「君とならどんな明日も叩ける」というフレーズは、シリーズ全体を象徴する印象的な一節としてファンに語り継がれている。
第6話エンディング「DETARAME ROCK&ROLL THEORY」
七条レタス作詞、IOSYSのD.wattによる作曲・編曲で、完全に“なる”のテーマ曲といえる破天荒なロックナンバー。ギターとベースが暴れるように鳴り響き、テンポの急変とリズムの遊びが連続する実験的な構成だ。 タイトル通り“理論なんて関係ない、感じろ!”というメッセージが全開で、なるの自由奔放なキャラクターと見事にシンクロする。 ステージ演出では照明が激しく点滅し、彼女がステージの上を駆け回る姿が描かれる。音楽そのものがキャラクターの躍動を体現しており、ファンの間では“イロドリミドリのライブシーンの真骨頂”と称される。
第7話エンディング「Change Our MIRAI!」
fu_mouによる作詞・作曲・編曲。この曲はアニメの物語全体のテーマを集約するような位置づけにあり、“未来を変える”という前向きなフレーズが印象的だ。 学園フェスへ向けて一致団結するメンバーの姿と重なり、映像では彼女たちが手を取り合ってステージに向かうシーンが描かれる。軽快なテンポとシンセポップ調のサウンドが作品のクライマックスにふさわしく、最終話での再登場(劇中歌)によって視聴者に強い達成感を与えた。
第8話劇中歌「Change Our MIRAI!(Live ver.)」
最終話で披露されるライブバージョンは、まさに集大成。これまでの全メンバーがステージに立ち、それぞれのパートを繋ぎながら演奏する構成になっている。イントロのドラムが鳴り始めた瞬間に観客の歓声が響き、過去7話の積み重ねが一気に報われるような演出がなされている。 アニメとしては短い作品だが、このライブシーンだけで「一つの青春を見届けた」と感じさせるほどの完成度を誇る。視聴者の多くが“最終話で泣いた”と語り、配信後のSNSでも「短編なのに最終ライブで泣かされた」と話題になった。
キャラクターソング・イメージソング群の魅力
本作の楽曲群は、アニメの放送に合わせてCD化・配信展開も行われた。各キャラクターのソロ曲には、彼女たちの性格や人間関係を象徴する詞とアレンジが込められている。 たとえば芹菜の「ドラムスティック・スイング」は明るく勢いのあるロックチューンで、彼女の快活さをそのまま音にしたような一曲。一方でアリシアナの「ルミナスコード」は、クラシック調のピアノイントロから始まり、精密な構成の中に熱情を宿すという“理性と情熱の共存”を描く名曲として人気が高い。 また、なずなの「手のひらのメロディ」や凪の「Silent Symphony」など、バンド全体の中でも静謐な曲調が挿入され、作品全体に緩急を与えている。これらのキャラソンはアニメの物語とは独立して聴ける完成度を持ちながら、各キャラクターの心情を深掘りする補完的役割も果たしている。
ファンの反応と楽曲の広がり
放送当時、SNSでは「毎回エンディングが変わるのが楽しみ」「曲が作品そのもの」といった感想が相次いだ。中でも第3話と第6話の楽曲は異彩を放ち、音楽ファンからも高い評価を受けた。 音楽配信サイトでは各楽曲がランキング上位に入り、放送終了後もライブイベントやゲーム内コラボとして再利用されている。アニメが終わっても楽曲が残り続ける――それこそが音楽アニメとしての理想的な循環だといえるだろう。
“聴かせるアニメ”としての完成度
『イロドリミドリ』は“観るアニメ”でありながら“聴くアニメ”でもある。各話で曲が変わる構成により、視聴者はまるでアルバムを一枚聴き終えたかのような満足感を得る。 ストーリーの進行に合わせて曲のテンポやジャンルが変化し、キャラクターの成長と音楽の変化が重なっていく流れは非常にドラマティックだ。 短編作品でありながら、音楽演出の豊かさとサウンドデザインの完成度においては長編アニメに匹敵する。まさに“音楽を主役に据えた青春群像劇”として、2020年代初頭のアニメ史に小さくも確かな爪痕を残したといえる。
[anime-4]
■ 声優について
個性の融合で成り立つ“音楽アニメ”の演技
『イロドリミドリ』の声優陣は、単なるアニメ出演者ではなく、“キャラクターと音楽を同時に表現するアーティスト”として選ばれた存在である。彼女たちは演技だけでなく実際に歌唱・演奏を行う場面も多く、声優でありながらリアルな“バンドメンバー”として作品を支えている。 この「声」と「音楽」の両立は、従来のアニメでは難しい要素であり、キャスティングには“声の響きがそのまま楽器のように機能するか”という観点が重視された。結果として、七者七様の声質がバランスよく調和し、まさに「イロドリミドリ=多彩な色の集合」というタイトルの意味を体現している。
明坂芹菜役:新田恵海 ― 太陽のような声で物語を牽引
主人公・明坂芹菜を演じるのは、新田恵海。彼女は音楽ユニットμ’s(『ラブライブ!』)のメインボーカルとしても知られ、既に“歌える声優”の代表格ともいえる存在だ。 新田の声は明るく伸びやかで、ドラムスティックを振るう芹菜の活発なイメージと完全に一致している。演技面では、テンションの高いギャグパートから感情を抑えたシリアスな場面までの振れ幅が絶妙で、特に最終話のライブシーンでは、演技と歌唱が見事に融合した“生きた芝居”を披露した。 制作スタッフによれば、彼女の収録時の掛け声や笑い声の自然さは「アフレコではなく本当に芹菜がそこにいるようだった」と語られており、現場のムードメーカー的存在でもあったという。
御形アリシアナ役:福原綾香 ― 理知と情熱の声を併せ持つ
アリシアナ役の福原綾香は、声優としてだけでなく音楽活動にも精力的なアーティスト。代表作に『アイドルマスター シンデレラガールズ』の渋谷凛役などがあり、クールな中に確かな熱を秘めた演技が評価されている。 彼女の透明感ある声質は、知的で完璧主義なアリシアナに理想的にマッチしている。特に英語の発音や低音のトーンコントロールが巧みで、ハーフ設定のキャラを自然に表現していた。 歌唱ではクラシックとロックを融合させた“フォルテシモBELL”の収録で、福原自身がボーカルアレンジの意見を出すなど、制作陣からも高く信頼されていたエピソードが残っている。
天王洲なずな役:山本彩乃 ― 優しさと温もりを宿した癒しの声
おっとりした性格のなずなを演じたのは、声優・歌手・舞台女優として幅広く活動する山本彩乃。柔らかく包み込むような声は、作品全体に“呼吸の余白”をもたらす存在だった。 アフレコ現場でも穏やかで和やかな雰囲気を作るタイプで、共演者のコメントでは「彼女の声を聴くと自然にテンポが落ち着く」と評されている。 演技ではセリフに“息遣い”を多く取り入れ、セリフとセリフの間の間(ま)を丁寧に扱うことで、なずなのマイペースさをリアルに伝えていた。彼女が担当した挿入歌「手のひらのメロディ」では、控えめながら心を溶かすような歌声が印象的である。
小仏凪役:佐倉薫 ― 精密さと繊細さを両立する演技
凪を演じた佐倉薫は、クラシック音楽の素養を持ち、発声とイントネーションに非常にこだわるタイプの声優として知られる。その経験が、理論派キーボーディストである凪の知的なキャラクターに見事に反映されている。 佐倉の声には“微かな震え”があり、それが凪の内面に潜む感情の揺れを自然に伝える。彼女はセリフを読む際に「凪が弾く音」を頭の中でイメージしてから声を出していたとインタビューで語っており、音楽的アプローチで演技を構築していたことがうかがえる。 特に凪が自分の弱さを吐露する回では、低音から高音への滑らかな移行が感情の波をリアルに伝え、視聴者の多くが“声優の演技で泣いた”とSNSで反響を寄せた。
箱部なる役:M・A・O ― 直感と勢いの女優型演技
元アイドルであり、現在は人気声優として数多くの作品に出演するM・A・O。彼女の演技は非常にダイナミックで、感情の振り幅が大きい。 なるというキャラクターは破天荒で衝動的な少女だが、M・A・Oの声にはどこか人懐っこい可愛らしさがあり、視聴者に嫌味を感じさせない。声の張り上げ方、笑い声、息の使い方――すべてがライブ感に満ちており、まさに“即興的演技”の極致。 アフレコ中にアドリブを加えることも多く、「芹菜!カレー食べに行こうぜ!」というセリフは脚本にない即興の一言だったと監督が語っている。この自由さこそが、なるというキャラクターを唯一無二の存在にしている。
月鈴那知・月鈴白奈役:ゆかな&悠木碧 ― 姉妹の呼吸を演技で再現
天才姉妹・那知と白奈を演じたのは、ベテランのゆかなと、若手実力派の悠木碧という豪華キャスト。この二人の組み合わせが、“技術と感性の継承”という作品テーマを象徴している。 ゆかなの演じる那知は、気品と厳しさを兼ね備えた声で、セリフの一音一音に明確な抑揚がある。その一方で悠木の白奈は、不安定で柔らかい声を使い、姉への尊敬と葛藤を繊細に表現している。 アフレコでは二人が実際に隣同士でマイクを共有し、呼吸を合わせるように演じたという逸話がある。そのリアルな“息のシンクロ”が、姉妹の絆をより生々しく伝えていた。
HaNaMiNa・S.S.L.のキャスト陣 ― 新世代の声優たちの挑戦
後輩バンド「HaNaMiNa」や「S.S.L.」のメンバーには、若手声優が多く起用された。新人に近いキャストを積極的に採用した理由は、“音楽の新しい風”を感じさせるためだとスタッフは語っている。 彼女たちはベテラン勢の中で緊張しながらも、現場にエネルギーをもたらす存在だった。特に、五十嵐撫子役の小泉萌香は、初々しい演技と素朴な歌声で視聴者から高い支持を得た。 また、生徒会長・芒崎奏を演じた鬼頭明里は、冷静で端正な声のトーンで“リーダーとしての威厳”を確立。彼女の芝居は、音楽的緻密さと精神的強さを兼ね備えており、S.S.L.というユニットの完成度を一段と引き上げた。
アフレコ現場の雰囲気とチームワーク
本作のアフレコは、通常のドラマ録音とは異なり「セリフ+リズム収録」という独自の形式で行われた。セリフのテンポが音楽に直結するため、声優陣はリズムキープを意識しながら演技を行う必要があったという。 現場ではメトロノームを鳴らしながら演技を合わせることもあり、声優たちが“ミュージシャンのように呼吸を合わせる”という稀有な環境だった。 また、短尺アニメでありながらリハーサルを重ねる時間が多く取られ、全員でテンションや間を確認し合うことで、一体感ある芝居が実現した。
声優陣の音楽活動への波及
アニメ放送後、声優たちはライブイベントや配信番組を通して“実際に演奏する”機会を持つようになった。とくに新田恵海や福原綾香が出演したステージイベントでは、『イロドリミドリ』の楽曲が生演奏で再現され、観客から大きな反響を呼んだ。 このように、アニメの枠を超えて声優陣がリアルの場でキャラクターを演じ続ける構図は、従来の声優活動の枠を超える新しい表現形態といえる。彼女たちはまさに“二次元と三次元をつなぐ存在”として、作品の世界を現実に拡張しているのだ。
まとめ:声が紡ぐ青春のハーモニー
『イロドリミドリ』の声優陣は、単なる演者ではなく“共演する楽器”でもある。声の表情、テンポ、リズムの切り方――そのすべてが音楽的であり、映像と音の間に完璧なバランスを生み出している。 短尺アニメでありながら、ここまで緻密にキャラクターと声を融合させた作品は稀であり、声優ファンからも音楽ファンからも高い評価を得た理由はそこにある。 まさに、彼女たちの声が作り出した“青春のハーモニー”こそ、『イロドリミドリ』というアニメの最も美しい旋律といえるだろう。
[anime-5]
■ 視聴者の感想
短尺アニメに詰まった“完成された青春”という驚き
放送開始直後、SNSではまず「7分という短い尺なのに、1話でしっかり感情が動く」との声が多く寄せられた。近年のアニメはテンポが速い作品が増えているが、『イロドリミドリ』はその中でも群を抜いて「凝縮された充実感」を持っていたと評価された。 ファンの多くは、キャラの日常描写が短いながらも的確に心情を掴んでいる点を称賛し、「セリフの一つひとつが音楽のようにリズムを持っている」と感想を寄せている。これは脚本と演出の巧みさ、そして声優陣の呼吸感によるものだ。 特に「第3話のテンポと間合いの心地よさ」「第7話のフェス準備の緊張感」など、各話に明確なリズムが存在し、“短いけど見応えのあるアニメ”として評価された。結果的に、ショートアニメの成功例として多くのクリエイターにも注目された作品となった。
ゲーム発アニメとしての完成度の高さ
『イロドリミドリ』は、音楽ゲーム『チュウニズム』発のスピンオフ作品という性質上、当初は「ファン向けの小規模企画」と思われていた。しかし放送が始まると、その完成度に驚く声が相次いだ。 SNSでは「ゲーム知らなくても普通に楽しい」「原作知識ゼロでもキャラがすぐ覚えられる」といった意見が多く、初見視聴者にとっても入りやすい構成が好評を博した。 特に、セガゲームズの他音楽タイトル(maimai、オンゲキなど)との繋がりを感じさせる演出が“ファンサービス過剰ではなく、自然に世界が広がる”と評価され、既存ファン層からも歓迎された。 音楽ゲームを長くプレイしてきたファンにとっては、「自分の叩いていた曲がアニメで動いている」という感動体験となり、作品の存在意義がより強調された。
キャラクター描写のリアリティが共感を呼ぶ
本作のキャラクターたちは、典型的な“アニメ的デフォルメ”ではなく、どこかリアルな青春像を持って描かれている。 芹菜の「なんとかなるよ!」という言葉の裏にある焦り、アリシアナの完璧主義と孤独、なずなの穏やかな優しさ、凪の理屈っぽさ、なるの無邪気さ――それぞれが視聴者のどこかの部分に重なり、「自分の学生時代を思い出した」という感想が多く見られた。 また、7話で描かれる“本気でぶつかり合う友情”の場面は、ファンの間で「まるで本物の部活のよう」と称され、リアルな青春群像としての評価を確立した。 視聴後のSNSでは「キャラが可愛いのに感情がちゃんと伝わる」「短いのに人生が詰まってる」といったコメントが多く、キャラクターの“人間味”が支持の大きな要因となった。
音楽演出への感動と技術的完成度への賛辞
視聴者の間で特に盛り上がったのは、やはり音楽シーンだ。各話のエンディングやライブ描写には「作画の動きと音が完全に一致していて鳥肌が立つ」という感想が数多く寄せられた。 楽器の指使い・手の動き・表情の変化など、1秒単位でこだわられた演出に“実際の演奏経験者”たちが感嘆の声を上げている。中には、「このアニメを見てギターを始めた」「自分も文化祭でバンドを組みたくなった」という投稿もあり、音楽アニメとしてのモチベーション喚起力の高さを示した。 また、作曲陣やレコーディングエンジニアへの注目も高まり、「アニメの音楽部門で一番音が良い」との評が専門家からも寄せられた。音質のクオリティが配信でもしっかり維持されていた点は、作品制作陣のこだわりを象徴している。
作画・色彩・キャラデザインへの絶賛
Hisasiによるキャラクターデザインがアニメ化に際して絶妙にブラッシュアップされた点も、ファンの支持を集めた。もともと彼の描くキャラクターは発色が強く、線の太さに特徴があるが、アニメではそれを柔らかくデフォルメし、背景との調和を図っている。 視聴者からは「カラフルなのに目に優しい」「7分アニメとは思えない作画安定度」といった声が上がり、特にライブ時の光と影の表現には“神作画”の称号が与えられた。 また、表情の細かな変化に対して「1コマごとの演技が丁寧すぎる」と感動するコメントもあり、ショートアニメとは思えない完成度に驚くファンが続出した。
テンポの良さとギャグセンスの絶妙なバランス
シリーズを通して、明るく笑える場面が多いのも本作の魅力。ネット上では「疲れた日に観ると元気が出る」「小ボケがテンポよくてクセになる」といった感想が見られた。 特に芹菜とアリシアナの掛け合いは「漫才コンビのよう」と評され、2人の関係性がファンの間で“芹アリ”と呼ばれて愛されている。なるの破天荒な発言や凪の無表情なツッコミなど、キャラ同士の相互作用が自然に笑いを生む構成も高評価だった。 ギャグと感動のバランスが絶妙で、1話の中で笑って泣けるというリズム感が「7分アニメの理想形」として語られている。
音楽ゲームファン・アニメファン双方の融合
『イロドリミドリ』のファン層は非常に幅広い。ゲームセンターで『チュウニズム』をプレイしていた層と、アニメを日常的に視聴する層が交わり、SNS上で新たなコミュニティを形成した。 放送後には「#イロドリミドリ感想会」というハッシュタグが自主的に広がり、ファン同士が“推し曲”“推しキャラ”を語り合う文化が生まれた。 また、音楽関係者や楽器店が公式に反応するなど、二次的な広がりも多く見られた。特に“音楽教育”の観点から「このアニメは子どもに楽器を持たせたくなる」と語るコメントもあり、文化的な影響も決して小さくない。
印象的な最終回への反応
最終話のライブシーンでは、SNSのトレンドに「イロドリミドリ」が一時ランクインするほどの盛り上がりを見せた。 ファンのコメントでは、「7分×8話でここまで泣かされるとは」「短編なのにエモーショナルすぎる」と絶賛の嵐。 特に、ラストで芹菜が「音楽って最高!」と叫ぶ瞬間は、作品全体を締めくくるメッセージとして多くの人の心に残った。映像と音、キャラの想いがすべて一体化した“音楽アニメの奇跡”と評されている。 また、エンドロールの最後に映る「To be continued in your heart(続きはあなたの心の中で)」というメッセージがファンの涙を誘い、後日談を望む声が相次いだ。
総評:短編アニメの限界を超えた感動体験
放送後、多くのアニメ評論家が『イロドリミドリ』を“短編アニメの到達点”と評価した。7分という枠内で、物語・音楽・感情・作画・演技すべてが調和している点は、他作品でも例が少ない。 また、“ゲーム由来アニメ=販促”というイメージを覆し、単体で芸術作品として成立していることも高く評価された。 ファンの間では「1クールにしてもよかった」「このテンポで映画版を見たい」という意見もあり、短編ながらシリーズ化を望む声が絶えない。 結局のところ、視聴者の多くが感じたのは「音楽って、やっぱり人を幸せにする」という素朴で普遍的なメッセージだった。 『イロドリミドリ』は、派手さではなく“心に残る音”で勝負した作品として、今も静かな人気を保ち続けている。
[anime-6]
■ 好きな場面
オープニングの学園風景と初めてのドラムスティック
多くのファンがまず挙げるのが、第1話の冒頭、舞ヶ原高校の朝の風景だ。朝日が校舎の窓に反射し、風に揺れる桜並木の中を芹菜が走り抜けるシーンは、たった数秒ながらも“青春アニメの始まり”を感じさせる。 ここで彼女がカバンからドラムスティックを取り出して空に掲げる描写が入る。この瞬間、視聴者は「これは音楽そのものを青春として描く物語なんだ」と直感する。セリフもBGMもほとんどなく、ただスティックが風を切る音だけが響く――それが物語全体の象徴的な導入になっている。 短編アニメでありながら、この最初のワンシーンで世界観と主人公の心情がすべて伝わる点は、演出面での秀逸さを物語っている。
バンド結成宣言のシーン ― “勢い”が友情を生む瞬間
第1話の終盤、芹菜が「バンドやろう!」と叫ぶ場面は、『イロドリミドリ』を象徴する名台詞として知られている。単位を取るための突発的な提案なのに、なぜか周囲が次々と巻き込まれていく。 なずなが「……まあ、楽しそうだし、いいかもね」と呟き、アリシアナが「全く、あなたという人は」とため息をつきながらギターを取る。このわずか十数秒のやりとりの中に、バンドという“偶然から生まれる絆”の奇跡が凝縮されている。 演出的にも、カットの切り替えが楽器のリズムと同期しており、芹菜の言葉がそのまま“ビート”として鳴る。見ている側が自然にリズムを感じるほどのテンポの良さで、多くのファンが「1話ラストで心を掴まれた」と語っている。
屋上での放課後ジャムセッション
第3話では、放課後の屋上で行われる即興演奏シーンが描かれる。風の音とアンプのノイズが混じる中、芹菜・なずな・凪の3人が音を合わせる――この瞬間が、ファンにとって“イロドリミドリが本当に始まった瞬間”として語り継がれている。 このシーンは作画と音響の連動が特に秀逸で、ドラムのスティックがシンバルを叩くたびに夕陽が反射し、ベースの弦が震えるたびに影が長く伸びる。音楽そのものが映像の一部として生きており、まるでミュージックビデオのような美しさだ。 視聴者のコメントには「風が音楽の一部になっている」「夕焼けがリズムを刻んでいる」といった感想が多く、アニメという表現の中で“音”と“空気”を同時に感じさせた稀有なシーンとして語られている。
アリシアナの独奏 ― 完璧と孤独の狭間で
第4話では、アリシアナが放課後の音楽室でひとりギターを弾く場面が印象的だ。彼女は仲間と衝突した直後で、誰もいない教室に響くギターの旋律が孤独そのものを表している。 カメラは正面からではなく、窓越しの反射を通して彼女を映す。ガラスに映る姿は二重像のように揺れ、まるで“理想と現実の狭間にいる自分”を象徴している。 その直後、ドアの向こうから芹菜の「一緒に叩こうぜ!」という声が響く。アリシアナが顔を上げる瞬間、BGMが途切れ、静寂の中でドアノブが回る――この演出の緊張感は、7分アニメとは思えないほど映画的だ。 視聴者の多くが「この回でアリシアナ推しになった」と語り、彼女の心の壁が崩れる過程を象徴する名場面として愛されている。
学園フェス前夜の星空
第7話の夜、メンバーが学園フェスの準備を終えた後、グラウンドに寝転んで星を眺めるシーンがある。 セリフはほとんどなく、ただ風の音と小さな笑い声が続く。芹菜が「ここにいる全員の音、ちゃんと聞こえてるよ」と呟き、なずなが「そっか……なら安心」と微笑む。この短い会話が、彼女たちの信頼関係を静かに描き出す。 照明は星空とキャンプライトの2色のみ。光の粒がキャラクターの瞳に反射する演出は、まるで“夢と現実の境界”のようで、ファンの間で「アニメ史上もっとも美しい夜空」と評されるほど印象的だった。 この場面の後、物語はいよいよクライマックスへと突入する。
最終話:Change Our MIRAI! ライブシーン
『イロドリミドリ』を象徴する最大の名場面。それは間違いなく最終話のライブシーンだ。 開演前の静寂、ライトが落ちる瞬間、そして芹菜のカウント「One, Two, Three, Go!」――そこから始まる“Change Our MIRAI!(Live Ver.)”は、音楽アニメの歴史に残る名演出といえる。 ステージの光がメンバーの影を長く伸ばし、アングルは観客の視点とステージ上の視点を交互に切り替える。凪の指先、なるの跳ねるベース、アリシアナの瞳の奥――そのすべてが感情の爆発として描かれている。 ラストサビで観客のサイリウムが七色に変わる演出は、「イロドリミドリ」というバンド名の由来そのもの。音と光が完全に同期する中で、芹菜の笑顔がアップになる。 ファンからは「7分×8話でここまで泣かせるなんて反則」「最終回のライブ、何度もリピートしてる」といった感想が多数寄せられた。 あの瞬間、“アニメ”と“ライブ”の境界は完全に消え去っていた。
エンドロール後の小さな余韻
最終話のエンディング後、わずか10秒の“おまけ”シーンが用意されている。 学園フェスの翌朝、芹菜が教室の黒板にチョークで「ありがとう」と書き、スティックで軽く叩く――その音が静かな教室に響く。誰もいない場所で鳴る一打が、まるで視聴者へのメッセージのように感じられる。 この余韻に涙したファンは多く、「この静寂の一打こそ、最高のエンディング」とSNSで称賛された。音楽の始まりをスティックの音で描き、終わりもスティックの音で締めるという構成は、作品全体の完成度を見事に象徴している。
ギャグパートの名場面 ― “芹菜の伝説的カレー事件”
ファンの間では感動シーンだけでなく、ギャグ回の名場面も語り草だ。中でも第2話の“カレー爆発事件”はシリーズ随一のコミカルエピソード。 学園祭の屋台練習で芹菜が「私のカレーはスパイスの嵐だ!」と張り切るが、鍋の中で化学反応が起こり、教室が爆煙に包まれる。 アリシアナが「スパイスの量を何倍にしたの!?」と叫び、凪が無表情で「理論的にあり得ない」と呟く――この掛け合いがテンポよく続き、ネットでは「イロドリミドリ=カレー部」と呼ばれるほど人気の回となった。 作品の真剣さとギャグのバランスを象徴する、愛すべき場面の一つだ。
静と動、笑いと涙――“余白”が生んだ名場面たち
『イロドリミドリ』の名場面を特徴づけるのは、派手な演出だけではない。むしろ、静かな瞬間――キャラの呼吸、視線、風の流れ――そうした“余白の時間”こそが心に残る。 監督がインタビューで語ったように、「短い時間の中で何も起きない時間を作る勇気」がこの作品の演出哲学だった。 そのため、セリフのない数秒間が音楽の一部として機能し、視聴者が“次の音を待つ”ような感覚を覚える。まさに“音を聴くアニメ”という表現がふさわしい。 名場面とは、必ずしも大げさな盛り上がりを意味しない――『イロドリミドリ』はそのことを、繊細な演出で証明した作品なのだ。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
明坂芹菜 ― “笑顔と衝動”で物語を動かす主人公
視聴者から最も多くの支持を集めたのは、やはり主人公の明坂芹菜だった。彼女は常に明るく、失敗しても前向きで、時に突拍子もない行動をとるが、その無鉄砲さこそが仲間を動かす原動力になっている。 ファンの間では「芹菜がいると空気が明るくなる」「彼女の笑顔で1日頑張れる」といった声が多く、彼女の明るさがまさに“作品の心臓”として機能していることがわかる。 とくに第1話でスティックを掲げて叫ぶシーン、第8話で涙ながらに「音楽って最高!」と叫ぶ場面は、多くのファンにとって忘れられない瞬間となった。 彼女の声を担当する新田恵海の感情豊かな演技も人気を後押しし、「元気系キャラなのに泣ける」「感情の起伏が自然」といったコメントが多く寄せられた。 芹菜は、“努力と勢い”を象徴するキャラクターであり、視聴者の多くが自分の青春時代を彼女に重ねていた。
御形アリシアナ ― クールで情熱的な完璧主義者
アリシアナは、ファンの間で「憧れの女性像」として人気を博したキャラクターだ。クールで知的、そしてどこかミステリアスな雰囲気を持つが、実際には仲間思いで情熱的。 その二面性が多くの視聴者を惹きつけた。 彼女の人気を決定づけたのは、第4話の独奏シーンだ。孤独の中でギターを弾く姿に「美しすぎて息を呑んだ」「彼女の指先が感情を語っていた」といった感想がSNSに多数投稿された。 一方で、ギャグ回では意外な天然っぷりを見せ、「意外とツッコミが下手」「笑い方が貴族っぽい」とファンを和ませた。 “完璧な人間ではなく、努力して完璧を目指す姿”こそが、アリシアナの最大の魅力として多くの視聴者の共感を呼んだ。
天王洲なずな ― 癒しの象徴、作品の“呼吸”を担う存在
「なずなが出てくると空気が柔らかくなる」という意見がファンの間で多い。 彼女の穏やかな声、ゆったりとした動き、そして“焦らない”生き方が、視聴者に安心感を与える。特に忙しない日常を送る社会人視聴者の間では「なずなのマイペースさに救われた」「彼女のセリフを聞くと深呼吸したくなる」と語る声が多かった。 また、なずなは“支える側の主人公”という評価もあり、バンド内では調整役としての存在感を放っていた。 彼女が語る「音って、心が揃うときに一番きれいに響くんだよ」というセリフは、作品のテーマそのものを象徴している。 その包容力と温かさから、ファンの間では“舞ヶ原の母”と呼ばれることもあるほどだ。
小仏凪 ― 理性と情熱のバランスが生む魅力
凪は一見クールだが、内面には強い情熱と繊細な感受性を秘めている。ファンの間では「感情を出さないのに伝わってくる」「沈黙が言葉より雄弁」といった感想が多く、彼女の静かな存在感が高く評価されている。 特に印象的なのが、第5話で彼女が初めて感情を露わにする場面。 音のズレに苛立ちながらも、仲間に「あなたたちの音が好き」と告げるシーンでは、多くのファンが涙を流した。 SNSでは「凪の“好き”が破壊力ありすぎ」「普段冷静だからこそ刺さる」といったコメントが相次ぎ、彼女の人気は一気に上昇した。 また、ゲーム・音楽好きの視聴者層からは「DTMに詳しい女子高生という設定がリアルで好感」との声もあり、“理論派女子”としての魅力も支持されている。
箱部なる ― 破天荒で憎めないトリックスター
「毎回笑わせてくれる」「存在するだけで場が明るい」と言われる箱部なるは、まさに“ムードメーカー”の象徴だ。 彼女の行動は常に予測不可能で、時にはステージ上で転び、時には演奏中に叫び出す。だが、その自由さがバンドに命を吹き込んでいる。 ファンの間では、「なるがいるから真面目すぎない」「彼女の笑い声で疲れが吹き飛ぶ」といった感想が多く、元気系キャラながらストレスのない明るさで支持を集めた。 また、アリシアナとのコンビも人気が高く、SNS上では「なる×あーりん」でイラストを投稿するファンも多い。 エネルギッシュで少し危なっかしい、しかし人一倍仲間思い――そんな“自由人”なるの姿は、ファンの心に強く刻まれた。
月鈴那知&月鈴白奈 ― 姉妹の絆と対照的な魅力
姉妹キャラクターとして登場した月鈴那知と白奈は、それぞれ異なるタイプのファンを惹きつけた。 那知は天才肌でクール、白奈は努力型で心優しい。二人のやり取りは、完璧な姉と必死に追いつこうとする妹という構図で、多くのファンが「姉妹回が泣けた」と語っている。 特に第6話での姉妹セッションはシリーズ屈指の名シーンで、二人の音が重なった瞬間に涙した視聴者も多い。 ファンの間では「那知の不器用な優しさが好き」「白奈の成長が見ていて嬉しい」といった感想が多く、二人の関係性を象徴するように「音楽で繋がる姉妹」という言葉がSNSでトレンド入りした。
HaNaMiNaメンバー ― 次世代の希望と憧れ
後輩バンド“HaNaMiNa”のメンバーも根強い人気を誇る。特に五十嵐撫子は“次世代の芹菜”と呼ばれ、彼女のまっすぐな性格がファンの心を掴んだ。 彼女の「失敗しても笑えばいいじゃん!」というセリフは、まるで芹菜の精神を引き継ぐようで、多くのファンが「バトンが繋がった瞬間」と感じたという。 また、小野美苗の素朴な人柄、葛城華の努力家な面など、サブキャラにも丁寧な個性づけがなされており、「モブが一人もいないアニメ」と評されるほど。 後輩組の存在は、作品に“時間の流れ”を感じさせ、舞ヶ原という学校が“音楽で育つ場所”であることを印象づけた。
S.S.L.メンバー ― カリスマ性と知性の象徴
生徒会ユニット“S.S.L.”の面々は、カリスマ的な人気を誇る。特に芒崎奏は「美人でリーダーでカッコいい」と女性ファンからの支持が厚く、ネット上では「理想の先輩キャラ」として話題になった。 藤堂陽南袴のラップシーンは「2次元でこんなにカッコいいMCが見られるとは!」と絶賛され、彼女を推す“バカマ推し”も多数登場。 桔梗小夜曲の繊細で人見知りな性格も人気で、ファンからは「陰キャでも輝ける希望の星」と称された。 S.S.L.の3人は、作品内での“もう一つの理想形”として機能し、視聴者にとっての“憧れ”の象徴となった。
ファン層の推し傾向と人気構造
SNS分析を見ると、全体の人気傾向は「芹菜>アリシアナ>凪>なずな>なる>那知>白奈」という順で推移していたが、性別や年代によって推しが大きく分かれるのが特徴的だった。 男性ファンは芹菜・アリシアナ・なるのようなエネルギッシュ組を好み、女性ファンは凪・なずな・白奈のような内面型キャラを推す傾向が強い。 一方で、音楽経験者の間では凪と那知の人気が圧倒的で、「技術者視点で見て尊敬できる」との声も多かった。 キャラクター人気が“外見の可愛さ”よりも“音楽との向き合い方”に基づいている点は、この作品ならではの特徴であり、多くのアニメファンがその誠実な作りに感動していた。
総評:多彩な個性が奏でる“七色のハーモニー”
『イロドリミドリ』の魅力は、どのキャラクターも主役になれるほどの深みを持っていることだ。 一人ひとりが音楽を通して成長し、互いの“色”を認め合うことで、作品全体が“七色のハーモニー”として完成している。 ファンの声を借りれば、「推しが変わるアニメ」「見るたびに違うキャラが好きになる」と言われるほど、登場人物全員が輝きを放っている。 この多様性こそが、『イロドリミドリ』が今なお語り継がれる理由であり、音楽をテーマにしたアニメの中でも特に“キャラが生きている”と感じられる稀有な作品である。
[anime-8]
■ 関連商品
映像メディア ― アニメ本編のBlu-ray&DVD化
『イロドリミドリ』の放送終了後、最も注目を集めたのが映像パッケージの発売だった。アニメ本編を収録したBlu-rayは、セガ公式のECサイトおよび一部アニメショップで限定販売され、ファンの間では“保存版”として高い人気を誇った。 パッケージには全8話に加え、未公開映像「芹菜たちのリハーサル風景」が特典として収録されている。短編アニメながらも音響監督によるオーディオコメンタリーが入っており、制作現場の裏話や音楽演出の秘密などが語られているのも魅力だ。 また、初回限定版にはHisasiによる描き下ろしジャケットと、キャストサイン入りポストカードが同梱され、予約段階で完売した店舗も多かった。 ファンの中には「本編7分を何十回もリピートしている」「映像を止めて作画を研究している」という人もおり、短尺作品ながら圧倒的な“映像的完成度”が高く評価されている。
音楽CD・配信 ― “音”のアニメが生んだ数々の名曲
本作において最も重要な関連商品は、やはりサウンドトラックとキャラクターソングだ。 メインテーマ「Change Our MIRAI!」はアニメの枠を超えて人気を博し、YouTube公式チャンネルで公開されたMVは放送当時50万再生を突破。音楽ゲーム『CHUNITHM』プレイヤーの中でも“神曲”として知られる存在となった。 サウンドトラック盤では、アニメ用に再録されたスタジオミックスを収録。原曲とは異なるアレンジが施され、ファンからは「同じ曲なのに全く違う印象」「映像を思い出して泣ける」といった声が上がった。 さらに、キャラ別のソロ楽曲もリリースされ、芹菜の「Sky High Energy!」、アリシアナの「Re:Sound」、凪の「Silent Logic」など、それぞれの性格を反映した構成となっている。 ストリーミング配信も展開され、SpotifyやApple Musicなどで世界中から再生可能となったことで、“日本の音楽アニメの代表作”としての地位を確立した。
書籍関連 ― 設定資料集とビジュアルファンブック
アニメ放送後、ファンの熱い要望に応えて刊行されたのが『イロドリミドリ公式ビジュアルファンブック』である。 本書はキャラクターデザイン、衣装設定、美術背景、絵コンテの抜粋などをフルカラーで掲載。特にHisasiによる初期デザインラフや、監督・脚本のインタビューが好評だった。 中でも注目を集めたのは「各キャラの演奏フォーム設定資料」。手の角度や立ち姿勢などが実際の演奏者の監修で描かれており、“音楽アニメとしての本気度”が感じられる内容となっている。 ファンからは「この資料集を読むともう一度アニメを見たくなる」「ページをめくるたびに音が聞こえる」と高い評価を受けた。 限定版にはイロドリミドリのロゴ入りクリアファイルと、未公開イラストカードも付属しており、今でも中古市場では高値で取引されている。
グッズ・フィギュア ― カラフルで可愛いライブアイテム
アニメの人気とともに、キャラクターグッズの展開も急速に拡大した。 アクリルスタンド、缶バッジ、Tシャツ、ラバーストラップ、マグカップなど、主要キャラ5人を中心に多彩な商品が登場。特に制服姿とライブ衣装の2種類がラインナップされたことで、コレクション性が高まった。 中でも人気を博したのは、セガプライズから登場した“芹菜&アリシアナ プレミアムフィギュア”。ステージ衣装の造形が細かく再現され、スティックやギターの質感にもこだわった逸品だ。 また、ライブ演奏中の姿をミニサイズで表現したデフォルメフィギュアシリーズ「ちびイロドリ」は、ファンの間で“机の上のバンド”として愛されている。 グッズ展開は“カラフル”“ポップ”“青春”をキーワードに統一され、作品世界の雰囲気をそのまま手に取れるような魅力を持っている。
コラボイベント ― ゲームセンター&カフェでの展開
セガ直営アミューズメント施設では、アニメ放送期間中に『イロドリミドリキャンペーン』が開催された。 限定描き下ろしポスターの展示や、オリジナルステッカーの配布、プリントシール機とのコラボなど、ファン参加型の企画が多数展開された。 また、秋葉原のセガカフェでは期間限定コラボカフェがオープン。キャラクターをイメージしたドリンクやデザートが販売され、「アリシアナのホワイトモカ」「芹菜のエナジーソーダ」など、細やかな再現度が話題になった。 店舗内では楽曲のライブ映像が流れ、ファン同士が自然に語り合う交流の場となった。 このカフェイベントは特に女性ファンの来店が多く、「青春の続きを味わえる場所」としてSNS上でも好評を博した。
ゲーム連動 ― “チュウニズム”で広がる音楽体験
もともと『イロドリミドリ』は音楽ゲーム『CHUNITHM(チュウニズム)』から生まれた作品であり、その世界はゲーム内でも継続的に展開している。 アニメ放送後には「Change Our MIRAI! (TV Size)」「DETARAME ROCK&ROLL THEORY」など、アニメバージョンの楽曲がゲーム内に追加され、プレイヤーの間で再ブームを巻き起こした。 さらに、プレイ画面の背景にアニメのカットが挿入される特別モードも実装され、ファンは「自分の叩く音とアニメの世界が繋がる感覚が最高」と歓喜した。 その後も期間限定イベントとして“イロドリミドリフェス”が実施され、ランキング上位者には限定称号やデジタルバッジが贈られた。 このように、アニメとゲームが双方向に支え合う構造こそが、『イロドリミドリ』というプロジェクトの最大の特徴といえる。
同人・二次創作文化 ― ファンによる愛の継続
放送終了後も、『イロドリミドリ』の熱はファンの手で燃え続けている。 コミックマーケットでは“イロドリミドリオンリー”の同人誌やイラスト集が登場し、キャラの日常やアフターストーリーを描く作品が人気を博した。 Pixivなどのオンラインプラットフォームでは、アリシアナ×芹菜や凪×なずなといったペア作品が多数投稿され、公式以上に多様な解釈が広がっている。 ファン同士の交流も盛んで、SNS上では“#イロドリミドリFA祭”というハッシュタグでイラストを投稿する文化が定着。 このような“ファンが作品を奏で続ける”現象は、まさに『イロドリミドリ』が掲げる“音楽で繋がる世界”そのものを体現している。
コレクターズマーケット ― 限定品と希少グッズの価値
中古市場では、『イロドリミドリ』関連商品の価値が年々上昇している。 特にBlu-ray初回限定版や、アニメ放送記念ポスター、コラボカフェ限定コースターなどは高値で取引される傾向にある。 一部のコレクターの間では「セガ音ゲー史を象徴する文化資産」として扱われており、初期グッズをフルコンプリートする“音ゲー遺産コレクター”も登場した。 こうした動きは、単なる懐古ではなく“音楽とアニメが融合した時代の象徴を残す”という文化的価値の証明といえる。
総評:作品世界を支える豊かな“メディアの響き”
『イロドリミドリ』の関連商品群は、単なる商品展開ではなく、作品の“音”と“物語”を拡張するためのメディア的連鎖そのものだ。 アニメを見て曲を聴き、曲を聴いてグッズを手にし、手にしたグッズを眺めながら再びアニメを思い出す――そうした循環がファンの中で続いている。 この一体感こそが、『イロドリミドリ』が短編アニメでありながら長く愛され続ける理由の一つだろう。 すべての関連商品が“音楽で繋がる”というコンセプトに基づき、ファンの日常に彩りを与え続けている。 それはまさに、“イロドリミドリ=日常の中の音楽”という作品哲学の延長線上にあるといえる。
[anime-9]
■ 中古市場と現在の評価
Blu-ray初回限定版 ― プレミア化した“短編の宝石箱”
『イロドリミドリ』のBlu-ray初回限定版は、発売から数年を経た現在でも高い人気を維持している。特に描き下ろしスリーブとキャストサイン入りポストカードが付属した限定セットは、ファンの間で“幻の逸品”と呼ばれ、オークションサイトや中古専門店では定価の2~3倍で取引されることも珍しくない。 アニメ専門中古ショップでは「状態良好・帯付き」で1万円を超える価格をつける店舗もあり、発売当初からのファンのみならず、放送後に作品を知った新規層の需要も加わっている。 なぜこれほどまでに価値が上がったのか。その背景には、“短編アニメの中で完成度が群を抜いて高い”という再評価がある。ショートアニメの名作は数あれど、映像・音・物語の三拍子が揃った作品は稀であり、『イロドリミドリ』はその筆頭格として語られることが多い。 Blu-rayの高画質で見るライブシーンの光や反射表現は、放送当時の配信画質では味わえなかった魅力があり、“アニメ音響の教材”として購入するファンもいるほどだ。
サウンドトラック・キャラソンCD ― 音の深みと再生回数の伸び
サウンドトラックおよびキャラクターソングCDは、いずれも中古市場で根強い人気を誇る。特に『Change Our MIRAI!(Complete Edition)』は限定プレス数が少なかったため、現在では2,000~3,000円台で取引されることが多い。 加えて、ソロ楽曲を収録した『Irodorhythm! Vol.1~Vol.3』シリーズもファンの間で高く評価され、「アニメから派生したキャラソンとは思えない完成度」として音楽的価値を再認識する声が増えている。 近年では、アナログレコード版が少量生産でリリースされ、その限定盤は瞬く間に完売した。レコード特有の温かい音質とイロドリミドリの楽曲が相性抜群で、「デジタルミックスより感情が伝わる」とコアファンの間で語られている。 配信版の再生回数も右肩上がりで、特に「DETARAME ROCK&ROLL THEORY」はTikTokなどでアニメ未視聴層にまで浸透。音楽作品単体としての命を長らく保っている。
書籍・資料集 ― 美術的価値の再発見
『イロドリミドリ公式ビジュアルファンブック』は、発売当初から人気が高かったが、現在では一時的に市場から姿を消すほどの入手困難品となっている。中古価格は定価の約1.5~2倍に上昇しており、美術系学生やアニメーター志望者が“資料目的で探す本”としても知られている。 特に、Hisasiによる原案イラストと、アニメ化に際してのデザイン調整稿の比較ページは、キャラクター造形研究における貴重な教材とされている。 また、巻末の「監督・脚本座談会」では、7分尺で物語を成立させるための構成術が詳細に語られており、“アニメ脚本の教科書”として業界関係者からも評価されている。 このように、単なるファンブックではなく、アニメ制作技法を学ぶ専門資料として再注目されている点が、中古市場での高騰を支えている。
グッズ・フィギュア ― 限定生産品の“幻化現象”
アクリルスタンドや缶バッジなどの小物系グッズは流通量が比較的多いため価格は安定しているが、問題はフィギュア類だ。 特にセガプライズ版「芹菜&アリシアナ プレミアムフィギュア」は、箱付き未開封品がプレミア価格で取引されており、2025年現在では1体8,000円前後で落札されることもある。 加えて、コラボカフェ限定のグッズ(特にコースター・ランチョンマット)は、推しキャラによって価格差が大きい。アリシアナと芹菜が描かれたデザインは高騰傾向にあり、“推し経済”の象徴的アイテムといえる。 さらに、ファンの間では“全キャラアクスタコンプリート”を目指すコレクターも多く、フリマアプリでは“まとめ売り10点セット”が高額取引される例も少なくない。 このように、『イロドリミドリ』のグッズは単なるキャラアイテムを超え、“青春と音楽の記憶を手に取る象徴”として価値づけられている。
イベント記念品・非売品 ― コアファンが狙う秘蔵アイテム
特に希少価値が高いのが、イベント限定配布の非売品グッズである。 例として、秋葉原セガカフェで開催されたコラボイベントで配布された“イロドリミドリ特製ピック型キーホルダー”は、現在では中古市場で5,000円以上の値をつけることがある。 また、キャンペーン抽選で当選した「直筆サイン入り色紙」「限定Tシャツ」は、出回り数が極端に少なく、コレクターの間で“最難関アイテム”として知られている。 こうした非売品は、作品とファンの間にあった“一瞬の思い出”を具現化した存在であり、価格以上の感情的価値を持っている。 アニメグッズ市場において、これほど短期放送の作品が長期間プレミア化するのは異例であり、それだけ『イロドリミドリ』がファンに深く愛されている証拠といえる。
海外市場での再評価 ― “Colorful Harmony”としての普及
近年、英語圏やアジア圏のアニメファンの間で『イロドリミドリ』の評価が再び高まっている。 海外配信プラットフォームで英語字幕版が公開されたことにより、“Colorful Harmony”という英題で紹介され、短編ながら心に響く音楽アニメとして再発見されたのだ。 特に音楽を通じて友情や努力を描く構成が、文化を超えて共感を呼び、海外ファンのレビューサイトでは平均評価が4.7/5という高スコアを記録している。 また、アメリカや台湾のアニメイベントでは、同作のコスプレやファンアートも見られるようになり、限定グッズが輸入経由で再流通するケースも増加している。 こうした国際的再評価は、“セガ音楽ゲーム文化の輸出”としても重要な成功例とされている。
ファンによるアーカイブ活動 ― デジタル保存と共有の潮流
近年のファン活動では、Blu-ray映像や音源をもとにした“非公式アーカイブ企画”がSNS上で活発化している。 特定話のカット分析やライブシーンの作画トレース、BGMの波形解析など、愛と分析が入り混じった活動が多く見られる。 これらのファンアーカイブは著作権の範囲を尊重しながら、作品文化の継承として機能しており、研究者やアニメ学校関係者が参照するケースも増えている。 こうした“ファンによる保存”の意識は、短編アニメが消費される時代において、『イロドリミドリ』が例外的に生き続けている理由の一つだろう。 デジタル上で再生されるたびに新たな感想が生まれ、作品は形を変えて響き続けている。
総評:時間を越えて奏でられる“短編アニメの名曲”
『イロドリミドリ』は、単なるメディア展開作品に留まらず、“時間を越えて再評価される短編アニメ”として確固たる地位を築いた。 中古市場の動向は、そのままファンの熱量を映す鏡であり、商品が値上がりする理由は「希少性」よりも「作品愛の持続」にある。 Blu-rayを所有すること、CDを聴くこと、グッズを飾ること――それぞれが、ファンにとって“音楽を続ける行為”と同義なのだ。 2020年代後半の今なお、SNS上では「今日もイロドリミドリを見返した」「曲を聴くとまた泣いてしまう」という投稿が絶えず流れている。 この作品は放送から年月が経っても、決して色あせない。むしろ時間と共に輝きを増す、“アニメという名の旋律”として、多くの人の心の中で鳴り続けている。
[anime-10]
![覇権 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5488/4571164385488.jpg?_ex=128x128)
![伝説 豪華盤 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4962/4571164384962.jpg?_ex=128x128)
![イロドリミドリLIVE'18~第2話「Over the 7 Lights」~【Blu-ray】 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7284/4571164387284.jpg?_ex=128x128)
![部活 (豪華盤 2CD+Blu-ray) [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4436/4571164384436.jpg?_ex=128x128)
![イロドリミドリ LIVE'19 ~第3話「ON YOUR MARK」~【Blu-ray】 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7673/4571164387673.jpg?_ex=128x128)
![大賞 (2CD+Blu-ray) [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5723/4571164385723.jpg?_ex=128x128)
![【送料無料】伝説(豪華盤)/イロドリミドリ[CD+Blu-ray]【返品種別A】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/862/wwce-31496-7-b.jpg?_ex=128x128)

![推薦 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3989/4571164383989.jpg?_ex=128x128)
![覇権 [ イロドリミドリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5464/4571164385464.jpg?_ex=128x128)