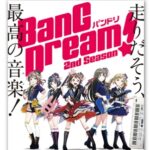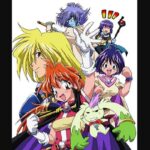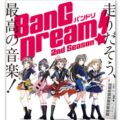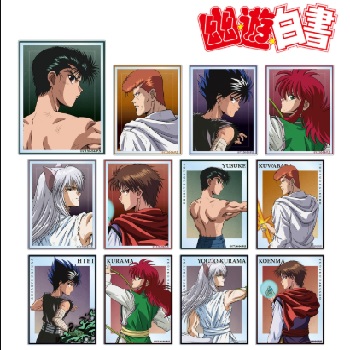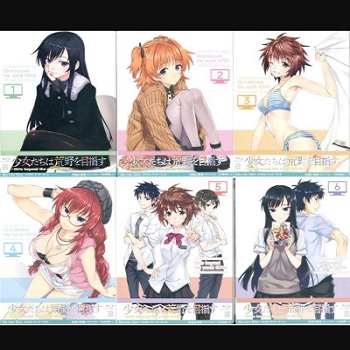【中古】 エガオノダイカ 1(Blu−ray Disc)/タツノコプロ(原作、アニメーション制作),花守ゆみり(ユウキ・ソレイユ),早見沙織..
【原作】:タツノコプロ
【アニメの放送期間】:2019年1月7日~2019年3月25日
【放送話数】:全12話
【放送局】:独立UHF局
【関連会社】:エガオノダイカ製作委員会
■ 概要
タツノコプロ55周年の節目に描かれた“もう一つの希望”
2019年1月7日から3月25日まで、独立UHF局を中心に放送されたテレビアニメ『エガオノダイカ』は、老舗アニメスタジオ・タツノコプロが創立55周年を迎える記念作品として制作された。タツノコプロといえば、『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカン』シリーズなど、数々のヒーローアニメを世に送り出してきた名門である。その長い歴史の中で、本作は“笑顔”という普遍的なテーマを、SF戦記というシリアスな舞台で描くという新しい挑戦を試みた意欲作だった。
制作陣は「笑顔」という言葉の持つ二面性に着目した。平和な国の象徴でもあり、時に自己防衛の仮面にもなるこの言葉を、戦争に翻弄される人々の生き様と重ね合わせながら、人間が持つ希望と絶望の両面を描いている。単に「笑顔を守るための戦い」ではなく、「笑顔を取り戻すための痛み」を真正面から描くという構成が、本作の根底に流れる思想だ。脚本を手掛けた猪爪慎一は、インタビューで「明るい未来を描くためには、暗闇の中にいる人々の姿をきちんと描く必要がある」と語っており、その言葉通り、作品全体に静かなリアリズムが貫かれている。
舞台設定:クラルスがもたらした光と影の惑星
物語の舞台は、地球から数万光年離れた星。そこでは、かつて地球を離れた人類が新天地を築き、複数の国家を形成していた。その中の一つである「ソレイユ王国」は、豊かな自然と平和を象徴する国として知られていた。だが、その繁栄を支えるのは「クラルス」と呼ばれる未知のエネルギー鉱石だった。クラルスは文明を発展させる光の源であると同時に、戦争兵器を動かすための燃料でもある。人類はこの力に依存することで繁栄を手に入れたが、その結果、クラルスをめぐる対立が生まれ、隣国「グランディーガ帝国」との戦争が始まることになる。
本作の世界観は、いわゆる「SFロボットもの」の形式を踏襲しつつも、極端な科学文明の末に訪れた倫理の欠落をテーマとしている。クラルスは単なるエネルギー資源ではなく、人間の欲望や罪の象徴としても描かれており、その扱い方が各国の思想や政治を映す鏡となっている。ソレイユ王国はクラルスを「人々の笑顔のために使う」理念を掲げるが、帝国側は「生存競争に勝つための力」として利用している。この価値観の衝突が、物語全体の駆動力になっているのだ。
物語構成:二人の少女が見る“同じ戦場の異なる風景”
『エガオノダイカ』の最大の特徴は、前半と後半で視点が大きく切り替わる二重構成にある。前半はソレイユ王国の王女・ユウキ・ソレイユの視点から始まり、明るく無邪気な少女が、戦争という現実を知らないまま「笑顔の国」を信じようとする姿が描かれる。しかし中盤以降、物語は帝国の兵士・ステラ・シャイニングの視点へと切り替わり、貧困と戦場で生き抜く彼女の目線から、“笑顔”がどれほど残酷な言葉になり得るかを見せつけてくる。
この構成は、タツノコ作品らしい「善悪二元論」の超越を目指すものであり、視聴者に両者の立場を体感させる仕掛けだ。王国と帝国、平和と侵略、守る者と奪う者——その対立の線引きは物語が進むにつれて曖昧になっていく。どちらの陣営にも「正義」があり、「笑顔」を守りたいという願いがある。戦争を描きながらも、最終的には「共感」を中心に据えた人間ドラマとして成立している点が、本作を単なる戦記アニメでは終わらせていない理由だ。
演出と映像表現:光と影が語る感情のドラマ
映像面では、監督・鈴木利正を筆頭に、緻密なディレクションが光る。背景美術は淡い光と柔らかな色調を多用し、王国の穏やかな空気を“絵画のような質感”で表現している。一方で、戦闘シーンにおけるクラルス兵器の発光や破壊描写は、冷たい青と鋭い白を基調にし、戦場の非情さを際立たせている。とくに注目すべきは、感情の転換点に合わせて画面構成を変える手法だ。ユウキが初めて「死」を目の当たりにする場面では、視界が狭まり、光源が彼女の背後に回ることで、“世界の中心が変わる瞬間”を直感的に伝えている。
また、キャラクターデザインを手掛けた梅下麻奈未の描線は、柔らかさの中に意志を感じさせるタッチで統一されており、少女たちの儚さと強さを両立している。戦闘ロボット「テウルギア」のデザインには、重量感と神秘性を両立させるために有機的な曲線が多用され、まるで“生きている機械”のような存在感を放つ。ロボットアニメという枠を守りながらも、感情表現を最優先する演出設計が徹底されている点が、本作の映像的魅力である。
テーマ:笑顔という理想と現実の交錯
タイトルにもある“エガオ”は、単なる感情表現ではなく、作品の哲学そのものだ。ユウキにとっての笑顔は、国民を守るための象徴であり、彼女が信じる「平和の証」。しかし、戦争によって次々と失われていく命を前に、笑顔を保つことは自己欺瞞にも変わっていく。一方のステラにとって笑顔は、生き抜くために身につけた“仮面”。人を殺さなければ生き残れない戦場で、笑っていなければ自分を保てないという皮肉な現実を映す。
この二人の対比を通じて、物語は“本当の笑顔とは何か”を探っていく。作中で繰り返されるセリフ「みんなの笑顔を守りたい」は、物語の進行に伴い意味を変化させていく。最初は純粋な理想、次第に苦しみの象徴、そして最後には赦しの言葉となる。この意味の変化こそが、『エガオノダイカ』というタイトルの真の意図を物語る。戦争や政治の枠を超えて、人間がどんな状況でも“笑顔であろうとする意志”を描いた点に、本作の普遍性がある。
音楽・音響が生む静かな余韻
音楽は伊藤翼が担当し、オーケストラとエレクトロニカを融合させたサウンドスケープを構築している。戦闘シーンでは金管の重奏が緊張感を煽る一方、ユウキやステラが内面と向き合う場面では、ピアノや弦楽器による静かな旋律が印象的に流れる。特に第12話で挿入される「星巡讃歌」は、シリーズを通して積み上げてきた希望と喪失のすべてを一曲に凝縮したような構成で、多くの視聴者の涙を誘った。
音響設計も秀逸で、無音の使い方が実に効果的だ。戦闘の爆音が消えた後の静寂、通信が途絶した瞬間の“間”が、登場人物たちの孤独や恐怖を語る。これにより、台詞以上に沈黙が物語を動かす瞬間がいくつも生まれている。音と映像の呼吸が合わさった時の緊張感は、タツノコ作品の中でも随一の完成度だ。
作品の意義と位置づけ:タツノコプロの新たな地平
『エガオノダイカ』は、単なる記念アニメではない。タツノコプロが長年築いてきた“正義の物語”の系譜に、新たな問いを突きつけた作品である。従来のタツノコ作品が描いてきた「守る者」と「戦う者」の図式を再構築し、現代社会における“希望の在り方”を模索した点にこそ意義がある。視聴者の中には、戦争描写の重さに戸惑う声もあったが、その痛みの中に“未来を信じるための勇気”を見出したファンも多い。
全12話という限られた尺の中で、戦争と平和、理想と現実、信念と喪失という複雑なテーマを緻密に描き切った構成は、まさに“記念作”の名にふさわしい完成度を誇る。ユウキとステラ、二人の少女の選択は、視聴者それぞれの心に異なる問いを残し続ける。戦争という絶望の中に、それでも笑おうとする人間の強さ——その光を描き切った『エガオノダイカ』は、タツノコプロの歴史に新しい1ページを刻んだと言えるだろう。
[anime-1]■ あらすじ・ストーリー
1. 平和な王国に生きる少女 ― ユウキ・ソレイユの無垢な日々
物語の始まりは、地球から遠く離れた惑星に存在するソレイユ王国。青く澄んだ空と穏やかな風に包まれたこの国では、王女ユウキ・ソレイユが、平和の象徴として国民に笑顔をもたらす存在として暮らしていた。彼女はまだ12歳。無邪気で好奇心旺盛、しかし幼いながらも王としての責務を学ぼうとしている。周囲には幼なじみのヨシュア・イングラム、教育係であり母代わりのような存在のレイラ・エトワール、そして国を守る騎士団長ハロルド・ミラーら、頼もしい大人たちがいた。 ユウキの世界は、まるで“戦争”など存在しないかのように穏やかだった。王城の中庭では花が咲き誇り、ユウキは民の笑顔を願って日々を送っていた。しかし、その平和は見せかけにすぎなかった。ソレイユ王国の国境では、すでにグランディーガ帝国との緊張が高まり、密かに戦端が開かれていたのだ。 ユウキの知らぬところで、国は崩壊へと向かい始めていた。
2. 戦争の影 ― 失われた笑顔とヨシュアの死
物語が静かに転調するのは、ヨシュアが国境地帯へ向かった日からである。彼は王国騎士団の若き戦士として最前線に派遣され、帝国の新型兵器に対抗する任務についた。だが、その戦いは圧倒的な差を前にして悲劇に終わる。激戦の末、ヨシュアは重傷を負い、ユウキの知らぬうちに命を落とす。彼の死は王国全体を揺るがせ、同時にユウキの心にも深い裂け目を残した。 「なぜ彼は帰ってこないの?」――彼女がその問いに向き合う時、初めて“平和な世界”が幻想だったことを知る。 ヨシュアの墓前で、ユウキは笑顔を失う。しかし同時に、彼の遺志を継ぐように「自分が民を守らなければ」という決意が芽生える。まだ子どもの彼女が、王国の象徴として立たねばならない瞬間だった。だが、その覚悟の裏には、誰にも見せられない恐怖と孤独が隠されていた。
3. 帝国の地で生きるもう一人の少女 ― ステラ・シャイニングの現実
視点は変わり、舞台はグランディーガ帝国へと移る。 ここで新たに登場するのが、17歳の兵士ステラ・シャイニング。幼い頃に家族を失い、記憶の一部を失った彼女は、生きるために軍に入隊し、戦場で生き延びる術を身につけていた。ステラは笑顔を作ることが癖になっていた。それは喜びではなく、防衛反応としての笑顔。冷たい現実を受け入れるために、自分を騙し続ける術だった。 彼女が所属するビュルガー分隊は、かつての激戦で仲間を多数失い、荒廃した戦場を渡り歩く部隊だった。新たに隊長として赴任したゲイル・オーウェンズは、厳格で無口な男。最初は反発しながらも、ステラや分隊員たちは彼の人間味に触れ、少しずつ信頼を深めていく。 帝国の兵士たちも、王国を憎んでいるわけではない。彼らもまた“家族を守るため”“生きるため”に戦っていた。敵と味方の境界が、ここで初めて視聴者の中で揺らぎ始める。
4. 鏡のような構成 ― 二つの物語が交錯する時
物語の後半では、王国のユウキと帝国のステラという、まったく異なる環境で育った二人の少女の視点が交互に描かれていく。 ユウキは王都防衛のために指揮を執る立場へと成長し、戦争の現実と真正面から向き合う。ステラは命令に従う兵士として、何人もの敵を撃ち、時に民間人を犠牲にして生き延びる。二人の間には直接的な接点はない。しかし、彼女たちは同じ空の下で、互いに“笑顔”という言葉を胸に戦っている。 この対比構成こそが『エガオノダイカ』の核心だ。 王女としての理想と、兵士としての現実。その距離が縮まるにつれて、二人の運命は静かに重なり始める。ユウキは民の命を守るために降伏を決断し、ステラは命令に背いて人を救う選択をする。立場は違えど、彼女たちが選んだ道の先には「誰かの笑顔を守りたい」という同じ祈りがあった。
5. 絶望と希望の狭間 ― クラルス停止計画
終盤、物語は惑星全体の運命を左右する決断へと向かう。 クラルスが生み出す無尽蔵のエネルギーは、同時に星を蝕む毒でもあった。その真実を知ったユウキは、戦争を終わらせるため、クラルスをすべて停止させる計画を立てる。クラルスが止まれば、兵器も文明も機能を失う。それは、世界を再び“無”に戻す行為だった。 ユウキの決意を知ったステラは、敵でありながらも彼女に協力する。レイラ・エトワール――ステラの実母でありながら、そのことを知らないまま――は、娘と知らずに彼女を守り、命を落とす。母の死とユウキの覚悟に触れたステラは、初めて“自分が生きる意味”を見出す。 最終話、崩壊する施設の中で二人は出会い、共にクラルス停止装置を起動する。彼女たちの行動は多くの犠牲を伴いながらも、戦争を終結へと導く。すべての兵器が止まり、静寂が訪れた惑星で、二人はただ微笑み合う。 その笑顔は、決して楽しいものではない。けれど、真実の痛みを知った者だけが浮かべられる、清らかな笑顔だった。
6. 終戦と再生 ― “笑顔の意味”が変わる瞬間
クラルスが停止した後、帝国と王国は停戦協定を結ぶ。荒廃した大地には新たな芽が芽吹き、かつて敵だった人々が共に街を再建し始める。ユウキは王国の再建を担い、ステラは孤児院で子どもたちと暮らしていた。二人はそれぞれの場所で、“笑顔”という言葉を再び信じようとする。 最終カット、ユウキが訪れたのは、かつてゲイルが運営していた孤児院。そこで出会った少女に、彼女は静かに語りかける――「笑顔はね、誰かのためにあるものなんだよ」。 物語はそこで幕を閉じるが、その言葉には本作の全テーマが凝縮されている。戦争を経ても、痛みを知っても、それでも人は笑おうとする。その笑顔こそが、未来を紡ぐ唯一の希望なのだ。
7. 構成の妙と視聴後の余韻
『エガオノダイカ』は、前半と後半で主人公が交代する構成を採用した珍しいアニメである。視点を完全に反転させることで、同じ戦争をまったく異なる立場から描き出し、視聴者自身に「正義とは何か」を考えさせる。しかもこの転換は唐突ではなく、物語の中盤でさりげなく行われ、気づけば“敵の物語”に共感している自分を発見する構造になっている。 この脚本構成は、戦争ドラマでありながら心理劇でもあるという独自性を生み出し、12話という短い尺の中で驚くほどの深みを実現している。最終回でユウキとステラが出会う瞬間、それまで積み重ねられた全ての悲劇が一点で交差し、“笑顔”というタイトルの意味が解き明かされる演出は見事の一言に尽きる。
8. 戦争のリアルと人間の希望
本作が他のロボットアニメと一線を画すのは、戦争を“悪”としてではなく“人間の選択の結果”として描いている点だ。どのキャラクターも理想を持ち、誰もが誰かを守ろうとしている。だからこそ、視聴者は誰も責めることができない。この構造は、近年のアニメ作品の中でも稀有な深さを持っている。 ユウキもステラも、最後には「笑顔のために」戦い、「笑顔のために」戦いを終わらせた。希望は簡単に手に入らない。だが、その希望を信じる心こそが、人間を人間たらしめる――。この作品が放送から数年を経ても語り継がれている理由は、まさにそのメッセージ性にある。
[anime-2]■ 登場キャラクターについて
ユウキ・ソレイユ ― 無垢と責任の狭間で成長する王女
物語の表側を照らす存在が、ソレイユ王国の王女ユウキ・ソレイユである。彼女は幼いながらも「民を笑顔にしたい」という純粋な理想を胸に抱き、平和を当然のように信じて生きていた。父王と母を早くに亡くした彼女は、育ての親のような存在であるレイラ・エトワールとハロルド・ミラーに支えられながら、まだ少女のまま王位継承者としての教育を受けていた。 しかし、ヨシュアの死によってその世界は崩れ落ちる。初めて経験する喪失は、彼女の中に“王女としての覚悟”と“ひとりの人間としての痛み”を同時に生み出した。以降、ユウキの笑顔は次第に“民を安心させるための仮面”へと変わっていく。 戦火の中で彼女は、自分の無力さを突きつけられ、それでも前を向こうとする。涙を流しながらも、誰かのために笑おうとするその姿は、作品全体の象徴である。最終局面では、戦争を終わらせるためにクラルスの停止を決意するが、それは同時に文明の崩壊を意味する選択だった。彼女は、王国を救うために自らの国を“滅ぼす”ことを選んだのだ。 その瞬間、ユウキというキャラクターは、単なる“理想主義の王女”ではなく、“覚悟をもった指導者”へと変化する。彼女の最後の笑顔には、悲しみも痛みも包み込みながら、それでも希望を信じる光が宿っている。多くの視聴者が彼女の成長に涙したのは、ユウキの選択が誰よりも優しく、誰よりも勇敢だったからだ。
ステラ・シャイニング ― 絶望の中で“笑顔”を覚えた兵士
もう一人の主人公ステラ・シャイニングは、ユウキの“鏡像”である。帝国軍の兵士として、荒廃した戦場を生き抜く彼女は、幼い頃に記憶を失い、孤児として育った。幼少期に経験した家庭内の孤立と冷遇は、彼女に「笑顔を作る」習慣を植え付けた。周囲に受け入れられるために、痛みを隠すために、彼女は常に笑っていた。 ステラは任務に忠実でありながら、心の奥底では「誰かのために生きたい」という想いを抱いている。だがその願いは、戦場では叶わない。仲間を守るために敵を殺し、命令を遂行するために民を犠牲にする。そのたびに、彼女の中の“笑顔”は意味を失っていった。 転機となるのは、隊長ゲイル・オーウェンズとの出会いだ。彼の不器用な優しさや、部下を想う言葉の数々が、ステラの凍りついた心を少しずつ溶かしていく。特に、ゲイルが命を懸けて部下を守った場面は、ステラにとって生き方そのものを変える契機となった。 終盤、ユウキとの邂逅によって、ステラは初めて“自分が守りたい笑顔”を見つける。かつては誰かに与えられた命令に従って笑っていた彼女が、最後は自分の意志で微笑む。その変化こそ、『エガオノダイカ』が描くもう一つの救いである。
ヨシュア・イングラム ― 理想の象徴と喪失の起点
ユウキの幼なじみであり、王国騎士団の若き戦士ヨシュア・イングラムは、物語の初期における“希望の象徴”だ。彼の口癖「気合と根性」は、古き良き熱血主人公を思わせるが、それゆえに彼の死は視聴者に強い衝撃を与えた。 ヨシュアは、ユウキにとって“戦うことの意味”を教える存在であり、同時に“戦争の犠牲”そのものでもある。彼がいなければ、ユウキは理想だけを掲げていられただろう。だが、彼を失ったことで、ユウキは現実と向き合うしかなくなる。 彼の死後、ユウキの部屋に残されたチェスの駒と未完成の戦術書は、彼が夢見た「共に笑える未来」を象徴している。直接的な登場シーンは短いものの、彼の存在は物語全体を貫く魂として残り続ける。
レイラ・エトワール ― 科学と母性の狭間に生きた女性
ユウキの教育係であり、同時にステラの実母でもあるレイラ・エトワールは、作品の中でも特に深い悲劇を背負った人物だ。かつては帝国でクラルスの研究を行っていた科学者だったが、テロ事件で夫を失い、ユウキを守る中で王国に仕えるようになった。 彼女は科学者としての冷静さと、母としての愛情の間で常に揺れている。戦争を止めたいという理性と、娘を守りたいという本能。その相反する想いが、彼女の行動を複雑にしている。 最終局面で、彼女はステラをかばって命を落とすが、その時も娘だとは知らないままだった。この皮肉なすれ違いは、物語全体の哀しみを象徴している。彼女の墓に刻まれた「WITH LOVE, THE OTHER MOM(もう一人の母より)」という言葉は、ユウキとステラ、二人の少女を繋ぐ架け橋として深く心に残る。
ハロルド・ミラー ― 現実主義の指揮官
ハロルド・ミラーは、ユウキの理想を支えながらも現実を突きつける存在だ。かつては理想に燃える騎士だったが、長年の戦争の中で多くの犠牲を目にし、現実主義者へと変わっていった。 彼はユウキにとって父のような存在であり、同時に最も厳しい教師でもある。彼の口癖「現実を見ろ」は、王国の崩壊が迫るたびに重みを増していく。 第9話での彼の最期は、作品屈指の名シーンとして語り継がれている。殿(しんがり)として敵軍を食い止め、最後にゲイルと相撃ちになる瞬間、彼の口元に浮かぶ微笑みは、“戦士としての誇り”と“父としての愛情”が交わる象徴だった。
ゲイル・オーウェンズ ― 戦場の父と呼ばれた男
帝国軍のビュルガー分隊を率いるゲイル・オーウェンズは、厳格で無愛想な軍人だが、その内側には深い人間愛があった。彼は孤児院を運営しており、戦争で家族を失った子どもたちを支援している。 ステラたち部下に対しても、口うるさく叱責しながらも、命を何よりも大切にしている。戦場での冷徹さの裏に、“誰かの笑顔を守りたい”という信念があるのだ。 彼の死はステラの成長に決定的な影響を与える。ハロルドとの戦闘で互いに命を落とす場面は、敵味方を超えた“理解”の瞬間として強烈な印象を残す。まさに、戦争という悲劇の中で生まれた“もう一つの父性”と言える存在である。
ビュルガー分隊の仲間たち ― 日常を彩る小さな光
ステラと行動を共にする分隊の仲間たちは、戦場における“人間らしさ”を象徴している。 リリィ・エアハートは、ステラを姉のように慕う明るい少女で、彼女の存在が分隊に温かみをもたらしている。 ヒューイ・マルサスは皮肉屋だが、内には仲間思いの優しさを秘め、時に自分を犠牲にして周囲を守る。 ピアース・ソーンは純朴で真面目な青年で、怪我により前線を離れるものの、最後まで仲間を想い続ける姿が印象的だ。 彼らの日常的なやり取りや冗談は、戦場という重い物語の中で唯一の“安らぎ”であり、人間の温もりを感じさせる場面として観る者の心を癒やしてくれる。
象徴としてのキャラクターたち
『エガオノダイカ』の登場人物は、それぞれが“笑顔”の異なる形を象徴している。 ユウキは「理想の笑顔」、ステラは「生き抜くための笑顔」、レイラは「母としての笑顔」、ゲイルは「守る者の笑顔」、ハロルドは「覚悟の笑顔」。それぞれの笑顔が重なり、戦争という悲劇の中に一本の希望の糸を通していく。 キャラクターの一人ひとりが、ただの登場人物ではなく、テーマの断片として配置されている点に、この作品の緻密な構成力が表れている。最終話でユウキとステラが見せた“あの笑顔”は、すべてのキャラクターの想いが結晶した瞬間だった。
[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
オープニングテーマ「エガオノカナタ」 ― 祈りのような出発点
本作のオープニングテーマ「エガオノカナタ」は、Chiho feat. majikoによって歌われた作品を象徴する一曲である。作詞は牧野圭祐とH△G、作曲・編曲は宮田“レフティ”リョウが担当している。この曲のタイトルにある「カナタ」という言葉は、“遠く離れた場所”を意味し、同時に“まだ届かない理想”をも象徴している。つまりそれは、ユウキとステラという、異なる場所に立つ二人の少女の距離そのものを示しているのだ。
イントロの透明感のあるピアノの旋律が、作品全体の幻想的な空気を一瞬で掴む。majikoの歌声は柔らかくも芯があり、サビで解き放たれる高音はまるで“祈り”のように響く。歌詞の中では「笑顔の向こうに光を探して」というフレーズが繰り返されるが、これはユウキの理想主義とステラの現実主義、その二つをつなぐ合言葉のようにも聞こえる。
オープニング映像では、王国と帝国の景色が交互に流れ、ユウキとステラのシルエットが重なっていく。静止画のような構図に動く光が差し込み、まるで“運命が少しずつ収束していく”様を暗示しているようだ。映像のラストでユウキが微笑み、ステラがその笑顔を見つめ返すカットは、彼女たちが直接出会う前から“心の中では繋がっている”ことを示す象徴的な演出である。
この曲のメロディラインは、優しさと悲しみの境界を漂うように構成されており、戦争という題材を扱いながらも、決して暴力的な印象を与えない。それどころか、「希望はまだある」と視聴者に静かに語りかけてくる。オープニングとしての役割を超え、物語全体の哲学を代弁する“もう一つの語り手”と言えるだろう。
エンディングテーマ「この世界に花束を」 ― 終焉と再生を繋ぐ旋律
エンディングテーマ「この世界に花束を」は、キミノオルフェが担当した曲で、作詞は蟻、作曲はKanata Okajimaと蟻、編曲はioniと菅原一樹によるもの。オープニングが“希望への願い”を表すなら、エンディングは“失われたものへの祈り”である。
静かに始まるギターとストリングスのアンサンブルは、戦争で傷ついた人々の心を包み込むような温かさを持つ。歌詞に登場する「枯れた花に水を注ぐ」という一節は、戦火の中でそれでも再生を信じる人々の姿と重なり、涙を誘う。
また、「あなたが残した笑顔が 今も私を照らしてる」というフレーズは、ヨシュアやゲイルなど、作中で命を落とした者たちの記憶が、残された者の中で生き続けていることを暗示している。
エンディング映像は、淡い光に包まれた風景と、幼い頃のユウキとステラの姿を思わせる二つの影が並んで歩くシーンで締めくくられる。そこには戦争の描写は一切なく、ただ穏やかな時間の流れがある。曲の最後にかすかに聞こえる風の音は、戦いの終わった世界の静けさを感じさせ、視聴者に深い余韻を残す。
このエンディング曲は、物語の各話を締めくくるだけでなく、視聴者の感情を「悲しみ」から「祈り」へと導く大切な役割を果たしている。毎回エンディングを聴くたびに、登場人物たちの命が確かに“そこにあった”と感じさせてくれるのだ。
挿入歌「星巡讃歌」 ― クライマックスを照らす命の歌
第12話で流れる挿入歌「星巡讃歌」は、Chiho feat. majikoによるもう一つの重要楽曲であり、物語の最終局面においてユウキとステラの行動を象徴する曲でもある。作詞はH△G、作曲・編曲は宮田“レフティ”リョウ。 この楽曲は、クラルス停止装置を起動させる直前、二人の少女が手を取り合うシーンで流れる。戦火が止むことのない惑星において、最後の希望として歌われるこの旋律は、まるで鎮魂歌と賛歌が一体となったような響きを持つ。
歌詞は抽象的ながらも、全体を通して“再生”と“赦し”をテーマとしている。「滅びの星に花を咲かせて」という一節は、戦争で荒れ果てた世界に再び笑顔を取り戻すというユウキの願いをそのまま言葉にしたものだ。majikoの繊細な声が震えるように伸び、サビで力強く放たれる瞬間、視聴者の胸にこみ上げる感情は計り知れない。
このシーンでは効果音が一切排除され、音楽と映像だけで全てが語られる。光が溢れる中でユウキとステラが微笑み合う描写は、“言葉を超えた理解”の象徴であり、まさにタイトル『エガオノダイカ』の結晶である。
「星巡讃歌」は放送当時、ファンの間で「涙なしには聴けない曲」と評され、SNS上でも“最後の3分が人生で一番泣けたアニメシーン”と話題になった。音楽と映像の融合が生み出すカタルシスは、タツノコプロの長い歴史の中でも屈指の完成度といえる。
楽曲群が織りなす物語のもう一つの層
『エガオノダイカ』における音楽は、単なるBGMや主題歌の域を超え、物語そのものを構成する“もう一つの脚本”である。オープニングは出発、エンディングは祈り、挿入歌は再生。それぞれが三幕構成のように配置され、音楽を通して視聴者が感情の流れを体験できるようになっている。 また、楽曲の制作陣が共通して“光”をテーマにしている点も注目に値する。宮田“レフティ”リョウが生み出す音の粒は、まるで夜空の星のように繊細で、どの楽曲にも一貫した透明感がある。これにより、作品全体のサウンドデザインが統一され、幻想的な世界観がより深まっている。
視聴者からは「音楽だけで泣けるアニメ」との声も多く、サウンドトラックは発売直後から高い評価を受けた。特に「星巡讃歌」は、アニメを知らないリスナーにも響く楽曲として音楽配信サイトで人気を博し、YouTubeなどでは“ファンメイドMV”が数多く制作された。
音楽が視聴者の心を動かし、再び作品世界へと引き戻す力を持つ――それこそが『エガオノダイカ』が持つ最大の魅力の一つである。
音楽を通じて描かれる“もう一つの笑顔”
三曲に共通しているのは、“笑顔”を単なる幸せの象徴としてではなく、“生きるための意志”として描いている点だ。 「エガオノカナタ」では、まだ届かない未来を信じる笑顔。 「この世界に花束を」では、失った者たちへの哀しみを包み込む笑顔。 「星巡讃歌」では、痛みを超えた希望としての笑顔。 それぞれの楽曲が、物語の三つの段階――理想・喪失・再生――を音楽で表現している。
この構成は非常に緻密で、まるで音楽自体がユウキとステラの心情を代弁しているかのようである。歌声の中にある“微笑みの震え”が、戦火の中でそれでも人を信じようとする彼女たちの姿と重なる。
エンディングの最後の一音が消えた後、残るのは静寂と温もり――それが、この作品における“エガオ”の真の形である。
■ 声優について
花守ゆみり(ユウキ・ソレイユ役) ― 少女の純真と王女の責任を両立する声
ユウキ・ソレイユを演じたのは、花守ゆみり。柔らかく澄んだ声質と、繊細な感情表現を得意とする実力派声優である。彼女の声は、まさにユウキというキャラクターの“無垢さ”と“脆さ”を象徴していた。 物語序盤では、まだ世界を知らない王女として、明るく無邪気に笑うトーンが中心。しかし物語が進むにつれて、花守の声色は次第に深みを帯びていく。ヨシュアの死を知った直後の震える声、民の前で微笑もうとする苦しげな息遣い、そして最終話で見せる静かな決意の声――そのすべてが成長の軌跡を音として刻んでいる。 彼女はインタビューで「ユウキは誰かを励ますために笑うけれど、その笑顔が自分を守る鎧でもある」と語っており、声の演技にもその意識が見て取れる。泣きながら笑うという難しい感情表現を、花守は台詞の“間”と“呼吸”で表現した。 特に最終話のラストシーン、ステラと共にクラルス停止装置を起動する直前の「これで、みんなの笑顔が守れるね」という台詞には、覚悟と安堵が同居しており、視聴者の心を強く揺さぶった。彼女の演技は単に“キャラクターを演じる”域を超え、“ユウキとして生きた”という印象を残す。
早見沙織(ステラ・シャイニング役) ― 冷静さの奥に燃える感情の炎
もう一人の主人公・ステラを演じたのは、早見沙織。彼女の透明感のある声は、多くの作品で知的かつ静謐な印象を与えてきたが、本作ではその声に“抑え込まれた激情”が宿る。 ステラというキャラクターは、感情を表に出さない兵士である。しかし、早見の演技は“感情を出さないこと”を演じるのではなく、“感情を押し殺していること”を伝える方向に舵を切っていた。その微妙なニュアンスの差が、彼女のステラを極めて人間的にしている。 戦闘シーンでの無機質な通信音声のようなトーンと、仲間を失った瞬間に滲み出る嗚咽。そのコントラストは圧巻だ。特に、レイラの死を目前にしたときの「やめてよ……もう、やめてよ……!」という叫びは、感情を抑えてきた彼女の限界が爆発する瞬間として、シリーズ屈指の名演と評されている。 また、最終話でユウキと共に装置を起動する場面では、声を張ることなく、静かに「行こう」と呟く。その声には、戦場を生き抜いた兵士の静かな誇りがこもっている。 早見の演技は、ステラという“無表情の中の人間味”を体現し、物語の後半を支える柱となった。
佐藤利奈(レイラ・エトワール役) ― 科学者の理性と母の愛情を声で両立
レイラ・エトワールを演じた佐藤利奈は、理知的で温かみのある声を持ち、作品に静かな重厚感を与えた。彼女の声のトーンは、物語における“安定”の象徴でもある。 レイラは、科学者としての理性と、母としての感情の狭間で揺れ動く難しいキャラクターだ。佐藤の演技はその二面性を巧みに表現しており、冷静な分析を語る場面では淡々とした口調で、ユウキを諭す場面では柔らかく包み込むような優しさを感じさせる。 そして最期のシーン、娘ステラを庇いながら命を落とす場面では、かすれた息遣いの中に「ユウキを……お願い」という台詞が紡がれる。その声は限界まで絞り出した“母の祈り”そのものであり、涙を誘った。佐藤の落ち着いた声質だからこそ、レイラの死は静かで崇高な印象を残す。
神奈延年(ハロルド・ミラー役) ― 戦場の信念を貫く低音の説得力
王国騎士団総長ハロルドを演じる神奈延年は、重厚で芯のある声で作品に現実感を与えた。彼の演技はまさに“戦場に立つ男”の説得力そのものであり、冷徹に見えて実は誰よりも民を想う人間味を持つハロルド像を完成させている。 彼の名演として語り継がれるのが、第9話の「前へ進め、王女陛下」という台詞。低く響く声にわずかな微笑を含ませ、死を覚悟した男の覚悟を一言で伝えた。神奈の落ち着いた低音は、緊迫した戦場シーンの中で強い静寂を生み出し、その後の戦闘音がより鮮明に響く演出効果も担っている。 また、ユウキとの対話シーンでは、声をわずかに柔らかくして“父のような温かさ”を漂わせるなど、細やかな感情のコントロールが際立つ。神奈延年の演技によって、ハロルドは単なる軍人ではなく“愛すべき導き手”として記憶された。
松山鷹志(ゲイル・オーウェンズ役) ― 無骨さの中に潜む優しさ
帝国側の象徴的存在・ゲイルを演じた松山鷹志は、その独特の低く温かい声で、無愛想ながらも信念に満ちた人物像を見事に作り上げた。 ゲイルは、戦争という状況下でも“命の尊さ”を忘れない人物であり、松山の演技はその優しさを声の奥に滲ませている。叱責するシーンでも決して怒鳴らず、淡々とした口調の中に「生きて帰れ」という想いが伝わる。 とくに戦死直前、ステラに「戦いの終わりを見届けてくれ」と告げる場面では、まるで父親が娘に託すような優しい響きがあった。視聴者からは「彼の声があったから、帝国側も人間味を感じられた」という感想が多く寄せられており、まさに作品全体のバランスを支えた存在である。
置鮎龍太郎(イザナ・ラングフォード役) ― 静かな知性で物語を引き締める
イザナ・ラングフォードを演じた置鮎龍太郎は、落ち着きと知性を兼ね備えた声の持ち主だ。彼の語り口は常に冷静で、戦況報告や政治的判断を行う場面では視聴者に安心感を与える。 しかし、その穏やかさの中には常に“死の覚悟”が潜んでいる。第10話で銃撃を受ける直前、「これで少しは役に立てるだろう」と微笑む台詞には、置鮎特有の余韻が宿り、静かな悲壮感を漂わせた。 彼の演技は大げさではなく、言葉の“間”で感情を語るタイプである。まさに「沈黙の中のドラマ」を感じさせる演技で、作品の重厚さを支えている。
早見・花守コンビの化学反応
本作を象徴するのは、ユウキ役・花守ゆみりとステラ役・早見沙織の“二重主演構成”だ。 この二人の声質はまったく異なる。花守は感情の起伏を柔らかく伝える声、早見は静かな中に熱を秘めた声。それが物語の前半と後半で対照的に配置され、まるで「光と影」が交互に照らし合うような演出になっている。 特筆すべきは最終話、二人の共演シーン。わずか数分の会話ながら、そこに積み重なった12話分の感情が凝縮されており、声の震えや呼吸までが演技の一部となっている。多くのファンが“声だけで泣けるアニメ”と評したのも、この場面の力によるものだ。
キャスティングの妙と全体バランス
全体としてのキャスティングは、実力派声優による“安定と深み”を重視した構成だ。主要キャラを経験豊富な声優が演じることで、物語に説得力を持たせ、サブキャラには個性派を配置して緊張と緩和を生んでいる。 また、戦場を描く作品でありながら、声優たちは叫び声や怒鳴り声を多用せず、抑えた芝居でリアリティを演出している点が特徴的だ。これにより、戦場の“静けさ”や“虚しさ”が強調され、他のロボットアニメとは異なる余韻を残す。
声が紡ぐ“笑顔”の記憶
『エガオノダイカ』の声優陣の演技には、共通して“静かな情熱”がある。誰もが大声で叫ぶことなく、心の奥底にある想いを声の震えや息遣いで伝えている。その繊細な演技が、物語のテーマである“笑顔の意味”をより深く浮かび上がらせているのだ。 最終的に、ユウキとステラの笑顔が視聴者の胸に残るのは、彼女たちを演じた声優たちが“本気で信じた笑顔”を声に乗せたからに他ならない。
[anime-5]■ 視聴者の感想
放送初期の印象 ― 「かわいい王女のアニメ」からの急転
『エガオノダイカ』が放送を開始した2019年1月、視聴者の多くは最初、王女ユウキ・ソレイユの無邪気な笑顔と鮮やかな色彩に惹かれた。「タツノコプロ55周年記念作品」という触れ込みもあり、王道のファンタジー冒険譚を期待したファンが多かったのだ。 SNSでは初回放送直後、「癒し系のアニメかと思った」「ユウキちゃんが可愛い」「背景がきれいで絵本のよう」という感想が相次ぎ、明るいトーンの作品という印象が広がった。 だが、第2話、第3話と物語が進むにつれて、その印象は一変する。王国と帝国の戦争が激化し、ヨシュアの死をきっかけにストーリーが急速に重くなると、「予想外にシリアス」「タイトル詐欺かと思った」「まさかこんな展開になるとは」という驚きの声が相次いだ。 特に第4話以降の展開は、SNSでトレンド入りするほど話題になり、視聴者の間では“裏切り系アニメ”として注目を集めるようになる。初見では軽い作品に見えて、実は戦争と倫理を正面から描く社会派ドラマだった――そのギャップが、多くの視聴者の記憶に強烈に刻まれた。
中盤の反応 ― 二重主人公構成への賛否
物語が帝国側の視点へ切り替わる中盤(第7話以降)では、評価が大きく分かれた。ユウキからステラへと主人公が交代する展開は、物語構成として非常に大胆であり、視聴者の戸惑いを招いたのも事実である。 「せっかくユウキの成長を見守っていたのに、いきなり視点が変わるのがもったいない」という意見がある一方、「敵側にも事情があるとわかって胸が締め付けられた」「この構成こそが作品の真骨頂」と絶賛する声も多かった。 特にステラの視点で描かれる帝国兵の生活は、それまで“敵”としか見えていなかった存在に人間味を与えたとして高く評価された。「彼女たちもまた笑顔を失った被害者だ」と共感する視聴者が増え、物語への没入度が一気に深まった。 アニメレビューサイト「MyAnimeList」や「アニメ!アニメ!」のコメント欄でも、「視点が変わる瞬間、タイトルの意味が理解できた」「この構成は挑戦的で勇気がある」といった意見が目立ち、作品の構成力そのものを評価する声が多かった。
終盤の反響 ― 涙と衝撃、そして静かな拍手
最終話の放送後、Twitterやアニメ掲示板では「涙が止まらなかった」「最終回で全てが繋がった」「タイトルの意味がわかって鳥肌が立った」という感想があふれた。 特にユウキとステラが手を取り合い、クラルス停止装置を起動する場面は、視聴者の間で“平成最後の名ラスト”と呼ばれた。戦争という絶望の中で、それでも笑顔を浮かべる二人の姿に、多くのファンが感情を揺さぶられたのである。 アニメファンの中では、「最終回の無音演出が完璧」「音楽と映像の融合が映画レベル」「最後の笑顔は永遠に忘れられない」といった称賛が相次いだ一方、「もっと長く見たかった」「12話では描ききれなかった部分がある」という惜しむ声も少なくなかった。 また、放送直後から“考察スレ”が立ち上がり、クラルスの正体やユウキとステラの関係性をめぐる議論が活発に行われた。「実は同一人物説」「クラルスは人間の感情エネルギー」など、多様な解釈がファンの間で共有され、作品の奥行きを示す結果となった。
SNSでの評価とファン層の特徴
『エガオノダイカ』は、放送当時からTwitter、Pixiv、YouTube、ニコニコ動画などで活発に話題になった。特に女性視聴者層とアニメ制作志向の若手クリエイターの支持が目立ち、作品分析やイラスト投稿が盛んだったのが特徴である。 ファンアートでは、ユウキとステラが手を取り合うイラストや、平和な日常を想像した“もしもエピソード”が数多く投稿された。中でも、「ユウキがステラに花束を渡す」構図のイラストは、ファンの間で象徴的なモチーフとして繰り返し描かれた。 また、SNS上では「戦争ものが苦手でもこの作品は見られた」「悲しいのに温かい不思議な感覚」というコメントも多く、重いテーマでありながら優しい余韻を残した点が高く評価された。 さらに、海外ファンからの反応も大きかった。英語圏では “The Price of a Smile”(原題の直訳タイトル)として配信され、「平和の代償を描いた哲学的アニメ」として議論が広がった。MyAnimeListのレビュー平均は7点前後と中堅だが、「静かに心を掴む佳作」として長く愛されている。
肯定的な意見 ― 「美しさと痛みの調和」
肯定派の意見として多く挙がったのは、「映像美とテーマ性の高さ」である。 戦争という題材を扱いながらも、血や暴力を過剰に描かず、あくまで“感情”と“選択”の物語として構成している点が、他のアニメにはない魅力とされた。特に女性視聴者からは、「登場人物全員に共感できる」「どちらの立場にも正義があるのがリアル」との声が多かった。 また、音楽の使い方や演出の繊細さも評価が高い。「星巡讃歌」が流れる最終話のシーンについては、「音と光だけで涙が出た」「セリフがなくても伝わる演出は芸術的」と絶賛され、アニメ誌の年間名シーン特集にも選出された。 一方で、キャラクターの感情描写が丁寧だったことも好印象を与えた。ユウキの成長やステラの変化を“演出ではなく心情で見せる”作りが、「丁寧に人を描いたアニメ」として支持されている。
否定的な意見 ― 「詰め込みすぎ」「尺の制約」
一方で、否定的な意見も存在する。最も多かったのは「12話では足りなかった」という声だ。 特に帝国編以降の展開が急ぎ足であった点について、「もう少しキャラクターの背景を描いてほしかった」「ゲイルやレイラの過去を掘り下げてほしかった」との意見が目立った。 また、一部の視聴者は「世界観設定が説明不足」「クラルスの正体や科学体系が曖昧」と感じたようだ。とはいえ、制作者側はインタビューで「すべてを説明しないことで、視聴者が考える余地を残したかった」と語っており、この点は意図的な演出でもあった。 物語が重すぎると感じた視聴者もおり、「もっとライトなストーリーを期待していた」「タイトルに“笑顔”が入っているからこそ、内容とのギャップに戸惑った」という声も一定数あった。
再評価の動き ― “静かな名作”としての定着
放送から数年が経過した現在、『エガオノダイカ』は“静かな名作”として再評価されている。 配信サービスでの再視聴が増え、YouTubeやSNSで「今見るとより深く刺さる」「この数年で最も印象に残ったアニメの一つ」と語るファンが増えている。 再評価の理由として、コロナ禍以降の社会情勢も大きい。分断、争い、そして“笑顔の重み”というテーマが、現実と重なって感じられるようになったのだ。 また、音楽や映像の美しさが高画質配信で再注目され、「Blu-rayを買い直した」「サントラを今でも聴いている」という声も多い。特に最終回のユウキとステラの会話シーンは、「数年経っても涙が出る」「自分の中の“希望”を思い出させてくれる」と語られることが多い。
総評 ― “笑顔の意味”を問い続ける作品
最終的に、『エガオノダイカ』は「派手さよりも静けさで語るアニメ」として記憶されている。 視聴者が最初に感じた“かわいい世界観”は、終盤にかけて“痛みを知った笑顔”へと変化していく。そのプロセスを12話で描ききったこと自体、極めて挑戦的な試みだった。 感想を総合すれば、肯定派も否定派も共通して「印象に残る」「考えさせられる」「一度見たら忘れられない」という点を挙げている。 つまり、『エガオノダイカ』は“好き嫌いを超えて心に残る作品”なのだ。終わった後も観る者の胸に問いを残し続ける――「あなたの笑顔は、誰のためのものですか?」というメッセージと共に。
[anime-6]■ 好きな場面
第1話「笑顔の王女」― 夢のような日常が始まりの光だった
視聴者の多くがまず心を掴まれたのは、第1話の序盤、ユウキ・ソレイユが青空の下で笑顔を見せるシーンである。 この場面はまさに作品タイトルの“笑顔”を象徴する瞬間であり、物語の出発点として印象深い。ユウキはまだ戦争を知らず、平和なソレイユ王国で友人や家臣たちと無邪気に過ごしている。カメラは彼女の表情を柔らかくアップで捉え、背景には淡い光が揺らめく。 この演出には、監督・鈴木利正の“静かな幸福感を視覚的に描く”という意図がある。視聴者はこの優しい時間に安心し、まるで絵本を読むような気持ちで彼女の笑顔を見守る。しかし、その幸福感こそが後の悲劇への伏線であることに、多くの人は気づかない。 放送当時、SNSでは「ユウキの笑顔が天使すぎる」「第1話の雰囲気だけで泣ける」という感想が並び、のちに「この笑顔がどれほど貴重だったかを後で痛感した」と語るファンも多かった。
第4話「ヨシュアの最期」― 優しさと喪失が交錯する衝撃の瞬間
シリーズ中でもっとも多くの視聴者が“心を抉られた”と語るのが、第4話でのヨシュア・イングラムの戦死シーンだ。 彼はユウキの幼馴染であり、王国を守るために自ら戦場へ赴く。しかし彼の死は唐突で、残酷なまでに静かに描かれる。爆音や派手な演出はなく、カメラは彼の倒れる姿を遠くから淡々と映す。その静けさが、かえって現実の重みを伝えてくる。 そして、戦場の通信を通じてユウキが「ヨシュア?」と呟く瞬間――その声には“信じたくない”という感情がにじむ。 このシーンではBGMが完全に消え、風の音と心臓の鼓動だけが響く。演出家の山本靖貴は後にインタビューで「音を抜くことで視聴者に呼吸の余地を与えた」と語っている。 視聴者の間では、「まるで自分がその場にいたような感覚」「静かなのに胸が張り裂ける」と高く評価された。この瞬間から、『エガオノダイカ』は“ただの戦争アニメではない”と印象づけられた。
第7話「ステラの微笑」― 無表情の少女が見せた小さな変化
帝国編の始まりを告げる第7話では、ステラ・シャイニングが初めて“心からの笑み”を見せるシーンが描かれる。 それは仲間たちと食事をしている何気ない場面。ゲイルやリリィたちの冗談に、彼女がほんの一瞬だけ口元を緩める――たったそれだけの描写だが、ファンの間で“奇跡の一コマ”として語り継がれている。 なぜなら、それまでのステラは常に無表情で、感情を封印して生きてきたからだ。その彼女がふと見せた小さな笑顔は、ユウキの“理想の笑顔”とは対照的に、“痛みを知った人間の笑顔”として映る。 視聴者の間では、「たった1秒の笑顔に救われた」「このシーンで涙が出た」との感想が相次ぎ、キャラクター成長の象徴として語られている。音楽は穏やかなストリングスが流れ、まるで日常の中に“希望の種”が芽生えたかのような余韻を残す。
第9話「ハロルドの最期」― 王女を導いた最後の背中
第9話の戦闘シーンで、ハロルド・ミラーがユウキに「民のためを思うなら、辛くとも前に進め」と告げ、殿を務めて戦死する場面は、多くのファンにとって“覚悟の瞬間”として印象的だった。 炎と煙の中、彼の機体が敵軍を食い止めるシーンでは、BGMに重厚な金管が流れ、画面全体が黄金色に染まる。その色は、まるで命を燃やす炎のようだ。 彼の最後の通信が切れたあと、ユウキが涙をこらえて「……進みます」と呟く。この短い一言に、彼女の成長と悲しみの全てが凝縮されている。 ファンの間では、「このシーンで作品を見直した」「ハロルドの生き様が美しすぎる」「あの“背中”が今でも忘れられない」と語られ、彼の墓石に刻まれた「WE GOT YOUR BACK」というメッセージが、作品を象徴する言葉として愛されている。
第10話「イザナの通信」― 命のリレーとしての言葉
第10話では、ユウキたちにクラルス研究の真実を伝えるため、イザナ・ラングフォードが命を懸けて通信を送るシーンがある。 通信の途中で銃弾を受けながらも、彼は笑って言う。「次に会う時は、酒に付き合え」と。 その瞬間、画面には通信ノイズが走り、声が途切れる。しかしその“途切れ方”があまりにも現実的で、視聴者は「本当に死を見届けたような感覚になった」とコメントしている。 この場面では、過剰な演出が排除され、むしろ“声”がすべてを語る。声優・置鮎龍太郎の静かな余韻のある声が、言葉以上の重みを与えている。 後にユウキがその通信を再生するシーンでは、BGMが再び流れ、彼の言葉が彼女の決断を導く。「死んでもなお、誰かを動かす声」というテーマがここに結実している。
第12話「星巡讃歌」― 二人の笑顔が世界を照らす
そして何よりも忘れがたいのが、最終話「星巡讃歌」のクライマックス。 ユウキとステラが手を取り合い、クラルス停止装置を起動する場面は、全話の感情が一気に爆発する瞬間である。 画面が光に包まれ、BGMとして「星巡讃歌」が流れ出す。歌詞の「滅びの星に花を咲かせて」は、まさにこの場面を予言する言葉だ。二人の手のひらが重なり、笑顔を交わす――その一瞬、戦争のすべてが静止し、音楽だけが流れる。 多くの視聴者が「声を出して泣いた」「このために全話を観てきた」と語り、YouTubeやX(旧Twitter)では“神回”のタグがトレンド入りした。 特筆すべきは、監督が意図的にBGMと照明のタイミングをずらし、最後の一音が消える瞬間に光が完全に白くなるよう設計した点である。その数秒の静寂が、彼女たちの“決意の笑顔”を永遠に封じ込めた。
余韻のエピローグ ― “笑顔”の意味を問いかけるラスト
物語の最後、ユウキが孤児院を訪ねるシーンもファンの間で語り草となっている。 ステラの姿はそこにないが、ゲイルの遺した子供たちの笑顔を見たユウキの微笑みには、確かな希望が宿っている。 ラストカットで映る青空と微風の音が、これまでの重い戦争描写を浄化するように響き、「この世界にも、もう一度笑顔が戻る」と感じさせる。 このラストを「完璧な静けさ」「優しい終わり方」と評するファンも多く、「悲しいのに救われるアニメ」として、長く愛される所以となっている。
視聴者が選ぶ名シーンランキングの傾向
後年行われたファン投票(アニメ雑誌企画・SNSアンケートなど)では、 1位:最終話のクラルス停止シーン 2位:第4話のヨシュアの死 3位:第9話のハロルドの最後 4位:第7話のステラの笑顔 5位:第1話のユウキの日常 という結果が多く見られた。 これらの上位シーンに共通しているのは、“静かな感情表現”である。激しい戦闘や派手な演出ではなく、あくまで“人の心”を描いた場面こそが印象に残る――それこそが『エガオノダイカ』という作品の本質なのだ。
[anime-7]■ 好きなキャラクター
ユウキ・ソレイユ ― 「純粋な笑顔」が象徴する希望の女王
ファン人気の頂点に立つのは、やはり物語の中心人物・ユウキ・ソレイユである。 彼女の魅力は、ただ“かわいい王女”であるという表面的な部分ではなく、「成長」と「覚悟」の物語を体現した点にある。序盤のユウキはまだ世界を知らず、笑顔だけで皆を幸せにできると信じていた。しかし、戦争の現実と大切な人の死に直面した彼女は、その笑顔を“痛みを知った強さ”へと昇華させていく。 この変化の過程を、視聴者はまるで親のような気持ちで見守った。SNS上では「ユウキが立ち上がるたびに泣いた」「彼女の涙が一番美しい」といった感想が絶えない。
また、彼女の“言葉”も印象的だ。
特に第11話の「私は戦いたくない。でも、みんなを守るために戦わなきゃいけない」という台詞は、多くのファンの心に残った。理想と現実の狭間で揺れるユウキの姿は、単なるアニメキャラを超えて、現代を生きる私たち自身の姿を映し出していたのかもしれない。
ファンアートや二次創作では、ユウキが“平和の象徴”として描かれることが多く、特に「花束」や「光」「星」をモチーフにした作品が人気を博している。彼女の名前“ソレイユ(太陽)”は、まさに物語の中で全てを照らす存在であった。
ステラ・シャイニング ― 戦場に咲く静かな勇気
もう一人の主人公・ステラ・シャイニングは、ユウキとは対照的な魅力を放つキャラクターである。 彼女は感情を抑え、任務を遂行することを第一とする兵士。しかし、その冷静さの裏には深い傷と孤独が隠されている。初めて視聴者が彼女の過去を知る回では、「ステラの人生がつらすぎる」「無理に笑う姿が胸に刺さる」と涙するファンが多かった。 ステラの“無表情”は無感情ではなく、“心を守るための仮面”だと後に明かされる。その仮面が少しずつ剥がれ、ユウキと出会って本当の笑顔を取り戻していく過程は、まさに『エガオノダイカ』の核心にあるテーマそのもの。
特に終盤、ユウキに向かって「どんな明日を君がもたらすのか、その可能性に賭ける」と言う場面は、シリーズ屈指の名台詞として知られる。この一言に、ステラがようやく“信じる勇気”を得たことが凝縮されているのだ。
放送当時、SNSでは「ステラが最後に笑った瞬間で泣いた」「彼女の笑顔が一番尊い」との投稿が相次ぎ、海外のファンの間でも「the soldier who learned to smile again(再び笑うことを覚えた兵士)」という愛称で呼ばれている。
レイラ・エトワール ― 科学者であり母、そして導きの存在
視聴者の間で静かに人気を集めたのが、ユウキの教育係でありステラの実母でもあるレイラ・エトワールだ。 彼女は理性的で穏やかだが、その内には誰よりも強い意志を持つ女性として描かれる。特に印象的なのは、第10話でユウキに語る「正しさだけでは、誰も救えないの」という言葉。科学者としての論理と、母としての感情――その狭間で揺れながらも、自分の信念を貫く姿が多くの視聴者に感銘を与えた。 彼女の人気は“母性”だけでなく、“知性”にも由来している。戦争を終わらせるために冷静に分析を続ける姿は、まさに“頭脳で戦う英雄”。その上で、最後には娘を守るため命を懸ける――その生き方は、視聴者に「愛の強さ」を改めて思い出させた。
ファンの間では、「レイラこそ真のヒロイン」「彼女の死で初めて泣いた」という感想が多く、年齢層の高い視聴者からの支持が特に厚い。
また、ステラが彼女の娘であることが明かされたときの衝撃と切なさは、多くのファンにとって“物語最大の感情の爆発点”となった。
ゲイル・オーウェンズ ― 無口な父性と人間の温かさ
帝国側の分隊長・ゲイルは、初登場時こそ厳格で冷たい印象を与えたが、回を追うごとにその人間味が滲み出てくる。 彼の人気の理由は、“戦場での優しさ”にある。部下に厳しく接しながらも、心の底では彼らを家族のように想っている。ステラを庇って命を落とす場面は、彼の無言の愛情の象徴だ。 ファンの間では、「ゲイルが死んだ回で泣いた」「彼の『戦いの終わりを見届けてくれ』という台詞が忘れられない」という声が非常に多い。 また、回想で描かれた孤児院のシーンも人気が高く、「彼が育てた子どもたちがステラの未来を照らす存在になっている」として、作品の“希望の種”を託した人物として称えられている。
リリィ・エアハート ― 無垢な笑顔が支えた帝国側の心
帝国分隊の紅一点・リリィも、視聴者から高い人気を得たキャラクターである。 彼女はステラにとって妹のような存在であり、重苦しい戦場の中で唯一“日常の温もり”を感じさせる存在だった。 リリィの魅力は、その明るさの裏にある繊細さだ。戦場で仲間を失いながらも、「ステラ姉がいるから大丈夫」と微笑む姿は、まさに“絶望の中の希望”。 最終話で彼女がゲイルの孤児院に戻り、子どもたちと笑うエピローグは、視聴者にとっての心の救済でもあった。ファンの間では「リリィの笑顔が本物の“エガオノダイカ”だった」と語られることも多い。
ハロルド・ミラー ― 忠誠と父性の象徴
王国側の将軍ハロルドは、“理想と現実の狭間で戦った男”として根強い人気を誇る。 若い頃から国を背負い続けた彼の姿は、ユウキにとっての「もう一人の父」であり、視聴者にとっても“重い責任を負う大人”の象徴であった。 特に第9話で彼が殿を務める際の「王女陛下、前へ進め」という言葉は、作品全体を通して最も多く引用されたセリフの一つである。 この台詞に、ファンたちは「泣かずにはいられなかった」「この言葉でユウキも、私も前に進めた」とコメントしている。彼の死後も、墓碑に刻まれたメッセージ「WE GOT YOUR BACK」はファンの合言葉のように使われ、SNS上で繰り返し共有された。
ファン層別の人気傾向とキャラ関係性の魅力
女性ファンの間ではステラ、男性ファンの間ではユウキとレイラの人気が特に高かった。 また、作品の“二人のヒロイン構成”が好まれ、「ユウキとステラの対比が最高」「どちらも欠けてはいけない存在」という声が多い。 一方で、「ユウキ×ステラ」という絆を“姉妹愛”や“魂のつながり”として解釈するファンも多く、SNSでは二人を並べたイラストや名言引用ポスターが数多く投稿された。 この作品におけるキャラ人気の特徴は、“単体での魅力”よりも“関係性で輝く”点にある。敵と味方、科学者と兵士、母と娘――そのすべてが繋がり合い、物語を成立させているのだ。
総評 ― 誰もが“笑顔”を背負っていた
『エガオノダイカ』のキャラクターたちは、誰一人として完全な善でも悪でもない。 それぞれが自分の信じる“笑顔”を守るために生き、そして戦っていた。 ユウキは“未来の笑顔”を、ステラは“亡き者たちの笑顔”を、レイラは“母の笑顔”を、ハロルドは“王国の笑顔”を信じていた。 視聴者はその多層的な“笑顔”の意味を通して、自分の中にもある「誰かを想う心」を再確認する。 それこそが、この作品が今なお多くの人の胸に残る理由であり、キャラクターたちが永遠に輝き続ける所以である。
[anime-8]■ 関連商品
Blu-ray & DVD ― 映像美と音の余韻を味わう決定版
『エガオノダイカ』のBlu-ray・DVDは、放送終了後の2019年春から夏にかけて全3巻構成で発売された。 ジャケットイラストはキャラクターデザインの中村直人が新規に描き下ろしており、ユウキとステラを中心に、全巻を並べると一枚の大きな絵になる仕様だ。コレクション性が高く、発売当初からファンの間では“飾るアニメBlu-ray”として人気を博した。
各巻には本編のほか、未公開映像・スタッフコメンタリー・ノンクレジットOP/ED・制作資料ギャラリーなど、充実した特典が収録されている。特に第3巻には、監督・鈴木利正と脚本家・猪爪慎一によるロングインタビューが収録され、作品制作の裏側や“タイトルの意味”が語られたことが話題になった。
ファンの間では、「このインタビューでようやく“エガオノダイカ”という言葉の重みがわかった」「監督が作品を通して語りたかったことが伝わる」といった感想が多く寄せられた。
また、Blu-ray版は音声がリニアPCMで収録されており、音楽と環境音の繊細な表現がテレビ放送時よりも格段に向上している。特に最終話の“無音からの音楽”の切り替わりは、「スピーカーから空気が変わる感覚」と評されたほどだ。
映像面でも、デジタルリマスターにより空や光の色合いがより深く再現されており、まさに“再び感動を体験できる”パッケージである。
サウンドトラック ― 光と影を紡ぐ音の世界
音楽担当・橋本由香利によるオリジナルサウンドトラック『THE PRICE OF A SMILE Original Soundtrack』は、2019年3月にランティスより発売された。 全25曲収録で、ユウキのテーマ「陽だまりの王国」、ステラのテーマ「静寂の兵士」、そしてクライマックスを彩る「星巡讃歌(インストver.)」などが収められている。
橋本はインタビューで「この作品では“音の呼吸”を大切にした」と語っており、旋律よりも空気や間を意識した作りになっている。
リスナーからは「BGMを聴くだけで涙が出る」「何気ない日常シーンの音楽まで意味がある」と高評価。特に人気の高いトラックは“交わる運命(Track12)”で、これはユウキとステラの視点が初めて重なる回で使用された曲だ。静かなピアノの旋律が重なり、二人の心の距離を音で表現している。
さらに、オープニングテーマ「エガオノカナタ」(歌:Chiho feat. majiko)とエンディングテーマ「この世界に花束を」(歌:キミノオルフェ)もCDシングルとして発売された。
前者は疾走感と希望を象徴する楽曲として、後者は静かな祈りを感じさせるバラードとして対照的な位置づけを持ち、どちらもファンに長く愛されている。特に「この世界に花束を」は、卒業式や結婚式などで使われたという報告もSNSで多く見られた。
書籍・ビジュアル資料集 ― 世界観を深く味わうファン必携の一冊
2019年秋に発売された『エガオノダイカ公式設定資料集』は、全160ページにわたりキャラクターデザイン、メカ設定、美術背景、脚本抜粋などが掲載された豪華本だ。 中でも注目されたのは、監督直筆メモによる「笑顔の定義とは何か」という制作初期コンセプトページ。そこには「笑顔=人間の尊厳」「光があるから影が生まれる」という言葉が書かれており、ファンの間では“聖書的資料”と呼ばれるほど象徴的な存在となった。
また、巻末には全話分の美術ボードと、クラルス装置の内部構造図が収録されている。これにより、作品中で曖昧だった科学設定を視覚的に理解できるようになり、「資料集で謎が解けた」と喜ぶファンが続出した。
Amazonレビューでも評価は非常に高く、「アニメをもう一度見返したくなる」「この本自体が芸術作品」といったコメントが並んでいる。
さらに、ムック本『アニメージュ・エガオノダイカ特集号』(2019年2月発売)では、声優陣の対談が掲載され、ユウキ役・花守ゆみりとステラ役・早見沙織の“笑顔論”がファンの間で話題になった。
早見は「ステラにとって笑顔は武器でもあり、救いでもあった」と語り、その発言は多くのファンがSNSで引用している。
グッズ展開 ― 日常に寄り添う「小さな笑顔」
グッズ展開は、アニメ放送と並行してアニメイト・ムービック・Amazon限定などで展開された。 主な商品は以下の通り: – キャラアクリルスタンド(ユウキ、ステラ、レイラ) – キャンバスアート(第12話ラストカットVer.) – 缶バッジコレクション全8種 – ミニタペストリー「星巡讃歌」デザイン – オリジナルマグカップ「笑顔の王国ロゴ入り」
中でも人気を集めたのは、ユウキとステラが背中合わせに立つアクリルスタンド。二人の表情がわずかに異なり、並べると“笑顔の意味”が対比的に浮かび上がるという粋なデザインだった。
また、クラルスをモチーフにしたペンダントチャームも女性ファンの間で好評で、「普段使いできるアニメグッズ」として再販希望の声が多数寄せられている。
限定特典付きBlu-rayを購入すると、非売品のポストカードセットが付属し、これが後にプレミア化。オークションサイトでは一時期高額で取引されていた。
コラボ企画・展示イベント ― ファンが作品世界を“体験”する場
放送当時から数ヶ月にわたり、東京・アニメイト秋葉原本店では「エガオノダイカ展」が開催された。 展示では原画や設定資料のほか、ユウキとステラの実寸大スタンディを設置。来場者が並んで写真を撮れるフォトスポットが人気を博した。 また、BGMが流れる特設シアターでは、最終話の“星巡讃歌”シーンを大画面で再生し、観客が静かに涙する光景が見られたという。
2020年以降には、アニメ放送1周年記念としてオンライン配信イベント「エガオノリユニオン」が実施され、キャストトークや朗読劇、音楽ライブが行われた。
花守ゆみりと早見沙織の朗読コーナーでは、新規書き下ろしエピソード「笑顔の記憶」が披露され、「ユウキとステラのその後」が少しだけ描かれた。この朗読劇は視聴者から「涙が止まらない」「まさか続編の片鱗が聞けるとは」と絶賛された。
さらに、2022年にはタツノコプロ創立60周年記念として、過去作品との合同展「TATSUNOKO UNIVERSE」内で『エガオノダイカ』の特設コーナーが設けられ、スタッフによるサイン入り台本が展示された。
ファンアイテムとコミュニティの広がり
グッズの枠を超え、ファンによる自主制作アイテムも盛んであった。 同人イベントでは「星巡讃歌ノート」や「ユウキ&ステラ メモリアルカード」などのハンドメイドグッズが販売され、公式が後に一部を参考にして公式グッズを出したという逸話も残っている。 オンライン上でも、ファン主導の寄せ書き企画「#EGAOproject」が開催され、世界中のファンが“笑顔”の写真とメッセージを投稿。 このハッシュタグは2020年時点で10万件を超える投稿数を記録し、タツノコ公式アカウントも「皆さんの笑顔が、作品の続きです」と感謝コメントを寄せた。
総評 ― 作品の“余韻”を形にした商品群
『エガオノダイカ』の関連商品は、単なる販促ではなく、“作品の余韻を生活の中に持ち帰る”というコンセプトで統一されている。 Blu-rayは映像の静謐さを再現し、サウンドトラックは音の呼吸を感じさせ、グッズや書籍はファンの心に寄り添う――そのすべてが、「笑顔の記憶を残すための媒体」として設計されているのだ。 結果として、『エガオノダイカ』は単なるアニメではなく、“体験としてのアート作品”へと昇華した。今なお関連商品が再販・再注目されているのは、その完成度と普遍性の証でもある。
[anime-9]■ 中古市場と現在の評価
中古市場での動向 ― 「静かに息づく名作」の証明
『エガオノダイカ』のBlu-ray・DVDは、発売から数年が経過した現在でも一定の人気を保っている。 2025年現在の中古市場を見ても、第1巻~第3巻セットでおおむね6,000~8,000円前後で取引されており、アニメの単巻作品としては安定した水準を維持している。発売当初の定価が各7,000円前後だったことを考えれば、プレミア化はしていないものの“手放されにくい作品”であることがわかる。
中古ショップでは、特に初回限定版の特典ブックレットや描き下ろしジャケットが付属した状態のものが人気で、コンディションが良いものは1万円以上で販売されるケースもある。アニメイトオンラインや駿河屋などの中古データでも、定期的に在庫が一掃される傾向が見られ、“根強い需要”が存在しているのが特徴だ。
また、Blu-rayを購入したファンの多くが「手放したくない」と語っている点も特筆すべきだ。SNSでは、「再生するたびに初心を思い出す」「自分にとってお守りのような作品」との声が多く、作品そのものが“コレクションではなく心の資産”として扱われている。
一方、DVD版はやや値下がり傾向で、レンタル落ち商品なども多く出回っているが、それでも再生回数が多い中古ディスクでも動作良好なものが多く、ファン層が丁寧に扱ってきたことがうかがえる。
サウンドトラックと主題歌CDの人気 ― 音楽の再評価
オリジナルサウンドトラック『THE PRICE OF A SMILE Original Soundtrack』は、中古市場で定価を上回る価格で取引されることもある。特に新品未開封品は2,500~3,500円前後で安定し、状態が良いものはコレクターアイテムとして需要が高い。 理由の一つは、近年の“癒し系インスト音楽”ブームだ。配信や作業用BGMとして人気が高まり、「静かな希望を感じる音楽」としてYouTubeやSpotifyでもリスナーが増えている。ファンの間では、「このサントラは戦争アニメというより祈りの音楽」と評され、再評価のきっかけとなった。
また、オープニングテーマ「エガオノカナタ」とエンディング「この世界に花束を」は、シングルCDだけでなくデジタル配信版のDL数が伸び続けており、今ではカラオケ配信でも一定の人気を保っている。
特にmajikoが歌う「エガオノカナタ」は、“勇気を出して前に進む女性像”の象徴としてTikTokで引用され、若年層の間で再注目されている現象もある。
グッズ・フィギュア市場 ― “手元に置きたい”という想いの継続
グッズ市場では、当時販売されたアクリルスタンドやポストカードが2020年代中盤になっても一定の人気を維持している。 特に人気が高いのは、「ユウキ&ステラ 連携スタンドセット」と「星巡讃歌キャンバスアート」。これらは生産数が少なかったため、現在では中古でも入手困難で、オークションサイトでは定価の2倍以上で落札されるケースもある。
興味深いのは、グッズが“鑑賞用”ではなく“日常の一部”として扱われている点である。
SNS上では、アクリルスタンドをデスクに飾って「今日もがんばろう」と自分を励ます投稿が多く見られ、まさに作品のメッセージである“笑顔のために生きる”が現実に浸透していることを示している。
さらに、ファンメイドのガレージキットや3Dプリント作品も少数ながら登場しており、個人クリエイターによってキャラクターたちが“新しい形で蘇る”動きも続いている。
再放送・配信による再評価 ― 時代と共鳴するテーマ
2020年以降、『エガオノダイカ』は配信サービス(dアニメストア、Amazon Prime Video、U-NEXTなど)で継続的に視聴可能となり、再評価の波が広がっている。 特に2022年のタツノコプロ60周年記念特集で再配信された際、「今見ると泣ける」「あの頃よりずっと刺さる」との声が相次いだ。
コロナ禍を経て“当たり前の日常が失われる痛み”を経験した視聴者にとって、本作の「笑顔を取り戻す」テーマはよりリアルに響いた。SNS上では、「ステラの表情が今の社会を象徴している」「“エガオノダイカ”はただのタイトルじゃなく、生き方の指針」と語る投稿も多い。
こうした再評価の動きにより、2023年頃から新規ファンが増加し、Blu-rayの中古需要やサウンドトラックの再注目にも繋がった。
さらに、英語圏や東南アジア圏のアニメコミュニティでも、英題 “The Price of a Smile” が再び注目されており、「A hidden gem(隠れた名作)」として紹介される機会が増えた。海外レビューサイトでは2024年時点でMALスコア7.3→7.6へと微上昇しており、じわじわと認知が広がっている。
ファンコミュニティの持続と創作活動
放送終了後から数年経っても、ファンコミュニティは静かに活動を続けている。 Pixivでは今なお「#エガオノダイカ」タグ付きの新規投稿が月に数件あり、特に記念日(放送開始日1月7日、最終回3月25日)には“追悼と祝福”を込めたイラストが多く投稿される。 また、同人誌即売会「COMITIA」では、二次創作サークルが定期的に短編小説や詩集形式で作品を発表しており、ユウキとステラの“その後”を描く物語が今も作られ続けている。
2024年には、ファン有志によるオンライン企画「#EGAOReunion2024」が開催され、世界中のファンが笑顔の写真と「私にとっての笑顔の代価」というメッセージを共有。1週間で1万件以上の投稿が集まり、タツノコプロ公式も「この作品はまだ終わっていない」とコメントを出した。
このように、ファンが“受け取った想い”を再び他者に渡す動きが続いており、それ自体が本作のメッセージを体現している。
アニメ史における位置づけ ― “静かな名作”から“思想的アニメ”へ
『エガオノダイカ』は、2010年代後半のアニメ群の中でも特異な存在である。 同時期の作品が派手なアクションや強烈なキャラクター性で注目を集めていた中、本作は“静けさ”“余白”“思考”を重視した。 評論家の間では「ポスト“少女終末旅行”的アニメ」とも評され、戦争を題材にしながらも、破壊ではなく“再生”を描いた稀有な例として挙げられる。
また、“二重主人公構成”という構造的挑戦も高く評価されている。敵と味方の両視点を対等に描いた点は、近年の群像劇アニメの流れを先取りしていたとも言える。
加えて、作品全体が“無垢な笑顔”と“痛みを知る笑顔”という二つの象徴によって構成されていることは、アニメ史的にも極めて哲学的だ。
2025年現在では、アニメファンの間で「再評価してほしいアニメ10選」などのランキングに名を連ねることが多く、“知る人ぞ知る傑作”という位置づけを確立している。
Blu-ray再販やサブスク配信の継続、そしてファンによる草の根的な支持によって、『エガオノダイカ』は“時間に耐えるアニメ”として静かに輝き続けている。
総評 ― 「笑顔」というテーマの普遍性
中古市場や再評価の動向を見ても、『エガオノダイカ』の魅力は消えていない。 派手な人気ではなく、静かに息づく熱――それこそが本作の真価である。 視聴者に問いかけられる「笑顔とは何か」「誰かを想うとはどういうことか」というテーマは、時代が変わっても色あせない。 だからこそ、ファンは今もBlu-rayを棚に並べ、サントラを聴きながら、ふとした瞬間にこの作品を思い出すのだ。
ユウキとステラが最後に交わしたあの笑顔は、スクリーンの中で終わったわけではない。
それは今も、彼女たちを愛したすべての人の心の中で生き続けている。
――「エガオノダイカ」とは、終わりではなく、“笑顔を受け継ぐ物語”なのだ。

![エガオノダイカ Emotional side【単行本版】1【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2331/2000007792331.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side【単行本版】2【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2314/2000007792314.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side【単行本版】3【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2313/2000007792313.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side14【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7748/2000007657748.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side7【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1383/2000007451383.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side16【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2262/2000007792262.jpg?_ex=128x128)
![エガオノダイカ Emotional side15【電子書籍】[ いわや晃 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8771/2000007728771.jpg?_ex=128x128)