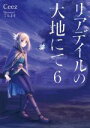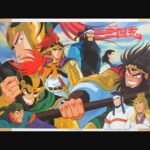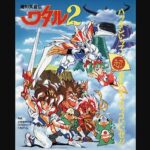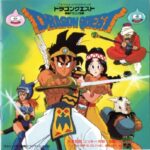【中古】モバイル雑貨 01.ケーナ&リット モバイルアクセサリーケース 「リアデイルの大地にて」
【原作】:Ceez
【アニメの放送期間】:2022年1月5日~2022年3月23日
【放送話数】:全12話
【放送局】:独立UHF局
【関連会社】:MAHO FILM、ランティス、リアデイル製作委員会
■ 概要
作品の立ち位置と“一歩目”
VRMMOを舞台にした異世界転生群像のなかで、『リアデイルの大地にて』は「圧倒的に強い主人公が、力づくではなく“生活”で世界をほどいていく」緩急で差別化されたタイトルだ。ハイエルフのケーナは最強格だが、物語が推進力を得るのはド派手なバトルよりも、人々と食卓を囲み、古い約束を手当てし、200年の“空白”に置き去られた関係を縫い直す場面からである。軽妙なユーモア、ほどよいお節介、そして時折の胸に刺さる回想が、温度差の少ない柔らかな作品体験を生む。
放送・メディア展開の骨子
アニメは2022年1月5日~3月23日に独立UHF局系でオンエア。ライトノベル発のメディアミックスとして、原作の生活感ある描写とゲームシステムの記憶を“人間関係の文法”へ翻訳することに注力した構成が特徴だ。1クールの中で出会い→寄り道→再会→緩やかな真相の気配、という循環を繰り返し、毎話の小目標(依頼・騒動・旅先の課題)を気持ちよく解決することで、見終わった後に微かな達成感と余韻が残る造りになっている。
主人公ケーナの“二重の記憶”
ケーナは「リアルの記憶」と「ゲーム時代の記憶」の二重写しで世界を見る。視聴者は、彼女が“かつてのプレイヤー仲間の痕跡”や“自分が残した塔・仕掛け”と再び出会うたび、〈世界は続いてきた〉という手触りを受け取る。最強設定は彼女のドラマを奪わない。むしろ、圧倒的な力をどう扱うか――見せびらかすのか、隠して日常に溶かすのか――という倫理が、毎回の選択の端々に滲む。
世界観:ゲームの残響から生活圏へ
この世界は“ゲーム由来のルール”が沈殿し、もはや“生活の常識”として固まっている。古塔の試練、里子システム出身の人物、アイテムやスキルの名残……それらはメタな仕掛けではなく、街路や市場、学舎や宗教制度の“地層”として描かれる。アニメ版は美術背景と間(ま)の取り方に余裕があり、にぎやかな市井と森の静けさ、工房の温度感まで画面に乗せることで、冒険と家事・育児が同じ生活線上にあることを伝える。
語り口とトーン:ゆるやかなコメディ+情の折り目
本作の笑いは“身内ノリ”に寄りすぎない。スカルゴの過剰な母至上主義、マイマイの直球すり寄り、常識人カータツのツッコミ――いずれも行動や社会的立場とのギャップでコメディが立ち上がる。そこに、ケーナの「保護者としての視線」が一枚布のように重なり、保護対象は子どもに限らず、迷子の王子や不器用な冒険者、価値観のずれた旧友まで広がっていく。軽口の直後に、ふと胸に残る一言を置く配剤がうまい。
テーマ:喪失の埋め方と“関係の再起動”
核にあるのは喪失の反転だ。リアルを失った少女の、ゲーム世界での再生。だが“取り返し”ではなく、“関係を初期化せずに再起動する”選択を彼女は続ける。200年の経過は残酷だが、ゼロベースには戻らない。残された遺物、語り継がれた評判、歪んだ伝説――それらを肩の力を抜き、必要なところだけほどいて結び直す。結果として、異世界ものにありがちな征服・統治の物語線は前景化しない。生活を営むことが、世界のチューニングでありケーナの救いでもある。
アニメ技法の見どころ
1クールで世界を一望するため、レイアウトは“地点”の印象づけを優先。銀の塔、王都、辺境、湖の塔……音と色で各地の記憶フックを作り、再訪時に即座に“戻ってきた感”が立ち上がる。アクションは必要十分に切れ味を出しつつ、過度に尺を割かない。むしろ静的な芝居で人間関係を張り直すカット割りにこそセンスが光る。OP/EDの手触りは物語の“やさしい重力”を補強し、視聴者の週一リズムに寄り添う。
視聴体験のタイプ分け
・日常癒やし型:料理・談笑・お風呂・買い物・小さな事件の解決で満たされる層 ・世界史好き型:ゲーム時代のギルドや塔の系譜、国家間の配置といった“地図の裏面”が楽しい層 ・キャラ観察型:里子三人の凸凹や、元プレイヤー勢の“中の人”事情にニヤリとする層 いずれも満たすが、入口は“癒やしと再会”に置かれているため、重厚長大な戦史よりも、今日の暮らしの体温が先に届く。
こんな人に刺さる
・最強主人公でも“踏まない”“壊さない”を選ぶ物語が好き ・派手さより、じんわり積もる満足感を求める ・ゲーム要素は“ギミック”より“歴史”として効いてほしい
総括(概要の要約)
『リアデイルの大地にて』は、VRMMOの残響と、人の営みの現在地をやさしく接続する。力を誇るのではなく、関係を直す。大事件は通り過ぎ、台所が主戦場になる。だからこそ、1話ごとの小さな決着が、視聴者の一週間をふっと軽くする――そんな、肩の力が抜けた“再起動譚”である。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
生命維持装置の停止から始まる“静かな死”
物語の原点は、少女・各務桂菜(かがみけいな)の「終わり」から始まる。現実では重度の事故により寝たきりとなり、機械の助けがなければ呼吸すら叶わなかった。唯一、彼女が心を自由にできたのがVRMMORPG《リアデイル》の世界――そこでのハイエルフ・ケーナとしての時間だった。 だがある夜、現実世界で生命維持装置が停止する。静かに閉じた瞼が、次に開かれたとき、桂菜はまったく別の場所で目を覚ます。それは彼女が何千時間も遊び込んだ“リアデイル”だったが、時間軸は彼女の知る時代から200年が経過していた。すでにゲームサーバーは存在せず、そこに広がるのは生身の人間たちの暮らす現実の世界。夢の延長ではなく、過去のプレイヤーが神話化された後の「続きの世界」だった。
転生後のケーナ――喪失と戸惑いのはざまで
ケーナは、自身のゲームアバターであるハイエルフの姿のまま目覚める。長命種特有の優雅な容貌と、かつてチート級と呼ばれたステータス、そして莫大な魔力。だが力よりも先に彼女を襲ったのは、“世界がもう誰の手も借りずに動いている”という孤独感だった。 かつての仲間もログアウトし、運営も存在しない。唯一残されたのは、彼女が築いた塔と、NPCだったはずの人々の“生活”。混乱しつつもケーナは現実的に生きることを決意する。異世界転生ものによくある「チュートリアル」も「使命」もない。目の前の現実に順応し、まずは食事を作り、寝床を整える。ゲームの中でただの数字だった空腹や疲労が、現実の感覚として戻ってきたとき、彼女の新しい人生が静かに始まった。
辺境の村での出会いと“母性”の再生
最初の拠点となるのが、かつての塔の近くにある辺境の村。ここで彼女は宿屋の女将マレールや娘のリットらと交流を深め、村に残る古い“塔の伝承”に自分の影を見いだす。彼らにとってケーナは「200年塔に籠もっていた魔女」。伝説の生き証人として崇められもするが、本人はそれを笑い飛ばす。 そんな生活の中で、ケーナは壊滅した村の生き残りである幼い少女ルカと出会う。ルカを引き取り、母のように世話を焼く姿は、かつて現実で何もできなかった自分への贖罪でもあり、再び誰かと“関わる”ことで取り戻した生の実感だった。
子どもたちとの再会——過去が形を持つ
旅の途中で、ケーナは思いがけない再会を果たす。 それはかつてゲーム内で“里子システム”を通じて作った自分の子どもたち——長男スカルゴ、長女マイマイ、次男カータツ。彼らは今やフェルスケイロ公国の重職に就くほどの存在となっていた。スカルゴは神殿の大司祭、マイマイは王立学院の校長、カータツは名工房を構えるドワーフの職人。 200年の時を超えて再会した母と子の関係は、温かくも滑稽だ。スカルゴは母親崇拝が過ぎて周囲を引かせ、マイマイは母への甘えが抜けず、カータツは常識人ゆえに頭を抱える。だが彼らの騒々しい愛情は、ケーナに“居場所”という実感をもたらした。 この再会を軸に、アニメは「ゲームの遺産が血縁に似た絆として残る」構造を明確に描く。生みの親がデータでも、心の結び目は確かに存在していた。
旅路と出会い——記録を拾い集める日々
ケーナは、過去の仲間=スキルマスターたちの塔を巡る旅に出る。それは単なる探索ではなく、失われた友人たちの痕跡をたどる巡礼でもあった。 道中では、商人のエーリネ、元騎士団長のアービタ、妖精クー、人魚族のミミリィなど、多彩な種族と触れ合い、時には助け合いながら世界の“今”を知っていく。かつてのリアデイルは数値と戦略の世界だったが、200年後のそれは人と人との関係によって運営される「生きた社会」になっていた。 塔の守護神との再会も象徴的だ。AIのように事務的だった存在が、時間の経過によって人格を帯び、皮肉を言うまでに変化している。ケーナは驚きつつも、彼らに“時の流れ”の重さを感じる。かつての仮想世界が、いまや自分を含めて“現実の世界”になっていた。
小さな事件の積み重ね——日常の冒険譚
物語の構成は1話完結型に近い。王子デン助(仮)との追走劇、学院や工房でのトラブル、浴場建設や祭りの準備……いずれも国の命運を賭けた大事件ではない。だが、こうした“暮らしの中の冒険”こそが本作の心臓部だ。 ケーナは事件を解決しながらも、力任せにねじ伏せることはほとんどない。知識や包容力、そしてちょっとしたズルさで問題を丸く収める。その過程で、村人たちや仲間たちが成長していく。主人公の圧倒的な力が他者を消さず、むしろ他者の活躍を引き出す方向に働いているのが心地よい。
過去のプレイヤーたち——リアデイルの“亡霊”たち
物語後半では、かつてのプレイヤーたちが次々と登場する。彼らは“気づけばこの世界にいた”という点でケーナと同じだが、到達した心境はさまざまだ。 竜人族のシャイニングセイバー、灰色の竜人エクシズ、冒険者クオルケなど、ゲーム時代の記憶を抱えながら現実に馴染もうとする姿は、ケーナの鏡像でもある。彼らとの邂逅は、かつてオンラインで交わされた“関係性の続き”を描くと同時に、プレイヤーが神格化された世界で“今を生きる”ことの意味を問い直すものでもある。 また、少年の姿をしたコイローグのエピソードでは、ゲームと現実の境界が曖昧になる恐怖が描かれる。悪役プレイを続けていた彼が、現実化した世界で罪を犯してしまい、ケーナに制裁される展開は、この作品が単なる癒し系で終わらないことを示す。
クライマックス——“再起動”の選択
アニメ最終盤では、ケーナが塔のネットワークを通じて“かつての自分の記録”と対峙する場面が描かれる。そこには、寝たきりの少女として過ごした時間、現実での孤独、そして「ここで終わるのなら幸せだった」と書き残したログが残っていた。 だが彼女はそれを消さず、上書きもせず、そっと保存する。過去を否定しないこと、それこそが彼女の生き方の根幹であり、この世界における“神に等しい力”の使い方だった。 力による秩序ではなく、記録の保存と継承によって世界を支える。アニメ版はその姿を淡く描き、視聴者に「彼女の物語はこれからも続く」という余韻を残して終わる。
エピローグ——“生きる”という日常への帰還
最終話でケーナは再び旅立つ。目的はもう明確なクエストではなく、ルカや仲間たちと共に“今日を生きること”。 画面には、静かな夕陽と食卓、笑顔が並ぶ。派手なエンディングではなく、生活の延長として物語が閉じるのが本作らしい。視聴者は、異世界という非日常を見終えた後に、現実の夕暮れの色を少しだけ柔らかく感じる。 『リアデイルの大地にて』のストーリーは、再生や転生ではなく、“日常をもう一度歩く”ことの尊さを描いたロードムービーであり、最終回の静けさがそのテーマをそっと締めくくる。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
中心人物――ケーナという“再生者”
物語の中心にいるのは、ハイエルフ族の女性ケーナ。彼女はVRMMORPG《リアデイル》の中で最強のひとりとして知られたスキルマスターNo.3であり、現実世界では生命維持装置に繋がれていた少女・各務桂菜でもある。 アニメ版では、この“現実と仮想の二重の存在”という設定を、派手なSF描写ではなく、ケーナの人間味を軸に描く。目覚めた彼女は全スキルを保持したまま、かつて築いた塔と莫大な遺産を手にしているが、まず選ぶのは戦いではなく生活。 彼女が最初に作るのは料理であり、最初に関わるのは子どもたちと村人たち。力を誇るのではなく、日々の営みの中で“誰かを笑顔にする”ことが彼女の存在意義として描かれる。アニメでは、声を担当する幸村恵理の柔らかいトーンが、強さよりも包容力を印象づけている。
スカルゴ――信仰とマザコンの狭間で
ケーナの第一の“子ども”にあたる長男スカルゴは、フェルスケイロ公国の大司祭にして高位エルフ。公的には神殿の象徴的存在だが、私生活では徹底したマザコン。母であるケーナを「母上殿」と呼び、彼女が関わることとなれば、国の政務すら放り出して駆けつけるほど。 真面目で威厳のある姿と、母親に甘えるギャップがコミカルに描かれ、作品全体のユーモアを支える重要キャラである。彼の過剰な愛情は単なるギャグで終わらず、“失われた家族への渇望”というテーマにも通じる。200年間待ち続けた息子の愛情表現として見ると、滑稽さの裏に切なさが潜む。
マイマイ――知識と感情のバランスを取る長女
次に登場する長女マイマイは、フェルスケイロ王立学院の校長を務める才女。見た目は穏やかで上品だが、母親への愛着は兄に負けない。ケーナを「お母様」と呼び、再会のたびに抱きつく姿は作品屈指の癒し場面でもある。 マイマイは知識人としての冷静さを保ちながらも、家族との再会では感情を隠せず、理性と感情の境界が揺れる。その揺らぎが、作品全体に人間味を与える。彼女の声を演じる名塚佳織は、知性と甘えの混ざった絶妙なバランスでマイマイを立体化している。
カータツ――常識人ゆえの苦労人
次男カータツは、ドワーフ族の鍛冶職人。王都に工房を構え、堅実で地に足のついた性格の持ち主。三兄妹の中では最も常識的で、兄妹の騒ぎに頭を抱える場面が多い。母を「おふくろ」と呼ぶ彼の言葉には、親しみと尊敬が混じる。 戦闘職ではなく生産職であるため派手さはないが、アニメでは彼の工房での描写が温かく、金属を打つ音と火花の美しい光が印象に残る。彼の存在は、作品の“生活のリアリティ”を支える礎になっている。
ルカ――失われた村の小さな希望
ケーナが旅の初期で出会う孤児の少女。滅びた村の唯一の生存者として、恐怖と喪失を抱えて生きていたが、ケーナに拾われて養子となる。言葉少なで、最初は感情表現も乏しかったが、物語が進むにつれて少しずつ笑顔を取り戻す。 ルカは“癒しの象徴”であると同時に、ケーナ自身が「母として生き直す」ためのきっかけでもある。彼女を抱きしめるケーナの姿は、現実で動けなかった桂菜の“もう一度の人生”を体現している。
オプス――悪魔のようで憎めない策士
ケーナの旧友であり、スキルマスターNo.13。フルネーム「オペケッテンシュルトハイマー・クロステットボンバー」という長大な名前の通り、クセの塊のような存在。 魔人族の男性の姿で現れ、戦略家としての知恵と狡猾さを持ち合わせるが、根っからの悪ではない。ゲーム時代のケーナの仲間でもあり、彼女と再び会話を交わすシーンでは、皮肉を交えながらも“旧友の再会”の温かみが漂う。彼の塔「悪意と殺意の館」は、108の死に方を体験できるという狂気のダンジョンだが、その裏には「生き延びろ」という愛の形が見える。
ロクシリウス&ロクシーヌ――忠誠と日常の象徴
ケーナの召喚従者である猫人族コンビ。通称ロクスとシィ。彼らはゲーム時代には戦闘サポートAI的存在だったが、200年後の世界では“生活を支える家族”として描かれる。洗濯や料理、掃除に奔走する姿がユーモラスで、異世界の壮大さの中に“普通の家の温もり”を感じさせる。 ロクスは忠実な執事型、シィは世話焼きの姉的ポジションで、ケーナとの掛け合いが家庭劇のように展開する。アニメでは動物的なしぐさと丁寧な芝居で、二人が単なるNPCではなく“命ある存在”として描かれている。
スピンオフ的な人々――世界を彩るサブキャラクターたち
『リアデイルの大地にて』の魅力は、脇役の厚みだ。 商人エーリネはケーナに貨幣価値を教える常識人として登場し、視聴者の“世界理解”を助ける存在。冒険者アービタは、熱血ながら義に厚く、ケーナに模擬戦を挑んでボロ負けする“お約束”の笑いを提供する。 また、人魚のミミリィのエピソードでは、異世界に迷い込んだ異種族の孤独が丁寧に描かれ、彼女の歌が村の“恐怖の正体”を解く鍵になる。こうした一話完結型のサブキャラ群が、作品世界の広がりを感じさせる。
元プレイヤー勢――時を越えた同志たち
竜人族のシャイニングセイバー、灰色の竜人エクシズ、そして性転換してしまった冒険者クオルケ。彼らは皆、かつて《リアデイル》でケーナと同じ空間を共有していたプレイヤーだ。 現実から断絶されながらも、この世界に馴染もうと奮闘する姿は、ケーナの孤独を癒やす存在であり、同時に“過去を背負ったまま生きる”ことの象徴でもある。特にクオルケの戸惑いは、アバターと現実の乖離をコミカルに、そして少し切なく描いている。 プレイヤーたちの再登場は、単なる懐かしさではなく、「かつてのゲームが人生になった世界」での生き方を照らす重要な要素だ。
フェルスケイロ王族と国家の人々
フェルスケイロ国王トライストと王妃アルナシィ、そしてやんちゃな王子デン助(仮)と王女マイリーネ。彼らは典型的な“権力者”ではなく、庶民的で人間くさい。王子の脱走騒動ではケーナが追跡役を務めるが、事件は最終的に母子の絆を強める小さなハートフル劇で終わる。 王女マイリーネはスカルゴに恋心を抱くが、その相手がケーナの息子と知る展開は視聴者に笑いと驚きをもたらした。こうした人間関係のユーモラスな“ずれ”が、この世界の平和な空気を作っている。
キャラクター全体の印象と構成の妙
アニメ版『リアデイルの大地にて』のキャラクター配置は、戦闘・生活・家族の三軸を常にバランスさせている。誰もが極端な役割に偏らず、笑い・涙・日常のリズムの中でそれぞれが輝く。 ケーナを中心に、家族的な輪がゆるやかに広がり、それぞれの背景や心情が重なって世界を形づくる。彼女が築く人間関係こそが“冒険の成果”そのものであり、この物語の最大の報酬でもある。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
音楽が描く“癒しと再生”の物語
アニメ『リアデイルの大地にて』における音楽の魅力は、物語のテーマである「再生」「生活」「温もり」を、旋律と歌詞で優しく包み込むことにある。 この作品は派手なバトルよりも静かな日常の瞬間を大切にしており、そのトーンを支えるのがTRUEのオープニングテーマ「Happy encount」と、田所あずさによるエンディングテーマ「箱庭の幸福」だ。 さらに、劇中で歌われる挿入歌「Mother of Pearl」(ミミリィ=二ノ宮ゆい)は、異種族の孤独と希望を象徴するような一曲として印象に残る。どの楽曲も単なるタイアップではなく、作品世界の情緒に溶け込む“第二のナレーション”として機能している。
オープニングテーマ「Happy encount」
希望の出発を告げる旋律 TRUEによるオープニング「Happy encount」は、明るいテンポに乗せて“新しい世界への第一歩”を祝福するような楽曲。作詞はTRUE自身の別名義である唐沢美帆、作曲は成本智美、編曲はトミタカズキ。 イントロから流れるストリングスの軽やかさが、ケーナが200年後の世界に目覚める瞬間の“光”と重なる。歌詞の中で繰り返される「出会いを信じて歩き出す」というフレーズは、ケーナが再び人と関わりを持とうとする物語のテーマをそのまま象徴している。 特にサビ部分の「君に出会えて良かった」という言葉は、家族・仲間・世界すべてへの感謝を内包しており、視聴者が毎週作品に戻ってくるたびに“この世界は優しい”と感じさせてくれる。 映像面では、ケーナが朝の光の中で笑顔を見せるカット、ルカや子どもたちが一緒に食卓を囲む場面、銀の塔を背景にした旅立ちのシーンなど、希望と温もりが混ざった映像演出が印象的だ。 TRUEの伸びやかなボーカルは、異世界ファンタジーの広がりよりも、柔らかい日常の光を描き出しており、作品全体の“優しい空気”を決定づけた。
エンディングテーマ「箱庭の幸福」
小さな世界の穏やかな光 エンディングテーマ「箱庭の幸福」は、田所あずさが歌うしっとりとしたバラードで、作詞は大木貢祐、作曲・編曲は神田ジョン。 この曲はタイトル通り、“大きな冒険の外側にある幸福”をテーマにしており、ケーナが築く家庭的な時間や、ルカとの静かな日常を思わせる。 イントロのピアノが静かに流れ、少しの間を置いて田所の声が優しく重なるとき、まるで異世界の夕暮れを眺めているような穏やかな気持ちになる。 「世界が遠くても 手を繋いでいられたなら」という歌詞は、現実世界で命を失った桂菜と、VR世界で新たに生きるケーナという存在の“境界を越える愛情”を暗示している。 エンディング映像では、ケーナとルカが並んで歩くシルエットや、焚火の前で微笑むケーナの姿が描かれ、視聴者に“明日も見よう”という安らぎを残す。 この曲の最大の魅力は、「感動を押しつけないこと」。静けさの中に温度があり、寂しさの奥に優しさが潜む。日常系ファンタジーとしての作品性を音楽で完璧に体現した一曲である。
挿入歌「Mother of Pearl」
孤独と再生を歌う声 劇中でミミリィ(二ノ宮ゆい)が歌う挿入歌「Mother of Pearl」は、まさに『リアデイルの大地にて』の世界観を象徴する一曲。作詞は大木貢祐、作曲・編曲は夢見クジラ。 タイトルの「Mother of Pearl(真珠母貝)」は、外敵に傷つきながらもその傷を覆って美しい真珠を生み出す存在を意味する。これは、悲しみを抱えながらも新しい命を生きるケーナやミミリィ自身の姿に重なる。 アニメ第5話でこの歌が流れる場面では、地下水脈に迷い込んだミミリィの孤独が表現され、彼女の歌声が洞窟に響く。村人たちはそれを“怪しい唸り声”と勘違いして恐れるが、ケーナがその正体を知ることで誤解が解け、悲しみの場が温かな出会いへと変わる。 二ノ宮ゆいの透き通る声は、透明な水のように澄み渡り、聞く者に“癒やし”と“寂しさ”の両方を届ける。 この曲は単なるBGMではなく、登場人物の心情を補足する重要な“物語のセリフ”のような役割を持っており、放送当時はSNS上でも「泣ける挿入歌」として多くの反響を呼んだ。
音楽と映像演出の融合
『リアデイルの大地にて』は、音楽と映像の“間(ま)”を非常に丁寧に扱う作品である。 オープニングのリズムとともに朝が始まり、エンディングの静けさとともに夜が訪れる。つまり音楽が時間の流れそのものを演出している。 特に印象的なのが、エピソードの終盤でBGMを一度完全に止め、静寂の後に「箱庭の幸福」が流れ出す瞬間。このタイミングは、視聴者の感情を自然に“落ち着かせる”設計となっている。 また、作中BGMにはストリングスとオカリナ、アコースティックギターを中心とした“自然音系”の音色が多用され、人工的な電子音を極力排している。これにより、元・VRゲームという設定の中にも、自然の息吹と人間味が感じられる構成になっている。
音楽スタッフと制作陣の連携
本作の音楽チームは、キャラクターの心理や背景を音で支えることを最優先しており、派手なメロディではなく「場面を呼吸させる音作り」を徹底した。 TRUEと田所あずさという、異なる方向性を持つアーティストを起用した点も巧妙である。TRUEは“前へ進む推進力”、田所は“立ち止まって考える安らぎ”を表現し、この2人の対比によって作品全体の呼吸が生まれている。 さらに、劇伴作曲陣はゲーム時代のモチーフをわずかに引用し、視聴者に“かつてのリアデイル”の記憶を思い出させるような旋律を散りばめている。これが200年という時の流れを“音で感じさせる”効果を生み出している。
キャラクターソングとイメージ展開
アニメ終了後に発売されたキャラクターソングアルバムでは、ケーナ、スカルゴ、マイマイ、カータツらがそれぞれの個性を生かした楽曲を担当。 ケーナの「銀環の風」では、彼女の穏やかな母性と旅人としての孤独を描写し、スカルゴの「祈りと暴走」では神官としての矜持と母への愛情をコミカルに融合させている。 マイマイの「あなたに贈る魔法」では教育者としての優しさと、娘らしい甘えのニュアンスが調和し、カータツの「鍛冶場の音」は、金属を打つリズムを取り入れたユニークな一曲に仕上がっている。 これらのキャラソンは、各キャラクターの“日常の延長線上にある心情”を音楽として表現しており、アニメの世界観をさらに深く掘り下げる試みとしてファンから高評価を得た。
視聴者の反応と音楽の余韻
放送当時、SNSでは「毎回EDで泣かされる」「朝と夜の切り替えが美しい」といった感想が数多く投稿された。 特に“Happy encount”のポジティブな出発感と、“箱庭の幸福”の静かな安らぎの対比が、現実の一週間のリズムに心地よく重なると評判だった。 視聴者の多くは「このアニメの音楽は、日常を少し優しく見せてくれる」と語り、配信版のサントラも高い人気を博した。 音楽はこの作品にとって、物語を語るもう一つの言葉であり、異世界と現実を繋ぐ架け橋だったと言えるだろう。
総括:音楽が紡ぐ“リアデイルの心拍”
『リアデイルの大地にて』の音楽は、壮大さではなく親密さで勝負している。 オープニングが「始まりの息吹」、エンディングが「眠りへの導き」、挿入歌が「心の傷を癒やす歌」。この三位一体の構成が、作品世界を有機的に動かしている。 ケーナたちが生きる世界は、もはやゲームではなく現実。その現実のリズムを優しく鳴らす音楽こそ、本作の“もう一つの主人公”である。
[anime-4]
■ 声優について
全体の印象 ― 物語の“呼吸”を作る演技陣
『リアデイルの大地にて』の声優陣は、いわゆる「異世界転生もの」のテンプレート的な派手さを避け、日常と感情の細やかな機微を軸に芝居を構築している。 主人公ケーナを演じる幸村恵理を筆頭に、個性的ながらもどこか“柔らかい声色”を持つキャストが集い、作品全体のトーンを穏やかに統一している。 このアニメでは、セリフそのものが世界の温度を決める。戦闘時の緊張感よりも、生活の一言、母子の会話、仲間とのやり取りが中心になるため、声優たちは「叫ぶよりも息を整える」演技を選択している。 その結果、視聴者はキャラクター同士の会話を通して、まるで自分がリアデイルの村や塔の片隅にいるかのような錯覚を覚える。アニメとしての派手な演技ではなく、生活を感じさせる声――それが本作の根幹だ。
ケーナ/各務桂菜役:幸村恵理
優しさと芯の強さを両立 主人公ケーナを演じる幸村恵理の存在感は、この作品を支える最大の要因といっていい。 彼女の声は、ほんの少しの温度差で印象を大きく変える繊細な質感を持ち、ハイエルフとしての神秘性と、人間・桂菜としての儚さを同時に感じさせる。 序盤では、目覚めたばかりのケーナが周囲に戸惑う様子を、やや高めで息の多い声で演じるが、物語が進むにつれて低音が増え、母としての包容力が加わっていく。 特に第3話、孤児ルカに初めて「おいで」と声をかける場面のトーン変化は圧巻。現実世界での桂菜の“生への諦め”と、ケーナとしての“新たな息吹”が一瞬で交差する。 幸村の演技は力強い決意を感じさせながらも、決して押しつけがましくない。聴く者の心を自然に解きほぐす声であり、まさに“再生を語る声”といえる。
スカルゴ役:小野大輔
重厚な威厳とコミカルな愛情の融合 フェルスケイロの大司祭スカルゴを演じるのは小野大輔。彼の低音ボイスが放つ重厚な響きは、神官としての威厳と信仰心を的確に表現している。 だが一方で、ケーナに対する愛情表現が始まると、一転してコミカルで子供っぽいテンションに切り替わる。この振れ幅こそが小野の真骨頂だ。 母を前にして暴走するスカルゴの台詞――「母上殿! どうかその尊きお姿をもう一度拝ませてください!」――このシーンでの芝居は、重厚な声をあえて“過剰な敬虔”に傾けることで笑いを生む。 小野はこのギャップを完璧にコントロールし、視聴者が“うるさいのに憎めない”と感じるキャラクターを成立させた。神聖さと滑稽さを一体化させる演技術は、まさに職人技。
マイマイ役:名塚佳織
理性と母性愛を行き来する声音 長女マイマイを演じる名塚佳織の演技は、知的な女性らしさと家庭的な温もりの絶妙なバランスで成立している。 マイマイは王立学院の校長という立場にありながら、母親の前では一気に甘えん坊の娘に戻る。名塚はこの変化を“声の重心”で表現する。公務時には低く安定したトーンで知性を感じさせ、母と話すときにはわずかに高く、語尾が柔らかくなる。 第6話でマイマイが「お母様、また一緒にご飯を食べたいです」とつぶやく場面では、幼少期の少女のような声色に戻り、視聴者の心をくすぐった。 名塚佳織の声が持つ包容力と、時折の脆さは、マイマイというキャラクターに“現実の娘のような温度”を与えている。
カータツ役:杉田智和
渋みとツッコミの妙 三兄妹の中で最も常識人のカータツを演じる杉田智和は、落ち着いた声色とリズミカルなツッコミのテンポで物語に“間”を作り出している。 杉田演じるカータツは、兄姉が暴走するたびに冷静なツッコミを入れるが、決して怒鳴らない。低く抑えた声で皮肉を交えることで、優しさとユーモアを同時に感じさせる。 また、鍛冶屋としての仕事シーンでは、金属を打つ音に負けない芯のある声で職人気質を体現しており、“働く人間のリアル”を声だけで表現している。 ケーナを「おふくろ」と呼ぶときの一瞬の照れを混ぜた声――そこに杉田の熟練がある。
ルカ役:高尾奏音
無垢の成長を声で描く ケーナの養子ルカを演じる高尾奏音の演技は、無垢さと成長の変化を繊細に描くものだった。 初登場時のルカは、恐怖に怯え、言葉数も少ない。高尾はこの状態を小さく、息を詰めたような声で表現し、次第にケーナに心を開くにつれて、音の響きが明るくなる。 最終話近くで「お母さん、ただいま」と言う声には、確かな自信と安心が宿っており、視聴者は彼女が本当に“この世界で生きている”と感じる。 子役的な演技ではなく、“成長する少女のリアル”を体現した声といえる。
オプス役:小田切優衣(AIキー役含む)
二面性を響かせる 策士オプスと、ケーナのAI補佐キーを演じた小田切優衣の仕事も注目に値する。 キーとしての演技は冷静で電子的な抑揚を持ち、まさにAIそのもの。一方、オプスとしての芝居は狡猾で人間臭く、同一声優であることを感じさせないほどの対比を見せた。 特にオプスの長いセリフ回しを、皮肉な笑いとともに流すテンポ感は見事。ゲーム開発者としてのリアルな一面を感じさせる声の“にじみ”が、彼の謎めいた存在を強調していた。
脇を支える豪華キャストたち
メインキャラ以外にも、脇を固める声優陣が非常に充実している。 ミミリィを演じる二ノ宮ゆいは、劇中歌と芝居を完全に統合し、歌声の透明感そのままに繊細な演技を見せる。 フェルスケイロ王子デン助(仮)を演じる田村睦心の少年声も軽快で、作品に“動”を与える重要なスパイスだ。 さらに、森なな子(ロクシリウス)、東城日沙子(ロクシーヌ)、高野麻里佳(マイリーネ)といったキャスト陣が、それぞれ短い出番でも確かな存在感を残す。彼女たちの声が重なることで、リアデイルの世界は“人が息づく音空間”となった。
アフレコ現場と演出面のこだわり
制作スタッフのインタビューによると、本作のアフレコ現場では「静けさを恐れない演技」が方針だったという。 セリフとセリフの間にある“余白”を大切にし、あえて間を取ることで日常感を出す。通常のアニメではテンポが遅くなるため避けられがちだが、『リアデイルの大地にて』ではその間こそが呼吸であり、生きている音として重要視された。 声優たちは、この独特の“呼吸の演出”に合わせてトーンを調整し、結果的に作品全体が穏やかなリズムを保っている。
声優陣が作り出す“家族”のリアリティ
声優の掛け合いにも注目すべきだ。ケーナ役の幸村と、子どもたちを演じる小野・名塚・杉田の収録は、ほぼ同時録りで行われた。そのため、即興的な反応や、自然な笑い声が多く残っており、アニメでは珍しく“会話の呼吸”がリアルに感じられる。 とくにスカルゴとマイマイが同時にケーナへ抱きつくシーンでは、三人の声が被る混線具合が生々しく、収録後の座談会でも「家族感がそのままマイクに入った」と話題になった。 この“偶然の息づかい”こそが、リアデイルの優しさを生んでいる。
総括 ― “穏やかに生きる声”が導く世界
『リアデイルの大地にて』の声優たちは、ただキャラクターを演じるのではなく、“この世界で暮らす人々の息づかい”を体現している。 戦闘よりも生活、叫びよりも囁き、激しさよりも温もり――そんな演技の選択が、この作品を他の異世界ファンタジーと一線を画すものにした。 彼らの声は、視聴者の心に静かに残る。まるでリアデイルの風が吹き抜けるように。
[anime-5]
■ 視聴者の感想・評価
総評――「静けさ」と「温かさ」で心を掴む異世界作品
『リアデイルの大地にて』は、派手な戦闘や複雑な政治劇を避け、淡々とした日常を描く“静かな異世界ファンタジー”として多くの視聴者に受け入れられた。 放送当時のSNSでは、「癒し」「優しい世界」「穏やかな時間」というキーワードが頻出し、視聴後の“心が落ち着くアニメ”として定評を得た。 視聴者の多くが評価したのは、テンポの緩やかさ、会話の自然さ、そしてキャラクター同士の距離感の柔らかさだ。 強くなることや征服することよりも、“生きること”に価値を置くストーリー展開は、異世界アニメが量産される時代の中で逆に新鮮だった。 「この作品には“焦り”がない」という声が象徴的で、慌ただしい日常の中で視聴者が“呼吸を整えるための30分”として楽しんでいたことが分かる。
ポジティブな感想――“癒し”と“人間味”の評価
好意的な意見の中心は、“穏やかで温かい空気感”に関するものが圧倒的に多い。 Twitterやレビューサイトでは、 – 「ケーナが強いのに威張らないところが最高」 – 「料理や会話の描写が本当に癒やされる」 – 「アニメの音楽と間の取り方が完璧」 – 「一話終わるごとに心が落ち着く」 といった声が寄せられた。
また、母と子の関係性を軸にしたドラマ構成も大きな支持を受けた。
特にスカルゴ・マイマイ・カータツの三兄妹が登場するエピソードでは、「親子の再会で涙が出た」「家族の絆を感じる異世界アニメは珍しい」と高評価。
彼らのコミカルな掛け合いも“ギャグが優しい”“嫌味がない”と好意的に受け止められ、作品全体の雰囲気を明るく保っている。
さらに、ケーナのキャラクター造形に対して「理想的な母親」「あんな上司や先生が欲しい」といった声も多く、彼女の包容力と人間味が世代を超えて共感を呼んだ。
一部のファンは、ケーナを「癒し系異世界の聖母」と呼び、ネット上では彼女の名言を引用するファンアートや日常ネタも増えた。
声優陣への賞賛――自然体の演技が心地よい
視聴者の多くは、声優陣の“芝居の柔らかさ”を高く評価している。 特にケーナ役・幸村恵理の演技は、「母のようで友達のよう」「強さと優しさが共存している」と絶賛された。 また、スカルゴ役の小野大輔については「宗教的な声の説得力がすごい」「マザコンなのに嫌いになれない」と、キャラクターの魅力を引き立てた点が好評だった。 この作品では感情を抑えた芝居が多いが、それでも“心の温度”が伝わる――その点を称賛する感想が特に目立った。
作画と美術への感想――丁寧な世界の表現
作画についても、「派手ではないが温もりがある」と好意的に受け止められた。 キャラクターデザインはシンプルながら柔らかく、背景美術は特に高評価。 森、湖、塔、村の景観描写には淡い光が多く使われ、視聴者は“空気の流れ”まで感じるような映像体験を得たという声が多い。 特に第1話の朝日と水面のシーン、第7話の湖の塔の夕景、第11話の夜の食卓シーンは「光の描き方が美しい」として再生回数が伸びた。 一方で、戦闘シーンは簡略化されている部分もあり、「もう少し動きを見たかった」という意見も少数ながら存在する。
音楽への感想――“心のBGM”としての存在
音楽に関しては、前章でも触れた通り、作品全体の評価を押し上げる要因になった。 TRUEの「Happy encount」は“朝の目覚めに合う曲”として好評で、「この曲で一日を始めたい」という投稿が放送中に多数見られた。 田所あずさの「箱庭の幸福」についても「聴くたびに涙が出る」「日常を包み込むような温かさ」と感想が寄せられ、ED曲を“癒しのテーマ”とする視聴者が多かった。 また、BGMの静けさを評価する声も多く、「アニメというより“ラジオドラマのような心地よさ”がある」といった表現も見られた。
物語構成への感想――“事件がないこと”の強み
『リアデイルの大地にて』の物語は、典型的な異世界アニメにありがちな“魔王討伐”や“国家転覆”といった大きな目標を持たない。 その代わり、日常の小事件や人との触れ合いを丁寧に積み上げる形式が取られている。 一部の視聴者からは「ストーリーがゆるすぎる」との意見もあったが、多くのファンはその“ゆるさ”こそが魅力だと受け取った。 「目的がないことで、かえって現実に近く感じる」「冒険ではなく暮らしを描く異世界ものは貴重」といった声が支配的である。 視聴者はケーナの行動を“見守る”感覚で視聴しており、まるで知人の新しい生活を応援するような距離感を楽しんでいた。
批判的意見――テンポと作画への軽い不満
もちろん、全体的な高評価の中でも一部には辛口な意見も存在する。 「ストーリーに大きな盛り上がりがない」「テンポが遅く感じる」といった声は、バトル重視の視聴者層から寄せられた。 また、「作画が安定しない回がある」「静止画が多い」といった作画面の指摘も少数見られたが、それでも“崩壊”レベルではなく、むしろ落ち着いた映像演出として好意的に捉えるファンもいた。 総じて、批判意見すらも「派手さがない」「静かすぎる」という性質のもので、作品全体の方向性がブレていない証拠ともいえる。
視聴者層の傾向――幅広い年齢層に支持
本作は10代後半~30代の若い層だけでなく、40代・50代のアニメファンからの支持も厚かった。 特に「疲れた心に効く」「仕事の後にちょうどいい」という感想が目立ち、視聴体験そのものが“癒しの時間”になっていた。 また、親世代がケーナと重ねて見るケースもあり、「子どもを見守る親の気持ちで見てしまった」「家族と一緒に観られる異世界ものは珍しい」といったコメントがSNSやブログで多く見られた。 子どもが一緒に見ても安心できる作風は、他の異世界アニメとの差別化にも成功している。
海外ファンからの反応
海外配信プラットフォーム(特にCrunchyrollなど)では、“Laid-back isekai(ゆったり異世界)”という新しいジャンルラベルで紹介され、多くのファンが共感を示した。 英語圏では“Gentle Isekai”“Healing Fantasy”という表現で呼ばれることが多く、YouTube上でも英語・スペイン語のレビューが多数投稿された。 特に「母性」「再生」「自然描写」の三点が普遍的に理解され、文化圏を超えて癒し作品として評価されたのは特筆すべき点だ。
印象に残るシーンと感想の広がり
– ケーナが初めてルカを抱きしめる場面:多くのファンが「涙腺崩壊回」として挙げた。 – 三兄妹の初対面シーン:笑いと感動が共存する奇跡の回として人気。 – 湖の塔での挿入歌「Mother of Pearl」:音楽と演出の融合として高評価。 – 最終回の食卓シーン:「静かに終わることの勇気」を称賛する声が多数。
これらのエピソードは、SNS上で繰り返し引用され、現在でも「癒しアニメの名シーン」として話題に上る。
総括――“心の休憩所”としての評価
総じて『リアデイルの大地にて』は、“戦わない異世界ファンタジー”としての価値を確立した作品といえる。 視聴者の多くがこのアニメを“心の休憩所”と位置づけており、疲れたときに見返す作品として定着している。 レビューサイトでも平均評価は高く、特に「ストレスのない世界観」「キャラの温かさ」「音楽の癒し」が三本柱として挙げられた。 派手さよりも安らぎを求める時代に、この作品は確実に一つの答えを提示した――“生きることそのものが冒険である”という静かなメッセージとともに。
[anime-6]
■ 好きな場面
1. ケーナが目覚める“静寂の朝”――現実と幻想の境目
シリーズ冒頭、第1話の目覚めのシーンは、多くのファンにとって特別な瞬間となった。 ベッドの上で目を開けたケーナの視界に映るのは、見慣れた《リアデイル》の草原。しかし音もなく風が吹き、鳥の声が遠くでこだまするその映像には、現実と夢の境界を曖昧にする繊細な空気が漂う。 この場面の魅力は、「転生した!」という派手な演出を避け、あくまで“静かな再生”として描いた点にある。 ケーナの小さな息づかいと、背景の淡い光のコントラストが、視聴者の心を柔らかく掴む。 彼女が窓の外を見て、ため息まじりに「……ログインした?」と呟く瞬間――その一言に、過去と現在、現実と幻想のすべてが交錯する。 この「静かな導入」に惹かれた視聴者は多く、「派手な転生より、この静けさに泣けた」とSNS上で称賛の声が相次いだ。
2. ルカとの出会い――“母になる”瞬間の温度
第3話のハイライト、ケーナがルカと出会う場面は、作品全体の心臓部といえる。 焼け落ちた村の瓦礫の中で、怯えた表情の少女ルカを見つけるケーナ。 彼女は最初、子どもに声をかけることをためらう。200年の孤独と、自身の存在の異常さを理解していたからだ。 しかし次の瞬間、ケーナは膝をつき、そっと手を差し伸べる。 「大丈夫、もう怖くないよ。」 この一言は、彼女自身が“生きることを受け入れた”瞬間でもある。 アニメでは光の演出が秀逸で、夕暮れに照らされた二人の影が寄り添うように重なる。 言葉よりも画面が語る、まさに“母の誕生シーン”だ。 視聴者の間では「この回で完全に作品に惚れた」「涙が止まらなかった」といった感想が爆発的に広がった。
3. 三兄妹との再会――笑いと涙の再生劇
第4~5話で描かれる、ケーナと三人の“里子”たち――スカルゴ、マイマイ、カータツ――の再会は、シリーズ屈指の名場面群だ。 それぞれが200年の時を経て成長し、母への想いを胸に抱えていた。 ケーナを見た瞬間、スカルゴは泣き崩れ、マイマイは飛びつき、カータツは苦笑しながらも「おふくろ……?」と声を震わせる。 この場面では笑いと感動が同居しており、視聴者の心を複雑に揺さぶる。 特に印象的なのが、スカルゴのセリフ「母上殿が、わたくしの奇跡でございます!」――重厚な小野大輔の声で放たれたその言葉は、冗談めかしながらも本気の感情を孕んでいる。 再会シーン後の食卓では、母と子が何気ない日常を取り戻す。“冒険”ではなく“暮らし”がこの作品の中心であることを、強く印象づけた名エピソードだ。
4. 湖の塔での挿入歌「Mother of Pearl」――孤独と共鳴の瞬間
第7話の湖の塔エピソードは、視聴者の間で「アニメ史に残る癒し回」と称えられた。 水底で孤独に歌う人魚ミミリィ。その声を聞いた村人たちは「怪物の唸り声」と恐れ、討伐隊を組もうとする。 だがケーナは、音に込められた感情を察知し、ただ一人湖へ潜る。 そのとき流れる挿入歌「Mother of Pearl」は、ミミリィの心そのもの。 ケーナが手を差し伸べ、水中で光に包まれるシーンは、まるで命の記憶を癒やすような映像美に満ちている。 台詞はほとんどないのに、二人の心が通じ合うのが分かる――その演出力に感嘆の声が続出した。 放送後、SNSでは「この一話だけで泣いた」「まるで映画のよう」といった感想が溢れ、Blu-ray版でも特典としてフルサイズ映像が収録されたほどの人気を誇る。
5. 王都での騒動とケーナの“お母さん力”
第8話以降で描かれる王都編は、シリーズ中盤のコミカルなハイライトだ。 スカルゴの暴走的な信仰心、マイマイの過剰な母愛、そしてカータツの現実的なツッコミ――それぞれの個性がぶつかり合い、騒がしくも愛らしいエピソードが連続する。 ケーナはその中心で、まるで学級担任のように皆をまとめる。 「もう、あなたたち大人でしょ」と呆れながらも、決して突き放さず見守る姿勢が印象的だ。 この場面では、ケーナの包容力が最も発揮されており、視聴者の間では「ケーナは異世界の理想の母」「この人に叱られたい」といったコメントが多く見られた。 作画的にも日常コメディのテンポが秀逸で、家族の喧騒が“幸福の音”として描かれている。
6. 過去のログとの邂逅――“生と記録”の対話
物語終盤、第11話に登場する「過去のログ」シーンは、本作の哲学的な核心に触れる。 ケーナが自らの塔の中で、200年前の“自分の記録データ”を発見する――そこには、生命維持装置に繋がれた現実の桂菜が、「もし次に目を覚ましたら、誰かと笑っていたい」と残したメッセージがあった。 彼女は静かに端末を閉じ、涙を流さず、ただ微笑む。 「ありがとう。もう、叶ったよ。」 この一言で、すべての物語が静かに回収される。 視聴者の多くがこの場面を“魂の浄化シーン”と呼び、「派手な最終決戦よりも何倍も胸を打つ」と高く評価した。 音楽は最小限、照明は柔らかく、画面全体が“静寂の救済”に包まれている。 異世界での冒険が、現実世界の少女の願いを成就させる――そんな優しい奇跡を描いた、シリーズ屈指の名場面である。
7. 最終話の食卓――“ここで生きる”という選択
最終話、ケーナとルカ、そして仲間たちが一緒に食卓を囲むシーンは、作品の象徴ともいえる。 豪華な食事ではなく、ありふれたスープとパン。しかし、そこにあるのは確かな幸福だ。 ケーナが「ごはん、いただきます」と呟く声が小さく響くと、音楽が消え、焚火の音と笑い声だけが残る。 視聴者の多くはこのラストに深い安らぎを覚え、「終わってほしくないけど、この終わり方が一番美しい」と語った。 スタッフもインタビューで「このシーンの“静けさ”をどう守るかに全精力を注いだ」と語っており、最終回の象徴的な映像美としてファンの記憶に残り続けている。
8. 余韻としての“日常”――終わらないリアデイル
エンディングロール後、ケーナが塔の窓辺で「明日も、いい日になりますように」と微笑むカットが挿入される。 このわずか数秒の映像が、視聴者の心に永く残った。 “物語が終わっても、世界は続いている”――そんな余韻を感じさせるラストは、ファンタジーでありながら現実の明日への希望にも繋がっている。 この最終カットこそが、『リアデイルの大地にて』という作品の核心であり、「静けさの中にある幸福」というメッセージを最も美しく表現した瞬間だった。
総括――“何も起こらないこと”の尊さ
本作の好きな場面を振り返ると、共通しているのは「大事件がない」ことだ。 剣も魔法もある世界でありながら、印象に残るのは人の手の温度、食卓の明かり、優しい声。 “何も起こらない日常こそ、奇跡なのだ”という静かなメッセージが、すべての名シーンに通底している。 『リアデイルの大地にて』は、視聴者に派手なカタルシスではなく、“生きることそのものへの感謝”を残して幕を閉じる。 そして、エンドロールが終わったあと、私たちもまた――“明日を少し優しく過ごそう”と思えるのだ。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
1. ケーナ ―
優しさと力強さを兼ね備えた“静かな主人公”
やはり『リアデイルの大地にて』で最も心を掴むのは、主人公ケーナだ。 彼女は典型的な“チート系最強キャラ”の立ち位置にありながら、その力を誇示せず、むしろ「どう使わないか」を常に考える。 彼女の本当の強さは、魔法の威力ではなく、“他者を理解しようとする姿勢”にある。 ルカや村人たちに寄り添い、失敗を責めず、過去を抱えながらも前に進む姿勢は、視聴者にとって希望そのものだ。 「私は、ただ誰かと一緒に笑っていたいの」――この言葉は、彼女が戦わない理由であり、異世界に生きる意味そのもの。
ケーナの魅力はまた、“再生”というテーマの体現者でもある点にある。
現実で命を落とした少女・桂菜が、VR世界の記憶をそのままにこの世界で生き直す。
その設定は一歩間違えば悲劇になりかねないが、彼女はそれを笑顔で受け止める。
まるで「悲しみを抱えたまま幸せになる」ことの美しさを、彼女の人生が示しているかのようだ。
視聴者は彼女を見るたびに、“やり直すこと”への勇気をもらう。
戦わずして心を救う主人公――ケーナはまさに、癒し系ファンタジーの象徴である。
2. ルカ ―
無垢の象徴、そして“もう一人のケーナ”
ルカはこの作品における“癒しの化身”であり、物語の中心的な emotional core(感情の核)でもある。 幼くして家族を失い、恐怖の中で震えていた少女が、ケーナに抱かれて少しずつ笑顔を取り戻していく過程は、視聴者の多くが涙したシーンだ。 ルカは単なる守られる存在ではない。 後半では、ケーナに「お母さん、無理しないでね」と声をかけるシーンがある。 その言葉は、彼女がただの子どもから“支える側”へと成長した瞬間でもある。 この関係性の反転――“守る者と守られる者”の境界がなくなる瞬間――が、作品の根底に流れる優しさの証だ。 ルカは視聴者に、“優しさは伝播する”ということを静かに教えてくれる。
3. スカルゴ
神官であり、究極のマザコン
スカルゴは“笑い”と“愛情”の両方を担う異色のキャラクターだ。 彼のマザコンぶりは尋常ではなく、登場するたびに視聴者を爆笑させる。 だが、その奇行の裏には、200年という時を経てなお母を想い続けた息子の純粋な愛が隠れている。 彼にとってケーナは「神」ではなく、「帰る場所」だ。 母への祈りを信仰に昇華し、国を導いてきたスカルゴの姿は、実は極めて人間的でもある。 彼のセリフ「母上殿は、我が心の光!」はギャグでありながら、同時に彼の生き方そのもの。 滑稽と真剣が同居する稀有なキャラクターであり、小野大輔の声が持つ重厚さとユーモアのバランスが絶妙に効いている。 視聴者の間では「母上クラスタ」「スカルゴ教」などの言葉が生まれ、ネタ的な人気も高い。 だが彼が真面目に母のため祈る姿に、思わず胸が熱くなる人も多かったはずだ。
4. マイマイ
知性と感情の狭間で揺れる“娘”
マイマイは理性的な知識人でありながら、母に会えばすぐに甘えん坊になるというギャップが愛されている。 王立学院の校長として生徒を導く彼女が、母の前で「お母様~!」と抱きつく姿には、誰もが微笑ましい気持ちになる。 彼女は頭脳明晰でクールな印象を保ちながらも、心の奥では“愛されたい子ども”のまま。 そのギャップが彼女の最大の魅力だ。 さらにマイマイは、“知識と愛情の両立”を象徴しているキャラクターでもある。 学問的に正しくとも、人の心を理解しなければ意味がない――その教えを彼女の言葉と行動が伝えている。 名塚佳織の演技は、この繊細なバランスを完璧に再現し、ファンの間では「マイマイ先生推し」が多数を占めた。
5. カータツ
理想の“常識人兄弟”
カータツは、暴走気味の兄姉の中で一人冷静さを保つ貴重な存在だ。 ドワーフ族らしく実直で誠実、そして“働く人”としてのリアリティを持つ。 視聴者は彼の職人気質と、家族を大切にする温かさに共感を覚える。 彼がケーナに「おふくろ、俺が作った鍋だ。使ってくれ」と照れくさそうに差し出すシーンは、さりげないが屈指の名場面。 派手ではないが、“心に残る優しさ”を体現する存在だ。 杉田智和の低音ボイスも彼の穏やかな人格にぴったりで、静かなカリスマ性を放っている。 カータツはこの作品における“地の重力”――つまり、世界を現実に引き戻す錨のようなキャラクターである。
6. オプス
皮肉屋であり、旧友の影
スキルマスターNo.13、オプスは物語にスパイスを加える存在だ。 ケーナの旧友としての複雑な距離感、敵でも味方でもない中立の立場、そしてどこか憎めない皮肉屋のキャラ性。 彼は“過去の亡霊”のように現れ、ケーナに“自分が残してきた世界の重さ”を思い出させる。 一見すると軽薄だが、根底には深い友情と孤独がある。 ケーナに対して「お前は本当に、あの頃のままだな」と言う場面では、声に哀しみがにじむ。 視聴者の間では「オプスのスピンオフが見たい」という声も多く、作品の余白を感じさせるキャラクターとして人気を博している。
7. ミミリィ
歌声で世界を癒す存在
人魚族の少女ミミリィは、物語中盤で強烈な印象を残すキャラクターだ。 彼女の透き通るような歌声は、まさに“音の癒し”そのもの。 孤独に歌う彼女の姿は、ケーナ自身の過去を投影したようでもあり、二人の共鳴がこの作品の核心を照らす。 二ノ宮ゆいの声は、歌と芝居の境界をなくし、感情そのものを音に変えている。 ミミリィは“癒しの象徴”でありながら、“悲しみを受け入れる強さ”も備えた存在で、彼女を好きだというファンは非常に多い。 特に女性視聴者からは「声も性格も美しい」「彼女の回で泣いた」という感想が多く寄せられた。
8. ロクシリウスとロクシーヌ
生活を支える忠実な従者たち
ケーナの召喚従者であるロクス(ロクシリウス)とシィ(ロクシーヌ)は、物語の“日常の潤滑油”。 二人の掛け合いはコメディのテンポを支える一方で、家族的な温かさを作り出す。 ロクスは忠実な執事型で、シィは姉のような存在。彼らは命令に従うAI的な存在だったはずが、いつの間にか“家族の一員”として生きている。 彼らがケーナに「お帰りなさいませ」と言う声に、AIではない“感情”が宿っているのを感じる。 この二人の存在が、リアデイルの世界を“ただのゲーム”ではなく“生きた家”へと変えている。
9. トライスト王とフェルスケイロの人々
人間らしさの象徴
フェルスケイロ王トライストや王妃アルナシィ、そして王子・王女たちは、いわゆるサブキャラでありながら、リアリティを強く感じさせる。 特に王子の小さな冒険騒動は、ケーナの優しさを引き出す装置として機能しており、“権力者にも家族がある”というメッセージを伝えている。 この作品に登場する人々は、誰もが欠点を持ち、時に間違いを犯すが、それでも憎めない。 だからこそ、視聴者はこの世界を“自分も住みたい場所”だと感じるのだ。
総括
“誰も悪人がいない世界”の優しさ
『リアデイルの大地にて』のキャラクターたちは、全員が“誰かを想って行動する”。 悪意や破壊よりも、誤解や不器用さから生まれる衝突が中心で、誰も完全な悪役として描かれない。 その結果、視聴者は安心してこの世界を愛せる。 ケーナという中心点を軸に、家族、友人、従者、王族、村人、すべてのキャラクターが優しい関係で繋がっている。 この“優しさのネットワーク”こそが本作最大の魅力であり、登場人物の誰かを好きになることが、作品そのものを好きになることと同義なのだ。
[anime-8]
■ 関連商品のまとめ
1. 映像関連商品
Blu-ray・DVD・配信版の展開
『リアデイルの大地にて』の映像商品は、テレビ放送終了後の2022年春から順次リリースされた。 Blu-ray・DVDともに全3巻構成で発売され、それぞれに初回限定特典が付属。ジャケットはイラストレーター・てんまそによる描き下ろしで、原作の柔らかな世界観をそのままに再現している。
第1巻には第1話から第4話までを収録し、封入特典として特製ブックレット(スタッフ・キャストインタビュー付き)と特典CDが付属。CDにはBGM集と、TRUEが歌うオープニング「Happy encount」のTVサイズ、さらに未発表インストゥルメンタルが収録された。
第2巻ではルカ編を中心に、特典として「ミミリィの歌(Mother of Pearl)フルバージョン」や高尾奏音・幸村恵理によるオーディオコメンタリーを収録。
最終巻である第3巻は、最終話を含む第9~12話を収録し、シリーズ全体を総括するスペシャルメイキング映像「リアデイルの裏側にて」が付属した。
さらに、KADOKAWA公式通販サイト限定版では、三巻収納BOXとB2サイズポスター、そして描き下ろしミニサウンドトラックが特典として追加され、ファンから高い評価を得た。
近年では配信プラットフォームでも広く展開されており、Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXTなど主要VODで全話視聴可能。特にPrime Videoでは放送終了後2週間でランキング上位に入り、「癒し枠」として定着した。
高画質配信版ではHDR補正が行われ、湖や草原などの自然描写がより鮮明に再現されている。再生環境によってはBlu-rayより美しい映像と評されることもあり、デジタル版購入者も増加傾向にある。
2. 書籍関連
原作・スピンオフ・公式ガイド
原作小説はCeezによるライトノベルで、ファミ通文庫(KADOKAWA)より2019年から刊行。現在も継続的に人気を維持しており、アニメ放送時に合わせて表紙をアニメ仕様にした「アニメ放送記念帯付き版」が再販された。 シリーズは第1巻から第8巻まで発売されており、各巻の表紙はてんまそによるイラスト。ハイエルフ・ケーナの幻想的な雰囲気が印象的で、書店のライトノベルコーナーでも際立った存在感を放っていた。
コミカライズ版は月見だしおの作画によって『WEBデンプレコミック』で2019年より連載が始まり、後に『電撃コミックレグルス』へ移籍。単行本はKADOKAWAから第1~5巻が刊行されており、アニメ化を機に大幅重版。
漫画版は原作よりもコメディ色が強く、ケーナと子供たちの掛け合いを中心にテンポよく進行する。ファンの間では「アニメで泣き、漫画で笑う」と評されるほど表情豊かな描写が魅力とされている。
さらに、アニメ制作陣のインタビュー・設定資料・美術ボードなどを収録した公式ガイドブック『リアデイルの大地にて ― 旅の手引き―』が発売された。
このガイドにはケーナのステータス画面、各地の地図、種族一覧、そしてケーナの子供たちの“没設定案”まで掲載され、世界観資料としての完成度が非常に高い。
出版当時、KADOKAWAオンラインでは限定特典として「ルカの描き下ろしミニ色紙」が付属し、即日完売する人気を見せた。
3. 音楽関連
心を包む優しい旋律たち
音楽関連では、TRUEのオープニング「Happy encount」と田所あずさのエンディング「箱庭の幸福」が単独シングルとしてリリース。どちらもアニメ放送に合わせて2022年1月にランティスより発売された。 CD版にはTVサイズ、フルサイズ、インストゥルメンタルが収録され、初回限定盤にはノンクレジットOP・ED映像を収めたBlu-rayが同梱。
特に「Happy encount」は“朝の目覚めにぴったりな曲”としてSNSで話題となり、アニメファンのみならず一般リスナーにも支持を拡大。
一方「箱庭の幸福」は、ケーナとルカの関係を思わせる優しいメロディが特徴で、YouTube公式チャンネルでは100万回再生を突破した。
また、BGMを手がけた神田ジョンと夢見クジラによるオリジナルサウンドトラックCDも高い評価を受けた。
全36曲を収録したアルバムには、ミミリィの挿入歌「Mother of Pearl(Full Ver.)」も収録されており、透明感ある歌声と穏やかなピアノの旋律が作品の余韻をそのまま再現している。
このサントラは、ファンの間で“疲れた時に聴くアルバム”として定着し、リラクゼーション系プレイリストにも多く採用されている。
4. ホビー・グッズ・フィギュア関連
アニメ放送後、KADOKAWAとグッドスマイルカンパニーのコラボによりねんどろいど ケーナが制作・販売された。 ハイエルフの装束、銀色の髪、柔らかな表情が精密に再現されており、交換用フェイスパーツ(微笑み顔/照れ顔/戦闘顔)も付属。 さらに、ルカのミニフィギュアと手繋ぎパーツも同梱され、“母娘セット”として飾れる仕様になっている。 このねんどろいどは発売前から大きな注目を集め、予約開始直後に完売。再販リクエストも多数寄せられた。
また、アクリルスタンド・缶バッジ・クリアファイル・アートボードなどの定番グッズが、アニメイト・ゲーマーズ・メロンブックスなどの店舗で販売された。
特に人気だったのは、描き下ろし「ケーナとルカのティータイムver.」シリーズで、淡い光の表現が高品質だと好評だった。
そのほか、マグカップ、トートバッグ、卓上カレンダーなどの日用品型アイテムも展開され、生活の中で“リアデイルの癒し”を感じられるラインナップが揃った。
5. コラボレーション・キャンペーン
アニメ放送期間中には、KADOKAWA公式の通販サイト「エビテン」およびカフェコラボ「キュアメイドカフェ」にて期間限定コラボが開催された。 店内ではケーナの好物をイメージした「銀環のエルフプレート」や「ルカのミルクティー」が提供され、注文特典として限定コースターやポストカードが配布された。 また、アニメイトでは「リアデイルの大地にて フェア」が実施され、関連グッズ購入で“特製しおりセット”がもらえるキャンペーンも展開。 これらの企画はSNSでも話題となり、ファン同士の交流を促すイベントとして人気を博した。
6. デジタルグッズ・オンライン展開
放送終了後、KADOKAWA公式よりLINEスタンプと壁紙配信が開始。 スタンプはケーナやスカルゴの名台詞をモチーフにしたユーモラスな内容で、「母上殿!」や「まったりしよう」など、ファンの間で日常的に使えるフレーズが人気を集めた。 また、スマートフォン用の公式壁紙セットは、てんまその新規イラストを使用。夜空を見上げるケーナとルカの姿は、ファンの中で“癒しのホーム画面”として定着している。
7. ゲーム・アプリでの登場
直接的なゲーム化はされていないが、2022年夏にKADOKAWA系スマホアプリ『ファンタジア・リ:コネクト』とのコラボイベントが実施された。 期間限定でケーナがプレイアブルキャラクターとして登場し、イベントストーリーでは「異世界の訪問者」として他作品のキャラと交流。 ボイス付きシナリオは完全新録で、幸村恵理の優しい語り口が再びファンを魅了した。 このコラボをきっかけに、他メディア作品への登場希望の声も増え、シリーズの“横の広がり”が加速した。
8. ファンブック・アート展・限定展示
アニメ放送1周年を記念して、2023年1月には秋葉原UDX内で『リアデイルの大地にて 原画&資料展』が開催。 各話の原画・美術設定・絵コンテが展示され、来場者には描き下ろしポストカードがプレゼントされた。 会場限定販売として「アートブック『ケーナの記録帳』」が頒布され、これはアニメの美術スタッフと監督によるコメント付き豪華本として高い評価を得た。 ファンブックは現在も中古市場で高値を維持しており、熱心なファンの間では“リアデイル聖典”と呼ばれている。
9. 総括 ― “癒し”を形にしたメディア展開
『リアデイルの大地にて』関連商品は、派手な展開よりも“温もりと実感”を重視したラインナップが特徴的である。 どの商品も、作品のテーマ――「穏やかに生きる」「誰かと共に過ごす幸福」――を形として感じられるよう工夫されている。 豪華さよりも“そっと手元に置いておきたい”優しいデザインが多く、ファンの生活に寄り添うような商品展開だった。 アニメの世界観がそのまま生活雑貨や音楽、書籍として広がり、まさに“癒しのメディアミックス”を実現したと言える。
[anime-9]
■ 中古市場・オークション動向
1. Blu-ray・DVDの中古価格動向
『リアデイルの大地にて』のBlu-ray・DVDは、発売当初から一定の需要があり、現在(2025年時点)でも中古市場で安定した取引が続いている。 特に注目されているのは、初回限定版の3巻BOXセットで、アニメイト・KADOKAWAストア限定特典の描き下ろし三方背BOXやミニサントラCDが付属する仕様。 2023年初頭には定価付近で取引されていたが、2024年以降に再評価の波が起こり、中古価格は一時的に上昇。 現在の相場では、3巻セットでおおよそ1万5000~2万2000円前後が相場。状態が良好な未開封品や、特典ポスター付きのものは2万5000円を超えるケースもある。
単巻での中古流通もあるが、特典が欠品している場合は価格が下落傾向。
特に第2巻は「ルカ編」や「ミミリィの歌」が収録されている人気巻であるため、他巻より高値で推移しており、1巻あたり5000~7000円台で安定している。
Blu-ray版が人気なのに対し、DVD版は比較的安価で流通し、コレクターよりも視聴目的の需要が中心。中古ショップやネットオークションでは3000円前後から入手可能だが、パッケージの保存状態にこだわるファンはBlu-rayを好む傾向が強い。
2. サウンドトラック・音楽関連商品の価値
音楽関連商品もコレクターズアイテムとして高い人気を保っている。 TRUEが歌うオープニングテーマ「Happy encount」と田所あずさのエンディング「箱庭の幸福」は、発売当時からAmazonやアニメイトで品薄状態となり、特に初回限定盤(Blu-ray付き)は現在中古市場で3000~4000円台で取引されている。 通常盤CDも1000円台後半で安定しており、音楽CDとしては比較的高値での推移が続いている。
サウンドトラックCD『リアデイルの大地にて Original Soundtrack』は、2022年春に発売されて以降、ファンの間で“癒し系アルバムの定番”とされている。
もともと生産数が少なく、再販が行われなかったため、現在では入手困難品となっており、中古市場では4000~6000円前後が相場。
新品未開封品は8000円を超えることもあり、オーディオファンからも評価が高い。
特に「Mother of Pearl」収録版は需要が集中しており、オークションでは競争率が高く、即決価格で落札されるケースも多い。
3. 原作ライトノベル・コミカライズの取引状況
原作小説シリーズは、アニメ化に伴い重版が行われたこともあり、市場にある程度の在庫が存在するため、入手自体は比較的容易。 ただし、アニメ帯付き初版や、表紙がアニメ版仕様になった特装版はプレミア化している。 現在、特装版1~8巻セットで6000~9000円前後、単巻では700~1200円が相場。 また、著者Ceezとイラストレーターてんまその直筆サイン入り本がイベント限定で存在しており、これらは非常に高額で取引される。 状態が良いものは2万円以上で落札されるケースも確認されている。
コミカライズ版は5巻セットで3000~4000円前後。アニメ放送記念の帯付き初版や限定ポストカード付きの特典版はプレミア傾向にあり、コンプリートセットで5000円を超えることもある。
漫画版は特に絵柄の人気が高く、完結後にファンが“保存用”として再購入するケースが多い。市場全体としては、原作よりも“装丁・特典”の価値が価格を左右している。
4. フィギュア・グッズ・限定アイテムの価値推移
グッズの中で最も高値を維持しているのは、ねんどろいど ケーナ&ルカセットである。 初回販売時の定価は約7200円だったが、再販が未定のため、現在は中古市場で1万2000~1万8000円前後まで上昇。 特に未開封・外箱美品のものはコレクター需要が高く、メルカリやヤフオクでは発売当時の2倍以上の値をつけることも珍しくない。 ルカのミニフィギュア付きセットは特に人気が集中しており、“母娘で飾れる”仕様がファン心理をくすぐっている。
一方、アクリルスタンドや缶バッジなどの小型グッズは、イベント限定・描き下ろしデザインのものほど高値で取引される傾向にある。
「ティータイムVer.」シリーズは現在でも1点1000円前後で取引され、全種コンプリートセットになると1万円を超える。
特に、キュアメイドカフェコラボ限定コースターは、配布枚数が少なかったため希少価値が高く、状態によっては3000円以上の値がつくこともある。
総じて、グッズ類は“限定生産+温かい絵柄”という条件から、供給よりも需要が上回る傾向にあり、年数が経つごとに価値がじわじわ上昇している。
5. ファンブック・資料集・アートブックの価値
ファンブック『リアデイルの大地にて ― 旅の手引き―』および展示会限定の『ケーナの記録帳』は、現在もっとも入手困難な関連書籍として知られる。 前者は定価2750円だったが、中古市場では状態良好品が8000~1万円前後、帯付き未開封品は1万2000円以上で落札されることもある。 後者の『ケーナの記録帳』はイベント限定のため、出品数自体が極端に少なく、確認されるたびにオークションでは激戦状態。 平均相場は1万5000~2万円前後、サイン入り・購入特典付きの場合は3万円を超えることもある。
これらの書籍は、単なるグッズではなく“資料性”が高いため、アニメファンだけでなくイラストレーターやデザイナーにも人気がある。
特に美術設定・ライティング資料・背景彩色の工程解説などが収録されており、同業者の学習素材としても需要がある点が特徴的だ。
6. オンライン市場・取引傾向
中古取引の主戦場は、メルカリ・ヤフオク・駿河屋・まんだらけの4つが中心。 メルカリは個人売買ゆえに価格変動が激しいが、需要の高さを反映して出品から数時間で落札されることも多い。 ヤフオクはコレクター層が多く、特典や保存状態による評価が細かく分かれるため、高品質品ほど高値を維持している。 駿河屋では“査定価格リスト”が公開されており、シリーズ商品の買取相場はBlu-ray BOXで約1万2000円前後、ねんどろいどで8000円台と安定している。 まんだらけでは、展示会限定アイテムなど希少商品にプレミアを上乗せして販売するケースが多く、コレクター向け店舗として一定の地位を確立している。
7. ファンコミュニティによる価値の持続
中古価格の安定には、作品のファン活動も密接に関わっている。 アニメ終了後もSNSやpixivでの二次創作投稿が続き、特にケーナとルカの“母娘愛”をテーマにしたイラストは根強い人気を誇る。 そのため、グッズや書籍は単なる過去の作品関連商品ではなく、“今も愛されている作品の証”として取引されている。 これが『リアデイルの大地にて』の中古市場を支える大きな要因となっており、他の癒し系ファンタジー作品に比べても異常なまでに安定した相場を形成している。 再放送や続編発表が行われれば、これらの相場はさらに上昇する可能性が高い。
8. 総括 ― “癒し作品”が生み出す持続的価値
『リアデイルの大地にて』の中古市場は、単なる希少性によるプレミアではなく、作品そのものへの長期的愛着によって支えられている。 派手なバトルやブーム的な人気ではなく、“静かで穏やかな癒し”を求める層が一定数存在するため、時間が経っても価値が下がりにくい。 グッズ、書籍、映像、音楽――どのカテゴリーにも共通しているのは、「持っていると心が落ち着く」という感覚だ。 つまり『リアデイルの大地にて』の商品群は、“所有する癒し”として機能している。 コレクターズアイテムであると同時に、日常の小さな安心の象徴。 その温かさが、この作品の中古市場を静かに、しかし確実に支え続けているのである。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
リアデイルの大地にて3【電子書籍】[ Ceez ]
リアデイルの大地にて4【電子書籍】[ Ceez ]
リアデイルの大地にて 6 (電撃コミックスNEXT) [ 月見だしお ]




 評価 4.75
評価 4.75リアデイルの大地にて 7 (電撃コミックスNEXT) [ 月見だしお ]




 評価 3.33
評価 3.33リアデイルの大地にて8 [ Ceez ]




 評価 4.67
評価 4.67リアデイルの大地にて 第2巻 [ 幸村恵理 ]
リアデイルの大地にて6 [ Ceez ]




 評価 5
評価 5
![リアデイルの大地にて3【電子書籍】[ Ceez ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9157/2000007829157.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて4【電子書籍】[ Ceez ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4886/2000008324886.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて 6 (電撃コミックスNEXT) [ 月見だしお ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3552/9784049153552_1_3.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて 7 (電撃コミックスNEXT) [ 月見だしお ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0345/9784049160345_1_4.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて8 [ Ceez ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9290/9784047369290_1_2.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて 第2巻 [ 幸村恵理 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1906/4988111661906_1_3.jpg?_ex=128x128)
![リアデイルの大地にて6 [ Ceez ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5094/9784047365094.jpg?_ex=128x128)