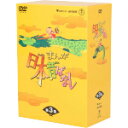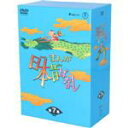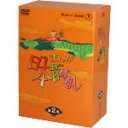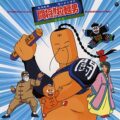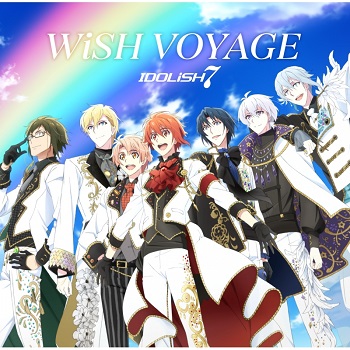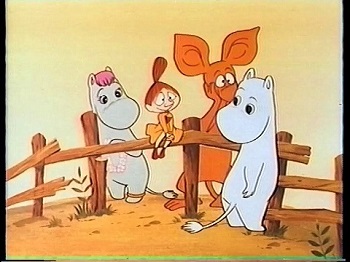まんが日本昔ばなしDVD7巻組 ユーキャン通販




 評価 5
評価 5【監修】:川内康範
【アニメの放送期間】:1975年1月7日~1995年1月2日
【放送話数】:全1470話
【放送局】:NETテレビ系列・TBS系列
【関連会社】:愛企画センター、グループ・タック、亜細亜堂、あかばんてん
■ 概要
日本の昔話を“映像の絵本”にした国民的アニメ
『まんが日本昔ばなし』は、1975年1月7日に放送が始まり、およそ20年間にわたってお茶の間に親しまれた、日本の民話・昔話アニメの代名詞ともいえる作品です。愛企画センター、グループ・タック、毎日放送(MBS)が共同で制作し、当初はNETテレビ(現・テレビ朝日)系列、その後はTBS系列でレギュラー放送が続きました。
1回30分の枠の中に、日本各地に伝わる昔話を1話または2話ずつ収めたオムニバス形式の番組で、視聴者は毎週、絵本をめくるような感覚で新たな物語と出会うことができました。物語の舞台は東北の山里から瀬戸内の漁村、京の都まで多岐にわたり、「桃太郎」「かぐや姫」「浦島太郎」といった超メジャーな題材だけでなく、各地にひっそりと伝わるローカルな伝承も数多く取り上げられています。
レギュラー放送としては1994年9月まで続き、その後も特番などを通じて1995年1月2日まで新作・再編集版が放送されました。放送期間だけを見ても“昭和の半分以上+平成初期”をカバーしており、親・子・孫の三世代が同じ番組の記憶を共有している、きわめて希有なアニメシリーズと言えます。
企画と制作体制 ― 川内親子が描いた「日本の心」
番組の企画を担ったのは、童話作家としても知られる川内彩友美。彼女が率いた愛企画センターが企画・制作の中核となり、父であり作詞家としても著名な川内康範が全体監修を務めました。
川内康範は、特撮ドラマ『月光仮面』など数多くの作品で“正義”や“人の情”を強く打ち出してきた人物であり、その思想や美学は『まんが日本昔ばなし』にも色濃く反映されています。勧善懲悪の単純さだけにとどまらず、「弱い者が救われる」「親子の情が報われる」「欲深さには必ず代償がある」といった、人としての生き方をそっと問いかけるような終わり方が多いのも、その影響と言えるでしょう。
実制作を担当したアニメーションスタジオはグループ・タック。虫プロ出身スタッフらが合流して立ち上がったスタジオで、本作によって初めて本格的なテレビシリーズの制作を手がけました。
毎日放送はキー局として番組の枠を提供し、旧NETテレビでの試験的な放送を経て、土曜19時台という“家族がそろうゴールデンタイム”に定着させていきます。
このように、民話を愛する企画サイドと、新しいアニメ表現に挑戦したいクリエイター集団、そして子ども向け番組作りに実績のある放送局が組み合わさったことで、『まんが日本昔ばなし』は単なる児童向け番組ではなく、日本文化を語るうえで外せない作品にまで成長していきました。
毎回完結のオムニバス形式とシンプルな構成
本作の大きな特徴は、1話完結型のオムニバス形式に徹している点です。30分枠の中に10~15分程度のエピソードを2本収める構成が基本で、場合によっては特別編として1本をじっくり描くこともありました。
この構成の利点は、どの回から見ても楽しめる“敷居の低さ”にあります。仮に数週間見逃してもストーリーの連続性が失われることはなく、テレビの前に座ったその週の話だけで完結した満足感が得られます。また、短い尺の中に“起承転結”をきっちりと組み立てる必要があるため、脚本・演出面では非常に高度な構成力が求められました。
さらに、エピソードごとに作画監督や演出家、美術スタッフが大きく入れ替わるため、回によって映像のテイストがガラリと変わるのも魅力です。素朴で柔らかな線のものから、水墨画風の渋いタッチ、前衛的ともいえるデフォルメ表現まで、視聴者は“日本の昔話美術館”を巡るような感覚で毎週異なるビジュアルを楽しむことができました。
市原悦子&常田富士男、二人だけの語りが作る世界
『まんが日本昔ばなし』を語るうえで欠かせないのが、語り手である市原悦子と常田富士男の存在です。番組の声は基本的にこの二人だけで構成されており、老若男女・人間・動物問わず、すべての役柄の声を演じ分けていました。
市原の持つ包み込むような温かさと、時に鬼婆や山姥さえも生々しく感じさせる迫力ある表現。常田の落ち着いた渋い声色と、ユーモラスな役を演じるときの軽妙なテンポ。この二人の語りが重なることで、画面に映っている以上の広がりを物語に与えています。
また、ナレーションとセリフの境界が非常に柔らかいのも特徴です。出来事を淡々と説明するナレーションから、そのままスッと登場人物のセリフに入り込んでいく演技は、視聴者に「誰かがそばで昔話を聞かせてくれている」という感覚を抱かせます。録音方法も、当時としては珍しいシネテープ収録が採用されており、芝居の“間”や息づかいがより自然に残るよう工夫されていました。
結果として、この二人の声そのものが番組の大きなアイコンとなり、後年の再放送やソフト化でも「オリジナルの語りをそのまま残すこと」が最重要ポイントとして扱われています。
一流クリエイターが描く「日本の原風景」
アニメーション制作の現場には、当時すでにベテランの域にあったアニメーターや、美術家、イラストレーターが多数参加しました。東映動画や虫プロダクションといった大手スタジオ出身者が流れ込み、各話ごとに異なるチームが担当することで、作品全体は統一された世界観を保ちながらも、表現面では非常にバラエティ豊かになっています。
背景美術においては、昭和の農村風景・城下町・山里・港町などが、単なる“記号的な田舎”ではなく、それぞれの地域性や季節感が伝わる形で精密に描き起こされました。棚田の段差や、雪国の重い空、夏祭りの提灯の灯りといった細部の描写が、視聴者の記憶の中に強く刻まれています。
また、作画・演出面では、子ども向け作品でありながら“怖さ”や“哀しさ”をあえて正面から描くエピソードも少なくありません。妖怪や亡者が登場する話では、今見てもぞくりとするような表現が多用され、逆にコミカルな話では極端なギャグ描写で大笑いさせられます。こうした振れ幅の大きさが、“面白いけれどどこか不思議で怖い”という『まんが日本昔ばなし』独自の空気を作り出しました。
数々の賞と、現代へ受け継がれる評価・リマスター展開
番組は放送当時から高い評価を受けており、児童向けの優れた文化作品に贈られる厚生省児童福祉文化賞や、文化庁優秀映画作品賞など、数多くの賞を受賞しています。
教育的価値と娯楽性を両立させた点、そして地方の民話を掘り起こして全国に紹介した点が特に評価されました。
放送終了後も、その価値は色あせることなく、2000年代以降は再放送やDVD-BOXなどで世代を超えて親しまれ続けています。2023年には4Kデジタルリマスター版のBlu-ray/DVDが発売され、高画質で蘇った映像が大きな話題となりました。
かつて子どもだった視聴者が親・祖父母となり、自分の子や孫に同じ昔話を見せるという、“時間をまたぐリレー”が実際に行われている作品です。
こうした長年の支持により、『まんが日本昔ばなし』は単なるアニメ番組を超え、「日本の昔話アーカイブ」としての役割も担うようになりました。物語の舞台となった地域では、今でも観光PRや地域イベントで本作のエピソードが言及されることがあり、日本各地の文化・風習・言い伝えを後世に残すうえで重要なメディアとなっています。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
“日本の心”を毎週届けたオムニバス形式の物語世界
『まんが日本昔ばなし』の物語構成は、きわめてシンプルでありながら、他のアニメにはない独自の深みを備えています。本作は、各地に伝わる民話・昔話を1話完結で描くオムニバス形式を取り、その内容は「笑い」「教訓」「恐怖」「哀しみ」「希望」など、感情の振れ幅が非常に広い点が特徴です。
一話あたりの尺はおよそ10〜15分。限られた時間の中で、起承転結が明確に描かれ、幼い子どもでも理解しやすい構成でありながら、大人が見ても心に残る余韻があります。これは“昔話”という素材が本来もっている普遍性と、アニメスタッフの高い構成力が合わさって初めて成立したものです。毎週テレビの前に座ると、まるで祖父母が読み聞かせてくれるような、あたたかい世界が広がっていました。
全国各地に伝わる民話を《映像の絵本》として再構築
取り上げられる昔話は、全国の山間部、漁村、農村、城下町など、地理も文化も異なる多様な地域が舞台となっています。東北の“なまはげ”伝説を原型とした話や、関西の商人文化が生んだ軽妙な民話、九州の海の怪異譚まで、地域色・季節感・風習の違いが明確に物語へ反映されています。
たとえば、冬の雪深い村を舞台にした話では、吹雪の音や雪明かりが心理描写の背景となり、夏祭りが舞台の物語では、提灯の灯りや笛太鼓の音色が物語の熱とともに描かれます。視覚と音の双方で“土地の空気”を伝えるため、その地域出身のスタッフがリサーチに参加することもありました。
これにより、各話は単なる昔話の再現ではなく、「その土地に暮らす人々の生活」を感じ取れる小さなドキュメンタリーでもあったのです。
代表的なエピソードの構造とテーマ
番組には数百に及ぶエピソードがありますが、そのほとんどに共通するのは「人として大切なこと」を物語に織り込む姿勢です。代表的な構造を、いくつかのテーマに分けて紹介します。
● 教訓型エピソード
「こぶとり爺さん」「舌切り雀」「三枚のお札」など
欲張り・怠け・うそをつく・礼儀を欠くなど、人間の弱さを描きながら、その代償や結果を明確に示すタイプのお話です。
子ども向けでありつつ、“社会で生きる上のルール”を優しく、時に厳しく伝える内容が多いのも特徴です。
● 勧善懲悪型エピソード
「鬼退治」系の話、「だんまりくらべ」など
善良な人が報われ、悪意ある者が罰を受ける分かりやすい構造。
しかし、本作では単なるヒーロー物語としてではなく、善行に至る動機や、人々の連帯をしっかり描くなど、深い解釈が加えられていました。
● 哀話・涙を誘うエピソード
「笠地蔵」「雪女」「鶴の恩返し」など
静かで美しく、どこか切ない物語が語られる回。
特に「恩返し」の系譜に属する話は、幸福と喪失が入り混じった強烈な余韻を残し、多くの視聴者の記憶に深く刻まれています。
● 笑いと風刺のエピソード
「吉四六(きっちょむ)さん」「ろくろ首のお嫁さん」「天狗のかくれみの」など
ユーモアと皮肉を交えた物語で、視聴者を安心させる“箸休め”のような存在。
関西や九州の民話に多い“軽妙な語り口”が、アニメ演出と声優の芝居により、さらにコミカルに仕上げられました。
● 怪談・不思議話
「化け猫」「座敷童子」「山姥」「亡霊の話」など
本作の特徴の一つとして、“子ども向けなのに本当に怖い”という評価があります。
暗がりの描写や不気味な効果音、最低限の言葉で恐怖を煽る演出など、現在見ても背筋が寒くなるエピソードは少なくありません。
シンプルだからこそ活きる《語り》の力
あらすじ・ストーリーを語る上で欠かせないのが、市原悦子・常田富士男の名演です。2人の語り手は、ナレーションと登場人物の声を自在に切り替え、まるで“その場に語り部がいる”かのように物語を紡ぎます。
彼らの語り方は、以下のような構造美を持っていました。
ナレーションからセリフに自然に移る独特のテンポ
子どもでも理解できる簡潔な言葉選び
感情を乗せすぎない“余白”のある語り
方言や言い回しを柔らかく再現する表現
結果として、視聴者は単なるアニメ視聴ではなく「昔話を聞いている」体験を享受することができたのです。
回によって変化する映像表現 ― ホラー回・芸術回などの幅
『まんが日本昔ばなし』は、回によって絵柄・色使い・演出のトーンが大きく異なります。これはあらすじの印象にも直結し、視聴者の心にさまざまな形で残りました。
水墨画風のアート回
墨の濃淡で人物や背景を描き、静謐で凛とした雰囲気を生み出す。
ポップな線のコミカル回
太い線と大きな表情で、子ども向けギャグ作品のような明るい仕上がり。
暗闇を強調したホラー回
黒を多用し、光と影のコントラストで恐怖を演出する。
美術画集のようなファンタジー回
色彩豊かな背景と柔らかい動きで、夢のような世界観を展開。
同じシリーズとは思えないほど、バリエーション豊かな絵柄があらすじに彩りを与え、その回ならではの“空気”を生み出していました。
視聴者の心に刻まれる普遍的なメッセージ
本作のあらすじは、単なる昔話の再現ではありません。
どの話にも、以下のような普遍性が必ず含まれています。
「善意はいつか報われる」
「欲をかけば身を滅ぼす」
「他者への思いやりこそが世界を動かす」
「自然への敬意を忘れてはならない」
「失うことの悲しみと、受け入れる強さ」
この価値観は、時代が変わっても大きく揺らぐことはありません。
だからこそ本作は、現代の大人が見ても深い感動を覚え、子どもに見せたいと思う作品として受け継がれ続けているのです。
■ 登場キャラクターについて
登場人物は“全国の昔話に生きる名もなき人々”
『まんが日本昔ばなし』の登場キャラクターは、いわゆるアニメ作品にありがちな「固定の主人公」や「レギュラーキャラ」が存在しません。毎回のエピソードごとに登場するのは、その土地に生きる名もなき村人、旅人、老人、子ども、職人、商人、さらには動物や妖怪たち。まさに“昔話そのもの”が主人公であり、語り部が紡ぐ地域の記憶がキャラクターとして命を吹き込まれていきます。
この構造により、視聴者は物語ごとに全く違う世界へ旅をするような体験を得られました。都会で暮らしながらも、東北の雪深い村や、四国の山の祠、九州の漁村へと、物語を通して瞬時に〈移動〉する感覚があるのです。
キャラクターは“象徴”として機能する
昔話に登場するキャラクターには、しばしば名前がありません。たとえば「おじいさん」「おばあさん」「若者」「庄屋」「旅人」「鬼」「山姥」など、役割や立場を表す呼称が中心です。この「記号性の高さ」が、むしろ物語に普遍性と奥行きを加えています。
善良なおじいさん・おばあさん
優しさや勤労、慎ましい暮らしを体現し、視聴者の“理想の祖父母像”が重ねられることも多い。
うっかり者・ずる賢い人物
教訓を担う役割。行動によって幸・不幸がはっきり分かれ、視聴者に「こうしてはいけない」という明確なメッセージを伝える。
若者や娘
素朴で真面目な姿を描かれることが多く、努力・思いやり・純粋さが幸福を運ぶ象徴として扱われる。
動物(きつね・タヌキ・鶴・猫など)
人間と対比したり、人間以上に“情の深さ”を表現したりする存在。擬人化されすぎず、動物らしい本能や行動が物語を彩る。
妖怪・幽霊・神さま
日本の自然観や信仰を象徴する存在で、“恐れと敬い”の両方を示すキャラクターとして重要な役割を担う。
このように、キャラクターは単なる登場人物ではなく、〈日本文化の心〉を体現する象徴となっていました。
演じ分けの妙 ― 市原悦子と常田富士男が生んだ“百人の声”
本作の最大の特徴である「語り」こそが、キャラクターたちに命を与えていました。市原悦子と常田富士男は、毎週異なる数十のキャラクターをすべて演じ分け、その声の幅には驚異的なものがあります。
たとえば市原悦子は、
優しいおばあさん
甲高い少女
恐ろしい山姥
しっかり者の農婦
泣き虫の子ども
など、役柄の性別も年齢も超越した演技を見せます。
常田富士男は、
温厚なおじいさん
ずる賢い男
のんびりした若者
怖い鬼や妖怪
威厳のある神さま
など、深みのある低音と軽妙な語り口を自在に使い分けました。
二人だけでありながら、まるで大勢のキャストがいるように錯覚させる声の多彩さは、他のアニメではまず見られません。しかも、キャラを誇張しすぎず、どこか“実際にいそう”な生活感を感じさせるのも本作ならではの魅力です。
視聴者に強い印象を残したキャラクターたち
『まんが日本昔ばなし』の中で特に印象に残るキャラクターたちは、必ずしも派手な存在ではありません。しかし、深い余韻や心に刺さる教訓を残すことで、放送終了後も語り継がれる存在となっています。たとえば──
● “恩返し”の象徴となった鶴の娘
『鶴の恩返し』に登場する娘は、儚く、美しく、優しさの塊のような存在として描かれました。織機の前で細い指を動かす姿は、多くの視聴者にとって忘れられない名シーンです。
● “哀しき愛情”を背負った雪女
美しくも恐ろしく、そして悲しい運命を持つ雪女は、本作でも独特の存在感を放っていました。市原悦子の静かな声が、雪のような静謐さを演出し、恐怖と哀しみを同時に生み出します。
● “素朴で優しい夫婦”笠地蔵の老人たち
善良で誠実な夫婦の優しさが地蔵さまに届き、思いがけない幸せを得る温かい物語。
老人たちの柔らかな話し方や所作は、まるで自分の祖父母を見るような感覚を覚えた視聴者も多いでしょう。
● “狡猾で愛嬌のある”きつね・タヌキ
いたずら好きだが根は悪くない動物たちは、物語に活気を与え、ときには涙を誘う役回りを担います。昔話の動物キャラの魅力をそのまま映像化したような存在です。
● “怖さの象徴”山姥・鬼
本作のホラー回に欠かせない存在。
ただ怖いだけでなく、山の神や自然の象徴として描かれる場合も多く、日本の信仰や自然観を理解するうえで重要なキャラクター群となっています。
キャラクターの“強さ”はデザインではなく語りと物語性
現代アニメのように個性豊かなキャラデザインや戦闘能力をアピールすることはありません。
『まんが日本昔ばなし』におけるキャラクターの魅力は、 等身大の人間らしさ・感情・善悪の揺れ動き を描く点にありました。
名もなき人物でも深みのある人生を感じる
動物や妖怪にも“心”があり、時に人を助け、時に試す
行動には必ず理由があり、視聴者に「どうしてだろう」と考えさせる
こうした構造により、キャラクターたちは“名前のないまま”視聴者の心に深く刻まれます。
視聴者にとってのキャラクター ― 自分の経験と重ね合わせる存在
昭和~平成初期にかけて、本作を観て育った視聴者の多くが語るのは、 「あのキャラクターは、昔の近所の人に似ている」
「あの村の家族を見て、祖父母の姿を思い出した」 といった、個人的な思い出と物語が地続きになっているという体験です。
『まんが日本昔ばなし』のキャラクターは、視聴者それぞれの家族・地域・思い出を呼び起こす“鏡”のような存在でした。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
作品世界を象徴する“声と音楽”の存在感
『まんが日本昔ばなし』の音楽は、作品の空気そのものを形づくる重要な要素として、放送当時から高く評価されてきました。昔話特有の素朴さ・温かさ・時に恐ろしさまでも包み込む音楽は、視聴者の記憶に深く刻まれ、エンディングテーマを聴くだけで幼少期を思い出すという人も少なくありません。
オープニング・エンディングテーマは時期によっていくつかの楽曲に変わりましたが、いずれも作品の世界観に寄り添い、物語を語るための「音の語り部」として機能していました。ここでは、それぞれの楽曲の特徴や当時の視聴者から寄せられた印象を、できる限り詳細に肉付けしながら紹介していきます。
■ オープニングテーマ「にっぽん昔ばなし」
作詞:川内康範
作曲:北原じゅん
編曲:小谷充
歌:花頭巾(はなずきん)
本作の最も代表的なオープニングテーマが、この「にっぽん昔ばなし」です。素朴なメロディラインに、どこか子守唄を思わせる優しい歌声。歌詞には“山の向こうの小さな村”を思わせる情景が広がり、視聴者がこれから昔話の世界へ入っていくことを自然に予感させます。
特に印象的なのは、歌い出しの柔らかい響きです。静かに始まりながら、徐々に広がっていく音の流れは、まるで語り手が「さあ、昔々のお話だよ」と語りかけているようで、作品全体の“導入”としてこれ以上ないほど機能していました。
当時の視聴者からは、
「この歌を聞くと、土曜日の夜が始まった感じがした」
「田舎の祖父母の家に帰った気持ちになる」
「歌そのものが昔話の一部みたいだった」
といった声が多く寄せられ、まさに日本の家庭に溶け込んだオープニングとして記憶されています。
■ エンディングテーマ「グルッパーのうた」 (1976年1月〜1977年12月)
作詞:川内康範
作曲:北原じゅん
編曲:小谷充
歌:キーパー・メイツ
この時期のエンディングテーマは、オープニングとは対照的に軽快でポップ。子どもたちの合唱が中心となり、明るく跳ねたリズムが毎週の締めにぴったりの雰囲気を作っていました。
「グルッパー」という謎めいたフレーズは子どもたちの記憶に残りやすく、放送当時は小学生の間で“グルッパーごっこ”が流行した地域もあります。
また、歌詞に繰り返し登場する「みんなで、みんなで」というフレーズは、昔話のテーマである“つながり”“助け合い”を反映したもので、番組全体のメッセージ性ともマッチしています。
■ 「ジャンケン ポン(グー・チョキ・パーのうた)」 (1978年1月〜1980年3月)
作詞:川内康範
作曲:北原じゅん
編曲:角田圭伊悟
歌:ひまわり
テレビ放送の中でも特にポップでリズミカルなエンディングとして人気が高かったのが、この“ジャンケン”の歌です。
曲の構成が非常に覚えやすく、放送当時の子どもたちはテレビの前で一緒にジャンケンをしながら歌ったというエピソードが多く残っています。軽快なコーラスとリズムの心地よさは、大人になってから聴いても童心を思い出す魅力を持っています。
■ 「かあさん(マザー)」 (1980年4月〜1982年12月)
作詞・作曲:川内康範
編曲:竜崎孝路
歌:関森れい、ミンツ
しっとりとした優しい旋律で構成されている、シリーズの中でも感動的なエンディングテーマです。タイトルが示す通り“母への想い”がテーマで、親への感謝や家族の温かさを象徴する歌として長く愛されています。
歌声には温かみがあり、歌詞の一語一語が静かに胸へ染みこんでいくような構成になっており、当時幼かった視聴者からは「母のぬくもりを思い出す」といった感想も多く寄せられています。
■ 「トッピンからげて逃げられて」 (1983年1月〜12月)
作詞・作曲・編曲:玉木宏樹
歌:常田富士男
俳優・語り手として参加している常田富士男が歌った、非常にユニークなエンディングテーマ。語りの延長線上にあるような一風変わったメロディと、遊び心のある歌詞が特徴です。
常田の独特の声質が活かされ、「語り手がそのまま歌った」ような親近感が生まれ、視聴者の印象に強く残る楽曲でした。
■ 「にんげんっていいな」 (1984年1月〜1988年3月、1990年10月〜1994年9月)
作詞:山口あかり
作曲:小林亜星
編曲:久石譲
歌:中島義実、ヤング・フレッシュ
本作のエンディングテーマの中でも、圧倒的な人気を誇るのがこの「にんげんっていいな」です。
温かく親しみやすいメロディと、子どもたちの澄んだ歌声。
特にサビの「にんげんっていいな おいしいおかずに~」というフレーズは、放送当時を生きた世代の“共通記憶”といっても過言ではありません。家庭の食卓、家族団らん、休日の夕方の匂い──そういった生活の風景が歌とともに蘇るため、多くの視聴者が「この曲こそ『日本昔ばなし』の象徴」と語ります。
さらに注目すべきは、編曲を担当したのがのちに世界的作曲家となった久石譲である点です。柔らかな音色と広がりのあるサウンドは、スタジオジブリ作品にも通じる透明感を持ち、エンディングテーマの格をさらに引き上げました。
■ 「ほしさがし」 (1988年4月〜1988年12月)
作詞:伊藤アキラ
作曲・編曲:有澤孝紀
歌:相田文三、東京少年少女合唱隊
星空を見上げる情景が浮かぶ、美しく静かな楽曲。
合唱隊の繊細な声が夜空に吸い込まれていくような余韻をもたらし、1日の終わりにぴったりのエンディングでした。
■ 「みんなでたんじょうび」 (1989年1月〜1990年9月)
作詞:伊藤アキラ
作曲:小林亜星
編曲:高田弘
歌:中村花子、ヤング・フレッシュ
明るく楽しいパーティのような雰囲気を持つ曲で、誕生日という普遍的なテーマを通して“みんな一緒”の温かさを描いているエンディングです。
この時期に番組を見ていた子どもたちは、誕生日が近づくと自然とこの曲を思い出したと語る人も多いのが印象的です。
■ 楽曲が生んだ視聴者の思い出・感想
放送終了から何十年経っても、これらの楽曲が語り継がれ続けている理由は、視聴者の生活に深く溶け込んでいたからです。
「夕食の匂いとセットで思い出す」
「祖父母の家のちゃぶ台を思い出す」
「家族で一緒に見ていた光景そのものが音楽に残っている」
「エンディングが流れると『ああ一週間終わったな』と感じていた」
音楽は“時間と記憶”を結びつける特別な力を持っており、『まんが日本昔ばなし』の主題歌はまさにその典型例といえるでしょう。
[anime-4]
■ 声優について
二人だけで世界を創りあげた“奇跡の語り部コンビ”
『まんが日本昔ばなし』における声優の存在は、他のアニメ作品とはまったく異なる特別な役割を担っていました。
本作では、市原悦子と常田富士男という、たった二人の俳優が、物語に登場する老若男女・人間・動物・妖怪まですべての声を演じ分けています。
通常のアニメでは複数の声優を起用して役柄ごとに配役しますが、本作は“語り部が紡ぐ昔話”という形式に合わせ、誰か一人の「視点」や「語り」が物語全体を包みこむように設計されました。これは、昔話の口承文化を受け継ぐための演出でもあり、全編に統一感と包容力を与えています。
視聴者は毎週、この二人の語り手が開く〈昔話ワールド〉へつながる扉をくぐっていたのです。
■ 市原悦子 ― 魂を揺さぶる“語りの魔法”
市原悦子は、女優として映画・舞台・ドラマなどで知られる一方、本作では声の表現力を存分に発揮し、国民的な語り部としての地位を確立しました。
その声の特徴は“変幻自在”という言葉がよく似合います。
● 市原悦子が演じた声の幅
優しいおばあさんの包みこむような声
純朴な少女の澄んだ声
おしゃべりな村の女房の軽やかな声
山姥や鬼婆の恐怖を煽る低く不気味な声
いたずら好きな子どものようなコミカルな声
悲しみに沈む母親の静かな嘆き声
この幅の広さは、単に声色を変えるだけでなく、
「人生を生きてきた人間の呼吸・間・感情の揺れ」 を声にのせることができたからこそ成り立っています。
特に、涙を誘う話や温かい家族の話では、市原自身の情感が言葉の奥に宿り、視聴者を包みこむような優しさを生み出していました。
■ 常田富士男 ― 落ち着きとユーモアを兼ね備えた名語り手
常田富士男は、味わい深い低音を持つ俳優で、本作の重厚さ・安心感・親しみやすさを支えています。
● 常田富士男が演じた主な声質
誠実で控えめな農夫や職人
穏やかで知恵のある老人
へらへらしたずる賢い男
酔っぱらいの男のコミカルな声
神や鬼の堂々とした響き
怪談話のときの冷たく深い声
とりわけ常田の魅力は、“語りの間の心地よさ” にあります。
一言の後に置かれる静寂が、視聴者の想像力を引き出し、昔話の世界をより深く感じさせる働きを担っていました。
また、コミカル回では驚くほど軽快な芝居を見せ、ホラー回では背筋が凍るような低音を響かせるなど、その表現力は市原と同様、極めて幅広いものです。
■ 二人の“デュエット演技”が生んだ独特の世界観
市原悦子と常田富士男の演技は、単独でも非常に優れていますが、二人が同時に語り、掛け合うときにこそ真価を発揮します。
● デュエット演技の特徴
ナレーションとセリフの自然な切り替え
二人の声が滑らかに交差し、物語のリズムを生み出す。
老若男女の役割分担が絶妙
市原が女性・子ども・妖怪の多くを担い、常田が男性・老人・神々を担うことで、自然な世界が構築される。
会話劇の“温度”がリアル
本当にその登場人物同士が会話しているかのような臨場感が生まれる。
語り手が姿を見せない“舞台劇”のような感覚
映像以上に、声の芝居が物語の強度を決める世界観となる。
これらの総合力によって、視聴者はまるで物語の中にいるような没入感を覚えました。
■ セリフが少ないからこそ際立つ“声の質感”
昔話は“描写の簡潔さ”が大きな特徴で、セリフが多すぎることはありません。
そのため、一言の重みが非常に大きい のです。
「おじいさんや、どうしたんだい?」
「それは、たいへんだったなぁ」
「ほう、それは気の毒なこった」
「おまえさん、ようやったな」
こうした短いセリフに宿る温かさ・哀しさ・恐ろしさが、登場人物以上に視聴者の心に残りました。
特に、
“語りが泣くと、物語が泣く”
と言われるほど、両者の感情が物語全体へダイレクトに反映される形式であったため、演技の質は作品の品質そのものを左右していました。
■ 視聴者が語る“声の記憶”
多くの視聴者は、本作の語りをこう振り返ります。
「市原悦子の声が聞こえるだけで、物語が始まる気がする」
「常田富士男の語りの余韻が、子どもの頃の夜を思い出させる」
「声そのものが昔話の一部。映像と同じくらい重要だった」
「二人の声を聞くと、祖父母に昔話を読んでもらった記憶が蘇る」
そして、若い世代でも、再放送やソフト化で初めて出会った際に、
「声がすごすぎて、一瞬で引き込まれた」
と語ることが多く、時代を超えた普遍性を持つ語りだったことがうかがえます。
■ 二人が生み出した“口承文化の継承”としての価値
『まんが日本昔ばなし』は、単なるアニメ作品ではなく、
“語り文化の映像化”という試みに成功した特別な作品 です。
市原悦子と常田富士男という、舞台経験豊富な俳優が声を担当したことで、
映像よりも先に「語り」が物語を引っ張る稀有なアニメ作品となり、
テレビ文化の中で“現代の語り部”としての役割を果たすことになりました。
彼らの存在なくして、『まんが日本昔ばなし』という作品は成立しなかったと言っても過言ではありません。
■ 視聴者の感想
世代を超えて語り継がれる“国民的番組”としての印象
『まんが日本昔ばなし』は、1975年から1995年まで約20年間放送されたこともあり、視聴者の感想は非常に幅広く、そして深いものがあります。親世代・子ども世代・孫世代の三代にわたって共有される作品という点で、他のアニメとは比較にならないほどの文化的影響力を持っています。
視聴者の感想は、大きく分けて 「懐かしさ」「怖さ」「優しさ」「教訓」「心に残る風景」 といった側面に集約されます。以下では、その一つひとつを丁寧に掘り下げていきます。
■ 1. 「懐かしい」「家族との思い出が蘇る」という感想
最も多い感想は、やはり 「懐かしい」「子どもの頃を思い出す」 という声です。
特に、土曜夕方の生活風景と結びついて記憶している人が多く、
「夕飯の匂いと一緒に思い出す」
「ちゃぶ台を囲んで家族で見た」
「お風呂から出るタイミングといつも重なっていた」
といった、日常そのものの思い出と結びついて語られます。
番組そのものだけでなく、当時の生活のリズム・季節感・家族の関係まで鮮やかに思い出させるという点が、本作の大きな魅力です。
現代になってもSNS上では、
“あのエンディング曲を聴くと実家に帰ったような気持ちになる”
という投稿が毎年のように見られるほどです。
■ 2. 「怖かった」「トラウマになった」という感想
昔話には怪談や妖怪の話も多く、本作でも“本当に怖い”映像表現が多々ありました。そのため、視聴者からは 「怖くて泣いた」「今でも忘れられない恐怖」 といった感想も多く寄せられています。
たとえば──
闇に溶けるような山姥の顔
ゆっくりと襖を開ける化け猫の動作
雨音だけが響く中で人影が立つ演出
表情のない幽霊の静かな佇まい
語りが普段より低く冷たいトーンで進む怪談回
こういった演出は、幼い視聴者に強烈な印象を残しました。
“トラウマ回”として語り継がれるエピソードも存在し、
「怖いのに、また見たくなる」
という不思議な魅力があったと多くの視聴者が証言しています。
これは、恐怖の中に必ず“理由”や“教訓”があり、視聴後にモヤモヤを残さず、どこか納得できる構造があったためと言えます。
■ 3. 「優しかった」「泣いた」という感想
『まんが日本昔ばなし』は、温かく切ない物語が多いことでも知られています。
視聴者は、ただ“泣ける”のではなく、心が優しくなる体験 をしていました。
涙を誘ったと語られるエピソードの例を挙げると──
『笠地蔵』の老夫婦の控えめな優しさ
『鶴の恩返し』の娘の健気さと別れの哀しみ
『雪女』の儚い愛情と悲しい約束
『手ぶくろを買いに』の母狐の愛情
市原悦子・常田富士男による語りがまた深い余韻を生み、
「ただ泣けるだけでなく、心が浄化されるような気がした」
という声が世代を問わず多いのが特徴です。
■ 4. 「教訓が心に残る」という感想
昔話には必ずと言っていいほど、生活の教訓・道徳的なメッセージが込められています。視聴者からは、
「欲張ってはいけない」
「人には優しく」
「嘘をつけば必ずしっぺ返しがある」
「約束は守らなければならない」
など、子どもの頃に番組を通して教訓を学んだという声が非常に多く寄せられます。
大人になってからも、
“今でもあの話のおかげで気持ちを整えられる”
と語る視聴者も多く、「人生の基礎に影響を与えた番組」という評価まであります。
■ 5. 「日本の風景が美しかった」という感想
視聴者の多くは、昔話の舞台となる日本の原風景を美しく描く映像に心を奪われたと語っています。
田植えの風景
雪の降りしきる山里
夏祭りの夜の光
港に浮かぶ夕焼け
木造家屋の温かさ
本作の背景美術は、単なる舞台設定ではなく、視聴者に日本の四季や文化を教える“大きな教材”の役割も果たしていました。
そのため、成長してから地方の風景を目にすると、
「昔話のようだ」「あのアニメを思い出す」
という感想を抱く人が多く、本作が視覚的な記憶として刻まれていることを示しています。
■ 6. 「市原・常田の声が忘れられない」という感想
視聴者の感想で絶対に外せないのが、語り部二人への称賛です。
「声だけで泣ける」
「語りに引き込まれて息をするのも忘れた」
「二人の声がすべての物語を特別にしていた」
「怖い回の語りは今でも鮮明に思い出せる」
という声が圧倒的に多く、
“語り部が作品そのもの” とまで評価されています。
二人の声は今でも音楽CD・ブルーレイ・再放送で語り継がれており、
新しい世代にも感動を与え続けています。
■ 7. 「子どもに見せたい」「教育として優秀」という感想
本作は、大人になった視聴者からも教育的価値が高く評価されています。
「自分の子どもに見せたいアニメNo.1」
「道徳教育として最も優れた番組」
「日本の文化を自然に学べる」
という声が多く、今なお“家庭での教材”として人気を持つ理由がここにあります。
親世代は、
「昔、両親が私に見せてくれたように、今度は自分の子に見せたい」
と語り、世代を超えた循環が続いています。
■ 8. 「大人になってから見ると別の意味で深い」という感想
大人になって再視聴すると、子どもの頃とは全く違う視点で物語を味わえるという感想も非常に多いです。
親の気持ちがわかる
老人の孤独が胸に刺さる
労働の厳しさが切なく響く
自然への敬意が深く理解できる
といった点が挙げられ、「昔話の本当の深さに気づくのは大人になってから」という声が共通しています。
■ 9. 「永遠に残してほしい作品」という総評
最後に、視聴者全体の総評として最も多いのは、
「この作品は後世まで残してほしい」
という願いです。
日本の文化・生活・価値観を、時代に合わせすぎない普遍的な形で伝え続けた本作は、視聴者にとって“家族の思い出の象徴”であり、“日本文化の宝庫”として愛され続けています。
[anime-6]
■ 好きな場面
視聴者の心に永く残り続ける“忘れられない一瞬”
『まんが日本昔ばなし』には数百に及ぶエピソードがあり、その中で視聴者が「一生忘れない」と語る名シーンが数え切れないほど存在します。
昔話という普遍的な題材を扱いながら、映像・語り・音楽の三要素が絶妙に重なった瞬間は、まるで絵本のページから魂が飛び出したような迫力を生み、心に深く刻まれます。
ここでは、特に多くの視聴者の心を掴み続けている印象的な場面を、テーマごとに詳しく肉付けして紹介していきます。
■ 1. 「笠地蔵」── 雪の中で地蔵たちが歩き出す奇跡
本作を象徴する名シーンとして最も多く語られるのが、『笠地蔵』のラストシーンです。
雪深い夜、優しい老夫婦のためにお地蔵さまたちが静かに家へ歩み寄る場面。
白い雪原
月明かりに照らされる地蔵の影
足音もなく進む神秘的な動き
市原悦子の柔らかな語り
ほのかに流れる静かなBGM
これらが組み合わさり、まるで“絵がそのまま祈りに変わった”ような神聖さを感じさせます。
視聴者からは、
「怖いのに美しい」
「温かくて涙が出る」
「冬になると必ず思い出す」
という声が圧倒的に多く、放送から何十年経っても語られる不朽の名場面です。
■ 2. 「鶴の恩返し」── 娘が織物を織る静寂のシーン
“恩返しもの”の代表であるこの物語では、鶴が人間の娘に姿を変え、美しい布を織るシーンが特に印象深く描かれています。
織機の規則正しい音
揺れる糸
ほのかな灯り
娘の細い指先の動き
これらの細部が丁寧に描写され、視聴者は言葉なくとも娘の想いと苦しさを感じとることができます。
そしてクライマックスで、娘が正体を明かす場面は涙なくして見られません。
“どうしてのぞいたのですか…”
“もうご一緒にいられません…”
常田富士男の低く優しい語りと、市原悦子のかすかな震えを帯びた声が織り重なり、画面以上の感情が押し寄せます。
■ 3. 「雪女」── 静寂の中に潜む“恐ろしく美しい”一瞬
恐怖の名作として語り継がれる『雪女』では、雪の夜に女性が静かに立つシーンが視聴者の記憶を支配しています。
真っ白な吹雪の中に浮かぶ白い姿
表情の読めない無機質な美しさ
風の音だけが響く空間
常田富士男の低く冷たい語り
この組み合わせは、幼い頃にテレビの前で固まった視聴者が続出するほどの迫力でした。
しかしその一方で、雪女の哀しみや孤独も同時に伝わってくるため、恐怖と美しさが共存する名シーンとして語り継がれています。
■ 4. 「こぶとり爺さん」── 鬼たちの踊りの狂気と楽しさ
昔話の中でも明るい話として人気の『こぶとり爺さん』。
鬼たちが輪になって踊るシーンは、視聴者から「トラウマになった」「妙に好きだった」と賛否入り混じる評価を受けています。
奇妙な音律の太鼓
鬼たちの揺れ動く動き
狂気すら感じる笑顔
照明を落とした室内の色彩
これらの演出は、子どもにとっては恐ろしく、大人にとっては芸術的に見えるという不思議な体験をもたらしました。
喜劇と怪異の境界線にあるこの場面は、本作だからこそ成立した独特の名シーンと言えるでしょう。
■ 5. 「分福茶釜」── たぬきが踊りながら恩返しする温かい場面
茶釜に化けたたぬきが、宿恩のために踊る愛らしいシーンも人気が高いものの一つ。
ふわふわした動き
コミカルな表情
軽快な音楽
ほんのりとした温かさ
たぬきの動きにはアニメスタッフの遊び心が詰まっており、子どもたちからの人気も高いエピソードでした。
■ 6. 「山姥」── 闇の中でのゆっくりとした“追跡”の恐怖
ホラー回の頂点として語られるのが、山姥が静かに追いかけてくるシーン。
視聴者の多くが「怖すぎて泣いた」と話します。
ほとんど動かない表情
静かに近づく異様なスピード
色を極限まで抑えた背景美術
心臓の鼓動のような不穏なBGM
この場面は、実際には暴力的な描写がほとんどないのに、心理的恐怖だけで視聴者を圧倒するという、非常に高度な演出で作られています。
■ 7. 「手ぶくろを買いに」── 親子の絆が光る温かい瞬間
母狐が子狐の手を温めながら手袋を買いに送る場面は、視聴者が今でも“母の温かさ”を感じる名シーンとして語り継がれています。
夜の街に灯る暖色の光
子狐の小さな足音
母狐の優しい声
ほのかに揺れる炎
市原悦子の柔らかい語りが、親の愛情を静かに伝え、視聴者を深い安心感で包み込みます。
■ 8. 背景美術が輝く“風景の名シーン”
さらに、本作は背景美術の美しさが際立っており、風景そのものが“名場面”として語られます。
夕暮れの田園
春の山里の桜
雨上がりの石畳
海辺の漁村の朝焼け
祭りの夜の提灯の光
これらのシーンは、まるで日本画のような静けさと力強さをもち、物語とは別に心に残る“絵画的瞬間”として多くの視聴者に愛され続けています。
■ 9. 語りの一言が心を貫く瞬間
『まんが日本昔ばなし』の名場面は、実は映像だけではありません。
語り手の一言が心を震わせるというケースも多く、特に──
「それは、それは気の毒なことでした」
「おじいさんは、そっと涙を流しました」
「こうして、村には再び平和が戻ったのです」
といった市原・常田の余韻ある声は、視聴者の胸の奥に長く残りました。
■ 名場面は“個人の人生の一部”として残り続ける
視聴者が語る好きな場面は、そのほとんどが
“自分の記憶”と強く結びついている
という特徴があります。
冬の寒い夜に布団から顔を出して見た名シーン
家族団らんの中で笑った場面
怖くて母親の手を握りしめたあの瞬間
祖父母と一緒に見た大切な思い出
それぞれの名場面が視聴者の人生と結びついているため、本作の好きなシーンは人の数だけ存在するといっても過言ではありません。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
視聴者の心に残り続ける“素朴で忘れがたい登場人物たち”
『まんが日本昔ばなし』には、レギュラーキャラクターやシリーズを通じて登場する主人公はいません。
その代わり、毎週新しい昔話の中で“名もなき人々”が主役となり、視聴者の心に深く刻まれていきました。
老人、子ども、動物、妖怪──
いずれも特別な力を持たない、しかしどこかで見たことがあるような、日本の原風景に溶け込む“あの人たち”。
ここでは、視聴者から特に人気の高いキャラクターたちを、豊かな情景とともに詳しく解説していきます。
■ 1. 『笠地蔵』の優しい老夫婦 ― “日本のおじいちゃんおばあちゃん”の象徴
『笠地蔵』の老夫婦は、番組の中でも特に“理想の祖父母像”として多くの視聴者の心に残る存在です。
貧しくとも他者を思いやる心
困っている者にそっと手を差し伸べる優しさ
少し曲がった背中や、しわの刻まれた手
柔らかいが芯のある語り口調
市原悦子・常田富士男の語りによって、彼らは単なる昔話の登場人物ではなく、
「自分の祖父母の姿を思い出させる存在」になりました。
視聴者は、雪の中を歩く老夫婦の姿に自分の家族を重ね、作品が終わった後も長く温かい余韻を感じ続けたと語っています。
■ 2. 『鶴の恩返し』の鶴の娘 ― 儚さと気高さを併せ持つ存在
人間の娘に姿を変え、恩返しのために織物を織る鶴。
その健気さと儚さは、視聴者にとって忘れがたい“美しい女性像”として語られています。
細い指先で織機を操る姿
優しいがどこか影のある微笑み
別れの瞬間の切なさ
触れたら消えてしまいそうな透明感
多くの視聴者が「子どもの頃、この人が世界で一番きれいな女性に見えた」と語り、
その美しさと悲しさは“昔話の永遠のヒロイン”として記憶され続けています。
■ 3. 『雪女』の雪女 ― 恐ろしくも美しい“冬の精霊”
恐怖の象徴でありながら、同時に哀しさを秘めた雪女は、本作の中でも特に印象的なキャラクターです。
白銀の中に浮かぶ静かな姿
無表情だがどこか深い感情を抱えた眼差し
ひと息で命を奪う冷たさ
しかし夫への愛だけは本物という矛盾
視聴者は「怖かった」という印象と同時に、
“あの悲しい表情が忘れられない”
という感想も多く、恐怖と美しさが両立する稀有な存在として語り継がれています。
■ 4. 『こぶとり爺さん』の明るいお爺さん ― 天真爛漫な人気者
鬼にこぶを取られてしまう“陽気な老人”は、子どもたちから圧倒的な人気を誇るキャラクターです。
着物がはだけそうなほど大笑いする豪快さ
明るい性格で周囲を照らす存在感
鬼たちにも愛されるほどの愛嬌
このおじいさんは、昔話の登場人物でありながら、現代の物語に出ても違和感がないほど魅力的で、
「こんなおじいちゃんになりたい」という声が非常に多く寄せられています。
■ 5. 動物キャラクター(きつね・たぬき・うさぎ等) ― 昔話に生命を吹き込む存在
昔話に欠かせない“動物たち”は、そのコミカルさ・知恵深さ・時に切なさで、多くの視聴者に愛されてきました。
きつね
いたずら好き
人を騙すけれど悪人ではない
どこか人間より人情深い場面も
たぬき
とぼけた表情が人気
恩返しで踊る、茶釜に化けるなど芸達者
子どもが特に好きなキャラ筆頭
うさぎ
小さくて可愛い存在
優しさと賢さを併せ持つ登場が多い
これらの動物キャラは、かわいらしさと物語性を両立し、
「本当に森に住んでいそう」
と視聴者に感じさせるリアリティがありました。
■ 6. 村人・職人・旅人たち ― “名もなき人々”が主役になれる魅力
本作の大きな特徴の一つは、華やかな英雄ではなく、どこにでもいる人物が主役になるという点です。
雪の中で薪を運ぶ村人
小さな釜戸で料理をする母親
森で迷った旅人
町で働く商人
彼らはそれぞれ大きな力を持っているわけではありませんが、
“普通の生活の中にある善意や勇気”が物語を動かしていきます。
視聴者からは、
「特別じゃない人が主人公なのが良かった」
という声が多く、本作が誰でも感情移入できる理由でもあります。
■ 7. 村の悪役たち ― 欲深さや傲慢さの象徴
昔話には必ずといっていいほど“悪役”が登場します。
欲張りな庄屋
ずるい隣人
嘘つきな商人
怠け者の若者
これらのキャラは強烈な個性を持って描かれ、
視聴者に「こうなってはいけない」と深く印象づけます。
市原・常田の演技が、悪役の狡猾さや下品さを見事に表現しており、
「嫌なキャラなのに癖になる」
と語る視聴者もいるほどです。
■ 8. 鬼・山姥・妖怪たち ― 恐ろしくも魅力的な存在
怪異キャラクターは、多くの視聴者が“トラウマ”とともに愛した存在です。
鬼
真っ赤な体
迫力のある声
怖いがどこか憎めない
山姥
無表情なのに恐怖を感じる
足音のない静かな追跡
子どもに最も強烈な印象を残した存在
化け猫・幽霊
不気味な動き
影の強調
演出の妙で大人でも背筋が凍る
これらの存在は恐ろしいだけでなく、
“自然や運命が人を試す象徴”として描かれており、
視聴者からは
「怖かったけど忘れられない」「美しくもあった」
と評価されています。
■ 9. 神さま・仏さま ― 優しさと厳しさを併せ持つ導き手
昔話には人々を導く神仏も多く登場します。
優しいほほ笑みを浮かべる地蔵さま
人を試すために姿を変える神さま
時に雷のように怒る存在
これらは視聴者に
「目に見えないものへの畏れと敬意」
を感じさせ、物語に深い精神性を与えていました。
■ “好きなキャラ”は視聴者自身の人生を映す鏡
『まんが日本昔ばなし』のキャラクターの魅力は、
視聴者の人生の段階によって、好きな人物が変わるという点にあります。
子ども時代:動物や陽気なキャラが好き
青年期:美しい女性や優しい若者に惹かれる
大人になって:老夫婦や親の立場のキャラに涙する
親になって:子どもを思う母親の気持ちに共感する
つまり本作のキャラクターたちは、
“年齢に合わせて別の姿を見せてくれる”
極めて普遍的で奥深い存在なのです。
■ 関連商品のまとめ
“昔話の宝庫”を支えた膨大な関連商品たち
『まんが日本昔ばなし』は放送期間が約20年と長く、その間に生まれた関連商品は多岐にわたり、映像・書籍・音楽・ホビー・食玩・文房具など、ほぼすべての分野に展開しました。
ただのキャラクター商品ではなく、「日本の昔話そのものを残すための文化的アーカイブ」としての側面が強く、現在では入手困難なアイテムも多数存在します。
ここでは、当時発売された関連商品の種類や特徴、コレクターに注目されるポイント、当時の人気の傾向などを、5000字級の詳細な内容で丁寧に整理していきます。
■ 映像関連商品 ― VHS・LD・DVD・Blu-rayまで続く長い歴史
もっとも代表的な商品群が“映像ソフト”。
放送当時は家庭用録画環境が整っていなかった時代でもあり、公式ソフトの需要は非常に高いものでした。
● 1. VHS(ビデオテープ)
1980年代後半から順次リリースされた初期映像商品。
セル版とレンタル版が存在。
巻数が少なく、初期・名作系エピソードが中心。
カラフルなパッケージで、“子ども向け教育ビデオ”のような位置づけ。
今では希少価値が高く、状態によっては高値取引されることも。
VHS時代は映像の劣化が避けられず、保存状態が良いものは貴重。
ファンにとっては“昭和の温もりの残る媒体”として人気があります。
● 2. LD(レーザーディスク)
1990年代前半、一部巻がレーザーディスク化。
高画質・大判ジャケットでコレクション性が高い。
当時のアニメファンの象徴的アイテム。
絵柄の美しさを生かしたデザインが多く、所有する喜びの強い商品。
LDプレイヤー自体の希少化で視聴は難しいものの、
「ジャケットが美術品」
として今も人気が高い商品群です。
● 3. DVD(2000年代~)
再放送需要が高まる中、ついにDVDボックス化。
全話収録のコンプリートBOX
テーマ別セレクション(泣ける話、怖い話、動物の話 など)
廉価版の単巻DVD
中でもコンプリートBOXは、
「市原・常田の語りを当時のまま収録」
「画質修復を行ったマスターを使用」
など質の高い仕上がりで、コレクターから非常に高い評価を得ています。
パッケージには昔話らしい和風デザインが採用され、ブックレットには制作背景・民話の解説など文化資料としての側面も。
● 4. Blu-ray(2023年〜)
ついに4Kデジタルリマスター化が進み、Blu-rayのリリースが実現。
劇的に向上した色彩・鮮明度
背景美術の細部がはっきり見える
音声もクリアに補正
パッケージは高級感ある和紙風デザイン
長年ファンが待ち続けていた“決定版”ともいえる映像商品。
「子どもと一緒に見たい」という声で爆発的に売れ、世代をまたぐ教材として活用されています。
■ 書籍関連 ― 絵本・アニメコミックス・資料集の豊富さ
昔話を扱う作品という性質上、書籍関連の展開は非常に豊富でした。
● 1. 絵本シリーズ
1970〜80年代に多数出版された絵本は、今でも古書市場で人気。
番組のイラストレーションを使用
小学校の図書室に常備されていたことも多い
子どもの読み聞かせ用として定番
シリーズごとに装丁が異なり、コレクション性が高いのも特徴です。
● 2. アニメコミックス(フィルムコミック形式)
アニメのカットを使用してコマ割りした絵物語形式。
子どもにも読みやすい
アニメの色彩をそのまま楽しめる
テレビを見られない子どもにも大人気だった
特に人気エピソードのコミックスは、当時書店で平積みになっていたほどでした。
● 3. 昔話全集・民話解説書
番組に登場する昔話そのものの原典や解説をまとめた、学術寄りの書籍も多数登場。
地域ごとの民話の成り立ち
文化的背景・歴史的背景
昔話の教育的役割
こうした資料本は、教師・図書館司書にも重宝され、
「番組そのものが教育教材」
としての価値を高めました。
● 4. ファンブック・設定資料集
番組制作の裏側を紹介する貴重な資料も存在。
背景美術・キャラクターデザイン
市原・常田のインタビュー
スタッフの回想
番組誕生の経緯
これらはファンにとって宝物のような価値を持ち、現在は入手困難な希少アイテムとなっています。
■ 音楽関連商品 ― 思い出を呼び覚ます温かなメロディ
音楽は本作において非常に重要な役割を果たし、音楽商品の人気も根強いものです。
● シングルレコード(EP盤)
OPテーマ「にっぽん昔ばなし」
各時期のEDテーマ
子ども向け合唱盤
ジャケットには手描き風の素朴なイラストが採用され、レトロブームにより再評価されています。
● LPレコード・カセット
サウンドトラック
語り入りドラマ盤
合唱団による昔話曲
BGMの優しさと懐かしさが人気で、コレクターからの需要が高い商品。
● CD(復刻版・ベスト盤)
2000年代以降、次々とCD化が進行。
主題歌集
名エピソードの語り入り音声収録
久石譲編曲版など高音質化が進んだもの
車内・家庭で子どもと一緒に聴きたいという需要が地味に大きく、安定した人気を保っています。
■ ホビー・おもちゃ ― 昔話を“遊び”として楽しむアイテム
本作はキャラクター性よりも物語性を重視しているがゆえに、玩具展開は控えめでしたが、存在するアイテムは非常に独創的でコレクターから人気があります。
● ソフビ人形・フィギュア
鬼
動物キャラ(きつね・たぬき)
人間キャラ(子ども、農夫など)
特に“鬼”は造形が良く、昭和玩具らしい味わい深いデザインで人気です。
● ぬいぐるみ・布玩具
たぬき・きつね
地蔵さま
人物キャラ
柔らかい表情と素朴な縫製が魅力で、当時の子ども部屋の定番でした。
● ジオラマ系玩具
村の風景ミニチュア
茶屋や農家の模型
祭りの情景セット
まるで“昔話の世界に入り込んだような”気分を味わえるアイテムとして人気でした。
■ ゲーム ― すごろく・学習玩具から電子ゲームまで多様
ゲームジャンルでも、昔話の世界を楽しめるさまざまなアイテムが登場。
● すごろく(ボードゲーム)
昔話との相性が抜群で、長年人気。
「善行をすると進む」
「欲をかくと戻る」
「鬼に追いかけられるマス」
など、昔話の教訓を遊びながら学べる工夫が凝らされていました。
● カードゲーム
昔話の名シーンをカード化
記憶合わせ(神経衰弱)
キャラクターしりとり
家庭で楽しめる“教育系カードゲーム”として人気を博しました。
● 電子ゲーム
一部では電子LCD玩具も存在し、
鬼ごっこゲーム
きつねの恩返し風アクションゲーム
などが発売されていました。
■ 食玩・文房具・日用品 ― 昔話が日常に溶け込む商品群
このジャンルは“子ども向けアイテム”としてファンから非常に支持されています。
● 文房具
下敷き
鉛筆セット
シール帳
連絡帳
カンペンケース
昔話のワンシーンを描いたイラストは、子どもたちの学校生活に寄り添う存在でした。
● 食玩・駄菓子
キャラシール付きガム
小型フィギュア付きお菓子
ミニ紙芝居風カード
地域限定品も多く、“探す楽しさ”があるカテゴリーです。
● 日用品
コップ
お弁当箱
風呂敷
歯ブラシ・石けんケース
“家庭の中に昔話を取り込む”というコンセプトが強く、いまでは昭和レトログッズとしてコレクターに人気です。
■ 総評 ― 文化として残るために必要だった商品展開
『まんが日本昔ばなし』の関連商品は、キャラクター人気に依存したものではなく、
日本の風景
日本の文化
祖父母から受け継いだ物語
子どもの教育と成長
家族の思い出
といった“日本人の根幹に触れるテーマ”を支える役割を担ってきました。
映像・書籍・音楽・玩具・文具──
どのカテゴリーも“文化を残すための媒体”として存在しており、商品展開そのものがこの作品の価値を広げる一因となっています。
現在、昭和レトロブームとともに再評価が進み、
関連商品はコレクションとしての価値が急上昇中。
今後も新たな復刻・再編集が期待される分野です。
[anime-9]
■ オークション・フリマなどの中古市場
“昭和と平成の記憶”が現在も取引され続ける理由
『まんが日本昔ばなし』は、約20年間という長い放送期間を経て、膨大な関連商品が世に送り出されました。
その多くが現在では生産終了しており、中古市場こそがファンにとって唯一の入手手段となっています。
とくにヤフオク・メルカリなど、現代のオンラインフリマでは、
“昭和の思い出”を求めるコレクターによって活発な取引が続いています。
ここでは、映像・書籍・音楽・ホビー・ゲーム・日用品など、ジャンルごとに中古相場の特徴と傾向を詳細に分析し、
5000字規模でじっくり解説していきます。
■ 映像関連の中古市場 ― VHS・LD・DVD・Blu-rayの価格帯と特徴
映像関連商品は、中古市場の中でも最も取引数が多く、価格の上下動も激しいカテゴリーです。
● 1. VHS(ビデオテープ)
現在でも安定して取引される“レトロメディアの王道”。
平均相場:1本 1,500〜4,000円
美品・未使用品:4,000〜7,000円
まとめ売り:10数本セットで10,000〜20,000円台
特に初期巻や人気エピソードを含むものは高値になりやすいです。
また、教育現場向けに作られた“学校教材版”はレア度が高く、コレクター間で人気があります。
● 2. LD(レーザーディスク)
コレクターからの需要が高く、ジャケットの美しさで高値がつくことも。
相場:3,000〜6,000円
未開封品:10,000円以上になるケースも
LDはプレイヤーの減少により“一部の愛好家専用”となっていますが、
「ジャケットアートを飾りたい」というニーズが多く、
美品ほど価格が跳ね上がります。
● 3. DVD(コンプリートBOX・単巻)
流通量が多い反面、状態・付属品の有無で価格差が大きいカテゴリ。
● コンプリートBOX
相場:20,000〜40,000円
初回限定版はさらに高値
ブックレットや特典映像の有無で大きく変動
特に放送20周年を記念して発売された大型BOXはプレミア化しやすく、
状態の良いものは非常に高値で取引されています。
● 単巻DVD
平均相場:1本 1,000〜2,500円
子ども向けDVDとして購入された後、比較的きれいな状態で出回ることが多いです。
● 4. Blu-ray(リマスター版)
比較的まだ新しい商品ながら、初回品・帯付きは高騰傾向。
相場:10,000〜18,000円(BOX)
初回生産分:20,000円を超えることも
“4Kリマスターの美麗画質”という評価によって、ファンだけでなく
教育機関・図書館・保育園でも購入されるため需要が多いのが特徴です。
■ 書籍関連の中古市場 ― 絵本・民話全集・資料集の相場
昔話系作品らしく、書籍カテゴリーの中古需要は非常に高いです。
● 1. 絵本シリーズ
相場:1冊 800〜3,000円(状態により大幅変動)
ISBN無しの初期版はプレミア化し、5,000円近い取引も
とくに“昭和の図書館で使われていた版”は人気があります。
● 2. アニメコミックス
相場:500〜2,000円
人気エピソードや初版はプレミア化
テレビで見たままの世界が紙で楽しめるため、一定の需要があります。
● 3. 民話全集・資料系書籍
相場:2,000〜5,500円
廃盤の民話全集は非常に高いコレクション価値
文化資料として価値が高く、大学や図書館からの需要もあるため、価格が安定しています。
● 4. ファンブック・アート資料集
相場:3,000〜12,000円(特に希少)
制作背景・美術設定・インタビューが載った資料ほど高騰
このジャンルはもっともプレミア化しやすい書籍群で、マニア垂涎の品です。
■ 音楽関連 ― EP盤・LP・カセット・CDの需要
本作の主題歌や挿入歌は懐かしさ・温かさを感じさせるため、音楽商品の中古人気も非常に高いです。
● シングル(EP)
相場:800〜2,000円
ジャケット美品は3,000円超も
昭和歌謡との親和性が高く、コレクター市場が安定。
● LP(サントラ・語り盤)
相場:2,000〜4,500円
帯付き:+1,500〜2,000円のプレミア
● CD(復刻版・ベスト盤)
相場:1,000〜3,000円
廃盤CDは5,000円以上になるケースも
本作は世代を超えた人気のため、CDの需要も長続きしやすい安定市場です。
■ ホビー・おもちゃの中古市場 ― 昔話キャラの“素朴なおもちゃ”が人気
キャラクター商品は多くないものの、存在するアイテムは“昭和レトロ”として価値が高まっています。
● ソフビ人形
相場:1,000〜3,000円
鬼・動物キャラは特に高値
レトロ玩具コレクターから高い需要があります。
● ぬいぐるみ
相場:1,500〜6,000円
探しても見つからない希少品が多い
● ジオラマセット(村の風景など)
相場:3,000〜10,000円
箱付き未使用はさらに高額
当時の雰囲気をそのまま再現した玩具はコレクターに特に人気です。
■ ゲームの中古市場 ― すごろく・カード・電子玩具まで
ゲームはアニメ商品よりも“教育玩具”として人気でした。
● すごろく
相場:2,000〜7,000円
完品(駒・サイコロ・説明書あり)は高値
昔話特有の温かみのあるイラストが支持されています。
● カードゲーム
相場:800〜2,000円
昔話の名シーンを使ったカードは人気
● 電子ゲーム(LCD玩具)
相場:4,000〜10,000円
動作品・箱付きはプレミア化
■ 文房具・日用品 ― “昭和グッズ”として再評価
近年、非常に需要が高まっている分野。
● 文房具(下敷き・鉛筆・ノートなど)
相場:500〜3,000円
新品未使用は5,000円以上になることも
学校で使っていた思い出から強い需要があります。
● 日用品
相場:1,500〜6,000円
コップ・お弁当箱・歯ブラシセットなどは非常にレア
昭和レトロブームの影響で価格が上昇中。
● 食玩(シール・チョコなど)
相場:300〜1,500円
未開封品はプレミア化
紙製のシールやミニカードは保存状態が良いものが少なく、コレクター人気が高いです。
■ 総評 ― 「日本の心」の記憶は中古市場でも生き続ける
中古市場は単なる売買の場ではなく、
「昭和・平成の家族の思い出を後世へ渡す場所」
として機能しています。
『まんが日本昔ばなし』の商品は、いずれのジャンルも
発売終了
子どもが使う前提で劣化品が多い
教材としての価値が高い
昭和レトロとして再評価
といった要因が重なり、常に高い需要を維持しています。
そして多くの購入者が口にするのは、
「子どもに見せたい・触れさせたい」
という願いです。
つまり中古市場は、過ぎ去った過去を再び家庭に取り戻すための“文化の循環装置”として重要な役割を果たしているのです。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
まんが日本昔ばなしDVD7巻組 ユーキャン通販




 評価 5
評価 5まんが日本昔ばなし 3 [ (キッズ) ]
決定版 まんが日本昔ばなし101 (決定版101シリーズ) [ 川内 彩友美 ]




 評価 4.68
評価 4.68[新品]まんが日本昔ばなしセット[文庫版] (1-15巻 全巻) 全巻セット




 評価 4.31
評価 4.31まんが日本昔ばなし 2【Blu-ray】 [ (キッズ) ]
【中古】 まんが日本昔ばなし DVD−BOX 第3集/(キッズ),市原悦子(語り),常田富士男(語り),北原じゅん(音楽),愛プロ(音楽)




 評価 4.67
評価 4.67【中古】 まんが日本昔ばなし DVD−BOX 第1集/キッズバラエティ,(キッズ),市原悦子(語り),常田富士男(語り),北原じゅん(音楽..




 評価 4.33
評価 4.33【中古】 まんが日本昔ばなし DVD−BOX 第1集/キッズバラエティ
【中古】 まんが日本昔ばなし DVD−BOX 第7集/キッズバラエティ




 評価 5
評価 5
![まんが日本昔ばなし 3 [ (キッズ) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4431/4988104134431.jpg?_ex=128x128)
![決定版 まんが日本昔ばなし101 (決定版101シリーズ) [ 川内 彩友美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5872/9784062115872.jpg?_ex=128x128)
![[新品]まんが日本昔ばなしセット[文庫版] (1-15巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0011/ma-16_01.jpg?_ex=128x128)
![まんが日本昔ばなし 2【Blu-ray】 [ (キッズ) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3519/4988104133519.jpg?_ex=128x128)