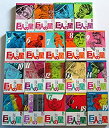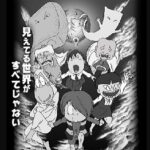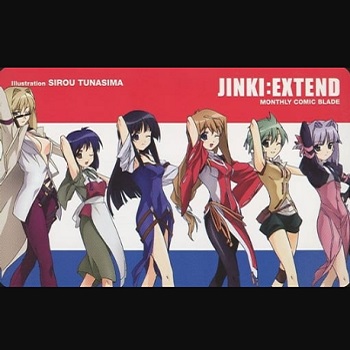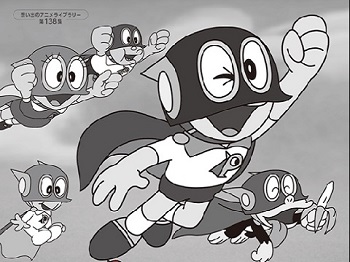【あしたのジョー&巨人の星】ジョー&飛雄馬 夢の競演 キーチェーンフィギュア Ver.2 矢吹丈&星飛雄馬
【原作】:梶原一騎、川崎のぼる
【アニメの放送期間】:1968年3月30日~1971年9月18日
【放送話数】:全182話
【放送局】:日本テレビ系列
【関連会社】:よみうりテレビ、東京ムービー、旭通信社
■ 概要
● アニメ化の経緯と放送の背景
1968年3月30日から1971年9月18日まで、日本テレビ系列で放送されたテレビアニメ『巨人の星』は、梶原一騎原作・川崎のぼる作画による劇画作品を原作とした、日本スポーツアニメ史に残る金字塔的存在である。原作は『週刊少年マガジン』に連載され、当時の若者たちの「努力」「根性」「栄光」を象徴する社会的テーマを内包していた。アニメ化にあたっては、東京ムービー(現トムス・エンタテインメント)が制作を担当し、虫プロダクション出身の人材を多数起用。これにより、ドラマ的演出とスポーツ描写の融合が実現した。
アニメ化の際、梶原一騎は制作サイドに自ら熱意をもって働きかけたという逸話が残っている。「この作品を世に出したい」という強い思いが、多くの制作者たちの心を動かし、結果として、3年半という長期にわたる放送が実現した。放送開始当初から高い視聴率を記録し、日本の家庭に“星飛雄馬”という名前が浸透していった。
● ストーリー構成と物語の核心
『巨人の星』は単なる野球アニメではなく、父と息子の葛藤と絆を軸にした人間ドラマである。かつて魔送球によって野球界を追放された元プロ選手・星一徹が、息子の飛雄馬に夢を託すところから物語が始まる。父の厳しい指導、あるいは狂気にも見えるほどの特訓によって少年は鍛え上げられ、「巨人の星」を目指す。 やがて飛雄馬は甲子園でライバルたちと死闘を繰り広げ、巨人軍に入団。彼が投げる“大リーグボール”は、単なる変化球ではなく、努力と才能、そして父との宿命を象徴する存在として描かれる。物語の後半では、彼の左腕が限界を迎え、選手生命と引き換えに完全試合を達成するという感動的なクライマックスへと向かう。
● アニメ版と原作版の相違点
原作の最終回では、飛雄馬が完全試合を達成した後、父・一徹との最後の勝負を終え、彼以外の仲間たちが祝福する中で、彼だけが孤独に去っていくという静かな幕引きであった。しかしアニメ版では、より感情に訴える形に改変されている。 試合後、倒れた飛雄馬を一徹が背負い、観客の拍手に包まれながらグラウンドを後にするシーンは、多くの視聴者の涙を誘った。その後、太陽に向かって飛雄馬が歩み出すカットで物語は幕を閉じ、努力と再生の象徴として語り継がれている。
● 制作スタッフと演出の革新
本作の演出には、当時としては極めて先進的な映像表現が導入された。作画監督を務めたのは熊瀬範彦、演出に長浜忠夫らが参加し、心理描写を強調するための象徴的なカットやモノクロ演出、カメラワークを駆使した“止め絵の美学”が話題を呼んだ。特に、飛雄馬が投げる魔球のシーンでは、スローモーションと残像、強烈な集中線を多用し、視聴者に圧倒的な臨場感を与えた。 また、音楽監督・渡辺岳夫による劇伴は、情感豊かでありながら緊張感を持つ旋律が多く、父子の葛藤を音で支える構成となっている。
● 社会的インパクトと文化的意義
『巨人の星』は、昭和40年代後半の日本社会における「高度経済成長期の象徴的アニメ」として位置付けられる。当時の日本は「努力すれば報われる」という価値観が支配的であり、飛雄馬の姿はサラリーマン社会の縮図として共感を呼んだ。 また、「巨人軍=理想」「星一家=庶民」「花形満=上流階級」という構図が明確に描かれ、社会階層や格差をテーマに据えた点でも先駆的だった。父・一徹の竹刀による指導は後年「スパルタ教育」という言葉を生み、教育論争にまで発展。テレビアニメが社会現象となる時代の幕開けを象徴した作品である。
● 再放送と後世への影響
放送終了後も『巨人の星』は何度も再放送され、そのたびに新たなファン層を獲得した。特に1980年代のアニメブーム時には、リマスター版が放映され、親子二代にわたって視聴された数少ないアニメの一つとして評価されている。 その影響は後年のスポ根アニメにも波及し、『アタックNo.1』『タイガーマスク』『ドカベン』『キャプテン』など、多くの作品がこのフォーマットを踏襲した。また、“努力・根性・勝利”の三拍子が揃った少年アニメの王道構成は、『ドラゴンボール』や『NARUTO』といった現代作品にも通底している。
● 名場面と象徴表現
アニメの中で象徴的な場面として語り継がれるのが、飛雄馬がちゃぶ台をひっくり返す一徹の姿を見つめるシーンである。これは日本の家庭における父権と反発の象徴として長く語られ、のちに「ちゃぶ台返し」という文化的フレーズを生み出した。また、飛雄馬が父の教えを胸に一人トレーニングを続ける夜のシーンは、映像美と心理描写が融合した名場面として、アニメ史の中でも特筆すべき存在である。
● エンディングとメッセージ
最終回では、エンドマークの後に飛雄馬、明子、一徹、伴、花形、左門ら主要キャラクターが登場し、視聴者に向けて直接感謝の言葉を述べる。飛雄馬が「3年半にわたりご視聴ありがとうございました」と挨拶した後、次番組『天才バカボン』のパパと握手するというユーモラスな演出で締めくくられた。 この“世代交代”の象徴的な演出は、当時のテレビアニメとして極めて異例であり、アニメ文化の成熟を感じさせるものであった。
● 評価と功績
『巨人の星』は、日本のアニメ史の中で「スポーツ根性もの」という新しいジャンルを確立しただけでなく、アニメの演出技法や心理描写の深度においても後続作品に計り知れない影響を与えた。昭和のテレビ史を語るうえで欠かせない存在であり、今なお多くの研究書やドキュメンタリーで取り上げられている。
努力と挫折、父子の確執、友情とライバル心——それらすべてが絡み合う『巨人の星』は、単なるスポーツアニメを超えた“人間の成長劇”として、半世紀を超えて輝き続けている。
[anime-1]■ あらすじ・ストーリー
● 星飛雄馬の誕生と父の過去
物語は、戦後の日本社会の中でひっそりと暮らす元野球選手・星一徹の姿から始まる。一徹はかつて読売巨人軍の選手として名を馳せたが、禁断の魔球「魔送球」を投じたことで打者を重傷に追いやり、野球界から追放された過去を持つ。己の夢を絶たれた男が、新たに託した希望の名が“飛雄馬”である。幼い飛雄馬に対する一徹の教育は、一般的な親子愛の範疇を超えていた。早朝の素振り、鉄球トレーニング、冬の水泳、時には涙をのんでの竹刀指導。息子を「巨人の星」とするために、彼は鬼のように厳しく育て上げる。 幼い飛雄馬にとって、父の笑顔を見ることはほとんどなかった。だが一徹の背中には、夢を託す男の悲しみと情熱が滲んでおり、それを誰よりも理解していたのが、姉の星明子だった。明子は家庭の支え役として父と弟を見守り、貧しいながらも温かい食卓を守り続ける。
● 友情と成長、そして初めての挫折
成長した飛雄馬は、青雲高校に進学。そこで伴宙太という頼もしい仲間と出会う。伴は飛雄馬とは正反対の陽気な性格で、彼の孤独な心を和らげる存在となる。一方で、名門紅洋高校の花形満や九州から上京してきた豪腕投手・左門豊作といった強敵も現れ、飛雄馬の前に立ちはだかる。 甲子園大会での激闘では、花形の華麗な打撃、左門の力強いピッチング、そして飛雄馬の努力の結晶・大リーグボール1号が火花を散らす。試合の描写は単なるスポーツシーンに留まらず、青春の痛みと輝きが交錯する人間ドラマとして展開される。 しかし、勝負の世界は非情だった。仲間との絆を感じながらも、飛雄馬は一徹の期待を裏切ることを恐れ、自らを極限まで追い込んでいく。その結果、肩を痛めてマウンドを降りることとなり、初めて「努力しても敗れる」現実に直面する。
● 巨人軍入団と新たなる挑戦
その後、飛雄馬は夢にまで見た読売巨人軍への入団を果たす。ここから彼の物語は第二章へと進む。巨人のユニフォームに袖を通した飛雄馬は、父の教えを胸に、プロの壁へと挑戦していく。しかし、彼には「球質が軽い」という致命的な弱点があった。 それを克服するため、彼は父との再会を果たし、再び鬼のような特訓が始まる。屋根の上に並べた鉄球をすべて弾き飛ばす、激流を遡って投球フォームを矯正する——常人では考えられない修行の日々が描かれる。 そしてついに生まれたのが、伝説の“大リーグボール”。第1号はボールの縫い目に回転を与えず、打者の目線を幻惑させる魔球だった。この新技は、彼に再び希望をもたらすと同時に、ライバルたちを震撼させた。
● ライバルとの再戦と宿命の闘い
プロの舞台では、花形満も左門豊作も再び立ちはだかる。花形は華やかなスター選手としてチームを率い、左門は庶民的な人情味を持ちながらも勝負師として進化していた。かつての高校野球時代の因縁が、巨人軍を中心に再燃する。 飛雄馬は彼らとの試合で大リーグボール2号、3号と新たな魔球を次々と開発。しかしその代償として、肩や腕には限界を超える負担が蓄積していく。一方で、父一徹との確執も深まる。息子に勝利だけを求める父と、それに応えようとする息子——二人の関係は、愛と狂気の狭間を揺れ動く。
● 破滅と栄光の最終章
物語のクライマックスは、飛雄馬の左腕が限界を迎える瞬間に訪れる。大リーグボール3号を投げるたびに腕が悲鳴を上げ、それでもマウンドに立ち続ける飛雄馬の姿は、努力と執念の象徴そのものだ。 彼が最後に挑むのは、父・星一徹との“最終対決”である。一徹が監督として立つチームとの試合で、飛雄馬は完全試合を目指す。試合中、明子は涙ながらに見守り、伴や花形も息を呑んでその瞬間を待つ。 そしてついに、飛雄馬は完璧な投球で完全試合を達成。しかしその代償として、左腕は完全に壊れてしまう。倒れ込む息子を一徹が背負い、満員の観客が拍手で送り出す——それがアニメ版『巨人の星』の象徴的なラストである。
● 終焉と余韻
試合が終わった後、飛雄馬は静かにグラウンドを離れ、夕日に向かって歩き出す。その後ろ姿には、勝利を超えた“人間の成長”というテーマが刻まれている。アニメではこのシーンの後、飛雄馬が視聴者に直接語りかける特別な演出が施された。「3年半にわたり応援してくださって、ありがとうございました。」という感謝の言葉と共に、彼は新しい時代にバトンを渡す。 続く映像では、次作『天才バカボン』のキャラクターたちが登場し、飛雄馬とバカボンのパパが握手する。シリアスな物語を締めくくるにふさわしいユーモアであり、テレビアニメの枠を超えた遊び心として今も語り継がれている。
● 作品が残したメッセージ
『巨人の星』の物語全体を通して語られるのは、“夢を追うことの尊さと代償”である。飛雄馬は父の期待と自らの野心の狭間で苦しみながらも、最後まで逃げなかった。彼の生き様は、当時の視聴者に「努力は裏切らない」「己を信じることの価値」を強く印象づけた。 また、父一徹の厳しさも、ただの暴力ではなく、時代背景に根差した愛の形として描かれている。高度経済成長期の日本において、家庭と社会の中で“勝つこと”が至上命題だった時代、その精神を象徴するのが星家の姿であった。 アニメのラストで飛雄馬が太陽に向かって歩き出すカットは、敗北と再生、そして希望のメタファーとして今なお語り継がれている。
● ストーリー構成の完成度と映像演出
3年半にわたる放送期間中、物語は明確な三部構成で展開される。 – 第1部:少年期と父子特訓編 – 第2部:高校野球とライバルたちとの激闘編 – 第3部:巨人入団と大リーグボール編 この構成によって、成長ドラマとしてのリズムが生まれ、視聴者は飛雄馬の人生を段階的に追体験できた。演出面では、心理描写を強調する影の使い方や、画面を割る“緊張線”が特徴的で、手描きアニメーションの表現力を最大限に引き出している。
● 物語の普遍性
『巨人の星』は時代を超えて共感を呼ぶ物語である。スポーツや野球という枠を超え、人が何かを成し遂げるために何を犠牲にするか、どう乗り越えるかを問う作品であり、その問いかけは現代にも通じる。努力・才能・宿命——この3つの軸が交錯する物語は、まさに日本的ドラマの原点であり、アニメ文化における“魂の作品”といえるだろう。
[anime-2]■ 登場キャラクターについて
● 星飛雄馬(ほし ひゅうま)
本作の主人公にして、日本アニメ史を代表する“努力の象徴”ともいえる存在。小柄で繊細な体格ながら、父・星一徹の過酷な特訓によって、精神的にも肉体的にも鍛え上げられた。彼の人生はまさに「野球にすべてを捧げた男」の物語である。幼少期から父の厳しい鍛錬に耐え抜き、心身ともに強靭な意志を身につけていく。 飛雄馬の魅力は、その純粋さとひたむきさにある。ライバルに敗れても決して諦めず、涙を流しながら立ち上がる姿は、昭和の視聴者の心を強く打った。野球への情熱は、単なるスポーツ選手としての範疇を超え、「夢を追う人間の象徴」として語られる。 声を担当した古谷徹の情感あふれる演技は、少年期の無垢さから青年期の苦悩、そして最終回の静かな覚悟までを見事に演じ分けており、視聴者に深い印象を残した。飛雄馬の代表的な台詞「父ちゃん、見ててくれ!」は、作品の象徴的な言葉として語り継がれている。
● 星一徹(ほし いってつ)
飛雄馬の父であり、物語の精神的中核を担う人物。かつて読売巨人軍の選手だったが、禁断の魔球「魔送球」によって打者を負傷させた過去を持つ。野球界を追われた後、己の夢を息子に託すことを決意し、家庭内で鬼のような教育者へと変貌する。 その教育は過酷を極め、竹刀による特訓やちゃぶ台返しといった行動は、後年“スパルタ教育”の象徴となった。一徹は冷酷な父親ではあるが、その根底には「息子に自分の見られなかった景色を見せたい」という愛がある。彼の行動は極端でありながらも、時代の父親像を体現しており、視聴者の間で賛否を呼んだ。 加藤精三による低く重厚な声は、一徹の威厳と狂気、そして不器用な愛情を表現しており、彼の存在を単なる“暴君”ではなく“人間的な父”として感じさせる。最終回で飛雄馬を背負いながら涙をこらえる一徹の姿は、昭和アニメ史に残る屈指の名場面の一つだ。
● 星明子(ほし あきこ)
飛雄馬の姉であり、家庭の支え手として作品全体の“心の救い”を担う存在。母親の不在の中、家事や看病を一手に引き受けながら、父と弟の間に生まれる激しい緊張を和らげる役割を果たす。彼女の穏やかで包容力のある性格は、男性中心の物語世界における希少な癒やしの象徴であり、作品の情緒的バランスを保っている。 白石冬美による柔らかい声は、明子の優しさを際立たせると同時に、彼女が抱える苦悩をも繊細に表現した。特に、飛雄馬が父との確執に苦しむ場面で、彼に向けて「お父さんを憎んじゃいけないの」と語りかけるシーンは、作品屈指の名台詞として多くのファンに記憶されている。彼女はまさに“家庭という戦場の中の平和の象徴”であり、視聴者に安らぎをもたらす存在だった。
● 伴宙太(ばん ちゅうた)
飛雄馬の最大の理解者であり、熱血と友情の象徴。彼の登場によって、物語に人間的な温かみが加えられる。大柄な体格と豪快な性格を持ちながらも、心は優しく、涙もろい。飛雄馬とは対照的に明るく社交的で、時にお調子者として物語にユーモアをもたらす。 伴は青雲高校時代から飛雄馬の親友として登場し、彼の孤独を理解し支え続けた。プロ入り後も変わらぬ友情を示し、飛雄馬が挫折しかけた時に「お前が倒れたら誰が俺の夢を叶えてくれるんだ!」と叫ぶシーンは、彼の真っ直ぐな友情を象徴している。 声を担当した八奈見乗児の熱のこもった演技は、伴の豪快さと人間味を完璧に表現し、彼を単なる脇役ではなく、作品全体の潤滑油的存在へと昇華させた。
● 花形満(はながた みつる)
飛雄馬の永遠のライバルであり、彼とは正反対の境遇で育った青年。裕福な家庭に生まれ、エリート意識に満ちた性格だが、飛雄馬と出会うことで次第に真の野球道を学んでいく。紅洋高校時代からの宿敵として描かれ、彼の華麗なフォームと冷静な頭脳は飛雄馬の努力主義と鋭い対比をなす。 花形の魅力は、単なる“敵”としてではなく、成長する人間として描かれる点にある。彼は飛雄馬と競い合う中で自らの慢心を捨て、誇り高きライバルへと進化していく。 井上真樹夫のクールで知的な声質は、花形の品格と孤高さを見事に表現し、女性視聴者からの支持も高かった。彼の登場によって、物語はより立体的なドラマ性を帯び、勝負の中に“美学”という新たな要素が加わった。
● 左門豊作(さもん ほうさく)
九州出身の豪放磊落なライバル。純朴で正義感が強く、田舎育ちゆえの人情味と根性を持ち合わせる。巨人入団後も花形とは異なる“庶民派ヒーロー”として、飛雄馬と互いに切磋琢磨する存在となる。 左門の名シーンといえば、甲子園決勝での死闘。泥にまみれながらも飛雄馬と正々堂々と戦い、敗北を潔く受け入れるその姿勢は、多くの視聴者に感動を与えた。「男の勝負は逃げたら終わり」という台詞は、彼の生き方そのものを象徴している。 演じた兼本新吾の力強い九州弁混じりの演技は、リアリティと情熱を兼ね備え、左門というキャラクターを一層魅力的にしている。
● アームストロング・オズマ
アメリカから来日した黒人選手で、飛雄馬の最後の試練として登場する人物。彼の存在は、野球というスポーツが国境を越え、異文化との競争・共存の象徴として描かれている。オズマは圧倒的な身体能力と冷静な頭脳を持ち、飛雄馬の魔球を攻略するために科学的分析を行う。 二人の対決は、単なる勝敗を超えた“精神の戦い”として描かれ、国籍・人種・文化の壁を越えたスポーツマンシップの象徴となった。小林清志の低く響く声が、オズマの知性と威圧感を見事に表現し、最終盤の緊張感を高めている。
● 川上哲治(かわかみ てつはる)
実在の巨人軍監督をモデルにしたキャラクターで、アニメでは星飛雄馬の才能を見出し、導く立場として登場する。現実のプロ野球界を背景に、アニメの中で実在の人物が登場するという演出は当時としては画期的だった。 川上は厳格でありながらも選手思いの監督として描かれ、飛雄馬に「勝負は心の強さで決まる」と諭すシーンは、彼の哲学を象徴する名場面である。声を演じた星野充昭の誠実で落ち着いた演技は、現実味と尊敬を同時に感じさせた。
● キャラクター群像の意味
『巨人の星』に登場するキャラクターたちは、単なる野球選手ではなく、それぞれが「努力」「才能」「愛」「信念」といった人間の本質を体現している。星飛雄馬と星一徹の親子関係は“宿命と愛”を、花形と左門の存在は“階層と友情”を、伴と明子は“支えと救い”を象徴する。 これらのキャラクターの対比と絡み合いによって、作品は単なるスポーツアニメの域を超え、“人生劇場”としての完成度を高めている。
[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
● オープニングテーマ「ゆけゆけ飛雄馬」──希望と根性の象徴
『巨人の星』の主題歌といえば、何といっても「ゆけゆけ飛雄馬」である。作詞は東京ムービー企画部、作曲と編曲は渡辺岳夫が手がけ、アンサンブル・ボッカが力強く歌い上げたこの楽曲は、昭和アニメを代表するスポーツソングとして今なお語り継がれている。 イントロから響く金管のファンファーレは、飛雄馬の情熱と未来への疾走感を象徴しており、歌詞には「行け行け 飛雄馬 栄光の星をめざせ」という直球のメッセージが込められている。アニメのオープニング映像では、父・一徹の厳しい表情、飛雄馬のトレーニング風景、燃える太陽と野球ボールが重なる映像が挿入され、視聴者の心を一瞬で物語世界に引き込んだ。 この曲の魅力は、単なる応援歌ではなく「努力を美徳とする日本的精神」をそのまま音楽で表現している点にある。放送当時、少年野球チームではこの曲を応援歌として使用するチームも多く、学校の運動会で流された記録も残っている。いわば『巨人の星』が国民的アニメへと昇華していく過程を象徴するテーマ曲であり、昭和の少年たちにとっての“心の号令”だった。
● エンディングテーマ「ゆけゆけ飛雄馬(別バージョン)」──孤独と余韻
オープニングと同じタイトルを冠しながらも、エンディングで流れる「ゆけゆけ飛雄馬」は、アレンジやテンポが異なる。こちらはより哀愁を帯びた旋律で、1日の戦いを終えた飛雄馬の孤独や疲労感を表現している。 エンディング映像には、夕焼けに染まるグラウンドで一人ボールを投げ続ける飛雄馬の姿や、姉・明子が縫い物をしながら弟の帰りを待つシーンなどが描かれ、物語全体を温かく包み込むような余韻を与える構成となっている。 特に印象的なのは、ラストに流れる“白いボールが夜空へ飛んでいく”カットであり、それは飛雄馬の夢と孤独の象徴として、視聴者の胸に深く残る。渡辺岳夫の作曲は、戦いのリズムと静かな情感を見事に融合させ、アニメ音楽における心理描写の新たな境地を切り開いた。
● 副主題歌「友情の虹」──青春群像を彩る旋律
副主題歌として挿入された「友情の虹」は、ジ・エコーズが歌う軽快で明るいナンバー。タイトル通り、友情をテーマにした爽やかなメロディが印象的で、飛雄馬と伴宙太、そしてライバルたちの関係性を象徴する一曲である。 劇中では、試合の合間や練習風景の回想シーンでこの曲が流れ、飛雄馬が苦悩の中にも笑顔を取り戻す瞬間を演出した。スポ根アニメにおいて「友情」を明確に打ち出したこの楽曲は、以後のアニメソング文化に多大な影響を与えた。 また、当時のEPレコード盤では「ゆけゆけ飛雄馬」とカップリングされ、全国のレコード店で子どもたちに大人気となった。歌詞の中にある「涙のあとには虹が出る」という一節は、まさに本作全体のテーマ「努力の果てに光がある」を端的に表している。
● 学校対抗編の応援歌──チームスピリットを盛り上げる名曲群
作品中盤に登場する「青雲健児の歌」(青雲高校応援歌)や「紅洋の旗」(紅洋高校応援歌)は、作中のチーム対抗試合を彩る挿入歌として特別に制作された。どちらも渡辺岳夫による作曲で、アンサンブル・ボッカがコーラスを担当。 「青雲健児の歌」は、飛雄馬が所属する青雲高校の精神を象徴する勇壮なメロディであり、「紅洋の旗」は花形満率いる名門校の誇りを表現した荘厳な旋律が特徴だ。これらの曲は、対照的なキャラクター同士の精神性を音楽で描き分ける試みとして高く評価され、当時のサウンドトラック盤にも収録された。 また、これらの応援歌が挿入される試合シーンでは、観客席の熱気と選手たちの緊張感が音楽によって見事に調和し、アニメとは思えない臨場感が生み出されていた。音楽演出の巧みさは、当時のアニメ界でも際立っていたといえる。
● 挿入歌「クールな恋」──青春と葛藤の狭間で
松島由佳が作詞、村井邦彦が作曲した「クールな恋」は、本作の中では珍しい“恋愛”をモチーフとした挿入歌である。この曲は、飛雄馬が一瞬だけ見せる人間らしい感情、すなわち“青春の息吹”を象徴している。 劇中で流れるのは、明子がピアノを弾く穏やかな場面や、花形が自身の孤独を思い返す夜のシーンなど、物語の中でも静寂が支配する瞬間である。歌詞に込められた「情熱を隠して今日も戦う」というフレーズは、登場人物たちの胸の内を代弁しているようでもある。 この曲が流れることで、『巨人の星』という作品が単なる根性アニメではなく、繊細な心理ドラマとしての側面も持っていたことを証明している。渡辺岳夫と村井邦彦という二人の音楽家の共演は、当時のアニメ音楽の幅を広げた重要な試みであった。
● 劇伴音楽──渡辺岳夫が描いた“感情の設計図”
『巨人の星』の音楽を語る上で欠かせないのが、渡辺岳夫による劇伴スコアである。彼は、クラシック的な旋律構成と日本的情緒を融合させ、登場人物の感情を音楽で立体的に描いた。 一徹が飛雄馬に竹刀を振るう場面では重低音のブラスが響き、怒号と共に圧迫感を増す。一方で、明子が弟を見つめるシーンでは、弦楽器とハープが静かに流れ、家庭のぬくもりを感じさせる。このような音楽の緩急は、当時としては非常に革新的であり、“音で心理を描く”アプローチの原点ともいえる。 また、飛雄馬が魔球を完成させる訓練シーンでは、シンバルの連打とティンパニの高鳴りが緊張を演出し、まるで実写映画のクライマックスのような臨場感を生んでいた。アニメ音楽としての完成度は非常に高く、後年の『タイガーマスク』や『あしたのジョー』など、同系統作品の音楽構成にも多大な影響を与えた。
● 主題歌の社会的影響と文化的広がり
「ゆけゆけ飛雄馬」は放送当時から国民的ヒット曲となり、子ども向けの歌謡番組やNHK『みんなのうた』などでも放送された記録がある。小学校の合唱曲として取り上げられた地域もあり、アニメソングとしては異例の社会的浸透を見せた。 さらに、プロ野球球団や社会人野球チームでもこの曲を応援BGMとして使用する例が増え、実際のスタジアムで鳴り響く場面も多かった。1960~70年代の野球少年たちにとって、この曲はまさに「夢へのファンファーレ」であり、時代の精神そのものを代弁していたと言える。 平成以降も、この曲は数々のリメイクやカバーが制作され、声優による新録バージョンや、オーケストラ編成での演奏なども発表されている。特にアニメ放送50周年記念アルバムでは、現代的なアレンジによって再録され、往年のファンだけでなく若い世代にも再評価された。
● 総評──音楽が語る『巨人の星』の魂
『巨人の星』の音楽は、単なるBGMや主題歌に留まらず、物語そのものを“音”で語る役割を担っている。飛雄馬が走るときのトランペット、一徹の影に流れる重厚なベースライン、友情の場面を包むアコースティックギター──そのすべてが、登場人物の感情の波を表現している。 音楽監督・渡辺岳夫の構成力と、歌唱陣の熱演が融合した結果、作品全体が「音で感情を増幅させる」構造を持つに至った。『巨人の星』の主題歌群は、日本アニメ史において“スポ根サウンド”というジャンルを確立させた礎であり、以降の数多くのアニメソングに影響を与え続けている。
[anime-4]■ 声優について
● 声優陣の魅力とキャスティングの意図
『巨人の星』の成功を語る上で欠かせないのが、その圧倒的な“声の演技力”である。1960年代後半のアニメ業界において、ここまでドラマ性と心理描写を重視した声優演技は極めて珍しく、当時のアニメファンや制作者の間で大きな衝撃を与えた。 本作のキャスティングは、キャラクターの内面と人生背景を正確に表現できる実力派俳優を中心に構成されており、単なる声の当て方ではなく「演技によるドラマ表現」が追求された点に特徴がある。監督の長浜忠夫は、声優を“もう一人の演出家”として扱い、声の抑揚や呼吸までも物語の一部として計算していたという。 その結果、星飛雄馬の叫びや一徹の怒号、明子の優しさといった感情の振れ幅が、リアルな人間ドラマとして視聴者の心に届く形となった。まさに、『巨人の星』は“声優の演技力が作品を支えた”アニメの代表例である。
● 星飛雄馬役:古谷徹 ─ 少年の熱と苦悩を演じた青春の声
主人公・星飛雄馬を演じたのは、若き日の古谷徹。彼はこの役で一躍注目を集め、後に『アムロ・レイ(機動戦士ガンダム)』や『安室透(名探偵コナン)』など、時代を代表する声優へと成長していく。 当時まだ20代前半だった古谷は、少年期の無邪気さから青年期の苦悩、そしてプロ入り後の孤独と決意まで、声ひとつで演じ分ける稀有な才能を見せた。特に特徴的なのは、感情が高まると声のトーンが震えるように上ずる“涙声”であり、それが飛雄馬の繊細な心情をより生々しく伝えていた。 古谷自身も後年、「星飛雄馬は自分の青春そのものだった」と語っており、実際に収録現場では監督の要望で何度もリテイクを重ね、声に“魂の揺れ”が宿るまで演じ込んだという。 代表的な名演は、巨人軍入団試験のシーンでの「父ちゃん、見ててくれ!」という叫びだ。この一言にこもる感情は、今も多くのファンの記憶に刻まれている。
● 星一徹役:加藤精三 ─ 威厳と愛情を併せ持つ父の声
一徹役の加藤精三は、舞台俳優としてのキャリアを持つベテランであり、その低く響く声は“父の威厳”を象徴していた。彼の声は重厚でありながらもどこか悲哀を帯びており、鬼のような指導者でありながら、一人の人間としての苦悩を見事に表現している。 収録中、加藤は「ただ怒鳴るだけではこの男は描けない」として、声の奥に微かな震えや間を取り入れ、愛情と狂気の境界線を表現した。特に飛雄馬を叱責する場面では、セリフの一文字一文字に重みがあり、その声だけで場の空気を支配していたと言われている。 彼の「ちゃぶ台返し」は今でこそコミカルな象徴として語られるが、当時の演技は怒りを通り越した“絶望の爆発”として描かれており、加藤の演技があったからこそ、そのシーンが伝説となったのである。最終話での「飛雄馬、よくやった」という一言は、加藤精三の代表的名台詞としてファンの間で語り継がれている。
● 星明子役:白石冬美 ─ 優しさと芯の強さを兼ね備えた母性的演技
明子を演じた白石冬美は、その柔らかくも芯のある声で“理想の姉”像を作り上げた。彼女の声は、聞くだけで心が落ち着くような包容力を持ち、荒々しい男たちの世界の中で唯一の癒やしとなっている。 白石はインタビューで「明子は弱いようで一番強い女性」と語っており、声のトーンを“静かな強さ”として表現することにこだわった。弟を見守る時の穏やかな声、父を諫める時の少し低めの厳しい声、そのバランスが絶妙で、アニメの感情構造を支える要素となっていた。 特に、飛雄馬が肩を痛めて苦悩する回での「お父さんを恨んじゃだめ」というセリフは、白石の静かな演技力が光る名場面である。彼女の声があったからこそ、家庭という荒波の中に温もりが生まれたと言えるだろう。
● 伴宙太役:八奈見乗児 ─ コメディと熱血の両立
伴宙太を演じた八奈見乗児は、後に『ヤッターマン』シリーズなどでも知られる名バイプレイヤーである。彼の特徴は、豪快な笑い声と絶妙な間の取り方で、重苦しくなりがちなドラマの中にユーモアと人情を吹き込んだ。 伴は作品全体の“潤滑油”のような存在であり、飛雄馬に寄り添う姿勢が視聴者の共感を呼んだ。八奈見はインタビューで「伴のセリフは、心でしゃべらないと軽くなる」と語っており、収録では常に感情を全身で表現していたという。 特に、飛雄馬を励ますシーンでの「お前が倒れたら俺が誰を応援すりゃいいんだ!」という台詞は、八奈見の熱演によって涙を誘う名シーンとなった。明るさと熱さのバランスが見事であり、声優としての表現力の高さが光る役である。
● 花形満役:井上真樹夫 ─ クールで孤高の貴公子
花形満を演じた井上真樹夫は、その端正で知的な声質によって、花形のエリート的な魅力を余すことなく表現した。彼の演技は、ライバルでありながらも敬意を持って飛雄馬と接する花形の複雑な心理を巧みに描いている。 井上は当時すでに『ルパン三世』シリーズの石川五ェ門役などでも知られており、冷静沈着なトーンに内面の情熱を潜ませる表現力に長けていた。花形が敗北を悟る場面での「俺はお前に勝ちたかった」や、「君は僕の太陽だ、飛雄馬君」という言葉には、井上の演技哲学が凝縮されている。 その声には上流階級的な品格と孤独が共存し、花形という人物を単なる敵役ではなく、心の奥で友情を抱く“もう一人の主人公”へと昇華させた。
● 左門豊作役:兼本新吾 ─ 土の香りを持つ男らしさ
左門豊作を演じた兼本新吾は、地方出身者特有の温かみを持つ声を活かし、田舎の純朴さと不屈の精神を体現した。豪快な九州弁交じりのセリフは親しみやすく、視聴者にとって最も“血の通ったキャラクター”として人気を博した。 彼の演技には、勝負師としての激しさと人間的な温かさが共存しており、特に甲子園決勝戦後に飛雄馬に握手を求める場面では、声の震えによって感動が倍増した。兼本の演技がもたらしたリアリティは、アニメの中に“生身の人間”を感じさせるものであった。
● アームストロング・オズマ役:小林清志 ─ 威厳と知性の声
アメリカ出身の黒人選手・オズマを演じたのは、渋い低音で知られる小林清志。彼の声は理性的で落ち着きがありながら、どこか人間的な温かさを感じさせる。オズマは単なる強敵ではなく、スポーツマンとしての誇りを持った“もう一つの理想”を体現する存在であり、小林の演技によってキャラクターの深みが際立った。 特に飛雄馬との最後の対決前に発する「君の魂のボールを、受け止めてみたい」という台詞は、スポーツの本質を語る名言として今なお語り継がれている。
● 声優たちが生んだ“人間ドラマ”
『巨人の星』における声優陣の演技は、後のアニメ作品に多大な影響を与えた。彼らはキャラクターを演じるだけでなく、その“生き様”を声で伝えることに挑戦していた。怒鳴り、泣き、笑い、沈黙する──そのすべてがドラマの一部であり、視聴者は“声の芝居”によって心を揺さぶられた。 特に古谷徹と加藤精三の父子対決シーンは、アニメ史上でも屈指の名演技として語り継がれている。二人のセリフの応酬は、まるで舞台芝居のような緊張感を持ち、実際に放送当時は録音現場でもスタッフが涙したといわれるほどである。
● 総評──声の力が作り出した“魂のアニメ”
『巨人の星』は、映像や脚本だけでなく“声”によって物語を完成させた稀有な作品である。各声優が自らの人生を重ねるように演じたことで、アニメが“子どもの娯楽”から“人間ドラマ”へと昇華した。 彼らの声は半世紀を経た今でも色褪せず、再放送やリマスター版でもその迫力と感情が鮮明に伝わる。まさに、声優陣の演技があったからこそ『巨人の星』は永遠の名作となり得たのである。
[anime-5]■ 視聴者の感想
● 放送当時の社会的反響と家族の風景
1968年から1971年という放送時期、『巨人の星』はまさに日本が高度経済成長の真っただ中にあった時代を背景に登場した。そのため、視聴者の多くは“家族でテレビを見る”という文化を共有しており、毎週土曜日の夜に茶の間で父母と子どもが並んでこのアニメを観るという光景が各家庭で見られた。 当時の世代にとって、星一徹の厳しい父親像は“昭和の親父”そのものだった。子どもたちは飛雄馬に自分を重ね、父親たちは一徹に自らを重ねていたとも言われる。中には、「アニメを見て涙を流すなんて思わなかった」という当時の成人視聴者の声もあり、子ども向けアニメを超えた“家族の物語”として受け止められていたことが分かる。 また、ちゃぶ台をひっくり返す一徹の姿は「怖い父親の象徴」であると同時に、「それでも息子を愛している父の苦悩」としても理解され、視聴者の感情を複雑に揺さぶった。家族で視聴した世代の中には、「放送のあと父とキャッチボールをした」「翌日、学校で友達と魔球の練習をした」といったエピソードも多く残っている。
● 子どもたちが感じた“努力と夢”への憧れ
当時の少年視聴者の多くは、星飛雄馬の姿に強い憧れを抱いた。彼が涙と汗を流しながらも夢に向かって突き進む姿は、学校やクラブ活動に励む子どもたちの理想像となった。 視聴者の感想の中には、「飛雄馬のように努力すれば夢は叶うと信じて野球を始めた」「魔球を投げようとして親に怒られた」といった微笑ましい思い出も多い。中でも印象的なのは、「アニメを観た翌日、グラウンドに行くと誰もが飛雄馬のフォームを真似していた」という証言で、作品がどれほど子どもたちの生活に影響を与えたかを物語っている。 また、飛雄馬が涙をこらえて父の期待に応えようとする姿は、「我慢」や「忍耐」といった当時の社会的価値観とも強く結びついており、子どもたちの中に“努力は裏切らない”という信念を植え付けた。現代の視点から見ると厳しすぎる訓練も多いが、それを「立派な男の成長」として受け止める空気が時代にはあった。
● 母親世代・女性視聴者の視点──家庭の中の“愛の形”
『巨人の星』はスポ根アニメでありながら、女性視聴者からの共感も多かった。特に母親世代は、星家の貧しさや明子の健気な姿に深く感情移入したという声が多い。「貧乏でも家族が支え合う姿に泣いた」「明子が弟を想う気持ちは母の愛と同じ」といった感想が寄せられており、本作が家族愛を描いたヒューマンドラマとしても評価されていたことが分かる。 また、女性の中には「星一徹のような父は怖いけれど、あの時代には必要だった」とする意見もあり、父権主義的な側面すら“時代の象徴”として受け入れられていた。視聴者の中には、飛雄馬の姿を「息子に重ねて応援していた」と語る母親も多く、最終回の父子の抱擁シーンでは実際に涙したという証言が多く残る。
● 青年層・学生たちが感じた“現実との重なり”
放送当時、高度経済成長期に働く若者たちにとって、『巨人の星』は単なるアニメではなく“人生の応援歌”だった。飛雄馬の努力は、会社で働くサラリーマンや学生の奮闘と重なり、「俺も頑張ろう」という活力を与えた。 特に大学生や新入社員の視聴者からは、「飛雄馬が巨人に入団する回を見て、自分も就職試験を頑張ろうと思った」「一徹の言葉を上司の叱責に重ねた」という声が多く寄せられている。つまり、視聴者は彼らの“夢と現実の狭間”をこの作品に見出していたのだ。 このように、『巨人の星』は子どもだけでなく大人たちにも精神的な影響を与えた稀有なアニメであり、その社会的共感の広がりが国民的作品としての地位を築いた。
● 最終回への反響と“涙の完結”
1971年の最終回放送時、視聴率は20%を超え、まさに“国民的フィナーレ”となった。SNSなどのない時代であっても、翌日の新聞投書欄や雑誌の編集部宛てに、数千通を超える感想が寄せられたという記録が残っている。 多くの視聴者が共通して語ったのは、「最後に飛雄馬が父に背負われる場面で涙が止まらなかった」という感動の声だった。一方で、「あのまま彼がどこに行ったのかを知りたかった」「完全試合の後も続きが見たかった」といった“余韻を惜しむ声”も少なくなかった。 さらに、エンドマークの後に挿入された飛雄馬の“視聴者への挨拶”シーンも強い印象を残した。飛雄馬が「3年半の間、ありがとうございました」と視聴者に直接語りかける演出は、アニメ史上初の試みであり、テレビの前の視聴者はまるで本人から感謝を受け取ったような気持ちになったという。この瞬間、多くの人が彼を“架空の人物”ではなく“現実に生きた青年”として受け止めた。
● 再放送世代の感想──時代を越えて受け継がれる熱
1980年代以降、再放送やビデオ化によって『巨人の星』を初めて観た世代からも熱い感想が寄せられた。再放送を観た子どもたちは、「昔のアニメなのに迫力がある」「飛雄馬の目の輝きに心をつかまれた」と感動を語り、アニメ技術が進化した時代でもその表現力に圧倒されたという。 また、当時の親世代が子どもと一緒に再放送を観るケースも多く、「自分の少年時代を思い出した」「親子で同じアニメに涙した」といった世代を超えた感動体験も生まれた。特にDVD化やデジタル配信によって、映像の鮮明さが増した2000年代以降、若い世代が“昭和の熱量”をリアルに感じる機会が増えた。現代のSNSでも、「#巨人の星を初めて観た」「昭和アニメの熱がすごい」という投稿が絶えない。
● 現代の視聴者が見る“巨人の星の教訓”
現代の視聴者にとって、『巨人の星』は単なる懐かしの作品ではなく、親子関係や努力論を見つめ直す“教材”のような存在でもある。現代社会では「過度なスパルタ」「ブラック根性」などが批判される傾向にあるが、その中で一徹と飛雄馬の関係は、愛の厳しさと責任を考えるきっかけとして語られている。 SNS上では、「今見ると父の愛が痛いほど伝わる」「一徹は時代が違えば名コーチだったかもしれない」といった、冷静かつ深い分析的な感想も増えている。逆に、「飛雄馬のような頑張り方は危険だ」「自分を追い詰めすぎる現代人への警鐘だ」とする意見もあり、作品が持つ“努力の哲学”が今も議論を呼ぶほどの力を持っていることが分かる。 それでも多くの視聴者が共通して挙げるのは、「本気で何かを目指す姿は美しい」という肯定的な想いだ。半世紀が経った今でも、『巨人の星』が放つ熱量と誠実さは時代を超えて心に響き続けている。
● 視聴者の心に残る名台詞とその影響
感想の中で特に多く引用されるのが、飛雄馬の「父ちゃん、見ててくれ!」や、一徹の「飛雄馬、行け!」という台詞だ。これらの言葉は、単なるセリフではなく人生の標語のように人々の記憶に残り、テレビアニメの言葉が人の生き方に影響を与えた数少ない例でもある。 また、「努力に勝る天才なし」「涙は恥ではない」といったテーマ的フレーズも、視聴者の人生観に影響を与え続けた。これらの台詞は、現代のビジネス講演や教育現場でも引用されることがあり、『巨人の星』がアニメを超えて“人生哲学の源泉”となったことを物語っている。
● 総評──“共に生きたアニメ”としての記憶
視聴者にとって『巨人の星』は、ただ観るだけの作品ではなく、人生の節目に寄り添ってくれる存在だった。初放送で涙し、再放送で懐かしみ、親子で観て語り合う——そうした体験が世代を超えて受け継がれている。 「飛雄馬が太陽に向かって歩く姿は、自分の人生を照らす光だった」と語る視聴者も多く、彼らにとってこの作品は希望と努力の象徴そのものである。 『巨人の星』は放送から半世紀以上を経てもなお、視聴者の心に「夢を信じる勇気」を呼び起こす。まさに、アニメ史における永遠の名作として、観る者の人生と共に息づき続けているのである。
[anime-6]■ 好きな場面
● ちゃぶ台返し──家庭と情熱の象徴
『巨人の星』の中で最も有名なシーンといえば、やはり星一徹による「ちゃぶ台返し」である。父親の厳しさと怒りが凝縮されたこの瞬間は、日本アニメ史における象徴的場面として知られる。多くの視聴者にとって、ちゃぶ台返しは単なる暴力的表現ではなく、夢に破れた男が息子に託した情熱の爆発であった。 一徹がちゃぶ台をひっくり返す瞬間、画面全体に雷鳴のような効果音が響き、茶碗や味噌汁が宙を舞う。その一瞬の静寂の後に訪れる、飛雄馬の涙と明子の悲しげな表情。このシーンは、家庭という小さな舞台の中で描かれる“愛と衝突”の縮図であり、視聴者は誰もが息をのんだ。 当時のファンの多くは、「父が怒る時の怖さを思い出した」「家族の関係がリアルすぎて胸が痛くなった」と語っている。一方で、「あの場面こそ、一徹が本気で息子を信じている証」と肯定的に捉える意見も多い。結果として、この場面は“昭和の親子像”の象徴として、半世紀を超えて語り継がれている。
● 明子の涙──家庭を支える静かな強さ
激しい父子の衝突の裏で、視聴者の心を静かに打つのが姉・明子の涙の場面である。父と弟の争いを見守りながらも、どちらの味方にもなれない苦しみ。それでも彼女は、家族が壊れないよう祈るように微笑む。その一瞬の表情が、見る者の胸を締めつけた。 特に印象的なのは、飛雄馬が一徹の特訓に耐え切れず家を飛び出す夜。玄関の灯りを見つめ、何も言えずに流す明子の涙。この場面はセリフを最小限に抑え、BGMだけで感情を描いており、渡辺岳夫の静かなピアノ曲が切なさを増幅させる。 女性視聴者からは「明子の涙で初めて泣いた」「彼女こそこの物語の影の主人公」との声も多く、明子の存在が『巨人の星』の感情的バランスを支えていたことが改めてわかる。
● 伴宙太の友情──笑いと涙が同居する名シーン
伴宙太が飛雄馬を励ます場面も、ファンの間で“泣ける名シーン”として語り継がれている。特に印象的なのは、飛雄馬が肩を壊して再起不能になりかけた回で、伴が涙ながらに「お前が倒れたら、俺の夢はどうなるんだよ!」と叫ぶ場面だ。 このセリフには、友としての愛情だけでなく、「自分も彼の努力に支えられてきた」という相互の絆が凝縮されている。伴の豪快さの裏にある人間らしい弱さが表現され、視聴者の多くが「伴が泣くと自分も泣いた」と語っている。 このシーンは、熱血スポ根アニメの中に“人間味”を与えた重要な瞬間でもあり、友情の尊さを感じさせる。八奈見乗児の感情をむき出しにした演技が、この場面を永遠の名場面へと昇華させた。
● 花形満とのライバル対決──美学と執念の融合
飛雄馬と花形の対決は、『巨人の星』における最も劇的な構図のひとつである。特に印象深いのは、巨人軍入団後に再び相まみえる“東京ドーム決戦”のシーン。両者のフォームが交錯し、白球が夕日に溶け込むカットは、アニメ史に残る映像美として語られる。 花形が放つ一言、「お前の努力には敬意を表する。しかし、勝つのは俺だ!」に対し、飛雄馬が無言で構える——この沈黙の演出が凄まじい緊張感を生んだ。 このシーンでは、単なる勝敗ではなく、“野球を通じて人として成長する姿”が描かれる。視聴者からは「花形が悪役ではないのが良い」「ライバルを憎むのではなく尊敬しているところが感動的」との声が多く寄せられた。 また、井上真樹夫のクールな声と古谷徹の熱を帯びた声の対比が、二人の精神的距離を見事に表現しており、音声演出としても高く評価されている。
● 大リーグボール誕生の瞬間──努力の結晶
アニメファンの間で“最も胸が熱くなるシーン”として語られるのが、飛雄馬が初めて“大リーグボール1号”を完成させる場面だ。 彼は何度も失敗を繰り返し、肩を痛めながらも諦めなかった。ついにボールが奇跡のような軌道を描き、父・一徹がその投球を見て無言でうなずく——この瞬間、視聴者は「努力は裏切らない」というメッセージを全身で感じ取った。 演出面では、投球シーンを極端なスローモーションと残像で表現し、ボールの回転を止めることで“神の一球”を演出している。BGMの高揚、汗の飛沫、観客の息を呑むカットの積み重ね——そのすべてが奇跡の誕生を象徴していた。 放送当時、「自分も魔球を投げたくて家の前で練習した」という少年たちの声が殺到し、まさに世代のロマンとして刻まれた。
● 一徹との最終対決──父子の愛と別れ
シリーズの頂点とも言えるのが、最終回の父子対決である。 一徹が監督としてベンチに立ち、飛雄馬が投手として最後の試合に挑む。観客席には伴、花形、左門、そして涙を浮かべる明子の姿。 完全試合を目指す飛雄馬は、壊れかけた左腕で渾身のボールを投げ続ける。痛みで顔を歪めながらも、一徹の教えを胸に刻み、「この試合で父を超える」と決意する姿に、日本中が涙した。 試合後、飛雄馬が崩れ落ち、一徹が彼を背負ってグラウンドを去るシーン——この場面に心を動かされなかった視聴者はいないだろう。拍手と夕陽の光、無言の父子。あの静寂の中に、何年分もの葛藤と愛情が詰まっていた。 放送後には「父と一緒に泣いた」「言葉では表せないほど感動した」という感想が相次ぎ、アニメの枠を超えた“人間ドラマ”として語られるようになった。
● 太陽に向かう飛雄馬──永遠のエンディング
最終回のラスト、飛雄馬が太陽の光に向かって歩き出す場面は、日本アニメの中でも屈指の美しいラストシーンとされている。 背中だけを映し、音楽も静まり返る中で、飛雄馬の影が次第に遠ざかっていく。この“背中で語る演出”は、彼が努力と孤独を受け入れ、人生の次のステージへと歩み出すことを象徴していた。 多くの視聴者は「まるで自分の人生を見送るような気持ちだった」と語り、少年から大人へと成長する自分を重ねたという。 また、エンドロールの後に飛雄馬が視聴者へ感謝を述べるシーンが挿入されることで、物語が現実と地続きであるかのような感覚を生み出した。 この演出は後のアニメ作品にも影響を与え、『あしたのジョー』『タッチ』など、スポ根作品の“去りゆく背中の美学”の原点となった。
● 名場面が語り継がれる理由
『巨人の星』の名場面は、単なるドラマチックな演出ではなく、“人の心を映す鏡”として成立している。視聴者が泣いた理由は、飛雄馬が自分自身の努力や夢を思い出させる存在だったからだ。 また、演出陣が映像の緩急を重視し、叫びや沈黙、光と影を使って感情の波を表現したことも名場面の多さに繋がっている。 例えば、飛雄馬が一人夜のグラウンドで素振りを続ける場面は、台詞ひとつなくとも彼の孤独と情熱を感じさせる。こうした“語らない名場面”が多いのも本作の特徴であり、視聴者自身が想いを投影する余白を残していた。
● 総評──世代を超えて心に残る瞬間
『巨人の星』の好きな場面は人それぞれだが、共通しているのは“人間の情熱と絆が描かれている”という点である。ちゃぶ台返しの怒りも、魔球の成功も、涙の別れも、すべては「夢を追う人間の姿」を象徴していた。 視聴者にとってそれは懐かしい思い出であると同時に、自分の人生を照らす原点でもある。 半世紀を経た今も、SNSでは「このシーンで泣いた」「この一言が忘れられない」と語られ続けており、『巨人の星』が残した名場面は、時代を超えて生き続けている。
[anime-7]■ 好きなキャラクター
● 星飛雄馬──努力と孤独を背負った“昭和のヒーロー”
多くの視聴者が真っ先に挙げる好きなキャラクターは、やはり主人公・星飛雄馬である。彼は単なる野球選手ではなく、“努力”という概念を具現化した存在として描かれている。 子どもの頃から父の過酷な訓練を受け、友人との遊びも犠牲にして野球一筋に生きる。その姿に、当時の少年たちは「自分も飛雄馬のように強くなりたい」と夢を重ねた。 しかし同時に、彼の物語は「孤独の物語」でもあった。父の期待を背負い、自らを極限まで追い詰めていく姿には悲哀が漂う。視聴者の中には「飛雄馬の頑張りが切なくて見ていられなかった」「あんなに努力しても報われない現実がリアルだった」と語る人も多い。 彼の魅力は、挫折してもなお立ち上がる強さにある。魔球を完成させるために血のにじむ練習を重ね、仲間を裏切るような選択をしてでも夢を貫こうとする姿は、誰よりも人間臭く、熱く、純粋だった。 そして最終回での“父に背負われる”ラストは、彼が一人の少年から一人の男へと成長した瞬間を象徴する。視聴者にとって飛雄馬は、時代を越えて「自分を奮い立たせる存在」として記憶されている。
● 星一徹──愛と狂気を併せ持つ“究極の父親像”
次に多くの支持を集めるのが、星一徹である。彼は作品の中で最も激しく、そして最も人間的なキャラクターだ。 一徹は、かつて自身の夢を果たせなかった男。だからこそ、息子に自らの未練を託す。その行為は、表面的には暴力的で冷酷に見えるが、実際は誰よりも息子を愛していた。 「鬼のような父親」と恐れられながらも、一徹の中には“愛するがゆえに突き放す”という葛藤が常に存在する。彼の名台詞「男はな、涙を見せずに努力するものだ!」は、当時の社会全体が抱いていた父親像を象徴していた。 視聴者の中には、「自分の父を思い出した」「あの厳しさの裏にある愛情を今ならわかる」という声も多い。 また、一徹が時折見せる静かな優しさ──明子への眼差しや、倒れた飛雄馬の肩にそっと手を置く仕草──に、人間としての温もりを感じるという意見もある。 “ちゃぶ台返し”という強烈な印象を持つ彼だが、その裏に潜む愛と後悔こそが一徹の本質であり、多くの視聴者が彼を「憎めない父」として記憶している。
● 星明子──静かな愛の象徴
飛雄馬と一徹という二人の強烈な男たちの間に立つ、もう一人の中心人物が姉の星明子だ。 彼女の存在は、作品全体に“優しさ”と“安定”をもたらしている。飛雄馬が挫折するたびに支え、時に父を諫め、家庭を守る姿はまさに「昭和の理想の女性像」である。 しかし、ただの優しさでは終わらない。彼女は家族の苦しみをすべて背負いながらも、決して弱音を吐かない。その姿に女性視聴者からの共感が集まった。「明子の涙で泣いた」「彼女の微笑みが救いだった」との声が放送当時から多かった。 また、彼女は物語の中で“希望の象徴”として描かれる。どんなに家庭が壊れそうになっても、彼女が笑顔でいる限り家族は再生できる。そんな“信じる力”が、彼女の最大の魅力である。 視聴者にとって明子は、“見守る愛”“耐える愛”の象徴であり、現代でも「理想の姉・母・妻」として語り継がれている。
● 伴宙太──庶民の明るさと涙の友情
伴宙太は、物語の中で最も親しみやすいキャラクターであり、作品に温かみを与えた存在だ。 彼は大柄で豪快だが、情に厚く、仲間思い。飛雄馬が苦しい時には誰よりも近くに寄り添い、彼の努力を笑顔で支える。「飛雄馬、お前ならできる!」という励ましの一言に、どれほどの視聴者が救われただろうか。 伴の魅力は、その“人間臭さ”にある。勝っても負けても素直に笑い、涙を見せる。努力を讃え、友情を大切にする。まさに「昭和の男の友情」を体現したキャラクターだった。 特に人気が高いのは、飛雄馬の故障時に彼が号泣するシーン。「お前が立ち上がらないと、俺の夢も終わるんだ!」と叫ぶその瞬間、伴はただの脇役ではなく、飛雄馬の心そのものを代弁する存在になっていた。 八奈見乗児の人情味あふれる声も相まって、伴宙太は多くのファンに“永遠の親友キャラ”として愛され続けている。
● 花形満──ライバルであり理想の対極
花形満は、星飛雄馬の永遠のライバルでありながら、同時に彼を最も理解する人物でもある。 裕福な家庭に育ち、恵まれた才能を持つ花形は、飛雄馬とは正反対の存在だ。しかし、彼は努力の天才・飛雄馬に出会うことで、初めて“本当の勝負”を知る。 花形の魅力は、敵対しながらも常に敬意を失わないことだ。彼は飛雄馬を倒すために努力を惜しまず、時に己のプライドを捨てて成長する。つまり、花形もまた“努力の人”である。 視聴者の中には、「花形の冷静さに憧れた」「彼の言葉に救われた」という声が多く、特に女性ファンの人気は高かった。 「お前の努力には敬意を表する、だが勝つのは俺だ!」という名台詞に象徴されるように、彼の生き方は“勝負の美学”そのものである。井上真樹夫の知的な声が花形の品格を際立たせ、作品に華を添えた。
● 左門豊作──純朴さと正義の象徴
九州出身の左門豊作は、豪放磊落なキャラクターとして、視聴者の心を掴んだ。彼の「どげんしても勝つ!」という方言混じりのセリフは親しみ深く、観る者に勇気を与えた。 左門は、裕福でも天才でもない。だが努力と根性で強者に挑み続ける姿は、視聴者に“自分にもできる”という希望を感じさせた。 彼の人気の理由は、勝っても驕らず、負けても潔い性格にある。花形とは違う意味でのライバルであり、飛雄馬にとって“人間的な鏡”のような存在だった。 特に甲子園での一騎打ちシーンは多くのファンにとって忘れられない場面で、「真っ向勝負こそ男の誇り」という彼の生き様が強く印象に残った。 左門は、努力・友情・誠実さを兼ね備えたキャラクターとして、昭和アニメの“庶民派ヒーロー”の代表的存在である。
● アームストロング・オズマ──国境を越えたライバル
オズマは『巨人の星』の物語終盤に登場する異色のキャラクターであり、飛雄馬の精神的成長を促す存在として描かれた。 彼は黒人選手であり、圧倒的なパワーと理性的なプレーで観客を魅了する。だが彼の本質は「勝つためではなく、最高の野球をするために戦う男」である。 飛雄馬との対決においてオズマが放つ「君の魂のボールを受け止めてみたい」という台詞は、スポーツマンシップの極致を表しており、視聴者の多くがこの言葉に感動した。 オズマの存在は、当時の日本アニメにおいて“異文化との交流”をテーマにした先駆的なキャラクターであり、人種や国境を越えて友情を描いた点でも高く評価されている。 彼の姿は、“強さと優しさを兼ね備えた理想のアスリート像”として記憶され、今も多くのファンに愛され続けている。
● 総評──個性の競演が生んだ人間ドラマ
『巨人の星』がここまで愛され続けているのは、どのキャラクターも“人間的な弱さと強さ”を併せ持っているからである。 飛雄馬の努力、一徹の愛、明子の優しさ、伴の友情、花形の誇り、左門の正義、そしてオズマの魂——それぞれの生き方が、視聴者にとっての人生の教科書となった。 彼らの関係性が生み出すドラマは、単なる野球物語ではなく“人生の縮図”であり、見る人の年代や立場によって共感する人物が変わるのも本作の魅力である。 まさに、『巨人の星』はキャラクターたちの息づかいによって作られた「群像劇の傑作」なのだ。
[anime-8]■ 関連商品のまとめ
● 映像関連商品──VHSからBlu-rayまでの軌跡
『巨人の星』の映像ソフト化は、1980年代後半から始まった。当初はアニメブーム再燃の波に乗る形で、一部の人気エピソードを収録したVHSビデオが東宝やポニーキャニオンなどから販売された。これらは当時まだ家庭用ビデオデッキが普及し始めた時期であり、限定生産のものも多かった。初期巻には「ちゃぶ台返し」や「大リーグボール誕生」といった名場面が収録され、ファン垂涎のアイテムとなった。 1990年代にはレーザーディスク(LD)版が登場し、画質の良さと大画面での視聴体験がアニメファンの間で人気を集めた。LD版では特典として設定資料やアニメ制作スタッフのコメントが封入され、コレクターズアイテムとしての価値が高まった。 2000年代に入ると、全話を収録したDVD-BOXが発売される。初回限定版には、豪華ブックレットやオリジナルイラストジャケット、ノンクレジットOP/ED映像などが付属。さらに2010年代にはデジタルリマスターによる高画質版DVD、2020年代にはBlu-rayコンプリートBOXが登場した。Blu-ray版では音声のクリア化と映像の色補正が施され、当時の放送では見えなかった細部まで鮮明に再現されている。 特典ディスクには、主題歌「ゆけゆけ飛雄馬」のライブ映像や、声優・古谷徹のインタビュー、そして幻の未公開カットも収録されており、まさに“永久保存版”と呼ぶにふさわしい構成となっている。
● 書籍関連──原作・資料集・アートワーク
原作漫画『巨人の星』(原作:梶原一騎、作画:川崎のぼる)は、講談社の『週刊少年マガジン』で連載された国民的ヒット作品である。アニメ放送と並行して刊行された単行本は累計2000万部を突破し、現在も復刻版が発売され続けている。 また、アニメ版の人気を受けて「アニメコミック」版も複数刊行された。これは放送映像のセル画をコマ割りし、セリフ付きで構成したもので、ファンが映像を再現できる貴重な媒体だった。 その後、2000年代にはアニメ設定資料集『TVアニメ 巨人の星 設定原画集』や『大リーグボールの秘密 全資料集成』などが出版され、キャラクターや作画スタッフの詳細な情報が明らかにされた。特に、作画監督・杉井ギサブローや音楽担当・渡辺岳夫の証言を収録したインタビュー本は、アニメ史研究の貴重な資料として評価が高い。 さらに、近年は『巨人の星 完全読本』(双葉社)や『昭和アニメ傑作選 巨人の星の時代』など、文化史的視点から作品を分析する書籍も登場しており、単なるファンアイテムを超えて「社会現象としての巨人の星」を再考する動きが広がっている。
● 音楽関連──名曲「ゆけゆけ飛雄馬」とその再録
アニメの顔とも言えるオープニング曲「ゆけゆけ飛雄馬」は、1968年の放送開始時にEP盤(ドーナツ盤)として発売された。作曲は渡辺岳夫、歌唱はアンサンブル・ボッカ。このシングルは当時のオリコンチャート上位にランクインし、子どもから大人まで幅広く支持された。 その後、アニメ放送終了後にも再販が続き、1970年代には『アニメ主題歌大全集』シリーズに収録。さらに1980年代にはCDとしてリマスター再録版が登場した。 また、副主題歌「友情の虹」や応援歌「青雲健児の歌」「紅洋の旗」もアルバム『巨人の星 音楽集』に収録され、2000年代にはサウンドトラック完全版CDとして復刻された。特にリマスター版では、当時のモノラル音源を最新技術でステレオ変換しており、音の厚みが格段に向上している。 さらに2020年には、放送50周年を記念して「巨人の星 音楽大全」が発売。声優・古谷徹による新録ナレーション入りバージョンや、オーケストラ編成での再演など、時代を超えた新アレンジが話題を呼んだ。音楽面から見ても、この作品は“昭和アニメ音楽の金字塔”として今なお輝きを放っている。
● ホビー・おもちゃ関連──昭和レトロの温もり
『巨人の星』は、昭和40年代の子ども文化を象徴するキャラクターグッズの宝庫でもある。放送当時、バンダイやタカラ(現:タカラトミー)から多くの玩具が発売された。 代表的なのは「星飛雄馬ピッチング人形」。ぜんまい式でボールを投げる仕組みで、子どもたちの間で大人気となった。また、「ちゃぶ台返しゲーム」など、一徹の象徴的シーンをモチーフにしたユニークな玩具も販売され、家庭内での笑いを誘った。 他にも、プロ野球ボードゲーム「巨人の星 大リーグボール勝負!」や、フィギュア型ジオラマ「飛雄馬の特訓セット」など、遊びながら作品世界を再現できる商品が続々と登場。近年ではこれらの復刻ミニチュア版がガチャガチャ商品として再発売され、“昭和レトロブーム”の中で再注目されている。 特に2020年代以降、フィギュアブランド「メディコム・トイ」や「海洋堂」が精巧な飛雄馬・一徹のPVCスタチューを発売。ちゃぶ台やグラウンドを再現した情景台座付きで、当時の雰囲気をそのまま再現している。
● ゲーム関連──多様なプラットフォームで蘇る“巨人魂”
ゲーム分野でも『巨人の星』は長年にわたり展開されている。 1980年代には、エポック社やタカラからボードゲーム「巨人の星 甲子園への道」やカードゲーム「飛雄馬の挑戦!」が発売。サイコロとカードを使って特訓や試合を進める形式で、子どもたちの間で長く遊ばれた。 1990年代にはファミリーコンピュータ用ソフト『巨人の星 熱闘編』が登場。原作の名シーンを再現したストーリーモードを搭載し、飛雄馬の魔球開発や花形との対決をプレイヤー自身が体験できる内容だった。 2000年代にはPlayStation2や携帯アプリ向けにもリメイク作品が登場し、3Dアニメーションによる再現映像やボイスドラマが追加されるなど、当時のファンだけでなく若い世代にも人気を博した。 スマートフォン時代の現在では、コナミの「プロ野球スピリッツA」やバンダイナムコの「スーパーロボット大戦DD」など、他作品とのコラボイベントに飛雄馬や一徹が登場することもある。50年以上経っても、彼らの熱血ぶりはゲームの世界でも健在である。
● 日用品・文房具・食玩──日常に溶け込む“星家”の面影
1970年代当時、『巨人の星』の人気は文房具や日用品にも波及した。 キャラクターが描かれたノート、鉛筆、下敷き、消しゴム、筆箱などが全国の文具店に並び、学校生活を彩った。特に人気だったのは「飛雄馬の決意ノート」シリーズで、表紙に「努力」「根性」「夢」といった言葉が書かれていた。 また、明子の優しさをイメージした「明子姉さんメモ帳」や、「ちゃぶ台メモスタンド」など、ユーモアのある商品も多数存在した。 食玩では「巨人の星チョコスナック」や「魔球ガム」など、カードやシール付きのお菓子が発売され、コレクション文化の先駆けとなった。近年ではロッテやバンダイから“昭和アニメ復刻シリーズ”として再販されるなど、懐かしの味として再評価されている。
● 総評──“巨人の星”は文化そのもの
『巨人の星』関連商品は、単なるグッズの域を超え、昭和の生活文化そのものを映し出している。テレビアニメが家庭の中心だった時代、この作品は玩具・文具・音楽・書籍といったあらゆる分野で子どもたちの日常に溶け込んでいた。 そして21世紀に入った今、リマスター版や復刻商品を通じて、当時の熱狂を再び味わうことができる。 飛雄馬や一徹たちは、もはや“キャラクター”ではなく“日本人の心象風景”の一部となった。映像、音楽、文具、玩具、そのどれを手に取っても、そこには「努力」「夢」「親子愛」という普遍のテーマが息づいている。 『巨人の星』の関連商品群は、時代の変化とともに形を変えながらも、今なお人々の心に“熱い昭和の魂”を灯し続けているのである。
[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場
● 映像関連商品──VHS・LD・DVDのコレクター市場
中古市場で最も取引が活発なのが、やはり『巨人の星』の映像関連商品である。特に1980年代から1990年代初期にかけて販売されたVHSやLD(レーザーディスク)は、現在も根強い人気を誇る。 VHS版は、アニメ放送当時を知る世代のコレクターを中心に需要が高く、ヤフオクやメルカリでは状態の良いものが1本あたり2,000~4,000円前後で取引されている。特に初期巻や最終巻は人気が高く、帯付き・ジャケット破損なしの美品では5,000円を超えることもある。 LD版はさらにコアなファンに支持されており、ブックレット付きのコンプリートBOXになると1万円以上の値がつくことも珍しくない。近年ではLDプレイヤー自体が希少になっているため、動作確認済みの完品セットはコレクターズアイテムとして高騰傾向にある。 2000年代に発売されたDVD-BOXもプレミア化している。特に初回生産限定の「巨人の星 全話収録DVD-BOX(解説書・特典映像付き)」は、発売当時3万円台だったものが、現在では状態次第で6万円を超える落札例も報告されている。 Blu-ray版についても、未開封品や特典付き限定版は定価を上回る取引が増加中。特に2020年発売の「50周年記念Blu-ray Complete BOX」は、在庫が少なくファンの間で“幻のBOX”と呼ばれている。
● 書籍・資料関連──原作初版と限定ムックの価値
原作漫画『巨人の星』の初版本は、昭和40年代の講談社コミックス版が最も高値で取引されている。帯付き・書き込みなし・日焼け少なめの美品セットでは10巻揃いで1万円前後、初版マークが残る完全初版セットは3万円を超えることもある。 さらに、当時の『週刊少年マガジン』連載号をそのまま保存しているファンもおり、梶原一騎の原作コメントや予告ページを含む状態で出品されると、1冊あたり1,500~2,500円程度で取引されている。 アニメ放送当時に発行された「TVアニメ特集号」や「サンデー増刊アニメ号」などの雑誌掲載記事も人気が高く、とくに表紙に飛雄馬や一徹が登場している号はコレクターズアイテムとして1冊3,000円前後で落札される傾向がある。 設定資料集やアートワーク集などの後年出版物も評価が高く、2005年刊行の『巨人の星 設定資料大全』(双葉社)は現在中古で5,000~8,000円前後、帯付き新品同様品では1万円近い値がつくこともある。 また、川崎のぼる直筆サイン入りの原画集やイベント限定販売のアーカイブブックは、入手困難なためオークションでは即決5万円台での取引も確認されている。
● 音楽関連──アナログ盤と復刻CDの再評価
アニメ主題歌「ゆけゆけ飛雄馬」のEPレコード(キングレコード版)は、昭和アニメソングの代表格として中古市場でも高値安定。保存状態の良いジャケット付き美品では3,000~5,000円、未開封品では1万円以上になることもある。 LP盤『巨人の星 音楽集』も人気で、渡辺岳夫作曲による劇伴曲がフル収録された初版盤は、帯付きで5,000~7,000円前後の価格帯。特にアンサンブル・ボッカのオリジナルコーラスを完全収録したバージョンは希少性が高く、コレクターの間で取引が活発だ。 CD再販盤も根強い人気を誇り、2000年代の「巨人の星 音楽大全」は中古価格で3,000~4,500円前後を維持している。さらに、50周年記念版として限定販売された“リマスターCDボックス”は、限定500セットの生産で既に完売。現在はメルカリなどで2万円台の値をつけるプレミア商品となっている。 一方で、非公式カバーアルバムやオーケストラ編曲盤も一部で取引されており、マニアの間では“聴き比べ文化”が形成されている。特に古谷徹本人がナレーションを務めた再録盤は人気が高く、即決で落札されることも多い。
● ホビー・おもちゃ──昭和レトログッズの再評価
『巨人の星』関連のおもちゃは、1970年代のブリキ玩具やソフビ人形、特訓器具を模したギミック玩具など、バラエティに富んでいる。 特に人気が高いのは、マルサン製「星飛雄馬特訓人形」(ぜんまい式ピッチングアクション付)で、箱付き・動作確認済みの完品なら3万円前後で取引される。未使用のデッドストック品は希少で、近年では8万円近くの値をつけた例もある。 また、「ちゃぶ台返しゲーム」や「大リーグボール発射セット」など、作品の名場面を再現したおもちゃもコレクターズアイテムとして人気。特に“ちゃぶ台返し”をギミック化したミニチュアトイは、現代のリバイバル商品としてガチャガチャでも復刻され、当時を懐かしむファン層に支持されている。 ぬいぐるみやキーホルダー、ミニフィギュアなどの小物類も価格が上昇傾向。未開封の状態であれば1,000~3,000円台の相場で、全種セットのコンプリート品は1万円を超える場合も多い。 昭和レトロブームの影響で、これらのアイテムは「懐かしいだけでなく、芸術的価値を持つ」と再評価され、オークションでの落札競争が活発になっている。
● ゲーム関連──ボードゲーム・レトロソフトのコレクター熱
『巨人の星』を題材としたボードゲームは、1970年代当時にいくつか発売された。タカラ製「巨人の星すごろくゲーム」は人気が高く、全パーツ揃い・外箱良好品は5,000~7,000円で取引される。サイコロやコマが欠けている場合でも、最低1,500円前後の需要がある。 エポック社が発売した「飛雄馬の特訓野球ゲーム」も珍しく、プラスチック製の球場フィールドと人形が付属する立体型仕様が特徴。完品は1万円以上、未使用品では2万円に達することもある。 電子ゲームでは、ファミコン版『巨人の星 熱闘編』(1986年発売)がコレクターズ人気を保っており、箱・説明書付きの完品は3,000~5,000円前後。 一方、MSX版やPC-8801向けの非公式移植ディスク、同人制作の「魔球シミュレーター」などは非常に希少で、マニア間では1枚1万円を超える取引も確認されている。 現在でも「昭和スポ根アニメのゲーム化作品」として一定の需要があり、レトロゲーム専門店では展示販売されるケースも増えている。
● 文房具・日用品・食玩──“昭和雑貨”の人気急上昇
キャラクター文具や食玩は、近年の昭和レトロブームの波に乗って再び注目を集めている。 1970年代に発売された「星飛雄馬ノート」「努力消しゴム」「根性下敷き」は、使用済みでも500~1,000円、未使用の新品状態では2,000円以上の価格で取引されている。 特に、当時サンスター文具から発売された「明子姉さんカレンダー」は希少で、オリジナルパッケージ付き美品だと1万円以上の値がつく。 食玩関連では、「巨人の星チョコスナック」「魔球ガム」などに封入されたキャラクターシールが人気。全20種コンプリートの状態なら5,000円前後で取引されることもある。 また、2020年代に入ってからは、これら昭和雑貨を再現した復刻グッズも登場。新品ながら“昭和デザイン”を再現したレプリカ商品が話題を呼び、ファンと新世代の橋渡しとなっている。
● 総評──半世紀を超えて価値を保ち続ける“国民的財産”
『巨人の星』の中古市場は、単なるコレクターズマーケットではなく、“昭和の文化遺産”を守る場へと進化している。 映像作品は技術的価値、音楽や玩具はノスタルジー的価値、文具や食玩はデザイン的価値──それぞれ異なる角度から再評価が進んでいる。 近年は、状態の良い初期商品や未開封グッズが減少しており、希少性が年々高まる一方で、「親子二代で集めている」というコレクターも増加。 オークションサイトだけでなく、実店舗型の昭和グッズ専門ショップでも展示・販売が行われ、文化資料として保存されるケースも増えている。 まさに『巨人の星』の関連商品は、“時代を超えて受け継がれる熱血の証”。それは、飛雄馬の投げた一球のように、今も人々の心の中をまっすぐに飛び続けている。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
【中古】巨人の星 1〜19巻セット KC
巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.2
巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.9




 評価 5
評価 5巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.18




 評価 5
評価 5巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.3




 評価 5
評価 5巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.17




 評価 5
評価 5巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.8
巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.4




 評価 5
評価 5巨人の星 COMPLETE DVD BOOK VOL.11




 評価 4
評価 4