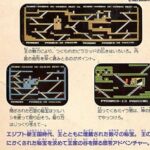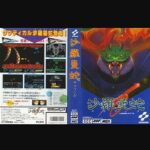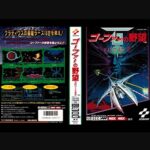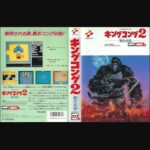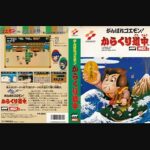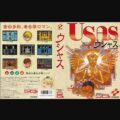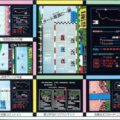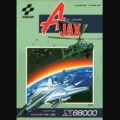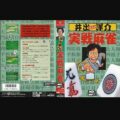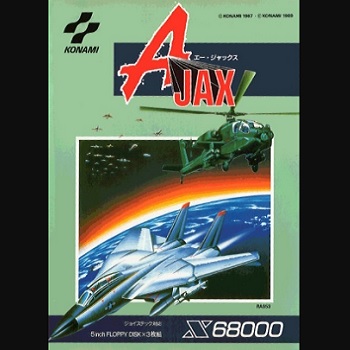【発売】:コナミ
【対応パソコン】:MSX
【発売日】:1988年8月27日
【ジャンル】:アクションパズルゲーム
■ 概要
● タイトルと基本データ
1988年8月27日、当時のパソコンユーザーにとって身近な存在だったMSX向けに、コナミから発売されたアクションパズルゲームが『王家の谷 エルギーザの封印』です。前作『王家の谷(King’s Valley)』の正式な続編にあたり、海外では「King’s Valley II」というタイトルで知られています。対応機種はMSXとMSX2の2種類で、どちらもROMカートリッジメディアで提供されました。ゲーム内容そのものは共通ながら、グラフィック表現や演出に差があり、当時としては珍しい“同内容・別パッケージ”としてMSX1版とMSX2版が並行して販売されたことも話題になりました。ジャンルとしては横から見下ろすようなサイドビュー画面で主人公を操作し、仕掛けだらけの遺跡を攻略していくアクションパズル。全60ステージというボリュームに加え、ユーザーが自分でマップを作成できるエディットモードまで搭載しており、一本のソフトの中に“遊ぶ”と“作る”の両方の楽しみが詰め込まれた贅沢な構成になっています。
● 宇宙へ広がった世界観と物語
前作は古代エジプトのピラミッドを舞台にした、比較的ストレートなトレジャーハントものでしたが、続編となる本作ではスケールが一気に拡大します。舞台は地球ではなく、レムールという架空の惑星に点在するピラミッド群。主人公は前作の主人公ビックの十三代目の子孫「ビック13世」と設定されており、時代的にもかなり未来、宇宙を股にかけて遺跡を調査する考古学的な冒険譚として再構築されています。物語の核になっているのは「地球のピラミッドは、もともとレムールからやってきた古代宇宙人のテクノロジーである」というSF的な解釈です。ピラミッドは単なる墳墓ではなく、死後に魂をレムールへ転送するための装置であり、副葬品はその制御システムの一部として機能していた――という設定が語られます。しかし、長い年月にわたる盗掘によってそのシステムが破綻し、暴走。レムール側にある制御中枢ピラミッドのエネルギーが暴発すれば、地球そのものが危機に陥る状況に。そこでビック13世がレムールのピラミッドに突入し、歴代の王族の魂が封じられた「ソウルストーン」で封印された60の部屋を踏破しながら、暴走を止めるスイッチへたどり着く――というのが大まかなストーリーです。古代文明と宇宙SFを組み合わせたこの世界観は、シンプルなドット絵のゲームながらプレイヤーの想像力を刺激し、ステージひとつひとつの仕掛けが、単なるパズルを超えて「宇宙的スケールの危機を食い止める行為」として感じられるような雰囲気作りに貢献しています。
● ゲームの目的と基本ルール
ゲームの基本的な目的は明快です。各ステージ内に散らばっているソウルストーンをすべて集め、封印が解かれた出口の扉から脱出すればクリアとなります。画面は横視点の固定画面またはスクロール画面で構成され、ビック13世は左右移動とハシゴの昇り降り、そしてジャンプとアイテム使用を駆使して進んでいきます。フィールドは複数のフロアに分かれ、ハシゴで上下へ移動しながら、敵の巡回ルートやブロックの配置を観察して最適なルートを組み立てるのがプレイの基本です。画面端は上下左右ともループしており、右端まで進むと左端に出てくるなど、ステージを“ぐるりと一周する”感覚で利用できる構造になっているのも特徴的です。床や壁は、掘削可能なブロックと絶対に壊せないブロックに分かれていて、特定のアイテムを使用することでのみブロックを崩せます。アイテムには敵を倒す武器系と、地形を掘り進むための道具系が存在し、どれをどの順番で使うかがそのままステージ攻略の鍵になります。さらに、本作の重要なルールとして「一度に持てるアイテムは1種類だけ」「アイテムや武器を持っているあいだはジャンプができない」という制限があります。このため、単なるアクションの腕前だけでなく、“ここでは武器を捨ててジャンプで避けるべきか、それともあえて武器を持ったまま敵を処理しつつ回り道をするべきか”といった判断が常に求められる、頭と手を同時に使うゲーム性になっています。
● ステージ構成とボリューム感
『エルギーザの封印』は、全体で6つのピラミッドを探索していく構成で、各ピラミッドには10の部屋が用意されています。つまり、合計60ステージという当時としては破格のボリュームが収録されていることになります。各ステージは、画面1枚で収まるコンパクトなものから、最大で6画面分にまたがる大規模なマップまでさまざまで、狭い空間でミリ単位の動きを要求される緊張感の高い面もあれば、広いフロアを行き来しながら複数のギミックを連鎖させるパズル性重視の面もあります。難易度カーブは比較的なだらかで、序盤は基本ルールやギミックを学ばせるチュートリアル的なステージが中心ですが、中盤以降になると「一度ミスするとやり直し確定」という仕掛けや、敵の動きと自分の操作タイミングをぴったり合わせなければ突破できない構造が増え、じっくり腰を据えて挑むタイプのゲームへと変貌していきます。BGMも2ステージごとに変化し、10面ごと、つまり次のピラミッドに移動する節目には簡単なデモシーンが挿入されます。これにより、単調になりがちなパズルアクションに“章仕立て”のメリハリが与えられており、「ここを抜ければ次のピラミッドだ」という分かりやすい目標意識がプレイヤーのモチベーションを支えます。また、残機はゼロスタートでステージをクリアするごとに1機増えていく方式で、各ステージクリア後にはパスワードも表示されるため、少しずつ攻略を進めていける親切設計になっています。
● 表現面の特徴とSCCサウンド
本作を語るうえで外せないのが、専用音源チップ「SCC(コナミ独自のカスタムサウンド)」の搭載です。カートリッジ内部にこのチップが組み込まれていることで、MSX本体の標準音源だけでは出せない厚みのある音色や、エキゾチックな旋律が鳴り響きます。エジプト風のスケールを取り入れたメロディや、神秘的な響きのベースラインは、惑星レムールの不思議な遺跡を探索しているという雰囲気を強く盛り上げてくれます。作曲陣にはコナミのサウンドチームが名を連ねており、一部の楽曲は後年ニンテンドーDS用ソフト『悪魔城ドラキュラ ギャラリー オブ ラビリンス』でアレンジされるなど、ゲーム音楽としても高い評価を受けています。グラフィック面では、MSX2版は多色表示と滑らかなスクロール・細かな背景描写によって、ピラミッド内部の階層構造や壁画の模様がより鮮やかに表現されています。一方のMSX1版はハードウェアの制約ゆえに敵キャラが単色スプライトになっていたり、アイテムに黒い縁取りが施されていたりしますが、その分ソウルストーンが強く輝きを放つ演出が印象的で、レトロPCらしい味わいを感じさせるビジュアルになっています。同じ内容を2つのハードで楽しめるため、グラフィックの印象がかなり変わる点も、本作がコレクターから注目される要因のひとつです。
● エディットモードとユーザー参加型企画
『エルギーザの封印』が単なるパッケージゲームにとどまらず、長く語り継がれる存在になった理由のひとつが「ステージエディットモード」の搭載です。ゲーム内の専用モードから、ブロックやハシゴ、敵の配置などを自由に編集でき、自分だけのオリジナルステージを作成できます。当時の取扱説明書には、方眼紙のような専用投稿用紙が付属しており、プレイヤーが自作ステージを描いてメーカーに送ると、各種パソコン誌と連動したエディットコンテストに応募できる仕組みになっていました。『MSXマガジン』『MSX・FAN』『Beep』『コンプティーク』といった雑誌名を冠した賞が用意され、入賞作品は「エディットコンテスト優秀作品集」という特製ROMカートリッジに収録されます。この特別版は金色のカートリッジで、ゲーム開始時には受賞者の名前入り表彰状が画面に表示されるという、まさに“一点もの”のプレミアム仕様でした。単に用意された60ステージを遊ぶだけでなく、プレイヤー自身がパズル職人として頭をひねり、その成果を全国のユーザーと共有できる――そんな当時としては先進的な“ユーザー参加型企画”が、本作の存在感を大きく押し上げています。
● 現在から見た『エルギーザの封印』の位置づけ
発売から長い年月が経った現在でも、『王家の谷 エルギーザの封印』はMSXを代表するアクションパズルの一本としてしばしば名前が挙がります。攻略の難しさとパズルの完成度から、当時すべてのステージを自力で解ききったプレイヤーは少数派だったとも言われ、インターネット上の個人ブログやレトロゲーム紹介サイトでは、今でも攻略記やプレイ日記が更新されています。また、中古市場では状態のよいMSX2版パッケージがかなりの高値で取引されることも珍しくなく、箱・説明書・ハガキ等が揃った完品は数万円台で落札される例も見られます。単に昔の名作というだけでなく、「MSXでしか遊べないコナミタイトル」「ユーザー参加型のエディットコンテストを実施した作品」「SCCサウンドが光るアクションパズル」といった複数の側面を併せ持つことで、ハードの歴史を語るうえでも外せない一本になっていると言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● アクションとパズルが一体になった独特のゲーム性
『王家の谷 エルギーザの封印』の一番の魅力は、“走って飛んで敵をかわす”というアクションゲームの楽しさと、“正しい手順を見つけていく”パズルゲームの面白さが、見事に一体化している点にあります。見た目だけならシンプルな横視点の固定画面(あるいはスクロール画面)ですが、ステージ内のソウルストーンをすべて回収し、脱出扉までたどり着くためには、敵の動きやギミックの発動タイミング、ブロックの配置などを総合的に考えなくてはなりません。しかも、ビック13世はアイテムを1種類しか持てず、何かを手にしている間はジャンプが封じられるという制約があります。このルールが非常に重要で、「ここでは敵を倒すために武器を持つべきか」「それともジャンプを使うために何も持たずに進むべきか」といった判断が常に問われる構造になっており、プレイヤーは一手先、二手先を読みながら行動することになります。ただ敵をやっつければいいわけでも、ただブロックを壊せばいいわけでもない、“総合的なパズルアクション”としての完成度が、本作ならではの大きな魅力です。
● シンプルなルールから生まれる奥深い戦略性
操作体系自体は、カーソルキーで移動とハシゴの昇り降り、スペースキーでジャンプまたはアイテム使用という、とても覚えやすいものです。しかし、そのシンプルさに反して、プレイの戦略性は非常に高く設計されています。たとえば、武器は何度でも投げられる一方で、ハンマーやスコップなどの掘削アイテムは使うと消えてしまいます。そのため「どのブロックを壊すか」「どこをあえて残して足場にするか」といった選択が、ステージ攻略の成否を左右します。また、画面端がループしている構造も戦略性を増す要素です。右端から出て左端へ移動できる特性を利用して敵を“巻く”のか、それともソウルストーンへの最短ルートとして活用するのか――場面ごとに最適解が変わり、何度も試行錯誤しているうちに、“パズルを解いた”という達成感が積み重なっていきます。計画的に行動しないとすぐに袋小路に陥ってしまう一方、冷静に順序立てて攻略すれば必ず答えが用意されている“理詰めのゲーム”であることが、多くのプレイヤーから支持されている理由と言えるでしょう。
● 豊富なステージとギミックが生む飽きさせない構成
全60面というステージ数は、当時のアクションパズルとしてはかなりの大ボリュームです。しかも単に数が多いだけでなく、各ステージごとに新しいギミックや組み合わせが登場するため、プレイヤーが飽きる間を与えません。二度踏むと消えてしまう床、一定回数通ると崩れるハシゴ、通過すると天井から壁が伸びてきてプレイヤーを押し潰そうとする増殖壁、押して足場にできる移動石、片方向からしか通れない扉など、特徴的な仕掛けが多数用意されています。これらのギミックは単独で出てくるだけでなく、複数が絡み合うように配置されているため、「ここで床を消してしまうと戻れなくなる」「増殖する壁を利用しないと上のフロアに届かない」といった“パズル的な読み”が重要になります。さらに、スロウマンやフロウマンといったミイラ男、ジャンプしながら追いかけてくるピョンシー、球体になって転がるロックロールなど、敵キャラクターも性質が異なっており、それぞれの行動パターンを把握したうえで利用したり避けたりする必要があります。このように、ステージ構成とギミックのバリエーションが豊富で、プレイヤーに常に新鮮な課題を投げかけてくる点が、本作のリプレイ性を大きく高めています。
● サウンドとビジュアルが生み出す“宇宙ピラミッド探検”の雰囲気
本作を印象づける重要な要素が、コナミ独自のSCC音源チップを搭載したサウンドです。標準のPSG音源だけのタイトルに比べて、音の厚みや響きが明らかに豊かで、エジプト風の旋律をベースにした神秘的なBGMが、レムールのピラミッド内部という舞台設定を強烈に演出しています。2面ごとに曲が切り替わるため、長時間遊んでいても耳が疲れにくく、10面ごとのピラミッド移動デモでは、通常プレイとは違う雰囲気の楽曲が流れて“一区切りついた”感覚を味わえます。こうした楽曲の一部は、後年の『悪魔城ドラキュラ』シリーズ作品でアレンジされて使われるなど、単体のゲーム音楽としても高く評価されています。グラフィック面では、MSX2版ならではの多色表現や滑らかなスクロールにより、壁画や柱、棺などの装飾が細かく描き込まれ、未来の宇宙遺跡という独特の世界観を表現。またMSX1版では敵が単色スプライトで描かれる反面、ソウルストーンの輝きがより際立つなど、ハードウェアごとの特徴を活かした演出がなされています。こうした視覚と聴覚の相乗効果により、単なるパズル画面を眺めているだけのはずなのに、どこか異世界に迷い込んだような没入感を得られるのが、本作の大きな魅力となっています。
● エディットモードがもたらした“創る楽しさ”
『エルギーザの封印』が他の同時代のアクションパズルと大きく異なるのは、プレイヤー自身がステージを作成できるエディットモードを備えていることです。ゲーム内のエディット画面から、ブロック・ハシゴ・敵・ギミックなどを自由に配置して、自分だけのオリジナルステージを構築でき、作成したマップはカセットテープやディスクに保存することも可能でした。しかも、コナミはこの機能を活かして全国規模のステージコンテストを開催し、雑誌『MSXマガジン』『MSX・FAN』『Beep』『コンプティーク』と連動して優秀作品を募集しました。入賞者には、応募作品を収録した特製ROMカートリッジ「エディットコンテスト優秀作品集」が金色カートリッジの形で贈呈され、ゲーム起動時には受賞者名入りの画面が表示されるという、当時としても非常にユニークな企画が行われています。こうしたユーザー参加型の仕掛けによって、『エルギーザの封印』は“用意されたステージを遊ぶゲーム”から“自分でパズルを設計するツール”へと広がり、友人同士でステージデータを交換したり、雑誌の読者投稿コーナーを通じて全国のプレイヤーとアイデアを競い合ったりと、コミュニティ全体が盛り上がる一因となりました。遊ぶ側と作る側の境界線をぼかし、ユーザー自身をゲームの“共同クリエイター”として巻き込んだ点も、本作の魅力として語り継がれています。
● 歯ごたえと達成感が両立した難易度バランス
本作は決して“気軽にサクサク遊べる”タイプのゲームではありません。後半ステージになると一手のミスが致命的になり、敵の動きやブロックの配置を再検討するために何度もやり直しを余儀なくされます。その一方で、理不尽な運要素でプレイヤーを追い詰めるのではなく、必ず論理的な解法が存在するように組み立てられているため、「あと一歩で解けそうなのに解けない」というジリジリとした悔しさと、「ようやく道筋が見えた!」というひらめきの快感が交互に押し寄せます。残機制も独特で、ゲーム開始時は残機0という緊張感の高いスタートながら、ステージを1つクリアするごとに1機ずつ増えていく仕様になっているため、少しずつ腕前と攻略知識が積み上がっていく実感を持ちやすくなっています。さらに、各ステージクリア時にパスワードが表示されるので、一気に60面を遊び通さなくても、少しずつ時間をかけて挑戦できる点も大きな安心材料です。この“高い難易度だけれど諦めずに付き合っていける”絶妙なバランスが、レトロゲーム好きの間で本作が“歯ごたえのある名作パズル”として語られる理由になっています。
● 現代の視点から見ても色あせない魅力
現在では、MSXそのものがレトロハードとして扱われる時代になりましたが、『王家の谷 エルギーザの封印』は、今なおエミュレーターや実機環境で繰り返し遊ばれているタイトルのひとつです。アクションとパズルの融合という骨太なゲームデザイン、SCC音源による印象的な音楽、ユーザー参加型のエディットコンテストなど、本作が持つ要素はむしろ現代のインディーゲームシーンとも通じる普遍性を備えています。レベルデザインの妙は、今の視点でプレイしても唸らされるほど緻密で、ステージクリアのたびに「この配置を思いついた開発者は相当なパズル好きに違いない」と感じさせてくれます。また、“MSXでしか遊べないコナミタイトル”としての希少性や、中古市場でのプレミア化も相まって、コレクターズアイテムとしての価値も高まっています。単なる懐かしさだけでなく、ゲームデザインの教科書のような側面を持つ作品として、これからも多くのレトロゲームファンや開発者志望のプレイヤーに遊ばれ続けるであろう点も、『エルギーザの封印』の大きな魅力と言えるでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
● まず押さえておきたい基本操作と視点の持ち方
『王家の谷 エルギーザの封印』の攻略を語るうえで、最初に意識したいのは「行き当たりばったりで動かない」という姿勢です。左右移動・ハシゴの昇降・ジャンプ・アイテム使用という操作だけを見ると、普通のアクションゲームのように感じてしまいますが、本作は一手のミスが後戻りできない状況を生み出しやすい構造になっています。特に、掘削アイテムでブロックを壊したあとや、消える床・消えるハシゴを使ったあとに戻るルートが塞がれてしまうことが多いため、動く前に「このブロックを壊したらどこへ行けて、逆にどこには行けなくなるのか」「ハシゴを何度使うと消えてしまうのか」を頭の中でイメージしておくことが重要です。同じように、画面端がループしている特性も、慣れないうちは混乱の原因になりますが、端から端へ抜けることで敵を撒いたり、ショートカットルートを作ったりできる便利な仕掛けでもあります。まずは1面や2面といった序盤ステージで、敵がいない状態やギミックが少ない場面を利用し、「端から出るとどこへ出るのか」「ハシゴを何度通ると消えるのか」「掘ったブロックはどの程度足場に影響するのか」など、ゲームのルールを身体で覚えてしまうと、後々の難所での判断スピードが格段に変わってきます。
● 序盤の進め方と基本テクニック
序盤のピラミッドは、プレイヤーに操作とルールを教える役割を持ったステージが中心です。この段階で意識したいのは、「敵の動きをよく観察する」「アイテムを取る前にルートを構想する」「ソウルストーンの配置からゴールまでの全体像を早い段階で把握する」という三点です。例えば、柩から現れるミイラ敵は、ハシゴを昇り降りするものや床を徘徊するものなどタイプが分かれていますが、どの敵も一定のパターンで動きます。柩の位置と動き出しの方向を確認し、「このハシゴに近づくとミイラが降りてくる」「この段にいるときだけ安全」といった“安全地帯”を把握しておくと、慌てずに行動できるようになります。また、ステージに入ったらいきなりアイテムに飛びつくのではなく、まずは画面を見渡してソウルストーンの総数と配置を確認し、どの順番で回収すれば遠回りせずに済むかをざっくりと考えておきましょう。掘削アイテムは一度使うと消えるため、序盤で無駄に床を掘ってしまうと終盤で足場が足りなくなり、やり直しを余儀なくされます。逆に、床を残しておけばジャンプで届く位置が増えたり、敵から逃げる際の逃げ道になったりと、“壊さないこと”が攻略になる場合も多いのが本作の面白いところです。
● 中盤以降で壁になるポイントと乗り越え方
2つ目・3つ目のピラミッドに差し掛かる頃から、ステージは一気に複雑さを増していきます。ここで特にプレイヤーを悩ませるのが「一度きりのチャンスを要求する仕掛け」と「時間差で動くギミックの組み合わせ」です。消える床や増殖する壁を使うステージでは、ギミックが発動してから安全地帯に逃げ込むまでの時間がシビアに調整されており、少しでもタイミングを誤ると挟まれて身動きが取れなくなり、残機を失うことになります。こうした場面では、いきなり本番ルートに挑戦するのではなく、あえてソウルストーンを無視して“ギミックの動作テスト”をするのがおすすめです。床が消えるまでの歩数、壁が降りてくる速度、敵がその付近に到達するまでの時間などを何度か試し、感覚を掴んでから本番ルートに挑むと成功率がぐっと高まります。また、中盤ステージでは「ゴール前でアイテムを持て余す」「途中で武器を取ってしまいジャンプできずに詰む」といった状況になりがちです。アイテムを拾う前に「このアイテムを使った後、別のアイテムが必要になる場面はないか」「ジャンプが必要なルートはないか」をチェックし、必要な場所に近づいたタイミングで初めてアイテムを取るようにすると、詰みパターンを大幅に減らせます。
● 終盤ステージ攻略の考え方とリセットの割り切り
後半のピラミッドに入ると、ステージの構造もギミックの組み合わせも容赦のないレベルになってきます。特に、「ソウルストーンの回収順を少し間違えただけで二度と復帰できない」「敵の位置を1マスずらしただけで安全ルートが消える」といった、非常にシビアな設計のステージが増えます。この段階では、クリアまでの手順を“パズルとして紙に書き出す”ような感覚でアプローチするのが有効です。画面を見ながら「まず右上のストーンを取り、その後に左下へ移動」「この扉を通る前にブロックを押しておく」といった手順を簡単にメモしておき、トライ&エラーを重ねるたびに修正していくことで、自分だけの攻略チャートができあがっていきます。また、終盤ステージでは“リセットの割り切り”も重要です。「この時点でブロックを壊してしまった」「この敵の位置ではもう抜けられない」と気づいたら、無理に足掻くよりもさっさとやり直したほうが時間の節約になります。残機はステージクリアごとに増えていくため、序盤〜中盤のステージである程度ストックを稼いでおき、終盤は“試行錯誤のための燃料”として惜しまず使う、という発想に切り替えると気持ちが楽になります。理不尽なランダム要素は少ないゲームなので、必ず“正しい手順”が存在すると信じて、少しずつパターンを詰めていくことが攻略の近道です。
● 敵キャラクター別の立ち回りと活用術
本作では、敵は単に避けるだけの存在ではなく、「足場」として利用できるものもいるのが特徴です。例えば、ロックロールは最初は煙状で出現し、一定時間経つと球体になって床を転がり始めます。転がっている最中は触れるとミスになりますが、停止中は上に乗って足場として利用可能です。武器を当てて任意の場所で止めることもできるため、高い足場へ届かないときに“動く台”として活用すると攻略の幅が大きく広がります。ミイラ系のスロウマンやフロウマンは動きにクセがあり、前者は床をゆっくり徘徊するだけ、後者はハシゴを高速で昇り降りします。スロウマンは移動速度が遅いぶん、通り道を読みやすく、武器がなければ“タイミング避け”、武器があれば“排除してから行動”と、状況に合わせた対応がしやすい敵です。一方、フロウマンはハシゴを利用して追ってくるため、ハシゴの上や下でうかつに立ち止まらないこと、画面端ループや一方通行扉を使って引き離すことが重要になります。ピョンシーはジャンプしながらプレイヤーを追うタイプの敵で、ジャンプ中は下をくぐり抜けられる特性があります。慣れてくると、わざと自分の方へ引き寄せてからジャンプを誘発し、その隙に背後をすり抜けるといった“小技”も使えるようになります。敵ごとの行動パターンと弱点を理解し、「倒すか」「避けるか」「利用するか」を瞬時に判断できるようになれば、ステージ攻略がぐっと楽になるでしょう。
● ギミック対策:消える床・増殖壁・回転扉など
厄介なギミックへの対処法を体系的に押さえておくと、初見のステージでも焦らず対応できるようになります。消える床は、一定回数踏むと消えて落下してしまう仕掛けで、回数は見た目で判断しづらいため、「重要ルートには極力使わない」「渡り切ったらもう戻らない前提でルートを構成する」という意識を持つと安全です。重要なソウルストーンの手前に消える床がある場合は、先に別ルートを探索し、戻る必要がない配置になっているか確認してから挑むと、無駄なミスを減らせます。増殖する壁は、特定地点を通過した瞬間に天井から壁が伸びてくるギミックで、タイミングを誤ると押し潰されますが、逆に上手く使えば敵の通り道を塞いだり、自分用の足場を作ったりと、攻略の武器にもなります。トリガー地点を見つけたら、まずは安全な場所で発動させて増殖する範囲を確認し、「どの高さで止めれば登れるのか」「敵を閉じ込められる位置はどこか」を見極めましょう。回転扉や一方通行扉は、通れる向きが限定されているため、むやみに出入りすると“閉じ込められる”原因になります。扉の形状と行き先を観察し、「この扉を通った後、戻るルートは存在するか」「別の扉との組み合わせでループ構造になっていないか」を確認してから進む癖をつけると、後戻りできない状況を避けやすくなります。
● 残機・パスワード管理と効率的な再挑戦法
攻略を進めるうえで、残機とパスワードの管理も非常に重要です。本作はステージクリアごとに残機が1つ増える仕様なので、どうしてもクリアが難しいステージに直面したときは、その手前の比較的簡単なステージを利用して残機を増やす、いわば“残機稼ぎ”のような発想も有効です。パスワードがステージごとに用意されているため、いったん覚えてしまえば、次にプレイするときにそこから再開が可能です。特に終盤の難関ステージは、数回のチャレンジで突破できるとは限らないため、ミスを重ねるたびに最初からやり直していては心が折れてしまいます。ノートやメモアプリなどにステージ番号とパスワード、簡単な状況メモ(「増殖壁ステージ」「ロックロール必須」など)を書き残しておくと、次回プレイ時にすぐ目的のステージから再開でき、効率よく試行錯誤を続けられます。また、「今日はこのステージだけ解く」といった小目標を決めて取り組むことで、長時間の連続プレイによる集中力の低下やイライラを軽減できるのも大きなポイントです。粘り強く取り組むゲームだからこそ、自分のモチベーション管理も“攻略法の一部”と考えておくと良いでしょう。
● 上級者向けのやり込み要素と自作ステージ攻略
全60面をクリアしたあとも、『エルギーザの封印』にはやり込み要素が残されています。代表的なのは「できるだけ少ない手数でクリアする」ことを目標にした自己ベスト更新プレイです。敵を倒さずにやり過ごすルートを探したり、掘削アイテムの使用数を減らしたり、ロックロールを巧みに利用して遠回りをショートカットしたりと、タイムアタックとは異なる“手順最適化パズル”として楽しむことができます。また、エディットモードで作った自作ステージを自分で攻略する、友人同士で交換して解き合うといった遊び方も、上級者にとっては大きな魅力です。自分でステージを作ってみると、開発側の気持ちがよく分かるようになり、「こんな配置ではプレイヤーが詰んでしまう」「このギミックを組み合わせると理不尽に感じる」といったバランスの取り方を肌で理解できます。その経験を踏まえて改めて公式ステージをプレイすると、「ここにハシゴを1本置くだけで難易度が劇的に変わるのか」「このブロックの位置はプレイヤーの心理を計算している」といったレベルデザインの妙に気づき、ゲームの見え方が一段深まるはずです。作る側と解く側の両方を経験することで、『王家の谷 エルギーザの封印』という作品の奥深さを、より立体的に味わえるでしょう。
■■■■ 感想や評判
● 初見プレイヤーが受ける全体的な印象
『王家の谷 エルギーザの封印』を初めて触れた人がまず感じるのは、「説明されれば単純そうなのに、実際にやってみると驚くほど歯ごたえがある」というギャップです。操作自体は方向キーとジャンプ、アイテム使用だけというシンプルなものですが、ソウルストーンをすべて回収したうえで出口にたどり着くという条件が、ステージの構造と絡み合うことで強烈なパズル性を生んでいます。最初は「ミイラを避けて石を回収するだけのアクションゲームかな」と軽い気持ちで挑んだプレイヤーが、数面進むころには「このブロックを壊したらもう戻れないのでは」「ここで敵を倒してしまうと足場がなくなるのでは」と一手一手を慎重に考えるようになり、いつの間にかじっくり腰を据えて遊ぶ“本格パズル”として向き合っている、そんな印象に変わっていきます。エジプト風のビジュアルやSCC音源による印象的な音楽も相まって、画面は小さくとも重厚な世界に迷い込んだような感覚を味わえることが、多くのプレイヤーの心に残るポイントになっています。
● パズル好きから見た評価と満足度
特に評価が高いのは、「アクション要素を持ちながらも、解法が明確に存在するパズルとして設計されている」という点です。敵の動きやギミックの発動条件、アイテムの制限を丁寧に観察すれば、運任せではなく必ず筋道の通った解き方が見えてくるため、“理不尽に感じない難しさ”としてパズル好きから好意的に受け止められています。一見すると逃げ場がないように見える場面でも、画面端のループやロックロールの特性、一方通行扉の配置などに着目すると、意外な抜け道やショートカットが隠されており、「あ、ここを足場として使えということか」「この順番で石を取ればいいのか」と気づいた瞬間の快感は格別です。ステージ数が多いだけでなく、各面の構造に“余計な飾り”が少なく、本当に必要な要素だけでパズルが組み立てられているため、解き進めるごとにレベルデザインの妙に感心させられるプレイヤーも多いでしょう。難易度は決して低くありませんが、そのぶん一面クリアごとの達成感が大きく、パズルを解くこと自体が好きな人にとっては、長く付き合える一本だと評価されています。
● アクションゲームとしての感触と意見
一方で、純粋なアクションゲームとして見た場合の感想はやや分かれます。ビック13世の移動やジャンプの挙動は素直で、敵の当たり判定も理不尽さは少ないため、操作感そのものは好意的に受け入れられることが多いです。ただし、“何かを持っている間はジャンプできない”“アイテムは1種類しか持てない”といったルールが、反射神経で切り抜けるアクションというより、「動く前に考えるアクション」へとプレイヤーを誘導します。そのため、瞬時の判断と派手な動きを好むタイプのアクションファンからは、「もう少しスピード感が欲しい」「敵をなぎ倒して進む爽快感は薄い」と感じられることもあります。とはいえ、敵のパターンを読み切ってギリギリのタイミングでハシゴを駆け上がったり、ロックロールを足場に華麗に飛び移ったりと、“成功したときの気持ちよさ”はしっかり用意されており、頭と手を同時に使う楽しさが好きなプレイヤーには高く評価されています。「アクションの爽快感」を求めるか、「アクションを含んだパズルの緊張感」を求めるかで、印象が大きく変わる作品と言えるでしょう。
● 音楽・グラフィックへの賛辞
感想の中でよく挙がるのが、SCC音源ならではの音楽の充実ぶりです。エジプト風の民族的なフレーズと、どこか未来的なコード進行が組み合わさったBGMは、単なる“遺跡探検”の枠を超えて、「宇宙のどこかにある古代文明の遺産を巡っている」という本作独特の世界観を際立たせています。2面ごとに曲調が変わる構成も好評で、「この曲が流れるステージは難しいけれど好き」というように、BGMとステージの思い出がセットで語られることも少なくありません。グラフィックについても、MSX2版の多色表示による柱や壁画の描き込み、棺の細かなデザインなどが“コナミらしい仕事の細かさ”として称えられています。一方のMSX1版も、制約の中で工夫された単色スプライトや、ソウルストーンが強く光る演出などが独特の味わいを生み出しており、「どちらの版にも良さがある」「敢えてMSX1版の無骨な雰囲気が好き」という声もあります。視覚・聴覚の両面で、当時のMSXソフトとしてはトップクラスの完成度を誇ることから、技術面に興味を持つユーザーや、ゲーム音楽ファンからの評価も高い作品です。
● 難易度への賛否と“理不尽さ”のライン
本作の評判を語るうえで避けて通れないのが、その難易度に対する賛否です。「歯ごたえがあってやりがいがある」とポジティブに受け止めるプレイヤーがいる一方で、「中盤以降が難しすぎて挫折した」「攻略情報なしでは最後まで行けない」と感じるプレイヤーも少なくありません。とくに、ソウルストーンの取得順序やギミックの発動タイミングがシビアな終盤ステージでは、わずかな操作の遅れや順番の間違いで詰んでしまうケースが多く、「あと少しだったのに」「また最初からやり直し」という悔しさが積み重なります。ただし、多くのプレイヤーが共通して口にするのは、「難しいけれど、理不尽な運ゲーではない」という感覚です。敵の動きは一定で、ギミックも決まった条件で発動するため、きちんと観察と検証を重ねれば、必ず仕組みを理解してクリアへの筋道を立てることができます。この“高難度だが必ず解ける”設計思想のおかげで、時間をかけて攻略した人ほど強い達成感と愛着を抱きやすく、「とても人には勧めにくいけれど、自分にとっては忘れられない一本」といった、ややツンデレ気味な評価をされることも多いタイトルです。
● エディットモードとコンテストが残した印象
エディットモードに対する感想は、当時のMSXユーザーの記憶の中でも特に印象深いものになっています。単にステージを遊ぶだけでなく、自分でギミックや敵配置を考え、オリジナルの難問ステージを組み上げていく作業は、小さなゲームデザイナーになったような気分を味わえるものでした。自作ステージを友人に解いてもらい、「ここは難しすぎる」「この仕掛けは面白い」と感想をもらうコミュニケーションも、当時のPCゲームならではの楽しみ方です。また、雑誌と連動したエディットコンテストの存在もプレイヤーの記憶に強く残っています。受賞作品が専用のROMカートリッジとしてまとめられたことや、ゲーム起動時に名前入りの画面が表示されたことなど、“自分の作ったステージが公式に認められる”体験は、多くのMSXユーザーにとって特別な出来事でした。「この作品がきっかけで、ゲーム作りに興味を持った」「将来、ゲームクリエイターを目指そうと思った」という人もいたであろうことが想像できるほど、エディットモードは本作の評価を押し上げる重要な要素になっています。
● 現代のレトロゲームファンから見た再評価
年月を経て振り返ったとき、『王家の谷 エルギーザの封印』は、単なる懐かしの一本という枠を超えて、「今遊んでも通用する堅牢なゲームデザインの見本」として再評価されつつあります。エミュレーター環境や動画配信を通じて初めてこの作品に触れた若い世代のレトロゲームファンからも、「古いゲームなのに手ごたえがあり、理詰めで解く楽しさがある」「BGMや雰囲気が今でも魅力的」といった感想が聞かれます。もちろん、インターフェースやレスポンス、ヒントの少なさなど、現代のゲームに慣れたプレイヤーからすると不親切に感じる部分も存在しますが、それを補って余りある“パズルとしての完成度”と“世界観の一貫性”が評価のベースになっています。また、MSX1版とMSX2版の両方が存在することから、ハードウェアの違いによる表現の差異を比較して楽しむ人も多く、「どちらの版で遊ぶか」そのものがレトロゲームファンの語り合いのテーマにもなっています。長い年月の中で、単に“昔のコナミの名作”というだけでなく、「プレイヤーと共に遊び方・遊ばれ方が育ってきた作品」として独自の位置を占めていると言えるでしょう。
● 総評:人を選ぶが刺さる人には刺さりまくる一本
総じて、『王家の谷 エルギーザの封印』の感想や評判をまとめるなら、「間違いなく人を選ぶが、ハマる人には深く突き刺さるゲーム」です。軽い気持ちで“アクション寄りの作品”を期待すると、そのシビアな難易度やパズル性に圧倒されてしまうかもしれません。しかし、じっくり考えながら一手一手を積み上げていくタイプのゲームが好きな人にとっては、これ以上ないほどのやりごたえを持つ一本です。美しいサウンドと雰囲気のあるグラフィック、60面に及ぶ緻密なステージ構成、ユーザー参加型のエディットコンテストという、複数の魅力が一つにまとまっているため、当時遊んだプレイヤーにとっては“MSX時代を象徴する思い出のソフト”として記憶されていることが多い作品です。今から遊ぶ場合でも、じっくり時間をかける覚悟さえあれば、昔と変わらない“ひらめきと達成感の連続”を体験できるでしょう。
■■■■ 良かったところ
● 一見シンプルなのに“考えさせる”ゲームデザイン
『王家の谷 エルギーザの封印』の長所として真っ先に挙げたくなるのが、「見た目はシンプルなのに中身はものすごく練られている」ゲームデザインです。画面に表示される要素は、主人公・敵・ブロック・ハシゴ・扉・ソウルストーンといった、ごく限られたパーツに絞られていますが、その組み合わせ方によって、まるで性格の違う60のステージが生まれています。特別に凝った演出や派手な仕掛けがなくても、アイテムを拾う順番やブロックを壊すタイミングを少し変えるだけで、結果が大きく変わるように作られているため、「たったこれだけのマップなのに、こんなに頭を使うのか」と感心させられます。遊び方を覚えてしまえば、あとはプレイヤー自身の“考える力”がストレートに試されるので、クリアできたときの満足感が非常に高く、「自分の手で謎を解いた」という実感を強く味わえるのが大きな魅力です。
● アクションとパズルのバランスが絶妙
良かった点として多くの人が口を揃えるのが、アクション性とパズル性のバランスが見事に噛み合っていることです。敵の動きを見てタイミングよくジャンプしたり、ハシゴを駆け上ったりする瞬間は、アクションゲームらしい緊張感があります。一方で、アイテムをどこで拾ってどこで使うか、どのブロックを壊し、どれを足場として残すか、といった判断は完全にパズルの世界です。どちらか一方に偏ることなく、ステージによって「操作テクニックが重要な面」「手順を考え抜く面」がうまく配分されているため、飽きずに遊び続けられます。たとえば、敵の数が少なくギミック重視の面ではじっくりルートを考えることに集中でき、逆に敵が多く配置された面ではパズルとしては単純でも、身軽なアクション捌きが要求される、といったメリハリがはっきりしているのが気持ちよいところです。「ただ難しいパズル」でも「ただ忙しいアクション」でもない、“頭と指の両方を使う面白さ”に、作品としての独自性と完成度の高さがよく表れています。
● 世界観とサウンドが生む“謎の遺跡を探検している”感覚
本作をプレイしていると、ステージの構造や難易度とは別に、じわじわと効いてくるのが世界観とサウンドの力です。舞台は古代エジプト風のピラミッドでありながら、実際には惑星レムールという宇宙のどこかにある世界という設定になっており、古代文明とSFが入り交じった雰囲気があります。遺跡を思わせるブロックや棺、壁画のような模様が、MSXのグラフィックで丁寧に表現されていて、シンプルなドット絵ながら不思議と“空気感”が伝わってきます。そこに重なるのが、SCC音源ならではの深みのあるBGMです。どこか民族音楽を思わせる旋律と、宇宙的な広がりを感じさせるコード進行が組み合わさり、ピラミッド内部の静けさや緊迫感、未知のテクノロジーに触れているような神秘さを演出してくれます。2面ごとに曲が変わることで、ピラミッドの奥へ進むにつれ空気が少しずつ変化していくような感覚も味わえ、「ただのパズル画面」がいつの間にか一本の長い冒険譚の一場面のように感じられるのが実に見事です。ゲーム性だけでなく、こうした雰囲気作りの巧さも、本作の“良かったところ”として語り継がれている大きな理由です。
● ステージエディットとコンテストの存在感
他の多くの同時代タイトルと比べて際立っている長所が、ステージエディット機能と、それを活かしたコンテスト企画です。プレイヤー自身がブロックや敵を配置し、オリジナルのパズルステージを作成できる機能は、当時の家庭用ゲームとしてはかなり先進的なものでした。単に難しいステージを作るだけでなく、「どうすればプレイヤーが“ひらめき”を感じられるか」「どこまで追い詰めれば理不尽にならずに済むか」など、作り手の視点で試行錯誤する楽しさを味わえます。そして、その成果を雑誌のコンテストに応募し、優秀作が特製ROMとしてまとめられたという事実は、多くのMSXユーザーにとって忘れ難い体験になっています。自分の考えたステージが公式に認められ、名前入りの画面で祝福してもらえる――そんな体験は、「ゲームは遊ぶだけではなく、一緒に作り上げるもの」という価値観をプレイヤーにもたらしました。この“ユーザー参加型”の仕組みは、今でこそマリオメーカーのような作品で一般的になりましたが、当時としては非常に先鋭的であり、本作の大きな功績として高く評価されているポイントです。
● 難しいのに“納得できる”難易度設計
高難度のゲームは往々にして賛否を生みますが、『エルギーザの封印』が多くのプレイヤーから好意的に受け止められているのは、その難しさが“理不尽さ”ではなく“論理性”に基づいているからです。敵の動きは一定で、ギミックの発動条件も明確であり、パターンを理解しさえすれば、必要な手順は必ず導き出せるように作られています。「あと一歩で解けそう」と感じながら何度も挑戦し、試行錯誤の末に攻略ルートを見つけたときの達成感は非常に大きく、「時間をかけたぶんだけ報われる」構造がしっかりと成立しています。さらに、ステージクリアごとに残機が増えていくシステムや、各面に用意されたパスワードのおかげで、長期的にじっくり挑めるという配慮も行き届いています。“短時間で手軽に遊ぶ”スタイルには向かないものの、“腰を据えて一本のゲームに取り組む”楽しさを味わわせてくれる作品であり、「難しいけれど不公平ではない」と感じられる難易度バランスは、本作の美点として挙げられるでしょう。
● MSX1版とMSX2版、それぞれに異なる魅力
同名タイトルでMSX1版とMSX2版が別パッケージとして存在する点も、この作品ならではの良いところです。同じゲーム内容でありながら、ハードウェアの違いにより、プレイ感覚や見た目の印象が細かく異なります。MSX2版ではカラー数の多さやスクロール処理の向上によって、背景やキャラクターがより華やかに描かれ、SCC音源と相まって“完成された一本のパッケージソフト”という印象が強くなっています。一方MSX1版では、敵が単色スプライトで表現されたり、アイテムが黒く縁取られていたりと、制約の中で工夫を凝らしたドット絵が味わい深く、ソウルストーンの輝きを強く感じられる演出など、こちらにしかない見どころもあります。どちらの版を遊ぶかによって、“同じゲームなのに違う体験”を味わえるのは、レトロPC時代ならではの贅沢なポイントです。コレクターにとっては両方集める楽しみがありますし、ゲームファンにとっては「同じデザインを違うハードで実現すると、こういう違いが出るのか」という学びに繋がる部分でもあり、本作の価値を一段と高めています。
● 長く語り継がれる“MSXらしさ”の凝縮
最後に挙げたい良かった点は、『王家の谷 エルギーザの封印』が“MSXらしさ”を凝縮した一本として、今なお語り継がれていることです。限られたハードウェアの制約の中で、アイデアと工夫で勝負する――そんな時代の空気が、全60面のステージとエディット機能の隅々にまで詰まっています。アクションとパズルを組み合わせた骨太なゲーム性、SCC音源を駆使した印象的なサウンド、ユーザーが参加できるコンテスト企画、MSX1・MSX2両機種に渡る展開など、当時のコナミが持っていた技術力と企画力が、一本のカートリッジにぎゅっと詰め込まれているのです。結果として、本作は単なる“懐かしいゲーム”を超えて、MSXというプラットフォームそのものを象徴する存在のひとつになりました。良かったところを総合すれば、「遊んで楽しい」「考えて楽しい」「作って楽しい」、そして「振り返っても楽しい」――そんな四重の魅力を備えた作品であると言えるでしょう。
■■■■ 悪かったところ
● 高難度ゆえに途中で挫折しやすい
『王家の谷 エルギーザの封印』の短所としてまず挙げられるのは、そのストイックなまでの高難度です。パズルとしてきわめてよく作り込まれている反面、ひとつのステージを突破するまでに何十回とやり直すことも珍しくなく、遊ぶ人をかなり選ぶ作りになっています。特に中盤以降は、ソウルストーンの取得順を少しでも間違えると復帰不可能になったり、ギミックのタイミングをわずかに外すだけで詰み状態に陥ったりする場面が増え、慎重に考えて進めているつもりでも「最後で詰んでやり直し」ということが頻繁に起こります。昨今のゲームのように段階的なヒント機能や難易度選択が用意されているわけではないため、あるステージで完全に行き詰まってしまうと、そこで気持ちが折れてしまうプレイヤーも少なくありません。「必ず筋道の通った解法がある」と分かっていても、そこに到達するまでの試行錯誤の量が多く、短時間での達成感を求める人にはかなり厳しい作りになっていると言えるでしょう。
● ヒントや誘導がほとんどない不親切さ
もうひとつの欠点として、ゲーム内でのヒントやプレイヤーへの誘導がほとんど用意されていない点が挙げられます。現在の感覚からすると、たとえば序盤のステージで代表的なギミックの使い方を段階的に学ばせるチュートリアルや、詰まりやすい場面で軽いアドバイスが表示されるといった仕組みが期待されますが、本作にはそうした親切設計がほぼ存在しません。説明書には基本的なルールやアイテムの使い方が書かれているものの、各ステージ固有の“考え方”まではフォローされておらず、プレイ中は画面に表示された情報だけで解法を導き出さなければなりません。そのため、たとえば「消える床をあえて残しておく」「敵を足場として利用する」といった応用テクニックに気づかないまま、何度も同じパターンで失敗を繰り返してしまうケースが多くなります。プレイヤーに自由な発想を促すという意味では長所とも言えますが、せめて数ステージに一度くらい、「このタイプの仕掛けはこういう使い方もできる」というサンプルを示してくれていれば、挫折する人はもう少し減ったのではないかと感じられる不親切さがあります。
● インターフェースや操作感が現代の基準から見ると厳しい
MSXというプラットフォーム自体の限界もありますが、インターフェース面の古さは避けがたい短所として感じられます。ジャンプとアイテム使用が同じキーに割り当てられている仕様は、ルールを理解すれば納得できるものの、初めて遊ぶ人にとっては誤操作の原因にもなりがちです。アイテムを持っているときはジャンプができないため、「うっかり武器を拾ったせいで必要なジャンプができなくなり、やり直しになった」という状況も頻繁に起こります。また、階段やハシゴの昇り降りも、キャラクターの立ち位置が1マスずれると反応しないことがあり、敵に追われている最中にハシゴに掴まり損ねてミスになると、操作性への不満につながりやすくなります。こうした細かい“引っかかり”は、当時のアクションゲームとしては許容範囲かもしれませんが、現代のプレイヤーが触れると「せめて操作ボタンを分けてほしかった」「もう少し判定を甘くしてほしい」と感じる部分であり、ゲームそのものの難易度とは別のところでストレスを生む要因になっています。
● プレイ時間が延びがちで気軽に遊びにくい
全60面というボリュームは長所である一方で、悪い意味で“腰が重い”ゲームになっている側面もあります。一つひとつのステージが歯ごたえのあるパズルとして作られているため、サクサクと次々クリアしていくことは難しく、1面に1時間以上かけてようやく突破、ということも珍しくありません。そのため、「ちょっとした空き時間に数分だけ遊ぶ」といったライトなプレイスタイルとは相性が悪く、「よし、今日はこのゲームに集中するぞ」という覚悟とまとまった時間が必要になります。パスワード機能があるとはいえ、頭の中から完全にステージ構造が抜けた状態で数日後に再開すると、「そもそもどこまで理解していたのか」を思い出すところからやり直しになることも多く、プレイリズムを維持しづらいのも難点です。結果として、忙しい社会人や、他にも遊びたいゲームがたくさんあるプレイヤーにとっては、「興味はあるけれど、腰を据えて取り組む余裕がなくて手を出しづらい」という存在になってしまいがちです。楽しいゲームであることは間違いないのに、その楽しさにたどり着くまでに必要な時間的コストが高い、というのは否めない弱点でしょう。
● エディットモードの敷居の高さと保存環境の制約
本作の大きな特徴であるステージエディットモードも、視点を変えると弱点を抱えています。マップ作成が可能と言っても、MSXの画面上でカーソルを動かしながらブロックや敵を一つひとつ配置していく作業はなかなか骨が折れ、慣れていないと非常に時間がかかります。しかも作成したステージを長期的に保存するには、別途カセットテープやディスクドライブなどの外部記憶装置が必要で、すべてのユーザーがその環境を持っていたわけではありません。結果として、「エディットモードがあるのは知っているけれど、実際に使ったことはほとんどない」「コンテスト用紙にマップを描いただけで、ゲーム内で詳細なテストはできなかった」といったプレイヤーも多かったと考えられます。コンテストというアイデア自体は素晴らしいものの、環境面や操作性のハードルが高く、機能を十分に活用できたユーザーが限られてしまった点は、もったいないところと言えるでしょう。現代のツールのように、マウス操作やGUIで直感的にステージを組み立てられる環境であれば、さらに多くの名ステージが生まれていたかもしれません。
● 情報入手が難しく、攻略手段が限られていた
発売当時を振り返ると、このゲームのもうひとつの弱点は“攻略情報へのアクセスのしづらさ”でした。インターネットがなかった時代、攻略の頼みの綱はパソコン雑誌の特集記事や読者投稿コーナー、もしくは友人との情報交換くらいであり、運よくその号を手に入れられなければ、特定のステージの解法に永遠にたどり着けない可能性もありました。ゲーム側にもヒント機能がないため、一人で黙々と挑戦し続けるしかなく、「どうしても解けないステージが一つだけ残ってしまった」「最後の数面だけは結局クリアできなかった」というプレイヤーが多く出てしまったのは、この作品の残念な側面です。現在はエミュレーター環境や動画配信、攻略サイトなどのおかげで情報へのアクセスが容易になりましたが、当時の状況を考えると、「もう少し公式側がフォローしてくれてもよかったのでは」と思わされる部分があります。ゲーム自体の難しさに加えて、周辺環境がその難しさをさらに増幅してしまった、という意味で“悪かったところ”に数えられる要素でしょう。
● 入手性や対応機種によるハードルの高さ
最後に、ゲーム本体そのものの話ではありませんが、入手性や対応機種という観点から見た弱点もあります。本作はMSXおよびMSX2専用ソフトであり、他機種への移植は行われませんでした。そのため、後年になってから遊びたくなった場合、実機とソフトを揃えるハードルが高く、現代のプレイヤーにとっては“気軽に手を出せない名作”になってしまっています。中古市場でも人気タイトルのひとつとして扱われており、状態の良いパッケージは高価になりがちで、新規にコレクションに加えようとするとかなりの出費を覚悟しなければなりません。エミュレーターなどの手段もありますが、そこに依存せざるを得ない状況そのものが、この作品との出会いを遠ざけていると言えるでしょう。プラットフォームの寿命とともに遊ぶ機会が減ってしまったという意味では、名作であるがゆえに惜しいポイントであり、“もっと多くの人に触れてほしいのに触れにくい”というもどかしさも、このゲームに対する評価の一部となっています。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
● 主人公・ビック13世の“地味だけど頼れるヒーロー感”
『王家の谷 エルギーザの封印』で最もプレイヤーにとって身近な存在が、主人公のビック13世です。派手な必殺技や派手な演出を持っているわけではなく、青い探検服に身を包んだ、どこにでもいそうな“真面目な青年”といった雰囲気のキャラクターですが、プレイを重ねれば重ねるほど、その素朴さが魅力として感じられてきます。武器もナイフやブーメランといったシンプルなものが中心で、体格も特別に屈強というわけではありません。それでも、レムールの過酷なピラミッド群にたった一人で潜り込み、暴走する装置を止めるために命がけで挑む姿には、言葉では語られない覚悟がにじんでいます。特に、何度もミスを重ねてステージをやり直しているうちに、「また落ちてしまった、ごめん」「今度こそ助けてみせる」と、プレイヤー側が勝手に感情移入してしまうタイプの主人公であり、“派手さよりも実直さ”を好むプレイヤーからはかなりの支持を集めています。前作の主人公ビックの十三代目という設定も、家系に受け継がれてきた使命感や、代々続く探検家としての誇りを想像させ、歴史の長さを感じさせるポイントになっています。
● ミイラたちの“怖くてかわいい”敵キャラクター
このゲームの敵キャラの中でも印象的なのが、スロウマンやフロウマンといったミイラ系のキャラクターたちです。どちらも棺から登場する点は共通していますが、スロウマンは床をゆっくり歩いていくだけ、フロウマンはハシゴを高速で昇り降りするなど、行動パターンがはっきり分かれています。デザインはコミカル寄りで、ホラー映画のような不気味さは薄く、どこか憎めない姿をしていますが、プレイ中は油断しているとあっさりやられてしまう厄介な相手です。特にフロウマンは、プレイヤーが油断してハシゴのそばでモタモタしていると、ものすごい勢いで駆け上がってきて進路を塞いでくるため、「見た目はかわいいのに性格は容赦ない」というギャップが印象に残ります。プレイヤーによっては、あまりにも何度も邪魔をされるせいで“心のライバル”のような感情を抱くこともあり、「あのステージのフロウマンさえいなければ……」と、特定のミイラに対して妙な愛着を覚えてしまうことすらあります。怖さとユーモアが絶妙なバランスで同居している点が、ミイラたちが人気の敵キャラとして語られる理由でしょう。
● ロックロールという“頼れる相棒”
多くのプレイヤーから特に人気の高いキャラクターが、球体状の敵ロックロールです。最初は煙状でふわりと現れ、しばらく辺りを見回したあと、丸くなって床をコロコロと転がり始めるという独特の登場パターンを持っています。転がっているときに触れるとミスになってしまう危険な存在ですが、一度止まればその上に乗ることができ、足場として利用できるという性質が、他の敵とは一線を画しています。プレイヤーは、武器を当てて任意の位置でロックロールを止め、届かなかった段差に到達するための“移動する足場”として活用していきます。敵でありながら攻略の鍵を握る相棒でもあるという、この二面性が非常にユニークで、「ロックロールをうまく使えるようになったら、このゲームが一段と楽しくなった」と感じるプレイヤーも少なくありません。見た目もコロンとした丸いシルエットで、ドット絵ながらどこか愛嬌があり、ステージによっては“ロックロールをいかにうまく使うか”がテーマになっている場面もあるため、「今日の主役はビック13世よりロックロールかもしれない」と思わせてくれる魅力的な存在です。
● ピョンシーのコミカルな追跡と愛されキャラぶり
煙となって現れ、ひょいひょいとジャンプしながらプレイヤーを追ってくるピョンシーも、忘れがたい敵キャラクターの一人です。ジャンプ中は下をくぐり抜けられるという特性を持っており、慣れてくると、その動きを逆手に取って“誘導してかわす”楽しさを味わえます。プレイヤーを執拗に追いかけてくる行動パターンは脅威ではあるのですが、ジャンプのモーションがどこかコミカルで、緊張感の中にもクスッと笑える瞬間があるのが魅力。特に、うまくタイミングを合わせてピョンシーの下をすり抜けたときには、追いかけてくる様子が妙にかわいく見えてしまい、「さっきまであれほど憎らしかったのに、なんだかペットみたいに思えてきた」という感情の変化を味わえることもあります。ゲーム全体がシリアスな設定を持っている中で、こうしたコミカルな動きをする敵がいることで、画面にほどよいユーモアが生まれ、プレイヤーの心に余裕を残してくれるのがピョンシーの大きな役割と言えるでしょう。
● 無機物でありながら存在感のある“ソウルストーン”
キャラクターという括りで見ると、プレイヤーから意外と愛着を持たれているのが、各ステージに散らばっているソウルストーンです。本来は“歴代王族の魂が宿った石”という設定であり、人格や台詞を持つわけではありませんが、全ステージを通して常にプレイヤーの最優先目的として存在し続けるため、ゲームを進めるほどに強い印象を残します。特にMSX1版では、このソウルストーンが非常に強く輝く演出がなされており、暗い遺跡の中でぽつんと光る様子が、「ここが目指すべき場所だ」と無言で語りかけてくるように感じられます。ステージによっては、ただ取るだけではなく、“どの順番で取るか”“どの足場を残しながら取るか”が重要になるため、プレイヤーにとっては「自分を試してくる試験官」のような存在でもあります。すべてのソウルストーンを取り終えた瞬間に、出口に向かうルートが見えてきたり、敵の動きが噛み合って突破口が開けたりすると、「よくここまでたどり着いた」と石から褒められているような気持ちになることすらあります。無機質なオブジェクトでありながら、“このゲームを象徴するキャラクター”と呼びたくなる存在です。
● プレイヤーの想像でふくらむ“脇役たちの物語”
『エルギーザの封印』は、テキストでキャラクター同士の会話が描かれるようなタイプのゲームではありません。そのぶん、プレイヤーの想像によってキャラクター像が自由にふくらんでいく余地があります。例えば、棺から現れるミイラたちに対して、「もともとはこのピラミッドを守っていた番人だったのかもしれない」「レムールに移住してきた王族の兵士なのではないか」といった背景を思い描くこともできますし、ロックロールに関しても、「元は儀式に使われていた球体で、暴走したシステムに組み込まれているのでは」など、ゲーム内に明記されていない設定をファン同士が語り合う楽しみ方もあります。ビック13世についても、十三代続く探検家の家系にまつわるエピソードを想像したり、前作の主人公とのつながりを思い浮かべたりすることで、画面のドット絵を超えた“物語のキャラクター”として捉えられるようになります。このように、情報量を最低限に絞ったキャラクターデザインが、プレイヤーひとりひとりの想像力を刺激し、各自の頭の中で独自のドラマが展開していく――それもまた、“好きなキャラクター”が多く生まれやすい理由のひとつと言えるでしょう。
● 総括:少ないキャラ数で強い印象を残す設計
改めて振り返ると、本作に登場するキャラクターの数は決して多くありません。主人公のビック13世と、数種類の敵キャラクター、そして無機物のようでいて象徴的なソウルストーンや棺、ピラミッドの装置たち――それだけで構成された世界にもかかわらず、多くのプレイヤーの記憶に強く残っているのは、それぞれの役割とビジュアル、行動パターンが非常に明確で、印象に残りやすくデザインされているからです。敵は単に“倒す対象”ではなく、ステージギミックと結びついたパズルの一部として機能しており、その行動特性を理解すること自体がゲーム攻略に直結します。その過程で、プレイヤーは自然と特定のキャラクターに親しみや苦手意識を抱き、“お気に入り”や“因縁の相手”を心の中に持つようになります。結果として、『王家の谷 エルギーザの封印』は、豪華な演出や膨大なキャラクター数に頼らずとも、少数精鋭の登場人物たちでプレイヤーの記憶に深く刻まれるタイトルとなりました。派手さはないけれど、遊び終えたときに「ビック13世やあのミイラたちは、今もあのピラミッドで動き続けているような気がする」と感じさせてくれる――そんな余韻を残してくれるキャラクターたちこそ、このゲームの隠れた魅力と言えるでしょう。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
● 「MSX版」と「MSX2版」が別パッケージになった特別なタイトル
『王家の谷 エルギーザの封印』の大きな特徴のひとつが、「MSX用」と「MSX2用」の2種類が別パッケージとして発売されたという点です。単一のROMカートリッジを挿して、MSX1・MSX2どちらでも動作するタイトルは他にもありますが、本作のように“ハードごとに専用版を用意して発売する”というケースは、コナミのMSXタイトルの中でも特例に近い存在とされています。 これは、同じゲーム内容でありながら、MSX1とMSX2それぞれのハードウェア特性を最大限活かした表現を目指した結果とも言え、グラフィックや演出、見た目の印象に明確な差が出るように作られているのがポイントです。日本国内では両方のバージョンが流通しましたが、海外ではMSX版のみが発売され、MSX2版は日本限定という位置づけになっていました。 そのため、当時のMSXユーザーにとっては「どちらのパッケージを買うか」「MSX2を持っているのに誤ってMSX1版を買ってしまわないか」といった、ちょっとした悩みや失敗談もセットで語られるタイトルになっています。
● MSX1版:制約の中で工夫されたシンプルなグラフィック
まずMSX1版は、TMS9918系のビデオチップに合わせたグラフィックで構成されており、敵キャラクターが単色スプライトになっているほか、アイテムが黒い縁取りで描かれるなど、8bitらしい“はっきりした輪郭”が特徴です。 色数やスプライトの制限が厳しい分、シルエットや配置で情報を伝えるよう工夫されており、ミイラやロックロールといった敵も、シンプルな色使いながら一目で判別できるようデザインされています。また、MSX1版ならではのポイントとしてよく挙げられるのが、ソウルストーンが強く輝く演出です。背景が比較的落ち着いた配色でまとめられていることと相まって、ステージ内に点在するソウルストーンが“目的地の灯台”のような存在感を放ち、「まずあの光る石をどう回収するか」というプレイ方針を自然に意識させてくれます。 描画性能の制約から、画面切り替えやスクロールの面ではMSX2版に比べて素朴な印象がありますが、その分“いかにもMSX1らしいレトロな味わい”を楽しめるのが魅力と言えるでしょう。
● MSX2版:描き込みと色数が増し、雰囲気重視の表現に
一方のMSX2版は、Yamaha V9938(MSX2用ビデオチップ)の表現力を活かし、背景の描き込みや色数が大きく向上しています。 ピラミッド内部の壁や柱にはより細かな模様が施され、棺の装飾もリッチになっており、同じステージ構成でも「MSX1版=素朴でシャープ」「MSX2版=重厚で雰囲気重視」といった違いを感じ取ることができます。キャラクターの配色も増えているため、ビック13世の服装や敵キャラの色分けがわかりやすく、画面全体に“コナミ後期MSXタイトルらしい華やかさ”が加わっています。ゲーム内容そのものはMSX1版と共通で、ステージ構成や仕掛けのルールに大きな差はありませんが、視覚的な情報量が増えたことで、「俯瞰マップを眺めながら細部を読み取る楽しさ」が強くなっているのがMSX2版の特徴です。また、MSX2版は日本国内のみでのリリースだったこともあり、現在のレトロゲーム市場では“ややレア度の高いパッケージ”として扱われています。
● サウンド面:どちらもSCC音源対応という贅沢仕様
サウンドに関しては、MSX1版・MSX2版ともにSCC音源を内蔵したメガROMカートリッジとして提供されており、どちらの環境でもリッチなBGMを楽しめます。 SCC(Sound Creative Chip)は、標準のPSGに加えて5chの追加音源を持つコナミ独自チップで、『サラマンダ』や『パロディウス』、『メタルギア2 ソリッドスネーク』など、同時期の人気タイトルにも使われたことで知られています。 本作のBGMもこのSCCの恩恵を受けており、MSX1版であっても音の厚みや奥行きはMSX2版に引けを取りません。そのため、「グラフィック重視ならMSX2版、音楽重視ならどちらでもOK」という評価になることが多く、サウンドだけを切り取ってしまえば、対応機種による大きな差は感じにくい構成になっています。エミュレーターで遊ぶ際も、SCCのエミュレーションさえしっかりしていれば、どちらのバージョンでも当時と近い“鳴り”を味わえるのが嬉しいところです。
● ゲーム内容・操作性の違いはほぼ共通、細かな挙動差に注意
ゲームプレイの中核部分――ステージ構成、ソウルストーンの配置、敵やギミックの基本パターン――については、MSX1版とMSX2版で大きな差はありません。国内の攻略サイトやファンページでも、「両バージョンの攻略は基本的に共通で考えられる」と説明されており、どちらか一方でパターンを覚えれば、もう一方でもほぼ同様に通用します。 ただし、細かな挙動や見た目の印象に関しては、MSX1/2のハード差に起因する“手触りの違い”が存在します。たとえば、背景の描き込み量や色使いの差によって敵やギミックの視認性が変わり、「MSX1版のほうがソウルストーンが見つけやすい」「MSX2版は情報量が多いぶん、最初はやや見づらいが雰囲気は抜群」といった感じ方の違いが生まれます。また、一部のプレイヤーの間では、“岩男”(ロックロール系の敵)の挙動や見え方に微妙な差があると指摘されることもあり、攻略サイトによっては「ゲームプレイ面で目立つ差はこの敵キャラくらい」と補足されている例も見られます。 とはいえ、難易度バランスやステージ構造が変わるレベルの差ではなく、“微妙な手触りの違い”として意識する程度で十分でしょう。
● 海外ユーザーと日本ユーザーで違った体験
対応パソコンの違いは、そのまま“遊び手の体験差”にも繋がっています。先述の通り、MSX2版は日本国内限定だったため、欧州などのMSXユーザーは、長らくMSX1版のみを遊ぶことになりました。 その結果、海外コミュニティでは「単色スプライトとシンプルな背景を持つ高難度パズルゲーム」としての印象が強く、後年になって日本のMSX2版の存在を知り、「こんなに描き込みの細かいバージョンがあったのか」と驚かれるケースも少なくありません。一方、日本のユーザーにとっては、MSX1とMSX2どちらを所有しているか、あるいは両方を持っているかによって選択肢が変わり、「最初はMSX1版で遊び、あとからMSX2本体を入手してグラフィックの違いに感動した」といった思い出も語られます。MSX文化そのものが地域によって少しずつ違う顔を持っている中で、『エルギーザの封印』は“同じゲームでありながら、遊ぶ環境によって見えている景色が違う”という、ちょっと面白い現象を生んだタイトルと言えるでしょう。
● 実機派とエミュレータ派、それぞれのおすすめ環境
現在この作品を遊ぶ場合、実機かエミュレーターかでおすすめの環境も変わってきます。実機派であれば、MSX2本体とMSX2版カートリッジを揃えるのがもっともリッチな体験になりますが、中古市場での流通数や価格を考えると、ハードルは高めです。 一方、MSX1本体とMSX1版カートリッジの組み合わせであれば、グラフィックこそシンプルですが、ゲーム内容は同じであり、ソウルストーンの輝きやレトロな雰囲気も相まって“素朴な名作パズル”として十分に堪能できます。エミュレーター派であれば、MSX2モードをサポートするエミュレーター上でMSX2版を動かすのが手軽で、画面キャプチャや配信などにも向いています。また、SCC音源の再現度が高いエミュレーターを選べば、実機に近い音楽体験が可能で、「MSX1版とMSX2版を並べて比較してみる」という遊び方も簡単です。 “どのパソコンでどう遊ぶか”という選択そのものが、このゲームの楽しみ方の一部になっていると言っても良いでしょう。
● どのバージョンを選ぶべきか:それぞれの魅力と向いているプレイヤー像
最後に、「これから遊ぶならどの環境・どのバージョンが向いているか」を整理してみます。まず、グラフィックや雰囲気を重視し、“できるだけ当時のコナミMSX2らしい完成された画面で遊びたい”という人にはMSX2版がおすすめです。背景の描き込みや色数の多さによって、惑星レムールのピラミッド群という世界観がより豊かに伝わり、「遊ぶ前からワクワクする」ビジュアル体験が得られます。逆に、“レトロPCらしいストイックな画面と、くっきりしたスプライトの味わいが好き”という人や、“ソウルストーンの強い輝きが印象的な画面を楽しみたい”という人にはMSX1版が向いているでしょう。どちらもSCC音源による音楽クオリティは共通なので、サウンド面での差を気にする必要はほとんどありません。 また、「海外で遊ばれてきたバージョンを体験してみたい」「日本限定のMSX2版の雰囲気を味わいたい」といった、歴史的・文化的な興味から選ぶ楽しみもあります。最終的には、“自分が求めるレトロ感”に合わせて環境を選ぶのがベストであり、どのバージョンを遊んでも、このゲームが持つ骨太なパズル性と独特の世界観はしっかり味わえるはずです。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
★ソーサリアン
: ・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1987年 ・販売価格:PC版およそ7,800円前後 『王家の谷 エルギーザの封印』と近い時期のPCゲームとして、まず外せないのが日本ファルコムのアクションRPG『ソーサリアン』です。PC-8801/PC-9801など日本のパソコン市場を代表する機種向けに発売され、キャラクターを育成しながら数本の“シナリオ”を自由な順番で攻略していくスタイルが大きな話題になりました。プレイヤーは戦士や魔法使いなどで構成されたパーティを組み、横スクロールのアクション画面で敵を倒しつつ、謎解き要素を含んだステージを進行していきます。RPGとしての成長要素と、アクションとしての操作性、さらにシナリオごとにガラリと雰囲気が変わる構成力が高く評価され、後に数多くの追加シナリオがリリースされるほどの人気シリーズとなりました。当時のPCゲームユーザーにとっては、「長く遊べる大作」として強い存在感を放っていた一本です。
★ハイドライド3 闇からの訪問者
: ・販売会社:T&Eソフト ・販売された年:1987年 ・販売価格:PC版およそ7,800円前後 アクションRPGの草分けとして知られる『ハイドライド』シリーズの3作目にあたるタイトルで、PC-8801やPC-9801、FMシリーズなど多数のパソコンに展開されました。シリーズ伝統の“体当たり”バトルをベースにしつつも、時間経過による昼夜の概念や、食事・睡眠などのパラメータ管理を導入し、よりシミュレーション色の濃い作品へと進化しています。プレイヤーは広大なフィールドやダンジョンを探索しながら、謎の敵“闇からの訪問者”の正体を追っていきますが、単に敵を倒すだけではなく、各町の人々との会話やヒントも重要な攻略要素になっていました。『エルギーザの封印』と同じく“シンプルな画面の中に意外なほど複雑なシステムを詰め込んだ作品”であり、当時のPCユーザーの中で強い印象を残したタイトルのひとつです。
★夢幻戦士ヴァリスII
: ・販売会社:日本テレネット ・販売された年:1988年 ・販売価格:PC版およそ8,800円前後 女子高生が剣を手に異世界で戦うという、当時としては非常にキャッチーな設定で人気を博したアクションゲームシリーズの続編です。PC-8801やPC-9801、さらに後年にはメガドライブやPCエンジンなどにも移植され、アニメーション調の演出とストーリー性の高さが話題になりました。プレイヤーは主人公ユukoを操作し、横スクロールのステージを進みながら、魔物を切り払い、ボスと戦っていきます。ゲーム中にはイベントシーンやキャラクター同士の会話が豊富に盛り込まれており、アクションゲームでありながら“物語を追う楽しさ”が前面に出ているのが特徴でした。同じ横視点アクションでも、『エルギーザの封印』がパズル寄りの骨太な作りであるのに対し、『ヴァリスII』はビジュアルとストーリーで魅せるタイプであり、プレイヤーの好みによって遊び分けられていたと言えるでしょう。
★メタルギア(MSX2版)
: ・販売会社:コナミ ・販売された年:1987年 ・販売価格:MSX2版およそ6,800円前後 同じくコナミがMSX2向けに送り出した名作として、『メタルギア』の存在も外せません。後に家庭用ゲーム機で大ヒットシリーズとなる“ステルスアクション”の原点にあたる作品で、プレイヤーは特殊部隊の一員ソリッド・スネークとなり、敵基地に潜入して“二足歩行戦車メタルギア”の破壊を目指します。銃を乱射して敵を薙ぎ倒すのではなく、視界や物音といった要素を意識しながら敵を避けて進むプレイスタイルが斬新で、「見つからないように進むこと自体がゲームの核」というデザインは当時大きなインパクトを与えました。『エルギーザの封印』が“考えるアクションパズル”なら、『メタルギア』は“考える潜入アクション”といった位置づけであり、どちらもMSXというハードの上で独自の遊び方を提案したコナミらしいタイトルです。
★グラディウス2(MSX版)
: ・販売会社:コナミ ・販売された年:1987年 ・販売価格:MSX版およそ6,800円前後 アーケードで人気を博した横スクロールシューティング『グラディウス』の続編として、MSX向けに発売されたのが『グラディウス2』(アーケードの『グラディウスII GLOGIOUS」』とは別作品)です。パワーアップカプセルを集めて、自機ビックバイパーをカスタマイズしていくシステムはそのままに、MSX独自のステージ構成やギミックが多数盛り込まれており、家庭用ならではのやり込み要素が充実していました。SCC音源によるBGMも高く評価され、コナミMSXタイトルの中でも“音楽の良さ”が特に語られる一本です。『エルギーザの封印』と同様、メガROM+SCCという構成で、アクション性の高さと音楽の迫力が、MSXユーザーにとって大きな魅力になっていました。同じハード上で、パズル寄りのアクションとシューティングの両方が楽しめるという意味で、当時のコナミのラインナップは非常にバランスが取れていたと言えます。
★ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー(PC版)
: ・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1987年 ・販売価格:PC版およそ7,800円前後 家庭用ではファミコン版がよく知られていますが、PC-8801やPC-9801向けにも展開された『ドラゴンスレイヤー』シリーズの一作です。プレイヤーは父親・母親・息子・娘といった“家族”キャラクターを切り替えながら広大なマップを探索し、各キャラ固有の能力を使い分けて仕掛けを解いていきます。ジャンプ力に優れる者、攻撃力に優れる者、狭い場所に入れる小柄な者など、誰をどのタイミングで使うかが攻略のカギとなり、『エルギーザの封印』のように“ルートと手順を考えて進む”タイプのゲームが好きなプレイヤーには非常に刺さる内容でした。軽快なBGMとコミカルなグラフィックの裏側に、かなり骨太なマップ設計と謎解き要素が隠されており、“かわいい見た目に騙されて買ったらものすごく手強かった”という思い出を語るユーザーも多い作品です。
★Xak(サーク)
: ・販売会社:マイクロキャビン ・販売された年:1989年(企画・情報は88年頃から) ・販売価格:PC-8801版およそ8,800円前後 マイクロキャビンがPC-8801/PC-9801向けにリリースしたアクションRPGで、美しいグラフィックとハイクオリティなサウンド、そしてシリアスなストーリー展開が高く評価されました。プレイヤーは若き剣士ラトクを操作し、見下ろし型のフィールドで敵と戦いながら各地を巡ります。当時としては細かく描き込まれたキャラクターグラフィックや背景、印象的なオープニングデモなどが話題となり、「PCゲームもここまで表現できるのか」と驚かせたタイトルの一つです。『エルギーザの封印』よりやや後発ながら、同年代のPCゲーマーにとっては同じ“80年代後半の空気”を共有する作品であり、ハードの限界に挑む表現へのこだわりという点で、どちらの作品も共通した魅力を持っています。
★ファンタジーゾーンII(PC版)
: ・販売会社:日本テレネット/他(機種ごとに異なる) ・販売された年:1988年 ・販売価格:PC版およそ6,800円前後 セガの人気シューティング『ファンタジーゾーン』の続編で、家庭用やパソコン向けにも移植されたタイトルです。PC-8801やPC-9801向けのバージョンでは、アーケード版をベースにしつつも、ハード性能に合わせたアレンジが加えられていました。ポップな色使いとコミカルな敵キャラクター、そして“お金を貯めて装備を買う”というシステムが特徴で、難易度は高めながらも、何度も挑戦したくなる中毒性を持っています。『エルギーザの封印』と比べるとよりアクション寄り、反射神経寄りのゲームですが、“ステージ構成の妙”や“限られたリソースをどう使うか”という設計思想の部分では通じるものがあり、当時のプレイヤーにとってはどちらも“繰り返し遊んで上達を実感できる作品”として愛されました。
★シルフィード(PC-8801版)
: ・販売会社:ゲームアーツ ・販売された年:1986年(88年前後も各機種で話題継続) ・販売価格:PC-8801版およそ8,800円前後 疑似3D表現を取り入れた縦スクロールシューティングとして有名なのが、ゲームアーツの『シルフィード』です。PC-8801版では、ワイヤーフレームやポリゴン風のオブジェクトを駆使したグラフィックで、“自機が奥へ飛び込んでいく”ような立体感が見事に表現されました。当時のPCユーザーにとっては、“技術デモとゲーム性の両立”という意味で衝撃的なタイトルであり、80年代後半になってもなお「すごいゲーム」として語られ続けていました。『エルギーザの封印』が固定画面(もしくは小規模スクロール)の中で緻密なパズルを展開していたのに対し、『シルフィード』は画面いっぱいに広がる宇宙空間と迫力の演出で攻める作品であり、同じPCゲームでもアプローチの違いが非常に対照的です。“限られたスペックをどう料理するか”という点で、どちらも当時の開発者の工夫が詰まったタイトルと言えるでしょう。
★大戦略II
: ・販売会社:システムソフト ・販売された年:1987年 ・販売価格:PC版およそ9,800円前後 シミュレーションゲーム分野で大きな存在感を放っていたのが、システムソフトの『大戦略』シリーズです。その続編である『大戦略II』は、PC-9801などのビジネス寄りパソコンを中心に多くのユーザーを獲得し、“じっくり遊ぶ戦略ゲーム”の代表として人気を集めました。プレイヤーは陣営の司令官となり、マップ上のユニットを指揮して敵軍と戦い、占領や補給などを考慮しながら戦線を押し上げていきます。派手なアクションこそないものの、ユニット配置や生産計画を練る楽しさは格別で、1つの対戦に何時間も費やすことも珍しくありませんでした。『エルギーザの封印』と同時期のPCゲームとして、“アクションパズル”、“アクションRPG”、“シューティング”、“戦略シミュレーション”など、ジャンルの幅広さを象徴する一本であり、当時のPCゲーム市場がいかに多様だったかを示す好例となっています。
――以上のように、『王家の谷 エルギーザの封印』が登場した1980年代後半のPCゲーム市場では、アクションパズルだけでなく、アクションRPGやシューティング、シミュレーションなど多彩なジャンルの“名作”が次々と生まれていました。同じ時代に遊ばれていたこれらの作品と並べて眺めると、『エルギーザの封印』がMSXという舞台で、どれほど独自性の高いチャレンジをしていたかが、より立体的に見えてくるはずです。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
偉大なるコナミのMSXゲーム伝説 週刊アスキー・ワンテーマ【電子書籍】[ MSXアソシエーション ]




 評価 5
評価 5![偉大なるコナミのMSXゲーム伝説 週刊アスキー・ワンテーマ【電子書籍】[ MSXアソシエーション ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3678/2000002913678.jpg?_ex=128x128)


![【中古】【表紙説明書なし】[MSX] Yie Ar KUNG-FU(イー・アル・カンフー) 初期パッケージ版 コナミ (19850110)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/7/cg10027006.jpg?_ex=128x128)