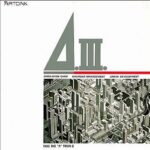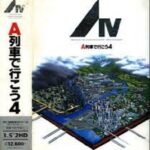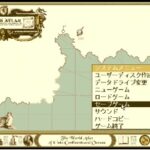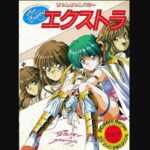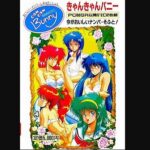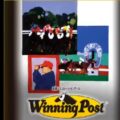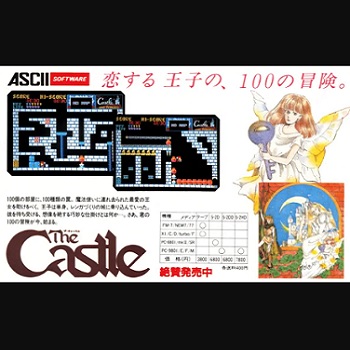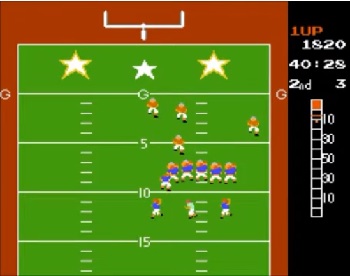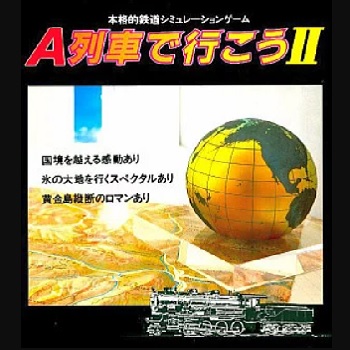
2in1ゲーミングノートパソコン 13.4型 180Hz Ryzen AI MAX 390 メモリ32GB SSD1TB Webカメラ 顔認証 Bluetooth Wi-Fi 7 Windows11 日本..




 評価 5
評価 5【発売】:アートディンク
【対応パソコン】:PC-9801、X68000
【発売日】:1988年7月
【ジャンル】:シミュレーションゲーム
■ 概要
● シリーズの誕生と進化の系譜
1988年にアートディンクが世に送り出した『A列車で行こうII』は、日本のパソコンシミュレーション史における転換点と呼べる存在である。本作は、1985年に登場した初代『A列車で行こう』の続編として開発され、前作の持っていた都市開発と鉄道経営という二つの要素をさらに深化・拡張させた。初代では単一のマップで限られた条件下の経営を行う構造であったのに対し、『A列車で行こうII』ではマップの多様性を導入し、アメリカを思わせる地域のほか、中国、シベリア、日本列島、ヨーロッパといった五つの舞台が用意された。これにより、単なる鉄道経営シミュレーションにとどまらず、各国の地理的特徴や経済発展段階を考慮した「世界スケールの都市モデル」を楽しめる作品へと進化したのである。
アートディンクは当時、国産シミュレーションゲームを牽引する存在として知られており、同社の開発チームは「リアルタイムに動く街」という概念をPC上で実現することに強い情熱を注いでいた。まだ3D表現が限られていた時代に、同社はドット単位で描かれた車両やビル群を時間経過に合わせて動かすアルゴリズムを作り込み、プレイヤーに“自分が作った街が成長していく”感覚を初めて体験させた。
● 前作からの改良点とシステム拡張
『A列車で行こうII』の最も大きな改良点は、プレイヤーが自由に駅を設置できるようになった点にある。前作では「A列車」が通過している線上にしか駅を建設できず、鉄道網の自由度が制限されていた。この制約が撤廃されたことで、都市開発の戦略性は飛躍的に高まった。さらに、列車の移動距離と運行コストが利益に反映されるように調整され、鉄道経営のリアリティが増した。
また、地形整備や土地活用に関しても新たな仕様が加わり、「整地」と呼ばれる独特のテクニックがプレイヤーの間で注目を集めた。これは一度線路を敷設して撤去すると、その跡地が整地された扱いとなり、住宅や商業施設が建ちやすくなるという仕様である。都市の発展を計画的に促すためにプレイヤーが試行錯誤を重ねるこのシステムは、後のシリーズ作品にも受け継がれていく“街づくりの楽しさ”を象徴する要素となった。
● ゲームデザインの哲学と「経済のシミュレーション」
『A列車で行こうII』は単なる鉄道運行ゲームではなく、都市全体の経済構造を扱う社会的シミュレーターでもある。プレイヤーは列車のダイヤを組むだけでなく、どの地域に駅を置き、どの産業を活性化させるかを考慮する必要がある。新たな駅を設ければ人口が流入し、周囲に商業ビルや住宅が建設される。やがて地価が上がり、企業が参入し、さらに人口が増える――この経済循環の連鎖こそが、アートディンクが「A列車」シリーズで追い求めた都市発展のダイナミズムであった。
本作では、プレイヤーの投資判断や列車の運行方針が直接街の景観と経済バランスに影響を与える。路線を引きすぎればコストが嵩み、利益が圧迫される。一方で駅の設置を怠れば都市の発展が停滞する。この絶妙なバランス感覚が、シミュレーションとしての深みを与えている。
● 技術的挑戦と当時のPC事情
1980年代後半の日本のPC市場は、NECのPC-9801シリーズとシャープのX68000が高性能機として競い合っていた時代である。『A列車で行こうII』はこの両プラットフォーム向けに発売され、それぞれのマシン性能を引き出す最適化が行われた。特にX68000版ではグラフィックの描画スピードと解像度が格段に向上し、滑らかに走る列車や細やかに変化する街の景観が高く評価された。
ただし、当時の最新機種であるNECの「PC-9801VX」シリーズでは、セーブデータが正常に保存できないというバグが存在し、これはユーザー間で大きな話題となった。この不具合はハードウェア側の仕様変更に起因するもので、アートディンクは公式に修正版を発表することなく、その後のシリーズで安定化を図った。こうした技術的トラブルすらも、黎明期のPCゲームが持つ“生の時代感”としてファンに語り継がれている。
● 世界観と5つのマップの魅力
前作が単一マップだったのに対し、本作では「アメリカ編」「中国編」「シベリア編」「日本列島編」「ヨーロッパ編」の5つの地域設定を選択できる。これらは単なる地形の違いではなく、それぞれの経済成長段階や地勢条件が異なるため、プレイスタイルが自然に変化する設計となっている。例えばシベリア編では広大な平原と限られた資源をどう開発するかが課題となり、日本列島編では複雑な地形と高密度な都市圏をどう整理するかが鍵になる。マップの広さや産業バランスも多彩であり、同じシナリオを繰り返しても毎回異なる展開を楽しめるのが特徴だ。
アートディンクはこの“地理的多様性”を通じて、プレイヤーに「世界経済を動かす鉄道王」としての感覚を体験させることを意図していた。都市育成ゲームでありながら、どこか国際的な経営シミュレーションの香りが漂う点が、後の『A列車で行こうIII』以降にも通じる方向性を示している。
● シリーズ内での特異な立ち位置
『A列車で行こうII』はシリーズ中でも珍しく、後年にリメイクや移植、廉価版の再発売が行われなかった作品である。そのため、オリジナル媒体であるPC-9801版やX68000版をプレイできる環境は限られており、長らく“幻の続編”と呼ばれてきた。2014年になってようやく、X68000版がレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」で復刻され、多くのファンが再びその世界に触れる機会を得た。
この再配信によって、本作が持つ緻密な都市形成シミュレーションの完成度や、当時のアートディンクの技術的情熱が改めて再評価されるようになった。今日においても、「II」はシリーズの中で特に“実験的かつ挑戦的な作品”と位置づけられている。
● 当時の評価と文化的意義
発売当時、専門誌では「現実の都市計画に最も近いゲーム」として高い評価を受けた。プレイヤーの行動が直接的に経済に影響するという設計思想は、後の『シムシティ』シリーズにも通じる革新性を持っていたとされる。特に、都市を俯瞰しながら交通インフラと経済活動を同時に設計するという発想は、当時のパソコンユーザーの知的好奇心を強く刺激した。
この作品の登場により、「シミュレーションゲーム=難しい」というイメージが変わり、“考える楽しさ”を味わう新しいジャンルとして定着していく。『A列車で行こうII』は、アートディンクの看板シリーズを確立しただけでなく、日本における「都市経営ゲーム文化」の礎を築いた記念碑的存在といえるだろう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● “街が生きている”という感覚を体験できるゲーム
『A列車で行こうII』が今なお語り継がれる理由のひとつは、プレイヤーの行動が時間の流れとともに「街の呼吸」として反映される点にある。プレイヤーが線路を敷き、列車を走らせると、周辺に住宅が建ち、工場が操業を始め、やがて商業施設が集まり始める。この連鎖がリアルタイムに進行することで、画面上の街がまるで有機的な生命のように変化していく。
1988年当時、パソコンゲームでここまで「ダイナミックに動く都市」を再現できたタイトルはほとんど存在しなかった。特に、昼夜の切り替えや季節の移ろいを感じさせる細やかな演出は、プレイヤーに「時間が経つことの意味」を実感させる仕組みとして秀逸だった。自分が敷いた一本の鉄路が、街全体の経済や住民の生活を変える――その感覚こそが、本作の最大の魅力といえる。
● 経営と都市開発のバランスが生む深い戦略性
『A列車で行こうII』は、鉄道会社の経営を題材にしているが、単なる資金管理シミュレーションではない。列車を走らせる目的は利益を得ることだけでなく、街の成長を促し、都市の価値そのものを高めることにある。駅を増やせば乗客は増えるが、建設コストがかさむ。貨物列車を活用すれば工場を活性化できるが、経路が複雑になれば運行の効率が下がる。この「利益と発展のバランスを取る」設計が、プレイヤーに思考の幅を与えている。
また、列車ダイヤを手動で設定できるのも大きな魅力の一つだ。時間帯ごとに列車本数を増減させたり、複線化によってラッシュ時の混雑を緩和させたりと、プレイヤーの戦略眼が問われる。計画性を重視するプレイヤーも、即興的に街を作り変えるプレイヤーも、それぞれの遊び方で都市経営の妙を楽しむことができる。
● 世界観とマップの多様性が生む物語性
前作では一つのマップで完結していたが、『II』では五つの異なる地域が舞台となる。それぞれのマップは、地形・資源・交通需要・人口構成などが大きく異なるため、単なる難易度差ではなく“地域ごとの個性”としてプレイヤーに挑戦を投げかける。
たとえば「アメリカ編」では広大な平原と整備されたインフラを活かして大規模な幹線網を作り上げるのが楽しい。一方、「中国編」では山岳地帯の多い地形が障害となり、限られた資源で効率的な鉄道網を構築する戦略性が求められる。「シベリア編」は、寒冷地ゆえに人口密度が低く、鉄道運営だけでなく物流の工夫も必要だ。「日本列島編」では地形の複雑さと需要の高さが共存しており、まさに現実の日本社会の縮図のようなプレイ体験を味わえる。そして「ヨーロッパ編」は古い街並みを残した景観が美しく、文化的な香りが漂う経営が楽しめる。
このように、マップごとにプレイスタイルが変わるため、ひとつのゲームで複数の物語を体験しているかのような没入感が生まれる。
● プレイヤーの想像力を刺激する“無言のストーリー”
『A列車で行こうII』には、いわゆるストーリーモードや登場人物による会話イベントは存在しない。しかし、だからこそプレイヤー自身の想像力が物語を紡ぐ原動力になる。小さな町に最初の駅を建てた瞬間、そこに“住む人々”の姿を思い描く。列車が走り始め、町が発展し、ビルが立ち並ぶと、プレイヤーはいつの間にか「この街に暮らす人々の営み」を頭の中で想像している。
アートディンクは、言葉や演出でプレイヤーを導くのではなく、「動的な風景」を通してストーリーを感じさせるという手法を採用した。この“語らない物語”こそが、後の『A列車で行こうIII』や『IV』、さらには家庭用移植版『A列車で行こうMD』などにも受け継がれていく精神的核となっている。
● グラフィックと音楽の静かな美しさ
当時のパソコン性能を考慮すると、『A列車で行こうII』のビジュアル表現は驚異的だった。X68000版では高解像度のドットグラフィックが採用され、列車の車体やビル群の陰影、道路を走る自動車の動きまで丁寧に描き込まれていた。PC-9801版では色数こそ制限があるものの、シンプルで見やすい構成にまとめられ、経営状況の把握がしやすいインターフェースが高評価を得ていた。
さらに忘れてはならないのがBGMである。軽快なジャズや静かなピアノ曲がゲームの雰囲気を支え、都市が成長していく過程にリズムを与える。とりわけ、朝の通勤ラッシュを思わせるアップテンポな曲調や、夕暮れ時の落ち着いた旋律は、プレイヤーに“時間の流れ”を感覚的に伝える重要な要素となっている。音楽を担当した作曲家のセンスが光り、当時のPCスピーカーでもその空気感を十分に感じ取ることができた。
● 現実の鉄道ファンにも訴える構造美
この作品の魅力は、単にゲームとして面白いというだけでなく、鉄道そのものの構造的美しさを体験できる点にもある。複線や単線、信号の設置、列車のすれ違いなど、現実の鉄道運行の原理を理解していなければ効率的な運行はできない。線路を一つの路線網として整理し、ボトルネックを見つけて解消する作業は、まるで鉄道エンジニアそのものの思考である。
この「リアリティ」と「想像性」の融合が、鉄道ファンや都市計画好きの心をつかんだ。後の『A列車で行こうIV』以降で実装される信号制御システムや複雑な経済要素の原点は、まさにこの『II』にあると言ってよい。
● 何度でも遊びたくなるリプレイ性
本作のもう一つの魅力は、リプレイ性の高さにある。マップの選択だけでなく、鉄道網の設計方針、駅の間隔、列車の本数など、無数の要素が都市発展の結果を左右するため、同じ条件でも二度と同じ街は生まれない。さらに、時間をかけて遊ぶほど街が成熟し、都市景観が少しずつ変化していく。その変化を眺めること自体が、このゲーム最大のご褒美である。
多くのプレイヤーは、最初こそ「黒字経営」を目指して慎重に計画を立てるが、やがて「もっと美しい街を作りたい」「この地形に合った理想の鉄道網を作りたい」という創造欲に駆られる。利益追求のゲームでありながら、最終的には“自分だけの都市を完成させる芸術”へと変化していく――その奥深さが、30年以上経った今でも色あせない魅力なのだ。
● アートディンク流の“知的遊び”
『A列車で行こうII』は決して派手なゲームではない。戦闘も、アクションも、派手なイベントも存在しない。それでも多くのプレイヤーが惹かれるのは、この作品が持つ「考える楽しさ」に他ならない。プレイヤーの判断一つで都市の姿が変わる――その責任と自由を同時に味わえる設計は、アートディンクが提唱した“知的遊び”の真骨頂である。
ゆっくりと変化していく街並みを眺めながら、自分の作った社会がどう発展していくのかを見届ける。そこには、単なるシミュレーションを超えた「人間と社会の関係」を見つめる哲学が宿っている。『A列車で行こうII』は、遊びながら考える――そんなアートディンクの理念をもっとも鮮やかに体現した作品と言えるだろう。
■■■■ ゲームの攻略など
● 序盤の資金管理がすべてを決める
『A列車で行こうII』は、序盤の判断ひとつで後の都市発展が大きく変わるゲームである。最初に与えられる資金は限られており、むやみに線路を敷きすぎると、開業前に資金が底をついてしまう。したがって、最初に選ぶマップと鉄道の方向性を慎重に見極めることが重要だ。 初期のコツとしては、「短距離・高需要区間」から始めること。住宅地と工業地帯、あるいは港湾エリアと市街地など、需要が自然に発生しやすい区間を結ぶ路線を最初に建設することで、初期投資を最小限に抑えつつ収益を上げやすくなる。
また、列車の本数を増やしすぎないことも重要である。序盤は運行コストが利益を圧迫しやすいため、最初の路線では1~2本の列車を運行させるだけで十分。乗客数が安定してから増便を検討すれば、安定した黒字経営へとつながる。
● 駅の設置と路線レイアウトの基本
『II』では、駅を設置する場所が都市発展の中心となる。駅周辺には住宅や商業施設が自然発生する仕組みがあるため、「どこに駅を置くか」が経営戦略の要だ。 初心者は、まず地形と道路の位置を確認しよう。山や川が多いマップでは、整地費用や橋の建設費が高額になるため、比較的平坦な土地を選ぶのが望ましい。駅の間隔は長すぎても短すぎても非効率であり、理想的には画面上で2~3ブロック分の距離を保つとよい。
さらに、将来的な複線化を見据えたレイアウトが重要だ。単線のまま都市が発展すると、列車のすれ違いができずに運行が詰まりやすくなる。早い段階で複線を敷ける余地を残しておくと、後半の発展に柔軟に対応できる。
線路を引いたあとは、駅周辺の整地を利用して住宅地を誘導しよう。一度線路を敷いて撤去すると、その跡地に建物が建ちやすくなる“整地テクニック”を駆使することで、計画的に街を拡大できる。
● ダイヤ設定のコツと効率化
『A列車で行こうII』では、列車ごとに細かい運行スケジュールを設定できる。ダイヤ編成の仕組みを理解することで、収益と混雑緩和を両立できるようになる。 まず、朝と夕方の時間帯は通勤需要が高まるため、列車の運行間隔を短く設定する。逆に深夜や昼間は需要が落ちるので、運行を減らしてコストを抑えるとよい。
また、複数の列車が同一路線を走る場合は、駅での停車時間を微調整することでスムーズな運行を実現できる。停車時間を1~2分短縮するだけでも、全体の回転率が上がり、遅延や渋滞を防げる。
さらに上級者の間では、貨物列車と旅客列車を同一路線に共存させる「複合運行」が人気だった。貨物列車は利益率が高い反面、駅の数が多いと非効率になるため、短距離専用の支線を引いて分離運行するのが理想的な戦略である。
● 都市発展を促すための“呼吸の設計”
本作では、都市の発展には時間が必要である。プレイヤーが一定期間、列車を走らせ続けることで徐々に建物が増えていくため、焦らずに「街が育つのを待つ」姿勢が大切だ。 プレイヤーの間では、この成長の“リズム”を読み取ることが上達への鍵とされていた。たとえば、駅周辺の住宅が増え始めたら、次の路線を敷くタイミングである。逆に、建設ラッシュが止まり、景気が停滞しているようなら、貨物路線を新設して工業地帯を活性化させるとよい。
この「街の呼吸」を読む力は、単にゲーム攻略のテクニックではなく、経営シミュレーションの醍醐味そのものだ。アートディンクの開発陣は、プレイヤーが“都市という生き物”の成長を観察する楽しさを感じられるよう設計していたといわれている。
● 経営バランスと資金繰りのテクニック
都市経営で最も重要なのは、赤字を出さずに持続可能な収益構造を築くこと。序盤に黒字化したとしても、駅や路線を増やしすぎるとすぐに支出が上回ってしまう。プレイヤーの中には、あえて“銀行的経営”を目指す人もいた。これは、一定の収益を貯めてから次の開発に着手する戦略で、焦って拡張するよりも結果的に効率が良い。
また、不要になった路線を早めに撤去するのも有効な手段だ。撤去した跡地は整地効果で建物が増えるうえ、維持費を削減できる。投資と撤退の判断を柔軟に行うことが、長期的な成功のカギを握っている。
● 上級者のためのテクニックと“遊び方の自由度”
『A列車で行こうII』は、単なるクリアを目指すゲームではなく、プレイヤー自身が目標を設定するタイプの作品である。ある人は「人口100万人都市を作る」ことを目指し、またある人は「赤字を一切出さずに10年経営を続ける」ことに挑む。こうした“自己設定型プレイ”ができるのも本作の自由度の高さゆえだ。
上級者の間で知られていた裏技のひとつに、土地の“整地連鎖”を利用した高速都市成長法がある。これは、線路を一定間隔で敷設→撤去→再敷設を繰り返し、整地済みエリアを広げて建物の出現を促すテクニックだ。この手法を駆使すると、わずか数年で巨大都市を作り上げることができた。
また、貨物列車の経路を最短化し、製造業と商業地区を効率的に結ぶ“物流最適化”も高度なテクニックの一つだった。こうした戦略を磨くことで、プレイヤーは単なる鉄道経営者から、都市経済を操る「プランナー」へと成長していく。
● トラブルとバグへの対処法
PC-9801版では、環境によってセーブデータが破損するバグが報告されており、プレイヤーは定期的にバックアップを取ることを推奨されていた。また、長期間プレイすると一部のグラフィックデータが化ける現象も発生することがあり、ユーザー同士で対策情報を共有する“コミュニティ文化”が形成されていた。
このような不具合への対応力も、当時のPCゲーマーの“攻略力”の一部だった。限られた環境の中で最適解を見つける――それが1980年代後半のパソコンシミュレーション文化の象徴でもある。
● “終わりのない”都市経営の楽しさ
『A列車で行こうII』に明確なエンディングは存在しない。だからこそ、プレイヤーは「どこで終わりとするか」を自ら決めなければならない。すべての土地を開発し尽くしても、まだ改善の余地が見つかる。駅の配置を変えるだけで交通の流れが変わり、街の姿が一変する。そうした“終わりのない挑戦”が、本作の最大の魅力であり、攻略の本質でもある。
長時間プレイすることで、最初に作った小さな町が大都市に成長し、そこに自分だけの歴史が刻まれていく。攻略とは、単に数字や利益を追うことではなく、“街と共に生きる”ことなのだ――そう感じさせてくれるのが、『A列車で行こうII』という作品なのである。
■■■■ 感想や評判
● 静かな熱狂――1980年代後半のパソコンゲーマーたちの驚き
『A列車で行こうII』が発売された1988年当時、ゲーム業界の中心はまだアクションやRPGが主流で、シミュレーションは一部のマニア向けジャンルに過ぎなかった。そんな中で、本作は「鉄道を通して都市を発展させる」というユニークなコンセプトで多くのプレイヤーの心をつかんだ。 雑誌『LOGiN』や『マイコンBASICマガジン』のレビューでは、「まるで街が呼吸しているようだ」「自分が作った世界が動いていく感覚に夢中になる」といったコメントが多く寄せられ、派手な演出こそないものの、その静かな熱狂ぶりは当時のPCゲーマーの間で話題になった。
特にX68000ユーザーの間では、グラフィックの滑らかさと高精細な街並みの描写が絶賛された。列車が走るたびに変化する風景、線路沿いに立ち並ぶ建物の変化――それらを見守るプレイヤーの体験は、当時としては革新的だった。
● メディアの評価――「知的な遊び」としての価値
多くのパソコン誌では、『A列車で行こうII』を“知的ゲーム”として高く評価している。特に経済シミュレーションの側面を重視する声が多く、「プレイヤーの経営判断が街の発展を左右する」「数字ではなく景観で成果を感じられる」といった独特のゲーム体験が紹介された。 『テクノポリス』誌では、「プレイヤーの創造力と現実感を融合させた傑作」と評され、都市形成ゲームとしての完成度の高さが称えられた。一方で、初心者にはやや取っつきにくいという指摘もあり、「慣れるまでに時間がかかるが、理解した瞬間から離れられなくなる」というレビューが印象的だ。
この「ハマるまでが難しいが、ハマると抜け出せない」構造は、後に『シムシティ』(1989年)にも共通して見られる。つまり『A列車で行こうII』は、日本における“都市経営シミュレーション文化”を切り開いた先駆的存在として、のちのゲーム史にも大きな影響を与えたといえる。
● プレイヤーの声――“遊ぶほどに哲学になる”
当時のユーザーから寄せられた感想の中で特に多かったのは、「気づいたら夜明けまで街を眺めていた」というものだ。プレイヤーが手を加えなくても時間が流れ、街が少しずつ変化していく様子を見守るのが楽しい――この“観察の快楽”こそが本作の本質だった。 あるプレイヤーは雑誌の投稿欄で「列車が街を育て、街が列車を育てる。その循環を見ているうちに、まるで自分が都市そのものになった気がした」と語っている。このように、ゲームでありながらどこか人生観や社会哲学を感じさせる作品として捉えられていたのも特徴だ。
また、一部の教育関係者の間では「経済や都市構造の理解に役立つ教材になる」との評価もあり、パソコン教室で教材的に使われた事例もあった。鉄道ファンだけでなく、都市デザインや地理に興味を持つ層にも広く受け入れられた稀有な作品である。
● 開発者への敬意――“アートディンクの職人精神”
プレイヤーや批評家の間では、アートディンクという開発会社そのものへの尊敬が高まった。派手な宣伝やコマーシャル展開を行わず、純粋に完成度の高さだけで勝負していた同社の姿勢は、多くのファンの信頼を得た。 特に印象的なのは、ゲーム内の細部にまで宿るこだわりである。列車が駅に停車する際のブレーキ音、貨物列車が走る際の微妙な速度差、地形の勾配によるスピードの変化――これらはほとんど説明書にも書かれていない要素だが、プレイヤーがプレイの中で気づくと深い感動を覚える。「このゲームには“職人の魂”がある」と評した評論家もいたほどだ。
● 批判的な声――“難しすぎる”という壁
もっとも、『A列車で行こうII』には一定の批判も存在した。特に初心者層からは「何をすればいいかわからない」「説明書を読んでも理解できない」という意見が目立った。チュートリアルが存在しないため、初めてプレイする人にとっては鉄道の仕組みや経営の流れを理解するのに時間がかかったのだ。 また、経営バランスがシビアで、赤字経営になると挽回が難しいという点も指摘されている。システムの理解が進めば面白くなるが、それまでに離脱してしまうプレイヤーも少なくなかった。
それでも、多くのユーザーはその難しさを“やりがい”として受け止めており、「簡単に攻略できないからこそ面白い」「自分の頭で考える楽しさがある」と肯定的に捉える声が多数を占めた。これはまさに、アートディンク作品に共通する“硬派な設計思想”への賛辞でもあった。
● 海外ユーザーと再評価の波
本作は国内向けに制作されたが、X68000版を中心に一部の海外ファンの間でも注目を集めた。1990年代初頭、海外フォーラムでは「Japanese Train Simulation」として紹介され、独特の都市育成システムが「欧米の都市経営ゲームとは異なるアプローチ」として話題になった。 さらに2010年代に入ると、レトロゲーム配信サイト「プロジェクトEGG」での復刻を機に再び注目を浴び、当時を知らない新世代のゲーマーからも「30年前のゲームとは思えない完成度」「現代のシミュレーションの原型」として再評価された。YouTube上ではプレイ動画や都市紹介が多数投稿され、今では“クラシック・シム”の名作として位置づけられている。
● 雑誌レビュー・メディアスコアの傾向
発売当時の媒体レビューを振り返ると、『A列車で行こうII』のスコアは総じて高かった。 – 『LOGiN』誌:85点/100点 – 『テクノポリス』誌:9/10評価 – 『Oh!X』誌(X68000専門誌):グラフィック部門で満点評価
グラフィックと音楽の完成度、そして操作性の向上が特に高く評価されており、前作からの進化が明確だったことが支持を集めた。逆に「難解さ」と「セーブ不具合」が減点要素とされたが、それを補って余りある“世界の広がり”がプレイヤーの心をつかんだ。
これらのレビューを総合すると、評価の核は「派手さではなく知的満足感」であり、まさにアートディンクらしい哲学が反映された結果といえる。
● 現代に通じる“温故知新”の魅力
『A列車で行こうII』は、今の時代に遊んでも古さを感じさせない。むしろ、現代の作品が失いがちな“静かな時間の流れ”を大切にしており、プレイヤーに考える余白を与えてくれる。テンポの速いゲームが主流となった今だからこそ、この“観察と構築のゆとり”が新鮮に感じられるのだ。
SNS上では、「いまのA列車シリーズよりもIIのシンプルさが好き」「当時の制限が逆に創造力を引き出した」といった声も多く見られる。技術的制約があった時代だからこそ、プレイヤーが想像で補い、自分の街を“物語化”していった――それがこの作品の普遍的な魅力だろう。
● 総評――“時間をデザインする”ゲームの原点
総じて、『A列車で行こうII』は「時間をデザインするゲーム」として多くの人の記憶に残っている。プレイヤーが都市の成長を見守り、その時間の流れそのものを楽しむ――この哲学は、後の『A列車で行こうIII』『A列車で行こうIV』、さらには『A列車で行こう9』などの現代シリーズにも脈々と受け継がれている。
派手さはなくとも、プレイヤーの想像と知性を信じる設計思想。それこそがアートディンクの信条であり、『A列車で行こうII』が今なお語り継がれる理由である。静かな鉄路の上を走る列車のように、この作品の魅力は時を超えてゆっくりと人々の心に響き続けている。
■■■■ 良かったところ
● 都市が「成長していく喜び」を可視化した設計
『A列車で行こうII』で多くのプレイヤーが最初に感動するのは、街が自らの意思で動いているかのように成長していく様子である。鉄道を敷き、駅を設けると、その周囲に少しずつ住宅が建ち、商店が並び、街路が形成されていく。この“目に見える進化”が、プレイヤーの行動と直結している点が非常に秀逸だ。 他の経営シミュレーションでは、グラフや数字で成長を実感するケースが多いが、本作では街そのものがプレイヤーの成果を語ってくれる。線路一本を引くだけで街の形が変わり、時が流れるにつれて地形が再構成されていく。このビジュアルな成長の実感が、プレイヤーに「街づくりの手応え」を与えてくれるのだ。
この仕組みは、当時としては革新的だった。リアルタイムで変化する都市システムを持つゲームはほとんど存在せず、アートディンクは膨大な計算処理を独自の軽量化技術で実現していた。結果として、プレイヤーは単なる鉄道経営を超え、「自分が作った世界が呼吸する」という、今までにない感覚を味わえた。
● 完成されたインターフェースと操作性の快適さ
前作に比べ、操作性の向上は大きな進歩だった。マウス操作が限定的だった時代に、キーボードだけで複雑な経営を行えるよう設計されたUIは驚くほど直感的だ。建設モード・運行モード・資金管理モードが明確に分かれ、切り替えもスムーズ。特に線路敷設の際のカーソル追従やスナップ機能の精度は、当時のPCシミュレーションの中でも群を抜いていた。
また、メニュー構成が論理的で、経営指標や列車情報が一目で分かる点も高評価の理由の一つだ。限られた解像度の中で視認性と操作性を両立させたUIデザインは、アートディンクが持つ“情報美学”の賜物といえる。特に「マップ全体を見渡せる俯瞰視点」と「駅周辺の詳細画面」をワンタッチで切り替えられる点は、後のシリーズにも受け継がれた画期的な発想だった。
● サウンドと映像の静謐な調和
『A列車で行こうII』の魅力を語る上で欠かせないのが、音楽とビジュアルの調和である。BGMは派手ではなく、むしろ控えめで穏やかな旋律が多い。しかしその静かなリズムが、プレイヤーの集中を深め、都市経営の時間を心地よく彩ってくれる。 昼夜の変化に合わせてトーンが切り替わる演出や、走行音・ブレーキ音などの効果音の繊細な使い分けも見事だ。特に夜の街並みで流れる落ち着いたピアノの旋律は、多くのプレイヤーにとって印象的なシーンとして記憶されている。
グラフィック面では、ビル群の立体感や鉄道の陰影、列車が走り抜ける際の滑らかな動きなど、当時の技術を極限まで引き出していた。画面全体に漂う「静かな生活感」が、他のゲームにはない温度を生み出している。こうした演出の繊細さが、“見守るゲーム”としての本作をより特別な存在にしている。
● プレイヤーに「考える余地」を与えるデザイン哲学
アートディンクが生み出す作品には一貫して「考える楽しさ」がある。本作もその哲学の象徴だ。明確なクリア条件や制限時間がなく、プレイヤーが自ら目標を設定し、自ら答えを見つけていく構造になっている。 例えば、利益を追求するプレイもあれば、美しい街並みを作ることを目的とするプレイもある。どちらも正解であり、自由な発想が尊重される。その自由さこそが、プレイヤーに“都市創造の思想”を抱かせる。
ゲームが“指示に従うもの”だった時代において、『A列車で行こうII』は“自分で世界を設計する遊び”を提示した。この自由度の高さと自己表現性こそが、本作最大の美点だといえる。
● 現実の社会構造を見事に反映した経済モデル
本作では、鉄道の収益だけでなく、都市の発展そのものが企業利益に影響するよう設計されている。つまり、プレイヤーの選択が経済循環を直接的に生み出すのだ。人口が増えれば乗客数が増加し、商業地が拡大すれば貨物輸送の需要が増える。こうした相互関係の精度が非常に高く、経済学的な観点から見てもよくできたシミュレーションになっている。
さらに、単に“利益を出す”だけでなく、“社会をどう成長させるか”を考えさせる構造になっている点も深い。鉄道会社の経営者としての視点と、都市開発者としての視点が両立しているため、プレイヤーは自然と「公共性」と「企業利益」の両立を意識するようになる。
これは単なるゲームを超えた社会学的体験であり、都市経営の倫理や理念を学ぶ教材としても価値があると評された。
● “遊びながら学べる”知的満足感
当時のプレイヤーからは、「プレイしているうちに都市の仕組みを理解できる」「鉄道経営の奥深さを実感した」という声が多かった。ゲームでありながら、都市設計・交通政策・資源配分など、現実世界の要素を自然に学べる構造が高く評価された。 アートディンクの開発チームは、“エンターテインメントと知的刺激の両立”を目指しており、本作はその理想を最も洗練された形で具現化している。遊びながら思考を促す設計思想が、後の『ルナティックドーン』や『シムシリーズ』などに影響を与えたとされる。
● 時間の流れを感じさせる演出の妙
多くのプレイヤーが感動したのは、“時間の重み”を感じさせる演出だった。日が昇り、列車が通勤客を運び、夜になると街の灯りがともる――このサイクルを繰り返すうちに、プレイヤーはまるで自分がその世界に生きているような感覚を覚える。 時間経過によって街が変化し、建物が老朽化したり、新しい企業が進出したりする様子は、まさに「世界の呼吸」を見ているようだ。これらの演出は当時のPC技術では極めて難しく、アートディンクの技術者たちの執念が実現させたといわれる。
現代の高速テンポなゲームとは異なり、『A列車で行こうII』は「ゆっくり流れる時間の豊かさ」を教えてくれる。これが多くのファンにとって“癒し”として機能していた。
● 長く遊べる構成とリプレイ性
一度プレイを終えても、次のマップではまったく異なる展開が待っている。地形・資源・人口分布の異なる5つのマップは、それぞれが独立した挑戦を提供し、繰り返し遊ぶほど発見がある。 さらに、プレイヤーが自由に目標を設定できるため、「効率重視プレイ」「景観重視プレイ」「鉄道模型的プレイ」など、何通りもの楽しみ方がある。これにより、単なる1本のゲームではなく“自分だけの世界生成ツール”として長期間遊べる魅力があった。
発売から35年以上が経った今でも、愛好家がプレイし続けている理由は、この無限の遊び方にある。
● 総評――“静かなる傑作”としての存在感
『A列車で行こうII』の良かった点を総合すれば、それは「派手さを捨て、知性と静寂の中に深い快感を見出したこと」に尽きる。アートディンクが目指したのは、誰もが夢想する理想の都市を、自分の手で形にできる体験だった。その理念はプレイヤーの心に深く刻まれ、時代を超えて共感を呼んでいる。 現代の最新シリーズと比較しても、本作の持つ「シンプルさと美しさの均衡」は失われていない。プレイヤーが考え、観察し、感情を重ねながら作り上げる――そのプロセスこそが“良かったところ”の本質であり、『A列車で行こうII』が今も輝きを放つ理由なのである。
■■■■ 悪かったところ
● 説明不足でハードルが高かった初見プレイヤー体験
『A列車で行こうII』の最大の難点として多くのプレイヤーが挙げたのが、“何をすればいいのか分からない”という点だった。 当時のパソコンゲームはまだチュートリアル文化が浸透しておらず、マニュアルを熟読しなければ基本操作すら理解できないものが多かった。本作もその例に漏れず、スタート直後に線路を敷く手順や列車の購入方法、ダイヤ設定などが一切説明されていない。そのため、初プレイで資金を使い果たして倒産してしまうケースが頻発した。
多くのプレイヤーが「気づいたら赤字になっていた」「列車が走らない理由が分からない」と戸惑い、特に初心者には取っ付きづらい印象を与えた。結果的に、本作は“遊び方を自分で見つける”ことを前提とした設計になっており、学習曲線が非常に急だったのである。
現代のプレイヤーから見れば、それは自由度の高さとして評価されるかもしれないが、当時は“不親切なゲーム”と捉えられることも多かった。
● 難易度バランスの極端さ
『II』はリアルな経営シミュレーションを追求した結果、バランスが非常にシビアになっていた。序盤の投資判断を誤るとすぐに資金難に陥り、赤字が続くと挽回がほぼ不可能になる。しかもローンや救済措置が存在しないため、破綻した時点で事実上ゲームオーバーとなる仕様だった。 また、路線を増やすごとに運行コストが膨らみ、利益を維持するためには緻密な運行管理が必要になる。これが熟練プレイヤーにはやりがいを感じさせた一方で、初心者には非常に厳しかった。
特に「利益が出ない理由が数値上では分からない」という問題もあり、どの要素が経営を圧迫しているのかを分析するのが困難だった。このように、リアルさを追求した結果として生まれた“現実的すぎる難しさ”が、一部のプレイヤーを遠ざける要因となった。
● 操作レスポンスと処理速度の遅さ
当時のPC-9801やX68000といったハードウェアの性能を考えると、膨大な都市データをリアルタイムで処理するのは限界に近い負荷だった。特に後半、都市が発展して建物や列車の数が増えると、画面スクロールや操作入力に対する反応が極端に遅くなる。 プレイヤーの間では「後半の処理落ちが激しい」「早送りが欲しい」といった意見が多く、長時間プレイするほどテンポの悪さが気になった。特に複線運用を始めると列車同士の衝突判定や信号処理に時間がかかり、待ち時間が増えるのがストレスだったという声も多い。
また、ハードによってはメモリ制限の関係でグラフィック表示が崩れることもあり、PC性能に強く依存したゲームだったことも短所として挙げられる。
● インターフェースの煩雑さと慣れの必要性
操作性が改善されたとはいえ、すべての機能をキーボード操作で行う設計は依然として複雑だった。メニュー階層が深く、列車の情報確認や資金管理画面を開くたびに複数のキーを押す必要がある。 また、地形の拡大縮小や路線の角度調整などが直感的ではなく、慣れるまでに時間を要した。マウス対応が限定的であったことも、UIの不親切さを際立たせていた。
プレイヤーの中には「操作を覚えるまでに1週間かかった」「効率的に動かすコツをつかむまでに何度もリセットした」と語る人も多い。とはいえ、この“慣れ”のプロセスを楽しむ層もおり、アートディンク特有の“学びながら遊ぶ”設計の難点と魅力が表裏一体になっていた。
● バグとデータ保存の不具合
本作の技術的な欠点として特に知られているのが、PC-9801VXシリーズなど一部機種で発生したセーブデータの不具合だ。セーブが正常に完了せず、長時間プレイしたデータが破損するケースが報告されていた。これはハードウェアの仕様変更によるもので、アートディンクも完全な修正パッチを出すことができなかった。 そのため、プレイヤーはこまめにバックアップを取るなど自己防衛策を講じる必要があった。
また、長時間プレイを続けると画面上のオブジェクトが消えたり、道路や線路が途切れて表示されるバグも存在した。こうした不具合はハード性能の限界によるもので、当時の技術では避けがたい問題だったが、没入感を損なう要因になっていたことは否めない。
● リアル志向ゆえの地味さ
多くのプレイヤーが指摘したもう一つの弱点は、「地味さ」である。『A列車で行こうII』は派手な演出やイベントがなく、淡々と時間が流れていく設計だ。戦闘もストーリーもないため、刺激を求めるプレイヤーには物足りなかった。 特に、当時流行していた『ドラゴンクエストIII』や『イースII』などのRPG作品と比較すると、視覚的にも物語的にも地味で、“遊びながら考える”ことに価値を見出せる人でなければ楽しめなかった。
この点は、後に『A列車で行こうIII』以降でイベント的演出や街の発展アニメーションを強化することで改善されるが、『II』単体では“静かすぎるゲーム”という印象を持たれることが多かった。
● 経済シミュレーションのブラックボックス化
もうひとつの欠点は、内部計算の“見えなさ”である。利益や人口の増減の仕組みがプレイヤーからはほとんど見えず、「なぜ黒字になったのか」「どの駅が赤字なのか」を把握しづらい。数値の推移を表示するグラフや統計表が簡素だったため、経営分析を行いたい層には不満が残った。 特に鉄道経営の収支構造が複雑で、路線距離、駅の位置、列車数、貨物輸送量といった要素が絡み合っており、それらを直感的に理解するのは難しかった。プレイヤーは経験的に“儲かる路線”を見つけるしかなく、理論的な経営を楽しみたい層には物足りなかっただろう。
この不透明さが、後のシリーズで統計ウィンドウや収支分析グラフの実装につながっていく。つまり、『II』の不満点が、シリーズ全体の進化を促す原動力にもなったと言える。
● マップごとの難易度格差と理不尽さ
五つのマップが選べるのは魅力だったが、その難易度差が極端だった。「アメリカ編」は比較的バランスが取れていたものの、「シベリア編」や「中国編」は資源配置が厳しく、初心者が遊ぶには不向きだった。逆に「日本列島編」は土地が狭く、建設コストが高いため、利益を出す前に資金が尽きることが多かった。 これらのマップを攻略するには、都市計画の経験が必要で、簡単にクリアできるルートが存在しなかった。結果的に、プレイヤーの一部は「特定マップしか遊ばなくなった」と語っている。
この不均衡さは、バランス調整という観点で見れば弱点だが、一方で“挑戦の余地”として評価する声もあった。
● 一部ユーザー環境での互換性問題
当時のPC市場は多様な規格が混在しており、ディスプレイやサウンドボードによって挙動が変わるケースが多かった。X68000版では問題が少なかったものの、PC-9801版では解像度や色設定の違いによって画面が正しく表示されないこともあった。また、FM音源ボード非搭載機では音楽が鳴らず、ゲーム体験が大きく損なわれることもあった。
こうした環境依存の問題は、1980年代PCゲームの宿命でもあるが、当時のユーザーからは「設定が難しすぎる」「音が出ない」という苦情が一定数寄せられていた。
● 総評――完成度の高さゆえに露呈した“玄人向け”設計
『A列車で行こうII』の悪かった点を総合すると、どれも“完成度が高すぎたがゆえの難しさ”に起因している。リアルを追求した結果、初心者にとって敷居が高くなり、システムの複雑さが一部ユーザーを遠ざけた。それでも、本作が「難しくてもやりたくなる」作品であることは疑いない。 アートディンクは、万人にわかりやすいゲームではなく、理解した者に深い満足を与える“知的娯楽”を目指していた。その設計思想は、多くの人にとって挑戦的であったが、同時に唯一無二の存在感を生み出した。
結果的に、『A列車で行こうII』の“悪かったところ”は、同時に“魅力の裏返し”でもあった。難しさ、地味さ、不親切さ――それらすべてが、この作品を時代を超えて語り継がれる伝説にしたのである。
[game-6]■ 好きなキャラクター
● “A列車”そのもの――物語の語り手としての列車
『A列車で行こうII』には、アニメやRPGのような登場人物はいない。だが、シリーズの名を冠する「A列車」こそが、このゲームにおける主役であり、象徴的なキャラクターである。 プレイヤーが最初に購入し、最初に走らせる車両――それがA列車だ。朝日を浴びながら静かにホームを出発し、やがて夕暮れの街を走り抜けていくその姿は、まるで街の鼓動を運ぶ心臓のように描かれている。
この列車が通過するたびに街が活性化し、人々の生活が変わっていく。工場に人が集まり、商業地が広がり、住宅街が明かりを灯す。A列車は、単なる交通手段ではなく、都市そのものを“生かす存在”として描かれている。
多くのプレイヤーがこの列車に深い愛着を抱くのは、彼らの努力と時間の象徴だからだ。ゲームを始めた瞬間から最後まで、A列車は無言のままプレイヤーの決断に従い、忠実に都市の未来を走り続ける。ある意味、この列車こそが『A列車で行こうII』の“語り手”であり、“キャラクター”なのだ。
● プレイヤー自身――無名の都市設計者という存在
もうひとりの主人公は、画面の外にいるプレイヤー自身だ。 『A列車で行こうII』では、主人公に名前も顔も設定されていない。肩書きも経歴も語られない。しかし、だからこそプレイヤーは完全に「都市を設計する神」としてその世界に没入できる。
プレイヤーが線路を敷けば、人々はその路線を利用し、街は形を変える。経営に失敗すれば街は衰退し、成功すれば豊かに成長する。そのすべての責任と自由が、無言のプレイヤーに託されている。
多くのファンはこの匿名性を好意的に受け止め、「自分がこの街の設計者になれる」「見えない存在として世界を見守る感覚が好き」と語る。RPG的なキャラクターが存在しないことで、プレイヤー自身が物語の主役となり、想像力が街に命を吹き込む。これもまた、アートディンクらしい“無名の主人公像”である。
● 街の住民たち――姿なきキャラクターたちの息づかい
『A列車で行こうII』では、街を行き交う人々は直接描かれない。だが、住宅の灯り、駅前のビル、道路を走る車――それらのすべてが「住民の存在」を感じさせる演出として機能している。 あるプレイヤーは、「夜に駅の灯がともる瞬間が好きだ。あの光のひとつひとつに人の生活を想像してしまう」と語っている。そう、このゲームにおける“キャラクター”とは、人の姿ではなく“風景そのもの”なのだ。
列車が通過するたびに変化する街並みは、まるで無数の人生が交錯しているようである。学校帰りの子供、工場へ向かう労働者、家族連れ――プレイヤーは誰も見えない彼らの存在を、街の息づかいとして想像する。それがこのゲームが持つ詩的な魅力だ。
アートディンクはあえて“キャラクターを描かない”ことで、プレイヤーの想像力を刺激し、街に「見えない住民たち」を住まわせたのである。
● 列車たちの個性――動く登場人物たち
本作には複数の車両タイプが存在し、それぞれに個性がある。 通勤型のA列車はまじめで安定した働き者。貨物列車は力強く、都市の産業を支える無骨な存在。そして特急車両は華やかで、都市間を結ぶエネルギーを象徴している。 プレイヤーによっては、これらの車両に“人格”を見出すことさえある。「貨物列車は街の血管」「A列車は心臓」「特急は夢を運ぶ」と語られることも多く、それぞれがプレイヤーの物語の中で異なる役割を担っている。
特に印象的なのは、列車がすれ違う瞬間や駅で停車している光景だ。そこには、無数の人々の行き交い、生活のリズム、社会の動きが凝縮されている。こうした“無言のドラマ”を感じ取れるのも、『A列車で行こうII』という作品の文学的な側面だといえる。
● 都市そのもの――もうひとりの主人公
多くのプレイヤーが口をそろえて語るのは、「街そのものがキャラクターだった」ということだ。 最初は何もない土地に線路を敷き、駅を建て、数年の時間を経て高層ビルが立ち並ぶ。その変化はまるで人の成長のようで、プレイヤーは“街を育てる親”のような気持ちになる。
時に街は予期せぬ方向に発展し、時に衰退する。道路が渋滞し、工場が閉鎖され、住宅が消える――まるで生き物が老いるように。その一瞬一瞬に感情を揺さぶられるプレイヤーは少なくない。
あるファンは、「都市を見ていると、自分の人生を見ているようだった」と語った。この“街の人格化”こそが、他のシミュレーションゲームにはない深い共感を生む要素であり、『A列車で行こうII』の最大の芸術性である。
● アートディンク開発チームという“裏のキャラクター”
本作を語る上で忘れてはならないのが、開発者たちの存在だ。アートディンクは小規模なチームながら、妥協を許さない職人気質で知られていた。 プログラマー、デザイナー、音楽担当――それぞれの分野の専門家が、自分の感性を信じて創り上げた結果が『A列車で行こうII』である。彼らの姿勢そのものが、この作品に宿る“人格”としてプレイヤーに伝わってくる。
多くのユーザーは、このゲームに「開発者の息吹」を感じ取っている。無言の都市、静かな列車、丁寧な設計――そのすべてに、人間らしい温度がある。
ゲームに制作者の魂が宿ることを証明した作品として、『A列車で行こうII』は今なお特別な位置を占めている。
● プレイヤー同士の“想像の共有”というキャラクター性
1980年代後半、インターネットがまだ普及していなかった時代、本作のプレイヤーたちは雑誌投稿欄や同人誌、PC通信ネットを通じて自分の街を語り合っていた。 「私の街の人口は30万人になりました」「特急列車を“希望号”と名付けました」――そんな投稿が『LOGiN』や『Oh!X』に掲載され、プレイヤー同士が互いの都市を“物語”として共有していたのだ。
つまり、当時のプレイヤーたち自身が、このゲーム世界の“登場人物”でもあった。彼らが語る街のエピソードは、まるで小説のように多様で、各々の人生観が反映されていた。
このように、『A列車で行こうII』は単なるゲームに留まらず、プレイヤーと作品が共同で“都市というキャラクター”を創造する、極めて文学的な体験を生み出した。
● 総評――キャラクターなきゲームが描いた“人間”
『A列車で行こうII』には、主人公も敵もいない。しかし、そこには確かに「人間の物語」がある。 列車は黙々と走り、街は変化し、プレイヤーはその過程を見守る――この静かな営みの中にこそ、人間の営みの本質が映し出されている。 本作はキャラクターを描かずに「人間そのもの」を描いた稀有なゲームであり、その思想性こそが多くのファンの心を掴み続けている理由だろう。
アートディンクが提示したのは、派手な英雄譚ではなく、“都市と人間の共生”という永遠のテーマである。A列車、街、プレイヤー、住民――そのすべてが一体となって紡ぐ物語。それが『A列車で行こうII』という作品の魂であり、今も静かに走り続ける無言のキャラクターたちの姿なのである。
[game-7]● 対応パソコンによる違いなど
● PC-9801版 ― 国内標準機での安定性と普及力
1980年代後半、日本のパソコン市場の中心にあったのがNECのPC-9801シリーズである。『A列車で行こうII』のPC-9801版は、この国内主流機種向けに最適化されており、最も多くのプレイヤーが体験したバージョンだった。 このバージョンの特徴は「堅実さ」と「互換性の広さ」である。アートディンクは、PC-9801の各モデルごとのメモリ容量やグラフィック仕様の違いを考慮し、表示解像度640×400ドットを基本に、8色から16色の描画パレットを駆使して街並みを表現した。 建物や列車の色合いはやや淡く、全体的に落ち着いたトーンで統一されているが、その分、画面上の情報が視認しやすく、長時間プレイでも疲れにくい設計になっている。
また、PC-9801版は操作系がシンプルで、CPU負荷を抑えた動作が特徴だった。高性能なモデルでなくとも安定して動作するため、当時のビジネスユーザーや教育機関にも導入されやすかった。特に、FM音源ボードを搭載していれば、軽快なジャズ調のBGMが鳴り、都市の発展を音楽で感じられる演出も楽しめた。
ただし、前述した通り、一部の「PC-9801VX」シリーズではセーブが正常に行えないという問題が報告されており、ユーザーの間で注意が促されていた。この不具合はシリーズ史に残る“仕様事故”として知られているが、それを除けば総じて安定性の高いバージョンだったといえる。
● X68000版 ― 技術の粋を集めた“理想のA列車”
もう一方のX68000版は、グラフィックとサウンドの両面で、当時のPCゲームの限界を押し広げた作品だった。 シャープが開発したX68000は「パーソナルワークステーション」とも呼ばれる高性能機で、解像度512×512ドット・65,536色同時発色という圧倒的な描画力を持っていた。これにより、『A列車で行こうII』の都市表現はより滑らかで立体的になり、列車や建物の陰影、季節や時間帯による光の変化までも繊細に描かれた。
列車がカーブを通過する際のドット単位の動きや、駅ホームに停車した際の微妙な減速表現など、アートディンクが目指していた“リアルタイムに動く都市の呼吸”を完全に再現していたといわれている。
また、サウンドチップにはYAMAHA YM2151(8音FM音源)とOKI MSM6258(ADPCM音源)が搭載されており、PC-9801版よりも豊かな音響表現が可能だった。
とくにX68000版オリジナルのBGMは、重厚なシンセベースと軽快なブラスを組み合わせた都会的なジャズアレンジで、プレイヤーの没入感を飛躍的に高めた。音楽ファンの中には、このサウンドトラックを“ゲーム音楽史の隠れた名盤”と評する者も多い。
● 表現力の違い ― 都市の息づかいの再現度
PC-9801版とX68000版を比較すると、最も大きな違いは「動きのなめらかさ」と「風景の質感」である。 PC-9801版は8方向スクロールの限界があり、列車や背景の動きがややカクつく印象を受ける。一方、X68000版では、線路や建物の描画がフレーム単位で補完され、列車がスムーズに走行して見える。 また、背景色のグラデーションもより自然で、特に夕暮れ時の空や夜景の光が柔らかく溶け合う様子は、当時のPCゲームとしては驚異的だった。
それに加えて、X68000版は処理速度が高速なため、大規模都市を構築しても処理落ちが少なく、長時間プレイでもテンポが維持される。PC-9801版では都市が発展するにつれて動作が重くなる傾向があったため、快適性という点ではX68000版に軍配が上がる。
とはいえ、PC-9801版の淡い発色と堅実な動作には、独特の温かみがあり、こちらを好むプレイヤーも多かった。二つのバージョンは単なるスペック差ではなく、同じ設計思想を異なる表現で体験できる“二つの個性”として並び立っている。
● 操作感・UI構成の違い
インターフェース面では、PC-9801版がキーボード中心だったのに対し、X68000版はマウス操作に対応していた点が特筆される。 建設モードでは、マウスで線路をドラッグするだけで直感的に敷設でき、マップの拡大縮小やメニュー操作もスムーズだった。これにより、複雑な都市構造を作る作業が格段に快適になった。 また、情報ウィンドウの表示やグラフ切り替えなどがより高速で、複数のパネルを同時に開ける設計は、後の『A列車で行こうIII』や『A列車で行こう4』のUI設計にも大きな影響を与えている。
一方、PC-9801版はマウス非対応環境でも操作できるよう設計されており、当時のオフィスパソコンや教育現場など、マウスを常備していない環境でも動作可能だった。
結果として、PC-9801版は「堅実さと互換性」、X68000版は「操作の洗練とスピード」という方向でそれぞれ強みを持っていたと言える。
● サウンドの違い ― FM音源とADPCMの表現力
サウンド面の違いも印象的だ。 PC-9801版では主にFM音源ボード(YAMAHA YM2203または2608)を利用しており、3音~6音のシンセサウンドでジャズ調のBGMを再生する。一方、X68000版はFM音源+ADPCMの組み合わせにより、より豊かな音色と奥行きを実現した。 特にドラムパートの迫力やベースラインの重厚感は、PC-9801版では再現できない深みがあり、音楽愛好家の間では「X68版こそ本来のA列車サウンド」と語られることも多い。
また、音質の違いだけでなく、曲そのもののアレンジにも差がある。PC-9801版が軽快なスウィングジャズを基調としているのに対し、X68000版はよりフュージョン寄りのアプローチを採用している。これは機種性能を生かしたアレンジ変更であり、単なる移植ではなく“再構築されたA列車II”として位置づけられる。
● ビジュアル上の微妙な差異と雰囲気の違い
ビジュアル表現においては、X68000版の鮮やかさに対し、PC-9801版はくすんだパステル調の発色を持っている。この色味の違いがプレイヤーの印象を大きく変える。 PC-9801版では、どこか“郷愁を誘う日本的な風景”が広がり、静けさと落ち着きを感じさせる。一方、X68000版はより近代的でクールな都市空間を描き、アメリカ西海岸やヨーロッパの都市のような雰囲気を漂わせている。 同じマップでも、見せ方や色彩によってまるで異なる世界を旅しているかのような感覚が味わえるのは、当時としては非常に贅沢な体験だった。
● 技術的限界と作品への影響
一方で、両機種版とも当時のハードウェア制約と格闘していたことは確かだ。 PC-9801版ではメモリの制約により建物のバリエーションが少なく、特定条件で建設されるビルが重複するケースがあった。X68000版ではこれを改良し、グラフィックパターンを増やして街並みに多様性を持たせているが、データ容量の問題から音楽トラック数が若干削減されている。 つまり、両者はお互いに“補完関係”にあり、どちらか一方が完全上位版というわけではない。ハード性能を最大限に引き出した結果、別々の魅力を備えた双子の作品として仕上がっているのだ。
● 総評 ― 二つの“同じ世界”の異なる表現
『A列車で行こうII』は、PC-9801版とX68000版で同じゲームシステムを共有しながらも、体験の質が明確に異なる。 前者は日本の都市開発文化に根ざした「静的な完成美」を、後者はテクノロジーによる「動的な臨場感」を重視していた。 どちらのバージョンにも、アートディンクの設計思想――“街は生き物である”という哲学――が確かに息づいており、異なるアプローチで同じ夢を描いている。
この二機種版の存在は、当時のPC文化そのものの多様性を象徴している。
ひとつの作品が複数のハードウェア上で異なる顔を見せる――その魅力を最も端的に示した例こそ、『A列車で行こうII』だったのである。
● 同時期に発売されたゲームなど
★ シムシティ(Maxis/1989年/価格:9,800円)
1989年、アメリカのMaxis社が発表した『SimCity(シムシティ)』は、都市を育てるという点で『A列車で行こうII』と最も比較される存在だ。 プレイヤーは市長となり、住宅・商業・工業のゾーニングを行い、税率や公共施設を整備して街を発展させていく。 『A列車』が鉄道と経済の関係に焦点を当てたのに対し、『シムシティ』は行政とインフラの運営をテーマとした。 両作品は互いに影響を与え合い、日本のシミュレーション文化を世界レベルに押し上げた「都市開発ゲーム双璧」として語り継がれている。
★ クリスタルソフト『レリクス』(1986年/価格:7,800円)
本作は日本のパソコンゲーム黎明期における異色作で、1988年ごろにもリメイクや移植版が相次いだ。 主人公が“霊体”として他人の肉体を乗り移るという斬新な設定を持ち、アクションとストーリーが融合した幻想的な作品である。 『A列車で行こうII』がシステム面での緻密さを追求したのに対し、『レリクス』は雰囲気とテーマ性を重視した作品であり、日本製PCゲームが持つ多様性を象徴していた。
★ 光栄『信長の野望・全国版』(1986年/価格:9,800円)
歴史シミュレーションの代表格。プレイヤーは戦国大名の一人となり、日本全国の統一を目指す。 アートディンクの『A列車』が“現代の都市を創る”ゲームであるのに対し、『信長の野望』は“歴史を再構築する”シミュレーションだった。 経済・外交・戦闘を数値化した設計思想は、『A列車』シリーズの経営シミュレーションにも通じており、光栄(現コーエーテクモ)とアートディンクは“シミュレーションの双璧”と称されることもあった。
★ T&Eソフト『ハイドライド3』(1987年/価格:8,800円)
アクションRPGとして高い評価を受けた『ハイドライド』シリーズの第3作。 プレイヤーは時間・空腹・善悪値といった複雑な要素を管理しながら冒険を進める。 この“多重パラメータ制”は、のちにアートディンクの都市バランスシステムにも通じる発想といえる。 同時期にこうした「複雑さを楽しむ」ゲームが支持されていたことは、当時のPCユーザーの知的志向を物語っている。
★ スクウェア『アルファ』(1986年/価格:7,800円)
本作は宇宙を舞台にした戦略シミュレーションで、恒星間移民をテーマにした壮大な物語を描く。 PC-8801/9801シリーズで展開され、静謐な宇宙音楽と抽象的なビジュアルが印象的だった。 『A列車で行こうII』のような経済シミュレーションとは異なるが、“人類とテクノロジーの未来”を問う哲学的作品という共通点がある。 1980年代後半、日本のPCゲームはすでに単なる娯楽を越えた思想性を備え始めていた。
★ アスキー『ザ・コーポレーション』(1988年/価格:9,800円)
資本主義社会を舞台にした企業経営シミュレーション。プレイヤーは社長となり、社員の採用・株式の売買・競合企業の買収などを行う。 『A列車で行こうII』の鉄道経営シミュレーションと並び、当時の“経済を遊ぶ”ゲームとして話題を呼んだ。 アスキーらしいビジネスユーモアとリアルな企業戦略が融合しており、実際の経営教育教材として使われた例もある。
★ マイクロキャビン『XZR(エグザイル)』(1988年/価格:8,800円)
アクションとRPG要素を融合させた中東風の冒険活劇。 宗教と政治、文化の衝突といった重厚なテーマを扱い、PCゲームに物語性をもたらした。 『A列車で行こうII』が都市の中に人間社会の縮図を描いたように、『XZR』は歴史と思想の衝突を描き、当時の“表現の自由度の高さ”を象徴した作品といえる。
★ エニックス『アクトレイザー』(1989年/価格:9,800円)
厳密には家庭用ゲーム機(スーパーファミコン)向けだが、開発思想はPCゲーム文化の延長線上にあった。 アクションと都市建設の二層構造を持ち、神が地上を再生するというテーマを扱う点で『A列車で行こうII』との共通性が見られる。 後年、アートディンク作品にも“神の視点で街を眺める”という発想が受け継がれ、この時期の開発潮流の影響は無視できない。
★ スターフィッシュ『海戦シミュレーション 大海原に戦艦を見た』(1988年/価格:8,800円)
戦艦や潜水艦を指揮して戦略を立てるリアルタイム海戦シミュレーション。 『A列車で行こうII』が平和的な都市開発を描いたのに対し、本作は“戦略とリソース配分”を戦争という文脈で表現している。 いずれも限られた資源をどう使うかという思考性が中心にあり、ジャンルは異なれど根本的な“シミュレーション哲学”は共通していた。
★ エニックス『ポートピア連続殺人事件』(PC移植版/1985年→1988年再販/価格:6,800円)
堀井雄二による推理アドベンチャーの名作。1988年にはPC-9801向けに再販され、再び注目を集めた。 都市を舞台にした人間ドラマという点では、『A列車で行こうII』の“無言の街”とは対照的だが、同時代に“都市を舞台に物語を描く”流れが強まっていたことを象徴する。 シミュレーションとアドベンチャーが並立していたこの時期は、日本PCゲーム史の最も多彩な時代であった。
● まとめ ― シミュレーション黄金期の中で
1988年前後は、まさに国産PCゲームの“シミュレーション黄金期”と呼ばれる時代だった。 鉄道経営・戦国戦略・都市開発・企業運営――それぞれ異なる角度から現実社会をモデル化した作品が次々と誕生し、プレイヤーは“考える遊び”の魅力に目覚めていった。 『A列車で行こうII』はその中心にあり、他の作品たちと互いに刺激し合いながら“知的エンターテインメント”という新しいジャンルを確立した。 今振り返れば、1988年はまさに日本のPCゲーム文化が成熟し始めた節目の年だったといえるだろう。
この時代を生きたゲームたちは、いずれも「数字や構造の裏に人間ドラマを見いだす」作品群であり、その系譜は今もなお続いている。
『A列車で行こうII』は、その潮流の中で最も静かで美しい“都市の叙事詩”であり、同時代作品とともに日本のPC文化の記憶に深く刻まれている。




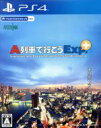

![A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[Nintendo Switch 2] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2128/nxs-p-ayayf.jpg?_ex=128x128)

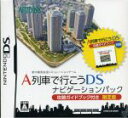
![【中古】[PS] A5 A列車で行こう5 アートディンク (19971204)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271015.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS] A.IV.Evolution Global(A.IV. エヴォリューション グローバル) A列車で行こう4 グローバル アートディンク (19951122)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270108.jpg?_ex=128x128)