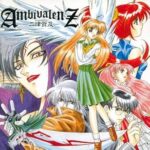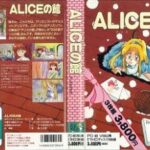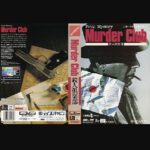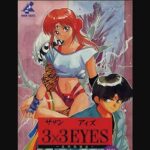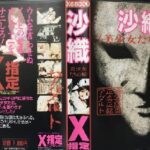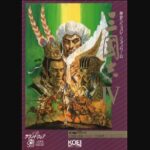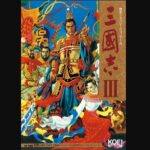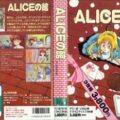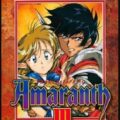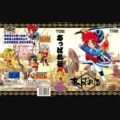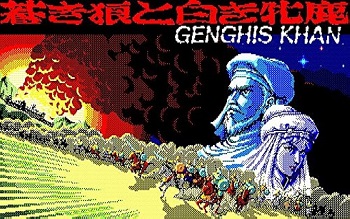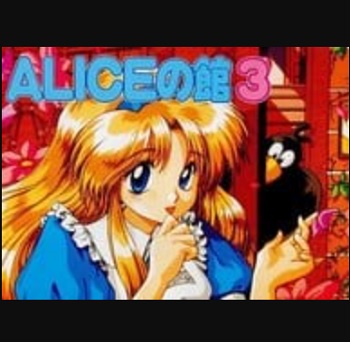
ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..




 評価 5
評価 5【発売】:アリスソフト
【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS、Windows
【発売日】:1995年4月
【ジャンル】:ゲーム集
■ 概要
シリーズの出発点と経緯
『ALICEの館3』は、1995年4月にアリスソフトからリリースされたPC用ゲーム集であり、同社の名物シリーズ「ALICEの館」の三作目にあたります。このシリーズは、アリスソフトが手掛けてきた数多くのアダルトゲームや実験的短編をまとめた“バラエティパック”的な存在で、単なるゲームソフトというよりも、同社の創作活動やファンとのコミュニケーションの一部を形にした特別な作品群でした。もともとは1989年に発売された『Rance -光をもとめて-』に収録されていた制作者コメントコーナーから派生した企画であり、ユーザーとの交流や遊び心をそのまま別商品化してシリーズ化したものといえます。
この「館」シリーズは、商業的な大作タイトルとは異なり、自由度が高く、スタッフのユーモアや未発表の試みが詰め込まれている点に特徴がありました。『ALICEの館3』もその流れを汲みつつ、PC-9801、FM TOWNS、そしてWindows版と複数の環境に対応するなど、当時のPCゲーム市場の動きを反映しています。
収録された短編ゲームの数々
本作には、アリスソフトお得意の短編アドベンチャーやミニゲームが複数収録されています。代表的なものとして、豪快なアクション要素を含む「にせなぐりまくりたわぁ」、シリアスかつ耽美的な雰囲気をもつ「哀少女ローラ」、学園を舞台にした過激な設定が印象的な「女教師悶絶地獄」、ユーモアとファンタジーが融合した「アリスのぼ~けん」などが挙げられます。これらはいずれも大作ではないものの、短時間で遊べる娯楽作品としてまとめられており、ユーザーが気軽に触れられる“実験室”のような場として機能しました。
さらに、開発の途中で没になった企画や、過去作の音楽データをまとめたBGM集も収録されており、資料的価値が高い点もシリーズならではです。通常のゲーム作品には収まりきらない試みや未完成のアイディアをそのままユーザーに提供するという姿勢は、ファンにとって「開発現場の空気を感じられる」体験でした。
「配布フリー宣言」としての意義
『ALICEの館3』が特筆すべきは、後年アリスソフトの「配布フリー宣言」の対象作品となったことです。これは同社が古い作品群を公式に無料公開し、インターネットを通じて誰もが手軽に入手・プレイできるようにした試みです。当時としては珍しい大胆な施策であり、メーカーの垣根を越えてユーザーとの距離を縮める意図が感じられました。
この方針は、作品のアーカイブ化や保存活動の面でも重要でした。90年代前半のPCゲームは、プラットフォームの多様性や媒体の寿命によって、入手が難しくなる傾向にありました。そうした中で、開発元自らが“公式に配布可能”と宣言することは、後世のプレイヤーにとって大きな恩恵となり、現在でも自由にアクセスできる点で評価されています。
当時のパソコン環境と市場背景
1995年という年は、PCゲーム市場において大きな転換期でした。PC-9801シリーズは依然として日本国内で主流のビジネス機でしたが、グラフィックやサウンドの面で限界を迎えつつあり、FM TOWNSのようなマルチメディア対応機がユーザー層を引き付けていました。さらにWindows 95の発売が目前に迫り、OSの移行期に差し掛かっていたのです。
『ALICEの館3』は、このような環境を反映して複数プラットフォームに対応しました。これにより、従来のPC-98ユーザーだけでなく、よりリッチな映像表現を楽しみたいFM TOWNS派や、これから普及するWindows環境のユーザーにも触れる機会を提供しました。作品そのものが実験的であるだけでなく、展開の仕方にも当時の技術的背景が刻まれています。
シリーズの中での位置づけ
「館」シリーズは、アリスソフトにとってファンサービスや社内文化の発露の場でした。第一作は単なるコメント集から始まり、第二作で短編や音楽を本格的に取り込み、第三作ではさらに遊びの幅を広げています。そのため『ALICEの館3』は、「シリーズの完成度を高め、実験精神をユーザーと共有する転換点」といえるでしょう。
この作品を通じてユーザーは、単なる製品版の完成ゲームだけではなく、制作途中の断片や遊び心をそのまま体験できました。これは現在でいう“開発者ブログ”や“インディーゲームのプロトタイプ公開”に近い感覚であり、90年代半ばという時代において先駆的な試みだったといえます。
■■■■ ゲームの魅力とは?
多彩な短編作品を一度に楽しめる贅沢感
『ALICEの館3』の最大の魅力は、やはり複数の短編作品をひとつのパッケージで味わえる点にあります。通常のアダルトゲームはシナリオをじっくり進める大作志向が多かったのに対し、本作ではコンパクトにまとまった物語やアイディアを短時間でプレイできます。「にせなぐりまくりたわぁ」のようなアクション寄りのバカゲー的タイトルもあれば、「哀少女ローラ」のように耽美で陰鬱な雰囲気をまとった作品も含まれており、振れ幅の大きさがプレイヤーを飽きさせません。
この“詰め合わせ”感は、まるでオムニバス映画や短編集のようで、ユーザーの好みによって気軽に取捨選択できる柔軟さがありました。大作を遊ぶ合間の息抜きとしても、アリスソフトの作風を一気に味わう入門用としても機能する、独特のポジションを確立しています。
開発スタッフの遊び心と実験精神
『ALICEの館3』では、通常の製品版には盛り込めないようなアイディアが惜しみなく投入されています。例えば、「女教師悶絶地獄」は挑発的なテーマと過激な演出で注目を集めましたし、「アリスのぼ~けん」では社内のスタッフやシリーズ既存キャラをメタ的に扱うパロディ的な展開が繰り広げられます。こうした内容は、商業作品としてはリスクが高くても、シリーズの「館」という舞台だからこそ許される自由度があり、制作者のユーモアや冒険心がそのまま形になっているのです。
当時のユーザーにとっては「ゲームの裏側を覗いているような体験」であり、これがシリーズのファンに長く愛される理由の一つとなっています。
多様なジャンルの詰め合わせによる新鮮さ
一般的なPCゲームはジャンルを明確に絞ることが多いのに対し、本作はアドベンチャー、アクション、ノベル、さらには没企画の資料的コンテンツまでが同居しています。ユーザーはプレイするたびに全く異なるジャンルを行き来するため、単調さを感じることがありません。
例えば、「にせなぐりまくりたわぁ」ではボタン連打や反射神経が問われるのに対し、「哀少女ローラ」では静かにテキストを読み進め、心理描写を堪能します。この落差こそが面白さであり、ひとつのソフトの中に“ミニゲームセンター”のような体験を持ち込んだ点が高く評価されました。
ファンにとっての資料的価値
『ALICEの館3』には、没になった企画や試作段階のデータが収録されており、これらは単なる遊びではなく、アリスソフトの歴史を知るうえで重要な資料的価値を持ちます。ファンは「こんな企画が存在していたのか」と驚き、未完成のラフスケッチや試作シナリオからスタッフの思考過程を推測する楽しみを味わいました。
これは後年、ゲーム保存活動や資料研究の分野からも注目される要素となり、単なるアダルトゲームの枠を超えた文化的意義を持つことにつながっています。
BGM集の魅力と音楽体験
短編作品に加えて、アリスソフト過去作の音楽をまとめたBGM集が収録されていた点も魅力です。当時のPCゲーム音楽はFM音源やMIDIに依存しており、プレイヤーによって再生環境の違いが大きかったのですが、本作ではそれらをひとつの形で体験できるようになっていました。
音楽はプレイヤーの記憶を呼び覚まし、過去作へのノスタルジーを刺激します。例えば『Rance』シリーズの楽曲を聴いて冒険を思い出したり、『ドラゴンナイト』系統の楽曲で熱いバトルを想起したりと、音楽が単なる付属要素を超えた意味を持っていたのです。
「配布フリー宣言」による開放感
『ALICEの館3』は後年、配布フリー作品となり、誰でも自由にダウンロードして遊べる対象となりました。このことにより、ファン同士がネット上で手軽に共有できる文化が生まれ、アリスソフト作品の“開かれた入り口”としての役割が強まりました。
商業的な利益を第一にするのではなく、ブランド文化を広めるために作品を解放する姿勢は、ユーザーにとって非常に好感を持たれました。ゲームを単なる商品ではなく「ファンとの共有財産」として扱う理念が、シリーズ全体の魅力をさらに高めているといえます。
独自のユーモアと世界観
アリスソフトといえば、シリアスな物語の中にもギャグや風刺を盛り込む独特の作風で知られています。本作でも「スタッフの悪ふざけ」と「本気のシナリオ」が同居し、プレイヤーを翻弄します。ある作品では笑い転げるようなギャグが展開され、次の作品では思わずしんみりするようなドラマが描かれる。この振り幅が、結果的に“人間味あるゲーム会社”としてのブランドイメージを強化しました。
ファンにとって、『ALICEの館3』はただのアダルトゲーム集ではなく、「アリスソフトの魂」が詰まった作品として語り継がれています。
■■■■ ゲームの攻略など
短編ごとの攻略方針を把握することの大切さ
『ALICEの館3』は一つの大作を攻略するというよりも、複数の短編ゲームをどう遊びこなすかが鍵となります。タイトルごとにジャンルもゲーム性も異なるため、まずはそれぞれの作品の特性を理解することが大切です。アクションならば操作に慣れること、アドベンチャーならば選択肢の把握やテキスト読みのリズムが重要になります。攻略の第一歩は「これはどのような遊びをさせたいゲームか」を見抜くことにあります。
「にせなぐりまくりたわぁ」の攻略ポイント
このタイトルは、単純明快な連打系のアクションゲームです。敵を倒す、障害物を突破する、そのすべてがボタン操作のスピードに直結します。攻略のコツとしては、無理に長時間プレイせず「集中できる短時間勝負」に持ち込むことです。また、リズムを体に覚えさせると連打の効率が上がり、結果的にスコアも伸びていきます。反射神経だけではなく、プレイヤーの“手の慣れ”がものを言う作品です。
「女教師悶絶地獄」での選択肢攻略
この短編はアドベンチャー形式で進み、選択肢によって展開が分岐します。難易度はそれほど高くありませんが、選択肢を誤るとバッドエンドに直行するケースが多く、プレイヤーの観察眼が試されます。ポイントは「提示される選択肢の文面を額面通りに受け取らない」ことです。開発スタッフのユーモアやひねりが効いており、時には裏をかくような行動が正解につながります。セーブ・ロードを駆使しながら全ルートを確認していくのが定石です。
「哀少女ローラ」のシナリオ攻略
この作品は、全体の雰囲気がシリアスで耽美的。選択肢よりも、シナリオを正しく追って世界観に没入することが求められます。攻略という観点から言えば、分岐よりも「テキストを読み飛ばさないこと」が重要です。伏線やキャラクターの心理描写に気付くことで、より深く物語を理解できます。クリア自体は難しくないのですが、内容をきちんと咀嚼することが真の攻略につながります。
「アリスのぼ~けん」の進行のコツ
本作の中でもユーモラスな位置づけのこの短編は、軽快なテンポで進むアドベンチャーです。キャラクター同士の掛け合いを楽しむことが中心なので、攻略というよりは「会話の流れを追う」姿勢が必要です。ただし、スタッフや既存キャラクターが多数登場するため、アリスソフト作品を遊んできたファンほど理解度が高まり、より深い笑いが得られるという構造になっています。
BGM集や没企画の楽しみ方
攻略とは少し趣が異なりますが、BGM集や没企画データの楽しみ方も一種の“攻略”です。BGMをただ聴くだけではなく、「この曲はどの作品のどの場面で流れたか」を思い出すクイズのように楽しむと記憶が鮮明になります。また、没企画は「もし完成していたらどうなっていただろう」と想像するのが醍醐味です。これらを深読みすることで、本作の魅力が倍増します。
難易度とプレイ時間の目安
本作は収録タイトルによって難易度が大きく異なります。アクション系は慣れるまで手強く感じられますが、短編アドベンチャーは比較的易しく、数十分から数時間でクリアできます。全タイトルを遊び尽くすのに必要な時間は10~15時間程度であり、大作と比べれば軽めのボリュームです。ただし、隠し要素や分岐をすべて埋めるとなると倍近くの時間が必要になるため、コレクション感覚でじっくり攻略する楽しみもあります。
裏技や遊び心を探す楽しさ
『ALICEの館3』には、制作スタッフの遊び心が随所に隠されています。特定の条件で隠し画像や隠しメッセージが現れるなど、ユーザーを驚かせる小ネタが豊富です。これらは当時のゲーム雑誌やファン同士の情報交換によって広まっていきました。攻略本のような形で体系的にまとめられてはいませんが、その“自力発見”のプロセスがプレイヤーの喜びになっていました。
効率的なプレイ方法
短編を一つずつ丁寧に進めるのもよいですが、効率的に楽しみたいなら「ジャンルの異なる作品を交互に遊ぶ」方法がおすすめです。シリアスな物語の後に軽いアクションを挟むことで気分転換になり、集中力が持続します。さらに、BGM集などを合間に聴くことでテンポがよくなり、シリーズ全体をバランスよく消化できます。
全体を攻略する上での心得
総じて、『ALICEの館3』の攻略に必要なのは、忍耐力や操作スキルではなく「作品の幅を受け入れる柔軟さ」です。ひとつのジャンルに慣れてしまうと戸惑うこともありますが、むしろその落差を楽しむことが本作の正しい向き合い方といえます。攻略とは単にクリアすることではなく、「アリスソフトの開発姿勢そのものを体験すること」なのです。
■■■■ 感想や評判
発売当時のユーザーからの第一印象
1995年4月に『ALICEの館3』がリリースされた当時、多くのユーザーは「これほど多彩な短編をまとめたアダルトゲームは珍しい」という新鮮な驚きを抱きました。パッケージを開いた瞬間に、複数の異なるゲームやコンテンツが収録されていることが分かり、ユーザーは一種の福袋を開けるような期待感を味わったのです。特にシリーズを追い続けていた熱心なファンは「今回はどんな突飛な企画が入っているのだろう」とワクワクしながらプレイを始め、アリスソフトならではの“遊び心”を再確認しました。
ゲーム雑誌やメディアの評価
当時のPCゲーム雑誌でも『ALICEの館3』は紹介されましたが、扱いはやや特殊でした。大作アドベンチャーやRPGと比べると規模は小さいものの、「アリスソフトの開発姿勢を知る上で重要な作品」と評され、ファン向けの資料的価値やユニークさに高い評価が集まりました。特にメディアが注目したのは“没になった企画の収録”や“BGM集の提供”といった実験的な部分で、「単なる遊びの域を超えた文化的アーカイブ」として紹介されたケースもあります。
ファンのコミュニティにおける評判
インターネット黎明期のファン掲示板や同人誌では、『ALICEの館3』は頻繁に話題に上りました。特定の短編作品の内容をネタに盛り上がったり、BGM集を自分の環境で再生して楽しむ報告が交わされたりと、ゲームを超えた文化的な交流が生まれました。特に「にせなぐりまくりたわぁ」のような軽快なアクションは、仲間内でスコアを競い合う遊び方も広まり、ゲーム自体よりも「誰が最も連打できるか」という雑談ネタとして活用されることもありました。
「配布フリー宣言」後の再評価
2000年代以降、『ALICEの館3』が「配布フリー宣言」対象作品として公開されると、新しい世代のプレイヤーが気軽に触れることができるようになりました。その結果、当時プレイしていなかった若いファンや研究者が「アリスソフトの90年代文化を体験できる貴重な資料」として注目し始めました。配布フリー化によって「レトロゲーム保存」の文脈でも評価され、インターネット上では「昔のエロゲーが無料で遊べる」という驚きとともに話題を呼びました。
ユーザーの好意的な感想
プレイヤーから寄せられた好意的な声には以下のようなものがありました。 – 「一つのソフトで色々な遊びができて得した気分」 – 「短編だから気軽に遊べるのが良い」 – 「没作品の資料を見られるのがファンにはたまらない」 – 「音楽が懐かしく、過去の作品を思い出した」 – 「アリスソフトのスタッフの個性が強く出ていて面白い」
これらの感想は、作品の多様性や資料的価値に好意を寄せる意見であり、「単なるエロゲーではない」ことを示しています。
否定的な意見や辛口の評判
もちろん、全てが高評価だったわけではありません。一部のユーザーや評論家は次のような否定的な意見を述べています。 – 「短編ばかりで本格的な作品を期待すると肩透かし」 – 「ボリュームが少なく感じる」 – 「作品によって完成度に差が大きい」 – 「万人におすすめできる内容ではない」
これらは本作の性格を正しく捉えた批判でもあります。大作RPGやアドベンチャーを期待するプレイヤーにとっては物足りない部分があったのは事実であり、「実験作だから仕方がない」と割り切れるかどうかで評価が分かれました。
シリーズ全体を通しての評価の位置づけ
『ALICEの館3』はシリーズの中で「中間地点」として位置づけられることが多いです。第一作の自由奔放な雰囲気、第二作での拡張性を経て、三作目では「多彩さと資料性」がさらに強調されました。後年の『ALICEの館4』以降につながる実験的姿勢が確立したことから、「シリーズの骨格を固めた作品」として高く評価されています。
後世に残した影響
この作品の存在は、アリスソフトに限らず他のメーカーにも影響を与えました。特典ディスクやファン向けミニゲーム集といった形で、未発表企画や資料を公開するスタイルが広まっていったのです。現在のゲーム業界で一般的になっている「ファンディスク」や「開発資料の公開」の先駆けとして、『ALICEの館3』は無視できない存在になっています。
総合的な評判のまとめ
総じて、『ALICEの館3』の評判は「大作を求める人には物足りないが、ファンにとっては宝物」という形に集約されます。遊びとしての満足度だけでなく、アーカイブ的な意味やスタッフの遊び心を直に感じられる点で高評価を得ており、配布フリー化によってさらにその価値は広まりました。
■■■■ 良かったところ
多様なジャンルが一度に楽しめる満足感
『ALICEの館3』の長所として最も多く挙げられるのは、収録作品のジャンルの幅広さです。アクション、アドベンチャー、シリアスなノベル、ユーモラスなパロディ、さらには没企画や音楽集といった資料性の高いコンテンツまで盛り込まれており、ひとつのソフトで複数の体験を味わえるお得感がありました。ユーザーは気分に応じてゲームを選び、飽きずに遊び続けることができたため、「ボリュームのわりに満足感が大きい」という意見が多く見られました。
アリスソフトらしいユーモアの詰め合わせ
アリスソフト作品の魅力といえば、やはりブラックユーモアや皮肉を効かせた笑いのセンスです。本作でも「にせなぐりまくりたわぁ」や「アリスのぼ~けん」に代表されるように、制作者たちの遊び心が全開でした。スタッフ自身がネタとして登場したり、既存シリーズのキャラを茶化したりするパロディ要素は、長年のファンにとって大きなご褒美となりました。シリアス作品の合間にこうした笑いを差し込む構成も巧みで、プレイヤーを飽きさせない仕掛けが随所に感じられます。
資料性の高さと歴史的価値
本作に収録された没企画や試作データは、当時としては異例の公開でした。通常、ボツになった要素は外部に出ることはなく、ファンが知る機会も限られていました。『ALICEの館3』ではそれをあえて提示することで、「開発の裏側を共有する」というユニークな姿勢を打ち出しました。この取り組みは後に研究者やアーカイブ愛好者からも注目され、アリスソフトが単に娯楽を提供するだけでなく、自らの歴史をファンと分かち合う姿勢を持っていた証拠として評価されています。
BGM集による音楽的満足度
過去作のBGMをまとめて収録した音楽集も、ユーザーから高い評価を受けました。懐かしいメロディを再び耳にすることで過去作の思い出がよみがえり、ファンは「この曲はあのシーンで流れていた」と語り合いました。当時はゲーム音楽を個別に聴く環境が整っていなかったため、公式にBGMを聴けるという点は大きな魅力でした。音楽を通じてファン同士の交流が生まれるなど、単なるおまけにとどまらない価値を生んでいます。
短時間で楽しめる手軽さ
各収録作品は大作ではなく短編に特化しているため、数十分から1時間程度で区切りがつくものが多く、忙しい社会人や学生にも遊びやすい構成になっていました。「ちょっと遊んで気分転換」「空いた時間に軽くプレイ」といった形で楽しめるのは、本作ならではの長所です。特に当時は長大なRPGやシミュレーションに時間を取られるユーザーが多かったため、このような気軽さは歓迎されました。
ファンサービスとしての側面
『ALICEの館3』は、単なる新作ゲームではなく、ファンに対する「プレゼント」的な性格を持っていました。開発途中のアイディア、ネタ的要素、スタッフの遊び心などを詰め込むことで、「ここまで見せてくれるのか」という驚きと嬉しさを提供しました。この“距離の近さ”は、他のメーカー作品にはなかなか見られない要素であり、アリスソフトがファンと一緒に楽しむ姿勢を強く打ち出していたことを物語っています。
配布フリー化による開放感
後年、配布フリー作品に指定されたことも「良かった点」として挙げられます。かつては中古市場でしか入手できなかった作品が、公式から自由にダウンロード可能となったことで、新規ファンや研究目的のプレイヤーにも広く開放されました。この方針は「ユーザーに作品を還元する」という意味合いを持ち、アリスソフトの好意的な姿勢が強く印象づけられました。
ファン同士の交流を活発にした効果
収録された内容は話題性に富んでおり、ファン同士が「どの短編が一番面白かったか」「BGMで一番好きな曲はどれか」と議論を交わす場が多く生まれました。インターネット掲示板や同人誌といった場で活発に意見交換され、単なるゲーム以上に「コミュニティを盛り上げる材料」となったのです。この波及効果は、シリーズを長寿化させる大きな原動力となりました。
シリーズの完成度を高めた点
第一作・第二作で築かれた「ALICEの館」という企画を、第三作でさらに成熟させたことも評価点です。単なる寄せ集めではなく、内容のバランスや構成に工夫が見られ、ユーザーが自然な流れで楽しめる仕上がりになっていました。これによってシリーズのブランドイメージはさらに確立し、後の『ALICEの館4』以降につながる基盤が完成したといえます。
総評としての「良かったところ」
総じて、『ALICEの館3』の良さは「遊びの多様性」と「資料的価値」、そして「ファンサービス精神」にあります。派手な大作ではないものの、アリスソフトの創作姿勢を濃縮したソフトであり、ファンにとっては宝物のような存在です。短編ながら心に残る作品や音楽に触れることができ、加えて“開発の裏側”まで覗ける体験は他に代えがたい魅力でした。
■■■■ 悪かったところ
大作ゲームを期待すると肩透かしになる点
『ALICEの館3』は短編や実験的な作品を詰め合わせたバラエティパックという性格上、「Rance」シリーズのような長編ストーリーや「大悪司」のような戦略性を持った大作を期待したプレイヤーには物足りなく感じられる部分がありました。プレイ時間も一作あたり短く、シナリオが深く掘り下げられていないため、「ボリューム不足」との声が多く挙がりました。ファンディスク的な性格を理解せず購入した人にとっては「軽すぎる」「本編と比べると中身が薄い」と映ったのです。
作品ごとの完成度のばらつき
収録作品が複数あるということは、それぞれの完成度に差が出ることを意味します。特に「にせなぐりまくりたわぁ」のようにアイディアは面白いがゲーム性は単調なものもあり、「遊びのネタとしては良いが、繰り返しプレイするほどではない」と評されることもありました。逆に「哀少女ローラ」のような短編ノベルは完成度が高く好評でしたが、全体の中で突出してしまい「もっと深掘りしてほしかった」と惜しまれる結果となりました。このアンバランスさは、詰め合わせ型作品の宿命といえるでしょう。
万人向けではない過激な内容
アリスソフト作品の特徴でもある挑発的な作風は、本作でも健在です。特に「女教師悶絶地獄」のようなタイトルは非常に過激で、当時から「人を選ぶ」内容だと指摘されていました。笑いとして受け止められるユーザーにとっては刺激的で面白いのですが、シリアス作品を好む層やストーリー性を重視するプレイヤーからは「悪ふざけが過ぎる」と否定的に受け取られることもありました。こうした極端な作風の振れ幅はシリーズの魅力であると同時に、評価を分ける要因でもありました。
収録数の割にボリューム不足と感じる人も
本作は複数の作品を収録しているものの、ひとつひとつのボリュームは小さく、短時間でクリアできる内容が大半です。そのため「数は多いが中身が薄い」と感じる人も少なくありませんでした。アリスソフトのファンであれば満足できるものの、「一つのゲームで長く遊びたい」と考えるユーザーには物足りなさが残ったのは否めません。
操作性やシステム面での不便さ
アクション系タイトルの操作性は、当時のPC環境では必ずしも快適とは言えませんでした。キーボード主体の操作は反応が遅れることもあり、ゲームパッドに対応していないことで不満を持つユーザーもいました。また、セーブやロードの仕組みが簡易的で、途中から気軽にやり直すことが難しい場面もありました。こうしたUI・操作性の不便さは、現在の視点から見ると特に際立つ欠点といえるでしょう。
統一感に欠ける構成
短編が複数詰め込まれていることでジャンルの多様性は魅力である反面、「ひとつの作品としての統一感がない」という批判もありました。プレイヤーによっては「つぎはぎの寄せ集めのように感じる」と述べる人もおり、まとまりのある一本の作品を求める層には響きにくかったのです。オムニバス的な魅力を評価するかどうかで大きく評価が分かれる部分でした。
グラフィックの古さ
1995年当時はWindows 95の発売が間近に迫り、グラフィック表現も急速に進化していた時期でした。その中で『ALICEの館3』のグラフィックはPC-9801を前提とした比較的シンプルなものが多く、「最新のゲームと比べると見劣りする」という声もありました。FM TOWNS版などでは多少リッチに表現されましたが、プラットフォームによる差は埋めきれず、グラフィック面で満足できなかったユーザーも存在しました。
一部ユーザーには理解されにくいコンセプト
「ファンディスク的な企画」という性質は、熱心なアリスソフトファンには魅力的でしたが、一般ユーザーにとっては「なぜ中途半端な企画ばかりなのか」と戸惑う要因となりました。特に『ALICEの館』シリーズを知らない新規プレイヤーがいきなり本作に触れると、「ネタが分からない」「他作品を知らないと楽しめない」と感じることが多かったのです。ファン層とライトユーザー層の間で評価が分かれるのは、このコンセプトの特殊さが理由でした。
中古市場での流通と誤解
発売当時から数年後、本作は中古ショップで比較的安価に流通しました。そのため「廉価版的なゲーム」と誤解されることも多く、作品の性質を理解しないまま購入したユーザーが「安っぽい」と否定的な感想を述べることがありました。これは作品そのものの質というよりも、販売形態や流通状況が誤解を招いた結果だといえます。
総合的な「悪かったところ」
まとめると、『ALICEの館3』の欠点は「短編ゆえの物足りなさ」「完成度のばらつき」「過激すぎる要素」「操作性やグラフィックの古さ」などに集約されます。ただしこれらは、裏を返せば「シリーズ独自の個性」や「実験的精神」の裏返しでもありました。つまり、万人に受け入れられる作品ではないが、アリスソフトのカラーを好むファンにとっては欠点すら魅力に変わるという性質を持っていたのです。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
キャラクター評価が分かれる理由
『ALICEの館3』はオムニバス形式で構成されているため、特定の主人公やメインヒロインが存在するわけではありません。その代わり、収録された短編ごとに独自のキャラクターが登場し、作品を象徴する存在として記憶に残ります。ユーザーの「好きなキャラクター」が作品ごとに分散しやすいのはこのシリーズならではの特徴です。プレイヤーは、ゲーム性だけでなくキャラクターの個性や描写の仕方に注目し、思い入れを抱くことになります。
「哀少女ローラ」のローラ
もっとも強い印象を残したキャラクターのひとりが、『哀少女ローラ』の主人公・ローラです。彼女は儚げで悲劇的な運命を背負った少女として描かれ、その繊細な心理描写や物語性がプレイヤーの心を深く打ちました。アリスソフト作品の中でも、コミカル要素を排した純粋な悲劇的キャラクターは珍しく、プレイヤーから「エロゲーという枠を超えた存在」と評されることもありました。彼女を通して「館シリーズは単なる寄せ集めではなく、本気で人間ドラマを描こうとした作品も含んでいる」という事実を強く印象づけたといえるでしょう。
「女教師悶絶地獄」の女教師
タイトルそのままに強烈なインパクトを放ったのが「女教師悶絶地獄」に登場する教師キャラクターです。誇張された表現と過激なシナリオは賛否両論を呼びましたが、その強烈な存在感によって「忘れられないキャラ」として語られることが多くなりました。良くも悪くもアリスソフトらしいキャラであり、彼女のインパクトをきっかけに本作を記憶に留めたプレイヤーも少なくありません。シリアスとは対極にあるユーモアと過激さの象徴的存在でした。
「にせなぐりまくりたわぁ」の主人公
単純明快なアクションゲームである「にせなぐりまくりたわぁ」の主人公は、キャラクター性というよりも“プレイヤーの分身”としての存在でした。しかし、その名前や世界観の馬鹿馬鹿しさが妙にツボにはまり、「あの無駄に必死な主人公が好き」という声も多く聞かれました。ストーリー性が薄いにもかかわらず、ゲームのテンポやシュールな演出によってキャラクターに愛着を持つプレイヤーがいたことは、アリスソフトのユーモアセンスの勝利ともいえます。
「アリスのぼ~けん」のキャラクターたち
「アリスのぼ~けん」には、アリスソフトの他作品からのゲストキャラやスタッフを模したキャラクターが多数登場しました。ユーザーの間で人気を集めたのは、この“お遊び”キャラクターたちです。既存作品のキャラが異なる文脈でパロディ的に描かれたり、スタッフの分身が登場したりすることで、ファンは「ここまで遊んでくれるのか」と嬉しい驚きを覚えました。好きなキャラクターというより「好きなネタ」として支持されることも多く、アリスソフトのファン文化を象徴する要素のひとつになっています。
BGM集に紐づくキャラクターたち
本作のBGM集を聴いたプレイヤーは、曲を通じて過去作のキャラクターを思い出しました。「この曲を聴くとランスを思い出す」「ドラゴンナイトの戦闘シーンがよみがえる」など、BGMによって蘇るキャラの記憶もまた“好きなキャラクター”の範疇に入っていました。直接登場するわけではありませんが、音楽を媒介にキャラクターを追体験できる点は本作ならではの楽しみ方でした。
没企画に登場予定だったキャラクター
没になったゲーム企画やシナリオ断片に登場していたキャラクターたちも、ある意味でプレイヤーに強い印象を残しました。「完成していればどんなキャラになっていたのか」と想像を掻き立てられ、ファンの間では「幻のキャラクター」として語られることもありました。こうした未完成の断片が逆に人気を集めたのは、本作が実験的かつ資料的性格を持っていた証拠です。
ユーザーによる推しキャラクターの多様性
『ALICEの館3』における“推しキャラ”は、ファンごとに大きく異なります。悲劇的なヒロインに心を奪われる人もいれば、ギャグキャラの強烈さを愛する人もおり、あるいは没企画のキャラに魅力を感じる人もいました。これほどプレイヤーごとに意見が分かれるのは、ひとつの作品に複数の方向性を内包している本作ならではの特徴です。
総合的なキャラクター評価
総じて、『ALICEの館3』のキャラクターは「深く作り込まれた大作的ヒーロー・ヒロイン」ではなく、「印象に残る個性派」や「ネタ的存在」が中心でした。だからこそ、ユーザーにとって忘れられない体験となり、それぞれの短編に独自の“顔”を与えています。ファンの記憶に強く残るキャラクターたちが散りばめられている点こそ、本作の隠れた魅力といえるでしょう。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
PC-9801版の特徴
『ALICEの館3』の中心的なプラットフォームは、やはり日本国内で圧倒的シェアを誇っていたPC-9801シリーズでした。PC-98版は当時の標準的な16色表示を基本とし、グラフィックはやや簡素ながらも実用性を重視した構成になっていました。サウンドもFM音源が主体で、プレイヤー環境によっては内蔵スピーカーのみでの体験となるケースもありました。 このバージョンは「最も普及していた」という点が重要で、幅広いユーザー層が気軽に本作を入手できました。一方で、表現面では他機種に比べると古さを感じさせる部分もあり、96年以降のWindowsやマルチメディア対応機に比べると質感に差が生じたのは否めません。
FM TOWNS版の特徴
FM TOWNS版は、当時マルチメディアPCとして売り出されていたTOWNSの強みを生かした作りになっていました。特筆すべきはCD-ROMドライブを標準搭載していたため、グラフィックデータや音声の表現に余裕があり、PC-98版よりも鮮やかな色彩と高音質なサウンドで楽しむことができました。 特にBGM集の再生においてはFM TOWNSの能力が存分に発揮され、CD-DA音源によるクリアな音質でファンの心を掴みました。また、当時としてはリッチなビジュアルも提供されており、「同じゲームでもここまで印象が違うのか」と驚かれることも多かったのです。
Windows版の特徴
Windows版は、95年当時に普及し始めていた新しいOS環境に対応したバージョンです。グラフィックの表示方法やサウンドドライバの違いから、動作が安定しており、ユーザーにとって「新しいPC環境で問題なく動く安心感」が最大の利点でした。 ただし、Windows版は移植的な性格が強く、FM TOWNS版のような映像・音声強化は見られませんでした。それでも、時代の転換期に「アリスソフトがいち早くWindows対応を進めていた」という実績は大きく、ユーザーからは「先見性がある」と評価されました。
プラットフォームごとの体験の違い
同じ『ALICEの館3』でも、どのプラットフォームで遊ぶかによって印象は大きく変わりました。PC-98版は普及率の高さゆえ「誰でも遊べる安心感」、FM TOWNS版は「リッチな音と映像による没入感」、Windows版は「次世代OSでの安定感」というように、それぞれ異なる強みを持っていました。 この違いは、ユーザー同士の交流の中でもしばしば話題にされ、「TOWNS版は音がいい」「Windows版は安定してる」「98版は一番身近」といった比較がなされました。結果的に、本作はユーザー環境に応じて複数の遊び方が存在するという特異な作品となったのです。
動作環境に依存する快適さの差
当時のPCゲームは、今のように統一されたハードウェア規格ではなく、プレイヤーの環境によって大きく快適さが左右されました。たとえば、PC-98版では搭載しているFM音源カードの種類によってBGMの聞こえ方が変わることがあり、同じ作品でも環境ごとに違う体験が生まれました。一方で、FM TOWNSは標準仕様が強みとなり、安定した音質を保証していました。Windows版は汎用性が高く、後年の環境でも比較的動作しやすい点が好まれました。
コレクター的観点からの価値
複数のプラットフォームに展開されたことで、現在ではコレクターの間で「どのバージョンを所有しているか」が話題になることもあります。PC-98版は流通量が多いため比較的入手しやすい一方、FM TOWNS版は生産数が限られており、希少価値が高いとされます。Windows版は保存状態が良ければコレクション性もあり、OSの移行期を象徴する資料として評価されています。このように、対応機種ごとの違いは、単に遊び方だけでなく、コレクションの世界でも価値を生み出しています。
シリーズの進化を象徴するマルチ展開
『ALICEの館3』が複数プラットフォームに展開されたこと自体が、アリスソフトの進化を示しています。それまでの作品はPC-98に限定されることが多かったのに対し、本作では「複数環境で同時に楽しめる」ことを意識し、結果的に多様なユーザー層にリーチすることができました。これはシリーズがファンディスク的存在から「幅広いPCユーザーへの入口」へと発展していく過程を象徴していたともいえます。
総合的なまとめ
対応機種による違いは、グラフィック・サウンド・安定性・希少性といった複数の要素に直結していました。プレイヤーがどの環境で遊んだかによって『ALICEの館3』の印象は変わり、その多様性こそがシリーズの懐の深さを示していました。結果として本作は「機種ごとに異なる体験を提供する」というユニークなポジションを築き、単なる短編集を超えて時代のPC文化を映す鏡となったのです。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1995年前後のPCゲーム市場の状況
『ALICEの館3』が登場した1995年4月は、日本のPCゲーム業界にとって大きな転換期でした。PC-9801の時代が終わりに近づき、Windows 95の登場によってOS環境が劇的に変わる直前でした。FM TOWNSはまだ健在でしたが普及率は限定的で、DOSからWindowsへの過渡期においてユーザーの関心は「どの環境でゲームを楽しむか」に集中していました。 このような時代背景の中で登場した『ALICEの館3』は、アリスソフトらしい実験的な短編集でありながら、複数プラットフォーム対応をいち早く実現した作品として位置づけられます。同時期には大作アドベンチャーやRPG、さらには美少女ゲーム市場の隆盛を象徴するタイトルが次々と登場しており、プレイヤーにとっては選択肢が豊富な時期でした。
★『同級生2』
・エルフ・1995年・8,800円前後 同時期に発売された代表的な作品のひとつが、エルフの『同級生2』です。恋愛アドベンチャーの金字塔とも言える本作は、前作『同級生』で築かれたシステムを大幅に進化させ、複数ヒロインとの関係を同時進行させる自由度の高さで高評価を獲得しました。ユーザーは日常生活をシミュレーションしながら好きなキャラクターを攻略できるため、「時間管理」「行動選択」という新しい遊びを体験しました。 『ALICEの館3』の短編集的アプローチとは対照的に、長期的な没入感を重視した本格派であり、同じ時代の美少女ゲームでありながらアプローチの違いが際立ちました。
★『To Heart』
・Leaf・1995年・8,800円前後 Leafの『To Heart』もこの頃に注目を集めたタイトルです。後の美少女ゲームのスタンダードを築いた作品であり、日常的な学園生活を舞台にしつつ、キャラクターの個性を丁寧に掘り下げるスタイルが評価されました。 『ALICEの館3』が奇抜で実験的な短編の集合体だったのに対し、『To Heart』は安定感と普遍性を重視した王道路線の作品であり、両者を比較すると90年代半ばの美少女ゲームの多様性が際立ちます。
★『下級生』
・エルフ・1995年・8,800円前後 エルフが同じ年に送り出したもう一つの代表作が『下級生』です。『同級生』シリーズの流れを汲みつつ、さらに多彩なキャラクターや広大なフィールド探索を盛り込むことで、プレイヤーに“青春群像劇”を疑似体験させる仕掛けを持っていました。攻略キャラの多さ、そして自由度の高さは、当時のプレイヤーにとって新鮮な驚きとなり、長時間遊び込めるタイトルとして支持されました。 短編の集合体である『ALICEの館3』とは真逆の「大作感」が売りであり、同時期の市場を象徴する好対照の作品です。
★『YU-NO この世の果てで恋を唄う少女』
・エルフ・1996年(開発・告知は1995年)・8,800円 厳密には翌年の発売ですが、1995年時点で話題になり始めていたのがエルフの『YU-NO』です。並行世界を行き来する壮大なシナリオと分岐構造を持ち、後に伝説的な名作とされました。開発中から雑誌で大きく取り上げられ、95年のユーザーにとっては期待値の高いタイトルのひとつでした。 『ALICEの館3』が軽快な短編集として提供する楽しさに対し、『YU-NO』は“物語を徹底的に体験させる”ことに重点を置いた対極のアプローチでした。
★『プリンセスメーカー2』
・ガイナックス・1995年・9,800円 シミュレーションRPGとして大きな注目を集めたのがガイナックスの『プリンセスメーカー2』です。プレイヤーが父親となり、娘を育成して人生を導くという斬新なテーマは、当時のユーザーに新鮮な衝撃を与えました。 アリスソフトの『ALICEの館3』とはジャンルが大きく異なるものの、共通するのは「実験的で新しい体験を提供する」という姿勢です。美少女ゲーム市場における革新性という点で、両者は同時代の挑戦者として比較されます。
★『デザイア』
・C’s ware・1994年末~1995年話題作・8,800円 C’s wareの『デザイア』もこの時期に注目を集めました。SF的な設定とサスペンス要素を組み合わせ、重厚なシナリオと大人向けのテーマ性で高く評価されました。美少女ゲームでありながら、社会派ドラマ的な雰囲気を持っていたため、プレイヤーからは「ただの恋愛ゲームではない」と称されました。 『ALICEの館3』の軽さとは真逆ですが、同じ時代に「重厚さ」と「軽快さ」という両極の作品が存在したことは市場の広がりを示しています。
★『エスカレーション・エンジェル』
・エルフ系列・1995年・7,800円 比較的ライトなアドベンチャーとして話題になったのが『エスカレーション・エンジェル』です。ポップな雰囲気と明快なストーリー展開で、重厚な大作を敬遠するユーザーに人気を集めました。『ALICEの館3』の短編的な軽さに通じるものがあり、気軽に遊びたい層にとってはちょうどよい選択肢でした。
★『河原崎家の一族2』
・elf・1995年・8,800円 サスペンスとホラー要素を取り入れたシリーズ作で、独特の緊張感がプレイヤーを惹き込みました。心理描写や人間関係のもつれが重視され、「哀少女ローラ」のようにシリアスな雰囲気を好むユーザーに支持されました。こうしたホラー系の流れもまた、当時の美少女ゲーム市場における一つの方向性でした。
★『遺作』
・elf・1995年・8,800円 同じくエルフから登場した『遺作』は、閉ざされた学園を舞台にサスペンスを展開する作品です。心理戦や選択肢による緊張感は高く、ユーザーからは「緊張感がたまらない」との声が多く聞かれました。『ALICEの館3』の実験的・ライトな性格と好対照を成し、当時の市場の幅広さを象徴するタイトルでした。
総合的な比較とまとめ
1995年前後のPCゲーム市場は、『同級生2』や『To Heart』のような正統派恋愛ADV、『プリンセスメーカー2』のような育成シミュレーション、『デザイア』や『遺作』のようなサスペンス重視の作品、そして『ALICEの館3』のように短編詰め合わせ型と、多様性に満ちていました。 『ALICEの館3』は大作と肩を並べる存在ではなくとも、軽快さと資料性、遊び心という独自の価値を打ち出したことで、この激戦期の中でも記憶に残る作品となりました。まさに「大作と小品が共存する90年代PCゲーム市場」を象徴する一例と言えるでしょう。
[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 英雄伝説IV 朱紅い雫[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004170m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチ/5インチソフト RPGツクール -Dante98-(ログインDISK&BOOKシリーズ)[3.5インチ/5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006306m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト カード型データベース アシストカード[アシストカルク体験版付][3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8922/155009819m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アンジェラス 〜悪魔の福音〜[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4538/155005895m.jpg?_ex=128x128)