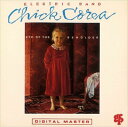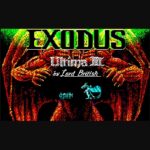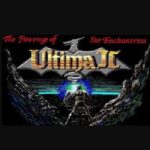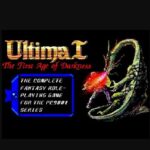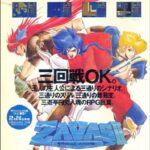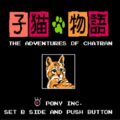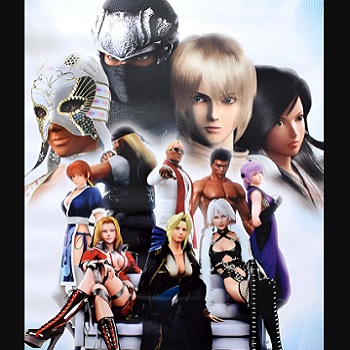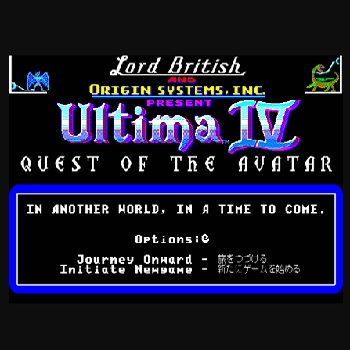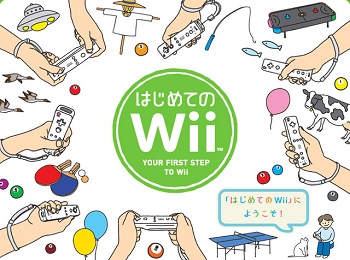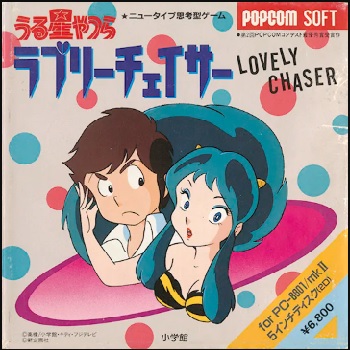【2/5はエントリーでP10倍!】G TUNE DG-I7G60 ゲーミングPC デスクトップ パソコン Core i7 14700F 32GB メモリ 500GB SSD GeForce RT..




 評価 3.88
評価 3.88【発売】:ポニーキャニオン
【対応パソコン】:PC-9801
【発売日】:1992年6月18日
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
発売と背景
1992年6月18日、ポニーキャニオンは日本のパソコン市場に向けて『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』をリリースしました。このタイトルは、もともと米国のゲームメーカーであるSSI(Strategic Simulations, Inc.)が1991年に発表した作品をベースとしています。SSIは『アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ』(AD&D)の公式ライセンスを取得していた会社であり、その豊富な経験を活かしてデジタルRPGの世界にTRPGの魅力を落とし込むことに長けていました。本作もまさにその成果のひとつであり、クラシックなテーブルトークRPGの雰囲気を画面上に再現しようとした意欲的なプロジェクトだったのです。
日本での発売にあたり、ポニーキャニオンはPC-9801シリーズを主力対象としました。当時のPC-9801は国産パソコンの主流であり、RPGを楽しむゲーマー層が厚く存在していました。TRPGの知識を持つプレイヤーだけでなく、「ダンジョン探索型RPG」というジャンルを新鮮に感じるパソコンユーザーに広く受け入れられる土壌が整っていたのです。
物語の舞台設定
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の物語は、架空の都市ウォーターディープの地下で巻き起こる異変から始まります。この都市は『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の世界観をベースにした「フォーゴトン・レルム」キャンペーンセッティングの中心的な都市であり、多くの冒険者が行き交う巨大都市として知られています。
物語の導入はシンプルでありながらプレイヤーの想像力を大きく刺激するものでした。ウォーターディープの支配者ケルベン・アランソンは、市民を脅かす不穏な気配が地下から迫っていることを察知します。そしてプレイヤーが操る冒険者の一行は、都市を守るためにその地下迷宮へと調査に乗り込むことになります。プレイヤーに課せられた使命は「地下に潜む邪悪の源を突き止め、討ち払うこと」。この明確かつ重厚な目的が、ダンジョン探索の動機づけとして機能していたのです。
ゲームシステムの基盤
本作の最大の特徴は、アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ第2版のルールを基盤に設計されていることです。キャラクターの種族や職業、ステータスの計算式、戦闘の仕組みなどが原作ルールブックに忠実に再現されています。
例えば、プレイヤーは冒険の開始時に4人のキャラクターを自分で作成します。種族は人間、エルフ、ドワーフ、ハーフリングなどから選び、職業は戦士、魔法使い、僧侶、盗賊などが用意されていました。それぞれの組み合わせによってパーティの特色が大きく変化し、自由度の高いキャラクターメイキングを実現していたのです。また冒険を進める中で仲間となるNPCをパーティに加えることもでき、最大で6人の隊列を組んで迷宮を攻略していく流れになります。
戦闘はリアルタイム進行で、敵と遭遇するとその場で攻撃や魔法の指示を出すことになります。完全なターン制ではなく、プレイヤーの反応速度や指示のタイミングが結果を左右する点が、従来のPC-RPGと異なるスリルを生み出していました。
3Dダンジョン表現
画面表示は擬似的な3D方式を採用し、プレイヤーは一人称視点で迷宮内を進んでいきます。通路や部屋がマス目状に区切られ、それをスムーズに移動することで探索が進行するスタイルは、当時としては非常に先進的でした。
敵やアイテムが出現する位置、扉や仕掛けの場所、隠し通路などを一つひとつ自分で発見していく必要があり、探索の達成感は抜群でした。プレイヤーによっては方眼紙にダンジョンマップを自作していくなど、昔ながらのTRPG的な遊び方も復活させることになったのです。
開発スタッフと移植展開
本作の開発は、後に世界的なゲームスタジオとして名を馳せるWestwood Studiosが担当しました。ディレクターを務めたブレット・W・スペリーは、過去に『DragonStrike』などのファンタジー作品に携わっており、その経験を存分に活かして本作を完成させました。
音楽にはポール・S・ムードラが参加し、重厚で幻想的なBGMを構築。プレイヤーを中世ファンタジーの世界へと深く没入させる役割を担いました。後に移植版がAmigaやメガCD、スーパーファミコンといった複数のプラットフォームに展開され、日本では特にメガCD版の音楽を古代祐三や川島基宏が手掛け、さらに効果音には崎元仁が関わるなど豪華な布陣が話題となりました。
また、操作面においては元々PCのマウス操作を前提に作られていたため、SFC版はスーパーファミコンマウスに、メガCD版はセガマウスに対応するなど、ハードごとの工夫が凝らされていました。
当時のパソコン市場との関係
1990年代初頭の日本のパソコン市場は、国産独自規格のPC-9801シリーズが支配的でした。グラフィック性能やサウンド機能はまだ限られていましたが、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』のような先進的なダンジョンRPGは、ユーザーに「パソコンでしか味わえないゲーム体験」を強烈に印象づけました。
それまでの日本製RPG、たとえば『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』のようなコマンド式ターン制RPGに慣れたユーザーにとって、本作のリアルタイム制バトルと自由度の高い探索は大きな衝撃であり、RPGジャンルの多様性を広げる一因となったのです。
総合的な位置づけ
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は、単なるダンジョン探索型RPGにとどまらず、テーブルトークRPGの精神をデジタルへ落とし込んだ記念碑的作品でした。その後のRPG史においても、「西洋的ファンタジーRPGの魅力」を日本のプレイヤーに強く伝えた存在であり、後のゲーム開発者にも多大な影響を与えました。
特にパーティ制や一人称視点、リアルタイム戦闘という要素は、その後のPCゲームやコンソールRPGに継承され、ジャンルの発展を後押ししていくことになります。
■■■■ ゲームの魅力とは?
自由度の高いキャラクターメイキング
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の大きな魅力の一つは、冒険の始まりからプレイヤーが自分の手でパーティを作り上げられる自由度にありました。キャラクターの種族や職業を選び、能力値を振り分ける過程は、TRPGを知っている人にとってはおなじみの楽しみであり、初心者にとっても「自分だけの英雄を作る」という実感を味わえるポイントでした。
戦士は前衛で盾役を担い、魔法使いは強力な呪文を駆使し、僧侶は回復や補助にまわる。盗賊は罠の解除や鍵開けといった探索に欠かせない役割を持ちます。こうした職業の組み合わせによってパーティの性格は大きく変わり、同じゲームでもプレイスタイルが全く異なる体験となるのです。
緊張感を生むリアルタイム制バトル
従来の多くのRPGはターン制を採用していましたが、本作ではリアルタイムで敵との戦闘が進行します。敵が襲い掛かってくる状況で、プレイヤーは即座に「攻撃」「魔法」「回復」「アイテム使用」といった行動を選択しなければなりません。
この仕組みは、戦術的な判断だけでなく、反射神経や冷静さをも問うものになっていました。通路の角を曲がった瞬間にモンスターと鉢合わせしたり、背後から襲撃されたりする場面では、焦って誤った指示を出すとパーティ全滅につながる緊張感がありました。RPGに「アクション性」という新たな要素を持ち込んだ点は、当時として非常に斬新でした。
探索の面白さとダンジョンデザイン
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は、単なる戦闘だけでなく探索そのものの楽しさに重点が置かれています。ダンジョン内には隠し扉や落とし穴、仕掛けや謎解きが多数配置され、プレイヤーは五感を研ぎ澄ませて進む必要がありました。
特に仕掛けはシンプルながら巧妙に作られており、「この壁は怪しい」「床の模様が不自然だ」と気づいた時の快感は大きなものでした。謎を解き明かした瞬間に新たな通路が開け、物語の核心へと近づいていく感覚は、このゲームならではの魅力です。
グラフィックと音楽の臨場感
グラフィックは今の基準からすればシンプルですが、当時のパソコンRPGとしては非常に洗練されていました。石造りの通路や不気味に光る松明、迫りくるモンスターの姿は、プレイヤーの想像力を刺激し、恐怖や緊張感を高める役割を果たしました。
さらに音楽や効果音がその臨場感を一層引き立てています。重厚なBGMが迷宮の不気味さを強調し、扉が軋む音やモンスターの咆哮がプレイヤーを画面の向こうの世界へと引き込みました。特にメガCD版では古代祐三らの手によって楽曲がアレンジされ、ハードごとの魅力を最大限に引き出していた点も注目すべきポイントです。
仲間NPCの存在感
探索を進める中で仲間として加わるNPCは、単なる戦力補強にとどまらず、物語を彩る存在でした。彼らには背景や動機が設定されており、どの仲間を加えるかによってプレイ体験は微妙に変わっていきます。
時にはプレイヤーの判断で加入を断ることもでき、その選択が冒険の雰囲気を変えることもありました。こうした「自分の選択によって冒険が形作られる感覚」こそ、本作が高く評価される理由の一つです。
テーブルトークRPGの再現性
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は、AD&D第2版のルールをベースにしているため、TRPG経験者にとっては馴染み深く、初心者にとってはTRPGのエッセンスを手軽に味わえる作品でした。サイコロを振って能力を決定するような要素や、ルールブックに則った呪文体系など、原作ファンを満足させるディテールが詰め込まれています。
こうした「紙と鉛筆で遊んでいた体験をデジタルで楽しめる」という点が、当時のプレイヤーに強い魅力を与えました。
繰り返し遊べるリプレイ性
同じダンジョンでも、パーティ編成を変えることで全く異なる攻略体験が生まれる点も本作の魅力でした。戦士を多めにすれば力押しの戦闘が可能ですが、魔法使いを中心に据えれば一撃必殺の魔法を駆使する戦略が取れます。盗賊を重視すれば罠解除や探索がスムーズになり、より安全な冒険ができます。
このリプレイ性の高さによって、プレイヤーは何度もゲームをやり直し、自分なりの理想的なパーティを追求する楽しみを味わえたのです。
総評としての魅力
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は、RPGの基本要素である「成長」「戦闘」「探索」を高次元で融合させた作品です。そこにリアルタイム進行や自由なキャラクターメイキングが加わることで、当時の他のRPGにはない独自の体験を提供していました。
このように、本作は単なるゲームを超えて「ファンタジー世界での冒険」を強く実感させるものとなり、その魅力は今なお色あせることがありません。
■■■■ ゲームの攻略など
序盤の進め方と心構え
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の攻略を語る上で、まず触れなければならないのは序盤の立ち回りです。ゲーム開始直後、プレイヤーは比較的弱い装備と低いレベルのキャラクターでダンジョンに挑むことになります。そのため、いきなり敵に突っ込むのではなく、まずは慎重に行動範囲を広げ、少しずつ経験値を積み重ねることが重要です。
序盤は特に回復手段が限られているため、僧侶の呪文を使うタイミングや休息の判断が大きな意味を持ちます。戦闘後に無理をして奥へ進むよりも、一度引き返して安全地帯で休むことでパーティを立て直すのが王道の戦術です。この「引き際を見極める」姿勢が、長期的な攻略において大きな差を生みます。
職業ごとの役割と使い方
攻略の中核となるのが、各職業の役割分担です。戦士は前衛で攻撃と防御の要となり、敵の攻撃を受け止める役割を担います。装備できる武具が多いため、強力なアイテムを手に入れた時に真価を発揮します。
僧侶は回復魔法や補助呪文でパーティを支える存在であり、毒や麻痺といった状態異常の治療にも不可欠です。魔法使いは序盤こそ呪文の使用回数が少なく頼りないものの、中盤以降は強力な攻撃魔法で戦局を一変させる切り札になります。盗賊は戦闘力こそ控えめですが、罠解除や鍵開けといった探索において欠かせない能力を持っています。
これらの職業の役割を理解し、バランスの取れたパーティを編成することが、安定した攻略につながります。
中盤の壁と突破法
中盤に差し掛かると、敵の攻撃力や耐久力が大幅に上がり、序盤のような力押しでは通用しなくなります。特にアンデッド系モンスターや魔法を操る敵が登場すると、戦闘の難易度は飛躍的に高まります。
この段階で重要なのが「リソース管理」です。呪文やアイテムを温存するか、ここぞという場面で一気に使うかの判断が攻略を左右します。また、マップ全体を探索して有用なアイテムを集めることも大切です。例えば強力な武器や防具は、見逃せない隠し部屋や謎解きの先に用意されていることが多いため、徹底した探索が必要になります。
謎解きと仕掛けの攻略
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の魅力的な要素のひとつに、多彩な謎解きや仕掛けがあります。壁の模様に隠されたスイッチ、特定のアイテムを置くことで作動する装置、順序を間違えると閉じ込められてしまう部屋など、ダンジョンはプレイヤーを試す仕掛けに満ちています。
攻略のコツは、細部に注意を払い、怪しいと思った場所をくまなく調べることです。時には「このアイテムには用途がない」と思ったものが後の謎解きに必要となる場合もあります。安易に捨てず、手持ちの装備やアイテムを整理しながら進む柔軟さが求められるのです。
終盤の強敵とラスボス戦
ゲームの後半になると、プレイヤーは数々の強敵と対峙することになります。特に魔法を多用する敵や、状態異常を付与してくるモンスターは脅威です。パーティ全体のレベルを十分に上げ、装備を整えて挑むことが前提となります。
ラスボス戦では、単に力をぶつけるだけでは勝利できません。戦士が盾となって敵の攻撃を受け止め、僧侶が絶え間なく回復し、魔法使いが強力な呪文を叩き込み、盗賊が隙を突いて攻撃する。全員が役割を果たしてこそ、勝利への道が開けるのです。この総力戦の緊張感こそが、本作のクライマックスにふさわしいものでした。
裏技や小技の存在
一部のバージョンでは、操作の工夫やバグを利用することで有利に進められる裏技が存在しました。例えば特定の手順で敵をはめて行動不能にしたり、セーブとロードを駆使してアイテムを複製したりする方法が、攻略本や雑誌で紹介されたこともあります。
ただし、こうした裏技を使うかどうかはプレイヤー次第であり、純粋に試行錯誤しながら突破する達成感を大切にする人も多くいました。
攻略の本質
結局のところ、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の攻略の本質は「準備」と「観察」に尽きます。十分な休息、パーティのバランス、持ち物の管理、そしてダンジョンの隅々に注意を払う観察眼。これらを積み重ねてこそ、迷宮の奥深くに潜む真実へとたどり着けるのです。
プレイヤーは常に緊張感と達成感を味わいながら、困難を一歩ずつ乗り越えていく。この「困難を克服する快感」こそが、本作の攻略の醍醐味であるといえるでしょう。
■■■■ 感想や評判
当時のプレイヤーの第一印象
1992年当時、日本のPCユーザーにとって『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は非常に新鮮な体験でした。最初に目にするのは石造りの地下迷宮。薄暗い通路や重厚な扉がプレイヤーを迎える演出は、従来の国産RPGにはあまり見られなかった“本格的な洋風ダンジョン探索”の空気を強烈に印象付けました。
多くのプレイヤーは「緊張感が桁違いだ」と感じ、角を曲がるたびに息を呑むような体験を語っています。一歩一歩が未知との遭遇であり、敵の姿を視認するまでのドキドキ感がとにかく強かったのです。
雑誌やメディアでの評価
当時のPCゲーム雑誌では、本作はしばしば高い評価を受けました。特にリアルタイム制のバトルや、TRPGを忠実に再現したシステム面が注目を浴び、「これまでの日本製RPGとは一線を画す作品」と紹介されています。
一方で、難易度の高さに対しては賛否が分かれました。攻略本なしで完全クリアするには相当な根気と観察力が必要であり、「やりがいがある」と賞賛する声と「敷居が高い」と感じる声の両方が存在したのです。
熱心なファン層の形成
本作は、単なる一過性の話題作にとどまらず、熱心なファン層を形成しました。特にテーブルトークRPG経験者からは「AD&Dをここまでデジタルに落とし込めるとは思わなかった」という驚きと喜びが寄せられました。
また、方眼紙にマッピングしながら遊ぶスタイルを復活させたという意味でも、古くからのゲーマーに強いノスタルジーを呼び起こしました。家庭用ゲーム機でRPGに親しんでいた層とはまた異なる“濃い”ユーザー層に支持されたのです。
不満点に対する声
もちろん、全てが絶賛というわけではありませんでした。日本語版における翻訳のニュアンスやインターフェースの使い勝手に不満を持つ声もありました。特に当時のPC環境では動作が重いと感じるユーザーもおり、「遊びやすさよりも本格派志向に振り切っている」という評価を下す人もいました。
ただし、それらの不満を差し引いても「挑戦しがいのある硬派なRPG」としての評価は揺らぐことはなく、むしろ「万人向けではないが、ハマる人には深く刺さる」という個性的な立ち位置を確立していたのです。
海外での評価との比較
海外においても『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は高く評価されていました。特にアメリカやヨーロッパのゲーム誌では「西洋ファンタジーの世界観を忠実に描き出した傑作」と評され、続編の開発につながるほどの人気を博しました。
日本国内ではRPGといえばドラクエやFFといったJRPGが主流だったため、リアルタイム戦闘や西洋風ダンジョン探索に馴染みのない層にはやや取っつきにくい面がありました。しかし一方で、「海外のRPGはこんなにも奥深いのか」と衝撃を受けたユーザーも多く、後のウルティマシリーズやウィザードリィリメイク作品の人気にも影響を与えたと考えられます。
リプレイ性への評価
評判の中で特に多く挙げられたのが、リプレイ性の高さでした。パーティの編成を変えるだけで攻略難易度や進め方が大きく変わり、何度でも遊び直せるという点は、雑誌のレビューやユーザーの感想でも好意的に取り上げられています。
「次は魔法使いを2人にして挑戦してみよう」「盗賊を外したらどうなるか試したい」といった具合に、試行錯誤そのものが楽しみと化すゲームデザインが支持されたのです。
現代から振り返った評価
発売から30年以上が経った今、レトロゲーム愛好家の間では『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は「クラシックRPGの名作」として語られます。システムやグラフィックは時代を感じさせますが、その硬派な設計思想や独特の緊張感は現代のプレイヤーにも新鮮に映ります。
インディーゲームが隆盛を迎える現代においても、「本作のDNAは今なお生きている」と評されることが多く、リメイクや精神的続編を望む声も根強いのが特徴です。
総合的な評価
総じて、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は「難しくも奥深い名作」として記憶されています。万人向けではないが、挑戦を好むプレイヤーにとっては至高の一作であり、当時の日本市場に「洋ゲーRPG」の存在感を強く印象付けた作品でした。
熱烈なファンを獲得しつつ、賛否が分かれる硬派な作風。その評価の二極化こそが、本作の独自性と存在意義を物語っているといえるでしょう。
■■■■ 良かったところ
本格的な西洋ファンタジーの世界観
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の良かった点として最初に挙げられるのは、徹底した西洋ファンタジーの再現度です。日本のRPGは当時すでに数多く存在しましたが、どこか日本的な解釈が入り込み、完全に海外的な雰囲気を感じられる作品は限られていました。ところが本作は、TRPG「アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ」の公式ルールに基づき、舞台やキャラクター設定が細かく作り込まれていたため、「海外の物語をそのまま冒険している」ような没入感を味わえました。プレイヤーはただ敵を倒すだけでなく、ウォーターディープという都市の背後にある文化や伝承までも想像できる豊かさを感じられたのです。
緊張感のあるダンジョン探索
本作の探索は、常に一歩間違えば全滅の危険をはらむ緊張感に包まれていました。通路を進むごとに「次の角には何があるのか」「この扉を開けたらどうなるのか」という不安と期待が交錯します。この感覚は、ただマップを埋めていくだけではなく、自分自身が迷宮の奥へ足を踏み入れているようなリアリティを伴っていました。
特に隠し扉や罠の存在は、プレイヤーに注意深い観察を促しました。「ここで見逃したら後悔するかもしれない」というプレッシャーは、緊張を楽しさに変えてくれる重要な要素だったのです。
自由度の高いパーティ編成
冒険に臨むパーティを自分で作り上げられる自由度は、多くのプレイヤーにとって最高の魅力でした。どんなメンバーを選ぶかで戦略が変わり、「今回は魔法主体でいこう」「次は力押しの戦士集団で挑んでみよう」といった具合に、遊ぶたびに異なる冒険が楽しめました。
この自由度は、同じゲームを繰り返し遊ぶ動機にもつながりました。リプレイするたびに新しい発見があり、プレイヤーは「自分だけの冒険譚」を築き上げることができたのです。
緻密な謎解きと仕掛け
ダンジョンに配置された謎解きや仕掛けは、ゲームを単調にさせない工夫として高く評価されました。単なる敵との戦闘だけではなく、壁に仕掛けられたスイッチや、特定のアイテムを使わないと解けない謎がプレイヤーを待ち受けていました。
プレイヤーは「知恵と観察眼」を武器にして挑むことになり、謎を解いた瞬間の達成感は格別でした。この「戦闘だけでなく頭脳も駆使するRPG」という点は、当時のゲームにおいて非常に新鮮で、良かった点としてしばしば感想に挙げられています。
雰囲気を盛り上げる音楽と効果音
音楽と効果音の演出は、ゲームの雰囲気を支える大きな柱でした。荘厳で緊張感のあるBGMは、ダンジョン探索の恐怖とワクワク感を一層引き立てました。さらに扉が軋む音、モンスターの咆哮、アイテムを拾うときの効果音など、細部まで作り込まれたサウンドはプレイヤーの想像力を刺激しました。
特にメガCD版の音楽は、古代祐三ら著名な作曲家による手掛けられたものであり、その完成度の高さは多くのユーザーの記憶に残っています。「音楽が冒険の一部になっていた」という声も少なくありませんでした。
TRPGファンをうならせるルール再現
AD&D第2版のルールを取り入れたことで、TRPG経験者にとっては「紙と鉛筆で遊んでいた世界が目の前に広がった」と感じられる作品でした。ステータスの扱いや呪文の構造が忠実に再現されており、「これは間違いなくAD&Dだ」と納得させる説得力がありました。
単なるコンピュータゲームとしてだけでなく、TRPGを知る人々にとって「自分が遊んできた世界をPCで再体験できる」喜びがあったのは、本作ならではの大きな利点でした。
硬派な難易度とやりごたえ
本作は簡単にクリアできるゲームではありません。しかし、この「難しい」という評価こそが良い点として挙げられる場合もありました。攻略の過程で何度も全滅し、工夫と努力を重ねてようやく突破したときの達成感は、易しいゲームでは得られないものでした。
「挑戦を乗り越えることで得られる満足感」がゲーム全体を貫いており、それを好むプレイヤーにとっては非常に魅力的だったのです。
プレイヤーの創意工夫を刺激
限られたリソースの中でどう戦うか、どの呪文をどのタイミングで使うか、敵との距離をどう取るかなど、プレイヤーの判断が結果を大きく左右しました。攻略本や解説に頼らず、自分の知恵で困難を乗り越えたときの喜びは格別であり、プレイヤーに「工夫して挑戦する楽しさ」を教えてくれました。
このように「考える余地」を多く残していた点が、長く遊ばれる要因にもなったのです。
総合的な「良かったところ」
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は、世界観の重厚さ、探索の緊張感、自由度の高いパーティ編成、謎解きの面白さ、音楽の臨場感など、複数の要素が高い次元で組み合わさっていました。プレイヤーに「本物の冒険」を体験させる力があり、その完成度は当時のPCゲームの中でも群を抜いていました。
一言でまとめれば、「挑戦心をくすぐる骨太なRPG」。これこそが、多くのユーザーが本作を記憶に残る名作として語り継いでいる理由なのです。
■■■■ 悪かったところ
難易度の高さによる敷居の高さ
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』は硬派なゲームとして知られていますが、それは同時に「難しすぎる」という評価にもつながりました。序盤から敵の攻撃が苛烈で、少し気を抜くだけで全滅することも珍しくありません。ゲームバランスはあえて厳しく設計されており、TRPGに慣れたプレイヤーにはやりごたえと映りましたが、家庭用RPGに慣れたユーザーには「とっつきにくい」と感じられました。
特に序盤でパーティ編成を誤った場合、進行が極端に困難になることがありました。柔軟にリカバリーできないシステムが、新規ユーザーの心を折る原因になったのです。
インターフェースの不便さ
本作は当初マウス操作を前提に作られていたため、日本のPCユーザーにとっては馴染みにくい操作体系になっていました。キーボードだけでの操作は直感性に欠け、戦闘中の素早い判断を妨げる場面も多々ありました。
また、メニューの配置やコマンド選択がやや複雑で、「アイテムを使う」「魔法を唱える」といった基本動作に時間がかかることがありました。戦闘がリアルタイム進行である以上、この操作性の悪さはストレスにつながりやすかったのです。
翻訳の問題点
日本語版における翻訳は、当時としては丁寧に行われていた部類ではありますが、専門用語の多さや直訳的な表現がプレイヤーの理解を妨げることがありました。AD&Dのルールに準じた用語はTRPG経験者には分かりやすいものの、一般ユーザーには馴染みがなく、「なぜこの呪文はこういう効果なのか」と混乱する場面も見られました。
物語上の会話や説明文も硬い印象があり、没入感を削ぐ要因となったと指摘する声もありました。翻訳の質が作品全体の印象を左右したのは事実でしょう。
ビジュアル面の物足りなさ
当時としては優れた3D表現を導入していたとはいえ、ビジュアル面に関しては「単調さ」を指摘する声もありました。ダンジョンの景色が似通っており、長時間プレイすると「どこを歩いているのか分からなくなる」と感じるプレイヤーも少なくありませんでした。
また、敵グラフィックのバリエーションが限られていたため、後半になると新鮮味が薄れてしまうという意見もありました。物語の背景を盛り上げるには十分でしたが、視覚的な多様性に欠けていたのは否めません。
セーブやロードの制約
セーブ機能に関しても、一部のプレイヤーは不満を抱いていました。好きな場面で気軽にセーブできない仕様や、ロードのテンポの悪さが、攻略中のストレスにつながったのです。
特に全滅後の復帰が煩雑で、「やり直しに時間がかかる」ことはユーザー体験を損なう要因でした。やりごたえを重視した設計の裏返しとして、不親切さが目立つ結果になったといえるでしょう。
テンポの悪さ
探索そのものが醍醐味である一方で、その進行速度は決して速くありません。階層を一つ進むごとに何度も戻り、体勢を整えてから再挑戦する必要がありました。この繰り返しが「緊張感」と「達成感」を生み出していた反面、「作業感が強い」と捉える人もいました。
また、リアルタイム戦闘といえどもアニメーションは簡素で、攻撃や呪文の演出に迫力が欠けていた点もテンポの悪さを助長しました。
ライトユーザーへの不親切さ
RPG初心者やライトユーザーにとって、本作はあまりに敷居が高く、チュートリアル的な要素も不足していました。「どう進めていいか分からない」「攻略本がないと理解できない」といった感想は多く見られました。
結果として、幅広い層に浸透するというよりも、限られた熱心なファン層に支持される形になってしまったのです。
総合的な「悪かったところ」
まとめると、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』の欠点は「本格志向がゆえの敷居の高さ」に集約されます。難易度の高さ、操作性の不便さ、翻訳の硬さ、ビジュアルの単調さなど、ライトユーザーにとっては障壁となる要素が多く存在しました。
しかし同時に、それらの欠点は「硬派で挑戦的な作品」という個性を際立たせる要因でもありました。万人受けはしなかったものの、熱心なゲーマーにとってはむしろ魅力的に映ったのです。
[game-6]■ 好きなキャラクター
プレイヤーが創り出すキャラクター
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』において特筆すべきは、プレイヤーが自分でキャラクターを作り上げる仕組みにあります。名前・性別・種族・職業・能力値を組み合わせることで、自分だけの冒険者を生み出せるのです。そのため、「好きなキャラクター」とは単にゲームに用意された人物ではなく、プレイヤー自身が思い入れを込めて育て上げた存在になります。
「自分が初めて作った魔法使いが一番忘れられない」「前衛で戦い抜いたドワーフ戦士に感情移入していた」など、プレイヤーごとに異なる「推しキャラ」が存在するのは、このゲームならではの特徴です。まさに“自分の物語の主人公”を作り上げられる点が、多くの人にとって好きなキャラクターにつながっていました。
頼れる前衛 ― 戦士系キャラクター
多くのプレイヤーが支持するのは、やはり戦士系のキャラクターです。重装備でパーティの最前線に立ち、仲間を守りながら敵を切り伏せる姿は、冒険の象徴といえます。特にドワーフ戦士や人間戦士は耐久力が高く、最後まで仲間を守り抜く頼もしさが印象に残ります。
「このキャラがいたから全滅を免れた」という経験は多くのプレイヤーが語っており、彼らは単なるゲーム上の駒ではなく“仲間”として強く記憶されているのです。
知略の要 ― 魔法使い
魔法使いは序盤こそ打たれ弱く、成長の遅さから苦労させられる存在です。しかし、中盤から後半にかけて強力な呪文を習得すると、その存在感は一気に増します。敵の群れを一掃する火球、強力な防御魔法、探索を助ける便利な呪文。戦局をひっくり返す一撃を放つたびに、プレイヤーは魔法使いへの愛着を強めていきます。
「序盤で守ってあげたキャラが、終盤ではチームの切り札になる」という成長の物語性も、多くのプレイヤーにとって心に残るポイントでした。
陰の功労者 ― 盗賊
派手さはないものの、多くのプレイヤーが「なくてはならない」と語るのが盗賊です。罠を解除し、鍵を開け、ダンジョンの探索をスムーズにしてくれる彼らは、戦闘では控えめでも冒険全体の安定感を支えてくれます。
一見地味な役回りが、長い冒険を続けるほどに「このキャラがいないと困る」という存在感に変わっていく。そうした影の功労者としての立ち位置が、盗賊を「好きなキャラクター」として挙げる理由になっているのです。
癒しと信頼 ― 僧侶
僧侶は回復と補助のスペシャリストとして、パーティを陰から支え続けます。戦士がダメージを受けても、僧侶の存在があればすぐに立ち直れる。毒や麻痺などの厄介な状態異常を治すこともでき、冒険の継続に不可欠な役割を担っていました。
プレイヤーの感想として「僧侶がいなければここまで進めなかった」「回復呪文の安心感が心強かった」といった声が多く見られ、頼れる存在として好感を持たれていました。
途中で加わる仲間NPCたち
物語を進める中で登場するNPCたちも、プレイヤーの好きなキャラクターとしてしばしば挙げられます。彼らは固有の背景を持ち、特定の条件で仲間になってくれる存在です。性格や能力が異なるため、誰をパーティに迎えるかはプレイヤーの選択次第であり、冒険の雰囲気を変える要素となりました。
特定のNPCに感情移入し、何度も仲間に迎え入れるプレイヤーも少なくなく、「固定の4人ではなく、仲間をどう活かすか」という戦略性を楽しめたのです。
プレイヤーごとの思い入れ
『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』のキャラクターに対する愛着は、プレイヤーごとに全く異なります。同じゲームを遊んでいても、ある人にとっては「魔法使いが一番好き」になり、別の人にとっては「頼れる戦士が一番心に残った」となる。その違いこそが、このゲームの魅力の一つでした。
固定された主人公がいないからこそ、プレイヤー自身の体験や選択が「好きなキャラクター」を形作っていく。そこに本作の奥深さと、語り継がれる理由があるのです。
総合的な魅力としてのキャラクターたち
最終的に、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』における「好きなキャラクター」とは、特定の一人を指すのではなく「自分が一緒に冒険した仲間たちすべて」だといえるでしょう。前衛で盾となった戦士も、最後に決定打を放った魔法使いも、罠を解除して道を切り拓いた盗賊も、癒しを与えてくれた僧侶も、それぞれが冒険の中で欠かせない存在となり、プレイヤーの記憶に刻まれています。
「誰か一人を選ぶことが難しいほど、みんなが大切な仲間だった」。この感想が多くのプレイヤーに共通している点こそ、本作が愛される理由を物語っているのです。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
PC-9801版 ― 日本市場の中心的存在
1992年にポニーキャニオンからリリースされたPC-9801版は、日本国内における本作の代表的なバージョンでした。NECのPC-9801シリーズは当時の標準的なパソコンであり、特にビジネス層や学生層に幅広く普及していたため、最も多くのユーザーが触れたのはこのバージョンだったといえるでしょう。
グラフィックは16色表示ながらも、精細なドット絵によってダンジョンの雰囲気を十分に描き出しており、日本人ユーザーの想像力を刺激するには十分でした。一方で、英語版を翻訳したテキストはやや直訳的で、表現に硬さが残っていたのは否めません。それでも「パソコンでここまで本格的な洋RPGが遊べる」という体験は衝撃的であり、多くのファンを獲得しました。
PC-AT互換機版 ― オリジナルに最も近い体験
日本国内ではややマイナーでしたが、海外で標準的に遊ばれていたPC-AT互換機版も存在しました。これはSSIとWestwood Studiosが手掛けたオリジナル版に最も近いものであり、グラフィック・サウンド共に当時のIBM PC環境向けに最適化されていました。
日本のユーザーでこの環境を体験できた人は少なかったものの、「本場の洋RPGはこういうものだ」という生の体験を味わえた点で貴重な存在でした。PC-9801版との違いを比較するプレイヤーも現れ、海外との技術的・文化的な差を実感させるバージョンでもありました。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1992年6月18日に『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』がPC-9801向けに発売された頃、パソコン市場はRPGを中心に数多くの名作が登場していました。ここでは代表的な10タイトルを取り上げ、それぞれの内容や魅力を紹介していきます。
★『ソーサリアンフォーエバー』
・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:大ヒットした『ソーサリアン』をリメイクし、追加シナリオや現代的なアレンジを加えた作品。シナリオベースのRPGであり、仲間を育てて複数の冒険に挑むスタイルは根強い人気を誇りました。
★『イースIV ザ・ドーンオブイース』
・販売会社:ハドソン(開発:トンキンハウス) ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:アドルの新たな冒険を描いたアクションRPG。シンプルな操作性とスピーディなバトルが特徴で、ファルコム監修の下、家庭用機だけでなくPCユーザーからも注目を集めました。
★『ロードス島戦記II』
・販売会社:コンピュータエンターテインメントスタジオ(CEST) ・販売年:1992年 ・販売価格:約12,800円 ・ゲーム内容:人気小説『ロードス島戦記』を題材にしたPC向けRPGの続編。重厚なストーリーとキャラクタービジュアルが特徴で、TRPG的要素とシナリオ重視の展開が評価されました。
★『エメラルドドラゴン』PC-98版
・販売会社:アルファシステム ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:元はPC-8801用に登場した作品をPC-98向けに移植したもの。竜と少女の冒険を描く感動的な物語が特徴で、戦闘は半リアルタイム制を導入。プレイヤーの心を掴むドラマ性で名作の一つに数えられています。
★『マイトアンドマジックIII』
・販売会社:ニューコンピュータシステム ・販売年:1992年 ・販売価格:約12,800円 ・ゲーム内容:海外製の人気RPGシリーズの移植版。広大なマップと膨大な選択肢を備え、パーティ制による自由な冒険が可能でした。『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』と同じく洋RPGの影響を強く感じさせる作品です。
★『ラストハルマゲドン』PC-98版
・販売会社:ブレイングレイ ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:モンスターを主人公に据えた異色RPG。人類滅亡後の世界でモンスターたちが地球を守るという独特のストーリーは賛否を呼びましたが、強烈な個性で根強いファンを獲得しました。
★『ルナティックドーン』
・販売会社:アートディンク ・販売年:1992年 ・販売価格:約12,800円 ・ゲーム内容:シナリオの決まったRPGとは異なり、自由度を重視したオープンエンドRPG。プレイヤーは冒険者として様々な依頼をこなし、戦士や盗賊としての人生を歩むことができました。自由度の高さが話題を呼びました。
★『覇邪の封印リメイク版』
・販売会社:ポニーキャニオン ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:1984年に発売された名作RPGのリメイク。フィールド移動や戦闘システムが改良され、より遊びやすくなったことで再評価されました。懐かしさと新しさが融合した一作です。
★『英雄伝説II ドラゴンスレイヤー』
・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1992年 ・販売価格:約9,800円 ・ゲーム内容:『英雄伝説』の続編であり、感動的なシナリオと堅実なRPGシステムで人気を博しました。シリーズの物語性をさらに深めたことで、ストーリードリブンRPGとして高い評価を受けました。
★『ウルティマVI 偽りの予言者』
・販売会社:ポニーキャニオン ・販売年:1992年 ・販売価格:約12,800円 ・ゲーム内容:アメリカ発の大人気シリーズ『ウルティマ』の第6作。リアルタイムに近いシステムと自由度の高さで知られ、膨大な世界観が特徴でした。日本市場でも「洋RPGの代表」として存在感を放ちました。
総合的な位置づけ
このように、『アイ・オブ・ザ・ビホルダー』と同時期に発売されたパソコンゲームは、シナリオ重視の国産RPG、自由度に富んだ海外RPG、リメイクによる再評価作品など多彩でした。特に1992年前後はRPGが「ストーリー性」と「自由度」の両面で大きな進化を遂げた時代であり、本作はその中でも「TRPGのデジタル化」という独自の立ち位置を築いたのです。
[game-8]
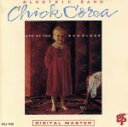




![【中古】アイ・オブ・ザ・ビホルダー [CD] チック・コリア・エレクトリック・バンド](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kuroneko-books/cabinet/imgrc0067012401.jpg?_ex=128x128)