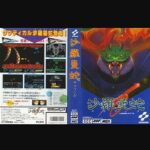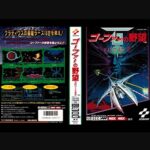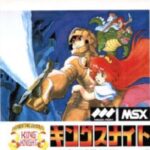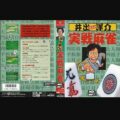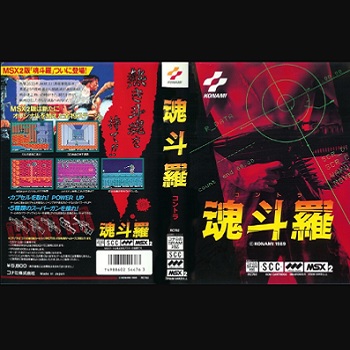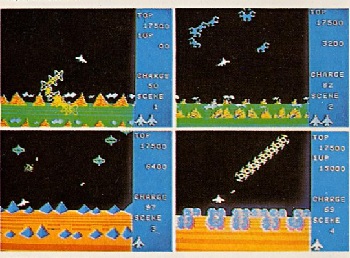
【公式・直販】 ゲーミング PC ノートパソコン 新品 Lenovo LOQ 15IRX9 15.6インチ FHD IPS液晶 Core i5 13450HX Core i7 13650HX選択..




 評価 4.44
評価 4.44【発売】:電波新聞社
【対応パソコン】:MSX
【発売日】:1984年4月
【ジャンル】:シューティングゲーム
■ 概要
アーケードの革新を家庭に――電波新聞社版『エクセリオン』の登場
1984年4月、電波新聞社は、当時まだ黎明期にあったパソコン用ソフト市場の中で、ひときわ注目を集めたタイトルをMSX向けに送り出した。その名が『エクセリオン(EXERION)』である。もともとこの作品は1983年にジャレコがアーケード向けに開発・発売した縦型スクロール型シューティングであり、擬似3D背景を用いた立体的な演出と、宇宙船の“慣性”を感じさせる操作性で話題を呼んだ。電波新聞社は、その人気作をMSXパソコンに移植することで、アーケードの魅力を家庭に持ち込み、多くのユーザーに“家庭で遊べる業務用ゲーム”の新たな価値を提示したのである。
MSX黎明期における挑戦的移植
当時のMSXは、まだ性能的にもグラフィック的にも制約が多く、アーケード作品を完全に再現することは極めて困難だった。にもかかわらず『エクセリオン』は、滑らかに動く擬似3Dスクロール背景や、独特の「慣性移動」をしっかりと再現することに成功している。プレイヤーが操る戦闘機「エクセリオン号」は、操作直後にすぐ止まらず、一定の惰性をもって進行方向を変える。この“重み”のある操作感は、他の同時期シューティングではほとんど見られない特徴であり、リアリティとスリルを生み出す大きな要因だった。
さらに、背景が常に流れ続けることによって、固定画面型シューティングとは異なる“空間の広がり”が演出されている。これはハードウェア的に無理をしてでも挑戦した結果であり、MSXプレイヤーに「家庭用でもここまで表現できるのか」と驚きを与えた。
デュアルショットとシングルショット――二重武装の戦略性
『エクセリオン』の最大の特徴のひとつは、2種類の異なる武装システムである。 ひとつは「デュアルショット」。こちらは弾数制限こそないが、画面上に1発しか同時に存在できないという制約がある。敵を撃った弾が画面外へ消えるまで次弾が撃てず、タイミングと距離感の見極めが重要となる。 もうひとつが「シングルショット」。こちらはボタンを押し続けることで連射が可能だが、発射回数に限界がある。乱射すると弾切れを起こし、危険にさらされる。
この2つを状況に応じて使い分ける戦略性がプレイの醍醐味であり、プレイヤーには冷静な判断力が求められる。アーケードの興奮を家庭でも体感できるよう設計されたこの要素は、単なる移植に留まらず、“新たな操作体験”として記憶に残る存在になった。
多様な敵と緻密な攻撃パターン
敵キャラクターたちは単なる雑魚ではなく、編隊を組んで一糸乱れぬ動きを見せる。中には螺旋を描くように降下してくるもの、急停止からの奇襲を仕掛けるものなど、多様なパターンを持っており、プレイヤーは常に反射神経と先読み力を試される。 ステージが進むごとに、敵の動きは激しさを増し、画面内は常に緊張感で満ちていく。これらの攻撃をかわしつつ、弾数制限のある武器を駆使して反撃するというバランスの妙が、『エクセリオン』ならではのゲーム体験を生み出していた。
“擬似3D”の衝撃と技術的挑戦
当時のMSXで、奥行きを感じさせるスクロールを実現したタイトルはごく僅かだった。『エクセリオン』の背景は、星空が遠ざかっていくように動くことで、プレイヤーに“自機が実際に進んでいる”感覚を与える。この技術は、単に画面を動かすのではなく、速度や層ごとに異なるパターンを重ねて描くことで、遠近感を再現していた。結果として、平面的なシューティングが主流だった時代に、“立体的に宇宙を飛ぶ”という新しい感覚を実現したのである。 これにより『エクセリオン』は、技術的にも美学的にも他のタイトルとは一線を画す存在となった。
ボーナスステージと派生作品の存在
MSX版『エクセリオン』には、アーケード版にはない追加要素として“ボーナスステージ”が導入されている。このステージでは、特定条件を満たすことで突入でき、制限時間内に敵を一定数撃破すると高得点が得られる仕組みだった。この試みは、アーケードの単調なスコア競争に新しいリズムを与え、家庭版ならではの遊び心を表現していた。 さらに、後年には『エクセリオンII ZORNI』というMSXオリジナルの続編的タイトルも登場。グラフィックの強化やステージ構成の変更が加えられ、ファンの間では「アーケードを超えたエクセリオン」として語られることもあった。
SG-1000版との関係と完全移植の評価
セガの家庭用ハード「SG-1000」にも『エクセリオン』は移植されており、MSX版はこのバージョンをベースにしている。そのため基本的な構成や敵パターンはほぼ共通しているが、電波新聞社によるMSX版はグラフィック面で若干の改良が施され、発色や背景の滑らかさが向上している。また、音源のチューニングもMSXハードに合わせて調整され、SEの響き方がより明瞭になったと評価されている。 当時のファンの間では「SG-1000よりもアーケード版に近い」「背景の動きがより滑らか」といった声が多く、移植作品として高い完成度を誇った。
MSX初期を象徴する存在
『エクセリオン』は、単なる移植作ではなく、MSXという新しい標準規格パソコンの可能性を示した象徴的なソフトでもあった。まだ“ゲーム機ではないパソコンで遊ぶ”という文化が定着していなかった時代に、家庭用でアーケード体験を味わえることを証明した点で、その意義は大きい。 本作の成功をきっかけに、他社も次々とアーケード移植に挑戦し、MSXゲーム市場は一気に拡大していく。後の名作『ゼビウス』『グラディウス』などが登場する下地を作ったのは、まさにこの『エクセリオン』だったといえる。
時代を超えて語り継がれる“慣性の美学”
『エクセリオン』は、グラフィックやサウンドの派手さよりも、操作感そのものに重点を置いた作品である。滑らかに漂うような自機の動き、タイミングを見極めて撃つ緊張感――これらは後のシューティングゲームにも多大な影響を与えた。現代のプレイヤーから見ても、当時のハード性能を超えた工夫と挑戦心に満ちた作品として、今なお“80年代初期の名作”として語り継がれている。
■■■■ ゲームの魅力とは?
独自の操作感が生み出す没入感
『エクセリオン』の最大の魅力は、なんといっても「慣性」を重視した操作感にある。一般的なシューティングゲームの多くは、レバーを離せば自機がすぐ停止する設計になっている。しかし本作では、操作を止めても機体がわずかに滑り続ける。プレイヤーは自機の動きを常に予測し、数フレーム先を見据えて操作する必要がある。これは単なる難易度上昇のための仕掛けではなく、まるで本当に宇宙空間を航行しているかのような“重力のない空間での浮遊感”を再現するための演出だった。 この“物理的なリアリティ”は、1984年当時としては革新的な試みであり、ゲーム世界に命を吹き込んだ技術的・表現的成果といえる。
戦略的な武器選択の面白さ
本作のもうひとつの魅力は、2種類の武器システムが織りなす戦略性にある。弾数制限のない「デュアルショット」は安心感があるが、連射ができないために攻撃テンポが遅くなりがちだ。一方、弾数制限付きの「シングルショット」は短時間での集中砲火が可能だが、撃ちすぎると弾切れを起こす。この対照的なバランスが、プレイヤーの思考を常に刺激する。 特にボーナスステージや中盤以降の高速敵が出現する局面では、どのタイミングでどちらのショットを使うかが勝敗を分ける。弾道の速度や射程を体感的に把握しておく必要があり、アクションと戦略が高次元で融合しているのが『エクセリオン』の真骨頂だ。
音と映像が織りなす緊張のリズム
MSXという限られた音源でありながら、『エクセリオン』のサウンド設計は実に巧妙だ。シンプルな効果音しか鳴らないにもかかわらず、発射音や爆発音の「間」の取り方が絶妙で、プレイヤーの集中を途切れさせない。特に、弾を発射した直後の“静寂”が緊張を生み、次の敵編隊が現れた瞬間に再び鼓動が高まる。このリズムが、プレイヤーの感覚をゲーム世界へと引き込む。 映像面でも、当時としては画期的だった「星空の奥行き感」がゲームの雰囲気を格段に高めている。背景の動きが単なる装飾ではなく、プレイヤーの集中力を支える“リズムの一部”として設計されていた点は、制作者の美学が感じられる部分だ。
アーケードの興奮を家庭で味わう贅沢
1980年代初頭、アーケードゲームの隆盛期にあっても、家庭で同等の体験を再現することは容易ではなかった。『エクセリオン』はその壁を破り、家庭用として“ほぼ同等の緊張感”を提供した稀有な作品である。 MSXのキーボード操作やジョイスティック操作に対応し、当時のユーザーは自宅でまるでゲームセンターのような雰囲気を楽しむことができた。特に、難易度の高い敵の出現パターンやステージ構成はアーケードの再現度が高く、電波新聞社による移植の完成度の高さを感じさせる。 多くのプレイヤーが「MSXでもここまで動くのか」と感嘆し、当時の雑誌でも「アーケード移植の成功例」として高い評価を得た。
“遊び心”を刺激するボーナスステージ
シューティングゲームは、どうしても単調な撃ち合いになりやすい。しかし『エクセリオン』では、その緊張感をほぐすために“ボーナスステージ”が挿入されている。通常ステージで一定の条件を満たすと突入でき、敵を連続で撃墜する爽快感が楽しめる。BGMが明るく変化し、短時間でスコアを稼ぐことが可能となるため、緊迫した本編の中に一種の“癒し”を与える構成になっていた。 また、このボーナス要素があることで、プレイヤーは単に生き残るだけでなく、「高得点を目指す」というもう一つの目標を持つようになる。スコアアタック文化の礎を築いた作品の一つとしても評価されている。
緻密に設計されたステージバランス
ステージの構成は単純に見えて非常に緻密に設計されている。敵の出現タイミング、攻撃角度、背景の流れるスピードが絶妙に調整されており、プレイヤーが油断した瞬間に画面端から高速で敵が飛来する。序盤はチュートリアル的な構成で操作に慣れさせ、中盤からは敵の動きに心理的な罠を仕掛けてくるような緊迫感が加わる。終盤では敵弾の速度と数が極端に増し、反射神経と判断力が同時に問われるようになる。 この緻密な設計が、ただのシューティングではなく「戦いのシミュレーション」としての深みを与えている。
シンプルさの中にある完成美
『エクセリオン』には複雑なストーリーも派手な演出も存在しない。それでも人々を惹きつける理由は、純粋に“プレイする楽しさ”が詰まっているからだ。ゲームデザインが緻密で、無駄な要素が一切ない。撃つ・避ける・判断するという原始的な快感がそのままプレイヤーの指先に伝わる。 当時の子どもたちにとっては、単なる暇つぶしの娯楽ではなく、自分の技術や集中力を試す“挑戦の舞台”であり、大人たちにとってもそのシンプルさが逆に中毒性を生んだ。時代を経ても飽きない普遍的な面白さが、まさに『エクセリオン』の魅力の核といえる。
グラフィックとサウンドの調和
MSX版『エクセリオン』では、限られたカラーパレットながらも巧みな配色で“宇宙”を表現している。深いネイビーブルーの背景に、白や黄色の星が点滅し、敵キャラクターは緑や赤で差別化されている。これらのコントラストが、画面の視認性を高めると同時に、プレイヤーの集中を助けるデザインとなっている。 サウンド面では、BGMの代わりに短い効果音がアクセントとして配置され、無音の時間をあえて演出として利用している点が特徴だ。戦場の静寂と爆発音の対比が、まるで宇宙空間の孤独さを表現しているかのようだ。
挑戦心をくすぐる難易度設定
『エクセリオン』の難易度は決して優しくない。だが、その手応えこそがプレイヤーを夢中にさせる。ステージが進むにつれて敵のスピードは上がり、弾幕の密度も増す。最初は絶望的に感じられる局面でも、練習を重ねることで突破できるようになる。この“上達の実感”がプレイヤーの心を掴んで離さない。 単に反射神経だけでなく、弾道の軌跡や敵の出現パターンを記憶して挑む必要があり、攻略の過程そのものが楽しさを生む設計になっている。
時代を超えるシンプルな面白さ
現代のゲームと比べれば、グラフィックやサウンドは素朴かもしれない。だが、『エクセリオン』が放つ“操作する快感”“避ける緊張”“撃ち抜く爽快感”は、今もまったく色あせていない。複雑なシステムや演出を排し、プレイヤーの感覚だけで楽しませるデザインこそが、時代を超えて評価され続ける理由である。 このゲームは単に「古い作品」ではなく、シンプルなゲームデザインの理想形の一つとして、多くの開発者にも影響を与え続けている。
■■■■ ゲームの攻略など
序盤の心構え――慣性を制する者が勝つ
『エクセリオン』の攻略を語るうえで最も重要なのは、まずこのゲームの“慣性”を理解することだ。一般的な固定画面型シューティングとは違い、レバーを離しても自機はすぐには止まらない。この惰性を逆手に取るか、振り回されるかでプレイの安定度が大きく変わる。 攻略の第一歩は「止まる練習」だ。敵を撃つ前に、まずは自機の慣性を感覚的に掴み、どれくらいの時間で停止するのか、どの距離で方向転換が可能かを体で覚えておくことが必要である。これは単調に思えるが、実際にプレイを安定させるための最も基本的かつ重要なステップである。
デュアルショットとシングルショットの使い分け
前章でも触れたが、本作の攻略では「武器の切り替え」が勝敗を決定する。 デュアルショットは1発ずつ撃ち、弾が画面外に消えるまで次弾を撃てないため、敵が画面上に多数出現する場面では不利になる。一方で、弾数制限のない安心感があるため、序盤の練習には向いている。 一方のシングルショットは、押しっぱなしで高速連射ができるため、敵が複数並んで出現する局面では圧倒的な火力を発揮する。ただし、弾数が限られており、撃ちすぎると弾切れになってしまう。 攻略のポイントは、敵の出現パターンを把握したうえで「どの局面で弾を温存するか」を見極めること。ステージ序盤で乱射すると、後半で弾不足になりやすい。特に中盤の敵編隊は回避不能な配置で出現することもあるため、連射は“ここぞ”という場面まで我慢するのが賢明だ。
敵のパターンを読む――ランダムではない動き
『エクセリオン』の敵は一見ランダムに飛んでいるように見えるが、実際には明確な出現パターンが存在する。例えば、序盤の敵は斜め方向から徐々に降下してくる固定パターンで構成されているが、中盤以降になると画面端から高速で突入する“奇襲型”や、突然静止して弾を撃つ“狙撃型”などが混じってくる。 プレイヤーは、敵が登場した瞬間にその種類を判断し、軌道を先読みして動く必要がある。 コツとしては、「敵が出た位置」よりも「出た方向」を見ること。敵が左上から出たなら、次は右下側から出る可能性が高い――このように、反対方向の安全地帯を意識することで、危険を未然に回避できる。 慣れてくると、画面に出現した瞬間に次の行動を自然に取れるようになり、プレイが格段に安定する。
スコア稼ぎの極意――ボーナスステージの活用
『エクセリオン』では、一定条件を満たすと突入できる“ボーナスステージ”が高得点のカギを握っている。このステージでは通常よりも多くの敵が一斉に出現し、制限時間内に撃墜数を稼ぐことでボーナスポイントが加算される。 攻略のコツは、「敵を一気に倒そうとしない」こと。焦って乱射すると、弾数制限に引っかかり、後半で敵を取り逃してしまう。敵の進行方向を予測し、左右の移動を最小限に抑えて弾を節約するのが理想だ。 また、敵が画面外へ逃げる前に確実に撃ち抜くためには、慣性を利用して“滑り撃ち”を行うと効果的。少し横移動しながら撃つことで、弾の発射間隔を保ちながら敵を効率よく撃墜できる。
中盤以降の難関――敵の多重攻撃をどう捌くか
ステージが進むにつれて、敵の行動は激しさを増していく。特に中盤では、敵が上下左右から挟み撃ちを仕掛けてくるシーンが頻発する。 このとき、焦って中央に留まるのは危険だ。中央は一見安全に見えるが、上下からの奇襲を避けにくく、敵弾に囲まれやすい。 おすすめの戦略は“画面端の斜め移動”。画面左下または右下を起点にして、斜め上へ移動しながら撃つと敵の弾を避けやすくなる。さらに、敵が降下してくるタイミングで一気に方向転換すれば、敵の裏をかくことも可能だ。 また、敵が編隊で現れるタイミングを覚えることで、事前に移動準備を整えることができる。アドリブではなく“型”を作ることが安定攻略の近道である。
終盤ステージの心構え――「守りのプレイ」への切り替え
終盤のステージでは、攻撃よりも回避を優先するプレイが求められる。敵の弾幕が激しくなるため、攻撃の隙を見つけにくい場面が増える。ここで無理に撃とうとすると、反応しきれずに被弾してしまうことが多い。 攻略のポイントは「撃たない勇気」。敵が画面下まで降りてくるのを待ち、位置をずらして避ける。安全なタイミングで反撃に転じる方が生存率が高い。 また、慣性のために回避行動が遅れることを防ぐには、先読みの意識を強く持つことが重要だ。画面の中央付近よりも上に出ると危険なので、終盤はあえて下部にポジションを固定し、敵の出現パターンに合わせて小刻みに動くスタイルを心掛けたい。
裏技・隠し要素――マニアの間で語り継がれる小技
MSX版『エクセリオン』には、当時のプレイヤーの間で密かに語り継がれた小技や裏技がいくつか存在する。代表的なのが「敵を撃たずに一定時間避け続ける」と発生する“隠しボーナス”である。これは特定の条件を満たすと、次のステージ開始時に追加得点が与えられるというものだ。 また、電源投入後に特定のキー操作を行うことで、タイトル画面の一部が変化する隠しメッセージも確認されている(ただし機種やバージョンによって挙動が異なる)。このような“遊び心”も、当時のパソコンゲームならではの魅力であった。
スコアアタックと競技性
『エクセリオン』は、単にクリアを目指すゲームではなく、“スコアを極める”こと自体が目的となる構造を持っている。敵の種類ごとに得点配分が異なり、特定の編隊を完全に壊滅させるとボーナスが加算される。このため、プレイヤーは安全に進むか、リスクを負って高得点を狙うかという選択を常に迫られる。 特に上級者の間では、「1発も被弾せずにボーナスステージへ突入する」というプレイスタイルが流行し、その記録は当時のゲーム雑誌にも掲載されたほどだ。こうした競技性の高さが、長年ファンに愛され続ける理由のひとつでもある。
練習と上達のコツ
初心者が上達するためには、“敵の種類ごとに回避の型を覚える”ことが近道だ。たとえば、直進型の敵は左右移動で対応できるが、回転しながら降下する敵には上下移動が有効――といった具合に、パターンごとに反応を固定化しておく。 また、慣性の動きを利用して「停止するための移動」を意識するのも重要だ。止まりたい位置より少し早めに逆方向へ入力することで、正確にポジションを取れるようになる。この“慣性キャンセル”を身に付けると、敵弾をギリギリで避ける爽快感が格段に増す。
ミスした後の立て直し
残機を失うと緊張が途切れやすくなるが、『エクセリオン』ではリカバリーのタイミングを冷静に見極めることが大切だ。再スタート直後は敵の出現数が少ないため、この間に画面中央の安全地帯を確保しよう。慌てて攻撃せず、自機の動きを取り戻すことに集中する。 ゲーム全体を通して重要なのは、「焦らず一定のテンポを維持する」ことだ。敵が速くても、自分が速く動く必要はない。常にリズムを一定に保つことが、高難度ステージを突破する最大の秘訣である。
終わりなき挑戦へ
『エクセリオン』には、明確な“最終ステージ”という概念が存在しない。一定ステージをクリアするとループし、さらに難易度が上昇する“無限サイクル型”の構造を持つ。プレイヤーはスコアを更新し続け、自分自身の限界と戦うことになる。 この「終わりがない戦い」こそが、80年代のアーケード魂を最も色濃く残す要素であり、MSXという限られた舞台で再現した電波新聞社の意欲は、今なお高く評価されている。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーが感じた“未来の操作感”
1984年当時、『エクセリオン』を初めて手に取ったプレイヤーたちは、一様に「今までのシューティングとは違う」と驚きを隠さなかった。特に多く語られたのが、あの独特の“慣性による浮遊感”である。従来のゲームが単純な左右移動で完結していたのに対し、本作では自機の動きを予測して操作しなければならず、まるで宇宙空間で戦っているかのような没入感を味わえた。 当時の雑誌レビューでも「自機が空間の中を滑るように動く感覚が斬新」「単なる撃ち合いではなく、操縦感覚そのものが楽しい」といったコメントが多く掲載され、MSX黎明期の技術的挑戦作として高く評価されていた。
また、少年層だけでなく大人のパソコンユーザーにも好評だった点も特筆に値する。ゲームセンター文化に抵抗のあった社会人世代が、「家でアーケード気分を味わえる」として本作を購入するケースも多く、結果的にMSXという新しい家庭用パソコン市場の拡大にも寄与した。
電波新聞社の移植力への驚き
移植元のジャレコによるアーケード版は、当時の業務用基板としては高度なグラフィックを誇っていた。したがって、MSXのスペックで再現するのは難しいと考えられていたが、電波新聞社は大胆な最適化を行い、処理落ちを最小限に抑えながら擬似3Dスクロールを見事に表現した。 当時のレビュー記事では、「MSXでこの立体感を出したのは奇跡に近い」「技術的な限界に挑んだ執念を感じる」といった称賛の声が上がっている。 さらに、グラフィック面でアーケード版の配色やドット配置をうまく簡略化しつつ、雰囲気を損なわない再現を果たした点も好感を持たれていた。電波新聞社の職人的な移植技術は、後の同社のタイトル群(『グラディウス』移植や『スクランブル』など)にも引き継がれていく。
「難しいけれど、やめられない」中毒性
多くのプレイヤーが口を揃えて語ったのが、「難しいけれど何度も挑戦したくなる」という中毒性だ。 最初は自機の挙動に戸惑い、思うように敵を倒せずにゲームオーバーを繰り返す。しかし、少しずつ慣れていくと、慣性を利用した“滑り撃ち”や“先読み回避”が自然にできるようになり、スコアが伸び始める。この上達の実感が、プレイヤーのモチベーションを高めた。 当時のファンの中には、「一晩で100回以上プレイした」「気づいたら夜が明けていた」という熱狂的な証言も残っている。単純なルールながらも、プレイヤー自身の技術成長を確かに感じられる設計が、長く遊ばれ続けた理由だ。
専門誌・業界紙の評価
1984年から1985年にかけて、『MSX・FAN』や『ログイン』、『テクノポリス』など当時のパソコン誌では『エクセリオン』がたびたび取り上げられた。特に印象的だったのは、「アーケード移植の成功例」という言葉が多く見られた点である。 『MSX・FAN』誌では「MSXの性能を知るうえで欠かせない作品」と評され、グラフィック表現と操作性の両立を高く評価。『ログイン』では「擬似3D表現の完成度は、MSX初期タイトルの中でも群を抜く」と記されている。また、『テクノポリス』誌面では、「当時の若者たちが“パソコンでもゲームができる”と実感した最初のタイトルのひとつ」として紹介された。 これらのメディア評価は、単なる人気作品としての価値を超え、『エクセリオン』が文化的にも重要な意味を持っていたことを裏付けている。
一部プレイヤーの批判と意見の分かれ
もちろん、すべての評価が肯定的だったわけではない。一部のプレイヤーからは「操作が難しすぎる」「弾切れのルールが理不尽」といった意見も見られた。特に初心者層にとって、弾の制限や慣性の挙動は大きな壁であり、「避けて撃つ」だけではクリアできない点にストレスを感じる人もいた。 それでも、そうした批判は裏を返せば“本気で遊び込んだ証”でもあった。単純明快なゲームが多い時代に、ここまでプレイヤーに“習熟”を求めるデザインはむしろ斬新であり、難易度が高いからこそ“自分の力で克服する楽しさ”が味わえると肯定する声も同時に上がっていた。 結果的に、『エクセリオン』は“やさしさより深さ”を求めるユーザーに強く支持されるタイトルとなった。
ボーナスステージの爽快感に魅了されたユーザーたち
多くのプレイヤーが思い出として語るのが、ボーナスステージに突入したときの快感である。通常ステージの緊張から一転、明るいBGMとともに敵が次々と現れるボーナス面は、まさに“ご褒美”の時間だった。 プレイヤーの中には、このステージでいかに効率よく撃墜できるかを研究する者もおり、スコアアタックを楽しむ層の中心的な話題となった。「本編よりもボーナスステージのために遊んでいた」という声も少なくなく、この部分だけを繰り返す“リセットプレイ”を楽しむユーザーも存在した。 こうした遊び方の多様化も、『エクセリオン』が単なる移植作品を超え、プレイヤーの創意を刺激する“遊びの場”になっていた証である。
MSXユーザーコミュニティでの再評価
1990年代以降、MSX愛好家の間で本作の再評価が進んだ。MSXクラブの会報誌やインターネット掲示板では、「慣性システムの完成度は今見ても秀逸」「技術的制約を超えている」といった声が多数寄せられている。 また、後年になって登場したエミュレーター環境で再プレイするユーザーからは、「当時より滑らかに感じる」「今でも操作が面白い」といった感想もあり、時間を経てもその本質的な面白さが失われていないことが確認できる。 さらには、インディーゲーム開発者の間でも“慣性挙動”の再現を試みる動きがあり、『エクセリオン』を参考にして開発されたファンメイド作品も登場している。まさにレトロゲーム史に残る“教科書的存在”といえる。
現代のレトロゲームファンの視点から
現在のレトロゲームファンにとって『エクセリオン』は、単なる懐古対象ではなく“技術と発想の原点”として映る。YouTubeやニコニコ動画などで実況プレイが投稿されるたびに、「40年前のゲームとは思えない」「MSXでこの滑らかさはすごい」といったコメントが並ぶ。 また、近年はプロジェクトEGGなどの配信サービスで再発売されており、若い世代が初めて触れる機会も増えている。現代のゲーマーが“慣性挙動”を面白いと感じるのは、それだけ本作の設計が時代を超えて優れていた証だ。
総評――時代を超えた「動きの芸術」
『エクセリオン』は、派手な演出や豪華なストーリーで魅せるタイプの作品ではない。だが、操作の気持ちよさ、手触りの確かさ、そしてプレイヤーが少しずつ上達していく感覚――これらを40年前に提示していた点で、非常に先進的な作品だった。 当時の技術を極限まで引き出し、シンプルな中に深い緊張とリズムを生み出したそのデザインは、今見ても色褪せることがない。難易度の高さや独特の挙動が人を選ぶ作品ではあるものの、それも含めて“挑戦の美学”を体現したゲームといえるだろう。 プレイヤー、評論家、開発者――誰の視点から見ても、『エクセリオン』はMSX初期を代表する伝説的タイトルであることに疑いはない。
■■■■ 良かったところ
操作の「重み」がリアルな宇宙戦を演出
『エクセリオン』の最も印象的な長所として多くのプレイヤーが挙げるのが、“慣性を持つ操作感”だ。単に左右へ素早く動くのではなく、スッと滑るように進む挙動は、当時のシューティングでは異例のリアルさを持っていた。これにより、まるで宇宙空間で推進力をコントロールしているような臨場感を味わえる。 この感覚が他のどのゲームにもない没入感を生み、プレイヤーを引き込む大きな魅力となった。慣性を制御できるようになると、操作そのものが快感に変わり、上達の実感が強く得られる。この「手触りの良さ」は、MSX初期のゲームデザインの中でも際立つ完成度を誇っていた。
シンプルながら深みのあるゲームシステム
当時の多くのシューティングは、「敵を撃ち落とす」「スコアを稼ぐ」という明快な目的のみだったが、『エクセリオン』はその中に“思考”の要素を巧みに組み込んでいる。2種類のショットをどう使い分けるか、どのタイミングで弾を温存するかという判断が、単調な反射ゲームを超えた戦略性を生み出している。 特にシングルショットの弾数制限は、プレイヤーに「無駄撃ちの抑制」と「冷静な判断」を求める設計であり、単に早く撃つだけでは勝てない構造が秀逸だ。ゲームを重ねるほどにその奥深さが理解できる点が、多くのファンを虜にした。
美しくもミニマルなグラフィックデザイン
MSXという制約の多い環境の中で、『エクセリオン』のグラフィックは驚くほど洗練されている。背景は深い宇宙空間を思わせる濃紺のトーンで構成され、そこに点滅する星々が静かな広がりを感じさせる。敵キャラクターのデザインも単色ではなく、ドットの重ね方によって微妙な立体感を表現しており、当時の技術で可能な限りの「奥行き」を演出していた。 また、プレイヤー機体のシルエットも印象的で、単なる点滅ドットではなく、推進口が光るアニメーションが入るなど、細部にこだわりが見える。全体として、シンプルながら計算された美しさがあり、長時間プレイしても目に優しく疲れにくい点も評価された。
“音の余白”が生み出す緊張と没入感
BGMがほとんど存在しないにもかかわらず、『エクセリオン』の音設計は極めて印象的だ。発射音、爆発音、敵の出現音――それらが静寂の中で際立つよう配置され、プレイヤーの神経を集中させる効果を持っている。 特に、弾を撃った後に一瞬訪れる“無音の間”が絶妙で、この間合いがまるで宇宙空間の無音のリアリティを再現しているかのようだ。音を削ぎ落とすことで逆に“聴かせる”構成は、後年のクリエイターにも影響を与えたと言われている。音の設計がここまで意識的に行われたMSXタイトルは、当時としては極めて稀だった。
アーケード版に迫る再現度
家庭用移植としての完成度も高く、当時のMSXプレイヤーに大きな衝撃を与えた。アーケード版『エクセリオン』の特徴である擬似3D背景や滑らかな動きを、MSXの制約下でも違和感なく再現していた点は賞賛に値する。 電波新聞社の移植チームは、画面描画の最適化やスプライトの使用数を極限までチューニングし、処理落ちを防ぐために独自の描画制御ルーチンを導入していた。この努力により、当時のプレイヤーは「アーケードが家で遊べる」という夢を現実に感じた。雑誌レビューでも「ハードの限界を超えた移植」としてたびたび取り上げられたほどだ。
スコアアタックの奥深さ
スコアリングの設計も見事だった。単に敵を倒すだけでなく、敵の種類ごとに異なる得点配分があり、全滅ボーナスを狙うリスクとリターンのバランスが巧妙に設計されている。 また、ボーナスステージでの高得点獲得がスコアアタックの要となっており、「1ステージ目でどれだけ完璧に倒せるか」が上級者の腕を分ける指標だった。プレイヤー同士でスコアを競い合う文化が自然に生まれ、当時の雑誌にもハイスコア投稿が相次いだ。 この“競技性のあるシステム”が、単なる一人遊びを超えた“対人間”の熱狂を生み出していた点も良さのひとつである。
ボーナスステージの開放感とリズム感
通常ステージの緊張感とは対照的に、ボーナスステージの明るく軽快なテンポは多くのプレイヤーの心を掴んだ。制限時間内に敵を撃ち続ける爽快さと、短いBGMの高揚感が一体となり、まるで呼吸を取り戻すような感覚を与えてくれる。 この緩急の付け方が見事で、「緊張と解放」のリズムがプレイ全体のテンポを整えている。プレイヤーに心理的な“休憩”を与えると同時に、再び本編に戻る際の集中力を高める効果を持っていた。ストイックなゲームの中で一瞬の“ご褒美”を感じさせる構成は秀逸だ。
バグが少なく安定した完成度
MSX初期のゲームの中には、長時間プレイすると処理落ちや表示崩れが発生するものも多かったが、『エクセリオン』は非常に安定していた。特に動作フリーズやスプライトのチラつきがほとんどなく、ハードの性能を的確に理解して作られていたことがうかがえる。 こうした安定性はプレイヤーのストレスを軽減し、長時間のプレイにも耐えうる設計を実現していた。発売から数十年経った今でも、オリジナルROMを実機で起動すれば安定して動作するという報告があり、プログラムの堅牢さは今なお評価が高い。
プレイヤーの成長を感じられる設計
『エクセリオン』は、プレイヤーが“自分の上達”を最も実感しやすい作品のひとつだ。最初は制御不能に思えた慣性が、次第に手の延長のように扱えるようになる。敵の出現パターンを覚え、スムーズに避け、正確に撃てるようになる過程がそのままプレイヤーの達成感となる。 この「習熟の喜び」がゲームデザインに深く根付いており、ミスをしても再挑戦したくなるモチベーションを与えてくれる。いわば“努力が確実に報われる設計”が、長年愛され続ける理由でもある。
MSXユーザーにとっての「誇り」
最後に、多くのユーザーが語る“良かった点”として、MSXというプラットフォームへの誇りがある。当時、ファミコンやアーケードが華やかな時代にあって、MSXユーザーはしばしば「性能が劣る」と揶揄された。 しかし『エクセリオン』は、そのイメージを覆した。「MSXでもここまでできる」という証明となり、ユーザー同士の絆を強める存在となったのだ。発売当時のコミュニティ誌『MSXマガジン』の投稿欄には、「MSXでアーケードを超えた!」という声が多数寄せられたという。 本作は単なるゲームではなく、“MSX文化を自信に変えた”象徴的タイトルとして記憶されている。
総評:静かな熱狂を生んだ完成作
『エクセリオン』の良さを一言で表すなら、「派手ではないが、心に残るゲーム」だ。強烈なビジュアルもBGMもないが、プレイヤーの指先に残る感覚と緊張のリズムが、何十年経っても鮮明に思い出される。 操作の美しさ、設計の誠実さ、挑戦の充実感――それらが一体となって、80年代初期の名作としての地位を確立している。プレイヤーの記憶に深く刻まれた“静かな熱狂”こそが、『エクセリオン』の最も良かったところである。
■■■■ 悪かったところ
慣性操作の難易度が高すぎる
『エクセリオン』の特徴であり魅力でもある“慣性操作”は、同時に最大の壁として多くのプレイヤーを苦しめた要素でもある。レバーを離しても自機が止まらず、惰性で進んでしまうため、初心者は思った通りに動かすことができない。敵弾を避けたつもりが滑り過ぎて被弾する、撃ちたい方向に微調整できない――といったストレスを感じた人は少なくなかった。 当時の雑誌レビューでも、「リアルだが難解」「慣性の制御に慣れるまでが地獄」といった意見が複数見られる。確かにこの設計は画期的だったが、初めてプレイする層にとっては“とっつきにくさ”が大きなハードルとなった。難易度設定の段階的調整やチュートリアル的なステージ構成がなかったことが、挫折率を高める一因でもあった。
弾数制限によるストレス
シングルショットの弾数制限は戦略性を生んだ一方で、プレイヤーによっては「不自由さ」として受け取られた。特に敵の出現が急増する中盤以降では、弾切れによってなすすべもなくやられるケースが頻発し、「撃ちたいのに撃てない」感覚がストレスになりやすかった。 また、弾の残数が視覚的にわかりにくく、いつ弾切れになるのか予測しづらい点も不評のひとつ。せめて画面上に残弾を示すインジケータやサウンド警告があれば、テンポを損なわずに戦略的に立ち回れただろう。 ゲームデザインとしては挑戦的だが、遊び手に優しくない部分があったことは否めない。
単調に感じられるステージ構成
『エクセリオン』は、その技術的挑戦が評価される一方で、ステージ構成自体にはあまり変化がないという意見も多い。背景が常に宇宙空間のままで、敵の種類やパターンも限定的なため、長時間プレイすると“似たような展開”が続く印象を受ける。 この単調さは、当時のハード性能による制約の影響も大きい。グラフィックのバリエーションを増やすことが難しかったとはいえ、ステージごとに色調を変えたり、スクロール速度に変化をつけたりといった演出があれば、飽きにくくできたかもしれない。 「あと一歩の演出力があれば、名作から伝説になった」と語るファンもいるほどである。
リズムを崩す当たり判定の厳しさ
もうひとつの課題は、当たり判定の広さだ。『エクセリオン』では、自機の判定がやや大きめに設定されており、敵弾が少しかすっただけでも撃墜されてしまうことが多い。とくに高速で敵が出現する後半ステージでは、理不尽に感じる場面が少なくなかった。 当時のプレイヤーの声には、「見た目では避けたのに当たった」「自機の中心だけを判定にしてほしかった」といった意見も多く、慣性のある操作と相まって“避けづらいゲーム”という印象を強めていた。 この点は後年のシューティングゲームで改善されていく部分でもあり、当時としては“まだ洗練されきっていない”段階のデザインだったといえる。
難易度曲線の急激な上昇
本作の難易度設計は、序盤と中盤の間に大きな壁が存在する。最初の数ステージまでは敵の動きが緩やかで、操作に慣れる時間が与えられるが、ある時点から突然、敵の出現速度や攻撃密度が倍増する。 このバランスの急変により、初心者の多くが中盤で脱落してしまう傾向が見られた。もう少し段階的に難易度を上げていれば、より広い層に遊ばれた可能性もある。 「中盤の壁を越えた人だけが本当の楽しさを味わえる」という構造は、やり込み派にとっては燃える要素だったが、カジュアルなプレイヤーを遠ざける結果にもなっていた。
ゲームの終わりが見えない無限ループ構造
『エクセリオン』には、明確なエンディングが存在しない。一定のステージをクリアすると再び最初に戻り、敵の速度と数だけが増していく“無限ループ式”である。 この構造はアーケード的スコアアタックには最適だが、「達成感が得にくい」と感じたプレイヤーも多かった。「何面まで進めば終わりなのか」「いつクリアと呼べるのか」が曖昧なため、モチベーションを保ちづらいという意見が少なからず見られた。 また、当時の家庭用プレイヤーは“エンディング”を求める傾向が強く、ゲームセンター的な無限ループ構造は家庭用ゲームとしてはやや時代の先を行き過ぎていたともいえる。
サウンド表現の物足りなさ
効果音中心の構成は雰囲気作りに成功していたが、一方で「静かすぎる」「BGMがないと寂しい」という意見も根強かった。特に長時間プレイするユーザーにとって、無音の時間が続くことは集中力を削ぐ原因にもなり得た。 同時期の他タイトルでは、簡易的でもBGMを導入していた作品もあり、それらと比較されると“音楽的な演出”の面で見劣りしたのは否めない。 音の少なさが“宇宙の孤独”を表現していると評価する声もあった一方で、より多くの層に親しんでもらうには、もう少し音の彩りが必要だっただろう。
バリエーションの少ない敵キャラクター
敵のデザインや動きが似通っていることも、やや単調さを感じさせる要因となった。序盤と終盤で色やスピードは変化するものの、基本的な行動パターンは大きく変わらないため、長く遊ぶと新鮮味が薄れてしまう。 また、ボス的な存在がいないため、プレイヤーの中には「節目となる達成感がない」と感じる人もいた。限られたメモリ容量の中で動作を優先した結果ではあるが、もう少し個性的な敵パターンやギミックがあれば、緊張感の持続に繋がっただろう。
操作ボタン配置の不便さ
MSXのジョイスティックやキーボード操作において、2ボタン構成はまだ一般的ではなかった。そのため、デュアルショットとシングルショットを素早く使い分ける際に、ボタン配置の違和感を覚えるプレイヤーも多かった。 特にキーボード操作では同時押しや連射が難しく、「咄嗟に撃てない」「左利きだと操作しづらい」といった声もあった。ハードウェア側の制限とはいえ、プレイヤー体験の一貫性を損ねていた部分といえる。
中断機能の欠如
1980年代のパソコンゲームとしては当然ではあるが、途中セーブやポーズ機能が存在しないことも、当時のプレイヤーには不便に感じられた点だった。 特に長時間集中してスコアを狙うゲームであるため、ちょっとした休憩すら許されない設計は現代的に見れば過酷である。社会人ユーザーからは「一度始めたらやめられない」「家族に呼ばれても中断できない」といった苦笑交じりの声もあったという。 現在では当時の仕様を“ストイックな魅力”と見る向きもあるが、家庭用ソフトとして考えればユーザーフレンドリーさに欠けていたのは確かだ。
現代視点での評価――挑戦の代償
今改めて『エクセリオン』を振り返ると、その“悪かった点”の多くは、同時に“挑戦の結果”でもあることに気づく。慣性挙動はリアリティを追求したがゆえに操作難度が上がり、静かな音設計は雰囲気を演出する一方で一部には物足りなさを与えた。つまり、本作の短所はそのまま“実験的精神の副作用”なのだ。 開発陣がMSXの限界を超えようとしたがゆえに生まれた粗削りさは、今となってはむしろ味わい深い。欠点が多くてもなお語り継がれるのは、そこに“本気の挑戦”があったからである。
総評:不完全だからこそ愛される作品
『エクセリオン』は決して完璧なゲームではない。だが、その未完成さゆえにプレイヤーの心に残る作品である。遊びにくさ、理不尽さ、限界――それらすべてが“1984年という時代の証”として美しく輝いている。 後の世代が本作を再評価する理由は、技術の高さではなく、“不便さの中に確かな創意がある”からだろう。完成されすぎた作品にはない「荒削りな熱意」が、今なおプレイヤーの記憶を離さない。 この不完全さこそが、『エクセリオン』の真の魅力であり、同時に最も“悪かったところ”として愛され続けている点なのかもしれない。
[game-6]■ 好きなキャラクター
プレイヤーの分身 ― 主人公機「エクセリオン号」
『エクセリオン』における“主人公”とは、もちろんプレイヤーが操る戦闘機「エクセリオン号」である。この機体こそが本作の象徴であり、プレイヤーの感情を最も投影する存在だ。 そのデザインは、当時のゲームとしては非常に洗練されており、細い翼と流線形のボディが特徴的だ。アーケード版のデザインを受け継ぎつつも、MSX版ではやや丸みを帯びたドット構成になっており、機体の推進口が点滅する演出が「生命を持つ機械」のような印象を与えている。 この点滅アニメーションは単なるグラフィックではなく、プレイヤーの心理に働きかける巧妙な表現だ。星々の中を漂う孤独な戦闘機――その“孤高の姿”に感情移入したプレイヤーも多く、「エクセリオン号は無口な主人公のようだ」と語る人さえいた。
また、この機体は他のゲームのようにパワーアップを重ねて強くなるタイプではなく、最初から最後まで同じ装備で戦い抜く。だからこそ、プレイヤー自身の技術が成長する過程がそのまま“機体の成長”に見える。この“変わらぬ主人公”という存在感は、まさに80年代初期のゲームデザインの美学を体現していた。
敵キャラクターたちの美しい秩序
『エクセリオン』に登場する敵たちは、個性豊かな動きを見せるが、どこか“統一された美”を感じさせる。まるで一つの軍団が統率されているように、一定のリズムで現れ、同じ方向に旋回し、同じタイミングで攻撃してくる。 この整然とした動きが、ゲーム全体に秩序と緊張感を与えており、プレイヤーに「崩してはならない編隊」を破壊する快感を味わわせる。 特に中盤に登場する“高速スライダー型”の敵は人気が高い。縦横無尽に動きながらも、一度リズムを掴むと見事な連撃で全滅できる。この敵との“呼吸の一致”を感じられる瞬間が、多くのプレイヤーにとって忘れられない体験だった。
最初に出会う敵 ― スカイインベーダー
最初のステージに登場する小型戦闘機「スカイインベーダー」は、シリーズを通してプレイヤーの印象に強く残る存在だ。動きは単調だが、まっすぐ突っ込んでくるそのシンプルさが、初心者にとって最初の“敵らしい敵”として機能している。 その形状は円形を基調としており、どこかクラゲのようにも見える。単純なドットパターンながらも、上下の点滅で「生物的な呼吸」を感じさせるデザインが秀逸だ。プレイヤーにとっては“最初に撃ち落とした敵”として、特別な記憶に残る存在となっている。
編隊で迫る ― オルビタル編隊
中盤以降に登場する「オルビタル編隊」は、『エクセリオン』の象徴的な敵グループといえる。彼らは単独で攻めてくることはなく、常に隊列を組み、一定の軌跡を描いて動く。その動きは一見シンプルだが、実際には高度な誘導パターンで構成されており、プレイヤーの位置を感知して微妙に変化する。 そのため、見た目は同じ動きをしているように見えても、毎回わずかに異なるタイミングで接近してくる。これにより、プレイヤーは反射的な動きではなく“リズム感”を意識した操作を求められる。多くの上級者がこの編隊を「美しい敵」と呼んだのも納得だ。
奇襲型 ― カモメ型エネミー
一部のステージでは、上空から急降下してくる“カモメ型”の敵が出現する。この敵は軌道を描きながら高速で落下してくるため、予測が難しい。しかも、他の敵と異なり、ほぼ無音で登場するため、油断していると一瞬で衝突してしまう。 この敵は多くのプレイヤーにとって“トラウマ”でもあり、“目の端に映った瞬間の恐怖”を味わった人も多い。それでも、このカモメ型を完全に避けきり、逆に撃墜できたときの達成感は格別で、「憎たらしいけど好き」と語る人も少なくなかった。
ボーナスステージのアイコン ― ブレイン・ドローン
ボーナスステージに登場する“ブレイン・ドローン”は、プレイヤーの緊張を和らげる不思議な敵である。外見は丸く、まるで風船のようにふわふわと動くが、撃ち落とすと爽快な効果音とともに高得点が入る。 彼らは“敵”であると同時に“スコアチャンス”の象徴であり、プレイヤーに「撃つ喜び」を思い出させる存在だった。無機質な宇宙戦闘の中で、少しだけユーモラスなデザインが挿入されていることも、『エクセリオン』のセンスの良さを感じさせる。 この敵が出現すると、プレイヤーの表情が自然と緩む。まさに、“戦場における一瞬の安らぎ”のような存在である。
無音の存在 ― 背景そのものがキャラクター
『エクセリオン』では、背景そのものも一種の“キャラクター”として機能している。絶えず動く星空は単なる背景ではなく、プレイヤーの移動感覚を支配する“もう一人の敵”のような存在だ。 星々の動く速度が速くなるにつれ、プレイヤーの心拍数も上がり、まるで敵と会話しているかのような感覚に陥る。この「環境をキャラクター化する設計」は、後のSFゲームにも受け継がれていく要素となった。 特に夜空のような深い青のトーンは、単色ながらも豊かな情緒を生み出し、プレイヤーによっては「無言の相棒」として星々を感じていたという。
記憶に残る「最後の一機」
プレイヤーにとって最も感情移入できる瞬間は、残り1機で迎える終盤だ。画面下に表示される小さな自機アイコンが、まるで「最後の希望」を象徴しているように見える。敵の猛攻の中、最後の1機で戦い抜くその時間こそが『エクセリオン』のドラマである。 この“最後の一機”という概念が多くの人の記憶に残っているのは、単なるゲームオーバーの直前ではなく、“自分自身の限界と向き合う瞬間”だからだ。プレイヤーの間では「最後の一機こそが本当の主人公」と言われることもあった。
キャラクター性を超えた「抽象の美」
『エクセリオン』の登場キャラクターたちは、いずれも具体的な名前や設定が与えられていない。しかし、その匿名性こそが本作の魅力でもある。明確なストーリーを語らない代わりに、プレイヤーが自由に想像を広げられる余白がある。 ある人にとって敵はエイリアンの軍団、またある人にとっては宇宙のウイルス――といったように、個々の想像が世界観を補完していく。この“無名のキャラクターたち”が多くの思い出を生んだことは、後の派手な演出中心のゲームにはない静かな美徳だ。 無機質で、匿名で、それでも記憶に残る。『エクセリオン』のキャラクターたちは、まさに“ドットの中に宿る魂”そのものだった。
総評 ― 名もなき戦士たちの詩
『エクセリオン』には、派手なキャラクターデザインも、台詞も存在しない。それでも、プレイヤーたちはそこに人格を見出し、感情を投影してきた。自機は孤独な戦士、敵は秩序を持つ宇宙の群れ、そして星々はその戦いを静かに見守る観客――。 この“無言のドラマ”が、後の多くの作品に影響を与えたのは間違いない。キャラクター性を文字や声で語らず、動きとリズムで感じさせる――それこそが『エクセリオン』の真の芸術性であり、40年経った今でも多くのファンが「好きなキャラクターは“無名の敵”」と語る所以である。
[game-7]●MSX版とアーケード版の違い
1. グラフィック表現の差 ― 擬似3Dの再現度
アーケード版『エクセリオン』の最大の特徴は、奥行きを感じさせる「擬似3Dスクロール」だ。背景の星空が手前から奥へと流れるように動き、プレイヤーはまるで宇宙空間を突き進んでいるような感覚を得られた。 しかしMSXは、当時のVRAM速度や描画チップの制限により、同様の滑らかさを完全に再現するのは困難だった。そのため、MSX版では“段階的な背景移動”による立体感の表現にとどまり、星の流れも一定速度で、アーケード版より“平面的”な印象となった。 ただし、電波新聞社はこの制限を逆手に取り、背景をやや暗く、星の輝度を強めに描くことで深みを演出。結果として、硬質な“宇宙の静けさ”が際立つ、独特の味わいを持つ移植になった。
2. 自機の挙動と慣性の感覚
アーケード版の操作性は、8方向レバー+2ボタンによる精密な慣性制御が特徴で、スティック入力の微妙な力加減で滑走距離が変化した。滑る感覚は“物理的リアルさ”に近く、初めて触れた人はその挙動に驚いたものだ。 MSX版では、ジョイスティックやキーボード操作によるデジタル入力が基本であり、細やかなアナログ的制御は難しかった。その結果、慣性は簡略化され、「一定の惰性を持つものの、アーケードよりも扱いやすい」バランスに調整されている。 つまり、アーケードが“職人の操作精度を要求する硬派な挙動”だったのに対し、MSX版は“家庭でも楽しめる範囲での慣性再現”を目指した設計といえる。
3. 弾の種類と発射制限のバランス
アーケード版では、「デュアルショット」と「シングルショット」の2種が実装されており、特にデュアルショットは画面上に最大1発しか発射できない仕様がリアルなテンポを生んでいた。MSX版でも同様のシステムを採用しているが、弾速・発射間隔が微妙に異なる。 アーケードでは高速かつ滑らかに飛ぶ弾が緊張感を作っていたのに対し、MSX版では処理落ちを避けるため、弾速をやや遅く、反応しやすくした。 また、MSX版ではシングルショットの残弾制限がより厳しく設定されており、弾切れになりやすい。この点について当時のユーザーからは「戦略的で面白い」「でも理不尽」と意見が分かれたという。
4. 敵の動きとパターン数の違い
アーケード版の敵はスプライト数に余裕があり、滑らかな編隊飛行や多彩な攻撃パターンを見せた。画面上で同時に10体以上が入り乱れるシーンもあり、圧倒的な密度感が魅力だった。 一方MSX版では、スプライトの同時表示数に制限があるため、一度に登場する敵の数が少なめ。その代わり、出現タイミングを細かく調整し、リズム的な戦いに焦点を当てた構成となっている。 そのため、アーケード版が“物量で攻めるスリル型”だとすれば、MSX版は“テンポを読むリズム型”といえる。敵の数では劣るが、パターンの組み合わせで緊張感を作り出す構成力が光っていた。
5. グラフィックの再構成と発色
アーケード版では当時としては珍しく、マルチレイヤー背景と複数色のスプライトを同時に使用していた。敵の体表がグラデーションのように輝く表現は、当時のゲーマーに強烈な印象を与えた。 MSX版では、ハード制約のためにカラーパレットが少なく、単色中心の構成となったが、その分、敵の形状が明確に見えるよう工夫されている。 さらに、アーケードでは存在しなかった“星の点滅アニメーション”を追加し、夜空の動きを強調することで、少ない色数ながらも深い雰囲気を出していた。電波新聞社が持つ「色の間引きと陰影表現」の技術が発揮された部分である。
6. サウンドの違い ― 効果音中心のMSX、旋律的なアーケード
アーケード版『エクセリオン』は、独特の電子音BGMとともに進行する。特にステージ開始時の上昇音や敵撃破時の電子パルス音は、プレイヤーの緊張を高める重要な演出だった。 一方、MSX版ではサウンドチップの制約によりBGMがほぼ存在せず、効果音のみで構成された静寂の世界となっている。この“無音の宇宙”がかえって独特の臨場感を生み、音の少なさが逆に没入感を強めた。 つまり、アーケードが「音で盛り上げる作品」だったのに対し、MSX版は「音を削って空間を感じさせる作品」として方向性がまったく異なっていた。
7. 難易度バランスとテンポの違い
アーケード版は敵弾の速度が速く、反射神経を試す“瞬発系の難しさ”だったのに対し、MSX版は敵の出現間隔を調整してあり、戦略的なプレイを重視している。 また、MSX版はリスタート後の敵出現パターンが固定化されているため、覚えゲー的な攻略が可能で、努力で克服できる設計になっている。アーケード版では毎回微妙に異なるランダム要素が加わっており、安定攻略が難しかった。 そのため、MSX版は“家庭で繰り返し練習して上達する楽しみ”が強く、アーケードとは違うプレイ体験を提供していた。
8. ゲーム構造とエンディング要素
アーケード版は、無限ループに近い構成で、エンディングは存在しない。MSX版も基本的には同様だが、一定条件で出現するボーナスステージが追加されており、プレイヤーに明確な“区切り”を与えている。 このボーナスステージはアーケードにはなかったMSX独自要素であり、家庭用に適した「報酬型の構成」になっている。これにより、達成感と再挑戦意欲を両立することに成功した。 つまり、MSX版は“繰り返し遊べるアーケードライク”でありながら、“一息つける家庭用のテンポ”を備えたハイブリッド作品だった。
9. 総評 ― 「体感のゲーム」から「思考のゲーム」へ
アーケード版『エクセリオン』が追求したのは、“操作と反射神経の融合”というスリルの体験である。一方、MSX版が提示したのは、“状況判断とリズム制御”の思考型体験だった。 どちらも同じタイトルでありながら、プレイヤーが得る感覚は全く異なる。アーケードは瞬間の緊張を、MSXは長時間の集中を重視している。 ハードの制限の中で「遊びの本質」を別の角度から引き出したMSX版は、単なる移植にとどまらない“再解釈”の作品といえる。今なおファンが「MSX版の静けさが好き」と語るのは、まさにこの哲学の違いに魅力を感じているからだ。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1984年前後は、日本のパソコンゲーム黎明期の中でも特に革新の波が押し寄せた年だった。
『エクセリオン(MSX版)』が登場したこの時期、各メーカーが独自の方向性を打ち出し、アーケード移植だけでなく“家庭用独自の創造”が始まりつつあった。
ここでは、同時期に発売された代表的な10タイトルを紹介し、『エクセリオン』との共通点・対照点を整理する。
★1. ザナック(コンパイル)
・販売会社:コンパイル ・発売年:1984年(MSX) ・販売価格:4,800円前後 ・内容:人工知能(AI)がプレイヤーの行動に応じて難易度を変化させる革新的STG。 『エクセリオン』が“物理的な操作感”を重視したのに対し、『ザナック』は“知的な反応性”を導入した最初期の作品である。敵の出現や弾幕の密度がプレイヤーの撃ち方で変化し、常に新しい展開を体験できる設計は後のシューティング史を変えた。 当時、両作を遊んだプレイヤーからは「エクセリオンは体感の宇宙、ザナックは思考の宇宙」と評されたという。
★2. イー・アル・カンフー(コナミ)
・販売会社:コナミ ・発売年:1984年(MSX / アーケード) ・販売価格:4,800円 ・内容:格闘ゲームの先駆け。多彩な敵と技、反射神経を試す攻防。 『エクセリオン』と同様、アーケードの熱をMSXで再現した移植成功例として評価が高い。コナミが描いた“等身大キャラの戦い”は、電波新聞社の“抽象的な宇宙戦”とは対照的だったが、どちらも「入力の手触り」を重視していた点が共通している。 同時期に発売されたこの二作が、「家庭用でもアーケードの緊張感は再現できる」という認識を広げた。
★3. ギャラガ(ナムコ)
・販売会社:ナムコ ・発売年:1981年(アーケード)/1984年(MSX移植) ・販売価格:4,500円 ・内容:『ギャラクシアン』の進化版で、敵が捕獲してくる斬新なシステムを採用。 MSX版『エクセリオン』と同じく宇宙を舞台にした固定画面STGであり、敵の編隊と“間合いの読み合い”という点で通じる部分が多い。 ただし、『ギャラガ』は「敵の秩序」を見せる演出が強く、エクセリオンが“慣性の混沌”を描いたのに対し、こちらは“規律とリズム”を追求した作品だった。
★4. ボスコニアン(ナムコ)
・販売会社:ナムコ ・発売年:1983年(アーケード)/1984年(MSX) ・販売価格:4,800円 ・内容:自由移動型の宇宙戦闘を実現した斬新なシューティング。 エクセリオンが「固定画面の限界を押し広げた」作品なら、ボスコニアンは「フィールドそのものを開放した」作品だった。 両者は同じ宇宙をテーマにしていながら、方向性が真逆である。エクセリオンが“瞬間の技術”を求めたのに対し、ボスコニアンは“長期戦略”を要求する。 この2作が共存した1984年は、STGが“多様化の時代”に突入した象徴的な年でもあった。
★5. スターソルジャー(ハドソン)
・販売会社:ハドソン ・発売年:1984年(PC-8801) ・販売価格:5,200円 ・内容:縦スクロール型STGの金字塔。爽快な連射と隠しボーナス要素で人気を博した。 『エクセリオン』が“重量感と緊張”を重視したのに対し、『スターソルジャー』は“爽快感とスピード”を売りにした。 どちらも“撃つ快感”を軸にしているが、前者が「宇宙の静寂」を描いたのに対し、後者は「宇宙の熱狂」を表現している。ジャンルの方向性が分岐し始めた分水嶺的作品と言える。
★6. ナイトローダー(電波新聞社)
・販売会社:電波新聞社 ・発売年:1984年(MSX) ・販売価格:4,500円 ・内容:近未来の道路を疾走するカー・シューティング。 『エクセリオン』と同じ開発・販売元であり、同社が「立体感とスピード感」を得意としていたことが分かる。 ナイトローダーでは、道路の奥行きと遠近感を描く技術がさらに進化しており、擬似3D表現の系譜として『エクセリオン』の延長線上にある。 開発スタッフの中には、エクセリオン移植チームのメンバーも関わっていたとされ、電波新聞社の技術力の高さを示す作品である。
★7. ハイドライド(T&Eソフト)
・販売会社:T&Eソフト ・発売年:1984年(PC-8801 / MSX) ・販売価格:5,800円 ・内容:アクションRPGの草分け的存在。リアルタイムで戦うフィールド型RPG。 『エクセリオン』が“操作と反射神経”を重視したのに対し、ハイドライドは“探索と成長”に重きを置いた。 異なるジャンルではあるが、「画面上の1キャラクターを通じて世界を感じる」という根本の設計思想は共通しており、当時の日本PCゲームが“操作と没入”を中心に進化していたことを示している。
★8. グラディウス(コナミ)
・販売会社:コナミ ・発売年:1985年(アーケード)/1986年(MSX) ・販売価格:5,800円 ・内容:横スクロールSTGの革命児。パワーアップ・カプセル制を導入。 『エクセリオン』の慣性操作は、この『グラディウス』のスピード制御システムに影響を与えたとされる。 MSX移植版では処理落ちや敵数制限が課題となったが、プレイヤーが自分で“成長させる自機”という思想は、『エクセリオン』の“変わらぬ主人公機”との対比で語られることが多い。 “静と動”という二つの対極の魅力が、80年代STGを支えていた。
★9. シーザーの野望(光栄)
・販売会社:光栄(現コーエーテクモ) ・発売年:1984年(PC-8801) ・販売価格:6,800円 ・内容:歴史シミュレーションの初期作。戦略性と地図表現が特徴。 一見『エクセリオン』とは無関係に思えるが、共通しているのは「操作によって世界を支配する感覚」だ。 STGが“瞬間的支配”を描くのに対し、シミュレーションは“長期的支配”を描く。どちらもプレイヤーに「支配の快感」と「責任の緊張」を与えるゲームデザインであり、1984年のPCゲームが目指していた“インタラクティブな没入”の象徴的な例である。
★10. スペースマンボウ(コナミ)
・販売会社:コナミ ・発売年:1984年(MSX) ・販売価格:4,800円 ・内容:宇宙を舞台にした横スクロールSTG。美しい星空と魚型戦艦が印象的。 『エクセリオン』と同時期のMSX宇宙系タイトルの中でも特に人気が高く、「静かな宇宙」と「攻撃的なデザイン」を両立させた美的センスで高く評価された。 両作は“宇宙の描き方”が異なる――エクセリオンが“孤独と無音の宇宙”を描いたのに対し、スペースマンボウは“生命と光の宇宙”を表現した。 この二つの世界観が、80年代MSXゲームの“宇宙観の二大潮流”を形成したといわれる。
■ 総括 ― 1984年という創造の交差点
これらの作品群を見ると、『エクセリオン』が属した1984年前後の時代がいかに豊穣であったかがわかる。 アーケードのスピード感を持ち込みつつ、各社が「自宅での没入」をどう作るかを模索していた。『エクセリオン』はその中で、“リアルな操作感”というテーマを掲げ、後のゲーム表現に道を開いた。 同時代のライバルたちは皆、異なる方向から「プレイヤーの感覚を拡張する」挑戦をしており、その相互刺激が80年代ゲーム文化を形づくったのである。
[game-8]

![【中古】[お得品]【表紙説明書なし】[FC] エクセリオン(EXERION) ジャレコ (19850211)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102491.jpg?_ex=128x128)