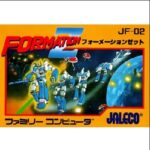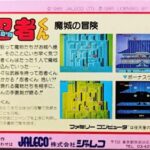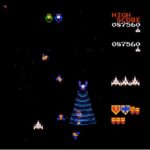【中古】 ファミコン (FC) エクセリオン (ソフト単品)日焼け有り
【発売】:ジャレコ
【開発】:トーセ
【発売日】:1985年2月11日
【ジャンル】:シューティングゲーム
■ 概要
ジャレコ初のファミコン参入作品としての意義
1985年2月11日、ジャレコ(JALECO)は家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」における初のタイトルとして『エクセリオン』を世に送り出した。アーケードでの成功を受けて開発されたこの作品は、単なる移植ではなく、家庭用の環境に合わせて再構築された一種の実験的タイトルでもあった。当時のジャレコは業務用ゲームで急成長を遂げていたが、家庭用市場はまだ黎明期。任天堂・ナムコ・ハドソンなどが勢力を伸ばす中で、自社ブランドを確立するための“第一歩”としてこの作品が選ばれた。
ファミコン版『エクセリオン』は、1983年に稼働したアーケード版をベースにしながらも、グラフィック構成、画面比率、敵配置、慣性システムなどに独自の調整を施しており、アーケード版の再現を目指すというよりも「家庭用向けに遊びやすく再設計されたシューティング」と言える。ジャレコの技術陣が限られたROM容量の中で、どこまで原作の臨場感を維持しながら遊びやすさを追求できるか──それが当時の開発上の挑戦であった。
舞台設定と物語の背景
物語の舞台は、銀河の辺境に存在する惑星「エクセリオン」。この惑星は、突如として現れた敵勢力ゾルニ軍の侵略を受け、壊滅の危機に瀕していた。プレイヤーは最終防衛戦力「ファイターEX」のパイロットとなり、宇宙空間を縦横無尽に飛びながら侵攻してくる敵艦隊を撃破していくことになる。 本作ではストーリー要素こそ簡潔だが、「孤独なパイロットが無限の宇宙に挑む」というテーマ性が漂っており、当時としては珍しいSF的世界観を背景に据えていた点も印象的だ。
また、ステージ背景に広がるグリッド状の立体描写は、単に視覚的な演出にとどまらず、プレイヤーに「奥行きのある空間」を感じさせることを目的としている。これは後の3D表現への萌芽ともいえる技法であり、1980年代初頭のドット技術としては画期的な試みだった。
独自の慣性システムと操作感
『エクセリオン』最大の特徴は、従来の固定型シューティングとは異なる“慣性”の概念を導入した点である。ファイターEXはボタンを離してもすぐには停止せず、しばらく滑るように移動を続ける。この挙動により、プレイヤーは自機の動きを常に先読みして操作する必要があり、他の作品にはない緊張感とリズムが生まれている。
この慣性システムは、単に難易度を上げるためではなく、宇宙空間の無重力感を表現する意図があった。敵の弾を避けるには、反射的な操作ではなく、「次の瞬間どこに自機が移動するか」を予測して行動しなければならない。そのため、プレイヤーは自然と“機体を操縦している”という没入感を得られるよう設計されている。
2種類のビームと戦略性
攻撃手段として用意されたのは「シングルビーム」と「デュアルビーム」の2種類。シングルビームは連射が可能である代わりに火力が低く、デュアルビームは2発同時発射による高威力攻撃が可能だが、発射後のクールタイムが発生する。これらを場面ごとに使い分ける戦略が、プレイの深みを生み出している。
シングルビームで雑魚敵を掃討しつつ、危険な大型敵や敵編隊が接近した際にはデュアルビームを放つ――このリズムの切り替えが本作の醍醐味であり、プレイヤーの判断力が試される要素でもある。さらに、ビームの残弾制限がないにもかかわらず、発射間隔のタイミング管理が求められるため、単調な連射ゲーに陥らない絶妙なバランスが実現されている。
ファミコン移植による変化と制約
アーケード版は縦画面仕様であったのに対し、ファミコン版はテレビの横長画面に合わせた横画面設計となった。この変更により、敵との距離感が近くなり、戦闘がよりスピーディかつ迫力あるものに変化している。背景のグリッドも新たに描き直され、家庭用の制限の中でも立体感を再現する工夫が施された。
ただし、同時表示スプライト数やメモリ容量の制約から、敵の出現パターンや攻撃頻度はアーケード版よりも簡略化されており、プレイヤーによっては「テンポが異なる」と感じることもあった。それでも、家庭用に最適化された調整によって、当時のファミコンユーザーには十分な新鮮味をもって受け入れられた。
BGM・効果音の印象
サウンドはファミコン特有の三和音構成で、BGMは戦闘中も淡々と流れ続けるミニマルな電子音。効果音の存在感が強く、ビーム発射音や爆発音がリズムを刻むように鳴り響く構成となっている。とくにビームの発射音には独特の金属的な響きがあり、画面全体に緊張感を与える。音楽的にはシンプルだが、その無機質さがかえって宇宙戦の孤独さを際立たせており、プレイヤーの記憶に残るサウンドデザインと評価されている。
ゲーム構成とステージ進行
『エクセリオン』には明確な「ステージクリア」の概念があるものの、実際には無限ループ型の進行を採用している。敵の出現パターンやスピードが徐々に上がっていくため、プレイヤーの集中力と操作技術が長期的に試される構造だ。特定の条件を満たすとボーナスステージが出現し、敵編隊を全滅させることで高得点を狙える。このスコアアタック要素は、当時のアーケード文化を家庭用に移植した象徴でもあり、後のファミコンタイトル(例:ゼビウス、スターソルジャーなど)にも影響を与えた。
開発背景と技術的挑戦
当時のジャレコ開発チームは、アーケード作品を短期間でファミコンに落とし込むという厳しいスケジュールを課せられていた。ファミコンのROM容量はたった32キロバイト前後、RAMも限られており、アーケード基板での表現をそのまま再現するのは不可能だった。そこで彼らは、「再現ではなく再構成」というアプローチを採用し、グラフィックを簡略化しつつもスピード感を損なわないようプログラム設計を工夫した。
とくに注目すべきは、慣性処理のアルゴリズム。ファミコンではフレームごとに自機位置を補正する演算が重く、処理落ちを避けながら自然な滑りを表現するには絶妙なチューニングが必要だった。結果として、『エクセリオン』の操作感はファミコン初期作品の中でも独自の手触りを持つものとなり、のちの開発者たちが「ジャレコの技術力を象徴する一作」として語るほどになった。
総評としての位置づけ
『エクセリオン』は、単なる移植作ではなく、ファミコンという新しい舞台で“宇宙戦の感覚”を表現した意欲的な作品である。アーケード時代の熱気を家庭のテレビにそのまま持ち込み、1980年代の子どもたちに「家庭でもアーケードの緊張感を味わえる」ことを実証してみせた。その挑戦心こそが、後のジャレコタイトル――『フォーメーションZ』や『シティコネクション』――へとつながっていく礎となったのだ。
■■■■ ゲームの魅力とは?
ファミコン黎明期における新感覚の“宇宙戦体験”
『エクセリオン』が持つ最大の魅力は、1985年当時としては極めて斬新だった「慣性付きの宇宙空間シューティング」というプレイフィールにある。ファミコンがまだ『ゼビウス』や『ギャラガ』のような固定画面型・縦スクロール型の模倣作品であふれていた中で、本作はプレイヤーの操作に“滑り”を加え、まるで宇宙を漂うような独特の浮遊感を実現した。
この挙動は単なる技術的な gimmick(ギミック)ではなく、プレイヤーの心理的没入を強く誘発する要素として機能していた。ボタンを離しても止まらない機体。じわりと前に出て、勢い余って敵の弾にかすめる――そんな感覚は、単純な反射神経ゲームではなく、空間を読む戦術的な思考を要求する新しいシューティング体験だった。今で言う「慣性制御シミュレーター」の原型的存在と言えるだろう。
2種類のビームを使い分ける戦略性
プレイヤーが操るファイターEXは、2種類のショットを駆使して敵を撃破していく。ひとつは「シングルビーム」。こちらは連射可能で扱いやすい主力兵器であり、テンポよく撃てるため初学者でも安心して使用できる。一方で、威力は控えめで、密集した敵集団やボス格の敵を仕留めるには時間がかかる。
そこで活躍するのが「デュアルビーム」だ。名前のとおり2発同時に放つ高火力ショットで、直撃すれば一瞬で敵編隊を壊滅させる威力を持つ。しかしそのぶん発射後にはチャージタイムが必要となり、短時間ながら無防備になるリスクもある。したがって、どのタイミングで強力な攻撃を繰り出すか――その判断が勝敗を分ける。
この「瞬発力と隙のリスク管理」という二律背反の設計が、プレイヤーの判断力を鍛える絶妙な緊張感を生んでいる。単に撃ち続けるだけの単調なシューティングではなく、“攻めるか、避けるか”の呼吸を読み合う駆け引きのある戦闘が展開されるのだ。
独自のテンポ感と緩急の演出
『エクセリオン』のゲームテンポは、他のファミコン初期作品とは明らかに異なる。敵の出現スピードや攻撃頻度が緩やかに変化していくことで、プレイヤーに緊張と緩和のリズムを刻み続ける。特に注目すべきは、敵編隊が波のように押し寄せてくるステージ構成。ひとつの波を越えた瞬間に訪れる静寂が、次の猛攻を予感させる“間”を生み出している。
この設計は、当時のアーケード文化――「1コインでどれだけ長く生き残るか」という耐久的プレイスタイル――を家庭用に再構成したものであり、プレイヤーの集中を長時間維持させることに成功している。BGMが淡々と続くなか、効果音だけが戦況を語る。この静寂の中の緊張こそが、『エクセリオン』ならではのドラマ性なのだ。
慣性操作が生む没入感と学習性
本作をプレイした多くの人が感じるのは、「最初は思いどおりに動かせないのに、慣れてくると異様なほど気持ちよくなる」という操作の中毒性である。初見では“滑りすぎて当たる”という印象を持つかもしれないが、実際にはこの慣性の挙動を身体で覚えることで、プレイヤーは次第に“宇宙空間の物理”を理解していく。
慣性制御に慣れると、敵の弾をギリギリでかわしながら逆襲する――いわば“重力を手懐ける感覚”が味わえる。シンプルな操作なのに、熟練度が上がるほど自在な動きが可能になる設計は、後の『グラディウス』や『R-TYPE』のような操作学習型STGの先駆けといっても過言ではない。
グラフィックの立体感と宇宙演出
『エクセリオン』の背景には、当時としては珍しい“疑似3Dグリッド”が描かれている。これは単なる装飾ではなく、プレイヤーが自機の位置や移動方向を直感的に把握するための視覚的補助として機能している。さらに、敵機がグリッド上を立体的に動くように見える演出も巧妙で、平面の画面に奥行きを与える効果を生み出していた。
ジャレコの開発陣は、アーケード基板のスプライト処理をファミコンの制約下で模倣するために、複数のタイル描画を組み合わせる工夫を行っている。その結果、敵の動きや爆発表現にも「広がり」を感じさせる描画が実現された。特に敵が分裂しながら消滅するアニメーションは、当時のプレイヤーの印象に強く残っている。
緊張感を生むサウンドデザイン
音楽面の派手さはないが、音そのものが持つ“間”と“余白”が緊迫感を支えている。ビーム発射音は硬質な電子ノイズで、まるで金属を弾くような乾いた響き。爆発音も短く鋭いパルスで構成され、無音に近い空間の中で際立つ。この構成が、宇宙空間の孤独や無機質な戦いを強調しており、プレイヤーに“静寂の中の戦闘”を体験させる。
当時の多くのファミコンタイトルはBGM重視だったが、『エクセリオン』はあえてそれを抑え、音の配置で感情を誘導する。現代のゲームデザインの観点から見ても、サウンドによる“心理的演出”を意識した先駆的作品といえる。
難易度バランスとリプレイ性
『エクセリオン』の難易度は一見高めに感じられるが、実際には練習を重ねることで着実に上達が実感できる設計になっている。敵の出現パターンには一定の法則性があり、プレイヤーは次第にその“波”を読めるようになる。慣性操作に慣れたプレイヤーほど、スコアを伸ばす楽しみが増していく構造だ。
また、ステージ構成がループ制であるため、プレイヤーごとの“限界突破”を競うスコアアタック性が高く、友人同士でスコアを競い合うことができた。家庭用ゲーム機で「終わりなき挑戦」を味わえるという点も、当時の子供たちにとって新鮮だった。
アーケード版との違いが生んだ個性
アーケード版は縦画面仕様であり、敵の動きがより立体的で広範囲だったのに対し、ファミコン版は横画面化によって敵との距離が縮まり、緊迫した戦闘を強調する方向に変化している。この結果、より“瞬間反応型”のプレイ感覚が得られ、短時間でもスリリングな戦闘を楽しめる作品になった。
一方で、スプライト制限による同時敵数の減少が、逆に“見やすさ”を生み、プレイヤーが操作感覚に集中できるようになった。つまり、ファミコン移植による制約が、結果的に“シンプルで中毒性の高い遊び”へと昇華した好例といえる。
1980年代の子供たちに刻まれた“宇宙の孤独”
『エクセリオン』をプレイした世代にとって、このゲームは「派手さよりも静かな緊張を楽しむ」不思議な存在だった。スコアアタックを繰り返すうちに、次第に背景の星空に吸い込まれていくような感覚を覚える。敵を倒しても終わらない戦い、再び迫り来る無限の敵群。そこには勝利もエンディングもなく、ただ生き延び続けることだけが目的――それがこのゲームの根底に流れるテーマだった。
その孤独感と達成感のコントラストが、多くのプレイヤーの心に残り、のちに「ファミコン初期の名作シューティング」として語り継がれる理由となった。
■■■■ ゲームの攻略など
まず押さえておきたい基本操作と挙動
『エクセリオン』の攻略において最初に理解すべきは、自機の慣性挙動だ。通常のシューティングのように“押したら動く・離せば止まる”という単純な操作ではない。方向キーを離しても機体はしばらく滑り続けるため、停止や旋回にはワンテンポ早い入力が必要になる。 たとえば、敵弾を避ける際には「次の瞬間の位置」を予測して移動を始めなければならない。この一拍先読みの感覚が身につけば、戦場の生存率は大きく向上する。
慣れるまでは、ステージ序盤であえて敵弾をギリギリでかわす練習をするとよい。滑りながらの回避は、初見では制御不能に感じるかもしれないが、徐々に体で覚えてくる。感覚をつかむまで焦らず、少しずつ距離感を掴むのがコツだ。
シングルビームとデュアルビームの使い分け術
攻撃の基本となるのは、2種類のビーム――「シングルビーム」と「デュアルビーム」だ。どちらを使うかによって戦況が大きく変わる。 シングルビームは連射可能でテンポよく撃てるが、敵を倒すまでに時間がかかる。一方、デュアルビームは一撃の破壊力が高く、敵編隊をまとめて撃破できるが、発射後に“空白時間”が生まれる。この間に敵が反撃してくるため、無闇に乱発すると危険だ。
おすすめの戦術は、「シングルビームで弾幕を張りながら、デュアルビームをタイミング狙い撃ちで差し込む」方法だ。具体的には、敵が集団で直線的に迫ってくる場面――たとえば開幕の中型敵編隊や、敵母艦からの迎撃波――で、デュアルビームを放つと効果的。反対に、ランダムに動く小型敵相手には、シングルビームの手数で確実に対応するのが良い。
デュアルビームを撃つ際は、慣性移動を利用して「撃ちながら離脱」するのが上級テクニック。正面で撃ってしまうと、チャージ中に被弾しやすい。撃つ瞬間に横方向へスライドして、ビーム発射後にはすでに回避態勢に入る――この“撃ち逃げ”を体で覚えると、難易度が一段下がるだろう。
敵の出現パターンを覚えることが勝利の鍵
『エクセリオン』はアーケードライクな構成を持っており、敵の出現パターンはランダムではなく固定化された波状進行になっている。つまり、プレイを重ねることで次にどの敵がどの方向から出るのかを覚えれば、先手を打てる。 初めの数ステージは出現位置や軌道が分かりやすいが、中盤以降になると左右対称に敵が現れるパターンや、編隊が分裂して動く配置も登場する。
対策としては、「画面中央付近をキープしながら、敵の動きを観察する」こと。上端に張り付くと、慣性によって回避行動が遅れやすい。常に中央~下段を意識し、敵が上から降りてくるタイミングで横移動を入れると安全に処理できる。
また、敵が隊列で現れるときは、隊長機を最優先で撃破すること。隊長を倒すと隊列が崩壊し、残りの敵の動きが鈍る。この“リーダー狙い”は高得点を得る上でも有効なテクニックだ。
スコア稼ぎのポイント
本作では、ただ生き延びるだけでなく「スコア稼ぎ」を極めることが上級者への道だ。敵を連続で倒すとコンボボーナスが加算され、特定の波をノーミスで突破すると隠しボーナスも出現する。特に、敵が編隊を組んで出てくる場面でデュアルビームを的確に当てれば、一瞬で大量得点を獲得できる。
もう一つの稼ぎテクニックは「画面端の敵を追い込む」方法。エクセリオンの敵は画面外に逃げる前に一瞬停止する癖がある。その瞬間を狙ってビームを撃てば、確実に撃破できる上に次の波のテンポを崩さない。これを繰り返すと、スコアの伸びが飛躍的に上がる。
スコアを意識してプレイすることで、単なる反射ゲーから「戦術を設計するゲーム」へと進化する。これはアーケード時代のDNAを色濃く受け継いだシステムと言える。
ボーナスステージの出現条件
『エクセリオン』には一定条件で出現するボーナスステージが存在する。敵を一定数連続で撃破し、被弾せずに特定の波を抜けると突入できる仕様になっている。ボーナスステージでは敵が一斉に現れ、制限時間内に全滅させれば高得点が得られる。
ここで重要なのは「焦らず軌道を予測して撃つ」こと。敵の出現タイミングは毎回固定だが、慣性操作を誤るとビームが空を切る。動きすぎず、あらかじめ配置を覚えておくと、ほぼパーフェクトクリアが狙える。
このステージは1回の成功で数千点の差が出るため、ハイスコア狙いには絶対に外せない要素である。
難所攻略:敵弾の読み方と避け方
中盤以降、敵の弾幕が密度を増してくる。『エクセリオン』の弾は他作品よりも速く、慣性の影響で避けづらいため、「避ける」のではなく「弾を誘導する」発想が必要になる。 敵が発射する直前に少しだけ動いておくと、弾がプレイヤーの直前ではなくその先を狙って飛ぶ。これにより、弾道のズレが生まれ、結果的に安全な軌道が確保できる。
また、敵の種類によって発射間隔が異なるため、パターンを覚えるのも有効だ。たとえば、ザコ敵タイプAは1秒周期で弾を撃ち、タイプBは2発連射後に1秒停止する。この間に懐へ入り込んで撃つと確実に仕留められる。
リスクを抑えるポジショニング術
攻略の鍵は「安全地帯を見極める」ことだ。画面中央は全方向から攻撃されやすいが、慣性を制御しやすいエリアでもある。左右端に寄りすぎると、滑りすぎた際に戻る余地がなくなる。 理想の位置取りは、画面中央からやや下。ここなら敵弾の軌道を見やすく、上方向の迎撃と回避を両立できる。
また、ステージ後半では“敵が自機を狙って突進する”パターンが増えるため、正面衝突を避けるには「斜め軌道」を活用しよう。慣性で自然に斜め移動するように入力することで、敵の狙いを外しながら攻撃を続けられる。
終盤攻略:持久戦への備え
終盤では、敵の出現間隔が短くなり、プレイヤーの反応速度が試される。ここで焦って動きすぎると慣性でコントロールを失い、連続被弾に繋がる。あえて“止まる勇気”を持つことが重要だ。 敵が途切れる瞬間に位置をリセットし、次の波に備える。休むタイミングを意識できるかどうかで、クリア率は大きく変わる。
また、ファミコン版『エクセリオン』にはステージループ仕様があるため、完全クリアという概念は存在しない。つまり、「どれだけ長く生き残れるか」こそが真の目的だ。後半は体力よりも集中力との勝負になる。音やリズムに身を任せる感覚で、テンポを維持するのが長期プレイの秘訣だ。
上級者の裏技・テクニック
実は、慣性を逆手に取る“スライドショット”というテクニックが存在する。横移動中にビームを撃ち、すぐに逆方向へキーを入れることで、弾だけが直進し、自機が逆に流れる。この動作により、敵弾を避けながら攻撃を続けられる。特にデュアルビーム時に効果的で、リスクを大幅に減らせる。
さらに、敵が画面下に潜り込む前に撃ち落とすと、希に“消滅ボーナス”が発生する仕様もある(スコア上昇が通常より数百点高い)。これはバグではなく、仕様として設計された隠し得点で、スコア稼ぎプレイヤーの間で知られたテクニックだ。
こうした細かな奥行きが、シンプルなルールの中に“職人芸的”な深みを生んでおり、『エクセリオン』が今なお愛好家に語られる理由でもある。
■■■■ 感想や評判
当時のプレイヤーが感じた“未知の手触り”
1985年当時、『エクセリオン』をプレイした子どもたちの第一印象は、「とにかく操作がむずかしい」だった。十字ボタンを離しても止まらない――その挙動は、当時の固定型シューティングに慣れたプレイヤーにとって衝撃的だった。 だが同時に、「これこそ本当の宇宙空間を飛んでいる感じがする」と語る声も多く、他作品にはない“無重力感”が強烈な印象を残した。
特に、慣性による滑りがうまく操れるようになった瞬間の快感は格別で、「最初はストレスだったのに、後半はそのクセにハマる」といった意見が多く見られた。
子どもたちの中には、友人同士で「どれだけ長く生き残れるか」を競い合う“耐久プレイ大会”を開く者もいたという。シューティングの上達過程がそのまま「慣性を読めるようになる自分の成長」として体感できるゲーム――それが『エクセリオン』の魅力だった。
ゲーム雑誌・専門誌での評価
発売当時、ゲーム専門誌『ファミリーコンピュータマガジン』や『マイコンBASICマガジン』では、『エクセリオン』は“異色のシューティング”として取り上げられた。 特に評価されたのは、操作感覚の革新性とSF的な演出表現。同時期にリリースされた『ゼビウス』や『スターフォース』がスピード感を前面に出していたのに対し、本作は静けさと浮遊感を重視した“対極の方向性”を打ち出していた。
誌面では「上達するほど奥が深く感じられる」「単純明快なのに中毒性がある」と高評価を得ており、特に熱心な読者投稿コーナーでは“慣性マスター”を名乗るプレイヤーが攻略法を寄稿するなど、コアな人気を集めていた。
ただし一方で、「スピード感がない」「敵が少なくて地味」という声もあり、評価は割れた。しかし、否定的な意見ですら「このゲームは人を選ぶが、ハマる人にはたまらない」と結論づけられており、結果的には“マニア受けする硬派なタイトル”として定着していった。
ファミコン参入第1弾としての意義
『エクセリオン』が語り継がれるもう一つの理由は、ジャレコの家庭用参入第一弾ソフトだった点だ。 当時のゲームファンの間では「ジャレコがファミコンに来た!」という話題性が強く、ゲームショップの店頭では、ジャレコのロゴ入りパッケージが目立っていた。
ファミコン初期のソフトは、グラフィックや音楽に制約が多い中で各社が独自色を模索していた時期。そんな中で、『エクセリオン』は“技術的挑戦”を感じさせる一本として高く評価された。
特にプログラマ層からは、「慣性処理をあのメモリで実現したのは驚異的」との称賛が寄せられた。のちに『フォーメーションZ』などを手掛けるスタッフが在籍していたこともあり、技術者の研鑽の場としても重要なタイトルだったのだ。
後年のレトロゲームファンからの再評価
1990年代後半以降、レトロゲームの研究やレビュー文化が盛んになると、『エクセリオン』は再び注目を集めるようになった。 「ファミコン黎明期の異端作」「アーケード移植を超えた家庭用独自作品」として語られることが増え、特にコレクターやYouTuberによるプレイ動画では、その独特な操作性が再評価された。
多くのプレイヤーが共通して挙げるのは、“慣れたら楽しい”という中毒的な成長体験である。
現代のゲーマーにとっても、初期の数分は戸惑うが、操作のクセをつかむと一気に爽快感が増す。まるで自分の指が機体と一体化するような感覚――このプレイヤーの“学習による快感”が、他のレトロSTGでは味わえない深みを与えている。
また、グリッド状の背景や立体的な敵配置を「当時の3D表現の萌芽」として捉える意見も多く、技術史的観点からも価値の高い作品として再評価されている。
プレイヤーコミュニティでの人気の広がり
近年のSNSや掲示板では、『エクセリオン』は「地味だけどクセになるファミコン」としてよく話題に挙がる。 「最初は意味がわからないのに、やめられなくなる」「敵をかわしながら滑る瞬間が最高」といった投稿が多く、2020年代に入っても根強い人気を保っている。 さらに、同作のBGMをリミックスしたファンアレンジや、ドット絵を現代風に再現したファンアートなども登場し、静かながら愛され続けていることがうかがえる。
ファミコン実機でプレイする愛好者の中には、「慣性のあるゲームの原点」として『エクセリオン』を基準に他のSTGを比較する人も多く、“慣性系STG”の元祖という評価も定着している。
批判的意見とその背景
もちろん、すべてのプレイヤーが高く評価したわけではない。当時から「動きが重すぎる」「敵の種類が少ない」「スピード感に欠ける」といった批判も存在した。 これらの意見の多くは、“アーケード版との比較”が前提となっている。縦画面だったアーケード版の方が敵のバリエーションや視野の広さがあり、ファミコン移植版はそれを簡略化したことで「単調に感じる」とする声もあった。
ただし後年、この“簡略化”が逆に遊びやすさや集中のしやすさを生み、家庭用ならではのテンポを確立していたと評価が改められている。つまり、『エクセリオン』の評価は時代とともに変化し、短期的には地味でも長期的には味わい深い作品として位置づけられるようになったのだ。
評論家による総合的評価
近年のレトロゲーム評論家たちは、『エクセリオン』を“感覚学習型ゲーム”と定義することが多い。すぐに上手くならないが、経験がプレイヤーの技術を直接変えるタイプのゲームであり、80年代中期においてこの構造を成立させていたことは特筆すべきだとされている。
評論家の中には、「ファミコンの技術的限界を逆手に取った設計」「抽象的な宇宙の表現美」「サウンドによる孤独演出」を高く評価する声も多い。特に効果音によるリズム的没入は、後の『スターソルジャー』シリーズや『グラディウスII』に通じる“戦闘の音楽化”の原点とも言われている。
結果として、現在では『エクセリオン』は“先駆的な設計思想を持つ作品”として教科書的な存在となり、ファミコン史において技術面・演出面の両方から語られる重要な一作とされている。
ファンの声が証明する“長寿タイトル”
発売から40年近く経った現在でも、レトロゲームの愛好者からは「今遊んでも面白い」「当時理解できなかった良さが今になってわかる」との声が多い。 特に中高年層のファンの間では、「あの頃のファミコンでこんな動きを再現していたのがすごい」と技術的な驚きが再燃している。
このように『エクセリオン』は、単なるノスタルジーの対象にとどまらず、“理解が深まるほど評価が上がるゲーム”として、世代を超えて愛されている。初見では不器用に感じられるその挙動が、実は緻密に計算されたデザインの賜物である――その事実に気づいた瞬間、誰もがこのゲームの真価を実感するだろう。
■■■■ 良かったところ
慣性操作が生む“唯一無二の浮遊感”
『エクセリオン』の最大の長所は、何といっても慣性のある操作感に尽きる。 当時のシューティングゲームの多くは、自機の動きがピタリと止まり、画面内をスピーディに動き回るタイプが主流だった。しかしこの作品では、「押したら加速、離してもすぐには止まらない」という滑らかな挙動が導入され、宇宙空間の無重力感を忠実に再現している。
プレイヤーは単に敵を撃つだけでなく、“機体を制御する”感覚そのものを楽しむことができる。
この慣性の存在によって、シューティングが反射神経だけのゲームではなく、「物理を読むゲーム」へと進化した。
最初は難しく感じても、コントロールが身体に馴染んでくると、敵弾を滑るように避けながら射撃する快感が病みつきになる――この感覚は他作品にはない“操縦の楽しさ”そのものだ。
無駄を削ぎ落としたミニマルなデザイン美
『エクセリオン』は、当時の他のファミコンタイトルに比べて極めてシンプルだ。ステージ構成は単調、ストーリー説明も最小限。だが、この“無駄のなさ”こそが美学だった。 敵、弾、背景、効果音――すべての要素が必要最小限に整えられ、余計な情報が一切ない。だからこそ、プレイヤーは自分の操作と結果に100%集中できる。
この設計思想は、後のミニマルデザインの先駆けとも言える。
現代のプレイヤーが触れても、「なんて静かで研ぎ澄まされた空間なんだ」と感じることだろう。
本作の“寡黙さ”は、アクション性を際立たせるための意図的な選択であり、限られたファミコンのスペックを最大限に生かした設計だった。
家庭用ゲームとしての完成度の高さ
アーケード作品の移植というと、当時は「劣化版」「簡略化」という言葉が付きまとった。 しかし『エクセリオン』は、単なる劣化移植ではなく、家庭用向けに再構築された完成度の高いリメイクといえる。 横画面化によって敵との距離が近くなり、プレイヤーはより緊迫した戦闘を味わえるようになった。スピード感と反応性のバランスが絶妙で、アーケード版を知らなくても十分に面白い。
また、ファミコン独自のチップ音を活かした効果音設計も秀逸だった。ビーム発射音が独特の鋭い電子音で、敵を撃破するたびにリズムを刻むような快感がある。
まるで“音で戦っている”ような感覚を生み出し、家庭でもアーケード的な臨場感を再現していた。
シンプルながら奥の深い戦略性
攻撃手段が2種類しかないにもかかわらず、『エクセリオン』の戦略性は驚くほど奥深い。 連射可能なシングルビームと、高威力だがリスクのあるデュアルビーム。この二択だけで、プレイヤーの思考と判断が試される。 敵の出現パターンや自機の慣性を考慮しながら、“今どちらを使うべきか”を常に判断しなければならない。
つまりこのゲームは、反射神経に頼らず“読み”と“予測”で勝負するタイプのシューティングなのだ。
一見シンプルでも、実際にやり込むと「状況判断のゲーム」であることがわかる。
この“選択の緊張感”が、プレイヤーを飽きさせず、繰り返し遊びたくさせる中毒性を生んでいる。
立体感のある背景表現と没入演出
グリッド状の背景は、当時のファミコンではほとんど見られなかった疑似3D表現だった。 この背景は単なる模様ではなく、プレイヤーに奥行きを錯覚させ、自機の移動方向を把握しやすくするためのデザイン的仕掛けだった。 そのため、視覚的なガイドラインとしても機能し、プレイ中に方向感覚を失うことが少ない。
さらに、この背景と慣性挙動が組み合わさることで、“無限に広がる宇宙空間”という錯覚が生まれる。
実際には2Dの固定画面なのに、まるで3D空間を滑空しているように感じられる――これこそが『エクセリオン』の魅力の真骨頂だ。
プレイヤーの成長を感じられる設計
『エクセリオン』は、プレイすればするほど“上達を体感できる”タイプのゲームだ。 最初のうちは敵弾を避けるのも困難だが、慣性のクセを覚えると、自分でも驚くほど滑らかに避けられるようになる。 この「最初は難しいが、慣れると面白い」という成長曲線が非常に心地よい。
また、敵の出現パターンが固定化されているため、練習によって確実に上達できる。
これはプレイヤーが“努力で上手くなれる”ことを体感できるゲームデザインであり、80年代のファミコン文化において非常に重要な価値観だった。
静寂が生む緊張感と没入性
BGMが控えめで、戦闘中はほぼ効果音だけ――この“静けさ”が逆に緊張感を生む。 常に電子音が鳴り響くわけではなく、静寂の中で一瞬響くビーム音や爆発音が、まるで宇宙の無音世界にいるような没入感を演出している。 他のファミコン作品が“にぎやかさ”でプレイヤーを引き込むのに対し、『エクセリオン』は“音の間”で魅せる稀有な存在だった。
この緊張感は、単なる演出ではなく、プレイヤーの集中を極限まで高める仕掛けでもある。
音が少ないからこそ、目と指が頼りになる――その結果、プレイヤーはより深く画面の世界に入り込む。
ファミコン黎明期の意欲作としての価値
『エクセリオン』が高く評価される理由のひとつは、「ジャレコがファミコンに参入した最初の一歩」だったことだ。 この一本で、同社は“アーケード技術を家庭に落とし込む”という方向性を明確にした。 『フォーメーションZ』『シティコネクション』『フィールドコンバット』へと続くジャレコのDNAは、この作品にすでに刻まれている。
また、当時の技術的制約を考えると、この規模の動きと慣性処理を32KB程度のROMで実現していたのは驚異的だった。
つまり『エクセリオン』は、ジャレコの技術力の証明でもあり、“ファミコンでもここまでできる”ことを世に知らしめたタイトルだった。
シンプルで繰り返し遊べる中毒性
ストーリーがない、キャラクターがいない――にもかかわらず、何度も遊びたくなる。 その理由は、スコアアタックの絶妙な設計にある。敵の波や得点バランスが巧みに調整されており、プレイヤーは「次はもう少し長く生き残る」「もう少し点を稼ぐ」と自然に挑戦を続けてしまう。
この中毒性は、“永遠に終わらないゲーム”の美学だ。エンディングがなくても満足できる構造を成立させていたのは、初期ファミコン作品の中でも特筆すべき点である。
総評:静かに光る孤高の名作
総じて『エクセリオン』は、派手さや賑やかさを求める作品とは対極にある。 だが、その静けさ、緻密さ、そして“滑る操作感”によって、唯一無二の存在感を放っている。 プレイヤー自身の感覚とリズムで世界を支配するようなプレイフィールは、時を経ても色あせない魅力だ。
ファミコン黎明期にあって、ここまで完成されたバランスを持つタイトルは少ない。
そして40年経った今も、多くのファンが「エクセリオンの慣性が忘れられない」と語る――それこそが、本作の良さのすべてを物語っている。
■ 悪かったところ
慣性システムの難解さと初見プレイヤーの戸惑い
『エクセリオン』が持つ“慣性のある操作感”は、最大の魅力であると同時に、最大の壁でもあった。 ファミコン黎明期のプレイヤーは、直感的に「押せば動く・離せば止まる」操作に慣れていたため、滑るような動きに強い違和感を覚えた人が多い。 そのため、初プレイ時には“思うように動かせず、敵弾にすぐ当たってしまう”という体験がほぼ必ず起こる。
慣れるまでに時間がかかる設計は、アーケードの常連には好評でも、家庭用では敷居が高かった。
家庭用ゲームは短時間で楽しめる“気軽さ”が求められるが、『エクセリオン』はプレイヤーの学習を前提とした設計であり、その点が当時の子どもたちにはやや不親切に映った。
つまり、意欲的すぎたシステムが仇となり、「難しいゲーム」という印象を持たれてしまったのだ。
多くのファミコン初期ソフトが“すぐ遊べる気持ちよさ”を重視していた中で、『エクセリオン』は理解に一段階努力が必要な“知的なシューティング”だった。
テンポの遅さと単調さ
『エクセリオン』のプレイテンポは、他の同時期のSTGと比べてやや遅めに設計されている。 敵の出現間隔が長く、BGMも淡々としているため、緊張感が途切れる瞬間が生まれる。 その静けさが魅力でもあるのだが、テンポを求めるプレイヤーにとっては「もっさりしている」「爽快感に欠ける」と感じられる部分も多かった。
特に、敵を全滅させた後に次の波が来るまでの数秒間は、何も起こらずに漂うだけの時間が生じる。
この“無音の間”が、集中しているプレイヤーには呼吸のリズムとして心地よいが、カジュアル層には“間延び”と受け取られてしまった。
一方で、テンポが緩やかすぎるためにスコアアタック中の緊張感が続かず、上達しても「爆発的な爽快感」が得にくいという意見もあった。
敵キャラクターのバリエーション不足
本作の欠点としてよく挙げられるのが、敵の種類が少ない点である。 序盤から終盤まで、登場する敵のデザインや動きに大きな変化がなく、ステージごとの新鮮さが乏しい。 背景は変化するものの、プレイヤーが戦う相手の挙動が似通っており、長時間プレイすると単調さを感じやすい。
これはファミコンのメモリ制約による部分が大きく、32KB程度のROMではスプライトパターンに限界があったため、敵の種類を増やすことができなかったとされる。
しかしながら、当時のプレイヤーからは「もう少し変化がほしかった」「ボス戦のような盛り上がりがない」との声が寄せられており、
ゲームデザインとしても“緊張の起伏”を生み出す要素が足りなかった点は否めない。
もしジャレコが続編や拡張版を制作していれば、敵AIや攻撃パターンの多様化によって、さらに深みのある戦略性を実現できたかもしれない。
ビジュアルの地味さと没個性な印象
当時のファミコン市場では、キャッチーなキャラクター性を前面に押し出したゲームが人気を集めていた。 『マリオブラザーズ』『ゼビウス』『ツインビー』といったタイトルは、それぞれに印象的なキャラや世界観を持っていたが、『エクセリオン』はその点でやや地味だった。
主人公機ファイターEXには特徴的なデザインがなく、敵キャラにも名前や設定がほとんど与えられていない。
結果として、ゲーム全体が“抽象的な宇宙戦”に留まり、感情移入しにくい印象を与えていた。
ファミコンのパッケージアートもややシンプルで、子どもが手に取りたくなるような華やかさには欠けていた。
そのため、店頭で並んだときに他作品に比べて目立たず、購買意欲をそそられにくかったという指摘もある。
BGMの少なさと演出面の淡白さ
『エクセリオン』の音響演出は静寂を重視した設計だったが、それが裏目に出ることもあった。 プレイ中、BGMが単調に続くか、あるいは無音に近い状態が長く続くため、「盛り上がりに欠ける」と感じる人も多かった。
当時の他のSTG――『スターフォース』『バトルシティ』『ギャラクシアン』など――では、
戦闘の進行に合わせてBGMが変化したり、敵全滅時に効果音が鳴ったりと、音の演出で達成感を演出していた。
それに対し、『エクセリオン』は終始ストイックで、得点や成功の瞬間を“音”で祝ってくれない。
このため、遊んでいても“報酬感”が弱く、達成感が伝わりにくいという欠点がある。
静けさが魅力でもあり、また同時にプレイヤーとの距離を作ってしまう要因でもあった。
リプレイ性の乏しさ
『エクセリオン』はスコアアタックがメインで、ステージをクリアしても次に特別な報酬や演出がない。 つまり、「進行のご褒美」や「次の目標」が存在しない。 何度も遊べる反面、「どこまで行っても同じ」という感覚に陥りやすく、モチベーションを維持するのが難しいという声も多かった。
当時のプレイヤーの中には、「せめてステージごとに敵の背景色や効果音が変化すればよかった」と指摘する人もいた。
また、スコアの上限が早い段階で見えてしまうため、やり込み層以外には長く続ける理由が薄いと感じるケースもあった。
この“終わりなき戦い”という構造は哲学的ではあるが、
家庭用のユーザー層――特に子どもたち――には“達成感の欠如”として受け取られてしまったのだ。
当時の市場競合に埋もれてしまった不運
『エクセリオン』が発売された1985年前後は、ファミコン市場が急拡大していた時期。 任天堂・ナムコ・ハドソン・コナミといった大手が立て続けにヒット作を出しており、 『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼビウス』といったビッグタイトルの陰に隠れてしまった。
ジャレコは後に人気作を生み出していくが、デビュー作である本作は宣伝規模も小さく、
“ファミコン参入第1弾”というインパクトが十分に浸透しなかった。
ゲームそのものの完成度は高いにもかかわらず、商業的にはやや地味な存在に留まったのは、時代の波に埋もれた不運といえる。
結果としての「人を選ぶゲーム」
総じて、『エクセリオン』は“理解すれば面白いが、すぐには伝わらない”作品だった。 慣性操作・静かな演出・単調なステージ――どれも意図があるが、プレイヤーの成熟を求めすぎた。 この“ハイコンテクスト”な作りこそが、ファミコン初期としては珍しいが、同時に万人向けではなかった。
その結果、子どもには難解、大人には地味、という評価に落ち着いてしまったのが惜しいところだ。
しかし、それこそが『エクセリオン』の個性であり、後年の再評価に繋がる伏線にもなっている。
今となっては魅力に変わった“欠点”
興味深いのは、当時“悪い点”とされた部分の多くが、現在では“味わい”として評価されていることだ。 テンポの遅さは“緩急の妙”に、静寂は“没入感”に、難しさは“奥深さ”に―― 時代を超えることで、欠点が長所に転じているのだ。
つまり『エクセリオン』の弱点は、1985年当時のプレイヤーにとっては理解されにくかっただけで、
後の世代にとってはむしろ“唯一無二の個性”として映っている。
この構造的なギャップが、ゲーム史的にも興味深い。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
主人公機「ファイターEX」──無言のヒーロー
『エクセリオン』における唯一の主役、それがプレイヤーが操る「ファイターEX」だ。 この戦闘機にはセリフも人格もない。しかし、不思議なことに、プレイを続けているうちにまるで意志を持っているかのような存在感を放ってくる。 滑るように漂い、重力を無視して宙を舞うその姿は、無言ながらも孤高の戦士を思わせる。
ファイターEXは、決して派手な機体ではない。デザインはシンプルで、白とグレーを基調とした機体色。
だがその無機質さこそが、プレイヤーの想像力を刺激する。プレイヤーの指先の動きに忠実に反応し、
時には暴走するかのように滑走する――この“暴れ馬のような操作感”が、まるで機体と対話しているような錯覚を与えるのだ。
慣性を伴う独特の挙動によって、ファイターEXは単なる自機を超えた“プレイヤーの分身”となる。
この機体と心が一体になる瞬間――それこそが『エクセリオン』最大のドラマであり、多くのプレイヤーが「ファイターEXが好き」と語る理由でもある。
ゾルニ軍の戦闘機群──機械的美しさと不気味さ
敵勢力であるゾルニ軍の機体群も、無個性のようでいて実はよく見ると多彩な造形をしている。 赤や青の色調で構成された敵艦は、有機的なラインを持ち、まるで生物のように蠢く。 特に後半ステージに登場する敵の一部は、まるで昆虫のような羽ばたきを見せ、電子音とともに滑らかに移動する。
これらの敵キャラは、単なる障害物ではなく、プレイヤーの操作を読み取るかのように動くことがある。
つまり、ゾルニ軍の機体はAI的な存在として“生きている”ように見えるのだ。
1985年という時代に、敵の動きに“意志”を感じさせる設計は非常に珍しく、無言の機械同士の戦いという
抽象的なテーマを引き立てていた。
特に印象的なのは、敵が一斉にフォーメーションを組んで突撃してくる瞬間だ。
整然と並ぶ編隊の動きは美しく、そこにデュアルビームを撃ち込んで崩壊する様は、まるで無音のバレエのよう。
敵を単なる的ではなく“動きの美学”として描いていた点は、当時のSTGの中でも際立っていた。
登場しない“人間”が想像させるドラマ
『エクセリオン』には、パイロットや司令官など、人間のキャラクターは一切登場しない。 しかしプレイヤーは自然と、“この機体を操る誰か”の存在を想像してしまう。 それは孤独な宇宙戦士かもしれないし、無人機を操るAIかもしれない。
この“描かれないキャラクター性”が、本作の深い魅力の一つだ。
セリフがなくても、背景の静けさや敵の圧力から“命の気配”が感じられる。
プレイヤーが想像する余地を残したまま世界が成立しているため、
プレイ中の一瞬一瞬が“語られない物語”として心に刻まれる。
この構造は、後の『グラディウス』シリーズや『R-TYPE』にも引き継がれ、
「無名のパイロットが戦う宇宙戦争」というSTGの王道スタイルを確立するきっかけにもなった。
ボーナスステージの敵群──名もなき挑戦者たち
ボーナスステージに登場する特殊編隊の敵たちは、 通常ステージとは異なる規則的な動きを見せる。彼らはプレイヤーの腕前を測る“試練の存在”だ。 一体一体の動きに無駄がなく、一定のリズムで現れては消える。 まるで「お前は本当にこの宇宙で生き残れるのか」と問いかけてくるかのような厳しさを持っている。
ボーナス敵たちに感情はない。だがプレイヤーにとっては、繰り返し挑むうちに“宿敵”のような存在になる。
完璧に倒せたときの達成感は、まるで長年のライバルに勝利したかのような喜びだ。
このように『エクセリオン』の“キャラクター”とは、顔や名前のある存在ではなく、
プレイヤーが感情を投影する対象として成立しているのだ。
敵弾そのものがキャラクター化されている
もう一つ見逃せないのは、“弾”の存在感である。 『エクセリオン』の敵弾は非常に速く、しかも慣性によって軌道を読みづらい。 それゆえに、プレイヤーはこの弾一発一発を“生きている何か”のように意識せざるを得ない。 敵そのものよりも、弾の動きが人格を持って見える瞬間があるのだ。
特に後半ステージの弾幕は、まるで“意思を持つ光”の群れのようで、
避けながら撃つという行為が、敵との会話のようなリズムを生み出している。
こうした「弾をキャラクターとして感じさせる演出」は、後年の弾幕系シューティングの原点ともいえる。
プレイヤー自身が物語を紡ぐ存在
『エクセリオン』の世界には、ストーリー説明も、登場人物の紹介も存在しない。 しかし、その空白こそがプレイヤーを“主人公”にしている。 誰の言葉も導きもなく、無限の宇宙でただ一人戦い続ける―― その行為そのものがキャラクターの物語なのだ。
プレイヤーがどのように戦い、どのように負けるか。
その積み重ねが“自分自身のストーリー”となり、ファイターEXの人格を形作っていく。
プレイヤーの熟練度や選択によって、キャラクター像が自然に変化していく点が、
『エクセリオン』における“キャラクター体験”の真の本質だと言えるだろう。
無名であることが価値になる世界
このゲームに登場する誰もが“名前を持たない”。 だが、その匿名性が逆に普遍性を生んでいる。 プレイヤーは年齢も性別も関係なく、この無名のパイロットになりきることができる。 そこにあるのは、“誰にでも開かれた戦いの物語”だ。
多くのファンが「キャラがいないのに心に残る」と語る理由はここにある。
『エクセリオン』のキャラクター性は、画面上の存在ではなく、プレイヤーの心の中で生まれる。
無名の戦士として、無限の敵に挑む――それがこの作品の哲学であり、
静かな名作と呼ばれる所以でもある。
象徴としての“孤独”のキャラクター化
最後に挙げたい“キャラクター”は、実体ではなく孤独という概念そのものだ。 広大な宇宙空間にただ一人。助けも声もなく、無限に湧く敵を相手に戦い続ける。 この孤独感が、まるで登場人物のようにプレイヤーに寄り添う。
『エクセリオン』を象徴するキャラクターは、ファイターでも敵でもない。
それは“孤独”そのものであり、プレイヤーが戦うたびにその存在を感じることができる。
静かで寡黙な戦いの中に宿る哲学的な感情――それが、多くのファンが今なおこのゲームを愛する理由だ。
[game-7]
■ 中古市場での現状
ファミコン初期を代表する“ジャレコ第1号”としての希少性
『エクセリオン』は1985年2月11日に発売された、ジャレコのファミリーコンピュータ参入第1弾タイトルである。 この“メーカー初参入作”という立場が、中古市場において非常に大きな意味を持つ。 ファミコンの歴史を体系的に収集しているコレクターにとって、「メーカーのデビュー作」は一種の節目として重要視されるため、 この作品も同時期の他タイトル(たとえば『ギャラクシアン』や『バトルシティ』など)よりも相場が安定しやすい。
また、流通量自体はそこまで少なくないものの、初期流通分は箱や説明書が紙質の薄い仕様だったため、良好な保存状態のものが少ないのが現状だ。
そのため「完品」「美品」とされる個体は年々減少しており、ここ数年で価格がじわじわと上昇している。
ヤフオク!での販売・落札傾向
ヤフオク!では、『エクセリオン』の出品は月平均で10~20件ほど確認できる。 取引価格はソフト単体で1,200~2,200円前後、 箱・説明書付きの完品状態で3,000~4,500円前後が相場となっている。
とくに注目すべきは、「初期ロット版」と呼ばれる箱デザインの一部違い。
初期生産分では背面の著作権表記が英字で「JALECO LTD.」と書かれており、
後期版では「株式会社ジャレコ」に変更されている。
この違いを見分けられるコレクターは限られるが、初期ロットは希少性が高く、状態が良ければ5,000円を超える落札例もある。
説明書付きでも、折れや日焼けがあると評価が下がり、入札数が伸びない傾向にある。
一方、動作確認済・写真付き・清掃済といった出品はウォッチ数が多く、安定して即決される。
ファミコンコレクターの中では、“状態よりも動作保証を重視する派”と“外観保存を重視する派”の二極化が進んでおり、
『エクセリオン』はその両方から一定の需要を保っている。
メルカリでの流通動向と価格帯
フリマアプリ「メルカリ」では、『エクセリオン』の出品はほぼ常時見られる。 出品価格はソフトのみで1,000~1,800円、完品で2,500~3,800円前後が主流だ。
メルカリの特性として、出品者が個人であるため状態説明がまちまちで、
写真の明るさや撮影角度によって印象が大きく変わる。
そのため、実際の落札価格は「見た目の清潔さ」に左右されやすく、
日焼けやラベル剥がれが目立つ品は値下げ交渉後に1,000円以下で売却されることもある。
逆に、箱・説明書・ハガキ・発泡スチロール内枠付きの“完全完品”は即売れしやすい。
特に「動作確認済」「即購入OK」「送料無料」などの条件を満たす出品は24時間以内に売り切れる例も多い。
この傾向から、ファミコンソフトの中では比較的回転の速いタイトルといえる。
なお、メルカリのユーザー層には「親子で遊びたい」「懐かしのゲームを飾りたい」というライトコレクターも多く、
そうした層には“箱デザインの懐かしさ”が訴求している。ジャレコのロゴがレトロ感を演出しており、
インテリア目的の購入も増えている点が特徴だ。
Amazonマーケットプレイスでの価格推移
Amazonの中古販売では、『エクセリオン』は相場やや高めで推移している。 中古価格は3,000~5,000円前後、Amazon倉庫発送の“プライム対応品”は4,500円を超えることもある。 理由として、Amazonでは「完品」「状態良好」などの出品基準が厳しく、安価な中古品が少ないことが挙げられる。
また、Amazonのユーザーは購入目的が「コレクション」よりも「動作プレイ目的」であるケースが多く、
実際にファミコン実機で遊びたい人が選ぶ傾向が強い。
そのため、メンテナンス済み・端子清掃済・黄ばみ除去済などの付加価値をつけた出品は高値でも売れやすい。
ただし、注意点として「中古・可」など曖昧な状態表記のものは、
実際には箱欠品や日焼けがあるケースも多く、購入時には販売者レビューの確認が推奨される。
市場全体としては、Amazonはややプレミアム価格帯で安定しており、
他のフリマサイトより高めに取引される傾向が続いている。
楽天市場・駿河屋などショップ系サイトでの動向
中古専門ショップが集まる楽天市場では、『エクセリオン』の価格は2,800~4,200円前後が中心。 ゲーム専門店が出品しているため、動作保証付き・返品対応ありなどの安心感が強く、 初心者コレクターやプレゼント用途の購入が目立つ。
また、大手中古販売サイト「駿河屋」でも定期的に取り扱いがある。
駿河屋の買取・販売履歴をみると、
・ソフト単体(並品)…約1,300~1,700円
・完品(良品)…約2,800~3,500円
・未開封品(極美品)…4,500円以上
で安定して推移している。
駿河屋では「在庫切れ」になることもしばしばあり、
補充された際には即日完売することも珍しくない。
とくに“外箱・説明書の状態ランクA”が付いた商品は争奪戦になるほど人気が高い。
保存状態による価格差と価値の変動
ファミコンソフト全般に言えることだが、『エクセリオン』も保存状態による価格差が非常に大きい。 黄ばみ、ラベル剥がれ、箱潰れ、説明書の折れなどがあると、価値は半減する。 一方で、箱の角が立ち、ラベルも鮮明な“ショーケース級”の美品は、同じタイトルでも2倍以上の値で取引されることがある。
また、近年では“外装クリアケース付き”や“レトロ保護袋入り”など、
コレクション用途に特化した出品も増えており、状態にこだわる層の需要が拡大している。
特にファミコン黎明期(1983~85年)の作品は、経年劣化による黄ばみが進行しているため、
今後も「美品・完品」の希少性はさらに高まると予想される。
未使用・新品の市場価値
新品・未開封状態の『エクセリオン』は非常に稀少だ。 市場では年に数回しか確認されず、出品された場合は8,000~10,000円前後で即売されるケースが多い。 パッケージのビニールが残っている個体はコレクター間で高値取引され、 場合によっては12,000円を超えることもある。
ただし、ファミコンの未開封品は“未確認動作品”であるため、
実際に遊べる保証はない。それでも、“時代を閉じ込めたアーカイブとしての価値”を重視するコレクターに人気がある。
近年の市場トレンドと今後の見通し
2020年代に入ってから、レトロゲームのコレクション需要が急上昇している。 コロナ禍による“おうち時間”需要や、配信者によるレトロレビュー動画の影響で、 ファミコン初期ソフトの人気が再燃したのだ。
その中でも『エクセリオン』は、「知る人ぞ知る名作」「地味だが味わい深いタイトル」として静かなブームを見せている。
特にYouTubeやSNSで“ファミコン1作目特集”が組まれるとき、ジャレコの代表として必ず名前が挙がるため、
安定した中古需要が生まれている。
今後も極端な値上がりはしないと見られるが、完品美品は年々希少化するため、
コレクション目的で探している人は早めに確保しておくのが賢明だろう。
まとめ:静かな人気を保ち続ける“玄人向けタイトル”
中古市場における『エクセリオン』は、決して高額プレミア品ではない。 しかし、“ファミコン初期の象徴的存在”として、安定した需要を持つタイトルだ。 その地味で硬派な内容が、ライト層よりもむしろレトロゲーマーやコレクターの心を掴んでいる。
ジャレコの技術的挑戦とファミコン史的価値を同時に備えた一本として、
市場でも“静かに値を保つソフト”として位置づけられている。
つまり、『エクセリオン』は派手な高騰を見せることはなくとも、
失われない評価と、確かな存在感を持つレトロゲームなのだ。

![【中古】[お得品]【表紙説明書なし】[FC] エクセリオン(EXERION) ジャレコ (19850211)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102491.jpg?_ex=128x128)