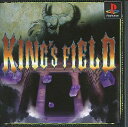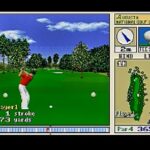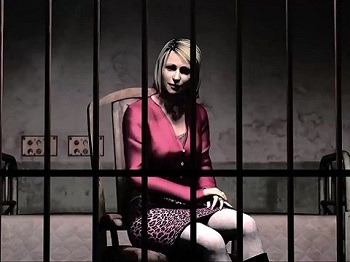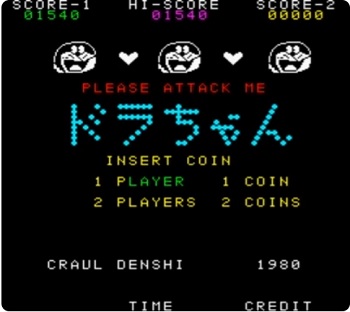【中古】 KING’S FIELDII(キングスフィールド)/PS
【発売】:フロム・ソフトウェア
【開発】:フロム・ソフトウェア
【発売日】:1994年12月16日
【ジャンル】:アクションロールプレイングゲーム
■ 概要
フロム・ソフトウェア初の家庭用ゲーム作品としての位置付け
1994年12月16日にフロム・ソフトウェアが発売した『キングスフィールド』は、同社にとって初の家庭用ゲーム市場参入作であり、後の名声へと繋がる重要な出発点でした。それまで同社は業務用ソフトウェア、特にオフィス向けやビジネス用アプリケーションの開発を手掛けており、ゲーム業界とは無縁の存在と見られていました。しかしバブル崩壊を経て、新しい事業の柱を模索していた中で「家庭用ゲームへの参入」という大きな転換が行われます。その挑戦の果実が『キングスフィールド』だったのです。 発売日はプレイステーション本体の発売(1994年12月3日)からわずか13日後。事実上のローンチタイトルと呼べるほど早い時期に市場へ投入されました。まだユーザーにとって「プレイステーション」というハード自体が未知の存在であった中で、完全3DポリゴンによるダークファンタジーRPGは強烈なインパクトを与えました。
フルポリゴン3Dと一人称視点がもたらした衝撃
本作最大の特徴は、ゲーム画面がすべて「一人称視点」で進行し、背景からキャラクター、アイテムまで全てがフルポリゴンで描写されていた点です。当時の日本におけるRPGといえば『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』に代表されるように、俯瞰視点やキャラクターが並んで行動する形式が主流でした。プレイヤーはキャラクターを操作するというよりも「冒険者一行を眺める」立場で物語を体験していたのです。 しかし『キングスフィールド』では、プレイヤーは主人公ジャンの視点そのものを共有します。暗い地下墓所を歩くときの息苦しさ、曲がり角を進む際の恐怖、モンスターと対峙した時の圧迫感。これらは従来のRPGにはなかった「没入感」を生み出しました。特に、戦闘に突入するためのエンカウント演出が存在せず、探索中に突然モンスターが迫ってくるシームレスな進行は、緊張感を極限まで高めていました。
舞台設定とゲームの基本構造
物語の舞台となるのはヴァーダイト王家の地下墓所です。プレイヤーは王国の兵士であるジャンとして、この広大かつ危険に満ちた墓所を探索していきます。全体は5層に分かれており、それぞれに独自のモンスターや罠、仕掛けが配置されています。墓所は長年の改築や封印によって複雑に入り組んでおり、地図にも載らない通路や隠し扉が数多く存在します。 ゲームの進行は単純で、プレイヤーはとにかく奥へ奥へと進むことになります。しかし道中では鍵を探したり、魔法陣を解除したり、敵を倒して経験値や装備を得るなど、数多くのハードルが待ち構えています。さらに、外の世界に出ることはできず、プレイヤーは常に墓所という閉ざされた空間の中で行動を続けるため、緊張感が途切れる瞬間がありません。この閉塞感こそが、本作特有の魅力であり恐怖でもあります。
操作体系と独自の戦闘感覚
操作は十字キーによる前進・後退・旋回、L1R1ボタンによる平行移動、L2R2での視点上下といった構成でした。今でこそ一般的に思えますが、当時はまだ「3D空間を自由に移動する」操作体系自体が珍しく、慣れるまで時間がかかるプレイヤーも多かったのです。戦闘は打撃武器が主体で、攻撃ボタンを押すと振りかぶり、しばらくしてから攻撃判定が発生する仕組みでした。この“溜め”による独特のテンポが、戦闘を単調にせず、緊張感を生み出しました。 また魔法も存在しますが、消費MPが多く、回復手段も限られているため多用はできません。必要な場面で切り札として使うスタイルが推奨されており、戦略的な選択が求められます。さらに特定の条件を満たすと発動できる「魔法剣」は非常に強力で、後の『アーマード・コア』シリーズに継承される要素ともなりました。
技術的背景と制約を逆手に取ったデザイン
グラフィックは当時としては最先端でしたが、当然ポリゴン数や描画能力には限界がありました。そこで開発陣は「暗い地下墓所」という舞台を選ぶことで、遠景を描く必要をなくし、むしろ視界の悪さを雰囲気作りに活用しました。結果として、狭い通路や薄暗い空間は恐怖心をあおり、ポリゴンの粗ささえもリアリティに変えてしまったのです。 また、テキストやNPCの会話は最小限に抑えられており、プレイヤーは断片的な情報から世界を想像することを求められました。この“語られない余白”が、フロム作品に脈々と受け継がれていく独特の作風の源流となっています。
日本のRPG文化に投じられた「異物」
1990年代前半の日本のRPGは、親しみやすいキャラクターや感情移入しやすいストーリーが重視され、「冒険を気軽に楽しめる娯楽」としての側面が強調されていました。その中で『キングスフィールド』は、難易度が高く不親切で、プレイヤーに忍耐と観察力を要求する作品として登場しました。これは多くのユーザーにとって衝撃であり、「遊びやすさ」を求めていた層には拒絶感を与えました。しかし一方で、PC向けRPGのような硬派な作風を求めていたプレイヤーにとっては「待ち望んでいた作品」でもあったのです。こうして『キングスフィールド』は、万人向けではないものの熱狂的なファンを生み出すことに成功しました。
シリーズと後世への影響
本作は単発で終わらず、続編『キングスフィールドII』『III』『IV』へと繋がり、さらに外伝的作品や精神的後継作『SHADOW TOWER』『Demon’s Souls』『Dark Souls』へとその系譜は進化していきます。 特に「死と隣り合わせの探索」「断片的に語られる世界観」「不親切さを逆に魅力へ転化するデザイン」といった要素は、後年のフロム作品を象徴するキーワードとなり、『キングスフィールド』はまさにその原点と呼ぶべき存在です。
総合的な位置づけ
『キングスフィールド』は、単に一つのゲームタイトルに留まらず、フロム・ソフトウェアというメーカーの哲学を決定づけた作品でした。プレイステーション初期のタイトルとしては異端であり、同時に時代を先取りした挑戦的な作品です。その硬派さゆえに賛否両論を呼びましたが、後世から振り返れば、この作品こそが「ソウルライク」と呼ばれるジャンルの萌芽であり、日本のゲーム史における重要なターニングポイントであったと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
探索の手応えと未知の発見
『キングスフィールド』の一番の魅力は、やはり探索そのものにあります。プレイヤーは何の説明もなく地下墓所に放り込まれ、地図も方角も示されない中で、自分の感覚と注意力だけを頼りに進まなければなりません。曲がり角の先に何が潜んでいるのか、壁を調べると隠し通路が開くのか、それとも罠が牙をむくのか。プレイヤーの行動一つひとつが冒険の成果を左右します。 単純な一本道ではなく、寄り道や隠しエリアが多いため、探索がそのまま報酬に直結する設計は強い中毒性を生み出しました。何気なく壁に触れたら新しい通路が見つかり、その先で強力な武器や魔法を手に入れる。こうした小さな「発見」が重なるたび、プレイヤーは再び次の扉を開きたくなるのです。
没入感を生むダークファンタジーの世界観
舞台となるヴァーダイトの地下墓所は、光が届かない閉塞的な空間でありながら、重苦しいBGMや響き渡るモンスターの鳴き声によって、異様なまでの臨場感を持っています。プレイヤーはキャラクターの目を通して歩くため、まるで自分自身がその場所に立っているかのような錯覚を覚えるのです。 また、墓所にいるNPCたちは皆どこか冷淡で、明るい言葉をかけてくれるキャラクターはほとんどいません。こうした無機質な人間関係や、断片的に語られる王国の歴史が、逆に世界のリアリティを高めています。プレイヤーは「語られない部分」を想像することで、この世界に深く引き込まれるのです。
シームレスな戦闘と緊張感
当時のRPGでは一般的だった「戦闘画面への切り替え」は一切なく、敵は探索中にそのまま襲い掛かってきます。これにより「安全地帯」という概念が存在せず、常に緊張感が続きます。遠くでうめき声が聞こえたら、次の瞬間にスケルトンが現れるかもしれない。そうした緊迫感がプレイヤーの心拍数を上げ、戦闘の一つひとつを真剣勝負に変えるのです。 攻撃モーションは遅く、敵にヒットさせるには距離感とタイミングを計らなければなりません。一撃の重さは大きいですが、相手の攻撃もまた致命的であり、常に「死」と隣り合わせ。戦闘が単なる作業でなく、挑戦そのものになっている点が、多くのプレイヤーに忘れがたい体験を与えました。
自由度とプレイヤー主導の進行
『キングスフィールド』は、次に何をすべきかを丁寧に示してくれません。鍵を探すのか、強力な装備を手に入れるのか、それとも回復手段を確保するのか。すべてはプレイヤーが自分で判断しなければならないのです。 この「不親切さ」は一見すると不便に思えますが、逆に自由度の高さを保証する仕組みでもあります。プレイヤーは好きな順路を選び、場合によっては強敵を避けて先に進むこともできます。こうした自己決定の積み重ねが、ゲームを「自分自身の冒険」として感じさせる要因になっています。
リスクとリターンの絶妙なバランス
強力な装備や魔法はたいてい危険な場所に置かれており、そこへ辿り着くためには命を懸けた探索が必要です。例えば強い剣を手に入れるには、隠し通路を抜けた先にいるモンスターを倒さなければなりませんし、貴重な回復アイテムは高価で、安易には手が出せません。 このリスクとリターンの関係が、プレイヤーに常に緊張感を持たせます。そして苦労して得た報酬は、他のRPG以上に達成感をもたらすのです。「あの角を曲がらなければ手に入らなかった」「恐怖に打ち勝ったから報われた」という実感が、プレイヤーの記憶に強烈に刻まれます。
当時の他作品との差別化
1994年当時の家庭用RPGは、まだドット絵やスプライトを多用した2D表現が主流でした。『キングスフィールド』は、そうした既存の枠組みから大きく飛び出し、「ポリゴンによる一人称視点RPG」という新しい道を切り開きました。 同時期に海外PC市場では『Ultima Underworld』や『The Elder Scrolls: Arena』といった作品が登場していましたが、日本の家庭用ハードで同じような試みを行ったのは『キングスフィールド』がほぼ唯一と言える存在でした。これにより、ユーザーに「未知のジャンルを体験している」という感覚を与え、強烈な個性を放つことになったのです。
語られないストーリーが生む余白の魅力
本作には、ドラマティックなイベントや豪華な演出はほとんどありません。語られるのは断片的な伝承や、NPCのつぶやき程度です。しかしその「不足」が逆にプレイヤーの想像力を刺激し、物語を自分なりに補完させます。 これは後の『Demon’s Souls』や『Dark Souls』にも通じる手法であり、プレイヤー同士が「このキャラは実はこういう背景を持っているのでは?」と議論する余地を生み出します。つまり、ストーリーを語り過ぎないことが、長く語り継がれる要因にもなったのです。
上達を実感できる設計
序盤は何度も死に、どうしても進めないように感じますが、プレイヤーが学びを積み重ねることで少しずつ前進できるようになります。敵の動きを読み、攻撃のタイミングを掴み、罠を警戒する。そうした経験が次第に身につき、「昨日は勝てなかった敵に今日は勝てた」という喜びが得られるのです。 この「プレイヤー自身の成長がゲーム進行に直結する感覚」は、フロム作品共通の魅力であり、当時のRPGでは珍しい体験でした。
■■■■ ゲームの攻略など
序盤を生き延びるための心得
『キングスフィールド』最大の壁は、プレイ開始直後の数十分にあります。プレイヤーは剣一本を手に、地図も持たないまま墓所に放り出されます。初期の敵であるスケルトンや食人植物でさえ、油断すれば瞬く間にプレイヤーを葬り去ります。ここで心が折れてしまう人も少なくありません。 序盤の攻略法としては、まず無理に敵と正面から渡り合わないことです。敵の出現位置を覚え、危険だと判断したら回避に徹することが重要です。近場に配置された樽や宝箱から回復アイテムや少額のゴールドを回収し、戦える環境を少しずつ整えましょう。この「逃げる勇気」を身につけることこそが、最初の関門を突破するカギです。
安全地帯の確保と拠点活用
地下一階には兵士の宿舎や教会、商店があります。特に「ライト商会」では装備品や回復アイテムを購入できますが、値段が高いため序盤から大盤振る舞いするのは禁物です。まずは小さな戦闘で稼ぎつつ、少しずつ装備を整えることが推奨されます。 また、教会の存在は精神的にも重要です。セーブや回復が可能な拠点が近くにあるだけで探索のリスクを大幅に軽減できます。プレイヤーは常に「次の帰還ポイント」を意識しながら進み、無理をしすぎない計画的な行動を取ることが肝心です。
戦闘の基本:ヒット&アウェイ戦法
戦闘は正面から殴り合うのではなく、相手の攻撃を誘い、隙を突いて一撃を叩き込むのが基本です。攻撃モーションが遅いため、ボタンを押してから当たり判定が出るまでのタイムラグを計算に入れなければなりません。このラグを理解できるかどうかで生存率は大きく変わります。 また、敵の攻撃は連撃になることが多く、1発目を食らったら続けて致命傷を受けることもあります。そこで有効なのが左右への平行移動です。L1、R1を使ってステップするように敵の攻撃をかわし、反撃のチャンスを伺うのです。この「ヒット&アウェイ」を体得することで、プレイヤーは徐々に戦いを支配できるようになります。
資源管理とサバイバル意識
『キングスフィールド』では回復アイテムやMP回復手段が極めて限られています。ポーションを乱用すればすぐに金欠になり、魔法を乱発すればあっという間にMP切れで詰みます。そのため、敵と戦うか逃げるか、アイテムを温存するか使うかといった判断が常に求められます。 特に重要なのは「竜の泉」と呼ばれるMP回復ポイントの存在です。これを復活させることで長期的に魔法を使えるようになりますが、泉を再生させるためには危険なエリアを攻略しなければなりません。資源を管理しつつ、そのリスクをどう乗り越えるかが中盤以降の攻略テーマになります。
マップ構造と探索のセオリー
墓所の各階層は入り組んでおり、無闇に進むとすぐ迷子になります。探索の基本は「未踏エリアを一つずつ潰す」こと。行き止まりの壁を調べる、怪しい影を見逃さない、といった地道な作業が必要です。 また、ゲーム内の地図は完全ではなく、全てを把握できるわけではありません。そのため、自分でメモを取ったり、ランドマークを意識的に覚えると迷いにくくなります。トラップや隠し扉の位置も、一度発見したら忘れないようにすることが次の探索に役立ちます。
魔法と魔法剣の扱い
序盤では魔法は心強い切り札ですが、消費MPが大きく、連発はできません。効果的に使うには、敵の動きを止める、距離を取る、ボス戦で隙を作るといった場面に絞るのが理想です。 さらに熟練プレイヤーの間で語り草となったのが「魔法剣」の存在です。特定の剣と魔力値の組み合わせで発動できる特殊技で、強烈なエフェクトと攻撃力を誇ります。ただしゲーム内で明示されることはなく、自力で見つけるか情報を交換しなければ気づかない仕様でした。これを知るか知らないかで攻略難度が大きく変わり、当時のプレイヤー同士の話題を盛り上げる要素にもなりました。
中盤以降の装備と成長戦略
探索を進めるにつれ、より強力な装備や魔法が手に入ります。ここで重要なのは「無理をしない更新」です。新しい武器を見つけても、攻撃速度が遅く自分のスタイルに合わなければ逆効果になります。また、防具も単純に防御力だけでなく、重量や移動速度との兼ね合いを考える必要があります。 成長面では、レベルアップによる体力上昇が戦闘の安定感を大きく左右します。序盤は慎重に雑魚敵を狩って経験を積み、基礎能力を固めるのが鉄則です。中盤以降は探索の幅が広がり、強敵を相手にする機会が増えるため、自分のプレイスタイルに合った装備と魔法を見極めることが攻略の鍵となります。
終盤の難所と攻略のコツ
後半になると、敵の攻撃力やスピードが格段に上がり、一撃死のリスクが増えます。ここでは「敵を正面から受け止めない」姿勢がより重要です。罠や暗闇の中に強敵が潜んでいるケースも多く、音や気配に耳を澄ませることが必要になります。 また、終盤に至っても資源管理の重要性は変わりません。むしろ長丁場の戦闘や連戦が多くなるため、回復手段を節約しつつ切り札を温存する戦略が必須です。最終層に挑む際は、必ず回復アイテムと装備を整え、撤退ルートを確保してから挑戦することが生存率を高めるポイントになります。
裏技や小ネタ
『キングスフィールド』には当時のプレイヤーが共有していた小ネタや裏技も存在しました。特定の壁の裏に隠されたショートカットルート、敵を無理に倒さず引きつけて安全地帯から攻撃する方法、NPCから予想外のアイテムを入手できるイベントなど、知識が攻略を大きく助ける場面が多いのです。 こうした情報は当時、ゲーム雑誌や友人同士の会話で広まっていき、コミュニティの中で「発見を共有する楽しみ」を育みました。今ではインターネットで簡単に調べられますが、当時の「誰も知らない秘密を見つけた」という体験は、本作特有の大きな魅力でした。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーの反応
1994年末に登場した『キングスフィールド』は、プレイステーション本体が発売されて間もない時期ということもあり、大きな注目を集めました。当時のプレイヤーにとって「フルポリゴンの一人称RPG」という響きは非常に新鮮で、最初に画面を見た時点で強烈な印象を残したのです。 ただし、実際にプレイしてみるとその難易度と不親切さに驚かされる人が多く、「何をしていいかわからない」「数分でやられてしまう」といった声も少なくありませんでした。結果として、発売当初の評判は賛否が極端に分かれる形になり、「革新的だけれど人を選ぶゲーム」というイメージが形成されました。
ゲーム誌やメディアによる評価
当時のゲーム雑誌に掲載されたレビューを振り返ると、「技術的には画期的だが、遊びやすさに欠ける」という論調が目立ちます。ポリゴンによる3D表現や一人称視点の採用は高く評価された一方で、「初心者お断り」とも言える難度設計は批判の的となりました。 一方で、マニア層やRPGファンからは「本格的な冒険が味わえる」と好意的に受け止められた例もありました。特にパソコンゲームのウィザードリィ系タイトルを遊んでいたプレイヤーにとっては、「家庭用機でここまで硬派なRPGが出るとは思わなかった」と歓迎されました。
ユーザーコミュニティでの語り草
発売から時間が経つにつれて、徐々にプレイヤー同士の情報交換が盛んになりました。隠し扉や魔法剣の存在、竜の泉の再生方法といった攻略情報は口コミや雑誌の読者投稿コーナーで広まり、やがて「知っているかどうかで攻略の難度がまるで違う」という状況を作り出しました。 こうした「プレイヤー同士の共有」が盛り上がったのも、『キングスフィールド』ならではの魅力でした。完全にガイドのない状態で挑むよりも、仲間と情報を交換しながら少しずつ真実に近づいていく、その過程がまるで現実の冒険譚のように感じられたのです。
熱心なファン層の形成
一般的なライトゲーマーからは敬遠されがちだった一方で、本作に心を奪われたプレイヤーは強烈な支持者となりました。何度も死を繰り返しながら少しずつ前に進む体験や、説明不足ゆえに想像力を掻き立てられる世界観に魅了された人々は、「これこそが真の冒険だ」と絶賛しました。 このような熱心なファン層が後の続編や関連作を支える土台となり、フロム・ソフトウェアのゲーム作りが「硬派」「挑戦的」「独自路線」と評されるきっかけになったと言えます。
後年の再評価と“ソウルライク”の原点
21世紀に入り、『Demon’s Souls』や『Dark Souls』シリーズが世界的な成功を収めると、『キングスフィールド』は「ソウルライクの始祖」として再び注目を浴びるようになりました。 「死と隣り合わせの探索」「不親切さを逆に魅力に変える設計」「断片的に語られる物語」など、ソウルシリーズで高く評価された要素の多くは、この初代『キングスフィールド』ですでに芽吹いていたのです。現代のプレイヤーからは、「あの頃すでにフロムはフロムだった」と振り返られることも多く、ゲーム史における意義が改めて認識されるようになりました。
海外プレイヤーの視点
海外市場では、当時すでにPC向けに『Ultima Underworld』や『The Elder Scrolls: Arena』といった3DダンジョンRPGが存在していました。そのため、『キングスフィールド』は「日本発のフルポリゴンRPG」として注目されましたが、難度の高さや操作性の癖はやはり賛否を呼びました。 ただし、後年のフロム作品人気によって逆輸入的に評価が高まり、「プレイステーション初期にこんな尖ったゲームが存在したのか」と再発見される流れも生まれました。特にゲーム史を研究する層やコレクターにとっては「外せない一作」と位置づけられています。
一般的な評価と“通好み”の印象
総じて『キングスフィールド』は、「初心者向けではないが、ハマる人にはとことん刺さる」という通好みの作品として語られ続けています。華やかな演出や分かりやすい導線が求められていた時代に、あえて硬派で暗い世界観を打ち出した姿勢は異端でしたが、それが逆に個性となり、フロム・ソフトウェアというメーカーの存在感を強烈に印象づけました。 いま振り返れば、この賛否両論こそがフロム作品の特徴であり、その原点が『キングスフィールド』にあったと考えられるでしょう。
■■■■ 良かったところ
没入感の高さと緊張感あふれる探索
『キングスフィールド』の最も称賛されるポイントは、徹底した没入感にあります。一人称視点で描かれる地下墓所は、狭い通路や暗闇が続き、わずかな足音やモンスターのうめき声だけが耳に届きます。プレイヤーは現実の自分がその場に立っているような錯覚を覚え、ゲームの外側から眺めるのではなく、世界に「閉じ込められる」感覚を味わいます。 その緊張感は常に途切れず、何気ない曲がり角や扉の向こうに潜む未知の存在を想像させることで、探索が恐怖と期待を同時に抱かせる特別な体験となっていました。
プレイヤーの成長が直に感じられる設計
多くのRPGではキャラクターのレベルが上がれば敵に勝てるようになりますが、本作ではプレイヤー自身の学習と経験が結果に直結します。最初は攻撃を当てることすら難しかった敵に対しても、操作に慣れ、敵の動きを読む力がつくことで、次第に安定して勝てるようになります。 この「自分が上達している」という実感は他のゲーム以上に強く、やられてばかりだった序盤を乗り越えた時の達成感は格別です。単なる数値の積み重ねではなく、プレイヤーの腕前が反映される構造こそ、多くの人に「本当の冒険をしている」と思わせた要因でした。
探索報酬の多様さと隠し要素の魅力
墓所の至るところに隠された通路や宝箱は、探索のモチベーションを大きく高めました。壁を調べると現れる隠し扉や、何気なく寄り道した先で発見する強力な装備は、プレイヤーに驚きと喜びを与えます。 また、こうした発見の多くはゲーム中で明示されず、プレイヤーが自分の目と耳で気づくしかありません。そのため「気づいた者だけが得をする」という構造があり、攻略情報を持たずに自力で発見したときの喜びはひとしおでした。この「努力が報われる仕組み」がプレイヤーの探索意欲を支えたのです。
緊張感を演出するサウンドとビジュアル
本作のBGMは派手さを抑え、重苦しい旋律や不協和音を多用しています。敵が現れる前の静寂や、不意に響く低音がプレイヤーの心を不安にさせ、探索をより恐ろしいものに変えました。 また、ポリゴン表現の粗さは当時の限界でもありましたが、それを逆手に取った暗がりの演出が功を奏しました。見えないことが恐怖を生み、視界が制限されることで「次に何が出てくるかわからない」緊張感を増幅させたのです。この点は技術の制約を魅力へと昇華した好例と言えます。
プレイヤー主導の自由度
本作には「次はここへ行け」といった明確な導線がありません。そのため、プレイヤーは自ら選択して行動し、自分なりの攻略ルートを作り上げることができます。これは「自由度が高すぎて不親切」とも捉えられましたが、同時に「自分だけの冒険をしている」という実感を与えてくれました。 特定のイベントやお使い要素も存在しますが、ほとんどが任意であり、完全に無視して進めてもゲームが成立する点は当時のRPGとしては異色でした。余計な縛りを感じず、探索と戦闘そのものに集中できる点は多くのプレイヤーに支持されました。
硬派な世界観とキャラクター造形
NPCたちはどこか冷淡で、明るく振る舞う者はほとんどいません。彼らは最低限の情報を提供するだけで、物語を華やかに盛り上げることはありません。しかし、その素っ気なさが逆に「この世界では誰もが生き延びることで精一杯なのだ」というリアリティを与えていました。 また、断片的に語られる王国の歴史や墓所の由来は、想像力を掻き立てます。プレイヤーは与えられた断片を自分なりに組み合わせ、物語を補完していく楽しみを味わうことができました。これは後のフロム作品にも受け継がれる「語られない物語」の魅力の原型と言えます。
後続作品やゲーム文化への影響
『キングスフィールド』で培われた要素は、その後のフロム・ソフトウェア作品に数多く受け継がれました。『アーマード・コア』に見られる独特の操作感や、『Demon’s Souls』『Dark Souls』で確立された高難度かつ高密度なゲームデザインの源流は、確かにこの作品に存在します。 また、当時の日本の家庭用ゲーム市場において「プレイヤーを選ぶ硬派なRPG」が堂々と発売されたこと自体が稀有であり、後の「マゾゲー」文化やソウルライクの誕生に繋がったと評価されています。結果として、『キングスフィールド』は単なる一タイトルにとどまらず、日本のゲーム史に残る特異点となったのです。
■■■■ 悪かったところ
序盤の理不尽な難易度
『キングスフィールド』の大きな課題としてまず挙げられるのは、ゲーム開始直後からプレイヤーに襲いかかる高難度です。初期装備は心許なく、回復手段もほとんどない状態で墓所に放り込まれるため、わずかな油断でゲームオーバーになってしまいます。 特にスケルトンや食人植物のような序盤の敵であっても、数発の攻撃で致命傷を受けてしまうバランスは、多くの初心者を挫折させました。これにより「理不尽すぎる」「まともに遊べない」という印象を与え、せっかくの革新的な試みが広く浸透することを妨げたのです。
チュートリアル不足と不親切な設計
現在のRPGでは当たり前となったチュートリアルやガイドが、本作にはほとんど存在しません。セーブポイントの場所や回復手段の存在すら明示されず、装備品の性能も実際に使ってみなければ分からない仕様でした。 また、アイテム説明が簡素すぎるため、入手したアイテムの用途が分からず放置してしまうケースも多く、攻略本や雑誌の情報がなければ正しく活用できない場面が少なくありませんでした。この「手探り感」が魅力である一方、ユーザーフレンドリーさを欠いていたことは否めません。
グラフィックと3D酔いの問題
当時としては先進的だったフルポリゴン表現ですが、テクスチャの粗さや描画の荒さが目立ち、長時間プレイすると3D酔いを訴えるプレイヤーが続出しました。特に歩行時の上下揺れは「臨場感」を狙った演出でしたが、結果的に酔いやすさを助長する要因になりました。 また、暗い墓所を舞台にしたことで視界が狭く、壁のパターンも似通っていたため、プレイヤーが方向感覚を失いやすかったのも欠点でした。雰囲気作りには成功したものの、快適さを犠牲にした部分は確かに存在していました。
移動速度の遅さとテンポの悪さ
移動速度が遅く設定されているため、単純に探索するだけでも時間がかかります。戦闘時には適切なテンポで緊張感を生み出す効果がありましたが、探索に戻ると「もどかしい」と感じるプレイヤーも少なくありませんでした。 また、一度行った場所を再び通る際、すでに敵も罠も知っているのにゆっくりと歩かされるため、ストレスが溜まる原因になりました。この点は続編で改善されますが、初代を体験した当時のユーザーからは「テンポの悪さ」が批判されました。
目的を見失いやすい構造
自由度の高さは魅力である一方で、明確な指針が欠けていたため、プレイヤーは「次にどこへ行けばいいのか分からない」という状況に陥りやすかったのです。結果として、無駄に同じ場所を彷徨ったり、強すぎる敵がいるエリアに迷い込んでゲームオーバーになるなど、理不尽さを感じる場面が頻出しました。 これは「自分で考えて行動する自由」と「プレイヤーを導く適度なガイド」のバランスが崩れていたことを意味します。当時の多くのユーザーにとって、この自由さは「不親切」と同義だったのです。
リソース不足による表現の限界
プレイステーション初期の作品ゆえ、グラフィックや処理能力に限界がありました。そのため、キャラクターの表情や動きはぎこちなく、テキストも簡素で淡々としています。演出の弱さが「淡泊すぎる」「盛り上がりに欠ける」と感じられる一因となりました。 また、敵の種類も現代の基準から見れば少なく、同じようなデザインが繰り返し登場します。これにより後半の探索がやや単調に感じられるという批判もありました。
万人向けでないデザイン哲学
全体を通して言えるのは、本作が「誰にでも楽しめるように作られていない」という点です。高い難易度、説明不足、暗い世界観といった要素は、ゲーム初心者やライトユーザーにとっては障壁でしかありませんでした。 結果として、本作はコアゲーマーや硬派なRPGファンには評価されたものの、一般的なプレイヤー層には受け入れられにくく、「尖りすぎた実験作」という印象が残ってしまったのです。
[game-6]■ 好きなキャラクター
主人公ジャン ― 無口な冒険者の存在感
本作の主人公ジャンは、いわゆる「喋らない主人公」として描かれています。多くのRPGでは主人公が物語をリードしたり仲間と会話を重ねることで性格づけがなされますが、『キングスフィールド』ではジャンの感情は一切語られません。しかし、その無口さがかえってプレイヤー自身を投影させる余地を与え、「自分がジャンである」という没入感を強化しました。 また、圧倒的な死のリスクにさらされながらも墓所を探索する姿は、プレイヤーにとって「もう一人の自分」であり、「過酷な冒険を生き抜く象徴」として強く印象に残ります。
墓守の親子 ― 不気味さと人間臭さの同居
序盤で出会う墓守の親子は、本作のキャラクター性を象徴する存在です。彼らは単なる情報源やアイテムの売り手に過ぎませんが、淡々とした口調と無表情な描写が逆に不気味さを際立たせています。一方で「墓を守る」という行為自体には人間らしい責任感や生活感が滲み出ており、プレイヤーに妙なリアリティを与えました。 特に、地図を入手するために関わるイベントでは、「ゲーム的な便利さ」と「キャラクターとしてのリアリティ」が交差し、プレイヤーの記憶に深く刻まれます。
ライト商会の商人 ― 無機質な取引相手
地下一階にあるライト商会で出会う商人は、探索を続ける上で欠かせない存在です。武器や防具、回復アイテムを販売してくれるのですが、その口調や態度には温かみが一切なく、完全に「ビジネスライク」に徹しています。 このドライなキャラクター性は、従来のRPGに登場する「親切で人情味のある店主」とは対照的であり、本作独特の冷徹な世界観を強調しました。愛想がなくとも、彼の存在がなければ冒険は成立しない。そのギャップがプレイヤーに強い印象を残しました。
教会の神官 ― 希望の象徴と不気味さ
教会にいる神官は、プレイヤーにとってセーブや回復を担う重要な存在です。彼の存在があることで「死に戻り」の負担が軽減され、探索を継続する勇気が湧きます。しかし、彼の言葉は決して優しくはなく、儀式的で冷たい響きを持っています。 プレイヤーにとっては救済者であると同時に、不気味さを漂わせる存在。この二面性が強烈な印象を残し、「信仰と恐怖が共存する空間」を演出していました。
寡黙な兵士たち ― 沈黙が語る世界観
序盤に登場する兵士たちは、主人公と同じ王国の兵士でありながら、皆疲弊しており士気も低く、救いのない言葉を発します。彼らは長い間墓所に閉じ込められ、絶望の中でただ命令に従っているだけの存在に見えます。 明るさや友情を提供することはなく、ただ「ここでは誰もが孤独に戦っている」という事実を突きつけてきます。この無力感を抱えた兵士たちの姿が、プレイヤーの孤独感を一層強めたのです。
敵キャラクターへの愛着
『キングスフィールド』では、敵キャラクターでさえ印象深く語られることが多いです。スケルトンのぎこちない動き、食人植物の不気味な挙動、暗闇の奥から突然現れる大型モンスター。彼らは単なる障害物である以上に、プレイヤーの恐怖体験を形作る重要な存在でした。 何度も倒され、ようやく勝てるようになった時には「憎らしい敵」から「克服すべき試練」へと認識が変わり、ある意味では愛着に近い感情を抱くこともありました。この「敵にも記憶に残る個性がある」という点は、後のフロム作品の敵キャラデザインにも受け継がれています。
キャラクター全体に漂うドライさ
総じて本作のキャラクターたちは、親しみやすさやユーモアをほとんど持ちません。むしろ無機質で、必要最低限の言葉しか語らない者ばかりです。しかし、そのドライさこそが『キングスフィールド』らしさを形作っています。 プレイヤーは彼らに感情移入するのではなく、「この世界では人々がこう生きている」というリアリティを感じ取るのです。その結果、キャラクターの一言一言が重く響き、印象深く残るという独自の体験が生まれました。
[game-7]■ 中古市場での現状
ヤフオク!での取引状況
ヤフオク!では『キングスフィールド(初代)』は今も一定数の出品が確認できます。価格帯は2,000円前後から4,000円程度が主流で、状態や付属品の有無によって相場が変動します。特に「ケースにスレあり」「説明書欠品」といった不完全な品は安価に落札されることが多く、1,500円前後で手に入る場合もあります。 一方で、ケース・ラベルが美品で説明書が揃った完品は人気が高く、入札が複数集まって3,000円以上に跳ね上がることも珍しくありません。オークション形式よりも「即決」で出品されるケースが増えており、コンディションの良いものほどウォッチリストに登録されやすく、終了間際に競り合いが起こりやすい傾向があります。
メルカリでの販売傾向
フリマアプリのメルカリでは、出品数が比較的安定しており、価格帯は2,000円~3,000円前後に集中しています。「送料無料」「即購入可」といった条件のものが特に人気で、状態が良ければ短期間で売れてしまうケースが多いです。 ディスクに傷がある、ケースにひび割れがあるなど状態が悪いものは1,500円台まで値下げ交渉されることが多く、売却までに時間がかかることもあります。一方で、未使用に近いコンディションや動作確認済みのものは安定して2,500円~3,000円で取引されています。出品者の説明文の丁寧さや写真枚数が価格に大きく影響する点も特徴的です。
Amazonマーケットプレイスでの価格設定
Amazonマーケットプレイスでは、出品価格はやや高めに設定される傾向があります。中古品であっても3,000円台が中心で、特に「Amazon倉庫発送」や「プライム対応」の商品は安心感から相場が高くなる傾向があります。 また、説明書やケースの状態が明記されていない出品も多く、購入者はレビューや出品者の評価を参考に選ぶ必要があります。利便性の高さから多少高額でも購入されやすく、Amazonでは“安さより安心感”が優先されているようです。
楽天市場での取り扱い
楽天市場では、中古ソフト専門店やリユースショップが出品しており、価格はおおむね2,500円~3,800円程度に収まります。ショップによってはポイント還元や送料無料キャンペーンが行われており、実質的に他のフリマサイトと変わらない価格で購入できるケースもあります。 ただし、出品数自体はヤフオク!やメルカリに比べると少なく、欲しいタイミングで必ず見つかるとは限りません。楽天を利用する場合は、在庫切れになりやすいことを念頭に置いて探す必要があります。
駿河屋での安定した相場
中古ゲーム販売大手の駿河屋では、在庫がある場合には2,200円~3,000円前後で販売されることが多いです。駿河屋はコンディションの表記が比較的丁寧で、状態による価格差も明示されているため、安心して購入しやすいのが強みです。 ただし人気タイトルやレトロゲームは在庫切れになりやすく、『キングスフィールド』も需要が集中すると一時的に「在庫なし」表示が続くことがあります。再入荷を狙う場合は通知サービスを活用すると効率的です。
未開封品・完品の希少性
発売から30年近くが経過した現在、未開封品や帯・ハガキ付きの完品は非常に希少です。市場に出回ることは稀で、見つかった場合には5,000円以上で取引されることもあります。外箱やシュリンクが残っているものはコレクター需要が高く、即決で落札される傾向があります。 一方で、ディスクやケースが通常使用に耐えうる状態であれば、プレイ用としての需要は依然として健在です。そのため「遊ぶ用」と「コレクション用」で市場価値が二分化しているのが現状です。
市場の変動要因と今後の見通し
中古市場の価格は、フロム・ソフトウェアの最新作リリースや記念イベントと連動して変動する傾向があります。たとえば『エルデンリング』や『ダークソウル』の関連ニュースが盛り上がると、原点である『キングスフィールド』への注目が高まり、一時的に相場が上がることがあります。 また、配信サービスや復刻版の登場は相場を押し下げる要因になります。もし将来的にPlayStation公式のクラシックタイトルとして再配信されれば、中古市場での需要はやや落ち着くかもしれません。しかし、物理メディアとしての希少価値は揺らがず、今後もコレクター市場では一定の価格を維持すると予想されます。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
【中古】 KING’S FIELDII(キングスフィールド)/PS
【中古】[PS] KING'S FIELD III(キングスフィールド3) フロム・ソフトウェア (19960621)
【中古】 KING’S FIELDIII(キングスフィールド)/PS




 評価 5
評価 5
![【中古】[PS] KING'S FIELD III(キングスフィールド3) フロム・ソフトウェア (19960621)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270306.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] KING'S FIELD II(キングスフィールド2) フロム・ソフトウェア (19950809)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270065.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS] KING'S FIELD II(キングスフィールド2) PlayStation the Best(SLPS-91003) フロム・ソフトウェア (19960712)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/6/cg10276538.jpg?_ex=128x128)