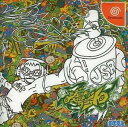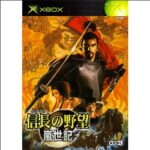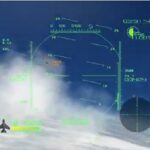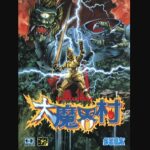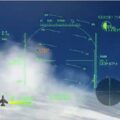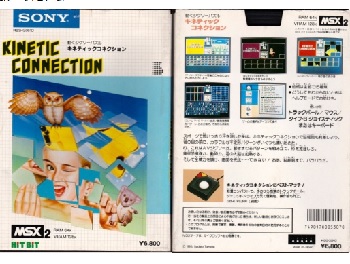【中古】Xbox ジェットセットラジオフューチャー
【発売】:セガ
【開発】:スマイルビット
【発売日】:2002年2月22日
【ジャンル】:アクションゲーム
■ 概要
Xboxローンチを彩ったセガの挑戦
2002年2月22日、日本国内でマイクロソフトの家庭用ゲーム機「Xbox」が発売されました。その記念すべきローンチタイトルのひとつとして登場したのが、セガが開発・販売を手掛けた『ジェット セット ラジオ フューチャー』です。本作は、ドリームキャストで高い評価を受けた『ジェットセットラジオ』の流れを汲みつつ、より大規模で洗練されたゲーム体験を提示することを目的とした作品でした。セガは既にハード事業から撤退していたため、Xbox参入にあたり、強烈なインパクトを残せるソフトが必要とされていました。その中で「フューチャー」は、単なる続編ではなくリブート的な位置付けを持ち、プレイヤーに「新世代のセガ」を印象付ける役割を担っていたのです。
セルシェーディングが描き出すコミック的表現
『ジェット セット ラジオ フューチャー』最大の特徴は、セルシェーディング技術を駆使したビジュアル表現にあります。当時のゲームはリアル志向へと傾き始めていましたが、本作は真逆のアプローチを取り、アニメや漫画のような色彩感覚で構築された3D世界を提示しました。キャラクターの輪郭線を強調し、ビビッドな色合いで街を彩るグラフィックは、プレイヤーに強い没入感を与えるだけでなく、「ゲームは現実の模倣にとどまらない」というセガのメッセージを体現していました。この手法は現在では一般的ですが、当時は非常に革新的で、業界のグラフィック表現の幅を広げた存在といえます。
舞台となるショウワ99年のトーキョー
物語の舞台は「ショウワ99年」という独自の年号が刻まれる近未来都市「トーキョー」。現実の東京をベースにしながらも、サイバーでポップな装飾が施された空間が広がり、現実と虚構が混ざり合ったような独特の雰囲気を漂わせています。渋谷を思わせる繁華街や工業地帯、下水道、遊園地など、ステージの舞台設定は多岐にわたり、それぞれのエリアが異なるライバルチームや障害物によって彩られます。街は単なる背景ではなく、スケートで駆け抜け、グラフィティを描くことで初めて意味を持つ「遊び場」として機能し、プレイヤー自身が都市に痕跡を刻んでいく体験が提供されました。
ストーリーと主要キャラクター
プレイヤーは若者ストリートチーム「GG」のメンバーとなり、街に自らの存在を示すために活動していきます。登場キャラクターは前作に登場したビート、ガム、コーン、ヨーヨーなどの面々に加え、クラッチやジャズといった新メンバーも加わり、さらに個性豊かになっています。 物語の敵役としては、前作で印象的だった鬼島警部に代わり、破天荒で短気な「ハヤシ警部」が登場。彼は単に警察の象徴ではなく、戦車やロボットすら動員するなど、常識外れな存在としてプレイヤーを苦しめます。さらに都市を支配する巨大組織「六角グループ」や、その頂点に立つ六角ゴウジが立ちはだかり、ストリートの自由と巨大権力の衝突というテーマが濃厚に描かれます。終盤では、街そのものを支配しようとする壮大な計画が明らかになり、プレイヤーはグラフィティを武器に巨大な陰謀へと挑むことになります。
新しいアクションと操作性の強化
ゲームシステムも進化を遂げています。前作の爽快なグラインドやスプレーアクションは健在ですが、新たに「ブーストダッシュ」などスピード感を増幅させるアクションが追加されました。これにより街を滑走する快感は格段に高まり、単なる移動そのものがエンターテインメントとして成立しています。また、最大4人での対戦プレイにも対応し、仲間同士でスコアを競ったり、ライバル同士の駆け引きを楽しむことができるようになりました。
当時の社会背景と作品の意義
2000年代初頭は、グローバルなゲーム市場で日本のメーカーが次世代機戦争に挑んでいた時代です。セガはハード事業を降りたものの、個性的なソフトを武器に再起を図ろうとしていました。その中で『ジェット セット ラジオ フューチャー』は、「セガらしい遊び心」と「時代を先取りするデザインセンス」を兼ね備えた作品として位置づけられました。とりわけ、ストリートカルチャーや反体制的なメッセージを持ち込んだことは、当時のゲーム業界において異彩を放っており、ファンにとっては「セガがまだ攻め続けている」という証でもありました。
プレイヤーへの体験の残響
実際に本作を手にしたプレイヤーは、その独創的な世界観と音楽、自由度の高いアクションに衝撃を受けました。都市を滑走しながら壁にスプレーを描き、自分だけの足跡を残していく体験は、他のゲームでは味わえない解放感を生み出しました。また、キャラクターごとのデザインや個性が強烈で、プレイヤーそれぞれに「お気に入りの一人」が存在する点もファンの間で大きな話題となりました。
個性豊かなプレイアブルキャラクター
『ジェット セット ラジオ フューチャー』の魅力のひとつは、プレイヤーが操作できるキャラクターの多彩さです。最初に選べるのは「ヨーヨー」ですが、ゲームを進めることで「ビート」「ガム」「コーン」などシリーズお馴染みの面々が仲間に加わり、やがて新メンバーも増えていきます。 それぞれにデザインや性格が際立っており、スケートアクションの得意分野やスピード感も微妙に異なるため、単なる見た目の違いではなく、プレイヤーごとのプレイスタイルに影響を与えました。たとえば、ヨーヨーは小回りが利き初心者にも扱いやすい反面、トップスピードでは劣ります。対して「ビート」はクセのないバランス型で、本作の象徴的存在。「クラッチ」のような新キャラは赤髪に灰色のパンツという強烈なビジュアルに加え、仲間加入時の特殊条件が話題となり、ゲーマーの間で「捕まえ方」について議論が交わされるほどでした。
ストリートに巣食うライバルチーム
本作では、プレイヤーが街を支配していく過程でライバルチームとの抗争が頻繁に発生します。前作から引き続き登場する「ポイズンジャム」や「ノイズタンク」、女性チームの「ラブショッカーズ」に加え、新勢力として「ラピッド99」や「イモータルズ」といった強烈なチームも登場。 特に「ラピッド99」は、元々ガールズバンドとして活動していた過去を持ち、ストリートギャングへと転じた経歴を持つ異色のチームです。彼女たちは黒と赤の派手な衣装に網タイツという挑発的なデザインで、ファンからの人気も高く、「女性ストリートカルチャーの象徴」とも言われました。一方で「ノイズタンク」は完全にロボット化され、無機質で冷酷な雰囲気を漂わせ、プレイヤーに無言の圧をかけてきます。このように、チームごとの背景やデザインの差異が、単なる敵役以上の存在感を生み出していました。
ハヤシ警部と六角ゴウジの存在感
敵キャラクターの中でも突出した存在が、ハヤシ警部と六角ゴウジです。ハヤシ警部は、前作の鬼島警部を超える奇人として描かれ、短気で乱暴な性格から銃を乱射したり、戦車や戦闘機まで投入したりと常識外れの行動を繰り返します。その一挙手一投足がユーモラスでありながらも恐ろしく、プレイヤーに強烈な印象を残しました。 一方、六角ゴウジは都市を掌握する巨大財閥「六角グループ」の会長であり、物語の最終的な黒幕です。都市開発の名の下に「ロモゲ・ヘモ・ビリ・ホ・パン」という洗脳装置を建設し、市民を支配しようと企む姿は、単なる悪役以上に権力の象徴として描かれました。終盤の異空間での最終決戦は、現実離れした演出とともにプレイヤーの記憶に強く刻まれることになります。
プロフェッサーKとラジオの存在
本作を語る上で欠かせないのが、海賊ラジオ「ジェットセットラジオ」のDJ、プロフェッサーKの存在です。彼はプレイヤーの行動を実況し、時に挑発し、時に鼓舞する役割を担っています。彼の独特な喋りと声のトーンは、単なるナレーションではなく、プレイヤーに「街を共に駆け抜けている仲間」という感覚を与えました。 前作に比べて髪が銀髪交じりになり、年齢を感じさせつつもなおカリスマ的存在感を放っており、ゲームの世界観に厚みを加えています。ラジオ放送があることで、街の出来事や対立構造が自然に解説され、プレイヤーがストーリーを没入的に理解できる仕組みになっていました。
ビジュアルとサウンドの融合
『ジェット セット ラジオ フューチャー』は、映像と音楽の融合度が極めて高い作品でした。ビジュアル面ではセルシェーディングを軸にしつつ、ステージごとにライティングや色調が異なり、街の空気感を鮮やかに描き出しました。たとえば繁華街はネオンが眩しく、下水道は緑がかった不気味な光に満ちており、単なる「場所」ではなく「感情を揺さぶる舞台」として機能していたのです。 音楽面では、ヒップホップやテクノ、ロック、エレクトロといった多彩なジャンルを融合させたサウンドトラックが用意されました。曲ごとにクセの強さが異なり、プレイヤーの行動とシンクロすることで、街を滑走する体験がリズムゲーム的な快感に変わります。ファンの間では今なおサウンドトラックが語り草になっており、「ゲーム音楽の金字塔」と評されるほどの影響力を持っています。
技術的進化とXboxの性能
本作がドリームキャストからXboxへと舞台を移したことで、技術的進化も顕著でした。Xboxのハード性能を生かし、ステージは広大かつシームレスに構築され、ロード時間も短縮。敵や仲間の数が増えても処理落ちしにくい安定感は、当時としては高水準でした。また、「マンガブラー」と呼ばれる残像効果や光の演出など、表現面でも新世代機ならではの表現が導入され、プレイヤーの目を惹きました。セガはこれらの技術を単なるデモンストレーションではなく、遊びの快感に直結させる形で活用し、「未来のアクションゲーム像」を提示したのです。
ストーリーの進行とゲーム構造
『ジェット セット ラジオ フューチャー』のストーリーは、章仕立てで進んでいきます。各チャプターごとに異なる敵勢力やライバルチームとの対決が用意され、都市の支配権を広げていく流れとなっています。進行は自由度が高く、プレイヤーはどのエリアから攻略するかをある程度選べるため、「一本道ではない冒険感」が強調されています。単にステージをクリアするのではなく、「自分の痕跡を残しながら街を解放していく」実感が得られる点が、従来のアクションゲームとは一線を画していました。
警察勢力との攻防
ライバルチーム以上に印象的なのが、ロッカク警察(ケーカン)との戦いです。通常の警官から、武装した重装備警官、さらには戦車やヘリコプターまで投入されるスケールの大きさは、当時のプレイヤーにとって衝撃でした。単純に「捕まらないように逃げる」のではなく、グラフィティを使って彼らを撃退できる仕組みが用意されており、ストリートカルチャーと権力との衝突をゲーム的に表現していました。特に「武装ケーカン」に対しては、通常の体当たりでは倒せず「ブーストダッシュ」が必要というルールが設けられ、戦術的な工夫を促しました。
ライバルチームのキャラクターデザイン
敵チームのデザインには強烈な個性があります。「イモータルズ」は全員がミイラ姿で、古代遺跡を思わせるビル街を拠点に活動。「ドゥームライダーズ」は赤いマフラーをたなびかせるバイカー風の集団で、わずかな登場ながら強烈なインパクトを残しました。「ラピッド99」は、ブルマに網タイツという奇抜な衣装が特徴で、プレイヤーの記憶に残る存在となりました。彼女たちが音楽活動からストリートギャングに転じたという設定は、単なる敵ではなく「背景を持ったキャラ」としてのリアリティを感じさせました。
異色の存在・NT-3000とゼロビート
本作には、ライバルチーム以外にも特異な存在が登場します。たとえば「NT-3000」はヨーヨーそっくりのロボットであり、ストーリーの重要な転換点を担っています。「俺がホントのニセモノだヨゥ!」というセリフはシリーズ屈指の印象的な一幕で、ファンの間では長く語り草となっています。 また「ゼロビート」は六角ゴウジが生み出したビートのコピー体で、漆黒のボディに青く光る目という不気味なデザイン。人間味のあるビートとの対比が鮮烈で、「権力により個性を奪われた存在」として物語的な象徴となっています。
六角グループ幹部たち
物語後半では、六角ゴウジを支える幹部たちが立ちはだかります。「アーム少佐」は伸縮自在のロングアームを武器にし、「ファイア参謀」は女性でありながら火炎放射器を操る強烈なキャラクター。このような幹部キャラは単なる中ボスではなく、六角グループという組織が持つ異様さを表すピースとなっていました。終盤でプレイヤーが挑むのは、単なるストリートの抗争ではなく、都市全体を牛耳る組織との全面対決へと発展していきます。
サポートキャラクターとユーモラスな演出
「ロボィ」や「ポッツ」といったサポートキャラクターの存在も忘れてはなりません。毒舌気味なロボィは、ノイズタンクのプロトタイプという裏設定を持ち、物語にちょっとしたSF的要素を加えました。犬の「ポッツ」は条件を満たすと二足歩行で操作可能になり、ファンにとっては隠れた目玉要素。こうした遊び心のある演出は、重厚なストーリーにユーモラスな緩急を与え、ゲーム体験を豊かにしていました。
ストリート表現の象徴としてのグラフィティ
本作のゲームプレイの核は「グラフィティ」です。前作ではプレイヤーが自由に画像を取り込んでオリジナルのグラフィティを描けましたが、Xboxにはその機能がなかったため、本作では内蔵された多彩なパターンから選択する形式に変更されました。とはいえ、スプレーを吹きかけるモーションや壁に刻まれていく音、完成したアートのインパクトは健在で、プレイヤーは「街を自分の色に染め上げる」実感を強く味わえました。グラフィティそのものがストリートカルチャーの反抗心と自由を象徴しており、それをゲームシステムの中心に据えた点が、作品のアイデンティティを際立たせています。
■■■■ ゲームの魅力とは?
スピード感と操作の快感
『ジェット セット ラジオ フューチャー』の大きな魅力は、インラインスケートを履いたキャラクターを操作して体感できるスピード感です。グラインドでガードレールを駆け抜けたり、歩道橋をジャンプで飛び越えたり、ブーストダッシュで一気に加速する感覚は、他のアクションゲームでは味わえない独特の爽快感を持っています。滑走そのものがゲームの中心に据えられているため、単なる移動がプレイの快感と直結しており、「街を滑る」こと自体がエンターテインメントになっているのです。
自由度の高さと探索の楽しさ
本作はステージクリア型でありながら、箱庭的な広がりを持つマップ構造が魅力のひとつです。建物の屋上へ登ったり、下水道の奥を探索したりと、プレイヤーの好奇心に応じて行動範囲を広げられる仕組みが用意されています。必ずしも決められたルートを辿る必要はなく、「どうやって目的の場所にたどり着くか」を考える探索要素が大きな楽しみになっていました。隠されたグラフィティソウルを探すコレクション要素もあり、やり込みを好むプレイヤーにとって長期的なプレイ意欲を刺激する仕組みでした。
個性的なキャラクターデザイン
プレイヤーキャラクターやライバルチームのメンバーは、いずれも強烈なビジュアルを持ち、アメコミやストリートファッションを取り入れたデザインが光ります。たとえば「ガム」は胸元を大胆に露出したセクシーなコスチュームで印象を残し、「コンボ」は巨大な体格に派手なネックレスを下げるなど、シルエットだけで個性が分かるような造形がなされています。この多様性は単なる見た目の違いに留まらず、プレイヤーに「自分の好きなキャラで街を駆け抜ける」楽しさを提供しました。キャラを集めていく過程そのものがゲームのモチベーションとなり、プレイヤーの没入感を高めていました。
ストリートカルチャーと反骨精神
本作が他のアクションゲームと決定的に異なるのは、「ストリートカルチャー」を前面に押し出している点です。都市の壁や路地に自らのグラフィティを残す行為は、単なるスコア稼ぎではなく、「既存の権力に抗う若者の表現」として描かれています。対立するのは警察や巨大企業であり、その図式は「自由と支配」「個性と権力」の衝突を象徴しています。遊んでいるプレイヤーは自然と「都市を解放するレジスタンス」の一員として振る舞うことになり、ストーリーを進めるほどに「自分自身が街を取り戻している」という実感を得られるのです。
音楽とのシンクロが生み出す没入感
『ジェット セット ラジオ フューチャー』は、サウンドトラックの完成度の高さでも語り継がれています。ヒップホップ、テクノ、ロック、ファンク、エレクトロなど、多様なジャンルをミックスした音楽は、単なるBGMにとどまらずプレイヤーの行動と一体化して響きます。スケートで加速しながら流れるリズムは心拍数を高め、グラフィティを描き終えた瞬間に響くサウンドは達成感を増幅しました。特にNaganuma Hideki(長沼英樹)が手掛けた楽曲は独特のサンプリングとビート感で人気を集め、後年になってもサントラがコレクターズアイテムとして扱われるほどの存在感を放っています。
多人数プレイの面白さ
今作では最大4人までの対戦プレイが可能となり、友人同士での熱いバトルが楽しめました。単なる点数の競い合いだけでなく、誰が最も速くグラフィティを描けるか、どこまで街を支配できるかといった競争要素が、パーティゲーム的な楽しさをもたらしました。当時のXboxはネットワーク機能をアピールしていたものの、日本ではオンライン要素は普及途上だったため、ローカルマルチの重要性が高く、家庭用機として「仲間とワイワイ遊ぶ」魅力をしっかり備えていた点は評価されました。
演出の派手さとビジュアル表現
加速時の残像「マンガブラー」、火花や光の軌跡など、本作の演出はとにかく派手で視覚的インパクトに満ちていました。当時のプレイヤーは、現実にはあり得ない演出が画面いっぱいに展開されることで、「自分がアニメや漫画の世界に飛び込んだかのような感覚」を味わえたのです。ゲームが単なる模倣ではなく「非現実の楽しさを表現できる」ことを証明した好例でもありました。
他タイトルとの差別化
2000年代初頭のゲーム市場は、リアル志向のグラフィックやFPSの台頭が主流になりつつありました。その中で『ジェット セット ラジオ フューチャー』は、あえて現実感を追求せず、コミック調のセルシェーディングとストリートカルチャーを融合させた方向性を選びました。この選択こそがセガらしい独自性であり、「大手メーカーが作った商業作品でありながらカルト的な雰囲気を持つ」という稀有な存在感を生み出しました。
やり込み要素とコレクション性
『ジェット セット ラジオ フューチャー』には、単にストーリーを追うだけでなく、やり込みを楽しめる要素が多数盛り込まれています。その代表が「グラフィティソウル」の収集です。街の各所に散らばるソウルを集めることで、新たなグラフィティパターンを解放できる仕組みとなっており、プレイヤーは探索のモチベーションを常に保てました。また、キャラクター解放条件にも特殊なチャレンジが設定されており、特定の場所でレースに勝つ、決められた条件をクリアするなど、一筋縄ではいかない達成感を与えてくれます。これにより、ストーリークリア後も長期間遊び続ける理由が生まれていました。
リズムと動作の一体感
本作の操作感は「音楽と身体がシンクロする」ような感覚を強く意識してデザインされています。キャラクターがスケートで滑る音、グラフィティを吹き付けるスプレーの音、そしてバックで流れるビートが絶妙に噛み合い、自然とプレイヤーがリズムを刻みながら行動してしまう設計です。この「無意識のうちに体が音楽に乗る」感覚は、リズムゲーム的な快感を持ちながらも、アクションゲームとしての自由度を損なわない絶妙なバランスを実現しています。
海外市場でのカルト的人気
日本国内でのXboxは販売規模が限られていたため、本作が大ヒットすることはありませんでした。しかし、北米や欧州のプレイヤーの間では、独特なビジュアル表現とストリート文化へのリスペクトが評価され、後に「知る人ぞ知る名作」として語り継がれることになります。とくに欧米の若年層は、ヒップホップやグラフィティといった文化に馴染みがあり、本作のコンセプトに強く共感しました。その結果、口コミやレビューサイトを通じて高評価が広まり、海外ゲーマーコミュニティにおけるカルト的な人気を獲得したのです。
ビジュアル面の時代を超えた新鮮さ
セルシェーディングを用いたグラフィックスタイルは、20年以上が経過した現在に見てもなお古さを感じさせません。むしろ、当時のリアル志向ポリゴン作品の多くが時代の制約を強く残している中で、本作の表現は「アートスタイルによる時間の超越」を体現しています。つまり、技術的な進歩によらずとも「デザインの選択」で普遍的な価値を持ち得ることを示したのです。この先進性は後続のゲームやアニメ調タイトルにも影響を与え、「スタイライズ表現」の地位を確立する一助となりました。
プレイヤーが作り出す物語性
本作のストーリーは明確に用意されていますが、プレイヤーはその枠を超えて「自分自身の物語」を作り出せる余地を持っています。例えば、どのキャラクターで攻略するか、どのルートから進めるかによって体験の印象は変わり、プレイヤーの選択そのものが物語性を持ちます。さらに、グラフィティを描いた場所や方法が違えば、自分のトーキョーは他人とは異なる姿に染まっていくのです。この「プレイヤーごとの都市」が存在する感覚こそが、本作を特別な体験へと昇華させていました。
アートとゲームの融合
『ジェット セット ラジオ フューチャー』は、ゲームでありながら「プレイするアート」としての側面を強く打ち出しました。キャラクターデザイン、音楽、街並み、グラフィティ、それらすべてが有機的に繋がり、プレイヤーの体験全体を「作品」として成立させています。当時、商業的な大作ゲームがリアリティやボリュームを追求していた中で、本作はあえて「芸術性」「カルチャー性」を重視し、プレイヤーに文化的な体験を提供しました。この独自の立ち位置が、今なおファンの心を掴み続ける理由のひとつです。
後世への影響力
本作のスタイルや思想は、その後のゲーム業界やカルチャーシーンに少なからず影響を与えました。セルシェーディングを採用したゲームは徐々に増え、ストリートカルチャーをテーマにした作品も登場するようになります。また、音楽とゲームの融合を模索する動きも活発化し、リズムやサウンドデザインを重視するアクションゲームの先駆けとして評価されるようになりました。さらに近年では、インディーゲームの世界で「JSRF風」と形容される作品も見られ、20年を経てもなお影響力を持ち続けていることがわかります。
■■■■ ゲームの攻略など
基本操作をマスターすることが第一歩
『ジェット セット ラジオ フューチャー』の攻略で最初に重要となるのは、キャラクターの基本操作をしっかりと体に馴染ませることです。スケートでの滑走は単なる移動手段にとどまらず、攻撃や回避、探索すべての土台になっています。特に「グラインド」の操作感は、初心者にとって最初の壁となりがちです。レールや縁に近づいたときに自然と乗れるよう意識し、カメラ操作も合わせて使うことでスムーズに行動できます。ブーストダッシュは体力(ターボゲージ)を消費するため乱用は禁物ですが、戦闘や長距離移動では不可欠なテクニック。まずは「ここぞ」という場面で自然にブーストが出せるよう練習することが、攻略の出発点となります。
グラフィティの描き方とタイミング
本作の勝敗を分ける要素のひとつが「グラフィティ」をいかに効率よく描けるかです。スプレーアクションは、敵チームとの抗争やステージ攻略において「街を制圧した証」として機能します。特に警察との戦闘中やライバルとの対峙では、立ち止まって描く時間がリスクになるため、タイミングの見極めが重要です。敵をうまくかわした直後や、ジャンプから着地した瞬間など、わずかな隙を見つけてスプレーを吹き付ける技術を習得すると攻略がぐっと楽になります。序盤は焦らず、安全なポイントを確保して描く練習を繰り返すのが良いでしょう。
キャラクターごとの適正を活かす
キャラクターは見た目だけでなく、ステータスや得意分野に違いがあります。スピード重視のキャラはレースや広いステージで有利ですが、操作がシビアになる傾向があります。逆に小回りの効くキャラは狭い場所や高低差の多いステージで活躍します。例えば、ヨーヨーは最初に使うキャラだけあって扱いやすい反面、後半の高速展開では力不足を感じやすいでしょう。一方で「ビート」はオールラウンダーとして使いやすく、「クラッチ」や「ジャズ」といった仲間は条件付きで加入するため、特殊なプレイ体験を提供します。攻略に行き詰まったときは、キャラクターを切り替えることで新たな突破口が見えてくることも少なくありません。
ステージ攻略のポイント
各エリアには特徴的な構造やギミックがあります。渋谷ターミナルのような人の多い街中では、警察との交戦が避けられないためスピードと回避が重要です。工業地帯や下水施設のようなステージでは足場が不安定で、ジャンプのタイミングを誤ると落下してしまうリスクが高いため、慎重さが求められます。さらに万博スタジアムや高層ビル群では、高低差を利用した立体的な移動が攻略のカギになります。「どのルートで進むか」をあらかじめ把握しておくことが、攻略をスムーズにするコツです。
ライバルチームとの対決の心得
敵チームとの戦闘は、単純な殴り合いではなく、スピードとグラフィティを駆使した陣取り合戦に近い性質を持っています。彼らは積極的に妨害してくるため、正面から戦うよりも「相手の動きを避けながら自分の行動を通す」ことを優先するべきです。ラピッド99のように俊敏で妨害が巧みなチームには、地形を活用して追いかけられにくい場所でグラフィティを描くのが有効。ノイズタンクのように硬い相手には、ブーストダッシュをうまく絡めて押し切る戦法が求められます。
ハヤシ警部戦の突破法
序盤から終盤にかけて執拗に追いかけてくるハヤシ警部は、攻略の大きな壁です。彼は銃を乱射し、時に戦車や巨大ロボットまで投入してきます。正面からまともに相手をするのは得策ではなく、基本は回避を優先しながら「警部の攻撃モーション後に生まれる隙」を突いて行動するのがコツです。特に戦車との戦闘では、地形を利用して死角を作り、そこから一気にグラフィティを描き切るのが有効。慌てずパターンを見極めれば、突破は十分可能です。
六角ゴウジとの最終決戦
物語終盤、六角ゴウジとの戦いは演出も難易度もシリーズ屈指の盛り上がりを見せます。洗脳塔「ロモゲ・ヘモ・ビリ・ホ・パン」での戦いは、敵の攻撃パターンが多彩で、画面演出も派手なため混乱しやすいですが、基本は冷静に「安全に動ける足場」を確保しながらグラフィティを刻んでいくことが重要です。異空間に飲み込まれた後の「アクム」と化したゴウジ戦では、背中にある弱点を狙う必要があります。焦らずターゲットを絞り、ブーストを織り交ぜて攻撃を叩き込むことで勝機を見出せるでしょう。
やり込み・裏技要素
本作には、隠しキャラクターや条件付きの仲間加入など、裏技的な要素も多数存在します。特定の条件を満たすことでライバルチームのメンバーが使えるようになったり、グラフィティソウルを一定数集めると新たなパターンが解放されたりします。これらをコンプリートするには、通常プレイ以上の粘り強さと探索心が求められます。また、一部のキャラは「特定の章で特定の行動を取る」といった条件を必要とするため、攻略本や情報サイトで調べるプレイヤーも多かったですが、試行錯誤しながら条件を突き止めること自体が楽しみでもありました。
効率的なグラフィティソウル収集法
本作のやり込み要素の中心である「グラフィティソウル」は、街のあちこちに散らばっており、通常のルートを進むだけではすべて回収できません。ソウルの配置は高所や見えにくい場所にあることが多く、攻略には「地形を覚える」ことが不可欠です。特にジャンプ台やレールのつながりを駆使して高所へアクセスするルートは、マップを探索しながら何度も試行錯誤して見つける必要があります。効率的に集めるコツは、一度ストーリーを進めきった後に、操作に慣れたキャラクターを使って「収集だけを目的に探索する」こと。プレッシャーなくソウル探しに集中できるため、結果的に早くコンプリートに近づけます。
初心者が注意すべき落とし穴
『ジェット セット ラジオ フューチャー』は一見ポップな雰囲気ながら、操作や構造を理解するまでは難易度が高めに感じられます。特に初心者が陥りやすいのは、カメラ操作を軽視してしまうことです。本作は立体的なステージが多いため、キャラの進む方向とカメラアングルが合っていないと、ジャンプをミスして落下したり、グラインドの乗り継ぎに失敗したりしがちです。まずは「移動と同時にカメラを動かす」意識を徹底することが、序盤の安定プレイへの近道です。また、警察との交戦で「無理に戦おう」としてしまうのも初心者の誤りがちな点。あくまで逃げる・かわすを優先し、安全を確保してから行動する癖をつけると格段に攻略がスムーズになります。
上級者向けテクニック
本作をやり込むプレイヤーは、単にステージをクリアするだけでなく、最短ルートや高得点を狙う遊び方に挑戦します。上級者向けのテクニックとして代表的なのが「ブーストキャンセル」と「ルート最適化」です。ブーストダッシュはゲージを消費しますが、適切なタイミングでジャンプや壁蹴りに繋げることで消費を抑えつつ加速を維持できます。さらに、レールを繋げる際にわざと斜めに飛び移ることで距離を短縮し、より効率よく目的地に到達する技術も重要です。こうした工夫を積み重ねることで、同じステージでも攻略時間を数十秒単位で縮めることが可能となり、スピードラン的な遊び方へと発展していきます。
プレイスタイルごとの楽しみ方
攻略においては「どのようなプレイスタイルを取るか」によって楽しみ方が変わってきます。スピードを重視してゴールを目指す人もいれば、隅々まで探索してグラフィティを描き尽くす人もいます。前者はテクニカルな操作を追求する「アスリート的な楽しみ方」であり、後者は「自分の痕跡を街に刻む芸術的な楽しみ方」といえるでしょう。また、キャラクターごとの個性を堪能するプレイヤーも多く、「誰でプレイするか」によってモチベーションが変わる点も本作ならではの醍醐味です。
難所攻略の心得
ゲームを進めていくと、操作精度や判断力を試される難所がいくつも登場します。高層ビル群のジャンプ連続エリアや、下水施設の狭い足場は特に事故が多発するポイント。こうした場面では「勢いで突破しようとせず、一度落ち着いて地形を確認する」ことが重要です。タイミングを見極める余裕を持つことで、無駄なミスを大幅に減らすことができます。さらに、敵が同時に出現する場面では「倒す順序」を決めることで効率よく切り抜けられます。焦って全員に対応しようとするのではなく、最も厄介な相手から順に処理する発想が攻略を安定させます。
攻略本やネット情報に頼らない楽しみ
発売当時はインターネット掲示板や攻略本で情報を集めるプレイヤーも多くいましたが、本作の真の面白さは「自分で発見すること」にあります。隠されたルートや加入条件を偶然見つけたときの喜びは格別で、「街を自分の目で切り開いていく」感覚をより強く感じられます。もちろん全要素をコンプリートするには外部情報が役立ちますが、初回プレイではあえて情報に頼らず試行錯誤することで、探索と発見の楽しさが最大限に活きるのです。
リプレイ性の高さ
ストーリーを一度クリアした後も、別のキャラを使って再挑戦したり、収集要素を埋めたりと、リプレイ性が高い点も本作の特徴です。さらに友人との対戦モードを利用すれば、純粋にアクションの腕前を競う遊び方も可能。プレイヤーが遊び込めば遊び込むほど、新しい発見や成長を感じられるため、単なる「一周クリアで終わる作品」ではなく、長期的に愛され続ける余地を持ったタイトルとなっていました。
■■■■ 感想や評判
プレイヤーの第一印象
発売当時、本作を手に取ったプレイヤーの多くがまず驚いたのは「グラフィックの独創性」でした。セルシェーディングによるアニメ風の映像表現は、2000年代初頭の家庭用ゲームとしてはまだ珍しく、画面写真を見ただけで「ほかのゲームとは違う」と感じさせる力を持っていました。実際に遊んでみると、スピード感ある滑走と派手なエフェクトが融合し、「動かしているだけで楽しい」という印象を強く残したと語るプレイヤーが多かったのです。
自由度の高さへの評価
ストーリーを追いかけるだけでなく、街を探索してグラフィティを描きまくる楽しさは、多くのゲーマーにとって新鮮な体験でした。従来のアクションゲームがゴール地点を目指す一本道構造だったのに対し、本作は「自分の選んだルートで街を制圧する」自由さを備えており、「遊んでいるうちに自然と自分だけの物語が出来上がっていく感覚がある」との声が多く寄せられました。
操作難易度に関する賛否
一方で、操作性の難しさについては賛否が分かれました。カメラワークやジャンプのタイミングは慣れるまで難しく、特に初心者には「思った場所に着地できない」「警察に捕まってばかり」という不満が出やすかったのです。ただし、操作に慣れたプレイヤーからは「難しいからこそ上達の実感が大きい」「やり込むほど快感が増す」との声もあり、いわゆる「スルメゲー(噛めば噛むほど味が出る作品)」として支持される側面もありました。
音楽への圧倒的支持
特に高く評価されたのが、音楽の完成度です。長沼英樹を中心とした楽曲群は、ヒップホップやエレクトロを軸にしながら、遊び心あふれるサンプリングや奇抜なリズム構成を用いており、ゲーム音楽の枠を超えた魅力を持っていました。プレイヤーからは「サウンドトラックを繰り返し聴いている」「曲を聴くと当時のプレイ体験が鮮明によみがえる」といった感想が数多く寄せられ、後にサントラCDがコレクターズアイテムとして高値で取引されるほどの人気を誇りました。
日本と海外での温度差
日本国内では、Xbox本体自体の普及が限定的だったため、本作の知名度やプレイ人口は限られていました。そのため「知る人ぞ知る名作」としてひっそりと評価されるに留まったのです。しかし海外、とくに北米や欧州では事情が異なり、Xboxユーザーの間で「ローンチ期の傑作」として高く評価されました。欧米ではストリートカルチャーへの親和性が高く、ゲームと音楽とビジュアルが一体となった本作は「時代を象徴するスタイルゲーム」として熱狂的に支持されたのです。
ゲーム雑誌での評価
当時の国内外のゲーム雑誌レビューでも、本作はビジュアルと音楽面で高い点数を得ました。特に「斬新な世界観と演出は唯一無二」「芸術作品としての完成度が高い」といった論評が目立ちました。一方で「操作性にクセがある」「日本市場で受け入れられるには敷居が高い」といった指摘もあり、総合評価としては良作~名作のラインに位置づけられることが多かったです。
ファンコミュニティでの語り継がれ方
本作を愛したプレイヤーたちは、発売から年月が経った後もオンライン掲示板やSNSで語り合いを続けています。「このゲームで初めてストリートカルチャーを知った」「音楽の影響でDJやグラフィティに興味を持った」といった人生レベルの体験談も少なくなく、単なるゲームの枠を超えて文化的な影響を残したことが伺えます。続編を望む声も多く、リマスターや移植の要望は今なお絶えません。
総合的な評判
まとめると、『ジェット セット ラジオ フューチャー』は「操作に慣れるまでの難しさ」や「Xboxの普及度の低さ」といったハードルを抱えながらも、その独創的な世界観、音楽、アート表現によって強烈なインパクトを残しました。特に海外市場ではカルト的な人気を獲得し、今なお「Xbox初期を代表するタイトル」「時代を先取りした名作」として評価され続けています。
■■■■ 良かったところ
独創的で色褪せないビジュアルスタイル
本作を語る上で最も多くのプレイヤーが「良かった」と挙げるのは、その独創的なグラフィック表現です。セルシェーディングによるアニメ調のビジュアルは、2002年当時のゲーム市場ではまだ新鮮で、今見ても古さを感じさせません。輪郭線を強調したキャラクター、極彩色に彩られた都市空間、派手なエフェクト――そのすべてが一体となり、まるでプレイヤーが漫画やアニメの世界に飛び込んだような体験を生み出しました。これにより「ただのゲーム」ではなく「ひとつの芸術作品」として評価されることも多く、ビジュアル面での好意的な声は非常に強かったのです。
音楽の中毒性と完成度
「音楽が素晴らしかった」という感想も圧倒的多数を占めます。長沼英樹を中心に構成されたサウンドトラックは、ヒップホップやファンク、テクノなどをミックスし、遊んでいるうちに自然と体がリズムを刻んでしまうような中毒性を持っていました。プレイヤーからは「音楽のおかげでステージ攻略が苦にならなかった」「曲を聴くだけでプレイの感覚を思い出せる」といった声が寄せられ、サントラを単独で聴くファンも多く存在しました。これは、他のアクションゲームにはあまり見られない「音楽が体験の核になる」珍しいケースであり、非常に高く評価された部分です。
スピード感と操作の爽快さ
インラインスケートで街を駆け抜けるスピード感は、まさに本作の代名詞ともいえる魅力でした。グラインドでレールを滑走する際の爽快感、ブーストダッシュによる一気の加速、ジャンプから着地までの浮遊感。これらが一体となった操作体験は「コントローラを握っているだけで気持ちが良い」と評され、多くのプレイヤーが中毒的に遊び続けました。単なる「移動」そのものをここまで楽しく表現した点は、当時の他作品にはない大きな特徴として好意的に受け止められています。
キャラクターの個性と魅力
個性的なキャラクターデザインも、「良かったところ」として多く挙げられます。ビートやガムといったシリーズおなじみのキャラに加え、クラッチやジャズといった新規キャラが登場し、プレイヤーそれぞれに「推し」が生まれました。「誰を操作するか」を選ぶ楽しみは、ゲーム進行そのものを彩り、単なるアクション体験以上の愛着をプレイヤーに与えました。衣装や仕草、口癖に至るまで強烈な個性が詰め込まれており、ゲームクリア後も「このキャラが好きだった」という記憶が残り続ける点は大きな魅力でした。
ストリートカルチャーを体感できる世界観
「街を自分の色に染め上げる」というコンセプトは、プレイヤーに強烈な満足感を与えました。壁や道路にグラフィティを描き、敵対勢力を押しのけ、自分たちのテリトリーを拡大していく体験は、まさにストリートカルチャーの疑似体験であり、当時の若者にとって新鮮で刺激的なものでした。プレイヤーの多くが「自由を体感できた」「支配からの解放を自分の手で掴んだ気分になれた」と語っており、単なるアクションを超えた感情的な満足を得ていたことが伺えます。
世界的なカルト的人気
日本ではXboxの普及率の低さからプレイヤー数自体は限られていましたが、海外では本作の独創性が高く評価されました。とくに欧米のプレイヤーは、グラフィティやヒップホップに親和性を持つ文化的背景から、本作を「カルチャーを体験できるゲーム」として熱狂的に支持しました。こうした海外での評価が後年逆輸入的に国内ファンにも伝わり、「実は名作だった」と再評価される流れを作ったのも、本作の良い点として挙げられます。
リプレイ性の高さ
一度クリアしても、キャラクターを変えて再挑戦したり、収集要素をコンプリートしたりと、リプレイ性の高さも好評でした。とくに「グラフィティソウル」集めや隠しキャラの加入条件など、やり込み要素はプレイヤーを何度も街へ駆り立てました。「遊べば遊ぶほど新しい発見がある」という感想は多く、プレイ時間を積み重ねるごとに楽しみが広がる点は、好意的に評価されています。
ビジュアルとサウンドの融合
最後に、ビジュアルと音楽が一体となって演出する「体験の総合芸術性」こそが、多くのプレイヤーにとって最大の「良かったところ」でした。映像と音が絶妙にシンクロし、街を駆け抜ける感覚そのものがライブパフォーマンスのように感じられる――その体験は他のゲームではなかなか得られないものです。この点については当時のゲーム誌でも「アートとエンタメの融合」と評されており、後年に至るまでファンが語り続ける理由のひとつとなっています。
■■■■ 悪かったところ
操作性のクセと難しさ
最も多くのプレイヤーが挙げた不満点は「操作性のクセの強さ」でした。インラインスケートをベースにした操作は爽快感がある一方で、細かなコントロールが難しく、思った通りにキャラクターを動かせないという声が少なくありませんでした。特にジャンプからの着地位置を調整するのがシビアで、初心者はステージの構造に翻弄されやすかったのです。「慣れるまでに挫折した」という感想もあり、カジュアル層にはハードルが高いと受け止められました。
カメラワークの不安定さ
3Dアクションゲームに共通する課題ですが、本作でも「カメラワークの不安定さ」がしばしば問題視されました。狭い通路や高低差のある場所では視点が急に切り替わり、プレイヤーが状況を見失って操作ミスを招くことが多々ありました。特に警察やライバルとの交戦中に視点が乱れると致命的で、「敵を避けようとして落下してしまう」「視点のせいで敵を見失う」といった不満が寄せられました。
難易度のバランス
「序盤は簡単なのに、後半から急に難しくなる」という難易度バランスへの指摘もありました。ライバルチームとの戦闘や、ハヤシ警部が戦車や巨大ロボットを投入してくる場面は演出としては派手ですが、プレイヤーによっては「理不尽に感じる」と捉えられました。また、隠しキャラ解放条件の一部がかなり厳しく設定されており、普通に遊んでいるだけでは気づきにくい点も「敷居が高い」と批判された要因のひとつでした。
ストーリー進行の分かりにくさ
自由度が高い反面、どこに行けばストーリーが進むのか分かりづらいという声もありました。広いマップを探索するのは魅力的ですが、次の目的地が明示されない場面では迷ってしまうプレイヤーが多く、「ただ街をさまよっているうちに疲れてしまった」という感想も見受けられました。特に当時はナビゲーション機能が簡素で、プレイヤーに自力での探索を強いる設計だったため、人によっては不親切に感じられたのです。
日本市場での不遇
ゲーム自体の完成度とは別に、日本市場では「Xboxの普及率が低かった」という点が本作にとって大きな逆風でした。遊んだ人からの評価は高くても、そもそも本体を持っている人が少なく、口コミで盛り上がりにくい状況にありました。そのため「良いゲームなのにプレイ人口が少なすぎる」という不満がファンの間で共有されることになります。プレイヤーからは「もしPlayStation 2で出ていたらもっと遊ばれていたのでは」という意見もあり、プラットフォームの選択が惜しまれる形となりました。
前作ファンの一部からの戸惑い
『ジェットセットラジオ』からの流れを期待していたプレイヤーの中には、「前作と雰囲気が変わりすぎて戸惑った」という感想もありました。前作のキャラは一部続投しているものの、設定やストーリーはリブート的に刷新されていたため、「思い入れがあったキャラが別人のように扱われている」と感じた人もいたのです。また、前作であった「自由に画像を取り込んでグラフィティを作れる機能」が削除されたことも残念がられました。これにより「遊びの幅が狭まった」とする声も一定数ありました。
一部プレイヤー層にとっての敷居の高さ
総じて「クセが強すぎる」というのが本作の弱点でもありました。操作の難しさ、ストーリーのわかりにくさ、敵の強さなどが組み合わさり、ライトゲーマーには厳しい内容となっていました。その結果、コアなゲーマーやカルチャー好きからは熱烈に支持されつつも、幅広い層への普及には至らなかったのです。
[game-6]■ 好きなキャラクター
シリーズの顔・ビート
シリーズを代表するキャラクターといえば、やはり「ビート」です。緑色のサングラスとヘッドフォンがトレードマークで、前作から続投している存在感のあるキャラ。リーダー格ではないものの、シリーズのパッケージや広告で中心的に扱われており、多くのプレイヤーにとって「ジェットセットラジオ=ビート」という印象が強いでしょう。性格的には自由奔放で、街を駆け抜けながら軽やかにグラフィティを残していく姿に憧れを抱いたファンは少なくありません。
華やかで大胆なガム
「ガム」はそのビジュアルでファンの心を掴んだキャラクターです。胸元を大胆に露出した衣装に、白と青緑を基調としたセクシーなコスチュームは、登場時から大きなインパクトを残しました。性格的には少し気の強い女性として描かれており、仲間の中でもひときわ存在感を放ちます。プレイヤーからは「見た目の派手さと操作時の爽快感がマッチして好き」という意見が多く、シリーズ全体を通じても人気上位に入るキャラでした。
コミカルな存在・ヨーヨー
序盤から操作できるキャラクター「ヨーヨー」は、黄緑の髪に水色のパーカーというカラフルなデザインで、口癖の「ヨゥ!」が印象的です。序盤でプレイヤーが最初に触れるキャラということもあり、多くの人に親しまれました。途中で物語上、仲間から外れる展開があるため、プレイヤーの記憶にも強く残る存在です。「最初に操作したキャラだから愛着がある」という声や、「少しドジっぽさが可愛い」という意見が寄せられるなど、親しみやすさが人気の理由になっています。
クールなガラム
「ガラム」は筋肉質で頼れる兄貴分的なキャラクター。黒いタンクトップに身を包み、仲間の中では大人びた雰囲気を漂わせています。ファンからは「力強いデザインで格好いい」「スピードキャラとは違う安定感がある」といった声が多く、特に男性プレイヤーから人気を集めました。見た目も含めて“硬派”なイメージを持つキャラクターで、チームのバランスを取る存在として好まれています。
新キャラ・クラッチの異彩
本作で新たに加わるキャラクター「クラッチ」は、赤い髪に赤いジャケットという強烈なビジュアルを持っています。加入条件も特殊で、グラフィティソウルを40個以上集めていると仲間になる代わりに、一度ソウルを奪って逃げるというイベントが発生します。このユニークな加入過程がファンの記憶に残り、「他のキャラとは違うインパクトがあった」と高評価されました。プレイヤーからは「クセのあるキャラだけど憎めない」「条件付き加入が燃える」といった感想も多く、異彩を放つ存在でした。
ミステリアスなジャズ
「ジャズ」は白髪に黒の上着、そして長い黄色のマフラーが特徴的なキャラクター。登場場所や加入条件が特定のチャプターに限られているため、仲間にするまでのハードルが高い存在でした。その分、仲間にしたときの喜びは大きく、プレイヤーからは「苦労して手に入れた分、特別な愛着がある」という声が寄せられています。クールで神秘的な雰囲気を持つデザインも人気の理由で、女性ファンから支持を集めました。
犬のポッツという癒し
忘れてはならないのがマスコット的存在の「ポッツ」です。前作から引き続き登場する犬で、条件を満たすと二足歩行で操作できるようになるというユニークなキャラ。シリアスな展開や激しいバトルが続く中で、ポッツを操作して遊ぶひとときは癒しの時間となり、多くのプレイヤーに愛されました。ファンからは「ポッツがいたから最後まで楽しめた」「意外と操作感が良くて笑った」といった声が寄せられ、隠れた人気キャラクターとなっています。
ライバルチームの魅力的なメンバー
プレイヤーキャラだけでなく、敵チームのメンバーにもファンは多いです。特に女性グループ「ラピッド99」は、その奇抜なファッションと挑発的な雰囲気から根強い人気を誇ります。また、ノイズタンクやポイズンジャムといったライバルたちも、倒した後にプレイアブルとして使える条件があるため、「敵だったキャラを操作する楽しみ」に惹かれるファンも少なくありませんでした。
[game-7]■ 中古市場での現状
ヤフオク!での取引状況
ヤフオク!では、『ジェット セット ラジオ フューチャー』の出品数は多くはありませんが、根強い需要が存在します。落札価格は状態に応じて幅があり、ディスクに傷やケースの擦れがあるものは 1,500円~2,000円前後で取引されることが多いです。一方で、比較的状態が良く説明書が完備されたものは 2,500円~3,500円で安定しています。特に出品者が「動作確認済み」「初期化済み」と明記している場合、ウォッチリストに多く登録され、終了間際に入札が集中する傾向があります。希少な未開封品が出品されるケースもごくまれにあり、その場合は 5,000円を超える即決価格で落札される例も見られます。
メルカリでの販売傾向
フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクに比べて出品数が安定しており、価格帯は 2,000円~3,000円が主流です。特に「ケースや説明書あり」「全体的に綺麗」といった状態の良い出品は、2,500円前後で短期間のうちに売れるケースが多く確認されています。逆にディスクに傷があるものや付属品の欠品が目立つものは、値下げ交渉を経て 1,800円前後で取引される傾向があります。人気の理由は「Xbox初期を代表する作品」というプレミア感で、コレクターや当時遊んでいたファンが購入者の中心層となっています。
Amazonマーケットプレイスでの相場
Amazonマーケットプレイスでは、価格帯がやや高めに設定される傾向があります。中古品は 3,000円~4,500円程度が中心で、特に「Amazon倉庫発送」や「プライム対応」といった利便性を備えた出品は、4,000円台でも売れている例があります。Amazonの場合、出品数が少ないタイミングでは価格が吊り上がることもあり、需要と供給のバランスによって値動きが激しくなるのが特徴です。
楽天市場での取り扱い
楽天市場では、ゲームショップや中古専門店が出品しており、価格帯は 3,000円~5,000円前後で推移しています。楽天はポイント還元を重視するユーザーが多いため、他より少し割高でも「ポイント利用で実質安く買える」という需要があります。また、在庫が安定していないため、「在庫なし」表示が長期間続くこともあり、タイミングによっては入手難易度が上がることもあります。
駿河屋での流通状況
中古ゲームの大手ショップ「駿河屋」でも取り扱いがあります。標準的な中古品で 2,500円~3,500円前後が相場で、状態が良いものはそれ以上になるケースも見られます。駿河屋は「買い取り価格」も公開しているため、需要が高い時期には査定額が上がり、供給が減った際に販売価格が跳ね上がることがあります。人気タイトルの一つとしてリストアップされることも多く、同店での取り扱いはコレクターにとって安定した購入先となっています。
コレクション需要と今後の展望
『ジェット セット ラジオ フューチャー』は Xbox 初期の名作としてカルト的な人気を誇るため、中古市場では「遊ぶため」だけでなく「コレクションするため」に購入する人が多いのが特徴です。そのため、状態の良い品や未開封品には今後もプレミアが付く可能性があります。また、シリーズの続編やリメイクへの期待が再燃するたびに中古価格が上昇する傾向もあり、ゲームファンの間では「値崩れしにくい安定銘柄」として認識されつつあります。
[game-8]
![【中古】[DC] ジェット セット ラジオ(JET SET RADIO) セガ (20000629)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1036/0/cg10360199.jpg?_ex=128x128)