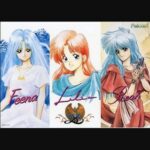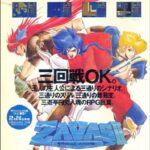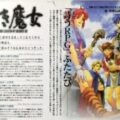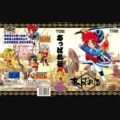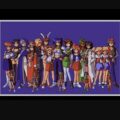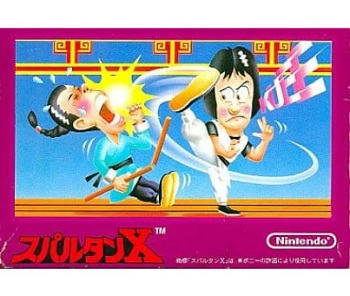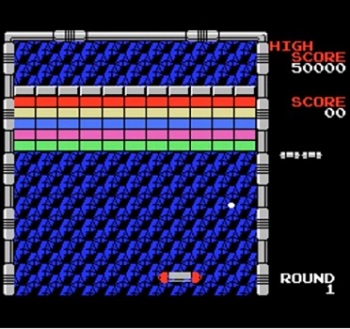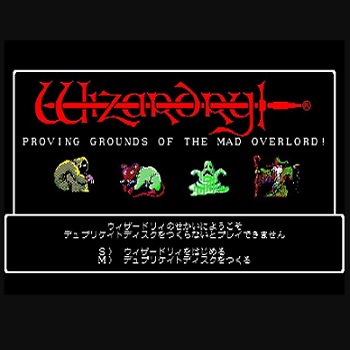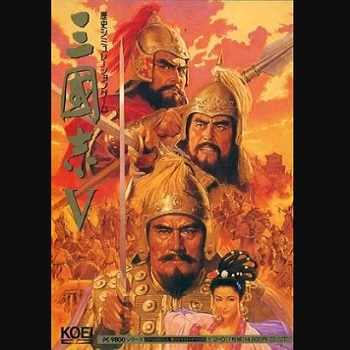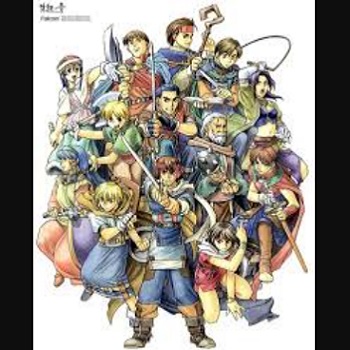
【発売】:日本ファルコム
【対応パソコン】:PC-9801、Windows
【発売日】:1996年5月24日
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
作品の基本情報とシリーズ内での立ち位置
『英雄伝説IV 朱紅い雫』は、日本ファルコムが手掛ける長寿RPGシリーズ「英雄伝説」の第4作にあたるタイトルであり、「白き魔女」「海の檻歌」と並んで〈ガガーブトリロジー〉と総称される三部作のひとつです。シリーズ全体で見ると「ドラゴンスレイヤー英雄伝説I・II」に続く“第2期”に位置付けられており、その中でも時間軸としては最も過去の出来事を描いた物語になっています。
発売時期と対応プラットフォーム
オリジナル版は1996年5月24日、PC-9801シリーズ向けに発売されました。当時としては5インチFD・3.5インチFD・CD-ROMと複数メディアで展開され、価格は12,800円(税込3%込み)という、ボリューム感のあるRPGらしい設定でした。 その後、1998年にはプレイステーション版、2000年にはWindows向けのリメイク版が登場し、2005年にはリメイク版をベースにしたPSP版も発売されるなど、長く遊ばれ続けている作品です。
舞台となる世界「エル・フィルディン」とガガーブ世界観
物語の舞台となるのは、2柱の神をめぐる因縁に支配された大地「エル・フィルディン」。ここは、巨大な地殻の裂け目「ガガーブ」によって他大陸と隔てられた世界であり、同じ三部作である『白き魔女』の舞台ティラスイールとは、ガガーブを挟んで対になる位置関係にあります。 人々を守護する正しき神バルドゥスと、破壊と変革を体現する邪神オクトゥム――この2柱の信仰がぶつかり合う宗教対立が、国家間の争いや人々の憎しみを生み、物語全体に重い影を落としています。ガガーブ三部作は作品ごとに主人公や舞台が異なりますが、世界の歴史や宗教観は互いにつながっており、『朱紅い雫』はその中でも神話の根っこに最も近い時代を描くエピソードだといえます。
兄妹アヴィンとアイメル、悲劇から始まる物語
本作の主人公は、孤児の少年アヴィン。彼は妹アイメルと共に、正神バルドゥスを祀る大聖堂カテドラールで育てられていました。しかしある日、大聖堂はオクトゥムを奉じる邪教徒たちの襲撃を受け、世界の均衡を保つとされるバルドゥスの神宝をめぐる争いに巻き込まれてしまいます。大混乱の中、最高導師エスペリウスは、兄妹にそれぞれ神宝「カベッサ」「クエルポ」を託し、命からがら逃がそうとしますが、やがて兄妹は追っ手から身を守るため互いの居場所すら知らぬまま別々に生きることを選ばざるを得なくなります。子どもにはあまりに過酷な別離の決断から、物語は静かに幕を開けます。やがて8年の歳月が流れ、17歳になったアヴィンは、自分を匿ってくれていた老賢者レミュラスの最期を看取ります。その際、レミュラスから「アイメルの消息を知る賢者ディナーケン」の存在を告げられたアヴィンは、幼なじみのマイルと共に妹を探す旅へと踏み出していきます。神々の対立が生む戦乱の気配と、ひとりの少年の“家族を取り戻す”という小さな願いが交差する、その導入部分だけでも本作が「個人的なドラマ」と「神話的スケール」の両方を併せ持つ作品であることが伝わってきます。
コマンドRPGとしての骨格と戦闘システムの特徴
ジャンルとしては、いわゆるコマンド選択式のRPGに分類されますが、本作はその中で戦術性の高い戦闘システムを取り入れている点が特徴的です。フィールドやダンジョンのマップがそのまま戦闘画面として利用され、敵と接触するとそこで戦闘が開始されるという構造になっています。戦闘は1キャラクターずつ行動順が回ってくる個別ターン制で、プレイヤーは「どこへ移動し、どの敵を射程に捉えて攻撃するか」をユニットごとに指定していきます。タクティカルRPGの要素を強く感じさせつつ、操作はあくまでコマンドRPGに近いという、当時としては珍しいスタイルです。また、攻撃や魔法を実行すると画面下部に専用の戦闘アニメーションが再生され、敵味方が派手に動くことで“見ていて楽しい戦闘”を演出しています。演出を重視しつつも、テンポを損ねないようアニメーション速度を変更したり、表示をオフにしたりできるオプションも用意されており、遊び手の好みに合わせてプレイフィールを調整できる設計になっています。
魔法システムと成長システムの概要
本作の魔法は、白魔法・黒魔法・精霊魔法という3系統に加え、キャラクターごとに固有の“特殊魔法”を備える構造になっています。いずれもMPを消費して使用する点はオーソドックスですが、黒魔法には「一度の詠唱で複数回分の効果を溜め込める効力」、精霊魔法には「精獣と呼ばれる召喚獣を呼び出して自動行動させる」など、それぞれ独自の個性が与えられており、プレイヤーはパーティ構成や戦略に応じてどの系統を伸ばすかを考える必要があります。成長システムも一工夫されており、キャラクターには一般的な“レベル”だけでなく、武術レベル・魔術レベルという2種類の熟練度が存在します。通常攻撃を繰り返せば武術レベルが、魔法を活用すれば魔術レベルが上昇し、それぞれに応じてステータスが伸びるという仕組みで、いわば『ザナドゥ』型の熟練度システムをRPG風にアレンジしたものといえるでしょう。
オープンシナリオと自由なパーティ編成
『朱紅い雫』PC-9801版の大きな特徴として挙げられるのが、「オープンシナリオ」と呼ばれる構造と、それを支える高い自由度です。本作では、各地の街に設けられた斡旋所で“仕事(クエスト)”を受注し、それを達成することで報酬や経験を得ていきます。メインストーリー自体は一本の柱として存在しますが、寄り道的な依頼やサブイベントが膨大に用意されており、それらをどの順番で、どこまでこなすかはプレイヤー次第です。 さらに、町々に散らばる仲間候補をスカウトして自由にパーティを編成できるシステムも採用されており、アヴィンと相棒マイル以外のメンバーを入れ替えながら、自分好みのチームで冒険を進められます。中には加入に契約金が必要なキャラクターや、特定のオープンシナリオで活躍する人物も存在し、「誰を連れていくか」が単なる好みだけでなく攻略にも関わってくるのが面白いところです。
PC-9801版とWindows版の位置づけの違い
同じ『朱紅い雫』でも、PC-9801版と2000年に発売されたWindowsリメイク版では、ゲームとしての性格が大きく異なります。PC-9801版は、膨大なオープンシナリオと自由なパーティメイク、高めの難易度を売りにした“自由度重視”のRPGでした。一方、Windows版ではシナリオを大幅に再構成し、イベント量やキャラクター描写を厚くする代わりに、パーティ編成や寄り道要素はかなり整理されています。 マップ構造や戦闘システムも『白き魔女』『海の檻歌』のWindows版に近いスタイルへと統一されており、とくにWindows版は“ドラマを味わう英雄伝説”としての完成度が高いと評価されることが多いです。どちらが優れているというより、「プレイヤーの選択の幅を楽しむPC-9801版」「物語の濃さを堪能するWindows版」というふうに、同じタイトルでも方向性の違う2つの体験が用意されている、と捉えると分かりやすいでしょう。
後のシリーズ作品への橋渡しとして
『朱紅い雫』のシステムや世界観は、その後の『英雄伝説 空の軌跡』をはじめとする“軌跡シリーズ”にもさまざまな形で受け継がれていきます。クエストをこなしながら各地を巡る構造や、宗教組織と謎めいた敵対勢力の対立、人と神(あるいは超越的存在)の関係に踏み込んだ物語など、後年の作品で洗練される要素の原型が本作にはすでに顔を出しています。 そうした意味で、『英雄伝説IV 朱紅い雫』は単独のRPGとして楽しめるだけでなく、「ファルコムRPGの変遷を語るうえで欠かせない転換点」としても重要な位置を占めるタイトルだといえるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
宗教対立と家族のドラマが絡み合う、シリーズでも屈指の重い物語
『英雄伝説IV 朱紅い雫』の一番の魅力としてまず挙げられるのは、「神々と宗教戦争」という大きなテーマと、「離れ離れになった兄妹の再会」という個人的なドラマが、同じ一本の線でつながっている点です。正神バルドゥスと邪神オクトゥムの対立は、世界規模の宗教対立として各地の紛争や迫害を生み出し、そのひずみの中で、主人公アヴィンと妹アイメルの運命が翻弄されます。プレイヤーは最初、ただ妹を探すだけの旅だと思って出発しますが、各地で起こる事件や人々の告白を通じて、自分が抱えている神宝の意味、宗教戦争の真相、そして自分自身の出自に向き合わされていきます。序盤はマイルやシャノンとの掛け合いが多く、比較的明るい雰囲気で旅を進められますが、物語が進むにつれて徐々に空気は重くなり、親しい人物の死や裏切り、信じていたものが揺らぐ展開が連続します。前作『白き魔女』が“旅情もの”に近いほのぼのとしたタッチだったのに対し、本作は「人と神の関係」「信仰がもたらす救いと悲劇」といったテーマを前面に押し出していて、シリーズの中でもとりわけシリアスで陰りのあるトーンが強い作品です。この重さが人を選ぶ一方、ストーリー重視のRPGが好きなプレイヤーには強烈な印象を残し、長年ファンの心に残り続けている大きな要因になっています。
「神話級のスケール」と「人間くさい会話」が同居する世界観
物語の背景となる世界「エル・フィルディン」は、ガガーブという巨大な断崖によって外界から隔てられた“神々の眠る地”とされており、その成り立ち自体が一種の神話として語られています。町や村に点在する教会、バルドゥス神殿とオクトゥムを奉じる邪教徒たちの地下礼拝所、かつて神々が降り立ったとされる遺跡など、マップの至るところに宗教的なモチーフが散りばめられており、どこを歩いても「この世界は神と人の歴史の延長線上にある」という雰囲気が強く感じられます。一方で、登場人物たちの会話は意外なほど人間くさく、アヴィンとマイルのたわいない掛け合いや、マイルを追いかけてくる少女シャノンの騒がしさ、盗賊団シャムシールの面々の軽妙な会話など、シリアスな世界観の中にも日常的なユーモアがしっかり盛り込まれています。神々の争いがもたらした悲劇を真正面から描きつつも、決して“暗いだけの世界”にはしていないバランス感覚が、本作の世界観の魅力と言えるでしょう。プレイヤーは、神話級の大きな物語の中にいるにもかかわらず、目の前にいる仲間たちの感情や小さな喜怒哀楽に共感しながら旅を続けられるのです。
PC-98版ならではの「オープンシナリオ」と圧倒的な自由度
とくにPC-9801オリジナル版で強く評価されているのが、「オープンシナリオ」と呼ばれるクエスト制の構造と、それに支えられた自由度の高さです。各地の町には“斡旋所”が存在し、そこで依頼(仕事)を請け負ってはこなしていく、というループがゲーム全体に組み込まれています。仕事の内容は行方不明者の捜索、盗賊退治、珍しいアイテムの収集、ダンジョンの攻略など多岐にわたり、その数は100件を超えるほどと言われるほどのボリュームがあります。 これらの仕事は、メインシナリオの進行度に応じて出現したり消滅したりし、どの依頼を優先するか、どのタイミングで一気に片づけるかはプレイヤー次第です。メインストーリーだけを追いかければ比較的短時間でクリアできる一方、オープンシナリオを丁寧にこなしていくと、世界の裏側や街の人々の事情、仲間たちの意外な過去など、表には見えない断片的なドラマが見えてきます。この「本筋から少し外れて寄り道をすると、世界が一段深く見えてくる」という感覚は、後の『空の軌跡』以降の「ブレイサークエスト」システムにも通じる、本作ならではの魅力と言えます。
仲間のスカウトとビルドを楽しめる、自由なパーティ編成
アヴィンと相棒のマイルを除く仲間キャラクターは、基本的に“スカウト制”になっており、各地の町や施設を訪れることで加入条件を満たしていきます。情報屋から「どこどこにこんな人物がいる」という噂話を聞いて会いに行ったり、特定のオープンシナリオをクリアすることで加入イベントが発生したりと、仲間集め自体がひとつの探索要素になっているのが面白いところです。中には、パーティインに契約金が必要なキャラクターや、特定の仕事を進めると真価を発揮するキャラも存在し、誰を連れて行くかを考えるだけでもひとつのゲームになっています。 さらに、本作では“キャラクターメイキング”が導入されており、ゲーム開始直後の質問への回答や選択によって、アヴィンの初期能力・成長傾向・習得魔法の系統・特殊魔法などが変化します。プレイのたびに異なるビルドを試せるので、「今回はガチガチの前衛型で物理寄り」「次は精神重視で黒魔法特化」といった遊び方が可能です。オート戦闘によるレベル上げ環境と相まって、周回プレイでいろいろな育成パターンを試す“やり込みRPG”としても楽しめる設計になっています。
タクティカルバトルと魔法システムが生む、じっくり味わう戦闘の面白さ
戦闘自体の魅力も、『朱紅い雫』の評価を語るうえで欠かせません。フィールドやダンジョンのマップ上で、そのまま敵味方が入り乱れて戦う「ダイレクト・コンバット・バトル」は、移動と攻撃射程の兼ね合いが重要なタクティカルバトルになっています。行動順は行動力に応じた個別ターン制で、素早いキャラほど行動回数が多く回ってくるため、「誰を先に動かして敵の進路を塞ぐか」「どの位置に退避させれば遠距離攻撃を安全に通せるか」といった盤面の読み合いが自然に生まれます。 魔法システムも個性が強く、白・黒・精霊の3系統に、それぞれ役割がはっきり分かれています。白魔法は回復や補助に優れ、フィールド上でも使用できるため、探索中の安定度を大きく高めてくれます。黒魔法は「効力」の概念によって単体に複数回叩き込んだり、複数の敵に一気にヒットさせたりできるため、使いどころを考える楽しさがあります。精霊魔法は精獣を召喚してオート戦闘させるスタイルで、召喚して放置するだけで魔術レベルが上がる一方、自分が動かないと経験値効率が落ちるなど、育成との兼ね合いを考えさせる設計です。終盤になると、黒魔法の高位スペルや強力な特殊魔法が解禁され、「物理で地道に削るか、MP管理をしながら魔法で一気に片づけるか」という選択が常に付きまといます。難易度はシリーズの中でも高めで、油断していると雑魚戦でも全滅しかねませんが、そのぶん戦術がハマったときの達成感は格別です。
BGM・ビジュアル演出が支える、切なくも美しい雰囲気
ファルコム作品といえば外せないのが音楽ですが、本作も例外ではありません。タイトル画面で流れる「朱紅い雫~memoria~」をはじめ、村や城下町、戦闘、ボス戦など、場面ごとに印象的な楽曲が多数用意されています。PC-98版ではFM音源による力強いサウンドが特徴で、金属的なベースラインと素朴なメロディが組み合わさった“いかにもPC-98らしい”音作りが、エル・フィルディンという世界の少し物悲しい空気感をよく表現しています。 さらに、本作はファルコムRPGで初めてMIDI音源に正式対応したタイトルでもあり、対応環境ではFM音源とはまた違った柔らかいサウンドで同じ曲を楽しめます。FM版のストレートな迫力を好むか、MIDI版の表現力の高さを好むかはプレイヤーの好み次第ですが、「同じ曲を2つの音色で聴き比べられる」という音楽的な楽しみ方ができるのも面白いところです。グラフィック面でも、戦闘中に画面下部に表示されるカットイン風の演出や、PC-98後期らしい繊細なドット絵のキャラクター立ち絵・背景が、物語の雰囲気を盛り上げています。後に登場するWindows版では、オープニングムービーや章間ビジュアルなどが追加され、よりドラマチックな演出へと強化されましたが、その源流はこのPC-98版の表現にあります。
Windows版・PSP版で変化した魅力と、遊び分けの楽しさ
『朱紅い雫』は、PC-9801版と後年のWindows版・PSP版でゲーム内容がかなり異なるという珍しいタイトルです。PC-98版は自由度重視で、100本以上に及ぶオープンシナリオや自由なパーティ編成が売りである一方、イベントシーンやキャラクターの掘り下げはやや淡く、“プレイヤーの想像に委ねる余地”が大きい作りでした。これに対してWindows版では、シナリオが四部構成に再編され、章間ビジュアルや追加イベントによって、アルチェムやラエル、ダグラスやルキアスといったサブキャラクターにも豊富なエピソードが与えられています。 その結果、プレイの自由度は大きく削られたものの、物語の密度やキャラクター描写の濃さは飛躍的に高まり、「読むRPG」としての完成度は非常に高いと評価されています。PSP版『The Legend of Heroes IV: A Tear of Vermillion』は、このWindows版をベースに携帯機向けにチューニングされたもので、どこでもセーブできる利便性や遊びやすさが加わり、現代の環境でも比較的触れやすいバージョンになっています。 つまり、『朱紅い雫』というひとつの作品の中に、「高難度で自由度の高いPC-98版」と「シナリオ重視で遊びやすいリメイク版」という二つの顔が存在しており、どちらを選ぶか、あるいは両方を遊び比べるかで印象が大きく変わるのも、この作品ならではの楽しみ方と言えるでしょう。
“尖っているからこそ忘れがたい”中期ファルコムRPGの代表格
総じて、『英雄伝説IV 朱紅い雫』は、完成されたバランスの名作というより、「挑戦的なアイデアが詰め込まれた実験作」に近い立ち位置のゲームです。戦闘は重く、難易度も高めで、人によってはテンポの悪さを感じるかもしれません。それでも、高度なタクティカル性や練り込まれた魔法システム、プレイヤーの選択で大きく変わる育成要素、そして宗教と家族のドラマが交錯する重厚な物語など、一つひとつの要素はどれも強い個性を放っています。後の『軌跡シリーズ』で洗練されていく要素の“原石”がここに詰まっていると考えると、シリーズ史的な意味でも非常に興味深い作品です。粗削りな部分を含めて「こういう時期のファルコムが好きだ」と語るファンも多く、だからこそ今でもPC-98版のデータを残そうとする有志のサイトや、リメイク版のプレイ感想が途切れずネット上に残り続けているのでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
まず押さえたい全体方針――「無理をしない」「稼ぎをサボらない」
『英雄伝説IV 朱紅い雫』は、当時のファルコム作品の中でも難度が高めに調整されているRPGです。序盤から“ちょっと寄り道しただけで全滅”ということも珍しくなく、「行ける場所=行っていい場所」ではないのがポイントになります。攻略の基本はとにかく「無理をしないこと」と「稼ぎをサボらないこと」。敵の強さが明らかにおかしいエリアに踏み込んでしまったら素直に退却し、一度戻って装備やレベルを整え直す勇気が重要です。また、本作は換金アイテムを売ってお金を得る方式かつ、装備やテント、契約料などの出費が非常にかさむ構成なので、こまめな戦闘とオープンシナリオの消化による資金稼ぎが不可欠です。メインシナリオを一直線に追いかけようとするとすぐ行き詰まるため、「メインを一歩進めたら、1〜2件の仕事を片付けてレベルとお金を整える」というサイクルを意識すると安定します。
キャラメイクのコツ――アヴィンのビルド方針を最初に決める
ゲーム開始直後に行われる質問イベントは、アヴィンの能力値や成長傾向、習得する魔法系統、特殊魔法などに影響を与える“キャラメイク”になっています。ここで「どのタイプのアヴィンにするか」をある程度イメージしておくと、後の育成がぐっと楽になります。初回プレイで安定しやすいのは、筋力と技能を高めた前衛寄りビルドに白魔法または精霊魔法を組み合わせるタイプ。物理攻撃で着実に削りつつ、白魔法で回復を担える構成にしておくと、序盤の長いダンジョンも落ち着いて攻略できます。逆に、魔法特化ビルドは中盤以降の伸びが非常に優秀な反面、序盤の生存難度が一気に上がります。黒魔法特化のアヴィンは、強力な範囲魔法を覚えた途端に世界が変わるほどの強さを発揮しますが、そこに到達するまでが「紙装甲でMPも少ない」状態になりやすいので、初見で選ぶ場合はこまめなセーブと慎重な立ち回りが必須です。いずれにしても、技能(物理命中・回避)と精神(魔法命中・抵抗)を意識して伸ばしていくと、終盤の命中率・生存率が大きく変わります。
序盤攻略:ウルト村〜フィルディン間の“死の街道”を乗り切る
多くのプレイヤーが最初につまずくポイントが、ウルト村からフィルディンへ向かう街道です。脇道に入ると斥候鳥の群れなど明らかに場違いな強敵が出現し、準備不足のまま突っ込むと一瞬で壊滅させられます。ここでのコツは「寄り道をしすぎない」「退却を惜しまない」の二点です。街道マップは一画面ごとの切り替え式になっているので、敵の気配を感じたら画面端へ移動して退却コマンドを使うクセを付けておくと、致命的な全滅を防ぎやすくなります。また、ウルト村周辺である程度レベルを上げ、初期装備から1段階上の武器防具へ更新しておきましょう。店では初期からかなり先のエリアで使うような高性能装備まで並んでいますが、序盤から無理して揃える必要はありません。まずは「命中率と防御力をひとつ上のランクに上げる」程度の買い物に抑え、資金をテント代や回復アイテムに回すのが堅実です。
レベル上げと資金稼ぎ――オート戦闘を使った“ながら稼ぎ”
本作は経験値・お金ともに要求量が多く、まともにやっているとかなりの時間を“戦闘と往復”に費やすことになります。そこで活躍するのがオート戦闘機能です。各キャラクターの行動方針を設定しておけば、あとは敵と接触するだけで自動的に戦ってくれるため、レベル上げや熟練度稼ぎが格段に楽になります。前衛には高命中武器を持たせ、後衛には白魔法や遠距離武器を優先して装備すると、オート戦闘でも安定しやすくなります。黒魔法育成を兼ねたい場合は、雑魚敵の多いエリアで黒魔法優先行動に設定し、“トドメを魔法で刺す”状況を意識的に作ると効率が上がります。また、毒状態を利用してフィールド上でちょくちょく回復魔法を使うと、白魔法の熟練度がみるみる上昇していくため、後半の高位回復魔法を早めに習得したい人にはおすすめです。資金面では、敵がドロップする換金アイテムをしっかり回収し、無駄な買い物を控えるのが基本。仲間の契約料やテントの購入費用はかなり重いので、「本当に今必要な仲間・装備かどうか」を一度立ち止まって考えるクセをつけると、金欠で詰まりにくくなります。
魔法系統別の運用とおすすめの役割分担
白魔法は「パーティの保険」であり、最低一人は安定して扱えるキャラクターをパーティに入れておきたい系統です。フィールドでの回復手段としても非常に重要なので、アヴィンかマイル、あるいは他の白魔法使い候補に集中して習得させ、常時パーティインさせると攻略が安定します。黒魔法は“攻撃の切り札”であり、ボス戦や耐久力の高い敵集団を相手にするときに真価を発揮します。効力を溜めて複数回分まとめて叩き込む、範囲攻撃で雑魚を一掃するなど、状況に応じて使い分けると良いでしょう。ただし、消費MPが重くMP回復手段も限られているため、長期戦では「ここぞ」という場面に絞って使うのがコツです。精霊魔法は、召喚した精獣が自動で動いてくれるため、地形が入り組んだダンジョンなどで“邪魔にならない位置に出す”ことを意識する必要があります。風属性の精獣は命中・回避に優れ、終盤まで一線級で戦えることが多いので、誰か一人は風系精霊を担当させておくと心強いです。全体としては、白1〜2人・黒1人・精霊1人程度のバランスを意識しつつ、パーティごとに役割が偏りすぎないよう調整するのが理想的です。
中盤以降のダンジョン攻略――マッピングと“撤退ライン”の見極め
ゲームが進むにつれて、ダンジョンは分岐の多い迷路型の構造が増えていきます。マップパターンの使い回しも多いため、「さっきと同じ形の部屋を何度も通っている気がする」と感じる場面も多いでしょう。ここで重要なのが、自分なりの簡易マッピングを行うことと、「どこまで進んだら帰るか」という撤退ラインを予め決めておくことです。紙やメモ帳を用意し、部屋の形と出入口の位置だけでもざっくり書き残しておくと、ループ構造の把握や宝箱の取り逃し防止に役立ちます。また、MPとテントの残数を見ながら、「MP残量が半分を切ったら一度戻る」「テントが0になったらそれ以上奥へ進まない」といった、目安を決めておくと無茶な深追いをせずに済みます。中盤以降の洞窟には、明らかに周囲の敵より強力な固定エンカウント(部屋に入ると必ず戦闘になる敵)が配置されていることが多く、無策で突入すると一方的に蹂躙されることもしばしばですが、その先には強力な装備やレアアイテムが眠っていることも多いので、十分に鍛えてから再挑戦する“チャレンジダンジョン”として捉えると、攻略のモチベーションが上がります。
ボス戦・強敵戦の考え方――バフ・デバフと行動順操作を意識する
ボス戦では、殴り合いの火力勝負に持ち込むよりも、バフ・デバフや行動順のコントロールを意識した方が安定します。技能や精神を強化する補助魔法で味方の命中率と回避率を底上げし、敵には命中率低下や行動阻害系の魔法を重ねることで、被ダメージを大きく減らせます。特殊魔法の中には、敵の動きを止める、クリティカルヒットを確定させる、魔法を無効化して弱体化させるといった“切り札級”のものも多く、これらを上手く活用できるかどうかで難易度がガラリと変わります。前衛は常に“壁役”と“攻撃役”を明確に分け、壁役は敵の進路を塞ぎつつ攻撃を引き受け、攻撃役は側面や背後から確実にダメージを重ねる配置を心がけましょう。精霊魔法を使う場合は、精獣を敵の後衛付近に召喚して撹乱役を担わせると、敵の陣形を崩しやすくなります。ボスのHPが高く長期戦になりがちな本作では、「いかに被害を抑えながら安全に削り続けるか」が何より重要です。そのため、黒魔法の大技を連発して一気に押し切るだけでなく、MP切れを見越した持久戦プランを同時に用意しておくと、詰み状況に陥りにくくなります。
便利な小ネタ・裏技的テクニック
有名なテクニックとして、アヴィンの移動速度を上げる“裏技”がよく知られています。これを活用するとフィールド移動と稼ぎ作業の効率が一気に上がり、オープンシナリオの消化もかなり快適になります。また、オート戦闘と方向キー固定を組み合わせた簡易“放置レベリング”も、長時間の稼ぎプレイには便利です。敵の強さと自軍の安定度が釣り合っているエリアを選び、壁に向かって歩かせ続けながらオート戦闘をONにしておくことで、ある程度まで自動的に熟練度と資金を稼ぐことができます。もちろん、やりすぎるとゲームバランスが大きく崩れてしまうので、「どうしても勝てないボスに詰まったときの救済策」くらいに留めておくと、程よい歯ごたえを残しつつ楽しめるでしょう。
周回プレイでの楽しみ方――ビルドと編成を変えて“別のゲーム”に
一度クリアしたあとも、『朱紅い雫』は周回プレイとの相性が非常に良いタイトルです。アヴィンのビルドをガラリと変えたり、あえて特定の仲間だけを使う縛りプレイをしたり、オープンシナリオをどこまで消化するかの方針を変えてみたりすると、同じ物語でも体感難度や遊び方がまったく違って見えてきます。たとえば、1周目は白魔法もこなす前衛寄りアヴィンで安全重視、2周目は黒魔法特化で「魔法火力で押し切る」スタイルにしてみる、といった遊び方をすると、序盤〜中盤の印象が大きく変わるのを実感できるはずです。また、「今回はこのキャラを必ずパーティに入れる」という自分ルールを決めると、オープンシナリオでの会話や台詞の印象も変化し、キャラクターの新たな一面に気づけるでしょう。自由度の高さゆえに、“遊び方を考えることそのもの”が攻略の一部になっている――それが『朱紅い雫』の攻略面での最大の魅力と言っても過言ではありません。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーが受けた第一印象
『英雄伝説IV 朱紅い雫』がPC-9801向けに登場した当時、プレイヤーのあいだでまず話題になったのは「前作とはガラッと雰囲気が変わった」という点でした。『白き魔女』は、旅芸人一座と共に巡礼の旅を続けながら、人々との出会いと別れを描く“旅情RPG”として受け止められていましたが、『朱紅い雫』は序盤こそコミカルな場面もありつつ、早い段階から宗教戦争と神々の対立という重いテーマが顔を出します。そのため、当時のPCゲーム誌やユーザーのレビューでは「明るいロードムービー風だった前作に比べて、一気にシリアス路線に振れた」というコメントが目立ちました。 さらに、戦闘システムも自動戦闘主体からタクティカル寄りの個別ターン制へと大きく変化し、難易度もぐっと上がったことから、「じっくり腰を据えて遊ぶ骨太RPG」という印象を持つプレイヤーが多かったようです。一方で、気軽さやテンポを重視していたファンからは「前作より取っつきにくい」という声も挙がり、発売当初から賛否のはっきりした作品だったと言えます。
ストーリーへの評価――重くも印象に残る宗教ドラマ
物語面に関しては、「重いけれど忘れ難い」といったニュアンスの評価がよく語られます。神々の名のもとに行われる信徒同士の争いや、信仰が人々にもたらす救いと同時に、残酷な差別や迫害を引き起こす様子が丁寧に描かれており、その中でアヴィンが“妹を探す”という個人的な目的と“世界全体の行く末”との間で揺れ動いていく様子は、多くのプレイヤーの記憶に強く刻まれました。特に、中盤以降に訪れるいくつかの悲劇的なイベントは、当時のレビューや回顧記事でもしばしば具体的なシーン名と共に言及されるほどインパクトが大きく、「英伝シリーズでも屈指の鬱展開」として語られることもあります。 その一方で、「救いがまったくないわけではない」という点も好意的に見られており、過酷な運命の中でも必死に足掻くアヴィンや仲間たちの姿勢、結末に向けて少しずつ見えてくる希望の光が、“ただ暗いだけではないドラマ”として支持されています。前作をプレイしていると、世界観のつながりや時代の違いに思いを馳せられる仕掛けが随所にあり、その点もシリーズファンから高く評価されたポイントです。
システム面への評価――自由度とストレス要素の紙一重
ゲームシステムについての感想は、まさに“諸刃の剣”という表現がふさわしい内容になっています。オープンシナリオや自由なパーティ編成、熟練度ベースの成長システムなど、「遊び方を自分で組み立てる」楽しさを評価する声は非常に多く、「当時としては破格の自由度を持ったRPG」として好意的に語られます。 一方で、その自由度を支えるために難易度や稼ぎ前提のバランスが厳しくなっていることから、「作業感がきつい」「初見では進むべき場所が分かりにくい」といった不満も少なくありません。特に、テントが高価でフィールドセーブしづらい点、雑魚戦でも油断すると全滅しかねない戦闘バランス、マップ使い回しが多く単調に感じる街道・ダンジョン構造は、当時から現在に至るまで“問題点”として繰り返し挙げられています。 そのため、感想を読み比べると「ガッツリやり込みたい派にはたまらないが、ライト層には敷居が高い」という評価に落ち着くことが多く、“人を選ぶ名作”というポジションが定着していると言えるでしょう。
グラフィックとサウンドへの評価――PC-98末期らしい味わい
ビジュアル・サウンド面は、総じて好意的な印象が多数を占めます。PC-98後期の作品らしく、解像度こそ現代基準では控えめながら、キャラクターの立ち絵や背景グラフィックには細やかなドットワークが光り、戦闘時のカットイン風アニメーションも「派手すぎず、地味すぎずちょうどいい」と評されることが多いです。 また、音楽面ではファルコムサウンドチームによる楽曲が高く評価されており、タイトルテーマ「朱紅い雫~memoria~」や町・ダンジョン・ボス戦のBGMは、シリーズの中でも印象に残る楽曲として名前が挙がることもしばしばです。特に、本作がファルコムRPGとして初めてMIDI音源に正式対応したタイトルであることから、「FM音源とMIDI音源で雰囲気の違いを楽しめる」「自分の好きな音源でプレイできるのが嬉しい」といった感想も多く見られます。 グラフィックそのものよりも、音楽と合わせて作り出される“切なく物悲しい世界の空気”に惹かれたプレイヤーが多かったようで、「ストーリーの重さとサウンドの相性が抜群」という評価は、今でもしばしば語られています。
PC-98版とリメイク版(Windows・PSP)で分かれる評価
『朱紅い雫』は、プラットフォームによってゲーム内容がかなり違うこともあり、どのバージョンを基準に語るかで感想が分かれる珍しい作品です。PC-98版に馴染みのあるプレイヤーは、オープンシナリオの膨大さや高難度バランス、キャラメイクの奥深さを「当時のPC-RPGならではの醍醐味」として肯定的に語る一方、「今から遊ぶにはさすがに不親切」「マップ構造や移動の面倒さがきつい」といった率直な意見も残しています。 これに対し、Windows版やPSP版から入ったプレイヤーは、シナリオの再構成やイベント追加によってキャラクター描写が濃くなった点、どこでもセーブやインターフェースの改善によって遊びやすくなった点を高く評価する傾向にあります。一方で、パーティ自由編成やオープンシナリオが大きく削られたことで、「自由度という意味では別作品」「PC-98版とは別物として楽しむべき」という意見も根強く、シナリオ重視派とシステム重視派で好みがくっきり分かれる形になっています。 いずれにせよ、「どのバージョンも一長一短で、それぞれに良さがある」という点では共通認識が形成されており、シリーズ全体を追っているファンほど“遊び比べ”を推奨することが多いのが特徴的です。
難易度とゲームバランスへの賛否――“歯ごたえのある良作”か“理不尽ゲー”か
本作を語るうえで避けて通れないのが、難易度やゲームバランスに関する感想です。強めの敵が序盤から登場し、レベル上げにも資金稼ぎにも時間がかかる構成のため、「しっかり準備を整えて挑むタイプのRPGが好きな人」にとっては非常にやりごたえのある作品として受け止められています。オート戦闘や裏技を駆使してじっくりキャラを鍛え、強敵にリベンジを繰り返すプレイスタイルがハマった層からは、「最近のRPGにはない骨太さ」「苦労して倒したときの達成感が大きい」といった好意的な評価が多く見られます。 一方で、遊び始めてすぐに強敵との遭遇や金欠に悩まされるため、「序盤で心が折れた」「中盤以降のダンジョンが長すぎて投げてしまった」といった声も少なくありません。特に、フィールドセーブに高価なテントが必要な仕様や、マップの使い回しに起因する道中の冗長さは、「自由度の高さと引き換えにプレイヤーへの負担が大きすぎる」と指摘されることが多いポイントです。 こうした事情から、「高難度RPGが好きかどうか」で評価が真っ二つに割れる典型的なタイトルとなっており、現代のレビューサイトやブログでも、その点を前置きしたうえで紹介されるケースがよく見られます。
現在の評価――“ガガーブで一番好き”と語るファンも多い
発売から年月を重ねた現在、『朱紅い雫』は“知る人ぞ知るガガーブの問題作”であると同時に、「ガガーブ三部作の中で一番好き」と挙げるファンも多いタイトルになっています。完成度が高く万人向けと言われやすいのは『白き魔女』ですが、「ストーリーの重さや宗教テーマの深さ」「ビルドやオープンシナリオの自由度」といった点で、本作を推す声は根強く、ネット上の回顧記事や個人レビューでも「粗いけど忘れられない」「一番印象に残っているのは朱紅い雫」というコメントが散見されます。 また、『空の軌跡』以降の“軌跡シリーズ”からファルコム作品に触れた新しい世代のプレイヤーが、シリーズのルーツを辿る中で『朱紅い雫』に行き着き、「システムや演出に軌跡の原型が見えて面白い」「あの頃のファルコムの挑戦精神を感じる」といった感想を寄せるケースも増えています。レトロゲームとしての入手ハードルは決して低くありませんが、Windows版やPSP版の存在もあって“過去の名作を掘り起こす”文脈で語られることが増え、シリーズ全体の歴史の中で、独自の存在感を放つ作品として再評価が進んでいると言えるでしょう。
シリーズ全体の中での位置づけと、ファンの総評
総じて、シリーズファンの間での『朱紅い雫』の評価を一言でまとめるなら、「粗削りだが、シリーズの転換点となった意欲作」という表現がしっくりきます。宗教対立と神々の因縁という重いテーマ設定、オープンシナリオや自由なパーティ編成といったシステム面での挑戦は、後の『空の軌跡』以降の作品に大きな影響を与えており、その意味で“現在の英雄伝説をかたちづくった原点の一つ”として語られることが多いです。 他方で、遊びやすさやバランスという観点から見ると、必ずしも万人向けではなく、「今から遊ぶならある程度の心構えが必要」「不便さも味として楽しめるかどうかが分かれ目」といった但し書きが必ずと言っていいほど付いて回ります。その結果、「好きな人はとことん好き」「合わない人にはまったく合わない」という極端な評価になりやすく、それこそが本作の個性であり魅力でもあります。シリーズの歴史を俯瞰して見たとき、『朱紅い雫』は“完成された傑作”というより、“後の名作へと続く橋のような作品”であり、その橋の上でしか味わえない独特の体験が、多くのプレイヤーの記憶に強く残り続けているのです。
■■■■ 良かったところ
物語の重さと「家族」を軸にしたドラマが心に残る
本作の長所として真っ先に挙げられるのが、「神々の争い」「宗教対立」という壮大なテーマと、「離れ離れになった兄妹が再び互いを探し求める」というごく個人的なドラマがうまく噛み合っている点です。世界規模の戦乱や教義の対立といったスケールの大きな出来事の中心に、アヴィンとアイメルというひと組の兄妹の物語が据えられているため、プレイヤーは常に“世界の命運”と“ひとりの少年の願い”の両方を同時に感じながら物語を追っていくことになります。しかも本作は、単なる勧善懲悪に陥らないよう丁寧に作られており、正神・邪神の二元論だけで割り切れない灰色の領域が随所に描かれます。信仰ゆえに非情な決断を迫られてしまう人々、神に祈りながらも現実の苦しみから逃れられない庶民、理想と現実の間で揺れる指導者たち……といった、さまざまな立場の人間模様が重なり、物語はどんどん立体的な厚みを増していきます。そこへ、アヴィン自身の出自や、妹に託された運命が絡んでくることで、物語終盤にはかなり感情を揺さぶられる展開が続きます。単純なハッピーエンドではありませんが、「ここまで描いたからこそ、この結末で良かったのかもしれない」と思わせてくれる着地を見せてくれるのは、本作ならではの“良さ”と言えるでしょう。
自由度の高さが生む「自分だけの冒険」の感覚
PC-98版の『朱紅い雫』を語るうえで欠かせないのが、オープンシナリオと自由なパーティ編成がもたらす“遊びの幅”です。各地の斡旋所で仕事を受け、どの依頼から片付けていくか、どのタイミングでメインを進めるかを自分の判断で決めていく構造は、今の視点で見てもかなり野心的な作りです。同じ章立てのシナリオでも、あるプレイヤーは序盤からオープンシナリオを可能な限りこなしてから先へ進み、別のプレイヤーはメインを優先しつつ、気になった依頼だけを拾っていく……といった具合に、進行ルートが自然と人それぞれ変わります。その結果、「自分はこのタイミングであの事件に遭遇した」「自分のパーティではこのキャラが大活躍した」といった体験の差が生まれ、“他人のプレイ日記を読むのも楽しいゲーム”になっているのが本作の良いところです。依頼の内容も、単なるお使いにとどまらず、盗賊団の連続イベントや、仲間キャラの背景に関わるものなど、世界観の理解を深めてくれるものが多く、寄り道をするほどエル・フィルディンという世界が立体的に見えてくる構造も魅力的です。
キャラクターメイキング+熟練度システムの奥深さ
アヴィンの能力や成長方針を決めるキャラメイク要素と、武術レベル・魔術レベルという熟練度システムの組み合わせも、プレイヤーから高く評価されているポイントです。ゲーム開始時の選択肢によって、前衛寄りの“殴ってなんぼ”なアヴィンにも、黒魔法で敵を焼き払う魔術師アヴィンにもなり得るため、プレイスタイルに合わせた主人公像を描けます。そのうえで、戦闘中の行動内容によって武術レベル・魔術レベルが個別に上がっていくため、「今回は物理多めで筋肉ゴリゴリに育てよう」「次は魔法偏重でガラスの大砲にしてみよう」といった遊び分けが周回ごとに楽しめます。称号システムでステータスを任意に成長させられる点も、“自分でビルドを組み立てていく感覚”を強めており、攻略サイトを見ずに試行錯誤しているだけでも「この配分は失敗だったから次の周回は変えてみよう」と、自然と研究したくなる奥深さがあります。育成の自由度が高いとゲームバランスが崩れがちですが、本作は敵の強さもそれに見合うように設定されているため、「工夫しないと勝てないが、工夫すればきちんと応えてくれる」気持ちの良い手応えを感じられるのも良い点です。
タクティカルな戦闘がもたらす“考える楽しさ”
ダイレクト・コンバット・バトルと呼ばれる戦闘システムも、“考えて動かすのが好きなプレイヤー”にとっては大きな長所です。行動力の高いキャラほど行動回数が増え、移動と攻撃射程、前衛・後衛の位置取り、精霊召喚の配置などを常に意識する必要があるため、単に攻撃コマンドを連打するだけでは済みません。敵のAIもただ突っ込んでくるだけでなく、HPが減ると逃走を試みたり、射程の長い攻撃役を狙ってきたりと、それなりにいやらしい動きをしてくるため、「どうやって敵の行動を制限するか」「誰を囮にして誰を守るか」といった作戦を練る楽しさがあります。特殊魔法やバフ・デバフを駆使してこちらに有利な盤面を作り、少しずつ形勢を傾けていく過程は、戦略SLGやタクティカルRPGが好きな人ほど刺さるポイントでしょう。戦闘アニメーションも、テンポと演出のバランスが程よく、オプションで速度を変えたりオフにしたりできる柔軟さも含めて、“遊び手に委ねる”姿勢が感じられるのは本作の良いところです。
音楽・グラフィックが醸し出す独特の雰囲気
ファルコムらしいクオリティの高いBGMと、PC-98末期らしい繊細なドット絵は、本作の魅力を語るうえで外せません。タイトルの「朱紅い雫~memoria~」をはじめ、各地の町やダンジョン、ボス戦に至るまで、どの曲も耳に残るフレーズが多く、プレイから年月が経ってもメロディを口ずさめるという人も少なくありません。FM音源によるパワフルなサウンドと、MIDI音源による表現力豊かなアレンジを聴き比べられる点も、音楽好きなプレイヤーには大きな魅力となっています。グラフィック面では、キャラクターの立ち絵や背景美術が、当時のPC-98作品の中でもかなり丁寧に描き込まれており、特に大聖堂カテドラールや神殿関連のマップは“宗教都市”の荘厳さを巧みに表現しています。戦闘時のカットインや魔法エフェクトも、マシンパワーが限られた環境で工夫を凝らした表現になっており、ドット絵ならではの想像力を刺激する“味”が感じられるのは、今なお本作を評価する大きな理由になっています。
PC-98版とリメイク版、それぞれに際立つ長所
同じタイトルでありながら、PC-98版とWindows/PSP版で性格がかなり違うおかげで、「どのバージョンにも明確な良さがある」というのも『朱紅い雫』のユニークなところです。PC-98版の良さは何といっても圧倒的な自由度と、“当時のPC-RPGならでは”の骨太さ。オープンシナリオの量、ビルドの幅、やり込み甲斐のある難易度は、自由に自分の遊び方を見つけるのが好きなプレイヤーにとって極めて魅力的です。一方、Windows版・PSP版はシナリオの再構成やイベント追加によって、キャラクター描写や物語の流れが格段に分かりやすく、感情移入もしやすくなっています。システム周りも遊びやすい方向に整理されているため、「ストーリーをしっかり味わいたい」「今の感覚で無理なく遊びたい」という人にはこちらの方が向いています。つまり、“同じ物語の別解釈”を2種類用意してくれているようなもので、片方を遊んでからもう片方に触れると、「ああ、ここはこう変えたんだ」「このキャラはこっちのバージョンの方が掘り下げが厚い」といった比較ができ、それ自体がファンにとっては大きな楽しみになっています。
シリーズ全体を見渡したときの“転換点”としての良さ
『朱紅い雫』は、単体のRPGとしての魅力に加えて、「英雄伝説」シリーズ全体の流れを考えたときの“ターニングポイント”としても良い意味で特別な作品です。クエスト制や自由なパーティ編成、宗教組織を軸にした重厚な世界観など、後の『空の軌跡』以降で花開く要素の多くがここで試験的に導入されており、“現在の英雄伝説”への橋渡しをしたタイトルと言っても過言ではありません。ストーリーやシステムの一部に粗さが見られるのも事実ですが、それでも「ここから“軌跡”への流れが生まれたのだ」と考えると、その実験性そのものが作品の魅力として感じられてきます。シリーズの歴史を辿る楽しみを提供してくれるという意味で、『朱紅い雫』はファルコムファンにとって“押さえておきたい1本”であり、だからこそ今なお多くのプレイヤーが「多少の不便さはあるけれど、それを補って余りある魅力がある」と語り継いでいるのです。
“尖り”を含めて愛される、記憶に残るRPGであること
総合的に見れば、本作の良かったところは「丸く収まっていない」点にこそ集約されているのかもしれません。遊びやすさ一辺倒ではなく、ときに不親切とも言える高いハードルを用意しながら、それを乗り越えた先でしか味わえない達成感や物語体験をしっかり用意している――その姿勢が、後年まで強い印象を残しています。完成度の高い“整った名作”ではなく、尖った要素がたくさん詰まった“印象深い問題児”として愛されていることこそが、『英雄伝説IV 朱紅い雫』に対して多くのプレイヤーが抱く、最大の褒め言葉と言えるでしょう。
■■■■ 悪かったところ
序盤からプレイヤーの心を折りかねないシビアな難易度
本作の大きな欠点としてまず挙げられるのが、「最初からかなり手加減なしの難易度」であるという点です。とくにウルト村からフィルディンへと向かう序盤の街道は、多くのプレイヤーにとっていきなりの“死地”になりがちな場所で、脇道に一歩足を踏み入れただけで斥候鳥の群れに袋叩きにされる、という経験をした人は少なくないでしょう。ここでの敗北は「この世界は危険だ」ということを教える意味でもあるのですが、RPGに慣れていない人にとっては理不尽な初見殺しに感じられやすく、「なんとなく歩いていたら一瞬で全滅した」「どこが正規ルートなのか分からずに何度もやられた」といったストレスになりがちです。さらに、戦闘そのものも敵の攻撃力・命中率が総じて高く、油断して先頭を歩かせているキャラが集中攻撃を受けて即戦闘不能、というパターンも多発します。しっかり準備して慎重に進むプレイスタイルならやり応えとして楽しめますが、「ストーリーを味わうために手軽に遊びたい」という層にはかなり厳しい難度で、ここで脱落してしまうプレイヤーが出てしまうのは、やはりマイナス点と言わざるをえません。
テント必須のセーブ仕様と利便性の低さ
フィールドでのセーブが高価なテントに依存しているシステムも、多くのプレイヤーから不評を買った部分です。宿屋や特定のポイントで行う通常セーブに加えて、“一度だけ使える中断セーブ”が用意されてはいるものの、長いダンジョンや街道を進む際にはどうしてもフィールドセーブに頼りたくなります。しかし、そのたびに200ロゼという決して軽くない金額を支払わなければならないため、「セーブを節約したい」という心理が働き、結果として慎重なプレイを強制されます。家族や兄弟と一本のデータを共有して遊ぶような環境では、「自分だけ頻繁にテントを使うと怒られそうだから我慢する」といった、ゲームの外側の事情まで絡んでくることもあり、純粋な遊びやすさからするとどうしてもマイナスに働きやすい仕様です。開発側としては「日常的な移動中は中断セーブ、ボス前にテントで本セーブ」という棲み分けを狙っていたのでしょうが、現実には“こまめにセーブしたいプレイヤーほど金欠になる”というジレンマを生み出してしまい、結果としてプレイ体験を窮屈にしている面があります。
慢性的な金欠とコスト感覚の厳しさ
テントだけでなく、装備品や仲間の契約料など、何をするにもお金がかかる経済バランスも、本作の“悪かったところ”としてよく指摘されます。敵を倒して得られるのは直接の通貨ではなく換金アイテムで、その換金レートも固定でさほど高くないため、ある程度まとまった資金を作るには相応の戦闘回数をこなす必要があります。それにもかかわらず、店頭には序盤からかなり高額な武器防具がずらりと並び、仲間を雇う契約料まで加わるため、「テントを買うか装備を買うか」で常に悩まされる状況に陥りがちです。とくに初見プレイ時には、「せっかくだから強そうな武器を買おう」「この仲間は面白そうだから入れてみよう」と試しているうちに財布が空になり、肝心なときにテントも回復アイテムも買えない、といった事態が頻発します。戦闘で敵が逃げてしまうと換金アイテムも得られない仕様も相まって、せっかく苦労して削った敵を取り逃がし、何の見返りもなく消耗だけが蓄積される、という“徒労感”を覚えやすいのも難点です。お金のやりくりを含めたシビアなサバイバル感を楽しめる人にはプラスにもなりますが、多くのプレイヤーにとっては「もう少しだけ緩くしてほしかった」と感じる部分でしょう。
マップ使い回しと移動のダルさ
街道やダンジョンのマップパターンがかなり限られており、同じ形の画面が延々と続く構造も、プレイしているとどうしても気になってくる欠点です。一画面ごとの固定マップがパイプのようにつながっていく方式自体はマッピングしやすい利点があるものの、部屋のバリエーションが少ないうえに、少し構造を変えただけの“似たような画面”が頻繁に登場するため、長時間プレイしていると「またこの形か」「今どこを歩いているのか分からなくなった」という感覚に陥りがちです。オープンシナリオを進めるために同じ街道を何度も往復させられる場面も多く、その都度ランダムエンカウントが発生することを考えると、移動そのものが大きなストレスになってしまいます。ワープに相当する手段も一応存在するものの、拠点同士を結ぶ限定的なもので、そこから目的地までの距離が長いケースも少なくありません。結果として、「ただの移動に時間を取られすぎる」「ダンジョンの奥に宝箱を取りに行くだけでひと仕事」という印象が強くなってしまい、折角の自由度を“移動の面倒さ”が削いでしまっている面は否めません。
キャラクター掘り下げの偏りと、メインシナリオの物量不足
仲間キャラが多数登場し、自由にパーティに加えられる一方で、それぞれの人物像の掘り下げにはかなり差がある、というのも惜しい点です。メインシナリオに深く食い込むキャラや、特定のオープンシナリオと密接に関わるキャラはある程度しっかり描かれますが、“そこそこ強いけれどあまりイベントに絡まない”タイプの仲間も多く、せっかく気に入ってパーティに入れても、ストーリー上で見せ場が与えられないままエンディングを迎えてしまうこともあります。また、メインシナリオそのものの分量も、オープンシナリオを含めてようやく前作と同程度と言われるくらいで、ストーリーだけを追うと“あっさり終わってしまう”感が否めません。自由度の高さゆえに、プレイヤーの選択次第で「ほとんど絡む機会がない仲間」が出てきてしまうのはシステム上仕方ない側面もありますが、それでも「もう一歩、全員にスポットライトを当ててほしかった」と感じるファンは少なくありません。エンディングでアヴィンのもとに仲間たちが集結する演出も、仲間にしなかったキャラは登場しない仕様になっているため、少人数で攻略したプレイでは「思っていたよりも画面が寂しい」という印象を受けてしまうこともあります。
戦闘テンポとエンカウントバランスの重さ
戦術性の高いバトルシステムは本作の魅力である一方、そのテンポの重さは確かにマイナス面として意識されやすい部分です。攻撃や魔法を行うたびに専用のアニメーションが表示され、初見では「よく動くな」と感心するものの、長時間のレベル上げやダンジョン攻略では、その一つひとつのモーションが徐々に負担に感じられてきます。オプションで高速化やアニメOFFにできるとはいえ、エンカウント率も決して低くなく、一回あたりの戦闘にかかる時間も長めなため、“とにかく数をこなす”タイプの雑魚戦がどうしてもダレがちです。また、MPを回復する手段がテント以外ほとんど存在しないこともあり、黒魔法を主力にしていると、ダンジョンの途中でMPが尽きてしまい、そこから先は「通常攻撃でちまちま削るだけ」という、やや単調な展開に陥ることも少なくありません。特に長いダンジョンでは、「まだ続くのか」「そろそろ戻るべきか」とMP残量と相談し続けることになり、じっくり遊びたいときでも、戦闘テンポとリソース管理の厳しさがブレーキになってしまうのは否定できないところです。
ステータスバランスの偏りとビルドの“最適解”が見えやすいこと
技能・精神といったステータスが命中・回避・クリティカルなどの判定に大きく影響するバランスも、RPGとして見るとやや偏りが強い部分です。物理攻撃にしろ魔法にしろ、最終的には技能・精神が高いキャラほど安定してダメージを与え、敵の攻撃も避けやすくなるため、「火力は装備や魔法で補うとして、とにかく技能・精神を最優先に上げるのが正解」という考えに収束しがちです。その結果、プレイヤー間のビルド談義でも「最終的にはこう育てるのが無難」といった“テンプレート”が共有されてしまい、せっかく自由度の高い育成システムなのに、実用性を重視すると選択肢が絞られてしまう、というジレンマを抱えています。魔法系統のバランスも、終盤になるほど黒魔法と風属性精霊が特に強く、他の属性や白魔法メイン構成は「やや器用貧乏」な印象を持たれがちです。もちろん、工夫次第でどのビルドでも攻略は可能ですが、「どう育ててもなんとかなる」タイプのRPGと比べると、プレイヤーの自由なビルドを許容する余地はやや狭く感じられるかもしれません。
現代の感覚から見ると厳しいインターフェースと入手環境
これは当時のPC-98作品全般にも言えることですが、現代のプレイヤーからすると、インターフェースや操作感がどうしても古さを感じさせるのも事実です。メニュー操作や移動速度、ウィンドウの切り替えなど、今のRPGに慣れた目で見ると「ひと手間多い」と感じる部分が散見されますし、マシンスペックやOSの違いから、オリジナルのPC-98版を遊ぶにはエミュレーション環境などの準備が必要になります。Windows版・PSP版が存在するとはいえ、それぞれの環境での入手難度や動作の安定性を考えると、「やってみたいと思ってもハードルが高い」と感じる人が出てしまうのは避けられません。作品そのものの欠点とは少し違うものの、“名作だけれど遊びにくい”“興味はあるのに触れる機会が少ない”という意味で、現代における『朱紅い雫』の弱点のひとつになっていると言えるでしょう。
「自由度」と「遊びやすさ」の両立にあと一歩届かなかった惜しさ
総合的に見ると、本作の悪かったところは、どれも“自由度を高めるために負担も増えてしまった”という一点に集約されます。オープンシナリオや自由な編成・育成システムは非常に魅力的ですが、それを支えるバランスが厳しすぎるがゆえに、プレイヤー側に強い忍耐力と研究心を要求してしまっているのです。もし、テントの価格がもう少し安かったり、マップのバリエーションが増えて移動が快適だったり、金策の手段がもう少し多かったりしたなら、「自由度の高さ」と「遊びやすさ」の両方を備えた、より多くの人に勧めやすい作品になっていたかもしれません。その意味で、『朱紅い雫』は“あと一歩で万人向けになり得た意欲作”であり、その一歩に届かなかったからこそ、「好きな人にはたまらないが、人を選ぶ一作」という評価が今なお付きまとっていると言えるでしょう。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
主人公アヴィン――無口で不器用だからこそ胸に残る主人公像
『朱紅い雫』で“好きなキャラクター”として真っ先に名前が挙がるのは、やはり主人公のアヴィンです。ただし、その魅力は「熱血漢でよくしゃべる典型的なRPG主人公」というタイプとは真逆で、どちらかと言えば寡黙で、感情表現も不器用な青年として描かれています。幼い頃に大聖堂襲撃事件で妹と生き別れ、賢者レミュラスに匿われながらひっそりと成長した彼は、どこか“世界から取り残された”ような影をまとっており、その雰囲気が物語全体のトーンともシンクロしています。旅の目的も「世界を救う」より先に「妹を探す」という、ごく個人的でささやかな願いから始まるため、アヴィンの行動原理は一貫して家族への想いに根ざしています。世界の命運が懸かった場面でも、彼の心の中には常にアイメルの存在があり、「英雄としてどうするべきか」ではなく「兄としてどう生きるべきか」という視点で葛藤する姿が多くのプレイヤーの共感を呼びます。物語後半で明かされていく自身の出自や、背負わされる運命に対しても、アヴィンは決して大仰な言葉で語ることはなく、ほんの少し表情や口数が変わるだけ――その“控えめな変化”がかえって説得力を生み、「この作品だからこそ成立する主人公像」として印象に残るのです。「口では多くを語らないが、行動で示すタイプの主人公が好き」というプレイヤーにとって、アヴィンは間違いなく忘れがたいキャラクターでしょう。
マイル――相棒ポジション以上の存在感を持つ幼なじみ
アヴィンの幼なじみであり、旅の最初から最後まで寄り添う相棒マイルも、人気の高いキャラクターのひとりです。どこか素朴で人懐っこい雰囲気を持ち、アヴィンの無口さを補うように場を和ませるムードメーカー的な役回りを担っていますが、単なるお調子者に終わらない“芯の強さ”も持ち合わせています。戦闘面では遠距離攻撃や白魔法を活かしてパーティの安全を支える縁の下の力持ちであり、シナリオ上でも「アヴィンにとっての支え」の象徴として描かれます。プレイヤーによっては、「アヴィンよりもマイルの方が感情移入しやすい」という意見もあるほどで、弱音も吐けば羨望も嫉妬も抱える、非常に人間味のあるキャラクターです。物語が重くなりがちな本作において、彼の軽口や少し情けないリアクションが緊張を和らげてくれる場面も多く、「シリアス一辺倒にならない空気」を作っている功労者とも言えます。だからこそ、マイルに関わるイベントで描かれる彼自身の葛藤や、アヴィンとの距離感の変化はとても印象的で、「最後までこの二人の関係を見届けたくなる」という声が多いのも頷けます。
シャノン――物語の空気を変える“騒がしくて健気なヒロイン”
序盤から中盤にかけてアヴィンたちの旅に騒がしい彩りを添えるのが、マイルの追っかけ娘とも言える少女・シャノンです。彼女はとにかく明るくてよくしゃべり、すぐに騒動を起こす問題児タイプですが、その根底には「好きな人を追いかけていたい」「自分も誰かの役に立ちたい」という、年相応のまっすぐな想いがあります。とくに、宗教対立や神々の因縁といった重いテーマが前面に出てくる本作において、シャノンの存在は“日常の温度”を思い出させてくれる貴重な要素です。彼女がいるからこそ、アヴィンたちの旅は単なる世界の命運をかけた戦いではなく、“少し騒がしくて、少し切ない青春の記憶”としても心に残るのかもしれません。彼女のドタバタぶりに最初は辟易していたプレイヤーも、物語が進むにつれて見えてくるシャノンなりの優しさや不器用さに触れることで、「気づけば一番印象に残っていた」と語ることが多く、賑やかで健気なヒロイン像として好意的に受け止められています。
アイメル――姿の少なさがかえって想像を掻き立てる“物語の中心”
実際にプレイしている時間の長さだけで見れば、妹アイメルの登場シーンは決して多くありません。しかし、彼女は間違いなく物語の中心にいる存在であり、その“姿の少なさ”がかえってプレイヤーの想像力を刺激します。幼い頃の別れの記憶と、大聖堂襲撃時に交わされた約束、そして「どこかで生きているはずだ」という希望だけを頼りに旅を続けるアヴィンにとって、アイメルは“失われた家族”の象徴であり、同時に“奪われた日常”そのものでもあります。プレイヤーは、アヴィンや周囲の人々の口から断片的に語られるアイメル像を通してしか彼女を知ることができず、そのもどかしさが、「一刻も早く再会の瞬間を見たい」という感情につながっていきます。重要な場面での再登場や、物語終盤で明かされる彼女の立場・役目などはネタバレを避けますが、そこで示される彼女の選択や言葉は、『朱紅い雫』という作品全体への印象を決定づけると言っても過言ではありません。「出番の多さ」ではなく「物語への影響力」でこれほど強く記憶に残るキャラクターはそう多くなく、アイメルを“好きなキャラ”に挙げるプレイヤーが多いのは、まさにその象徴と言えるでしょう。
大人たちの魅力――エスペリウス、レミュラス、ディナーケンらが背負うもの
若い主人公たちを取り巻く“大人のキャラクターたち”も、本作の魅力を語るうえで外せません。最高導師エスペリウスは、大聖堂襲撃の混乱の中でアヴィンとアイメルに神宝を託し、自らはその場に残る決断をした人物として描かれます。彼の決断は、単に「子どもたちを逃がすため」というだけでなく、“信仰の象徴としてどう振る舞うべきか”という重い問いに対する答えでもあり、その姿勢はアヴィンの生き方にも目に見えない影響を与えています。また、アヴィンを匿い育ててくれた賢者レミュラスや、アイメルの消息を知るとされる賢者ディナーケンも、それぞれ違う形で“真実”に近づいている人物として描かれ、単なる導き手ではなく、自身の罪や後悔を抱えた「一人の人間」としての側面を見せてくれます。こうした大人たちの在り方は、少年少女の成長物語であると同時に、“大人たちの贖罪と決着”の物語でもあることを示しており、プレイヤーが年齢を重ねてから遊び直したとき、昔とは違った感情を喚起してくれる要素になっています。「子どもの頃はアヴィンたちに感情移入していたけれど、大人になってからプレイするとエスペリウスやレミュラスの気持ちが分かるようになった」という声が出るのも、本作ならではの深みです。
シャムシール団をはじめとした“周縁の人々”の存在感
オープンシナリオを通じて断片的に描かれる盗賊団シャムシールの面々や、各地の町で出会う人々も、プレイヤーそれぞれの“お気に入りキャラクター”としてよく名前が挙がります。シャムシール団は一見すると単なる盗賊集団ですが、連続する依頼やイベントを追っていくと、その背後にある事情や、彼らなりの正義が少しずつ見えてきます。正義の側から見れば“悪人”であっても、彼らにも守りたいものや折り合いをつけなければならない現実があり、オープンシナリオをやり込むほど「誰も単純な悪役ではない」という本作のテーマが浮かび上がってきます。また、宿屋の主人や情報屋、仕事の依頼人、街角で出会う子どもたちなど、名前すら覚えていないようなモブキャラにも、ふとした一言やささやかなエピソードで印象に残る存在が多く、「一人ひとりがこの世界で生きている」という実在感を支えています。プレイヤーの中には、「自分にとっての一番の推しキャラは、あるオープンシナリオで出てきた無名の依頼人だった」という人もおり、そうした“周縁キャラ”が記憶に残るのも、膨大なサブイベントを積み重ねた本作ならではです。
敵役・宗教関係者たちの“単純な悪ではない”描かれ方
邪神オクトゥム側につく司祭や信徒たち、宗教組織の内部で揺れる神官たちなど、いわゆる敵役・対立役も、『朱紅い雫』では単なる“悪の手先”として描かれていません。彼らの中には、自分の信じる神の教えを曲げられず、結果として過激な行動に走ってしまう者もいれば、組織の腐敗に気づきながらも、それでも信仰を捨てきれず葛藤する者もいます。そうした人物たちにほんの短いモノローグや背景が与えられることで、プレイヤーは「倒すべき敵」として憎み切ることができず、戦闘後に複雑な感情を抱くことになります。この“単純に割り切れない敵役”の存在は、物語全体に漂う重苦しさと同時に、“人間は誰しもどこかで迷いながら生きている”というメッセージを強く印象付けており、敵キャラを“好きなキャラクター”に挙げるプレイヤーもいるほどです。苛烈な行動を取る彼らですら、ただの記号ではなく、“信仰と現実の間で揺れる一人の人間”として描かれているところに、本作のキャラクター造形の奥行きが表れています。
どのキャラクターにも“弱さ”と“人間臭さ”がある世界
こうして振り返ってみると、『朱紅い雫』に登場するキャラクターたちの魅力は、決して「格好良さ」や「可愛さ」の一点で語り尽くせるものではありません。アヴィンもマイルもシャノンも、大人たちも敵役たちも、皆どこかに“弱さ”や“後悔”を抱え、それでも何とか前へ進もうとしている存在として描かれています。完璧な英雄も、絶対悪の魔王も出てこないこの世界では、それぞれが自分にとっての“正しさ”を信じ、時に間違え、時に傷つきながら選択を重ねていきます。プレイヤーは、そのひとつひとつの選択と結果を見届ける中で、「誰の立場に自分を重ねるか」によって好きなキャラクターが変わっていくのです。若い頃に遊んだときはアヴィンやシャノンに感情移入していた人が、年月を経て遊び直すとエスペリウスやレミュラス、あるいは敵側の人物に心を引かれるようになる――そんな“時間と共に変わる推しキャラ”の楽しみを提供してくれるのも、この作品ならではの魅力と言えるでしょう。どのキャラクターも決して完璧ではないけれど、その不完全さゆえに愛おしい。『朱紅い雫』という作品が長年語り継がれている理由のひとつは、まさにこの“人間臭さ”にあるのかもしれません。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
PC-9801版:1996年に出た“元祖・朱紅い雫”の味わい
まず最初に押さえておきたいのは、PC-9801版が『英雄伝説IV 朱紅い雫』のオリジナル版であり、ガガーブトリロジー中でも特に“骨太なPC-RPG”として作られているという点です。1996年当時のPC-98環境を前提にしているため、解像度・色数は今の基準から見ると控えめですが、そのぶんマップや戦闘画面、キャラチップなどは「限られたドットでどこまで情報を詰め込むか」という挑戦のような作りになっており、粗いながらも印象に残る画面構成になっています。オープンシナリオ制+斡旋所による依頼システム、自由度の高いパーティ編成、戦術性の高いタクティカル戦闘、かなりシビアな難易度設定など、「PC-98ユーザー向けのやり込み型RPG」として設計されているのが特徴です。ストーリー面でもイベント量・寄り道の幅が多く、プレイヤーの選択によって見ることのできるイベントやキャラの掘り下げに差が出やすい構造になっているため、「一周で全てを見せない」作り込みの濃さが“元祖版ならではの魅力”になっています。
Windows版:“新4”として再構成されたストーリー重視リメイク
一方で、2000年前後に発売されたWindows版は、公式にも「新 英雄伝説IV 朱紅い雫」と呼ばれ、同じIVでありながらシナリオやシステムが大きく再構築された“リメイク寄りのバージョン”です。雑誌記事などでも、パーティの入れ替えが物語の進行に沿ったものになり、オープンシナリオの斡旋所が廃止されていることが明記されており、よりストーリー主導の進行へと見直されていることが分かります。また、街道マップのバリエーション追加や障害物の整理などにより、“同じような画面が続く”というPC-98版特有の息苦しさを緩和し、RPG初心者にもかなりやさしいバランスに調整されたと紹介されています。PCスペックの向上を前提に、解像度や色数、インターフェースも一新され、フルスクリーン/ウィンドウの切り替えやMIDI音源でのBGM再生など、Windows時代らしい快適さと表現力を手に入れた“新生・朱紅い雫”と言えるでしょう。
シナリオ面の違い:同じ骨格でありながら別物レベルの改稿
物語の根幹――ガガーブ世界の時間軸や、アヴィンとアイメルの兄妹ドラマ、バルドゥスとオクトゥムの宗教対立といった“大枠”はPC-98版とWindows版で共通していますが、実際にはイベントの構成・描写・セリフのニュアンスがかなり異なっています。ガガーブトリロジーを論じた記事でも、「特に『朱紅い雫』は別物と言っていいほど内容が変わっている」とまで書かれており、PC-98版とWindows版とで“同じエピソードなのに展開や印象が違う”場面が多数存在します。たとえば序盤のレミュラスの遺言ひとつを取っても、PC-98版では「アイメルの居場所はディナーケンが知っている」と直接的に示されるのに対し、Windows版では「アイメルはオクトゥム教に命を狙われており、その居場所は誰にも明かされていない」といった形に書き換えられており、妹捜しの旅に“より強い緊張感”が生まれるよう配慮されています。また、中盤以降のキーイベントである“真実の島の壁画”に関しても、PC-98版ではアヴィンとミッシェルが一緒に奥へ進み、ミッシェルが壁画の解釈を語る流れになっているのに対し、Windows版では登場人物やセリフの役割が変化し、シナリオ上の意味付けが調整されていることが指摘されています。こうした細かな違いが積み重なった結果、「PC-98版は重く生々しいドラマが強く、Windows版はもう少し整理されて読みやすくなっている」と感じるプレイヤーも多く、どちらのテイストが好みかで評価が分かれるところです。
ゲームシステム・難易度バランスの違い
システム面でも、PC-98版とWindows版はかなり性格が異なります。PC-98版はオープンシナリオ+斡旋所による自由度の高さと引き換えに、敵配置・エンカウント・金策などが総じて厳しく、“気軽に遊ぶ”というより“腰を据えて攻略する”タイプのバランスでした。行き先を誤れば序盤から高レベルモンスターの群れに遭遇して全滅することも珍しくなく、テントによるフィールドセーブのコストも高いため、プレイヤー側にかなりの慎重さと試行錯誤を要求します。一方、Windows版では、上記の通り斡旋所が廃止され、パーティの入れ替えもシナリオに沿って行われる形になったことで、ルート選択の自由は減ったものの、迷いやすかった導線が明確になり、ストーリー追従型の遊び方でも行き詰まりにくくなりました。また、「RPG初心者にもやさしいバランス」と宣伝されているとおり、敵の強さや成長速度、資金周り等も見直されており、元のPC-98版を遊んだプレイヤーからは「別作品かと思うほどぬるくなった」との感想も聞かれるほどです。オリジナル版の“歯応えのある自由度”を取るか、リメイク版の“遊びやすさと物語のわかりやすさ”を取るかは、プレイヤーの嗜好次第と言えるでしょう。
グラフィック・サウンド・演出の進化
グラフィックとサウンド面では、Windows版はPC-98版から世代がひとつ進んだだけあって、解像度・色数・演出の面で大きくパワーアップしています。PC-98版では文字主体だった歴史紹介のオープニングが、Windows版ではムービーとフルカラーのビジュアルを交えた演出に置き換えられ、カテドラールやステンドグラスのシーンなどは“宗教都市の荘厳さ”を視覚的に強く印象付けるものへと変化しました。サウンドも、FM音源中心だったPC-98版に対し、Windows版ではMIDI音源対応となり、BGMの2ループ目以降にアレンジが変化するなど、PCならではの音楽表現が取り入れられています。また、インターフェース周りも刷新され、キャラクターにカーソルを合わせるとミニアイコンが表示されるUIや、顔グラフィック付きのステータス画面など、シリーズの後発作『海の檻歌』『白き魔女(Windows版)』との統一感を意識した作りになっています。一方で、PC-98版特有の16色ドット絵や、FM音源ならではの厚みのあるサウンドを好むプレイヤーも多く、「雰囲気込みでPC-98版こそ本家」と考えるファンも少なくありません。
発売順とシリーズ内での立ち位置の違い
ガガーブトリロジー三部作の中での“発売順”や“時系列”の扱いも、PC-98版とWindows版で微妙に印象が変わる要素です。ガガーブ世界の物語としては、『朱紅い雫(IV)→海の檻歌(V)→白き魔女(III)』の順に時間が流れていきますが、PC-98版では『白き魔女(III)→朱紅い雫(IV)』の順に発売され、Windows版では『白き魔女(III)→海の檻歌(V)→朱紅い雫(IV)』という順番でリリースされています。このため、PC-98版でリアルタイムに追っていたプレイヤーと、Windows版で三部作を揃えたプレイヤーとでは、「どの作品から入ったか」「どの作品に一番思い入れがあるか」が変わりやすく、シリーズ内での『朱紅い雫』の位置づけも微妙に異なる見え方をします。PC-98版では“白き魔女の次に出た新作”として遊ばれたのに対し、Windows版では“ガガーブ三部作を締めくくるリメイク的存在”として受け止められた側面もあり、これもまた「どの環境でプレイしたかによって印象が変わる」要因のひとつになっています。
(補足)PSP版など家庭用ゲーム機版との関係
本題からは少し外れますが、『英雄伝説IV 朱紅い雫』はその後、PSP向けに『The Legend of Heroes: A Tear of Vermillion』としてリメイク・ローカライズされ、海外では“ナンバリングを外した一作目”として発売されました。PSP版はWindows版をベースにしつつ、携帯機向けにインターフェースや戦闘テンポが再調整されており、グラフィックも解像度に合わせた再描画が行われています。バトルシステムも、元のタクティカル要素を残しつつ、より一般的なコマンドRPG寄りに整理されているため、“PC-98版→Windows版→PSP版”と順に触れていくと、「同じ物語と世界観が、ハードの世代に合わせて少しずつ姿を変えていった歴史」を体感できます。もっとも、今回のテーマである“対応パソコンによる違い”という観点で言えば、PC-98版は骨太で自由度の高いPC-RPG、Windows版は遊びやすさとビジュアル強化を重視したストーリー重視型RPG、という住み分けがされていると考えるのが分かりやすいでしょう。それぞれのバージョンが異なる方向性の魅力を持っているため、“どれが決定版か”というより、“どの時代のPC文化に触れたいか”で選ぶのが一番しっくり来る作品と言えます。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
★提督の決断III
・販売会社:光栄(現コーエーテクモゲームス) ・販売された年:1996年(PC-9801版) ・販売価格:16,280円(税込、PC-9801版の定価) 第二次世界大戦期の海戦を題材にしたウォーシミュレーションで、プレイヤーは日本海軍や連合軍の提督となり、艦隊運用や造船計画、技術開発、外交といった要素を通して戦局をコントロールしていきます。戦略レベルでは資源や工業力を背景にした長期的な国力運用が求められ、戦術レベルでは空母機動部隊や戦艦をどう組み合わせて艦隊決戦に挑むかといった判断が問われます。同じPC-98向けウォーゲームでも、本作はグラフィックやインターフェイスが洗練されており、「朱紅い雫」のようなRPGとはまったく方向性の違う“硬派な歴史シミュレーションの極み”として多くのPCユーザーに遊ばれました。シナリオごとにif展開も用意されており、「もしここで別の決断をしていたら……」という歴史改変の楽しさを味わえる点も、当時のPCゲームらしい魅力と言えます。
★銀河英雄伝説IV
・販売会社:ボーステック ・販売された年:1996年(PC-9801 3.5インチ版。初出は1994年だが96年にも再販・流通) ・販売価格:14,080円(税込、PC-9801 3.5インチ版の定価) 田中芳樹の人気SF小説『銀河英雄伝説』を原作としたターン制SFシミュレーションで、プレイヤーは銀河帝国か自由惑星同盟の一提督となり、星系をまたにかけた大艦隊戦を指揮します。星系マップ上で艦隊を運用し、補給や士気、提督ごとの指揮能力を考慮しながら戦略を組み立てるゲーム性は、TRPG的な“ロールプレイ”の楽しさと、ウォーシミュレーションの思考性を兼ね備えたものです。『朱紅い雫』がガガーブ世界の神々と人間の物語をRPG形式で語る一方、本作は群像劇としての銀英伝ワールドを、イベントと戦略マップの両面から追体験させてくれました。PC-98ユーザーにとっては、「朱紅い雫」で重厚なファンタジーを、「銀英伝IV」で重厚なSF戦記を――と、同じマシンでまったく違う世界観を楽しめた贅沢な時期でもあります。
★雫 〜しずく〜
・販売会社:Leaf(当時はアダルトゲームブランド) ・販売された年:1996年(PC-9801版。後にWindows版も発売) ・販売価格:おおよそ8,000〜10,000円前後(エディションやプラットフォームにより異なるが、同時期のLeaf作品の新パッケージ版は6,000〜1万円弱の価格帯が主流) 学園を舞台にしたホラータッチのアドベンチャーで、血縁やトラウマ、閉鎖空間の不安といった生々しいテーマを真正面から扱った問題作として知られています。一般的な恋愛ADVのように甘い日常が繰り広げられる一方、その裏側では宗教儀式めいた惨劇や、人体実験を思わせる暗い出来事がじわじわと浮かび上がり、プレイヤーの心をえぐる展開が続きます。テキストの密度が高く、BGMやイベントグラフィックも不穏さを強調する演出が多いため、同じ時期の『朱紅い雫』のダークな宗教・神話モチーフに通じる空気感を好むプレイヤーからは、「PC-98末期を象徴する“重い物語ゲーム”」として語られます。選択肢の積み重ねでエンディングが分岐する点も、コマンド選択型RPGである朱紅い雫と好対照です。
★痕 〜きずあと〜
・販売会社:Leaf ・販売された年:1996年(PC-9801版) ・販売価格:9,680円(PC-9801版「HDD専用/3.5インチ版」の定価) 『雫』に続いて発売されたホラー寄り恋愛ADVで、山間の旧家を舞台に、因習と血の呪いに翻弄される若者たちを描いた作品です。プレイヤーは別荘に招かれた青年となり、いとこたちとの交流を進めつつ、一族に伝わる恐ろしい風習の真相へと迫っていきます。序盤は和気あいあいとした会話やコミカルな掛け合いが多いものの、物語が進むにつれて徐々に不穏な空気が濃くなり、終盤では容赦のない展開が待ち構えています。そのギャップの強さが、のちのPCユーザーの間で“トラウマ級の作品”として語られるゆえんです。重苦しい世界観や宗教的なモチーフ、キャラクター同士の心理描写に重きを置いている点は、『朱紅い雫』のシナリオ傾向と近い部分もあり、当時のPC-98ユーザーの間では「朱紅い雫でRPGの暗い物語を、痕でADVの暗い物語を」とセットで楽しむ遊び方も見られました。
★Piaキャロットへようこそ!!
・販売会社:カクテルソフト(F&C) ・販売された年:1996年(PC-9801版ほか) ・販売価格:8,580円(税込、Windows版の定価。PC-98版も同程度の価格帯) ファミレスを舞台に、アルバイトとして働く主人公と個性豊かなウェイトレスたちとの交流を描いた恋愛シミュレーションで、暗く重い物語の多かったPC-98後期の中では、ポップで明るい雰囲気が際立つタイトルです。プレイヤーはシフトの管理やイベント発生の条件を意識しながら、好みのヒロインとの親密度を高めていきます。制服や店舗ごとのコンセプトデザインに凝っており、のちに家庭用ゲーム機へも展開される“ファミレスもの”の先駆け的存在になりました。『朱紅い雫』と発売時期が近いにもかかわらず、こちらは日常や恋愛を前面に押し出した作風で、同じPCで遊べる作品の振れ幅の大きさを象徴しています。重厚なRPGの合間に、軽い気持ちでプレイできる“癒やし枠”として選ばれることも多かったゲームです。
★ウェディングピーチ
・販売会社:KSS ・販売された年:1996年(PC-9801版など) ・販売価格:11,400円前後(PC-98版フロッピー版の定価) 同名の魔法少女アニメをPC向けにゲーム化した作品で、アドベンチャーパートとイベントCGを中心に、原作アニメの世界観を追体験できる構成になっています。プレイヤーは主人公のもも子たちと共に、ラブラブエンジェルとして悪魔族と戦いながら、学園生活や恋愛模様も楽しむことができます。TVアニメ由来ならではのカラフルなキャラクターデザインや、原作ファン向けのサービス要素が多く、「PC-98で動く魔法少女ゲーム」として話題になりました。『朱紅い雫』と同じく“愛”や“信仰”といったキーワードを扱いながらも、こちらは明るくハッピーな方向へと物語をまとめているため、シリアス続きになりがちな当時のPCゲームライブラリの中で、気軽に楽しめる一本として親しまれています。
★デビルフォースII 〜奪われた秘宝〜
・販売会社:コンパイル ・販売された年:1996年(PC-9801/Windows向け、PC雑誌『ディスクステーションVol.9』収録作) ・販売価格:単品販売ではなく雑誌付録。収録元の『ディスクステーションVol.3〜18』は1,980円(税別)が定価 ぷよぷよシリーズなどで知られるコンパイルが手掛けたシミュレーションRPGで、ファンタジー世界を舞台に、少人数のユニットを指揮してマップ攻略を行う作品です。マップはタイル状に区切られており、ユニットの移動力や攻撃射程、地形効果を考えながらじわじわと攻め上がっていくスタイルは、コンシューマ機のシミュレーションRPGに近い感覚で遊べます。低価格の雑誌付録ながらシナリオやBGMも作り込まれており、PC-98ユーザーの間では「ディスクステーション屈指の名作」として語られることもあります。『朱紅い雫』の戦闘がタクティカル寄りにシフトしていった流れと同じく、本作も“コマンド選択+タイル戦術”の面白さを凝縮しているため、当時のPCゲーマーにとっては両作を遊び比べることで、同時期のタクティカルバトル表現の違いを味わうことができました。
★リバイバル ザナドゥ2 リミックス
・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1995〜1996年頃(PC-9801版。オリジナルは1985年『ザナドゥ』の流れを汲むリメイク続編) ・販売価格:9,570円(PC-9801「リバイバル ザナドゥ2 リミックス」3.5インチ版の定価) アクションRPGの金字塔『ザナドゥ』を現代風に再構築した「リバイバル ザナドゥ」の続編で、より高難度のダンジョン攻略に特化したヘビーユーザー向け作品です。シンボルエンカウント式で戦闘に突入し、リアルタイムのアクション操作でモンスターと戦うスタイルは、同じファルコム作品でありながら『朱紅い雫』のコマンド選択式バトルとは対照的です。限られたリソースの中で装備や魔法をどう揃えるか、どのフロアをどの順番で攻略するかといった計画性が強く求められるため、当時のPCユーザーの間では「気合を入れて挑む硬派なダンジョンRPG」として認識されていました。ファルコムの“昔ながらのアクションRPGの系譜”と、“英伝シリーズのストーリー重視路線”を一緒に楽しめたことも、PC-98時代ならではの贅沢と言えるでしょう。
★Diablo(ディアブロ)
・販売会社:Blizzard Entertainment ・販売された年:1996年末(北米版PC版) ・販売価格:北米版の新作PCゲームとしておよそ50ドル前後(当時のPCゲーム一般的価格帯) 暗いファンタジー世界トリストラムを舞台に、プレイヤーが一人の冒険者として地獄の軍勢に立ち向かうハック&スラッシュRPGです。ランダム生成されるダンジョン、敵をなぎ倒して装備を拾い、また潜っていくという循環型のゲームデザインは、後のアクションRPGに多大な影響を与えました。マウス操作だけで移動と攻撃をこなせるシンプルさと、倒した敵から思わぬ強装備が出る“ガチャ的快感”の組み合わせは、当時のPCゲーマーに衝撃を与え、「PCゲーム=キーボードでじっくり考える」というイメージを覆した作品でもあります。『朱紅い雫』が重厚なテキストと戦略的なコマンドバトルで魅せるのに対し、Diabloはアクション性とランダム性で遊ばせる構造であり、同じ1996年前後にPCで遊べたRPGがいかに多様だったかを象徴するタイトルです。
★Quake(クエイク)
・販売会社:id Software(販売はGT Interactive ほか) ・販売された年:1996年(PC版) ・販売価格:北米のパッケージ版でおよそ50ドル前後(当時のフルプライスPCゲームの一般的な価格帯) 完全3Dポリゴンによる表現と重低音のサウンドで、プレイヤーに強烈なインパクトを与えたFPS(ファーストパーソン・シューティング)です。陰鬱な中世風ダンジョンや異形の怪物が徘徊するマップを、ショットガンやロケットランチャーを手に高速で駆け抜けていく体験は、それまでの2DベースのFPSから一段階進化した“本物の3D空間”として受け止められました。ネットワーク対戦も大きな特徴で、世界中のPCゲーマーがQuakeを通じてデスマッチを楽しみ、MOD文化やeスポーツの先駆け的なコミュニティを形成していきます。日本のPCユーザーにとっても、『朱紅い雫』のようにじっくり物語を味わうRPGと、Quakeのように反射神経を酷使するアクションFPSを同じWindows環境で遊び分けられる時代が到来したことは、PCゲームの選択肢が一気に広がった象徴的な出来事でした。
――以上のように、『英雄伝説IV 朱紅い雫』と同じ1990年代半ばには、PC-9801向けのシナリオ重視RPGや恋愛ADV、シミュレーションだけでなく、海外製のハック&スラッシュやFPSなど多種多様なPCゲームが登場していました。重厚なファンタジーRPGとしての朱紅い雫を語るうえで、同時期のこれらの作品群を並べてみると、「当時のPCゲーマーがどんな選択肢の中から朱紅い雫を手に取っていたのか」が、より立体的に見えてくるはずです。
[game-8]