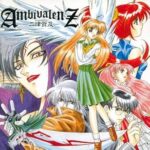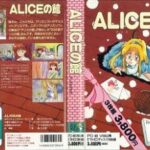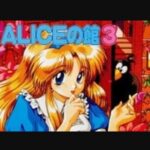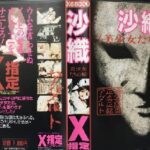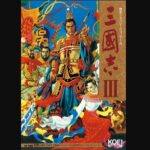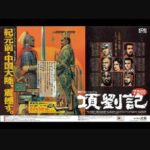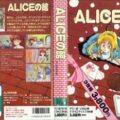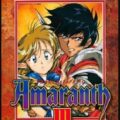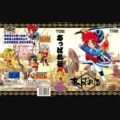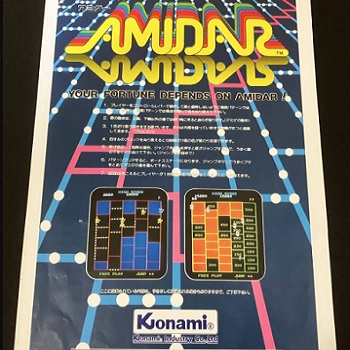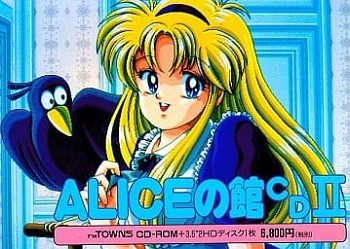
ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..




 評価 5
評価 5【発売】:アリスソフト
【対応パソコン】:PC-9801、X68000、FM TOWNS
【発売日】:1992年7月
【ジャンル】:ゲーム集
■ 概要
アリスソフトと『館』シリーズの位置づけ
1990年代初頭、日本のPCゲーム市場は多様化の時代を迎えていました。NECのPC-9801シリーズがビジネス用途から家庭用途にまで浸透し、またシャープのX68000や富士通のFM TOWNSといった高性能機がユーザーの支持を集め、開発者にとっても幅広いプラットフォームが選択肢として存在していました。アリスソフトはこの時代の潮流を背景に、アダルト向け作品を軸としつつ、ファンに向けた独自の企画やサービス精神を前面に出すブランドとして頭角を現していました。 その中で生まれたのが「ALICEの館」シリーズです。単なるゲームというよりも、短編ゲーム、ミニシナリオ、ボーナスコンテンツ、さらには音楽データや開発裏話をひとまとめにした「バラエティパック」という側面を強く持っていました。第一作『ALICEの館』が1989年末に登場し、ファンが求めていた“アリスソフトらしさ”を凝縮したコンテンツとして高評価を得ました。そしてその発展系として1992年7月にリリースされたのが『ALICEの館2』です。
発売時期とプラットフォーム展開
『ALICEの館2』は1992年7月に発売され、PC-9801シリーズ、X68000、そしてFM TOWNSといった複数のパソコン向けに展開されました。これはアリスソフトにとっても大きな挑戦であり、プラットフォームごとにユーザー層の特性が異なることを見据え、幅広いファンへリーチしようとした試みでした。 特にFM TOWNS版『ALICEの館2 CD』は、当時としては先進的なCD-ROMメディアを採用しており、過去のアリスソフト作品『あぶない天狗伝説』の収録など、既存ユーザーへの特典要素を兼ね備えていました。ハードウェアごとの表現力を生かしつつ、コンテンツの豊かさで勝負した点はシリーズの方向性を象徴しています。
収録されたコンテンツ群
『ALICEの館2』は単なる続編ではなく、アリスソフトのクリエイティブな実験場とも言える内容でした。なかでも有名なのは、『Rance III -リーザス陥落-』で登場するキャラクター「パットン」を主人公に据えた短編『なぐりまくりたわぁ』です。コメディタッチのストーリーと単純明快な操作性は、多くのファンに「気軽に楽しめるアリスソフトらしさ」を印象づけました。 さらに、『婦警さんDA』や『おかゆフィーバーの逆襲』といったユーモアあふれるタイトルも収録され、ゲーム性よりもアイディアやキャラクター性を楽しむ構成になっています。これらは一本一本が軽量で短時間で遊べる作りになっており、ユーザーがアリスソフトの世界観を気ままに味わえる「おもちゃ箱」のような性質を持っていました。
開発背景とアリスソフトの哲学
アリスソフトは「ユーザーとの距離感」を非常に大事にするブランドでした。『ALICEの館』というネーミング自体が、ファンを招き入れて裏側を覗かせるような“秘密の部屋”を連想させます。実際、ゲーム内には開発スタッフのコメントや小ネタが盛り込まれており、単なるプレイ体験を超えて「制作者の声を直接聞く」ような感覚を提供していました。 こうした姿勢は、のちのシリーズや他作品にも影響を与え、「遊び心のある企画集」という独特のジャンルを確立することになります。特に『ALICEの館2』は、アリスソフトが単なるメーカーではなく、ユーザーコミュニティとの双方向性を意識した存在であることを証明した作品と言えるでしょう。
1992年前後のPCゲーム市場における意義
1992年といえば、コンシューマー市場ではスーパーファミコンが大ヒットし、PCエンジンやメガドライブといった家庭用ゲーム機の競争が盛んでした。一方でパソコンゲームは独自の発展を遂げ、より大人向けのジャンルやクリエイター主導の実験的なタイトルが数多く登場していました。 『ALICEの館2』は、その中でも“おまけ集”という特異な位置づけを持ちながら、ファンを楽しませるエンターテインメント性で支持を集めました。単なる短編集ではなく、当時のPCゲーム文化を象徴する「遊びの精神」を強く感じさせる作品であり、後世から見ても重要な足跡を残しています。
総合的なまとめ
『ALICEの館2』は、アリスソフトが持つユーモア、サービス精神、そして実験的な創作姿勢を色濃く映し出したタイトルでした。シリーズの一環としてだけでなく、1990年代初頭のPCゲーム文化そのものを語るうえでも外せない作品であり、アリスソフトのファンにとっては“時代を象徴する宝箱”のような存在です。今日振り返っても、ただの追加ディスクや小品集ではなく、ブランドとユーザーの絆を深めた特別な作品として強く印象に残っています。
■■■■ ゲームの魅力とは?
多彩な短編ゲームが織りなすバリエーション
『ALICEの館2』の大きな魅力は、ひとつのパッケージで複数の短編ゲームを楽しめるという点にあります。通常、PCゲームといえば1本の物語やシステムに集中する構成が多い中、本作は「小さなアイディアを集約し、ユーザーに一度に提供する」という形式を採用しました。これにより、プレイヤーは気分に合わせてコンテンツを切り替え、まるでビュッフェのように“少しずついろいろな味”を楽しむことができたのです。特に『なぐりまくりたわぁ』のようにキャラクター性を前面に押し出した作品は、ユーザーに強烈なインパクトを与え、シリーズ外のファン層にも浸透しました。
キャラクター主導型のコメディ要素
アリスソフト作品の魅力のひとつに「キャラクターの強烈な個性」があります。『ALICEの館2』に収録されたゲームは、システム面の革新性よりもキャラクターの魅力やギャグ的要素に重点が置かれていました。 特に、Ranceシリーズから派生したキャラクターが登場することで、既存ファンにとっては「外伝的な楽しみ方」が可能となり、新規プレイヤーにとってもキャラクターの濃厚な個性を知るきっかけとなりました。アリスソフトの登場人物はしばしば“癖が強い”と評されますが、それこそがユーモアやドラマを生み出す源泉であり、本作でもその魅力が余すことなく活かされています。
ユーザーを意識した“おまけ感”と親近感
本作は「おまけディスク的」な立ち位置を持ちながらも、単なる二次的コンテンツに留まらず、ユーザーへのサービス精神を全面に押し出した作りでした。開発スタッフの遊び心が随所に感じられ、シリアスな物語よりも“気軽に笑って楽しめる時間”を重視しています。 また、スタッフのコメントやメッセージ的要素が盛り込まれている点も、他の一般的なゲームでは得難い親近感を醸し出しました。当時はインターネットも普及していなかったため、制作者とプレイヤーが直接つながる手段は限られていましたが、本作はその「距離感を縮める役割」を果たしていたのです。
時代を先取りしたコンテンツパッケージ
現代では、追加コンテンツやDLCが一般的となっていますが、1992年当時において「ひとつのディスクで複数の小作品を提供する」という発想は斬新でした。これにより、ユーザーは単価以上の満足感を得られるだけでなく、開発側も新しいアイディアを実験的に披露することが可能でした。言い換えれば『ALICEの館2』は、後のゲーム文化における「サイドコンテンツ」「おまけ要素」「クリエイターズルーム」的な発想の先駆けであったともいえます。
笑いと遊び心に満ちた空気感
当時のアダルトゲーム市場は、重厚な物語や濃密な演出を志向する作品も増えていました。しかし『ALICEの館2』はあえて肩の力を抜き、プレイヤーに笑いと気軽さを提供する方向性を選びました。 プレイ中は「ゲームを攻略する」というより「ユーモアを体験する」感覚が強く、ユーザーの多くは“クスッと笑える時間”を楽しむことを目的にしていました。こうしたライトな魅力は、アリスソフトが持つ多面的な作風のひとつを示すと同時に、当時のユーザーに新鮮な驚きを与えました。
ファンコミュニティを育む装置としての役割
本作は単体での完成度もさることながら、アリスソフトというブランド全体のファンを育成する役割も果たしました。短編作品を通じてキャラクターに親しんだユーザーは、自然と本編シリーズや他タイトルへ興味を広げていきます。 つまり『ALICEの館2』は、既存ファンへのサービスであると同時に、新たなファンをブランドに引き込む“入り口”でもあったのです。こうした二重の役割を担った点が、この作品を長く語り継がれる魅力的な存在にしています。
まとめ:笑いと多様性が織りなす独自性
『ALICEの館2』の魅力を総括すると、「多彩な短編」「個性的なキャラクター」「遊び心」「ユーザーとの近さ」が挙げられます。一本の長編ストーリーでは得られない体験を提供し、時に馬鹿馬鹿しく、時に意表を突き、常に“アリスソフトらしい笑い”を届ける。それこそが本作の価値であり、発売から30年以上経った今もファンの記憶に残る理由と言えるでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
攻略の基本姿勢 ― 気軽さを楽しむ
『ALICEの館2』は、従来のアリスソフト作品のように複雑なシナリオや長時間のプレイを要求するタイトルではありません。収録されているゲームは短編形式であり、攻略そのものが「作品を楽しむためのスパイス」となっています。 つまり「完全クリア」を目的とするよりも、「キャラクターとのやり取りを味わいながら遊ぶ」ことが本作の正しい攻略法といえるでしょう。中には難易度がやや高めに設定されているものもありますが、それらもあくまで笑いや驚きを引き出すための仕掛けであり、ストレスを与えるものではありません。
代表的な短編ごとの遊び方
収録作品はいくつかのジャンルに分かれており、それぞれにちょっとした攻略のコツが存在します。
『なぐりまくりたわぁ』
主人公パットンを操作し、シンプルなアクション性を楽しむ短編です。攻略のポイントは「リズムを崩さずコンボを繋げる」こと。敵キャラクターはギャグ的な動きを見せますが、パターンを覚えることでスムーズに進行できます。難易度は控えめで、初心者でも安心して楽しめる作りです。
『婦警さんDA』
一風変わったコミカルなアドベンチャー。選択肢によって展開が変わる形式で、攻略のコツは「突飛な選択を恐れず試す」こと。アリスソフトらしいユーモアが仕込まれているため、意外な選択肢ほど新しいイベントが見られる可能性が高いです。
『おかゆフィーバーの逆襲』
こちらはミニゲーム的要素が強く、操作の正確さよりも“おかしさ”を楽しむことに重点があります。真面目に攻略するより「わざと失敗してどんな演出があるか」を試すことが楽しみ方の一つとなっています。
難易度設計とプレイ時間
『ALICEの館2』は、全体的に難易度が低めに設計されており、1タイトルあたりのプレイ時間も数十分程度と短めです。これは“何度でも繰り返し遊んでほしい”という意図が込められているからです。プレイヤーが気軽に手を伸ばせるため、空いた時間に少し遊ぶといった使い方にも適していました。 特に1990年代初頭は、ヘビーなシナリオゲームが主流になりつつあった時期でもありました。そんな中で『ALICEの館2』は、ユーザーに“息抜きの場”を提供する存在として重宝されたのです。
隠し要素や遊び心
アリスソフト作品らしく、本作にもいくつかの“ちょっとした隠し要素”が用意されています。たとえば、特定の操作を繰り返すことでスタッフコメントが見られたり、通常では選ばないであろう選択肢を選ぶことで隠れイベントが発生したりします。 これらは攻略本に載るほどの大きな秘密ではありませんが、「ユーザーが自分で発見する楽しみ」を大切にした設計です。実際、当時のファン同士の交流では「この場面でこんなイベントが出た」という情報交換が盛んに行われ、コミュニティを盛り上げる一因にもなりました。
裏技や小ネタ
いわゆる“裏技”と呼べるものは少ないものの、細かい小ネタは数多く存在します。例えば、特定のタイミングでキーを連打するとキャラクターのセリフが変化する、といったものです。アリスソフトはこうした遊び心を仕込むのが得意であり、ユーザーの探究心をくすぐりました。 こうした小ネタは雑誌記事や口コミを通じて広まり、プレイヤーが「自分だけが見つけた」と思える体験を提供しました。攻略そのものが“情報共有の楽しみ”へと発展していた点も、本作の魅力的な攻略要素のひとつです。
効率的なプレイ方法
もし効率よく全タイトルを楽しみたいなら、まずは短時間で終わる作品から着手するのがおすすめです。軽く遊べる作品で雰囲気を掴み、その後にアクション性や選択肢分岐があるゲームへ進めば、全体をスムーズに制覇できます。 また、どのタイトルもセーブやリトライが容易なため「気軽に試行錯誤する」姿勢が重要です。特に分岐型アドベンチャーは、セーブを活用して全ての選択肢を試すことで隠れイベントを網羅できます。
まとめ:攻略より体験重視
総じて『ALICEの館2』の攻略は、テクニックや忍耐を試される類のものではなく、むしろ「遊びの幅をいかに楽しむか」が本質です。完全攻略を目指すよりも、ちょっとした発見や意外性を楽しむプレイスタイルこそが、この作品を最大限に味わう方法でしょう。攻略を終えた後には、「アリスソフトというブランドの遊び心に触れた」という充足感が残るはずです。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーの第一印象
1992年に『ALICEの館2』が発売されたとき、多くのプレイヤーは「豪華なおまけ集」というイメージを強く持ちました。アリスソフトはそれまでに『Rance III -リーザス陥落-』などを通じてブランド力を確立していたため、ファンの間では「本編の合間に楽しめるユーモラスな短編集」という位置づけで受け止められました。 特にPC-9801ユーザーからは「価格以上に内容が詰まっている」という肯定的な感想が多く寄せられ、遊びごたえよりも“サービス精神の象徴”として評価されることが多かったのです。
ファン層に与えたインパクト
『ALICEの館2』はアリスソフトのファン層に強いインパクトを残しました。収録作品の中で特に注目されたのは、やはり『なぐりまくりたわぁ』でした。『Rance』シリーズの人気キャラクターを主役に据えたこの短編は、ファンにとって「キャラクターの別側面を知ることができる」特別な機会であり、スピンオフ的な存在感を持っていました。 また、「婦警さんDA」や「おかゆフィーバーの逆襲」といった突拍子もないタイトルがもたらすユーモアも、当時のゲーマーにとって斬新でした。従来の真面目なストーリー展開に慣れたユーザーが、「こういう遊び方もあるのか」と驚かされたのです。
メディアや雑誌での評価
当時のPCゲーム雑誌では『ALICEの館2』を「軽快でユーモラスな作品」と紹介する記事が多く見られました。レビューでは、ボリュームを追求する大作ではないが、複数の小品が集約されることで「結果的に長く楽しめる構成になっている」といった指摘が目立ちました。 加えて、FM TOWNS版でのCD-ROM採用はメディアから高く評価されました。CDによる音声や演出の追加は「今後のパソコンゲームの可能性を示す試み」とされ、単なるバラエティパックにとどまらない実験的な価値が見いだされていたのです。
プレイヤー同士の口コミと広がり
口コミによる評価も重要でした。インターネットが普及していない当時は、友人同士の貸し借りや同人誌、ユーザーの集いといった場で情報が広まっていました。その中で「隠しイベントを見つけた」「こんなセリフがあった」といった小さな発見が語り合われ、コミュニティを盛り上げるきっかけとなりました。 とりわけ「おかゆフィーバーの逆襲」の奇抜さは話題を呼び、「攻略するより笑って楽しむ作品」として記憶に残ったプレイヤーも多かったのです。こうした“情報を共有する楽しみ”は、作品の人気を後押ししました。
長期的な評価とシリーズ内での位置づけ
発売から年月を経ても、『ALICEの館2』はシリーズの中で印象的な存在として語られ続けています。その理由は「ファンと制作者をつなぐ役割を担った」点にあります。長編RPGやシミュレーションがメインの時代に、短編の寄せ集めでありながらファンが愛着を持ち続けるのは、それだけブランドに親密さを与えたからです。 後年のプレイヤーからは「アリスソフトの遊び心が凝縮された作品」「本編では見られないキャラクターの側面を知ることができる貴重な一作」と再評価され、現在でもシリーズを語るうえで外せないタイトルとされています。
批判的な意見も存在した
もちろん評価がすべて肯定的だったわけではありません。一部のユーザーからは「内容が軽すぎる」「大作と比べると物足りない」という指摘も見られました。特にアクション性を求めるプレイヤーにとっては、収録作品の大半がユーモア重視であるため、ゲーム性そのものには物足りなさを感じたケースもあったのです。 しかし、そうした批判も「おまけ集的な作品」という前提を理解すれば大きな問題にはならず、むしろ「軽快さを楽しむためのもの」と受け止められることが多かったといえます。
まとめ:ユーザーとブランドの距離を縮めた一作
総合的に見れば、『ALICEの館2』はユーザーの間で「笑える」「気軽に遊べる」「キャラクターが魅力的」といった肯定的な感想が多数を占め、雑誌メディアからも「実験的でユーモラスな作品」と高く評価されました。批判的な声もありましたが、それ以上に「ユーザーとブランドをつなげる」役割を果たした点が大きな功績です。 この作品が残した評価は、単なるゲームの範疇を超えて「アリスソフトというブランドそのものの姿勢」を体現した証といえるでしょう。
■■■■ 良かったところ
キャラクター性の魅力を堪能できる
『ALICEの館2』の大きな長所のひとつは、やはりアリスソフトが誇るキャラクターたちの存在感です。『Rance III』から派生したパットンを主人公に据えた短編や、個性的でコミカルなキャラクターが織りなすストーリーは、多くのプレイヤーに「これこそアリスソフト」と思わせる要素でした。本編では見られないユーモラスな姿や、サブキャラクターの活躍を垣間見ることができる点が、ファンにとって非常に嬉しい要素となりました。
多彩なミニゲームのバリエーション
1本のゲームに複数の短編や小ネタを収録した形式は、ユーザーに「飽きのこない体験」を提供しました。アクション風、アドベンチャー風、ギャグイベント中心などジャンルが散りばめられており、次にどんな内容が出てくるのかというワクワク感が続きました。この「バリエーション豊富なおもちゃ箱感覚」こそが良かった点のひとつであり、当時のゲーム市場でも非常にユニークな立ち位置を確立していました。
遊び心とユーモアに満ちた構成
本作はシリアスさよりも笑いを優先しており、その遊び心がプレイヤーにとって心地よいものでした。真剣に取り組むよりも、肩の力を抜いて“笑いながら遊ぶ”ことができた点は、1990年代初頭のPCゲームの中でも珍しい魅力でした。ギャグや小ネタの積み重ねは、「次はどんな奇抜なアイデアが出てくるのか」と期待させる力を持っていました。
短時間で楽しめる気軽さ
『ALICEの館2』はどのタイトルも短時間でクリアできるように設計されており、忙しい日常の合間でも気軽に楽しめました。当時のPCゲームは長編化・複雑化が進んでいましたが、本作はあえて「軽量・短時間プレイ」という方向性を選び、それがプレイヤーの評価につながりました。「ちょっとした空き時間に遊べる」という手軽さは、良かった点として繰り返し語られる部分です。
ファンサービス的要素が豊富
スタッフコメントや遊び心のある演出、既存作品との関連性など、ファンサービス的な要素が多く盛り込まれていました。ユーザーは「開発者がこちらに向けて話しかけている」と感じることができ、作品により強い愛着を持つようになりました。こうした作りは、ファンコミュニティの形成に大きく貢献し、アリスソフトのブランドを支える柱の一つとなったのです。
価格以上の満足感
複数の短編が詰め込まれたボリューム感は、プレイヤーに「コストパフォーマンスが高い」と感じさせました。特にFM TOWNS版では過去作品『あぶない天狗伝説』の収録もあり、「一枚で二度三度おいしい」という得した感覚を得られたユーザーも多かったのです。この「お得感」は購入者の満足度を大きく引き上げ、良かった点として記憶に残っています。
シリーズの懐を広げた存在
『ALICEの館2』は、単なる“おまけ集”にとどまらず、アリスソフトのブランド力を高める役割も果たしました。キャラクターを別の角度から見せることで、シリーズ全体の世界観に厚みを加えたのです。こうした「広がりを見せる効果」も、良かったところとして高く評価されています。
まとめ:軽妙さと多様性の勝利
総合的に見て、『ALICEの館2』の良かったところは「キャラクターの魅力」「遊び心」「多様性」「手軽さ」に集約されます。これらが組み合わさることで、単なる小品集ではなく「ファンの心を掴む特別な作品」として位置づけられました。後年振り返ったときに、多くのユーザーが「笑いと親近感をくれたタイトル」と語るのは、まさにこうした良点が強く印象に残っているからでしょう。
■■■■ 悪かったところ
ボリューム不足を感じるユーザーもいた
『ALICEの館2』は多彩な短編を収録した“おまけ集”的作品であるがゆえに、長時間のプレイや濃厚な物語を期待していたプレイヤーには物足りなさを感じさせる部分がありました。一本一本の短編は短時間で終わる設計であるため、「気軽さ」を魅力と捉える人も多かった一方で、「もっとじっくり遊びたかった」「物語性を深く味わいたかった」という声も当時のファンから上がっています。
ゲーム性の薄さ
収録タイトルの多くはギャグやネタ重視であり、ゲームとしての奥深さや戦略性を期待すると肩透かしを食らう内容でした。例えば、アクション的な操作を要求する作品もあるものの、本格的な攻略性があるわけではなく、「遊び終わったらすぐに満足してしまう」という短命な印象を抱いたユーザーも少なくありませんでした。これは“ライトに遊ぶ”という狙いの裏返しでもあります。
作品間の完成度にバラつきがある
複数の短編をまとめた形式ゆえに、それぞれの完成度に差が出てしまったのも否めない点です。ある作品は「しっかりと作り込まれていて面白い」と評価される一方で、別の作品は「小ネタの域を出ていない」「開発途中の試作品のように感じた」と捉えられることもありました。この不均一さは、本作を大満足と評価できなかった要因のひとつです。
本編とのつながりを求めたファンの不満
『Rance』シリーズのキャラクターが登場することでファンの期待は大きく膨らみましたが、実際には“外伝的なお遊び”程度にとどまっており、「もう少し本編につながる物語が欲しかった」という声もありました。ファン心理としては「番外編として楽しめたが、せっかくなら本筋を補完するエピソードが欲しい」と感じられたわけです。これはブランド人気が高まっていたからこそ出てきた不満とも言えるでしょう。
プラットフォーム間の差異による不公平感
PC-9801版やX68000版に比べ、FM TOWNS版はCD-ROMの特性を活かした追加要素がありました。そのため「TOWNS版は豪華だが、他機種では物足りない」という印象を持ったユーザーも存在しました。当時は機種ごとに仕様差が出るのは珍しくなかったとはいえ、複数機種に展開していたからこそ「同じ作品を買ったのに体験が違う」ことへの不満は一定数見られました。
当時の市場環境との比較で埋もれる部分
1992年はPCゲームに限らず、コンシューマー市場でも大作が次々と登場した年でした。スーパーファミコンでは長編RPGや派手なアクションゲームが人気を博しており、その流れと比較すると『ALICEの館2』は“軽い小品集”という性質から、どうしてもインパクトの弱さがありました。特に新規プレイヤーにとっては「このタイトルだけで満足する」というより、あくまでアリスソフトのファン向けという印象に留まった可能性があります。
繰り返し遊ぶモチベーションの弱さ
短編中心であるがゆえに、一度遊んでしまうと“再プレイ欲求”はあまり強く生まれないという弱点もありました。隠しイベントや小ネタはあるものの、それを探すほどの動機があるかと問われれば、すべてのユーザーが熱心になるわけではありません。「笑って終わり」という感覚で満足してしまうユーザーが多かったのは、本作のライトな設計が招いた宿命ともいえます。
まとめ:魅力と引き換えに生じた弱点
『ALICEの館2』はファンサービスや笑いを重視した作品であるがゆえに、「軽快さ」という強みと引き換えに「ボリューム不足」「ゲーム性の薄さ」「再プレイ性の低さ」といった弱点も抱えていました。しかし、これらの悪かった点も“本作が持つ実験的な性質の裏側”であり、必ずしも致命的な欠点とはいえません。むしろ、そうした不満点があったからこそ「次回作での改善」に期待が寄せられ、シリーズが続いていくモチベーションにつながったと見ることもできます。
[game-6]■ 好きなキャラクター
パットン ― 本作を象徴する存在
『ALICEの館2』を語るうえで欠かせないのが、短編『なぐりまくりたわぁ』の主人公に抜擢されたパットンです。彼は本来『Rance III -リーザス陥落-』で登場したキャラクターで、堂々とした風貌と豪快な性格から人気を博しました。本作ではその彼が単独で主役を務めることになり、多くのファンに新鮮な驚きを与えました。 プレイヤーからは「豪快なキャラクターがギャグ要素にぴったり」「本編ではシリアスな側面もあったが、ここではおちゃらけた面が見られて楽しい」といった感想が多く寄せられています。彼の存在は、本作が“キャラクターの新しい魅力を掘り下げる場”であることを象徴しているといえるでしょう。
婦警さん ― コメディ色を強調するヒロイン
『婦警さんDA』に登場する婦警キャラクターも、プレイヤーの記憶に強く残っています。正義感に燃える婦警という設定でありながら、ストーリーはどこかコミカルに展開し、真面目さとユーモアのギャップが魅力を引き出しました。 ファンの間では「厳格さとドタバタ感が同居していて面白い」「選択肢によっては突拍子もない反応を見せるところが好き」と評価され、アリスソフトらしい“ギャップの笑い”を体現したキャラクターとして高く評価されました。
おかゆフィーバー関連キャラ ― ネタ枠の愛され者
『おかゆフィーバーの逆襲』に登場するキャラクターたちは、真剣に攻略する対象というより“ネタを提供する存在”として愛されました。中でも奇抜な言動やシュールな演出でプレイヤーを笑わせる役回りのキャラは、当時のユーザーに「くだらないけれど忘れられない」と強烈な印象を残しました。 「ネタキャラなのに妙に愛着が湧く」「一度見たら忘れられない存在感」といった感想もあり、これらはまさに“ギャグを楽しむゲーム”における象徴的存在でした。
スタッフの影を感じるキャラクターたち
『ALICEの館2』に収録された短編には、明確にキャラクター化された登場人物だけでなく、開発スタッフの遊び心を反映した“半ばメタ的な存在”も見受けられます。制作者のコメントや、キャラクターがプレイヤーに語りかけるような演出がしばしば盛り込まれており、ファンはそれを“キャラクターの一部”として受け止めていました。 この点については「スタッフの人柄がキャラを通じて感じられるのが面白い」「ただのゲームキャラではなく、開発者と直接やり取りしているような感覚になる」という評価が寄せられていました。
その他のサブキャラクターたち
各短編にはメインキャラクターだけでなく、脇を固めるサブキャラクターたちも登場し、彼らの存在が作品全体の彩りを豊かにしました。プレイヤーの中には「むしろサブキャラのクセの強さが忘れられない」という意見もあり、アリスソフトらしい“群像的な笑い”を支える役割を果たしていました。こうしたサブキャラたちがいたからこそ、短編が小粒であっても記憶に残るものとなったのです。
ファンによる好きなキャラ投票や交流
当時の雑誌や同人誌では、ファンが自発的に「お気に入りキャラクター」を語り合う場が設けられることがありました。その中で『ALICEの館2』の登場キャラも話題に上がり、特にパットンや婦警さんといった個性派が人気を集めました。ファン同士の交流の場でキャラクターの魅力が語られることで、彼らはゲームを超えて“アリスソフトの顔”の一部となっていきました。
まとめ:愛嬌とギャップが支持された
『ALICEの館2』のキャラクター人気は、ただ単にデザインや設定が良かったからではなく、「ギャップ」「遊び心」「笑い」を通じてユーザーに親近感を抱かせた点にありました。豪快なパットン、真面目さとドタバタを兼ね備えた婦警さん、そしてネタ枠でありながら愛されたおかゆフィーバー関連キャラ。これらが揃うことで、本作はファンにとって忘れがたいキャラクター群像を築き上げたのです。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
PC-9801版 ― 当時の標準機での体験
1992年の日本のPCゲーム市場において、PC-9801シリーズは“事実上のスタンダード”でした。『ALICEの館2』も当然この機種を中心に開発され、最も安定した環境で遊ぶことができました。 グラフィック表現は16色を基本としたEGA相当の画面で、解像度も高くはありませんでしたが、当時のユーザーにとっては見慣れたスタイルであり、不自由を感じることは少なかったといえます。またテキスト描画のスピードや操作感も安定しており、「普及機だからこそ安心して楽しめる」というメリットがありました。 一方で、サウンド面はFM音源ボードの有無によって体験が変化しました。FM音源を搭載していないユーザーはシンプルなBEEP音中心となり、フルに楽しむには周辺機器の投資が必要でした。この差は当時のユーザー間でよく話題になった要素です。
X68000版 ― 高性能を活かした演出
X68000版は「グラフィックの鮮やかさ」と「処理性能の高さ」によって、他機種よりも洗練された印象を与えました。特にアクション要素を含む『なぐりまくりたわぁ』では、スムーズな動作と滑らかなスクロールが評価されました。 また、解像度や発色能力の違いから、同じシーンでも「より色鮮やかで見栄えが良い」と評するプレイヤーも多く、X68000ユーザーにとっては自分のマシンの性能を誇る材料になったとも言われています。 ただし普及台数はPC-9801に比べて少なかったため、体験できるプレイヤーの母数が限定的で、雑誌などでも「一部のユーザーがうらやむ環境」として紹介されることがありました。
FM TOWNS版 ― CD-ROMによる拡張性
FM TOWNS版『ALICEの館2 CD』は、当時の最新技術であるCD-ROMを採用した点で特別な存在でした。これにより、音楽や演出の質が格段に向上し、BGMもCD-DA音源によって生音に近い迫力が再生可能となりました。ユーザーからは「PC-9801版やX68000版とは次元の違う豪華さ」と評されることも多く、まさにハイエンド機ならではの贅沢な体験を提供しました。 さらに、特典的要素として『あぶない天狗伝説』といった過去作品が同梱され、ファンにとっては“お得なパッケージ”として価値を高めていました。TOWNSユーザーは他機種ユーザーに比べ少数派であったものの、「持っていること自体が誇らしい」と感じるほどの優越感を与えたバージョンでした。
機種ごとの差異が生んだ議論
複数のプラットフォームに展開したことは、ユーザー間でしばしば議論を呼びました。「やはりTOWNS版が最強」と評価する声がある一方で、「PC-9801版こそが本来の基準」「X68000版の滑らかさが一番」といった主張もあり、ゲームの体験を超えて“マシンへの愛着”を語り合う場面が見られました。 こうした機種ごとの差は当時のPCゲーム文化の特色でもあり、ユーザー同士の会話を盛り上げる要素になったともいえます。
現代における評価
現代のレトロゲーム愛好家から見ると、これらの機種ごとの違いは「文化的価値」として大きな意味を持っています。同じ『ALICEの館2』であっても、画面の色合いや音楽の迫力が機種ごとに異なるため、コレクターや研究者にとっては比較の対象として面白いポイントとなっています。 また、エミュレーション技術が発達した今では、当時の違いを再現して遊ぶことも可能となり、「自分はあの頃PC-9801で遊んでいたけれど、TOWNS版はこんなに豪華だったのか」と驚く体験をする人も少なくありません。
まとめ:同じ作品でも体験は三者三様
『ALICEの館2』は、PC-9801、X68000、FM TOWNSという三つの異なる環境で展開されたことで、同じタイトルでありながら体験の仕方が大きく異なるという特徴を持っていました。 標準的で安心感のあるPC-9801版、性能を活かして華やかさを増したX68000版、そして豪華さと付加価値を兼ね備えたFM TOWNS版。それぞれが異なる良さと限界を持ち、結果としてユーザー間で語り継がれる多様な魅力を生み出したのです。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1992年前後のPCゲーム市場の背景
『ALICEの館2』が発売された1992年7月は、PCゲーム市場にとって変化の時期でした。NECのPC-9801が圧倒的シェアを誇り、ビジネス用からホビーユースまで幅広く利用されていた一方で、X68000やFM TOWNSのような高性能機もマニア層に人気を博していました。ジャンル的にはアドベンチャーやシミュレーション、アダルト要素を含む美少女ゲームが大きな比重を占めており、後に“黄金期”と呼ばれる時代へと突入していく直前でした。 ここでは『ALICEの館2』と同時期に話題を集めた代表的なPCゲームを10本紹介し、その内容や特徴を振り返ってみましょう。
★『同級生』
:エルフ/1992年/価格8,800円 美少女ゲーム史に革命を起こしたとされる作品。学園を舞台に、限られた日数でヒロインたちと交流し、恋愛関係を築くシステムは画期的でした。シナリオ分岐とマルチエンディングの完成度は非常に高く、後の恋愛シミュレーションの礎を築いたと言われています。
★『Rance IV -教団の遺産-』
:アリスソフト/1993年直前開発中(企画発表) 『ALICEの館2』と近しい時期に告知された人気シリーズの次回作。発売は翌年ながら、この頃すでに雑誌などで大きく話題にされていました。シミュレーション要素を取り入れた大作であり、アリスソフトの代表格として多くのユーザーが期待していました。
★『DESIRE』
:シーズウェア/1992年/価格8,800円 シーズウェアが送り出したアダルトADVで、複数視点を用いたドラマティックなシナリオ構成が特徴。推理小説的なサスペンス展開と、美少女ゲームの融合がユーザーに新鮮な体験をもたらしました。
★『Dragon Knight III』
:エルフ/1991年末~1992年人気継続/価格8,800円 “ドラゴンナイト”シリーズの第三作で、RPG要素とアドベンチャー要素を融合させた作品。1991年末のリリースながら1992年も強い人気を維持し、美少女RPGというジャンルの定番を築きました。
★『天使たちの午後III』
:ジャスト/1992年/価格7,800円 美少女ゲームの黎明期から続くシリーズの三作目。比較的軽めのアドベンチャーでありながら、キャラクターの心理描写に重点が置かれており、根強い人気を誇りました。
★『麻雀幻想曲II』
:Nichibutsu(日本物産)/1992年/価格6,800円 当時人気を博した麻雀+美少女要素を融合したタイトルのひとつ。ルール自体はシンプルながら、勝利することで展開される演出やキャラクター性が話題となり、ライトユーザーを中心に支持されました。
★『YU-NO 開発前史(菅野作品群)』
:エルフ/1992年企画段階 『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』は1996年発売ですが、1992年頃にはすでに菅野ひろゆきがシナリオ構築の基盤を作り始めていた時期です。当時の雑誌記事で「壮大な構想がある」と断片的に語られ、後の名作を予感させていました。
★『雀偵物語3』
:JAST/1992年/価格7,800円 探偵ストーリーに麻雀を組み合わせたユニークなタイトル。ゲーム進行の中で麻雀対局がストーリーのキーとなり、“ただの脱衣麻雀”から一歩進んだ内容が支持を集めました。
★『カスタム隷奴』
:Kiss/1992年/価格8,800円 のちに長くシリーズ化されることになる“KISS”ブランドの出発点のひとつ。育成システムや調教要素を取り入れ、他の美少女ゲームとは一線を画した存在として注目されました。
★『宇宙英雄物語』
:グローディア/1992年/価格9,800円 PCだけでなく家庭用にも展開されたタイトルで、壮大なスペースオペラ的世界観とアドベンチャー形式を融合。PCゲーマーに「一般ゲーム機とは異なるストーリーテリング」を見せつけた作品でした。
市場全体の動向と『ALICEの館2』の位置づけ
これらのタイトルと比べると、『ALICEの館2』は“軽量級のおまけ集”として独自の立ち位置を築いていました。大作やシナリオ重視の作品が増えていた時代にあって、「笑い」「サービス精神」「短時間で遊べる気軽さ」を前面に押し出した点は非常に個性的であり、逆にそれが魅力として受け入れられたのです。 つまり『ALICEの館2』は、同時期に登場した大作群と競合するのではなく、「息抜きの一作」としてファンの生活に寄り添う役割を担っていたといえるでしょう。
[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 英雄伝説IV 朱紅い雫[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004170m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチ/5インチソフト RPGツクール -Dante98-(ログインDISK&BOOKシリーズ)[3.5インチ/5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006306m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト [説明書のみ]ギゼ! XIX[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8590/155030101m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト カード型データベース アシストカード[アシストカルク体験版付][3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8922/155009819m.jpg?_ex=128x128)