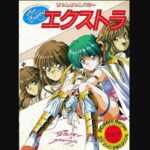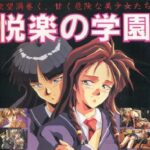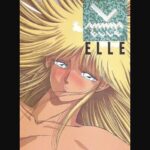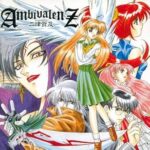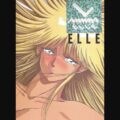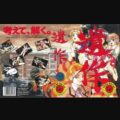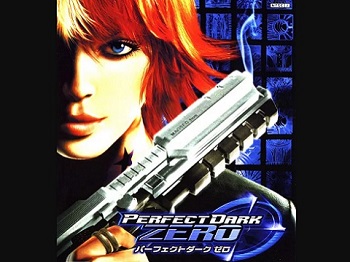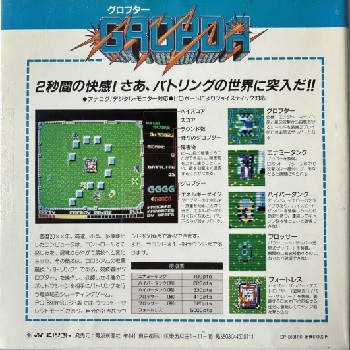ANGEL完全版 超合本版【電子書籍】[ 遊人 ]




 評価 4
評価 4【発売】:カクテルソフト
【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS
【発売日】:1993年10月1日
【ジャンル】:アドベンチャーゲーム
■ 概要
作品の基本データと全体像
1993年にカクテルソフトから発売された『ANGEL』は、PC-9801シリーズとFM TOWNS向けにリリースされた18禁アドベンチャーゲームで、当時のPC美少女ゲーム市場でもひときわ存在感のあったタイトルです。ブランド表記上はAVG(アドベンチャーゲーム)に分類され、コマンド選択式ADVを基盤にしつつ、シナリオ分岐ノベルやミニゲーム的な要素を組み合わせた構成になっており、「1本で3種類のゲームを遊べる」という売り文句で知られています。
対応機種は、PC-9801VM以降をターゲットにしたフロッピーディスク版と、FM TOWNS用のCD-ROM版という2系統。PC-98版は数枚組FDでインストールして遊ぶごく一般的な98ソフトのスタイルで、FM TOWNS版はCD-DAによる音楽再生を活かした豪華なBGM・効果音再生を特徴としていました。
価格帯も当時のアダルトPCゲームとして標準的な8,000円台に設定されており、雑誌広告などでも「遊人原作」「3つのゲームが1本に」というキャッチコピーが強く推されていました。後年には内容を凝縮した続編的位置づけの『濃縮ANGEL・120%』も登場し、この作品が一定の人気と話題性を持っていたことがうかがえます。
原作漫画『ANGEL』とゲーム化の背景
本作の最大の特徴は、成人向け漫画家・遊人の代表作のひとつである『ANGEL』をベースにしている点です。遊人は80〜90年代にかけて、ややコミカルでポップなタッチと、メリハリの効いたデフォルメ表現で人気を博した作家で、同じく成人向け漫画を原作としたゲーム『校内写生』とのコラボレーションもPCゲームファンの間でよく知られていました。『ANGEL』のゲーム版では、その「遊人らしさ」とも言える、軽妙な会話劇やテンポの良い展開、感情の起伏が大きく描かれるドラマ性が前面に押し出されています。
ゲーム版のキャッチコピーにも「遊人と『校内写生』スタッフが再結集」といった文言が使われており、単に人気漫画のキャラをゲームに落とし込んだだけではなく、原作の空気感を知り尽くした制作陣が改めてタッグを組み、PC向けアドベンチャーとして再構築する――という企画意図がうかがえます。プレイヤーは、原作でおなじみのヒロインたちと再び出会いながらも、ゲームオリジナルのシチュエーションや視点によって、漫画とは少し違った物語体験を味わえるようになっています。
もっとも、本作はあくまで成人向けタイトルであり、ストーリーの根幹には恋愛や男女関係が据えられているものの、ここでは具体的な描写には踏み込まず、「原作のテイストを大切にした恋愛ドラマ主体のアドベンチャー」として捉えるとイメージしやすいでしょう。プレイヤーは主人公視点で各ヒロインと関係を深めつつ、選択肢によって展開が変化していく、王道のテキストADV型ゲームとなっています。
3本立てパッケージという構成の特徴
『ANGEL』が当時のタイトルの中でも異彩を放っていたポイントが、「3種類のまったく違うゲームを1パッケージに収めた」という構造です。パッケージや公式紹介文でも強調されている通り、本作は単一の長編アドベンチャーではなく、性格の異なる3つのシナリオ(もしくはモード)が収録されたオムニバス的な作りになっています。
一本目は、テキストを読みながら画面下部のコマンドを選んで進行させていく、いわゆるコマンド選択式アドベンチャー。マップ移動や会話コマンドを駆使しながら、ヒロインの信頼を得たり、イベントフラグを立てていくオーソドックスな形式です。二本目は、よりノベルゲーム寄りの「シナリオ分岐型」スタイルで、読み物としての密度を高めつつ、要所要所で提示される選択肢によってエンディングが分岐する構造になっています。三本目は、短編エピソードやゲーム的な要素に比重を置いた構成で、ちょっとしたミニゲーム的な操作やテンポの良いイベント連打を楽しめる作りです。
この3本立てにより、プレイヤーの遊び方はかなり自由度が高く、「まずは軽めのシナリオから試してみる」「気になったヒロインが登場するパートから攻略する」といった楽しみ方も可能です。当時のアダルトADVは1本筋の長編が多い中で、オムニバス形式を採りつつ、それぞれゲーム性の異なる3つのモードを用意した点は、企画としてもチャレンジングな試みだったと言えるでしょう。
PC-9801版とFM TOWNS版の違い(概要レベル)
PC-9801版『ANGEL』は、フロッピーディスク数枚組で提供される、ごく一般的なPC-98向けアドベンチャーゲームの形態です。グラフィックは当時の98としては標準的な解像度と色数ながら、遊人の原作イラストを意識したキャラクターデザインと、PC-98特有のドット表現でヒロインたちを鮮やかに再現しています。また、FM音源によるBGMも作品の雰囲気づくりに一役買っており、静かな日常パートからドラマチックなイベントシーンまで、曲調の変化が物語の起伏を補強しています。
一方、FM TOWNS版はCD-ROMメディアを活かした構成になっており、CD-DAによる高音質なBGM再生や、機種によっては読み込みの速さを利用したテンポの良い画面切り替えが特徴です。グラフィック面でも、機種性能を活かした色数の増加や、よりなめらかなグラデーション表現などが期待でき、同じシーンでも「98版とTOWNS版では受ける印象が少し違う」と語るユーザーもいました。
ただし、ゲームの根幹となるテキストやシナリオ構造は共通しているため、「どちらか片方だけ遊んでも物語としては十分楽しめる」作りです。そのうえで、98版ならではのレトロPCらしい雰囲気、TOWNS版ならではのCD-ROMならではのリッチなBGMといった、それぞれの良さを比較する楽しみもありました。
当時のPCゲーム市場における『ANGEL』のポジション
1993年前後は、PC-9801向けの美少女ゲームが大きく進化していった時期で、多くのブランドがADVやSLG、RPGなど多彩なジャンルに挑戦していました。カクテルソフト自身も『Can Can Bunny』シリーズをはじめとした作品で知名度を高めており、『ANGEL』はそうした流れの中で「人気漫画原作×3本立て構成×成人向けADV」という、かなり目を引く組み合わせで登場します。
当時のユーザーにとって、雑誌広告の段階から「遊人原作のあの作品がゲームに」「3つのゲームを同時に楽しめる」というコピーは強いインパクトがありました。後に『濃縮ANGEL・120%』が発売されたことからもわかるように、本作は単発で終わるタイトルではなく、カクテルソフトのラインナップの中でも重要なポジションを占める作品として扱われていたことがうかがえます。
また、『ANGEL』のように漫画原作を土台としつつ、ゲームとしての構造を工夫したタイトルは、その後のアダルトゲームシーンにも少なからず影響を与えました。原作ファンを取り込むだけでなく、ゲームから入って漫画に興味を持つプレイヤーもいたとされ、「メディアミックス的な展開の初期例」として振り返られることもあります。
このように、『ANGEL』は単に刺激的な表現を盛り込んだだけの作品ではなく、原作漫画の人気とPCアドベンチャーゲームの技術的進化がうまく結びついた、1993年前後のPC美少女ゲームシーンを語るうえで外せないタイトルのひとつと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
原作テイストを活かした世界観とストーリーの魅力
『ANGEL』の一番の魅力は、やはり遊人原作ならではの世界観と、それをPCゲームとして再構築したストーリーテリングにあります。舞台となるのは、どこか現実と地続きでありながら、漫画ならではの誇張やドラマ性が色濃く反映された学園・日常空間です。プレイヤーは主人公の視点を通じて、ヒロインたちとの出会いやすれ違い、恋愛感情が芽生えていく過程を体験していきますが、その描かれ方が「一気に燃え上がるような恋」と「だらだらと続く日常」の両方をうまく取り込んでいるのが特徴です。 原作マンガは、軽妙なギャグと大人びたムードが同居する独特の作風で人気を博していましたが、ゲーム版でもその雰囲気は健在です。シリアスな場面では感情のぶつかり合いがしっかり描かれ、逆に日常パートでは肩の力が抜けたテンポの良い掛け合いが続きます。こうした緩急があるおかげで、単なる恋愛ADVにとどまらない「ドラマを追っている感覚」が強く、プレイヤーは自然と登場人物たちの感情の揺れに引き込まれていきます。 また、原作を読んでいなくてもストーリーは理解できるよう構成されている一方で、原作ファンが思わずニヤリとするような要素や雰囲気も随所に散りばめられており、「漫画とゲーム、どちらから入っても楽しめる」バランス感覚も魅力のひとつです。原作を知っていれば「あのキャラがこういう形で動くのか」といった楽しみが生まれ、初見であれば「この世界観、原作も読んでみたい」と逆に興味が広がる、そんな相互補完的な構造を持っています。
3本立て構成が生むボリューム感と遊びごたえ
『ANGEL』を語るうえで外せないのが、1本のパッケージに3種類のゲームスタイルを詰め込んだ「3本立て構成」です。どれも同じタイトルを冠しながら、シナリオの雰囲気やゲームシステムの比重が微妙に異なっており、単純にテキスト量が多いだけではない“遊びの幅”が確保されています。 ひとつめのモードは、昔ながらのコマンド選択式アドベンチャーとしての味わいが強いパートで、マップ移動や行動選択によってイベントを探り当てていくスタイルです。「誰に会いに行くのか」「どの場所を調べるのか」といったプレイヤーの選択が、フラグ発生やルート分岐に結びつくため、ノベルゲーム的な“読み進めるだけ”の感覚とはまた違う攻略の楽しさがあります。 ふたつめのモードは、物語性の濃さを前面に出したシナリオ重視型で、プレイヤーはテキストを読み進めながら、要所要所で現れる選択肢によってエンディングを変化させていきます。こちらは「一気に読みたい」「ドラマをじっくり味わいたい」というニーズに応える構成で、読み物としての満足感が高いのが特徴です。 そして、みっつめのモードはテンポ良くイベントが次々と発生する構造で、短時間で遊べるシーンや、ちょっとしたゲーム的アクセントを含んだ内容が中心。大作RPGのように何十時間も遊ぶタイプではありませんが、3つのモードを行き来しながら全ルートを埋めていくと、当時のPC-98/FM TOWNS用ソフトとしてはかなりのボリューム感があります。ひとつの世界観・キャラクターをさまざまなアプローチで味わえるため、「1本で3度おいしい」というキャッチコピーも決して大げさではない、という感覚をプレイヤーに与えてくれます。
キャラクター表現とビジュアル面の魅力
ビジュアル面も、『ANGEL』の魅力を語るうえで重要なポイントです。原作がもともと絵柄に定評のある漫画作品であるだけに、キャラクターデザインは非常に力が入っており、PC-9801の制約あるドット絵でありながら、ヒロインたちの表情や立ち姿、しぐさが生き生きと描かれています。 立ち絵やイベントCGでは、キャラクターごとに目線や口元の表情変化が細かく描き分けられており、怒っているときの鋭い視線、困惑しているときの戸惑いがちなしぐさ、照れているときの視線の泳ぎ方など、テキストだけでは伝わりづらい感情をしっかり補完してくれます。特に、クライマックスとなるシーンや、関係性が大きく動くイベントでは、背景や構図も含めて「1枚絵として印象に残る」演出が多く、プレイし終わった後も心に残るCGがいくつも思い浮かぶ、というユーザーも少なくありません。 また、服装や髪型、体のラインの描き方など、遊人作品らしいデザインセンスが存分に活かされている点も魅力です。ヒロインたちは単に“記号的なキャラ”ではなく、個性を感じさせるファッションや表情のバリエーションがあり、「パッケージを眺めているだけでも楽しい」と言われるほどでした。 もちろん本作は大人向けタイトルであり、恋愛の先にある濃密な関係性も描かれますが、ゲームとしての面白さは決してそこだけに依存しておらず、キャラクターの感情や日常の描写を丁寧に積み上げたうえで、大人向けのムードを“仕上げ”として盛り込んでいる印象です。そのため、物語としての厚みを楽しみたいプレイヤーにも十分応えてくれます。
演出・インターフェースがもたらす没入感
『ANGEL』は、シナリオやビジュアルだけでなく、画面構成やインターフェースの作り込みによっても没入感を高めています。テキストウィンドウの配置やフォントの視認性、選択肢の出し方などが丁寧に設計されており、長時間プレイしていても疲れを感じにくい点は、当時のPC-98/FM TOWNSソフトとしては大きな強みです。 BGMも、作品の空気を支える重要な要素です。穏やかな日常シーンには柔らかいメロディ、緊張感の高まるイベントではテンポの速い曲調や不協和音を織り交ぜたフレーズが流れるなど、シーンに応じた曲の切り替えがこまめに行われます。特にFM TOWNS版ではCD-DA音源を活かしたクリアなサウンドが特徴で、画面全体から伝わる臨場感が一段と増しています。 演出面では、画面のフェードイン・フェードアウト、キャラクターの立ち絵が切り替わるタイミング、視点の変化などが巧妙に組み合わされており、プレイヤーは自然に物語の流れに乗せられていきます。シリアスな場面では一瞬の間を取ってから次のテキストを表示する、コミカルな場面ではテンポ良く台詞が連打されるなど、「読ませ方」に関する細かな配慮も光るポイントです。 ユーザーインターフェースそのものは決して派手ではありませんが、逆にボタン配置や操作体系が素直で分かりやすいため、ストーリーに集中できるというメリットにつながっています。プレイヤーは複雑なシステムを覚える必要もなく、すぐに物語世界に没頭することができる――これも『ANGEL』の魅力として見逃せない部分でしょう。
当時ならではの「大人向けPCゲーム」としての魅力
1993年前後は、PC-98を中心とした美少女ゲーム市場が大きく広がっていった時期であり、その中で『ANGEL』は「原作付き・3本立て・18禁ADV」という組み合わせで強烈な個性を放っていました。当時のプレイヤーにとって、大人向けの恋愛ゲームはまだ“特別なソフト”という感覚が強く、パッケージを購入してじっくりと物語を味わうという体験そのものがイベントに近いものでした。 『ANGEL』はそうした時代背景の中で、「ただ刺激的であれば良い」という方向には走らず、あくまでキャラクター同士の感情や関係性を軸にストーリーを展開させているため、今振り返っても人間ドラマとして楽しめる部分が多く残っています。登場人物たちが抱える悩みや葛藤、すれ違いと和解といった要素は、年代を問わず共感しやすいテーマであり、90年代のテイストを色濃く残しつつも、今遊んでも「古いけれど味がある」と感じさせる内容になっています。 さらに、原作漫画という別メディアとの結びつきも、当時としてはかなり先進的な魅力でした。現在ではアニメやマンガのゲーム化は当たり前ですが、PC-98時代の“18禁ゲーム”という枠組みの中で、本格的な原作付きタイトルを展開すること自体が新鮮で、ファンにとっては「好きな作品の世界を、自分の選択で動かせる」という体験が大きなインパクトとなったのです。 総じて『ANGEL』は、原作の魅力を活かしつつ、3本立て構成やビジュアル表現、音楽・演出など、さまざまな要素を組み合わせてひとつの作品世界を作り上げたタイトルと言えます。単に当時の話題作というだけでなく、「90年代PC美少女ゲームの空気感」を濃厚に味わえる一本として、今なお語り継がれている理由は、まさにこの総合的な魅力にあると言えるでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
基本的な進め方とプレイスタイルのイメージ
『ANGEL』の攻略を考えるうえでまず押さえておきたいのは、「1本の大作を1周で遊び切る」というよりも、「3つのモードを行き来しながら、少しずつ世界を掘り下げていく」タイプのゲームだという点です。いきなり全ヒロインのエンディングやイベントを網羅しようとするより、最初の周回は「流れをつかむ」「どんなキャラクターがいて、どのような雰囲気の物語なのかを知る」と割り切るのが、精神的にもプレイ時間的にも負担が少なくて済みます。特に初回は気になったモードをひとつ選び、素直にそのままラストまで進めてしまいましょう。分岐やフラグの立ち方がなんとなく掴めてくると、「次はこのタイミングで別の選択を試してみよう」「このキャラを優先的に追いかけてみよう」といった方針が立てやすくなります。 ADVの攻略に共通するコツとして、こまめなセーブも非常に重要です。場面転換の前、選択肢が出る直前、特定のキャラクターと会話が盛り上がっているタイミングなど、後で分岐を変えてやり直したくなるポイントは多々あります。セーブ枠をいくつかのキャラクター用・ルート用に分けて管理しておくと、「このデータからはヒロインA狙い」「こちらは別のヒロイン狙い」と整理しやすくなり、周回を重ねても混乱しにくくなります。 また、3モードを遊ぶ順番にもある程度セオリーがあります。通常は、システム的にシンプルで物語を追いやすいモードから着手し、その後でコマンド選択式の探索要素が強いモードへ移ると、世界観の理解が進んだ状態でフラグ探しができるので効率的です。物語の全体像を一度把握しておくと、「このタイミングでこの場所に行けばイベントが起こりそうだ」といった予測も立てやすく、攻略がぐっとスムーズになります。
ルート分岐・イベント回収の考え方とコツ
『ANGEL』で複数のエンディングやイベントを見ていくうえで鍵になるのが、「特定のヒロインに対する行動の集中」と「時間・場所の選び方」です。テキストADVではよくある仕組みですが、同じ日時の中でも、どこへ行き誰と会うかによって、その後の展開が変化します。1周目は気の向くままに選んでしまって構いませんが、2周目以降は「この周はヒロインXを最優先」「この周ではYとの関係を深める」といった形で、ターゲットを絞って動くのが効率的です。 具体的には、登校・放課後・休日など、プレイヤーが行動を選べるフェイズで、狙ったヒロインが登場しそうな場所を優先的に訪問するのが基本的な戦略になります。同じ場所に何度も通うことで発生するイベントもあるため、「一度行って何も起きなかったから終わり」と判断せず、日を改めて再訪してみる姿勢が重要です。また、会話の途中で出てくる選択肢も、単なる好感度の上下だけでなく、フラグON/OFFに関わっている場合がありますので、違う選択を試す場合には、先ほど述べたこまめなセーブが役に立ちます。 イベントCGや特定のエンディングをコンプリートしたい場合は、メモを取りながら進めると管理が楽になります。「どの選択肢を選んだときにどんなイベントが起きたか」「どのタイミングで別のヒロインルートに分岐したか」を簡単に記録しておけば、後から別ルートを狙う際の道標になります。特に、『ANGEL』のように3つのモードが存在する作品では、「この出来事はどのモードのどのルートで見たのか」が混ざりやすいため、簡易的なプレイノートを作るとコンプリートへの距離がぐっと縮まります。
難易度・ゲームオーバーとつまずきやすいポイント
全体としての難易度は、当時のPC-98向けADVとしては中程度といった印象で、「理不尽なゲームオーバーが連発する」「パズル要素が極端に難しい」といったことはあまりありません。とはいえ、特定のイベントを見ようとするときに「特定の日付までに一定のフラグを立てておかなければならない」といった条件が隠れていることもあり、初見では自然にスルーしてしまうルートもあります。そうした意味では、“物語を1周見るだけならそこまで難しくないが、全分岐を埋めようとするとじわじわ手応えが出てくる”タイプの作品です。 つまずきやすいポイントとしては、まず「行動できる場所が増えた時」に何をすればいいか迷いやすいことが挙げられます。マップ上に訪問可能な場所がずらりと並ぶと、どこから探索すればいいのか分からなくなりがちですが、そういうときはまず“主人公に関係が深そうな場所”や“これまでイベントが起きた場所の再訪”から着手すると良いでしょう。新規のポイントは、メインのイベントを追いかける合間に少しずつチェックしていくイメージがオススメです。 また、一見すると何でもない会話の選択肢が、後のイベント解放条件になっていることもあります。テキストのニュアンスをよく読み、どの選択肢がヒロインの感情に寄り添っているか、あるいは反発してしまうのかを想像しながら選ぶことが大切です。もし選択を誤って、狙っていたイベントにつながらなかったとしても、それはそれで「別ルートの展開を見られた」と前向きに捉え、次の周回で別の選択を試すと、結果的にゲーム全体への理解が深まります。 なお、いわゆる“詰み状態”になってしまうケースは少ないものの、イベントを見落としていると、いつまで経っても物語が進行しないように感じる場面もあります。その場合は、数日前のセーブデータからやり直し、異なる行動パターンを試してみるのが近道です。焦らずに一歩引いて、全体の流れを整理し直すのも攻略の一部と考えると良いでしょう。
やり込み・周回プレイの楽しみ方と小技的なポイント
『ANGEL』を本格的に攻略し尽くそうとすると、自然と複数回の周回プレイが必要になってきます。全ヒロインのエンディングを制覇する、イベントCGをできる限り埋める、セリフ回しや細かな表情の違いを味わう――といった“やり込み”は、本作の楽しみ方の大きな柱です。1周目でお気に入りになったキャラクターがいれば、そのキャラに絡むイベントを徹底的に追いかける周回を作るのも良いですし、「敢えて普段選ばないような選択肢を選んでみる」「別のモードで同じキャラを見ると印象がどう変わるかを確かめる」といった遊び方も面白いものです。 周回プレイをスムーズにするためには、テキストスキップ機能や既読メッセージの早送りを活用すると快適です。重要なイベントや分岐ポイント以外はテンポ良く飛ばしてしまい、選択肢や新規イベントの手前では一旦速度を落として慎重に進めるというメリハリを付けると、何度も同じ序盤を繰り返すストレスを軽減できます。もしゲーム中にメッセージスピードやスキップに関する設定項目があれば、最初に自分の好みに合わせて調整しておきましょう。 小技というほどではありませんが、プレイ環境にも少し気を配ると、攻略のしやすさが変わってきます。例えば、セーブデータの名前に「Aルート2日目」「Bルート分岐前」など簡単なラベルを付けておくと、後から見返すときに非常に便利ですし、モードやヒロインごとにセーブスロットを分けておくと、「どこからやり直せばいいのか分からない」といった事態を避けられます。また、プレイ時間をある程度まとめて確保できると、物語の流れを忘れにくくなり、細かな伏線やキャラの心情変化にも気付きやすくなります。 最終的に全てのエンディングやイベントを回収できたときには、ゲーム開始当初とはまったく違った目線で物語を振り返ることができるはずです。「最初は理解できなかった行動が、別ルートを見たことで納得できた」「モードをまたいで見ると、このキャラの印象ががらりと変わる」といった発見も、『ANGEL』をやり込んだプレイヤーだけが味わえる醍醐味と言えるでしょう。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーが抱いた第一印象
『ANGEL』が店頭に並んだ当時、PC-98やFM TOWNSユーザーがまず強く惹きつけられたのは、パッケージに大きく打ち出された「遊人原作」「3種類のゲームを1本に収録」というインパクトのあるキャッチでした。すでに『校内写生』などで名前を知っていたユーザーにとっては、「あのスタッフがまた集結したらしい」「今度はどんなキャラクターやドラマが見られるのか」という期待感が非常に大きく、雑誌やショップのPOPを見た段階から“買う候補”に挙げていたという声が多く聞かれます。実際にプレイを始めてみると、まず目に飛び込んでくるのが、原作のテイストを色濃く反映したキャラクタービジュアルと、当時のPC-98としてはかなり描き込みの細かいイベントグラフィックです。まだ解像度も色数も限られていた時代に、髪の毛の流れや表情の微妙な変化まで丁寧に描かれており、「おお、ちゃんと遊人の漫画っぽい」と好意的に受け止めたユーザーが多かったようです。また、3本立て構成という情報だけを聞いて「ひとつひとつが薄味になっているのでは?」と不安視する向きもあったものの、実際に遊んでみると、それぞれ性格の違うシナリオやモードがしっかりと作り込まれており、「ボリューム不足どころか、むしろ予想以上に遊べる」という好印象へと変わっていった、という感想がよく語られます。
雑誌レビューやショップ店員からの評価
当時のPCゲーム誌では、成人向けタイトルでありながらも、原作付きADVとしての完成度や企画性が評価の対象になることが多く、『ANGEL』もその例外ではありませんでした。レビュー記事では、まず「3話構成で1話ごとにゲーム性のカラーが違う」という点が話題となり、「1本で3つの味を楽しめる」「好みの遊び方に合わせてモードを選べる」といったコメントがしばしば見られます。一方で、アドベンチャーとしての作りに関しては、コマンド選択式ADVパートの探索がややオールドスタイル寄りであることが指摘され、「最近のノベル寄りタイトルに慣れたプレイヤーには少し手探り感が強いかも」といった慎重な評価もみられました。とはいえ、それも“悪い意味での難解さ”ではなく、「フラグ探しを楽しめる人にはプラスに働くタイプの作り」として紹介されており、攻略好きなプレイヤー層にはむしろ好意的に受け止められています。ショップ店員のコメントとしては、「遊人原作というだけで手に取る人が多い」「パッケージのインパクトと広告のキャッチコピーで、棚に置いておくと自然に目が行くタイトル」といった、販売現場ならではの実感が残っています。発売直後は、人気ブランドの新作ほど爆発的な売れ行きではなかったものの、じわじわと口コミで広がり、「原作ファンが友人に薦める」「PC-98ユーザー同士の貸し借りで存在を知る」といった形でプレイヤーが増えていった作品という印象が強いようです。
プレイヤーからの好意的な感想と支持されたポイント
プレイヤーの具体的な感想として多く挙げられるのは、「キャラクター同士の掛け合いや感情の動きがしっかり描かれている」「ただ雰囲気を楽しむだけでなく、ドラマとしての起伏がある」という点です。登場人物たちは、単なる“記号的なヒロイン”ではなく、それぞれに喜怒哀楽や弱さを抱えた存在として描かれており、ルートを進めるうちに「このキャラにはこういう一面があったのか」と印象が変わっていくことも少なくありません。そうした変化の過程を丁寧に追っていける点が、多くのプレイヤーに好評でした。また、3本立て構成により、「じっくり読みたいときはシナリオ重視モード」「気軽にイベントをつまみ食いしたいときはテンポの速いモード」と、その日の気分に応じて遊び方を変えられる点も高く評価されています。長時間まとめてプレイすることが難しいユーザーからは、「短めのエピソードを少しずつ進められるので、忙しい中でも楽しめる」という声もありました。ビジュアルや音楽に関しても、「当時としてはかなり頑張っている」「BGMがシーンに合っていて印象に残る」といった好意的な意見が目立ちます。特にFM TOWNS版では、CD-DA音源を活かしたクリアなサウンドに対して「ヘッドホンで聴くと雰囲気に浸れる」「夜中にひとりで遊ぶと、世界に没入しやすい」といった、音楽面を推す感想が寄せられていました。総じて、「ストーリー・キャラ・ビジュアル・音楽がバランス良くまとまっている」というのが、多くのプレイヤーに共通する評価と言えます。
指摘された弱点や賛否が分かれた部分
一方で、『ANGEL』にはいくつかの“好みが分かれるポイント”も存在し、そこがプレイヤー同士の評価の違いとして表れています。もっともよく挙げられるのは、コマンド選択式ADVパートのテンポや探索の比重です。特定のイベントを起こすために、何度か同じ場所を訪れる必要がある構造は、80〜90年代ADVとしては標準的な作りとはいえ、「最近のノベルゲーム感覚で遊ぶと、少し冗長に感じる」「早くストーリーを進めたいのに、どこを調べればいいのか迷ってしまう」といった不満につながる場合もありました。また、3本立て構成という長所が裏返しになり、「それぞれのモードがもう一歩踏み込んでくれたら、さらに名作になっていたのでは」という、欲張りな意味での物足りなさを感じるプレイヤーもいたようです。「どれもよくできているのだけれど、どれかひとつを特化させて長編にしたバージョンも見てみたかった」という声は、その完成度の高さの裏返しでもあります。さらに、原作がすでに一定のファン層を持つ作品であったがゆえに、「漫画版のこのエピソードもゲームで見たかった」「このキャラの扱いはもう少し違う方が好みだった」といった、原作ファンならではの注文が出ることもありました。これは、既存ファンの期待値が高かった分、細部へのこだわりが強くなっているためであり、決定的な欠点というよりは、“贅沢な不満”と言える類のものです。
レトロPCゲームとしての現在の評価と語り継がれ方
発売から長い年月が経った現在、『ANGEL』はレトロPCゲームとして語られる機会が増えています。PC-98実機やエミュレータで昔のタイトルを遊び直す文化が広がる中で、「当時プレイできなかったけれど、今になって興味を持った」「中古ショップやオークションで見かけて存在を知った」といった新しいプレイヤーも少しずつ増えています。そうした人たちの感想として多いのが、「90年代前半の空気をこれほど濃厚に味わえる作品は貴重」「今の感覚から見ると不便な部分もあるが、その不便さも含めて味がある」という評価です。テキストの言い回しやキャラクターデザイン、BGMの雰囲気など、どれもが“あの時代ならでは”の色合いを帯びており、単に懐かしいだけではなく、ひとつの文化的な資料のような価値も感じさせてくれます。また、カクテルソフトの歴史を振り返るうえでも、『ANGEL』は「原作付き大人向けADVに本格的に挑んだ意欲作」として位置付けられることが多く、同社の代表的シリーズとはまた別のベクトルで語られる存在です。「ブランドの幅の広さを示したタイトル」「後の作品につながるノウハウが積み重ねられた作品」といった見方もあり、単発の話題作というよりは、カクテルソフトの系譜の中にしっかり組み込まれた一本として認識されています。今なお入手難度は決して低くありませんが、その分「苦労して手に入れたぶん、じっくり味わいたい」と語るファンも多く、コレクターアイテムとしてもゲームとしても、静かながら根強い支持を受け続けているタイトルだと言えるでしょう。
■■■■ 良かったところ
物語と演出面で「しっかりドラマしている」と評価された点
『ANGEL』の長所としてまず挙げられるのが、ストーリーと演出の「ドラマ性の強さ」です。大人向けPCゲームというと、どうしても刺激的なシーンばかりが取り沙汰されがちですが、本作はそこに至るまでの心情描写や人間関係の積み重ねが非常に丁寧で、「恋愛ドラマとしてきちんと読ませる」構成になっています。日常の何気ない会話から、ちょっとしたすれ違い、誤解、そこから生まれる不安や嫉妬といった感情の揺れが段階を追って描かれていくので、プレイヤーは主人公とヒロインたちを単なる“記号的なカップル”としてではなく、「ちゃんと悩みながら生きているキャラクター」として受け止めやすくなっています。また、重要なイベントほど「ちょっと長めの会話シーン」「その前後で静かなBGMに切り替える」といった演出上のメリハリが付けられているのも好評なポイントです。日常シーンでは軽快なテンポで台詞が進み、転機となる場面では画面の切り替えや間の取り方で“ここは大事なシーンだ”と自然に意識させてくれるため、物語全体の起伏がはっきりと感じられます。こうした作りのおかげで、プレイヤーが思わず先の展開を読みたくなる“引きの強さ”が生まれており、「ただ眺めているだけではなく、登場人物たちの選択に一喜一憂しながらプレイできる」という感想につながっています。原作が持つコミカルさとシリアスさのバランスも、ゲーム版ではうまく調整されており、重い話になりすぎず、それでいて軽すぎない“ちょうど良い温度感”が好意的に受け止められた要因と言えるでしょう。
3本立て構成が生む遊びごたえとコスパ感の高さ
もうひとつ大きな「良かったところ」として語られるのが、3本立て構成による遊びごたえです。当時のPCゲームとしては、1パッケージにここまで性格の異なる3つのモードを収録した作品は決して多くなく、プレイヤーからは「価格以上に遊べる」「1本で3本分の満足感がある」といった声が上がりました。ひとつめのモードでは、コマンド選択式ADVとしての“探索する楽しさ”が味わえますし、ふたつめのモードでは物語重視の読み物としてじっくり堪能でき、みっつめのモードではテンポの良いイベントラッシュでサクサク進められる――というように、気分に応じてプレイスタイルを切り替えられるのが非常に好評でした。特に、「仕事や学校の合間に少しだけ遊びたい」というユーザーにとっては、短めのエピソードをつまみ食いする感覚で進められる構成がありがたく、長時間腰を据えてプレイする週末と、平日の空き時間とで遊び方を変えられる柔軟さが評価されています。また、3本立てとはいえ1つ1つのモードが極端に薄いわけではなく、それぞれの中に複数のイベントやエンディングが用意されているため、コンプリートを目指そうとすると自然に周回プレイが必要になり、「気付いたらかなりの時間をこのゲームに費やしていた」という嬉しい悲鳴も聞かれます。単純なテキスト量だけでなく、分岐やイベントの配置にも工夫があるので、「ボリュームの割にだれる区間が少ない」「飽きる前に別モードへ気分転換できる」という形で、プレイ体験全体の満足度を高めている点も長所と言えるでしょう。
キャラクターデザインとグラフィックの完成度
ビジュアル面も、良かった点として必ず名前が挙がる要素です。原作付きということもあり、キャラクターデザインは非常に力が入っており、PC-98やFM TOWNSのスペックをフルに活かして“遊人画風”の魅力を可能な限り再現しています。限られたドット数でありながら、髪のツヤや目元の輝き、服の皺やシルエットなどが丁寧に描き込まれており、1枚絵の説得力が高いおかげで、プレイヤーがキャラに感情移入しやすくなっています。「このキャラはこういう性格だから、この表情が似合う」というニュアンスまできちんと反映されているので、テキストで語られる心情と絵の印象がずれにくく、物語への没入感を支えています。また、イベントCGの構図やカメラアングルにも工夫が見られ、同じヒロインでもシーンごとに印象が変わるように描き分けられている点が評価されています。少し距離を置いた全身寄りのカットでキャラクターの立ち位置や空気感を表現したり、顔のアップで心情の変化を強調したりと、演出の一環としてグラフィックが活用されているため、「ただきれいな絵が出てくる」のではなく、「その絵が物語の一部分を語っている」と感じられるのです。背景グラフィックについても、教室や街並み、夜の風景など、シーンごとの空気を感じさせる描写が行き届いており、舞台となる世界に“ちゃんと人が住んでいる”雰囲気を作ることに成功しています。結果として、「ビジュアルを眺めているだけでも楽しい」「イベントCG集を見返したくなる」という意見が多く、長く印象に残る作品になっています。
音楽・サウンドと操作性のバランスの良さ
音楽や効果音、インターフェースなど、「遊びやすさ」に直結する部分が総じて良くまとまっている点も、『ANGEL』の美点です。BGMは派手さこそないものの、場面場面の雰囲気に寄り添う曲調で構成されており、シリアスなシーンでは静かに緊張感を高め、コミカルな場面では軽快なフレーズで空気をやわらげてくれます。特にFM TOWNS版ではCD-DA音源を活用したサウンドが楽しめるため、「ヘッドホンでじっくり聴くと、ゲーム全体の印象がワンランク上がる」と感じるユーザーも少なくありません。SEの使い方も極端に多用されることはなく、必要なところで控えめに鳴らすことで、テキストとグラフィックを邪魔しない絶妙なバランスに保たれています。インターフェースに関しては、コマンド選択式ADVに慣れているユーザーであれば直感的に扱える素直な作りになっており、操作方法で戸惑うことはあまりありません。テキストの表示スピードを調整できたり、キー操作でサクサク読み進められたりと、長時間プレイしても指や目が疲れにくい設計になっている点も好評です。メッセージ送りや選択肢の決定に必要なキーがわかりやすく、マウス主体でもキーボード主体でもストレスなく遊べるので、「自分の慣れたスタイルでプレイできる」と感じるユーザーが多いのも納得できます。こうした“当たり前に快適であること”は、派手なセールスポイントとして語られることは少ないものの、ストーリー重視のADVにおいては非常に重要であり、『ANGEL』が今も「遊びやすいレトロゲーム」として挙げられる理由のひとつになっています。
原作ファンとPCゲーマーの両方が満足しやすい設計
最後に、原作漫画のファンと、PCゲーム側から入ってきたプレイヤーの双方に配慮された設計になっている点も、「良かったところ」としてしばしば語られます。原作ファンにとっては、見慣れたキャラクターたちがPC向けのドット絵・イベントCGとして再登場し、しかもプレイヤーの選択次第で原作とは少し違う展開や距離感を体験できること自体が大きな魅力です。「このキャラとこういう形で関係が深まるルートは、漫画では見られない」といった“ifストーリー”的な楽しみが用意されていることで、原作の世界観を壊すことなく、ゲームならではの広がりを持たせています。一方、原作を知らないPCゲーマーにとっては、単純に「よくできた恋愛ドラマADV」として楽しめる作りになっており、事前知識がなくてもキャラクターの背景や関係性がゲーム内で丁寧に語られるため、「途中から話についていけなくなる」といった心配はあまりありません。むしろ、プレイを通してキャラクターに愛着がわき、「終わったあとで原作漫画を探し始めた」「ゲームで気に入ったキャラの登場シーンを原作で確認したくなった」という声さえあるほどです。こうした“入り口がどちらでも楽しめる”構造は、今でこそ一般的なメディアミックス展開ではありますが、当時のPC-98/FM TOWNS向けタイトルとしてはなかなか贅沢な作りであり、『ANGEL』が今なお名前を挙げられる理由の一端となっています。総合すると、「ドラマ性の高さ」「3本立ての遊びごたえ」「魅力的なビジュアル」「快適なインターフェース」「原作とゲームの橋渡し」という複数の要素がバランス良くまとまっていることこそが、『ANGEL』の“良かったところ”として多くのプレイヤーに記憶されていると言えるでしょう。
■■■■ 悪かったところ
テンポのばらつきと「ダレ」を感じやすい構成
『ANGEL』の弱点としてよく挙げられるのが、シナリオやモードによってテンポの良し悪しに差が出てしまう点です。3本立てという贅沢な構成のおかげで、遊び方の幅が広がっている一方、それぞれのモードの設計思想が微妙に異なるため、「こちらのモードはテンポが良くて遊びやすいのに、あちらのモードはどうにも間延びして感じる」といったギャップが浮き彫りになってしまうことがあります。特に、コマンド選択式ADV寄りのパートでは、フラグを探してマップ上を何度も行き来する必要があり、プレイヤーによっては「同じ場所を行ったり来たりしているだけに感じてしまう」「重要なイベントにたどり着く前に気力が削られる」といった不満につながりがちです。これは、80〜90年代ADV全般に見られる作りではあるものの、ストーリー重視で遊びたい人にとってはややハードルに感じられる部分でもあります。逆に、テンポ良くシーンが切り替わるモードに慣れたあとで、探索比重の高いモードに移ると、余計にペースの遅さが目立ってしまうこともあり、「3本のうち、どうしても後回しになってしまうモードが出てくる」と感じるプレイヤーもいました。3つの味を楽しめること自体は長所でありながら、その“味の違い”がテンポのばらつきとして表面化してしまった点は、やや惜しい部分と言えるかもしれません。
分岐やフラグ管理の分かりづらさによるストレス
また、複数のルートやイベントを回収しようとしたときに、フラグ管理の見えにくさにストレスを感じるプレイヤーも少なくありません。『ANGEL』では、特定のキャラクターとの会話や行動選択が後の展開に影響を与える仕組みが多く盛り込まれていますが、その多くがゲーム内で明示されないまま裏側で処理されているため、「なぜこのルートに入れたのか」「なぜ今回はイベントが起きなかったのか」が直感的には分かりにくい場面があります。とくに、特定の日付までに誰かに会っておく、ある場所を一定回数訪ねておく、といった条件付きイベントは、初見プレイでは自然に逃してしまいがちで、「ひと通り進めたつもりなのに、回想モードやCGギャラリーに空きが残る」「同じように遊んでいるつもりでも結果が変わる」といったモヤモヤにつながることもあります。もちろん、ADVのフラグ管理にはある程度の試行錯誤が付き物ですが、3モードをまたいでイベントを探しているうちに、「どのモードのどのタイミングで、どんな選択をしたのか」が自分でも把握しにくくなってくることもあり、コンプリートを目指すプレイヤーには相応の根気が求められます。攻略本や雑誌の特集記事と併用すればある程度は解決できるものの、「ゲーム単体でもう少しヒントがあれば」「条件を示すセリフや演出がもう一段階わかりやすければ」と感じるユーザーも少なくなかったようです。シナリオの密度が高いがゆえに、フラグ管理の煩雑さをどう感じるかが、評価の分かれ目になっていると言えるでしょう。
UI・技術面の古さが際立つ部分
インターフェースや技術的な側面についても、現代の視点から見ればどうしても“古さ”が目立ってしまう部分があります。テキスト表示速度やスキップ機能は当時としては標準的なものの、「ワンタッチで既読部分を一気に飛ばしたい」「分岐ポイントだけをマークしておきたい」といった、現代のノベルゲームでは当たり前になりつつある機能はもちろん搭載されていません。これにより、周回プレイ時にはどうしても同じテキストを何度も読み飛ばす作業が発生し、「好きな作品だからこそ繰り返し遊びたいのに、その入口で少し腰が引けてしまう」というジレンマを抱えるプレイヤーもいます。また、画面解像度や色数の制限から、細かい文字がやや読みづらく感じられるケースもあり、長時間プレイすると目が疲れやすいという声も当時から存在しました。ウィンドウのレイアウトやメニュー構造自体は素直で分かりやすいものの、現代のUIに慣れたプレイヤーが触れると、「もう少しショートカットキーやメニューの階層に工夫が欲しい」「セーブ・ロードの画面が簡素で、どのデータがどのルート用なのか判別しづらい」と感じる場面もあるでしょう。FM TOWNS版では音質や読み込み速度の面で有利な一方、CDからのロードに起因する小さな待ち時間が挟まることもあり、「イベント前に一瞬間が空くのが気になる」といった意見も見られました。これらはあくまで時代相応の仕様とも言えますが、改めて遊ぶ際には、レトロゲームならではの“味”として許容できるかどうかがポイントになります。
シナリオの好みや原作との距離感に起因する賛否
シナリオ面では概ね高評価を得ている『ANGEL』ですが、そこにも一定の“好みの分かれ”は存在します。まず、原作漫画を読んでいるプレイヤーの中には、「もっとこのキャラを中心にしたエピソードが欲しかった」「原作で印象的だった場面がゲームでは扱われていない」といった物足りなさを覚える人もいました。ゲーム版のシナリオは、あくまで原作世界の一部を切り取り、ゲームとして再構成したものなので、原作の全エピソードを網羅できているわけではありません。そのため、「自分が特に好きだったサブキャラの出番が少ない」「原作に比べてキャラの性格がマイルドになったように感じる」といった印象を受けることもあり、思い入れが強いファンほど細部に対する注文が出がちです。また、逆に原作を知らずにゲームから入ったプレイヤーの中には、「登場人物の背景説明や過去エピソードが、もう少し丁寧でも良かった」「短いモードだとキャラの心情変化が急に感じられる」といった意見も見られます。3本立てという制約の中でさまざまなキャラクターを登場させているため、どうしても一部のキャラは“雰囲気でさらりと流される”ような描写に留まってしまうこともあり、その点をもどかしく感じるプレイヤーもいるわけです。さらに、物語のトーンそのものも、コミカルさとシリアスさ、大人向けのムードが入り混じった独特のバランスを持っているため、「もう少しライトなラブコメに振ってほしかった」「逆に、もっと徹底して重いドラマにしてほしかった」といった、方向性に関する好みの違いも生まれやすくなっています。つまり、作品のカラーがはっきりしているがゆえに、それにフィットするかどうかで印象が変わる――という側面が、評価のばらつきとして表れていると言えるでしょう。
入手性や環境面のハードルによる“もったいなさ”
ゲームそのものの出来とは少し別の観点になりますが、『ANGEL』は発売から年月が経った現在では、ソフトそのものの入手性やプレイ環境のハードルもマイナス要素になっています。PC-9801やFM TOWNSといったハード自体がすでに現役を退いて久しく、実機を揃えたうえで動作環境を整えるのは容易ではありません。中古ショップやオークションでソフトを見つけられたとしても、「メディアの劣化」「マニュアル欠品」「動作保証がない」といった不安要素がつきまとい、気軽に“試しに遊んでみる”とは言いにくい状態です。その結果として、興味を持った新規プレイヤーが実際に触れる機会はどうしても限られてしまい、「話には聞くけれど、現物に触れたことがない」「名前だけは知っている」といった“伝説化”を助長している面もあります。これは『ANGEL』に限らずレトロPCゲーム全般の課題ですが、完成度の高い作品であるがゆえに、「もっと多くの人が簡単に遊べる形で復刻されていれば」という“もったいなさ”を感じるファンの声も少なくありません。技術的・権利的なハードルがあることは想像に難くありませんが、せっかくの原作付きタイトルとしての魅力や、3本立てADVというユニークな構成が埋もれがちになっている点は、作品の悪いところというより“環境面での不利”として語られることが多い印象です。プレイのしにくさや入手の難しさが、そのまま作品への距離感につながってしまうのは惜しいところであり、「もう少し時代が新しければ、より広い層に知られていたのでは」と想像させる要因にもなっています。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
主人公と最初に出会う“王道ヒロイン”的存在
『ANGEL』のキャラクターの中で、多くのプレイヤーが「まず心を持っていかれる」と語るのが、主人公と最初に深く関わる、いわゆる“王道ヒロイン”タイプの女の子です。明るくて面倒見が良く、一見すると学園内のどこにでもいそうな普通の女の子なのに、ストーリーが進むにつれて内面の脆さや葛藤が見えてくる――そのギャップがプレイヤーの心を強くつかみます。日常パートでは冗談を言い合える親友のような距離感で、主人公を軽くからかったり、さりげなく励ましたりしてくれる存在ですが、ふとした瞬間に見せる寂しげな表情や、意地を張ってしまう不器用さが「守ってあげたくなる」感情を呼び起こすのです。彼女のルートでは、お互いの勘違いやすれ違いから気まずい空気になってしまう場面も描かれますが、最終的には素直な気持ちをぶつけ合うことで関係が一段深まっていきます。この過程が丁寧に描かれているため、多くのプレイヤーが「初回プレイでは自然とこの子のエンディングを目指してしまった」「他のルートを遊んでも、最終的にはこのヒロインに戻ってきてしまう」と振り返る、作品を象徴するキャラクターとなっています。華やかさという意味ではもっと目立つキャラもいますが、“物語の軸”としての安心感と、等身大の女の子らしさが絶妙なバランスで両立していて、「ANGELと言えばまずこの子」と名前を挙げる人が多いのも頷けるところです。
クール系ヒロインのギャップに惹かれるプレイヤーも多い
一方で、「最初からこのキャラ一択だった」と語るプレイヤーが多いのが、ややクールで近寄りがたい雰囲気をまとったヒロインです。教室の片隅で静かに本を読んでいたり、人付き合いがあまり得意ではなかったりと、初対面の印象はどこか冷たく、ときには棘のある言葉を投げかけてくることもあります。しかし、彼女のルートを進めていくと、そうした態度の裏側にある不器用さや、過去の出来事に起因する“人との距離感の取り方の下手さ”が少しずつ明らかになっていきます。プレイヤーの選択によって主人公が相手の領域に踏み込みすぎず、かといって突き放しもしない絶妙な距離感を保ち続けることで、彼女の心の壁がゆっくりと溶けていく描写は、このルート最大の見どころと言えるでしょう。特に印象的なのは、それまで素っ気ない態度ばかりだった彼女が、ふとした拍子に見せる照れや笑顔のシーンで、「いつもと同じ顔のはずなのに、そこに柔らかさが宿っている」と感じさせるグラフィックやテキストの説得力が光ります。「クール系キャラに弱い」「ギャップを楽しみたい」というタイプのプレイヤーにとって、このヒロインはまさにドストライクな存在であり、「3本立ての中で真っ先に攻略したのはこの子だった」「他のヒロインをプレイしても、結局このルートが一番心に残った」との声も少なくありません。
お姉さんポジションのキャラがもたらす安心感と大人の魅力
『ANGEL』には、同級生タイプのヒロインだけでなく、少し年上の“お姉さんポジション”のキャラクターも登場し、これがまた根強い人気を集めています。主人公にとって頼れる相談相手であり、時には軽口を叩きながらもさりげなくフォローしてくれる存在として描かれており、「等身大の恋」とはまた違う、少し背伸びをした関係性が楽しめるのが魅力です。彼女は大人びた視点から主人公の未熟さを指摘したり、恋愛や人間関係の難しさについて意味深な言葉を投げかけたりしますが、それは決して突き放すためではなく、「自分で考えて、乗り越えてほしい」という思いの裏返しであることが、物語の進行とともに分かってきます。そんな彼女がふとした場面で見せる弱音や、本当は誰かに甘えたいという本音が垣間見える瞬間は、プレイヤーにとって強い印象を残す名シーンになりがちです。「最初は頼れる大人だと思っていたのに、実は彼女も完璧ではなく、不安や寂しさを抱えている」と理解したとき、プレイヤーの中でキャラクターの像が一段と立体的なものになり、ただの“年上ヒロイン”を超えた存在として印象付けられます。年齢差や精神的な成熟度の違いが物語のスパイスとして機能しており、「同年代ヒロインとはまた違う深みのあるルートが楽しめた」と高く評価されることの多いキャラクターです。
元気系・ムードメーカーキャラの存在感
シリアスなドラマだけでなく、画面の空気を一気に明るくしてくれる“元気系”や“ムードメーカー”タイプのキャラクターも、『ANGEL』の魅力を語るうえで欠かせません。彼女たちは物語の中心となるルートを持つこともあれば、サブ的なポジションで登場することもありますが、いずれにせよ登場シーンのたびに場が華やぐ存在です。おしゃべりが大好きで、何でもすぐにリアクションを返してくれるタイプや、ちょっと抜けているけれど憎めないドジっ子タイプなど、性格づけはさまざまですが、どのキャラも“画面をにぎやかにする”という役割をきちんと果たしています。特に、シリアスな展開が続いた後で彼女たちが割って入ることで、プレイヤーの気持ちがふっと軽くなり、「このゲームは重い話だけではないんだ」と改めて感じさせてくれるバランス感覚が光ります。彼女たち自身のルートでも、その明るさの裏側にあるコンプレックスや不安が描かれることがあり、「いつも明るく振る舞っているのは、本当は誰かに頼ってほしいから」「場を盛り上げていないと、自分の居場所がないように感じてしまう」といった、ムードメーカー特有の孤独が垣間見える展開も印象的です。プレイヤーの中には、「シナリオの完成度という意味では他のヒロインの方が上かもしれないが、最終的に一番好きになったのはこの子だった」と語る人も多く、“いてくれるだけで嬉しい存在”として愛されているキャラクターたちと言えるでしょう。
サブキャラ・脇役の“妙なリアリティ”に惹かれる声も
メインヒロインたちだけでなく、クラスメイトや友人、教師といった脇役キャラクターも、『ANGEL』の世界を支える重要な存在です。彼らは決して物語の主役ではありませんが、何気ない会話やちょっとした一言が印象に残るように作られており、「このモブっぽいキャラが妙に好き」「セリフ回しがリアルで、実際にクラスにいそう」といった感想も少なくありません。例えば、主人公をからかいながらも、要所では真面目なアドバイスをくれる男友達や、口は悪いのに情に厚い同級生など、どのキャラもどこかで見たことがあるようなリアリティを持っています。こうした脇役たちが、ヒロインたちとの関係性を横から茶化したり、時に背中を押したりすることで、物語の空気が一気に“学生たちの群像劇”らしいものへと変化していきます。プレイヤーの中には、「メインヒロインを攻略するための舞台装置としてだけでなく、脇役たちもちゃんと生きている感じがするのが良い」と評価する声もあり、特定のサブキャラに強い愛着を抱くユーザーも少なくありません。ゲームとして表に出るのはどうしてもヒロインたちの物語ですが、その背後でこうしたサブキャラたちがきちんと動いているからこそ、世界全体が“ワンセット”として成立しているのだと感じさせてくれます。結果として、「お気に入りのキャラクターは誰か」と問われたとき、メインヒロインではなく、とある脇役の名前を挙げるプレイヤーが出てくるあたりに、『ANGEL』のキャラ造形の豊かさがよく表れていると言えるでしょう。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
PC-9801版の基本的な仕様と遊び心地
『ANGEL』が最初に想定していたメイン環境は、やはり当時国内で圧倒的シェアを誇っていたPC-9801シリーズです。98版の『ANGEL』は、複数枚のフロッピーディスクに分割された構成で、インストールを経てHDDから起動する、いわば“王道の98用アドベンチャーゲーム”という形態になっています。画面解像度や色数は、いわゆる98らしい落ち着いたパレットで、イベントCGもテキストウィンドウも比較的シンプルなレイアウトですが、そのぶん表示レスポンスが軽く、キー入力にも素直に反応するため、「長時間遊んでいてもストレスを感じにくい」という感想が多い環境です。 グラフィックは、色数の制約の中で陰影やハイライトを丁寧に付けた“98ドット絵”ならではの魅力が前面に出ています。原作漫画の雰囲気を細かな点描とグラデーションの工夫で再現しているため、今の視点で見るとどこかレトロでありながら、当時としては「かなり頑張ったビジュアル」として受け止められていました。テキスト部分も、読みやすさを重視したフォントと配置が採用されているので、ADVにありがちな“目の疲れ”が比較的軽いのも98版の美点です。 操作系に関しては、キーボード主体のプレイを念頭に置いた設計で、矢印キーとスペース、Enterキーなど、限られた入力だけで物語を進められるようになっています。マウスを使っても問題なく遊べますが、「片手でキーをポンポンと叩きながらテキストを読む」という、いかにも当時のPC-98ユーザーらしいスタイルがよく似合う作りです。ロード時間も、HDDにインストールしてしまえばそれほど気になることはなく、フロッピーから直接起動している場合でも、「イベント前に少しもたつく程度」で済むことが多い印象です。
FM TOWNS版の仕様と“豪華さ”を感じさせるポイント
一方、FM TOWNS版『ANGEL』は、CD-ROMメディアを前提とした構成になっており、当時としてはハイエンド寄りの環境で「よりリッチな演出」を楽しめるバージョンとして位置付けられています。最大の違いはやはりサウンドまわりで、CD-DAによるBGM再生に対応しているおかげで、PC-98版と比べて音の広がりや厚みが段違いです。同じメロディラインでも、TOWNS版で聴くと楽器のニュアンスや残響がはっきりと感じられ、静かなシーンでは澄んだピアノやストリングスが、コミカルな場面では軽快なシンセサウンドがくっきりと耳に届きます。 グラフィック面でも、TOWNSの性能を活かして色表現が一段階豊かになり、肌のグラデーションや髪の光沢、背景の空や街灯りの柔らかさなどが、98版と見比べると微妙に印象が変わってきます。もちろんキャラクターデザインそのものは共通ですが、色数に余裕があるぶん、イベントCGの雰囲気がやや“なめらか”に感じられ、特に暗がりのシーンや夕暮れ時のシーンでは、空気感の違いが分かりやすいでしょう。 CD-ROMベースゆえのロードの挙動も、98版との違いとして意識されやすい部分です。テキスト送り自体は軽快ですが、大きなイベントグラフィックを読み込む直前や、モードを切り替えるタイミングなどで一瞬の読み込み待ちが発生することがあり、「その“間”がかえって演出に感じられる」という人もいれば、「テンポが崩れるので気になる」という人もいます。このあたりは、プレイヤーの感性や当時の環境(ドライブ速度など)によって印象が変わるポイントと言えるでしょう。
操作感・ロード時間・安定性の違い
実際に両機種版を触り比べたユーザーがよく言及するのが、「操作の軽さとロードテンポのバランス」の違いです。PC-9801版は、前述の通りHDDインストールを前提にすればレスポンスが非常に良く、テキスト送りやコマンド選択の反応もキビキビしています。ADVパートでは、同じ場所を何度も行き来したり、選択肢を細かく試したりすることが多いため、この“軽さ”はプレイ快適性に直結する要素です。長時間のプレイでもストレスが溜まりにくく、まさに「仕事用マシンをゲーム機として酷使する」当時の98ユーザー的なスタイルにマッチしています。 FM TOWNS版は、CDからデータを読み出す仕様上、どうしても特定シーンで一息つくような読み込み待ちが挟まれることがありますが、その代わりBGMやグラフィックのリッチさが加わります。操作そのものの応答性は決して悪くなく、テキスト送りやメニュー操作はスムーズですが、イベントの切り替わりで“カチッ”と雰囲気を変えるような場面では、わずかなロードの間も含めて「次の展開へのタメ」として受け止めるプレイヤーもいました。 安定性という観点では、どちらも当時のOS・ハード構成に依存するため一概には言えませんが、普及台数の多さや実機検証の蓄積という意味ではPC-9801版の方が安心感がありました。TOWNS版は、対応機種やドライブの状態によって挙動が微妙に異なるケースもあり、「環境次第ではシビアな部分がある」と感じるユーザーもいたようです。もっとも、これはどちらかが優秀・劣っているというより、“業務機寄りの安定感を持つ98”と、“マルチメディア指向のTOWNS”の性格の違いが、そのままゲーム体験に反映されていると見るのが自然でしょう。
サウンド・BGMの印象の違いと没入感
サウンド面の差は、両機種版を語るうえで外せないポイントです。PC-9801版のBGMはFM音源によるシンセサウンドで、どこか“チップチューンと生演奏の中間”的な独特の味わいがあります。メロディラインがはっきりとしており、数曲聴いただけで耳に残るフレーズも多いため、「古いけれど、かえってそれがクセになる」「味のあるFM音源が作品のムードに合っている」と感じるプレイヤーが少なくありません。雑誌付録のサントラ企画などで、98版準拠のBGMが取り上げられていたこともあり、“PCゲームらしい音楽”の代表格として記憶しているユーザーもいるほどです。 一方、FM TOWNS版のBGMは、CD-DAならではのクリアな音質と音色の豊富さが特徴で、ピアノやストリングス、パーカッションなど、それぞれの楽器がよりリアルに響きます。同じ曲でも、TOWNS版で聴くと情感が増して聞こえる場面が多く、「夜のシーンや雨のシーンなど、環境音と組み合わさることで没入感が一段階増す」と評されることもありました。ヘッドホンを付けてプレイすると、キャラクターの台詞と背景音、BGMがひとつの空間として耳に入ってきて、まるでドラマCDを聞きながらADVを遊んでいるような感覚になる、という声もあるほどです。 どちらのサウンドが優れているかは完全に好みの問題ですが、「FM音源らしい粒立ちの良さとレトロ感を愛でるなら98版」「音に包まれるような臨場感やムード作りを重視するならTOWNS版」と考えると、自分に合った遊び方が見えてきます。BGMをじっくり聴くスタイルか、画面とテキスト中心でテンポよく読み進めるスタイルか――プレイヤーの嗜好によって、どちらのバージョンを好むかが分かれるポイントと言えるでしょう。
これから遊ぶならどちらを選ぶべきかという視点
では、もし今から『ANGEL』を遊ぼうとした場合、PC-9801版とFM TOWNS版のどちらを選ぶべきでしょうか。前提として、どちらの環境もすでに現役を退いて久しいため、実機を揃えるにせよ、当時のOSや周辺機器を整えるにせよ、ある程度のハードルが存在します。そのうえであえて指針を挙げるなら、「作品の空気感ごと90年代PCゲーム体験を味わいたい人」にはPC-9801版を、「BGMやビジュアルのリッチさを優先して、とにかく没入したい人」にはFM TOWNS版を推す、という分け方がしっくり来るかもしれません。 PC-9801版は、グラフィック・音楽・文字表示のすべてが“当時の美少女ゲームらしさ”を色濃く残しており、画面レイアウトやフォントを含めて「90年代前半のPCゲームをプレイしている」という実感を強く得られます。一方で、FM TOWNS版は、サウンドや色表現の向上により、より“作品としての完成度”に振った体験を提供してくれるバージョンと言えるでしょう。 ただし、物語の骨格やキャラクターの魅力といったコアな部分はどちらも共通であり、「どちらを遊んだからといって根本的な評価が変わるものではない」という点も押さえておきたいところです。機種による違いはあくまでスパイスであり、『ANGEL』という作品そのものの良さは、プラットフォームを問わず感じ取ることができます。もし両方に触れる機会があるなら、98版を先にプレイしてレトロな雰囲気を味わい、その後でTOWNS版の“リッチなリメイク感覚”を楽しむ、という順番も面白いでしょうし、逆にTOWNS版で世界に浸ったあと、98版で“原点に立ち返る”という遊び方も一興です。 いずれにせよ、『ANGEL』はPC-9801とFM TOWNSという2つのプラットフォームの個性を活かしながら、それぞれの環境に合わせた演出で同じ世界観を描き出したタイトルです。どちらを選んでも“間違い”ということはなく、自分が求めるレトロPC体験のスタイルに合わせて、好みのバージョンに手を伸ばしてみるのが一番と言えるでしょう。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
1993年前後のPC-9801/FM TOWNS界隈は、まさに「美少女ゲーム黄金期」の入り口ともいえる時代で、『ANGEL』の周囲にも、今なお名前が挙がる名作PCゲームが数多く並んでいました。この章では、その中から「当時これを遊んでいた人なら、きっと一度は耳にしたことがあるだろう」という代表的なタイトルを10本ピックアップし、ゲーム名・販売会社・発売年・販売価格(当時の定価ベース)とともに、どんな作品だったのかをじっくり振り返っていきます。『ANGEL』と同じく18禁指定の恋愛ADVから、骨太な歴史シミュレーションまで、PCゲーム文化の幅広さを感じながら読み進めてみてください。
★同級生
・販売会社:エルフ(elf)
・販売された年:1992年(PC-9801版)、1993年に他機種版も展開
・販売価格:PC-9801版・定価8,800円前後(当時のパッケージ表記による)
・具体的なゲーム内容:
PC恋愛アドベンチャーの歴史を語るうえで欠かせない金字塔が、この『同級生』です。舞台となるのは夏休みの街。プレイヤーは男子高校生となり、およそ二週間のあいだに、クラスメイトや幼なじみ、年上の女性たちと交流を重ねながら、それぞれのヒロインとの関係を深めていきます。特徴的なのは「時間管理」と「行動選択」が密接に結びついたゲームシステムです。
朝・昼・夕方・夜と時間帯ごとに行ける場所が変化し、ヒロインによって登場する曜日や時間も異なるため、「今日はどこに行くか」「誰を優先するか」というプレイヤーの判断が、そのまま物語の分岐に直結します。また、すべてのヒロインに家庭や学校での事情が細かく設定されており、ただイベントをこなすだけでなく、彼女たちの悩みを知り、支え、気持ちを通わせる「過程」に重きが置かれているのもポイントです。
当時としては大胆な大人向け描写を含みながらも、単なる刺激だけでなく、甘酸っぱくも切ない青春ドラマとしての完成度が高く、多くのユーザーに強烈な印象を残しました。後年の恋愛ADVの多くが、本作の時間管理型システムや群像劇的な構成に影響を受けていると言われており、『ANGEL』と同時代の作品を語る際には必ず比較対象として名前が出る存在です。
★大航海時代II
・販売会社:光栄(現・コーエーテクモゲームス)
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価9,800円前後
・具体的なゲーム内容:
歴史シミュレーションで名を馳せていた光栄が手掛けた海洋冒険SLGの代表作が『大航海時代II』です。プレイヤーは複数用意された主人公の中から一人を選び、ヨーロッパの港町から世界の大海原へと旅立ちます。
システム面では、航海による交易・探検・戦闘が一体となったゲームデザインが特徴で、各地の港で安く仕入れた物資を、別の地域で高値で売る「貿易」によって資金を稼ぎ、その資金をもとに船団を強化していく流れが基本です。また、世界各地に眠る遺跡や秘宝を探し出す「探索」要素や、海賊や敵対勢力との「海戦」も用意されており、プレイヤーごとに大商人を目指すのか、冒険家としてロマンを追うのか、あるいは海洋戦争に身を投じるのかといったプレイスタイルが分かれます。
当時のPC-9801環境としては非常に緻密なドットグラフィックと荘厳なBGMも高く評価され、恋愛ADVが主流だったユーザーの間でも、「合間にじっくり遊べる本格SLG」として支持を集めていました。『ANGEL』と同じハードで、まったくジャンルの違う作品がこれほど幅広く展開されていたことは、当時のPCゲーム市場の懐の深さを物語っています。
★天使たちの午後III 番外編 反省版
・販売会社:ジャスト(Just)
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価8,800円前後
・具体的なゲーム内容:
80年代末から続く人気シリーズ「天使たちの午後」の流れを汲む作品で、サブタイトルにもある通り「番外編」として位置づけられたタイトルです。舞台は現代日本の学校や街角で、プレイヤーは若い男性主人公の視点から、複数の女性キャラクターと出会い、さまざまなエピソードを体験していきます。
本作の特徴は、シリーズの中でも比較的ライトな構成でありながら、シナリオ単位で完結する短編集的な作りになっている点です。1エピソードごとのプレイ時間が長すぎず、PC-9801で気軽に起動して、空いた時間に一話読み進めるといった遊び方がしやすいデザインになっていました。テキストは当時の雰囲気を色濃く残したやや大人びた文体で、ヒロインたちの心情や関係性の変化を細かく描きながら、最終的にはややビターな余韻を残す話も多く、「甘さだけではない」恋愛ストーリーを求めるユーザーから支持されています。
『ANGEL』と同じく、成人向け描写を含みつつも、人間関係や心の揺れ動きを描こうとするスタイルは共通点があり、当時の恋愛ADVの表現が徐々にドラマ性を重視する方向へ進んでいたことを感じさせる一作です。
★初恋物語
・販売会社:GAMEテクノポリス
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価9,800円前後
・具体的なゲーム内容:
タイトル通り、「初恋」というテーマにフォーカスした恋愛アドベンチャーゲームです。学園生活を中心に、幼なじみやクラスメイト、先輩など、多彩なヒロインたちとの関係が描かれますが、派手な事件や超常現象が起こるわけではなく、放課後の帰り道や、文化祭の準備、試験前の教室といった、等身大の日常の一コマが丁寧に綴られていくのが特徴です。
ゲームシステムとしては、選択肢による分岐型ADVの王道スタイルで、定期的に提示される選択肢によって、その後のイベント発生やエンディングが変化します。攻略情報が少ない当時は、「このタイミングで誰と話したか」「どのイベントを優先したか」といった些細な行動が思わぬ結末につながることも多く、プレイヤー同士が雑誌の投稿欄などで情報交換を行いながら試行錯誤していたのも懐かしいポイントです。
『ANGEL』のように漫画原作を持つタイトルと比べると、ビジュアル面や話題性ではやや控えめですが、「等身大の学園恋愛」を真正面から描いた作品として、当時の読者層にしっかり刺さっていた一本と言えるでしょう。
★きゃんきゃんバニー エクストラ
・販売会社:カクテル・ソフト
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価8,800円前後
・具体的なゲーム内容:
カクテル・ソフトを代表する看板シリーズ「きゃんきゃんバニー」の一作で、恋愛ADVにゲーム要素を加えた、明るくポップな作風が特徴です。プレイヤーは主人公として、さまざまなヒロインと出会いながら「願いを叶える」ために奮闘していきますが、その過程でミニゲーム的な要素やパラメータ育成が挟まれ、単なる読み物ではない「遊び感」の強い構成になっています。
カラフルなグラフィックと、軽快なサウンド、そしてどこかコメディ寄りのイベント群は、『ANGEL』の持つやや劇画的で濃厚な雰囲気とは対照的です。同じメーカーが手掛けながらも、作品ごとにターゲット層やテイストを明確に変えており、当時のカクテル・ソフトが多様な路線を同時展開していたことがうかがえます。
恋愛ADVとしての攻略も、特定のヒロインだけに絞って好感度を上げるのか、複数のキャラクターとのイベントを幅広く拾っていくのかで展開が変化し、何度も遊ぶことで新しい発見がある作りです。『ANGEL』と合わせて振り返ると、カクテル・ソフトの「明るい路線」と「大人びた路線」の違いがよく見えてきます。
★カスタムメイト
・販売会社:カクテル・ソフト
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価は8,000~9,000円台とされる(資料により差異あり)
・具体的なゲーム内容:
『カスタムメイト』は、プレイヤー好みのヒロイン像を「カスタマイズ」していく発想がユニークな作品です。キャラクターの性格や外見の一部、シチュエーションなどを組み合わせることで、半ばオーダーメイドのような恋愛ADVを楽しめる構成になっており、当時としてはかなり実験的な企画でした。
ゲームとしてはテキストADVの枠組みを守りつつも、パラメータの組み合わせ次第で登場イベントのパターンやヒロインの反応が変わるため、「自分だけの理想のヒロイン」を作り出していく感覚が味わえます。『ANGEL』が原作漫画のキャラクター性を忠実に再現する方向性で作られているのに対し、『カスタムメイト』はプレイヤーの嗜好をシステムに落とし込むという、まったく別のアプローチでファンの心を掴んだ作品だと言えるでしょう。
また、当時のPC-9801としては比較的高解像度の立ちグラフィックと、豊富な表情差分も魅力で、カスタマイズの結果がビジュアル面にも反映されることで、遊び手のモチベーションを高めていました。今のキャラメイク系ゲームの源流のひとつとして見ることもできる、ユニークな存在です。
★クィーンズ・ライブラリー
・販売会社:カクテル・ソフト
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:当時のPC-9801版・1万円前後(RPGとしては標準的な価格帯)
・具体的なゲーム内容:
『クィーンズ・ライブラリー』は、同じカクテル・ソフト製ながら、恋愛ADVではなくRPGとして制作されたタイトルです。プレイヤーは一国の姫あるいはその側近の立場から、魔物の侵攻によって危機に瀕した王国を救うため、広大な世界を旅していくことになります。
ゲームシステムは、ダンジョン探索と拠点管理の要素を併せ持った構成で、図書館を拠点として装備や仲間の強化を行いながら、モンスターが徘徊するダンジョンに挑むという流れです。戦闘はターン制で、PC-9801の高解像度グラフィックを活かしたキャラクター立ち絵と敵モンスターのイラストが、当時のRPGファンに強い印象を残しました。
恋愛ADVが中心のブランドが、あえてRPGというジャンルに挑戦したこと自体が話題になり、「カクテルの描くファンタジー世界」という新鮮さも相まって一定の支持を獲得します。『ANGEL』と同年に発売されたことで、メーカーの幅広いラインナップを印象づけた一本です。
★シャングリラ2
・販売会社:エルフ(elf)
・販売された年:1993年(PC-9801版)
・販売価格:PC-9801版・定価9,680円前後
・具体的なゲーム内容:
『シャングリラ2』は、ファンタジー世界を舞台にした戦略シミュレーションゲームで、プレイヤーは複数の国が覇権を争う大陸で、自国を勝利に導く指揮官として采配を振るいます。マップ上の部隊を移動させて戦闘を行い、占領した拠点を基点に生産や補給を行うという、本格派SLGの作りが特徴です。
エルフといえば恋愛ADVのイメージが強いブランドですが、本作では戦略級のシミュレーションに、同社らしいキャラクターデザインやイベントシーンを組み合わせることで、「シリアスな戦記もの」と「美少女ゲーム的な魅力」を両立させています。戦況によってイベントが分岐したり、特定のキャラクターを生存させることで専用イベントが発生したりと、やり込み要素も豊富でした。
当時のPC-9801の処理能力を考えると、マップ上のユニット数や演出はかなり盛りだくさんで、ターン制ながら緊張感のある戦いが楽しめる点も好評でした。『ANGEL』と同時代のエルフ作品として、「テキスト中心の恋愛ADV」と「戦略SLG」という二つの極を見せた存在と言えるでしょう。
★ワーズ・ワース(WORDS WORTH)
・販売会社:エルフ(elf)
・販売された年:1993年(PC-98版)
・販売価格:PC-98版・1万円前後(版によって差異あり)
・具体的なゲーム内容:
『ワーズ・ワース』は、剣と魔法の世界を舞台にしたアクションRPGで、二つの世界の争いと、その狭間で運命に翻弄される主人公の物語が描かれます。プレイヤーはフィールドやダンジョンを探索しながら、敵との戦闘や謎解きをこなし、物語の真相に迫っていきます。
本作の強みは、重厚な世界観と濃密なストーリー展開です。古代の遺跡や封印された剣など、ファンタジーRPGの王道要素がふんだんに盛り込まれながら、登場人物たちの葛藤や感情が丁寧に描かれることで、単なる冒険活劇にとどまらないドラマ性を獲得しています。また、PC-98としては非常にリッチなビジュアルと演出、メリハリのあるBGMも相まって、当時のユーザーに強烈なインパクトを与えました。
『ANGEL』が現代学園を舞台にしたアダルトADVであるのに対し、本作はダークファンタジー色の強い物語とアクション性を押し出した作品であり、同じ18禁指定でも「冒険ファンタジーの文脈で大人向け表現を絡める」というまったく違う方向性を提示しています。PC-98時代の美少女ゲームの懐の深さを示す一例と言えるでしょう。
★バイブルマスター
・販売会社:グローディア(GLODIA)
ストローワラの情報交差点
・販売された年:1993年(PC-9801版)
ストローワラの情報交差点
・販売価格:PC-9801版・定価11,800円前後
ストローワラの情報交差点
・具体的なゲーム内容:
『バイブルマスター』は、ファンタジー世界を舞台にしたRPGで、魔法書(バイブル)を巡る物語が展開されます。プレイヤーは魔術師あるいはその弟子の立場から、各地を巡りながら新たな魔法や仲間を集め、世界を脅かす危機に立ち向かっていきます。
システム面では、「魔法書と魔法陣」を軸とした魔法構築要素が特徴で、特定の組み合わせによって新しい魔法を生み出したり、属性の相性を考えながら戦術を練ったりと、頭を使う戦闘が楽しめました。ドット絵で描かれたキャラクターとフィールドも丁寧に作り込まれており、当時としては高めの価格設定ながら、ボリュームとクオリティに見合った内容だと評価されています。
『ANGEL』と比べるとまったく異なるジャンルですが、「PC-9801で腰を据えて遊ぶRPG」という点では共通しており、同じ時期にこうした本格派RPGとアダルトADVが共存していたことが、PCゲーム文化の独自性を象徴していると言えるでしょう。
これら10本のタイトルは、いずれも『ANGEL』と同じ1993年前後にPC-9801/FM TOWNSユーザーの間で話題になっていた作品群です。学園恋愛物から戦略SLG、ファンタジーRPGまで、ジャンルの幅は非常に広く、その中で『ANGEL』は「人気漫画原作×美少女ADV×3本立て構成」というユニークな立ち位置を占めていました。こうして周辺作品を並べてみると、『ANGEL』がどのような時代背景の中で生まれ、どんなライバルたちと肩を並べていたのかが、より立体的に見えてくるのではないでしょうか。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
新・校内写生(4) &校内写生R (ニチブンコミックス) [ 遊人 ]
新・校内写生 ( 3) (ニチブンコミックス) [ 遊人 ]




 評価 4
評価 4![ANGEL完全版 超合本版【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4646/2000007224646.jpg?_ex=128x128)
![新・校内写生(4) &校内写生R (ニチブンコミックス) [ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8078/9784537138078.jpg?_ex=128x128)
![新・校内写生 ( 3) (ニチブンコミックス) [ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6173/9784537136173.jpg?_ex=128x128)
![【POD】交尾む男~ツルむおとこ~(1) [ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7412/2300000097412.jpg?_ex=128x128)
![新・校内写生(1) &校内写生リターンズ (ニチブンコミックス) [ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2182/9784537132182.jpg?_ex=128x128)
![リフレイム 超合本 1【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9701/2000013789701.jpg?_ex=128x128)
![Juliet ボクのお守り姫 超合本【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9680/2000013789680.jpg?_ex=128x128)
![学園天国ワイド版 大合本1 1〜2巻収録【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0415/2000006800415.jpg?_ex=128x128)
![学園天国ワイド版 大合本2 3〜4巻収録【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0289/2000006800289.jpg?_ex=128x128)
![Juliet 1【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4493/2000000154493.jpg?_ex=128x128)
![Juliet 〜ボクのお守り姫〜 3【電子書籍】[ 遊人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8344/2000006218344.jpg?_ex=128x128)