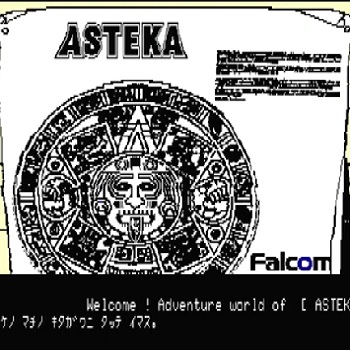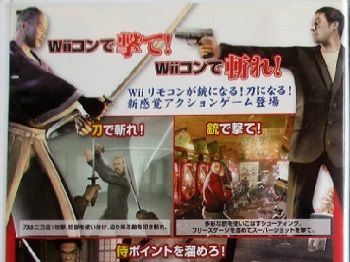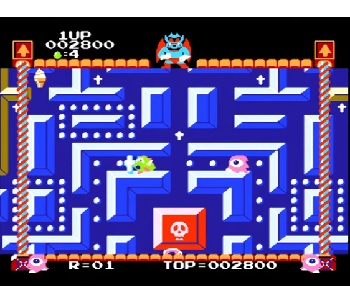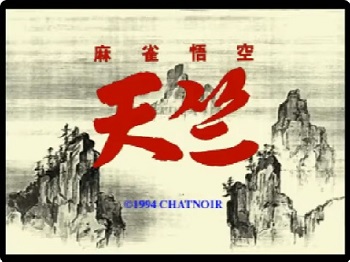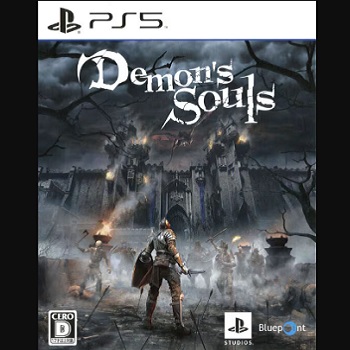
Demon's Souls




 評価 4.82
評価 4.82【発売】:ソニー・コンピュータエンタテインメント
【開発】:ブルーポイントゲーム
【発売日】:2020年11月12日
【ジャンル】:アクションロールプレイングゲーム
■ 概要
PS5ローンチを飾った伝説の再誕
2020年11月12日、ソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)は、PlayStation 5の発売と同時に『Demon’s Souls』をリメイク作品として世に送り出した。もともとは2009年にフロム・ソフトウェアが開発したPlayStation 3用アクションRPGとして登場し、後の“ソウルライク”というゲームジャンルを築いた歴史的作品である。PS5版は、ブルーポイントゲームズがリメイクを担当し、原作の骨格を忠実に守りながらも、グラフィック・サウンド・操作性を現代技術で徹底的に再構築している。 かつてゲーマーの間で語り草となった高難度と孤独な探索体験が、4K解像度の重厚な映像と立体音響、ハプティックフィードバックを備えたデュアルセンスコントローラーの感触によって新しい次元の没入感を獲得した。
制作の背景とリメイクの意図
ブルーポイントゲームズは、過去にも『ワンダと巨像』などの名作をリメイクしてきたスタジオであり、原作の精神を尊重しながらも最新ハードの力を最大限に引き出すことを使命としていた。開発チームは「一つひとつの石畳の質感まで忠実に再現する」と語り、ただの高解像度化ではなく、当時のプレイヤーが心の中で見ていた“理想のDemon’s Souls”を現実にすることを目指した。 結果として、PS5版はビジュアルだけでなく照明・陰影・質感・物理表現までも刷新され、霧の奥に潜む恐怖やボスの威圧感が生々しく伝わる仕上がりとなった。とりわけ、火炎に包まれる城壁や、魔術師の光弾が闇を裂く瞬間などは、単なるリマスターでは到底表現できないリアルさを持つ。
物語と世界設定
舞台は北の王国「ボーレタリア」。王アラントが禁断の力「ソウルの力」に溺れ、封印されていた“古の獣”を呼び覚ましたことで、国は色のない濃霧に覆われ、魂を喰らうデーモンが跋扈する荒廃の地と化した。プレイヤーは“デーモンを狩る者”として、死者たちの魂が集う「楔の神殿」に召喚され、5つの異なる世界へと旅立つ。そこには腐敗に満ちた坑道、亡霊の支配する塔、嵐の海岸、忌まわしい沼地などが存在し、それぞれが独自の地形と物語を秘めている。 ゲーム開始直後、プレイヤーは圧倒的な絶望感に包まれるが、その中で小さな達成を積み重ねていくことで、やがてこの異界の理不尽さすら美しく感じるようになる。リメイク版では、この“世界の沈黙と孤独”をより深く感じられるよう、環境音やエフェクトの調整が施され、PS5の3Dオーディオによって濃霧の向こうでうごめく敵の気配が耳でわかるほど繊細に再現されている。
ゲームシステムの核 ― 死と再生のループ
『Demon’s Souls』を語るうえで欠かせないのが、“死”を通じて学ぶという設計思想である。プレイヤーは幾度となく倒されながらも、敵の配置、罠の構造、攻撃パターンを少しずつ理解し、再挑戦を繰り返す。このプロセスそのものがゲーム体験の核であり、単なる失敗ではなく成長の証として機能する。 敵を倒すことで得られる“ソウル”は、レベルアップや装備の強化、魔法の習得に用いられるが、死ぬと全てをその場に落としてしまう。再びそこまで辿り着けば取り戻せるが、再び死ねば完全に失われる。だからこそ、プレイヤーは一歩一歩に緊張を伴い、慎重さと大胆さのバランスを試されるのだ。PS5版ではロード時間がほぼ皆無となり、死から再挑戦までがわずか数秒。テンポは向上しつつも、この冷徹なリスク構造は変わらない。むしろ快適さが失敗の恐怖を際立たせているとも言える。
PS5で進化した体験表現
デュアルセンスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーによって、武器の重さや盾での受け流し感が指先に伝わる。重厚な剣を振るうときの抵抗、矢を射る瞬間の緊張、魔法詠唱の脈動――これらは単なるボタン操作を越え、肉体で戦う感覚をもたらす。 また、光と影の表現が格段に進化し、松明の炎が壁を照らし、霧がゆらめく中に潜む敵の輪郭が浮かび上がる。ロード時間の短縮によって、ステージ間の移動もシームレスとなり、没入感が切れることはほとんどない。まるでプレイヤー自身がボーレタリアに閉じ込められたような錯覚を覚える。
オリジナル版からの変化と継承
PS5版は単なる“復刻”ではなく、ゲームデザインの哲学そのものを再現する“再構築”である。オリジナル版のもつ不気味で緊張感ある世界観を崩さぬよう、演出面の方向性はほぼ踏襲しつつ、操作性やUIを現代的に整備。 一方で、光源処理の変化により一部のボス戦では印象が変わったり、キャラクターデザインの解釈が分かれたりと、ファンの間で議論を呼んだ部分もある。それでも、原作で培われた“理不尽と公平の狭間を歩く楽しさ”は健在であり、今も多くのプレイヤーがその緊張と充実を噛みしめている。 また、オンライン要素として存在した「他プレイヤーの血痕」「幻影」「メッセージ」などのシステムも完全に再現。現代のサーバー環境に合わせて安定化され、PS3版では不安定だった通信面も格段に向上した。
芸術としての「孤独な探索」
『Demon’s Souls』の魅力は単なる難易度やアクション性に留まらない。敵の配置一つ、アイテムの位置一つが緻密に計算され、プレイヤーが絶望から希望へと導かれる心理的曲線を描いている。BGMは必要最低限に抑えられ、風の音や鎖の軋む音が恐怖を増幅させる。 プレイヤーは常に孤独でありながら、オンラインを通して他者の存在を“感じる”ことができる。この非同期的なつながり――つまり他人の死の痕跡や、警告のメッセージが残ることで成立する緩やかな共存――こそが、本作をただのアクションRPGではなく、人間の生と死、希望と絶望を描いたインタラクティブアートへと昇華させている。
評価と影響
PS5版『Demon’s Souls』は、その完成度とリメイク手腕が高く評価され、世界中のメディアから数々の賞を受賞した。グラフィックやロード時間の短さはもちろん、原作を知らない新規プレイヤーにも“これが次世代の体験だ”と印象づける出来栄えであった。 一方、難易度の高さやプレイヤーへの説明不足といった点もそのまま継承されており、「親切な設計ではないが、それが魂を燃やす」と評されることも多い。結果として、このリメイクはただの懐古ではなく、挑戦することの価値を改めて問い直す作品として、2020年代のゲーム文化に深い足跡を残した。 その後、『エルデンリング』などフロム作品に触れる若い世代の多くが、このPS5版をきっかけに原点を知り、改めて“死にゲー”の原型がここにあったことを再認識している。
■■■■ ゲームの魅力とは?
プレイヤーを試す「死」と「学び」の快感
『Demon’s Souls』最大の魅力は、他のどんなゲームとも異なる“死の意味”の重さにある。多くのゲームでは、死は単なるリセットだが、この作品では死が学びの過程そのものである。敵の配置や罠の仕掛けを理解し、ミスを反省し、慎重に再挑戦する。その一連の過程が、プレイヤーの成長を肌で感じさせる。 プレイヤーが経験するのは「絶望」から「覚醒」への変化だ。最初は敵の一撃で倒される無力感に苛まれるが、次第にその行動を読み、対策を立て、ついには勝利を掴む。その達成感は他のどんな報酬よりも強烈で、“自分自身の力で困難を超えた”という実感を与えてくれる。PS5版ではロード時間の短縮によりテンポよく再挑戦でき、挑戦と克服のリズムがより自然に感じられるようになった。
緻密に設計された「孤独の美学」
このゲームの世界には、派手な演出も賑やかな会話もほとんど存在しない。静寂と陰影、遠くで聞こえる風や鎖の音が、プレイヤーに圧倒的な孤独を感じさせる。 だがその孤独こそが、『Demon’s Souls』の世界を支える美学だ。PS5の高精細グラフィックによって、崩れかけた石橋、薄暗い通路、霧の向こうで揺れる松明の炎などが現実のような質感で描かれ、プレイヤーの想像力を刺激する。 そして、他のプレイヤーが残した血痕やメッセージが、見知らぬ人との“ゆるいつながり”を生み出す。これは従来のマルチプレイとは違い、他者の存在を感じながらも孤独に戦うという、独自の感情体験をもたらす仕掛けである。
PS5世代で蘇る圧倒的な没入感
次世代機の性能を活かした本作では、すべての感覚が“体験の質”を向上させている。ハプティックフィードバックによる武器の重みや衝撃の再現、アダプティブトリガーの抵抗感が戦闘をよりリアルにする。剣を振ると手元に残る反動、盾で受けた際の鈍い振動が、まるで自分が本当に戦っているかのような錯覚を与える。 また、PS5の3Dオーディオは恐怖を新たな次元に引き上げた。敵の足音がどの方向から近づくのか、見えない何かが背後に立っているのか——その音の立体感がプレイヤーの緊張を極限まで高める。 さらにロード時間のほぼゼロ化によって、死から再挑戦までの流れが途切れず、ストレスではなく挑戦欲を生むテンポが維持されている。技術的進化が、ゲームデザインの哲学と完全に融合しているのだ。
世界観の語り方 ― 「沈黙の物語」
『Demon’s Souls』は、セリフやムービーで物語を説明しない。世界の断片、残された遺体、朽ちた碑文、そしてNPCの何気ない独り言から、プレイヤーが自ら“物語を読み解く”。 これは「環境叙述」と呼ばれる手法であり、プレイヤー自身が探索を通じて世界の過去を再構築する体験が生まれる。ボーレタリアの滅びの理由、かつての英雄たちの最期、デーモンの正体――すべてがプレイヤーの想像力に委ねられている。 PS5版では、光と影のコントラストや微細な環境音が加わり、無言のストーリーテリングがより深みを増している。例えば、湿った洞窟に響く水滴の音や、亡霊の呻き声が遠くから聞こえる瞬間など、言葉ではなく空気で物語る演出が印象的だ。
緊張と報酬のバランス
『Demon’s Souls』のプレイ体験は、常に緊張と報酬の絶妙なバランスの上に成り立っている。ひとつのミスで全てを失う可能性があるからこそ、成功の一瞬が何倍もの快感になる。 ボス戦では、敵の動きを読み、攻撃を受け流し、隙を突く。わずかな油断が死を招くが、それを克服して勝利を掴んだ瞬間の高揚は筆舌に尽くしがたい。 さらに、攻略の順序をプレイヤー自身が選べる自由度も魅力の一つだ。どのエリアから挑むか、どの武器や魔法を使うか、誰と協力するか。自由であるがゆえに、責任もすべてプレイヤーに委ねられる。自分だけの冒険を設計する面白さが、何度も周回プレイを誘発する。
非同期型オンラインの革新
本作のオンライン要素は、今なお斬新だ。プレイヤーは他者の世界に干渉しないが、残した“痕跡”が世界に影響を与える。 地面に残された警告メッセージ、誰かの血痕、協力プレイや侵入といったシステムが、有機的に繋がり合っている。この非同期的な交流は、プレイヤー同士が直接会話することなく、互いの存在を感じる不思議な温かみを持つ。 CEDEC AWARDSで「非同期型コミュニケーション」として高く評価されたように、この仕組みは『Demon’s Souls』を単なるゲームの枠を超えた“体験装置”にしている。
リメイクによる再発見と再評価
PS5版『Demon’s Souls』の登場は、かつての名作を知らない世代にその魅力を再認識させるきっかけとなった。 新しい世代のプレイヤーは、映像の美しさにまず驚き、やがてその奥に潜む“恐ろしくも美しい哲学”に引き込まれていく。ゲームが単なる娯楽ではなく、人間の忍耐と理解を試すアートであることを体感するのだ。 一方で、オリジナル版を知るベテランは、細部の変化に懐かしさと新鮮さを同時に覚える。過去と現在の技術が交錯するこのリメイクは、単なる再生産ではなく、文化的リマスターとしての価値を持っている。
“ソウルライク”の原点としての存在感
今日、数多くの「ソウルライク」ゲームが生まれているが、その根底には『Demon’s Souls』が築いた設計思想がある。 高難度、リスクとリターンの緊張感、プレイヤーの理解力に依存するシステム設計、そして孤独な探索の中にある希望。これらの要素が、後の『DARK SOULS』や『BLOODBORNE』、『ELDEN RING』へと受け継がれた。 PS5版の登場は、改めてこの作品が“原点”であることを証明した。リメイクによって最新技術を纏いながらも、その哲学は一切揺らがず、むしろ現代のゲームに欠けがちな“プレイヤーの尊厳”を取り戻したと言える。
■■■■ ゲームの攻略など
最初の一歩 ― クラス選択の重要性
『Demon’s Souls』では、ゲーム開始時に選択するクラス(職業)が攻略難易度を大きく左右する。初心者に人気が高いのは「神殿騎士」や「王族」だ。神殿騎士は高い防御力と信仰による回復奇跡を兼ね備え、序盤の生存率が高い。一方、王族は魔法使いタイプで、MP自動回復という特性を持ち、遠距離攻撃によって安全に敵を倒せる。 ただし、どのクラスを選んでも最終的には自由に成長できる。重要なのは、自分の得意な戦闘スタイルを見つけることだ。近接で敵を斬り伏せる爽快さを求めるなら戦士系、慎重な立ち回りを好むなら魔法型を選ぶとよい。 PS5版では操作の反応速度が向上しているため、盾受けから反撃に転じる「パリィ」や回避を駆使する戦い方がより直感的に行える。初心者も恐れずに、まずは自分のスタイルを確立することが攻略の第一歩となる。
序盤の指針 ― 学びと準備の時間
最初のダンジョン「ボーレタリア宮」は、チュートリアル的な要素を持ちながらも、決して易しくはない。敵の動きを観察し、盾で防御し、反撃のタイミングを覚える。この“観察と対応”こそが、すべての基本となる。 また、序盤で特に意識すべきは「ソウルの使い方」だ。敵を倒すと得られるソウルは、レベルアップや武器強化に使用できる貴重なリソースだが、死ぬと失われる。最初は不用意に貯めず、こまめに拠点へ戻って使う習慣をつけることが大切だ。 攻略のリズムを掴むうえでは、「恐れず死ぬ」ことも重要。初見の罠や敵の挙動を体験し、次に備える。死を重ねるたびに自分の行動が洗練され、世界の仕組みを理解していく。このサイクルを受け入れた瞬間から、本作の本当の面白さが開花する。
ボス戦 ― 緊張と戦略の極致
各ステージの最深部には“デーモン”と呼ばれる強力なボスが待ち受けている。どのボスも見た目・行動・弱点が異なり、プレイヤーに新たな戦い方を要求する。 例えば、「塔の騎士」は巨大な盾と槍を持つ強敵だが、まず周囲の弓兵を排除してから脚を攻撃することで隙を作れる。「ファランクス」戦では、中心のボスを守るスライム兵を火炎壺で焼き払う戦術が有効だ。 本作のボスは単純な“強さ”よりも、“攻略の理解度”を問う設計になっている。ボスの挙動を観察し、行動パターンを覚えることが勝利への近道だ。無理に攻撃せず、敵の癖を見極めて少しずつ削る冷静さが求められる。 PS5版ではアニメーションや攻撃モーションがより滑らかになり、ボスの動きが読みやすくなっているため、反応重視のプレイヤーには有利に感じられるかもしれない。
魔法・奇跡・武器強化の使いこなし
『Demon’s Souls』では、戦闘手段が多彩だ。 魔法は遠距離から敵を焼き払う強力な手段であり、特に「ソウルの矢」「火の玉」などは序盤から終盤まで頼りになる。奇跡は回復や補助を担い、探索の安定性を高める。信仰値を上げれば強力な回復魔法を使えるようになり、長期戦での生存率が上がる。 武器強化も非常に重要で、楔石や魂を用いて段階的に性能を上げていく。物理攻撃力を上げるだけでなく、属性を付与して特定の敵に有利に立ち回ることもできる。たとえば「炎のロングソード」は、スライム系の敵に絶大な効果を発揮する。 PS5版ではエフェクトや衝撃音がより明確になっており、魔法の詠唱や武器の一撃に“手応え”がある。見た目の美しさだけでなく、成長の実感を五感で味わえるのがリメイク版の特徴だ。
ソウル傾向とイベントの理解
『Demon’s Souls』特有のシステム「ソウル傾向」は、プレイヤーの行動によって世界が変化するという仕組みだ。敵を倒す、NPCを救う、あるいは誤って人を殺すなどの行為が、世界を「白」または「黒」に傾けていく。 白傾向の世界では敵が弱体化し、新たな道が開かれたり、NPCイベントが発生したりする。逆に黒傾向では敵が強化され、報酬が増える一方で危険度も上がる。 この複雑なシステムを理解し、意図的に傾向を操作することが上級者への道だ。PS5版では、オリジナルよりも傾向が視覚的にわかりやすくなり、攻略の計画が立てやすくなっている。 プレイヤーは単に敵を倒すだけでなく、「世界そのものをどう導くか」という選択を常に迫られているのだ。
マルチプレイ ― 協力と侵入の駆け引き
オンラインプレイもまた、攻略の一部として重要である。協力プレイでは、他のプレイヤーを自分の世界に召喚し、強敵を共に討伐できる。一方で、他人の世界へ“侵入”して戦いを挑むプレイヤーも存在する。 この協力と敵対の両立が、『Demon’s Souls』のオンライン体験をユニークなものにしている。味方として共闘するか、あるいは自ら悪意を帯びた“黒ファントム”となるかは自由。 PS5版ではサーバーの安定性が向上し、マッチング速度も快適になっている。戦略的な協力プレイを通して強敵に挑む楽しさはもちろん、緊張感あふれる侵入戦での心理戦も健在だ。 また、他者が残した血痕やメッセージが攻略のヒントになることも多く、オンラインの“痕跡”がプレイヤーの命を救う場面もある。
周回プレイと成長のループ
一度クリアすると、より強い敵と報酬が待つ“2周目”に突入する。これは「New Game+」と呼ばれ、プレイヤーの装備やステータスを引き継いだまま、より過酷な挑戦に挑むモードだ。敵の攻撃力やHPが大幅に上がるが、得られるソウルも多くなる。 この周回プレイが、本作の中毒性を生んでいる。完璧な装備を揃える、未クリアのイベントを回収する、異なる戦闘スタイルを試す――プレイヤーごとに目的が変化し、無限のリプレイ性を持つ。 PS5版では、ロードの速さと映像の美しさがその没入感をさらに高めており、つい“もう一周だけ”と続けてしまう。周回を重ねるほど、ボーレタリアの世界はより深く、より悲しく、そして美しく見えてくる。
攻略の心得 ― 「焦らず、観察し、学ぶ」
最も重要なのは、焦らないこと。『Demon’s Souls』はスピードよりも理解を重視するゲームだ。 敵の動きを観察し、環境を読み、少しずつ安全地帯を確保する。攻撃よりも防御を優先し、確実なタイミングで反撃する。この地道な積み重ねが、どんな強敵にも通じる最強の攻略法だ。 そして何より、「死ぬことを恐れない」こと。死は終わりではなく、次へのヒントだと考える。この哲学こそが、プレイヤーを真の意味で強くする。 本作を攻略するとは、単にゲームをクリアすることではない。自分の心の弱さを乗り越えることそのものが、『Demon’s Souls』という作品の真のゴールなのだ。
■■■■ 感想や評判
プレイヤーが語る“原点回帰の衝撃”
2020年にPS5と同時発売された『Demon’s Souls』リメイク版は、世界中のゲーマーに強烈な印象を残した。 発売当初からSNSやゲームメディアのレビュー欄は興奮に満ち、「これぞ次世代機の幕開けにふさわしいタイトルだ」「初めて霧の向こうに足を踏み入れた瞬間、息を呑んだ」といった声が相次いだ。 多くのプレイヤーが特に驚いたのは、ビジュアル表現の進化と忠実な再現性の両立だった。PS3版の記憶を持つ古参プレイヤーは「昔の記憶の中の理想の風景が、そのまま現実になった」と表現し、新規プレイヤーは「難しいのに手を止められない」と感嘆した。 単なるリメイクに留まらず、当時の感情を再現することに成功した点が、最も高く評価されている。
メディア評価 ― 技術と哲学の融合
各国のゲームレビューサイトでも高評価が続出した。Metacriticでは平均スコア90点台を記録し、IGNやGameSpotなど主要メディアが“グラフィック、操作性、忠実度、そして魂を受け継いだ設計哲学”を絶賛した。 特に注目されたのは、次世代機の性能を活かしながらも原作のゲームデザインを壊さなかった姿勢だ。ロードの短さや操作感の滑らかさが新鮮でありながら、理不尽なほどの難しさや緊張感は健在。 日本国内のレビューでは、「このゲームがあったからこそ、ソウルシリーズの文化が生まれた」「プレイヤーを信じる設計が素晴らしい」との意見が多く見られた。 グラフィックや操作の快適さだけでなく、“プレイヤーの体験そのものを尊重した設計”こそが、長年愛され続ける理由だと評価されている。
初心者とベテランで異なる印象
リメイク版を通じてシリーズ初挑戦となったプレイヤーも多いが、彼らの多くが口にしたのは「死んでも諦めたくならない」という点だ。 一般的に高難度ゲームは挫折を生みやすいが、『Demon’s Souls』は逆にプレイヤーを挑戦へと駆り立てる。 失敗しても“自分のせい”だと納得できる公平なルール設計、そして小さな成功が積み重なる達成感が、挑戦を続ける動機になる。 一方、PS3版経験者は「当時の恐怖と孤独が、より美しく蘇った」と語る。霧の質感や音の演出が深まり、当時の記憶を上書きするような没入感を味わえたという。 つまり、新旧プレイヤー双方が異なる角度から同じ感動を共有できる――これこそがリメイクの理想的な姿だ。
オンライン体験への賛辞
ネット上では、非同期型オンラインシステムへの再評価も多く見られた。 他のプレイヤーの血痕やメッセージが残り、それを通じて匿名の協力や裏切りが起こる。この絶妙な“距離感”が、「人との繋がりを最小限の情報で感じさせる革新」として再び注目を集めた。 PS5版では通信の安定性が向上したこともあり、「侵入戦がよりスリリング」「協力プレイが快適になった」といった感想が多い。 他人の失敗から学ぶ、知らない誰かに助けられる――この非同期コミュニティの体験は、現代のオンラインゲームにも通じる“匿名共感”の原点として再評価されている。
ビジュアル面の驚嘆 ― “記憶を超えた再現”
プレイヤーから最も多く寄せられた称賛は、やはりビジュアルの美しさだ。 オリジナルの持つ退廃的で静謐な雰囲気を壊すことなく、4K/HDRによる光と影の演出が新たな芸術性を生んだ。 松明の炎が壁を照らし、濃霧が揺らめき、血の跡が湿った床に滲む――その一つひとつが恐ろしくも美しい。 特に人気が高いのは、ボーレタリア王城の石畳や、嵐の祭祀場で雷が走る瞬間など、息を呑むほどの景観描写。 一部では「原作の荒削りな雰囲気が好きだった」という声もあったが、総じてリメイク版の映像美は“記憶の中の理想形”を忠実に形にしたと評価されている。
批評家たちが語る“挑戦するゲームの価値”
多くの批評家が指摘するのは、『Demon’s Souls』が持つ“プレイヤーを信じる哲学”だ。 現代の多くのゲームがチュートリアルや誘導でプレイヤーを守る中、本作は一切手を差し伸べない。 だからこそ、成功した瞬間の喜びが格別であり、「ゲームの本質的な面白さを思い出させてくれる作品」と評される。 一方で、「万人向けではない」「説明が少なすぎる」といった指摘もあるが、それを欠点ではなく“美学”として受け止めるプレイヤーが多い。 この作品を通して、ゲームが“易しさ”ではなく“理解”によってプレイヤーを導くメディアであることを再認識したという意見も少なくない。
サウンドと没入感への感動
レビューではグラフィックだけでなく、サウンドデザインにも高い評価が集まった。 PS5の3Dオーディオ機能を最大限に活かした立体的な音響が、恐怖と緊張を倍増させている。 遠くで響く剣戟、風の唸り、滴る水音――それらがすべてプレイヤーの位置感覚に作用し、世界の“温度”まで感じられるようになった。 BGMも印象的で、ボス戦では重厚なオーケストラが流れ、戦闘の緊迫感を演出する。静けさと激しさの対比が絶妙で、音そのものがストーリーテリングの一部となっている。 多くのプレイヤーが「ヘッドホンで遊ぶと別次元」「恐怖と美しさが同居する音の芸術」と語っている。
日本国内コミュニティでの熱狂
国内SNSや掲示板では、発売当時から“デモンズリメイク祭り”とも呼べる盛り上がりを見せた。 攻略情報を共有し合う文化は健在で、プレイヤー同士が「ここに隠し通路がある」「このNPCを助けるとイベントが変化する」といった発見を楽しんでいる。 また、フォトモード機能によって美しい景観を撮影し、SNSで共有する動きも盛んだ。「ただのゲームではなく、世界を旅する体験」と表現するプレイヤーも多く、 リメイク版は“見る・聞く・感じる”全感覚的な作品として再評価されている。
批判的な意見と受け止め方
もちろん、すべてが絶賛というわけではない。 一部のプレイヤーは「難しすぎて途中で投げ出した」「原作の荒々しさが失われた」と指摘する。 しかし、それすらも『Demon’s Souls』らしい議論を呼ぶ要素として受け入れられている。 ゲームにおける“理不尽と挑戦”の境界を再び問い直す契機となり、プレイヤー同士が哲学的な対話を交わす姿も見られた。 この作品は、単なる娯楽の枠を超えて、「挑戦するとは何か」「人はなぜ困難に惹かれるのか」という普遍的なテーマを問い続けている。
総評 ― 2020年代に蘇った魂の名作
『Demon’s Souls』PS5版は、単なる過去の名作の復活ではなく、“新たな文化の継承”と言える。 その難しさも、孤独も、そして達成感も、2020年代の最新技術と共に再び息を吹き返した。 「懐かしいのに新しい」「苦しいのにやめられない」――そんな矛盾した感情こそが、このゲームの本質であり、世界中のプレイヤーがこの矛盾を愛している。 リメイク版によって、初めて本作に触れた人も、十年以上前から魂を捧げてきた人も、共通して感じたのはただ一つ。 “この世界には、確かに魂がある”ということだ。
■■■■ 良かったところ
PS5の性能を最大限に活かした圧倒的グラフィック
多くのプレイヤーがまず賞賛したのは、PS5という新世代ハードの性能をフルに引き出したグラフィックの美しさだ。 4K解像度による細部の描写、レイトレーシングを用いた光と影のコントラスト、そしてHDRによる自然な色彩。 これらが融合することで、ボーレタリアの崩れた石畳の質感、霧の流れ、炎の反射などが生々しく再現されている。 特に暗闇の奥から松明の灯りが揺れる瞬間や、雷鳴が轟く嵐の祭祀場など、原作では想像するしかなかった情景が、リアルな質感を伴って現れる。 “美しいのに怖い”“絶望の中に荘厳な美がある”という独特の雰囲気が、PS5の技術によって芸術的なレベルにまで高められている。
ロード時間の短さがもたらす快適なテンポ
PS3版では、死ぬたびに数十秒待たされるロード時間があった。しかしPS5版では、それがほぼ消滅。 わずか数秒で再挑戦できるため、失敗してもすぐに立ち上がることができ、テンポの良さがプレイ意欲を維持させてくれる。 このロードの短縮は単なる快適性の向上にとどまらず、“死と再挑戦”という本作の哲学そのものをより自然に感じさせる。 死を恐れず、試行錯誤を繰り返す。このゲームが伝えたいメッセージを、ロード時間の短さが支えている。 その結果、プレイヤーはストレスよりも“挑戦の快感”を強く感じるようになり、没入感が格段に高まった。
原作の魂を尊重したリメイクの完成度
ブルーポイントゲームズによるリメイクの姿勢は、「原作への深い敬意」が感じられると高く評価された。 キャラクターの動きや敵の挙動、マップの構造、戦闘のバランスなど、すべてが忠実に再現されている。 しかし単なるコピーではなく、UIの改善や操作レスポンスの調整など、現代的なプレイ感覚に合うよう随所に洗練が施されている。 特にメニュー操作の直感性、アイテム管理のしやすさ、カメラ操作の滑らかさなど、細かい改善点が快適さを生み出している。 これにより、「懐かしいけれど新しい」という理想的なリメイク体験が実現した。
デュアルセンスによる“手応えのある戦闘”
PS5のデュアルセンスコントローラーが生み出すハプティックフィードバックは、戦闘の感触を新次元へと引き上げた。 剣を振るうたびに感じる金属の重み、盾で攻撃を受け止めた際の衝撃、魔法詠唱の振動――それらがすべて指先に伝わる。 特に大型武器で敵を叩きつけたときの“ドンッ”という反動は圧巻で、まるで本当に鋼を打ちつけているような感覚だ。 また、アダプティブトリガーによって弓を引くときの抵抗や魔法詠唱の力の溜まりが実感できる。 プレイヤーの五感を刺激し、単なるボタン操作を“体験”へと変換した革新として、多くのレビューで称賛された。
没入感を支える音響デザインとBGM
本作の音響表現は、グラフィックと並んで高く評価されている。 PS5の3Dオーディオ機能によって、敵の足音や鎧の軋み、遠くで鳴る風や炎の音が立体的に響き渡る。 ボーレタリア城の静寂を破る剣戟音や、デーモンの咆哮が背後から迫る感覚は、まるでホラー映画のような緊張感を生み出す。 また、オーケストラアレンジされたBGMも圧巻で、特にボス戦では壮大で悲壮な旋律が戦いの重みを強調する。 音の静と動を巧みに使い分けることで、プレイヤーの感情を自然に導く設計となっており、耳で感じるドラマを体験できる。
緊張と達成のバランスが完璧
『Demon’s Souls』の魅力は、絶望の中に小さな希望を見出すゲームデザインにある。 敵は強く、油断すれば一撃で倒されるが、努力と理解によって必ず乗り越えられる。 この“理不尽ではない難しさ”が、多くのプレイヤーを虜にした。 攻略を進めるごとに成長が実感できるため、敗北さえも次の勝利へのステップとして楽しめる。 PS5版では操作性の改善により、ミスが理不尽に感じる場面が減少し、より純粋に「自分の腕で勝った」という満足感を得られるようになった。 一度ボスを倒した瞬間の“震えるような達成感”は、この作品を語るうえで欠かせない。
フォトモードの導入で広がる楽しみ方
リメイク版から追加されたフォトモードは、意外にも多くのファンから好評を得ている。 戦闘の合間にキャラクターや風景を自由に撮影でき、表情やフィルター、構図を細かく調整することも可能。 この機能によって、プレイヤーは自分だけの“ボーレタリア紀行”を記録する楽しみを得た。 TwitterやInstagramでは、霧に包まれた城壁や、血塗られた戦場の中で微笑むキャラクターなど、芸術的なスクリーンショットが多数共有されている。 フォトモードは単なるオマケではなく、この世界の美しさを再発見するツールとして機能している。
NPCとストーリーの奥深さ
NPCとの出会いと別れもまた、多くのプレイヤーの心に残った。 救いを求める者、堕落した騎士、信仰に狂った聖職者――どのキャラクターにも悲劇があり、彼らの行動には必ず理由がある。 プレイヤーがどう行動するかによって、彼らの運命が変わることもあり、一度きりの出会いが強い印象を残す。 PS5版では表情の描写や声優演技がより繊細になり、彼らの“心の揺れ”が伝わるようになった。 とくに「火守女」や「オストラヴァ」との関わりは、多くのプレイヤーが“この世界での唯一の救い”と語っている。
コミュニティ文化と再び生まれた熱狂
リメイク版の登場により、かつての『Demon’s Souls』コミュニティが再び活気を取り戻した。 攻略情報を共有したり、協力プレイで助け合ったりする文化がSNSや動画配信で再燃。 「初見殺しの罠に驚くリアクションを楽しむ配信者」や「ボスを素手で倒す挑戦動画」など、プレイヤー発のコンテンツも増加した。 この再び巻き起こった熱気は、“デモンズの時代が帰ってきた”と評され、PS5の普及初期における象徴的な存在となった。 古参ファンにとっては懐かしさを、新規プレイヤーには新鮮な挑戦を与える。世代を超えて魂が繋がる瞬間が、このリメイクによって実現したのである。
まとめ ― 完成されたリメイクの理想形
総じて『Demon’s Souls』PS5版の“良かったところ”は、原作の精神を損なわずに、現代の技術で再構築した完成度に尽きる。 ビジュアル、操作、音響、テンポ、演出、どの要素を取っても次世代機のショーケースにふさわしい。 それでいて、ゲームデザインの哲学は一切変えず、プレイヤーが自らの力で困難を克服する構造を維持している。 この“古さと新しさの完璧な融合”こそ、多くのレビューが満点を付けた最大の理由だ。 リメイクの在り方を示す模範として、後世のゲーム開発者にも影響を与え続ける作品である。
■■■■ 悪かったところ
初心者には依然として高すぎるハードル
『Demon’s Souls』はリメイクによって操作性や快適さが大きく改善されたものの、難易度そのものはオリジナルと変わらず非常に高い。 特に初見のプレイヤーにとっては、「どこで何をすべきかが分からない」という状況に陥りやすい。 序盤から容赦ない敵の配置やトラップが連続し、ほんの数分で何度も死を繰り返すことになる。 この難しさはシリーズの“味”でもあるが、ゲーム初心者には理不尽と感じられることも多く、「チュートリアル不足」「説明が少なすぎる」といった不満が見られた。 リメイクにあたり、もう少しプレイヤーを導く工夫――たとえば、最初のボーレタリア宮攻略で少しだけガイドを設けるなど――があっても良かったという声は少なくない。
操作レスポンスの改善が“原作の感覚”を変えた
PS5版は全体的に操作の応答が良く、カメラの挙動や攻撃動作もスムーズになっているが、それが一部の原作ファンには「違和感」として映った。 オリジナルのPS3版では、武器の重さを感じさせる“鈍さ”が緊張感を生んでいた。 しかしリメイク版ではモーションが軽快になり、“武器を振るたびの重み”や“遅れによる判断の妙”が薄れたと感じる人もいる。 また、一部の敵AIの挙動が変更されているため、原作で有効だった戦法が通用しないケースもあり、古参プレイヤーには戸惑いを生んだ。 リメイクとして完成度は高いが、「違いを楽しむ余裕」がない人にはマイナス要素に感じられる部分である。
キャラクターデザインの賛否
PS5版のキャラクターやモンスターのリデザインは、全体的に写実的でリアルな方向に振られている。 しかしこれが、「原作の持つダークファンタジー的な不気味さが薄まった」と感じる人も多かった。 特に、火守女(メイデン・イン・ブラック)やいくつかのボスの造形は、“恐ろしさよりも美しさが強調された”と評される。 結果として、PS3版で漂っていた“異形の世界に迷い込んだような不安感”が若干弱まったという意見が散見される。 ブルーポイントがリアルさを追求した結果としての変化ではあるが、“想像に任せる余白”を好むプレイヤーからは惜しまれる点となった。
新規ボーナス要素の少なさ
リメイク版は原作を忠実に再現する方針のため、新しいストーリーやステージなどの追加要素がほとんどない。 一部のファンは、「せっかくのリメイクなのだから、新しいボスや隠しイベントがあってもよかったのでは」と感じている。 PS5のハードパワーで新たな挑戦を期待していた層からは、“リメイクというよりリビルドに留まった”というやや残念な評価も見られた。 例えば、未実装エリアとして有名な「嵐の地の六つ目のアーチストーン」が復活するのではと噂されたが、実現はしなかった。 原作への敬意を重視した判断とはいえ、追加要素を望むファンにとっては少々物足りない結果だった。
ボイス・演出の印象が変わった部分
一部のキャラクターのボイスアクターや演技方向が変更されたことも議論を呼んだ。 オリジナル版で印象的だった台詞回しやトーンが変更され、キャラクターの印象が微妙に変化している。 特に“火守女”の語り口がやや感情的になった点や、“ストーンファング坑道”の鍛冶屋エドの声質が異なる点は、ファンの間で好みが分かれた。 PS5版の演出はリアル寄りの演技を追求しているため、ゲーム的な演出の誇張が抑えられたことによる“印象の薄れ”が指摘されることもある。 映画的な表現を求めた結果としての自然な進化だが、原作独特の“奇妙な台詞回し”を懐かしむ声も少なくない。
難易度調整の偏り
全体として難易度の設計は原作を維持しているが、部分的に戦闘バランスの調整が加えられたことで、一部エリアの難度が極端に感じられる。 特に「腐れ谷」や「嵐の祭祀場」では、敵の攻撃力と数が多く、初見ではほとんど逃げ場がない。 一方で「塔のラトリア」や「ファランクス」などは対策が分かると一気に楽になるなど、難易度のムラが残っている。 また、強力な武器や魔法を早期に入手できるバランスも健在で、知識があるプレイヤーは序盤を簡単に突破できてしまう。 攻略の自由度が高い反面、初見と熟練の差が非常に大きく出るゲーム構造になっている点は賛否が分かれる部分だ。
物語の演出が希薄に感じられることも
『Demon’s Souls』は意図的に説明を省いた“沈黙の物語”が特徴だが、近年のストーリー主導型RPGに慣れたプレイヤーには不親切に映る。 物語の断片を拾い集め、背景を自分で想像する構成は深みがある反面、「何をしているのか分かりにくい」「目的が曖昧」と感じる人も多い。 PS5版では環境描写のリアリティが増したため、“語らない演出”がより強調され、ストーリーを追いたい層には冷たい作品と映る場合がある。 この点はフロム作品全般の特徴でもあるが、リメイクで少し補足説明や新規演出を追加する余地はあったかもしれない。
UIとメニュー操作のクセ
PS5版でUIは刷新されたものの、アイテムや装備の管理は依然として複雑だ。 持ち運べる重量の制限が厳しく、少し拾いすぎるとすぐに「重量オーバー」となってしまう。 特に初心者は、どのアイテムが重要か分からず、必要な装備を持ち帰れない状況に陥る。 倉庫に預けることで解決できるが、戦闘中に重量制限で動きが鈍くなる仕様は今なおストレス要素として残っている。 また、UIのデザインがスタイリッシュすぎて一目で理解しにくいとの指摘もあり、ゲームシステムの深さがUIに阻まれていると感じるユーザーもいた。
一部バグ・挙動不具合の報告
発売当初、一部プレイヤーの間ではフレームレートの乱れや特定条件下での敵挙動バグが報告された。 特にオンラインプレイ時のラグや、マルチプレイ中の同期ズレなどが発生することもあったが、後にパッチで改善されている。 大きな問題ではないものの、「PS5初期タイトルとしてはやや不安定な時期があった」という印象を持つユーザーも存在する。 安定性の向上によって快適に遊べるようになったが、初期の印象が一部のユーザー体験を損なった点は否めない。
高難度ゆえの“孤立感”
このゲームの魅力でもある“孤独な戦い”は、同時にプレイヤーを遠ざける要素にもなり得る。 他人との協力や会話よりも、孤独の中で淡々と挑み続ける設計は、人によっては「精神的にきつい」と感じる。 オンライン要素があっても、非同期型のためリアルタイムの助け合いができず、孤立感が強い。 その結果、「綺麗だけど寂しい」「達成感よりも虚無感が残る」と感じるプレイヤーも少数ながら存在する。 孤独の美学が極まった作品であるがゆえに、一部のプレイヤーにとっては過酷すぎる体験となってしまうこともある。
総評 ― 完璧ではないからこそ“デモンズ”らしい
こうした不満点を挙げるプレイヤーも多いが、それらは同時に『Demon’s Souls』の本質と深く結びついている。 完璧に整えられたゲームではなく、どこか不親切で、理解するまでに時間がかかる――だからこそ、クリアした瞬間の達成感が他の作品にはない重みを持つ。 リメイクとしては完成度が非常に高いが、“挑戦的な設計哲学”を維持した結果、万人向けにはなり得ない。 だが、それこそが『Demon’s Souls』という作品のアイデンティティであり、20年以上の時を超えても変わらぬ魂の証明と言えるだろう。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
火守女(メイデン・イン・ブラック) ― 闇の中で導く存在
『Demon’s Souls』の象徴的存在といえば、やはり「火守女(メイデン・イン・ブラック)」である。 彼女はプレイヤーが死と再生を繰り返す中で唯一、無条件に寄り添ってくれる存在だ。 目を閉ざし、静かな声で語りかけるその姿は、厳しい世界の中での“救い”であり、“癒し”でもある。 PS5版では彼女のキャラクターモデルが一新され、よりリアルな質感と穏やかな表情で描かれた。 声優の演技も深みを増し、わずかなトーンの変化で優しさと悲哀を同時に感じさせる。 「心の力を持つ者よ……ソウルを力に変えましょう」 このセリフはシリーズを象徴するフレーズとして、多くのプレイヤーの記憶に残っている。 彼女はプレイヤーを成長へ導くだけでなく、時にこの世界の運命そのものに関わる存在でもある。 静謐で、しかし確かな温もりを持つ彼女の存在は、絶望の世界における唯一の“光”といえるだろう。
オストラヴァ王子 ― 理想と現実の狭間で
ボーレタリアの若き王子「オストラヴァ」は、多くのプレイヤーにとって印象的な人物の一人だ。 彼は勇敢でありながらも繊細な理想主義者で、崩壊した王国を前に“正義”を貫こうとする。 プレイヤーが彼を助けることで一時的に共闘する場面もあり、その誠実な言動が胸を打つ。 しかし、ストーリーが進むにつれて彼の理想がいかに脆く、現実がいかに非情であるかを痛感させられる。 PS5版では彼の表情や声の演技がよりドラマチックに描かれ、感情の揺れが繊細に伝わるようになった。 プレイヤーが最後に彼と再会した時、その結末をどう受け止めるかは人それぞれだが、 多くの人が「彼の純粋さこそ、ボーレタリアの滅びの象徴だった」と語る。 英雄的でありながらも儚い――彼はまさに“悲劇的理想主義者”の象徴である。
鍛冶屋エドとボルドウィン ― 黙して支える者たち
激戦の合間に訪れる安息の場、「楔の神殿」には、プレイヤーの旅を陰で支える人物たちがいる。 その中でも鍛冶屋エドとボルドウィン兄弟は、多くのプレイヤーに親しまれている存在だ。 彼らは多くを語らないが、武器を鍛えるその背中に“職人としての誇り”が宿る。 エドは特別な魂を用いた武器強化を担う熟練の鍛冶屋で、火花を散らしながら鉄を打つ姿はまるで儀式のようだ。 一方でボルドウィンはどこか軽薄で口が悪く、時に皮肉を言うが、実は面倒見が良い。 この対照的な兄弟は、戦いに疲れたプレイヤーの心をふと和ませてくれる存在であり、 彼らの台詞一つひとつに“人間味”が感じられる。 「武器は命だ。錆びついた刃じゃ、勝てる戦も勝てねえぞ」 この一言が、デーモンに挑むプレイヤーを奮い立たせる。 彼らの存在は、冷たい世界の中で感じられる数少ない“ぬくもり”の象徴である。
“北の巨人の地”の伝承に関わる者たち
本作の未踏の地として語られる「北の巨人の地」。 PS5版ではその扉は依然として閉ざされたままだが、そこに関わるとされるキャラクターたちがプレイヤーの想像を掻き立てる。 特に“巨人の守り人”や“失われた英雄”の伝説は、登場人物の断片的な語りから断続的に語られるのみで、 その“語られない物語”がファンの間で人気を博している。 明確な姿を見せないからこそ、彼らの存在には神秘的な魅力がある。 ファンの間では「もしこの地が実装されていたら、どんなキャラクターが登場したのか」という議論が今も続いており、 その余白こそが“想像で世界を広げる喜び”を生んでいる。
失われた者たち ― NPCの悲哀
『Demon’s Souls』の登場人物は、例外なく悲しみや罪を背負っている。 腐れ谷の聖女アストラや彼女の護衛セレン・ヴィンランドなどは、信仰と現実の狭間で苦悩する人物として特に人気が高い。 アストラは清らかな祈りを捧げながらも、腐敗に覆われた谷で己の信仰を試される。 その結末はプレイヤーの行動次第で変わるが、どの道を選んでも“完全な救い”は訪れない。 このように、本作のキャラクターは誰もが「正義」と「破滅」の境界に立つ存在として描かれている。 PS5版では、彼らの表情や声の抑揚が繊細に再現され、プレイヤーの心に強い共感や罪悪感を呼び起こす。 人間の愚かさと美しさを同時に描き出すキャラクター造形こそ、『Demon’s Souls』の真髄といえる。
暗殺者ユーリア ― 悲しみと誘惑の魔女
“塔のラトリア”で出会う魔女ユーリアは、妖艶さと悲しみを併せ持つキャラクターとして人気が高い。 捕らえられた彼女を助けるかどうかによって、その後の展開が大きく変わる。 彼女の放つ魔法の力と、どこか儚げな微笑みは、プレイヤーに複雑な感情を抱かせる。 「私は……あなたの力になりたいのです」 この言葉の裏には、裏切りにも似た真意が潜んでいるかもしれない。 PS5版のリメイクでは、光沢のある瞳や繊細な動作がリアルに描かれ、 単なるNPCではなく、まるで生きている人間のような存在感を放つ。 彼女は“デーモンに堕ちる人間”の象徴でもあり、プレイヤー自身の欲望と恐れを映す鏡のようなキャラクターだ。
ストーンファング坑道の作業者たち ― 名もなき人々のドラマ
『Demon’s Souls』の世界には、名もなき人々の悲劇が散りばめられている。 ストーンファング坑道に登場する鉱夫たちは、かつて人間だったが、今はソウルに囚われた亡者と化している。 彼らは敵として登場するが、その動きはどこか人間らしさを残しており、攻撃するたびに罪悪感が胸を刺す。 PS5版ではその表情や挙動がよりリアルに描かれ、労働者としての苦しみや哀れさが一層際立つ。 一人ひとりに物語がある――そう感じさせる演出が、この作品全体の“悲劇の厚み”を支えている。 このような“脇役の存在感”こそ、『Demon’s Souls』のキャラクター描写の真骨頂だ。
プレイヤー自身が“もう一人の主人公”
『Demon’s Souls』の世界において、最も重要なキャラクターは“プレイヤー自身”かもしれない。 選んだ外見や性別、装備によって姿は異なるが、彼(彼女)は常に孤独と向き合う。 NPCとの会話や選択肢を通して、プレイヤーは何者でもない存在から“デーモンを狩る者”へと成長していく。 その過程で、プレイヤー自身がこの世界にとってどんな意味を持つのかを問い続ける。 PS5版ではキャラクターメイキングが大幅に進化し、細部まで自分の理想像を作り込める。 美しい英雄として戦うことも、恐ろしい亡者のような姿で生きることもできる。 “自分が物語の一部になる”という感覚が、リメイクによってより鮮明に感じられるようになった。
総評 ― 絶望の中の“人間ドラマ”
『Demon’s Souls』のキャラクターたちは、ただのNPCではない。 彼らはそれぞれの信念、後悔、欲望、祈りを胸に抱き、滅びゆく世界の中で懸命に生きている。 その姿にプレイヤーは共感し、時に苦しみ、時に救われる。 リメイク版では、表情や声の演出、光の描写によってその人間性がより鮮明に表現された。 どんなに世界が絶望に満ちていても、人が人を想う心がある限り、この物語は悲劇では終わらない。 火守女の囁き、オストラヴァの誇り、鍛冶屋の汗、アストラの祈り―― それらが織りなす人間ドラマこそ、『Demon’s Souls』という名の“魂の叙事詩”の真価である。
[game-7]
■ 中古市場での現状
PS5ローンチタイトルとしての位置づけと流通傾向
『Demon’s Souls』(PS5版)は、2020年11月12日にソニー・コンピュータエンタテインメント(現SIE)から発売されたローンチタイトルの中でも、特に注目度が高かった作品だ。 発売当初はPS5本体の品薄と重なり、「ハードが手に入らないのにソフトだけが売れている」という珍しい現象すら起きた。 そのため初期出荷分が少なく、数ヶ月にわたって店頭・通販サイトの在庫が安定しなかった。 現在では再生産と流通が落ち着き、中古・新品ともに安定して入手できる状態となっているが、 初期版パッケージ(白背景に炎をまとう騎士のデザイン)はコレクター人気が高く、状態の良いものは今もやや高値で取引されている。 デジタル版が普及した現代においても、本作のような“象徴的ローンチタイトル”は中古市場で長期的な需要を保ち続ける傾向がある。
ヤフオク!での取引価格と傾向
ヤフオク!では2024年以降も安定した出品数があり、落札価格の相場は2,800円~4,500円前後で推移している。 状態による価格差が大きく、特に「ケースに擦れがある」「ディスクに傷あり」「説明書欠品」などの品は3,000円以下で落札されやすい。 一方で、外装やラベルの状態が良く、動作保証や写真付きの出品は即決3,800円~4,500円で売買されるケースが多い。 新品未開封の初版パッケージに関しては、すでにプレミア価格化しており、5,000円~6,000円台で落札される例もある。 興味深いのは、海外版(北米パッケージ)をコレクション目的で入手する層が一定数存在する点で、 こちらも状態次第では4,000円を超える価格で安定している。 出品者のコメントには「PS5の性能を試すために購入した」「初期タイトルとして記念に保存した」といった声も多く、 単なる中古ソフトというより、PS5黎明期の象徴的なアイテムとして扱われている。
メルカリでの販売動向とユーザー傾向
フリマアプリ「メルカリ」では、出品数が多く、取引も活発に行われている。 相場は2025年現在で2,500円~3,800円前後が主流。 状態の良い中古品(ケース・説明書・ディスクに傷なし)は2,900円~3,300円で早期に売れており、 特に「動作確認済み」「即購入可」「送料無料」などの文言を付けた出品が人気を集める。 出品文には「DLC付き」「初回特典コード未使用」などの記載も見られるが、 すでに特典コードは利用期限切れのため、実質的な価値は低い。 ただし“未開封特典付き完全版”をコレクション目的で求めるユーザーもおり、 そのような出品は4,000円前後で即売れする傾向にある。 一方、ディスクやケースにやや難ありの商品は1,800円~2,200円台で値引き交渉が多く、 「PS5デビュー作として一度遊んでみたい」という層にリユースされている。 全体的にメルカリでは「ライトユーザー向けの手軽な市場」として機能しており、 出品者と購入者の間で価格交渉やコメントが活発に行われているのが特徴だ。
Amazonマーケットプレイスでの価格帯と在庫状況
Amazonのマーケットプレイスでは、2025年現在でも定期的に在庫が補充されている。 中古価格の中心帯は3,500円~4,800円程度。 Amazon倉庫発送(FBA)対応の商品は、やや高めの4,200円~4,800円に設定されており、 “プライム対象”“即日発送可”といった条件を重視する購入者が多い。 また、新品扱いの在庫(未開封品)はメーカー希望小売価格よりやや下回る5,000円前後で販売されていることが多い。 レビュー欄では、「ロードの速さに驚いた」「PS5を買ったらまずこのゲームを遊ぶべき」というコメントが多く、 本作が依然として“ハードの性能体験ソフト”として評価されていることがうかがえる。 一方で、2021年頃に比べると出品数が減少傾向にあり、 中古ソフトの再販・再流通よりも、デジタル版での購入者が増えている。 それでも物理パッケージ版の人気が維持されているのは、コレクター需要と所有欲によるものだ。
楽天市場での販売価格とショップ傾向
楽天市場では、主に中古ゲーム専門店やリユースショップが出店しており、価格は3,000円~4,200円前後で安定している。 楽天はポイント還元やセール期間中の値引きが大きいため、実質価格は2,500円台まで下がることもある。 中古ショップの多くは「ケース・ディスク共に良好」「動作確認済み」と明記しており、 美品クラスの商品はランキング上位に表示される。 また、送料無料ラインを設ける店舗が多く、 複数タイトルをまとめ買いするユーザーも多い。 この傾向は特に「ソウルシリーズをまとめて揃えたい」というファン層に顕著で、 『ダークソウル』『ブラッドボーン』『エルデンリング』と並べて購入する例が増えている。 つまり、『Demon’s Souls』は単独で遊ばれるだけでなく、“ソウルライク系の原点”としてコレクション的価値を持ち続けている。
駿河屋での中古価格と在庫推移
中古ゲームの老舗「駿河屋」では、本作は常に一定の人気を保っており、販売価格は2,900円~3,600円前後で推移している。 特に“状態:良い~非常に良い”の在庫はすぐに売り切れる傾向があり、 再入荷通知を設定するユーザーも多い。 駿河屋はコンディションの記載が細かいため、コレクター層に信頼されている。 「外箱スレあり」「説明書欠品」「動作確認済み」などの記載が透明性を保っており、 安定した市場価格を形成している。 また、同店ではPS3版の中古も依然として扱われており、こちらは2,000円前後で購入可能。 そのため、「原作とリメイクを比較したい」という層が両方を購入する例も多い。 こうした購買傾向は、“ゲームをプレイするだけでなく歴史を体験する”という近年のゲーマーの志向を象徴している。
デジタル版との価格差と市場の二極化
PS5のデジタルストアでは、『Demon’s Souls』は現在も通常価格7,590円(税込)で販売されている。 一方、中古市場では3,000円前後と半額以下で購入できるため、価格差が明確だ。 このため、「価格重視のプレイヤーは中古パッケージ」「利便性重視のプレイヤーはデジタル版」という二極化が進んでいる。 また、デジタル版にはロードの早さや利便性という利点があるものの、 パッケージ版は中古販売・貸出が可能なため、依然として需要が根強い。 特にコレクター層にとっては、ケースアートやディスクデザインを含めた“所有体験”そのものが価値となっている。
今後の価値変動と展望
2025年時点では、『Demon’s Souls』の中古価格はほぼ安定期に入っている。 ただし、今後シリーズの新作(例:フロム・ソフトウェアが手がける新規IPや続編的作品)が登場すれば、 「原点を遊び直したい」という需要から一時的に再注目され、価格が上昇する可能性がある。 また、PS5後期モデル以降でディスクレス版が主流になると、パッケージ版の希少価値が上がる見込みもある。 そのため、中古で購入する際は「状態の良い初期版パッケージ」を選ぶのが賢明だ。 時間が経つほど美品の流通量は減少し、コレクター価格に移行していくことが予想される。 ゲームとしての価値だけでなく、PS5時代を象徴する文化的アイテムとしての側面も無視できない。
総評 ― “原点”として残り続ける価値
中古市場における『Demon’s Souls』は、単なるリメイク作品ではなく、 「ソウルライクというジャンルの起点」を体験できる貴重な作品として位置づけられている。 グラフィック、操作感、音響、デザイン――どれを取っても今なお第一線級であり、 数年経ってもその完成度は色褪せていない。 PS5の黎明を飾ったこの一本は、単なるゲームを超え、世代交代の象徴となった。 中古でも安定した人気を保つ理由は、 そこに“挑戦する者の魂”が宿っているからだ。 たとえ価格が下がっても、その価値は下がらない―― 『Demon’s Souls』は今も、そしてこれからも、プレイヤーの記憶に刻まれ続ける一本である。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
Demon's Souls




 評価 4.82
評価 4.82ソニー・インタラクティブエンタテインメント 【PS5】Demon’s Souls [ECJS-00001 PS5 デモンズソウル]
【中古】 Demon’s Souls/PS5




 評価 5
評価 5【中古】PS5 Demon’s Souls




 評価 5
評価 5【中古】PS5Demon’s Souls
【新品】PS5 Demon’s Souls【メール便】
【中古】 Demon’s Souls/PS3




 評価 4
評価 4【中古】 Demon’s Souls PlayStation3 the Best/PS3




 評価 3
評価 3【中古】PS3 Demon’s Souls(デモンズソウル) PlayStation 3 the Best




 評価 5
評価 5
![ソニー・インタラクティブエンタテインメント 【PS5】Demon’s Souls [ECJS-00001 PS5 デモンズソウル]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1457/4948872015875.jpg?_ex=128x128)

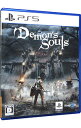



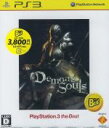
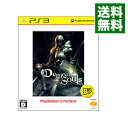
![Demon’s Souls[PS5] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_1449/ecjs-1.jpg?_ex=128x128)