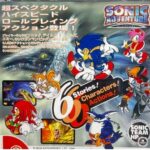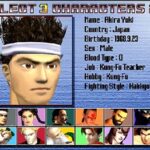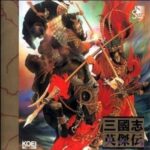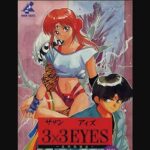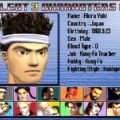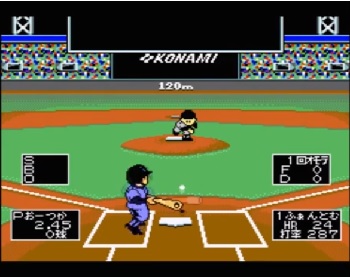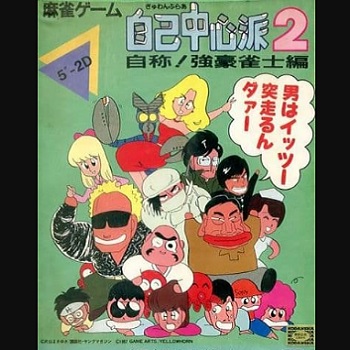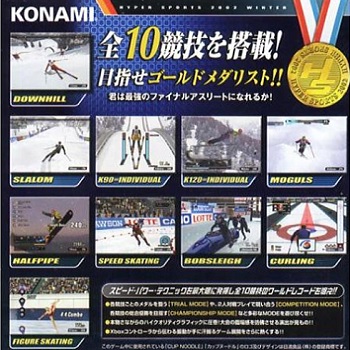【送料無料】【中古】DC ドリームキャスト July
【発売】:フォーティファイブ
【発売日】:1998年11月27日
【ジャンル】:アドベンチャーゲーム
■ 概要
1998年11月27日――家庭用ゲーム機市場に大きな注目が集まっていたその時期、セガの新ハード「ドリームキャスト」が華々しく登場した。ハードの発売と同時に複数のソフトが用意され、いわゆる「ロンチタイトル」としてユーザーの期待を担った作品群の中に、フォーティファイブが送り出したアドベンチャーゲーム『July(ジュライ)』がある。本作は、従来の家庭用ゲームが持っていた「娯楽性」や「気軽な遊び心地」とは大きく異なり、重厚かつシリアスな世界観を軸に据えていた点で特異な存在感を放っていた。
『July』は、一言でまとめるなら「世紀末アドベンチャー」である。当時、20世紀の終わりを目前に控え、世界各地でノストラダムスの予言や終末思想にまつわる言説が話題になっていた。新聞や雑誌、テレビ番組でも「1999年、人類滅亡説」がしばしば取り上げられ、それはオカルト的なブームを超えて社会的な関心事となっていた。そうした空気を色濃く反映しつつ、本作は新興宗教の台頭、大企業の陰謀、遺伝子工学やテロリズムなど、当時の世相を鋭く反映した題材をふんだんに盛り込み、プレイヤーを不安と緊張に満ちた物語へと引き込んでいく。
物語の中心に据えられたのは二人の主人公。ひとりは日本に暮らす大学生・高村誠(たかむらまこと)。彼は6年前にイギリスで発生したバス爆破テロ事件に巻き込まれ、妹を失い、母は昏睡状態に陥り、家族は崩壊の危機に立たされる。父との確執を抱えながら祖父と暮らす誠は、心に深い傷を抱えつつも日常を続けていたが、やがて大規模な陰謀に巻き込まれていく。そしてもうひとりは、メキシコ出身の青年・ヨシュア。彼は「セックスレス体」と呼ばれる生殖能力を欠いた特異体質を持ち、それゆえ幼少期から研究機関で非人道的な実験対象とされてきた。施設から脱走した後は追跡者への復讐を胸に秘め、日本へと潜伏する。この二人の生き様が交錯し、世界規模の不安を孕む物語が展開する。
本作の最大の特徴は「ザッピングシナリオ」と呼ばれるシステムだ。プレイヤーは誠とヨシュア、二人の視点を切り替えながら物語を進める。異なる立場、異なる背景を持つキャラクターを行き来することで、事件の全体像が少しずつ立ち現れる仕組みであり、プレイヤーはまるで群像劇を追うような没入感を体験できる。これは当時のアドベンチャーゲームとしても挑戦的な構造であり、後の作品群に大きな影響を与えたと評価されている。
また、ビジュアル面の魅力も語らずにはいられない。キャラクターデザインを手掛けたのは、漫画家として独自のタッチを持つトニーたけざき氏と、アニメーション業界で高い評価を得ていた梅津泰臣氏という豪華な布陣である。彼らが描き出したキャラクターは総勢150人以上。子どもから老人まで、善人も悪人も、美形もそうでない人物も、すべて立ち絵付きで用意された。従来のアドベンチャーゲームでは主要キャラクターのみがビジュアル化されるのが一般的であったため、この点は大きな驚きをもって迎えられた。登場人物が「群像」として機能する物語の性質と合致し、プレイヤーに「実際に社会の中で様々な人々と関わっている」かのような臨場感を与えたのである。
ゲームの舞台は日本の首都圏――東京、神奈川、千葉といった地域に限定されている。しかし、その制約が逆に功を奏し、テレビドラマや特撮作品のように「現実と虚構が混ざり合う架空の街並み」を構築していた。架空の宗教団体の集会場や、製薬企業の研究施設、雑踏の街角など、実在の都市風景を思わせる背景が緻密に描かれ、プレイヤーに身近さと不気味さを同時に感じさせる。
そして、重厚なBGMと無機質で硬質なUI(ユーザーインターフェイス)が、作品全体の雰囲気をさらに強調する。テロや戦争といった要素が散りばめられたシナリオと相まって、『July』は当時のゲーム市場において異色の「鬱ゲー」とも呼ばれる空気をまとっていた。明るくカラフルなアクションやRPGが主流であった時代に、これほどまでにダークで思想的なテーマを真正面から描いたゲームは稀であり、プレイヤーに強い印象を残した。
発売元のフォーティファイブは、当時まだ大手メーカーと比べれば小規模な会社でありながら、こうした意欲的な作品をロンチで送り出したこと自体が注目された。セガがドリームキャストを「次世代のネットワーク機能を備えたハード」として売り出していた背景の中で、『July』は派手さよりも「物語性」や「人間描写」に重きを置くことで、硬派なゲーマーやアドベンチャー愛好者に訴えかけるポジションを築いたといえる。
総じて『July』は、1990年代末の時代背景を色濃く映し出した問題作であり、ドリームキャストのロンチラインナップの中でもひときわ個性的な存在であった。終末への不安が世間を覆っていたあの時代、プレイヤーはコントローラーを握りながら、自分自身の不安や社会への違和感と向き合うような体験を味わったのではないだろうか。
■■■■ ゲームの魅力とは?
『July』の魅力を語る上でまず欠かせないのは、その独特な「世紀末感」と「社会派ドラマ性」である。1998年の発売当時、ゲームはまだ「遊び」や「ファンタジーの世界」に属するものとして受け止められることが多かった。カラフルでポップな世界観、あるいは冒険心を煽るヒーロー的ストーリーが主流であり、重苦しく人間の暗部に切り込む作品は少数派だった。その中にあって『July』は、予言や終末思想、宗教と科学の対立といったテーマを前面に打ち出し、プレイヤーに「考えさせる」体験を強いた。この異色性こそが、まず第一の魅力といえる。
さらに、シナリオの構造自体が画期的だった。「ザッピングシナリオ」と呼ばれるシステムは、複数の主人公を切り替えながら進行するものであり、従来の一本道的なアドベンチャーゲームとは一線を画していた。高村誠の物語を追っているとき、彼の目の前で起きた事件の裏にはヨシュアの行動が関わっていたり、逆にヨシュアの視点では誠の存在が影となって浮かび上がったりする。プレイヤーはその断片的な視点を繋ぎ合わせることで、初めて全貌に近づける。単なる「主人公二人制」ではなく、視点切替がシナリオ理解そのものに直結している点は、当時のアドベンチャーゲームファンに強烈な印象を残した。
また、人物描写の濃さも『July』の魅力だ。150人以上の登場人物全員に立ち絵が用意されており、それぞれのキャラクターが細部まで描き込まれているのは異例中の異例だった。多くのゲームでは「モブキャラ」とされる人々も丁寧にデザインされていることで、画面の中に現れる人々が単なる背景ではなく「社会の構成員」として息づいている感覚を与える。善人も悪人も、美男も不美人も、年齢や社会的立場も多種多様で、現実世界と同じように「人間の多様性」が描かれている点は、プレイヤーにとって新鮮だった。これはトニーたけざき氏と梅津泰臣氏という、異なる個性を持つ二人のクリエイターが協力したからこそ成し得た芸当であり、アドベンチャーゲームのビジュアルの在り方を広げたとも言える。
音楽や演出も見逃せない。本作のBGMは、重厚で不安を煽るような旋律を中心に構成されており、シナリオの陰鬱なテーマと絶妙に呼応している。場面によっては静かなピアノが淡々と流れることで、逆に恐怖や不安を増幅させる効果を生んでいた。また、UIデザインはシンプルで硬質。無機質なインターフェイスが、まるで研究施設や監視社会を象徴するようにプレイヤーの目に映り、ゲーム全体の雰囲気を強固に支えている。
『July』はまた、プレイヤーに「自分の選択が世界に影響する」という感覚を与えるゲームでもあった。アドベンチャーゲームの多くは、選択肢を通じて分岐が発生する仕組みを採用していたが、本作ではその選択が人間関係や事件の流れに重く響く。例えば誠が誰とどんな会話をするかによって、人間関係の糸口がつながるか切れるかが変わり、その影響がヨシュアの物語に跳ね返ってくる。小さな分岐の積み重ねが大きな展開の違いを生み、プレイヤーは「自分の行動が確実に物語を動かしている」という実感を抱けた。
さらに、『July』の魅力は「リアリティの演出」にもある。舞台となる首都圏の街並みは、実在の都市をモデルにしたと思わせるような背景グラフィックで描かれており、現実世界の延長線上に物語が存在していると錯覚させる。実際に東京や神奈川に暮らしているプレイヤーにとっては「見覚えのある風景がシナリオの中で不穏な事件の舞台となる」ことで、一層没入感が高まった。
そして、何よりも特徴的なのは「問題提起」の色合いだ。テロリズム、遺伝子工学、新興宗教の狂信、巨大企業の闇。これらは現実社会に存在する課題でもあり、プレイヤーはゲームを進めながら「もし自分がこうした事態に巻き込まれたら?」と自問せざるを得ない。エンターテインメントでありながら現実への鋭い批評性を持つ作品は少なく、だからこそ『July』は記憶に残るゲームとなった。
要約すれば、『July』の魅力とは以下の要素が複雑に絡み合うことにある。
終末思想を前提とした重厚なテーマ性
二人の主人公を行き来するザッピングシナリオ
圧倒的なキャラクター数と多様な人間描写
不安を掻き立てる音楽と冷徹なUIデザイン
現実感を伴う都市描写と社会派的メッセージ
これらが合わさることで、『July』は単なるゲームを超えた「体験」として多くのユーザーに刻まれた。
■■■■ ゲームの攻略など
『July』はアドベンチャーゲームに分類される作品でありながら、一般的なコマンド選択式のADVとは一線を画した特徴的なシステムを持っている。そのため、攻略のポイントも「単に正しい選択肢を選ぶ」以上の工夫が必要となる。ここではプレイをスムーズに進めるための心得や、効率的な楽しみ方、さらにマニアックな遊び方までを解説していこう。
● 基本は「ザッピングシナリオ」を意識する
本作の最も重要な攻略要素は、二人の主人公――高村誠とヨシュア――の視点を切り替えて進める「ザッピングシナリオ」だ。誠の物語で得た情報がヨシュアの行動に影響したり、ヨシュアの復讐劇が誠の生活に影を落としたりする。プレイヤーは常に「片方の視点で見えなかったことが、もう一方の視点で補完される」という意識を持って選択肢を選ぶ必要がある。
攻略のコツとしては、片方の主人公を一気に進めるのではなく、適度に切り替えながら進行させることだ。そうすることでストーリーの因果関係が理解しやすくなり、伏線の回収も鮮やかに感じられる。逆に、一方に偏って進めてしまうと「なぜこの展開になったのか?」という疑問が残り、理解が追いつきにくくなる。
● 選択肢は「短期的な結果」より「長期的な流れ」を重視
『July』に登場する選択肢は、一見すると些細に思えるものも多い。例えば「誰と会話を続けるか」「どの場所に立ち寄るか」といった小さな判断だ。しかし、その積み重ねが後の展開を大きく左右する。特に誠の物語では、人間関係の構築が後のシナリオ分岐に直結しており、早い段階での選択がエンディングの分岐条件になっていることも少なくない。
攻略を意識するなら、「今の選択肢がどのキャラクターにどのような影響を与えるか」を常に意識することだ。短期的には不利に思える行動でも、長期的には重要な情報を得るきっかけになる場合がある。例えば、あるキャラクターに冷たく接するとその場では好感度が下がるが、後にそのキャラクターが敵対組織と関わる伏線に繋がるなど、先を見据えた判断が必要となる。
● フラグ管理の重要性
アドベンチャーゲームの攻略において避けて通れないのが「フラグ管理」だが、『July』は特にこの要素が色濃い。誠とヨシュア双方の物語が複雑に絡み合うため、片方で立てたフラグがもう一方の展開を変化させることもある。そのため、プレイヤーは一周目のプレイだけでは全てのルートを把握するのは難しい。
効率的に攻略するには、まずは一度じっくりと物語を最後まで追い、全体の構造を把握することが大切だ。その上で二周目以降は意識的に異なる選択肢を選び、未回収のイベントやキャラクターの背景を補完していく。セーブデータを分けて管理するのも有効な手段であり、重要な分岐点ごとにセーブしておけばやり直しが効きやすい。
● 難易度とプレイヤー体験
『July』はアクション性がないため、ゲームオーバーの意味での「難易度」は高くない。しかし、シナリオを完全に理解し、全てのエンディングを見るという点では難易度が高い部類に入る。というのも、本作の物語は非常に複雑に入り組んでおり、登場人物の数も多いため、誰がどの勢力に属し、どのような思惑を抱いているのかを整理しながら進める必要があるからだ。
初見プレイでは混乱することも多いだろうが、それもまた本作の「攻略する楽しみ」のひとつである。推理小説を読み解くように、情報を少しずつ繋ぎ合わせていく過程が、他のゲームにはない醍醐味を生んでいる。
● 裏技的な楽しみ方
『July』には、いわゆるアクションゲームのような隠しコマンドや裏技は存在しない。しかし、プレイヤーの工夫次第で「裏技的な楽しみ方」は可能だ。例えば、意図的に誠の選択を冷徹に行い、人間関係を断ち切って進めてみると、物語の雰囲気が大きく変わる。逆に、ヨシュアを徹底して「復讐よりも人間性を選ぶ」ルートで進めると、意外な展開に辿り着くこともある。こうしたプレイスタイルの違いが新しい発見をもたらし、リプレイ性を高めている。
また、一部のキャラクターには特定の条件を満たさないと出会えない場合もあり、それを探すのも攻略の一環となる。これらは攻略本やファンサイトで取り上げられることも多く、当時のプレイヤーたちは情報交換を通じて新しいルートやイベントを発見していった。
● 攻略まとめ
『July』を攻略するための基本的な心得をまとめると次の通りである。
主人公を適度に切り替えて進める。
選択肢は短期的な効果より長期的な影響を重視。
フラグ管理を徹底し、セーブデータを活用する。
一周で全てを理解しようとせず、周回プレイを前提に楽しむ。
プレイスタイルを変えてリプレイすることで新しい発見がある。
これらを意識することで、『July』の複雑な物語構造をより深く味わい、全ての結末に辿り着くことができるだろう。攻略という行為が、単なる「エンディングを見るための作業」ではなく「作品世界を解き明かす探究」に変わるのが、このゲームならではの魅力なのだ。
■■■■ 感想や評判
『July』が発売された1998年は、ゲーム業界にとって大きな転換期だった。新世代機「ドリームキャスト」が登場し、家庭用ゲームは3Dグラフィックスやネットワーク機能を武器に、従来とは違う体験を提示しようと模索していた。その中で『July』は、グラフィックや派手なアクションではなく、重厚なストーリーとキャラクター描写を武器にした「異端のロンチタイトル」として注目を集めた。では、実際に遊んだプレイヤーや当時のメディアはどのように受け止めたのか。ここからはその感想や評判を多角的に振り返ってみたい。
● プレイヤーからの第一印象
発売当初、多くのプレイヤーはまず「重たい雰囲気」に驚かされた。ドリームキャストの他のロンチタイトルが比較的分かりやすい娯楽性を持っていたのに対し、『July』は冒頭からテロ、宗教、遺伝子工学といったシリアスな要素を前面に押し出し、明らかに「気軽に楽しむゲーム」とは異なる空気を漂わせていた。「鬱ゲー」と評する声も当時のゲーム雑誌に掲載されていたが、その一方で「ここまで挑戦的なシナリオを家庭用ゲームで味わえるとは思わなかった」という感嘆の声も多かった。
特にプレイヤーの間で話題になったのは「150人以上のキャラクターが全員立ち絵付き」という点だ。脇役やモブであっても丁寧にデザインされたキャラクターが画面に現れることで、物語世界に厚みが生まれており、「ただの背景キャラにすら存在感がある」と好意的に語られた。キャラクターデザインを手がけたトニーたけざき氏と梅津泰臣氏の絵柄の対比や調和についても「一目で誰が描いたかわかるのに不思議と世界観に馴染んでいる」と評価された。
● メディアレビューの傾向
当時のゲーム雑誌やレビュー記事では、『July』は賛否が大きく分かれるタイトルとして扱われた。ある雑誌は「社会派アドベンチャーの傑作候補」と高評価を与え、深いテーマ性やシナリオの緻密さを絶賛していた。一方で「テンポが重く、明るいゲームを期待するユーザーには不向き」と注意を促す記事も少なくなかった。総合点としては70点から80点程度に収まることが多く、突出した大絶賛ではないが「特定層に強く刺さる作品」として位置づけられた。
また、ドリームキャストのロンチタイトルとしては比較的地味な存在であったこともあり、売上面で突出した数字は残せなかったが、その独特の方向性は確実に一部の熱心なユーザーに支持された。レビュー欄には「この作品の存在がドリームキャストの幅を広げた」といった意見が掲載されることもあった。
● ネット黎明期に広がった口コミ
1998年といえば、まだインターネット掲示板や個人サイトがゲームファンの情報交換の場として広がり始めた時期だ。『July』についても、当時の掲示板やファンサイトでは「理解するのが難しいがハマる人にはとことんハマる」という書き込みが多く見られた。シナリオの考察や、ヨシュアの体質に込められた意味、新興宗教団体のモデルがどこなのか、といった議論が交わされ、プレイヤー同士で物語の深読みを楽しむ文化が形成されたのもこのゲームならではだった。
特に「ノストラダムスの大予言」と関連づけてストーリーを解釈する動きは盛んで、「これは本当に1999年に向けた問題提起なのでは?」といった推測が飛び交った。ゲームを超えて時代の不安を投影する鏡のような存在として語られた点も、『July』のユニークな評価のひとつである。
● 長期的な評価の変遷
発売から年月が経つにつれ、『July』は「カルト的な名作」としての評価を固めていった。初期には「暗すぎて遊びづらい」と敬遠したプレイヤーも、後年になって改めてプレイし直すと「今だからこそ理解できるテーマ性がある」と再評価するケースが多かった。特に現代においては、テロリズムや遺伝子研究、新興宗教の問題は依然として社会に存在しており、『July』が描いた題材が決して古びていないことに気づかされる。
そのため、インターネット上では「今リメイクすればもっと注目されるのではないか」という声も根強い。グラフィックや操作性を現代的に刷新しつつ、シナリオの骨格はそのまま活かせば、再び話題を呼ぶ可能性は高いと考えられている。
● プレイヤーの声をまとめると…
ポジティブな意見としては、
「これほどまでに重厚なアドベンチャーは他にない」
「キャラクターの多様さに圧倒された」
「社会派的なテーマが考えさせられる」
「ザッピングシナリオが新鮮で没入感が高い」
ネガティブな意見としては、
「テンポが遅く、だれる部分がある」
「暗い雰囲気に合わず途中でやめた」
「分岐条件が複雑すぎて攻略本なしでは厳しい」
といったものが目立つ。つまり、『July』は万人向けの娯楽ではないが、自分に合ったプレイヤーにとっては忘れがたい体験を与える「尖った作品」だったと言える。
まとめると、『July』の感想や評判は決して一枚岩ではなく、評価が二極化したこと自体がこの作品の存在感を強調している。挑戦的なテーマと実験的なシステムにより、当時のユーザーに「賛否両論の衝撃」を与えた本作は、今なお語り継がれる価値を持つ一本なのである。
■■■■ 良かったところ
『July』を実際にプレイしたユーザーの間で最も多く語られたのは、その「他にない独自性」だった。ドリームキャストのロンチタイトルとして登場したこの作品は、派手さや分かりやすさを前面に出すのではなく、あえて「重く、考えさせる」方向へ振り切った。そのため遊びやすさよりも「記憶に残る体験」を重視するユーザーからは熱烈に支持され、さまざまな「良かった点」が挙げられている。以下ではそれを整理しながら詳しく見ていこう。
● 圧倒的なキャラクターデザインと多様性
まず第一に評価されたのは、150人を超える登場人物の存在感だ。多くのアドベンチャーゲームでは、主人公と主要な数人にしか立ち絵が用意されないことが多い。しかし『July』では、端役に至るまで全員にしっかりとビジュアルが与えられていた。これはプレイヤーにとって大きな驚きであり、「まるで現実の社会の中で様々な人と関わっている」かのような臨場感を生み出した。
キャラクターデザインを担当したのが、漫画家のトニーたけざき氏とアニメーターの梅津泰臣氏という豪華な組み合わせであったことも大きい。二人の異なる作風が織りなすことで、キャラクターの多様性が強調され、同じ世界に属していながらも個性豊かに描き分けられていた。その結果、プレイヤーはモブキャラにすら印象を持ち、物語全体を「群像劇」として楽しめるという贅沢な体験を味わえた。
● ザッピングシナリオの斬新さ
「二人の主人公を切り替えながら物語を進める」というシステムは、当時のユーザーにとって新鮮そのものだった。片方の視点で意味が分からなかった出来事が、もう一方の視点に切り替えることで繋がりを見せる。このパズルのような構造は、ただ物語を追うのではなく「事件の全体像を解き明かす」楽しさをもたらした。
プレイヤーは探偵小説を読むかのように、二人の視点から得られる情報を頭の中で組み合わせていく必要があり、その能動的な参加感が高く評価された。「自分が物語を理解する主体になれる」という感覚は、一本道のゲームにはない魅力として語られている。
● 時代性とシリアスなテーマ
『July』のシナリオは、1990年代末の社会状況を色濃く反映していた。ノストラダムスの大予言や新興宗教の台頭、テロリズムへの不安といったテーマは、当時現実のニュースでも大きく取り上げられていた要素である。そうした題材をゲームというエンターテインメントに取り込み、フィクションの形で体験させたこと自体が斬新だった。
プレイヤーの中には「現実と地続きの不安を疑似体験するようで怖かった」と語る人も少なくなかったが、それは同時に「他では得られない体験だった」という意味でもある。娯楽の域を超えて、社会への問題提起を感じられる作品として評価された点は『July』の大きな強みであった。
● 音楽と演出の相乗効果
『July』の雰囲気を決定づけたもう一つの要素が、音楽とUI演出だ。BGMは全体的に静謐かつ不安を煽る曲調で、重いテーマ性を下支えしている。特に緊迫したシーンでの低音主体の楽曲は、プレイヤーの心拍数を上げる効果があり、「ただ文章を読むだけなのに体が緊張する」と感想を漏らす人もいた。
また、UIは無機質で冷たいデザインを採用しており、まるで研究施設の端末や監視システムを操作しているかのような印象を与えた。このUIは当時「地味」と捉えられることもあったが、シナリオの内容と組み合わさることで「不安定な近未来感」を演出し、結果的に高い評価を受けた。
● プレイヤーの選択が響く体験
選択肢の積み重ねによって分岐するストーリー構造も好意的に受け止められた。特に誠とヨシュアの視点が互いに影響し合う仕組みは、プレイヤーに「小さな選択が世界を変えていく」実感を与えた。この体験は単なるエンディング分岐ではなく、物語全体を解き明かす探究心へと繋がり、プレイヤーを夢中にさせた。
結果的に「何度も周回して遊べるアドベンチャー」としてリプレイ性が高く評価されている。1回目では見えなかった真相が、2回目以降に異なる選択をすることで徐々に姿を現す。その過程が「自分が物語の真実に迫っている」という手応えを強く感じさせたのだ。
● 総評としての「良かったところ」
以上のように、『July』の良かった点をまとめると次のようになる。
キャラクターデザインと人物の多様性:主要キャラ以外にも命が宿っていると感じさせる構成。
ザッピングシナリオの新鮮さ:二人の主人公を行き来しながら真実を掴む感覚。
社会派テーマの挑戦:現実の不安を題材に取り込むことで強烈な印象を残した。
音楽・UIの演出:プレイヤーの心理に作用する雰囲気作り。
リプレイ性の高さ:選択肢の積み重ねが物語の解釈を深めていく。
これらはすべて、当時の他のゲームではなかなか得られない体験であり、だからこそ『July』は20年以上経った今でも「心に残る異色の名作」として語り継がれているのである。
■■■■ 悪かったところ
どんなに個性的で魅力的な作品であっても、長所と同じくらい短所が語られるものだ。『July』はその挑戦的な姿勢ゆえに高い評価を受けた一方で、多くのプレイヤーから「遊びにくさ」「理解の難しさ」といった不満も寄せられた。ここでは、当時のプレイヤーやメディアが指摘した「悪かったところ」に焦点を当て、その原因や背景を詳しく見ていこう。
● 全体のテンポが重く遅い
まず多くの意見として挙げられるのが、ゲーム進行のテンポの遅さだ。『July』はシナリオをじっくり読ませるタイプのアドベンチャーゲームであり、派手な演出や爽快感のあるアクションは存在しない。画面上ではテキストを追い続ける時間が大半を占め、緊迫したシーンであっても淡々と文字と静止画で進むことが多い。
このスタイル自体は「小説を読むような没入感」として高く評価する人もいたが、一方で「プレイしていて眠くなる」「動きが少なくて飽きやすい」という声も少なくなかった。特にドリームキャストのロンチタイトルとして期待して購入した層からは「新世代機なのに画面が地味」という厳しい評価が寄せられた。
● 雰囲気が暗すぎる
『July』は終末思想やテロリズム、新興宗教など、現実社会でもセンシティブな題材を扱っている。加えてBGMやUIも不安を煽るようなデザインで統一されており、全編を通じて重苦しい雰囲気が漂っていた。これを「世界観が統一されていて素晴らしい」と感じるプレイヤーもいたが、逆に「気が滅入る」「鬱ゲーすぎる」として途中でプレイをやめてしまった人も多かった。
当時のゲーム市場では、明るくテンポの良いアクションやRPGが主流だったこともあり、こうした暗さは「受け入れにくい」とする層を生んでしまったのだ。
● 分岐条件が複雑すぎる
『July』はザッピングシナリオを採用しており、プレイヤーの選択によってエンディングが変化する。しかし、その分岐条件は非常に複雑で、ちょっとした会話の選択や移動の有無が後の大きな展開を左右することも多い。そのため、攻略本やネット上の情報がなければすべてのルートを見るのはほぼ不可能に近いという意見も少なくなかった。
一周目でバッドエンドにたどり着き、「なぜこうなったのか分からないまま終了した」というプレイヤーも多く、「フラグ管理が不親切」との不満が散見された。セーブ分岐を細かく作らなければならない煩雑さも、ユーザーにとって負担となっていた。
● 登場人物の多さが裏目に出ることも
150人以上のキャラクターが登場する点は本作の大きな特徴であり長所でもあったが、その数の多さが「誰が誰だか分からなくなる」という混乱を招くこともあった。モブにまで立ち絵が与えられているため印象には残るものの、プレイヤーが把握しきれず、ストーリーを追う上で混乱してしまうこともあった。
主要キャラクターと脇役の線引きが分かりづらく、「結局この人は何のために出てきたのか」と疑問が残るケースもあったのだ。情報量の多さがプレイヤーの負担になり、作品を「難解」と感じさせる一因となっていた。
● グラフィック表現の限界
ドリームキャストは当時としては高性能な3D描画能力を備えていたが、『July』はテキスト主体のADVであるため、その性能を十分に活かしていないように見えた。背景やキャラクターイラストの質自体は高かったが、他のロンチタイトルと比べると「新世代機らしさ」が感じられないという意見も多かった。
特に、リアルタイム3Dを駆使したタイトルと同時期に発売されたことで「古臭い印象」を持たれやすく、グラフィック面では過小評価されがちだった。
● 売上面での苦戦
ドリームキャストのロンチラインナップとしては地味な存在だったこともあり、『July』は商業的に大きな成功を収めることはできなかった。一般層にとっては「よく分からない暗いゲーム」と映り、購入を見送られるケースが多かった。こうした売上の低迷もまた「作品としての存在感はあるが成功とは言い難い」という評価に繋がった。
● 総評としての「悪かったところ」
こうした意見をまとめると、『July』の悪かった点は以下のように整理できる。
ゲーム進行のテンポが遅く、冗長に感じられる部分がある。
全体の雰囲気が暗く、遊び続けるのに精神的な負担が大きい。
分岐条件が複雑で、不親切に感じるユーザーも多い。
登場人物が多すぎて把握しきれず、物語が分かりにくい。
ドリームキャストの性能を活かし切れていないとの指摘。
商業的には地味で、売上が伸びなかった。
『July』は挑戦的であるがゆえに強い個性を放ったが、その個性が裏目に出てしまう部分も少なくなかった。万人向けではなく、好みが大きく分かれる「クセの強い作品」であったことが、悪かったところとしてしばしば語られている。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
『July』には150人を超える登場人物が存在し、全員に立ち絵が用意されているという異例の仕様がプレイヤーを驚かせた。そのため、単なる「背景キャラ」に見える人物にすら強烈な個性が与えられ、プレイヤーごとに「お気に入り」が異なるという面白さが生まれていた。ここでは、多くのファンが印象に残った、あるいは「好き」と語ったキャラクターたちを中心に、その理由や魅力を丁寧に掘り下げてみよう。
● 高村誠 ― 苦悩を抱えた等身大の主人公
まず多くのプレイヤーが共感を寄せたのは、日本人大学生の主人公・高村誠だ。彼は6年前のバス爆破テロ事件で妹を亡くし、母は昏睡状態に陥り、父とは関係が冷え切ってしまったという重い過去を背負っている。にもかかわらず、日常を続けようと努力し、大学生として生きる姿にプレイヤーは「普通の若者が非日常に巻き込まれていく怖さ」を重ね合わせた。
誠の魅力は、その「等身大の弱さ」にある。完璧なヒーローではなく、時に迷い、逃げたいと思う。しかしそれでも事件と向き合わざるを得ない状況に立たされる彼の姿は、多くのプレイヤーに感情移入を促した。ゲームを通じて「誠には幸せになってほしい」と願うユーザーが非常に多く、まさに物語の軸として愛される存在だった。
● ヨシュア ― 復讐と孤独に生きるもう一人の主人公
一方で、強烈な人気を博したのがもう一人の主人公・ヨシュアである。彼は「セックスレス体」という特異体質を持ち、研究機関から非人道的な扱いを受けてきた過去を持つ。そのため彼の物語は、復讐と孤独に彩られている。
ヨシュアの魅力は「悲劇性」と「力強さ」の同居にある。復讐の鬼と化している一方で、心の奥底には人間らしい温かさを失っていない。プレイヤーは彼の行動を通じて、「人は過酷な運命にさらされても人間性を捨てられるのか、守れるのか」というテーマに直面する。シリアスな作品である『July』において、ヨシュアは最も象徴的な存在として記憶されている。
● サブキャラクターの存在感
『July』では主要キャラクターだけでなく、サブキャラクターや一見モブに見える人物にも強い印象を残す者が多かった。例えば、誠の祖父は「家族を失った少年を支える存在」として、多くのプレイヤーに安心感を与えた。また、大学の友人たちは事件の渦中で対照的な反応を見せ、現実の人間関係を思わせるリアリティを与えていた。
さらに、宗教団体の信者や研究機関の職員など、本来なら単なる脇役にすぎない人物たちも、それぞれの人生や背景を匂わせる描写があり、「このキャラクターの視点でも物語を描けそう」と感じさせるほどの奥行きがあった。これにより、ファンの間では「推しキャラ」が細分化し、各自が「自分だけの好きなキャラクター」を語り合う楽しみが生まれた。
● キャラクターデザインの魅力
キャラクターの人気を支えたのは、やはりビジュアル面の強さだ。梅津泰臣氏の艶やかでスタイリッシュなデザインと、トニーたけざき氏のユーモラスかつリアルな人物描写が組み合わさり、『July』のキャラクター群は「現実と虚構の間」に存在するような独特の雰囲気を持っていた。
ファンの間では「梅津キャラ派」と「トニーキャラ派」に分かれることもあり、それぞれが好きなキャラクターを熱弁する様子も見られた。たとえば「梅津氏が描いた女性キャラの艶やかさが忘れられない」という意見もあれば、「トニー氏が手がけた不器用な中年キャラが妙に味わい深い」と語る声もあった。
● プレイヤーごとに違う「推しキャラ」
『July』の面白い点は、ファンの間で「このキャラクターが好き」という答えが大きく分かれることだ。誠やヨシュアといった主要人物を推す人もいれば、ほんの数シーンしか出ないサブキャラを「心に残る」と語る人もいる。これは150人以上もの人物がしっかりとデザインされ、個性を持って登場しているからこそ可能になった現象だ。
プレイヤーがそれぞれに「推し」を見つけられるのは、群像劇としての『July』の大きな魅力であり、キャラクター人気の多様性が作品の評価をさらに豊かにしている。
● 総評としての「好きなキャラクター」
『July』に登場するキャラクターは、主要人物もサブキャラも含め、全員が「物語の世界を形づくる部品」以上の存在感を持っている。プレイヤーはそこから自分なりの共感や好みを見出し、語り継いできた。
高村誠:苦悩を抱えながらも成長していく等身大の主人公
ヨシュア:悲劇と復讐を背負いながら人間性を模索するもう一人の主人公
祖父や友人などのサブキャラクター:支えや対照的な存在としてリアリティを演出
宗教団体や研究機関の人物:モブ的立場でありながら強烈な個性を持つ
こうした「好きなキャラクター」がプレイヤーごとに異なることこそが、『July』が他のゲームと違う唯一無二の魅力なのだ。
[game-7]
■ 中古市場での現状
1998年11月27日に発売された『July』は、ドリームキャストのロンチタイトルという位置づけながらも、商業的には大ヒットに至らず、知る人ぞ知る「カルト的な作品」として語り継がれてきた。そのため現在の中古市場においては、需要と供給が特殊なバランスを保っており、流通量が極端に多いわけではないものの、熱心なファンやコレクターの間で一定の人気を保ち続けている。ここでは、主要な中古取扱市場ごとに『July』の現状を詳しく見ていこう。
● ヤフオク!での取引状況
オークション形式の代表格であるヤフオク!では、『July』は定期的に出品されているが、常に数点が並ぶ程度で、大量出品されることは少ない。取引価格帯はおおよそ 2,000円~4,000円前後 に収まることが多い。
状態によって値段の振れ幅は大きく、ケースにスレや黄ばみがあるもの、説明書の欠品やディスク盤面に小傷があるものは2,000円台前半で落札されやすい。一方で、ケース・ディスクともに良好で、付属品が揃っている美品は3,500円前後まで値が上がることがある。特に「動作確認済み」と明記されているものは安心感から人気があり、入札数が伸びやすい。
未開封新品や極美品に関しては、ほとんど市場に出ないが、出た場合は5,000円を超える即決価格が設定されることもある。ドリームキャストのロンチタイトルとしてのコレクター的な価値を重視する層が一定数存在するため、外箱やビニール包装が完全な状態で残っているものは希少性が高く、オークションでも注目を集めやすい。
● メルカリでの販売状況
フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクに比べて取引がスピーディーであり、『July』も出品されれば短期間で売れていく傾向が見られる。価格帯は 2,000円~3,200円程度 が主流で、「箱あり・説明書付き・ディスク良好」といった条件のものが人気を集めている。
特に「送料無料」「即購入可」と明記されている商品は、相場より高めでも売れやすい。逆にケース割れや説明書の欠品がある場合は、1,800円前後に値下げしないと動きが鈍い。
また、メルカリは個人出品者が多いため、商品の状態表記にばらつきがあり、写真でしっかり確認する必要がある。コレクター層の間では「メルカリは思わぬ掘り出し物がある」と評される一方で、「説明不足でトラブルになりやすい」という指摘もある。
● Amazonマーケットプレイスでの価格動向
Amazonマーケットプレイスでは、『July』は中古ソフトとして継続的に出品されているが、価格帯はやや高めに設定されることが多い。相場は 3,000円~5,000円前後。Amazon倉庫から発送される「プライム対応品」は、利便性を重視する購入者に人気があり、3,500円~4,000円での出品が中心である。
ただし、Amazonは他のプラットフォームに比べて「即購入」しやすい環境が整っているため、多少高値でも「安心料」として購入されることが多い。そのため価格は安定しがちで、安値での出品はすぐに売り切れてしまう傾向にある。
● 楽天市場での取り扱い
楽天市場では、ゲームショップや中古専門店が『July』を取り扱っており、販売価格は 3,000円~4,500円程度 に設定されることが多い。楽天ポイント還元やショップごとのキャンペーンがあるため、他のプラットフォームより多少割高でも「実質的にはお得に購入できる」と考えるユーザーもいる。
ただし、楽天市場は出品数自体が少なく、常に購入できるわけではない。大手中古ショップがまとめて在庫を放出したタイミング以外では、品切れ状態が続くことも珍しくない。
● 駿河屋での相場
中古ゲームの大手専門店である駿河屋でも、『July』は継続的に取り扱われている。価格帯は 2,500円~3,800円前後 に落ち着いており、他のプラットフォームに比べると比較的安定している。状態によっては在庫切れになることもあるが、再入荷の頻度はそこそこ高く、購入を検討するなら駿河屋をチェックするのが安全策とされている。
駿河屋の特徴は、商品状態の説明が詳細であること。ディスクの傷やケースの劣化が明記されているため、購入前に安心して判断できるという利点がある。そのため、コレクター層からの信頼も厚い。
● コレクター需要と希少性
『July』はドリームキャストのロンチタイトルという特別な位置づけであり、ゲームの内容以上に「ハードの歴史を語る上で外せない作品」としてコレクターに注目されている。そのため、状態の良いものや新品未開封品の需要は根強い。
また、本作は売上本数が多くなかったため、流通量が少ないことも価格を底支えしている。特に「帯付き」「販促チラシ付き」といった完全版に近いセットは希少性が高く、プレミアム価格で取引される傾向がある。
● まとめ
現在の中古市場での『July』は、以下のように整理できる。
ヤフオク!:2,000~4,000円。状態による振れ幅が大きい。新品は希少で高値。
メルカリ:2,000~3,200円。出品数は少なめだが回転が早い。
Amazonマーケットプレイス:3,000~5,000円。利便性ゆえに高値でも安定して取引。
楽天市場:3,000~4,500円。出品数は限られるがポイント還元などで実質的に割安感あり。
駿河屋:2,500~3,800円。安定した相場で、状態説明が丁寧。
総じて、『July』は決して高額プレミア化しているわけではないが、コレクター需要と供給の少なさが価格を安定させており、今後も「隠れた名作」として一定の価値を持ち続けると考えられる。ドリームキャストの歴史を振り返るうえでも、手にしておきたい一本といえるだろう。
[game-8]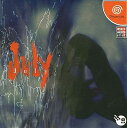

![【中古】[DC] July(ジュライ) ファーティファイブ (19981127)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1036/0/cg10360004.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS] 魔法少女プリティサミー PART2 In the julyhelm(パート2 イン ザ ジュライヘルム) パイオニアLDC (19970314)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270676.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【訳あり新品】【PS】魔法少女プリティサミー PART2 In the Julyhelm[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/noimage.jpg?_ex=128x128)