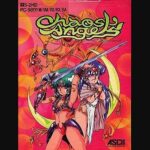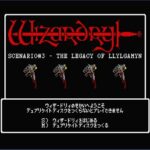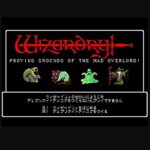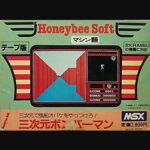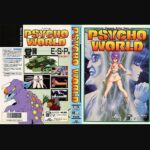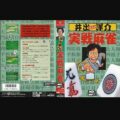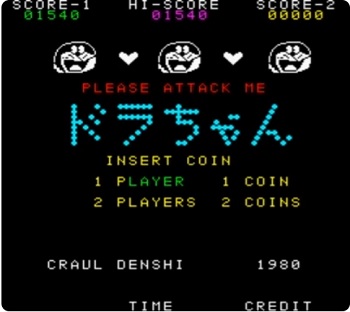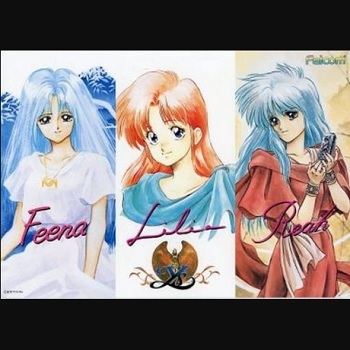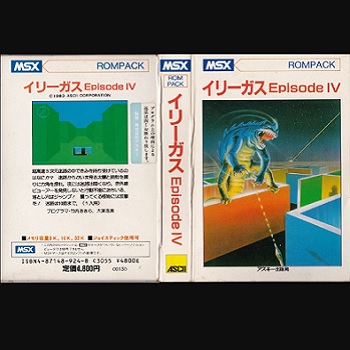
MSX-BASICでゲームを作ろう 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる [ 山田 直樹 ]




 評価 4.5
評価 4.5【発売】:アスキー
【対応パソコン】:MSX、Windows
【発売日】:1983年
【ジャンル】:アクションゲーム
■ 概要
◇ 幻の「Episode IV」――アスキーが生んだSF的迷宮脱出の傑作
1983年、パソコン黎明期の日本で、アスキーはMSXユーザーの度肝を抜く一本を世に送り出した。その名は『イリーガス Episode IV』。タイトルにある「イリーガス(ΙΛΙΓΞ)」とはギリシャ語で“渦巻き”を意味し、プレイヤーを目まぐるしく回転するような迷宮世界へ誘う象徴的な言葉だった。当時としては異例の“エピソードナンバリング”を採用しており、『テセウス』をEpisode Iとするシリーズ構想の一部として登場したが、間のII・IIIはついに姿を現さなかったことから、ファンの間では“失われた章”として長く語り継がれている。
◇ 作者・竹内あきらの技術哲学と革新性
開発を手掛けたのは、『テセウス』や『オリオン80』で知られる竹内あきら氏。彼は限られたメモリとグラフィック性能しか持たないMSXで、いかにして没入感ある世界を表現するかに挑戦していた。『イリーガス Episode IV』では、従来の平面マップ型ではなく、疑似3Dによる一人称視点を採用。これによりプレイヤーはまるで迷宮の中を自らの足で歩くような臨場感を味わえた。 MSXのSCREEN3モードを利用し、解像度わずか64×48ドットという極めて低い表示領域の中で3D空間を構築するという発想は、当時としては常識外れの実験的試みであった。解像度を犠牲にした代わりに、滑らかでスピーディーなアニメーション描画を実現。画面切り替え式が主流だった時代において、プレイヤーが方向転換や前進を行うたびに、まるで映画のワンカットのように景色が流れるその動きは、多くのゲーマーを驚かせた。
◇ ストーリー設定――崩壊する銀河帝国と孤独な脱出劇
物語は、銀河帝国の誕生から2000年後、腐敗と反乱が蔓延する時代が舞台。 反乱軍が砂漠の惑星アル・マザールに地下基地を建設しているという情報を得た帝国軍は、かつて繁栄した都市ム・モンクに特殊部隊を派遣する。しかし、激しい対空砲火によって部隊は壊滅。生き残ったのは、下士官H.T一等軍曹ただ一人だった。 プレイヤーはこのH.T軍曹となり、崩壊した都市の迷宮から脱出を試みる。敵のセンサーをかいくぐり、限られた物資で生き延びながら出口を探すという孤独で過酷なサバイバルが繰り広げられる。 この設定は当時のSF映画――特に『スター・ウォーズ』や『メトロポリス』、さらには『惑星ソラリス』のような哲学的要素を彷彿とさせる。竹内氏が描いた“テクノロジーと人間の対比”は、単なる迷路ゲームに留まらず、文学的な深みを持ってプレイヤーに問いかける構造を成していた。
◇ ゲームシステム――生存を懸けたリアルタイム探索
ゲームの目的は単純明快、「迷宮からの脱出」である。しかし、プレイ体験は極めて緊張感に満ちている。 まず特徴的なのが“時間経過”の概念。ゲーム内では時間が流れ、太陽が昇り沈む。空の色や星の位置が変化し、それによってプレイヤーは方角を推測できる。昼間は視界が良好だが、夜になると暗闇が支配し、前方の壁すら見えにくくなる。このとき役立つのが「赤外線ビューア」というアイテム。入手することで暗闇でも周囲を確認でき、SF的なガジェット感を強調する要素でもある。 さらに、スタミナ(体力)システムが導入されており、行動すればするほど消耗する。食料や水を見つけて回復しなければ、倒れてゲームオーバーとなる。これにより、単なる探索ではなく“資源管理”の戦略性が加わっている。 敵として登場するのは警備ロボット。巡回ルートを持ち、視界に入ると即座に警報が鳴り響く。プレイヤーは探知機の音を頼りにロボットの接近を察知し、隠れる・逃げる・タイミングを見計らって移動するなど、まるでステルスゲームの原型のようなプレイが求められた。当時、この緊迫感の演出は画期的だった。
◇ 実装技術――制約を逆手に取った芸術的プログラミング
本作の最も特筆すべき点は、限られたMSXの性能を極限まで使い切った設計思想だ。64×48ドットという解像度は、現在の基準では“豆粒”のような世界だが、竹内氏はその中で立体感と方向感覚を巧みに再現している。壁の陰影は濃淡のパターンで表現され、移動時のカメラワークは擬似的に滑らかに補間。これはアニメーション的手法と数値的座標計算を融合させた当時としては高度な技術だった。 また、時間の流れを空の色や星の動きで表現する発想は、プログラマの美学が感じられる演出である。単に時計を表示するだけではなく、“環境そのものが時間を語る”というコンセプトが、後の環境シミュレーションゲームの先駆けとも言える。 0~9の数字キーで任意ステージを選べるショートカットも搭載されており、研究者的なプレイヤーがシステムを解析しやすいよう配慮されていた点も興味深い。つまり、当時すでに“ユーザー体験”という概念を重視していた作品なのである。
◇ シリーズ構想と失われた章の謎
『イリーガス Episode IV』はその副題が示す通り、シリーズの一環として企画された。Episode Iに相当する『テセウス』との繋がりは確認されているものの、Episode IIとIIIに該当する作品は未発見である。このことから、一部では「開発途中で中止された」あるいは「他タイトルとして改題された」との説がある。竹内氏が後年手掛けたプログラムの中に共通する構造が見られることから、技術的な進化の途中段階に位置する幻のエピソードが存在した可能性も指摘されている。 アスキーはこのシリーズを通じて“ギリシャ神話的構造を持つSF”を描こうとしていたとも言われており、『テセウス』が“迷宮と知恵”、『イリーガス』が“脱出と孤独”をテーマとしていた。もし続編が存在したなら、それは“再生”や“創造”といった哲学的命題に踏み込んでいたかもしれない。
◇ 現代における評価と再発見
2020年代以降、レトロゲーム研究の文脈で『イリーガス Episode IV』は再び注目を集めている。特にMSXエミュレーターの普及により、当時の環境を再現してプレイできるようになったことで、その実験性と完成度の高さが再評価された。ファンの間では“3D迷宮ゲームの祖”と呼ばれ、後の『メタルギア』シリーズや『キングスフィールド』などの立体探索ゲームに通じる要素を見出す声も多い。 また、アスキーが残した技術資料の中には、開発メモと思われる断片が存在し、そこには「空の動き」「赤外線視界」「スタミナ=時間」というキーワードが並んでいる。これらは、現代的な“サバイバルメカニクス”の原型とも解釈できる。つまり、『イリーガス Episode IV』は単なるMSXゲームにとどまらず、後世のゲームデザイン思想にまで影響を与えた実験作だったのである。
■■■■ ゲームの魅力とは?
◇ 技術と物語が融合した先駆的世界観
『イリーガス Episode IV』の魅力を語る上で欠かせないのが、単なる「迷路脱出ゲーム」を超えたその構築的世界観である。当時のMSXタイトルの多くは、シンプルなパズルやスコアアタック型が主流だったが、本作は「銀河帝国の崩壊」という壮大なSF叙事詩を背景に持ち、その世界観をプレイヤー自身の体験として感じさせる設計がなされていた。 背景説明は最小限でありながら、プレイヤーが迷宮を進むたびに見えてくる荒廃した構造物、冷たい金属の通路、無機質な警備ロボットの足音によって、自然と“帝国崩壊後の廃墟”を想像できる。まるで文学的な余白を活かした映画のように、語られない部分をプレイヤーの想像力が補完していく。その物語と体験の融合こそが本作最大の魅力といえる。
◇ 恐怖と静寂のコントラストが生む没入感
本作は音の使い方にも独特の演出がある。BGMはほとんど存在せず、代わりに響くのは自分の足音と探知機の警告音だけ。何も起こらない時間が続いたかと思えば、突如として機械音が鳴り、ロボットの気配が近づく――その瞬間の緊張感は、ホラー映画さながらだ。 この“静と動のリズム”が、プレイヤーの心理を見事に操っている。ゲームデザイン的に見ると、これは「音の情報が行動判断に直結する」仕組みであり、今日のサウンドデザインの原点ともいえる構造である。 また、画面の低解像度が逆に“見えない恐怖”を演出していた点も見逃せない。敵の姿がはっきり見えない分、プレイヤーは想像でその脅威を補い、結果として一層の没入を感じるのだ。
◇ 当時の常識を覆した「滑らかさ」への挑戦
1983年のMSXゲームの多くは、キャラクターや背景の描画切り替えがぎこちなく、コマ送りのような動作が当たり前だった。そんな中で『イリーガス Episode IV』は、“滑らかに移動する3D視点”を実現した極めて珍しい存在だった。 64×48ドットという低解像度を逆手に取り、1フレームあたりの描画データを軽量化することで、CPU負荷を抑えながら滑らかなアニメーションを可能にしている。この「動きの気持ちよさ」は、現在のプレイヤーがエミュレーターで触れても驚くほど。限界を知り尽くしたうえで、“体感の質”を最優先に設計されたゲームだったといえる。 滑らかな視点移動と音の演出の組み合わせにより、プレイヤーは迷宮を「歩いている」という感覚を初めて味わうことができた。この感覚は、後に登場する『ウィザードリィ』や『ダンジョンマスター』のような3DダンジョンRPGの感触にも通じるものであり、本作はその黎明期に位置する重要な作品である。
◇ “時間が流れる”世界で生き抜くリアリズム
もうひとつの大きな魅力が、“時間の経過”という要素だ。 画面の空に描かれる太陽と星が動き、夕暮れとともに周囲が暗くなり、やがて夜が訪れる――それは単なる演出ではなく、ゲームプレイそのものに影響を及ぼす。暗闇では視界が悪く、行動リスクが増す。夜の冷気を象徴するかのように、スタミナの減少速度も上がる。プレイヤーは太陽の位置や星の動きから現在時刻と方角を推測し、計画的に進まなければならない。 こうしたリアルな時間感覚の導入は、現代の“オープンワールドゲーム”にも通じる思想だ。昼夜サイクルがプレイ体験を左右するという構造は、この時代の小さなプログラムの中で既に芽生えていた。竹内氏は限られたリソースの中に“現実”を生み出そうとしたのだ。
◇ 生存と探索のバランスを絶妙に保つ設計
スタミナの概念もまた、単なる体力ゲージにとどまらない。本作では「生き残る」ことがすなわちゲームの進行条件であり、行動のたびに減るスタミナが、プレイヤーに慎重な判断を促す。無駄な移動を避け、アイテムを効率よく使うことが攻略の鍵となる。 さらに、食料や水の入手は運任せではなく、探索行動の報酬として配置されている。これにより、プレイヤーは“迷路の全域を調べる動機”を自然に得る。つまり、システムがストーリー体験を支えているのだ。これは現代ゲームデザインの基本原則――「遊びの動機をシステムで作る」――を早くも体現していたと言える。
◇ 銀河戦記と人間ドラマの融合
本作の世界観は、単なるSFではなく“人間の孤独”を描いている。主人公H.T軍曹は、誰もいない都市を一人歩き続ける。仲間の死体、壊れたロボット、瓦礫の山。これらの光景がセリフなしで語りかけてくる。 この無言の物語性が、当時のプレイヤーに強い印象を残した。 「敵を倒す快感」ではなく「生き抜く切なさ」を感じさせる作品であり、アクションよりも精神的な没入を重視するその姿勢は、アートゲーム的とすら言える。 『イリーガス Episode IV』のストーリーはテキストで語られないが、プレイヤーが自分自身の想像で“脱出の意味”を構築する。その余白の広さが、長年にわたって語り継がれる要因の一つである。
◇ 隠されたシリーズ構想がもたらすロマン
Episode IVと銘打たれたことは、当時のユーザーの間でも話題となった。 「なぜIVなのか?」「他のエピソードは存在するのか?」――この謎めいた設定は、プレイヤーの探究心を刺激した。結果として、本作はゲームそのもの以上に“想像の余白”を提供する存在になった。 ゲームファンの中には、「Episode II・IIIは社内試作として存在したのでは」と推測する者もいれば、「実はEpisode IVという題名自体が、混沌の渦=イリーガスを象徴するメタファーだ」と解釈する者もいた。 このように、作品そのものが“神話”化していく過程こそが、イリーガスのもう一つの魅力である。
◇ 後世への影響と“原点”としての意義
『イリーガス Episode IV』は、その後の日本製パソコンゲームに多大な影響を与えた。迷宮探索をリアルタイムで描く手法は、後の3DダンジョンRPGやステルスゲームに繋がり、時間や体力をリアルに管理する仕組みは、“サバイバルゲーム”というジャンルの先駆けになったといっても過言ではない。 また、MSXという教育・開発志向のプラットフォームで“体験重視の作品”を作り上げた点も特筆すべきだ。 『イリーガス Episode IV』は、当時のハード性能を超える野心を示した実験であり、技術と芸術の狭間に生まれた稀有な傑作である。
■■■■ ゲームの攻略など
◇ 基本操作とゲーム開始時の仕組み
『イリーガス Episode IV』の操作はシンプルながら、奥深い設計となっている。スタート時には数字キー「0~9」のいずれかを押しながらスペースキーを入力することで、任意のステージから開始できる。これは単なるショートカットではなく、ゲーム全体を“訓練と実戦”のように体験させる工夫でもある。初心者はステージ1から順に進め、ゲームの感覚を掴むのが望ましいが、上級者はあえて中盤以降の難関ステージから挑戦し、自分の腕を試すこともできる。 操作系は方向キーによる移動と回転、スペースキーでのアクションが中心。視点が擬似3Dで描かれるため、方向感覚を失いやすいが、太陽や星の位置を参考にすることで自分の向きを把握することができる。この“自然の要素をコンパス代わりに使う”発想が、本作ならではの臨場感を生んでいる。
◇ 迷宮の構造と地形の理解
本作の迷宮は単なる箱状の通路ではなく、複雑に入り組んだ立体構造となっている。行き止まりや分岐点の配置が絶妙で、無計画に進むとすぐ方向を見失う。迷宮の壁面は色調や模様によって微妙に異なり、壁の濃淡から“今どのエリアにいるか”を推測することができる。 攻略の第一歩は、この視覚情報の違いを覚えることである。たとえば、薄灰色の壁は中央層、赤味がかった壁は外縁部、青系の壁は地下への通路を示すことが多い。竹内あきら氏はマップに一切のテキストを用いず、色彩と形だけで方向を感じさせる設計を行った。プレイヤーは無意識のうちに迷宮の“地理感覚”を養っていくのである。
◇ アイテムの収集とその役割
迷宮内にはさまざまなアイテムが散らばっており、それぞれが生存や探索に重要な役割を果たす。 – 食料・水:スタミナを回復する基本資源。特に長時間の探索時には生命線となる。 – 赤外線ビューア:夜間でも視界を確保できる最重要アイテム。これを入手するまでは、夜が訪れる前に安全地帯へ戻るのが鉄則。 – 探知機:敵ロボットの接近を知らせる警報装置。ビープ音の間隔が短くなるほど敵が近い。 – 地図断片:特定の地点で拾える半透明のパネル。いくつか集めると迷宮全体の構造を部分的に把握できる。 アイテムの配置はランダムではなく、プレイヤーの行動パターンを試すように意図的に分散している。スタミナが少ない状態で重要アイテムの位置にたどり着くよう誘導される構成は、まさに計算されたゲームバランスといえる。
◇ 警備ロボットの行動パターンを読む
敵として登場する警備ロボットは、一定のルートを巡回している。プレイヤーがその行動を理解することで、危険を最小限に抑えられる。ロボットは大きく3種類に分けられる。 1. パトロール型:一定の区画を往復し続ける。音を頼りに位置を予測し、背後をすり抜けるのが有効。 2. 探索型:プレイヤーが一定範囲に入ると進路を変更し、近づいてくるタイプ。動きを読んで遮蔽物に隠れることが大切。 3. 警報型:接触すると即座に周囲のロボットを呼び寄せる。発見されたら一刻も早く逃げなければならない。 探知機の警告音はこれらの敵の存在を知らせる唯一の情報源である。音の間隔・高さ・テンポを記憶し、ロボットの種類と距離を判断することで、聴覚を使った攻略法が成立する。この要素は、後のステルスゲームデザインに通じる実験的試みでもある。
◇ スタミナと時間の管理術
本作では、スタミナ=生命力であり、時間の経過によって減少していく。行動を焦ると体力を浪費し、休みすぎれば夜を迎えて視界を失う。まさに“生存シミュレーション”的な緊張感が常に伴う。 攻略のコツは、昼間に可能な限り探索を進め、夕方になったら安全地帯で休息を取ること。夜間に赤外線ビューアを持たずに移動するのは危険極まりない。また、スタミナが少ないと移動速度が微妙に低下するため、早めの食料補給を心がけることが重要である。 もう一つの戦略は、“地形記憶”を活用することだ。昼間に特徴的な壁や角度を覚えておけば、夜になっても目印として利用できる。プレイヤー自身の観察力が攻略の鍵を握る設計だ。
◇ 効率的な探索ルートとマッピングの工夫
当時のゲームには自動マップ機能など存在しなかったため、プレイヤーは紙にマップを描いて進むのが基本だった。『イリーガス Episode IV』も例外ではなく、むしろ“マッピングの面白さ”を体験の一部としている。 効率よく探索するためには、まず入口から最初の三叉路までを中心軸とし、左右どちらに進んだかを明確に記録すること。地図の方位は太陽の位置を基準に南を下にして描くと分かりやすい。敵の出現位置やアイテム配置をメモしていけば、再挑戦時に効率的なルートを構築できる。 竹内氏はマップの設計に「回遊構造」と「封鎖構造」を交互に配置しており、探索を進めるほどに“パターンを読み解く快感”が増すようデザインされている。熟練者になると、地図を見ずとも音や壁の色でおおよその位置を把握できるようになるだろう。
◇ 特殊条件と隠し要素
本作には明確な“裏技”という概念は存在しないが、開発者の遊び心を感じさせる隠し要素はいくつか存在する。 – 特定の時間帯(深夜帯)にのみ現れる“光る壁”を通過すると、ショートカット通路に出る。 – 一定のスタミナ残量で脱出すると、エンディングのメッセージが微妙に変化する。 – 赤外線ビューア未所持で夜を生き延びると、“勇者コード”と呼ばれる隠し称号が出現する。 これらは明確な攻略本には載っておらず、プレイヤー同士の口コミで広まった。アスキー誌の読者投稿欄でもたびたび議論され、当時のプレイヤーたちの間で「真の脱出条件を探す探求心」が熱く語られたという。
◇ 難易度とリプレイ性
『イリーガス Episode IV』は非常に難易度が高い。しかし、それは理不尽さではなく、プレイヤーの観察力と判断力を鍛える設計によるものである。敵の行動を見抜き、時間を読み、スタミナを管理しながら最短経路を探す――すべてが論理的思考に基づく。 また、前述のステージ選択機能により、プレイヤーは自分の得意なエリアを何度も再挑戦できる。これにより、単なるクリア目的の一発勝負ではなく、繰り返し遊んで攻略法を洗練させる楽しさが生まれている。 この自由度と試行錯誤のバランスこそ、後のローグライクゲームの根底にある“リプレイアビリティ”の萌芽とも言える。
◇ 攻略の本質――「恐れず、観察せよ」
最終的に『イリーガス Episode IV』の攻略で最も大切なのは、スピードでも記憶力でもなく、観察と冷静さである。プレイヤーが慌てれば敵に捕まり、無駄な行動はスタミナを奪う。逆に、状況を俯瞰し、環境の変化を読み取ることができれば、脱出への道は見えてくる。 竹内氏が設計したこの作品は、単なるアクションやパズルではなく、「自分の感覚と世界との対話」を体験させるゲームである。攻略とは、プログラムを解くことではなく、“世界を理解すること”なのだ。
■■■■ 感想や評判
◇ プレイヤーが受けた“孤独と緊張”の体験
『イリーガス Episode IV』を初めてプレイした人の多くが口をそろえて語るのは、「孤独の感覚」と「静寂の緊張」である。BGMのない世界、遠くで響く警備ロボットの足音、暗闇に沈む廃墟――そのすべてがプレイヤーの感情を研ぎ澄ませる。 1983年当時、このような演出を採用した作品はほとんど存在せず、プレイヤーの多くは“怖いのにやめられない”という不思議な魅力に取り憑かれた。ログイン誌やマイコンBASICマガジンなどの投稿欄には、「このゲームの静けさに引き込まれる」「音のない世界が逆にリアルだ」といった感想が多数寄せられた。 この反応は、単なるゲームとしての面白さだけではなく、プレイヤーの感情体験を設計した作品として評価されていた証でもある。
◇ メディアによる評価――“MSXの限界を超えた”と絶賛
専門誌のレビューでは、本作の技術的挑戦が高く評価された。特に注目されたのは、SCREEN3による3D表現と、滑らかな移動描写である。 『ログイン』1984年号では、“MSXの限界を軽々と飛び越えた異端作”と称され、「動きの滑らかさは8ビット機の奇跡」とまで評された。 また、同誌の技術特集では「プログラム構造の洗練さ」にも触れられており、描画ルーチンの工夫や、演算処理の最適化技術が解説されるなど、プログラマ視点からも注目された。 こうした報道がきっかけとなり、本作は単なる“ゲーム”ではなく、「技術の芸術作品」として語られる存在になった。
◇ 一般プレイヤーの感想――難しさと達成感の両立
当時のユーザーにとって『イリーガス Episode IV』は、決して易しいゲームではなかった。方向感覚を失いやすく、敵のパターンも容赦がない。しかしその分、出口にたどり着いた瞬間の達成感は強烈だったという。 あるプレイヤーは回想している。「夜明けの太陽を見ながら脱出できたとき、本当に涙が出た」。この感想は多くのファンの記憶にも残っている。時間経過と環境変化がプレイヤーの努力を映し出す――この設計が“生きて帰る喜び”をリアルに演出していたのだ。 SNSやレトロゲーム掲示板では、今でも「スタミナ切れ直前の緊張感」「探知機の音が夢に出た」といったコメントが見られる。40年以上経った今でも、プレイヤーの心に残る“体験型ゲーム”として評価され続けている。
◇ 批評家たちの分析――“ゲームが文学になる瞬間”
後年の評論家たちは、『イリーガス Episode IV』を単なる脱出ゲームではなく、“自己と空間の対話を描いた作品”として分析している。 ゲーム史研究者の一人は次のように述べた。 > 「イリーガスは、プレイヤーが世界を観察し、自分の存在を確かめながら前進していく哲学的体験である。これはまさに、文学が描こうとする内面の冒険をインタラクティブに再現したものだ。」 この評価は非常に興味深い。竹内あきら氏のプログラムは、数式と論理で構築された世界であるにもかかわらず、プレイヤーに人間的な感情――恐怖・孤独・希望――を呼び起こす。つまり、『イリーガス Episode IV』はゲームでありながら“表現芸術”の領域に足を踏み入れた先駆けであった。
◇ 海外コミュニティでの再評価
MSX文化は日本発祥であるが、ヨーロッパや南米でも愛好家が多い。その中で『イリーガス Episode IV』は“忘れられたSFアドベンチャー”として再発見され、英語圏のレトロゲームフォーラムでは「MSXのメタルギアよりも早く、ステルス性を導入した作品」と評された。 特に、夜間に赤外線装置を使って敵を回避するメカニクスは、後の“潜入ゲーム”の原型と見なされている。YouTubeやTwitchでも海外プレイヤーによる実況が投稿され、 「当時のハード制限を考えると信じられない」「音と光だけで緊張感を作るセンスが素晴らしい」などのコメントが多く寄せられた。 こうして、40年の時を経て本作は国境を越え、“失われたテクノロジーアート”として再評価されつつある。
◇ 当時のプレイヤーが語る思い出
1980年代をリアルタイムで経験したプレイヤーたちは、口々に「イリーガスは他のどのゲームとも違った」と語る。 「攻略本がなくて、みんなで地図を描き合った」「友人と昼夜逆転して赤外線装置を探した」「探知機の音が鳴るたびに息を止めた」――そんな思い出話が今も語られる。 特に印象的なのは、“一人称視点で迷う感覚”がリアルだったという意見。画面の小ささや単純な色の変化が逆に想像をかき立て、「自分が本当に閉じ込められている感覚」に襲われたという。 この心理的没入こそ、現代のVRゲームに通じる要素であり、『イリーガス Episode IV』がいかに時代を先取りしていたかを物語っている。
◇ 雑誌投稿・ファンコミュニティでの熱狂
『別冊LOGIN1 MSX GAME BOOK』(1985年)に掲載された「マイクロ・イリーガス」の存在も、ファン熱を高めた一因だった。この簡易版を自分で打ち込み、動かして遊んだユーザーが、「本家との違い」を探りながら交流したのである。 掲示板やユーザーグループの間では、隠し通路の情報や敵の挙動解析が活発に行われ、“脱出研究チーム”と呼ばれる愛好会まで生まれた。 その熱気はまさに、今日のインディーゲームコミュニティに通じるものであり、プレイヤーが開発者の意図を読み解き、作品を育てていく文化がここにあった。
◇ 批判と課題――“不親切さ”も魅力の一部
もちろん、すべての意見が肯定的というわけではなかった。難易度の高さや説明不足に不満を漏らす声も存在した。「方向感覚を完全に失う」「マップがなさすぎて理不尽」などの意見も多い。しかし、その“突き放すような設計”が逆に熱狂的な支持を生む結果となった。 「理不尽なのではなく、世界が冷たいだけだ」と語るファンもおり、ゲームの不親切さが作品のテーマ性(孤独と崩壊)と一致していたため、批判がそのまま魅力に転化していたのである。 この“ユーザーの解釈に委ねる姿勢”は、後のアート系ゲームや環境シミュレーション作品へと受け継がれていった。
◇ 現代の視点から見た“特異な完成度”
現代のプレイヤーがエミュレーターを通じて本作を体験しても、その完成度の高さに驚かされる。 単なる懐古趣味を超え、今なおプレイヤーを没入させる力があるのは、ゲームデザインそのものが普遍的だからだ。 プレイヤーが環境を読み、限られた情報で判断し、命を守る――この構造は最新のサバイバルゲームにも共通している。 つまり、『イリーガス Episode IV』は時代を超えても色あせない“人間的体験の核”を持っていたと言える。
◇ 総評――“無音の迷宮が語りかける芸術”
総じて、『イリーガス Episode IV』の評判は、40年を経た今も高い評価で安定している。 技術的挑戦、演出の静謐さ、哲学的ストーリー、そして何よりも“自分で世界を解釈する自由”がある。 この作品は、当時の少年たちに「想像力で世界を補う喜び」を教え、プログラマーたちには「限界を超える創造性」を示した。 静かな迷宮の中でプレイヤーは孤独に立ち尽くす――だが、その静寂こそが『イリーガス Episode IV』という作品の最も美しい瞬間であり、1980年代日本パソコン文化の象徴的傑作として語り継がれている。
■■■■ 良かったところ
◇ 低解像度の制約を創造力に変えた表現力
『イリーガス Episode IV』の最も称賛される点は、64×48ドットという極めて低い解像度を「制約」ではなく「表現手段」として昇華させた点にある。当時のパソコンは描画速度や色数に大きな制限があり、リアルな空間表現など夢のまた夢とされていた。ところが本作は、その限界を逆手に取り、粗いドットで構成された空間に“想像の余白”を与えた。 プレイヤーはぼやけた輪郭の中に壁や影を見出し、限られた色調の変化から時間の流れを感じ取る。つまり、見る人の想像力を呼び覚ます設計がなされていたのだ。これはまるで印象派絵画のように、すべてを描かずに「感じさせる」美学に通じる。後年のインディーゲームデザイナーたちが「情報を削ることで想像を生む」というデザイン哲学を提唱したが、その原点はすでに本作の中にあった。
◇ 時間・環境・生命の三位一体システム
本作が評価されるもう一つの理由は、ゲーム内世界に“生きている”感覚を与える設計にある。時間の経過による昼夜の移り変わり、太陽と星の動き、スタミナの減少と回復――これらが全て連動し、プレイヤーは「世界が自分とは別に動いている」と感じる。 1983年当時、ゲームの多くは「常にプレイヤー中心の時間軸」で動いていた。しかし『イリーガス Episode IV』は、プレイヤーが操作しなくても世界が変化していく。太陽が沈み、視界が暗くなる。敵の巡回も時間で変化する。プレイヤーは世界の一部として存在することを実感する。 この“環境シミュレーション的リアリティ”は、現代のオープンワールドゲームにも通じる思想であり、黎明期にして極めて先進的だった。
◇ サウンド演出の大胆な“無音美学”
多くの80年代ゲームが電子音のBGMを多用していた中で、『イリーガス Episode IV』はあえてほとんど音を排した。プレイヤーが聞くのは、足音、探知機の警報音、そして時折の電子的なノイズだけ。この静寂こそが、作品の緊張感を生んでいる。 “音がない”という選択は、実は大胆なデザイン哲学の表れだ。音楽によって感情を誘導するのではなく、プレイヤー自身の鼓動と想像がBGMになる。この手法は、後のホラーゲーム『サイレントヒル』や『バイオハザード』などにも受け継がれる“静寂の恐怖”の源流といえる。 プレイヤーはヘッドフォン越しに微かな電子音を聞き取りながら、息を潜めて進む――その瞬間、ゲームの中と現実の境界が曖昧になるのだ。
◇ ゲームデザインに宿る哲学性
『イリーガス Episode IV』は、単に“迷路を抜ける”だけのゲームではない。プレイヤーに求められるのは、状況判断・時間管理・観察力といった思考力であり、行動そのものが“生存哲学”を体験する手段になっている。 例えば、スタミナが尽きそうな時に食料を使うか、それとも温存して次の安全地帯まで耐えるか――その判断が常に命運を分ける。プレイヤーは合理的に考え、限られたリソースで最善を尽くす。この構造はまさに“限界下の意思決定”という哲学的テーマを内包しており、ゲームを通じて人間の選択とは何かを問いかけてくる。 この思想的深みが、後年の評論家から“哲学的サバイバルゲーム”と称される所以である。
◇ 敵AIの完成度と心理的緊張
警備ロボットのAI(人工知能)設計も、当時としては非常に洗練されていた。敵が単純なランダム移動ではなく、プレイヤーの位置に反応し、音や視界の範囲で探索行動をとる点は画期的だった。 プレイヤーが通った道を一時的に巡回ルートとして記憶するため、“逃げた方向を追われる”という状況が自然に発生する。これが、ただの敵キャラクターではなく、“知覚する存在”としての恐怖を与えている。 このAI設計により、ゲーム全体に「生き物のような緊張感」が生まれ、プレイヤーは常に見られているような感覚を抱く。心理的圧迫と達成感のバランスが絶妙で、当時のユーザーからは「一歩進むたびに心臓が鳴るゲーム」と称された。
◇ 物語を語らない“語り”の妙
『イリーガス Episode IV』には、ほとんどテキストによるストーリーテリングが存在しない。しかし、プレイヤーが体験する出来事そのものが物語を紡いでいく。 廃墟の通路を抜け、空を見上げ、太陽が沈む瞬間に“この惑星にも時間が流れている”と気づく。その瞬間に、言葉のないドラマが心に生まれる。 このような“体験による物語”の構造は、後のゲームデザイン理論において「エマージェント・ナラティブ(自発的物語)」と呼ばれる考え方に一致する。1983年にすでにその萌芽を示していた本作は、まさに物語を語らずして語る芸術作品であった。
◇ リプレイ性とプレイヤー学習の快感
本作のもう一つの良点は、プレイヤーが“上達を実感できる”設計だ。最初は方向感覚を失いがちでも、プレイを重ねるうちに音・光・壁の模様で位置を判断できるようになる。 つまり、プレイヤーが学習することで、世界がより明確に“見えるようになる”のだ。この体験は、知識や経験が直接的にプレイ感覚を変えるという、極めて人間的な満足感をもたらす。 ゲームをクリアすることが目的ではなく、世界を理解していく過程そのものが楽しさになる――この構造は後の『ダークソウル』などに通じる“学習の喜び”の原点である。
◇ 視覚と聴覚を通じた“没入型インターフェース”
GUIもなく、HUDも最低限。プレイヤーは数字やゲージに頼らず、自分の感覚で状況を把握する。この極端なミニマリズムが、結果的に究極の没入感を生んでいる。 視界の端でわずかに変わる色のトーン、遠くで響く電子音、空の星々――これらがすべて情報源となる。プレイヤーが“自分の身体感覚を通じて世界を読む”という設計思想は、VRの根幹にも通じる。 つまり、本作は「HUDを捨てたリアル志向インターフェース」の先駆けであり、今日のゲーム体験設計における感覚的UIの原点といえる。
◇ 挑戦する心を刺激するバランス設計
多くのプレイヤーが本作を“難しいが癖になる”と評する理由は、リスクとリターンのバランスが見事だからだ。スタミナが減る恐怖、暗闇の不安、敵の足音――その緊張感の中で出口を発見した時のカタルシスは圧倒的。 どんなに厳しくても、必ず“わずかな光”が見えるよう設計されており、プレイヤーは「次こそは」と再挑戦する気持ちを掻き立てられる。 つまり、ゲームが“人間の挑戦本能”を引き出すように作られているのだ。失敗しても挫折ではなく、「次はもう少し賢くなれる」という前向きな学びが残る。これは本作最大の美点といえる。
◇ 芸術とテクノロジーの融合点
『イリーガス Episode IV』を語る上で、最後に挙げるべき長所は、芸術的感性と技術的革新の融合である。 単なるプログラムの集合体でありながら、そこに“詩的情景”が存在し、プレイヤーに感情を与える――これは極めて稀有な現象だ。竹内あきら氏が目指したのは、コンピュータを“表現の道具”に昇華させることだったのだろう。 彼の設計思想は、「テクノロジーが人間の想像力を拡張する」という哲学に根ざしており、だからこそ40年経っても色褪せない普遍性を持つ。 この作品を体験することは、まさにゲームというメディアの可能性を目撃する行為であり、それこそが多くのプレイヤーが「良かった」と口を揃える理由なのである。
■■■■ 悪かったところ
◇ 初心者を寄せ付けない圧倒的な難易度
『イリーガス Episode IV』が高い評価を得る一方で、最も多く指摘されたのがその難易度の高さである。 ゲームを始めた瞬間から目的地の説明がなく、プレイヤーは暗闇の中に放り出される。画面上にはわずかな情報しか表示されず、方角や位置のヒントも一切ないため、初見では何が起きているのか理解するまでに時間がかかる。 当時のプレイヤーの多くが「最初の5分で迷子になった」と語り、特に方向感覚を失いやすい点が不評だった。 MSXのスペック上、ミニマップやコンパスのような補助機能を導入するのは難しかったとはいえ、もう少し導入の丁寧さがあれば、初心者の脱落を防げたかもしれない。 その意味で、本作は挑戦的であるがゆえに“門戸が狭すぎる”作品でもあった。
◇ 操作説明と目的提示の不足
『イリーガス Episode IV』には、ゲーム中に明確な操作ガイドや目的説明が存在しない。スタート時に何をすべきかが曖昧で、慣れないプレイヤーは最初の行動で迷ってしまう。 たとえば、「スタミナが減る仕組み」や「赤外線ビューアの重要性」は、実際にゲームオーバーを経験して初めて理解できる仕様であり、試行錯誤を強制されるデザインだった。 その結果、初期段階で多くのユーザーが挫折し、「雰囲気は素晴らしいが、何をすればいいかわからない」という感想が散見された。 これは80年代当時の“説明しないゲーム哲学”の一環でもあるが、現代の視点から見ると、情報不足による理不尽さとして受け取られやすい部分である。
◇ グラフィックの抽象性による誤解
64×48ドットという低解像度表現は本作の特徴であり魅力でもあるが、同時に視覚的誤認を招く欠点でもあった。 壁と通路の境界が曖昧で、遠近感の表現も単純な色の濃淡に頼っているため、プレイヤーは「今どちらの方向を向いているのか」が分からなくなることが多い。 また、敵ロボットの描写も抽象的で、近づいてくるのか離れていくのか判断が難しい場面がある。結果として、プレイヤーは理不尽な形で捕まり、ゲームオーバーになることも少なくなかった。 こうした情報視認性の低さは、当時の技術的制約の範囲内での工夫ではあったものの、ゲーム体験としては不便に感じられることが多かったようだ。
◇ スタミナシステムの厳しさとテンポの悪さ
スタミナ制の導入はリアリティを高めた一方で、プレイヤーの自由度を制限してしまう側面もあった。 行動するたびにスタミナが減り、休むことも限られているため、プレイヤーは常に“焦り”を感じながら探索しなければならない。特に、回復アイテムの出現頻度が低く、食料や水を見つけるまでに倒れてしまうことが多い。 このリスク過多な設計がプレイヤーのストレス要因になっていた。緊張感を演出する狙いは成功しているものの、「探索したいのにスタミナが持たない」という不満も目立つ。 一部のプレイヤーは「ゲームというより、サバイバル実験だ」と皮肉交じりに語っており、バランス調整の面では課題を残していた。
◇ 時間経過システムの難しさ
昼夜の概念や太陽の動きによる時間表現は革新的だったが、同時にプレイヤーの混乱を招く要素にもなっていた。 特に夜間になると視界が極端に狭くなり、赤外線ビューアがない状態では事実上行動不能に陥る。しかも時間は止まらず、スタミナだけが減っていくため、夜を迎える=ほぼ詰み状態になるケースも多かった。 また、太陽の位置から方角を判断するという仕組みは、理論的には面白いが、ゲーム内のグラフィックが簡素なため方向が分かりづらく、実用性よりもコンセプト重視に感じられた。 このように、システムそのものは先進的であったが、プレイヤーの理解を助ける仕組みが不足していたため、“理屈ではすごいが遊びづらい”という印象を与えてしまった。
◇ リアルすぎる孤独感と緊張の持続
多くのプレイヤーが絶賛した“静寂の演出”だが、一部からは「静かすぎて怖い」「精神的に疲れる」との声もあった。 音楽が存在しない世界で、暗闇の中を何十分も歩き続けるという体験は、没入感を生むと同時に、心理的負担をも生み出す。 特に当時の子供たちにとっては、敵の音や画面の暗さが“トラウマ的体験”になったという証言もある。 ゲームデザインとしては成功だが、エンターテインメントとしての“楽しさ”よりも“緊張と恐怖”が勝ってしまったという点は否めない。 これは竹内あきら氏の演出哲学――「プレイヤーの感情を揺さぶる」――が強く出すぎた結果でもある。
◇ 理不尽なゲームオーバー判定
『イリーガス Episode IV』では、警備ロボットに接触した瞬間にゲームオーバーとなる。回避手段はあるものの、敵の動きが速く、視界の制限も重なって、理不尽な死を迎えることが多い。 しかも、ゲームオーバーになるとセーブ機能がないため、最初からやり直しになる。これは現代では考えられないほどのペナルティであり、努力が無に帰す体験がプレイヤーの挫折を招いた。 再挑戦ごとにスタート位置が変わるステージもあり、運の要素も絡むため、攻略よりも「耐久戦」のように感じられる場面も多かった。 当時のハードの制限上、セーブ機能を実装できなかったことは理解できるが、難易度の高さと相まって“根気のいる作品”という印象を強めていた。
◇ ストーリーの断片性と謎の多さ
本作のストーリーは設定面では壮大だが、ゲーム内で語られる情報がほとんどないため、プレイヤーには伝わりにくい。 公式資料や雑誌インタビューを読まない限り、主人公の名前や目的さえ分からないという状況で、物語的動機づけが弱かった。 「なぜ脱出するのか」「帝国とは何か」といった要素が提示されないままゲームが進むため、世界観の深みを十分に感じられないという指摘もある。 これは抽象的で芸術的な魅力としても受け取れるが、多くのユーザーにとっては“情報不足による理解不能”と映った。 シリーズ構想の一部であることを示す“Episode IV”という副題も、結局その後の作品が出なかったため、永遠の謎として残ってしまった。
◇ 技術的制約ゆえの単調さ
滑らかな動きや独特の雰囲気は称賛されたが、プレイヤーの行動パターン自体は単調になりがちだった。 攻撃やジャンプといった多彩なアクションはなく、基本的には「進む・避ける・逃げる」の繰り返しで構成されている。これにより、長時間プレイすると単調さや倦怠感を覚えることがあった。 また、マップ構造にも一部似通ったパターンがあり、方向を見失った際に「同じ場所をぐるぐる回っている」感覚に陥るプレイヤーも多かった。 竹内氏の設計思想は「思考による探索」に重きを置いていたが、プレイの変化を生む要素が少なかったことは否定できない。
◇ 総評――挑戦作ゆえの“完成しきらない美しさ”
総じて、『イリーガス Episode IV』の“悪かったところ”は、裏を返せばその実験精神の副作用である。 技術的にも思想的にも時代を先取りしすぎており、当時のプレイヤー層やハード性能が追いついていなかった。 もしリメイク版や現代的UIを備えた移植版が存在していれば、間違いなく再評価の声がさらに高まっただろう。 つまり、本作の欠点は“完成度の低さ”ではなく、“時代がまだこの作品を理解できなかった”ことにある。 不便で、難解で、孤独――だが、その不完全さこそが『イリーガス Episode IV』の美しさであり、挑戦する者だけが辿り着ける体験を形作っていたのだ。
[game-6]■ 好きなキャラクター
◇ 孤独な主人公 ― 帝国軍下士官H.T一等軍曹の存在感
『イリーガス Episode IV』における“キャラクター”とは、台詞や顔グラフィックを伴う人物ではない。だが、プレイヤーが操作する主人公 ―― 帝国軍下士官「H.T一等軍曹」には、驚くほど深い人間性が感じられる。 彼の名前は冒頭でわずかに触れられるのみで、外見の描写も一切ない。それにもかかわらず、多くのプレイヤーが「彼を覚えている」と語るのはなぜだろうか。 理由の一つは、体験を通して彼の人格が形作られていく構造にある。 孤立無援の砂漠惑星で、壊れた都市ム・モンクの迷宮を一人さまよう。仲間は死に絶え、通信も途絶えた。食料を求めて瓦礫を探り、ロボットを避けて息を潜める。 その行為の一つ一つが、プレイヤー自身の感情と結びつき、“H.T”という存在が脳内で立体的に形成されていくのだ。 彼は「語られない主人公」――だが、プレイヤーの行動そのものが彼の言葉になる。沈黙を貫く孤独な軍曹こそ、1980年代日本パソコンゲーム史の中でも特異な“無名の英雄像”である。
◇ 主人公に投影されるプレイヤー自身の姿
H.T軍曹の最大の魅力は、プレイヤーが彼を“自分自身”として感じられる点にある。 彼は勇者でも天才でもなく、ただ「生き延びようとする一人の兵士」にすぎない。その等身大の立場が、プレイヤーに深い共感を呼び起こした。 スタミナを失い、夜の闇に迷い、恐怖に震える――それはH.T軍曹ではなく、プレイヤー自身の感情である。つまり本作は、キャラクター性を外在化せず、体験そのものの中に内包させた極めて独創的な設計なのだ。 この構造により、プレイヤーは「H.T軍曹を操作する」のではなく、「H.T軍曹として生きる」ことになる。 その没入感こそが、今日に至るまで語り継がれる『イリーガス Episode IV』最大の魅力であり、彼が“無表情のまま最も印象的な主人公”と評される理由でもある。
◇ 敵であり環境でもある ― 警備ロボットのキャラクター性
『イリーガス Episode IV』には、人間の登場人物がいない。その代わりに、プレイヤーの前に立ちはだかるのは警備ロボットたちである。 一見無機質な存在だが、プレイヤーが長くプレイするほどに、それぞれの動きや音の個性が感じられてくる。あるロボットは重低音を響かせて巡回し、またあるロボットは鋭い電子音で接近を知らせる。 この違いは単なるプログラム上の仕様ではなく、機械に“個性”を与える演出として機能している。 たとえば、特定のステージに登場する“赤い光を放つ高速型ロボット”は、プレイヤーから「ハンター」と呼ばれ、恐怖の象徴として語られている。 また、“静かに近づいてくる黒いロボット”は、その行動パターンの読めなさから“ゴースト”とあだ名され、ファンの間で都市伝説的な存在となった。 これらの機械的キャラクターは、セリフも感情も持たないにもかかわらず、敵対者としての存在感を強く放っている。 プレイヤーが音を聞き分け、行動パターンを学ぶ過程で、ロボットたちは単なる障害ではなく、ある種の“対話相手”として感じられるようになるのだ。
◇ “見えない登場人物”としての都市ム・モンク
本作では、舞台となる惑星アル・マザールの旧都市「ム・モンク」自体が、もう一人のキャラクターのように存在している。 崩壊した建築群、無人の通路、沈黙するエネルギー炉――その一つ一つがかつての文明の痕跡を語る。 都市は死んでいるようで、どこか“まだ生きている”ような感覚を与える。プレイヤーが歩くたびに、遠くで金属音が響き、壁の影に残された人影のような模様が過去を暗示する。 ム・モンクは、セリフを持たないキャラクターでありながら、最も雄弁に“語る存在”である。 竹内あきら氏は、この都市を単なる背景ではなく、「失われた帝国の記憶」として設計している。 プレイヤーが脱出を試みるその瞬間、都市そのものが彼を見送るように静かに光る――それは、人間と文明の対話を象徴する美しい演出である。
◇ 無言のAI ― “存在しない上官”の影
本作では、プレイヤーが序盤に無線通信機を拾うことがある。しかし、通信を試みてもノイズしか返ってこない。 この「応答のない上官」という存在が、物語全体に不気味な影を落としている。 プレイヤーは何度も通信を試すが、応答はない。だが、時折“聞き間違いかもしれない”程度の電子ノイズが、人の声のように聞こえる瞬間がある。 この演出が非常に秀逸で、プレイヤーは「もしかしたら誰かが生きているのでは」と希望を抱く。しかし、それは決して確証に変わらない。 この“見えないキャラクター”の存在感は、心理的にプレイヤーを揺さぶり、孤独の中にかすかな温もりを感じさせる。 上官の声が本当に存在するのか、それともH.T軍曹の幻聴なのか――その解釈はプレイヤーに委ねられている。 この曖昧さこそ、『イリーガス Episode IV』が“物語を語らない物語”として高く評価される理由の一つである。
◇ プレイヤーが作り出す“もう一人の自分”
『イリーガス Episode IV』では、ゲームを繰り返すうちに、プレイヤー自身が二人目の自分を作り出していく感覚を覚える。 初回プレイでは恐怖と混乱に支配されるが、再挑戦するたびに冷静さと洞察力を身につけ、“経験者としての自分”が頭の中に生まれる。 やがてそのもう一人の自分が、迷宮での判断を導いてくれるようになる。 この構造は、心理学的に“自己分身投影”と呼ばれる現象で、プレイヤーが主人公H.Tと一体化しながらも、同時に“観察者の視点”を持つ状態である。 つまり、本作における“好きなキャラクター”とは、単なるゲーム上の人物ではなく、プレイヤーの中に形成される新たな人格でもあるのだ。 この感覚を体験した者は、ゲームを終えた後も長くその余韻を心に残す。
◇ ファンの間で語られる“幻の女性隊員”説
『イリーガス Episode IV』には、実際には登場しない“女性隊員”の存在が一部で噂されていた。 これは、ゲーム中に極めてまれに表示される特殊なシンボルパターンが、人の横顔に見えるという偶然から生まれた都市伝説だ。 プレイヤーたちはその姿を“L.T(ルテナント)”と呼び、主人公のかつての仲間、あるいは恋人であると想像した。 この“見えないキャラクター”がファンの想像の中で成長し、後年の二次創作では「通信が届かない理由」「脱出を急ぐ理由」を象徴する存在として描かれることもあった。 竹内氏が意図したものかは不明だが、こうした想像がキャラクターを生み出す現象そのものが、本作の魅力を物語っている。
◇ 総評 ― “存在しない登場人物たち”の深い余韻
『イリーガス Episode IV』には、派手なキャラクターデザインもセリフもない。それでも、多くのプレイヤーの心に“誰か”が残っている。 それは、無言で歩き続けるH.T軍曹、機械のように規則正しく動く警備ロボット、そして文明の残骸そのものであるム・モンク。 彼ら(あるいはそれら)は、いずれも人間性の断片を映し出している。 孤独、恐怖、希望、記憶――そうした感情が、キャラクターの形を取らずにプレイヤーの中で育っていく。 だからこそ、本作の“好きなキャラクター”とは、明確に存在する誰かではなく、プレイヤーが体験の中で生み出した“心の中の登場人物”なのだ。 竹内あきらがこの作品に込めた最大の意図は、キャラクターを描くことではなく、「プレイヤー自身がキャラクターになること」だったのかもしれない。 そして、その理念こそが『イリーガス Episode IV』を40年経った今も“心に残るゲーム”たらしめている。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
◇ MSX版 ― 低解像度が生んだ独自の“圧迫感”
『イリーガス Episode IV』のオリジナルプラットフォームは、1983年に登場したMSX版である。 このバージョンは64×48ドットという極端に低い解像度で動作し、SCREEN3モードを使用して描画されている。 現代の目から見ると粗いモザイクにしか見えないが、当時のプレイヤーにとっては“迷宮の中に閉じ込められているような圧迫感”を生む独特の体験だった。 MSXの制約が、結果的にゲームの緊張感を増幅する要素として機能していたのである。 プレイヤーは不明瞭な映像から壁の形や距離感を推測しなければならず、視覚ではなく感覚で空間を“読む”ことを要求された。 つまり、MSX版は単なるゲームではなく、人間の知覚を使って遊ぶ“感覚シミュレーション”と呼べる内容だった。
加えて、MSXの音源(PSG)の限られた3音チャンネルを巧みに使い、環境音的なノイズを生成。
BGMを排除する代わりに、空間に漂う電子的な“ハム音”を持続的に鳴らすことで、プレイヤーに“生きた都市の残響”を感じさせた。
これは当時の他作品では見られない演出手法であり、竹内あきら氏が持つサウンドプログラムへの独自感覚を象徴している。
◇ PC-8801版(非公式移植を含む) ― くっきりとした3D迷宮の再構成
後年、有志による非公式移植として制作されたPC-8801版では、描画解像度が上がったことで迷宮の構造がより明確に視認できるようになった。 背景の明暗差が増し、壁の質感や奥行きが分かりやすくなったことで、MSX版のような“圧迫感”よりも“探索感”が強調されている。 また、PC-8801の高速描画性能によって移動アニメーションも滑らかに再現され、処理落ちがほとんど感じられなかった。 その反面、独特の不安定な空気感が薄れたという意見もあった。 プレイヤーの中には「MSX版の粗さがかえって怖かった」と語る者も多く、どちらを“正統”とするかは意見が分かれるところだ。
さらに、PC-8801版では一部のユーザーによってBASICコード解析が進められ、マップデータの構造やAIのパターンが研究対象となった。
これは本作が単なる娯楽作品にとどまらず、プログラミング教材的価値を持っていたことを示している。
ゲームそのものを分解して理解するという文化は、当時のパソコン少年たちの学びの一部であり、『イリーガス Episode IV』はまさに“遊べるアルゴリズム”だったのだ。
◇ X68000でのリメイク風移植 ― 重厚なグラフィックと再構築された恐怖
1990年代初頭、X68000ユーザーの間で本作をリスペクトしたリメイク風作品が登場した。 このバージョンはアスキー非公式ながら、オリジナルの構造を踏襲しつつ、解像度と色数を劇的に向上させた。 滑らかなグラデーションによる空の色変化、壁面の反射光、床のメタリックな質感――それらが重厚な3Dダンジョンとして再現され、MSX版の“抽象的恐怖”が“映像的恐怖”に変わっていた。 特に太陽の動きをリアルタイムに再現し、画面上に光が差し込む表現はX68000の描画能力を最大限に活かしていた。
ただし、ファンの中には「リアルすぎて怖くない」「情報量が多すぎて空気が軽くなった」と感じる人もおり、MSX特有の“省略の美”が失われたと評する意見も根強い。
それでも、この移植版は原作の思想を理解した上で拡張を試みた希少な例として、レトロゲーム研究の中ではしばしば取り上げられる。
◇ Windows版(復刻・アーカイブ版) ― 過去をそのまま現代に
2000年代以降、アスキー関連の復刻企画やアーカイブプロジェクトによって、Windows上で動作する『イリーガス Episode IV』のエミュレーション版が公開された。 このバージョンではオリジナルのMSXコードがそのまま再現され、グラフィックも音声も忠実に再現。 ウィンドウサイズ変更やセーブステート機能が追加され、現代の環境でもプレイしやすくなった。 特筆すべきは、当時の雰囲気を損なわずに“保存と体験の両立”を果たした点だ。 これにより、かつてプレイできなかった世代のユーザーが本作に触れる機会を得た。 また、海外のMSXファンコミュニティではWindows移植版をベースに多言語化パッチが作成され、“Illygas Episode IV”として英語圏のファンにも広がった。
しかし、この移植で浮き彫りになった課題もある。現代のモニター環境では解像度の低さが逆に見づらく、オリジナルの“ぼやけた恐怖感”を完全に再現するのは難しかった。
一部では「高解像度化によって緊張感が減った」との声も上がり、技術の進化がもたらすジレンマを象徴する事例ともなった。
◇ 技術の進化と原作精神の継承
各バージョンを比較して見えてくるのは、竹内あきら氏の設計思想がどの時代でも中心に存在しているという事実である。 どんなにグラフィックが向上しても、音声がリアルになっても、根底にあるのは「観察」「生存」「孤独」という三つの体験軸。 ハードウェアが変わるたびに表現は変化しても、その軸がぶれることはなかった。 むしろ、異なる機種でプレイするたびに、プレイヤーは同じ構造の中で異なる感情を得る。 これは、技術が変わっても“人間の感じ方”は変わらないことを証明するような設計哲学だった。
◇ 総評 ― “ハードを超えて生き続ける迷宮”
『イリーガス Episode IV』の面白さは、どのプラットフォームでも体験の核が失われない点にある。 MSXでは想像の恐怖、PC-8801では論理の探求、X68000では映像による没入、そしてWindows版では記録としての再体験――いずれも同じ迷宮でありながら、異なる表情を見せる。 まるで“同じ夢を異なる夜に見る”ような不思議な感覚を味わえるのだ。 40年を経ても本作が語られ続けるのは、ハードの性能に依存しない“本質的なデザイン”が存在するからだろう。 竹内あきらが作り上げたこの作品は、どんな時代にも通じる“知覚の迷宮”であり、パソコンという枠を超えて今なお生き続けている。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1983年は、日本のパソコンゲーム文化が大きく変革を迎えた年だった。
各メーカーがMSXやPC-8801、FM-7などの機種に参入し、ジャンルや技術の多様化が進んだ。
『イリーガス Episode IV』もその潮流の中で誕生した作品であり、同時期のタイトルを比較すると、当時の開発思想や時代背景がより鮮明
★1. テセウス
(アスキー/1983年/価格:6,800円) 『イリーガス Episode IV』の前身とされる作品。竹内あきらが手掛けた3D迷宮探索ゲームで、シリーズ的には“エピソード1”に位置づけられている。 画面構成や移動の仕組みは『イリーガス』と共通しており、視点の切り替えを使わずに擬似3D空間を表現したことが話題を呼んだ。 迷宮構造はより単純だが、謎解き要素や方向感覚の訓練という点では、本作の実験的基盤といえる。 “エピソード4”である『イリーガス』が洗練された心理的サスペンスを描いたのに対し、『テセウス』はまだ“原初の迷宮”を模索するような印象が強い。 この二作を続けて遊ぶと、竹内氏の3D空間への挑戦の軌跡を体感できる。
★2. オリオン80
(日本ソフトバンク/1982年末発売/価格:6,500円) PC-6001向けに発売された竹内あきらの初期代表作。 宇宙を舞台にした探索型アクションであり、視点や雰囲気の面で『イリーガス』に通じる部分がある。 特に、制限時間やエネルギー管理などの概念がすでに導入されており、“リソースと恐怖のバランス”を重視する設計思想が芽生えていた。 グラフィックは粗いが、音の演出と心理的緊張感の構築は後の『イリーガス』の原型といえる。 当時のレビューでは「不親切だが中毒性がある」と評され、竹内氏の作家性を示す最初の一歩となった。
★3. ポートピア連続殺人事件
(エニックス/1983年/価格:7,800円) 堀井雄二が手掛けた国産アドベンチャーゲームの金字塔。 コマンド入力方式を採用し、“物語を読み進めるゲーム”という新たなジャンルを確立した。 『イリーガス Episode IV』と比較すると、こちらはストーリー重視の“会話型探索”であり、同時期の日本PCゲームが「抽象的探索」から「物語的探索」へと移行する過程にあったことを示している。 どちらも“人間の知覚と判断”をテーマにしている点は共通しており、方向性の違う二人の作者が、異なる角度から“思考する遊び”を提示していた。
★4. ザ・キャッスル
(マイクロキャビン/1983年/価格:6,800円) MSXを代表するアクションパズルの一つ。 プレイヤーは城内を探索し、鍵を集めて姫を救出する。滑らかなスクロールと高い難易度で人気を博した。 『イリーガス Episode IV』の迷宮が“閉じた恐怖”を描いているのに対し、『ザ・キャッスル』は“挑戦的な思考パズル”として明るい方向性を示している。 両作はジャンルこそ違えど、迷宮という構造を舞台にした精神的挑戦という共通点を持っていた。 この作品の成功が、MSXにおける「迷宮探索系ゲームの流行」を後押ししたとも言われている。
★5. ハイドライド
(T&Eソフト/1984年/価格:7,800円) 『イリーガス』の翌年に登場し、日本RPGの黎明期を象徴する作品。 敵を直接体当たりで倒す独特のシステムと、フィールドとダンジョンの融合構造が話題となった。 『イリーガス』が“孤独なサバイバル”を描いたのに対し、『ハイドライド』は“世界を救う冒険”という英雄譚を描く。 この時期、ゲームは“個人の生存”から“社会的使命”へとテーマが広がっており、その転換点に『イリーガス Episode IV』は位置していた。 言い換えれば、『イリーガス』はヒーロー物語の前夜を象徴する作品だったのだ。
★6. ドアドア
(エニックス/1983年/価格:6,800円) 中村光一のデビュー作であり、後の『ドラゴンクエスト』チームの原点。 キャラクターの可愛らしさとユーモラスな操作性が人気を呼んだ。 『イリーガス』が極端に無機質な世界観を採用したのに対し、『ドアドア』は親しみやすさと操作直感性を重視した正反対の設計。 両者の対比は、1980年代初期の日本ゲームが“抽象芸術的表現”と“娯楽的快楽”の両極へ分岐していったことを象徴している。 竹内あきらと中村光一――同世代ながら異なる哲学を持つ二人の作品は、日本ゲーム史における表現の多様性の原点でもある。
★7. スペースマンボウ
(KONAMI/1983年/価格:7,000円) MSX初期の代表的シューティングゲーム。 滑らかなスクロールと重厚なサウンドでMSXの限界を超えたと評された。 『イリーガス』が探索と心理的緊張をテーマにしているのに対し、『スペースマンボウ』は動的反射神経とビジュアルインパクトで勝負している。 同じハードウェア上で、静と動、恐怖と快感という両極の体験が並立していたことは、当時のMSX文化の奥深さを示している。
★8. ナイト・ロア
(ウルティマソフト/1983年/価格:海外版 $39.95) イギリス製の等角視点アクションアドベンチャー。日本でもマニア層に輸入された。 陰影のついた立体表現と、昼夜の変化によるプレイフィールの変化が話題となり、『イリーガス Episode IV』の“時間経過システム”と同様のアイデアを先駆的に示していた。 この偶然の一致は、同時代的な発想の共鳴を感じさせる。 日本の竹内氏と英国のアルティメイト社、遠く離れた二つの開発環境で、同じテーマが同時に追求されていたのだ。
★9. ザナドゥ
(日本ファルコム/1985年/価格:7,800円) 『イリーガス』の2年後に登場し、日本PCゲーム界を席巻したアクションRPG。 システム面ではまったく異なるが、閉鎖空間での探索、限られたリソース、緊張感ある音楽など、精神的な系譜は繋がっている。 『イリーガス』が個人の孤独を描いたのに対し、『ザナドゥ』は社会構造を含む冒険譚へと発展した。 この2作品を比較すると、日本ゲームが“内省の体験”から“外的冒険”へ進化していく過程を感じ取ることができる。
★10. スペランカー
(アイレム/1983年/価格:6,800円) 洞窟探索アクションの金字塔。極端な難易度で知られ、当時のプレイヤーを恐怖させた。 『イリーガス Episode IV』とは異なるジャンルながら、“一歩のミスが命取りになる緊張感”という点で通じ合う。 どちらも“死”を軽く扱わず、プレイヤーに生き延びる価値を実感させるデザインであった。 この年、日本のゲーム開発者たちは“死と再挑戦”を通じてプレイヤーの精神に訴える表現を模索していたのである。
◇ 総評 ― “1983年という創造の爆心地”
1983年のゲーム界は、アクション、アドベンチャー、迷宮探索、そしてRPGの原型が一気に花開いた時代だった。 その中で『イリーガス Episode IV』は、どのジャンルにも分類しがたい“知覚実験作品”として独自の立ち位置を占めていた。 他のゲームが“物語”や“ルール”を明示する中で、本作はあえて何も語らず、プレイヤーに感じさせることを選んだ。 この姿勢は、現代のインディーゲームやアートゲームの原型とも言える。 『イリーガス Episode IV』は、時代に埋もれながらも確実に“後の表現者たちに影響を与えた”静かな革新作であった。
[game-8]![MSX-BASICでゲームを作ろう 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる [ 山田 直樹 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8904/9784297148904_1_33.jpg?_ex=128x128)