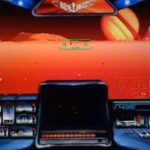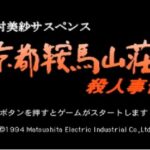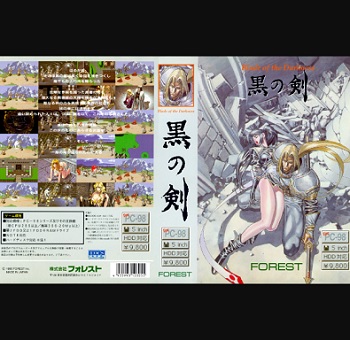【中古】プレイディアソフト ウルトラマンパワード 怪獣撃滅作戦
【発売】:バンダイ
【発売日】:1994年3月20日
【ジャンル】:格闘ゲーム
■ 概要
1994年3月20日、家庭用ゲーム機市場において新世代の波として注目されていた「3DO REAL」のローンチと同時に、バンダイが送り出したタイトルが『ウルトラマンパワード』である。本作は、特撮ヒーロー作品の代名詞である「ウルトラマン」シリーズを題材にした格闘アクションゲームであり、特に海外で制作された実写ドラマ『Ultraman: The Ultimate Hero』(日本での放映タイトルは『ウルトラマンパワード』)をベースとしている点が大きな特徴だった。これにより、従来の円谷プロ制作の日本版ウルトラシリーズとは一線を画す独特の映像美や演出を家庭用ゲーム機で体感できるようになったのである。
当時の3DOは、CD-ROMを媒体に採用したことで従来のROMカートリッジ機とは比べものにならない大容量を誇り、実写映像や高音質音源を収録できるのが強みとされていた。本作はまさにそのポテンシャルを示す作品で、ステージ冒頭や幕間に挿入される実写ムービー、オープニング主題歌のフル収録、そして実写取り込みによるキャラクターグラフィックといった「新時代の映像表現」が前面に押し出されている。これによりプレイヤーは、従来のドット絵では再現しきれなかったリアリティあるウルトラマンや怪獣の姿を操作するという体験を味わうことができた。
ゲームモードは大きく分けて4種類が用意されている。まず「VISUAL MODE」では、原作ドラマの1話から3話を再構築したストーリーモードを体験できる。ウルトラマンパワードがバルタン星人やケムラー、レッドキングといった怪獣たちと対峙し、ステージ開始前と終了後に実写ムービーが挿入されることで、テレビドラマを操作する感覚を楽しめるのだ。次に「BATTLE MODE」では、ウルトラマンパワードを操作して全8ステージを順にクリアしていくアーケードライクな形式が採用されている。このモードでは対戦の合間に一人称視点のVTOL(ストライクビートル)シューティングパートが追加されており、怪獣に先制ダメージを与えてから本格的な格闘戦に突入できる。プレイヤーは緊張感のあるシューティングを経て、そのまま巨大ヒーローのアクションへ移行する流れを体感することになる。
また「VS MODE」では、1Pがウルトラマンパワード、2Pが怪獣を操作する対戦が可能だ。演出上の都合により怪獣同士の対戦は不可能で、常に片方はウルトラマンを操作する仕様となっているが、友人との対戦プレイでは臨場感のあるバトルを楽しめた。そして「DATA BASE」では、原作のスチール写真や資料画像を閲覧できるというファンサービス的要素が盛り込まれていた。これは当時、放送自体の視聴環境が限られていた『ウルトラマンパワード』を補完する意味合いもあり、ファンにとっては貴重なコレクション機能であった。
システム面では、従来のSFC版『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』に近い2D格闘アクションを踏襲しつつ、新たな要素が加えられている。代表的なのは「防御」動作の導入、敵の必殺ゲージを吸収する「挑発」、そしてコマンド入力による必殺技発動である。特に必殺光線である「メガ・スペシウム光線」を放つには、ゲージを最大まで溜め、一定時間維持する必要がある。条件を満たすと画面上部のカラータイマー周囲に配置された8つのランプ、通称「みなぎりメーター」が点滅し、光線発動の合図となる。従来作品では体力を0にした後、必殺技でとどめを刺す必要があったが、本作では体力を削りきると自動的にフィニッシュ演出が発生するように改良され、テンポが向上した。
登場する怪獣たちも多彩である。バルタン星人やケムラー、レッドキング、ジャミラ、ゴモラといったシリーズを代表する存在に加え、オリジナル要素として「バルタン星人II」が最終ステージに登場する。このあたりは原作の放送が完結する前にゲームが発売されたため、終盤に登場するドラコやゼットンといった怪獣を収録できなかった事情がある。その代替措置として用意されたのがバルタン星人IIであり、シリーズファンの間では「幻のラスボス」として語られることも少なくない。
『ウルトラマンパワード』が特筆すべきなのは、原作のアクション表現とゲーム内アクションが乖離していた点を逆手に取り、「本来見たかった格闘戦」を実現していることだ。原作ドラマはアメリカのテレビ規制の影響で格闘表現が制限され、押し合いや組み合い主体の戦闘描写が多かった。しかし本作ではパンチやキック、投げ技といった肉弾戦が存分に描かれ、怪獣を豪快に叩きつけるといった“日本のウルトラマン的”アクションを体感できる。その意味で、本作は原作を補完するどころか、新たな価値を与えるメディアミックス展開となっていた。
総じて『ウルトラマンパワード』は、3DOの技術力を示すデモンストレーション的役割と、ファンのコレクション欲を満たす資料性、さらに「理想のパワード像」を実現するアクションゲーム性を兼ね備えた作品だった。1994年当時、約5万本を売り上げたという数字は、3DOの国内普及台数を考えれば決して小さなものではなく、ローンチタイトルとしては大きな存在感を示したと言えるだろう。今なお3DOというマイナー機のライブラリにおいて、『ウルトラマンパワード』は「唯一のウルトラマンゲーム」という肩書きと共に、コレクターやファンの記憶に強く刻まれている。
■■■■ ゲームの魅力とは?
『ウルトラマンパワード』の魅力は、一言でまとめると「原作では描けなかった理想のアクションを、自らの手で体験できること」に尽きる。特撮番組『ウルトラマンパワード』は、アメリカで制作された作品ゆえに放送規制の影響を強く受け、格闘描写は押し合いや組み合い中心で、日本のウルトラシリーズに馴染みのあるファンからは物足りなさを指摘されていた。だが、このゲームではそれらの制約を完全に取り払ったかのように、ウルトラマンがパンチやキックで怪獣を圧倒し、豪快に投げ飛ばし、必殺光線を叩き込むといった「本来期待されていた戦い」を存分に楽しめる。原作にあった不満点を逆手にとり、ゲームだからこそ可能になった爽快さを前面に押し出した点が、まず最大の魅力である。
さらに特筆すべきは、実写取り込みグラフィックの迫力だ。当時の家庭用ゲーム機でここまでリアルな質感のウルトラマンと怪獣を操作できる作品は他になく、3DOというハードの特性を最大限に生かした「画面の説得力」がプレイヤーを惹きつけた。光線技の発射時には画面全体を覆うエフェクトと重低音の効果音が鳴り響き、テレビの中で見ていたヒーローの力を自分の指先から解き放つ感覚を与えてくれる。投げ技で怪獣を叩きつける際の重量感あるモーションも見事で、「特撮では見られなかった動きをゲームで実現する」というメディアミックスの理想形がここにあったと言える。
また、各モードのバリエーションも魅力を高めている。ストーリーを追体験できる「VISUAL MODE」は、原作映像を要所に挿入することで「自分が物語に参加している」という没入感を演出している。単なるアクションゲームに留まらず、作品世界の一部を自らの操作で切り開く感覚は、ファンにとって格別だった。一方で「BATTLE MODE」ではアーケードライクな連戦形式が楽しめ、シューティングと格闘が組み合わさったユニークなゲーム体験を味わえる。そして「VS MODE」は友人同士の対戦で盛り上がれる要素として機能し、パーティーゲーム的な楽しさをも提供していた。最後に「DATA BASE」は、当時視聴環境の限られていた『ウルトラマンパワード』を補完する貴重な資料集であり、ファンの所有欲を満たす役割を果たしていた。
音楽面も忘れてはならない魅力だ。3DOの大容量CD-ROMにより、テレビ放送で使用されたオープニング主題歌をフル収録することが可能となった。従来のROMカートリッジでは実現が難しかった“歌入り楽曲”をゲーム内で聴けるという体験は、プレイヤーに強い印象を与えた。さらに、パンチやキックの打撃音、怪獣の咆哮、光線が放たれるまでのチャージ音といったサウンドエフェクトは臨場感たっぷりで、映像と相まって本当に特撮の世界に飛び込んだかのような錯覚を覚えさせてくれる。
もう一つ注目したい魅力は「挑発」というシステムだ。敵のゲージを吸収するこのアクションは、従来のシリーズにはなかった駆け引きを生み出している。単に攻撃を叩き込むだけでなく、「いつ挑発を挟んでゲージを有利にするか」という心理戦が、対戦ゲームとしての奥深さを生んでいた。特に対人戦では、この挑発の使いどころが勝敗を大きく左右することもあり、単なるキャラクターゲームを超えた戦略性を楽しめた。
そして、何よりも『ウルトラマンパワード』の魅力を支えているのは「ファン心理への応答」である。原作のアクションが物足りなかった、あるいはもっと迫力ある戦いを見たい——そうした思いに応えるように、本作ではウルトラマンが怪獣を投げ飛ばし、力強い格闘を繰り広げる。そのギャップは、原作に親しんでいたファンにとって「こうあってほしかった」という理想像であり、それを自分の手で実現できるという事実が、長く記憶に残る魅力となった。
また、ゲームとしての完成度は決して洗練されていたわけではない。操作レスポンスや当たり判定に粗さがあったり、対戦仕様の制約があったりする。しかし、それすらも「1990年代半ばの技術が挑んだ限界の成果」として受け止められ、むしろ時代を象徴する味わいとして記憶されている。3DOというプラットフォーム自体が短命で終わったこともあり、『ウルトラマンパワード』は「唯一のウルトラマンゲーム」という特別な立ち位置を持ち続け、ゲーム史的にも稀少価値を帯びている。
総合すると、『ウルトラマンパワード』の魅力は「映像・音響・資料性・アクション性」の4点が融合した体験にある。映像は実写取り込みでリアルさを追求し、音響はCDならではの豪華さで盛り上げ、資料性はファンの知識欲を満たし、アクション性は原作を超える迫力を実現した。これらが一体となって、単なるキャラクターゲームでは終わらない、「ウルトラマンファンの理想を叶える一本」として強く存在感を放っているのである。
■■■■ ゲームの攻略など
『ウルトラマンパワード』を遊ぶ際、まず理解しておきたいのは「システムの特性」と「各怪獣のクセを見極めること」である。本作は単なるボタン連打のアクションではなく、ガードや挑発、ゲージ管理といった要素を把握しないと先に進めない難度設計になっている。特に「VISUAL MODE」や「BATTLE MODE」の中盤以降は、相手の攻撃力や耐久力が一気に上がり、ただ力押しでは突破できない。ここでは、システムの基本攻略から、各ステージごとの対策、さらに隠し要素や裏技的な楽しみ方までを掘り下げてみたい。
● 攻略の基盤 ― システムを理解する
本作の最大の特徴は「ゲージ管理」と「防御・挑発の駆け引き」である。プレイヤーは攻撃を当てたり時間経過でゲージを蓄積し、満タン状態を一定時間維持することで「メガ・スペシウム光線」を放つことができる。しかしこの条件が非常に厳しい。しゃがみガードをするだけでゲージが減ってしまうため、防御を多用すると光線発動が遠のく。よって「必要最小限のガード」と「安全な距離取り」が重要になる。
また、挑発によって相手のゲージを吸収できる点は戦略性を大きく変えている。リスクを承知で挑発を挟むか、それとも堅実に立ち回るか——状況判断が問われるのだ。特に対人戦では、この挑発の成功が勝敗を決定づける場面も多く、上級者同士の戦いでは心理戦の比重が大きくなる。
● VTOLシューティングのコツ
「VISUAL MODE」と「BATTLE MODE」では、ウルトラマンに変身する前にストライクビートルを操作するシューティングパートが挿入される。ここで怪獣に与えたダメージは、そのまま格闘戦に持ち越されるため、攻略を有利に進めるための大切な要素となる。
攻略の基本は「撃墜されるまで粘る」こと。照準を大きく振り回さず、細かい動きで怪獣の体をなぞるように攻撃を続ければ、効率よくダメージを稼げる。撃墜自体は避けられないが、可能な限り長く粘ることで、本戦での怪獣の体力を大幅に削った状態から始められる。これは特に中盤以降の強敵(レッドキングやダダなど)相手に重要な布石となる。
● 各怪獣攻略のポイント
バルタン星人(序盤)
最初の壁だが、動きは緩慢で攻撃力も控えめ。ここでは操作に慣れつつ、挑発や光線発動の練習を行うのがよい。投げを積極的に狙ってリズムを掴もう。
ケムラー
背丈が低く、立ちキックがスカりやすい。低い姿勢で潜り込んでくるため、しゃがみ攻撃や投げを中心に組み立てるのが安全。遠距離からの不用意な攻撃は控えよう。
レッドキング
火力が非常に高く、被弾すると一気に体力を削られる。無理に攻めず、ガードと差し返しを意識すること。起き上がりに飛び込みを重ねるのは危険で、堅実な立ち回りが求められる。
テレスドン
地中に潜り込む動作を持ち、回避性能が高い。姿を現した瞬間に中距離攻撃を置いて潰すのが定石。飛び道具のような光線を安易に狙うと空振りしやすい。
ダダ
本作屈指の強敵。無敵の突進技や鋭い対空を持ち、飛び込みはほぼ封じられる。ゲージを温存しつつ、確定状況での反撃を狙うしかない。焦らず持久戦に持ち込もう。
ジャミラ
動きは緩やかだが、攻撃のリーチが長い。距離を取って戦うと不利なので、密着して投げや打撃で畳みかけたい。原作の悲哀を感じさせるキャラクターだが、攻略面では油断大敵。
ゴモラ
重量級の動きと高い耐久力を誇る。投げ後の追撃が狙いやすいため、組み付きからの連携を重点的に練習すると良い。光線を狙うならダウン直後がチャンス。
バルタン星人II(ラスボス)
グラフィックこそ初期バルタンの流用だが、行動パターンは強化されており手強い。突進攻撃を的確にガードし、反撃を差し込むこと。ここまでに光線の扱いに慣れていれば勝機は見える。
● メガ・スペシウム光線の使いどころ
本作の象徴的な必殺技である「メガ・スペシウム光線」は、発動条件が厳しく、実戦で決めるには相応の工夫が必要となる。おすすめは「敵がダウンした直後」や「突進技をガードさせた後」の硬直に合わせること。発生が遅いため、生半可な場面では潰されてしまうが、決まれば敵の体力を半分近く削る威力を誇る。プレイヤーの腕が問われる大技だが、それだけに成功した際の爽快感は格別だ。
● 隠し要素・裏技
当時のゲーム誌などで紹介された小ネタとして、1Pと2Pのキャラクターを入れ替える隠しコマンドがある。これにより、ウルトラマンを2P側が使用することが可能になるが、怪獣同士の対戦は不可能という仕様は最後まで変わらない。また、DATA BASEに収録されたスチール写真は、ファンの間で「これを見るためだけでも買う価値がある」と語られるほどで、実質的な“裏のご褒美”とも言える要素であった。
● 攻略全体のまとめ
『ウルトラマンパワード』は、単なるキャラゲーに収まらず「学習と工夫」が必要なゲーム設計がなされている。序盤はシンプルな攻撃で勝てるが、中盤以降はゲージ管理、挑発の駆け引き、VTOLでの先制ダメージ蓄積など、あらゆる要素を駆使しなければ突破できない。高難度ゆえに子供の頃に挫折したプレイヤーも多いが、逆に言えばクリアできたときの達成感は非常に大きく、今なお語り草となっている。難しさと爽快さ、その両方が本作の醍醐味であり、攻略を突き詰める過程そのものが一つの魅力となっているのだ。
■■■■ 感想や評判
『ウルトラマンパワード』(3DO用ソフト/1994年3月20日発売)は、発売当時から今日に至るまで、さまざまな角度から評価されてきたタイトルである。その評判を整理してみると、大きく「映像・演出に対する称賛」と「ゲームバランスや仕様に対する厳しい意見」、そして「コレクターズアイテムとしての価値」という三本柱に分けられるだろう。以下では、当時のプレイヤーや雑誌媒体、さらには現代のレトロゲーム愛好家の声を交えつつ、その評価を掘り下げてみたい。
● 発売当時の熱狂と期待
1994年春、3DOが日本に上陸した際、バンダイがローンチに合わせて投入した『ウルトラマンパワード』は、多くのファンにとって「新時代のウルトラゲーム」として強い注目を集めた。当時のゲーム雑誌では「実写取り込みのキャラクターが動く新鮮さ」「原作映像をそのまま見られる豪華さ」が大きく取り上げられ、3DOの可能性を示すショーケース的タイトルとして位置づけられていた。特に誌面レビューでは「グラフィックは家庭用としては突出」「ムービー挿入でまるでビデオを操作しているよう」と評され、映像面のインパクトに関してはほぼ満場一致で高評価だった。
一方で、アクションゲームとしての出来については当時から賛否が分かれていた。操作レスポンスがやや重く、光線技の発動条件が厳しい点は早くも問題点として指摘されており、「見た目は派手だが遊びやすさは今一歩」という評価も散見された。
● プレイヤーの声 ― 原作ファンの感動
実際に本作を手にしたウルトラマンファンからは、「原作では物足りなかった格闘シーンを自分で体験できる」という点に強い支持が集まった。『ウルトラマンパワード』はハリウッド制作ゆえに、原作ドラマの戦闘シーンが規制で地味だったことが知られている。ところがゲーム版ではパンチやキック、投げ技といった豪快なアクションを繰り出せるため、「これこそ本来のパワードだ」と感じたプレイヤーも多かった。
あるファンは当時の雑誌投稿欄で「テレビでは押し合うばかりだったパワードが、ゲームでは力強く戦ってくれる。自分の手で“本物の格闘”をさせられるのが嬉しい」と語っている。つまり、ゲームが原作を補完し、むしろ原作を越える“理想像”を提供していたのである。
● ゲームとしての難易度に対する意見
しかし一方で、難易度の高さに挫折したプレイヤーも少なくなかった。特に「ダダ」の強さは当時から悪名高く、無敵突進技や鋭い対空技に阻まれてクリアできないという声が続出した。実際、VISUAL MODEには9回という多めのコンティニュー回数が用意されていたが、それでも突破できず途中で投げ出すプレイヤーも多かったようだ。
ゲーム誌のレビューでも「見ごたえはあるが、子どもが気軽に楽しめる難易度ではない」「ファン向けの一本」といった評が見られ、万人向けというよりは熱心なウルトラファンやアクションゲーム上級者に向けたタイトルと位置づけられていた。
● 対戦モードの制約に対する批判
もう一つの評判の分かれ目は「VS MODE」にあった。対戦自体は可能だが、必ず1Pがウルトラマン、2Pが怪獣を操作する仕様であり、怪獣同士の対戦やウルトラマン同士の対戦は不可能だった。この制約はファンの間で不満点として取り沙汰され、「なぜ自由に選べないのか」「怪獣対怪獣の夢の対戦をやりたかった」という声が多く上がった。
中には「隠しコマンドで2Pがウルトラマンを使えるのは面白いが、それだけでは物足りない」と評する意見もあり、対戦アクションとしての評価を下げる要因になっていた。
● メディアによる評価の温度差
雑誌レビューでは、映像表現やファンサービス性を重視するメディアは好意的な論調を示したが、純粋にゲーム性を軸に採点する媒体では点数が伸び悩む傾向があった。例えばある雑誌では「グラフィック90点、サウンド85点、操作性60点、総合70点」といったように、視覚・聴覚面は高評価だが操作性やゲームバランスで減点される、といったパターンが多かった。
これにより、「ウルトラファンには強く推せるが、アクションゲーム好きに勧めるのは難しい」という微妙な立ち位置に落ち着いていったのである。
● 現代のレトロゲーマーからの再評価
2020年代に入り、レトロゲーム愛好家やYouTube配信者が本作を取り上げることが増え、再評価の流れも生まれている。特に「実写取り込みグラフィック」の出来は、今見ても独特の魅力があり、当時の挑戦的な試みとして高く評価されるようになった。また、3DOという短命ハードにおける数少ない有名タイトルという希少性も相まって、「マニア向けのコレクション価値が高い一本」として注目を集めている。
一方で、実際にプレイしてみると操作レスポンスの鈍さやバランスの厳しさに戸惑う人も多く、「見る分には面白いが、遊ぶには根気がいる」という意見も根強い。つまり、映像資料的価値とゲーム的価値が乖離している点は、現代においても評価の分かれ目となっているのだ。
● 総合的な感想
まとめると、『ウルトラマンパワード』の感想や評判は「ファン向けの強烈な体験」であると同時に「ゲームとしては粗削り」という二面性に集約される。ファンにとっては、原作で見られなかった格闘アクションを補完してくれる夢のような存在であり、資料的価値も兼ね備えた宝物だ。一方で、ゲーム性だけを求めるプレイヤーにとっては、難しすぎる・自由度が低い・操作が重いといった欠点が前に出やすい。
この二極化した評価こそが、本作のユニークな位置づけを際立たせている。つまり『ウルトラマンパワード』は「万人受けする作品」ではないが、「理解あるファンにとっては唯一無二の名作」なのである。その特殊性が、発売から30年近く経った今なお語り継がれる理由と言えるだろう。
■■■■ 良かったところ
『ウルトラマンパワード』(3DO/1994年)の「良かったところ」は、単なるキャラクターゲームとしての域を超え、当時の家庭用ゲームの新しい表現手法やファンサービスを先鋭的に提示した点にある。ここでは、その魅力的な側面を一つひとつ掘り下げていく。
● 1. 実写取り込みの迫力あるグラフィック
最も大きな評価点は、やはり実写取り込みグラフィックである。ウルトラマンや怪獣たちの姿が、ドット絵ではなく実写の質感を残したままゲーム内で動く――この体験は、当時のプレイヤーに強烈なインパクトを与えた。レッドキングの分厚い肉体、ダダの異様なシルエット、バルタン星人の鋏の質感など、テレビで見たままの存在感が家庭用ハードの画面に再現されていたのである。
従来のスーパーファミコン版『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』はドット絵で表現されていたが、本作では質感が一気にリアルに。これにより「怪獣と真正面から戦っている」感覚が増し、没入感が飛躍的に高まった。
● 2. ムービーと操作が融合した演出
ステージの合間に挿入されるムービーも、ファンにとって大きな喜びだった。ウルトラマンへの変身シーン(通称「ぐんぐんカット」)や、原作映像を編集した導入ムービーは、単なる観賞映像ではなく、ゲームプレイを盛り上げる“物語のフック”として機能していた。
たとえば、VISUAL MODEではムービーでストーリーを見せた後、実際に自分の操作で怪獣と戦う流れになる。この「映像で見せて、操作で体感させる」構成は、当時としては非常に画期的で、プレイヤーは「映像の中に自分が入り込んだ」ような感覚を味わうことができた。
● 3. CD-ROMならではの豪華な音響
もう一つの大きな評価点は音響面である。本作では3DOのCD-ROMの特性を活かし、テレビ放送版のオープニング主題歌を収録していた。ゲームを起動して主題歌が流れるだけで「ウルトラマンの世界に入った」という高揚感を味わえるのは、当時のファンにとって特別な体験だった。
また、パンチやキックの打撃音、怪獣の咆哮、光線のチャージ音や発射音といった効果音も厚みがあり、画面の迫力をさらに補強していた。映像と音響が噛み合うことで、アクションの一つひとつに“重み”が生まれていたのである。
● 4. VTOLシューティングの導入
BATTLE MODEやVISUAL MODEで挿入されるVTOLシューティングは、一見すると小さな要素に思えるが、実はゲーム体験を大きく豊かにしていた。変身前に自らの操縦で怪獣にダメージを与え、その成果を本戦に引き継げるという設計は、プレイヤーに「自分が戦闘の全過程に関与している」という感覚を与えた。
この「事前攻撃→格闘戦」への流れは、単調になりがちな対戦格闘にメリハリを与え、ステージごとに緊張感を高めていた。特に子供たちにとっては「ウルトラマンになる前に地球防衛軍の一員として戦う」というロールプレイ要素を楽しめる点が魅力だった。
● 5. 資料性の高さ ― データベースモード
DATA BASEモードに収録されたスチール写真や資料画像は、当時のファンにとって非常に貴重なものだった。『ウルトラマンパワード』という作品自体、テレビ放送や映像ソフトの流通が限定的で、視聴機会が少なかった。そんな中で、ゲーム内で高品質のスチール写真を閲覧できるのは、ファンの知識欲やコレクション欲を強く満たした。
この資料性の高さは、ゲームプレイの合間に「所有する満足感」を生み出し、単なるアクションゲーム以上の意味を持たせていたと言える。
● 6. 原作では見られなかった“理想のアクション”
原作ドラマ『パワード』は、アメリカの規制により格闘表現が大きく制限され、ウルトラマンと怪獣が押し合うだけの戦闘シーンが多かった。しかしゲーム版では、ウルトラマンがパンチやキックを繰り出し、怪獣を豪快に投げ飛ばすことができる。ファンにとっては「これこそ自分の見たかった戦い」だった。
つまり、本作は原作の弱点を補完し、「理想のパワード像」を提示したのである。この点に関して、多くのファンが「ゲーム版の方がかっこいい」と感じたのも頷ける。
● 7. 難しさを克服した時の達成感
本作は難易度が高く、簡単にクリアできるゲームではなかった。だが、その分攻略に成功したときの達成感は格別である。特に中盤以降の強敵――ダダやレッドキングを突破できた時の喜びは、他のゲームでは得難い経験だった。
この「苦労してこそ報われる」という設計は、一部のプレイヤーには不満を呼んだが、やり込み派にとっては熱中できる要素となり、「何度も挑戦したくなる」動機づけになった。
● まとめ
『ウルトラマンパワード』の「良かったところ」を総合すると、
実写取り込みによるリアルなグラフィック
ムービーと操作が融合した没入感の高い演出
CD-ROMならではの豪華な音響
VTOLシューティングの新鮮さ
資料性の高さとコレクション的価値
原作を超える格闘アクションの実現
難易度を克服したときの達成感
これらが一体となり、単なるキャラクターゲームに留まらず、ウルトラマンファンにとって“夢を叶える一本”となった。欠点は多々あるものの、良かった点の輝きが強すぎて、それを補って余りある魅力を放っている。それこそが本作が今なお語られる理由であり、3DOという短命ハードの中で特別な存在として位置づけられる所以である。
■■■■ 悪かったところ
『ウルトラマンパワード』(3DO/1994年)は、映像面やファンサービスで高い評価を得た一方で、ゲームとしての完成度においては多くの課題を抱えていた。そのため、発売当時から「見た目は素晴らしいが遊びにくい」という評価が付きまとい、後年の再評価においても必ず言及される弱点となっている。ここでは、その“悪かったところ”をいくつかの観点から掘り下げていく。
● 1. 難易度の高さと不親切な設計
本作最大の問題点は、全体的に難易度が高すぎることである。特に中盤以降に登場するダダやレッドキング、終盤のバルタン星人IIは非常に手強く、初心者はもちろん、アクションゲームに慣れたプレイヤーでも何度もコンティニューを余儀なくされる。
VISUAL MODEではコンティニュー回数が9回と多めに設定されているが、それでも突破できないという声が当時のプレイヤーから相次いだ。BATTLE MODEでは3回しかコンティニューできない仕様のため、最後まで到達するのは至難の業だった。ゲーム全体に「子ども向けキャラクターゲーム」というより「やり込み派向けハードゲーム」としての側面が強く、万人に優しい作りではなかったのが大きな欠点である。
● 2. メガ・スペシウム光線の扱いにくさ
本作を象徴する必殺技「メガ・スペシウム光線」は、発動条件が非常に厳しい。ゲージを満タンにした状態を一定時間維持しなければならず、しかもしゃがみガードをするだけでゲージが減少する仕様のため、実戦で条件を満たすのは困難を極める。ようやく放てても発生が遅く、相手にガードされたり攻撃で潰されたりするケースが多かった。
必殺技であるにもかかわらず、実用性が低く「魅せ技」にとどまってしまった点は、多くのプレイヤーから不満が上がった。威力自体は高く直撃すれば大ダメージだが、その“リスクとリターンの釣り合い”が崩れていたのである。
● 3. 操作レスポンスの重さ
当時の3DOというハードの性能的制約や実写取り込み表現の影響もあり、操作レスポンスは軽快とは言い難い。ボタンを押してから技が出るまでに微妙な“溜め”があり、格闘アクションとしての爽快感を損なっていた。特に対戦モードではこの重さが顕著で、他社の同時期の格闘ゲーム(『ストリートファイターII』や『餓狼伝説』シリーズ)に慣れたプレイヤーからは「動きがもっさりしていて反応が鈍い」という意見が多かった。
つまり、本作は“映像作品としてのリアルさ”を優先したがゆえに、ゲームプレイの操作感が犠牲になってしまったのである。
● 4. VS MODEの制約
対戦モードは一見すると本作の目玉の一つだが、実際には制約が多すぎて不満を呼んだ。1P側は必ずウルトラマンを操作しなければならず、怪獣を自由に選んで戦うことができない。怪獣同士の夢の対決やウルトラマン同士の対戦ができない仕様は、多くのプレイヤーにとって大きな不満点だった。
隠しコマンドを使えば1Pと2Pを入れ替えることは可能だが、それでも「怪獣同士で戦わせたい」という要望には応えられなかった。せっかく多彩な怪獣が登場しているにもかかわらず、対戦で自由に遊べない点は大きな機会損失だったといえる。
● 5. 原作再現度の不十分さ
本作は原作を補完する形で制作されたが、細部を見ると再現度に物足りなさを感じる部分も多かった。代表的なのが「制限時間の誤差」である。ウルトラマンといえば3分間という制限が象徴的だが、本作では制限時間が2分に短縮されており、「ウルトラマンらしさ」を損なっていると感じたファンも少なくなかった。
また、開発・発売時期の関係で、終盤に登場する重要怪獣(パワード版ドラコやゼットン)が未収録となっている点も残念な部分だ。これらの怪獣は原作における盛り上がりの要所を担っていただけに、ファンから「なぜいないのか」と落胆の声が上がった。
● 6. ゲームバランスの粗さ
全体的にバランス調整が荒削りで、怪獣ごとの強さに大きな偏りがあった。特にダダの理不尽な強さは多くのプレイヤーにトラウマを残し、ゲーム誌でも「最大の壁」として取り上げられるほどだった。逆に一部の怪獣はパターン化すれば容易に倒せてしまい、バランスの極端さが目立った。
このアンバランスさは、アクションゲームとしての完成度を下げる要因となり、純粋なゲーム性を求める層からは低評価につながった。
● 7. 3DOというハードの限界
本作の問題点はソフト単体にとどまらず、3DOというプラットフォームの限界とも深く結びついていた。3DOは当時としては先進的なマシンだったが、普及台数が少なく、操作レスポンスやロード時間にも課題を抱えていた。そのため、『ウルトラマンパワード』がどれだけ魅力的でも、遊べる環境が限られ、普及面で大きなハンデを背負っていた。
また、他機種での移植も行われなかったため、3DOを所有していなければ触れることができなかった点も、ファンにとってはマイナス要素だった。
● まとめ
『ウルトラマンパワード』の悪かったところを総合すると、
難易度が高く不親切
必殺技が扱いにくい
操作レスポンスが重い
VSモードの自由度不足
原作再現の不完全さ
ゲームバランスの粗さ
3DOというハードの限界
といった問題点に集約される。これらの欠点が積み重なった結果、ゲームとしての完成度は「ファン向けに偏った作品」という評価に留まり、万人に広く受け入れられることはなかった。
しかし逆に言えば、この不完全さゆえに「時代の制約を背負った挑戦作」として強い印象を残し、今なお語り草となっている。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
『ウルトラマンパワード』(3DO/1994年)には、ウルトラマンパワード本体をはじめ、シリーズおなじみの怪獣や宇宙人が数多く登場する。いずれも原作を彩った印象的な存在であり、ゲームにおいても強烈な個性を発揮している。そのためプレイヤーごとに「このキャラが好き」「このキャラに苦しめられたけど思い出深い」といった推しが分かれるのも、本作の魅力の一つだろう。ここでは、それぞれのキャラクターを振り返りながら、なぜ多くの人に印象を残したのかを詳しく掘り下げていきたい。
● 主人公 ― ウルトラマンパワード
当然ながら、本作の中心はウルトラマンパワードその人である。原作ドラマではアメリカの規制もあり、激しい格闘を見せる機会が少なかったが、本作ではパンチ、キック、投げ、必殺光線といった「日本のウルトラマンらしい戦い」が思う存分楽しめる。プレイヤーは操作を通じて、ようやく“理想のパワード”を体感することができた。
また、ゲームにおけるウルトラマンパワードは、挑発によるゲージ吸収や、みなぎりメーターを光らせて撃つメガ・スペシウム光線といった特徴的なシステムを背負っている。こうした独自要素が「他のウルトラマンゲームとは違う特別な存在」という印象を強め、主人公キャラでありながらプレイヤーの「推し」として語られることが多い。
● バルタン星人
ウルトラマンシリーズの顔役とも言えるバルタン星人は、本作でも第一ステージから登場し、早くも存在感を放っている。実写取り込みによって再現された鋏の光沢、独特の甲高い声、あの印象的なポーズは、プレイヤーに「ついにバルタンと自分の手で戦える」という感慨を抱かせた。
また、BATTLE MODEのラスボスとして登場する「バルタン星人II」も印象的だ。オリジナルの追加要素として設定されたこのキャラクターは、原作には登場しないためファンの間では賛否両論があったが、「自分だけのバルタンを倒した」という体験を残しやすく、ゲームならではの特別感を演出していた。
● レッドキング
「怪獣使い」の代表格ともいえるレッドキングは、本作でも圧倒的な火力でプレイヤーを苦しめた。その攻撃力は群を抜いており、油断していると数発の打撃であっという間に体力を奪われる。攻略の観点では多くのプレイヤーを挫折させた壁であるが、その強さゆえに「倒せたときの達成感が大きい」として人気も高い。
また、実写取り込みの迫力はレッドキングの重量感を際立たせており、他の怪獣以上に“怪獣らしい怪獣”として記憶に残る。多くのプレイヤーが「一番印象に残っている敵」として名前を挙げる理由も納得だ。
● ダダ
『ウルトラマンパワード』における最凶の壁として語られるのがダダである。細身の人型怪獣でありながら、ゲームでは無敵突進や鋭い対空技を持ち、ノーマル難易度でも圧倒的な強さを誇った。プレイヤーからは「最強の敵キャラ」「ここで投げ出した」という声が多く、苦い思い出とともに語られることが多い。
しかし、その“理不尽さ”こそがダダの人気を高めた一因でもある。「あのダダに勝てた」という体験はプレイヤーの誇りとなり、結果的に“嫌いだけど忘れられないキャラ”から“むしろ好きなキャラ”へと印象が変化していった例も多い。
● ジャミラ
原作において悲劇的な存在として知られるジャミラも、本作に登場する。実写取り込みによって再現された不気味さと哀愁漂うビジュアルは、プレイヤーに強烈な印象を与えた。ゲームでは攻撃リーチが長く、間合い管理を誤ると苦戦させられる相手だが、倒すたびに原作の背景を思い出し「少し切ない気持ちになった」というプレイヤーも多かった。
そのため、単なる強敵という以上に“心に残るキャラクター”として挙げられることが多く、人気投票などでは必ず一定数の票を集める存在である。
● ゴモラ
怪獣王ゴモラは、重量級の動きと高い耐久力でプレイヤーを圧迫する。スピードはないが、一撃の重さと持久力でじわじわと追い詰めてくるため、「戦っていて緊張感があった」という声が多い。投げ後の追撃や光線との駆け引きなど、プレイヤーに攻略の工夫を強いる相手として評価されている。
また、ゴモラはシリーズ全体を通して人気の高い怪獣であり、ゲーム内での扱いもその人気を裏切らない出来だったことから、多くのプレイヤーに「お気に入りの敵」として記憶されている。
● テレスドン
地中からの潜行攻撃を持つテレスドンは、他の怪獣とは異なる“いやらしさ”を発揮する。地中に潜られると攻撃を空振りさせられやすく、初見のプレイヤーを混乱させる存在だった。攻略には冷静な対応が求められ、ゲームを通じて「敵の行動を読む大切さ」を学ばせるキャラとも言える。
印象的な派手さは少ないが、「攻略の緊張感をくれたキャラ」として根強い人気がある。
● ファンごとの“推し”の違い
興味深いのは、どのキャラクターが好きかがプレイヤーによって大きく異なる点だ。
「理不尽に強いからこそ、乗り越えた達成感が忘れられない」としてダダを推す人。
「豪快な火力で印象に残った」としてレッドキングを推す人。
「悲しい存在として心に刺さった」としてジャミラを推す人。
「やっぱりウルトラマンパワード自身が最高」と主人公を推す人。
このように、ゲーム体験そのものが“推しキャラ”を決める要因となっているのだ。
● まとめ
『ウルトラマンパワード』に登場するキャラクターたちは、単なる敵や味方の枠を超え、プレイヤー一人ひとりの記憶に強く刻まれる存在となった。ウルトラマンパワード自身の力強いアクション、バルタン星人の象徴性、レッドキングやダダの強烈な難敵ぶり、ジャミラの悲哀、ゴモラやテレスドンの重量感ある存在感――これらすべてが「自分にとっての一番」を生み出し、プレイヤーの心を掴んだのである。
本作のキャラクターは、単に“勝った/負けた”という記憶ではなく、戦いを通じて感じた緊張、達成感、切なさを含めて、プレイヤーの「好きなキャラ」として語られ続けている。それこそが『ウルトラマンパワード』のキャラクター表現の真価と言えるだろう。
[game-7]
■ 中古市場での現状
『ウルトラマンパワード』(3DO/1994年3月20日発売)は、現在においても3DOという短命ハードの存在感とあいまって、レトロゲーム市場では独自の立ち位置を占めている。販売本数は約5万本程度とされており、決して多い部類ではないが、当時の3DO普及台数を考えればむしろ健闘した方である。その希少性と、ウルトラマンという人気IPの組み合わせは、30年近く経った今もコレクターやファンの間で注目を集め続けている。ここでは、中古市場における取引傾向や価格帯、各販売チャネルの特徴を細かく整理してみたい。
● ヤフオク!での傾向
ヤフオク!では、3DOというマイナーハードのタイトルにもかかわらず、定期的に『ウルトラマンパワード』の出品が見られる。出品数自体は決して多くないが、根強い需要があるためウォッチリストに入れられるケースが多い。
価格帯はおおむね 4,000円~7,000円程度が中心。状態によって大きな差があり、ディスクのみや説明書欠品などの不完全品は4,000円前後で落ち着く一方、箱・説明書・帯が揃った完品は6,000円を超えることも多い。特に状態が良いものは競り合いが発生し、7,000円以上に跳ね上がる例もある。
また、未開封新品やほぼ新品に近い美品が出品されるケースは稀で、その場合は1万円を超える値付けがされることもある。3DOソフト全体の市場が狭いため、熱心なコレクターが入札に参加すると相場以上に跳ね上がるのも特徴だ。
● メルカリでの販売状況
フリマアプリ「メルカリ」でも、『ウルトラマンパワード』は不定期に出品される。こちらはオークション形式ではなく即決価格であるため、売り手の価格設定に大きく左右される。
相場は 5,000円~8,000円程度が主流。ヤフオク!よりやや高めに設定される傾向があるが、その分「即購入可」「送料無料」といった条件が揃うとすぐに売れてしまうことが多い。特に「動作確認済み」「付属品完備」と記されたものは人気が高く、数日以内に取引が成立するケースが多い。
一方で、ディスクにキズがあるものやケース破損品は4,000円前後に値下げされるが、それでも「希少性」を理由に数週間以内には売り切れる傾向がある。
● Amazonマーケットプレイスでの価格
Amazonマーケットプレイスでは、専門ショップや個人出品者による販売が見られる。ここでは価格帯がやや強気に設定されることが多く、 7,000円~1万円前後が中心となっている。
Amazonでは「プライム対応」や「返品可」といった安心感が付加価値となり、相場より高くても購入されやすい。コレクターやライトユーザーが「確実に手に入れたい」と考えた場合、多少の割高感があってもAmazonを選ぶケースが多い。
● 楽天市場での取り扱い
楽天市場では、レトロゲーム専門店が出品していることが多く、価格帯は 6,000円~9,000円程度に集中している。ショップ出品ゆえに商品状態の説明が丁寧で、写真や保証が充実している分、個人出品よりやや高めの価格設定になりやすい。
楽天市場を利用する購入者は「多少高くても安心できるショップから買いたい」という層が中心であり、その意味で信頼性と希少性を兼ね備えた取引の場となっている。
● 駿河屋での販売状況
中古ゲームの大手ショップ「駿河屋」でも、『ウルトラマンパワード』は取り扱われている。相場は 5,500円~7,500円前後と比較的安定しており、在庫がある場合は比較的買いやすい価格で入手できる。ただし人気商品であるため、在庫切れになることも少なくなく、入荷待ちの状態が続くこともしばしばだ。
駿河屋の強みは「商品状態ランク」が明確に提示される点で、コンディションを重視するコレクターから支持されている。
● 中古市場全体の特徴
総じて言えるのは、『ウルトラマンパワード』は 3DOというプラットフォームの中ではトップクラスに人気が高いタイトルだということだ。ウルトラマンという知名度の高さ、実写取り込みという話題性、そして「3DO唯一のウルトラマンゲーム」という希少性が相まって、常に一定の需要が存在している。
状態による価格差も顕著で、
ディスクのみ … 3,500円~4,500円前後
箱・説明書あり … 5,000円~6,500円前後
完品美品 … 7,000円~1万円
未開封新品 … 1万円以上
という階層が形成されている。
● コレクターズアイテムとしての価値
『ウルトラマンパワード』は、単なる中古ソフトというより「コレクターズアイテム」としての価値が強い。ウルトラマンファンにとっては「唯一の3DOタイトル」という特別感があり、ゲーム内容以上に「所有していること」自体に意味があるのだ。実際、SNSなどでは「3DOを手放した後も『ウルトラマンパワード』だけは残している」というコレクターの声も見られる。
また、1990年代前半という時代性もプレミア性を高めている。当時は家庭用ゲーム機の世代交代期であり、3DOのような挑戦的ハードは短命に終わった。その中で発売された本作は「失われた時代の遺産」として、歴史的な価値も帯びているのだ。
● まとめ
『ウルトラマンパワード』の中古市場での現状をまとめると、
取引価格はおおむね 5,000円~1万円前後で推移
完品・美品は高値安定、未開封はプレミア価格
ヤフオク!は競り合いで相場以上に跳ねやすい
メルカリは即売れ傾向が強く、出品数は少なめ
Amazonや楽天は高めだが安心感を重視する層に人気
駿河屋は安定した価格だが在庫切れが頻発
という特徴がある。
つまり本作は、ゲームの出来そのもの以上に「希少性」と「ウルトラマンブランド」によって市場価値を維持しているタイトルであり、今後もコレクター需要が途切れることはないだろう。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
【中古】Switch なりキッズパーク ウルトラマンR/B
【中古】 ウルトラマン Fighting Evolution Rebirth/PS2
【中古】 ウルトラマン Fighting Evolution 0 バンプレストベスト/PSP




 評価 5
評価 5



![【中古】【箱説明書なし】[SFC] ウルトラマン バンダイ (19910406)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005017.jpg?_ex=128x128)
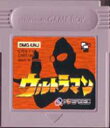
![【中古】[PS5] オーバーライド 2:スーパーメカリーグ ULTRAMAN DX Edition(ウルトラマン デラックスエディション) オーイズミ・アミュ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480065.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【箱説明書なし】[GB] ウルトラマン(ULTRAMAN) ベック (19911229)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/8/cg10188267.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【新品】【PS5】オーバーライド2:スーパーメカリーグ ULTRAMAN DX Edition [PS5版][お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10530000/10537753.jpg?_ex=128x128)