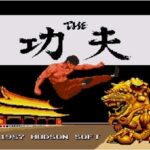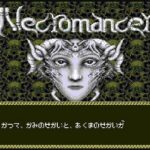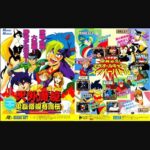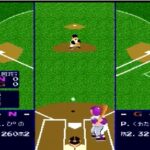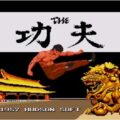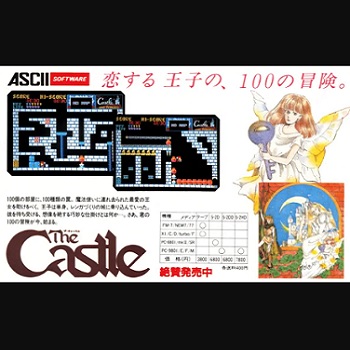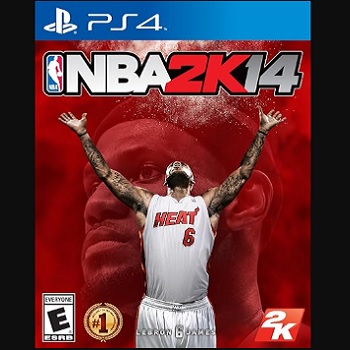【中古】カトちゃんケンちゃん 【PCエンジン】
【発売】:ハドソン
【開発】:ハドソン
【発売日】:1987年11月30日
【ジャンル】:アクションゲーム
■ 概要
1987年11月30日、PCエンジン初期ラインナップの勢いを象徴するかのように、ハドソンから放たれた横スクロールアクションが『カトちゃんケンちゃん』だ。題材は当時の国民的人気バラエティの探偵パロディ枠。プレイヤーは“カトちゃん”または“ケンちゃん”のどちらかを選び、誘拐事件の真相を追う探偵として、市街地、海岸、墓場、雪山、空中回廊、最終アジト…といったバラエティ豊かなロケーションを進む。ゲームの骨格は横移動・ジャンプ・体術のシンプルな三拍子だが、PCエンジンの描画力を活かした“顔だけリアルな二頭身”キャラ、大ぶりなスプライト、細やかな表情差分によって、テレビで見知った二人の“やり取り”を画面上で再現しているのが最大の個性だ。
操作感は二人のフィーリング差で味が分かれる。足場に強く長めの跳躍で刻む“カトちゃん”、最高速と反発が鋭い“ケンちゃん”。選ばなかった相棒はときに助け、ときに邪魔をする“半NPC”として登場し、画面外から空き缶を落としたり、場面転換の寸劇でヒントを飛ばしたりと、探索のテンポをお笑い的に崩しながらも進行のフラグを匂わせる。この“茶化し”が、ただの横スクにミニコントの“間”を付与している。
ルール面では、残機+ライフゲージの併用が特徴。敵接触やタイマーで徐々に体力が削られる一方、オブジェクト(消火栓、ゴミ箱、街路樹など)をキックしてコインや食べ物を引き出せば回復ができる。攻撃は接近戦のキック、踏みつけ、そして“しゃがみ続けて放つ”コミカルなガス攻撃の三系統。どれも万能ではないため、敵種や足場構成に応じて使い分けが求められる。ボスにはキックのみ有効、といった限定条件もあり、ボス戦は間合い管理と着地硬直の処理がカギを握る。
構成は“6フィールド × 各4エリア”を基本単位に、エリア3どこかに隠された“鍵”でボス部屋の扉を開ける仕組み。鍵を取り逃すと進行できないが、巻き戻しワープが用意され、理不尽な詰みには陥らないデザインだ。もっとも、マップには順ワープと逆ワープ、罠付きスプリングなど“知らなければ痛い目を見る”仕掛けが多数潜む。フィールドの合間に差し込まれるスロット式ボーナス(コイン消費でライフ・残機・コインの増減)も、先の難所に備える駆け引きとして効いている。
難度の手触りは“覚えゲー寄りのテクニカル”。等速で歩ける最序盤こそ間口は広いが、足場が狭く敵配置がイヤらしくなる中盤以降は、滑りやすい地形やリフト間の距離、焚き火や落穴の“一発死”トラップが圧を増す。反面、出現パターンは固定で、練習すれば確実に上達の手応えが返るタイプ。タイムラインを詰め、どこでコインを稼ぎ、どのオブジェクトを蹴れば足場が出るか――段取りを体に覚え込ませると、道が拓ける。
演出面は“テレビ的メタ”が随所に顔を出す。相棒の仮装ネタ、変顔ダッシュ、天から降る大量の小道具、無敵化時の某小道具風所作など、視覚ギャグがゲームプレイと地続きになるよう仕込まれており、クリア後の“種明かし”で小道具の正体(ワイヤーで吊っている、素材がゴム等)を示すに至っては、番組の“舞台裏ジョーク”の延長線だ。BGMは軽妙なコント調から、哀愁のメロディ、ボス前の緊張感まで幅広く、画面の密度に負けない存在感でシーンを牽引する。
総じて、『カトちゃんケンちゃん』はタレント起用の話題性に甘えず、探索仕掛け・演出・難度設計を一体化させた“強度のある横スク”。PCエンジンの大きなキャラと色数を前面に押し出しつつ、テレビ的ユーモアを制御したゲーム文法に落としている点が、今でも語り草になる理由だ。初見には厳しいが、覚えと操作精度が噛み合った瞬間の“スルリと抜ける快感”は、同時代機の名作群と肩を並べる。
■■■■ ゲームの魅力とは?
『カトちゃんケンちゃん』の魅力を語るうえで外せないのは、「芸能人キャラクターゲーム」でありながら、しっかりと“遊べる作品”に仕上がっていた点だ。当時、人気タレントやアニメキャラを題材としたゲームは少なくなかったが、どれもファンアイテム的色合いが濃く、ゲーム部分が粗削りなケースが多かった。しかし本作は、バラエティ的なユーモアを組み込みつつも、横スクロールアクションとしての基盤を極めて堅実に作り込み、PCエンジンの性能を最大限に引き出したところが支持を集めた。
まず目を引くのがグラフィック表現のインパクトだ。顔の再現度は驚くほどリアルで、表情がコントの一場面のように変化する。その一方で身体は二頭身にデフォルメされており、そのアンバランスさが逆にコミカルな味わいを演出する。敵キャラや背景の描き込みも緻密で、ビル街の看板や墓場の墓石、海辺の波しぶきなど、細部に遊び心が散りばめられていた。アーケード移植ではなくオリジナルタイトルで、ここまで大きなキャラを滑らかに動かせる点は、当時の家庭用機として大きな衝撃だった。
次に挙げたいのがユーモアとゲーム性の融合である。しゃがみ続けると繰り出せる「おなら攻撃」、相棒が時にはお助け役、時にはお邪魔キャラとして乱入してくる仕掛け、無敵アイテムの演出に仕込まれたコント小道具。これらは単なるお笑い要素にとどまらず、プレイヤーが“ゲームとして使えるギミック”として組み込まれていた。例えばおなら攻撃は、背後から迫る敵への有効な手段として成立しており、笑えるだけでなく攻略の幅を広げている。つまりギャグと実用性を同時に体験させる設計になっていたのだ。
さらにフィールド構成の多彩さも魅力のひとつ。単調な横スクロールではなく、ステージ内に隠されたワープポイント、スロットマシン形式のボーナスゲーム、相棒が現れる寸劇などが織り込まれ、プレイヤーを飽きさせない。ときに理不尽とも思える罠や逆ワープもあるが、それも含めて「何が起こるかわからないドタバタ感」が本作ならではの空気を作っていた。探索心と好奇心が自然と掻き立てられる構造で、発見の喜びを与えてくれる。
そして忘れてはならないのが音楽の完成度だ。作曲を手掛けた国本剛章によるBGMは、コミカルな軽快さとシリアスさの緩急が巧みに切り替わる。とくに序盤の明るい曲から、ステージが進むごとに哀愁や緊張感が高まっていく構成は、まるでドラマの演出のようにプレイヤーの心を掴む。また、やられたときのとぼけたジングルが、ドリフ的な“コントのオチ”を連想させ、遊びの世界観を強化している点もユニークだ。
総合すると、『カトちゃんケンちゃん』の魅力は「テレビ的な笑い」と「ゲーム的な歯ごたえ」の絶妙なブレンドにある。芸能人ゲームという色物枠に収まらず、笑いながらも真剣に遊べる本格派のアクションゲーム――この二面性こそが、当時のプレイヤーに強い印象を残し、PCエンジンの代表作の一角に数えられる理由である。
■■■■ ゲームの攻略など
『カトちゃんケンちゃん』は、見た目のコミカルさに反してかなりの難易度を誇るアクションゲームだ。攻略を進めるにあたっては、まず基本操作やキャラクター特性を理解することが不可欠になる。ここではキャラクターごとの違いから、序盤・中盤・終盤のポイント、隠し要素や裏技までを体系的に整理してみよう。
キャラクター選択のコツ
ゲーム開始時に選べるのはカトちゃんかケンちゃん。両者は見た目だけでなく、操作感にも差がある。
カトちゃんは滑りにくく、安定した操作が可能。そのぶん移動スピードは遅いが、ジャンプの滞空時間が長く、狭い足場やトゲトゲ配置に対応しやすい。初心者向けともいえる安定型だ。
ケンちゃんは逆にスピードが速く、ジャンプの飛び出しが鋭い。ただし滑りやすいため、リフトや氷のステージでは操作精度が問われる。慣れたプレイヤーにはスピーディーで爽快感のあるキャラだ。
攻略に行き詰まる人の多くはキャラ選びから見直すことで突破口を見いだせる。
攻撃方法の活用
敵への攻撃は主に「キック」「ジャンプ踏み」「おなら攻撃」の3種類。
キックは最も基本的だが、リーチが短い。ボス戦ではキックが唯一の有効打になるため、間合い管理を習得しておく必要がある。
ジャンプ踏みは複数の敵を連鎖で倒すことができ、コイン稼ぎや進行ルートの確保に便利。特に浮遊敵が多いステージでは有効だ。
おなら攻撃は一見ギャグだが、背後から迫る敵を一掃できるので緊急回避に重宝する。狭い通路や墓場ステージで特に役立つ。
ステージ攻略の要点
序盤(1~2面)
チュートリアル的役割を持ちながらも、すでにワープや隠しアイテムが散りばめられている。ここでオブジェクトを蹴って回復やコインを稼ぐ習慣を身につけると後半が楽になる。
中盤(3~4面)
敵配置がいやらしくなり、リフト間移動や逆ワープなどが増える。特にフィールド3以降は「鍵」を取り逃さないことが最大のポイントだ。ボーナスゲームでライフや残機を増やしながら進めたい。
終盤(5~6面)
足場の狭さや焚き火、飛び道具を持つ敵など、理不尽に思える仕掛けが目白押し。最終エリアでは“鍵がなくても進める裏技ルート”も存在するが、それを知らないと延々探索することになる。ボス戦は大男ばかりだが、パターンを覚えれば勝機はある。
ワープと隠し要素
各フィールドにはワープポイントがあり、ショートカットも可能。ただし「逆ワープ」や「罠ワープ」も仕込まれているので、安易に飛び込むと1-1に戻されるケースもある。これを逆に利用して、ライフ稼ぎやアイテム回収を繰り返すプレイヤーもいた。
また、街灯や木を蹴ることで“ハチ助”という1UPキャラが出現するなど、探せば探すほど仕掛けが発見できる。墓場ステージでは“墓石を蹴ると鍵が出る”という大胆な仕組みもあり、当時のプレイヤーを驚かせた。
ボーナスゲームの活用
スロットマシンはコインを使って挑戦できるお楽しみ要素。大当たりを出せばライフや残機を一気に増やせるため、安定クリアを目指すなら積極的に活用したい。ただし欲をかきすぎるとコインが尽き、逆に詰むこともあるのでバランスが肝心だ。
裏技・小ネタ
当時のゲーム雑誌や裏技本で紹介された小ネタも多い。例えば「一定の条件で特定のステージにスキップできるワープ」や、「相棒キャラが普段と違うコスプレを見せる隠し演出」など。こうした要素を探す楽しみも本作ならではだった。
総じて本作の攻略は「地形のクセを覚える」「相棒の妨害や仕掛けを読み切る」「ライフと残機をコインで管理する」この三点に尽きる。笑いに包まれながらも、緻密なルート攻略を積み重ねる達成感は、当時のアクションゲーマーに強烈な印象を残した。
■■■■ 感想や評判
『カトちゃんケンちゃん』が発売された1987年当時、PCエンジンそのものがまだ登場したばかりの新ハードだった。だからこそ、この作品はハードの知名度を押し上げる“広告塔”的な存在となり、多くのプレイヤーやメディアから注目を浴びた。
当時のプレイヤーの声
発売直後の反応で特に多かったのは、グラフィックのインパクトに対する驚きだ。家庭用ゲームで、テレビに映るコント芸人の顔がそのままゲーム内に再現されていることは衝撃的で、少年誌や口コミでも「まるでテレビ番組がゲームになったようだ」と話題になった。
一方で、プレイを重ねるうちに明らかになったのは難易度の高さ。序盤は楽しく進めるが、中盤以降の罠配置や敵ラッシュに苦戦し、投げ出してしまった人も少なくなかった。しかしそれでも「理不尽ではなく、パターンを覚えれば確実に突破できる」と語る熟練プレイヤーも多く、結果的に“やり込みゲー”としての評価を獲得していった。
ゲーム雑誌での評価
当時のファミ通やマル勝PCエンジンといった雑誌では、グラフィック表現や演出のユーモラスさが高く評価された。特に「顔がリアルすぎて笑える」「二頭身キャラとリアルな表情のアンバランスさがクセになる」といったコメントが目立つ。
ただし難易度の点では賛否が分かれた。レビュー欄では「初心者には厳しい」「PCエンジンを手にしたばかりのライトユーザーは面食らう」といった意見もある一方、「ゲーマーを自認するなら挑戦して損はない」と高評価する声もあり、全体として“実力派向け”という位置付けがなされていた。
コミカル演出への反響
プレイヤーや視聴者からは、ゲーム内で再現されたドリフ的なギャグ演出が好評だった。特に相棒キャラが妨害に来たときの変顔や、おなら攻撃、仮装イベントなどは、単なるおふざけではなく「番組を知っているとさらに笑える」要素として楽しめた。番組を知らない世代にとっても、純粋にシュールで愉快な要素として機能していた。
後年の再評価
時代が進むと、本作は「タレントゲーム=駄作」という一般的なイメージに反して、しっかり遊べる良作として再評価されるようになった。特にPCエンジンの名作を振り返る記事や動画では、「初心者お断りの高難度」「番組ネタ満載の演出」「クセになるBGM」といった特徴が再び注目を浴び、レトロゲーマーの間で語り草となっている。
また、海外版(『J.J. & Jeff』)では大幅にローカライズされ、一部の下品なギャグがカットされたことから、日本版の独自性が強調され、今ではコレクターズアイテム的な価値も高まっている。
総合的な評価
まとめると、当時の『カトちゃんケンちゃん』は「とにかく難しいが、挑戦する価値のあるゲーム」という位置付けだった。そして年月を経た今では、PCエンジン初期を代表する一本として、ファンの間で愛され続けている。芸能人を題材にした“色物作品”の枠を超え、本格アクションとして成立している点が評価を押し上げた最大の要因といえるだろう。
■■■■ 良かったところ
『カトちゃんケンちゃん』の評価を支えたのは、単なるタレントゲームに終わらず、プレイヤーが「これは遊び応えのある一本だ」と実感できる長所がいくつも備わっていた点にある。ここでは、その“良かったところ”を大きく分けて紹介していこう。
1. PCエンジンの性能を存分に発揮したグラフィック
まず最初に挙げられるのは、当時の家庭用ゲームとしては圧倒的にリアルだったキャラクターグラフィックだ。顔の表情が細かく描き分けられ、しかも状況に応じてコミカルに変化する。番組ファンはもちろん、知らない人でも「ここまで顔が似ているのか」と驚きをもって受け止めた。PCエンジンの“高解像度・多色表示”の強みを見事に体現したソフトといえる。
2. コミカルと実用性が融合した演出
「おなら攻撃」や「相棒の妨害イベント」といったギャグ要素は、単なる笑いのためだけではなく、ゲーム攻略にも絡んでくる。プレイヤーは思わず笑いつつも、それが戦略として機能する。お助けイベントで得られるヒントや仮装演出も、ファンをニヤリとさせながら進行をサポートしており、笑いと遊びの両立が実現されていた。
3. バリエーション豊かなステージ構成
街、海、墓場、雪山、空中、そして敵アジト――各フィールドは雰囲気がガラリと変わり、常に新鮮な挑戦が待ち受ける。隠しワープや逆ワープ、スロットマシンなど、バラエティ性に富んだ仕掛けは飽きさせず、「次はどんなステージだろう」とワクワクさせてくれる。
4. 攻略性の高さとやり込み要素
一度では突破できないような罠や配置も、何度も挑戦するうちにパターンを覚えて克服できる作りになっている。運要素が少なく、純粋にプレイヤーの腕前や学習によってクリアできるバランスは、当時のゲーマーに“やりごたえ”を強く感じさせた。高難度でありながら理不尽さは少なく、達成感の大きさが好評につながった。
5. 音楽の完成度
国本剛章によるBGMは、場面ごとに雰囲気が切り替わり、ゲーム体験を盛り上げる。特に1-2の哀愁漂うメロディや、やられたときのとぼけたジングルは強烈に印象に残る。軽妙なギャグ演出と音楽が相互作用し、独自の世界観を築いていた点はプレイヤーから高く評価された。
6. ファンに嬉しいネタの数々
「加トちゃんペッ!」「バカ殿様」といった番組でお馴染みのキャラクターがゲーム内で見られるのも大きな魅力だった。当時の視聴者にとってはテレビとの架け橋のようであり、ファンアイテムとしての価値も十分に兼ね備えていた。
総合的な評価
こうした要素が積み重なり、『カトちゃんケンちゃん』は「タレントゲームなのに遊べる」どころか「タレントゲームだからこそ楽しい」という好意的な評価を得た。番組ファンにとってはお笑いの延長線上で楽しめ、ゲーマーにとっては攻略の歯ごたえを存分に味わえる。結果として、当時のPCエンジンユーザーにとって“買って損のない一本”と記憶される存在になったのだ。
■■■■ 悪かったところ
『カトちゃんケンちゃん』は総合的には高評価を得ていたが、全てのプレイヤーにとって快適だったわけではない。むしろ、そのユニークさや挑戦的な作りが裏目に出て、「ここはちょっときつい」と感じる部分も多かった。以下に具体的な“悪かったところ”を掘り下げてみよう。
1. 難易度の高さ
最も多く指摘されたのが、全体的な難易度の高さだ。序盤は楽しく進めるものの、中盤以降は敵の出現数や配置がいやらしく、足場の狭さや焚き火などの即死トラップも相まって、クリアに至るまでには相当の根気が必要だった。特にライトユーザーや番組ファンが“タレントゲーだから軽いノリで遊べるだろう”と手にした場合、あまりの難しさに挫折してしまうケースも少なくなかった。
2. 操作性の癖
カトちゃんとケンちゃんの操作感の違いは魅力でもあったが、逆に「どちらを選んでも動かしにくい」と感じる人もいた。特に滑りやすい挙動やジャンプの慣性は、慣れるまでに時間がかかる。足場移動が多いゲーム性と相まって、ストレス要因となることがあった。
3. 妨害イベントの煩わしさ
相棒キャラが妨害に登場する仕組みはユーモアとしては面白いが、シリアスに攻略を目指すプレイヤーからするとテンポを崩される要素として不満を呼んだ。「敵に集中しているときに頭上から物を落とされる」「変顔で画面が乱れる」など、理不尽と感じられる瞬間も多かった。
4. ネタの下品さ
本作の演出はお笑い番組のノリを反映しているため、「おなら攻撃」や「排泄物に関する敵キャラ」など、下品すぎると受け止めるプレイヤーもいた。子供が親の前で遊ぶと微妙な空気になるといった声もあり、万人向けとは言いがたい部分だった。
5. ボスの単調さ
各エリアのボスは“大男の色違い”というパターンで、バリエーションに乏しい。雑魚敵やステージギミックは多彩なだけに、「ボスだけは手抜き感がある」と評されることもあった。もう少し個性を出していれば、盛り上がりに一層厚みが出ただろう。
6. 不親切なワープ構造
ワープ装置は探索の醍醐味でもあったが、逆ワープや罠ワープが多く、知らずに飛び込むと延々戻されることもある。説明不足のまま進めると「クリアさせる気があるのか」と苛立つプレイヤーもいた。これは攻略本や友達との情報交換が前提の時代だったからこそ成立していた仕様ともいえる。
総合的に見て
こうした“悪かったところ”は、難易度設計や演出を優先した結果とも言える。開発陣は「ゲーマーなら乗り越えられる」と想定していたが、結果的に番組ファンのライト層を突き放してしまったのは否めない。それでも「理不尽さと紙一重の挑戦的バランス」がゲームの個性を形作っており、ここを愛せるかどうかで評価が大きく分かれる一本となった。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
『カトちゃんケンちゃん』は、芸能人を題材にしたゲームという性質上、主人公の二人が大きな注目を浴びるのは当然だが、実際にプレイしたユーザーの記憶に残ったのは、それだけではなかった。ここでは多彩なキャラクターの中から、特に人気や愛着を持たれた存在を紹介していこう。
1. 主人公・カトちゃん
滑りにくい安定型の性能を持つカトちゃんは、初心者プレイヤーにとって頼れる存在だった。ジャンプの滞空時間が長く、足場移動に強い点から「一番扱いやすいキャラ」として支持された。
さらに特徴的だったのは、顔グラフィックの表情。攻撃を食らったときの変顔や、相棒へのツッコミのような仕草など、実際の加藤茶を彷彿とさせる演出が多く、ファンからは「テレビそのまま」と高評価だった。
2. 主人公・ケンちゃん
スピードとジャンプ力に優れたケンちゃんは、アクションに慣れたプレイヤーに人気があった。操作難度は高いが、その分スピーディーに駆け抜けられたときの爽快感は格別。
また、ケンちゃんが妨害役に回ったときのコミカルさも好評で、仮装姿や悪戯っぽい表情に「むしろ邪魔しに来るケンちゃんの方が好き」という声すらあった。
3. 相棒(妨害/お助け役)としての存在感
本作独自の魅力として語られるのが、「選ばれなかった方の主人公」がゲーム中に干渉してくる仕組みだ。邪魔をしてくることも多いが、その演出がシュールで笑えるため、嫌われるどころか逆に愛される存在となった。特に「空き缶を頭上から落とす」や「パラシュートで降りてくる」といった突飛な登場シーンは、今でも印象に残る名場面として語られている。
4. 敵キャラクターたち
『カトちゃんケンちゃん』の敵は、ただの障害物ではなくユーモアにあふれていた。
ハッシー(首の長い恐竜):一見巨大に見えるが、実は体が小さいというギャップで人気。火を吐くパターンもあり、攻略の壁でありながら愛嬌のある存在だった。
ウ○コ系の敵:下品ではあるものの、当時の子供にはインパクト抜群で「バカっぽくて好き」と語られることが多かった。
雷様にそっくりの敵:高木ブーを思わせる姿に、ドリフファンはニヤリとした。
こうした敵たちは「番組的ノリ」をそのままゲームに落とし込んだ存在であり、単なるやられ役以上の記憶を残している。
5. 特殊演出キャラクター
ゲーム中に見られる仮装や演出で登場する“お助けキャラ”も人気が高い。加トちゃんの「加トちゃんペッ!」や、ケンちゃんの「バカ殿様」など、番組でお馴染みのネタを拾った演出は、ファンにとって嬉しいサプライズだった。これらは攻略には直接関係ないものの、「見られると得した気分になる」と好意的に受け止められていた。
総合的に見て
『カトちゃんケンちゃん』は、主人公二人だけでなく、敵やお助けキャラまで含めて“キャラ立ち”が非常に強いゲームだった。プレイヤーごとに「自分はカトちゃん派」「ケンちゃん派」といった好みが分かれ、さらに「ハッシーが好き」「妨害してくるケンちゃんがむしろ愛しい」といった声も多く、登場人物全体が話題性を持っていた。ゲームがただのアクションに留まらず、コント的なキャラ劇場になっていたことが、強い印象を残したのだ。
[game-7]
■ 中古市場での現状
1987年に発売された『カトちゃんケンちゃん』は、PCエンジン初期の代表作でありながら、今なお中古市場で根強い人気を保っている。芸能人キャラを題材としたゲームは時代を経ると注目度が下がりがちだが、本作はPCエンジンの歴史を語るうえで外せない一本として、コレクターやレトロゲーマーの間で高い需要がある。以下では、主要な取引プラットフォームごとに現状を見ていこう。
★ ヤフオク!での取引価格
ヤフオク!では『カトちゃんケンちゃん』は比較的コンスタントに出品されている。
相場帯は2,500円~4,000円前後が中心。状態によって価格が大きく変動する。
箱や説明書が揃った美品は入札が集まりやすく、即決で4,000円以上になることも珍しくない。
説明書欠品やラベルの色あせなどがある場合は2,000円台前半からスタートする傾向。
ごく稀に未開封品や新品同様の状態で出品されることもあり、その際は1万円近い値段がつくこともある。
★ メルカリでの販売状況
フリマアプリ「メルカリ」では、出品から売却までの回転が早く、相場はヤフオクよりやや安め。
主な取引価格帯は2,000円~3,200円程度。
状態が良く「箱・説明書付き・動作確認済み」と記載されている商品は2,800円前後で短期間に売れる傾向がある。
動作未確認や箱なし品は2,000円前後に落ち着くケースが多い。
出品者によっては人気ネタを強調した写真を載せ、ファン需要を狙うケースも見られる。
★ Amazonマーケットプレイスでの販売価格
Amazonでは中古ゲームショップが出品していることが多く、価格帯はやや高めに設定されがち。
目立つのは3,500円~5,000円前後での販売。
「動作保証あり」や「Amazon倉庫発送」の商品は安心感があるため、多少高値でも売れやすい。
プレミア扱いされることもあり、特に外箱や付属品が揃った美品は上限5,000円台で安定している。
★ 楽天市場での取り扱い状況
楽天市場では、レトロゲーム専門店や中古販売業者が出品。
販売価格帯は3,000円~4,500円程度が多い。
楽天ポイントを活用できる分、多少割高でも購入する層がいるため、安定して在庫が回転している。
★ 駿河屋での販売状況
中古ゲーム大手の駿河屋でも取り扱いがあり、安定した価格で推移している。
在庫ありの場合は2,800円~3,800円程度で提示されるケースが多い。
人気タイトルのためタイミングによっては在庫切れになることもあり、入荷通知を設定するユーザーも多い。
状態ランク(可・良い・非常に良い)で価格が細かく変動し、コンディション説明が丁寧に記載されているのも特徴だ。
総合的に見た中古市場での位置付け
『カトちゃんケンちゃん』は、現在でも「PCエンジンを象徴するタレントゲーム」としてコレクター人気が高い。そのため、30年以上経った今でも安値では出回りにくい。美品や完品であれば4,000円前後が標準的な落札価格となり、未使用に近い品はプレミア価格になる傾向にある。
加えて、海外版『J.J. & Jeff』との比較需要や、ドリフファン・志村けんファンによる追悼的なコレクション需要もあり、値段が下がりにくい作品の一つといえるだろう。


![【中古】ハドソン カトちゃんケンちゃん PCエンジンHuカードソフト【取扱説明書・パッケージ傷みあり】[10]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/otakarasouko/cabinet/_448/1240010394782_1.jpg?_ex=128x128)