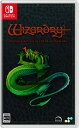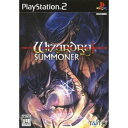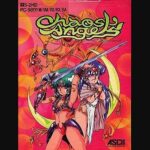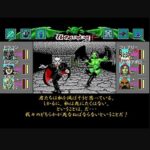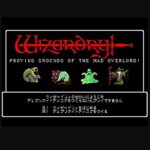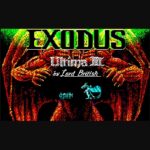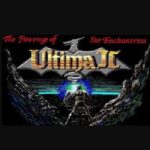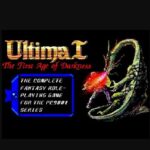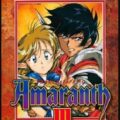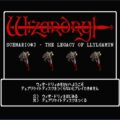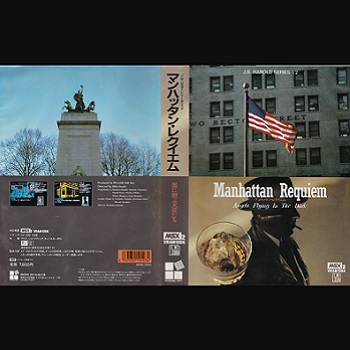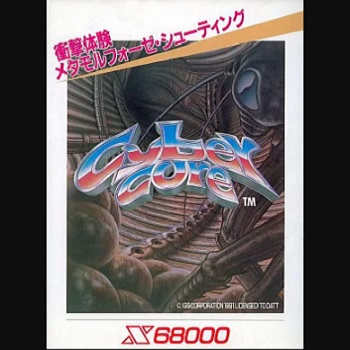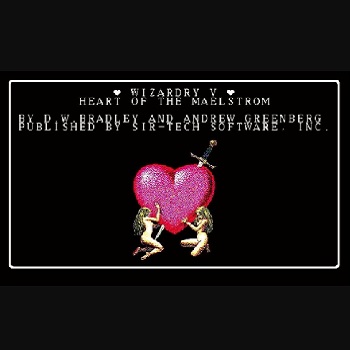
【中古】[PS] ウィザードリィVII ガーディアの宝珠(Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant) ソニー・コンピュータエンタテインメ..




 評価 5
評価 5【発売】:アスキー
【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、FM TOWNS
【発売日】:1991年
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
ウィザードリィVとはどんな作品か
アスキーが発売した『ウィザードリィV 災渦の中心(Heart of the Maelstrom)』は、PC-8801・PC-9801・FM TOWNSといった日本の主要パソコン向けに登場した本格的ダンジョンRPGである。もともとアメリカのSir-Tech社が1988年にApple IIやCommodore 64向けに開発したタイトルで、日本版はそれをアスキーが丁寧にローカライズしたものだ。『ウィザードリィIV ワードナの逆襲』に続くナンバリングタイトルであり、開発の主導はデイヴィッド・W・ブラッドリーによって行われた。彼の手による3作(V~VII)は後に「ブラッドリー三部作」と呼ばれ、シリーズに新風を吹き込んだ時期として知られている。
物語の舞台とテーマ
本作の舞台は「マエルストロム(Maelstrom)」と呼ばれる、秩序と混沌、火・水・風・土といった4つの自然の力が交錯する幻想世界である。プレイヤーは冒険者の一団を率い、かつて均衡を守っていた大魔術師ゲートキーパーを救出し、彼を囚えた邪悪な魔術師ソーンを討伐する旅に出る。単なる迷宮探索ではなく、世界の調和を取り戻すという壮大な神話的テーマを持ち、プレイヤーはその渦中に巻き込まれることとなる。
システム面での進化
ウィザードリィVは、シリーズの中でも特に大きな進化を遂げた作品だ。まず、戦闘システムには新たに「射程距離」の概念が導入され、前衛と後衛の区別がより明確化された。これにより、従来後衛から魔法しか使えなかったキャラクターが弓などの遠距離武器で攻撃可能となり、戦闘の幅が一気に広がった。また、盗賊や忍者が戦闘中に「隠れる」ことで奇襲攻撃を仕掛ける戦術も追加され、職業ごとの個性がより活きるバランスとなった。 さらに、ダンジョン内には水辺や池などの新要素が加えられ、「水泳」スキルが登場。水深によっては泳ぎ切れず溺れることもあり、探索時の緊張感を一層高めている。細部の改良として、レベルアップ可能なキャラクターにマークが付いたり、進行方向を示すコンパスが画面に追加されるなど、ユーザビリティの向上も図られている。
迷宮設計の刷新
これまでのシリーズでは、20×20の定型的な正方形ダンジョン構造が基本だった。しかし本作ではこの形式を脱却し、より複雑で立体的な構造を採用。単に「踏破」するだけではなく、各階層で出会うNPCたちとの会話やアイテムの入手がクリアの鍵を握る。迷宮内には謎めいた井戸や封印扉が点在し、冒険者の知識や観察力が試される仕掛けが多数用意されている。プレイヤーは単なる「探索者」ではなく、物語に介入する一人の「存在」として描かれている点が、シリーズ初期とは大きく異なる。
グラフィックと演出
グラフィック面ではワイヤーフレームによる3Dダンジョン表現を踏襲しつつ、敵キャラクターやイベントシーンのイラスト表示領域を拡大。PC-8801・9801版ではイラストレーターの末弥純が描く独特の重厚なモンスターが登場し、FM TOWNS版では幡池裕行らによる新たな彩色が加えられた。これらの違いは、同じ作品でありながら機種ごとに異なる美術的味わいを見せる要素となっている。音楽もまた印象的で、FM TOWNS版では作曲家・田中公平が担当し、オーケストラ調の旋律で幻想的な世界観を強化している。
登場キャラクターたち
物語の中心人物であるゲートキーパーは、三軸の門を守護する聖なる魔導師。世界を災厄から護る存在でありながら、弟子のソーンによって封印されるという悲劇に見舞われる。一方、ソーンは己の野心に溺れ、世界の理を歪めようとする裏切り者として描かれる。彼の存在は単なる悪ではなく、「創造と破壊」「自由と秩序」といったテーマの象徴でもあり、単純な勧善懲悪を超えた深みを物語に与えている。 また、冒険の途中で出会う多彩なNPCたちは、プレイヤーにとって単なる情報源ではなく、選択によって運命を左右する存在として機能する。彼らの言葉や行動は、プレイヤーの判断によって物語を異なる方向に導くため、1周目では見逃してしまう展開も多い。
ストーリー構成の特徴
本作の物語は、単なる「救出と討伐」ではなく、「調和の再生」を軸に展開する。ゲートキーパーが象徴する秩序と、ソーンがもたらす混沌。その狭間に立つ冒険者たちは、どちらの価値観にも属さず、自らの意思で均衡を取り戻そうとする。この構造は、プレイヤー自身が「神話の中の登場人物」であるかのような没入感を生み出している。 また、SF的要素も巧みに取り入れられており、時間停止装置や冷凍睡眠装置など、ファンタジーとテクノロジーが融合した不思議な雰囲気が漂う。これらの要素は、後の『ウィザードリィVII』へと連なるテーマ的伏線ともなっている。
日本版の展開と文化的影響
日本ではアスキーが移植を担当し、PC版のほかスーパーファミコン版(災渦の中心)としても人気を博した。SFC版では表現の規制により一部グラフィックが修正されたものの、遊びやすさが大幅に改善され、家庭用RPGユーザー層にも広く浸透した。また、PlayStation版『ニューエイジオブリルガミン』に収録されたリメイクでは3DCGによるモンスター描写が加わり、クラシックRPGの魅力を現代的な形で再現したことが評価されている。 この作品を通じて、「ダンジョン探索型RPG」というジャンルが日本のPC文化に根づき、後の国産RPG開発者たちに強い影響を与えた。例えば、『真・女神転生』や『世界樹の迷宮』といった作品群に見られる、重厚な世界観と戦略的戦闘システムの融合は、本作の思想を受け継いだものといえる。
総評
『ウィザードリィV』は、古典的RPGの形式を保ちながらも、物語性・戦略性・演出の三要素を高次元で融合させた名作である。シリーズを重ねるごとに進化してきた「ウィザードリィ」というフォーマットを、次の世代へと橋渡しした存在でもあり、その影響は現在のRPG文化にも脈々と息づいている。
■■■■ ゲームの魅力とは?
戦略性の深化と新たなシステムの魅力
『ウィザードリィV』の魅力を語る上でまず外せないのは、シリーズの伝統的な難度を維持しながらも、戦略性を格段に向上させた点である。従来の「前衛=攻撃」「後衛=支援」という固定的な構図を崩し、武器の射程という概念を導入することで、パーティ構成に柔軟さが生まれた。弓やクロスボウによって後衛でも直接攻撃が可能になり、これまで以上にプレイヤーの戦術的判断が重要になる。盗賊や忍者が戦闘中に“隠れる”ことで奇襲攻撃を仕掛ける要素も追加され、敵との戦闘は単なる力比べではなく、「どう動くか」を問う知的勝負に変化している。 さらに呪文体系も整理され、新しい魔法が追加されたことで戦闘のバリエーションは大幅に広がった。例えば、敵の行動を封じる、隊列を乱すといった戦術的魔法は、これまでにない緊張感を生む。プレイヤーは状況判断力を駆使し、仲間の特性を最大限に活かす必要がある。
探索の醍醐味を深めるダンジョン設計
本作のダンジョンは、単なる「迷宮」ではなく、物語世界そのものを体現する舞台として設計されている。水辺、井戸、隠し扉、複雑に入り組んだ階層構造――それぞれがプレイヤーの好奇心を刺激する仕掛けだ。水泳スキルの導入によって「水中を進む」「潜って新しいルートを見つける」といった立体的探索が可能となり、従来のシリーズにはなかった冒険感を生み出している。 また、各階層に配置されたNPCは単なる会話相手ではない。彼らはしばしばクエストの鍵を握り、選択肢次第で敵にも味方にもなりうる。NPCとの駆け引きは単調な探索に物語的厚みを与え、プレイヤーの想像力を刺激する。この「対話を通じて進む冒険」は、後のRPGが重視する“ストーリー主導型の探索”の先駆けといえる。
グラフィック表現と幻想的な世界観
『ウィザードリィV』は、シリーズ伝統のワイヤーフレーム型3Dダンジョンを踏襲しながら、ビジュアル面で飛躍的な進化を遂げた。敵キャラクターのイラストはより緻密になり、特にPC-8801・9801版では末弥純の手による重厚なデザインが世界観を支配している。魔物の一体一体が「禍々しくも神々しい存在」として描かれ、画面に現れるたびにプレイヤーは背筋を伸ばすことになる。 FM TOWNS版では、当時としては高解像度かつフルカラー表示に近いグラフィックで、幻想的な光彩を放つダンジョン空間を表現。光の反射や水のきらめきといった微細な演出は、従来の無機質な迷宮のイメージを一新させた。結果として、プレイヤーは単なる地図上の移動ではなく、まるで“異界を歩く”ような没入感を味わえる。
音楽とサウンドが生み出す緊張感
音楽面も本作の大きな魅力のひとつだ。FM音源による重厚な旋律は、ダンジョン探索時の緊張感を際立たせる。特にFM TOWNS版で音楽を担当した田中公平の楽曲は、クラシック的な和声とシンセサウンドを融合させ、ファンタジー世界に荘厳な空気を与えている。 一方、PC-9801版ではその音色の制限を逆手に取り、静寂と残響を巧みに使った構成となっている。効果音の一つひとつ――ドアの軋む音、罠が発動する瞬間の衝撃音、敵出現時の金属音――がプレイヤーの感覚を研ぎ澄ませ、音そのものが「恐怖の演出」として機能している。
ストーリーと神話性の融合
『ウィザードリィV』の物語は、単なる善と悪の対立を超えた“神話的世界”の再構築を目指している。ゲートキーパーとソーンという師弟の関係は、光と闇、秩序と混沌の対比を象徴しており、その葛藤が世界全体のバランス崩壊として顕現する。プレイヤーはその狭間で行動する存在として描かれ、選択の積み重ねによって自らの“信念”を問われる。 この構図は古典的RPGの枠を超え、哲学的な問いを内包している。「何が正義か」「均衡とは何か」というテーマは、プレイヤーに単なる攻略以上の体験を与え、プレイ後に深い余韻を残す。
プレイヤー体験としての“緊張と快感”
『ウィザードリィV』は難易度が高いことで知られるが、その厳しさこそがプレイヤーに“達成の快感”を与える。罠を解除できずに全滅したり、道を間違えて深層に迷い込むといった緊張感は、現代のオートセーブ中心のゲームでは味わえない。だが、だからこそ一歩一歩の進行が記憶に刻まれる。 特に、本作ではプレイヤーの選択と結果が密接に結びついており、攻略の自由度が高い。決まった順路が存在せず、NPCから得る情報や入手アイテムの順序によって進行が変化する。再プレイの価値が非常に高く、全貌を解き明かすには何度も迷宮に挑む必要がある。その「繰り返しの中で理解が深まる構造」こそ、ウィザードリィシリーズの真骨頂である。
日本のRPG文化に与えた影響
ウィザードリィVは、国内のPCユーザーに「本格派RPGの面白さ」を知らしめた作品でもある。戦略性・ストーリー性・難易度の三拍子が揃った構成は、後の日本製RPGの方向性に強い影響を与えた。特に「プレイヤーの想像力に委ねる語り方」や「ロールプレイ重視の設計思想」は、『真・女神転生』シリーズや『ダンジョンマスター』などに受け継がれている。 さらに、本作を通じてプレイヤーたちは“自分のパーティを自分の物語として育てる”という感覚を学んだ。これはゲームを単なる娯楽から“体験型物語”へと進化させる契機となり、以後のRPGに大きな転換点をもたらした。
まとめ:静かな狂気が生む中毒性
全体を通して、『ウィザードリィV』は派手な演出よりも静かな緊張感を重視している。ダンジョンの暗闇、NPCの不穏な言葉、そして理不尽とも思える試練――それらがプレイヤーを徐々に“中毒”にしていく。このゲームを最後までやり抜くためには、知恵と忍耐が必要だが、だからこそクリアした瞬間の喜びは計り知れない。 この「知的なストイックさ」と「冒険の手応え」が融合したバランスこそが、ウィザードリィVの最大の魅力であり、今なお古典RPGファンの心を掴んで離さない理由である。
■■■■ ゲームの攻略など
攻略の基本方針 ― 慎重さと計画性が鍵
『ウィザードリィV』の攻略は、無計画に突き進むプレイでは必ず行き詰まる。最初に心掛けたいのは、「準備こそが最大の防御」というシリーズ共通の鉄則である。冒険を始める前に、パーティ編成・職業バランス・魔法習得順を明確に計画しておくことが求められる。 おすすめの基本構成は、前衛に戦士系(ファイターやロード)2名、後衛に魔術師・僧侶・盗賊、そして万能型としてビショップを加える6人編成だ。ファイターは前線で盾となり、ビショップは鑑定と魔法の両面を支える。盗賊は宝箱の罠解除やドア開錠で必須の存在であり、彼がいなければ冒険そのものが立ち行かない場面も多い。 また、本作は罠の種類が非常に多彩で、解除に失敗すると一瞬で全滅することもある。頻繁に街に戻ってセーブを重ねながら探索するのが最も安全な進行法である。
序盤攻略 ― 慎重な探索と資金の確保
冒険のスタート地点となる「ブレシングの街」では、最初に装備を整えるための資金集めが重要になる。序盤は敵も比較的弱いが、油断すると毒攻撃や麻痺攻撃を受けるため、回復呪文やポーションを常備しておきたい。 序盤の効率的なレベル上げには、街近くの浅い階層でスライムやコボルドといった低ランクの敵を倒すのが基本。特に「ミニデーモン」など魔法を使う敵が出現する階層では、魔法耐性の低いキャラクターが一撃で倒される危険があるため、盾や防具の強化を早めに行うと良い。 また、序盤から“泉”や“井戸”といった水辺を探索することで、水泳スキルの成長も図れる。スイムレベルを上げておくと中盤以降の探索範囲が大きく広がるため、早い段階で意識して育てたい要素である。
中盤攻略 ― NPCとの会話がカギを握る
中盤以降、単純な戦闘だけでは先に進めない。迷宮内に散らばるNPCたちの存在が、攻略の分岐点となる。彼らは一見無関係な情報を語るが、その中に重要なヒントが隠されている。特に「鍵付き扉」「封印の間」「三軸の門」に関する情報は、物語進行と密接に関わるため、聞き逃してはならない。 NPCによっては、アイテムを要求したり、特定のモンスターを倒すことで態度を変える者もいる。そのため、対話の順序や選択肢によってストーリー展開が微妙に変化する点も見逃せない。ウィザードリィVでは「力押しで突破する」ことがほぼ不可能なため、会話ログを丁寧に記録しておくと後で助けになる。 また、この時期になると敵の呪文が強力化し、即死系や状態異常系の魔法が頻繁に飛んでくる。アンチマジックの呪文や魔除け装備を揃えることで、被害を最小限に抑える戦略が求められる。
終盤攻略 ― 災渦の中心へ
終盤では、「三軸の門」と呼ばれるエリアへの進入が最大の難関となる。ここは本作における最深層であり、迷宮の構造そのものがプレイヤーの心理を試すように設計されている。マップが複雑に入り組んでいるだけでなく、転送装置や隠し通路が多数存在し、方向感覚を失いやすい。 特に注意すべきは、敵の中でも屈指の強さを誇る「アークデーモン」「マリリス」「グレーターライカー」といった高位魔族だ。彼らは高い魔法抵抗と即死級の攻撃を併せ持ち、正面から挑むと全滅必至。事前に防御呪文を重ねがけし、弱点属性を突ける魔法を準備してから挑もう。 そして最終戦では、師ゲートキーパーを封印した張本人・ソーンとの戦いが待ち構えている。彼はあらゆる魔法を跳ね返す「魔法盾」を展開しており、通常の手段ではほとんどダメージを与えられない。特定のイベントアイテムを使用することで初めて防御を崩せる仕組みになっており、これを知らないと永遠に勝てないため、前段階の探索と情報収集が決定的に重要である。
効率的なレベルアップと資金稼ぎ
中盤以降のレベル上げには、「深層手前の強敵を狩る」よりも「安全に狩れる敵を繰り返す」戦略が有効だ。特に経験値効率の良いモンスターとして知られるのが「ミスリルスライム」や「シャドウゴースト」など。彼らは危険度も低めで、一定の金策にもなる。 また、宝箱の罠解除を繰り返すことで盗賊のスキルを効率的に上げられる点も見逃せない。失敗時のリスクはあるが、成功時には高額の宝石や希少武具が手に入るため、結果的に戦力の底上げにつながる。 街に戻っての鑑定は必ずビショップに任せ、呪われた装備はすぐに解除する癖を付けておくと良い。こうした「管理の細やかさ」こそが高難度RPGを生き抜く秘訣である。
裏技・小ネタ的な楽しみ方
ウィザードリィVには、プレイヤー間で語り継がれる“裏技”や“隠し仕様”も存在する。代表的なのは、NPCのセリフパターンを特定の順序で聞くと隠しイベントが発生するというもの。これは公式には明示されていないが、一部のキャラクターが通常と異なるリアクションを見せる場合がある。 また、アイテムの合成バグを利用した“無限ゴールド”技や、状態異常を利用して経験値を不正に獲得する方法などもファンの間で知られている。ただし、これらは本来の緊張感を損ねるため、初回プレイでは控えた方が良いだろう。 むしろ、正攻法で進めながら偶然こうした発見をした時の喜びこそ、本作の醍醐味といえる。
プレイヤーへの心理的挑戦
『ウィザードリィV』は単なるゲームではなく、「プレイヤーの精神力を測る試練」のような側面を持つ。理不尽なトラップ、突然の全滅、セーブ前に戻る絶望感――それらは現代のゲームでは稀有な体験だ。だが、同時にそこには強い没入感と達成感がある。 プレイヤーは幾度も失敗を重ねながら学び、少しずつ迷宮の構造を理解していく。その過程こそが“攻略”の真髄であり、すべての敗北が次の勝利への布石となる。ある意味でこのゲームは、現実世界の困難を乗り越える訓練のようでもあるのだ。
総括:攻略という名の自己探求
最終的に『ウィザードリィV』をクリアしたプレイヤーは、単なる勝利者ではなく、“知恵と忍耐で試練を克服した者”としての誇りを得る。迷宮を進む過程で、プレイヤーは自分の判断力・記憶力・忍耐力を試され続ける。 この作品における攻略とは、敵を倒すこと以上に「自分を知ること」に近い体験だ。思考し、恐れ、諦めず進む――その精神の積み重ねこそが本作の本質であり、ウィザードリィVが“最も人を育てるRPG”と評される理由でもある。
■■■■ 感想や評判
プレイヤーたちの第一印象 ― “原点回帰と革新の共存”
『ウィザードリィV』が登場した当時、シリーズファンの間では「再び本格派RPGが帰ってきた」との声が多く聞かれた。前作『IV ワードナの逆襲』が異端的な構造実験作であったのに対し、本作はクラシックな冒険譚へと立ち返ったからである。 しかし単なる原点回帰ではなく、射程やスイミングスキルなど新機軸が加えられたことで、従来のプレイヤーにも新鮮な挑戦を提供した。この“伝統と革新のバランス”が、多くのユーザーに好意的に受け止められた理由のひとつである。特に当時のPC雑誌『LOGiN』や『Oh!PC』では、シリーズの完成度と新要素の融合を高く評価し、「単なる続編ではなく、熟成の一作」と評された。
中級者から上級者まで魅了した高難度設計
難易度の高さは、ウィザードリィシリーズの代名詞だが、本作のバランスは絶妙である。初心者には容赦ない一方、上級者にとっては“緊張感と報酬のバランス”が見事に調整されていた。特に、プレイヤーの判断が命運を分ける戦闘システムは高く評価され、「一手の選択が生死を分けるRPG」という賛辞を得た。 レビューサイトや当時のユーザー投稿を見ると、「一歩進むたびに心臓が高鳴る」「死の恐怖が快感に変わる」といった表現が多く見られる。これは現代の自動回復・オートマッピング中心のRPGとは異なり、紙とペンで地図を描き、慎重に進むスタイルだからこそ生まれる感情である。
グラフィックへの称賛とFM TOWNS版の完成度
グラフィック面で特に注目を集めたのが、FM TOWNS版の存在である。当時としては非常に高品質なフルカラー描写を実現し、キャラクターや背景の陰影が際立っていた。末弥純によるデザインの重厚さと、幡池裕行の彩色センスが融合したその画面は、PCゲーム誌で“美術品のような迷宮”と評されるほどだった。 また、敵キャラクターの一枚絵が拡張されたこともプレイヤーから好評を得た。ワイヤーフレームの無機質な空間に突如現れるモンスターの荘厳な存在感――それが、プレイヤーに“異界と遭遇している”という感覚を強烈に植え付けたのである。
音楽・演出への高い評価
音楽も本作の評価を押し上げる要因のひとつであった。特にFM TOWNS版の田中公平によるサウンドトラックは、「RPG音楽の芸術化」と評されるほどの完成度を誇る。クラシカルな旋律に混じる緊張感のある低音や、魔法詠唱時の効果音の重みは、プレイヤーの想像力をかき立てた。 また、敵登場時の演出や戦闘BGMの変化など、従来よりも“演出意識の高い”設計が見られたことも注目点である。これは後の日本製RPG(特にファルコム作品やスクウェア作品)が「演出の文法」を取り入れていく礎となったとされる。
シナリオへの賛否 ― “理解する者だけが辿り着ける”
一方で、物語の抽象性に戸惑うプレイヤーも少なくなかった。ウィザードリィVは直接的なストーリーテリングを排し、断片的な言葉や象徴的な出来事で物語を語る。そのため、プレイヤーによって解釈が分かれる。「結局ゲートキーパーは何者だったのか?」「ソーンの真意とは?」など、考察を呼ぶ構成となっており、“理解する者だけが辿り着ける”神秘性がファン層を二分した。 ただし、それを“挑戦的な物語構造”として評価する層も多く、「ゲームというメディアがプレイヤーに思索を促した最初期の例」と見る評論家もいた。
国内雑誌でのレビュー評価
当時の『マイコンBASICマガジン』や『TECH Win』などの評価を参照すると、総合評価は軒並み高得点を記録している。特に、 – システムの完成度:9/10 – 難易度バランス:8/10 – 世界観・演出:10/10 といったスコアが並び、“大人のRPG”として特集が組まれたこともあった。 また、PC-9801版の快適な動作と高速ロードは、同時期のRPGと比較しても優秀であり、「技術的にも芸術的にも成熟した一作」と評された。
プレイヤー同士の交流と“共有する冒険”
本作の人気は、ファン同士の情報交換文化を生み出した点にもある。当時はインターネット掲示板がまだ一般的でなかったが、雑誌投稿欄やBBS上での“マッピング共有”“アイテム検証”が盛んに行われた。特に「水辺の探索条件」「隠し通路の座標」といった情報はプレイヤー間の協力で発見されることが多く、その過程自体がひとつのコミュニティ体験となった。 この“プレイヤー同士で攻略を組み立てる文化”は、ウィザードリィシリーズの象徴的な要素であり、ゲームが「孤独な冒険」でありながら「共有される知的体験」であることを体現していた。
海外での反応と文化的評価
海外では『Heart of the Maelstrom』としてリリースされ、英語圏でも根強いファンを獲得した。特にRPG専門誌『Computer Gaming World』では、「最も思索的なウィザードリィ」と評され、ダンジョンデザインの自由度や哲学的な物語構造を称賛された。 一方で、「難解すぎる」「手探りすぎる」といった批判もあり、当時のアメリカではカジュアルゲーマー向けRPG(ウルティマVIやバードテイルズなど)との差が際立った。しかし、今日では“プレイヤーの想像力を信頼したRPG”として再評価されている。
現代における再評価
2020年代に入ってからも、『ウィザードリィV』はレトロゲームファンの間で頻繁に話題に上がる。PC-8801版やFM TOWNS版の復刻動画が配信されるたびにコメント欄では「当時の雰囲気が最高」「この緊張感はいまでも色褪せない」といった声が寄せられている。 特に“手描きマッピング”“一歩一歩の重み”“死のリスクと隣り合わせの探索”といった古典的要素が、現代のプレイヤーに“失われた冒険体験”として新鮮に映っている。これらの要素が評価され、レトロRPG界隈では“リルガミン三部作の頂点”と称されることもある。
総評 ― 記憶に刻まれる“試練の迷宮”
最終的に多くのファンが語るのは、「ウィザードリィVは人を選ぶが、一度ハマると抜け出せない」という点である。ストイックな難易度と美しい世界観が、プレイヤーに孤独と達成感を同時に味わわせる。 グラフィックや音楽の進化だけでなく、プレイヤーの“心の在り方”を問うような深さがあり、ただのゲームを超えた“体験”として記憶に残る。ウィザードリィVは、当時のプレイヤーにとって人生の一部であり、今なお“挑戦する者”の象徴であり続けている。
■■■■ 良かったところ
シリーズの伝統と革新を見事に融合した完成度
『ウィザードリィV』の最大の長所は、シリーズの“古典的魅力”と“現代的進化”を両立させた完成度の高さにある。前作『IV ワードナの逆襲』で実験的に振れた構造を一度リセットし、再び王道のパーティ型ダンジョンRPGとしての基礎を取り戻した一方で、射程やスイミングスキルなどの新要素を大胆に導入している。 このバランス感覚が絶妙で、古参プレイヤーからは「懐かしさと新鮮さが同居する奇跡的な設計」と高く評価された。単なる回帰ではなく、シリーズの“文法”を守りつつ、“構造そのものを再構築する”試みが成功している点は、本作の特筆すべき功績である。
世界観の深みと神秘的なストーリー
本作の世界設定は、単なる冒険舞台ではなく、哲学的・神話的な構造を持つ点が特に秀逸である。プレイヤーが挑むのは「三軸の門」を中心とした“世界の調和”という壮大なテーマであり、物語全体に「光と闇」「秩序と混沌」「創造と破壊」という対立構造が織り込まれている。 これにより、敵であるソーンや封印されたゲートキーパーといった登場人物に単純な善悪の区分がない。すべての存在が「世界の一部」として位置づけられ、プレイヤー自身の選択がその均衡に影響を及ぼす。この“多層的な世界観”がプレイヤーに深い思索を促し、単なる攻略の枠を超えた体験をもたらしている。
知的刺激に満ちたゲームデザイン
『ウィザードリィV』のダンジョン構造は、単に複雑というだけではなく、論理的思考力を試すように設計されている。各階層には仕掛けや謎解きが散りばめられており、マッピングや情報整理が攻略の鍵となる。 たとえば、水辺を進むルートではスイミングスキルの数値を考慮する必要があり、安易な突入は命取りになる。一見無関係なNPCの発言が、後の重要なヒントとなることも多く、プレイヤーは細部の情報を記録しながら推理を重ねていく。 この“知識と洞察による突破”の快感は、まさに知的パズルのようであり、後のRPGが忘れがちな“考える楽しさ”を存分に味わえる構造だ。
緊張感を生む難易度バランス
本作の難易度は決して易しくないが、その厳しさが絶妙な緊張感を生み出している。敵の配置や罠の種類はランダム要素を含み、常に油断できない。だが理不尽ではなく、慎重に準備し、冷静に判断すれば突破できる設計になっている。 プレイヤーの成長とともに、難易度の感覚が自然に変化していく点も素晴らしい。序盤は「生き延びるだけで精一杯」だが、中盤以降は「戦略を立てて突破する快感」が増していく。 一歩間違えれば全滅する緊張と、突破したときの達成感。そのコントラストが強烈で、プレイヤーを何時間も没頭させる中毒性を生んでいる。
グラフィックと音楽の芸術性
グラフィック面での完成度もシリーズ随一といえる。特にPC-9801版では、末弥純によるモンスターイラストが圧倒的な存在感を放っており、そのダークで幻想的な筆致はプレイヤーの想像力を刺激する。敵が画面に現れるたびに、単なる戦闘相手ではなく“儀式的存在”として感じられるのだ。 FM TOWNS版では幡池裕行らによる彩色が加わり、幻想性がさらに増している。色彩の深みや光の効果が、ダンジョン探索をまるで美術館での体験のように変えている。 音楽においても、田中公平の手による荘厳なサウンドが高く評価されており、特に戦闘曲の緊張感と静寂のコントラストは“RPG音楽の完成形”と称された。
NPCの存在感とストーリーテリング
NPCの描かれ方も、ウィザードリィVの大きな魅力だ。従来作のNPCが単なる情報源だったのに対し、本作では彼らが物語の歯車として機能している。ある者は協力者となり、ある者は裏切り者として立ちはだかる。 会話の中に散りばめられた断片的な言葉が、プレイヤーの想像を掻き立て、やがて大きな真実に繋がる構成は秀逸。特に、終盤で明らかになるソーンとゲートキーパーの関係性は、静かな感動を呼ぶ名シーンとして語り継がれている。
プレイヤーへの挑戦と成長の実感
ウィザードリィVをプレイした者が口を揃えて語るのは、「自分自身が成長したと感じられるRPG」だということだ。 単なるキャラクター育成ではなく、プレイヤー自身の思考力・洞察力・忍耐力が試される。失敗から学び、記録し、試行錯誤を重ねることで、次第に迷宮を支配する感覚を得る。 “死を恐れながらも前へ進む勇気”をプレイヤーに要求する本作は、ゲームを通じて達成感と自己超越を体験させる稀有な存在である。
日本文化との親和性と影響力
『ウィザードリィV』は、単なる海外RPGの移植に留まらず、日本のゲーム文化に深く根付いた作品でもある。アスキーによるローカライズは非常に丁寧で、翻訳文体やアイテム名称に日本語独自の美意識が感じられる。 その結果、以後の日本製RPG――特に『真・女神転生』や『世界樹の迷宮』などの“ダンジョン系作品”に多大な影響を与えた。 世界観の構築、難易度設計、テキストの重厚さといった多くの要素が、本作を通じて“日本的RPG”として昇華されたといっても過言ではない。
リプレイ性と探索の自由度
一度クリアしても再挑戦したくなる高いリプレイ性も、本作の長所だ。NPCとの会話選択や入手アイテムの順序によって展開が微妙に変化し、周回ごとに新しい発見がある。 さらに、戦略を変えることで全く異なる体験を得られる点も魅力的だ。たとえば、魔法主体のパーティと物理重視のパーティでは、同じ敵との戦い方がまるで異なる。 この“自由度と発見の連続”がプレイヤーの好奇心を途切れさせず、プレイ時間が数十時間を超えても飽きることがない。
総評:静寂の中に宿る深い満足感
総じて、『ウィザードリィV』の“良かったところ”は、派手な演出や快適さではなく、“緻密に作られた静かな深み”にある。 緊張と達成感、恐怖と美しさ――相反する感情を同時に味わわせる稀有な体験。それがこの作品の真の価値である。 プレイヤーが迷宮を進むほどに、その構造美と物語の重層性に気づき、やがて静かな満足感が心に残る。 『ウィザードリィV』は、派手さを求めない者にこそ深く響く“成熟した冒険譚”であり、今なお語り継がれる理由がここにある。
■■■■ 悪かったところ
難易度の高さが一部プレイヤーを遠ざけた
『ウィザードリィV』の最も指摘された欠点のひとつは、あまりにも高い難易度設定である。 シリーズを通して「死と隣り合わせの緊張感」を特徴としてきたが、本作はその傾向がさらに強まっており、初見プレイヤーにとっては過酷な試練となる。敵の攻撃力や罠の即死性が高く、油断すると数時間分の進行が一瞬で失われることも珍しくない。 また、セーブポイントが限定的であり、途中でのリトライが難しい。結果として、“緊張感”を楽しめる層には好評だった一方で、“理不尽さ”と感じるプレイヤーも多かった。特に、RPG初心者や物語重視のプレイヤーには敷居が高く、当時のレビューでも「忍耐力が試されるRPG」と評されていた。
操作性とユーザーインターフェースの不便さ
本作は1980年代後半の設計思想を色濃く残しており、UI(ユーザーインターフェース)の不便さが指摘されている。 例えば、パーティの装備変更やアイテム管理が煩雑で、ひとつの行動を実行するたびに複数のコマンドを経由しなければならない。また、呪文やアイテムの名称が英語略称(例:MAHALITO、DIALMAなど)で表示されるため、シリーズ初心者には理解しづらかった。 さらに、マップ表示や自動マッピング機能が一切なく、プレイヤー自身が方眼紙を使って地図を描く必要がある。この“原始的システム”が本作の魅力である一方で、現代の視点から見ると“不親切”と感じられる部分でもある。 FM TOWNS版では若干の改善が見られたものの、操作レスポンスの重さやメニュー遷移の多さは完全には解消されなかった。
テンポの悪さと冗長な移動時間
ダンジョンの構造が複雑化したことで、探索に要する時間が膨大になっている点もマイナス要素として挙げられる。移動スピードが遅く、階層間の移動に多くの手間がかかるため、ストレスを感じるプレイヤーも少なくなかった。 特に後半の「三軸の門」では、転送装置やループ構造の多さから迷いやすく、目的地にたどり着くまでに何度も同じルートを往復することになる。この構造自体は“探索の緊張感”を生むが、長時間プレイすると単調な疲労感を与えてしまう。 また、エンカウント率が非常に高いため、一歩ごとに戦闘が発生することもあり、リズムが途切れやすい。戦闘バランス自体は良好だが、テンポ面での冗長さは否めない。
シナリオの説明不足と抽象的な展開
本作の物語は神話的・象徴的な表現を重視しているが、その反面、ストーリーの理解が難しいという批判もある。 プレイヤーが受け取る情報は断片的であり、NPCの台詞やイベントの意味を自分で推測する必要がある。これが知的な魅力として機能する一方で、「結局何をしているのか分からない」と感じるプレイヤーも多かった。 特に、終盤の展開やラスボスの動機などが明示されず、プレイヤーが“世界の理”を自ら解釈する必要がある点は、物語に没入しにくいという意見を生んだ。 雑誌レビューでも、「物語性を感じるまでに相当な読解力が必要」「ストーリーがプレイヤーに冷たい」といったコメントが掲載されている。
新システムの説明不足と不透明さ
射程・スイミングなどの新要素が導入されたが、それらの説明がほとんどゲーム内に存在しない点も問題視された。 特に水泳スキルは、失敗すると即溺死するという極端な仕様でありながら、どの深さで危険になるかが明示されない。初見プレイヤーが“試行錯誤で死を学ぶ”構造はシリーズらしいが、不親切と感じる人も多かった。 また、射程の概念も直感的に理解しづらく、前衛・後衛の位置関係を誤ると攻撃が届かないこともあった。このような“不透明な仕様”が、一部プレイヤーには理不尽と受け止められた。
テンポを損ねる高頻度エンカウント
ウィザードリィVのエンカウント率は、シリーズでも特に高い部類に入る。階段を2~3歩進むだけで敵が出現するケースも多く、探索より戦闘が主軸になってしまう場面が目立つ。 これにより、緊張感が維持される一方で、テンポの悪化を招いている。敵が強力なため、短時間で複数回戦闘を繰り返すとリソース管理が厳しくなり、頻繁に街へ戻る必要がある。 これが冒険の“リアルさ”を生むとも言えるが、効率を重視するプレイヤーにとっては煩雑に感じられた。
初心者を突き放す難解なシステム
ウィザードリィシリーズは元々コアユーザー向けの設計だが、本作では特に“シリーズ経験者前提”の部分が多い。職業の転職条件、呪文の体系、ステータス変動などが複雑で、マニュアルを熟読しないと理解できない要素も多い。 これにより、新規ファンが入りづらいという構造的な問題が生まれた。特にPC版ユーザー以外の一般プレイヤーが参入しづらく、結果として“ファン向け専用タイトル”という印象を強めてしまった。 スーパーファミコン版で多少の調整が加えられたものの、根幹のシステムはそのままであり、“初心者排除設計”という評価は最後まで付きまとった。
一部バランス崩壊と理不尽な要素
終盤の敵には、極端に防御力や魔法耐性の高いモンスターが存在し、適切な戦略を知らないと“詰み状態”に陥ることがある。特にラスボス・ソーン戦では、イベントアイテムを入手していなければ一切ダメージが通らず、詰みセーブになるケースも報告されている。 こうした“情報前提の設計”は、攻略本なしでは突破が難しく、一部では「理不尽ゲー」と揶揄された。 また、宝箱の罠や敵の特殊攻撃により、即死する確率が高いことも不満点として挙げられた。難易度の高さと不公平感の境界が曖昧で、慎重派プレイヤー以外には負担が大きい。
総評:完成度の高さゆえの“硬派すぎる設計”
『ウィザードリィV』の欠点は、作品としての完成度が高いがゆえに“硬派すぎる”点に集約される。 徹底したリアリズム、試練としての難易度、説明を省いた設計――それらはシリーズの哲学として一貫しているが、同時に間口を狭めてしまった。 とはいえ、これらの“悪い点”を逆に魅力として語るファンも多い。実際、ウィザードリィVはその不親切さと厳しさこそが“挑戦する者の証”であり、苦しさを乗り越えた後に得られる達成感が格別なのだ。 つまり、“悪い点”がそのまま“唯一無二の個性”になっている――これこそ、ウィザードリィVという作品の矛盾であり、同時に美徳でもある。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
ゲートキーパー ― 世界の均衡を見守る“静寂の守護者”
『ウィザードリィV』において最も印象的な存在のひとりが、三軸の門を守護する大魔導師ゲートキーパーである。 彼はかつて「四大の力(火・水・風・土)」の調和を司り、世界の秩序を維持してきた。しかし、愛弟子ソーンの裏切りによって封印され、長きにわたって静寂の中に閉じ込められている。 その姿は単なる被害者ではなく、むしろ“運命の観測者”のような威厳を放っており、プレイヤーが彼に辿り着くまでの過程は、まるで信仰に近い緊張感を伴う。 彼の存在はシリーズを通じて語られる“光と闇の均衡”を象徴しており、プレイヤーが迷宮を踏破する目的そのものを体現していると言ってよい。 静かに語られる台詞の一つひとつが深く胸に残り、戦いではなく理解によって真実に至るというテーマを、彼の存在が見事に表現している。
ソーン ― 愛と野心が交錯する“裏切りの弟子”
ソーンは、ゲートキーパーの高弟でありながら、世界の理を自らの手で書き換えようとした野心の持ち主である。 彼は単なる悪役ではなく、“知と力を追い求めた者の末路”という人間的悲劇を体現している点で、多くのプレイヤーに強い印象を残した。 その動機には「師を超えたい」という純粋な願望も含まれており、物語終盤での彼の言葉には、単なる支配欲を超えた哲学的ニュアンスが込められている。 特に、ラスボス戦前の対話シーンでは、彼の中に残る人間的葛藤が垣間見え、プレイヤーによっては“同情”すら抱くほどである。 そのデザインもまた特徴的で、PC版・SFC版で異なるビジュアルが用意されている。末弥純による原画版では冷徹な貴族のような風格を持ち、SFC版ではより神格的な存在として描かれた。どちらも“人間を超えた存在”というテーマを見事に体現している。
アモンとバリ ― 冒険を導く神秘的な存在
迷宮を探索する過程で出会う“アモン”と“バリ”という双子の存在も、多くのプレイヤーに印象を残したキャラクターだ。 彼らは一見ただの案内人のように見えるが、実際には世界の根幹に関わる存在であり、ゲートキーパーやソーンの理念を象徴する“二面性”を担っている。 アモンは理性と秩序を、バリは情熱と混沌を象徴しており、プレイヤーがどちらの意志に共鳴するかによって受け取る印象が変化する。 この二人の対話は単なるイベント以上の意味を持ち、プレイヤーに「何を守り、何を捨てるか」という選択を突きつける。 多くのファンが「アモンとバリの言葉が心に残った」と語るのは、彼らの台詞がゲーム全体の哲学を凝縮しているからだ。
酒場のマスター ― 無口な助言者としての魅力
街の拠点である酒場にいる無名のマスターも、静かな人気キャラクターのひとりだ。 彼は多くを語らず、冒険者たちのやり取りを見守るだけだが、その無言の存在感が作品全体の雰囲気を引き締めている。 時折、プレイヤーが特定のイベントを進めると短い助言をくれることがあり、その一言が次の行動を決定づけることもある。 彼はまるで“プレイヤーのもう一つの意識”のような存在であり、緊張感に満ちたダンジョン探索の合間に訪れる彼の静かな店は、一瞬の安らぎを与えてくれる。 このキャラクターの存在が、“死と隣り合わせの冒険”にわずかな人間味を与えていることは間違いない。
盗賊キャラクター ― 影に生きる職人魂
ウィザードリィシリーズにおいて盗賊は欠かせない職業だが、本作の盗賊たちは特に個性的で、人間味にあふれている。 プレイヤーが自作するキャラクターであっても、探索中のトラップ解除や鍵開けの成功率の高さによって、パーティ内での信頼が深まっていく。 中でも、自分が作り上げた盗賊が何度も死線をくぐり抜け、罠解除を成功させるたびに愛着が増していくという体験は、RPGの中でも特別な感情を呼び起こす。 多くのプレイヤーが「自分の盗賊こそが主役」と語るのは、彼らが物語上の英雄ではなく、“プレイヤーとともに成長した相棒”として記憶に刻まれるからだ。
モンスターたちの個性と魅力
敵キャラクターにも独自の魅力がある。 特に末弥純が描くモンスターたちは、恐ろしさと神々しさを併せ持ち、まるで宗教画のような存在感を放つ。 例えば「グレーターデーモン」は圧倒的な威厳を持ち、プレイヤーが出会った瞬間に本能的な恐怖を覚えるほどの迫力を持つ。 一方で「マーメイド」や「スフィンクス」といった存在には、美しさと哀しさが共存しており、戦うことに躊躇を覚えるプレイヤーもいた。 この“敵ですら物語の一部”と感じさせるキャラクターデザインが、本作の芸術的完成度を支えている。
女性キャラクターの魅力と儚さ
ウィザードリィVでは、女性キャラクターの描かれ方にも独特の美学がある。 例えば、迷宮内で出会う女性魔導師や巫女は、力強さと神秘性を兼ね備えており、単なる“装飾的存在”にとどまらない。 彼女たちはプレイヤーに試練を与える者であると同時に、時に助言を与える存在でもあり、“誘惑と救済”の象徴として描かれている。 そのデザインも繊細で、80年代末期のグラフィックながら、陰影の表現が美しく、多くのプレイヤーが「忘れられない存在」として記憶している。
仲間キャラクターへの愛着と喪失の痛み
『ウィザードリィV』において、プレイヤーが自ら作成した仲間キャラクターは単なるデータではない。 彼らは冒険の苦楽を共にする“分身”であり、時に死亡し、時に復活しながら絆を深めていく。 しかし蘇生に失敗した場合、キャラクターは永久に失われてしまう。 この“取り返しのつかない喪失”が、他のRPGにはない重みを生み出している。 あるプレイヤーは「仲間の死が自分の責任に思えて胸が痛かった」と語り、また別のプレイヤーは「だからこそ生き残った者への愛着が強くなった」と述べている。 この“喪失と絆”の感覚が、ウィザードリィシリーズ最大の感情的魅力であり、Vではその完成形に到達している。
総評:人間と世界の“在り方”を映すキャラクター群
『ウィザードリィV』のキャラクターたちは、単なる登場人物ではなく、プレイヤー自身の内面を映す鏡のような存在である。 ゲートキーパーの静謐、ソーンの野望、アモンとバリの二面性、盗賊の職人気質――それらすべてが「人間とは何か」「秩序とは何か」という問いを内包している。 プレイヤーが誰に共感し、誰を憎み、誰を救うかによって、物語の意味そのものが変化する。 だからこそ、本作のキャラクターたちは30年以上経った今も鮮烈な印象を残している。 『ウィザードリィV』は“登場人物に感情を移すRPG”ではなく、“登場人物に自分を投影するRPG”であり、その点で永遠に色褪せない。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
各機種版の位置づけと発売背景
『ウィザードリィV』は、アスキーによって日本向けに複数のパソコンへ移植された。その主な対応機種は、PC-8801、PC-9801、そしてFM TOWNSの3種類である。 これらのプラットフォームは1980年代後半から1990年代初頭にかけて日本のパソコン文化を支えた主要機であり、各機種の性能差がそのままゲーム体験の違いに表れている。 アスキーは機種ごとのハードウェア特性を理解し、単なる移植にとどまらない最適化を施した。結果として、同じ『ウィザードリィV』でありながら、それぞれに独自の“味わい”を持つバージョンが生まれている。
PC-8801版 ― シリーズの伝統を継ぐ“渋みのある原典”
PC-8801版は、シリーズの正統的な継承者として位置づけられる。グラフィックは8色表示ながら、末弥純によるイラストが持つ筆致の重みと陰影表現が際立ち、限られた色数で幻想的な雰囲気を見事に再現している。 音楽はFM音源を最大限に活かし、低音が効いた荘厳な旋律を奏でる。特に戦闘BGMやイベント時の曲は、制約の多い音色ながらも緊張感を生み出しており、当時のプレイヤーから「最もウィザードリィらしい音」と称された。 また、ロード時間が短く、動作も軽快だったため、長時間の探索プレイに向いていた点も評価が高い。操作体系はキーボード主体で、マウス操作非対応だが、その分コマンド入力のテンポが良く、シリーズ経験者にとっては心地よい操作感があった。 総じて、PC-8801版は“質実剛健な原点回帰”として多くのファンに愛されており、「迷宮探索の静寂」が最も際立つバージョンといえる。
PC-9801版 ― 快適性と視覚演出の向上
PC-9801版は、88版の精神を引き継ぎながらも、より現代的なプレイフィールを志向したアップグレード版といえる。 グラフィックは640×400ドットの高解像度モードに対応し、16色表示によってキャラクターや背景の細部がより鮮明になった。特にダンジョン内の光と影のコントラスト表現が向上し、迷宮に立体感が生まれている。 また、インターフェース部分も改善され、文字フォントが見やすくなり、ステータス表示の情報量が増えた。88版ではシンプルだったメニュー構成に、アイコンや装備の状態マークなどの視覚的要素が追加され、操作の分かりやすさが向上している。 音楽面では、PC-9801のFM音源チップ「YM2203」および「YM2608」を用いた豊かな音響表現が可能になり、88版よりも広がりのあるサウンドを実現。 ファンの間では「88の硬派さに対し、98は完成度の高さで勝負する」と評され、遊びやすさと没入感の両立が最も取れているバージョンとして高い人気を誇る。
FM TOWNS版 ― 表現の極致に到達した豪華仕様
FM TOWNS版は、3機種の中でも圧倒的に表現力が高い“最上位版”として知られている。 まず注目すべきは、フルカラー(256色表示)によるグラフィック。末弥純に加えて幡池裕行ら複数のアーティストが参加し、彩度と陰影が織りなす美麗な画面が話題となった。ダンジョンの光源効果や敵キャラクターの質感は、当時のPCゲームとしては破格のクオリティであり、海外作品にも劣らない芸術性を誇る。 さらに、音楽面では大きな進化が見られた。作曲は『ワンピース』や『サクラ大戦』で知られる田中公平が担当。FM音源とCD-DAを組み合わせたサウンドは、これまでの電子音主体のBGMとは一線を画し、まるで映画音楽のような迫力を持っていた。 また、TOWNS版では一部イベントに簡易アニメーションが導入され、敵の出現時に微細なモーションがつく演出も追加。 当時の雑誌『PC Engine FAN』や『ログイン』では「ウィザードリィがついにビジュアルの時代に突入した」と特集が組まれるほどで、ファンの間では“究極のウィザードリィ”として語り継がれている。
機種間の演出差とプレイヤー体験の違い
同じストーリーでありながら、機種ごとに与える印象が異なるのも『ウィザードリィV』の特徴だ。 PC-8801版では“暗闇と静寂の中で考える冒険”という精神性が強く、まさにプレイヤーの想像力が補完するタイプの体験が味わえる。 一方で、PC-9801版では視覚的な完成度が高く、ゲームとしての快適性が際立つ。そのため、シリーズ初心者でも入りやすい構成になっていた。 FM TOWNS版は、視覚・聴覚・演出のすべてを極めた“映像的RPG”へと進化し、まるでファンタジー映画を体験しているかのような感覚をプレイヤーに与える。 このように、どの機種版にも明確な個性があり、単なる性能差にとどまらず“作品性の違い”として成立している点が、アスキーの移植技術の高さを物語っている。
プレイヤーの評価と人気の傾向
ファンの間では、PC-9801版が“最もバランスの取れた移植”として支持される傾向が強い。グラフィック・音・操作性のいずれも安定しており、シリーズ初体験者にもおすすめしやすい構成となっている。 一方で、PC-8801版は“原点の味”としてコアファンに愛されており、現在でもエミュレータを使って88版を再プレイする愛好者が存在する。 FM TOWNS版は入手難易度が高く、プレミア化しているが、その完成度から“幻の決定版”と呼ばれ続けている。特に田中公平サウンドとフルカラー演出を評価する声が多く、「芸術としてのRPG」という観点で語られることが多い。
総評:同じ“迷宮”に宿る三つの個性
PC-8801版の静謐、PC-9801版の洗練、FM TOWNS版の豪華――この三つのバージョンは、それぞれが異なる方向性で『ウィザードリィV』の魅力を引き出している。 どれも一長一短があり、どの機種を選んでも“リルガミンの精神”に触れられることに変わりはない。 ハードの進化とともに、ゲームがどのように深化していくかを体感できる点で、本作はまさに“時代を超えて成長したウィザードリィ”の象徴といえるだろう。 今なおレトロPCファンの間で「どの版が最高か」という議論が絶えないのは、この作品が単なる移植ではなく、3つの異なる芸術表現として完成しているからにほかならない。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
★『ソーサリアン』
(日本ファルコム・1987年・価格7,800円) 日本ファルコムの看板シリーズ『イース』に続く人気作であり、アクションRPGという新ジャンルを確立したタイトル。プレイヤーは冒険者集団を作り、数々のシナリオをこなしていく。 特徴的なのは“老化システム”で、時間の経過によりキャラクターが年老い、最終的に引退してしまうという現実的要素を導入していた。 この「キャラクターが有限である」という感覚は、ウィザードリィの“命の重み”と共鳴する部分があり、どちらもプレイヤーに“決断の責任”を意識させる構造を持っていた。
★『ハイドライド3』
(T&E SOFT・1987年・価格8,800円) 『ハイドライド』シリーズの第3作で、リアルタイム戦闘に加え、善悪の概念や経験値のバランスなど倫理的要素を導入した意欲作。 ウィザードリィVと同じく“プレイヤーの選択が世界に影響する”構成であり、単なるレベルアップではなく「どう生きるか」を問う点で哲学的な共通性がある。 また、PC-8801やPC-9801など複数機種に展開され、当時のハードスペックを限界まで引き出した作品として評価された。
★『ザナドゥ シナリオII』
(日本ファルコム・1986年・価格8,800円) ファルコムが生んだ伝説的RPG『ザナドゥ』の拡張版。膨大な迷宮と高い難易度で知られ、攻略には長期的な戦略が求められた。 『ウィザードリィV』の複雑なダンジョン構造や謎解き要素と同じく、当時のプレイヤーに“マッピング文化”を根付かせた一因となった。 この作品を通じて、「地図を描きながら進む」楽しみが多くのRPGファンに浸透し、後の国産RPG開発にも影響を与えた。
★『夢幻の心臓III』
(クリスタルソフト・1987年・価格9,800円) 国産RPGの老舗クリスタルソフトによる名作シリーズ第3弾。広大なフィールドマップと自由度の高いシナリオ構成が魅力。 『ウィザードリィV』が“迷宮の深さ”を追求したのに対し、『夢幻の心臓III』は“世界の広さ”を重視した構造で、両者は正反対の方向からRPGの可能性を探った存在といえる。 また、善悪だけでなく中立的な選択肢が設けられ、プレイヤーの価値観を試す仕組みも共通していた。
★『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』
(日本ファルコム・1989年・価格8,800円) ファルコムの人気シリーズ『ドラゴンスレイヤー』の派生作品として誕生した王道ファンタジーRPG。 感情豊かなストーリーテリングと音楽面の完成度が高く、RPGに“物語性”を明確に導入した先駆けでもある。 一方で、『ウィザードリィV』はあえて抽象的なストーリー構成を取り、プレイヤー自身に物語を補完させる設計を採用している。 両作品は、「語るRPG」と「語らないRPG」という対照的なアプローチであり、当時のプレイヤーに選択肢の多様性を示した。
★『ブラックオニキス』
(BPS・1984年・価格7,800円) 日本初期の3DダンジョンRPGとして知られる金字塔。『ウィザードリィ』シリーズの直接的な影響を受けた作品でもある。 キャラクター育成、町での交流、迷宮探索などの要素を日本的にアレンジし、後の国産RPGの基盤を築いた。 『ウィザードリィV』が“原点への回帰”を掲げていたのに対し、『ブラックオニキス』は“国産化の起点”という点で対照的な立ち位置を持つ。
★『ラストハルマゲドン』
(ブレイングレイ・1988年・価格9,800円) 人類滅亡後の地球を舞台に、悪魔たちが人類の遺産と戦うという異色の設定で話題を呼んだ。 重厚な世界観と哲学的テーマが特徴であり、『ウィザードリィV』の“光と闇の均衡”の物語と通じる部分がある。 戦闘システムはターン制だが、グラフィックやBGMが当時としては非常に高水準で、プレイヤーに“崇高さと不気味さ”を同時に感じさせた。
★『デーモンズリング』
(ハミングバードソフト・1989年・価格9,800円) PC-9801向けに発売されたコマンド入力型RPG。魔法体系が緻密で、詠唱に独自の文字列を入力する仕組みが特徴的だった。 プレイヤーの“記憶力”と“探索力”を試すゲームデザインは、『ウィザードリィV』の理不尽とも言える難度設計に通じる硬派な作りだった。 コマンド入力を通じて“自分で呪文を唱える”感覚を実現した点は、後のハードRPG愛好家に高く評価された。
★『アークス』
(ウルフチーム・1988年・価格9,800円) リアルタイム戦闘とアニメーションを融合させたアクションRPG。ファンタジー世界を舞台にしながら、スピード感と爽快さを重視していた。 『ウィザードリィV』の“静寂と緊張のRPG”とは対極にあり、同時期のプレイヤーに“ゲーム体験の選択肢”を与えた存在でもある。 当時の雑誌では「アークス派か、ウィザードリィ派か」と比較記事が組まれたほど、RPGの二極化を象徴する作品だった。
★『アンジェラス ~悪魔の福音~』
(トンキンハウス・1988年・価格9,800円) 宗教的テーマと黙示録的世界観を扱ったアドベンチャーRPG。天使と悪魔の戦いを描きながら、人間の欲望や信仰を問う内容が特徴。 グラフィック演出やBGMに荘厳さがあり、『ウィザードリィV』の神話的世界観と共鳴する雰囲気を持っていた。 また、当時としては珍しくマルチエンディングを採用し、プレイヤーの行動次第で救済か破滅かが分かれるという構成が注目された。
同時代における『ウィザードリィV』の位置づけ
こうして見ていくと、『ウィザードリィV』が登場した時代は、RPGが“ゲームから思想へ”進化しつつあったことが分かる。 多くの作品が、単なる冒険や戦闘を超え、人間の生き方・善悪・信念を問いかける方向へ進化していた。 その中で『ウィザードリィV』は、「静謐」「孤独」「試練」を軸に据え、プレイヤー自身の内面と対話させることで独自の位置を確立した。 アクション性や派手な演出よりも、思索と戦略を重視する姿勢は、後の硬派RPG――たとえば『真・女神転生』や『ダークソウル』など――の源流にもなったといえる。
総評:1980年代末、RPG黄金期の象徴として
1988年から1990年にかけては、パソコンRPGの“多様化”が進んだ時期であり、 『ウィザードリィV』はその中でも“精神性を極めた作品”として特別な存在だった。 同時期の他作品が「物語」や「システムの革新」を競う中で、本作は「RPGの根源――探索・恐怖・成長――」を徹底的に追求した。 その硬質な魅力は、時代を超えてなお、多くのプレイヤーに“迷宮に挑む覚悟”を思い出させる。 まさに、『ウィザードリィV』は1980年代末のRPG文化を象徴する“静かなる巨星”であり、 その存在があったからこそ、以後の日本RPGが多彩な方向へと枝分かれしていったのである。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
SUPERDELUXE GAMES 【Switch】Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord(ウィザードリィ) 通常版 [HAC-P-BCCKA NSW ウィザー..




 評価 4.2
評価 4.2Game*Spark Publishing 【Switch】Wizardry外伝 五つの試練 通常版 [HAC-P-BK9AA NSW ウィザ-ドリィ ガイデン イツツノシレン ツウジョ..
【中古】 ウィザードリィ リルガミンサーガ/PS
SFC ウィザードリィ5 (ソフトのみ)【中古】 スーパーファミコン スーファミ
【中古】 ウィザードリィ リルガミンサーガ(再販)/PS
SFC スーパーファミコンソフト アスキー ウィザードリィ5 WIZARDRY・V3DダンジョンRPG スーファミ カセット 動作確認済み 本体のみ 【..
【中古】 ウィザードリィ エクス −前線の学府−/PS2
【中古】ウィザードリィサマナー
【中古】(新古品・未使用品) ウィザードリィ エンパイアII 〜 王女の遺産 〜 (廉価版)
【中古】 ウィザードリィ6禁断の魔筆/スーパーファミコン




 評価 3
評価 3![【中古】[PS] ウィザードリィVII ガーディアの宝珠(Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant) ソニー・コンピュータエンタテインメ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270094.jpg?_ex=128x128)