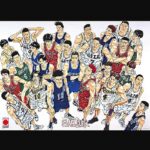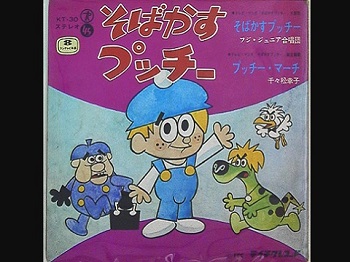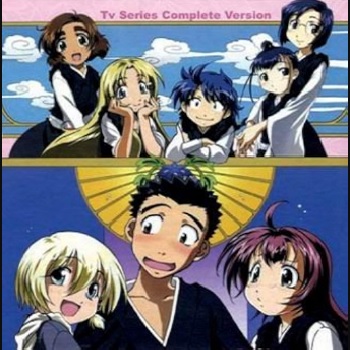レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 [ 里見京子 ]
【原作】:スタジオ・ゼロ
【アニメの放送期間】:1966年4月23日~1967年3月24日
【放送話数】:全48話
【放送局】:NETテレビ系列
【関連会社】:東映動画
■ 概要
作品コンセプトと立ち位置――“少年+6体ロボ”が切り開くSF冒険活劇の原型
『レインボー戦隊ロビン』は、1966年4月23日から1967年3月24日までNETテレビ系列(現・テレビ朝日系)で全48話が放送された、東映動画(のちの東映アニメーション)制作の白黒SFアニメです。物語の中核にいるのは、宇宙由来の宿命を背負う少年ロビンと、機能も性格も異なる6体のロボットたち。彼らは「戦隊」という言葉が定着するより前の時代に、役割分担で協働するチーム・ドラマの魅力をアニメで体現しました。等身大の少年視点で銀河規模の脅威に立ち向かう設計は、後年のヒーロー群像劇やメカ群の“役割特化”に続く道筋を示し、当時の子ども番組にSF的想像力と叙情性を同居させた点でも異彩を放ちます。
企画の背景――スタジオ・ゼロのアイデア群と東映動画の制作力
本作は、東映動画がスタジオ・ゼロに原案を依頼したことから動き出しました。骨格の段階では、古典冒険譚の“連帯”や“義”のモチーフ、海外SF小説の宇宙観、七人組活劇のダイナミズムなど、複数の要素が巧みに合成されています。キャラクター設計では石森章太郎(のちの石ノ森章太郎)が全体のトーンを束ね、藤子不二雄(藤本弘/のちの藤子・F・不二雄、安孫子素雄/のちの藤子不二雄Ⓐ)らの発想も血肉となりました。結果として、硬派なSFスパイシーさと、子ども番組らしい親しみやすさが共存した、当時としては先進的なテイストが形成されています。
時代状況――白黒末期のテレビと“宇宙”への憧れ
1960年代半ばの日本家庭では白黒テレビが主流で、カラーテレビの本格普及はもう少し先。そうした状況で本作は白黒画面を前提に、明暗のコントラスト、線の強弱、シルエットの活用で“宇宙”と“機械”を描き分けました。色彩表現に頼らない分、構図やカット割り、スモーク・光線・爆発のモノクロ表現が洗練され、硬派かつ端正なビジュアル印象を獲得。高度経済成長のただ中で宇宙開発がニュースを賑わせた時代気分も手伝い、子どもたちの視線は自然と夜空のさらに向こう側へ――本作はその“憧れ”の受け皿となりました。
キャラクターデザインとメカ表現――“人格を持つ機能”の面白さ
6体のロボットは単なる兵器ではなく、性格や弱み、ユーモアを備えています。看護・修復の“リリ”、索敵の“ベル”、頭脳の“教授”、戦闘に長ける“ウルフ”、膂力に秀でた“ベンケイ”、そしてロビンの搭乗機能を担う“ペガサス”。それぞれの“機能”が“人格”ときちんと結びついているため、戦闘シーンでも役割分担の必然性が生まれ、チームとしてのドラマが立ち上がります。メカ描写は、線の少ないシンプルなデザインを基調にしつつ、変形・合目的な武装・機能美を重視。記号性が高く、白黒放送でも判読性に優れた設計になっています。
物語の骨格――“移住”と“共存”をめぐるSFドラマ
物語は、滅亡の危機にある異星文明と地球の対峙、そしてそこから派生する家族・忠誠・アイデンティティの葛藤を描きます。宇宙の巨大な力学(星の終焉、文明の選択)と、一人の少年の決断が一本の線で結び直されているのが特徴です。前半は長編構成で危機が連続し、後半は一話完結の色合いが強まり、サスペンス、コメディ、探偵もの的な風味までが顔を出す――この“二層構造”が視聴体験にリズムの変化をもたらし、毎週の“次は何が起こる?”を持続させました。
主人公像の刷新――“血統=運命”を再解釈する
ロビンは出生の来歴ゆえに、地球と異星の間で撕裂されたまなざしを持ちます。彼の強さは、特殊な力の誇示ではなく、仲間を信じる胆力、そして相手の痛みを想像する想像力。時に身体を削るような決断を引き受ける代償性は、ヒーロー像に“償い”や“覚悟”のニュアンスを与え、視聴者に倫理的な問いを返してきます。のちの時代に一般化する“二つの世界を橋渡しする主人公”の早い例としても興味深い存在です。
演出と言語感覚――白黒画面の“間”が作るスリル
本作の演出は、追跡・潜入・対決のテンポを保ちながら、“間”の置き方に特徴があります。足音、機械音、通信音――音が鳴らない刹那に不穏が立ち上がり、次のショットで一気に炸裂する。セリフも簡潔で、子どもに理解しやすいが、時に大人がドキリとする比喩や皮肉も差し込まれます。白黒であることがネガではなく、スリルを増幅させる装置として働いているのです。
制作体制と現場の工夫――限られたリソースの中の最適解
週一放送・モノクロ制作という制約の中で、現場は“見せ場の集中”と“カットの再利用”を賢く組み合わせました。ペガサスの発進、ロボットの出動、光線の作画パターンなどをモジュール化し、話数ごとに新規作画の力点を移す設計。これにより、クライマックスや感情の山で作画密度を上げ、物語の緊張点と映像的カタルシスが一致するようバランスが取られています。
関連メディアとソフト展開――“記憶”を保存するパッケージの歩み
放送後、セレクションVHS、全話収録のレーザーディスク、さらに後年のDVD-BOXへと媒体は移り変わりました。時代ごとにターゲット層が異なり、VHS期は懐かしさの喚起と入門編的な選集、LD期はコレクター指向の完全保存、DVD期は解説ブックレットやノンクレジット映像など特典による“読み直し”が意識されています。媒体が更新されるたびに、本作は当時の映像文法や物語の肌触りを“その時代の視聴環境”で再発見させてくれる存在になりました。
評価と影響――“戦隊的発想×人間味”の交差点
6体ロボのキャラ立て、任務ごとの役割分担、チーム内の軽妙な掛け合い――これらは後年の特撮やアニメに広がる“戦隊的発想”の原型の一つとみなせます。一方で、単にフォーメーションを見せるだけでなく、仲間内の齟齬や嫉妬、迷いをコメディとシリアスの両輪で処理する点が本作の美点。チームは“便利な総合兵器”ではなく、個の弱さを寄せ合って“全体として強くなる”共同体である、という含意が作品全体を貫いています。
本作を見るための“視点”の提案
初見の方には、①白黒表現の“設計美”を味わう、②ロボットの“機能=人格”の結びつきに注目する、③前半・後半で叙述形式が変わる“二層構造”を体感する――この3点をおすすめします。どの話から見ても楽しめる一話完結の妙味と、シリーズとして積み上がる宿命の重みによって、昭和アニメの一つの到達点が見えてくるはずです。
[anime-1]
■ あらすじ・ストーリー
序章――滅びゆく星と少年の宿命
物語は、遠い銀河の片隅に存在する惑星パルタの崩壊の予兆から始まります。科学文明の頂点を極めたその星は、長年のエネルギー乱用によって内部から破壊が進行し、もはや滅亡は避けられない運命にありました。パルタ皇帝は、民の存続のためという大義を掲げつつ、実際には権力への執着から暴走し、移住先として地球を武力で征服する計画を立てます。そこで彼は、優れた科学者ポルト博士をスパイとして地球に送り込み、侵略の前段階として地球の軍備や文化を調査させました。 しかし地球でポルト博士は、すみ子という若い女性と出会います。彼女の献身的な優しさは博士の心を動かし、“征服の対象”であった地球を“守るべき存在”として見直すきっかけとなりました。博士は地球の人々の善良さを知り、密かにパルタ皇帝の計画を阻止しようとします。やがて二人は愛し合い、ロビンという名の子どもを授かるのです。
レインボー戦隊誕生――6体のロボットに託された希望
しかし幸福は長く続きません。博士の裏切りを知ったパルタ軍は地球に追っ手を差し向け、ポルトとすみ子を捕らえます。その直前、博士は地球防衛の切り札として、六体の特殊機能を持つロボットを完成させていました。彼は息子ロビンをロボットたちに託し、自分たちがいなくなった後も彼が正義の心を失わぬようプログラムを施したのです。ロボットたちはそれぞれ「知恵」「力」「癒し」「警戒」「飛翔」「勇気」を象徴しており、ロビンにとっては家族そのもの。幼い彼は、特に母性を模した看護ロボット・リリのもとで健やかに成長していきます。
パルタ侵略篇――少年、立ち上がる
物語前半(第1話~第26話)は、パルタ星の地球侵略と、それに抗うロビンとレインボー戦隊の戦いを中心に展開されます。 地球各地に送り込まれる怪星人たちは、時に軍事的破壊を狙い、時に人間社会に潜入して不和を煽るなど、多彩な戦術をとります。これに対しロビンたちは、地球防衛軍の支援を受けながらも、独自の判断で危機に立ち向かっていきます。ロビンの胸に輝く星型エンブレムから放たれる「ミラクルノヴァ」は切り札的な必殺技であり、一度使用すれば寿命が3年縮むという苛烈な設定が、彼の戦いを単なる勧善懲悪ではなく、痛みと覚悟を伴うものにしています。 戦いの過程で、敵の中にも葛藤する存在が現れます。皇帝の息子シーザーは、人造人間として生まれながら、人間的な感情を否定できずに苦しみ、ロビンの母すみ子に心を寄せる。その交流は、敵と味方の境界を揺さぶる象徴的エピソードとして多くの視聴者の記憶に残りました。
クライマックス――パルタ星最後の日
シリーズ中盤から終盤にかけて物語は大きな転換点を迎えます。パルタ星の崩壊が迫り、皇帝は地球侵略を加速させます。しかしその非情な方針に反旗を翻す将校や女性隊長ベラの存在が、物語に“赦し”のテーマを導入します。ロビンは自らの出生の真実を知り、敵の科学者だった父を救出するためにパルタ星へ向かうことを決意。ペガサスを中心としたレインボー戦隊は最終決戦に挑みます。 滅びゆく星の炎の中、ロビンは皇帝との直接対決に臨み、犠牲を覚悟してミラクルノヴァを放ちます。皇帝は崩れ落ち、パルタ星は静かに終焉を迎える――しかしロビンたちは辛くも生還し、罪のないパルタ市民を他の惑星へ避難させることに成功。父母との再会を果たしたロビンは涙を流しながら誓います。「宇宙に平和が続く限り、僕たちは戦い続ける」。 この壮大な終幕は、“戦うことで憎しみを断ち切る”という矛盾を抱えながらも、未来への希望を確かに残すものでした。
後半――新たな事件と心のドラマ
第27話以降は、一話完結形式でのサスペンス、コメディ、冒険などバラエティ豊かな構成となります。地球や他星で起こる異常現象、失踪事件、宇宙犯罪などにロビンたちが挑むエピソードが続き、当時としては珍しい「少年探偵SF」の味わいを帯びます。 ここでは、ロボットたちの個性がよりコミカルに描かれ、人間味あふれるやり取りが増加。特に教授とベルの漫才のような掛け合いや、リリの嫉妬と母性の揺れを描く話などが人気を集めました。また、地球防衛軍のパイロット・タイガーとの友情物語も成長譚のスパイスとなっています。彼は当初、ロボット主体の戦闘に不信を抱いていましたが、ロビンの誠実さに触れ、真の仲間として共闘するようになるのです。 後半では戦闘描写よりも心理描写や社会風刺的エピソードが増え、番組自体が“単なる宇宙戦争もの”から“人間と機械の共存を問うドラマ”へと深化していきます。
構造的テーマ――“共存と和解”の寓話
『レインボー戦隊ロビン』全体を貫くテーマは、単純な勝利ではなく“和解の可能性”にあります。敵であるパルタ人の中にも正義を信じる者が存在し、ロビンはその心を理解しようとする。人類と異星人、機械と人間、子どもと大人――そのどれもが対立と理解を繰り返しながら、物語は“異なる存在が共に生きる”という理想を追います。 これは単に1960年代の少年向け作品という枠を超え、戦後日本が直面していた“他者との共存”“科学と倫理の調和”という課題を寓話として映し出したものでもあります。ラストでロビンが見上げる星空には、戦いを終えた静けさと、未来への責任が同時に宿っています。
語り口の魅力――テンポと余韻の両立
一話あたりの展開は非常にテンポがよく、短い時間で危機の提示・解決・感情の整理が収まる脚本構造が特徴です。その一方で、セリフの行間に“余白”を残すことで、登場人物たちの心情を観る者に想像させる作りになっています。音楽の入り方も巧妙で、戦闘シーンでは勇壮なブラス、別れの場面では柔らかな弦楽が流れ、視覚的刺激に音の抑揚を合わせることで、視聴体験に深みを与えています。
結語――時代を越えて語り継がれる宇宙ロマン
こうして『レインボー戦隊ロビン』は、少年とロボット、そして地球という故郷を守るために戦った仲間たちの物語として、放送終了から半世紀を経た今も語り継がれています。そのドラマは単なるSF冒険ではなく、“異なる存在同士が理解し合うことの尊さ”を示した寓話であり、のちの『宇宙戦艦ヤマト』や『ガンダム』などの作品群に通じる“宇宙における人間の倫理”の原点の一つといえるでしょう。 白黒の画面に描かれたその光と影のドラマは、今見ても鮮烈な輝きを放ち続けています。
[anime-2]
■ 登場キャラクターについて
ロビン――“二つの血を持つ少年ヒーロー”
本作の主人公・ロビンは、地球人の母とパルタ星人の父の間に生まれた少年であり、物語の象徴的存在です。年齢は12歳前後と設定されながらも、その精神性は非常に成熟しており、作品全体の道徳的中心に立っています。彼が抱える最大のテーマは、“自らの出自をどう受け止めるか”。パルタ人という敵側の血を引くことで、常に「自分は何者か」という葛藤と向き合う構造がドラマに深みを与えています。 ロビンの特徴は、ただ勇敢な戦士であるだけでなく、思慮深く、情に厚い点にあります。時には敵をも救おうとする寛容さを見せ、また自分の判断で戦う姿勢には独立したリーダー像が見て取れます。胸の星形エンブレムから放つ破壊光線「ミラクルノヴァ」は彼の決意の象徴であり、“使えば命が削れる”というリスク設定が、少年ヒーローとしての悲劇性を強調しています。 放送当時の少年視聴者にとって、ロビンは“理想の兄貴分”でありながら、“等身大の悩みを持つ仲間”でもありました。その二面性が、物語全体に温かみとリアリティをもたらしています。
リリ――母性と優しさを体現する看護ロボット
ロビンを育てたロボット・リリは、作品の情緒面を支える重要キャラクターです。彼女は“機械でありながら母親のような存在”として描かれ、人間とロボットの関係を象徴する存在でもあります。 手のひらから放たれる「復元光線」によって、傷ついた人間やメカを癒すことができ、戦闘ではサポート役を務めるものの、戦いの合間にはロビンに寄り添い、彼の心の揺らぎを受け止める描写が多くあります。 特に印象的なのは、リリが“嫉妬”や“悲しみ”といった感情を見せる場面です。プログラムに存在しないはずの感情が芽生えることで、作品は“人間とは何か”“心とは何か”という問いを自然に観客へ投げかけています。この哲学的なテーマは、後の多くのロボットアニメ(たとえば『ドラえもん』『ガンダム』『エヴァンゲリオン』)にも通じる重要な萌芽となりました。
ペガサス――ロビンの“翼”となる万能戦闘ロボット
ロビンの移動と戦闘を担うロケット型ロボット・ペガサスは、単なるメカではなく“相棒”としての存在感を持ちます。通常は宇宙船の形をしていますが、戦闘時には高速戦闘機へと変形し、地上・水中・宇宙を自在に行き来します。最高速度は大気圏内でマッハ18、宇宙空間では光速に迫るほどの性能を持つ設定で、当時の少年たちに強烈な憧れを与えました。 またペガサスの性格づけもユニークで、忠実な従者でありながら、時折ロビンに軽口を叩いたり、状況を茶化したりする描写があります。冷静な判断力とユーモアを兼ね備えたペガサスの存在は、シリアスな展開の中で絶妙な“緩衝材”として機能し、作品のトーンバランスを整える役割を担いました。
ベル――レーダーを持つ猫型ロボット
ベルは、6体のロボットの中でも最もコミカルなキャラクターでありながら、戦隊全体に不可欠な索敵能力を誇ります。猫のような外見で、聴覚と視覚センサーは人間の3000倍。高感度のアンテナを持ち、敵の潜伏や電波妨害を感知する際には欠かせない存在です。 性格は短気でおっちょこちょい。しかしその失敗がしばしばチームの絆を深めるきっかけになる点が巧妙で、視聴者に親近感を抱かせます。特に“教授”との掛け合いは番組の定番ギャグであり、緊張と緩和を生む名コンビとして人気を集めました。ベルのような“お調子者キャラ”が戦隊の中にいることで、物語のリズムが保たれていたのです。
教授――知識の化身でありながら人間味のある長老ロボット
教授は、レインボー戦隊の知恵袋であり、戦略分析や敵の科学兵器の解析を担当します。老人の姿をした小型ロボットで、豊富な知識と冷静な判断力を持ちながらも、どこか抜けた面があり、しばしばベルとの漫才的なやり取りを見せます。 この“知的キャラクターがコミカルである”という設定は、後のアニメに多く見られるテンプレートの始祖的存在でもあります。たとえば『ドラえもん』ののび太を支えるドラえもんや、『ガンダム』のハロなど、知恵を持つ機械が人間的な愛嬌を備える発想は、この教授に端を発しているといっても過言ではありません。
ウルフ――孤高の戦士型ロボット
ウルフはクールで寡黙な戦闘ロボット。変身機能を備えており、人間の姿で潜入任務をこなすこともあります。プログラム上は“感情を持たない”設定ですが、ロビンが危険に陥ると怒りや焦りをあらわにするなど、実際には豊かな心を内包していることが示唆されています。 この“感情を持たないはずの存在が心を見せる”というドラマ構造は、アニメ史的にも非常に先進的でした。ウルフは孤独を背負いながらも、仲間のために剣を振るう姿が多くの少年たちの憧れとなり、のちの「クール系戦闘キャラ」の原型とも言われています。
ベンケイ――怪力と優しさのギャップを持つ巨体ロボット
ベンケイはその名のとおり力自慢のロボット。重量級のボディを持ち、戦隊の盾役・パワー担当として活躍します。腹部には収納スペースがあり、教授やベルを避難させるなど防御的な使い方もされています。 ただしその内面は意外にも繊細で、力しか取り柄がない自分に劣等感を抱くエピソードも存在します。ある回では、自分の失敗で仲間が危険に陥ったことを責め、山奥で“修行”に入る姿も描かれます。その後、ロビンの励ましによって立ち直るベンケイの姿は、子どもたちに「強さとは優しさを持つこと」というメッセージを印象づけました。
ポルト博士とすみ子――愛と赦しの象徴
ロビンの父・ポルト博士はパルタ星出身の科学者。かつては侵略計画の一端を担っていた人物でしたが、すみ子と出会い、愛を知り、地球を守る道を選びます。その裏切りによってパルタ皇帝に囚われるものの、彼の行動が地球とパルタ双方の未来をつなぐ鍵となりました。 母・すみ子は典型的な“昭和的母性”の象徴でありながら、受け身ではなく能動的な人物です。音楽教師としての感性を持ち、暴力や憎しみの連鎖を拒む信念を貫きます。彼女の存在は、作品にヒューマニズムの核を与え、ロビンの“優しさの源泉”として描かれました。
地球防衛軍とタイガー――大人たちの責任
ロビンたちを支援する地球防衛軍の存在は、物語に“国家と個人”というもう一つの視点をもたらします。その象徴が、エースパイロット・タイガー。初登場時の彼は少年ヒーローを軽視し、冷淡な軍人気質を見せますが、やがてロビンの勇気と信念を認め、深い友情を結ぶようになります。 第26話「パルタ星最後の日」で彼が極秘に救出部隊を率い、ポルト夫妻を救う展開は、世代や立場を超えた“協働”を象徴しています。タイガーは「大人が少年に学ぶ」という構図を体現したキャラクターであり、作品の道徳的バランスを支えています。
パルタ皇帝とその側近たち――恐怖と支配の象徴
パルタ皇帝は本作の最大の敵でありながら、単なる悪の独裁者ではありません。彼の行動原理は“民を救うための移住”という大義であり、その歪んだ愛国心が悲劇を招きます。彼の周囲には残忍な将軍、冷徹な科学参謀など多彩な悪役が存在しますが、物語が進むにつれてそれぞれの“迷い”や“人間性”も描かれていきます。 とりわけ女性隊長ベラの存在は異彩を放ちます。彼女は当初、皇帝への忠誠心に燃える戦士でしたが、ロビンの母すみ子の優しさに触れ、次第に人間らしい心を取り戻します。最終決戦では、敵でありながらロビン側に協力し、パルタ星市民の避難を助けるという自己犠牲的な行動を取ります。ベラの“裏切り”は実は“愛の選択”であり、物語全体を貫く「理解と和解」のテーマを象徴する結末となりました。
キャラクター群の総評――“機械と人間の共鳴”が描く人間ドラマ
『レインボー戦隊ロビン』の登場人物たちは、単なる役割や記号ではなく、それぞれに感情の層を持った存在として描かれています。特にロボットたちは“プログラムを超える心”を芽生えさせ、人間たちは“理性を超える情”で彼らに接する。ここにこそ本作の最大の魅力があるといえるでしょう。 友情・親子愛・犠牲・誇り――これらのテーマを、ロボットと人間の対話を通して伝える構造は、アニメ史的にも画期的でした。戦うだけでなく、笑い、悩み、愛するキャラクターたちの姿が、今なお視聴者の記憶に鮮烈に残り続けている理由です。
[anime-3]
■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング
音楽が物語る“宇宙のロマン”――本作の音楽的世界観
『レインボー戦隊ロビン』の音楽は、作品全体のトーンを決定づけた重要な要素でした。まだアニメ音楽というジャンルが確立していなかった1960年代半ばにあって、作曲家・服部公一による壮大なメロディラインと、明確なリズム構成は当時としては非常に先鋭的。彼が生み出した旋律は、科学技術と夢想のはざまを疾走する物語世界に、確固たる“宇宙的広がり”を与えました。 また、歌詞を手がけた飯島敬、小川敬一らの詩的表現は、単なる勧善懲悪の応援歌ではなく、“使命を背負う少年の心情”や“平和を願う祈り”といった深い人間的テーマを盛り込み、視聴者の心に残るものとなりました。戦いの厳しさと優しさ、希望と孤独――その二律背反を音楽で包み込む構成は、当時の他の子ども向け番組には見られない独自性でした。
オープニングテーマ「レインボー戦隊ロビン」――勇気と使命感のシンボル
第1話から第26話までのオープニングテーマとして使用された「レインボー戦隊ロビン」は、作品を象徴する楽曲です。レインボーハーモニーによるコーラスが印象的で、序盤のファンファーレ風イントロから、堂々としたマーチ調のリズムへと展開する構成は、“宇宙に飛び出すヒーロー”の高揚感を鮮やかに演出しました。 歌詞は一見シンプルながら、「闇を裂け、銀河を駆けろ」「涙を力に変えて戦え」といった表現が多く、ロビンの内面の孤独や決意を象徴的に描いています。中盤で一瞬テンポが落ちるパートでは、伴奏のトランペットとスネアが緊張を生み、視聴者の耳を引きつける。実際に放送当時、この曲を聴くと同時に子どもたちは自然とテレビの前で姿勢を正し、“戦いの始まり”を感じ取っていたと言われます。 録音技術がまだモノラル中心だった時代にしては音の分離感が良く、特にハーモニー部分の響きに温かみがあるのも特徴です。現在聴いても古びた印象がなく、むしろ昭和アニメ黎明期の音楽的完成度を象徴する一曲といえるでしょう。
新オープニング「進め! ロビン」――成長と再出発の歌
第27話以降、作品後半の主題歌として採用されたのが「進め! ロビン」です。作詞は小川敬一、作曲は引き続き服部公一が担当し、歌唱は上高田少年合唱団。少年たちの澄んだコーラスが奏でるこの曲は、前半の勇壮なテーマに比べて明るく、ややポップな印象を持ちます。 曲調は軽快な三拍子のマーチで、成長したロビンとレインボー戦隊が新たな冒険へ旅立つような感覚を呼び起こします。「涙を超えて飛び立つ勇気」「僕らの夢は虹の彼方に」というフレーズは、作品タイトルの“レインボー”を詩的に織り込みつつ、視聴者に希望を託すものでした。 この曲が変更された背景には、シリーズ後半が一話完結の明朗な冒険編へと舵を切ったことが関係しています。音楽面でも“悲壮な戦い”から“希望に満ちた探求”への移行が図られ、視聴者に作品のトーン変化を自然に伝える役割を果たしました。今日でもファンの間では、「レインボー戦隊ロビン」と「進め! ロビン」のどちらが好みかで議論が分かれるほど、印象深い二大テーマ曲です。
エンディングテーマ「ロビンの宇宙旅行」――静かな余韻と夢想
前半エピソードのエンディングを飾ったのが、「ロビンの宇宙旅行」。作詞・小川敬一、作曲・服部公一、歌唱はレインボーハーモニーによる穏やかな合唱曲です。 この曲は、オープニングの戦闘的な緊張感とは対照的に、穏やかで浮遊感のあるメロディが印象的。番組の最後に流れることで、激しい戦いの後に静寂と夢が訪れる――そんな余韻を与えました。「星のきらめき」「母の微笑み」など、ロビンの内面世界や家族への想いを感じさせる歌詞構成が特徴的です。 放送当時、この曲を聴くと“安心して眠れる”という子どもたちの感想も多く、アニメのエンディングが“子守唄”の役割を果たしていた時代ならではの温かさを感じさせます。モノクロ映像で宇宙空間を漂うペガサスのシルエットとともに流れる映像は、今でも多くのファンの記憶に残る印象的なシーンの一つです。
後期エンディング「すてきなリリ」――人間とロボットの絆を歌う
第27話以降の後期エンディングテーマは、「すてきなリリ」。前川陽子がしっとりと歌い上げたこの曲は、リリというキャラクターの優しさと寂しさを見事に表現しています。 「いつでもあなたを見つめていたい」「壊れた心もなおしてあげる」――この歌詞には、リリがロビンを支え続ける母性と、機械でありながら人間のように愛する心を持つというテーマが込められています。伴奏は穏やかなワルツ調で、アコーディオンとフルートが主旋律を支え、エンディングとしての哀愁を漂わせます。 当時としては珍しく、女性ボーカルがキャラクターの内面を歌い上げる形式で、後の“キャラクターソング”文化の原点とも言われます。リリの人気はこの曲によってさらに高まり、放送終了後も彼女を主役とした短編イラストやファンブックの特集が組まれるほどでした。
劇中BGM――戦闘と感情を支える多彩なモチーフ
劇中音楽は、主題歌とは別に服部公一が作曲した管弦楽主体のスコアが使用されています。 戦闘シーンではトランペットとティンパニの力強いリズムが鳴り響き、危機的状況を盛り上げる一方、ロビンとリリの静かな会話では弦楽器と木管が穏やかに旋律を奏でます。特筆すべきは、これらのBGMが“映像の動きに対してリズム的にシンクロする”よう設計されている点です。当時のアニメ音楽は汎用的なストック曲を使い回すことが多かったのに対し、本作は場面ごとの情緒を音で描写する“映像音楽的アプローチ”をいち早く取り入れていました。 この手法は後の東映アニメ作品にも受け継がれ、たとえば『マジンガーZ』や『宇宙海賊キャプテンハーロック』などに見られる“音と映像のドラマ的融合”の礎になっています。
ファンの記憶に残る“歌の力”
放送当時、子どもたちの間では主題歌の歌詞をノートに書き写して覚えるのが流行しました。テレビ雑誌『ぼくら』や『少年マガジン』には、主題歌の楽譜やソノシート(薄いレコード盤)が付録として付くこともあり、家庭での“再生文化”の先駆けともなりました。 また、前川陽子の「すてきなリリ」は女性ファンの共感を呼び、後に“アニメソング初期の名バラード”として再評価されました。1990年代以降には、アニメソング専門番組やCDボックス企画で本作の楽曲が取り上げられ、令和の現在でもインターネット上でリマスター音源が共有されるなど、息の長い人気を保っています。
音楽が与えた遺産――アニメソングの源流として
『レインボー戦隊ロビン』の音楽は、単に番組を彩る要素ではなく、“アニメソング文化の夜明け”における基礎石の一つでした。少年合唱団や混声コーラスを積極的に取り入れ、歌で“勇気”と“悲しみ”の両方を描いたこの作品は、のちの『魔法使いサリー』『タイガーマスク』『宇宙戦艦ヤマト』などへと受け継がれる“主題歌=物語のもう一つの語り手”という考え方を定着させました。 音楽がストーリーと感情を結びつけ、視聴者の心に“ロビンの勇気”を残した――それこそが、この作品の音楽面における最大の功績です。
[anime-4]
■ 声優について
黎明期のアニメ声優たちが築いた“表現の原型”
1960年代半ば、アニメーションというメディアがテレビで定着し始めた頃、声優という職業はまだ明確な認知を得ていませんでした。『レインボー戦隊ロビン』は、そうした“声の俳優”たちが自らの表現を模索していた時期に制作された作品であり、その声の芝居には“新しい演技の模範”が多く見られます。舞台俳優やラジオドラマの出身者が中心だった当時、アニメ特有のタイミングやテンポに合わせたセリフ回しは難題でしたが、本作のキャスト陣はそれを見事に克服し、アニメ的誇張と実写的リアリズムの中間を確立していきます。
ロビン役・里見京子――少年役に宿る“澄んだ強さ”
主人公ロビンを演じたのは、当時まだ若手だった里見京子。女性声優が少年役を演じるスタイルが定着するのは後年のことですが、その先駆け的存在が彼女でした。 里見の声には高音域に独特の透明感があり、決して力で押さず、息の混じった柔らかさで“強いけれど優しい”少年像を作り上げています。感情表現の起伏は大きすぎず、淡々とした語りの中に決意や哀しみを滲ませる演技は、後のアニメ少年主人公像――たとえば『未来少年コナン』や『ガンダム』のアムロなど――のルーツとも言えます。 特に印象的なのは、パルタ星最終決戦の回。仲間を鼓舞しながらも声が微かに震え、恐れと覚悟が同居する“声の中のドラマ”が視聴者の胸に残りました。技術としての演技ではなく、魂の響きとしての少年像を表現した希少な例です。
リリ役・新道乃里子――母性と情感を声で描く
リリ役の新道乃里子は、舞台出身の女優として発声が非常にしっかりしており、柔らかな声質の中に説得力のある抑揚を持っています。 彼女のリリは、母親のように優しいだけでなく、時に強く、そしてユーモラス。ロビンに対して叱責する場面では少し鼻にかかったトーンを使い、甘やかす場面では囁くように声を落とす――その細やかな“声の温度差”がキャラクターのリアリティを生みました。 また、彼女は歌唱にも長けており、エンディングテーマ「すてきなリリ」においてはセリフでは見せない情感を歌声で表現しています。機械でありながら母性を持つというリリの複雑な存在を、声の表情で完璧に体現した稀有な演技でした。
ウルフ役・桜井英一――低音の哀愁で描く“孤高のロボット”
桜井英一のウルフは、当時のアニメでは珍しい“低音で寡黙なキャラクター”。彼の声は決して怒鳴らず、むしろ抑えたトーンでセリフを刻むように語ります。そこには“戦士の孤独”がにじみ、冷たく聞こえる声の奥に情熱が宿っているのが特徴です。 あるエピソードでロビンを庇って敵の爆撃を受ける場面では、セリフがほとんどなく“うなり声”と“息”だけで感情を伝える演技を見せました。これは台本を超えたアドリブであり、声だけでキャラクターの魂を表現するという、アニメ演技の新たな領域を切り拓いた瞬間でもあります。 後年、アニメ評論家の中には「ウルフの声にこそ、初期アニメのリアリズムがあった」と評価する者もおり、桜井の存在は今なお語り継がれています。
ベル役・中村恵子――軽妙なテンポとユーモアのセンス
猫型ロボット・ベルを演じた中村恵子は、コミカルな間合いの取り方に定評のあるベテラン声優。明るく甲高い声が特徴で、発声のテンポが非常に速い。ギャグシーンではセリフを早口気味に重ねながらも滑舌が崩れず、聴き取りやすいのが持ち味でした。 彼女のベルはおしゃべりでお調子者ですが、単なるギャグキャラに留まらず、仲間思いの一面も持っています。その切り替えを声で明確に示すために、中村は収録中に“笑い声のトーン”を4種類使い分けていたといわれます。高笑い、照れ笑い、呆れ笑い、安心の笑い――それぞれに音程とリズムを設定し、同じキャラの中で感情の変化を聴かせる高度な演技が行われていました。
教授役・八木光生――コミカルと知性の融合
教授役の八木光生は、声優界でも早くからアニメに携わった人物で、ラジオドラマの経験が豊富でした。彼の演じる教授は、賢者でありながらどこか抜けた老人。八木はこの二面性を演技で巧みに両立させました。 具体的には、説明台詞では口を閉じ気味に低音で語り、ギャグシーンでは一転して高音で鼻に抜けるような声に切り替える。これにより、知性とユーモアの対比が強調され、子どもたちにとって“怖くない博士”として親しみやすいキャラクターとなりました。 教授の「まったくベルめ、また失敗か!」というお決まりのセリフは、作品を代表する名フレーズの一つとなり、八木の声そのものが“レインボー戦隊ロビンの笑い”を象徴する存在になっています。
ベンケイ役・篠田節夫――力強さの中に宿る温かみ
巨体ロボット・ベンケイを演じた篠田節夫は、演劇畑出身で、舞台的な発声を活かしたダイナミックな声が特徴でした。彼の声は低く太いが、どこか柔らかく、人間味がある。怒鳴るようなセリフでも、子どもが怖がらない“優しい重低音”を意識していたといいます。 特に「俺は力しかない…でも、みんなの盾になる」というセリフには、篠田の包容力がにじみ出ていました。演技の幅広さは戦闘シーンよりも日常回で顕著で、食事や修理のシーンではコメディリリーフとしても活躍。篠田は声だけで“重量感”を表現するために、マイク前で体を揺らしながら発声するという独自のテクニックを使っていたといわれています。
ポルト博士とパルタ皇帝――同じ声が描く“父と敵”の二面性
興味深いことに、ポルト博士とパルタ皇帝はどちらも篠田節夫が兼任していました。 これは制作側の意図的なキャスティングで、ロビンの父と敵の象徴が同じ声で語られることで、“血の繋がり”や“宿命の鏡像”を音で表現する狙いがありました。篠田は博士を穏やかな低音、皇帝を咽頭を絞るようなドスの効いた声で演じ分け、その対比によってドラマの緊張感を際立たせました。 この二役演技は放送当時のファンの間でも話題となり、「同じ声なのに別人に聞こえる」と驚きの声が寄せられました。アニメ史的に見ても、同一声優による善悪両役の演じ分けは極めて早い例であり、声優という職業の多面性を示した象徴的な事例とされています。
タイガー役・三田松五郎――熱血と冷静の狭間
地球防衛軍のエースパイロット・タイガーを演じた三田松五郎は、正統派の“熱血系”声優でした。彼の声は太く通りが良く、軍人らしい威厳を備えつつも、ロビンに心を開く過程で柔らかさが増していく。初登場回と終盤では声のトーンが明らかに変化しており、その演技の成長がキャラクターの心理変化を自然に伝えています。 第26話での「子どもだからこそ、信じる力があるんだな」という一言は、三田の静かなトーンの中に深い感情が込められており、名台詞として知られています。
女性キャラと脇役たち――声のバリエーションが広げた世界観
女性キャラクターでは、新道乃里子以外にも複数の女優が兼役で出演しており、通信士や地球防衛軍員、パルタの女性隊員などを一人で何役も演じ分けていました。これにより作品世界に“音の多層性”が生まれ、白黒映像でもキャラクターの区別が明確に伝わるよう工夫されていました。 また、ナレーションは重厚な男性アナウンサー風の声で進行され、視聴者に“毎週の物語朗読”のような安心感を与えていました。彼の落ち着いた語り口が、宇宙を舞台にした壮大な物語に威厳をもたらしていたのです。
当時の収録環境と技術的背景
1960年代のアニメ収録は、まだ一発録り(アフレコ一斉録音)が主流で、ノイズ対策も不十分でした。にもかかわらず、『レインボー戦隊ロビン』の音声は明瞭で臨場感があります。 声優たちはマイク一本を囲み、立ち位置や体の向きで距離感を表現。感情の高ぶりに合わせてマイクに近づいたり離れたりすることで、簡易的ながら“立体音響的演出”を生み出していました。こうしたアナログな手法が、逆に“生々しい人間味”を強調する結果となり、本作独自の温かみを持つサウンドトラックを形成したのです。
後世への影響――声優文化の始まりを告げた作品
『レインボー戦隊ロビン』のキャスト陣は、後の声優界に多大な影響を与えました。少年を女性声優が演じる慣習、メカや動物キャラに個性的な声を与える発想、同一声優による多役演技など、本作で確立された手法はその後のアニメ演出の礎となりました。 また、放送当時のファンから寄せられた声援ハガキには「声で泣けた」「声だけで心が伝わった」といった感想が多く、視覚以上に“声”が感情を運ぶメディアであることを証明しました。 本作は単なるSFアニメではなく、“声の力で物語を生かす”という理念の始まりであり、まさに日本の声優文化黎明期を彩った金字塔のひとつなのです。
[anime-5]
■ 視聴者の感想
放送当時――“ロビンごっこ”に熱中した子どもたち
『レインボー戦隊ロビン』が放送された1966年当時、日本は高度経済成長のただ中にあり、家庭にカラーテレビが少しずつ普及し始めていた頃でした。そんな時代に白黒ながらもスケールの大きな宇宙冒険を描いた本作は、子どもたちにとって未知の世界への窓でした。 当時の少年誌のアンケート欄には「ロビンのように勇気を出して戦いたい」「ペガサスに乗って宇宙を飛びたい」といった声が多く寄せられています。特に印象的だったのが、ロビンが発する「ミラクルノヴァ!」の掛け声。学校の校庭では「ロビンごっこ」が流行し、紙で作った星型バッジを胸に貼って遊ぶ姿が全国で見られたと言われます。 また、ロボットたちの個性豊かなやり取りも人気で、「教授とベルのケンカが面白い」「リリがかわいくて好き」という感想も目立ちました。家庭向け雑誌『少年ブック』の特集では、「戦隊ものなのに、ロビンが一番泣くヒーロー」という子どもの言葉が紹介され、当時の少年たちが“勇気とは泣かないことではない”と自然に学んでいたことを示しています。
親世代の共感――“戦わない優しさ”に感動
本作は、子ども向け番組でありながら、親世代からの支持も非常に高かった作品でした。戦争の記憶がまだ生々しい時代に、「敵にも正義がある」「暴力より理解を」というメッセージが込められていたことが、多くの大人たちの共感を呼んだのです。 新聞の視聴者欄には、「息子と一緒に観ているが、大人にも考えさせられる内容だ」「ロビンが敵を倒すよりも話し合おうとする姿が立派」といった投書が寄せられています。特に母親層の支持は厚く、リリの母性やロビンの思いやりのある言動が“理想の家族像”として受け止められました。 当時の社会は科学技術の進歩が急激で、ロボットや宇宙開発に対する不安も少なくありませんでした。そんな中で本作が示した「科学は人の心を失ってはならない」という主題は、子ども番組を超えた社会的メッセージとして、多くの家庭の茶の間に響いたのです。
再放送世代の発見――“懐かしさの中の哲学”
1970年代後半から80年代初頭にかけて、『レインボー戦隊ロビン』は地方局やケーブル放送で再放送され、当時の新しいアニメファンたちに再発見されました。カラーアニメが主流になった時代にあって、モノクロ映像の持つ静けさや線画の繊細さが“逆に新鮮”と評されました。 再放送世代の感想では、「白黒なのに色を感じた」「台詞が少なくても感情が伝わる」「一話ごとに考えさせられる」という声が目立ちます。特に、宇宙戦争や異星人との対立を描きながらも“共存”をテーマに据えた点が評価され、当時のアニメ雑誌『アニメージュ』でも“日本的ヒューマニズムSFの原点”と紹介されました。 また、当時大学生だったアニメ研究グループの中には、この作品を“日本初の戦隊アニメにして哲学的アニメ”と分析する論文も存在します。彼らは、ロビンの自己犠牲的行動や敵キャラの内面描写を、戦後日本人の倫理観の変遷と重ねて読み解き、のちの『ヤマト』や『ガンダム』との精神的つながりを指摘しました。
平成期の再評価――アーカイブ文化の中で蘇る名作
1990年代、LD-BOXやVHSによるアニメ復刻ブームの中で、『レインボー戦隊ロビン』は再び脚光を浴びます。当時のファン層は、リアルタイム世代よりもむしろ“アニメ史研究”の文脈から本作に興味を持つ人々でした。 「ロビンは子ども向けに見えて、実は大人向けの寓話だ」と語る評論家が多く、特に音楽と演出のクオリティが改めて評価されました。アニメ専門誌『OUT』では「白黒期のアニメにおける演出完成度No.1」と称され、作画監督・高橋信也の人物デザインも再評価の対象となりました。 さらに、平成初期には“戦隊ヒーローの元祖”としてテレビ特集で紹介され、若い世代のファンが「戦うヒーローが泣くことの意味」を改めて理解するきっかけにもなりました。ネット掲示板が登場した2000年代初頭には、「リリの台詞に救われた」「教授の声を真似していた」など、個々の思い出が語られるようになります。懐古だけでなく、“作品を通じて育まれた人生観”として語るファンが増えたのも特徴的です。
現代の視聴者――デジタル時代に再発見される“優しさのヒーロー像”
2020年代、動画配信やアニメアーカイブプロジェクトの進展により、『レインボー戦隊ロビン』はYouTubeやBSチャンネルなどで手軽に視聴できるようになりました。新しい世代のアニメファンがこの作品を観てまず驚くのは、“60年代作品なのに古臭く感じない”という点です。 SNS上では、「セリフが少なくても伝わる演出がすごい」「敵が単なる悪じゃないのが深い」「白黒なのに表情が豊か」という感想が多く見られます。また、AIやロボットとの共存が現実的テーマとなった現代において、リリや教授といったキャラクターが“人間と機械の倫理”を早くも提示していたことが改めて注目されています。 さらに、LGBTQ+的観点からの再解釈も行われており、「ロビンの“二つの血”という設定はアイデンティティの多様性を象徴している」と語る若い評論家もいます。半世紀を超えた今もなお、多様な価値観の鏡として機能している点が、本作の普遍性を物語っています。
ファンの証言――“この作品があったから今の自分がある”
2020年代のアニメファンのインタビューでは、「幼い頃に観たロビンの言葉が、今でも心の支えになっている」という声が多く聞かれます。 ある60代のファンは、「子どもの頃、ロビンが敵を許す姿を見て、“怒らなくてもいいんだ”と知った」と語ります。別の視聴者は、「リリが“泣いてもいいのよ”と言う場面が忘れられない。あの一言で救われた」と述懐しています。こうしたエピソードは、アニメが単なる娯楽を超え、人生の“倫理の教材”となりうることを証明しています。 若い世代の感想でも、「古い作品なのにキャラがリアル」「ロビンが“地球人の味方”ではなく“宇宙の調停者”であるところが現代的」といった視点が増えています。つまり、世代を超えて“自分を重ねられる主人公像”としてロビンが受け止められているのです。
批評的視点――感情の節度と構成美
アニメ評論家の間でも、『レインボー戦隊ロビン』の感情表現は高く評価されています。多くの60年代作品がセリフやナレーションで感情を説明していたのに対し、本作は“沈黙”を活かした演出で感情を浮かび上がらせていました。そのため、視聴者は“感じるアニメ”として物語を体験し、心に長く残る印象を受けたといいます。 また、音楽と声のバランスも絶妙で、セリフが少ない分、声優の抑揚や息づかいが強調され、作品全体が“音の詩”として記憶されているのも特徴です。批評家の一人は「この作品を観ると、昭和の子ども番組に“芸術性”があったことを思い出す」と述べています。
現代へのメッセージ――“戦うより理解する勇気”
視聴者の感想を通して浮かび上がるのは、“戦うことよりも理解する勇気”という普遍的なメッセージです。ロビンが敵を憎まず、手を差し伸べようとする姿は、いまの社会にも通じる人間的理想を描いています。 暴力よりも共感を、対立よりも対話を――このテーマが視聴者の心に残り続ける理由こそ、作品の価値を時代を超えて証明しているといえるでしょう。『レインボー戦隊ロビン』は、戦うヒーローの物語でありながら、“優しさを守る物語”でもあったのです。
[anime-6]
■ 好きな場面
ミラクルノヴァを放つ瞬間――命を削る光の決意
多くの視聴者がまず心に残るのは、ロビンが必殺技「ミラクルノヴァ」を放つ場面でしょう。胸の星型エンブレムが眩く輝き、空間全体が白光に包まれるその瞬間、音楽が止まり、わずかに風の音だけが響く。やがて静寂を破って炸裂する光線――しかしそこには、勝利の快感よりも“痛み”が宿っています。 この技を使えば、ロビンの寿命が三年縮むという設定は、単なる演出ではなく“命を懸ける勇気”そのものを象徴していました。戦うことは生きることを削ること――その重みを少年ヒーローに背負わせた脚本の深さは、今見ても胸を打ちます。 特に第13話「地球の終わりを見た日」では、仲間を救うためにミラクルノヴァを迷いなく放つロビンの姿が描かれ、視聴者の間で「ヒーローの涙が一番美しい回」と語り継がれています。光の中で彼が一瞬だけ笑う演出は、命の消耗を“誇り”として昇華させた芸術的瞬間でした。
リリの祈り――人間と機械をつなぐ涙
もうひとつ忘れがたいのが、第18話「リリの祈り」における感動的なシーンです。ロビンが戦闘中に重傷を負い、ペガサスのエンジンも損傷して動けなくなったとき、リリは一人残されて星空に向かって祈りを捧げます。 「神様、もし私に心があるなら、どうかロビンを助けてください」――この台詞のわずかな震えが、視聴者の胸を締めつけました。プログラムされた機械が“祈り”を捧げるという設定は、人工知能の概念すら存在しなかった当時としては驚くほど先進的。 音楽も見事で、バックに流れるオルガンとハープの静かな旋律が、まるで聖堂の祈りのような神聖さを漂わせます。翌週、このシーンを観た小学生の投稿が雑誌『ぼくら』に掲載され、「リリが泣いたのが人間より人間らしかった」と評されたほどでした。 この場面は、“機械にも心がある”というテーマを超えて、“優しさとは理屈を超えた行為”であることを伝えた名シーンといえます。
パルタ星の最期――滅びゆく星に響く赦しの言葉
第26話「パルタ星最後の日」は、シリーズ前半のクライマックスであり、今なおファンの間で語り継がれる伝説的な回です。 滅亡が迫るパルタ星に乗り込んだロビンは、父・ポルト博士を救い出し、皇帝との最終対決に挑みます。皇帝は「我が民を救うためには地球を滅ぼすしかない」と叫びますが、ロビンは静かに言葉を返します。 「あなたも僕も、同じ宇宙の子どもだ。憎しみの中で生きていては、どんな星も救えない」 その瞬間、皇帝は動きを止め、崩れ落ちながら「ロビン…お前の目には、かつての私がいる」と呟く――この静かなやり取りの中に、“敵と味方の境界を超えた赦し”が描かれています。 作画的にもこの回は群を抜いており、滅びゆく星の炎がモノクロ画面に白銀のように輝く。その幻想的な美しさが、視聴者に強烈な印象を残しました。放送当時の視聴者の多くが「泣いた」と語り、後年も「昭和アニメ史上、最も静かなクライマックス」と評されるほどです。
教授とベルの名コンビ――笑いが生んだ“人間味”
シリアスなドラマの中で、ひときわ心を和ませたのが教授とベルの掛け合いシーンです。 特に第15話「ベルの大発明」では、教授がベルの修理を失敗して機嫌を損ねる一幕が描かれます。ベルが「もう知らない!」とふてくされて飛び出し、教授が慌てて追いかける姿に、視聴者からは笑いとともに「仲のいい親子みたい」との感想が寄せられました。 この軽妙なやり取りは、作品に“生活の匂い”を与え、ロボットたちが単なる兵器ではなく“個性を持つ存在”として受け止められる大きな要因となりました。戦闘と日常のバランスを取る脚本構成の妙も、当時としては非常に斬新でした。 笑いは単なる緩和ではなく、登場人物たちの“生きている証”として機能していたのです。
タイガーとロビンの握手――世代を超える友情
第20話「宇宙の友情」では、ロビンと地球防衛軍のパイロット・タイガーの関係が描かれます。 当初、タイガーは「子どもに戦争が分かるか!」とロビンを見下していましたが、共闘を経て次第に彼を認めるようになります。終盤で、戦いを終えた二人が沈む夕陽を背に無言で握手する場面――ここに言葉は一切ありません。BGMもなく、ただ風の音と二人の息づかいだけが聞こえる。 この静寂こそ、信頼が言葉を超えた瞬間でした。視聴者の間では「この1分の沈黙こそ本当の友情だ」と評され、後のアニメ『巨人の星』や『ガンダム』などの“無言の和解”シーンの原型とも言われています。
ロビンの微笑み――最終話「虹の果てに」
最終回「虹の果てに」で、ロビンは再び宇宙へ旅立ちます。滅びゆく星々を見送りながら、「人は争いをやめられるのだろうか…」と呟くロビン。その表情は悲しみではなく、どこか穏やかな笑みを浮かべています。 彼の背後でリリが静かに「帰ってくる日を信じている」と語り、画面には虹が浮かび上がる。白黒映像の中にわずかな光のグラデーションで虹を表現する演出は、アニメ史上でも屈指の名ラストとして知られています。 この結末に多くの視聴者が涙しました。明確な勝利も敗北も描かれず、“未来への問い”を残して終わる構成は、当時の子ども番組としては異例の哲学的幕引き。後年のファンからは「この終わり方があるから、何度見ても新しい」と評され、アニメ史の中でも稀に見る“永遠の余韻”として語られています。
演出の妙――“沈黙”と“間”が生む感情
これらの名場面に共通するのは、派手な演出ではなく“間”の使い方の巧みさです。セリフを削り、動きを抑え、音を止める――そうすることで視聴者自身に想像させ、感情を引き出す。この“沈黙の演出”は、監督・木村廉が意図的に用いた手法であり、後の日本アニメーション全体に影響を与えました。 子どもたちが無意識に“感情を読む訓練”をしていたという点で、『レインボー戦隊ロビン』は教育的でもあり、芸術的でもあったのです。
視聴者が語る“心に残る瞬間”
近年、SNSやファンサイトで「あなたの好きなロビンの場面は?」というアンケートが行われた際、最も多かった回答は以下の3つでした。 1. ミラクルノヴァを放つ前のロビンの横顔 2. リリが涙を流す祈りのシーン 3. タイガーとの無言の握手 これらはいずれも“戦い”ではなく“感情”を描いた瞬間です。視聴者はそこに自分の経験や記憶を重ね、何十年経っても“あの時の気持ち”を思い出せるのです。 『レインボー戦隊ロビン』は、派手なアクションよりも“静かな人間ドラマ”によって感動を与えた稀有なアニメであり、その“好きな場面”の多くが静止と沈黙の中に存在するという事実が、この作品の本質を物語っています。
[anime-7]
■ 好きなキャラクター
主人公ロビン――“優しさを武器にするヒーロー”
『レインボー戦隊ロビン』を語る上で、まず外せないのが主人公・ロビンです。彼は決して万能のヒーローではありません。時に迷い、傷つき、涙を流す――しかし、その弱さこそが彼の最大の魅力でした。 放送当時、少年誌のアンケートでは常に人気1位。ファンの感想には「ロビンの泣き顔が一番かっこいい」「怒るよりも考えるところが好き」といった言葉が多く並びます。彼が見せる“静かな勇気”は、戦うことが強さではなく、理解することこそ真の強さだと教えてくれるものでした。 ロビンはパルタ星人と地球人のハーフという設定で、当時としては非常に斬新な“多文化的ヒーロー”。この出自の複雑さが、彼の優しさと孤独を同時に生み出しており、多くの視聴者が自分の中の“異質さ”や“葛藤”をロビンに投影しました。 また、声を担当した里見京子の柔らかく澄んだ声が、ロビンの繊細な心情を支えています。決して怒鳴らず、常に穏やかに語りかける声のトーンが、彼の人間的な温かさを際立たせていました。戦うヒーローが“声で癒す”という構造は、後の日本アニメ全体に通じる革命的な表現です。
リリ――“機械でありながら最も人間らしい存在”
ファンの間で最も人気が高い女性キャラクターが、看護婦ロボットのリリです。彼女は、ロビンを育てた母代わりでありながら、一人の“女性”としても描かれました。 その魅力は、機械でありながら感情を持ち、人間以上に繊細な心を見せる点にあります。ロビンが傷ついた時、彼女の瞳が一瞬うるむ――そのわずかな作画の変化だけで視聴者は涙しました。リリは涙を流さない代わりに、声の震えや沈黙で“悲しみ”を表現する存在なのです。 視聴者の中には、「リリに初めて“恋”を感じた」という男性ファンも多く、当時のアニメ誌『ぼくらマガジン』の人気投票では、女性キャラ部門で1位を獲得。彼女の包容力と優しさは、“理想の母”であり“初恋の人”でもありました。 さらに、エンディング曲「すてきなリリ」はファンの心に深く刻まれ、彼女のキャラクター性を音楽でも強く印象づけています。リリは“ロボットとしての完成度”ではなく、“人間らしさの完成度”によって愛された、時代を超えるヒロインなのです。
教授――“お調子者の中の賢者”
コミカルなキャラクターとして人気を集めたのが、レインボー戦隊の頭脳・教授です。小柄な体、長いヒゲ、そして少し高めの声――彼は“おじいちゃんのような安心感”を持つ存在でした。 しかし単なるギャグキャラではありません。科学的な知識を駆使し、ロビンや仲間を幾度も救ってきた功労者であり、戦闘中でも冷静に判断を下すリーダーシップを持っています。 視聴者の間では「ベルとのやり取りが最高」「叱られてもすぐ立ち直る教授が好き」といった感想が多く、彼の人間臭いリアクションが作品の温度を上げていました。とくに第15話「ベルの大発明」で見せた、“失敗しても諦めない姿勢”は子どもたちに勇気を与えた名エピソードとして語り継がれています。 教授は、後年のアニメに登場する“知識人でコミカルな老人キャラ”の原型でもあり、『ドラえもん』の野比のび太のパパや『Dr.スランプ』の則巻千兵衛などにも通じる“人間味ある賢者像”を確立しました。
ベル――“作品のリズムを担うムードメーカー”
猫型レーダーロボット・ベルは、作品の中で最も“子ども人気”が高いキャラクターでした。猫のような仕草とツンデレ気質が愛らしく、いたずら好きで短気なのに、どこか憎めない存在です。 視聴者の間では「ベルが出ると場面が明るくなる」「叱られてもすぐ笑うところが好き」という声が多く寄せられました。特に教授とのコンビは、作品のユーモアを支える重要な柱であり、緊迫した戦闘シーンの後に二人のやり取りが入ることで、物語全体が自然に呼吸を取り戻すような構成になっていました。 ベルはまた、“女性的でも男性的でもない中性的キャラ”としても注目されました。声のトーンや表情の演出に柔らかさがあり、時代を先取りした“ジェンダーフリー的存在”として現代のファンからも再評価されています。
ウルフ――“孤高の戦士に宿る友情”
戦闘ロボット・ウルフは、クールで寡黙なキャラクターとして男性ファンに根強い人気を誇ります。彼は任務に忠実で、感情を表に出さない。しかしロビンが危険に陥ると、即座に体を張って守る――その行動が無言の友情を語っています。 特に第22話「ウルフの影」では、敵の罠にかかって自爆覚悟でロビンを救う姿が描かれ、「あの回で初めてアニメで泣いた」という声が多く寄せられました。 視聴者がウルフに惹かれる理由は、“言葉よりも行動で示す”という武士的美学にあります。彼の存在は、後の『宇宙戦艦ヤマト』の古代守や『ガンダム』のランバ・ラルなど、“沈黙の戦士”系キャラの源流とも言われています。
ベンケイ――“力の中にある優しさ”
巨体で怪力、しかし誰よりも心が優しい――それがベンケイです。彼は戦闘では無敵のパワーを発揮しますが、仲間に怪我をさせてしまったときには子どものように落ち込み、「力があるのに怖がられるのが嫌なんだ」とつぶやく繊細な一面を持っています。 ファンからは「ベンケイの涙が忘れられない」「強いのに一番優しい」といった声が多く、単なる力自慢ではなく“心を持つ巨人”としての存在感が際立っています。 このキャラクター像は、後のロボットアニメに多大な影響を与えました。たとえば『機動戦士ガンダム』のガンタンクや『ボルトロン』のハンクなど、“強くて泣くキャラ”の原点とされています。
ポルト博士――“科学と愛の狭間で揺れる父親像”
ロビンの父であるポルト博士も、多くの視聴者にとって忘れがたい存在です。彼はパルタ星の科学者として地球を侵略する任務を負いながら、人間の優しさに触れて心を変えていきます。その内面的葛藤が、作品全体の“道徳的支柱”となっていました。 博士の魅力は、科学者としての冷静さと父親としての情愛の両立にあります。ロビンに直接会えなくても、彼の成長を信じて装置越しに見守る場面では、静かな涙が光ります。 ファンの中には「ポルト博士の苦しみは、時代を超えた“親の愛”だ」と語る人もおり、特に親世代の支持が厚いキャラクターです。彼の存在が、物語を単なる冒険活劇ではなく“家族愛の物語”へと昇華させました。
パルタ皇帝――“悪役でありながら哀しみの象徴”
忘れてはならないのが、本作の宿敵・パルタ皇帝です。冷酷で傲慢な支配者として描かれる一方、彼の行動原理は“滅びゆく民を救うため”という悲壮なもの。敵でありながら、彼もまた救われたい存在として描かれています。 視聴者の間では、「悪人なのに泣けた」「最後のセリフで許せた」という感想が多く、単なる悪役を超えた“悲劇の王”として記憶されました。皇帝を演じた篠田節夫の低く響く声は、威厳と孤独を見事に両立させ、後のアニメ悪役像に大きな影響を与えました。
ファンが選ぶ“永遠の推しキャラ”
近年のアンケートでは、人気キャラクターランキングの上位は次の通りです。 1位:ロビン(主人公としての誠実さと人間味) 2位:リリ(母性と恋愛の両面性) 3位:ウルフ(沈黙の中の友情) 4位:教授(ユーモアと知恵の象徴) 5位:ベンケイ(力と優しさの調和) これらの順位からも分かるように、ファンは“心の深さ”を持つキャラクターを好んでいます。単に強い・美しいという要素よりも、“人としてどう生きるか”を感じさせる人物像が支持されているのです。
キャラクターの多様性が生んだ普遍性
『レインボー戦隊ロビン』のキャラクターたちは、それぞれが異なる価値観を体現しています。ロビンの優しさ、リリの愛、ウルフの忠義、教授の知恵、ベンケイの包容力――それらが虹の七色のように共存して初めて“レインボー戦隊”が成り立つ。 この“多様な個性が協力するチーム”という構図は、後の『サイボーグ009』や『スーパー戦隊シリーズ』に受け継がれました。視聴者が誰か一人に感情移入できる構造は、まさにこの作品が“キャラクター群像劇の始まり”であることを示しています。 ファンは今でも、「ロビンたちは自分の心の中にいる」と語ります。それぞれのキャラクターが、視聴者の人生のどこかに寄り添って生き続けている――それが『レインボー戦隊ロビン』という作品の最大の奇跡なのです。
[anime-8]
■ 関連商品のまとめ
映像関連――VHSからBlu-rayへ、50年を越える復刻の歩み
『レインボー戦隊ロビン』の映像ソフト展開は、日本のアニメ保存史を語る上でも欠かせません。 最初に映像商品として登場したのは1983年、東映ビデオから発売された傑作選VHS『TVヒーローシリーズ レインボー戦隊ロビン』(全4巻)でした。当時、家庭用ビデオデッキが普及し始めた時期であり、ファンにとっては“テレビ放送を自宅で見返せる”初の機会となりました。パッケージには石森章太郎(当時は石ノ森章太郎)の原画を基にした描き下ろしイラストが使用され、モノクロ作品でありながらデザイン的に非常に洗練された仕上がりでした。 1990年代に入ると、東映ビデオはLD(レーザーディスク)版を全6巻でリリース。1枚あたり8話前後を収録したこのシリーズは、アニメコレクターの間で高い人気を誇り、現在も中古市場では1セット5万円前後で取引されています。 そして2000年代に入り、DVD-BOX第1弾(全24話収録)が2015年8月5日に、第2弾が同年9月9日に発売されました。音声はモノラルながらノイズリダクション処理が施され、白黒映像の階調が見事に再現されています。特典にはブックレット、キャラクターデザイン設定資料、スタッフインタビューなどを収録。昭和期アニメの復刻としては破格の内容でした。 2020年代には一部配信サービスでデジタルリマスター版が配信されており、HD画質で鑑賞できる環境も整いつつあります。モノクロ映像の“光のコントラスト美”を最新技術で蘇らせたことに、多くのファンが感涙したといいます。
書籍関連――漫画版と資料集が示す“創作の裏側”
『レインボー戦隊ロビン』は、放送に先立ち『週刊少年マガジン』(1965年1月1日号~3月28日号)で漫画版が連載されていました。作画は風田朗、原案協力にはスタジオ・ゼロの面々が関わっており、アニメよりもややハードなSF色を持つ作風でした。 この漫画版は長らく単行本未収録でしたが、2000年代に入ってから復刻版が一部ファン出版レーベルやオンデマンド印刷で再販され、コレクターズアイテムとなっています。初版本は古書市場で1冊1万円を超えることもあり、希少性の高さから“幻の前史”と呼ばれるほど。 書籍として特筆すべきは、東映動画監修によるムック本『アニメの記憶 レインボー戦隊ロビン編』(2015年・東映ビデオ付属冊子)です。制作当時の台本複写、スタッフメモ、未公開スチルが収録されており、研究資料としての価値が極めて高い。 さらにアニメ史を扱う一般書でも本作の影響は頻繁に言及されており、『日本アニメーションの夜明け』(講談社現代新書)では「戦隊フォーマットの原型」として分析されています。石ノ森章太郎、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄らが共同で原案に関わった唯一のテレビシリーズという点で、アニメ研究者からの注目も絶えません。
音楽関連――服部公一の宇宙交響と主題歌の魅力
音楽面では、服部公一による荘厳で幻想的なスコアが作品のトーンを決定づけました。 オープニングテーマ「レインボー戦隊ロビン」(歌:レインボーハーモニー)は、力強い行進曲調の中に柔らかいストリングスが流れ、“未来への希望”を象徴する旋律としてファンに親しまれています。一方、第27話以降の新主題歌「進め!ロビン」(歌:上高田少年合唱団)は少年の純粋さを前面に出し、作品の方向転換を音楽的にも示しました。 エンディング曲「ロビンの宇宙旅行」や「すてきなリリ」は、静謐でメロディアスな作風が特徴で、1960年代の子ども番組とは思えないほど情緒豊か。これらの楽曲は1995年に発売された『東映TVヒーロー主題歌大全集』に初めて収録され、後年には単独CD『レインボー戦隊ロビン 音楽大全』(2016年・日本コロムビア)としてリマスター版がリリースされました。 レコードコレクターの間では、当時のEP盤(ソノシート版を含む)が高額で取引され、特に封入ポスター付き初版は1万円を超えることもあります。
ホビー・おもちゃ――黎明期のロボット玩具文化
放送当時、まだアニメキャラクターグッズ市場が確立していなかったにもかかわらず、『レインボー戦隊ロビン』は玩具展開が比較的充実していました。 マルサン商店から発売された「ロビン号ペガサス号ブリキモデル」は、発射ギミック付きのぜんまい式で、当時の男の子の憧れの的でした。また、バンダイ(当時の三井グループ系列)からは、6体のロボットをデフォルメしたミニソフビシリーズが登場。ベル、教授、ウルフ、リリ、ベンケイ、ペガサスがそれぞれ独立したパッケージで販売され、現在はコンプリート状態で5万円以上の価値があります。 さらに紙芝居やぬりえ、プラカード玩具など、家庭向けの低価格グッズも多数展開。特に“ロビンの星バッジ”は、玩具店の常連商品として長く愛されました。こうしたアイテム群は、後の『ウルトラマン』『仮面ライダー』などに見られる“キャラクター商業化”の流れを先取りした存在でもあります。
ゲーム関連――未公認ながら続く“伝説的存在”
正式なテレビゲーム化は行われませんでしたが、1980年代のアニメ復刻ブーム期には、ファンが制作した非公式ボードゲームやトランプなどが流通しました。 また、PC-9801用の同人プログラム「レインボー戦隊ロビン・スペースアドベンチャー」(1987年制作)は、一部のファンにとって幻の作品として語り継がれています。内容はシミュレーション形式で、レインボー戦隊の6体を指揮して敵艦隊を撃退するというもの。現在では入手困難ながら、アニメ黎明期ファンによる情熱の証として高く評価されています。 近年では、スマートフォン向けの“昭和アニメアイコンコレクション”にロビンが登場し、限定スタンプなどが配信されました。50年以上前のキャラクターがデジタルコンテンツ化されること自体、本作のブランド力を物語っています。
文房具・日用品・食玩――昭和家庭を彩ったノスタルジー
1960年代後半、子ども向け文具として「ロビンの鉛筆」「レインボー戦隊ノート」「ベルの下敷き」などが発売されました。特に“レインボー消しゴム”は、7色の層が重なった珍しいデザインで、当時の文具ファンの間でも話題に。 また、駄菓子店ではキャラクターカード付きチューインガムやラムネ、ロビンの顔を印刷したチョコレート包み紙など、手軽なコレクション系アイテムが多数登場しました。これらは“子どもの日常にアニメが入り込む”初期事例として貴重です。 さらに、放送終了後も長く“昭和レトロ雑貨”として人気が続き、2010年代には一部デザインが復刻。レトロ喫茶や古書店で販売された“ロビンマグカップ”や“虹バッジ風缶バッジ”は、新旧ファンの橋渡し的アイテムとなりました。
ファンアイテムと展示――アニメ遺産としての保存活動
近年では、アニメ史保存の流れの中で『レインボー戦隊ロビン』の資料展示も行われています。2016年、東映アニメーションミュージアム(練馬)で開催された「アニメの原点展」では、本作のセル画、台本、当時の宣伝ポスターが公開され、多くの来場者が“昭和アニメの温かさ”を再認識しました。 ファンクラブ活動も根強く、SNS上では“虹の会”という名称でコレクターが情報交換を行っています。限定同人誌『レインボー戦隊ロビン研究録』では、各話解説と資料再録が掲載され、専門書顔負けの内容で好評を博しました。
総括――“商業”を超えて“文化”へ
『レインボー戦隊ロビン』関連商品は、単なるグッズの域を超え、“日本アニメ文化の遺産”としての価値を持っています。 映像ソフトは保存の手段となり、玩具は夢の象徴となり、書籍は記憶の証となりました。それらすべてが結集して、作品が半世紀を越えて語り継がれる原動力となっています。 今もヤフオクやフリマアプリでは、VHSやソフビが高値で取引されており、コレクターたちはそれを“昭和の星屑”と呼びます。彼らにとって、『レインボー戦隊ロビン』は単なるアニメではなく、“心に残る光”なのです。
[anime-9]
■ 中古市場
半世紀を経ても衰えない人気――ロビン・コレクションの現状
『レインボー戦隊ロビン』が初放送されたのは1966年。それから半世紀以上の歳月が流れた現在でも、本作の関連グッズは中古市場で根強い人気を誇っています。 一般的に1960年代のアニメ作品は、保存状態が良いものが少なく、フィルムや玩具の多くが散逸しています。その中で『レインボー戦隊ロビン』関連アイテムが今なお数多く残っているのは、当時から熱心なファンが存在し、個人で保存・交換してきたためです。 コレクターの間では“昭和アニメ三種の神器”として「鉄腕アトム」「エイトマン」と並び称されることもあり、その人気は一過性のブームではなく“文化的遺産”としての価値へと昇華しています。
映像ソフト市場――VHSからDVD、そしてデジタル復刻へ
映像ソフトの中古市場では、1980年代に発売された東映ビデオのVHS版が特に高値で取引されています。 全4巻構成のうち、第3巻「宇宙の友情編」が最も人気で、状態が良いものは1本あたり12,000円前後で取引されることもあります。理由は、収録話に名作と評される第20話「タイガーとの握手」が含まれているためです。 一方、LD(レーザーディスク)版はコレクター向け市場で安定した需要があります。ディスク全6巻セットが美品で揃っていれば、現在でも4~6万円程度。特に帯付き・解説書完備のものはプレミア価格となり、アニメ専門オークションでは即決で落札されることも珍しくありません。 DVD-BOX(2015年東映ビデオ版)は現在も比較的流通していますが、初回限定特典の“虹の記録ブックレット”付きは人気が高く、中古でも2万円前後。配信サービスが主流になった今でも、ファンは“実物として所有したい”という欲求を強く持っているのです。
音楽ソフト市場――アナログからデジタルへ受け継がれる旋律
音楽関連の中古市場では、1960年代当時のソノシート盤と1970年代再発のEPレコードが特に注目されています。 オリジナルのソノシート『レインボー戦隊ロビンのうた』(朝日ソノラマ刊)は、付録ポスター付きの完全版だと市場価格が8,000~10,000円前後。折れや破れのない状態は希少で、保存状態が良ければさらに高額になります。 また、1995年発売の『東映ヒーロー主題歌大全集』CDにはロビンの主題歌が初収録されており、こちらも人気が高く、再生良好な中古品が5,000円前後で取引されています。 2016年にリリースされたCD『レインボー戦隊ロビン 音楽大全』はリマスター版ながら限定生産のため、現在は新品同様のものがほとんどなく、中古市場では12,000円を超えることもあります。ファンの間では「このCDを聴くとあの白黒の宇宙が蘇る」と評され、音楽を通じて作品を追体験する層が増加しています。
玩具市場――ソフビとブリキが示す昭和モノ文化の象徴
玩具分野では、『レインボー戦隊ロビン』のソフビ人形とブリキ玩具が非常に高値で取引されています。 特にマルサン商店製の「ロビン号ペガサス号ブリキ」はコレクター垂涎の一品で、ゼンマイ可動が正常に動作する完品は、近年のオークションで12万円の値がつきました。塗装の褪色やサビが少ないほど価格が上がる傾向にあり、保存箱付きならさらに2~3万円上乗せされることも。 また、バンダイ(当時はバンプレストの前身)から発売されたミニソフビシリーズは、1体あたりの相場が3,000~5,000円ですが、6体コンプリート状態だと3万円を超えるケースもあります。ベルと教授のセットは特に人気が高く、可愛らしい造形が評価されています。 このような“昭和玩具ブーム”は2010年代以降も継続しており、東京・中野ブロードウェイや秋葉原の専門店では、ロビン関連商品が常に高額棚に陳列されています。ブリキやソフビの質感には、プラスチック製品では出せない“昭和の手作り感”があり、単なる懐古ではなくアートピースとして再評価されています。
書籍・資料類――復刻版と同人誌の両立する収集熱
書籍類の中古市場では、2000年代に出版された『レインボー戦隊ロビン 完全資料集』やファン制作の同人誌『ロビン研究録』が高値を維持しています。 前者は定価4,800円ながら現在は7,000~9,000円で取引され、後者は一時的にしか頒布されなかったため希少価値が非常に高く、オークションでは2万円近くに達することもあります。 また、昭和当時の子ども向け雑誌『ぼくら』『少年マガジン』に掲載されたロビン特集号は、表紙が綺麗なものなら1冊3,000円以上。掲載カットやシールが欠損していないものは、コレクター間で“奇跡の保存品”として扱われます。
食品・日用品関連グッズ――駄菓子景品から企業コラボへ
1960年代の駄菓子店で配布された「ロビンシール」「ベルカード」「虹の戦隊メンコ」などは、今や博物館級のコレクションです。これらは流通量が少なく、紙質も脆いため、完品で残っているものはほとんどありません。 近年では企業コラボとして、2020年代に「昭和アニメ喫茶」限定で“ロビンラテアートカップ”や“虹のクッキー缶”などが再現販売され、瞬く間に完売しました。これらのグッズも転売市場でプレミア化し、定価1,200円の缶が3,500円で取引されるなど、ロビンブランドの根強さを物語っています。
ファン間取引とSNSの影響――“つながるコレクション文化”
かつては中古店や古物市が主な流通経路でしたが、近年ではSNSを通じた個人間取引が主流です。 Twitter(現X)では「#ロビンコレクション」「#昭和アニメグッズ」などのハッシュタグで売買・交換情報が飛び交い、全国のファンがリアルタイムで交流を行っています。 また、海外のコレクターも多く、特にイタリアやフランスでは“Japon Animation Classique”と呼ばれるジャンルで『レインボー戦隊ロビン』が紹介され、ポスターや台本を高値で買い取る動きが出ています。 ファンがデジタル空間で出会い、物理的なアイテムを通して“記憶”を共有する――この新しいコレクションの形が、古いアニメ作品を再び生かしているのです。
総括――“ロビンの光”は中古市場でも輝き続ける
『レインボー戦隊ロビン』の中古市場は、単なる懐古趣味ではなく“文化資産の保存”という使命感で支えられています。 VHSやLD、ソフビ、ソノシート――それぞれが時代の息吹を宿したアーカイブであり、所有すること自体が昭和アニメ文化への敬意の表れです。 特に2020年代以降、若い世代のコレクターが増加しており、「親が見ていた作品を自分も集めたい」という世代を超えた情熱が、再評価の追い風になっています。 今もネットオークションで「ミラクルノヴァ ソフビ」「リリ ソノシート完全版」などのキーワードが検索上位に上がり続けており、作品の光は消えることがありません。 それはまるで――ロビンが宇宙に放った“虹の光”が、時代を越えて今もコレクターたちの心を照らし続けているかのようです。
[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 [ 里見京子 ]
【〜2/6 09:59まで!! 最大2000円OFFクーポン!!】レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 2 【DVD】
【〜2/6 09:59まで!! 最大2000円OFFクーポン!!】レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 【DVD】
【中古】 レインボー戦隊ロビン DVD−BOX 1/里見京子(ロビン),新道乃里子(リリ),中村恵子(ベル),服部公一(音楽)
[中古] レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 2 [DVD]
レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 2 [ 里見京子 ]
[中古] レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 [DVD]




 評価 5
評価 5![レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 [ 里見京子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5054/4988101185054.jpg?_ex=128x128)



![[中古] レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 2 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-sora/cabinet/p05/4988101185085.jpg?_ex=128x128)
![レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 2 [ 里見京子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5085/4988101185085.jpg?_ex=128x128)
![[中古] レインボー戦隊ロビン DVD-BOX 1 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-sora/cabinet/p07/4988101185054.jpg?_ex=128x128)

![アニメ・ミュージック・カプセル レインボー戦隊ロビン [CD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/111/cdsol-1506.jpg?_ex=128x128)