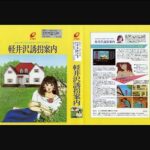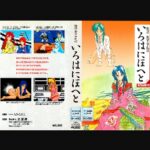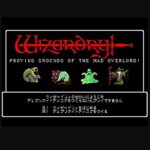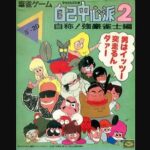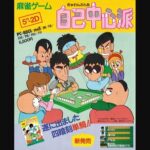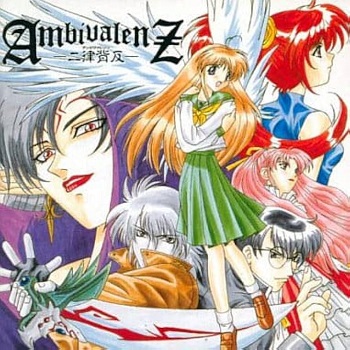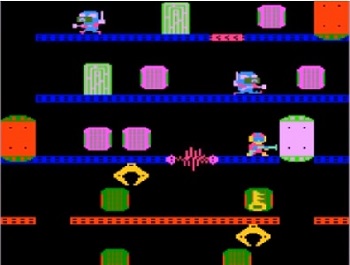2in1ゲーミングノートパソコン 13.4型 180Hz Ryzen AI MAX 390 メモリ32GB SSD1TB Webカメラ 顔認証 Bluetooth Wi-Fi 7 Windows11 日本..




 評価 5
評価 5【発売】:アスキー
【対応パソコン】:FM-7、PC-8801、X1
【発売日】:1986年
【ジャンル】:アドベンチャーゲーム
■ 概要
アリオンとはどんなゲームか
1986年にアスキーからパソコン用ソフトとして発売された『アリオン』は、アドベンチャーゲームの歴史を語るうえで外せない作品の一つです。本作は、アニメーション映画『アリオン』(同年3月公開)を原作に制作されたゲームで、プレイヤーは映画のストーリーを体験する形で進行していきます。発売当時、FM-7、PC-8801、X1といった国産パソコンに向けて提供され、ユーザーは各機種ごとに異なるグラフィックや音源の表現を楽しむことができました。
原作『アリオン』と安彦良和の挑戦
『アリオン』は、アニメーター・漫画家として知られる安彦良和が描いた漫画作品を基にしています。安彦良和は『機動戦士ガンダム』などでキャラクターデザインやアニメーション監督として高い評価を得てきましたが、『アリオン』は彼にとって初の本格的な漫画作品でした。その独自の世界観と壮大な神話的ストーリーは話題を呼び、劇場アニメ化も実現しました。ゲーム版はその映画公開と歩調を合わせるかたちでリリースされ、映画を観たファンにとっては物語を追体験できる貴重な一本となりました。
ゲームジャンルとシステムの特徴
ジャンルとしては「コマンド選択式アドベンチャー」に分類されます。プレイヤーは物語の主人公であるアリオンを操作し、画面に表示される選択肢からコマンドを選び、ストーリーを進めていきます。当時のパソコンゲームは、テキスト入力型のアドベンチャーが主流でしたが、『アリオン』は比較的わかりやすいインターフェースを採用しており、初心者にも親しみやすい設計がなされていました。選択肢に従って進むだけでなく、場面によっては探索や行動の選び方で展開が変化する場面もあり、プレイヤー自身が物語の進行に関与している感覚を味わえるのが魅力でした。
映画との連動性
『アリオン』の大きな特徴の一つが、映画で使用されたセル画をディジタイズしてゲーム中に取り入れている点です。1980年代中盤のパソコンゲーム市場では、実際のアニメーション素材を取り込む試みは非常に珍しく、当時のプレイヤーにとっては新鮮で衝撃的な演出でした。もちろん、当時のPC-8801やFM-7、X1といった機種の性能上、グラフィックの解像度や色数には限界がありました。そのため、セル画はある程度粗いドット絵に変換されていましたが、それでも安彦良和の繊細なキャラクターデザインや迫力ある戦闘シーンを再現しようとした努力は高く評価されています。
物語の進行と制約
ゲームのストーリーは、基本的に映画版『アリオン』の流れを追う形になっており、プレイヤーは神話的な冒険の一員として物語を進めていきます。ただし、当時の容量制限や表現方法の制約から、映画の全てのエピソードが収録されているわけではありません。一部のシーンや展開が省略されており、映画を観ていないプレイヤーにとっては「なぜここに来たのか」「どうしてこの人物と戦うのか」といった疑問が残る場合もありました。そのため、映画や漫画を知っている人には補完的な意味を持ち、知らない人には多少難解に感じられるゲームだったと言えるでしょう。
当時のゲーム市場における位置づけ
1986年の日本のパソコンゲーム市場は、まだ黎明期の熱気に満ちた時代でした。アクションやシューティングが主流であった中、アニメ映画と連動したアドベンチャーゲームという試みは斬新であり、プレイヤーに強い印象を与えました。特にアスキーはコンピュータ雑誌『LOGiN』などを通してゲームファンに強い影響力を持っており、同社のブランド力もあって『アリオン』は多くの注目を集めました。
技術的挑戦と限界
『アリオン』のもう一つの注目点は、先述した通り「セル画のディジタイズ画像」を使った点にあります。これはレーザーディスクを使ったアーケードゲーム『アストロンベルト』や『ドラゴンズレア』と同じような発想ですが、家庭用パソコンのスペックでそれを実現しようとしたのは革新的でした。しかし、データ容量の制約により、使用できる画像枚数には限界があり、アニメ映画のダイナミックな動きをそのまま再現することはできませんでした。それでも当時のファンにとっては、あのスクリーンで観た美しい映像を自分の家のパソコンで再び目にできる、というだけで特別な体験だったのです。
■■■■ ゲームの魅力とは?
アニメとゲームの融合が生んだ独自の魅力
『アリオン』の最大の魅力のひとつは、当時としては革新的であった「アニメーション映画とコンピュータゲームの融合」という試みです。1980年代半ばのパソコンゲーム市場では、まだ多くのタイトルがシンプルなドット絵やテキスト主体の画面構成にとどまっていました。その中で『アリオン』は、映画で実際に使用されたセル画をデジタル化して取り込み、プレイヤーがその映像を見ながら物語を進めていける仕組みを採用していました。これにより、ただのゲーム体験ではなく「映画を自分で操る感覚」を味わえるという新しい価値を提供していたのです。当時のプレイヤーにとっては、アニメの豪華なビジュアルを家庭用パソコンで再現できること自体が驚きであり、ゲームが“映像芸術”としての可能性を広げる瞬間を体感できたとも言えます。
選択肢を通じて進行するインタラクティブな物語
本作は「コマンド選択式」のアドベンチャーゲームであり、画面上に表示される複数の行動候補からプレイヤーが選ぶことでシナリオが進行していきます。例えば、「話す」「調べる」「移動する」といったシンプルな動作を選ぶだけで、物語が枝分かれし、展開が変わっていきました。1980年代のパソコンゲームにおけるアドベンチャーは、コマンド入力型が主流で、正しい単語を入力しないと先に進めない場合も多く、プレイヤーが辞書を片手に悩むこともしばしばありました。その点、『アリオン』は映画のストーリーをベースにしているため、誰にでも分かりやすく、比較的スムーズに進めることができるよう工夫されていました。これは、映画と同時期にゲームが発売された意味を強調するポイントでもあり、視聴者が「物語に参加する」という感覚を強める効果を持っていました。
安彦良和のアートワークが放つ迫力
アリオンの魅力を語るうえで外せないのが、やはり安彦良和のアートワークです。アニメーション映画『アリオン』のために描かれた膨大なセル画をデジタル化し、それをゲーム中で使用するという試みは、今で言えばアニメとゲームを横断するメディアミックスの先駆けでした。当時のPC-8801やFM-7のグラフィック性能は限られていたものの、原画の持つダイナミックな構図や力強い線は失われず、特に神々や怪物との対峙シーンでは、映画館で体験した迫力を追体験することができました。プレイヤーはただ文字を読むのではなく、ビジュアルによって物語世界に没入することができ、これが多くのアニメファンにとって強烈な体験となったのです。
神話的世界観の没入感
『アリオン』の物語は、ギリシャ神話をベースにした壮大なスケールで展開されます。神々の思惑に翻弄される人間の運命、運命に抗おうとする主人公アリオンの姿が描かれており、プレイヤーはただのゲームの登場人物ではなく、古代神話の中で生きる一人の英雄として行動している感覚を得られました。テキストの表現は当時のパソコンの制約により、すべてひらがなで表示されるという特徴がありましたが、それが逆に神話世界の古代感を強める効果を持っていたとも言われます。制限のある環境下で、物語体験をいかに豊かに見せるかという開発陣の工夫が、この作品の魅力を引き立てています。
プレイヤーごとの解釈を生む不完全性
本作は映画のストーリーをなぞる構成であるものの、容量の関係でどうしても一部が省略されています。そのため、映画や漫画を見ていないプレイヤーには展開が唐突に感じられる部分が多く、理解しづらいという声もありました。ところが、この「空白」が逆に想像をかき立て、プレイヤー自身が頭の中で補完する余地を生み出しました。当時は今のようにインターネットで情報をすぐに得られる時代ではなかったため、友人同士で「この場面は映画だとどういう意味なんだろう」「原作ではこうなっていた」と語り合うことが、ゲームの魅力をさらに広げる役割を果たしていたのです。
映像作品をゲームで体験する意義
1980年代は、映画やアニメとゲームを連動させる試みが始まった時代でした。『アリオン』はその中でも、映画公開とほぼ同時期に発売されたことで、作品世界を多角的に楽しむ「メディアミックス」の成功例とされています。ゲームを遊んだ人が映画館に足を運んだり、逆に映画を観た人が自宅で続きを追体験するためにゲームを購入したりと、双方が相互に観客を送り込む関係を築いた点も当時としては画期的でした。特にアニメファンにとっては、家庭のパソコンを通じて憧れのキャラクターやシーンに「触れられる」こと自体が大きな魅力だったのです。
■■■■ ゲームの攻略など
コマンド選択の基本と進行の仕組み
『アリオン』の攻略を考える際、まず理解しておくべきなのが「コマンド選択式アドベンチャー」というシステムの基本です。現代のアクションRPGのように自由にフィールドを歩き回るのではなく、プレイヤーは提示される複数のコマンド(例:しらべる、はなす、いどう、つかう など)から選択し、物語を進めていきます。一見すると単純に見えますが、当時のパソコンアドベンチャーでは「正しい選択肢を選ばなければ進めない」「順序を誤ると重要なイベントを見逃す」といった特徴があり、プレイヤーの推理力や記憶力が試されました。つまり『アリオン』の攻略は、ただ選ぶだけではなく「どの場面でどの行動をとるか」を考え、試行錯誤を繰り返す過程そのものがゲームの面白さを構成していたのです。
映画を知っていると有利になるポイント
本作の物語は劇場アニメ版『アリオン』を基にしているため、映画を観ているプレイヤーはストーリー展開やキャラクターの行動パターンを事前に把握できます。たとえば「このキャラクターは敵なのか味方なのか」「次にどの神殿へ向かうべきか」といった分岐点で迷いがちな場面でも、映画の知識があれば正しい選択肢を選びやすくなります。逆に映画を見ていない人にとっては、いきなり場面が飛ぶように感じられることがあり、なぜその展開になるのか理解するのに苦労したという声も多くありました。この「原作知識の有無による攻略体験の差」もまた、『アリオン』特有の攻略上の特徴といえるでしょう。
難易度の高さとトライ&エラーの楽しみ
『アリオン』は、選択肢を誤るとすぐにゲームオーバーになってしまうこともあるシビアなバランスを持っています。特に敵との戦闘や重要なイベントシーンでは、正しい順序でコマンドを実行しなければストーリーが進まないため、プレイヤーは細心の注意を払う必要がありました。しかし、この「失敗と再挑戦」のプロセスこそが、当時のアドベンチャーゲームの醍醐味でもあります。何度もやり直すうちに少しずつ正解のルートが見えてきて、最終的に突破できたときの達成感は格別でした。今で言えば「ダークソウル」シリーズのように、難しさそのものが熱中を生む要素となっていたのです。
効率的な攻略法の模索
プレイヤーたちは、繰り返しの試行錯誤の中で「効率の良いルート」や「必須アイテムの入手手順」を独自にまとめていきました。インターネットのない時代、こうした情報はゲーム仲間との口コミや雑誌の攻略記事が主な情報源でした。ノートに分岐や失敗パターンを書き留めて、どの選択肢を選んだらどうなるのかを地道に記録する「マッピング」作業も重要な攻略手段でした。こうした遊び方を通じて、プレイヤーは単にストーリーを追うだけでなく、自分なりの「攻略の道筋」を組み立てる楽しさを感じることができました。
隠し要素や小ネタ
『アリオン』は基本的に映画をなぞる内容でしたが、細部にはゲーム独自の演出や、プレイヤーの選択によって異なるセリフや展開が挿入される場面がありました。例えば、特定のキャラクターに話しかける順番を変えることで追加の情報が得られたり、通常はスルーできる場面で特定の行動を選ぶと別のイベントが発生したりといった小さな分岐です。こうした「寄り道要素」を探すことは、映画をすでに観たプレイヤーにとっても新鮮な驚きをもたらし、攻略情報を交換する文化を育みました。また、ファンの間では「このシーンのグラフィックは劇場版のどのカットを使ったものか」を議論すること自体が一つの楽しみであり、攻略と同時に作品世界への理解を深めるきっかけとなっていました。
■■■■ 感想や評判
発売当時のユーザーの反応
1986年に『アリオン』がリリースされた際、当時のパソコンゲームファンの間では「アニメの世界をそのままパソコンで体験できる」という点が大きな話題になりました。ファミコンが家庭用ゲーム市場を席巻していた時代に、PC-8801やFM-7といったマシンで、劇場用アニメ作品の映像をそのまま切り出して遊べるというのは、極めて新鮮な体験だったのです。多くのユーザーは、画面に映し出されるキャラクターや背景が見慣れたセル画の雰囲気を残していることに感動し、まるで映画を再び追体験しているような気分を味わいました。
一方で、当時のパソコンは処理能力や容量が限られていたため、表示されるグラフィックは粗く、色数も少ないものでした。そのため、「映画で観た美しい映像が完全には再現されていない」と残念がる声も少なからずありました。とはいえ、当時のプレイヤーにとっては「家庭で映画を遊べる」こと自体が驚異的であり、むしろ技術的な挑戦を高く評価する空気が強かったのも事実です。
雑誌やメディアでの評価
当時のゲーム雑誌では、『アリオン』は「新しいメディアミックスの可能性を示したタイトル」として紹介されました。特に『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』といった雑誌では、グラフィックの美しさや、アニメとの連動性が大きく取り上げられています。ただし一方で、「ゲーム性はやや物足りない」「映画を見ていない人には理解しづらい」といった批評も見られました。評価は決して一枚岩ではなく、「アニメファンにとっては必携の一本だが、純粋にゲームとして楽しもうとすると難しい部分がある」というのが総合的な世間の見方だったといえます。
このように、ゲームとしての完成度だけを見れば平均的ですが、映像表現の新しさやアニメとの連携という点で、1980年代のゲーム史において重要な位置づけを占める作品として語り継がれています。
ファンの感想と思い出
実際にプレイした人々の感想をひもとくと、当時の熱狂や戸惑いがよく伝わってきます。映画をリアルタイムで観たファンからは「映画の名場面を自分の手で進められるのが嬉しかった」という声が多く、グラフィックの粗さよりも“アニメの空気をパソコンで感じられる”ことに価値を見出していました。一方で、映画を観ていなかったプレイヤーからは「ストーリーが飛び飛びで分かりにくい」「なぜ急に敵と戦うのか流れが掴めない」といった意見も聞かれます。
また、当時の学生や子どもたちは、友人同士で情報を交換しながら進めるのが一般的でした。今のようにインターネット掲示板やSNSがない時代、攻略情報は雑誌の攻略記事か口コミに頼るしかなく、それが逆にゲーム体験を特別なものにしていました。「友達と一緒にエンディングを見た時の達成感が忘れられない」と振り返る人も多く、ゲーム以上に「体験を共有する場」として記憶に残っているのが印象的です。
後年の再評価とコレクターズアイテムとしての価値
時代が進み、90年代以降にCD-ROMやDVDといった大容量メディアが普及すると、『アリオン』のように容量制限で表現を削ぎ落とさざるを得なかった作品は一時的に影を潜めることになりました。しかし、レトロゲームブームが訪れると、その「不完全さ」や「挑戦的な実験精神」が再評価されるようになります。特に、アニメと連動して制作された点や、安彦良和のビジュアルを家庭用PCで楽しめるという事実は、コレクターの間で高く評価されています。
中古市場でも、『アリオン』のパッケージ版は比較的珍しい部類に入り、美品であれば高値で取引されることもあります。特に、FM-7版やX1版は流通量が少なかったため、プレミアムがつきやすい傾向があります。こうした背景もあり、ただのゲームソフトとしてではなく、「80年代アニメとパソコンゲームの架け橋」という歴史的価値を持つアイテムとして注目され続けているのです。
■■■■ 良かったところ
アニメの世界観を家庭で追体験できる喜び
『アリオン』の大きな魅力は、映画館で観たあの壮大な世界を自宅のパソコン画面で追体験できることでした。1980年代半ばは、映画を観に行ったとしても、家庭用にビデオソフトがすぐ出回る時代ではありませんでした。そのため、作品をもう一度味わいたいファンにとって、このゲームはまさに貴重な「もう一度アリオンの世界に触れられる手段」となっていました。セル画をデジタイズした画面が映し出されるたびに、映画で心を動かされたシーンが蘇り、単なる文字のやり取りにとどまらない映像体験が可能だったのです。
分かりやすい操作と没入感の両立
当時のパソコンアドベンチャーの多くは、コマンドをキーボードで直接入力するタイプが主流でした。「みる」「とる」「しらべる」などの動詞を正確に入力しないと進めないため、プレイヤーは辞書を片手にプレイすることも珍しくなかったのです。しかし、『アリオン』では選択肢から行動を選ぶ方式が採用され、初心者でもスムーズに遊べる仕様になっていました。これにより、物語に集中しやすく、映画を知っている人はもちろん、アドベンチャーゲーム自体が初めてという人でも取り組みやすかった点が好意的に受け止められました。また、簡単な操作ながらも、選択次第で展開が分岐する緊張感があり、自分が物語に影響を与えているという実感を得られるのも魅力の一つでした。
独自性の高いビジュアル表現
家庭用パソコンの性能がまだ限られていた時代に、映画のセル画を取り込んで表示するという試みは、非常に先進的でした。画面のドットは粗く、カラー表現も制限がありましたが、当時のプレイヤーたちは「映画そのままの迫力あるビジュアルを自分のPCで体験できる」という点に強い感動を覚えました。特に神々が登場するシーンや戦闘場面は、静止画であっても臨場感があり、「ゲームをしているのに映画を観ているようだ」と語る人も多かったのです。こうした映像演出は、同時代の他のアドベンチャーゲームとは一線を画し、独自の価値を築きました。
キャラクターへの強い感情移入
映画や原作漫画をすでに見ていたファンにとっては、ゲーム内に登場するキャラクターたちの表情やシーンが懐かしく、自然と感情移入できる点も大きな魅力でした。特に主人公アリオンの勇敢さや、彼を取り巻く神々や仲間たちとの関係性は、選択肢を通じて「自分が物語の一部になっている」という体験を強めます。ゲームを進めながら、アリオンが直面する試練や運命に共感し、プレイヤー自身もその一端を担っているような感覚が味わえるのです。
■■■■ 悪かったところ
物語の断片的な進行による分かりにくさ
『アリオン』は映画版をベースにしたアドベンチャーゲームですが、当時のパソコンの容量制限や開発スケジュールの都合から、映画の全シーンを完全に収録することはできませんでした。その結果、プレイヤーがゲームを進めていくと、いきなり場面が飛んだように感じる箇所があり、「なぜここに到達したのか」「どうして登場人物がこういう行動を取っているのか」が分かりにくいと評されることがありました。特に原作や劇場版を観ていない人にとっては、物語のつながりを理解するのが難しく、ストーリーを楽しみきれなかったという声もあります。
ゲーム性のシンプルさへの物足りなさ
本作はあくまで「コマンド選択式アドベンチャー」であるため、当時のアクションゲームやロールプレイングゲームのような複雑な操作や自由度の高い冒険要素はありませんでした。プレイヤーが行うのは画面に表示された選択肢から適切な行動を選ぶことであり、入力の幅は限定的です。そのため、「単調さを感じる」「すぐに答えを選んでしまえば物語が勝手に進んでしまう」という意見も見られました。特にゲーム性を重視するプレイヤーにとっては、挑戦のしがいが薄いと受け止められたのです。
難易度と不親切さのバランス
『アリオン』の進行はシンプルである反面、選択肢を間違えると即座にゲームオーバーになる場面が多々ありました。セーブ機能を使って進めることは可能でしたが、セーブポイントを見誤ると何度も同じシーンをやり直すことになり、ストレスを感じるプレイヤーも少なくありませんでした。さらに、ゲーム中のテキストがすべてひらがな表示だったため、子どもにとっては読みやすい一方で、大人のプレイヤーにはかえって違和感があったという感想も散見されます。ゲームとしての遊びやすさと世界観の再現をどうバランスさせるかという点は、当時から議論の的となっていました。
[game-6]■ 好きなキャラクター
主人公・アリオンの魅力
『アリオン』の物語を語る上で、やはり欠かせない存在が主人公のアリオンです。彼はギリシア神話の世界を舞台に、神々と人間の狭間で葛藤しながら成長していく若者として描かれています。当時のプレイヤーにとって、アリオンはただのゲームキャラクターではなく、「自分自身を投影できる英雄」でした。ゲーム内では、彼の行動を選択することによって物語の進行が左右されるため、プレイヤーは自然とアリオンの目線で世界を見つめることになります。ときに無鉄砲で、しかし正義感にあふれた姿は、80年代の少年少女にとって憧れの存在であり、ゲームのプレイ体験をより感情的なものにしてくれました。
ヒロインの存在感と物語の軸
アリオンの物語を語るうえで重要なのが、ヒロインの存在です。彼女はただの助演ではなく、アリオンの心を支える柱であり、プレイヤーの選択によっては彼女との関係性が強調される場面もあります。アニメ版でも彼女の描写は大きな見どころの一つであり、ゲームでもセル画を使った演出によって印象深く再現されています。プレイヤーの多くが「彼女の表情に心を打たれた」「彼女を守るために選択肢を必死に考えた」と振り返るように、ヒロインの魅力は本作の評価を支える大きな要素のひとつでした。
神々や敵キャラクターの迫力
『アリオン』では、ギリシア神話に登場する神々や怪物たちが数多く登場します。映画版で描かれたダイナミックな戦闘シーンを切り取ったグラフィックは、当時のパソコン画面に映し出されるだけで大きなインパクトを与えました。ゼウスやアポロンといった神々の存在感は圧倒的で、プレイヤーに「自分が神話世界にいる」という感覚を与えました。特に印象的だったのは、アリオンが宿命に抗いながら神々と対峙する場面で、ここではプレイヤーが選んだ一つのコマンドが勝敗を左右する緊張感を生み出しました。敵のセリフやビジュアルに刻まれた安彦良和ならではの筆致が、ゲーム体験をより豊かにしたのです。
脇を固めるキャラクターたちの個性
主人公とヒロインだけでなく、旅を共にする仲間や物語の脇役たちも、プレイヤーの記憶に強く残りました。ときにコミカルで、ときに厳しく、アリオンを支える彼らの存在が、ゲーム進行を助ける重要な要素となっていたからです。特定の仲間が発するセリフや行動が、選択肢のヒントになる場合もあり、彼らを無視してしまうとストーリーが行き詰まることもありました。プレイヤーたちは「このキャラの言葉を信じるべきか、それとも疑うべきか」と悩みながら進めることになり、結果的に強い印象を残したのです。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
FM-7版の特徴と体験
アスキーが発売した『アリオン』は、まずNECのPC-8801やシャープのX1と並んで、富士通のFM-7向けにもリリースされました。FM-7は1980年代前半から中盤にかけて、ホビーユーザーや教育機関向けに広く使われていたマシンで、グラフィック面ではそれなりの表現力を持ちながらも、同世代のマシンと比べるとやや色数に制限がありました。そのため、映画のセル画を取り込んだ『アリオン』のビジュアルも、他機種版と比較すると落ち着いた色調で、シンプルながらも独特の深みを感じさせるものでした。
また、FM-7版は動作の安定性が高く、当時のユーザーからは「ロード時間は多少長いが、遊びやすい」という意見が多く寄せられました。キーボード操作が中心でしたが、メニュー式のコマンドを選ぶ形式なので、文字入力の手間が少なく、物語に集中できる点が好評でした。FM-7は教育用として普及していたこともあり、学校やパソコン教室で『アリオン』を体験したという人も少なくなく、家庭にパソコンを持っていない子どもたちにとっては特別な体験になったようです。
PC-8801版の完成度と表現力
PC-8801版は、当時のパソコンアドベンチャーゲームの定番環境として多くの人がプレイしたバージョンです。PC-8801は8色表示ながらも高解像度グラフィックを扱えるため、『アリオン』のセル画データを比較的鮮明に再現できました。特に背景美術やキャラクターのシルエット表現に関しては、FM-7版よりも色彩が鮮やかで、映画の雰囲気をより忠実に再現していると評判でした。
音声再生は不可能でしたが、内蔵FM音源を使ったBGMや効果音が流れることで、臨場感が増していたのも特徴です。当時のプレイヤーは「まるでアニメを見ているようだ」と感想を漏らす一方で、「操作性がシンプルすぎる」と感じる人もいました。しかし、PC-8801版の映像美と音楽は、同時期のアドベンチャーゲームの中でも特筆すべきクオリティといわれています。
X1版の特色とファンの評価
シャープのX1は、グラフィックの鮮やかさに定評がありました。『アリオン』X1版もその強みを活かし、映画のセル画をできる限り鮮明に再現することに力を入れていました。特に色の再現性は高く、FM-7やPC-8801に比べても柔らかく自然なグラデーションを楽しむことができたといわれます。そのため、アニメ版を観て「色彩の美しさ」に心を奪われたファンにとっては、X1版が最も映画に近い雰囲気を感じられるバージョンだったとも評されます。
ただし、X1自体のユーザー数がPC-8801に比べて少なかったため、市場に出回る本数も限られており、当時プレイできた人はごく一部でした。その希少性が後年のレトロゲーム市場における価値を高める要因となり、コレクターズアイテムとして高額で取引されることもしばしばあります。X1版は「映像の美しさ」と「入手困難さ」が重なり、幻の名作と称されることもあるのです。
機種ごとの違いが生んだ多様な体験
『アリオン』は同じ内容のアドベンチャーゲームでありながら、対応パソコンごとに画質や音響、操作性に違いが見られました。このため、当時複数の機種を持っていたファンの中には、各バージョンを遊び比べて細かな差異を楽しむ人もいたといいます。例えば、FM-7版は落ち着いた雰囲気で遊べる一方、PC-8801版はBGMの演出が優れており、X1版は映像の発色に優れているといった具合です。結果的に、『アリオン』は一つの作品でありながら、ハードの個性を強く体感できる貴重なサンプルともなり、当時のPCゲーム市場における「多機種展開」の面白さを示した作品とも言えるでしょう。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
★ザナドゥ(XANADU)
・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1985年末(1986年も人気継続) ・販売価格:7,800円前後(機種による差あり)
『ザナドゥ』は、日本ファルコムが手がけたアクションRPGで、1980年代半ばのPCゲームシーンを代表する存在となりました。サイドビュー型の画面でダンジョンを探索し、モンスターと戦い、経験値を積みながらレベルアップしていくという、後の国産RPGの基礎となる要素をふんだんに盛り込んでいます。特に注目すべきは、その圧倒的なボリュームで、数十時間におよぶ冒険が用意されていた点です。当時のパソコンゲームは数時間で終わるものも多かったため、これだけの長編が家庭で遊べることは衝撃的でした。さらに、アイテム収集やキャラクター育成の要素は、当時のプレイヤーにとって新鮮で、中毒性のあるゲームプレイを生み出しました。『アリオン』と同時期に遊ばれた作品としては対照的で、アニメ的映像美を追体験するアドベンチャーが『アリオン』なら、自由度の高い冒険を体感できるのが『ザナドゥ』だったのです。
★ハイドライド3
・販売会社:T&E SOFT ・販売年:1986年 ・販売価格:7,800円前後
『ハイドライド3』は、国産アクションRPGの草分け的シリーズ「ハイドライド」の3作目にあたるタイトルです。時間の概念を取り入れた点が大きな特徴で、昼と夜でモンスターの出現や住民の行動が変化するという斬新な仕組みを導入しました。プレイヤーは剣と魔法を駆使して冒険を進めながら、徐々に明らかになる壮大なストーリーに引き込まれていきます。『アリオン』が一本道に近い展開だったのに対し、『ハイドライド3』は自由度の高い探索性を打ち出しており、当時のユーザーからは「自分で世界を切り開いていく楽しさがある」と好評を博しました。アニメとの連動性はないものの、独自の世界観をじっくり堪能できる点が支持を集めたのです。
★夢幻戦士ヴァリス
・販売会社:日本テレネット(ウルフチーム) ・販売年:1986年 ・販売価格:6,800円前後
『夢幻戦士ヴァリス』は、美少女が剣を手にして魔界を駆け巡るアクションゲームとして、80年代のPCゲームファンに鮮烈な印象を残しました。アニメ調のビジュアルを全面に押し出し、ストーリー性を重視した演出は『アリオン』と同じくアニメファンを引きつけました。さらに、『ヴァリス』は単なるアドベンチャーではなく、実際に操作して敵を倒すアクション性があり、アニメーションとゲームプレイの融合がより動的に感じられる作品でした。『アリオン』と並べて語られることも多く、どちらも「アニメとゲームの垣根を越える試み」として評価されています。
★ファンタジアン(FANTASIAN)
・販売会社:スクウェア ・販売年:1985年末(PC-8801版) ・販売価格:約7,800円
『ファンタジアン』は、後に『ファイナルファンタジー』を生み出すスクウェアが、RPGというジャンルで最初に本格的に挑戦したタイトルのひとつです。当時のパソコンゲームとしてはグラフィックやシステムがシンプルではありましたが、ストーリー性や冒険感を大切にした構成が注目を集めました。プレイヤーは剣と魔法のファンタジー世界を旅し、仲間と共にモンスターと戦いながら成長していきます。『アリオン』が映画をベースにした一本道の物語だったのに対し、『ファンタジアン』はオリジナルのファンタジー世界を自由に歩き回れるRPGらしい開放感を提供しており、「自分で物語を紡いでいる」感覚を楽しめる点が大きな魅力とされました。
★ハイドライドII シャドウ・オブ・ダークネス
・販売会社:T&E SOFT ・販売年:1985年(PC-8801、FM-7 など) ・販売価格:7,800円前後
『ハイドライドII』は、シリーズ第1作『ハイドライド』の成功を受けて登場した続編で、アクションRPGとして大きく進化を遂げた作品でした。体力や魔力の概念が強化され、ステータス管理の重要性が高まり、より戦略的なプレイが求められるようになりました。『アリオン』と同じ時期に遊ばれたこの作品は、「自分の腕前と選択で展開が変わる」という点でアドベンチャーゲームとは違ったゲーム性を提供しました。ユーザーの中には『アリオン』の静的な物語表現に物足りなさを感じ、『ハイドライドII』でアクション性を満喫したという人も多かったようです。
★ハイドライドIIスペシャル(PCエンジン移植版)
・販売会社:T&E SOFT / 日本テレネット ・販売年:1986年(PC-88版)、後にPCエンジン版が登場 ・販売価格:7,800円(PC版)
『ハイドライドII』の特別版として登場した本作は、パソコンの機種ごとに表現力が異なることを象徴するタイトルでした。PC-8801版では高解像度のグラフィックが際立ち、FM-7版では独自のカラフルな発色が楽しめるなど、遊ぶ環境によって見え方が大きく変わりました。プレイヤーの間では「同じゲームでも別機種版を試したくなる」という声が多く、結果として複数のプラットフォームで買い直すファンもいたほどです。こうした現象は『アリオン』にも共通しており、当時のマルチプラットフォーム展開の特性を物語っています。
★ドルアーガの塔(PC移植版)
・販売会社:ナムコ(アーケード版)、PC移植は日本電気ホームエレクトロニクスなど ・販売年:1985年(アーケード)、1986年(PC-8801/X1移植) ・販売価格:およそ6,800円~7,800円
『ドルアーガの塔』は、アーケードで大ヒットした後、家庭用パソコンやファミコンに移植された伝説的なアクションRPGです。プレイヤーは勇者ギルとして塔を一階ずつ攻略し、最上階に囚われたカイ姫を救い出すことを目指します。シンプルな見下ろし型の迷宮探索ながら、各階ごとに隠された宝箱の出現条件があり、それを発見することが次の階を攻略するために不可欠でした。
この「隠し要素を見つけるまで進めない」という仕様は、当時のゲーマーにとっては大きな挑戦でした。攻略法が分からず友人同士で情報交換をしたり、ゲーム雑誌の特集記事を切り抜いて攻略ノートを作ったりと、コミュニティ全体で知識を積み上げていく遊び方が定着しました。『アリオン』と同じく「背景を知っているかどうか」で楽しみ方が変わる点が共通しており、ストーリーを知っている人と知らない人で体験に差が出たことも興味深い対比となります。
★デーモンズリング
・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1986年 ・販売価格:7,800円前後
『デーモンズリング』は、ファルコムが手掛けたファンタジーアドベンチャーゲームです。プレイヤーは不思議な力を秘めた指輪をめぐる物語に巻き込まれ、数々の謎を解き明かしていきます。コマンド選択式の操作と、探索・会話を組み合わせた進行は、『アリオン』とも共通していますが、よりゲーム的な謎解き要素が多く盛り込まれているのが特徴です。
当時のレビューでは、「物語性とパズル性のバランスが取れている」「アニメ的な世界観を感じさせる演出が新しい」といった評価が寄せられました。『アリオン』が映画の追体験に重きを置いたのに対し、『デーモンズリング』はオリジナルの世界でプレイヤーを冒険へと導くタイプの作品でした。これにより、両作品を比較しながらプレイしたユーザーも多く、「アニメファンならアリオン、純粋なゲーム好きならデーモンズリング」と語られることもありました。
★サラダの国のトマト姫
・販売会社:ハドソン ・販売年:1986年 ・販売価格:5,800円前後
『サラダの国のトマト姫』は、野菜をモチーフにしたキャラクターたちが登場するユニークなアドベンチャーゲームです。プレイヤーはトマト王国の姫を救い出すために冒険を進め、コミカルな展開や風刺的なユーモアを楽しむことができました。特徴的なのは、野菜をキャラクター化するという斬新なアイデアで、当時の子どもたちに強い印象を残しました。
本作は『アリオン』と同じくテキスト主体のアドベンチャーですが、こちらは完全にオリジナルのシナリオとキャラクターで構成されています。『アリオン』が重厚な神話の世界を描いたのに対し、『サラダの国のトマト姫』は明るくポップな世界観で、誰もが気軽に楽しめる雰囲気を持っていました。プレイヤーの多くは「難しいけれどユーモラスで楽しい」「子どもから大人まで夢中になれた」と好意的に受け止め、アドベンチャーゲームの可能性を広げる存在となりました。
★ザナック(ZANAC)
・販売会社:コンパイル/ポニーキャニオン(MSX版)、徳間書店インターメディア(PC-8801版) ・販売年:1986年 ・販売価格:5,800円前後
『ザナック』は、コンパイルが手掛けた縦スクロール型のシューティングゲームで、アクションの緊張感とシステムの独創性で高い評価を得ました。本作の最大の特徴は「AIプラスシステム」と呼ばれる自動難易度調整機能です。プレイヤーの腕前や行動に応じて敵の出現パターンや弾幕の密度が変化し、同じステージでもプレイするたびに違う展開が待ち受ける仕組みになっています。これにより、何度遊んでも新鮮さを失わず、プレイヤーは「自分のプレイがゲーム世界に影響を与えている」という感覚を得ることができました。『アリオン』のようにシナリオを追体験する作品と比べると、純粋に反射神経と戦略を試される点が大きな違いであり、当時のプレイヤーはそれぞれの楽しみ方を比較しながら遊んでいました。
★イース(Ys I: Ancient Ys Vanished)
・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1987年(PC-8801版を皮切りに各機種へ展開) ・販売価格:7,800円前後
『イース』は、後に長寿シリーズへと発展していくファルコムの代表作であり、アクションRPGの歴史を語るうえで欠かせない一本です。物語は赤毛の冒険者アドル=クリスティンを主人公に、古代王国イースの秘宝をめぐる冒険が描かれます。特徴的なのは「半キャラずらし」と呼ばれる独特の戦闘システムで、敵に真正面からぶつかるのではなく、少し斜めや横から当たることでダメージを与える仕組みです。このシステムは、アクションゲームにありがちな「攻撃ボタンを押す」動作を省き、スピーディかつ直感的なバトルを可能にしました。
『アリオン』と比較すると、『イース』はアクション性が強く、物語のテンポもプレイヤーの操作によって大きく変わる点が特徴です。しかし両作品に共通しているのは「物語を体験するゲームである」という姿勢であり、テキストとビジュアルを通じてストーリーを追うという点で、どちらも当時のユーザーを物語世界に引き込みました。
★スーパーレイドック(SUPER LAYDOCK)
・販売会社:ボーステック(BPS) ・販売年:1986年 ・販売価格:6,800円前後
『スーパーレイドック』は、縦横スクロールを自在に組み合わせたアクションシューティングで、当時のMSXやPC-8801ユーザーに熱烈な支持を受けました。舞台は宇宙を航行する巨大戦艦を中心とした世界で、プレイヤーは多彩な兵装を持つ自機を操作し、迫り来る敵艦隊を撃退していきます。特に注目されたのは、ステージごとに戦闘システムが変化する仕掛けで、ある面ではシューティング、別の面では戦略シミュレーションのようにマップを動かしながら戦うなど、ジャンルを横断するような構成が話題となりました。
『アリオン』が「映画を追体験すること」に重きを置いたのに対し、『スーパーレイドック』は「ゲームとしての新しい遊び方」を模索した作品でした。ユーザーからは「斬新でやりごたえがある」「一作で二度美味しい」と高評価が寄せられる一方、「難しすぎる」「操作が複雑」と感じる声もあり、まさに当時のPCゲームらしいチャレンジ精神を象徴するタイトルだったといえるでしょう。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
アリオン(4) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]




 評価 5
評価 5アリオン(3) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]




 評価 5
評価 5【中古】アリオン 3/中央公論新社/安彦良和(文庫)
アリオン(2) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]




 評価 5
評価 5【中古】 アリオン 1 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】
【中古】アリオン 3/中央公論新社/安彦良和(文庫)
【中古】 アリオン 3 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】
【中古】 アリオン 2 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【宅配便出荷】
アリオン(1) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]




 評価 5
評価 5
![アリオン(4) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8319/9784122028319.jpg?_ex=128x128)
![アリオン(3) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8302/9784122028302.jpg?_ex=128x128)

![アリオン(2) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8081/9784122028081.jpg?_ex=128x128)
![【中古】 アリオン 1 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/05619348/bkncdddd9k4ukgmy.jpg?_ex=128x128)
![【中古】 アリオン 3 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/05619348/bkvymlukcthjxxuq.jpg?_ex=128x128)
![【中古】 アリオン 2 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【宅配便出荷】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo-omatome/cabinet/08430291/bk352molpzgmrw9w.jpg?_ex=128x128)
![アリオン(1) (中公文庫コミック版) [ 安彦良和 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8074/9784122028074.jpg?_ex=128x128)
![【中古】 アリオン 2 / 安彦 良和 / 中央公論新社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/08428480/bk352molpzgmrw9w.jpg?_ex=128x128)