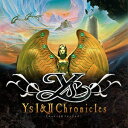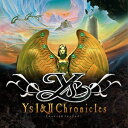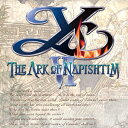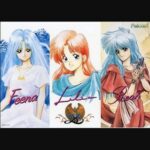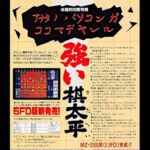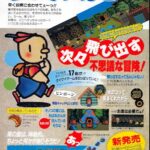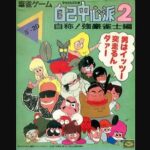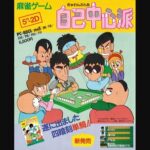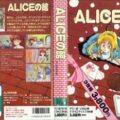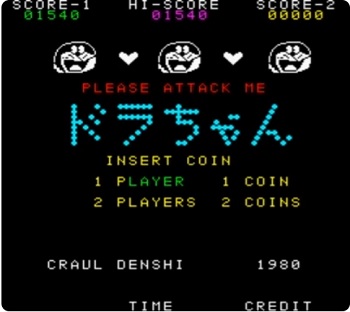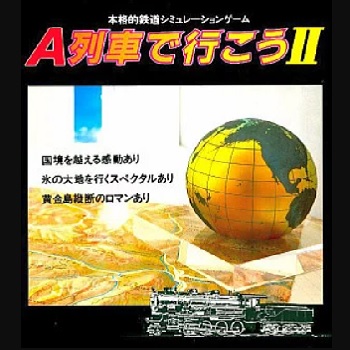イースX -Proud NORDICS-




 評価 5
評価 5【発売】:日本ファルコム
【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX、X1、FM77AV、X68000
【発売日】:1987年
【ジャンル】:アクションロールプレイングゲーム
■ 概要
イース伝説の幕開け──赤毛の冒険家アドルの最初の旅
1987年、日本ファルコムが発表したアクションRPG『イースI』は、後に長く続くイースシリーズの原点であり、日本のパソコンRPG史において欠かせない存在となった。舞台は嵐に包まれ外界から隔絶された地「エステリア王国」。若き冒険家アドル・クリスティンは、古代王国イースの謎を解き明かすためこの地を訪れる。そこで彼を待ち受けていたのは、古代の遺跡、封印された魔の塔、そして失われた二人の女神の物語だった。 プレイヤーはアドルを操作し、戦闘・探索・人々との交流を通じてこの地の真実を探る。単なる冒険譚ではなく、文明の光と闇、人と神の関係、そして“優しさ”をキーワードにした新しいRPG体験がここに生まれたのだ。
「優しさの時代へ」──難しさではなく心地よさを求めた革命
1980年代中盤のRPGは、総じて「長い」「難しい」「不親切」が当たり前だった。ユーザーの多くは、理不尽な難易度や複雑な操作を“やりがい”として受け入れていた。しかしファルコムは、そこにあえて「優しさ」という概念を導入した。『イースI』のキャッチコピー「今、RPGは優しさの時代へ。」は、まさにこの思想の象徴である。 アドルが敵に体当たりして攻撃する“ボタン不要”の戦闘は、複雑な入力を避け、直感的に遊べるように設計された。さらにHPが自動回復するシステム、どこでもセーブできる安心感、コンパクトで密度の高いマップ構成──これらすべてが「誰もが物語を最後まで楽しめるRPG」を目指した設計思想の結果だった。当時としては画期的な“プレイヤー・フレンドリー設計”が、以降の国産RPGデザインに多大な影響を与えていく。
体当たりで戦う──単純で奥深い「半キャラずらし」の妙
『イースI』の戦闘システムは、他のどのRPGにも見られない独特なスタイルを持っていた。敵に正面から突っ込むと双方がダメージを受けるが、横や斜めに“半キャラ”ほどずらしてぶつかると、一方的にダメージを与えられる。この“半キャラずらし”は、後のシリーズ作品でも語り継がれるほど有名な戦闘テクニックであり、プレイヤーに「慣れるほど強くなる」という実感を与えた。 魔法や複雑なコマンドは存在せず、あくまで「動き」そのものが戦術になる。この物理的な感覚は、まるで剣士としての呼吸を学ぶようで、単純操作ながら深い戦闘体験を成立させていた。システムの単純さがもたらす没入感──それこそがイースというシリーズの根幹にある“リズム”である。
ステータスと成長の設計──「短く」「密に」「完結する達成感」
『イースI』では、レベルの上限がわずか10に設定されている。序盤の敵を倒していくうちに、あっという間に成長し、物語の中盤には最高レベルに到達してしまう。この設計には意図がある。レベル上げに時間を費やすのではなく、ストーリーと探索に集中してもらうためだ。プレイヤーは「数字」よりも「行動」で成長を実感する。後半ではレベルアップによるごり押しができない代わりに、立ち回りの工夫と観察力が求められるようになる。 この設計思想は、当時のゲームデザインとしては非常に異質で、プレイヤーに“知恵で勝つRPG”という新しい感覚をもたらした。敵を倒す快感よりも、世界を理解し、人物の思いを感じ取ることがプレイの目的へと変化していくのだ。
人々との出会い──心の交流が生む物語の温度
イースIの世界には、単なるNPCではなく、“生きている人々”が存在する。占い師サラがアドルに託す使命、老婆ジェバの穏やかな言葉、盗賊団の頭ゴーバンの意外な知識、そして壁を壊して道を切り開く相棒ドギの豪快さ。それぞれの出会いが小さなドラマとなり、アドルの旅を支えていく。特に、記憶を失った少女フィーナと、詩人レアの存在は象徴的だ。二人の女性を通して“人の心”と“神話の真実”が結びつき、プレイヤーに深い余韻を残す。 これらの人物描写は、RPGのキャラクターが“機能的な存在”であった時代に、人間味を与えた革新的な試みだった。アドルが“誰かを助ける”たびに、プレイヤーもまた優しさを学ぶ──この感情の共有こそがイースI最大の魅力である。
画面構成と情報の見せ方──限られた空間に込めた緻密なデザイン
PC-8801やFM77AVといった当時のパソコンは、画面解像度も描画速度も限られていた。その中で『イースI』は、視覚情報の配置に徹底的な工夫を凝らした。プレイ画面は美しい装飾枠で囲まれ、下部にはHPや経験値、ゴールドなどの情報が棒グラフで表示される。戦闘中のダメージも色分けされ、プレイヤーは瞬時に戦況を把握できた。 また、ステータス画面やアイテム画面は呼び出すとポーズがかかる仕様で、緊張感を保ちながらも落ち着いて装備を確認できる。これらのUIデザインは、現代のゲームデザインにも通じる「情報整理の美学」を先取りしていたといえる。
古代文明の謎と“イースの本”──幻想と現実の狭間で
アドルが求める“イースの本”は、かつてこの地を支配していた古代王国の記録であり、女神たちの存在を示す鍵でもある。物語の進行とともに少しずつ真実が明かされ、プレイヤーは伝説と現実の境界を旅することになる。やがて浮かび上がるのは、“人が神を求めすぎたゆえに滅びた文明”というテーマ。これは単なるファンタジーではなく、人間の欲望と信仰、そして再生を描いた哲学的物語であった。 この深みのあるシナリオが、後の『イースII』へと自然に繋がり、シリーズをひとつの壮大な叙事詩として成立させる。ファルコムの物語構築力が、ここに確立されたのだ。
開発背景──ファルコム黄金期の創造力
『イースI』が誕生した1987年は、ファルコムにとってまさに創造の黄金期だった。『ドラゴンスレイヤーIV』や『ソーサリアン』といった名作が次々にリリースされ、同社は「日本PCゲームの象徴」と呼ばれていた。開発スタッフの中には、後に伝説となる作曲家・古代祐三も名を連ね、彼の手によるBGM「First Step Toward Wars」「Feena」などは、今なおゲーム音楽の金字塔として語り継がれている。 開発当時のPC性能では、滑らかなスクロールや多彩な敵アニメーションを実現するのは困難だった。それを補うため、テンポの良いBGMと操作レスポンス、物語展開のスピード感で“没入感”を生み出したのが『イースI』の革新だった。限界を逆手に取った設計力が、この作品の完成度を押し上げている。
短くも濃密な旅路──今なお愛され続ける理由
『イースI』のプレイ時間は長くても5~6時間程度。だが、その短さこそが完成度の高さを物語る。テンポよく展開するストーリー、心地よい成長バランス、記憶に残る音楽──そのすべてが無駄なく凝縮されている。ゲームの終盤、巨大なダームの塔を登り詰めたとき、プレイヤーは“終わってほしくない冒険”の感覚に包まれるだろう。 数多くのリメイクが制作され、PCエンジン版、Windows版、PSP版、スマートフォン版など、世代を超えて語り継がれているのは、この作品が「物語と操作感の両立」を極めた証拠である。『イースI』は単なる始まりではなく、今なお息づく“優しさの哲学”の原点なのだ。
■■■■ ゲームの魅力とは?
“シンプルさの中に深みがある”──体当たり戦闘の哲学
『イースI』の最大の魅力は、誰にでも理解できる操作体系と、それによって生まれる奥深い駆け引きにある。攻撃ボタンすら存在しないこの作品は、プレイヤーに「動きそのもの」を意識させる。敵との距離、角度、タイミング──この三つを感覚的に捉えることで、単純な“体当たり”が緊張感あふれる戦闘へと変化するのだ。 この“半キャラずらし”による攻撃は、慣れるほど上達を実感でき、プレイヤー自身の熟練がゲーム体験を変化させていく。ファルコムが狙ったのは、手の複雑な操作ではなく“頭と感覚で戦うRPG”だった。システムの極限までの削ぎ落としが、結果としてプレイヤーの集中を高め、戦闘にリズムと緊張を生み出している。
音楽の力でプレイヤーを導く──古代祐三サウンドの衝撃
『イースI』の魅力を語る上で欠かせないのが、その音楽である。作曲を担当した古代祐三によるサウンドトラックは、1980年代PCゲームの常識を覆した。当時のPC-8801のFM音源を限界まで引き出し、まるでライブ演奏のような厚みと疾走感を実現したのだ。 フィールドBGM「First Step Toward Wars」は冒険の幕開けにふさわしい高揚感を、ボス戦曲「Termination」はプレイヤーの緊張を極限まで高める。さらにエンディングを彩る「Feena」は、静かで神聖な旋律によってアドルの旅路を優しく包み込む。この一曲は後のシリーズ全体を象徴するテーマとなり、30年以上経った今でも多くのリスナーに愛され続けている。 ファルコムはこの作品を通じて「ゲーム音楽」を一つの芸術として確立した。音が物語を語り、感情を操り、世界を形作る──その始まりがまさに『イースI』だった。
短くも濃密なプレイ体験──テンポの美学
現代のRPGに比べれば、『イースI』のボリュームは決して多くない。しかし、わずか数時間で完結するこの旅には、一切の無駄がない。次の目的地が常に明確で、会話も要点を押さえ、戦闘から探索、イベントまでが滑らかに連動している。 ファルコムは「退屈な移動時間」や「不必要なレベル上げ」を排除し、プレイヤーが常に“動きながら考える”状態を保てるよう設計した。どの瞬間も新しい発見があり、音楽と演出がリズミカルに切り替わるため、プレイ中の没入感が途切れない。まさに「濃密な2時間映画」のような構成であり、限られた時間の中に満足感を凝縮する技術が光る。
キャラクターたちの温かさ──冷たい難易度の時代に灯る“優しさ”
アドルの旅は、孤独ではない。『イースI』の登場人物たちは、ゲーム内の目的を超えて、プレイヤーの心に寄り添う存在として描かれる。フィーナの純粋さ、レアの哀しみ、ドギの人懐っこさ──それぞれの性格や行動に“人間味”が込められている。 この“優しさ”の描写こそが、当時のゲーマーにとって新鮮な体験だった。命を削るような高難度RPGが主流の時代に、「人を信じ、助け、思いを受け取る」ことが主題の作品が登場したのは衝撃的だったのだ。イースの世界は血や怒りではなく、“共感”によって物語を動かしていく。それが本作の根底に流れる美徳であり、今でもシリーズを通して受け継がれている。
バランス設計の妙──“優しい”が“簡単”ではない
ファルコムの巧妙さは、ただ遊びやすくすることにとどまらなかった。レベルアップや装備の強化が頭打ちになる中盤以降、プレイヤーは「戦い方を変える」ことを求められる。敵の動きを観察し、半キャラずらしのタイミングを覚え、危険を察知する。このアクション的な要素が、緊張感を保ちながらも理不尽にはならない絶妙なバランスを生み出していた。 つまり、“優しさ”とは「救済」ではなく「理解される挑戦」だったのだ。ゲームがプレイヤーを見放さず、何度も試行錯誤を促す設計は、今でも多くのクリエイターに影響を与えている。
ストーリーの奥行き──神話と人間のドラマが交差する
『イースI』の物語は、単純な“冒険の始まり”にとどまらない。古代王国イースの失われた歴史、神の存在をめぐる信仰、そして人間の欲望によって崩壊した文明の悲劇──これらのテーマが重なり合い、プレイヤーに哲学的な余韻を残す。 特に印象的なのは、神殿に囚われていたフィーナの正体と、彼女のもう一人の存在・レアとの関係性だ。二人の女性は“女神”でありながら、人間の痛みを理解する存在として描かれている。アドルは彼女たちを救うことで、単なる冒険者から“伝説を継ぐ者”へと成長していく。 物語が完結してもなお、プレイヤーの胸には「イースとは何だったのか?」という問いが残る。その答えは、続編『イースII』へと引き継がれる──この連続性こそが、シリーズを永遠の物語にした。
ビジュアルと演出の進化──制約を美に変える職人技
当時のPCゲームは、ドット単位での表現に限界があった。だがファルコムのデザイナーたちは、その制約を逆に生かした。プレイ画面を額縁のような装飾で囲み、キャラクターの影や光を細やかに描き込むことで、プレイヤーの視線を自然に中心に誘導している。 ダームの塔や神殿内部のデザインは、硬質な石造りの質感と不思議な光の演出が融合し、当時のPCゲームでは異例の神秘性を放っていた。さらに、キャラクターの立ち絵やイベントシーンも画面切り替えで巧みに演出され、プレイヤーは一枚絵の中で感情の変化を感じ取ることができた。 “制限を創造に変える”というこの精神は、後のゲーム開発の理念にも通じている。
多彩な移植とリメイク──変わらぬ核、進化する体験
『イースI』は、PC-8801を皮切りにPC-9801、MSX、FM77AV、X1、そしてX68000と、数多くのプラットフォームに移植された。その後もPCエンジン版『イースI・II』、Windows版『イース・エターナル』、PSP版『イースI&IIクロニクルズ』など、時代を超えて何度もリメイクされている。 驚くべきことに、いずれのバージョンでも物語の核とシステムの本質は変わっていない。グラフィックや音質は進化しながらも、体当たり戦闘の手触りと“優しさ”の哲学だけはそのまま受け継がれている。プレイヤーの世代が変わっても、アドルの冒険は変わらず新鮮に感じられる──それがこの作品が“時代を超えるRPG”と呼ばれる所以である。
プレイヤーの心に残る“旅の余韻”
エンディングで流れる「Feena」の旋律とともに、プレイヤーはアドルの旅立ちを見送る。多くのRPGがクリア後の達成感を重視する中で、『イースI』は“寂しさ”を残して終わる。その感情が、次なる物語『イースII』への期待へとつながっていくのだ。 この「終わりの余韻」が、単なるゲームではなく“心の体験”として記憶に刻まれる。だからこそ、何十年経っても人々は再びイースの地を訪れ、あの音楽と風景に心を委ねたくなる。『イースI』の魅力とは、まさに“優しさと切なさが共存する冒険譚”なのである。
■■■■ ゲームの攻略など
序盤の立ち回り──冒険の始まりは“観察”から
アドルの冒険は、港町ミネアから始まる。最初に重要なのは、戦うことよりも「人に話を聞くこと」。この世界では、村人や店主のセリフが攻略の鍵を握る。占い師サラが「イースの本を探せ」と告げる場面を皮切りに、探索が一気に広がる。まずは武器屋でブロンズソードを購入し、北の平原でスライムやバットを倒して経験値を稼ぐのが定石だ。 序盤は敵の動きが単調で、半キャラずらしを覚える絶好の練習場所でもある。敵を正面からではなく、斜めにかすめるように当たる感覚を体で覚えておこう。この操作感に慣れることで、後半のボス戦でも有利に立ち回れるようになる。
資金とレベルアップのバランス
本作では、敵を倒すことで経験値とゴールドの両方が手に入る。序盤はゴールドが不足しがちなので、必要最低限の装備(ブロンズソード・シールド・アーマー)を優先的にそろえると良い。装備を整えたら、レベル5程度まで上げてから廃坑へ向かうと安定する。 ただし、イースIでは中盤でレベルが上限に達してしまうため、無闇なレベル上げは禁物。重要なのは“戦闘での感覚を磨くこと”であり、数値での強さに頼ると後半で苦戦する。序盤の段階で敵の動きを見極めるクセを付けておくことが、真の攻略につながる。
廃坑での探索──光源アイテムと慎重な進行
最初の大きなダンジョンである廃坑は、序盤の山場である。暗闇の中を進むためには「ブルーのネックレス」が必須。これを装備しておかないと、視界がほぼゼロになり、敵との遭遇が避けられない。敵は一気に強くなるが、ここで手に入る経験値とゴールドは多い。無理せず一歩ずつ進み、体力が減ったら安全地帯で立ち止まって自然回復を待つのがセオリーだ。 また、道中の宝箱から「ハーモニカ」を入手できる。このアイテムは直接的な戦闘アイテムではないが、後のイベントで重要な意味を持つ。こうした“ストーリー性のあるアイテム”がイースの魅力であり、すべての発見が冒険の記録として積み重なっていく。
中盤──ゼピック村とフィーナの救出
廃坑を突破した後は、ゼピック村へ向かう。ここで出会うのが、記憶を失った少女フィーナだ。彼女を助けるイベントを経て、物語は新たな段階に入る。村人の話を細かく聞き、サラの行方を追うことが次の目的になる。 この時期のポイントは、「装備の買い替えを急がない」こと。すでに敵のドロップで手に入る装備の方が店売りより強い場合がある。中盤の敵は攻撃が速く、正面からの戦いでは分が悪い。敵の進行方向を読んで、背後や斜めから体当たりする習慣をつけよう。
ボス攻略──反射神経よりもパターン理解
『イースI』のボスは、見た目こそ迫力があるが、全員に“明確な攻略法”が存在する。初見では倒せなくても、数回の挑戦で行動パターンを読み取れば突破できるのが特徴だ。 たとえば「ヴァガル」戦では、ボスの突進ルートを見極めて斜め方向へ少しずつずらして攻撃する。真正面に立つと高確率で反撃を受けるため、側面から半キャラずらしで当てるのがポイントだ。 終盤の「ダルク・ファクト」戦では、床が崩れるギミックに注意。安全なマスを探しつつ、敵の魔法弾を回避する冷静さが求められる。この戦いはシリーズ屈指の緊張感を誇るが、理不尽さは一切ない。動きの法則を見抜けば、必ず勝利が見える──この「公平な難易度」が、イースの設計哲学そのものなのだ。
回復とリングの使い方
フィールドでは立ち止まることでHPが自然回復する。これを活用し、戦闘と休憩を繰り返して進むのが基本だ。ダンジョン内では「ヒールリング」を装備すれば同様に回復できるが、ボス戦中は無効化されるため、使いどころを見極めよう。 また、「タイムリング」「パワーリング」などの特殊リングは、一時的にアドルの能力を強化する。強敵に挑む前や逃走ルートを確保する際に使うと効果的。リングは装備変更で瞬時に切り替えられるため、常にショートカット的な意識で運用すると戦術の幅が広がる。
お金の使い道──効率的な運用術
ゴールドは限られた資源だ。序盤から無駄な買い物を避け、必要な装備を計画的に購入しよう。特に注意したいのは、「すでに持っている装備も再購入できてしまう」点。オリジナル版では警告メッセージが出ないため、うっかり買ってしまうと無駄遣いになる。 また、病院での全回復サービスも有効だが、フィールドでの自然回復を活用すれば節約できる。節約した資金は中盤以降の強力な武具や回復アイテムに回すとよい。『イースI』は短時間でクリアできる作品だからこそ、資金管理が攻略を大きく左右する。
終盤──ダームの塔への挑戦
物語の最終局面では、伝説の塔「ダームの塔」に突入する。この巨大な構造物は、イースIのクライマックスにふさわしい緊張感を放つダンジョンだ。フロアごとに罠や謎解きが設けられ、プレイヤーの記憶力と判断力が試される。 ここでは、ドギの力で壊せる壁や隠し扉などの仕掛けを見逃さないことが重要。塔内では回復ポイントが限られるため、戦闘後は立ち止まってHPを回復させながら慎重に進もう。 最上階では、ラスボス「ダルク・ファクト」が待ち構える。床の崩落ギミックと魔法弾の連射がプレイヤーを追い詰めるが、敵の動きには法則がある。焦らず位置取りをキープし、攻撃チャンスを見逃さなければ勝利は目前だ。
隠し要素・裏技
オリジナルのPC版には多くの小ネタが存在する。たとえば、特定の場所でBGMを止めた状態でアイテムを使うと、別の曲が再生されるというバグ的仕様。また、リメイク版では特定条件を満たすことで、難易度調整パッチやボーナスイラストを閲覧できるなど、時代ごとに異なる“遊び心”が仕込まれている。 こうした仕掛けがあることで、プレイヤーはただ物語を追うだけでなく、“世界の裏側”を探す楽しみを味わえる。イースIは短いながらも、探索意欲を刺激し続ける作品である。
攻略の本質──“優しさ”を理解することが最大の鍵
『イースI』の攻略で最も重要なのは、システムを覚えることでもテクニックを磨くことでもない。このゲームの“優しさ”の設計思想を理解することだ。失敗しても何度でも挑戦できる環境、戦うだけでなく人々と話すことで開かれる道、そしてプレイヤー自身が成長する過程──それらすべてが攻略そのものになっている。 ファルコムは、プレイヤーを「試す」のではなく「導く」方向で難易度を設計した。だからこそ、『イースI』の本当の攻略法は、“焦らず、観察し、感じ取る”ことである。
まとめ──アドルの一歩は、プレイヤーの一歩
ミネアの港を出てからダームの塔を登り切るまでの道のりは短い。しかし、その中にはプレイヤーが自ら学び、考え、工夫する余地が無限に広がっている。ゲームをクリアすることはゴールではなく、「理解すること」こそが本作の真の目的だ。 アドルが旅の終わりに見た光景は、プレイヤーにとっても“次の冒険への始まり”となる。『イースI』の攻略とは、つまり「自分の中の冒険心を目覚めさせる旅」なのである。
■■■■ 感想や評判
当時のプレイヤーが受けた衝撃──“優しいRPG”という新概念
1987年当時、『イースI』が発売された瞬間、多くのPCゲーマーは驚きに包まれた。RPGといえば、マッピング用の方眼紙を用意し、敵の強さに挫折しながら攻略するという“忍耐のゲーム”だった時代。その常識を覆し、「誰もが最後までたどり着けるRPG」という方向性を明確に打ち出した本作は、まさに時代の転換点となった。 プレイヤーたちは「優しさの時代へ」というキャッチコピーに半信半疑だったが、実際にプレイしてみると、その意図がすぐに伝わる。複雑なコマンドも、難解なパズルも存在せず、ただ冒険を進める心地よさがあった。理不尽なゲームに慣れていた当時のファンほど、「こんなに自然に遊べるRPGがあるのか」と驚きと感動を覚えたという声が多く寄せられた。
雑誌・メディアでの高評価──革新的デザインとしての賛辞
ゲーム専門誌やパソコン情報誌では、『イースI』を「国産ARPGの金字塔」として高く評価している。特に注目されたのは、プレイヤーのストレスを徹底的に排除したゲームデザインである。 雑誌レビューでは、「アクションのテンポとRPGの成長要素がここまで自然に融合した作品は初めて」と評され、グラフィックやBGMも当時の技術水準を超える完成度とされた。特に古代祐三のBGMについては「PCでこの音が鳴るとは信じられない」と絶賛され、後に“ゲーム音楽という文化”を世に広めるきっかけにもなった。 一部のレビューでは「プレイ時間が短い」という指摘もあったが、それ以上に「密度が高く、無駄がない」「繰り返し遊びたくなる」という声が圧倒的に多かった。
ユーザーコミュニティの反応──“語り継がれる原点”
発売後、各プラットフォームに移植されるたびにプレイヤー層は広がっていった。特にPCエンジン版『イースI・II』の登場以降は、家庭用ユーザーにも一気に普及。SNSやファンサイトが登場する以前から、ファン同士の口コミで「イースは心に残るRPG」として語り継がれていた。 当時のプレイヤーの感想には、「戦闘が楽しい」「音楽に泣いた」「短いけれど忘れられない」という言葉が多く見られる。中には「初めてエンディングで涙が出たゲーム」と語る人も少なくなかった。難易度や演出よりも、“心に残る物語”が評価されるというのは、80年代のRPGとして極めて珍しい現象だった。
ファルコムファンの中での位置づけ
ファルコムは『ドラゴンスレイヤー』『ザナドゥ』など、ハードコアゲーマー向けの難易度を誇る作品を多く手がけていた。その流れの中で『イースI』が登場したことは、ファンの間で賛否を呼んだ。「簡単すぎる」「物足りない」と感じたベテラン層もいたが、圧倒的多数の新規プレイヤーはその“遊びやすさ”を歓迎した。 結果として、『イースI』はファルコムのファン層を一気に広げた作品となる。特に若年層や女性ゲーマーが初めて触れるPCゲームとしても人気を集め、“親しみやすいファルコム”というイメージを確立した。会社にとっても、本作がブランドの転換点となったのは間違いない。
音楽への称賛──BGMが心をつなぐ
「音楽を聴くためにイースを起動する」──そんな言葉が当時のファンの間でよく聞かれた。サウンドトラックはカセット、CD、レコードなど多くの形で発売され、発売から数十年を経た今もリメイクやコンサートで演奏され続けている。 特に「Feena」はシリーズ全体の象徴的テーマとして受け継がれ、『イースII』『イースVI』『イースIX』に至るまで、アレンジや引用が繰り返されている。多くのファンが「この曲を聴くと心が落ち着く」「旅の終わりを思い出す」と語るほど、音楽が物語と一体化しているのだ。 古代祐三は本作で一躍名を知られる存在となり、その後『ソーサリアン』『アクトレイザー』などでさらに名声を高めていく。『イースI』は、彼の作曲家人生を決定づけた作品でもあった。
現代プレイヤーの再評価──“古さ”ではなく“原点の力”
時を経て現代でも、『イースI』は多くのリメイク版でプレイ可能だ。PC、PSP、Steamなどで遊んだ新しい世代のプレイヤーたちからも、「古いどころか新鮮」との声が多い。 特に若いゲーマーは、「余計なチュートリアルがなく、すぐに遊べる」「音楽とテンポが最高」「短いのに満足感がある」と評価している。逆に、現代RPGの複雑なUIや長大なチュートリアルに疲れたプレイヤーにとっては、このシンプルな体験が“癒し”になっているという意見も多い。 リメイク版ではグラフィックやシナリオ演出が強化されたが、核となる“遊びの哲学”は変わっていない。時代を超えてもなお通用する設計思想こそが、『イースI』最大の魅力として再評価されている。
批評家の見解──“短さ”の中にある完成度
批評家の間では、『イースI』の短いプレイ時間がしばしば議論の的になる。しかし、彼らの多くは「短さ=欠点ではない」と結論づけている。むしろ、必要な情報とイベントが凝縮され、構成に一切の無駄がない点を「映画のような完成度」と評している。 さらに、後半で成長が止まりアクションスキルが試される設計についても、「プレイヤーを信頼している」との意見が多い。数字による強化ではなく、“プレイヤー自身の理解力と経験”が成長の鍵になる──この設計思想は、のちに『ダークソウル』などに通じる“学習型アクションRPG”の先駆けとも言われている。
海外での評価──日本発ARPGの礎
『イースI』は海外でも高い評価を受けており、特に北米・欧州では「The origin of Japanese ARPG」として語られている。PCエンジン版『Ys Book I & II』がTurboGrafx-16でリリースされた際、そのアニメ調演出と音楽が強烈な印象を残した。海外メディアは「Zeldaよりも速く、Final Fantasyよりも直感的」と評し、アクションRPGというジャンルを世界に広める橋渡しとなった。 その後、『イースI』は多言語化され、Steam版などで再び世界中のプレイヤーに遊ばれるようになる。35年以上経った今も、Steamレビューでは“overwhelmingly positive(圧倒的に好評)”の評価を維持していることが、この作品の普遍性を物語っている。
ファンの心に残る“体験”としての記憶
プレイヤーの多くは、イースIを単なるゲームとしてではなく、“人生の中の思い出”として語る。 初めてFM音源で聴いた「Feena」の感動、廃坑を抜けた時の達成感、ダームの塔を登り切った瞬間の緊張──それらは時間を超えて心に残る。特に80年代後半にPCで遊んでいた層にとって、『イースI』は青春の象徴とも言える存在になった。 近年ではサウンドトラックのリマスター盤や、公式コンサート「Falcom jdk BAND LIVE」での演奏などを通じ、当時のファンが再び“あの頃の冒険”を追体験している。時を経ても色あせない感動──それが、イースIの最も大きな魅力である。
総合的な評判──“RPGを変えた優しさ”の記憶
最終的に、『イースI』は「難しさではなく、心地よさで魅せるRPG」として評価された。戦闘のシンプルさ、音楽の芸術性、物語の温かさ──そのどれもが時代を超えて語り継がれている。 批評家もファンも一致して指摘するのは、「優しさ」という言葉の重みである。これは単なる易しさではなく、“プレイヤーを思いやる設計”という意味での優しさだ。ファルコムが築いたその哲学は、後の国産RPGすべてに影響を与えたと言っても過言ではない。 『イースI』は、RPGを「試練」から「体験」へと進化させた。だからこそ、35年以上経った今でも語り継がれ、愛され続けているのだ。
■■■■ 良かったところ
直感的で奥深い操作性──「体当たり」という革新
『イースI』の最大の長所は、攻撃ボタンを廃した戦闘システムにある。プレイヤーが敵にぶつかるだけで戦うという発想は、当時としては大胆で画期的だった。この単純な操作の中に、驚くほどの奥深さが存在している。 特に“半キャラずらし”というテクニックは、単なる当たり判定の隙間を突くものではなく、プレイヤーの感覚と反射を磨く仕組みだった。敵の移動パターンを読み取り、わずかに角度をずらして接触すれば、ダメージを受けずに倒せる。ここにはアクションゲーム的な楽しさとRPG的な成長要素が融合しており、誰でも遊びやすいのに、極めようとすると奥が深い。 この“直感で遊べる戦闘”は、その後のイースシリーズはもちろん、他のARPG作品にも大きな影響を与えた。結果として『イースI』は、操作性という観点からも“優しさの中に緊張感があるゲーム”として高く評価されている。
音楽の完成度──BGMが物語を語る
多くのプレイヤーが“良かった点”として挙げるのが音楽である。古代祐三が手掛けたBGMは、単なる背景音ではなく“感情の導線”そのものだ。 冒険の始まりを告げる「First Step Toward Wars」は、タイトル画面で流れるだけで胸が高鳴る。平原での探索曲「Palace」や、「Feena」の静謐なメロディは、プレイヤーの心に深く刻まれた。ダンジョンで緊張が高まる時、あるいはボス戦で血が滾る時──音楽がプレイヤーの感情と完全にシンクロする。 さらに特筆すべきは、FM音源を駆使した当時の技術的限界を超えるサウンド表現だ。3音という制約の中で、複数の旋律を錯覚的に聴かせるポリフォニックな手法は、まさに“電子音楽の芸術”。この完成度の高さが、イースシリーズを「音楽で語るRPG」として確立した理由である。
テンポの良さ──中だるみのない構成
『イースI』は、当時のRPGにありがちな“長くて冗長”な展開が一切ない。物語のテンポが非常に良く、常に次の目的が明確で、迷う時間が少ない。イベントが途切れることなく発生し、自然な流れで次の冒険へ導かれる構成は、当時のプレイヤーにとって驚くほど快適だった。 ダンジョンも複雑すぎず、地形の記憶と方向感覚で進める設計になっているため、マッピング不要でスムーズに探索できる。攻略を詰めていけば、どのプレイヤーも自力でエンディングにたどり着けるようになっており、難易度のバランスも絶妙だ。 この“適度な長さと明確な目的”がプレイヤーの集中力を途切れさせず、最後まで飽きずに遊べる理由となっている。まさに“RPGのリズム設計”の見本といえる。
キャラクターの魅力──心に残る出会い
本作の登場人物たちは、セリフの数こそ少ないが、一人ひとりに確かな印象が残る。アドルに使命を託す占い師サラ、彼女を慕うジェバ、囚われの少女フィーナ、詩人レア、そして力強い仲間ドギ。彼らの短い会話の中に、優しさや悲しみが詰まっている。 とりわけ、フィーナとレアの関係はシリーズを貫く神話の根幹でもあり、プレイヤーの記憶に強く刻まれた。初めて出会ったときの儚げな微笑み、別れ際に流れる「Feena」の旋律──その情感の深さは、当時のゲームでは極めて異例だった。 これらのキャラクターが、単なる情報提供役やNPCではなく、“心を動かす存在”として描かれている点は、今なお評価が高い。短いながらも物語の余韻が残るのは、この人間味あふれる描写があるからだ。
ビジュアル表現──制約を美に変えるデザイン
1987年当時のPCグラフィックは、色数も解像度も限られていた。しかし、『イースI』はその制約の中で“美しさ”を生み出している。 草原の緑、神殿の荘厳な石造り、洞窟の闇──限られたパレットで描かれた画面は、むしろ印象派絵画のような鮮烈なコントラストを生んでいる。さらに、キャラクターや敵モンスターの動きも滑らかで、各モーションに生命感がある。 特にダームの塔のデザインは秀逸で、フロアごとに色調や雰囲気が変化する構成は、当時としては画期的だった。まるで塔そのものが生きているような錯覚を覚える。ファルコムの美術センスと技術力の融合が、この作品を特別な存在にしている。
バランス調整の妙──挑戦と達成の快感
『イースI』の難易度は、“誰でもクリアできる”と言われるほど絶妙に設計されている。簡単すぎることもなく、かといって理不尽でもない。戦闘での失敗はプレイヤーの判断ミスであり、成功は確実に努力の結果として感じられる。 レベル制限により、後半は純粋なプレイヤースキルが問われるが、それが理想的な緊張感を生んでいる。敵のパターンを理解し、攻撃のタイミングを見極め、冷静に行動すれば必ず突破できる。 この「納得できる難易度」こそが、当時のゲーマーにとって何よりの快感だった。難しくても理不尽ではない──その信頼性が、ファルコムの作品全体への信頼へとつながっていった。
ストーリー構成──短くても深い叙事詩
『イースI』の物語は非常にコンパクトだが、無駄が一切ない。序章からクライマックスまでが滑らかにつながり、わずか数時間で壮大な神話を体験できる。この“密度の高さ”が、多くのプレイヤーに感動を与えた。 アドルの目的は明快でありながら、進むにつれて“イースの本”という象徴が人と神をつなぐメタファーへと変化していく。物語の核心に触れる頃には、単なる冒険が“歴史の継承”へと昇華する。この構成の巧みさは、短編小説にも似た完成度を誇る。 さらにエンディングで示される静かな余韻──“終わり”ではなく“始まり”を感じさせる構成──がプレイヤーの記憶に残り、続編『イースII』への期待を自然に生んでいる。
技術的完成度──当時のPCの限界を超えた表現力
『イースI』は、PC-8801やFM77AVといった限られた性能のハードウェア上で動作していたにもかかわらず、驚異的なスピードと安定性を実現していた。画面切り替えのテンポ、敵の動作、当たり判定の精密さ──どれも1980年代のPCゲームとしては破格の完成度である。 特に、読み込み時間の短さや処理落ちの少なさは、当時のファルコムの技術力の高さを証明している。プログラムの最適化とメモリ管理の巧妙さは、後にX68000やPCエンジンなど、より高性能な機種への移植を容易にした。 この“技術の確かさ”が、イースシリーズが長く続く土台となったことは間違いない。
リプレイ性──短時間で何度も味わえる満足感
クリアまでの時間が短いという特徴は、逆にリプレイ性を高めている。一度エンディングを迎えた後でも、「もう一度冒険したい」と思わせるのがイースIの魅力だ。 ゲームテンポが良く、最初から最後までスムーズに進行するため、再プレイ時には「最短ルートを探す」「効率的な装備順を見つける」といった楽しみ方もできる。また、リメイク版では難易度選択や追加要素により、熟練者にも新たな挑戦が用意されている。 短くも濃密な体験を何度も味わえることこそが、本作が長年支持され続ける理由の一つである。
総評──すべてが調和した“完成されたシンプル”
『イースI』の“良さ”を一言でまとめるなら、「シンプルの中に完成がある」だろう。操作、音楽、物語、テンポ、すべてがバランスよく調和しており、プレイヤーを最後まで飽きさせない。 その全体設計には、ファルコムの職人的なこだわりと、“遊び手への思いやり”が息づいている。 発売から数十年を経てもなお、「最初に遊んだRPGとして最高の思い出」という声が絶えない理由は、作品そのものに“優しさと完成度”が共存しているからだ。 『イースI』は、派手な演出も豪華なグラフィックもない。それでも、人の心を動かす力を持つ──それが本作最大の良さであり、国産RPG史に残る名作として語り継がれる所以である。
■■■■ 悪かったところ
ボリューム不足──わずか数時間で終わってしまう冒険
『イースI』は、プレイ時間が短いことが最大の欠点としてよく挙げられる。慣れたプレイヤーであれば、わずか5~6時間ほどでエンディングに到達してしまう。 当時のRPGは「長く遊べる=価値が高い」と考えられており、『ザナドゥ』や『ハイドライドII』のような10時間以上のボリュームを持つ作品が多かった。そのため、『イースI』のコンパクトな構成に物足りなさを感じるユーザーも少なくなかった。 また、ストーリー自体も「イースの本を集め、塔を登る」というシンプルな筋書きで終わっており、謎解きや寄り道要素が少ない。後半のダームの塔では展開が急ぎ足になり、エンディングもやや唐突に感じられる。 とはいえ、これは容量の制限(フロッピーディスク3枚以内に収める必要があった)によるもので、当時の技術的限界を考えれば致し方ない部分でもあった。それでも、多くのプレイヤーが「もう少し長く冒険したかった」と語るほど、作品の完成度が高かった証拠でもある。
レベル上限の早さ──成長が止まる中盤以降の単調さ
本作では、レベルの上限が10と非常に低く設定されている。そのため、物語の中盤に差し掛かる頃には最大レベルに到達してしまい、以降はどれだけ敵を倒しても成長しない。 この設計は「レベル上げによるごり押しを防ぐ」という狙いがあったが、結果として“成長の喜び”を失わせる要因にもなった。プレイヤーは後半、純粋に体当たりのテクニックだけで戦う必要があり、RPGというよりはアクションゲームの感覚に近づく。 また、敵を倒す動機が経験値からゴールド獲得に変わるため、プレイテンポに偏りが生じる。戦闘の面白さを維持する工夫がやや不足しており、この点については「もう少し段階的な成長要素が欲しかった」という意見が多い。 後のリメイク版『イース・エターナル』では、この問題が一部改善され、経験値や敵配置のバランスが調整されたが、オリジナル版においてはやはり「中盤で成長が止まる不自然さ」が課題として残った。
一部の操作性の不便さ──方向指定と会話システム
『イースI』では、人に話しかける際に正面からでなければ会話できない仕様になっている。しかもNPCが動き回るため、背後を向かれた瞬間に話しかけられず、無駄に追いかけ回すこともしばしばあった。 この“方向制限”は、当時としてはリアリティのある設計だったが、プレイヤーにとっては煩わしい仕様だったといえる。さらに、会話をスキップしたり履歴を確認する機能がないため、重要なヒントを聞き逃すと再び話しかけ直す必要があった。 また、アイテム画面の操作もやや独特で、装備変更をする際にカーソルの動作が少し重く感じる。戦闘中にリングやアイテムを素早く切り替えることができないため、テンポを崩す場面もあった。 後年のリメイクでは、これらの不便さがすべて改善されており、「原作の味わい」として受け止められているものの、当時の初見プレイヤーにとってはストレス要因だったのは確かだ。
戦闘の単調さ──スキルの幅が狭い
体当たり戦闘という独自システムは魅力的である反面、長時間プレイするとやや単調に感じられる。攻撃方法が1種類しかないため、どの敵に対しても似たような動きを繰り返すことになるのだ。 後半の敵はパターンこそ異なるものの、戦闘スタイルそのものは変化が少なく、魔法やスキルのような“新しい遊び”が生まれにくい。 一方で、アクションRPGとしては当時まだ黎明期であり、シンプルさこそが魅力でもあった。この「単調さ」を“味”として楽しめるかどうかが、評価を分ける部分となった。熟練者ほど「操作の精度を磨くのが楽しい」と語るが、RPG的な多様性を求めるプレイヤーにはやや物足りなさが残った。
終盤の急展開──唐突なストーリー進行
物語のクライマックスであるダームの塔に突入すると、それまでの流れが急激にスピードアップする。村での交流やサブイベント的要素がほとんどなくなり、一気にボスラッシュのような展開になるのだ。 この唐突なテンポ変化は、緊張感を高める意図もあったが、物語的な“間”がなくなる結果にもつながった。前半で描かれた“人との関わり”が薄まり、エンディングに向けての感情の積み上げがやや急ぎ足になる印象を与える。 特に、ラストバトル後のエンディングは静かに幕を閉じるが、その直前の展開が駆け足気味で「もっと余韻が欲しかった」という意見も多い。のちの『イースII』で物語が補完されることを考えれば納得できるが、単体作品として見ると“完結感の薄さ”は否めない。
敵の行動パターンの少なさとAIの単純さ
『イースI』の敵は基本的に“接近してくるだけ”の単純なAIで構成されている。ボスを除けば遠距離攻撃や特殊行動を行う敵は少なく、敵の行動が単調に感じられる。 このため、プレイヤーの成長に対して敵の動きが追いつかず、戦闘が作業化することもある。特にレベル上限に達した中盤以降は、戦闘の緊張感が薄れやすい。 ただし、これは開発当時のハード性能による制約も大きく、プログラム的に複雑なAIを組み込むのが困難だった事情もある。それでも、敵のバリエーションがもう少し豊かであれば、さらに深い戦闘体験が生まれたことは確かだ。
一部のバグや技術的制限
PC-8801版やMSX版などでは、環境によって画面のスクロールが遅れたり、特定の状況で敵が動かなくなるといったバグが報告されている。特にMSX2版ではスクロール速度が非常に遅く、テンポが損なわれるという不満が目立った。 また、当時の保存媒体であるフロッピーディスクは耐久性が低く、長期保存に向かないため、データ破損によるロード不能のリスクも存在した。 現代の視点で見れば致命的な問題ではないが、当時のプレイヤーにとっては“冒険が突然終わる”可能性を常に抱えていたことになる。技術的な限界の中で高品質を実現していたとはいえ、ユーザー体験を損なう要因であったのは事実だ。
アイテムの扱いに関する不親切さ
アイテムの説明が画面上に表示されないため、初見プレイヤーには用途が分かりにくいものがある。「ハーモニカ」や「ブルーのペンダント」など、ストーリー進行に関係するアイテムも、何に使うかが説明されないため、使用タイミングを逃すことがあるのだ。 また、同じアイテムを再び購入できてしまう仕様も混乱を招いた。システム的には重複して持てないが、購入自体は可能なため、お金を無駄にしてしまうプレイヤーが続出した。 これらの点は後のリメイク版で改善され、「同じ装備は購入できません」といったメッセージが表示されるようになった。だが、オリジナル版では“説明不足による迷い”が不満点として残った。
全体としての課題──完成度の高さゆえの限界
『イースI』の欠点は、言い換えれば「完成度が高すぎるがゆえに、さらに求めたくなる」点でもある。短く美しい構成、洗練された戦闘、音楽の完成度──それらがあまりに良くできていたため、プレイヤーは「もっと見たい」「もっと知りたい」と感じてしまった。 物語が続編『イースII』へと直結する構成も、単体としての満足度をわずかに削ぐ要因となっている。もしイースIが独立した作品であったなら、より強い完結感を持って評価されたかもしれない。 それでも、この“物足りなさ”が次作への期待を生み、シリーズを永遠に続く伝説へと押し上げたことも事実である。 つまり、『イースI』の悪いところは、同時に“次へ進ませる原動力”でもあったのだ。
[game-6]■ 好きなキャラクター
アドル・クリスティン──赤毛の冒険者、すべての始まり
シリーズを象徴する主人公・アドルは、『イースI』で初めてプレイヤーの前に姿を現した。彼の特徴である燃えるような赤髪は、単なる外見的アイコンではなく、「未知への情熱」を象徴している。17歳という若さで世界を旅し、嵐に閉ざされたエステリアに一人上陸する勇気と行動力。無口でありながら、誰よりも人々を救おうとする純粋な心。 この“語らぬ英雄”という設定は、プレイヤーが自分自身を投影できる余白でもあり、のちのRPG主人公像に大きな影響を与えた。アドルの人格は台詞よりも行動で語られる。倒れた人を助け、傷ついた者を励ます――そうした姿が静かな感動を呼ぶ。 彼は決して超人的な力を持つわけではない。戦闘は体当たり、魔法すら使えない。それでも立ち向かう勇気こそが、アドルの最大の武器である。『イースI』を通してプレイヤーが感じる“成長”とは、レベルアップ以上に、アドルという人間の“心の強さ”の体感なのだ。 このキャラクター性こそが、35年以上にわたりシリーズが愛され続ける根幹であり、プレイヤーにとって“最初に出会うアドル”が、今も特別な存在であり続けている。
フィーナ──儚くも清らかな“イースの象徴”
本作のヒロイン・フィーナは、プレイヤーにとって忘れられない存在である。神殿に囚われていたところをアドルに救われるという、物語の序盤での出会いが印象的だ。彼女は記憶を失っており、自身の正体もわからないままアドルの旅に関わっていく。 そのミステリアスさと、どこか人間離れした穏やかさは、多くのプレイヤーの心を惹きつけた。彼女の優しい微笑み、静かな口調、そして“何かを思い出しそうで思い出せない”という儚げな描写。これらが、イース世界に独特の哀愁を与えている。 やがて物語が進むにつれ、フィーナがイースの神聖な存在に深く関わっていることが示唆される。彼女は人と神の狭間に生きる存在であり、その宿命に苦しみながらも、アドルとの出会いを通じて“人の温かさ”を学ぶ。このテーマは『イースII』でさらに深まるが、本作においてもその片鱗が丁寧に描かれている。 フィーナはただのヒロインではない。“神話の中の人間性”を体現する存在であり、静けさの中に宿る強さを持つ女性として、多くのプレイヤーに深い印象を残した。
レア──詩と音楽で心をつなぐ少女
レアはゼピック村の詩人で、失くしたハーモニカを探しているというサブイベントで登場する。彼女の登場シーンは短いが、その存在感は非常に大きい。彼女が奏でるハーモニカの旋律、そして“Feena”という曲は、ゲーム全体を貫く主題としてプレイヤーの心に刻まれる。 彼女は物語上、フィーナと深い関わりを持っており、2人の関係は神話の双子のようでもある。レアは人間的で感情豊か、フィーナは神秘的で静謐。その対比が見事で、どちらも“イース”という世界を象徴する存在として描かれている。 レアの魅力は、悲しみを抱えながらも前を向こうとする強さにある。彼女は自らの運命を受け入れつつ、最後まで人としての心を失わない。その姿勢が、プレイヤーに“優しさとは強さである”というメッセージを与える。 短い登場ながら、シリーズ全体を通して語り継がれる象徴的存在となったのは、彼女が奏でた一曲のメロディが、作品の“魂”そのものであったからだ。
ドギ──力と友情の象徴
アドルの頼れる仲間・ドギ(Dogi)は、物語中盤以降で印象的な活躍を見せる。彼は盗賊団の一員として登場するが、その心根は善良であり、仲間思いの性格が魅力だ。 ドギの特徴は、壁を壊して道を切り開く豪快な行動力にある。彼はしばしばトラップに閉じ込められたアドルを救うが、その際のセリフ「壁を壊すのも楽じゃないんだからな!」は、シリーズファンの間で名言として語り継がれている。 力任せのキャラクターでありながら、単なる脳筋ではない。彼はアドルを心から信頼し、どんな危険にも笑って飛び込む。後のシリーズでも“相棒”として再登場し、イース世界の“人間らしい友情”を象徴する存在として定着していく。 ドギの登場によって、物語に“人の温かさと頼もしさ”が加わり、孤独な冒険者アドルの物語に彩りを与えている。
サラとジェバ──知恵と導きの象徴
ゼピック村の占い師サラは、アドルに“イースの本”を探す使命を託す人物である。彼女は単なる情報提供者ではなく、運命の分岐点でアドルを導く“賢者”のような存在だ。 その落ち着いた言葉の端々には、“人が自らの力で運命を切り開くべき”というメッセージが込められている。彼女の死後、アドルはその想いを胸に冒険を続けることになる。彼女は表舞台を去っても、物語の精神的支柱であり続けるのだ。 また、サラの叔母であるジェバは、物語に“人間的な温かみ”を与えるキャラクターである。彼女はフィーナを引き取り、まるで娘のように世話をする。その姿は、エステリアという荒んだ世界における“母性”の象徴でもある。 サラとジェバの二人が示す“知恵と愛”の対比は、『イースI』が単なる冒険譚ではなく、“人の心”を描いた物語であることを明確にしている。
ゴーバン──盗賊にして哲人
ゴーバンは一見すると粗暴な盗賊団の頭だが、アドルと出会うことで本質が明らかになる。彼は権力や金ではなく、“自由に生きること”を信条としている人物であり、アドルにとってはもう一人の師匠のような存在だ。 彼のセリフにはどこか哲学的な響きがあり、単なる悪人ではないことがすぐに伝わる。戦乱の世を知る大人として、若きアドルに“生き方の選択”を教える役割を担っている。 また、彼の側近であるドギとの関係性も深く、師弟愛にも似た絆が感じられる。ゴーバンが敵としてではなく“共に戦う仲間”として描かれた点は、当時としては非常に珍しい。善悪の二元論を超えた人間ドラマを、わずかな登場シーンで表現した秀逸なキャラクターといえる。
ルタ──夢と現実のはざまで揺れる青年
夢遊病に悩む青年ルタは、物語の中では小さな存在かもしれない。しかし、彼の描写には“人間の弱さ”と“希望”の二面性が凝縮されている。 ルタは自らの意思で行動できない悲しみを抱えつつも、最後には自分を取り戻す。その過程は、アドルが外の世界で戦うのに対して、ルタが内面の世界で戦っているようにも見える。 『イースI』の中で彼が果たす役割は小さいが、彼の物語は“心の解放”というテーマを象徴しており、プレイヤーに静かな印象を残す。シリーズ全体を通しても珍しい、“脇役なのに心に残る人物”である。
ラーバ──知識の探求者としてのロマン
考古学者ラーバは、イース文明の謎を追う学者であり、プレイヤーの分身とも言える存在だ。彼は知識を求めるあまり危険に身を投じるが、その姿勢はアドルと共鳴している。 ラーバの存在があることで、『イースI』は単なる冒険譚から“知的探求の物語”へと深みを増す。彼は人類の知への渇望を象徴するキャラクターであり、科学と神話が交錯するこの世界の構造を体現している。 彼の言葉の一つひとつが、後のシリーズに繋がる“歴史を継承する意志”を示しており、静かだが重要な役割を果たしている。
キャラクターの魅力の総括──人間味と神話性の融合
『イースI』のキャラクターたちは、すべてが“物語を動かす歯車”でありながら、それぞれが一人の人間として生きている。勇気、悲しみ、愛、犠牲――そのどれもが過剰に描かれず、余白を持って表現されている。 プレイヤーが彼らを好きになるのは、単に見た目や台詞の魅力ではなく、“行動ににじむ人間性”に共感するからだ。 この“人間味と神話性の融合”こそが、『イースI』という作品の最大の魅力であり、アドルを中心とした群像劇としての完成度を支えている。 だからこそ、プレイヤーはゲームを終えた後も、彼らの姿を心のどこかで覚えているのだ。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
各機種版の登場背景──マルチプラットフォーム展開の先駆け
1987年当時、日本ファルコムが『イースI』を複数のパソコン向けに同時期展開したことは、業界的にも極めて珍しい試みだった。当時のPC市場はメーカーごとに仕様が異なり、PC-8801、PC-9801、MSX、X1、FM77AV、そしてのちにX68000といった機種が競合していた。 ファルコムはこれらすべてに対応することで、より多くのユーザーに作品を届けようとした。結果として、『イースI』は“どのパソコンでも遊べる名作”として広く知られるようになり、国産ARPGの普及に大きく貢献した。 ただし、それぞれのハードウェア性能や音源チップ、グラフィック表示方式が異なるため、各バージョンには個性があり、ファンの間では“どの機種版がベストか”という議論が今なお続いている。
PC-8801版──原点にして完成形
PC-8801mkIISR以降で動作するこのバージョンが、ファルコムが最初に制作したオリジナル版である。グラフィックは8色表示ながら、独特の色使いで幻想的なエステリアの風景を見事に表現していた。 サウンド面では、内蔵FM音源(YM2203)を駆使したBGMが高く評価されている。古代祐三による楽曲は、この機種の音色を前提に作曲されており、まさに“イースの音”を確立したともいえる。 また、処理の軽快さも特筆すべき点で、ロード時間が短く、画面切り替えもスムーズ。PC-8801版を基準に、他機種への移植が行われたため、全体的なバランスの良さでは今も“原典”として評価されている。
PC-9801版──高解像度と洗練された表示
PC-9801版は、8801版をベースに解像度と発色数が向上しており、より鮮明で美しいグラフィックを実現している。特にキャラクタースプライトや背景の陰影処理が改善され、塔や神殿の荘厳さがより際立つ。 また、テキストフォントも読みやすく整えられており、物語の没入感が高まっている点も好評だった。 音源についてはFM音源ボード(86ボード)対応で、音の広がりと低音の深みが増した。8801版に比べて音の解像度が高く、特に「First Step Toward Wars」のイントロの迫力はファンの間で語り草となっている。 動作速度はハード性能に比例してやや速く、プレイヤーによっては“テンポが軽快すぎる”と感じることもあったが、全体的には完成度の高い上位版として知られる。
MSX2版──移植の試みと独自の味わい
MSX2版は、家庭向けとして普及していたMSXシリーズへの挑戦であった。しかし、このバージョンはハード性能の制約から、スクロールが遅く処理落ちが発生しやすいという難点を抱えていた。 それでも、色数やサウンドチップ(OPLL)による表現力は侮れず、特に音楽の再現度においては高く評価されている。MSXらしい柔らかな音色が、“やや牧歌的なイース”という印象を与えた。 ゲームバランスはほぼオリジナル準拠だが、戦闘時の当たり判定や敵の動作が微妙に異なり、やや難易度が上昇している。ファルコムの技術チームが限られたメモリ空間で忠実に移植を行った努力は、今でも高く評価されている。 総じて「技術的な挑戦を感じる誠実な移植」であり、MSXユーザーにとっては“自分たちのイース”として特別な思い入れを持つファンも多い。
FM77AV版──サウンドの真髄を味わえる名移植
FM77AV版は、BGMの音質面で最も評価の高いバージョンのひとつである。富士通のFM音源は音の厚みと表現力に優れており、古代祐三の楽曲をより立体的に再現している。 特にラストバトルBGM「Final Battle」は、オリジナルでは1フレーズしか存在しなかったが、FM77AV版では後半のメロディが追加されている。これにより、戦闘の緊張感と盛り上がりが格段に増しており、ファンの間では“真の完全版”と称されることもある。 また、グラフィック面では色の再現性が高く、他機種よりも柔らかい雰囲気を持っている。ゲーム全体のテンポも安定しており、ロードのストレスも少ない。 音楽重視のプレイヤーにとっては、FM77AV版こそ“耳で楽しむイース”として理想的な選択肢であった。
X1版──シャープな映像と滑らかな動作
シャープのX1版は、PC-8801版をベースに移植されたものであるが、独自のハード特性を活かして表示が非常に鮮明で、色の発色がクリアであった。 背景のコントラストが強めに設定されており、塔の外壁や洞窟の陰影がより立体的に見える。この視覚的な“硬質感”がX1版特有の雰囲気を作り出している。 動作も非常に軽く、敵の動きやスクロールも滑らかで、操作レスポンスが良い。X1特有の冷たい音質のFM音源も相まって、“緊張感のあるイース”という印象を与えるバージョンである。 グラフィックの美しさではPC-9801に次ぐクオリティと評され、限られたメモリ容量の中でここまで再現できた技術力は見事の一言に尽きる。
X68000版──究極のリメイク的存在
1988年に発売されたX68000版は、単なる移植ではなく“リファイン版”として位置づけられている。 X68000は当時、16ビットCPUと高解像度グラフィックを備えたハイエンドマシンであり、その性能を最大限に活かした豪華なビジュアルが実現された。背景は細部まで描き込まれ、キャラクターアニメーションも滑らか。BGMもFM音源+PCMのハイブリッド再生で、重厚なサウンドスケープを構築している。 特に塔の内部で流れる「Palace of Destruction」は、音圧と臨場感が他機種を圧倒しており、シリーズファンの間では“決定版”とされることが多い。 また、操作感も非常に洗練され、入力レスポンスが軽快。アドルの動きがより自然で、体当たり戦闘の精度も向上している。 このバージョンは、のちの『イース・エターナル』や『クロニクルズ』などのリメイクにおける“理想形”の原型ともいえる存在である。
音楽の差異──機種ごとの個性が生んだ名演
同じ曲でありながら、機種ごとにサウンドチップの違いがもたらす印象の差は非常に大きい。 PC-8801のシャープで硬質な音、FM77AVの暖かく包み込むような音、X68000の立体的で迫力ある音像──どれも同じメロディでありながら、聴く者の感情を異なる方向に揺さぶる。 こうした違いがファンの議論を盛り上げ、後年には「各機種版サウンド比較」のような同人CDまで制作されたほどである。ファルコムサウンドが“文化”として根付いた背景には、この多様な機種ごとの表現差が大きく関係している。
ファンによる評価とプレイ体験の違い
どの機種にもファンが存在し、今なお「自分が最初に遊んだイースが一番」と語られる。 PC-8801版は“原点としての完成度”、PC-9801版は“映像美”、FM77AV版は“音楽の厚み”、MSX2版は“温かい懐かしさ”、X68000版は“究極の進化版”として、それぞれ異なる価値を持っている。 また、機種ごとにキー操作の配置やレスポンスも異なり、プレイヤーの感覚に微妙な違いを生んだ。これらの差異が、プレイヤー一人ひとりの“思い出のイース”を形づくっている。 結果として、『イースI』は単なる一作品ではなく、“時代ごとに姿を変える伝説”として語り継がれることになったのだ。
総括──技術と情熱が融合したマルチ展開の金字塔
こうして見ると、『イースI』のマルチプラットフォーム展開は、単なる移植の枠を超えた“文化的実験”だったといえる。 それぞれの機種の性能に合わせて最適化しながらも、作品の本質──音楽、テンポ、感情表現──を損なわずに届けたファルコムの職人技は、まさに時代を先取りしたものだった。 機種ごとに表現の幅を広げ、プレイヤーの環境に合わせて最良の体験を提供するという発想は、現代のマルチプラットフォーム開発にも通じる哲学である。 『イースI』は、PC黎明期における“統一なき多様性”を乗り越えた奇跡の作品として、今なおファンの記憶に鮮烈に残り続けている。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
★ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー(日本ファルコム/1987年/価格7,800円)
ファルコムの代表的シリーズ『ドラゴンスレイヤー』の第4作にあたる作品で、『イースI』と同年に登場した。アトレイ家の家族がそれぞれの能力を活かしてダンジョンを攻略するという、ファミリー感あふれる構成が話題を呼んだ。 子どもが小さくて通れない通路を抜けたり、父親が重いブロックを動かしたりと、キャラクターごとに攻略ルートが異なる設計は当時として画期的だった。 アクション性の高さとパズル的思考を融合させた設計は、のちのメトロイドヴァニア系ゲームにも影響を与えている。『イースI』と同様に、“プレイヤーに考える楽しさを与える設計”という点で共通点の多い作品である。
★ハイドライド3(T&Eソフト/1987年/価格8,800円)
『ハイドライドII』で培われたアクションRPGの土台をさらに発展させたタイトル。時間経過や空腹度といったリアルタイム要素を取り入れ、世界をより“生きた環境”として描いた意欲作である。 3D視点のフィールド移動と、滑らかなアニメーションで表現された敵キャラが特徴的で、当時としては極めて先進的な設計だった。 『イースI』が“優しさ”を打ち出したのに対し、『ハイドライド3』は“現実感”を追求しており、同じARPGジャンルでありながら方向性の対比が興味深い。ファルコムとT&Eソフト、両者の哲学の違いを象徴する1987年の名作である。
★夢幻の心臓III(クリスタルソフト/1987年/価格9,800円)
国産RPGの草分け的存在として知られる『夢幻の心臓』シリーズの最終作。広大なマップと複雑な謎解き、重厚な世界観が特徴で、当時のプレイヤーを圧倒した。 物語は“人間の心”と“神の試練”をテーマにしており、哲学的なセリフや詩的な演出が多く、ハードな戦闘と静謐な語りの対比が印象的だった。 『イースI』が短く濃密な構成で心を掴む一方で、『夢幻の心臓III』は長大で深い没入感を追求しており、1987年は“RPGの多様性”が花開いた年であったと言える。
★ソーサリアン(日本ファルコム/1987年/価格9,800円)
ファルコムが『イースI』と同年にリリースしたもう一つの看板作品。アクションRPGにキャラクター育成とシナリオ追加システムを組み合わせた革新的タイトルである。 複数のシナリオを選んで遊ぶ構成、キャラの寿命・世代交代の要素など、自由度と長期的な育成要素を併せ持つ。 『イースI』が“物語の完成度”で魅せたのに対し、『ソーサリアン』は“拡張性と継続性”を提示した。まさに同一メーカー内で“二つの進化系ARPG”が誕生した象徴的な一年だった。
★ザナドゥ シナリオII(日本ファルコム/1987年/価格7,800円)
1985年のヒット作『ザナドゥ』の追加シナリオとして発売された本作は、シリーズ中でも特に高難度で知られる。 「ファルコム地獄」とまで呼ばれたその厳しさは、イースの“優しさ”と対極に位置する哲学的挑戦であった。 マップ構成の複雑さ、限られたリソース管理、非情な敵配置など、プレイヤーに“考えることを強制する”設計が特徴的で、まさに知恵と忍耐のゲームといえる。 この作品が存在したからこそ、『イースI』の「誰もがクリアできるRPG」という思想がより鮮明に際立ったのだ。
★ヴァリス(日本テレネット/1987年/価格8,800円)
“女子高生が異世界で戦う”という斬新な設定で話題を集めたアクションRPG。主人公・優子のビジュアルとアニメ調の演出は、当時の若年層プレイヤーに強烈な印象を残した。 ゲーム内ではアニメカットインを多用し、物語性を重視した演出が導入されている。これは『イースI』の“ストーリーで魅せるRPG”という方向性と共通しており、両作が“演出重視RPG時代”の幕開けを象徴していた。 また、音楽面ではテレネットサウンドチームによるシンセアレンジが高く評価され、“サントラ文化”を広めた点でもイースと並ぶ功績を残している。
★ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士(アスキー/1987年/価格9,800円)
海外発のRPG『ウィザードリィ』シリーズ第3作の日本版。国産PCユーザーに“ダンジョン探索RPG”の真髄を知らしめた作品である。 キャラクターロストや罠の緊張感は健在で、イースとは対照的な“シビアなロールプレイ体験”を提供した。 『イースI』が感情的な没入を重視したのに対し、『ウィザードリィIII』は戦略的・論理的思考を鍛える方向性で、RPGジャンルの幅を広げた存在といえる。
★デジタル・デビル物語 女神転生(T&Eソフト/1987年/価格9,800円)
原作小説をベースに制作されたこの作品は、“現代を舞台にしたRPG”という点で極めて異色だった。 悪魔召喚や交渉システムなど、後のメガテンシリーズの基礎を築いた意欲作である。 『イースI』が幻想世界で人の心を描いたのに対し、『女神転生』は科学と信仰、倫理と暴力といった現代的テーマに踏み込んだ。1987年のRPG界は、もはや“剣と魔法”だけでは語れない新時代に突入していたことを象徴している。
★ダンジョンマスター(FTL/日本語版発売1987年/価格9,800円)
3DリアルタイムダンジョンRPGとして登場した本作は、世界中のプレイヤーに衝撃を与えた。 マウス操作とリアルタイム行動、立体的なマップ設計など、当時の日本のPCではまだ見ぬ革新技術が詰まっていた。 『イースI』が“プレイヤーの感情”に訴える体験を重視したのに対し、『ダンジョンマスター』は“プレイヤーの感覚”そのものを試すゲームデザインを提示した。 この対照性こそ、1987年という年が“RPG進化の分岐点”であった証と言える。
★ブラックオニキス(BPS再販版/1987年/価格6,800円)
1984年に登場した国産RPGの先駆けだが、1987年にリメイク版が再発売され、新世代ユーザーにも広く知られることとなった。 滑らかな操作性とシンプルなインターフェースは、『イースI』の“遊びやすさ”の哲学に通じるものがあり、旧世代から新世代への橋渡し的存在とされた。 リメイク版ではBGMやビジュアルが刷新され、再び市場で注目を集めたことで、“国産RPGの歴史”を再認識させた功績を持つ。
総括──1987年は国産RPGの転換点
1987年は、まさに“RPG黄金期”の幕開けだった。『イースI』が「誰でも楽しめるRPG」を提示し、『ハイドライド3』が“現実的な挑戦”を、『ソーサリアン』が“拡張の概念”を、『女神転生』が“思想性”を打ち出した。 この年の作品群は、以後の日本ゲーム史において「多様性の起点」として位置づけられる。 中でも『イースI』は、感情・音楽・テンポ・物語を融合した“新しいRPGの形”を提示し、以降のRPGに“優しさ”という価値を根づかせた。 1987年という年は、単なる技術革新の年ではなく、“プレイヤーとゲームの関係”そのものが変わった象徴の年なのである。
[game-8]