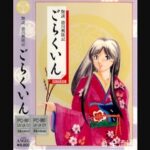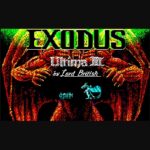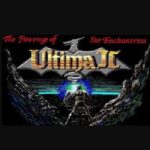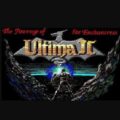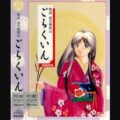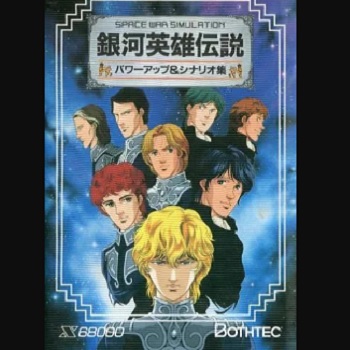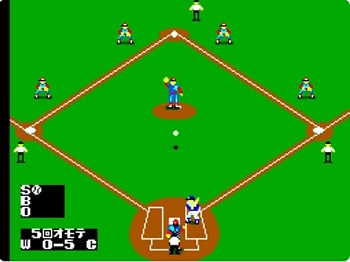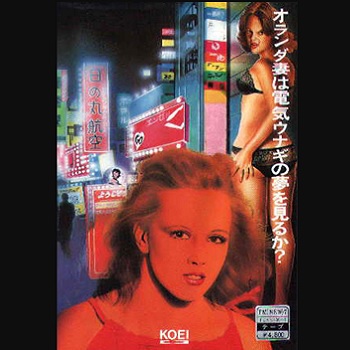
【セール】7/2発売 ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB 14型 165Hz Webカメラ 顔認証 Wi..
【発売】:光栄
【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、FM-7
【発売日】:1984年11月
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム
■ 概要
● 光栄が送り出した「黒歴史」とも呼ばれる一本
1980年代前半、まだ「信長の野望」や「三國志」といった歴史シミュレーションで名を上げる前の光栄は、いくつかの成人向けタイトルを通してパソコンゲーム市場に挑んでいました。その中でとりわけ強烈な存在感を放っているのが、1984年にPC-8801/PC-9801/FM-7向けに発売された「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」です。現在では“光栄の黒歴史”と冗談交じりに語られることも多い作品ですが、当時としてはアダルト要素と本格的なゲーム性を組み合わせた意欲作であり、日本の美少女ゲーム史・アダルトゲーム史を語るうえで欠かせない一本とされています。
● ストロベリーポルノシリーズ第2弾として誕生
本作は、光栄のアダルトレーベル「ストロベリーポルノシリーズ」に属するタイトルで、「団地妻の誘惑」に続く第2弾という扱いです。シリーズ自体は、「ナイトライフ」「団地妻の誘惑」「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」の3本を中心に語られることが多く、コアなパソコンユーザーのあいだでは“光栄アダルト三部作”といった呼び方も広まりました。アダルトであることを売りにしながらも、単なるお色気ソフトではなく、きちんとした世界設定やゲームシステムを備えたパッケージソフトとして流通していた点が特徴です。
● タイトルの由来とSFパロディとしての側面
長くてインパクトのあるタイトルは、アメリカのSF作家フィリップ・K・ディックの長編小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」のもじりです。原作小説は映画「ブレードランナー」の原作として有名であり、近未来の荒廃した都市で人造人間を追うハードボイルド風SFです。本作は、そのタイトルを大胆にパロディ化しつつ、火星製の高性能ダッチワイフや歌舞伎町風歓楽街といった要素を盛り込み、エロティックでありながらもどこかマヌケで“すこし不思議”なSF世界を作り上げています。真面目なSFへの敬意と、アダルトゲームならではのゆるいノリとが同居している点が、本作の雰囲気をよく表しています。
● 舞台は近未来東京・歓楽街「カブキチョウ」
物語の舞台は199X年という近未来の東京です。街では孤独な独身男性が不可解な死を遂げる事件が相次いでおり、警察は専従の捜査本部を立ち上げながらも、決定的な手がかりを掴めずにいました。犠牲者たちには「死ぬ直前にダッチワイフを購入していたが、現場から人形が消えている」という共通点があり、そこに何らかの秘密が隠されているのではないかと推測されます。プレイヤーが操作する主人公は、そんな折にダッチワイフメーカー「オランダ商会」から奇妙な依頼を受ける私立探偵です。依頼内容は“3日以内に同社製の高性能ダッチワイフ「北極6号」を3体集めろ。その間、午前11時から2時間おきに会社へ連絡せよ”というもの。金に困っている主人公はしぶしぶ依頼を受け、東京の歓楽街「カブキチョウ」へと足を踏み入れることになります。 この「カブキチョウ」は、現実の新宿・歌舞伎町を思わせるネーミングで、ナイトクラブやバー、風俗店らしき店が並ぶ大人の街として描かれます。マップ上には路地やビル街が広がり、さまざまな人々が行き交う様子を、当時の8ビットパソコンとしてはかなり頑張ったグラフィックで表現していました。
● 探偵RPG+アドベンチャーというハイブリッド構成
本作のジャンルは、ロールプレイングゲームとアドベンチャーゲームの要素を併せ持ったハイブリッド型とされています。プレイヤーはカブキチョウの俯瞰マップ上で主人公を移動させ、聞き込みをしながら事件の真相に迫っていきます。マップ中で人影や店の入口に接触すると、画面は会話やコマンド選択が中心のアドベンチャーパートに切り替わり、「話す」「調べる」「買う」といった行動を通じて情報やアイテムを集めていきます。これにより、RPG的な探索とアドベンチャー的な謎解きが交互に現れるテンポの良いゲーム進行が実現されていました。 また、主人公の能力値はゲーム開始時にルーレット形式で決定される仕組みになっており、毎回少しずつ違うパラメータでスタートすることで、リプレイするたびにプレイ感触が変わるよう工夫されています。体力や経済力、対人交渉に関わるステータスなどが変動し、それによって選べる選択肢や攻略の難易度にも差が出てくるため、当時の作品としては意外なほど遊びごたえのある設計と言えます。
● 成人向け要素とゲーム性の結びつき
「ストロベリーポルノシリーズ」の作品群は、性的な要素をただ画面に並べるのではなく、ゲームのルールや世界観に組み込もうとする姿勢が特徴とされています。本作も例外ではなく、登場人物との親密な関係はストーリー進行や謎解きに関わる要素として位置づけられています。主人公は聞き込みや捜査の一環として、さまざまな女性(そして、場合によってはそうでない相手)と親密な関係になることもありますが、それは専ら“情報を得るため”“相手が人間か高性能ダッチワイフなのかを見分けるため”という物語上の必然として扱われます。 一方で、行き過ぎた行動を取ると、あっさりとバッドエンドに直行することもあり、単に好奇心のまま選択肢を選んでいるとすぐに痛い目を見るバランスになっています。成人向けの題材を扱いながらも、ゲームとしての駆け引きやリスク管理を意識させるデザインになっている点は、後年シミュレーションゲームで評価を高める光栄らしい部分と言えるでしょう。
● 対応機種と発売形態
対応プラットフォームは、当時の主力8ビットパソコンであるPC-8801シリーズ、PC-9801シリーズ、そしてFM-7系統の3系統です。PC-8801/9801版では5.25インチフロッピーディスク1枚組のパッケージとして販売され、価格は7,800円前後という、当時のパソコンゲームとして標準的なレンジに設定されていました。 FM-7系ではカセットテープ版も存在し、ロード時間こそ長いものの、より安価なメディアとしてユーザー層を広げていました。こうした複数機種・複数メディア展開は、まだ市場が成熟しきっていなかった80年代前半ならではの光景であり、「少しでも多くのユーザーに届けたい」というメーカー側の事情も透けて見えます。
● 現在から見た「オランダ妻」の位置づけ
今日では入手困難なレトロアダルトゲームであり、公式に再発売される見込みもほとんどないことから、実際にプレイしたことのある人は限られています。しかし、雑誌記事やWebの回顧記事ではしばしば名前が挙がり、美少女ゲーム史やPC-8801ゲーム史を振り返るうえで、象徴的な作品として扱われることが多くなっています。 光栄という大手メーカーが、黎明期にこうした刺激的な作品を手がけていたという事実自体が、80年代パソコンゲーム文化の「何でもあり」な空気を物語っていますし、タイトルのセンスや設定の突拍子のなさ、そして妙に本格的なゲームシステムなど、どこを切り取っても話のネタに事欠きません。まさに、当時の勢いと遊び心がそのままパッケージになったような作品だと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● タイトルからしてプレイヤーを惹きつける強烈なインパクト
「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」という長く奇妙なタイトルは、初めて耳にした瞬間から強烈な印象を残します。真面目なSF小説の題名をもじりながら、「オランダ妻」「電気ウナギ」といった俗っぽい言葉を組み合わせた結果、品の良さと悪ふざけがごちゃ混ぜになった独特のムードが生まれています。当時のパソコンショップで、このタイトルがずらりとパッケージ棚に並んでいた光景を想像するだけでも、80年代前半の“何でもあり”な空気が伝わってくるようです。まだアダルトゲームというジャンルが定着しておらず、メーカーも手探りで挑戦していた時代に、ここまで突き抜けたタイトルを掲げられたのは、ある種の勢いと遊び心の賜物と言えるでしょう。タイトルを見ただけで内容が気になり、「どんなゲームなのか確かめてみたい」と思わせるフックとして、現在の視点で見ても非常に優秀です。
● 探偵RPGとアダルトADVを融合させた欲張りなゲーム設計
本作最大の魅力は、「私立探偵もののRPG」と「アダルトアドベンチャー」を1本にまとめてしまったような、ハイブリッド構成にあります。プレイヤーは私立探偵である主人公を操作し、俯瞰視点のマップを歩き回って聞き込みを行い、事件の真相や逃亡中の“北極6号”を追い詰めていきます。マップ上を移動して情報を集める部分はRPG的なフィールド探索であり、店や建物に入るとコマンド選択式の画面に切り替わってアドベンチャーゲーム的な聞き込みや調査が始まる──この切り替えのテンポが良く、単調な会話だけに終始せず、適度に“街を歩いている感覚”を味わえるようになっているのです。 当時のアダルト作品の中には、テキストと静止画だけの単純なゲームも少なくありませんでしたが、本作は明確な目的と制限時間、パラメータ管理やマップ探索など、かなり本格的なRPG的要素を備えていました。「エロいから買う」というより、「ゲームとして面白そうだから欲しい」と思わせる構造になっている点が、後年まで名前が語り継がれる理由のひとつでしょう。
● 制限時間と定期連絡が生み出すスリルと緊張感
ゲーム内では、依頼主であるオランダ商会から「3日以内に北極6号を3体探し出せ」「午前11時から2時間おきに必ず電話して報告せよ」という条件が課せられます。これは単なる設定ではなく、ゲームの重要なルールとして機能しており、決められた時間に連絡を怠ると依頼は打ち切りとなり、その時点でゲームオーバーになることもあります。プレイヤーは街を探索しつつ、時計の針の進み具合を気にかけながら行動しなければならず、「あの店に寄り道したいけれど、電話の時間を過ぎてしまわないか」「今は聞き込みを続けるべきか、それとも事務所に戻るべきか」といった判断を常に迫られます。 この“タイムリミット”は、ゲーム全体に適度な緊張感とスリルを与えています。のんびりとイベントを回収しているだけでは時間切れになってしまうため、いかに効率よく情報を集めて北極6号に辿り着くか、ルートを工夫する楽しみが生まれています。限られた時間の中で成果を上げるという構造は、後のビジネスSLGや歴史SLGにも通じる光栄らしい設計思想の萌芽としても注目できます。
● ルーレットで決まる能力値と毎回変わるプレイ感覚
主人公のパラメータをゲーム開始時にルーレットで決めるシステムも、本作ならではの魅力です。体力や財力、女性に対する魅力、情報収集力など、探偵としての資質を表す数値がランダムに振り分けられ、プレイごとに微妙に異なるキャラクターが出来上がります。能力が高い項目が多いと攻略が有利になる一方で、どれかのパラメータが極端に低いと、思わぬところで苦戦することもあります。 例えば、金回りが悪い主人公だと、情報を得るために必要な飲食代やプレゼント代を捻出するのに苦労し、頻繁にアルバイトをして資金を確保しなければならないかもしれません。逆に金はあるが体力が低いキャラクターだと、街を走り回っているだけで消耗しやすく、余計な移動を避けるルートづくりが重要になるでしょう。このように、スタート時点の“運”がプレイスタイルに影響を及ぼすため、「今回はどんな探偵として生きることになるのか」というワクワク感が生まれます。
● ユーモアと不条理が混ざり合った独特の世界観
ストーリーやイベントの端々には、真面目な推理ものとは一線を画す、かなりクセの強いユーモアが仕込まれています。火星からやってきた高性能ダッチワイフという設定自体がすでに相当なトンデモぶりですが、その上で歓楽街にたむろする人物たちも、どこか現実から半歩ズレたキャラクターとして描かれています。 真面目そうな会社員が妙に壊れた発言をしたり、警官にまで言い寄ることができてしまったり、常識的に考えるとありえない状況がさらっと差し込まれ、プレイヤーは思わず笑ってしまいます。こうした“悪ふざけのセンス”と、ハードボイルド風の探偵ドラマの雰囲気が同居していることで、本作は単なるエロパロディを超えた奇妙な味わいを持つ作品になっています。真面目なのか、バカなのか、その境界線があやふやな独特の空気感こそ、今も語り草になっている魅力と言えるでしょう。
● アダルト要素が「ゲームのルール」として機能する面白さ
本作における性描写は、単なるご褒美シーンではなく、ゲームの重要な仕掛けとして位置づけられています。主人公は、調査の過程で出会った人物と肉体関係を持つことができ、その結果として情報を引き出したり、相手が人間なのか、危険なダッチワイフなのかを判断したりします。しかし、むやみに関係を持とうとすると危険で、特定のアイテムを使わずにダッチワイフと行為に及ぶと、即座に“過剰な快感”によって昇天してしまい、ゲームオーバーになってしまうこともあります。 つまり、プレイヤーは性的な誘惑に対して“慎重な判断”を求められるのです。「ここで関係を持つべきか、それとも情報を得る別の手段を探すべきか」「この相手は人間なのか、それとも危険な人形なのか」といった読み合いが発生し、アダルト要素がそのまま緊張感とゲーム性に結び付いています。単に刺激的なだけでなく、ルール上のリスクと報酬のバランスが設計されている点が、本作をゲームとして面白くしている要因の一つです。
● 8ビット時代ならではのグラフィックとサウンドの味わい
ビジュアル面では、640×200前後の解像度と限られた色数を駆使し、歓楽街のネオン、ビルの立ち並ぶ路地、怪しげな店内の雰囲気などが、ドット絵ならではの味わいで表現されています。現在の視点から見れば粗い描線ではありますが、逆にその“想像の余地”がプレイヤーの妄想をかき立て、テキストと組み合わさることで独特の臨場感を生み出していました。また、パソコンのBEEP音やFM音源を使ったシンプルなBGMや効果音も、夜の街を歩き回る緊張感や、イベント発生時のドキドキ感をうまく演出しています。 アダルトゲームというジャンルは、のちに高解像度グラフィックやボイス付きの豪華な演出が当たり前になっていきますが、本作のような黎明期の作品は、限られた表現手段の中でいかに雰囲気を出すかが勝負でした。その結果として生まれた「粗いけれど想像を刺激する」グラフィックや、「妙に耳に残る」BGMは、当時を知るユーザーにとって忘れがたい魅力のひとつになっています。
● 光栄作品らしい“数値とシステム”の面白さ
光栄と聞くとシミュレーションゲームのイメージが強いですが、本作にもそうした“数値いじりの楽しさ”が片鱗として現れています。主人公の能力値管理、所持金のやりくり、時間制限、アイテムの使いどころなど、目に見えないパラメータを頭の中で組み立てながら最適な行動を選んでいく感覚は、のちの「信長の野望」や「三國志」と共通する部分があります。軽妙なテキストとアダルト要素に目が行きがちですが、真面目にルートを研究し、アイテムや行動順を最適化することで、より効率よく北極6号に辿り着けるようになる“攻略の余地”がしっかり存在しているのです。 単なるネタソフトではなく、「何度も遊べるゲーム」として成立していることが、本作の評価を支えている大きなポイントと言えるでしょう。
● 時代を先取りした“境界線ギリギリ”の表現
警官を含むさまざまな相手にアプローチできてしまう自由度の高さや、社会的なタブーすれすれのネタをギャグとして織り込む姿勢は、現在の倫理基準から見ると危うい部分もありますが、逆に言えば“その時代だからこそ実現できた表現”でもあります。テレビや家庭用ゲームでは到底扱えない題材を、パソコンという比較的クローズドな世界で思い切り振り切って見せた点が、当時のユーザーに強烈な印象を焼き付けました。 こうした“境界線ギリギリ”のセンスは、のちのサブカルチャー作品やギャグ漫画が取り扱う表現とも通じる部分があり、当時としてはかなり先鋭的な試みだったと言えます。時代が変わった現在から振り返ると、良くも悪くも80年代らしい大胆さと荒削りさが、そのまま魅力として封じ込められた作品だと感じられるでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
● 最初に押さえておきたい基本方針とプレイスタイル
本作を遊ぶうえで最初に意識したいのは、「時間」「お金」「体力」「情報」という四つのリソースをどうバランス良く回していくか、という点です。主人公は私立探偵として火星製ダッチワイフ「北極6号」を3体探し出さなければなりませんが、好きなだけ街を歩き回っていれば自然に見つかるというほど甘い構造にはなっていません。限られた日数と定期連絡の制限、体力の消耗、聞き込みや飲食にかかる費用など、行動には常にコストが付きまといます。したがって、攻略の第一歩は「とにかく歩き回る」ではなく、「目的地と寄り道を事前にイメージしながら効率的に巡回する」ことにあります。同じ場所を何度も往復していると時間も体力もむだに消耗してしまうため、ある地区に入ったら一気に用事を片付けてから別のエリアへ移動する、というように、一筆書きのルートを頭の中で描きながら進めると安定しやすくなります。
● 能力値ルーレットでの“キャラメイク”とリセット判断
ゲーム開始時に実行されるルーレットによる能力値決定は、プレイの難易度を大きく左右します。特に重要なのは「所持金」「体力」「対人交渉に関わるパラメータ(例えば色気や話術に相当する値)」の三つで、これらがあまりにも低いと、序盤から何をするにも苦しくなりがちです。攻略を意識するなら、最初に能力値が表示された段階で「これは明らかに厳しそうだ」と判断した場合には、思い切ってリセットしてやり直すのも手です。あまりストイックになりすぎる必要はありませんが、最低限「体力が極端に低すぎない」「初期資金がまったくのゼロに近いわけではない」といったラインを自分の中で決めておくと、無用な苦戦を避けることができます。逆に、運良くバランスの良いパラメータが出たときは、その周回でしっかりルートを研究しておくと、次回以降、多少不利な能力値でも経験でカバーしやすくなるでしょう。
● タイムリミットと定期連絡の管理術
物語が進行するあいだ、主人公は一定時刻ごとにオランダ商会へ電話して状況報告をしなければなりません。これを怠ると即座に依頼打ち切り、ゲームオーバーという展開もあり得るため、時計の確認は常に頭の片隅に置いておく必要があります。攻略のコツは、「次の連絡時間までに何ブロックくらい移動できるか」「何件分の聞き込みやイベント消化が可能か」を大まかに把握して行動することです。例えば、残り時間が少ないのに反対側のエリアへ移動しようとするのは危険な選択ですし、逆に時間に余裕があるなら、電話をかける前に近場の店一軒だけ覗いて情報を拾っておく、といった細かな調整もできます。また、あえて少し早めに連絡を済ませ、電話から電話までのあいだを“自由行動タイム”としてまとめて使うのも有効な戦術です。こまめに時計を確認する癖をつけ、「次の報告まではこのエリアで徹底的に聞き込みを行う」といった短期目標を設定しながら進めると、タイムリミットに追われる焦りを軽減しつつ計画的に攻略できます。
● マップ探索と聞き込みの優先順位づけ
歓楽街カブキチョウには多くの店舗や路地が存在し、片っ端から入っていくだけでも膨大な時間がかかります。そこで重要なのが、聞き込みの優先順位を付けることです。最初は地図感覚を掴むために一通り歩き回るのも悪くありませんが、ある程度地形を把握したら、「情報が得られやすい場所」「単なる時間つぶしになりがちな場所」を見極めていきましょう。一般に、酒場やバー、クラブ、情報屋風の人物が出入りしているエリアは有力な手がかりが多く、逆に特定のイベントを終えた後はほとんど新しい情報が出てこない場所もあります。何度訪れても同じ反応しか返ってこない店は、以後は寄り道候補から外してしまい、その代わりに「一度だけ訪れた怪しげな路地」「まだ奥まで入っていないビルの上階」など、未探索のポイントを重点的に攻めると効率が上がります。同じ場所で延々と会話ボタンを押すのではなく、「この店はもう用済み」「この人物は後半に再訪すると変化がありそう」といった印を心の中で付ける感覚で、探索対象を取捨選択していきましょう。
● お金と体力のやりくり、無駄遣いを避けるコツ
聞き込みの際には飲食を奢ったり、店のサービスを利用したりすることで情報を引き出す場面が多く、お金はあっという間に減っていきます。加えて、街を歩き回るだけでも体力が消耗し、疲労が蓄積すると行動に制限が出たり、重要な場面で失敗しやすくなったりすることもあります。そこで、お金と体力の管理は攻略に直結する要素となります。まず、お金に関しては「情報と引き換えに払う出費」と「気晴らしや好奇心による浪費」をきちんと区別し、後者は極力控えることが大切です。明らかに怪しい店構えの場所や、何度挑戦しても大して成果が得られない娯楽施設などは、序盤のうちは我慢してスルーする勇気も必要です。体力については、まとめて休息を取るタイミングを決めておくと良いでしょう。中途半端に消耗した状態で無理に歩き回るより、思い切って一度しっかり回復させてから再び行動を開始したほうが、結果的に行動回数を確保しやすくなります。「体力が半分を切ったら一度休息」「重要な聞き込みの前に余裕を持って体力を回復」といった自分なりのルールを決めておくと安定します。
● 親密イベントの扱い方と危険回避の考え方
本作には、登場人物との親密なイベントが多く用意されていますが、これらは単なるご褒美ではなく、攻略におけるハイリスク・ハイリターンな要素です。関係を深めることで重要な情報やアイテムを得られる一方、相手が本物の人間でなく危険なダッチワイフだった場合、無防備な接触はそのままゲームオーバーの引き金となってしまいます。したがって、攻略の観点からは「むやみに誘いに乗らない」「確度の高い情報やアイテムが期待できる場面だけ踏み込む」という慎重なスタンスが重要です。怪しげな人物や、明らかに何かを隠していそうなキャラクターとのイベントでは、事前に関連する情報を集めておき、「この人は人間である可能性が高い」「この店での噂からして危険度が高そうだ」といった判断材料を増やしてから決断するのが安全です。また、特定のアイテムが安全確認に役立つ場面もあるため、怪しい相手と深い関係に進む前には、手持ちの装備や道具を見直し、「いざという時の保険」があるかどうかを確かめておくと良いでしょう。
● アイテムの収集と使用タイミングの見極め
探索を進めていくと、さまざまなアイテムを入手できます。中にはイベントを進めるための必須キーアイテムもあれば、特定の場面で使うことで生存率を大きく高めてくれる便利な道具も存在します。攻略のポイントは、「何でもかんでもすぐ使う」のではなく、「どの場面で最大の効果を発揮するのか」を考えながら温存・投入を切り替えることです。例えば、ある種のアイテムは危険な相手との接触時に使うことでリスクを減らしてくれますが、序盤のお試しイベントで消費してしまうと、より重要な中盤以降の局面で手札が足りなくなる、といった事態も起こり得ます。テキスト中で「この先は危険だ」といったニュアンスが示されたり、周囲のキャラクターが警告を発していたりする場合は、「ここがアイテム投入のタイミングかもしれない」と意識しておくと良いでしょう。逆に、明らかにギャグ寄りのイベントや、ゲームの本筋とは関係の薄い寄り道的なシーンでは、貴重なアイテムを無駄に使わないよう注意が必要です。
● 情報整理とメモの活用で迷子を防ぐ
カブキチョウの街は決して広大というわけではありませんが、似たような路地や店が多く、慣れないうちは「さっきの情報はどの店で聞いたのか」「あの人物はどこで再会できるのか」といった点が混乱しがちです。そこで役立つのが、自前のメモです。紙でもテキストファイルでも構いませんが、「店の名前とおおまかな位置」「そこで得られた情報」「後で再訪すべきかどうか」といった簡単な記録を残しておくだけで、同じ場所を無駄に周回する事態を防ぎやすくなります。また、「北極6号らしき存在に関するヒント」や「失踪事件に関わる証言」は、時系列順に整理しておくと、後半になってから伏線がつながったときにスムーズに推理を進められます。特に初見プレイでは、一度きりしか聞けない貴重な言葉も紛れているため、少しでも気になったセリフはメモしておくくらいの慎重さが、安定攻略への近道になります。
● ルート研究とエンディング分岐の楽しみ方
本作は一本道に見えて、実際には行動選択や情報収集の順序によって、たどり着く結末やプレイ体験が変化する構造になっています。早い段階で有力な手がかりを掴み、効率よく北極6号を追い詰めるルートもあれば、別のキャラクターに肩入れした結果として回り道を強いられたり、思わぬバッドエンドに直行してしまったりするパターンも存在します。攻略面では、一度クリアしたルートを基準にして、「この場面で別の選択肢を選んだらどうなるか」「このイベントを後回しにした場合、終盤の展開は変わるか」といった検証を繰り返し、自分なりの“最短ルート”や“好みの展開を迎えるルート”を研究していく楽しみがあります。特に、時間・お金・体力をギリギリまで節約しながら最短手数で北極6号を3体揃えるようなプレイに挑戦すると、パズル的な面白さと達成感を味わえるはずです。最初から完璧を目指す必要はなく、まずは「とりあえずクリア」を目標にして、その後に少しずつルートを洗練させていくと、長く遊び続けられるでしょう。
■■■■ 感想や評判
● 発売当時のユーザーが受けた“ショック”と“笑い”
1984年前後のPCユーザーにとって、「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」というタイトルは、パソコン雑誌の広告ページでひときわ目を引く存在でした。当時のゲームといえば、スペースインベーダー直系のシューティングや、シンプルなアクション、テキスト中心のAVGが主流であり、そこへ突然“火星製ダッチワイフを追う私立探偵RPG”というコンセプトが現れたわけです。真面目なSF小説を連想させる題名と、露骨な大人向けワードを組み合わせたセンスは、良くも悪くも強烈で、雑誌をめくっていて思わず二度見した、という回想も多く語られます。実際にプレイしたユーザーの感想でも、「最初は悪ノリのエロゲーかと思ったが、想像以上にゲームとして作り込まれていて驚いた」「タイトルだけで買って、遊んでみたら意外に骨太だった」という声が少なくありません。まずはそのインパクトだけで話題をさらい、プレイしてみて“あれ、これ結構ちゃんとしているぞ”と評価が上方修正されていく──そんな流れで認知が広がっていった作品と言えます。
● アダルトゲームとしての評価と、ゲーム性への驚き
成人向けソフトとして見た場合、本作は「単なるお色気ソフトに留まらず、ちゃんと遊べるゲームだった」という点で高く評価されています。当時は“アダルト”と銘打ちながらも、実態は静止画が数枚出てくるだけの簡易ソフトや、ミニゲーム程度の内容のものも多く存在しました。そうした中で、「オランダ妻」は制限時間付きの捜査、ステータス管理、マップ探索、分岐イベントなど、本格的なRPG/ADVの構造を持ち込んでおり、“オマケのエロ”ではなく、“エロも含めてゲームシステムに組み込んでいる”点がユーザーを驚かせました。「アダルトゲームなのに真面目に作り過ぎ」「難易度が普通のRPGレベル」という感想もよく見られ、期待していたほど気軽に遊べない、と戸惑うプレイヤーもいたようです。一方で、そうした“本気度”を好意的に受け止める層からは、「ストーリーとゲーム性を両立させようとした先進的な試み」として、長く印象に残る一本になっています。
● シナリオ・世界観に対する賛否と“すこし不思議”な感触
シナリオ面では、火星からやってきたダッチワイフ、連続不審死事件、歌舞伎町風歓楽街という要素を、ハードボイルド風の探偵劇とエロパロディで強引にまとめあげたような世界観が特徴です。この独特の味付けは、プレイヤーによって評価が割れる部分でもありました。「突飛な設定とバカバカしさが病みつきになる」「どこまで本気でどこからギャグなのかわからない感じが面白い」といった称賛がある一方で、「真面目なSFを期待すると肩透かし」「エロギャグが強すぎてストーリーに感情移入しづらい」といった感想も見受けられます。ただ、全体としては“くだけたSFコメディ”として受け止めたプレイヤーが多く、深刻なドラマを求める作品というより、B級映画を観るようなノリで楽しむゲームとして記憶されているようです。ラストに向けて事件の全貌が明らかになる過程も、「真面目に筋は通しているが、どこかシュール」という印象を残し、“どことなく不思議で笑えるゲーム”という評価につながっています。
● 雑誌記事での扱いと“話題作”としての立ち位置
パソコン雑誌やゲーム専門誌でも、本作はしばしば紹介されましたが、その内容ゆえに誌面での扱いはやや特別でした。一般向けの誌面では、露骨な描写には触れず、「成人向けSFアドベンチャー」「探偵RPG風の構成」といった穏やかな表現を用いて、ゲームシステムやアイデアの面白さを中心に取り上げるケースが多かったようです。一方、マニア寄りのコーナーやレビューでは、“光栄が送り出した異色作”“タイトルの時点でやり過ぎ”といったニュアンスで、ちょっとしたネタ扱いをされつつも、ゲームとしての完成度を評価するコメントも合わせて掲載されていました。雑誌の読者投稿欄などでは、「隠れてこっそり遊んでいる」「友人の家でみんなで回しプレイした」といった声もあり、内容の過激さも相まって“こっそり共有される話題作”という位置づけを獲得していきます。表立って大々的に推されるタイトルではないものの、パソコンユーザーの間で“知っているとちょっと通ぶれるゲーム”として語り継がれていきました。
● 光栄ファンから見た“異色のルーツ作品”という評価
のちに歴史シミュレーションの大手となる光栄のファンから見ると、「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」は、非常に特異な位置づけの作品です。「信長の野望」「三國志」「ウイニングポスト」などの硬派なイメージから光栄を知った世代にとって、同じ会社がかつてアダルトなSFパロディを作っていたという事実は、驚き半分、微笑ましさ半分といったところでしょう。そのため、後年の回顧記事やインタビューでは、「若い頃のチャレンジ精神を象徴するタイトル」「黒歴史というより、むしろ会社の遊び心を示すエピソード」として紹介されることもあります。ファンの中には、「光栄の作品哲学は、この時期のアダルトゲームにも通じている」と捉え、時間管理やパラメータ性を備えた本作を、“歴史SLGへと続く試行錯誤の一環”として評価する向きもあります。真面目な歴史ゲームと、悪ふざけ全開のアダルトSFが同じメーカーから生まれた、その振れ幅の大きさも含めて、光栄という会社の懐の深さを印象づける存在になっていると言えるでしょう。
● 後年のレトロゲーム再評価での取り上げられ方
90年代後半以降、PC-8801やPC-9801といったレトロPCゲームを振り返る動きが強まると、「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」もその文脈でたびたび取り上げられるようになります。雑誌やWebサイトの特集では、“PC-88を代表する問題作”“タイトルが忘れられないソフト”として名前が挙がり、実際に遊んだ世代のライターが当時の空気感や、自室でこっそりプレイした思い出を語るケースも増えていきました。そこでは、単に「昔はこんな過激なゲームがあった」というショッキングな話題に留まらず、「時間制限付きの捜査ものとしてよく出来ていた」「アイデア自体はSF映画やノワール作品へのオマージュとして面白い」といった、ゲームデザイン面への評価も添えられることが多くなっています。一方で、現代の倫理観から見てかなり際どい要素も含むため、「今の基準では絶対にそのまま復刻できない」「良くも悪くも時代の産物」という注釈付きで扱われることがほとんどです。こうした“懐かしさと問題作感”の両方を備えた存在であることが、本作の再評価を複雑で興味深いものにしています。
● ユーザー間で語り継がれる笑い話・エピソード
当時のプレイヤーの回想をたどると、「オランダ妻」にまつわる笑い話や小さなエピソードが数多く残されています。例えば、親にバレないようにパッケージを隠していたのに、あまりにインパクトのあるタイトルが原因で、たまたま目にした家族に怪訝な顔をされた、といったエピソードや、「友人の家に集まって一台のPCを囲み、誰が一番上手く攻略できるかを競った」という、ちょっとしたパーティーゲーム的な遊ばれ方もあったようです。また、一見普通のNPCに対して軽い気持ちでアプローチした結果、予想外の展開から唐突にゲームオーバーになってしまい、その理不尽さに笑うしかなかった──といった体験談も典型的です。こうした“語りたくなる失敗談”が多いことは、それだけゲームに仕掛けや意外性が詰め込まれていた証拠でもあり、長く記憶に残る理由のひとつになっています。
● 批判的な意見:難易度・テンポ・倫理観への指摘
もちろん、評価が高い点ばかりではありません。攻略の項目でも触れたように、時間制限と定期連絡、リソース管理がシビアなため、「エロ目的で気軽に遊ぶつもりが、思った以上に難しくて挫折した」という声もあります。選択肢を誤ったり、情報収集の順番を間違えたりすると、あっさり詰んでしまうこともあり、総当たりで進めようとした初心者がストレスを感じやすいバランスであることは否めません。また、表現面に関しても、現在の視点から見ると不適切と感じられる要素が散見されます。特に、権力を持つ立場の人物や、公的な職業のキャラクターに対しても、同様のノリでアプローチできてしまう自由度の高さは、“度が過ぎた悪ふざけ”と受け止められることもあります。発売当時から、「笑えるけれど、ちょっとやりすぎでは」といった苦言が存在していたことも事実であり、その点は本作の影の側面として語られる部分です。
● それでも“忘れられない一本”として記憶される理由
賛否両論を抱えながらも、「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」が長く語り継がれているのは、やはり“一度見たら忘れられない強烈さ”と、“きちんと遊べるゲームとして成立していた”という二つの要素が同時に存在しているからでしょう。単なる過激なタイトルだけの作品であれば、時代が過ぎれば自然に忘れ去られてしまったかもしれません。しかし本作は、異様な設定とタイトルの裏側に、時間管理やパラメータ、探索の工夫など、ちゃんとプレイヤーに頭を使わせる仕組みを忍ばせていました。そのため、一度でも本気で攻略に挑んだ人にとっては、「あのバカバカしい世界観に、なぜか本気で熱中してしまった」という、他には代えがたい記憶として心に残ります。光栄の歴史を語るうえでも、日本のアダルトゲーム史を振り返るうえでも、避けて通れないターニングポイント的な一本──それが、多くのプレイヤーやライターが本作に寄せる最終的な評価だと言えるでしょう。
■■■■ 良かったところ
● 強烈なタイトルと設定が生み出す“忘れようとしても忘れられない”インパクト
本作の長所としてまず挙げられるのは、やはりタイトルと世界観のインパクトです。数あるパソコンゲームの中でも、「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」という名前を一度目にしたら二度と忘れない、というほどの印象を残します。意味ありげなのにどこかふざけている言葉の並び、SF的な響きと俗っぽさが同居したセンスは、当時のプレイヤーの記憶に強く焼き付いています。さらに、その奇妙なタイトルから想像される“ちょっと危ない近未来”というムードを、実際のゲーム内容もしっかりなぞっている点が魅力です。東京の歓楽街をモデルにした街並み、私立探偵という職業、失踪事件と謎のダッチワイフというキーワードが合わさり、「この世界の行く末を見届けてみたい」と思わせる導入に仕上がっています。“変わったタイトルのネタソフト”にとどまらず、作品全体がその奇抜さを軸にまとまっていることが、プレイヤーの心を掴んだ良い点と言えるでしょう。
● 探索RPGとアドベンチャーが自然に融合したゲーム構造
ゲームとしての骨格も評価できるポイントです。街を俯瞰視点で移動するマップパートと、会話や調査を行うアドベンチャーパートがスムーズに切り替わる構造は、今なお遊びやすいと感じられるつくりになっています。プレイヤーは単にテキストを読んで選択肢を選ぶだけではなく、自分の意思で“どの店に入るか”“誰に話しかけるか”を選びながら情報を集めていきます。これによって、画面の向こうで起きる出来事を眺めるだけでなく、自分が探偵として歓楽街を歩き回っている体験が生まれ、物語への没入感が一段高まっています。特に、マップ上で“怪しげな店構え”や“いかにも何かを知っていそうな人物”を見つけたときのワクワク感は、RPGとアドベンチャーの長所がうまく合わさっている証拠です。単純な構造に見えて、「この店は後回しにしよう」「さっき見かけた人物のところへ戻ろう」と自分なりのルートを組み立てていく楽しさがあることは、本作の大きな魅力でしょう。
● 時間・体力・所持金の三つ巴管理が生むスリルあるプレイ感覚
限られた日数の中で、定期的に依頼主へ連絡を入れながら捜査を進めるシステムは、本作の面白さの核となる部分です。街を歩き回るだけで体力は減り、聞き込みや遊興にはお金がかかり、油断すると連絡の時間を過ぎて依頼打ち切り──こうした制約が絶妙な緊張感を生み出しています。自由度を確保しつつも、「あまり寄り道し過ぎると痛い目を見る」というバランスが、プレイヤーに自然と計画性を要求するのです。この手のアドベンチャーは、行き当たりばったりで進めてもなんとなくゴールに辿り着けてしまうことがありますが、本作ではタイムリミットとリソース管理がそれを許しません。だからこそ、「今日はこの地区の聞き込みを集中的にやろう」「そろそろ連絡の時間だから、一度戻って体制を立て直そう」と、探偵らしい慎重さと戦略を考える楽しさが生まれています。単にイベントを追いかけるだけでは味わえない、“自分で捜査プランを組み立てている感覚”が強く感じられる点は、プレイヤーから見た大きな長所です。
● 能力値ルーレットによる“毎回違う探偵”を演じる面白さ
主人公の能力値をルーレットで決める仕組みも、当時としてはユニークで、今振り返っても魅力的なアイデアです。体力に恵まれたタフな探偵で始まる回もあれば、お金はあるがすぐ疲れてしまう軟弱なキャラクターになることもあり、ランダム性がプレイ体験を変化させます。これにより、「前回は余裕のあった行動が、今回はかなり綱渡り」「お金が乏しいから、今回は節約重視の堅実な捜査をしよう」といった形で、毎回違ったスタイルのプレイを楽しめます。やり込み派のユーザーにとっては、「貧乏かつ体力も少ない、いわゆるハードモード的な探偵でクリアを目指す」といった自分なりの課題を設定することもでき、遊び方の幅を広げる要素にもなっています。1回クリアして終わりではなく、「次はどんな探偵でどんなルートを辿るか」と想像したくなるリプレイ性の高さは、良かった点として多くのプレイヤーが挙げるところでしょう。
● 大人向け要素を“ゲームルール”に落とし込んだ設計センス
成人向けの題材を扱っていながら、イベントの多くは単なる飾りではなく、ゲームのルールと密接に結びついています。登場人物と親しくなる過程がそのまま情報収集やフラグ立てに繋がり、ある場面ではリスクを負って一歩踏み込む決断が必要になる一方、別の場面ではあえて距離を取ることが最善というケースもある──この駆け引きが独特の緊張感を生み出しています。特定の相手には慎重にならないと危険が伴うという構造は、テーマ的にもゲーム的にも一貫しており、「欲望のままに行動すると破滅する」という物語のメッセージがルールで表現されているとも言えます。結果として、大人向けの要素が単なる“おまけ”で終わることなく、攻略の成否を左右するファクターとして機能している点が、プレイヤーから高く評価される理由になっています。“アダルトだからこそ成立するルール”を設計しようとした姿勢は、後のジャンルの発展にも影響を与えたと見なせるでしょう。
● 80年代PCらしいグラフィック・サウンドの味わい深さ
技術的制約が大きかった時代にもかかわらず、街の雰囲気や登場人物の表情といった要素が、限られたドットと色数の中でうまく表現されている点も、ファンから好意的に語られるポイントです。夜の歓楽街を思わせる看板やビル群、路地裏の怪しい灯りなどは、細部まで描き込まれているわけではないものの、プレイヤーの想像力をかき立てるには十分な情報量を持っています。また、シンプルなサウンドも、事件の緊迫した場面やコミカルなイベントでさりげなく雰囲気を支えており、“当時のPCゲームらしい音と絵”が一体となって独自の空気を生み出しています。懐かしさ込みの評価ではあるものの、「粗いドットだからこそ想像が膨らむ」「耳に残る効果音が多い」といった感想は多く、レトロゲームならではの魅力として好まれています。
● キャラクターの濃さと会話イベントのテンポの良さ
登場するキャラクターたちも、一人ひとりが強い個性を持っている点が好評です。真面目そうに見えて妙にズレた発言をする人物、何を考えているのか掴みにくい情報屋風のキャラクター、主人公に対して異様にフレンドリーな店員など、短いテキストながら印象に残る人物が多く登場します。会話そのものもテンポが良く、短い文で状況や性格が伝わるよう工夫されているため、余計な説明に飽きることなく次から次へとイベントを追いかけてしまいます。この“サラッと読めるのに妙にクセになる”テキストの感触は、限られたメモリ容量の中で濃縮した会話を組み立てる必要があった時代ならではのものです。キャラクターの顔グラフィックと台詞が組み合わさることで、「この人とはまた会いたい」「この人の裏の顔を知りたい」と思わせる吸引力があり、プレイヤーを物語の奥へと引き込んでいきます。
● 光栄というメーカーの“懐の深さ”を感じさせる一作であること
プレイヤーの感想の中には、「このゲームの存在を知って、光栄という会社を別の角度から見るようになった」というものもあります。歴史シミュレーションのイメージが前面に出る以前に、こうした大胆なアダルト作品を手掛けていたことは、多くのファンにとって意外な発見でした。堅いイメージの企業が、かつては遊び心と実験精神に満ちた作品をリリースしていた──そのギャップが、ゲームそのものの魅力をさらに引き立てています。メーカーの変遷を知れば知るほど、「この一本がのちの代表作へと続くキャリアの一部だったのか」と感慨深くなり、本作を単なる“過去のアダルトゲーム”以上のものとして評価する声も少なくありません。企業の歴史を彩る一エピソードとしての面白さも、本作の“良かったところ”として挙げられる要素です。
● いま遊んでも話のネタになる“伝説級のネーミングと企画力”
最後に挙げたい長所は、“話のネタとしての強さ”です。ゲーム内容の細部まで覚えていなくても、このタイトルと大まかな設定だけで会話が盛り上がることは多く、レトロPC好きの集まりでは定番の話題のひとつになっています。「昔こんなゲームがあってね」と語るだけで場が和むような、ある種の伝説性を持っていることは、作品として大きな財産です。実際、現在でもレトロゲームの特集やトークイベントなどでは、本作の名前が出るだけで客席から笑いや驚きが起こることがあり、そのたびに「当時の企画力と勢いはすごかった」と再確認されます。ゲームとしてしっかり作り込まれているからこそ、“珍タイトル”の枠を超えて語り継がれているわけで、そうした存在感そのものが、本作最大の“良かったところ”なのかもしれません。
■■■■ 悪かったところ
● 難易度バランスがシビアで初見プレイヤーには敷居が高い
本作を語るうえでよく指摘されるのが、全体的な難易度の高さです。時間制限・定期連絡・体力や所持金の管理といった要素が重なり合い、初めて遊ぶプレイヤーにとっては相当に厳しい設計になっています。特に、ゲームがどの程度シビアなルールで動いているのか、マニュアルだけでは掴みにくい部分が多く、何となく街を歩き回っているうちに時間切れや体力切れに陥り、「気付いたら詰んでいた」という展開になりがちです。いわゆる“総当たりで全部の店を回る”ような進め方をすると、あっという間に日数やリソースが尽きてしまい、結局スタートからやり直しになることも少なくありません。「難しいゲームが好き」というユーザーにはやりごたえがありますが、気軽に物語や雰囲気を楽しみたいプレイヤーにとっては、序盤のハードルの高さが大きな欠点として感じられます。
● 手がかりが分かりづらく、理不尽に感じられるイベント進行
もう一つの弱点は、進行に必要なフラグや手がかりがやや分かりづらい点です。ある人物に一度会っただけでは真価が分からず、特定のタイミングや条件を満たしたうえでもう一度会いに行かないと重要な情報が得られない、といったイベントが少なくありません。ところがゲーム中では、それを直感的に示すサインが少なく、「なんとなく気になったからもう一度行ってみた」プレイヤーだけが偶然先に進める、という状況も出てきます。その結果、「なぜ進めないのか分からない」「どこで何を見落としたのか見当が付かない」という感想を抱きやすく、攻略情報がないと最後までたどり着きにくい構成だと感じる人も多いでしょう。とくに、限られた時間の中で動かなければならないゲーム性と噛み合うと、プレイヤー側からすると“試行錯誤する余裕を与えてくれない理不尽さ”として受け取られがちです。
● アダルト要素を期待したユーザーには“堅すぎる”ゲーム性
本作は成人向けレーベルのタイトルであり、パッケージから受ける印象もかなり刺激的です。そのため、「軽いノリで楽しめるお色気ゲーム」を期待して購入したプレイヤーにとっては、時間管理や探索、ルート構築といった骨太なゲーム性がかえってマイナスに働くこともありました。じっくり腰を据えて攻略に挑む覚悟がないと、頻繁にゲームオーバーを繰り返すことになり、当時のユーザーの中には「大人向けソフトなのに、構えて遊ばないといけない」「ちょっとした息抜き用にしては重たい」という不満を抱いた人も少なくないと考えられます。アダルトという看板から想像される“気軽さ”と、実際の“硬派な遊びごたえ”のギャップが大きいため、そのミスマッチをどう受け止めるかが評価の分かれ目になってしまった点は、本作の弱点と言えるでしょう。
● 今の感覚から見るとテンポが悪く感じられる操作性とUI
当時の基準から見れば標準的な作りですが、現代の視点でプレイしようとすると、操作性や画面遷移のテンポがどうしてももっさりと感じられます。マップ移動のたびに細かなキー入力が必要だったり、店に入る・出るだけでもワンテンポ余計な操作が挟まったりと、長時間遊んでいると“操作のストレス”がじわじわ積み上がっていきます。また、目的地や重要地点へのナビゲーションが一切なく、テキストのヒントだけを頼りにマップを頭の中で組み立てなければならないため、慣れないうちは「また同じ通りをうろうろしている」という感覚に陥りがちです。これは当時のPCゲーム全般に言えることでもありますが、本作では時間制限がある分、余計な移動によるロスがそのままゲームオーバーに直結しやすいため、テンポの悪さが欠点として強く意識されてしまいます。
● 表現や題材が人を選び、現代の感覚とは噛み合いにくい
火星製ダッチワイフや歓楽街を巡る探偵ものという設定自体がかなり尖っており、そこにパロディやギャグを交えた表現が重なるため、当時から「笑えるが、好みは分かれる」と言われていました。今の価値観から振り返ると、特定の職業や立場の人物をコミカルに扱い過ぎている印象を受ける場面もあり、人によっては不快感や違和感を覚える可能性があります。大人向け作品としてある程度の過激さは許容された時代とはいえ、現代のプレイヤーがそのまま受け入れられるかというと、微妙なラインも多いでしょう。特に、“どこまでが冗談でどこからがアウトなのか”という境界がはっきりしていない表現は、今の目で見ると不用意に見えることがあります。こうした価値観のギャップは、作品そのものが悪いというよりも“時代背景に依存した笑い”の宿命ではありますが、現代にプレイしようとする際の障壁になる点は否定できません。
● ガイド不足による迷走感と、遊び手を選ぶ不親切さ
ストーリーの大筋や世界観は魅力的な一方で、「次にどこへ行けばいいのか」「今何を目指しているのか」といった短期的な目標がゲーム内で十分に整理されていないのも欠点として挙げられます。序盤こそ依頼内容が明確に提示されるものの、その後は手探りで街を回らないとイベントの発生条件が見えにくく、プレイヤーは“何かを見落としている気がするが、どこを探せばよいか分からない”状態に陥りがちです。マニュアルや付属資料を読み込むことである程度補える部分もありますが、それでもなお「裏でどういうフラグ管理が行われているのか」が感覚的に掴みにくく、結果として試行錯誤の大半が“手探りで壁にぶつかる作業”になってしまうことがあります。こうした不親切さは、攻略情報が容易に手に入らなかった当時のユーザーにとっても、決して小さくないハードルでした。
● ビジュアルやシステムが時代相応で、今から触ると古さが目立つ
レトロゲームとして見れば味わい深いグラフィックやサウンドも、純粋に「今遊べるゲーム」として評価しようとすると、どうしても粗さや表現力の限界が気になります。人物の表情や動きは想像の余地を残すレベルにとどまり、イベントシーンも静止画とテキストの組み合わせが中心です。もちろん、それが悪いというわけではありませんが、後の作品と比べたときに、演出面でできることが限られているのは事実です。また、インターフェースもキーボード操作前提で設計されているため、アクション自体はシンプルでも、マウスやゲームパッドに慣れた世代からすると操作感に戸惑う場面が多いでしょう。本作に興味を持ったとしても、単に“昔の名作”という評判だけを聞いてプレイすると、表層的な古さにまず目が行ってしまい、本来の魅力に辿り着く前に離脱してしまう可能性があります。
● 再入手の難しさと、実際に遊ぶまでのハードルの高さ
ゲーム内容そのものとは少し離れますが、本作の評価を語る際に無視できないのが、“今となっては正規のルートで遊ぶことがほぼ不可能に近い”という点です。対応機種である8ビットPC自体がすでにレトロハードとなっており、実機を入手・維持するだけでも大きな労力が必要ですし、ソフトも中古市場にほとんど流通していません。そのため、作品に興味を持ったとしても、現代のプレイヤーが自分で触って評価を確かめることが極めて難しく、どうしても“当時の記憶を語る人”の主観に頼らざるを得ない状況になっています。これは本作固有の欠点というより、レトロPCゲーム全般が抱える問題ですが、結果として「評判だけ一人歩きして、実際の面白さや欠点が伝わりにくい」という歯がゆさに繋がっています。プレイ環境まで含めると、作品へのアクセス性の低さもまた、本作を語る上での“悪いところ”として挙げざるを得ないポイントです。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
● 主人公の私立探偵 ─ だらしなさとプロ意識が同居する“プレイヤーの分身”
まず挙げたいのは、名前こそ特別な設定が強調されないものの、物語の中心に立つ主人公の私立探偵です。彼は典型的なハードボイルド探偵とは少し違い、生活はどこかだらしなく、金にも女にも弱い部分を持ちながら、それでも依頼を引き受けたからには最後までやり遂げようとする妙な義理堅さがあります。プレイ中、彼の心理が直接描写されることはさほど多くありませんが、台詞の端々や行動の選択肢から、“根は真面目だが、いろいろ流されやすい中年男”といった人間像がにじみ出てきます。危険な依頼だと分かっていながらも高額報酬に釣られてしまうところ、無謀な聞き込みや無駄遣いで自分の首を絞めてしまうところなど、プレイヤー自身の選択がそのまま“情けない探偵像”を形作っていく感覚があり、そこがまた憎めない魅力につながっています。完璧なヒーローではなく、良くも悪くも“普通の男”が奇妙な事件に巻き込まれ翻弄される構図が、プレイヤーに親近感と笑いをもたらし、「このダメな探偵を最後まで見届けてやろう」という気持ちにさせてくれるのです。
● オランダ商会の担当者 ─ 事務的な口調の裏に見える得体の知れなさ
主人公に奇妙な依頼を持ち込むオランダ商会の担当者も、静かな存在感を放つキャラクターです。彼(あるいは彼女)の口調は基本的に淡々としており、ビジネスライクなやり取りの中で淡々と「北極6号を3日以内に回収せよ」「定時連絡を怠るな」と条件を突き付けてきます。一見すると会社員らしい冷静さときっちりした性格の持ち主に見えますが、読み進めていくと、“なぜそこまで必死に北極6号を回収させようとするのか”“この依頼にはまだ何か裏があるのではないか”といった疑念が少しずつ膨らんでいきます。感情をあまり表に出さないキャラクターだからこそ、その背景にある事情や本音を想像してしまい、プレイヤーごとに違った印象を抱かせる余地があります。中には「実はこの担当者もまた大きな計画の一部に過ぎないのでは」などと深読みするプレイヤーもいるほどで、直接的な描写が少ないにもかかわらず印象に残る、不思議な味わいの人物です。
● 北極6号 ─ 危険と魅力が同居する“謎のダッチワイフ”たち
作品のタイトルにも深く関わる「北極6号」は、ある意味で本作の真のヒロインとも言える存在です。火星で開発された高性能ダッチワイフという設定上、人間と見分けがつかないほどの外見と機能を備えており、その完璧さゆえに“危険な存在”として扱われています。ゲーム中では直接的な人格描写や長台詞が多く用意されているわけではありませんが、街に潜伏し、人間社会に溶け込みながらも何かを企んでいるかのような気配が、断片的な情報や噂話から匂わされます。その“姿が見えないのに存在感だけが膨らんでいく”演出が巧妙で、プレイヤーとしては「この人物は本当に人間なのか、それとも北極6号なのか」と、会う相手すべてを疑いながらゲームを進めることになります。直接会うまでの過程で築かれる“見えないヒロイン像”が、実際にその正体と向き合う場面の緊張感を一層高めており、敵でありヒロインでもある、アンビバレントな魅力を持ったキャラクターとして記憶に残ります。
● 歓楽街で出会うホステスや女性客 ─ 情報源であり、物語を彩る脇役たち
カブキチョウの酒場やクラブで出会うホステスや女性客たちは、それぞれが短い出番ながら強烈な個性を放っています。飄々とした口調で探偵をからかいながらも、ときどき核心に触れる一言を漏らす人物や、見た目は派手なのにどこか世慣れた諦念を感じさせる女性など、会話テキストだけでキャラクター像を立ち上げている点が印象的です。彼女たちはしばしば事件に直接関わる情報を握っており、軽い世間話のような会話からも、よく読むと重要なヒントが紛れ込んでいることがあります。プレイヤーとしては、単なる“一見の遊び相手”として接しているつもりでも、ゲームを進めるほどに「実はこの人たちも事件の裏側を知っているのでは」と気になってくるでしょう。短い登場シーンの中に、その人の人生や背景を感じさせるような台詞が織り込まれているため、「このホステスは好きだ」「あの店のママは妙に印象に残る」と、プレイヤーによって“推しキャラ”が分かれるのも面白いところです。
● 情報屋ふうの怪しげな男 ─ 信頼すべきか疑うべきか、プレイヤーを揺さぶる存在
歓楽街で重要な役割を果たすのが、いかにも裏社会を知り尽くしていそうな情報屋ふうの男です。彼は主人公に対して必要な情報を売ってくれる中立的な立場にも見えますが、その動機や忠誠心は最後まで明かされません。ときには助けになる情報を提供してくれる一方で、わざと不完全な情報を伝えているのではないか、と勘ぐりたくなる発言も多く、プレイヤーを常に不安定な気分にさせます。こうした“信用していいのか分からないキャラクター”は、ミステリーやハードボイルド作品では定番の役どころですが、本作でもそのポジションをうまく担っており、彼の一言でプレイヤーの行動方針が大きく変わることもしばしばです。「あの時、情報屋の言葉を鵜呑みにしなければ、違う結末に辿り着いていたかもしれない」と後から振り返らせるような存在であり、プレイ後の感想でも“好き嫌いが分かれるが印象深いキャラクター”としてよく名前が挙がります。
● 真面目すぎる警官 ─ コメディリリーフでありながら、街の空気を象徴する存在
街中で頻繁に遭遇する警官も、多くのプレイヤーにとって忘れがたいキャラクターです。表向きは真面目に治安維持をしているように見えるものの、主人公とのやり取りではどこか抜けたところがあり、思わぬ方向に話が転がっていくこともあります。完璧な正義の味方というよりは、どこか庶民的で、人間味のあるキャラクターとして描かれており、そのギャップがコミカルな魅力につながっています。歓楽街という舞台では、警官の存在は“秩序の象徴”でありながら、同時にこの街のゆるさや危うさを映し出す鏡でもあります。彼と会話を重ねるうちに、プレイヤーは「この街では、公的な立場の人間も含めて、皆どこかしらおかしい」という感覚を強めていきます。その意味で、彼は単なるギャグ要員ではなく、ゲーム全体の空気を象徴する重要なサブキャラクターと言えるでしょう。
● どこか影のある女性たち ─ 一筋縄ではいかない“もう一人の主役”たち
主人公が出会う女性たちは、見た目や役割だけでなく、内面にもそれぞれ違った“影”を抱えているように描かれている点が魅力です。仕事で仕方なく夜の街に立っている人、自分の置かれた環境に不満を抱えつつも淡々と日々をこなしている人、主人公に対してだけほんの少し心を開いたような素振りを見せる人など、短いテキストの中に人生の重さを感じさせる瞬間があります。プレイヤーは事件の真相を追いながら、同時に彼女たちの背景を想像し、時には同情や共感の感情を抱くことになります。必ずしも“恋愛の相手”として描かれているわけではありませんが、「このキャラクターには幸せになってほしい」「彼女の結末が気になる」と感じさせる力があり、プレイヤーそれぞれの心の中で“好きなキャラクター”として位置付けられていきます。
● 無名のモブたちが作り出す“生きた歓楽街”の雰囲気
最後に忘れてはならないのが、名前もろくに明かされないモブキャラクターたちです。通りを歩いているだけの人、酔っぱらって主人公に絡んでくる男、何かを匂わせる一言だけを残して去っていく人物など、数多くの“名無しの登場人物”が、街に厚みとリアリティを与えています。彼ら一人ひとりは決して深く掘り下げられてはいませんが、複数のモブのセリフが重なり合うことで、「この街には自分以外にも様々な人生が流れている」という感覚が生まれ、舞台となるカブキチョウを“ただのマップ”以上の場所にしてくれます。中には、プレイヤーの中で妙に印象に残るモブもいるでしょう。たとえば、何度話しかけても同じ愚痴をこぼし続ける客や、どこか諦めた笑みを浮かべる店員など、“名もなきキャラ”だからこそ逆に心に引っかかることがあります。そうした小さな印象の積み重ねが、プレイヤーごとに異なる“お気に入りの脇役”を生み出し、本作の世界をより豊かなものにしているのです。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
● マルチプラットフォーム展開が意味したもの
「オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?」は、PC-8801、PC-9801、FM-7という当時の主要8ビット機で遊べるように作られていました。今で言えば“マルチプラットフォーム展開”ですが、1984年当時にこれはかなり野心的な試みでした。それぞれのマシンはグラフィック解像度も音源も微妙に違い、ディスクかカセットかといった媒体も統一されていません。その中で同じゲーム体験を提供しつつ、ハードの個性を活かしたバージョン違いを実現していた点が、このタイトルの面白いところです。ユーザー側から見ると、「どの機種で遊ぶか」によって、画面の雰囲気やロード時間、操作感などが少しずつ変わり、“自分の愛機で動くオランダ妻”という特別な感覚を味わえました。
● PC-8801版 ─ 標準機ならではのバランスの取れた仕上がり
当時のパソコンゲーム市場で大きな存在感を持っていたのがPC-8801シリーズです。PC-8801版の「オランダ妻」は、まさに“標準版”と言える位置づけで、グラフィックやサウンド、動作の軽さなど、あらゆる面が平均点以上にまとまっています。8色前後の制約はあるものの、歓楽街のネオンや看板はメリハリのある配色で描かれ、画面を見た瞬間に「夜の街」を連想できる雰囲気に仕上がっていました。キャラクターの立ち絵も、線は太めながら表情の違いが分かるよう工夫されており、当時のユーザーにとっては十分に“ドキッとする絵”だったはずです。 また、PC-8801版は動作速度とロード時間のバランスが良く、ストレスの少ないプレイ環境が評価されていました。ディスク版ではシーン切り替え時に短いロードは入るものの、テンポを大きく損なうほどではなく、長時間のプレイでも「待たされてイライラする」感覚は比較的少なめです。グラフィックの鮮やかさと動作の軽さを両立した、もっとも遊びやすいバージョンとして、今でも“PC-88版が一番しっくりくる”と語るユーザーは少なくありません。
● PC-9801版 ─ ビジネス機発の“ちょっとリッチな”オランダ妻
PC-9801シリーズは当初ビジネス分野を主戦場としていましたが、徐々にゲーム市場でも存在感を増しつつありました。そのPC-9801版「オランダ妻」は、解像度の高さを活かした“少し大人びた雰囲気”が魅力です。線の密度が上がることで、キャラクターの輪郭や服のディテールがやや滑らかになり、背景のビル群もスッキリとした印象になります。派手さではPC-8801版に一歩譲る部分もありますが、その代わりに落ち着いた発色と細部の描き込みによって、“やや現実寄りの歓楽街”が立ち上がる感覚があります。 当時のPC-9801ユーザーは、仕事用・実用機としてこのマシンを所有しているケースも多く、「真面目な事務機でこんなソフトが動く」というギャップもこの版ならではの醍醐味でした。会社のデスクに載っているマシンで、夜中にこっそりこのゲームを起動していた──という、どこか罪悪感を誘うシチュエーションも、想像するとなんとも味わい深いものがあります。ゲーム内容自体は他機種版と大差ありませんが、“真面目な顔をしたPC-98で怪しい探偵劇を繰り広げる”という体験そのものが、PC-9801版の魅力と言えるでしょう。
● FM-7版 ─ カセット/ディスク両対応と独特の色使い
FM-7は、ホビー寄りのマシンとして多くのマニアに愛されていました。FM-7版「オランダ妻」の特徴は、カセットテープ版やディスク版など媒体の選択肢があったことと、発色の感触が他機種版とは少し異なる点です。カセット版ではロード時間が非常に長く、タイトル画面が出てくるまでじっと待たされることも珍しくありませんでしたが、その時間も含めて“儀式”のように楽しんでいたユーザーも多かったようです。一度ロードが完了してしまえば、その後は比較的安定して動作し、“苦労して読み込ませたゲームだからこそ、じっくり腰を据えて遊ぶ”という気分を高めてくれました。 グラフィック面では、FM系ならではの色の組み合わせや明度差の出し方が活きており、看板やネオンの光り方、キャラクターの肌色などに他機種とは違うニュアンスが感じられます。同じイベントシーンでも、「PC-88版はややポップ」「FM-7版は少し淡く柔らかい」といった印象の違いがあり、ユーザーの好みが分かれるところでした。FM-7ファンにとっては、「自分の愛機専用に最適化されている」ような愛着を抱きやすいバージョンと言えるでしょう。
● 画面構成・フォントの違いがもたらす“雰囲気の差”
機種ごとの差は、色数や解像度だけでなく、フォントや画面レイアウトにも現れていました。例えば、同じセリフでも、PC-8801のフォントで表示されるとどこか丸みを帯びた印象になり、FM-7のフォントだと若干角張った雰囲気に見える、といったように、文字の雰囲気そのものがキャラクターの印象を左右します。また、テキストウィンドウの枠線や影の付け方、コマンドメニューの配置なども、各機種の標準的なインターフェースデザインに合わせて微妙に調整されていました。 これらの違いは決して派手なものではありませんが、長時間プレイしているとジワジワ効いてきます。PC-8801版は「いかにもゲームらしいポップさ」、PC-9801版は「やや堅めで事務的な印象」、FM-7版は「ホビー機らしい遊び心」といった具合に、同じシナリオでも受ける印象が少しずつ変化するのです。こうした“文字と枠の雰囲気の差”は、画面写真だけでは伝わりにくいものの、実際に遊んだことのあるユーザーにとっては、「あの機種で見たオランダ妻の画面こそ、自分の中の本物」という強い記憶を作り出しました。
● サウンド表現の違い ─ BEEP主体か、FM音源か
サウンド面でも、機種ごとの個性が感じられます。PC-8801の一部構成やFM-7の初期モデルでは、BEEP音主体のシンプルな効果音が中心で、“チープだが味のある音”がゲームを彩っていました。メロディラインもシンプルなものが多く、短いフレーズがさりげなく鳴る程度ですが、それがまた夜の静けさや路地裏の寂しさを引き立てる役割を果たしています。 一方、FM音源対応の環境やPC-9801の一部構成では、より厚みのある音色でBGMを鳴らすことができ、歓楽街を歩くときの軽快なフレーズやイベントシーンでの緊張感ある音楽に、余裕のある表現力が加わります。もちろん、楽曲の構造そのものはシンプルですが、和音の響き方やベースラインの存在感が変わることで、“同じ曲なのに随分雰囲気が違う”と感じられることもありました。プレイヤーによっては、「あの機種の音の方が怪しさが増していて好き」「シンプルなBEEP版の方が、かえって想像をかき立てられる」と、音の好みでお気に入り版が分かれることも少なくありません。
● 媒体の違いが与えた遊び方への影響
ディスクかカセットかという媒体の違いも、プレイ体験に大きな影響を与えました。ディスク版はロードが高速で、シーンごとの切り替えも比較的スムーズなため、サクサク遊びたいユーザーには最適です。ゲームオーバーになってやり直す場合でも、再ロードにかかる時間が短く、「もう一回だけ挑戦してみよう」と気軽にリトライできます。これに対し、カセット版は一度電源を切るとまた長いロードをやり直すことになり、そのハードルの高さが「絶対に途中でミスしたくない」という緊張感に繋がっていました。同じゲームでも、ディスク版プレイヤーは細かく試行錯誤を繰り返すスタイルになりやすく、カセット版プレイヤーは“慎重に一手一手を選ぶ”遊び方になりがちだったと言えるでしょう。媒体の違いが、プレイヤーの心理と攻略スタイルを変えてしまう──これもまた、マルチプラットフォームならではの興味深いポイントです。
● どの機種版を選ぶべきか ─ それぞれの“らしさ”
今から歴史を振り返って「どの版がベストか?」を論じると、結局は好みの問題に行き着きます。グラフィックの見やすさと動作のバランスを重視するならPC-8801版、落ち着いた画面と“事務機で不謹慎なゲームを動かすギャップ”を楽しみたいならPC-9801版、ホビー機ならではの色味やカセットの儀式感まで含めて味わいたいならFM-7版、といった具合に、それぞれ違った魅力が存在します。 共通して言えるのは、どの機種版であっても物語の骨格やゲームシステムは同じであり、“火星製ダッチワイフを追う探偵劇”という根っこの部分の面白さは変わらないということです。そのうえで、「自分が当時使っていた、あるいは憧れていたマシンで動いていた姿こそが、心の中の本当のオランダ妻」という感覚が、プレイヤー一人ひとりの中に残っています。対応パソコンごとの違いは、単なるスペック差ではなく、“その人のパソコン人生と結びついた記憶”として刻まれている──それこそが、このゲームのマルチプラットフォーム展開が残した、最大の“違い”なのかもしれません。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
★ナイトライフ
・販売会社:光栄(光栄マイコンシステム) ・販売された年:1982年 ・販売価格:PC-8801版 7,800円前後(5インチFD版の例)
『オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?』より少し早い時期に登場した、光栄の“問題作”として有名なのが『ナイトライフ』です。夫婦生活をテーマにした大人向けソフトで、グラフィックやゲーム性そのものはシンプルながら、当時としてはかなり踏み込んだ内容を正面から扱ったことで知られています。画面には周期表や相性表といった情報が表示され、ユーザーは時間帯や体調などの条件をもとに、二人の夜をどう演出するかをシミュレーションしていきます。
当時のパソコン雑誌に掲載された広告はインパクトが強く、「パソコンがこんな使われ方をするのか」と多くの読者を驚かせました。遊びというより“生活実用ソフト”に近い立ち位置であり、今で言うライフスタイル系アプリの先駆けとも言える存在です。『オランダ妻』がアダルト×推理・探索RPGに進化した作品だとすれば、その土台となる「大人向けコンテンツをPCで扱う」という挑戦を最初に形にしたのが『ナイトライフ』だと言えるでしょう。
★団地妻の誘惑
・販売会社:光栄マイコンシステム ・販売された年:1983年 ・販売価格:PC-8801用 5インチFD版 6,800円(テープ版は4,800円など複数価格設定)
『団地妻の誘惑』は、アダルトとRPG風のマップ探索を組み合わせた作品で、国産アダルトゲームの草分け的タイトルとして知られています。プレイヤーはセールスマンとして団地を巡り、住人たちと会話したり、アイテムを入手したりしながら、少しずつ関係性を深めていきます。表面的には“訪問販売ゲーム”ですが、内部的には経験値や所持金、危険度など複数のパラメータが管理されており、無茶な行動ばかり取っていると痛い目を見るという、意外にシビアなゲームデザインが特徴です。
団地の各フロアを上下左右に移動し、どの部屋をノックするか、どのタイミングで退散するかを考える必要があるため、『オランダ妻』にも通じるマップ探索型の手触りがあります。生活感のある舞台設定と、ゲームとしての駆け引きがうまく噛み合っており、アダルト作品でありながら「ゲーム的に面白い」と評価されたことが、後の“ストロベリーポルノシリーズ”や『オランダ妻』へと続く大きなステップになりました。
★信長の野望
・販売会社:光栄 ・販売された年:1983年(PC-8801版) ・販売価格:PC-8801版 6,800円
『信長の野望』は、後に大ヒットシリーズとして発展していく歴史シミュレーションの原点です。プレイヤーは戦国大名の一人となり、内政・外交・軍事をバランスよく運営しながら全国統一を目指します。数字で表現される国力や兵力、米の収穫量など、当時のPCゲームとしては情報量が多く、プレイヤーは長期的な戦略を立てる楽しさに目覚めることになりました。
『オランダ妻』と同じ光栄ブランドながら、こちらは歴史と戦略に特化した硬派な内容で、「同じ会社が、夫婦生活のシミュレーションも、戦国大名の天下取りも作っている」というギャップは、今でも語り草です。大人向けレーベルで培われたユーザーインターフェースやパラメータ管理のノウハウが、結果的には歴史シミュレーションにも生かされていると考えると、光栄の幅の広さがより際立って見えてきます。
★ザ・ブラックオニキス
・販売会社:ビーピーエス(BPS)など ・販売された年:1984年(PC-8801版など) ・販売価格:PC-8801カセット版 定価約6,380円、MSX版 6,800円前後
『ザ・ブラックオニキス』は、国産RPG黎明期を代表するダンジョンRPGで、黒い塔の最上階に眠る秘宝“ブラックオニキス”の入手を目指す作品です。プレイヤーは仲間を集めてパーティを組み、3D表示の迷宮を少しずつ攻略していきます。敵との戦闘やレベルアップといった要素はシンプルながら、慎重に進まないとすぐに全滅してしまう緊張感があり、コツコツとキャラクターを鍛える楽しさが多くのユーザーを虜にしました。
8ビットPCの画面に表示される擬似3Dの通路は、それまでのアドベンチャーゲームとはまったく違う“冒険している実感”を与え、オリジナルの世界観とともに強烈なインパクトを残します。『オランダ妻』と同じPC-8801世代のゲームではありますが、アダルト路線とは正反対の正統派ファンタジーRPGであり、「あの時代のPCは、こんなにも多彩なジャンルを受け止めていたのか」と改めて感じさせる一本です。
★ハイドライド
・販売会社:T&E SOFT ・販売された年:1984年(PC-8801版など) ・販売価格:PC-8801版 6,800円
『ハイドライド』は、リアルタイムアクションRPGの先駆けとして知られる作品です。主人公ジムを操作してフィールドやダンジョンを移動し、敵に体当たりすることで攻撃・防御を行う“シンプルな戦闘システム”が特徴で、プレイヤーは攻めるタイミングと引くタイミングを自分の感覚で判断しながら冒険を進めます。
体力・魔力を回復させるために安全地帯で待機したり、経験値稼ぎの効率の良いポイントを探したりするプレイスタイルは、後のアクションRPGに大きな影響を与えました。同じPC-8801を舞台にしながら、『オランダ妻』が“歓楽街と探偵劇”を描いたのに対し、『ハイドライド』は“剣と魔法の世界”へプレイヤーを連れ出し、別方向からPCゲームの可能性を広げていったと言えるでしょう。
★北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ
・販売会社:アスキー ・販売された年:1984年(PC-8801SR版など) ・販売価格:PC-8801版 6,800〜7,480円前後
『オホーツクに消ゆ』は、堀井雄二が手掛けた推理アドベンチャーで、東京から北海道へと舞台を移しながら連続殺人事件の謎に迫る作品です。プレイヤーは刑事となり、聞き込みや現場調査を行いながら少しずつ真相を解き明かしていきます。特徴的なのは、コマンド選択式のインターフェースで、前作『ポートピア連続殺人事件』の“文字入力型”から一歩進んだ遊びやすさを実現している点です。
note(ノート)
+1
北海道各地を移動しながら手掛かりを集めていく構成は、旅行気分と推理小説のスリルを同時に味わえるものになっており、プレイヤーは雪景色や港町の空気をテキストとグラフィックから想像しつつ事件解決に挑むことになります。『オランダ妻』が大人向け探偵劇を、歓楽街の裏側から描いていたのに対し、『オホーツク』は刑事ドラマ的な視点で社会の影を描いており、同時期のPC-8801ユーザーに“異なるタイプのサスペンスアドベンチャー”を提供したと言えるでしょう。
★ポートピア連続殺人事件
・販売会社:エニックス(PC版) ・販売された年:1983年(PC版初出) ・販売価格:機種や媒体により3,600〜5,800円前後
『ポートピア連続殺人事件』は、日本のアドベンチャーゲーム史を語るうえで欠かせない作品です。プレイヤーは刑事の相棒となり、聞き込みや現場調査を通じて複数の事件の関連性を紐解いていきます。PC版ではキーボードからコマンドを入力する方式が採用されており、「現場に行け」「調べろ」などの言葉を自分で打ち込むことでゲームが進行します。
プレイヤーの想像力次第でいろいろなコマンドを試せる一方、適切な言葉を思いつかないと進展しない場面もあり、自由度の高さと不親切さが同居した作りでした。その一方で、後のタイトルに受け継がれていく“推理アドベンチャーの基本形”を築き上げた功績は大きく、『オランダ妻』が独自の方向に進化させた「街を歩き回って情報を集める」感覚の源流の一つとしても位置付けられます。
★ABYSS(アビス)
・販売会社:ハミングバードソフト ・販売された年:1984年(PC-8801版) ・販売価格:PC-8801版 6,800円
『ABYSS』は、ハミングバードソフトが手掛けたSFアドベンチャーゲームで、銀河規模の陰謀に巻き込まれた戦士が、記憶を失った状態から任務の真相に迫っていく物語です。PC-8801向けにはやや遅れて発売されたものの、宇宙を舞台にした硬派なストーリーと、難易度の高い謎解きでコアユーザーから評価を集めました。
画面には宇宙船内部や惑星基地の様子が描かれ、コマンド入力や選択式の操作を通じて、ログの解析や装置の操作などを行います。『オランダ妻』が地に足のついた歓楽街の裏側を描いていたのに対し、『ABYSS』は遥か彼方の宇宙で繰り広げられる軍事・諜報ドラマを描いており、同じPC-8801を舞台にしながらまったく違う“SFサスペンス”の世界を体験させてくれるタイトルでした。
★はーりぃふぉっくす
・販売会社:マイクロキャビン ・販売された年:1984年(PC-8801版) ・販売価格:当時のPC-8801用ADVの標準的な価格帯(おおよそ6,000〜7,000円台)
『はーりぃふぉっくす』は、マイクロキャビンが送り出した動物村を舞台としたアドベンチャーゲームです。重厚な殺人事件やハードなSFとは異なり、病を患った子ギツネを救うために母ギツネが旅に出るという、温かみのある物語が展開されます。プレイヤーは様々な動物たちと出会い、会話やアイテムのやり取りを通じて物語を前進させていきます。
ほのぼのとしたグラフィックと素朴なストーリーは、当時の「アドベンチャー=殺人事件かお宝探し」というイメージに一石を投じるものでした。『オランダ妻』が大人向けの世界を描いたのに対し、『はーりぃふぉっくす』はファミリー向けとも言える優しいタッチで、PCゲームの間口を広げたタイトルです。プレイヤー層の違いこそあれど、どちらも“物語を読み進める楽しさ”を重視したアドベンチャーゲームであるという点では、同じ時代の仲間と言えるでしょう。
★ミルキーウェイ
・販売会社:マイクロネット ・販売された年:1984年(PC-8801版) ・販売価格:当時のPC-8801向けSTGの一般的な価格帯
『ミルキーウェイ』は、宇宙を舞台にしたシューティングゲームで、近距離戦用と長距離戦用、性格の異なる2種類のメカを切り替えながら敵の猛攻をかいくぐるタイトルです。固定画面での激しい撃ち合いステージや横スクロールステージなど、複数のゲームパターンが用意されており、慣性の効いた独特の操作感をマスターする必要があります。
きびきびと動く自機と、次々と登場する多彩な敵キャラクターは、“遊びごたえのあるアーケードライクなPCゲーム”として当時のユーザーから注目されました。『オランダ妻』と発売時期の近いタイトルですが、こちらは純粋にアクション性を追求した内容であり、同じPC-8801環境が、アダルト探索RPGから本格シューティングまで幅広いジャンルを受け止めていたことを実感させてくれます。
このように、『オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか?』の周辺年代には、アダルトRPG、歴史シミュレーション、ファンタジーRPG、推理アドベンチャー、ほのぼの系ADV、シューティングといった多彩なPCゲームが次々と登場していました。同じ8ビットパソコンの上で、これほど異なる世界が並び立っていたことこそ、この時代のPCゲーム文化の豊かさを物語っていると言えるでしょう。
[game-8]


![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)


![【中古】PC-9801 3.5インチソフト はいぱぁセキュリティーズ[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004789m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝 II[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005030m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ファーランドストーリー 神々の遺産[HDD専用/3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004252m.jpg?_ex=128x128)