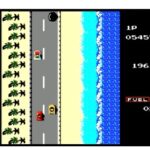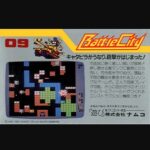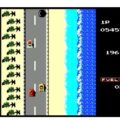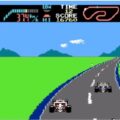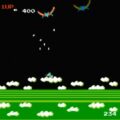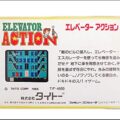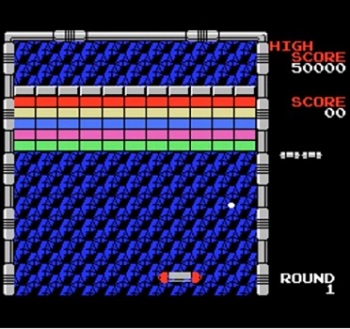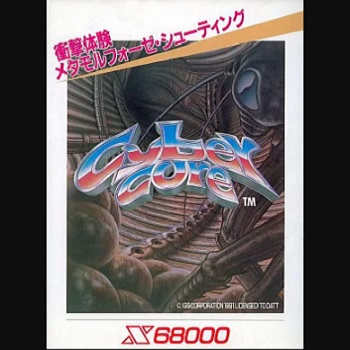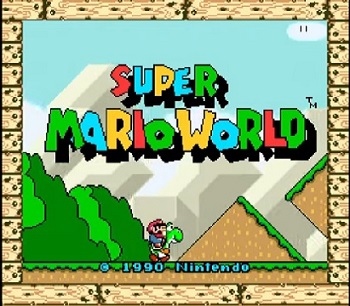【中古】 ファミコン (FC) ジッピーレース (ソフト単品)
【発売】:アイレム
【開発】:アイレム
【発売日】:1985年7月18日
【ジャンル】:レースゲーム
■ 概要
● ファミコン黎明期に登場した「走り抜ける爽快感」
1985年、アーケードから家庭用ゲーム機への移植が盛んになり始めた時代。アイレムが満を持してファミリーコンピュータに参入し、最初に送り出したタイトルが『ジッピーレース』である。原作は1983年に稼働した同名のアーケード版で、二輪バイクでアメリカ大陸を横断するというシンプルかつ壮大なコンセプトをもっていた。当時のプレイヤーにとって、“走る”ことをテーマにしたレースゲームは少なく、オートバイという題材も珍しかった。ファミコン版はそのアーケード感覚を家庭で味わえるよう工夫が凝らされており、プレイヤーはまるで大陸横断の冒険に挑むライダーそのものとなる。
● ロサンゼルスからニューヨークへ——全米横断の大冒険
ゲームの舞台はアメリカ合衆国。プレイヤーはオートバイを操り、西海岸ロサンゼルスを出発し、東海岸のニューヨークを目指す。各ステージは、砂漠地帯、山岳地帯、郊外のハイウェイ、そして都市部など、アメリカ各地をイメージした背景が描かれ、遠い地平線に沈む夕陽や夜のネオン街など、8ビットながらも多彩な景色の変化を楽しめた。当時としては、背景が単調にならないよう地形の表現を工夫しており、プレイヤーの想像力を掻き立てる“旅の物語”が感じられる作品だった。
● 燃料システムと敵車の存在
ジッピーレースの特徴は、単なるタイムアタックではなく「燃料(ガソリン)」を管理しながら走行する点にある。時間制限に追われるのではなく、燃料ゲージがゼロになるとリタイアとなる仕組みだ。そのため、コース上に設置された給油ポイントをうまく拾い、敵車の攻撃や接触によって無駄に燃料を失わないよう注意する戦略性が求められた。敵車は無差別に進路を妨害したり、急な割り込みでプレイヤーを転倒させたりと、ただ速く走るだけではクリアできないゲームデザインが光る。
● カメラアングルの切り替え演出
通常の走行時は見下ろし型のトップビューで展開するが、ゴール地点が近づくと一気に視点が切り替わり、バイクの背後からの“後方3D視点”に変化する。このダイナミックな演出は、当時のファミコン技術の中では異例の挑戦であり、立体感を演出する工夫として高く評価された。スピード感と臨場感が増すこの切り替え演出は、後の多くのレースゲームの演出方法に影響を与えたとも言われている。
● LEDランプ搭載カートリッジの衝撃
ファミコン版『ジッピーレース』は、ハード面でも話題を呼んだ。なんとカートリッジ本体に小型のLEDランプが内蔵されており、プレイ中に点滅するという独特の仕様だったのだ。これはアイレムの「遊び心」と「新しさへの挑戦」を象徴する仕掛けで、発売当時の子どもたちは“光るファミコンソフト”というだけで大きな驚きを覚えた。
● ゲーム性とテクニカル要素
ステージごとに登場するカーブ、橋、分岐、障害物などを見極め、バイクの操作を細やかに調整するテクニックが求められる。スピードを上げすぎると制御不能に陥り、敵車や障害物にぶつかって転倒。減速しすぎれば燃料が尽きてしまう。単純なレースではなく、「リスク管理」と「操作精度」の両立がスコアに直結する設計は、後年のレースゲームにも通ずる戦略性を先取りしていた。
● 当時のゲーム市場における位置づけ
1985年といえば、ファミコンが国民的ブームとなり、各メーカーが参入を始めた年である。ナムコやコナミ、ハドソンなどが続々と名作をリリースするなか、アイレムはこの『ジッピーレース』で存在感を示した。まだファミコン黎明期であり、グラフィック・サウンドともに制限の多い中、アーケード版の魅力を家庭機に落とし込んだ移植度の高さは当時のファンから「頑張っている方」と評された。
● 音楽とサウンドの印象
BGMは短いループながらも軽快で、長時間のプレイでも耳に残るメロディだった。エンジン音や衝突音といった効果音も特徴的で、限られた音源の中で疾走感を出す工夫が感じられる。特にステージ終盤のテンポアップは、プレイヤーの緊張感を高め、ゴール時の達成感をより強いものにしていた。
● ファミコン史に刻まれた“最初のアイレム作品”
アイレムにとって『ジッピーレース』は、ファミコン市場への第一歩であり、ここから『スパルタンX』や『魔鐘』など、数々の名作を生み出す礎となった作品である。派手な演出や複雑なシステムこそなかったが、「遊びやすさ」と「奥深さ」のバランスを重視した設計思想は、この時点ですでに確立されていた。
● 現代から見た『ジッピーレース』の意義
現在の視点で振り返ると、『ジッピーレース』はシンプルながらもゲームデザインの基本をしっかり押さえた良作だ。操作性、難易度曲線、ステージごとの変化、そして達成感。この4つの柱をバランスよく組み合わせた構成は、レースゲームというジャンルの礎を築いたともいえる。レトロゲームとして再評価される理由は、この普遍的な設計思想にあるだろう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● スピードと緊張感が同居する“駆け抜ける快感”
『ジッピーレース』の最大の魅力は、何といってもバイク特有のスピード感と、操作の一瞬の遅れが命取りになる緊張感が同居している点だ。スロットルを開けるたびに高鳴るエンジン音、風を切るように流れていく道路、そして一台一台異なる動きを見せるライバル車。プレイヤーは画面上のライダーと一体化し、ただ速さを求めるだけではなく、冷静さと集中力を維持することが求められる。この「危うさの中の爽快さ」こそが、シンプルな構成ながら多くのファンを魅了した理由である。
● 操作の手応えとゲームバランスの妙
加速と減速、左右への素早いハンドル操作、それらの動きが直感的でありながら、絶妙にミスを誘うバランスで設計されているのもポイントだ。プレイヤーは“速く走るほど危険が増す”というリスクと、“慎重に走るほど燃料が減る”というジレンマに常に晒される。つまり、最適解は状況に応じて変化し、毎回違った展開が生まれる。ここに「飽きさせないゲーム性」が存在する。難しすぎず、かといって単調にもならない――ファミコン時代における理想的な難易度調整のひとつとして、いまも語り継がれている。
● ステージごとに異なるアメリカの風景
『ジッピーレース』では、ロサンゼルスからニューヨークまでの長い旅路がステージとして構成されている。砂漠地帯を突っ走る乾いた風、雪がちらつく山岳ルート、湖畔を抜ける穏やかなカーブ――それぞれの風景が、簡素なグラフィックながら見事に“雰囲気”を伝えてくる。プレイヤーはバイクを操作しながら、まるで一本のロードムービーを観ているような感覚を味わえるのだ。当時の子どもたちにとって、それはまさに未知の国・アメリカを旅する体験そのものであった。
● シンプルなルールの奥に潜む戦略性
「敵車を避け、燃料を拾い、ゴールを目指す」――説明だけ聞けば単純だが、実際にプレイしてみるとその奥深さに驚かされる。敵車の動きには法則があるようでいてランダム性もあり、単調な反射神経ゲーにはならない。燃料を拾うタイミング、減速と加速の切り替え、路肩の利用など、プレイヤー自身の判断力がクリアの鍵を握る。攻略を重ねるほど上達を実感できる作りになっており、“プレイヤーの成長がそのまま結果に現れる”という構造が中毒性を生んでいた。
● ファミコン初期における技術的挑戦
当時のファミコンは、表示できるスプライト数や処理速度に大きな制限があった。しかし『ジッピーレース』は、複数の敵車が画面上をスムーズに動き回るだけでなく、道路のカーブや高低差を視覚的に表現するなど、限界に挑んだプログラム設計を見せている。さらに、ゴール前に視点が切り替わる「擬似3D演出」は革新的だった。後に『アウトラン』や『ポールポジションII』といった本格的なレースゲームが登場するが、『ジッピーレース』はその萌芽をすでに示していたと言えるだろう。
● カートリッジが“光る”という遊び心
本作の象徴ともいえるLEDランプは、他のどのソフトにもないユニークな仕様だった。プレイ中にチカチカと点滅する光は、子ども心を刺激するだけでなく、「いま走っている!」という没入感を高めてくれる演出でもあった。特に夜のステージで遊ぶと、部屋を暗くした中でランプが光り、まるでバイクのヘッドライトのように感じられたと語るプレイヤーも多い。この“ハードウェア演出”は、後年のファミコン文化を象徴する逸話の一つとなった。
● 絶妙な緊張感を作る音とテンポ
音楽は派手ではないが、リズミカルで耳に残るテンポ感が心地よい。ステージ中のBGMが短くループする一方で、転倒時や給油時には独特の効果音が鳴り、ゲームのリズムを崩さないよう巧みに設計されている。特に残り燃料が少なくなるとテンポが上がり、プレイヤーの焦燥感を煽る。この心理的演出は、ハード性能に頼らない“音のデザイン”として高く評価されている。
● 高いリプレイ性と競争心を刺激するスコアシステム
クリアまでにかかった時間や転倒の回数などがスコアに反映されるため、プレイヤーは何度も挑戦したくなる。単にゴールを目指すだけでなく、「より効率的に」「より速く」「よりスマートに」走るための最適ルートを探す楽しさがある。友達同士でスコアを競い合ったり、燃料を残したまま完走するチャレンジをしたりと、コミュニティ的な遊び方も自然に生まれていた。
● “失敗しても面白い”設計
転倒や燃料切れといったミスが単なるペナルティではなく、「次はどう走れば避けられるか」を考えるきっかけになる。プレイヤーの失敗を学びに変える構造は、アイレム作品に共通する哲学だ。失敗のたびに新しい発見があり、リトライを促す。だからこそ、難易度が高くても理不尽に感じない。このバランス感覚は、のちに『スパルタンX』などでも見られる「挑戦して上達する楽しさ」につながっていく。
● アイレムらしい“地味だけどクセになる”味わい
派手なエフェクトやライバルキャラとの会話などはないが、地味さの中に確かな手応えがある。何度プレイしても飽きない設計、プレイヤーの集中力を試す緻密なコース構成、控えめながら存在感のあるサウンド。この“渋さ”こそアイレム作品の本質であり、『ジッピーレース』はその原点として輝きを放っている。時間を経てもなおファンが多いのは、派手さよりも“遊びごたえ”を重視する開発姿勢が感じられるからだろう。
● 現代ゲーマーへの影響
『ジッピーレース』は、後の多くのライディングゲームの雛形となった。燃料制限、交通妨害、ルート管理といった要素は、のちの『ロードラッシュ』や『ライドオン!』などに受け継がれている。また、ミニマルなシステムと直感的な操作設計は、現代のインディーゲーム開発者たちからも“学ぶべき古典”として再評価されている。シンプルさの中に詰まった設計思想――それが『ジッピーレース』最大の魅力なのだ。
■■■■ ゲームの攻略など
● 基本操作の徹底理解から始めよう
『ジッピーレース』攻略の第一歩は、まず操作系の癖を完全に理解することから始まる。Aボタンでアクセル、Bボタンでブレーキ、十字キー左右でハンドル操作――このシンプルな構成ながら、慣れないうちはカーブの入り方ひとつで転倒してしまう。特にファミコン特有の微妙な入力感度により、連打や押しすぎが命取りになるため、「押す・離す・軽く倒す」といった指の感覚を体に覚えさせるのが肝心だ。最初はスピードよりも安定走行を意識し、敵車との距離感をつかむことが重要である。
● ステージごとの地形パターンを把握する
本作のステージは、アメリカ大陸横断をモチーフとしており、ステージごとに道幅・カーブ・障害物配置が異なる。序盤のカリフォルニア地帯では比較的道が広く、練習に適している。中盤の山岳ルートでは橋や崖が多く、直線が短いためハンドリング重視。終盤のニューヨーク付近では交通量が増え、敵車が頻繁に割り込んでくる。これらの特徴を覚えておくことで、先読み運転が可能になり、燃料の節約や転倒の回避につながる。攻略本のない当時、プレイヤーたちは自らの記憶力でこれらの地形を把握し、友人同士で「第3面のあのトンネルが鬼門だ」と情報を共有していた。
● 敵車の動きの癖を読む
敵車はただの障害物ではない。特定の車種ごとに行動パターンがあり、攻撃的なものと防御的なものが混在している。たとえば赤いスポーツカーは加速が速く、直線で無理な追い越しをかけてくるタイプ。一方で青いトラックはスピードは遅いが、進路をふさぐように蛇行する。こうした特徴を覚えておくと、敵車との距離を保ちながら安全に抜くタイミングを見極められるようになる。コツは、敵車の動きを予測して“早めにハンドルを切る”こと。焦って急ハンドルを切ると、コースアウトや転倒につながるので注意しよう。
● 燃料管理が生死を分ける
ジッピーレース最大の特徴は、燃料が尽きればゲームオーバーになる「燃料システム」である。スピードを出しすぎれば燃料消費が激しくなり、無理な追い越しで転倒すればさらに減る。燃料はコース上に点在する“ガソリンタンク”を拾うことで回復できるが、必ずしも安全な場所に設置されているとは限らない。敵車が密集する地点や、狭い橋の上などに配置されていることが多いのだ。ここで焦って突っ込むと事故を起こすため、冷静に状況を判断し、拾える時だけ拾う勇気も必要である。安定してゴールまで燃料を持たせるには、「スピードの緩急」と「ライン取りの最短化」を意識することが重要だ。
● ゴール直前の視点切り替えに注意
ゴール間際になると視点がトップビューから後方3D視点に切り替わる。この切り替え直後にミスをするプレイヤーが非常に多い。なぜなら、視点が変わることで奥行き感覚がズレ、距離や車線の把握が難しくなるからだ。攻略法としては、切り替えが始まる直前にスピードを少し落とし、安定走行を維持すること。焦らず中央車線をキープし、敵車を無理に抜かずに確実にゴールラインを通過するのが安全策だ。この3D視点の演出は見た目の派手さ以上にテクニカルで、ここを安定して乗り切れるかどうかが上級者の分かれ目となる。
● 失敗しにくいライン取りのコツ
特に狭い道や橋では、車体を道路の“右寄り”にキープすると比較的安全に走れる。左側には敵車が寄ってくるケースが多いため、右側を主体にラインを取ると避けやすい。ただし右端に寄りすぎると障害物に接触しやすいため、あくまで中央~右1/3あたりをキープするイメージがベスト。また、カーブに入る前に減速し、出口でアクセルを開ける基本テクニックを徹底することで、転倒リスクを大幅に減らせる。
● 難所:橋とトンネルの突破法
中盤ステージの橋は、画面外から敵車が飛び込んでくるため、反射神経だけでは対応できない難所である。攻略法は“敵の出現タイミングを覚える”ことに尽きる。敵車は決まった間隔で現れるため、何度かプレイして出現位置を体で覚えよう。トンネル内は視界が狭く、背景色が暗いため敵車との距離がわかりにくい。Bボタンで軽く減速し、中央寄りを走るのが安全だ。
● 燃料節約テクニック
ジッピーレースでは、速度が速いほど燃料の消費が激しくなるという特性がある。そのため、常に全開で走るのは得策ではない。下り坂や追い風の区間ではアクセルを離し、惰性で進むのが燃費走法の基本。また、敵車のスリップストリーム(背後走行)を活用することで、燃料消費をわずかに抑えることができる。これはゲーム上の仕様として完全に再現されているわけではないが、体感的にスムーズに走れるため実践的だ。
● 転倒後のリカバリー方法
転倒するとバイクが停止し、再スタートまでに大きなタイムロスが発生する。再スタート直後に再び敵車にぶつかる「連続転倒」は致命的なので、立ち上がりのタイミングには注意したい。コツは、転倒したら一呼吸おいて周囲の交通状況を確認してから再発進すること。また、転倒した地点によっては燃料タンクが消失するため、再スタート直後に無理に拾いに行かず、次の補給ポイントを狙う冷静さが重要だ。
● 裏技・隠し要素
本作には明確な裏技というものは少ないが、一部では「スタート時に一定のリズムでアクセルを連打すると初速が上がる」「特定の地点で敵車を連続で避けると燃料消費が一瞬止まる」など、当時のプレイヤーの間で噂された小ネタが存在した。また、カートリッジのLED点滅タイミングが内部処理と連動しているという説もあり、プレイヤーはその光を“燃料残量のサイン”として利用していたとも言われている。これらの裏話は、まさに80年代らしいファミコン文化の一端を象徴している。
● 安定してクリアするための練習法
上達への近道は「同じステージを繰り返し走ること」に尽きる。燃料切れや転倒でミスしても、焦らず同じコースを反復練習することで敵の動きや障害物の位置を自然に覚えるようになる。また、毎回スコアをメモしておくと、自分の成長が可視化でき、モチベーション維持にもつながる。プレイ時間10分前後で一走できるため、短時間でも集中して上達できるのも『ジッピーレース』の良さだ。
● 完走時の達成感とリスク管理
すべてのステージを走破し、無事ニューヨークにたどり着いたときの達成感は格別である。序盤の余裕から徐々に緊張が高まり、終盤には指先が汗ばむ。燃料ゲージがゼロ寸前でゴールしたときの安堵感は、他のどんなアクションゲームにも代えがたい。『ジッピーレース』は単なるレースではなく、「危険と焦りを制御する精神力のゲーム」でもあるのだ。ミスを重ねながら上達していく過程そのものが、攻略の醍醐味となっている。
■■■■ 感想や評判
● 当時のプレイヤーが感じた“スピードの衝撃”
1985年当時、『ジッピーレース』を初めてプレイした子どもたちは、画面上で流れる道路のスピード感に驚いたという声が多い。ファミコン黎明期のタイトルとしては、画面スクロールの滑らかさが際立っており、「まるで本当に走っているようだ」と感動を覚えたプレイヤーが少なくなかった。 単なる左右移動の繰り返しではなく、敵車との駆け引き、燃料の管理、そして視点が切り替わるゴール演出――これらの要素が当時のレースゲームには珍しい“ドラマ性”を生み出していた。特に、アメリカ横断という壮大なスケール感は、少年たちの冒険心を刺激し、「ゲームで旅をしている感覚」を与えたと語られている。
● 難易度の高さとやり込み要素のバランス
『ジッピーレース』は難しい。しかし、ただ難しいだけではなく、練習すれば確実に上達を感じられる構成になっている点が評価された。最初は敵車に何度も弾かれて転倒するが、コースを覚えていくうちに少しずつ距離を伸ばせる。「あと一歩でニューヨーク!」というギリギリの攻防を繰り返すうちに、気づけば何度もリスタートしてしまう中毒性がある。 プレイヤーの間では、「燃料ゲージとの戦いが熱い」「慎重さと大胆さのバランスが絶妙」といった感想が多く、ゲームデザインの巧みさを評価する声も多かった。
● 見下ろし視点と3D視点の融合に対する驚き
当時のファミコンユーザーの間では、ゴール付近でカメラアングルが変わる演出が話題となった。上から見下ろす2D視点から、いきなりバイクの背後に回り込む3D的視点に切り替わるという演出は、まさに“時代を先取りした感覚”をもたらした。 この演出に関して、当時の雑誌『ファミコン通信』(現・ファミ通)では「家庭用機でここまでの臨場感を再現できるとは」と評され、グラフィック技術の進化を感じさせる象徴的なシーンとして紹介された。後年の『アウトラン』などに繋がる立体的表現の萌芽と見る評論家も多い。
● LEDランプの記憶と“光るソフト”の話題性
『ジッピーレース』のカートリッジに搭載されたLEDランプは、子どもたちの記憶に強く残っている。プレイ中に赤く光るその小さなランプは、ゲームの進行と連動しているように見え、まるで本物のバイクのライトのようだと話題になった。当時、LEDが点くファミコンソフトは他にほとんど存在せず、友達の家に持って行って“光るソフト”を見せびらかすのが自慢だったという。 口コミでは「LEDの光で夜のプレイがかっこよく感じた」「あの点滅がスリルを増していた」といった意見が多く寄せられている。
● サウンド面への評価
BGMはシンプルながらも耳に残るメロディが印象的だった。ファミコンの2A03音源を駆使した軽快なリズムは、バイクのエンジン音と絶妙に調和し、プレイヤーの集中を高める。特に燃料残量が少なくなると音楽のテンポが速くなり、緊張感が高まる演出は“音でプレイヤー心理を操る”秀逸な設計として、今でも評価されている。 当時の雑誌レビューでも「音でゲームのテンポを作り出すセンスが光る」「耳で危険を察知できるレースゲーム」と評されたほどである。
● ファミコン参入初タイトルとしてのインパクト
『ジッピーレース』は、アイレムが初めてファミコンに送り出したタイトルであり、その挑戦的な姿勢がユーザーの間で高く評価された。アーケードで人気を博した作品を、限られた容量の中でどこまで再現できるか――その意欲的な試みは、後に続く他社への刺激にもなった。 当時、ゲーム誌では「移植度は高く、ファミコンとしては健闘している」「アイレムらしい堅実な作り」と評価され、グラフィックよりも操作性とゲーム性の高さを称賛する論評が多く見られた。
● 難易度に対する賛否両論
一方で、「難しすぎる」という意見も少なくなかった。特に燃料管理と敵車の妨害が重なる中盤以降は、初心者にとって非常に厳しく、クリアできずに諦めるプレイヤーもいた。だがその反面、「だからこそ燃える」「一度は挫折しても、再挑戦したくなる」というポジティブな声も根強かった。 ファミコン時代のゲームは、短時間で遊べるが長くやり込める設計が求められており、『ジッピーレース』はその理想形を体現していたともいえる。
● ゲーム誌・レビューでの評価
1985年当時の『コンプティーク』誌上では、「アーケードの興奮をそのまま持ち込んだ快作」として紹介され、特に操作感と臨場感の高さが評価された。 また、『ファミリーコンピュータMagazine』では「難易度は高いが、リズムを掴むと一気に快感が押し寄せる」「1ミスで緊張感が跳ね上がる構成が秀逸」と評され、スコアアタックの面白さが特集された回もある。 その後の“ファミコン黄金期”を代表するレースタイトルの一つとして、後年の回顧記事でもしばしば言及されている。
● 現代レトロゲームファンの再評価
21世紀に入り、レトロゲームブームが再燃すると、『ジッピーレース』も再び脚光を浴びるようになった。YouTubeやSNSでプレイ動画が紹介され、「このテンポ感がたまらない」「現代のゲームにはない潔さがある」と称賛されている。 特にファミコン世代以降の若いプレイヤーからは、「難しいけど理不尽じゃない」「何度も挑戦したくなる絶妙な手応え」といったコメントが多く、シンプルな中に詰まった“ゲームデザインの原点”として再評価されている。
● コレクターの間での人気
ファミコンコレクターの間では、『ジッピーレース』は“LED付きカートリッジ”として特別な存在だ。箱付き・説明書付きの完品は年々数を減らしており、「初期アイレム作品の象徴」として高値で取引されることもある。ゲーム内容の面白さだけでなく、1980年代という時代を象徴する工業デザイン的価値があるとされ、レトロゲーム展示イベントなどでも注目を集めている。
● 総合的評価とファンの想い
『ジッピーレース』は、単に懐かしいだけのゲームではない。そこには“挑戦する楽しさ”“失敗を糧に進む感覚”という、今なお通じる普遍的な魅力がある。 発売から40年近く経った今でも、「このゲームでゲームというものに夢中になった」「初めて“達成感”を知った作品」と語るファンが多いのは、その根底に“人を夢中にさせる仕組み”が確かに存在するからだ。 操作感、緊張感、燃料管理、そして光るカートリッジ――どれもが1980年代のゲーム文化を象徴する要素であり、『ジッピーレース』はファミコン史に確かな足跡を残した一本と言えるだろう。
■■■■ 良かったところ
● スピード感と緊張感の融合が見事だった
『ジッピーレース』が当時の子どもたちの心をつかんだ最大の理由は、その圧倒的なスピード感と、常に危険が隣り合わせという緊張感の融合にある。走行中の画面スクロールは滑らかで、風を切るような疾走感をプレイヤーに与えていた。敵車との距離が詰まる一瞬の判断で命運が決まるため、全神経を集中させてコントローラーを握る感覚は他のファミコンタイトルにはない魅力だった。 当時はグラフィックよりも「遊びの感覚」こそが最も重要視されており、その意味で『ジッピーレース』は“感覚的な快感”をプレイヤーに提供した稀有な作品であった。スピードを上げるたびに高鳴るエンジン音が、プレイヤーの心拍数とリンクしていくような緊迫感は、ファミコン初期の中でもトップクラスの没入体験だった。
● 操作性の直感的な良さ
多くのプレイヤーが口を揃えて褒めるのが、操作性の完成度の高さだ。Aボタンでアクセル、Bボタンでブレーキという単純な構成ながら、バイクの挙動は非常に繊細に再現されている。カーブでの微妙な減速、直線での加速、敵車の動きを読むタイミング――すべてが手に伝わる感覚で調整できるのが心地よい。 ゲーム中に「自分のミスが原因で転倒した」と明確に感じられる設計になっており、理不尽な敗北が少ない点も評価が高かった。「操作を極めれば確実に上達できる」という感覚が、プレイヤーのモチベーションを維持していた。
● 視覚的な演出とゴール時の達成感
ゴール間近でカメラアングルが切り替わり、後方視点になる演出は、当時のプレイヤーに強いインパクトを残した。「走り抜けた」という感覚が視覚的にも味わえるこの仕掛けは、ファミコンの演出技術として画期的だった。 さらに、ゴールした瞬間にBGMが切り替わり、画面に“ニューヨーク到達”と表示されるその瞬間、長い旅路を走り切った達成感が胸に広がる。多くのプレイヤーがこの瞬間を「努力が報われた瞬間」として記憶しており、シンプルながらも心理的なカタルシスを生み出す演出として評価されている。
● BGMと効果音の完成度
音楽面も『ジッピーレース』の良さを語る上で欠かせない。ステージBGMは短いループながらリズミカルで、プレイヤーの集中を切らさないテンポに仕上がっている。エンジン音のうなりや、敵車との衝突音、燃料が尽きる警告音なども的確で、限られた音源チャンネルを最大限に活用していた。 特筆すべきは、燃料が減るにつれてプレイヤーが自然と焦るように設計されている点だ。音の変化によって緊迫感を演出する手法は、まさに“耳で感じるゲームデザイン”の先駆けといえる。
● ファミコン初期としては驚くべき完成度
1985年という早い時期に、これだけのクオリティを持ったレースゲームを家庭用機で実現した点は特筆に値する。まだ“アクション”や“シューティング”が主流だった中で、リアルな走行感と戦略性を両立させた『ジッピーレース』は、ジャンルの多様化を象徴する作品でもあった。 プレイヤーたちは口々に「ファミコンでここまでできるのか」と驚き、後の『ロードファイター』や『エキサイトバイク』などに繋がる基礎を築いたと評された。
● LEDランプの存在が生んだワクワク感
ファミコンカートリッジにLEDランプを搭載するという発想は、まさにアイレムらしいユニークさの象徴だった。プレイ中にランプが点滅することで、まるで本物のバイクのヘッドライトが光っているように見える。このちょっとしたギミックがプレイヤーに「遊んでいる実感」を与え、所有欲を刺激した。 当時の子どもたちは「光るファミコンソフト」を友人に見せることが誇りだったと語っており、ハード面でも他社との差別化に成功していたと言える。
● 燃料システムがもたらす戦略性
多くのレースゲームが“スピード勝負”に重きを置いていた時代に、『ジッピーレース』は燃料管理という新たな軸を導入した。燃料をどこで拾うか、スピードをどこまで抑えるか、無理な追い越しを避けるか――プレイヤーが瞬時に判断を迫られるこのシステムが、ゲームに深みを与えていた。 単に速さを競うだけでなく、計画的に走る楽しさを体験できたことで、アクションゲームの枠を超えた“思考型レース”という新ジャンルを提示したとも言える。
● 繰り返し遊びたくなる中毒性
一度クリアしても、スコア更新やノーミス完走などのチャレンジが無限に存在する。プレイヤーが「次こそはもっと上手く走れる」と感じる設計になっており、難易度が高いにもかかわらず何度でも挑戦したくなる。 この“負けても楽しい”構造は、後の名作『スパルタンX』や『魔鐘』にも受け継がれたアイレム流ゲームデザインの原点であり、ファンの心を掴み続けている。
● ファミコン黎明期の空気を凝縮した一本
『ジッピーレース』には、1980年代中盤という時代特有の空気が詰まっている。まだゲームが「新しい文化」として世間に認知され始めた頃、子どもたちは自宅でアーケードの感覚を味わうことに熱狂していた。 電源を入れると光るカートリッジ、テレビから流れるピコピコ音、コントローラーを握る手の汗――そのすべてが当時の家庭の風景の一部だった。今なお多くのファンが「青春の一本」として『ジッピーレース』を挙げるのは、単に面白いゲームだからではなく、“初めてゲームに夢中になった体験”を象徴しているからである。
● アイレム作品らしい誠実なつくり
派手さよりも丁寧な設計、堅実な操作性、プレイヤーを裏切らない手応え――これらはまさにアイレムらしさそのものだ。 『ジッピーレース』では、短時間でも遊べ、何度も挑戦でき、失敗を通して上達を感じられる。そうした「繰り返し遊ぶほど味が出る構造」は、同社の後続作品にも脈々と受け継がれた。 発売当時は決して大ヒット作ではなかったが、30年以上経った今なお語り継がれていること自体が、その誠実な作りの証明である。
■■■■ 悪かったところ
● 初心者にはあまりに厳しい難易度設定
『ジッピーレース』が当時から指摘されていた最大の弱点は、その“容赦のなさ”にある。序盤こそ軽快に走れるが、ステージが進むごとに敵車の動きは激しくなり、道路も狭く、燃料の配置もいやらしくなっていく。特に中盤の山岳ステージ以降は、少しでも操作を誤ると転倒・爆発・燃料切れの三重苦が待ち受けている。 そのため、初心者が数分も経たずにゲームオーバーになるケースが多く、「難しすぎて楽しむ前に終わってしまう」との声が多く見られた。アーケード版の緊張感をそのまま家庭用に移植したがゆえに、調整不足と感じたユーザーも少なくなかったのだ。
● 燃料システムのシビアさ
このゲームの魅力のひとつである「燃料制限」だが、逆にプレイヤーを追い詰める要素として批判されることもあった。燃料ゲージが思いのほか早く減り、給油ポイントを逃すと即ゲームオーバー。しかも給油アイテムの配置がコース中央ではなく、敵車の密集地帯や障害物の直後など、拾うのが非常に難しい場所にある。 「もう少し救済措置がほしかった」「せめて燃料消費を緩やかにしてほしい」といった意見が当時のプレイヤーから多く聞かれた。上級者には戦略性として機能していたが、ライトユーザーには“理不尽”に感じられた要素である。
● 敵車の動きが不自然に感じることも
敵車のAIは単純なパターンに基づいて動いているため、時折不自然な行動を見せることがあった。例えば、プレイヤーの直前で急に方向転換してぶつかってくる、橋の上で左右に暴れる、あるいは画面外から高速で突っ込んでくるなど、予測不能な動きがストレスになることもあった。 一度ミスをすると連鎖的に次の敵車に当たり、立て直す間もなくゲームオーバーに――そんな状況が頻発し、「運ゲーっぽい」と感じたユーザーも多い。もう少し敵車の挙動に“読みやすさ”があれば、バランスが良くなったかもしれない。
● 単調になりやすいゲーム展開
全ステージを通して基本的な目的は同じ――走って、避けて、燃料を拾う。この繰り返しの中で、ステージごとの変化は背景やカーブの形状などに限られており、長時間プレイするとどうしても“単調さ”を感じてしまうプレイヤーもいた。 特に当時は『エキサイトバイク』のようにジャンプ台やコース編集といった遊びのバリエーションが登場し始めていたため、比較すると『ジッピーレース』のゲーム性はやや一本調子に見えてしまった。「せっかくのアメリカ横断なのに、もっとイベント的な演出や変化がほしかった」という意見も根強い。
● 音楽のバリエーションが少ない
BGM自体の完成度は高いが、全体のバリエーションが少ないため、長く遊ぶと飽きがくるという声もあった。特にループが短いため、プレイ時間が長くなるほど同じフレーズを何度も聴くことになり、耳に残りすぎてしまう。 当時のファミコンソフトの容量制限を考えればやむを得ないが、ステージごとにテーマ曲を変える、あるいはゴール直前にテンションが上がるBGMを用意するなどの工夫があれば、より印象深い作品になっただろう。
● グラフィックの表現力の限界
ファミコン初期というハードの制約上、背景や車の描写はシンプルにとどまっている。遠近感の表現も乏しく、橋やトンネルといった構造物はパターン的に見えてしまう箇所もあった。 特に“アメリカ横断”というスケールの大きなテーマを掲げているだけに、「もっと景色の変化を感じたかった」「都市や自然の表現が単調」との意見が挙がった。とはいえ、1985年という時代を考えれば、当時の技術水準としては十分健闘していたといえる。
● 視点切り替え時の難しさ
ゴール直前で3D風の視点に切り替わる演出は確かに斬新だったが、操作難易度が急に上がるという欠点もあった。奥行きの表現が曖昧なため、距離感が掴みにくく、敵車や障害物を避けにくい。 特に初心者にとっては「最後の最後で転倒して失敗」という悔しい体験をすることが多く、達成感よりも挫折感が残る場合もあった。この視点切り替えを「迫力のある演出」と見るか、「理不尽な罠」と感じるかで評価が分かれた部分である。
● リトライ性の低さ
コンティニュー機能がないため、一度ゲームオーバーになると最初からやり直しという仕様も不評の一因だった。長い距離を走り抜けた末に燃料切れでリタイアしても、また最初のロサンゼルスからやり直さなければならない。 当時の多くのプレイヤーは、「せめて途中セーブやステージセレクトがほしかった」「難所の練習ができない」と不満を漏らしていた。家庭用ゲームとしての遊びやすさという観点では、もう一歩配慮が足りなかったと言える。
● カートリッジのLEDが一部で誤解を招いた
“光るカートリッジ”は話題性こそ高かったが、一部では「LEDがついている理由がわからない」「ただ眩しいだけ」といった意見もあった。プレイヤーの中には、LEDの点滅がゲームの進行と連動していると思い込む人も多く、実際にはただの装飾だったことを知ってがっかりしたという声も。 結果として、“ gimmick(ギミック)に頼った演出”と捉える層も存在し、アイレムの真面目なイメージにそぐわないと感じる意見も一部にはあった。
● 中盤以降のテンポの悪さ
終盤のステージは敵車が多く、燃料配置がシビアなうえ、画面スクロールの速度がやや不安定になることがある。特に同時表示スプライトが多くなると処理落ちが発生し、一瞬のラグが命取りになる場面も。これがプレイヤーにストレスを与え、「テンポが崩れる」「スピード感が台無し」と感じたユーザーもいた。 ファミコンのハード性能の限界によるものではあるが、もう少し処理を軽くする工夫が欲しかったという意見は根強い。
● やや地味な印象を残すタイトルデザイン
タイトル画面やパッケージデザインは控えめで、他社の派手なソフトに比べるとインパクトが弱い。特に子どもたちが店頭でソフトを選ぶ際、「光るLED付き」という特徴を知らなければ見過ごしてしまう可能性もあった。 作品の中身は優れているだけに、もう少しパッケージや広告展開に“アメリカ横断のスケール感”を押し出していれば、当時の人気はさらに高まっていたかもしれない。
● 総評:惜しい完成度の名作
こうして見ると、『ジッピーレース』の“悪かったところ”の多くは、むしろ挑戦的な設計ゆえの副作用である。燃料システムや難易度の高さ、3D視点の導入など、当時としては先進的すぎた部分が一部のユーザーに合わなかったのだ。 つまり“欠点=挑戦の証”でもあり、この作品が1985年に持っていた革新性を示す裏返しでもある。決して致命的な欠点ではなく、時代を先取りしすぎたがゆえの“実験的名作”として、後年の評価はむしろ上昇している。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
● 主人公ライダー ― 無名のヒーロー像
『ジッピーレース』に明確なストーリーやキャラクター名は存在しない。だがプレイヤーたちにとって、ハンドルを握る無名のライダーこそがこの作品の“主人公”であり、“ヒーロー”であった。彼には名前もセリフもない。だが、エンジン音とともにひたすら前へ突き進むその姿勢が、どこか孤独で勇ましいと感じられた。 プレイヤー自身がそのライダーに“自分”を重ねることで、ゲーム体験はよりドラマチックになる。特に燃料が切れそうになりながらもゴールを目指す姿には、誰もが自分の限界と戦う主人公のような感情移入を覚えたという。無言のキャラクターがこれほどまでに存在感を放ったのは、1980年代のゲームらしい“想像の余地”があったからだろう。
● 敵車たち ― ただの障害物ではなく「走るライバル」
ジッピーレースに登場する敵車には、固定の名前や個性は与えられていない。しかしプレイヤーの間では「赤いスポーツカーのやつが一番厄介」「青いトラックはのろいけど邪魔」といった“あだ名”や“性格”が自然に生まれていた。 このように、敵車をただの障害物ではなく“意思を持ったライバル”として認識させるほど、動きが生々しかったのだ。前をふさぐ、急に割り込む、時には妨害してくる――その行動が人間味を感じさせ、まるで自分以外のレーサーたちと戦っているような臨場感を生み出していた。 プレイヤーによっては「どうしても腹が立つ赤い車」「避けたいけど出てくるトラック」など、強い印象を残した敵車を“キャラ”として記憶している人も少なくない。
● 給油トラック ― 命をつなぐ味方キャラの象徴
コース上に時折登場する給油車(ガソリンタンク)は、無機質なオブジェクトでありながら、プレイヤーにとっては“救世主”的存在だった。燃料ゲージが残り少ない状態で、視界の先にガソリンタンクのアイコンが現れた瞬間の安堵感は格別。まるで砂漠でオアシスを見つけたような喜びを与えてくれる。 このアイテムは、単なる補給ポイントという以上に、“希望の象徴”としてプレイヤーの記憶に残った。多くのプレイヤーが「あと少しで燃料が尽きる……! あっ、タンクだ!」という場面を体験しており、その瞬間のドキドキ感は『ジッピーレース』の名場面の一つとして語り継がれている。
● バイク ― 無言の相棒
主人公が乗るバイクも、明確な機種名は示されていない。しかし、そのシルエットや走行音から、プレイヤーの多くは“アメリカンな大型バイク”をイメージしていた。時にはハーレーのように見え、時にはスーパースポーツのように見える――この曖昧さが逆に想像力をかき立てた。 特筆すべきは、転倒後もすぐに立ち上がり、再び走り出すタフさ。まるで主人公と心を通わせた相棒のように、何度転んでも共にゴールを目指す。その姿が、当時の少年たちの「バイクへの憧れ」と重なり、“このバイクに乗って旅をしたい”という夢を抱かせたのだ。 プレイヤーにとって、ジッピーレースのバイクは単なる乗り物ではなく、信頼できる相棒だった。
● ゴール地点の観客たち ― ほんの一瞬の祝福
ファミコンの画面内では表現こそ簡素だが、ゴール地点には小さなドットで描かれた観客が配置されている。彼らは声も出さず動きもしないが、ゴールラインを越える瞬間、プレイヤーには確かに“誰かが見ている”という感覚が生まれた。 子どもたちはそれを想像の中で補い、「やった! ゴールしたぞ!」と喜びを共有していた。ドット絵の群衆に、現実の友人たちの姿を重ねていたプレイヤーも多い。ゲームがまだシンプルだった時代、わずかな演出が強い感情を呼び起こす力を持っていたのである。
● プレイヤー自身が物語を作る構造
『ジッピーレース』は物語を語らない。だが、それが逆に“プレイヤー自身が物語を作る余地”を残している。あるプレイヤーは「無口なライダーが一人でアメリカを横断している」と想像し、また別のプレイヤーは「大会で優勝を目指す若者」としてプレイした。 この“想像で補う余白”こそが、当時のファミコンゲームの魅力の一つであり、ジッピーレースもその代表的な例といえる。無言の主人公が走る姿に、プレイヤーが自分自身の物語を投影していたのだ。 だからこそ、セリフも演出もなくとも、プレイヤーたちは強い感情を抱いた。ゲームが“物語を感じさせる装置”になっていた初期の名作である。
● 敵車への“愛憎”とプレイヤー心理
興味深いのは、プレイヤーの間で「この車は嫌い」「この車はかわいい」といった擬人化的な感情が芽生えていた点である。赤い車は“挑発的なライバル”、青いトラックは“のんびり屋の妨害者”、黒い車は“危険な刺客”といった具合に、想像上のキャラクター付けが自然と生まれていた。 それは決して意図的な演出ではなく、シンプルなドット絵だからこそプレイヤーが自由に感情を投影できた結果である。現代のリアルなグラフィックでは得られない“想像の余地”が、ジッピーレースのキャラクターたちを生きた存在にしていた。
● 現代における“レトロキャラ”としての魅力
近年のレトロゲームブームでは、ジッピーレースのライダーや敵車をモチーフにしたドット絵アートやグッズがファンの手で制作されている。SNS上では「LEDが光るカートリッジを再現したキーホルダー」や「8bitライダーのピクセルアート」なども人気で、当時のキャラが新しい形で再評価されている。 無名の主人公ながら、“走り続ける男”という象徴的な存在として、レトロゲーマーたちの心の中で今も生き続けているのだ。
● プレイヤーにとっての永遠のヒーロー像
『ジッピーレース』のライダーには、勝利の笑顔も敗北の涙も描かれない。ただひたすらに走る姿だけがある。それこそが、この作品の美学である。失敗しても立ち上がり、燃料が尽きかけても進み続ける――その姿勢が、プレイヤー自身の人生観と重なると語るファンも少なくない。 「どんなに転んでも、もう一度立ち上がって走る」――このテーマが、言葉にならない形でゲーム全体に流れている。主人公の名は誰も知らない。それでも、彼は多くの人にとって“忘れられないヒーロー”なのである。
[game-7]
■ 中古市場での現状
● レトロゲーム市場での存在感
1985年に発売された『ジッピーレース』は、ファミリーコンピュータ初期の名作として知られ、レトロゲームコレクターの間で現在も高い人気を誇る一本である。 発売から40年近くが経過しているにもかかわらず、中古市場では今も安定した取引が行われており、特に「LEDランプ付きカートリッジ」という特徴がコレクター心理を刺激している。ファミコンソフトの中でも、“光る”ギミックを持つ作品は非常に珍しく、同時期のソフトの中では群を抜いた存在感を放っている。
● ヤフオク!での取引傾向
ヤフオク!では、『ジッピーレース』の出品数は比較的安定しており、常時10~20件前後が確認される。 相場としては、カートリッジのみで1,500円~2,800円前後、箱・説明書付きの完品になると3,000円~4,000円前後で取引されるケースが多い。 中でも状態の良い完品(外箱に色褪せがなく、説明書に折れや破れのないもの)は、即決価格4,500円~5,000円で落札されることもある。 特筆すべきは、LEDランプが正常に点灯するかどうかが価格に大きく影響する点である。点灯確認済みの出品には「動作確認済」「LED点灯OK」といった記載があり、入札数が急増する傾向にある。一方、LEDが故障している個体は1,000円以下まで落ちることもある。 1980年代のプラスチック製ラベルは経年劣化しやすく、日焼けやラベル剥がれが価格を左右するため、コンディションの見極めが重要となる。
● メルカリでの販売動向
フリマアプリ「メルカリ」でも、『ジッピーレース』は定期的に出品されている。 取引価格の中心は1,800円~3,200円前後で、特に「箱・説明書付き」「LED点灯確認済」「動作確認済」の三条件を満たすものが人気を集めている。 メルカリでは写真枚数と説明文の丁寧さが売れ行きに直結するため、LEDの光っている様子を掲載した写真付きの出品は、同じ価格帯でも早く売れる傾向がある。 また、状態が良く「コレクション目的」に耐える出品物は即購入されるケースも多く、レトロゲームコレクター層の需要が依然として根強いことを示している。 一方、カートリッジのみの出品でラベルに汚れがある場合は、1,200円前後まで下がることもあり、コンディションによる価格差が非常に大きいのが特徴である。
● Amazonマーケットプレイスでの価格帯
Amazonでは、駿河屋やブックオフオンラインなどの中古ショップが出品しており、2,500円~4,500円前後が相場である。 他のフリマサイトと比較するとやや高値だが、その分「動作保証付き」や「返品対応可能」などの条件が付いていることが多く、安心して購入したい層に人気がある。 また、Amazonでは新品同様(未使用・未開封)と表記された希少品もまれに登場し、そうした出品は6,000円~7,000円で即完売するケースがある。 特に2020年代以降、レトロゲームブームの再燃により、Amazon内での在庫は少なくなりつつあり、安定した取引が難しくなっている。
● 楽天市場での取り扱い状況
楽天市場では、主に中古ゲーム専門店や個人ショップが取り扱っており、2,800円~4,000円前後が主な販売価格帯となっている。 楽天の特徴として、外箱・説明書付きの商品が多く出品されており、特に「美品」と銘打ったものは4,500円を超えることもある。 また、コレクター向けに「状態ランク付き」で販売されるケースが多く、Aランク(非常に良い)やSランク(未使用に近い)の個体は人気が高い。 送料込み・即日発送対応などの条件を重視する購入者も多く、価格よりも“安心して買える店舗”を選ぶ傾向が見られる。
● 駿河屋での販売・買取価格
中古ゲーム専門の老舗・駿河屋では、『ジッピーレース』の取り扱いが継続的に行われている。 2025年現在、販売価格は2,200円~3,300円前後で、状態に応じてランクが設定されている。完品でLEDが点灯する動作品は3,000円を超えるが、ラベル剥がれやLED不良のものは1,000円台まで下がる。 また、買取価格も比較的高めに設定されており、完品で状態が良ければ700円~1,000円前後、カートリッジのみで500円前後が相場となっている。 駿河屋は定期的に“レトロゲーム買取アップキャンペーン”を実施しており、その時期に売却すれば高値がつく可能性もある。
● 中古品の状態と保存の注意点
発売から数十年が経過しているため、ソフトの状態には大きな個体差がある。LEDの点灯機構は経年劣化で接触不良を起こしているものが多く、分解清掃を行わないと光らないケースも少なくない。 また、ラベルの印刷は紫外線に弱く、日焼けや退色が発生しているものが多い。外箱も紙製のため、角潰れや色あせが目立つものが多く、保存状態の良い完品はますます希少になっている。 コレクターの間では、湿度管理されたケースに保管し、LED部分に負担をかけないよう乾燥剤とともに保存するのが主流となっている。
● 復刻・再販の可能性とデジタル配信
『ジッピーレース』は、長年にわたって公式な復刻やダウンロード配信は行われていない。かつては「Project EGG」などのレトロゲーム配信サービスでアーケード版が遊べる時期もあったが、ファミコン版の配信は確認されていない。 そのため、実機でのプレイにはオリジナルカートリッジが必要であり、実機環境を持たない新規ファンには少しハードルが高いタイトルとなっている。 しかし近年では、ファミコン互換機やエミュレーター環境の普及により、プレイ手段は再び広がりつつある。中古市場での需要が絶えないのは、この“実機で味わう懐かしさ”を求めるファンの存在が大きい。
● コレクター心理と希少価値
『ジッピーレース』は、単なる遊ぶためのソフトではなく、“コレクションアイテム”としての価値が年々高まっている。特に初期版(カートリッジラベルに印刷ズレがあるタイプや、初期ロットのLED明るさが強いタイプ)は、マニアの間で“初期個体”として高値で取引される。 また、アイレムのファミコン参入第一弾という歴史的意義も評価され、ゲーム保存団体や博物館級コレクターの収集リストにも名を連ねている。 レトロゲーム市場においては、“プレミアムソフト”というより“象徴的存在”として、コレクター文化の中で確固たる地位を築いている。
● 総評:今なお光を放つ名作
中古市場での安定した人気の背景には、単なる懐古趣味ではなく、『ジッピーレース』という作品そのものの完成度の高さがある。 LEDランプという物理的な輝きは、今では動作しない個体も多いが、そのデザインと発想自体が80年代の「遊び心」を象徴している。 価格こそ高騰していないものの、コレクター間では「持っておきたい一本」「光るファミコンソフトの代表格」として位置づけられており、今後も確実にその価値を保ち続けるだろう。 時代を越えて、プレイヤーの記憶と共に“光り続ける”――それが『ジッピーレース』という作品の真の魅力であり、現在の中古市場でもなお色褪せない理由である。
[game-8]
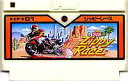
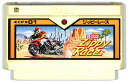
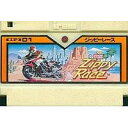
![【中古】【表紙説明書なし】[FC] ジッピーレース(Zippy Race) アイレム (19850718)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102056.jpg?_ex=128x128)


![【中古】アーケード基板 ジッピーレース [基板のみ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8702/180000534m.jpg?_ex=128x128)