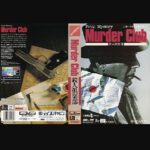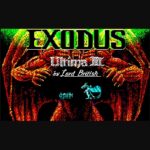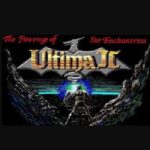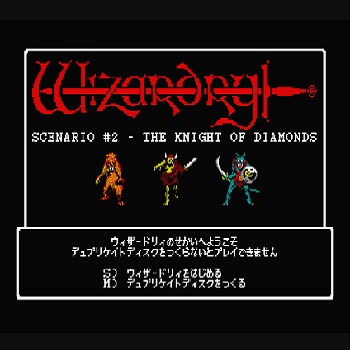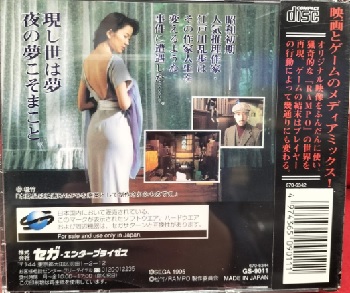【発売】:マイクロキャビン、TAKERU
【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSXturboR、FM TOWNS、X68000、Windows
【発売日】:1991年
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
サイバーパンクと東洋神話が融合した独自の世界観
1991年12月、マイクロキャビンとブラザー工業によるソフトベンダーTAKERUの協力体制で世に送り出された『幻影都市』は、当時のパソコンゲーム界でも異彩を放つ存在だった。PC-8801やPC-9801、MSXturboR、FM TOWNS、X68000、さらには後年のWindows版へと展開されたこの作品は、ただのRPGではなく「サイバーパンク」と「東洋伝奇」の要素を融合させた異色の超伝奇RPGとして注目を集めた。
舞台となるのは202X年の香港――返還後の世界で、地殻変動により一夜にして壊滅した旧市街。その廃墟の上に築かれた新都市「ネオ・ホンコン」には、科学と霊力、そして人間の欲望が交錯している。都市上層部に築かれた巨大な人工地殻「インナーエリア」と、崩壊した旧香港を基盤にした「アウターエリア」。その二重構造の街を舞台に、主人公・天人(テンジン)は、運命に導かれるように真実を追う旅へと踏み出していく。
マイクロキャビン黄金期を象徴するクリエイター陣
本作の企画・ディレクションを務めたのは『フレイ』や『サークII』で知られる中津泰彦。シナリオは加藤雅史、コンセプトデザインは百鬼丸、音楽は新田忠弘・福田康文・瓜田幸治らマイクロキャビン音楽チームが担当し、イラストレーションは橘田幸雄が手がけた。いずれもマイクロキャビンが誇る精鋭であり、彼らが培ってきた“Xakシリーズ”や“Fray”の演出技術が、本作でさらに進化を遂げている。
特に注目すべきは「操演システム」と呼ばれる新たな演出手法だ。これは従来のアニメーションによるイベントシーンを排し、キャラクタードットそのものを演技させるという画期的なもので、後の作品にも多大な影響を与えた。この技術により、ビジュアルシーンでは表現しきれない繊細な動作や心理描写が可能となり、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えたのである。
あらすじ:混沌の新香港に蠢く影
物語は人民警察の女性隊員・美紅が、荒廃したハイウェイで謎の少女を保護する場面から幕を開ける。その出会いをきっかけに、主人公・天人は壮大な陰謀へと巻き込まれていく。彼の旅は、自身の失われた記憶を取り戻す過程でもあり、同時に“人間とは何か”“神とは何か”という根源的な問いを突きつけるものでもある。
この物語には、企業支配、宗教的儀式、遺伝子改造、人造人間といったSF的要素が散りばめられており、そこに陰陽師や霊力、封印などの伝奇的モチーフが重ねられる。特に、組織「SIVA」が掌握する人工都市の裏側で展開される神話的な計画は、プレイヤーに現実と幻想の境界を意識させる仕掛けとして秀逸である。
ゲームシステム:操演とVRが生む臨場感
『幻影都市』のシステム面での特徴は、マイクロキャビン独自の「VRシステム(Visual Representation System)」と、前述の「操演システム」が融合した点にある。VRシステムは斜め見下ろし視点による立体的マップ表示を可能とし、細かな背景の奥行きや多重スクロールを実現。さらに操演システムによってキャラクターがリアルタイムで動作し、イベントを演じる。
この仕組みにより、プレイヤーは単なる文字や絵ではなく、登場人物たちの息遣いを感じ取るような臨場感を味わえる。特にクライマックスでの魔天教演舞堂での儀式シーンは、複数キャラクターの同時操演を実現したマイクロキャビン技術の結晶ともいえる名場面だ。
成長システムと戦闘の深み
戦闘はコマンド選択式のオーソドックスなRPG形式だが、キャラクターの成長システムには独自性がある。通常の経験値によるレベルアップに加え、武器ごとのスキルレベルが設定され、使い込むほどに命中率や攻撃力が上昇する。さらに天人が術を覚える仕組みは“ダーサの像”という封印を解放することによって得られるという設定で、単なる数値上の成長に留まらず、ストーリー上の意味づけが施されている。
術を覚える過程は物語の進行と密接にリンクしており、天人が新たな力を手に入れるたび、彼の過去や真実に近づくことになる。こうした「成長=記憶の回復」という設計は、プレイヤーの心理的没入感を高める仕掛けとして極めて巧妙だ。
音楽と演出:マイクロキャビン・サウンドの真骨頂
音楽面でも『幻影都市』は特筆に値する。MSXturboR版ではMSX-MUSICを標準サポートし、MIDI音源にも対応。PC-9801やX68000版ではFM音源に加えAD-PCMのドラム音を採用し、FM TOWNS版では高音質なサウンド再生を実現している。荘厳でありながらも緊張感に満ちたBGMは、香港の喧騒や地下儀式の不気味さを際立たせ、プレイヤーを物語世界へと引き込んだ。
特に戦闘中の楽曲はテンポの変化やシンセの重層構成が絶妙で、当時のユーザーから“サウンドだけでも価値がある”と評されるほどであった。
発売当時の技術的挑戦と評価
『幻影都市』は、1990年代初頭というパソコンゲームがビジュアル表現を競っていた時代に登場した。一般的なADVが静止画とメッセージウィンドウ中心であったのに対し、本作はリアルタイム操作型のマップと演出を融合。ストーリー進行とキャラクター表現を一体化させる試みは、まさに先駆的だった。
また、マイクロキャビン特有の「哲学的テーマ」と「緻密な演出」は本作にも色濃く反映されており、ただのRPGという枠を超えて“体験する叙事詩”として語られている。当時の雑誌レビューでも、「ストーリー性と世界観の深さが群を抜いている」と評価され、後年のマイクロキャビン作品群の礎となった。
後年の移植と再評価
発売から十数年後の2009年、PC-9801版をベースにしたWindows向け配信(プロジェクトEGG)によって再び注目を浴びた。さらに2017年にはWindows10対応版も配信され、新たな世代のファンに“幻の名作”として再発見されている。
再配信版では一部バグの修正や動作最適化が行われており、当時の空気感を保ちながらも快適なプレイ環境で楽しむことができる。特に“香港の街の光と闇を体感できる物語”として、今なおファンから語り継がれているのは、この作品の完成度の高さを証明しているといえるだろう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
重厚な物語と世界観の融合が生む没入体験
『幻影都市』の最大の魅力は、サイバーパンク的な未来都市のビジュアルと、東洋神秘主義を内包した伝奇的ストーリーの融合にある。香港という現実の都市をモチーフにしながら、そこに霊的な儀式や転生、封印といった要素を織り交ぜることで、プレイヤーは現代文明の光と影の両面を体感できる。
新香港(ネオ・ホンコン)の上層と下層に広がる格差社会、権力構造、そして巨大企業SIVAによる支配。これらの設定は、単なる舞台背景ではなく、キャラクターの行動や思想に直接影響を与える“世界のルール”として機能している。そのため、プレイヤーは天人たちの旅を追う中で、自然とこの都市の理不尽さや虚構性を理解していく。
この“世界が生きている感覚”は、当時のゲームとしては異例の完成度であり、プレイヤーが自分自身の存在を重ねるような没入体験をもたらした。
操演システムによる生きた演出
『幻影都市』が革新的だった理由の一つは、マイクロキャビン独自の“操演システム”の採用にある。キャラクターを単なるドット絵ではなく、まるで俳優のように演技させるというこの技術は、1991年当時のRPG界では驚異的だった。
例えば、美紅が少女を抱きかかえるシーン、シャオメイが儀式で舞う場面、敵との心理的駆け引きを示す動作など、どれもがプレイヤーの記憶に焼き付くほど細やかに描写されている。セリフを読むだけでは伝わりにくい感情を、キャラクターの動作や間で表現する手法は、当時のアドベンチャーゲームの枠を超えていた。
また、この操演システムは“mealシステム”という高度なスクリプトエンジンと連携しており、複雑な条件分岐やタイミング制御が可能だった。結果として、プレイヤーの行動によって微妙に異なるリアクションや演出が見られるという、リプレイ性の高い作りが実現されている。
VRシステムが描く立体的な都市の風景
操演システムと並ぶもう一つの魅力が、「VRシステム(Visual Representation System)」による視覚表現である。従来の2DマップRPGでは平面的にしか描けなかった都市を、斜め見下ろし型の立体構成で描くことで、プレイヤーに圧倒的な臨場感を与えた。
特に、香港の街並みを模したネオ・ホンコンの雑踏や、地下寺院、人工地殻の内部などは、当時のグラフィック技術を最大限に引き出した表現だといえる。光と影のコントラストを巧みに使い分けることで、都市の生々しさと幻想性を両立。人々の喧騒、機械の音、霧の立ちこめる廃墟など、細部まで「空気感」が作り込まれている。
これにより、プレイヤーは単にマップを移動しているだけでなく、まるでその場に立っているかのような錯覚を覚える。多重スクロールや交差構造を用いた通路設計は、後のRPGやアクションゲームにも影響を与えた要素の一つだ。
キャラクター同士の濃密なドラマ
『幻影都市』の物語は、ただの冒険譚ではない。天人、美紅、カッシュ、ホウメイ、シャオメイといった主要キャラクターたちが、それぞれの信念と過去を抱えて行動しており、その人間模様がドラマとして深く描かれている。
特に印象的なのは、師弟関係や恋愛、そして裏切りと贖罪といったテーマが緻密に絡み合う点だ。天人と美紅の関係にはプラトニックな絆が描かれ、一方で敵対組織の中にも人間らしい葛藤が潜む。善悪の二元論では割り切れない登場人物たちの心理描写は、プレイヤーに強い共感と苦悩をもたらす。
また、一部のキャラクターが性的嗜好や精神的トラウマを抱えており、当時のゲームとしてはきわどい題材にも踏み込んでいる。そうした“人間の多面性”の描き方こそ、本作が後年に“異端の名作”と称される理由の一つである。
音楽とサウンドが作る物語の深み
マイクロキャビン作品の中でも、『幻影都市』の音楽演出は特に高く評価されている。シンセサイザーを駆使した近未来的な旋律と、東洋音階を取り入れた幽玄なフレーズが絶妙に組み合わされ、サウンド面でも物語世界を支えている。
戦闘時の緊迫感あるテーマ曲、静謐な寺院のBGM、そして儀式の場で流れる荘厳な旋律。どれもがストーリーと完璧にシンクロし、プレイヤーの感情を高揚させる。特にMSXturboR版やX68000版での音質は、当時の家庭用ハードを凌駕するほどの完成度を誇った。
音楽の演出は単なる装飾ではなく、プレイヤーの体験を導くナビゲーションとしても機能している。例えば、天人が封印を解くシーンで音が静寂に包まれ、次の瞬間に爆発的なサウンドが鳴り響く演出は、まさに“聴覚による物語”そのものだ。
思想とテーマ性:神話的構造と近未来の融合
『幻影都市』の魅力は、表面的なグラフィックや演出だけではない。その根底に流れるテーマは、東洋思想や宗教観、そして人間存在への哲学的問いにある。
「人は神に近づけるのか」「科学と信仰は両立するのか」「記憶とは魂の残滓なのか」。こうした問いが、天人の旅やダーサの封印と密接に結びついて描かれている。単なるRPGの枠を越え、“思考する物語”として成立している点は、今なお語り継がれる理由の一つだ。
特に、人工的に再生された都市の中で“魂の救済”を模索する構図は、現代社会への風刺としても読むことができる。この思想的深みこそが、『幻影都市』を単なるゲームではなく、文学的作品へと押し上げている。
後世への影響とファンの熱狂
『幻影都市』は当時のセールス面では決して大ヒットではなかったが、後年に至るまで熱狂的なファンを生み続けている。その理由は、マイクロキャビン作品特有の“語りかける物語構造”と“演出美学”がプレイヤーの記憶に深く刻まれているからだ。
特に同社の『Xak』シリーズや『フレイ』をプレイしたユーザーにとって、『幻影都市』はその延長線上にある“成熟したマイクロキャビン世界”として受け止められた。ゲーム雑誌でも「シナリオ性・音楽・演出の三位一体が生む深い没入感」として高い評価を得ており、近年のレトロゲーム再評価の流れでも必ず名が挙がる一本である。
■■■■ ゲームの攻略など
基本的なプレイの流れと心構え
『幻影都市』はコマンド選択型のオーソドックスなRPGでありながら、物語の構造と成長システムが密接に絡み合っている。プレイヤーは主人公・天人を中心にパーティーを組み、香港の上層区域と下層区域を行き来しながら事件の真相を追っていく。 序盤ではストーリーの導入が重視されており、戦闘よりも探索と会話イベントを通して世界の仕組みを理解していくことが求められる。特に下層区域の人々との交流は、後に重要なフラグを左右するため、会話を丁寧に進めておくことが重要だ。
また、他のRPGと異なり、無闇なレベル上げは推奨されない。なぜなら、キャラクターの能力が単なるレベルではなく、武器スキルや術の獲得状況に大きく依存しているからである。戦闘を重ねることで経験値だけでなく「戦闘感覚」を掴むことが、真の攻略の第一歩となる。
戦闘システムの理解とコツ
戦闘はターン制のコマンドバトル形式。攻撃・防御・術・アイテムなど、選択肢自体はシンプルだが、戦闘ごとに細やかな戦略が必要になる。特に敵によっては通常攻撃よりも術攻撃のほうが有効な場合も多く、相手の属性を見極めることが重要だ。
本作の戦闘には「詠唱」という概念が存在する。術を使用する際、天人が呪文を唱える演出が入るため、発動までに時間がかかる。敵の行動パターンを予測し、あえて一手先を読んで詠唱を始めるタイミングを計ることが上級者の戦い方となる。
また、武器スキルレベルが命中率に影響するため、使用する武器を偏らせずにバランス良く鍛えるのがコツ。スキルが上がりすぎると一部の敵に攻撃が当たらなくなるという特性があるため、あえて成長を抑える“温存プレイ”も有効だ。
術(スキル)獲得の進め方
天人の成長で最も重要なのが「ダーサの像」の封印解除である。これは単なるアイテムイベントではなく、物語上の節目として設定されており、特定のダンジョンを攻略することで新たな術を得ることができる。 各ダーサ像には属性があり、例えば「風」「火」「水」「土」「光」「闇」といった六系統に分かれる。解除の順番はプレイヤーの行動によって変化するが、風→火→水の順で進むのが最も安定するルートとされている。
封印を解くたびに天人の能力が上昇するだけでなく、過去の記憶が一部回復する演出が入る。この心理的報酬の演出がプレイヤーの動機付けとなり、「術の習得=物語の進展」として機能する。
また、ダーサ像の封印解除には特定のアイテムやキーイベントが必要になるため、サブイベントを軽視しないことが重要だ。
パーティー構成と役割分担
『幻影都市』では、天人を中心に最大4人までのパーティーを組む。各キャラクターには明確な得意分野があり、それを理解して編成することが戦略の鍵になる。
天人:バランス型の主人公。術・物理ともに扱える万能タイプだが、術の覚え方にイベント依存があるため、使いこなすには進行管理が必須。
美紅(メイホン):防御と回復に優れたサポート型。物語後半で再加入した際には装備の強化が施されており、終盤では防御の要となる。
カッシュ:攻撃特化型。武器スキルを優先的に鍛えると高火力を発揮するが、耐久力がやや低いため装備管理が重要。
老師(ホウメイ):強力な術を扱うことができるが、MP消費が激しい。ボス戦では彼の術をどのタイミングで使うかが勝敗を分ける。
この4人を状況に応じて組み合わせるのが理想だが、バランスを重視するなら天人・美紅・カッシュ・ホウメイの固定編成が安定する。
装備とアイテム管理
『幻影都市』では装備品が豊富に存在し、それぞれに固有の効果が設定されている。特に中盤以降は「餓鬼玉」などのペナルティアイテムが登場するため、取得時には注意が必要だ。 このアイテムを装備してしまうとHPが徐々に減少していくが、MSXturboR版ではHP表示が簡易データから削除されているため、気付きにくいという罠がある。こまめにステータスを確認し、不自然なダメージが続く場合は装備を見直そう。
また、強力な武器は敵からのドロップよりも、特定のイベントや隠しショップで入手できることが多い。探索エリアの端やNPCの裏ルートをくまなく調べることで、思わぬレアアイテムを発見できる。
ボス戦の攻略ポイント
ボス戦は本作の醍醐味でもあり、単なる火力勝負ではなく戦術性が求められる。特に序盤の「暴走兵器戦」、中盤の「魔天教儀式戦」、終盤の「ダーサ封印守護者戦」は、それぞれ異なる戦略を要求してくる。
暴走兵器戦:通常攻撃ではダメージが通りにくく、術攻撃が主力となる。火属性が弱点。
魔天教儀式戦:敵の術封じ攻撃が厄介。アイテムでMPを温存しつつ、物理攻撃で削る戦法が有効。
ダーサ守護者戦:長期戦になるため、回復役の美紅を常に行動可能状態に保つことが最重要。
また、詠唱のタイミングを利用して敵の行動を“誘う”戦略も効果的だ。詠唱開始時に敵が攻撃してくる特性を逆手に取り、囮行動として詠唱を使うと被害を抑えられる。
探索とフラグ管理の重要性
『幻影都市』のストーリー進行には多くの分岐があり、特定のイベントを逃すと後の展開が変化する。特に下層区域での人々との対話や、アイテム収集イベントは複数のルートに関わってくる。 このため、プレイヤーは会話内容を注意深く読み、マップ上の小さな変化に気づくことが大切である。マイクロキャビン特有の「会話後の場所変化」システムを活かし、同じ人物に再度話しかけることで新たな展開が開く場合も多い。
また、終盤の一部イベントではパーティーメンバーの生死や選択肢がエンディングに影響する。セーブデータを複数保存し、分岐を試しながら進めるのがおすすめだ。
隠し要素と裏技
本作には、いくつかの隠しイベントや裏技が存在する。例えば、特定の場所で「操演モード」を利用すると通常では見られないキャラクター動作が再生される“デバッグ演出”があるほか、特定の音楽コマンド入力で未使用BGMを聴くことも可能だった(PC-9801版限定)。
また、プロジェクトEGG版ではゲーム開始時に特定のキーを押すことで、開発者メッセージを見ることができる。これは当時のマイクロキャビン作品に共通する“遊び心”の象徴といえるだろう。
■■■■ 感想や評判
発売当時の反響:重厚な世界観が熱狂的支持を集めた
1991年末から1992年初頭にかけて、『幻影都市』はPCゲーム雑誌や専門誌において大きな注目を集めた。当時のプレイヤーたちは、まずその“世界観の異質さ”に衝撃を受けたという。未来都市ネオ・ホンコンというサイバーパンク的な舞台に、東洋の神話や霊的儀式が融合した独特の雰囲気は、既存のRPGとはまったく異なる体験をもたらした。
特にPC-9801やMSXturboRユーザーからは「これまでのマイクロキャビン作品を超えた」「まるで小説をプレイしているようだ」という絶賛の声が相次いだ。従来の“剣と魔法のファンタジー”とは違い、コンピュータと魂、科学と霊術といった現代的テーマを扱った点が、新鮮な衝撃として受け止められたのである。
ゲーム誌『マイコンBASICマガジン』では、「映像的表現と脚本構成の完成度が群を抜いている」と評され、『ログイン』誌でも「RPGでありながら演劇的な表現力を持つ作品」として特集が組まれた。
ファンの熱量と語り継がれる魅力
『幻影都市』をプレイしたファンの間では、「登場人物がまるで実在するかのようだ」という感想が多く見られた。これは、操演システムによる“生きた演技”と、mealシステムによる繊細な会話分岐がもたらした結果である。
特に印象的と語られるのが、終盤で明かされる天人の過去と、美紅との関係性にまつわるドラマだ。プレイヤーの中には「エンディングで涙が止まらなかった」「こんなに人間臭い登場人物を描いたRPGは他にない」と語る人も多く、物語性の高さが本作最大の魅力として長く支持されている。
ファンの間では、“幻影都市の街路にもう一度立ちたい”という声も多く、現代のゲームフォーラムやSNSでも、リメイクを望む声が絶えない。特にX68000やFM TOWNSの美しいサウンドとビジュアルを覚えている世代には、懐かしさと共に「これを超える作品は少ない」と評されることが多い。
シナリオとキャラクターへの賛辞
シナリオ面では、“誰が善で誰が悪かが単純に分からない”という曖昧さが絶妙だと評価されている。マイクロキャビンのシナリオライター・加藤雅史による脚本は、プレイヤーに“判断の余地”を与える構造を持っており、単なる勧善懲悪を超えた人間ドラマを描き出している。
登場人物の中でも特に人気が高いのは、主人公・天人と美紅のコンビ、そして謎めいた存在シャオメイだ。彼らは単なる物語の駒ではなく、それぞれの思想や過去を背負った“生きた存在”として描かれており、その心理的描写がリアルで共感を呼ぶ。
また、敵対組織の人物たちにも魅力がある。単純な悪役ではなく、理想と狂気の狭間で苦しむ姿が描かれており、「敵なのに感情移入してしまう」という声も多かった。この複雑な人間関係こそが『幻影都市』の物語を深める大きな要素となっている。
音楽と演出への高評価
音楽面でも当時のプレイヤーや評論家から高い評価を得た。マイクロキャビンの音楽チームが手がけたBGMは、FM音源とMIDIを巧みに組み合わせ、硬質なシンセベースと幻想的な旋律を融合させていた。
特に、オープニングテーマとラストシーンの曲は「ゲーム音楽というより映画のサウンドトラックのようだ」と評され、サウンドトラックCDの発売を望む声も多かった。また、MEGA-CD版ではCD-DA音源による迫力あるBGMが追加され、これもファンの間で話題となった。
視覚的にも、操演システムによる演出とVRシステムによる立体背景が絶賛された。当時のハード性能を超えた表現力に「まるでアニメを見ているようだ」と驚いたユーザーも多く、演出美が本作の象徴として語り継がれている。
批評家による再評価:時代を先取りした作品
2000年代以降、レトロゲーム文化の再評価が進む中で、『幻影都市』は“時代を先取りしすぎた作品”として改めて注目を浴びた。後年の評論では「90年代にこの世界観を実現していたこと自体が驚異」と評され、特にストーリーの構成力とテーマの深さが再評価されている。
現代の評論家は、『幻影都市』を“Blade Runner以後の日本RPG”と位置づけることもある。近未来の都市を舞台に、人間性・信仰・テクノロジーの境界を問う構造は、後の『ゼノギアス』や『NieR:Automata』などの哲学的RPGに通じる部分があるという見解も少なくない。
このように、本作は発売当時よりもむしろ現在のほうが評価が高まっている作品であり、学術的視点からも研究対象として挙げられることがある。
批判的意見:難易度とUIの課題
一方で、当時から指摘されていた課題も存在する。特にMSXturboR版では、HPやMPの簡易表示が削除されているため、ステータス管理がやや煩雑になっていた。戦闘中に数値確認ができず、突然倒れるケースもあるなど、プレイヤーの不満点として挙げられた部分だ。
また、フラグ管理が複雑で、特定の会話イベントを逃すと重要な展開が進行しないという点も難点とされた。セーブを複数作らないと詰み状態になることがあり、「高難度でありながら説明不足」という声も少なくなかった。
それでも、多くのプレイヤーが「多少の不便を上回る魅力がある」と述べており、UIの不親切ささえも当時のゲームデザインの一部として受け入れられている節がある。
後年のプレイヤーによる体験談
プロジェクトEGGでの再配信後、新世代のプレイヤーが『幻影都市』を体験し、SNSやレビューサイトで熱い感想を投稿している。 「30年前のゲームとは思えないストーリー構成」「現代でも通じるテーマ性」「この時代にここまでの演出をしていたのが信じられない」など、肯定的な意見が圧倒的多数を占めている。
また、当時のプレイヤーが“再プレイ組”としてもう一度挑戦し、「若い頃は理解できなかった台詞の意味が今なら分かる」といった感慨深い声もある。年月を経ても色褪せない作品という証明であり、それこそが『幻影都市』の最大の遺産と言えるだろう。
総評:心に残る“体験型伝奇RPG”
総じて、『幻影都市』はマイクロキャビンの代表作の中でも特に思想的・芸術的な完成度が高い作品として位置付けられている。 シナリオ・音楽・演出・テーマが見事に融合し、“プレイヤーに考えさせるRPG”というスタイルを確立した点で、単なる娯楽作品の域を超えている。
そのため、現在でもファンサイトや動画投稿サイトでは、本作の考察やストーリー分析が続けられている。
“ゲームでありながら文学”と評されるこの作品が、今も人々の心に残り続けているのは、時代を越えて語りかける普遍的なメッセージを持っているからだろう。
■ 良かったところ
1. 東洋神秘と近未来SFが融合した唯一無二の世界観
『幻影都市』の最大の魅力として、多くのプレイヤーが挙げるのが「世界観の独創性」である。202X年の新香港(ネオ・ホンコン)という舞台設定に、陰陽道や呪術、転生といった東洋的なモチーフを絡めることで、科学と信仰、現実と幻影の狭間を描く構造が非常に秀逸だった。
通常のRPGが中世ヨーロッパ風ファンタジーを主軸としていた時代にあって、このような“サイバーパンク×伝奇”というアプローチは極めて異端であり、まさに唯一無二の存在感を放っていた。
特に、人工地殻で構成された新都市と、その下に眠る旧香港の廃墟の対比は象徴的で、「地上の光」と「地下の闇」が現代社会の二面性を投影している。
この構造そのものが作品のテーマを体現しており、プレイヤーに「人間の存在とは何か」という哲学的問いを投げかけてくる。
背景グラフィックの描写も秀逸で、ネオン輝く都市景観の中に霊的儀式が描かれるという対比が非常に美しい。マイクロキャビンが得意とする幻想的な美学が存分に発揮されており、プレイヤーはプレイするたびに“異世界を旅している”ような感覚を味わうことができた。
2. 物語性の深さとキャラクター描写の緻密さ
物語の重厚さと、登場人物たちの心情描写も大きな評価ポイントである。 主人公・天人が失われた記憶を取り戻していく過程は、単なるRPGの進行イベントではなく、プレイヤー自身の“内なる探索”として体験できる構造になっている。 師であるホウメイとの関係、美紅との絆、そして敵対する者たちの信念が交錯する人間ドラマは、映画や小説に匹敵する完成度を誇っている。
また、善と悪の境界が曖昧に描かれている点も秀逸で、「敵」とされるキャラクターにもそれぞれの信念や事情があり、単なる悪役では終わらない。
たとえば、組織SIVAの構成員たちにも理想や悲哀があり、プレイヤーによっては彼らの思想に共感すら覚える場面もある。
この“立場によって正義が変わる”構図こそが、『幻影都市』の物語を普遍的なテーマへと昇華させている。
3. 操演システムによる感情豊かな演出
『幻影都市』の演出面を語る上で欠かせないのが、マイクロキャビン独自の「操演システム」である。 従来のRPGでは、会話テキストと一枚絵でイベントを表現するのが一般的だったが、本作ではキャラクターのドット絵そのものを“演技させる”ことで、動きと感情が融合した新たな表現を生み出した。
特に印象深いのは、美紅が少女を抱きしめるシーンや、終盤の儀式でシャオメイが舞うシーンである。どちらもアニメーションやCGではなく、ピクセル単位で構築された“操演”によって表現されており、プレイヤーの心に強く残る。
当時のプレイヤーはこの表現に驚嘆し、「まるで登場人物が生きているようだ」「動きに感情が宿っている」と絶賛した。
この技術的挑戦は後のゲーム演出にも影響を与え、特に“リアルタイムで感情を伝える表現”を追求する作品群(例えば『ヴェインドリーム』や『イシターの復活』など)に通じていく。
『幻影都市』の操演システムは、単なるギミックではなく、ストーリーをより深く感じさせる装置として機能していたのである。
4. サウンドと音楽の完成度
音楽面においても『幻影都市』は特筆すべき完成度を誇る。新田忠弘・福田康文・瓜田幸治らによるBGMは、単なる背景音ではなく“感情を導く音”として設計されていた。 サイバーパンク調の電子音と、伝奇的なフレーズが融合することで、プレイヤーの心理を巧みに操る。
特に印象的なのが、戦闘シーンの緊迫したリズムと、儀式シーンの荘厳な旋律の対比だ。静寂から始まり、少しずつ音が重なり、最終的に爆発するように展開していく構成は、プレイヤーの感情曲線と完全に一致している。
MSXturboR版ではMSX-MUSICとMIDI音源に対応しており、当時としては驚異的な音質でゲーム世界を演出。
X68000版ではFM音源とAD-PCMの融合によってさらに厚みを増し、特にドラム音の迫力は今も語り草となっている。
マイクロキャビン作品に共通する“聴かせる音楽”の哲学が本作でも貫かれており、音楽単体でも芸術的価値を持つと評されている。
5. ビジュアル表現とアートデザインの美しさ
イラストレーター橘田幸雄によるキャラクターデザインとコンセプトアートは、『幻影都市』のビジュアル的魅力を支える重要な要素だ。 写実的なデザインでありながら、どこか幻想的な光を宿す登場人物たちは、東洋的神秘と近未来の冷たさを両立させており、作品のテーマを象徴している。
また、VRシステムによって表現された背景は立体的で、当時のパソコンRPGの中でも群を抜いていた。
多重スクロールによる奥行きの演出、光源の表現、廃墟の陰影など、細部にまで作り込みが感じられる。
これらの要素が相まって、『幻影都市』は単なる“プレイするゲーム”ではなく“眺める体験”としても評価されている。
6. 思想的テーマと文学的深み
『幻影都市』が他のRPGと一線を画す最大の理由は、その思想性の高さにある。 「人間とは何か」「記憶とは魂の残滓なのか」「科学は神に成り得るのか」といった問いが物語全体に貫かれており、プレイヤーは自然と自己の存在について考えさせられる。
特に、天人が封印を解くたびに記憶を取り戻すという構成は、単なるレベルアップイベントではなく“精神的成長の象徴”として機能している。
この点において、『幻影都市』はゲームでありながら文学的体験でもあり、他に類を見ない哲学的RPGとして後世に語り継がれている。
また、宗教・倫理・人間の欲望といったテーマが複雑に絡み合い、善悪や救済の定義すら曖昧に描かれている点も深い。
この曖昧さこそが作品のリアリティを高めており、プレイヤーに“選択の重み”を感じさせる。
7. 技術面と完成度の高さ
最後に、当時の技術水準をはるかに超えた完成度も“良かった点”として多く挙げられる。 MSXturboR専用として設計されたプログラムは非常に安定しており、描画やロードの速さも快適そのものだった。 また、キーボード・ジョイパッド・マウス操作の全対応、音源拡張への柔軟な対応など、ユーザビリティの高さも評価された。
メガCD版ではビジュアルシーンの追加や音声演出の強化が行われ、PC-9801版ではレイアウトと操作系が最適化されている。
いずれのバージョンもハードの特性を最大限に生かした設計となっており、「プラットフォームの限界を引き上げたゲーム」と称されるほどだった。
■ 悪かったところ
1. 難解すぎるストーリー構成と説明不足
『幻影都市』は、その緻密な世界観と深い思想性が評価される一方で、プレイヤーによっては「難しすぎる」「意味がつかみにくい」と感じられる部分も少なくなかった。 ストーリーは複数の組織・宗教・科学技術が入り乱れる複雑な構造をしており、序盤では専門用語や固有名詞が立て続けに登場する。 ゲーム内で明確な用語解説や背景説明が少ないため、初見プレイヤーは「誰が何を目的として動いているのか」が分かりにくいまま物語が進行してしまうことが多かった。
特に、“ダーサの封印”“SIVA”“人工地殻”といった重要ワードが断片的に提示されるだけで、ゲーム終盤まで真相が明かされない構成は、没入感を高める反面、理解のハードルを上げていた。
当時のゲーム誌レビューでも「ストーリーのスケールに対してプレイヤーへの説明が追いついていない」「途中で置いてけぼりになる部分がある」といった指摘が見られた。
一方で、こうした“難解さ”が本作の文学的魅力を高めているという意見も多く、結果的に『幻影都市』はプレイヤー層を明確に二分する作品となった。
2. フラグ管理の複雑さと進行不能バグ
もう一つ多く挙げられた不満点が、イベントフラグの管理の難しさである。 『幻影都市』では、特定の会話イベントやアイテム入手が後の展開に直結しており、ひとつでも取り逃すとストーリーが進まなくなるケースがある。 特に序盤の下層区域では、NPCに複数回話しかけなければ進行フラグが立たない仕様になっており、初回プレイでは原因が分からず立ち往生するプレイヤーが続出した。
また、一部のバージョン(特にPC-9801初期版)では、データディスクの読み込みミスによってイベントがスキップされるバグが報告されていた。
これにより、重要なイベントが発生しないままシナリオが破綻することもあり、後に修正版ディスクが配布されたという経緯がある。
さらに、プロジェクトEGG版の初期リリース時には、ディスク7のデータが欠落しているという致命的な不具合も発生しており、当時のユーザーからは「せっかく復刻されたのに最後まで遊べない」と苦情が寄せられた。
後に修正版が再配信されたが、こうしたトラブルも「マイクロキャビン作品はシステムが難解すぎる」と言われる一因となった。
3. 一部UIの不親切さと操作の煩雑さ
本作は複数のプラットフォームで展開されたが、共通して指摘されたのがユーザーインターフェースの煩雑さである。 特にMSXturboR版では画面解像度の制限により、キャラクターのHPやMPなどのステータスが常時表示されず、戦闘中に残り体力を確認できないという不便さがあった。 この仕様が原因で、知らないうちにHPが尽きて戦闘不能に陥ることもあり、プレイヤーの緊張感を高める反面、理不尽さを感じさせる要因にもなった。
また、メニュー操作もやや複雑で、アイテムや装備変更を行うたびに複数の階層メニューを開閉する必要がある。
PC-9801版やFM TOWNS版ではマウス操作に対応していたが、キーボード主体の設計が残っていたため、テンポの悪さを感じるユーザーも多かった。
特に中盤以降、戦闘とイベントの切り替えが頻発する場面では「操作レスポンスの鈍さが緊張感を削ぐ」といった声も挙がっている。
このように、当時としては高機能だった反面、ユーザビリティという観点ではやや時代を先取りしすぎた設計だったと言える。
4. 難易度のバランスと戦闘テンポの問題
『幻影都市』はシナリオ面での完成度の高さに比べ、戦闘バランスには賛否が分かれる部分がある。 序盤は敵の攻撃力が低く比較的簡単に進めるが、中盤から急激に難易度が上昇し、特定のボス戦では一気に全滅するケースも珍しくなかった。
また、詠唱システムによる戦闘演出は魅力的ではあるものの、1回ごとの戦闘時間が長くなりがちで、長時間プレイではテンポが悪く感じられた。
この仕様は特に経験値稼ぎやスキル育成の場面で煩雑さを生み、「戦闘が単調で長い」との意見につながった。
敵の回避率や状態異常の発生確率も高く設定されており、運の要素に左右される部分が多いのも問題視された。
とくに「武器スキルを上げすぎると命中率が下がる」という隠し仕様は、多くのプレイヤーを困惑させた要素である。
この点は後年のリリース時に公式からも「意図したバランス」と説明されたが、明確なチュートリアルがないため不親切さは否めなかった。
5. テキストテンポと表現の古さ
本作はシナリオ重視型RPGであるがゆえに、会話テキスト量が非常に多く、一度のイベントで数百行に及ぶこともあった。 そのため、文章を読み進めるテンポがやや遅く、また当時の機種ではスクロール速度が一定で調整もできなかったため、「セリフ送りが遅い」「イベント中にテンポが悪くなる」と感じるプレイヤーもいた。
さらに、90年代初期の文体で書かれた台詞やナレーションは、現在の感覚ではやや硬質に感じられる部分がある。
宗教的・哲学的な用語が頻出するため、「文章を読む集中力が試される」「セリフの意味が難解」との声もあった。
一部キャラクターの独特な話し方や思想的独白も、当時の若年層プレイヤーには難しく映ったようだ。
ただし、こうした“重厚な言葉”が作品の雰囲気を作っていたことも事実であり、文章の硬さを“味わい”として評価する層も多い。
6. セーブ・ロード周りの不便さ
当時のマイクロキャビン作品に共通して見られた問題だが、『幻影都市』も例外ではなく、セーブやロードの仕様がやや煩雑だった。 セーブ可能なタイミングが限定されており、ダンジョン内では記録できない場面も多いため、ボス戦で全滅すると長いプレイ時間が無駄になることもあった。 加えて、MSXturboR版ではディスク交換の頻度が多く、セーブ時にディスクを何度も入れ替える手間が発生した。
PC-9801版やX68000版ではやや改善されたものの、依然としてオートセーブ機能は存在せず、プレイヤーの慎重な管理が求められた。
これにより、“死に覚えプレイ”の緊張感は生まれたが、一方でストレス要素にもなっていた。
7. バグと互換性の問題
移植版の中でも、FM TOWNSおよびMEGA-CD版では音声・映像の同期ずれが報告されていた。 また、CD-ROMによるロード時間が長く、特にイベントシーンの切り替え時に数秒間の無音状態が生じる点が指摘されている。 これは当時のハード性能の限界によるもので仕方ない部分もあるが、プレイヤーの没入感を削ぐ要因となっていた。
さらに、Windows版(プロジェクトEGG配信版)では、一部の環境下で音源が正常に再生されない不具合や、フォント表示が崩れる症状が確認されており、安定性の面では完璧とは言えなかった。
これらの問題は、後にパッチで改善されたが、初期ユーザーにとっては印象を損ねる要素の一つであった。
8. 現代基準では遊びにくいデザイン
総合的に見ると、『幻影都市』は当時の技術と思想を極限まで詰め込んだ結果、“作品としての完成度”と引き換えに“遊びやすさ”を犠牲にしている部分がある。 操作レスポンスの遅さ、難解なシナリオ進行、UIの不親切さ、セーブ制限などは、現代のプレイヤーにはやや敷居が高い。
しかし一方で、それらの“遊びにくさ”が本作の緊張感や雰囲気を支えており、レトロゲーム愛好家の間では「不便さが作品の一部」として肯定的に受け止められている。
つまり、『幻影都市』の欠点は同時に“時代の証明”でもあり、マイクロキャビンというメーカーの挑戦的姿勢を象徴する要素なのだ。
■ 好きなキャラクター
1. 天人(テンジン) ― 記憶と宿命を背負う孤高の主人公
『幻影都市』の物語を牽引する主人公・天人(テンジン)は、多くのプレイヤーから“寡黙な英雄”として強い支持を集めている。 彼の魅力は、単なる勇者像ではなく、自己の存在意義を探す「内省的な旅人」として描かれている点にある。 序盤では無口で感情を表に出さない人物として登場するが、物語を進めるごとに彼の過去や使命が明らかになり、失われた記憶を取り戻す過程そのものがプレイヤーの体験と重なっていく。
天人の行動原理は「正義」や「使命感」ではなく、“己の真実を知りたい”という欲求に基づいている。
そのため、彼はしばしば周囲の人々や組織の意図に翻弄されるが、最終的には自らの意志で選択を下す姿が描かれる。
この“能動的な覚醒”こそが、彼を単なる主人公ではなく「物語の象徴」へと昇華させている。
また、戦闘面でも万能型のキャラクターであり、物理攻撃・術攻撃の両方を使いこなせる。
しかしその力は、物語中盤まで制限されており、封印を解くたびに少しずつ開花していく。
この演出が彼の“成長=記憶の回復”というテーマを見事に体現しており、プレイヤーが天人と共に歩んでいるという一体感を強く感じさせる。
多くのファンは、ラストシーンでの天人の静かな決意を「ゲーム史に残る名ラスト」と称えており、彼の存在はまさに『幻影都市』の精神的支柱といえる。
2. 美紅(メイホン) ― 強さと優しさを併せ持つ人民警察官
もう一人、プレイヤーの心に深く刻まれているのが、美紅(メイホン)である。 彼女は人民警察の隊員として登場し、正義感と責任感に溢れるキャラクターだが、同時に人間的な弱さや迷いを抱えている。 天人とは異なり、彼女は現実社会の中で生きる女性としての葛藤を背負っており、そのリアルな人間描写が多くのプレイヤーから共感を呼んだ。
特に印象的なのは、彼女が序盤で謎の少女を保護するシーンである。
その瞬間に彼女の「守る」という本能的な優しさが表れ、後の展開で天人と行動を共にする理由にもつながっていく。
彼女は単なるサポートキャラではなく、物語の“良心”として機能しており、天人の冷静さと対照的に、情熱と感情で物語を動かす存在だ。
また、再加入イベントでの彼女の成長ぶりは多くのプレイヤーに感動を与えた。
失敗と後悔を経てなお前を向く彼女の姿は、人間の強さと儚さを象徴している。
「最も人間らしいキャラクター」「現実にいそうなヒロイン」と評されることが多く、ファン人気の高いキャラクターである。
3. シャオメイ ― 儚くも神秘的な存在
物語全体の象徴的存在として語られるのが、シャオメイだ。 彼女は物語の鍵を握る少女であり、彼女の存在が天人や美紅、そして敵対勢力の運命を大きく変えていく。 シャオメイは一見すると無垢で神秘的な存在だが、その内側には人間を超えた力と悲しみを秘めている。
彼女が儀式で舞うシーンは、本作の中でも屈指の名場面とされており、“操演システム”による繊細な動きと音楽の調和が、プレイヤーの心を震わせた。
ファンの中には「シャオメイの儀式シーンを見るために何度もプレイした」という人も少なくない。
また、彼女の発する言葉の多くは詩的で、どこか哲学的でもある。
「光は闇を映す鏡」「あなたの中の記憶が、私の世界を作る」――これらのセリフはプレイヤーに深い余韻を残し、彼女が単なる登場人物ではなく“概念そのもの”として存在していることを感じさせる。
シャオメイは、ゲーム内での登場時間こそ限られているが、その影響力は絶大であり、“幻影都市”というタイトルを象徴する存在でもある。
4. カッシュ ― 熱血と信念を貫く戦士
カッシュは、物語中盤から仲間になる武闘派の青年で、プレイヤーからは「頼れる兄貴分」「純粋な戦士」として愛されている。 彼の直情的な性格と、どこか不器用な優しさが物語に人間味を与えている。
特に印象的なのは、彼が自らの信念を貫くために危険を承知で敵地に潜入するシーンだ。
その行動は無謀とも言えるが、天人や美紅のために戦う姿勢は非常に熱く、多くのプレイヤーが彼に共感を寄せた。
彼の武器スキルを鍛え上げることで、戦闘面でも圧倒的な強さを発揮し、“カッシュ頼み”の戦略を取るプレイヤーも多かった。
一方で、彼の不器用さや感情的な面もまた魅力の一部であり、プレイヤーの間では「最も人間臭い仲間」として人気が高い。
カッシュの存在があることで、重厚な物語の中に“人間的な熱”が生まれている。
5. ホウメイ(老師) ― 智慧と慈悲を併せ持つ導師
ホウメイは物語序盤から登場する年長の僧侶であり、天人の師として精神的支柱となる人物だ。 彼は世界の理と人の心を知る賢者として描かれており、その言葉には常に深い哲学が含まれている。 戦闘では強力な術を使いこなす頼もしい存在だが、同時に彼自身も過去に大きな罪と後悔を抱えている。
物語中盤、ホウメイが語る「人は己の影に怯え、やがてそれを神と呼ぶ」というセリフは、本作のテーマを端的に表すものとして多くのファンの記憶に残っている。
彼は単なる“導く者”ではなく、自らも苦悩する一人の人間として描かれ、老僧でありながら非常に人間味のあるキャラクターである。
ファンの間では「ホウメイがいなければ物語は成立しない」と評されるほど重要な存在であり、終盤の彼の決断はプレイヤーに強烈な印象を残す。
6. その他の魅力的な登場人物たち
『幻影都市』には上記以外にも数多くの印象的なキャラクターが登場する。 たとえば、情報屋のリーはコミカルな立ち位置でありながら、時に鋭い洞察で主人公を導く存在として人気がある。 また、敵対組織の幹部・南天は、カリスマ性と冷徹さを併せ持ち、彼女の過去を知ることで単なる悪役ではない深みが生まれる。
さらに、天人の過去を知る謎の人物や、儀式に関わる巫女たちなど、脇役たちにも明確な個性と背景が与えられており、それぞれが物語にリアリティを与えている。
この群像劇的な人物配置が『幻影都市』の奥行きを生み出しており、プレイヤーは誰か一人に強く感情移入するのではなく、全員の運命を見届けるような体験を味わえる。
7. プレイヤーが語る“心に残るキャラクター”
後年のファンアンケートやレビューでは、「天人」「美紅」「シャオメイ」の三人が特に人気上位を占めている。 天人は“内面の成長を象徴する主人公”、美紅は“人間的な強さと優しさの象徴”、そしてシャオメイは“存在そのものが物語”として、多くの人の記憶に刻まれている。
しかしそれだけでなく、ホウメイの哲学的言葉やカッシュの熱い行動に心を動かされたという声も多く、
「登場人物全員が何かを抱えているからこそ、全員が主役に見える」との意見も多い。
このように、『幻影都市』は単なるRPGではなく、“人の心を描く群像劇”として記憶されており、
登場人物の一人ひとりが、プレイヤーにとっての“好きなキャラクター”になり得る稀有な作品である。
●対応パソコンによる違いなど
1. MSXturboR版 ― オリジナルとして生まれた完成形
『幻影都市』の原点にあたるのが、1991年に発売されたMSXturboR版である。 このバージョンはシリーズの“基礎”でありながら、MSXハードの可能性を極限まで引き出した技術的挑戦として評価が高い。
まず特筆すべきは、マイクロキャビンが独自に開発した「操演システム」と「mealシステム」が最初に完全実装されたことである。
MSXturboRのCPU速度(Z80互換+R800モード)を活かし、当時としては驚異的な滑らかさでキャラクターが動作する。
また、MSX-MUSICとMIDI音源に両対応しており、音の厚みと奥行きが他機種よりも優れていた。
BGMのドラムパートの重低音や、儀式シーンの金属音の響きなど、MSX独特のFM音源サウンドが物語のサイバーパンク的雰囲気を完璧に支えている。
ただし、画面解像度はSCREEN5(256×212ドット)が基本であり、一部イベントのみSCREEN7(512×212ドット)を使用。
そのため、PC-9801版やX68000版と比べると表示情報量が少なく、キャラクター簡易データ(HP・MP表示など)が画面上から削除されている。
この点はプレイヤーにとって大きな違いであり、戦闘中にHPの残量が分かりづらいという不便さを感じる場面もあった。
一方で、ゲームテンポ自体は非常に軽快で、ロード時間も短く、操作レスポンスの良さはシリーズ随一。
「オリジナルにして最も快適なバージョン」と評される所以である。
また、戦闘時の術詠唱アニメーションは本作で初導入され、後のMEGA-CD版にも継承された。
詠唱中の天人の動作やエフェクトが他機種よりも長く演出され、プレイヤーの没入感を高めている。
MSXturboRユーザーの間では、今なお“幻影都市=MSXの到達点”と呼ばれるほどの完成度を誇る。
2. PC-9801版 ― 安定した高解像度と完成されたバランス
PC-9801版は、MSXturboR版の翌年に発売された移植版であり、最も多くのプレイヤーが体験したスタンダードなバージョンである。 画面解像度が640×400ドットに引き上げられ、グラフィックの情報量が格段に向上。 キャラクターの簡易データ表示が復活し、戦闘中にもHP・MPが確認できるようになったため、操作性と視認性が大幅に改善された。
また、内蔵FM音源に加え、外部MIDI音源にも対応しており、当時のRoland SC-55やMT-32を使用することで劇的に音質が向上した。
特にオープニングテーマや戦闘BGMの厚みは、MSX版からの進化を実感できる。
操作面では、キーボード・ジョイパッド・マウスのいずれにも対応。
メニュー操作も改良されており、テンポ良く進行できるようになっている。
イベントシーンのレイアウトも再設計され、画面左側にキャラクターステータス、右側にメッセージウィンドウを配置するという視認性の高い構成が採用された。
このUIデザインは後のFM TOWNS版・MEGA-CD版にも踏襲されることになる。
シナリオ内容自体はMSXturboR版と同一だが、細かい台詞の修正や演出テンポの最適化が施されている。
当時のレビューでも「バランスが最も良い」「完成度が高い決定版」と評されており、後にWindows版やEGG配信版のベースにもなった。
3. X68000版 ― 音と映像の“芸術的完成”
X68000版は、PC-9801版をベースに移植されたが、音と映像の品質が格段に高いことで知られている。 X68000の高性能FM音源とAD-PCMドラムが組み合わされ、BGM全体の迫力が一段と増している。 特にボス戦BGMの低音とリバーブの深さは、他機種版では味わえない重厚感がある。
グラフィック面でも、768×512ドットの高解像度表示により、背景やキャラクターの輪郭が滑らかに描かれている。
影や光源処理も繊細で、香港の街並みや廃墟の表現において「映画的」と評された。
一方で、移植に伴い処理が重くなる場面もあり、機種によっては戦闘エフェクト時に微細なフレーム落ちが発生することもあった。
X68000版の特徴として、“サウンド重視のプレイヤー”に強く支持された点が挙げられる。
当時、オーディオマニアの間では「ヘッドホンで聴く幻影都市」という楽しみ方が広まり、音響体験を通して作品世界を堪能する文化も生まれた。
音楽面においては、まさに決定版と言える仕上がりだ。
4. FM TOWNS版 ― 映像表現の強化と快適なロード環境
FM TOWNS版は、ブラザー工業が展開した自動販売システム「ソフトベンダーTAKERU」を通じて販売された特別な移植版である。 PC-9801版をベースにしながら、TOWNS特有のCD-ROM高速アクセスを活かし、ロード時間が大幅に短縮された。 さらに、パッケージ版とTAKERU版で微妙に仕様が異なり、パッケージ版ではサウンド出力がより高音質に調整されている。
内容面ではほぼPC-9801版と同一だが、TOWNS特有のガンマ補正と24bitカラー処理によって、グラフィックの色彩がより鮮やかになっている。
また、一部の演出シーンに微細なアニメーション効果が追加されており、視覚的な没入感が強化された。
当時のユーザーからは「最も快適に遊べる幻影都市」と評価されており、ロードの短さ・安定性・音質のバランスに優れる完成度の高い移植だった。
FM TOWNS独自のドライブ音と演出の静寂が織りなす“映画的リズム”を味わえたというプレイヤーの声も多い。
5. MEGA-CD版 ― コンシューマ向けアレンジとビジュアル強化
家庭用ハードとして移植されたMEGA-CD版は、MSXturboR版をベースにしつつも、完全なリメイクに近い構成を取っている。 まず、オープニングの誘拐シーンやカーチェイスなど、パソコン版では静止画のみだった部分がアニメーション演出に置き換えられている。 CD-DA音源による高音質BGMとボイス演出が追加され、家庭用機ユーザーにも訴求する作品に仕上がっていた。
ただし、メガCDのメモリ制限の関係で一部のVR多重スクロールがカットされ、背景の奥行き表現が簡略化されている。
また、戦闘テンポが若干遅く、ロードタイムも長めであることから、操作性に関してはPC版より劣るという意見もあった。
それでも、当時のプレイヤーは「家庭用機でここまで表現できるとは」と驚き、
特にボス戦で流れるCD音源BGMの迫力には多くのファンが感動した。
また、一部のキャラクターグラフィックが描き直されており、顔の表情や衣装の細部がより鮮明になっている。
6. Windows版(プロジェクトEGG) ― 現代への架け橋
2009年にPC-9801版をベースとしてWindows XP/Vista/7向けに配信されたのが「プロジェクトEGG版」である。 さらに2017年にはWindows10対応版がリリースされ、現在も入手可能な最も手軽な“幻影都市”として多くの新規ファンを生んだ。
内容はPC-9801版とほぼ同一だが、一部バグの修正や動作安定化が図られている。
初期配信時にはデータ欠落問題(DISK7未収録)があったが、後に修正版が公開されて解決された。
現代の解像度に合わせたウィンドウモードやキー設定変更など、プレイ環境は向上しているものの、音源エミュレーションの違いから当時の音質とは若干異なる印象を受ける。
それでも、「レトロPCを持っていなくても遊べる幻影都市」として再評価され、
レビューサイトやSNSでは「懐かしさと新鮮さが同居する」と評されている。
現行環境で最もアクセスしやすいバージョンとして、シリーズの入口的存在になっている。
7. 総括 ― それぞれの機種に宿る“幻影都市の顔”
総じて見ると、『幻影都市』はどのプラットフォームにも独自の個性がある。 MSXturboR版は技術的挑戦と軽快な操作性、PC-9801版は完成度と安定感、X68000版は音響美と映像美、FM TOWNS版は快適性、MEGA-CD版は演出強化、そしてWindows版は現代への架け橋――。
どのバージョンにも一長一短があり、ファンの間では「どれが決定版か」を語り合うのが恒例となっている。
だが、いずれの機種であっても共通しているのは、“操演システムによる生きた物語体験”と“哲学的テーマの深さ”だ。
その核が揺らぐことはなく、どの環境で遊んでも“幻影都市”が持つ荘厳な魅力は変わらない。
プレイヤーたちはこう語る――
「ハードが違っても、感じる空気は同じだった」と。
それこそが、『幻影都市』という作品の普遍的な力を物語っている。
●同時期に発売されたゲームなど
1. ★『サークIII』
(マイクロキャビン/1991年/9,800円) マイクロキャビンの代表作『サーク』シリーズの3作目であり、『幻影都市』と同時期に発売されたアクションRPG。 『サークIII』は『幻影都市』と世界観を共有する姉妹的存在であり、開発チームや音楽スタッフも多くが共通している。 特に音楽担当の新田忠弘と福田康文によるBGMは高い評価を得ており、当時のPCユーザーの間では“音楽のマイクロキャビン”という呼び名を確立した。
ゲームシステムはサイドビューアクション形式で、主人公が剣を振るいながら進む軽快な操作性を実現。
『幻影都市』が哲学的で重厚なサイバーパンク作品であるのに対し、『サークIII』はよりファンタジー寄りの王道冒険譚となっている。
両作品の違いを味わうことで、当時のマイクロキャビンが持つ「多彩な世界観表現の幅」を体感できる。
2. ★『ヴァリスIII』
(日本テレネット/1990年/9,800円) 『幻影都市』と近い時期に人気を集めていたのが、日本テレネットの『ヴァリスIII』である。 女子高生・優子が異世界の戦士として戦うというストーリーは当時のPCゲーム界で大きな話題を呼び、華やかなビジュアルとアニメーション演出が特徴的だった。 この作品も『幻影都市』と同じく、アニメ的演出と哲学的テーマを融合させた“ドラマ性重視のアクションRPG”として知られる。
『幻影都市』が香港の退廃都市を舞台に人間の業や記憶を描いたのに対し、『ヴァリスIII』は神話的世界での善悪の対立を軸にしている。
共通しているのは、“女性の強さ”と“宿命の選択”をテーマにしている点であり、当時のプレイヤーに「RPGにおける物語性の深化」を実感させた名作だ。
3. ★『ソーサリアン追加シナリオVol.5 神々の遺産』
(日本ファルコム/1991年/6,800円) 日本ファルコムによる人気RPG『ソーサリアン』の追加シナリオで、1991年にリリース。 この年、RPGファンの間では“重厚な世界観を持つシナリオRPG”が流行しており、『幻影都市』もその潮流の中に登場した。
『神々の遺産』では宗教・神話・文明崩壊といったテーマが描かれ、物語的にも『幻影都市』と共鳴する部分が多い。
同時代におけるRPGの成熟がいかに進んでいたかを示す好例であり、マイクロキャビンとファルコムが互いに刺激し合う関係にあったことが分かる。
4. ★『イースIII ワンダラーズ フロム イース』
(日本ファルコム/1989年/9,800円) 『幻影都市』より少し前に発売された作品だが、90年代初頭のPCゲームシーンを語る上で欠かせない存在。 シリーズ初の横スクロールアクションとして登場し、軽快な操作性と感動的なBGMでRPGファンの心を掴んだ。
特に『幻影都市』の音楽的演出や演出テンポは、この『イースIII』からの影響を受けているとも言われている。
“音で感情を操るRPG”という表現方法を確立したのはファルコムだが、マイクロキャビンはそれを“物語演出”としてさらに深めた。
その流れが『幻影都市』の操演システムに結実したといえる。
5. ★『レリクス 暗黒要塞』
(ボーステック/1991年/8,800円) 『幻影都市』と同年に発売されたボーステックのSFアドベンチャーRPG。 この作品は、“肉体を持たない意識体が他者に憑依する”という独特のシステムで注目を浴びた。 退廃的な未来世界を舞台にした点も共通しており、当時は『幻影都市』と並び「サイバーパンクRPGの双璧」と評されていた。
システム的には探索要素が強く、ストーリーよりも世界観や仕掛けを重視した構成。
対して『幻影都市』はストーリー主導型であり、同じサイバーパンク系でも“物語を読むRPG”として棲み分けがされていた。
両者を比較することで、1991年前後のPCゲームがどれほど多様な方向性を持っていたかがよく分かる。
6. ★『ナイトメア』
(マイクロキャビン/1990年/7,800円) マイクロキャビンが『幻影都市』の前年にリリースしたサイコ・ホラーアドベンチャー。 本作の開発で培われた心理描写と演出技術が、『幻影都市』の“操演システム”の原型になったとされる。
プレイヤーの行動によって登場人物の精神状態が変化する仕組みや、夢と現実が交錯する演出など、後の『幻影都市』に直結する表現が数多く見られる。
ある意味で『幻影都市』は、この『ナイトメア』で試みた「精神世界の物語表現」をさらに拡張した作品ともいえる。
7. ★『アークスII』
(ウルフチーム/1991年/8,800円) ウルフチームによるファンタジーRPGの第2作で、独自の3Dマップとアニメーション戦闘が話題を呼んだ。 当時のレビューでは「マイクロキャビンの幻影都市と並ぶ、映像演出型RPG」と紹介されており、 ビジュアルとドラマ性の融合を目指した点で共通する方向性を持っている。
『幻影都市』が現実的で硬質な世界を描いたのに対し、『アークスII』は幻想的で美しいファンタジー世界を舞台としていた。
どちらも“視覚表現の限界を超えようとしたRPG”であり、1991年という年が「PCゲーム演出革命期」であったことを象徴している。
8. ★『ガイアの紋章』
(TGL/1991年/8,800円) 戦略RPGとして登場した本作は、AI戦術と地形効果を重視した硬派な作品。 『幻影都市』がドラマ性で勝負したのに対し、『ガイアの紋章』はシステム性で評価された。
興味深いのは、両作品とも“人間とは何か”というテーマを根底に持っている点。
『ガイアの紋章』ではクローン兵の存在を通して倫理問題を問うており、
『幻影都市』の人工地殻と人造神のモチーフと重なる部分がある。
1991年前後のゲーム業界は、単なる娯楽から“哲学を語るメディア”へと変化しつつあった。
9. ★『夢幻戦士ヴァリスII』
(日本テレネット/1989年/8,800円) シリーズ中で特に人気の高い作品で、アニメ的演出の完成度が高かった。 『幻影都市』と比較すると、演出面ではアニメーション主体であり、操演システムによる動作演出とは対照的。 ただし、どちらの作品も“女性キャラクターの内面的成長”を描いており、 当時のPCゲーム界において「女性を主人公に据えるRPG」という新潮流を確立する役割を果たした。
10. ★『ザナドゥ・ネクスト』
(日本ファルコム/1990年/8,800円) ファルコムの代表作『ザナドゥ』の流れを汲む作品で、 『幻影都市』が登場する直前、PCゲームファンの注目を集めたタイトル。 探索・育成・哲学的な物語構成など、RPGの基礎要素を高い完成度で備えており、 『幻影都市』が“精神性と演出”で差別化を図るきっかけにもなった。
11. 総括 ― 1991年前後は“思想系RPG”の黄金期
これらの作品群を見ても分かる通り、1990~1992年は日本のPCゲームにおいて「思想・世界観の時代」とも言える。 単なる冒険や戦闘ではなく、プレイヤーに“考えさせる”RPGが次々と登場した。 『幻影都市』はその中心にあり、“サイバーパンク×超伝奇×哲学”という独自路線で確固たる地位を築いた。
同時代の他作品が王道ファンタジーを描く中で、『幻影都市』は“人間の記憶・意識・存在”という抽象的テーマに挑んだ点で特異な存在だった。
その意味で、この時期は日本RPG史における「思想的実験期」として記憶されるべき時代であり、
『幻影都市』はまさにその象徴的作品の一つといえる。
![【中古】[MD] 幻影都市 ILLUSION CITY(イリュージョン・シティ)(メガCD) マイクロキャビン (19930528)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1001/7/cg10017316.jpg?_ex=128x128)