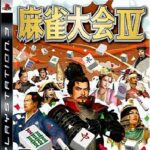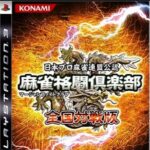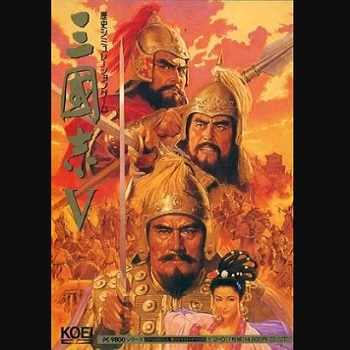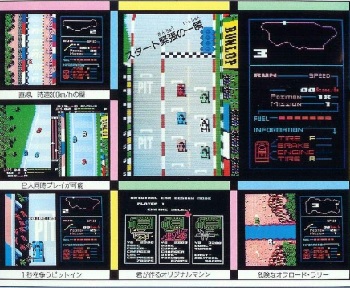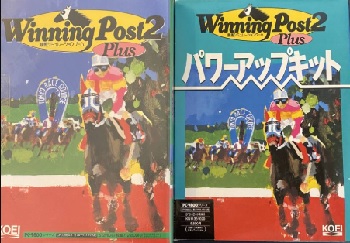【中古】PS3 機動戦士ガンダム Target in Sight PS3 the Best
【発売】:バンダイナムコゲームス
【開発】:ベック
【発売日】:2006年11月11日
【ジャンル】:アクションシューティングゲーム
■ 概要
『機動戦士ガンダム Target in Sight』は、2006年11月11日にバンダイナムコゲームスから発売されたプレイステーション3用のアクションシューティングゲームです。本作は、長く続いてきたガンダムゲームの歴史の中でも特に“挑戦的”な作品として位置付けられており、そのコンセプトや表現方法、さらにはゲームシステムに至るまで、従来のガンダム作品とは大きく一線を画す独自性を持っていました。
まず押さえておきたいのは、本作が「PS3ローンチタイトルのひとつ」であったという点です。2006年11月、ソニーが送り出した次世代ゲーム機プレイステーション3は、その高性能なグラフィック処理能力やブルーレイディスクを媒体とする大容量を武器に、家庭用ゲーム機の新時代を切り拓こうとしていました。その記念すべき船出を支えるタイトルのひとつとして『Target in Sight』が登場したこと自体が、非常に大きな注目を集める要因となりました。
リアルタイム描画へのこだわり
本作が当時のゲームファンを驚かせたのは、「全編がリアルタイム描画で構成されている」という点でした。従来の多くのゲームでは、プレイヤーの没入感を高めるためにプリレンダムービー(事前に作り込まれた映像)を挟み込み、迫力あるシーンを演出することが主流でした。しかし『Target in Sight』ではあえてそれを排し、ゲーム中に表示される映像のすべてをゲームエンジンによって描画するという試みがなされました。
これにより、ムービーシーンとプレイシーンの間に境界がなくなり、シームレスに物語と戦闘が繋がっていくという体験が可能になったのです。当時の技術的挑戦としては非常に大きく、2005年のE3で初めて発表された映像は、ガンダムファンだけでなくゲーム業界全体に強烈なインパクトを与えました。
舞台設定 ― 一年戦争の最終局面
本作の舞台は「一年戦争」の終盤、つまり開戦から1年が経過し、戦況が最終決戦へと向かう激動の3か月間です。プレイヤーは地球連邦軍またはジオン公国軍の兵士となり、それぞれの立場から戦場を駆け抜けます。
一年戦争はガンダムシリーズの原点であり、多くの外伝やスピンオフ作品が描かれる人気の時代背景です。その中でも“終盤”に焦点を当てることで、両陣営の消耗戦や戦局の緊迫感がより強調されており、プレイヤーに「敗北すれば命がない」という緊張感を与える構造になっています。
部隊編成とリソース管理
『Target in Sight』の大きな特徴のひとつが「部隊編成」システムです。プレイヤーは単なるモビルスーツのパイロットではなく、部隊を率いる指揮官としての役割も担います。戦闘で得たポイントを消費してモビルスーツを新たに入手したり、パイロットを補充したりすることで、少しずつ自分の部隊を強化していくことができます。
この仕組みによって、本作は単純なアクションゲームではなく、戦略シミュレーション的な側面をも備えた作品となりました。弾薬や補給といった要素も絡むため、無駄な消耗を避け、長期的な戦力運用を考えなければなりません。
機体ラインナップの豊富さ
収録されているモビルスーツの種類も、ファンの注目を集めました。主役機であるガンダムや量産機ジム、ジオンの名機ザクやゲルググといった定番はもちろんのこと、ジオン水泳部と呼ばれる水陸両用機(ゴッグ、ズゴック、アッガイなど)や、ゲームオリジナルでしか馴染みのないマイナー機体「ジム・ストライカー」や「ドム・キャノン」までも登場。さらにはタンク系のように従来のゲームでは冷遇されがちだった機体までもが丁寧に収録されています。
これにより「どの機体を使って戦うか」「自分だけの部隊をどんな編成にするか」という楽しみが広がり、ガンダムファンにとっては“図鑑的な満足感”をも味わえる作品となっていました。
シビアなゲームバランス
戦闘面のゲームバランスは極めてシビアであり、プレイヤー機といえども集中砲火を浴びれば一瞬で撃墜されてしまいます。これは「無双する爽快感」よりも「戦場でのリアルな恐怖感」を重視した調整であり、結果として「緊張感が半端ではない」との評価を受けました。
実際、味方との連携や部隊運用が必須であり、ひとりで敵部隊に突撃するような行為はすぐに死に繋がります。このリアリズムこそが『Target in Sight』最大の特徴であり、他のガンダムゲームでは味わえない体験となっていました。
PS3初期タイトルとしての位置づけ
発売当時、本作はグラフィックの美しさや新しい挑戦的システムで注目される一方、粗さや不便さも指摘されました。ロード時間の長さ、操作感の重さ、テンポの悪さといった欠点は確かに存在していました。しかし同時に「次世代機の可能性を示す意欲作」として、多くのプレイヤーに強烈な印象を残したのも事実です。
『Target in Sight』は、ガンダムゲームの歴史において決して万人向けではない作品ですが、その尖った方向性とリアルな戦場表現によって、今なお“異色の挑戦作”として語り継がれています。
■■■■ ゲームの魅力とは?
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の最大の魅力は、従来のガンダムゲームにはない“戦場のリアルさ”と“兵士としての緊張感”を、プレイヤー自身の手で体験できることにあります。アニメのような華麗な演出や派手な活躍よりも、あくまで「戦争の一兵士」として戦場に投げ込まれる臨場感を重視している点こそが、この作品を特別なものにしているのです。
1. 重厚なモビルスーツの挙動
まず特筆すべきは、モビルスーツの動きがとにかく“重い”ことです。これは決して操作性が悪いという意味ではなく、重量数十トンの鉄の塊を動かしているかのような実感を与える挙動になっている、ということです。足を踏み出せば地響きが響き、旋回ひとつにも惰性が働く。この感覚は、従来のゲームのような“人型ロボットを軽快に操作する”というものとは明らかに一線を画しています。
この重量感によって、プレイヤーは「自分はいま巨大兵器を操っている」という感覚をリアルに味わうことができるのです。操作に慣れるまで時間はかかるものの、その分没入感は極めて高いと言えるでしょう。
2. 部隊戦の緊張感
次に挙げられるのが「部隊戦のリアルさ」です。本作では一機で敵部隊を蹴散らすような無双プレイはできません。むしろ、味方との連携を怠ればすぐに集中砲火を浴びて撃墜されてしまいます。
仲間の位置を把握し、時には囮になり、時には援護射撃を行う――まさに「戦場の兵士」としての立ち回りが求められます。これにより、他のガンダムゲームでは味わえない「戦場でのリアルな恐怖感」と「勝利したときの達成感」が生まれるのです。
3. カスタマイズの自由度
ガンダムゲームの多くは、アニメの再現や特定キャラの活躍を追体験する形が主流でした。しかし『Target in Sight』では、プレイヤー自身が部隊の指揮官となり、モビルスーツの改造や塗装、武装の変更まで自由に行える仕組みが用意されています。
機体の性能を強化するだけでなく、カラーリングを自分好みに変えられる点もファンにとって大きな魅力でした。「自分だけの部隊を作り上げる」という遊び方ができるため、ガンダム世界における“ifの歴史”を体感できるような感覚があります。
4. マニアックな機体収録
本作がコアなファンを惹きつけた理由のひとつに、「マニアックな機体ラインナップ」があります。ジム・ストライカーやドム・キャノンといった知る人ぞ知る機体が登場するだけでなく、アッガイやゴッグといった水陸両用モビルスーツも丁寧に収録されており、“水泳部”ファンを歓喜させました。
さらにタンクタイプのような従来のゲームでは冷遇されがちな機体までしっかり登場することで、「兵器としてのガンダム世界」を強調する構成になっています。
5. リアルタイム描画100%の映像体験
『Target in Sight』は、ムービーシーンを一切使用せず、すべてをリアルタイムで描画するという試みに挑戦しました。これによって、プレイヤーはゲーム中にシーンが切り替わる瞬間でさえ「戦場にいる」という感覚を途切れさせることなく楽しむことができました。
爆発による煙、弾痕による装甲の傷、泥や砂で汚れていく機体――こうした描写がプレイ中にリアルタイムで反映されるため、まさに「ガンダムの戦場にいる」という臨場感を味わえるのです。
6. 戦略性の高いゲームデザイン
単純に操作技術だけではなく、部隊運用の戦略性が要求される点も大きな魅力です。例えば「どのミッションにどの機体を投入するか」「弾薬をどう配分するか」「敵をどこで迎え撃つか」といった選択が、戦局に大きく影響します。
こうした要素が組み合わさることで、プレイヤーは常に思考を巡らせながら戦わなければならず、勝利したときの達成感も非常に大きなものとなります。
7. 周回プレイによる楽しみ
本作では、クリア後にデータを引き継いで2周目以降をプレイすることができます。ここでは、原作アニメや外伝に登場するキャラクター(名前のみですが)が補充要員として登場することもあり、ファンにとってはたまらない要素でした。
「次の周回ではどんな部隊を作ろうか」「このキャラクターをどう活かそうか」と考える楽しみが生まれ、何度もプレイしたくなるリプレイ性を生んでいます。
8. 尖った方向性そのものが魅力
最後に、『Target in Sight』の魅力は「尖った挑戦作である」ということ自体にあります。万人向けの遊びやすさよりも、「リアルな戦場」「重厚な挙動」「シビアな難易度」といった要素に徹底的にこだわった姿勢は、ある意味で“硬派なゲーマー”や“熱心なガンダムファン”に向けられた挑戦状のようでした。
確かに不便さや粗さも多いですが、それ以上に「ここまで本物の戦争を意識したガンダムゲームは他にない」という独自の魅力が、本作を特別な存在にしています。
■■■■ ゲームの攻略など
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の攻略において最も重要なのは、「本作は単なるアクションゲームではなく、戦略とリソース管理を重視したシミュレーション性の強いタイトルである」という認識を持つことです。従来のガンダムゲームのように“主人公機で無双する”という発想では、すぐに敵の集中砲火に沈められてしまいます。本作の戦場は非常にシビアで、味方部隊の動きや戦況全体を見据えた立ち回りが攻略のカギを握ります。
1. 操作と挙動に慣れることが第一歩
攻略の前提として押さえておきたいのは、モビルスーツの操作感です。重量感を重視しているため、移動や旋回、ジャンプやブースト移動の挙動は、他のロボットアクションゲームに比べるとかなりもっさりとしています。最初は「動かしにくい」と感じるかもしれませんが、この重さを前提に立ち回ることが重要です。
例えば、敵に接近する際は一気に突っ込むのではなく、遮蔽物を利用しつつ徐々に距離を詰める必要があります。旋回速度が遅いため、敵に背後を取られると致命的になるので、常に正面を向けるような動きを意識しましょう。
2. 部隊運用と仲間との連携
本作の戦闘は、プレイヤー機一機の腕前だけでは勝利できません。部隊全体の運用が大きなカギを握ります。仲間を囮に使い、自分は側面から攻撃を仕掛ける、あるいは味方を援護して敵の足を止めるなど、常に連携を意識した立ち回りが必要です。
特に重要なのが「敵を各個撃破する戦術」です。敵部隊に真正面から突っ込むと数的優位であっという間に壊滅させられるため、敵をおびき寄せて分断し、一体ずつ確実に倒していくことが求められます。
3. ミッションごとの適正機体を選ぶ
攻略の面白さのひとつは「機体選び」にあります。本作には地上戦、都市戦、水中戦といった様々なシチュエーションが登場するため、それぞれのマップに最適なモビルスーツを選ぶことが重要です。
例えば、水辺や海中を含むマップではジオン軍の水陸両用モビルスーツ(ゴッグ、ズゴック、アッガイなど)が圧倒的な強みを発揮します。一方で、陸戦では動きが鈍重になり、敵に狙われやすくなるため不利に働きます。逆に都市部では小回りの利くジム系統が役立ち、広大な地形では長射程の砲撃型MSが有利に立ち回れます。
この「地形や敵編成に合わせて最適なMSを選ぶ」ことが、攻略の大前提となるのです。
4. カスタマイズと補給の重要性
戦闘で得られるポイントを消費して、モビルスーツを強化・改造していくことも大切です。装甲を厚くする、火力を強化する、機動性を改善するといったカスタマイズはもちろん、武器の選択も大きな影響を及ぼします。
また、補給要素を軽視してはいけません。本作では弾薬やエネルギーが有限であり、無駄撃ちをするとすぐに弾切れを起こしてしまいます。特に序盤は弾薬が限られているため、狙いを定めて確実に命中させる「節約プレイ」が攻略の基本となります。
弾薬を温存する工夫として、敵を近距離戦に持ち込み、格闘攻撃で倒す戦術も有効です。ただし格闘は隙が大きいため、必ず味方の援護や敵の硬直を突いたタイミングで仕掛けるようにしましょう。
5. 周回プレイでの強化
初回プレイでは限られた機体やパイロットしか利用できませんが、周回プレイを行うことでより多くのMSや人材を獲得できます。特に、原作や外伝に登場した有名キャラクターの名前が補充兵として登場することがあり、これが大きなモチベーションとなります。
周回を重ねてポイントを稼ぎ、部隊を強化していくことで、初回では苦戦したミッションも余裕を持って突破できるようになります。攻略法を研究するだけでなく、部隊を育て上げること自体がひとつの楽しみであり、やり込み要素となっているのです。
6. 敵AIの特徴を把握する
本作の敵AIは、従来のガンダムゲームよりもずっと賢く、油断するとすぐに包囲してきます。敵は単に攻撃を繰り返すだけではなく、位置取りや集中砲火を仕掛けるなどの動きを見せるため、プレイヤーは常に状況を把握して行動する必要があります。
攻略のコツは「敵の動きを観察すること」。突撃型の敵なら迎撃態勢を整え、砲撃型なら遮蔽物を利用して接近するなど、相手の行動パターンを知れば格段に戦いやすくなります。
7. 難易度とリトライ精神
『Target in Sight』の難易度は総じて高めです。油断すればすぐに撃墜され、部隊ごと全滅してしまうことも珍しくありません。しかし、こうした厳しいバランスは「再挑戦のモチベーション」を高める効果もあります。
一度の失敗で戦術を見直し、「次は遮蔽物をもっと意識しよう」「別の機体で挑もう」と試行錯誤を繰り返すことで、少しずつ突破口が見えてきます。攻略において重要なのは、失敗を恐れずにリトライする姿勢です。
8. 裏技的な立ち回り
本作には意図的に仕込まれた裏技やチートは存在しませんが、プレイヤー間で研究された「攻略テクニック」に近い立ち回りはいくつか知られています。
例えば、敵のAIは正面からの攻撃に強い反応を示すため、味方を前進させて敵の注意を引きつけ、その隙に側面や背後から攻撃を仕掛けると効率的に撃破できます。また、地形の段差や遮蔽物を活用し、敵の射線を切りながら狙撃することで、安全に戦果を挙げることも可能です。
こうした“戦場でのズル賢さ”を駆使することが、結果として部隊を生き延びさせるための重要なスキルとなります。
まとめ
攻略において大切なのは「兵士としてのリアリズムを受け入れること」です。本作は爽快感や簡単な勝利ではなく、「緊張感のある戦場」「失敗を繰り返して学ぶ体験」を重視した作品です。
敵の動きを観察し、地形を利用し、仲間と連携し、最適なMSを選ぶ――その積み重ねがようやく勝利に繋がります。攻略の道は険しいですが、その分突破したときの達成感は格別であり、この「試行錯誤と成長の実感」こそが、本作の最大の醍醐味なのです。
■■■■ 感想や評判
『機動戦士ガンダム Target in Sight』が2006年に発売された当時、ファンやメディアの間では賛否が大きく分かれました。プレイステーション3のローンチタイトルとして注目を集めただけに、その評価はとても幅広く、称賛と批判が入り混じった複雑な反応を生んだのです。ここでは発売当初の感想や、後年の再評価も交えながら、本作の評判を整理してみましょう。
1. 発売当時の第一印象 ― グラフィックの衝撃
発売直後、多くのプレイヤーが口にしたのは「とにかくグラフィックがすごい」というものでした。PS3の性能を見せつけるかのように描かれるモビルスーツの質感、爆発や煙の表現、機体に残る弾痕や泥汚れ――これらは従来のガンダムゲームにはなかった“リアルな戦場描写”でした。
特に、プリレンダムービーを一切使わず、全てリアルタイム描画で構築されている点は大きな驚きをもたらしました。ゲーム中に表示される映像がそのままプレイに直結するため、没入感が損なわれることなく「ずっと戦場にいる感覚」を味わえたのです。この映像面の革新性については、ほとんどのプレイヤーや雑誌レビューで高い評価を受けました。
2. 操作性とゲームバランスに対する厳しい声
一方で、多くの批判が集まったのは「操作性」と「ゲームバランス」でした。モビルスーツの動きは重量感を強く意識したものでしたが、その結果「もっさりしていて動かしにくい」と感じる人が少なくなかったのです。
また、敵の攻撃は非常に苛烈で、油断すると数秒で撃墜されることも珍しくありません。これまでのガンダムゲームで培われた「主人公機で敵をバッタバッタとなぎ倒す」というプレイスタイルは通用せず、プレイヤーにとっては戸惑いやストレスにつながりました。「リアルさは評価するが、ゲームとしては遊びにくい」という意見が頻出したのも、この独特なゲームバランスのためでした。
3. メディアのレビュー
ゲーム雑誌や専門メディアの評価も二分されました。
ポジティブな評価では、「戦場におけるモビルスーツの存在感をこれほどまでにリアルに描いた作品は初めてだ」「兵器としてのガンダムを体感できる」といった声がありました。
ネガティブな評価では、「操作が重く、戦闘がテンポ良く進まない」「同じようなミッションが多く、単調さを感じる」「PS3のローンチを代表するには未完成感が強い」といった指摘が目立ちました。
つまり、映像面の革新性は絶賛されながらも、ゲームとしての完成度には疑問符がつけられた、というのが当時の一般的な評価だったのです。
4. ファンの感想 ― 二極化する反応
ガンダムファンの間でも反応は大きく分かれました。
肯定的な感想
「これこそ本当のガンダムゲームだ。無双ではなく戦争を体験している」
「水陸両用機やマイナー機体までしっかり収録していて嬉しい」
「部隊運用やカスタマイズが楽しく、遊ぶほどに味が出る」
否定的な感想
「難しすぎて爽快感がない」
「ストーリー性やキャラのドラマが乏しく、感情移入できない」
「PS3のローンチでこれを選んだのはちょっと外した感がある」
特に“カジュアルなプレイヤー”と“硬派なゲーマー”の評価が大きく分かれたのが特徴的でした。前者には厳しすぎるゲームバランスが不評で、後者には「挑戦的で骨太なタイトル」と好意的に受け止められたのです。
5. 後年の再評価
発売から年月が経つと、本作は“異色の挑戦作”として再評価されるようになりました。ガンダムゲームの多くがキャラクターや物語を重視した演出寄りの作品である中、『Target in Sight』は「戦争のリアリズム」に真っ向から挑んだ希少なタイトルです。
「当時は遊びにくく感じたが、今振り返るとこういう硬派な作品も必要だった」「未完成感はあるが、コンセプト自体はガンダムの本質に迫っていた」といった意見が、インターネット上のレビューや個人ブログで散見されます。
特にYouTubeや配信文化が広がったことで、本作をプレイ動画で振り返る人も増え、「グラフィックは今でも意外と見劣りしない」「兵器としてのMS表現は唯一無二」といったポジティブな評価が再び注目されるようになりました。
6. 海外での評価
海外でも『Target in Sight』は発売され、「Mobile Suit Gundam: Crossfire」というタイトルで展開されました。こちらも評価は芳しくなく、特に欧米のゲームレビューサイトでは「操作が重く、不親切」「ストーリー演出が乏しく、盛り上がりに欠ける」といった辛口の批評が並びました。
ただし、海外では日本以上に“リアルな戦場シミュレーション”を好む層が一定数存在し、「アニメ的な誇張を廃した硬派なガンダム」としてコアな支持を集めたケースもありました。
7. ユーザーの思い出として
当時PS3本体と同時に購入したユーザーにとって、『Target in Sight』は“次世代機最初のガンダム体験”として強烈に記憶に残っています。中には「本体と一緒に買ったけれど難しくて途中で挫折した」「初めてのPS3ゲームだから愛着はある」といった思い出話を語る人も少なくありません。
ゲームとしての完成度には課題が多かったものの、“PS3と共に歩んだガンダムタイトル”という象徴的な立場から、今でも独自の存在感を放っています。
まとめ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の感想や評判を総括すると、
グラフィックとリアルタイム描画の革新性は大絶賛
操作性の重さやバランスの厳しさには批判多数
カジュアル層には不評、硬派ゲーマーや一部ファンには好評
年月を経て「異色作」として再評価される流れもある
という四点に集約されます。まさに“賛否両論”の代表的なタイトルであり、この二極化こそが本作を特別な存在にしていると言えるでしょう。
■■■■ 良かったところ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』は発売当初から賛否両論を巻き起こした作品でしたが、その中で「良かった」と高く評価された部分も数多く存在します。ここでは、ファンやプレイヤーが本作に魅力を見出したポイントを、映像表現・ゲームシステム・収録機体・プレイ体験などの観点から整理していきます。
1. 圧倒的なグラフィック表現
真っ先に挙げられるのは、当時としては群を抜いていたグラフィック表現です。PS3初期のタイトルでありながら、戦場に立つモビルスーツの質感や、砲撃時に舞い上がる土煙、爆発によって散る破片の描写などは、多くのプレイヤーに「次世代機の凄さ」を実感させました。
特に注目されたのは、機体が戦闘中に受けるダメージ表現です。被弾すれば装甲に傷が残り、時には煙を吹き出す。戦闘が長引けば泥や砂で外装が汚れていき、戦場にいるというリアリティを強く実感させてくれました。従来の「常に綺麗なMS」が戦っている従来のガンダムゲームとは一線を画す表現であり、プレイヤーを魅了しました。
2. リアルタイム描画100%の没入感
本作はプリレンダムービーを一切使用せず、全編をリアルタイム描画で構築しました。この仕様により、プレイヤーはカットシーンとプレイの間に区切りを感じることなく、常に戦場に没入し続けられます。
ムービーからゲーム画面に切り替わる際の“違和感”がなく、映像体験とゲーム体験が完全に一体化している感覚は、多くのユーザーから「本当に戦場にいるようだ」と高評価を受けました。この点は今でもガンダムゲーム史の中で特筆すべき挑戦だったと言えるでしょう。
3. 重量感あるモビルスーツの挙動
「良かった」と語られることが多いのが、モビルスーツの重量感です。操作性は重く、人間のように軽快には動けません。しかしその“重さ”こそがリアリズムを演出し、プレイヤーに「巨大兵器を操縦している」という感覚を与えてくれました。
例えば、ジムが走ればズシンズシンと大地を踏み鳴らし、ザクが旋回すれば機体がわずかに揺れながら回る。この挙動の一つひとつに「兵器としての説得力」が込められており、ロボットアニメ的な爽快さではなく、戦場シミュレーションとしての手触りを楽しむことができました。
4. 部隊編成とカスタマイズの楽しさ
ポイントを消費してモビルスーツを改造したり、新たなパイロットを補充したりできる部隊編成システムは、長く遊ぶほどに面白さが増す要素でした。
特に評価されたのは、単なる強化にとどまらず「自分好みの部隊を作れる」という点です。カラーリングの変更でオリジナル部隊を作ることができ、ジムばかりの量産部隊を運用したり、逆に水陸両用機で水辺戦を支配したりと、プレイヤーの個性が強く反映されるのです。
「俺の部隊」を編成する感覚は、コレクションと戦略性を同時に味わえる醍醐味として高く評価されました。
5. 豊富でマニアックな機体ラインナップ
『Target in Sight』に収録されたモビルスーツの種類は、従来の作品に比べて非常に幅広いものでした。ガンダムやゲルググといった定番に加えて、アッガイやズゴックといった水陸両用MS、さらにはジム・ストライカーやドム・キャノンといったマニアックな機体まで登場しました。
特にファンを驚かせたのは、従来のゲームでは冷遇されがちだったタンクタイプのモビルスーツまでも収録されていたことです。「どの機体にも出番がある」という姿勢は、ガンダム世界を兵器群として扱う本作ならではの魅力でした。
6. 周回プレイでのファンサービス
クリア後の周回プレイで、原作や外伝に登場するキャラクターの名前が補充兵として登場する要素も好評でした。ボイスや立ち絵はなくとも、「このキャラが自分の部隊にいる」というだけでファン心をくすぐるものがありました。
これによって周回プレイのモチベーションが高まり、「次は誰が仲間に加わるのか」という期待感を抱きながら繰り返し遊べる点は、ファンにとって大きな魅力だったのです。
7. 戦場の臨場感と緊張感
多くのプレイヤーが口を揃えて良かったと語るのは、「戦場の空気感」でした。砲撃が飛び交い、煙が立ちこめ、味方や敵が入り乱れて戦う戦場は、それまでのガンダムゲーム以上にリアルで恐ろしいものでした。
この緊張感は「常に死と隣り合わせである」という兵士の感覚を強烈に再現しており、ただのアニメの追体験ではない“戦争体験”を可能にしました。リアリティを追求した結果こそが、この臨場感の源泉となっていたのです。
8. コンセプト自体の新鮮さ
最後に、多くのプレイヤーが本作を評価した理由は「コンセプトそのものが新鮮だった」ことです。ガンダムゲームといえば、アニメの名場面を再現したり、主人公機で無双するような爽快な戦いを楽しむものが主流でした。
しかし『Target in Sight』は、それとは真逆の方向を突き進みました。「兵士として戦場に立つ」「一機では勝てない」「味方と連携して生き残る」――こうした体験は、それまでのガンダムゲームには存在しませんでした。
この“異色の挑戦”自体がファンにとって新鮮であり、たとえ粗削りであっても「こういう硬派な試みがあってもいい」と高く評価されたのです。
まとめ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の「良かったところ」をまとめると、
グラフィックの美麗さとダメージ表現
リアルタイム描画による没入感
重厚な挙動によるMSの存在感
部隊編成やカスタマイズの自由度
マニアックな機体収録
周回プレイでのファンサービス
戦場の緊張感
コンセプトの新鮮さ
といった点が挙げられます。完成度に課題はあったものの、プレイヤーに「ガンダムの戦争をリアルに体験する」という強烈な印象を与えたことは間違いなく、本作が後年に“異色作”として語られる理由もここにあります。
■■■■ 悪かったところ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』は、挑戦的で意欲的な作品であった一方で、多くのプレイヤーから「惜しい」「遊びにくい」と指摘される点も目立ちました。本作が当時「賛否両論」と評された背景には、この“悪かったところ”が少なからず影響しています。以下では、操作性・ゲームデザイン・演出・技術的問題など、具体的に批判が集まった要素を詳しく掘り下げていきます。
1. 操作性の重さと不親切さ
最も多くのプレイヤーから指摘されたのが「操作の重さ」です。
本作はモビルスーツの重量感を表現することを最重要視していたため、移動や旋回が非常にもっさりとしており、思い通りに機体を動かすのが難しくなっています。確かにリアリティは感じられるものの、「遊びやすさ」という観点では大きなマイナスでした。
さらに、チュートリアルが十分に整備されていなかった点も問題視されました。操作体系は従来のガンダムゲームとは大きく異なり複雑であるにもかかわらず、プレイヤーにわかりやすく学ばせる仕組みが弱かったのです。その結果、序盤で戸惑い、ストレスを感じたままプレイをやめてしまう人も少なくありませんでした。
2. 難易度の高さと理不尽さ
リアルな戦場を再現するために、敵の攻撃は容赦がなく、味方と連携しなければすぐに撃墜されるようなバランスになっています。これは硬派なゲーマーからは「やりごたえがある」と評価される一方で、多くのカジュアルプレイヤーには「理不尽」「難しすぎる」と受け止められました。
敵AIは数的優位を活かして集中攻撃を仕掛けてくるため、単独での行動はほぼ不可能です。しかし、味方AIの挙動は決して賢いとは言えず、プレイヤーがいくら工夫しても仲間が足を引っ張る場面も目立ちました。結果として「敵は強いのに味方は頼りない」という不満が募りやすい構造になっていたのです。
3. ミッションの単調さ
もう一つの弱点は、ミッション内容の単調さです。
本作のミッションは「敵部隊を殲滅せよ」「拠点を防衛せよ」といったシンプルなものが多く、シナリオ的なバリエーションに乏しいという批判がありました。戦闘そのものが重厚であるため、ミッションの目的や展開が単調だと飽きが早く訪れてしまいます。
また、演出面で盛り上げる仕組みが少なかったことも単調さを助長しました。例えば、アニメ的なドラマ演出や派手なイベントシーンがほとんどなく、戦闘そのものの緊張感はあっても「物語的な盛り上がり」に欠けていたのです。
4. キャラクター描写の希薄さ
ガンダムシリーズの大きな魅力のひとつは、個性豊かなキャラクターたちの人間ドラマです。しかし『Target in Sight』は兵士の視点を重視した結果、キャラクター性の描写が非常に薄くなっていました。
周回プレイで原作キャラや外伝キャラの名前が補充兵として登場する仕掛けはありましたが、ボイスやグラフィックはなく、単なる「名前のデータ」に留まっていました。そのため「このキャラがいるから頑張ろう」と感情移入するような体験は弱く、「キャラゲーとしての魅力が不足している」との声が多く上がりました。
5. ロード時間と処理落ち
技術的な部分でも問題はありました。当時のPS3はまだ開発環境がこなれておらず、本作でも「ロードが長い」「フレームレートが安定しない」といった不満が目立ちました。
戦闘が始まるまでの待ち時間が長いと没入感が削がれてしまい、処理落ちが発生するとリアルさを重視したゲーム性が逆にストレス要因となってしまいます。映像のリアルさを追求したがゆえに、ハード性能とのバランスが取り切れなかった点は、本作の弱点のひとつでした。
6. 演出不足と淡白なシナリオ
ストーリー演出における盛り上がりの乏しさも指摘されています。従来のガンダムゲームでは、名場面の再現や派手な演出が用意されていることが多かったのに対し、本作は「リアル戦場」を優先したため、ドラマ的な展開がほとんどありませんでした。
「兵士として戦うリアリズム」という方向性は評価できるものの、ドラマティックな要素を期待していたファンにとっては物足りず、「盛り上がりに欠ける」「遊んでいて感情が揺さぶられない」という不満につながりました。
7. カジュアル層を切り捨てた設計
本作が硬派なゲーム性を志向した結果、ガンダムゲームを“キャラクターゲー”として楽しんでいた層や、ライトユーザーにとっては敷居が高すぎるものとなってしまいました。
「難しいことは覚悟していたが、ここまで不親切とは思わなかった」「ガンダムの世界に入り込む前に挫折してしまった」という声が散見され、結果的に多くのプレイヤーが早々に離脱してしまったのです。これにより市場的にも大きな成功には至らず、“実験作”としての評価にとどまったとも言えるでしょう。
8. 発売時期の不運
最後に、本作が発売された時期的な不運も無視できません。PS3ローンチタイトルという期待値の高さが、逆にプレイヤーの厳しい目を招いたのです。「次世代機最初のガンダム」として大きな期待を背負ったにもかかわらず、粗削りさや不便さが目立ったため、失望感が余計に強調されてしまいました。
もしもう少し後の時期に、技術的な調整を経て発売されていれば、評価は異なっていたかもしれません。
まとめ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の「悪かったところ」を整理すると、
操作性が重く不親切
敵が強すぎて理不尽に感じやすい
ミッションが単調で演出も淡白
キャラクター性が薄く感情移入しにくい
ロード時間や処理落ちが没入感を妨げた
カジュアル層には敷居が高すぎた
PS3ローンチタイトルとして期待を裏切った
といった点に集約されます。
これらの課題は、作品全体の評価を分ける大きな要因となりました。つまり「リアルさを追求した結果、遊びやすさを犠牲にした」ことが、本作の最大の欠点であったと言えるでしょう。
■ 好きなキャラクター
『機動戦士ガンダム Target in Sight』は、従来のガンダムゲームと比べて「キャラクター性の演出」がかなり薄い作品です。物語を大きく盛り上げるカットインやボイス付きのドラマシーンが存在せず、基本的には無名の兵士たちが戦場に投入されるだけという仕様になっています。
そのため「特定のキャラを推す楽しみ」は他のシリーズほど明確ではありません。
しかし一方で、本作ならではの「キャラクターへの愛着」が生まれる瞬間があるのも事実です。ここでは、プレイヤーたちが語る“好きなキャラクター”の存在や、その理由について整理していきます。
1. 無名の兵士に芽生える愛着
本作では、パイロットの多くが名前だけの存在として登場します。フェイスグラフィックやボイスはなく、データ上のステータスと名前だけで構成されているため、他のゲームのように「このキャラが活躍したから好き!」という分かりやすい感情移入は起こりにくいのです。
しかし、何度も戦場を共にすると、不思議と「この兵士には生き残ってほしい」と感じるようになります。例えば、序盤からずっと出撃させているパイロットが戦闘で奇跡的に生き延びるたびに、「この兵士は頼れる相棒だ」と思えてくる。逆に、戦闘で撃墜され補充兵に置き換わってしまったときには、大きな喪失感を味わう。
つまり、無名の兵士であっても「戦場を共に過ごす時間」が積み重なることで、プレイヤーごとに“お気に入りの部下”が自然に生まれていくのです。この体験こそが、『Target in Sight』独自のキャラクター愛の形だと言えるでしょう。
2. 周回プレイで仲間になる原作キャラ
本作には、クリア後の周回プレイにおいて、原作や外伝に登場したキャラクターの名前が補充兵として登場する仕掛けがあります。
たとえば「ガンダム」や「機動戦士ガンダム外伝」シリーズに登場した兵士の名前が出てきたとき、ファンは思わずニヤリとします。ボイスや顔グラフィックはないものの、「この名前はあのキャラクターだ!」とわかるだけで、プレイヤーの想像力は膨らみます。
こうしたファンサービス要素により、特定のキャラクターを“自分の部隊の仲間”として迎え入れる喜びがありました。ガンダムファンにとっては「自分の部隊にあのキャラがいる」というだけで十分にモチベーションとなり、そのキャラを大切に戦わせようという気持ちが芽生えたのです。
3. ジオン軍兵士の存在感
地球連邦軍とジオン公国軍の両方でプレイできる点も、本作のキャラ体験に多様性をもたらしました。とくにジオン軍の兵士たちは、独特の雰囲気を持っており、ファンの間では「ジオン兵として生き抜く」プレイに特別な魅力を感じる人も多くいました。
ジオン側でプレイすることで、アニメでは敵役として描かれる兵士たちに感情移入でき、「無名のジオン兵こそがガンダム世界のもう一つの主役だ」と感じたプレイヤーも少なくありません。彼らを自分の部隊の中で育て上げる過程で、「好きなキャラクター」が自然に生まれていくのです。
4. 愛着が深まる瞬間のエピソード
プレイヤーの口コミや体験談を見ると、次のような“好きになった瞬間”が多く語られています。
序盤から出撃していたパイロットが奇跡的に何度も生還し、「この兵士は不死身か?」と感じて愛着が湧いた。
補充兵として加入した“原作キャラの名前”を見つけたとき、思わず声をあげて喜び、大事に使い続けた。
苦しい戦闘を共に乗り越えた兵士を「エース」として扱うようになり、他の兵士よりも優先的に強化してしまった。
こうした体験は、従来のキャラゲーの「決まった人気キャラを愛する」とは異なり、“自分だけの好きなキャラ”を見つけるという体験でした。
5. 「キャラゲーではないキャラゲー」としての魅力
多くのプレイヤーが指摘しているのは、本作が「キャラゲーらしくないキャラゲー」である点です。確かにビジュアルやボイスを伴ったドラマティックなキャラクター描写はありません。しかし、だからこそプレイヤーが自分の頭の中で物語を作り上げ、無名の兵士に感情を投影する余地が生まれました。
結果として、「この兵士は俺の相棒だ」「このキャラは絶対に生き残らせたい」という個人的な愛着が芽生え、プレイヤーごとに異なる“好きなキャラ”が存在する作品になったのです。
まとめ
『機動戦士ガンダム Target in Sight』の「好きなキャラクター」というテーマは、一見すると矛盾しています。なぜなら本作には、一般的な意味での「目立つキャラ」や「人気キャラ」が存在しないからです。
しかし実際には、
無名兵士に対する自然な愛着
周回プレイで仲間になる原作キャラの名前によるファンサービス
ジオン兵士としての視点から感じる魅力
プレイヤーごとの「自分だけのエース」を育てる体験
といった要素が重なり、他のガンダムゲームにはない「キャラ愛の形」が生まれました。
この“自分だけの好きなキャラクターができる”という点こそが、本作がユニークなキャラ体験を提供した証だと言えるでしょう。
■ 中古市場での現状
『機動戦士ガンダム Target in Sight』は、2006年11月11日に発売されてから十数年以上が経過しています。発売当時はプレイステーション3のローンチタイトルとして大きな注目を集めましたが、現在では“実験的で異色なガンダムゲーム”としてファンの間で語り継がれる存在となっています。
そのため中古市場においても、他の人気ガンダム作品とは異なるユニークな取引傾向を示しています。ここではヤフオク!、メルカリ、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、駿河屋といった代表的な流通経路ごとに現状を整理しながら、その価格帯や需要の変遷を詳しく見ていきます。
1. ヤフオク!での取引傾向
ヤフオク!では現在も一定数の出品があり、価格帯はおおむね 1,000円~2,000円前後 に落ち着いています。
ケースや説明書が欠品しているものは1,000円前後で出品されることが多く、入札数も伸びにくい傾向にあります。
一方、状態が良いものや動作確認済みと明記されたものは1,800円~2,000円ほどで落札される例が目立ちます。
ヤフオク!はオークション形式であるため、終了間際に入札が集中して価格が上がることもありますが、総じて取引は安定しており「希少価値が高騰する」という段階には至っていません。むしろ“コレクター向けに安定供給されているタイトル”という印象です。
2. メルカリでの販売状況
フリマアプリ「メルカリ」では、出品数が比較的多く、価格帯は 1,200円~2,000円程度 が主流です。
「ケース・説明書あり」「ディスクに目立つ傷なし」「動作確認済み」といった条件の商品は、1,500円~1,800円で短期間に売れる傾向があります。
一方、ケースに傷があるものやディスクに細かいスレがあるものは、値下げ交渉を経て1,200円前後で売買されるケースが多いです。
また、メルカリの特性上「送料無料」「即購入可」と記載されている出品は売れ行きが良く、送料込み2,000円以下であれば数日のうちに売れてしまうことが珍しくありません。
全体として“気軽に買いやすい中古ソフト”として扱われており、プレイヤー層はコレクターというより「昔遊べなかったから試してみたい」「安いから興味本位で買う」といったライト層が中心となっています。
3. Amazonマーケットプレイスの価格帯
Amazonマーケットプレイスでは、他の流通ルートよりもやや高めに価格設定される傾向があります。
中古品は 2,000円~3,000円前後 が中心で、特にAmazon倉庫から発送される「プライム対応品」は信頼性が高いため、多少割高でも購入されやすいです。
コンディションが「非常に良い」と明記されているものや、外装が美品のものは3,000円を超えることもあります。
Amazonは「確実に入手したい」「安心して購入したい」という需要に支えられており、出品数が安定しているため入手困難になることは少ないです。ただし、ヤフオク!やメルカリに比べると割高であるため、価格にこだわらない層が主な購入者層になっています。
4. 楽天市場での取り扱い
楽天市場では、ゲームショップや中古専門店が出品しており、販売価格は 2,000円~3,500円程度 で推移しています。
楽天ではポイント還元や送料無料キャンペーンがあるため、実質的にはAmazonと似た水準になります。特にコレクター向けに「動作保証あり」「外装に大きなダメージなし」といった記載をした商品が多く、安心感を重視した出品が目立ちます。
また、楽天市場では複数の中古ガンダムゲームとセット販売されるケースもあり、「Target in Sight」単体では安くても、他のソフトと組み合わせてコレクション用に買われる傾向があります。
5. 駿河屋での販売状況
中古ゲーム販売で有名な駿河屋では、『Target in Sight』は常時在庫が確認できるソフトのひとつです。
価格帯は 1,500円~2,200円前後 で安定しており、セール時にはさらに安くなることもあります。
ただし、人気のタイミング(ガンダム作品の新作公開や周年イベントなど)には在庫切れになることもあり、根強い需要があることを示しています。
駿河屋はコンディション表記が丁寧で、箱や説明書の状態によって細かく価格が変動します。そのため「多少高くても状態の良いものを手に入れたい」と考えるコレクター層に支持されていると言えるでしょう。
6. 新品・未開封品のレア度
新品・未開封品については、市場に出回ること自体が非常に稀になっています。もし出品があった場合、価格は 3,500円~4,500円前後 になるケースが多いです。
ただし、『Target in Sight』はPS3初期のタイトルであり、当時大量に出荷されていたこともあって「幻のレアソフト」ではありません。そのため、未開封品であっても極端に高騰することはなく、“ちょっとしたプレミア”程度にとどまっています。
7. 中古市場における位置づけ
『Target in Sight』は、中古市場において「手軽に入手できるが、一定のコレクション価値もあるソフト」として位置付けられています。ガンダムゲームの中でも異色の作品であり、今なお「硬派なリアル志向ガンダム」として記憶に残っているため、安定した需要が存在しているのです。
一方で、ゲーム内容そのものが万人受けするものではないため、価格が極端に上がることはありません。あくまで「歴史的な意義」や「PS3ローンチタイトルとしての記念性」を評価する層が中心となり、コレクター市場に支えられていると言えるでしょう。
まとめ
中古市場での『機動戦士ガンダム Target in Sight』を総括すると、
ヤフオク!:1,000円~2,000円、状態次第で落札価格が変動
メルカリ:1,200円~2,000円、ライト層に人気、即売れ傾向あり
Amazon:2,000円~3,000円、安心感を求める層に需要
楽天市場:2,000円~3,500円、コレクター向け出品が中心
駿河屋:1,500円~2,200円で安定、在庫切れになることも
新品未開封品:3,500円~4,500円程度、レア度は低いが希少性はある
このように、中古市場では決して高額にはならないものの、安定して流通しているソフトです。「遊ぶために安価で買う」ライト層と、「コレクションに加える」コア層の両方が購入者層として存在しており、長期的に見ても市場から姿を消すことはないでしょう。
結果として、『Target in Sight』はガンダムゲームの中でも“歴史的に興味深い一作”として、今なお手に取りやすい価格帯で取引され続けているのです。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
【中古】[PS2] 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 DVD同梱版 バンダイナムコゲームス (20030904)
[メール便OK]【新品】【NS】SDガンダム バトルアライアンス[Switch版][お取寄せ品]
SFC SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 大いなる遺産 セーブ可(ソフトのみ)【中古】




 評価 5
評価 5【中古】SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディションソフト:ニンテンドーSwitchソフト/マンガアニメ・ゲーム
SFC SDガンダムGX セーブ可(ソフトのみ)【中古】 スーパーファミコン スーファミ
【中古】 SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch/NintendoSwitch
【中古】N3DS SDガンダム ジージェネレーション 3D
【中古】[PS2] SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ(GGENERATION SPIRITS) バンダイナムコエンターテインメント (20071129)
【中古】[PS] SDガンダム Gジェネレーション・エフ(GGENERATION-F) バンダイナムコエンターテインメント (20000803)
【中古】PS4 SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ




 評価 1
評価 1
![【中古】[PS2] 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 DVD同梱版 バンダイナムコゲームス (20030904)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/1/cg10401066.jpg?_ex=128x128)
![[メール便OK]【新品】【NS】SDガンダム バトルアライアンス[Switch版][お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10610000/10616284.jpg?_ex=128x128)





![【中古】[PS2] SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ(GGENERATION SPIRITS) バンダイナムコエンターテインメント (20071129)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/3/cg10403167.jpg?_ex=128x128)
![【中古】[PS] SDガンダム Gジェネレーション・エフ(GGENERATION-F) バンダイナムコエンターテインメント (20000803)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/2/cg10272620.jpg?_ex=128x128)