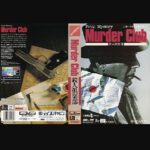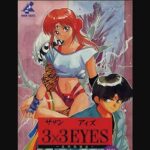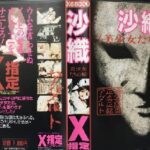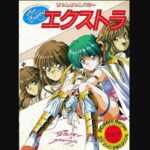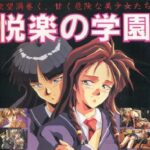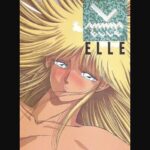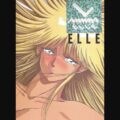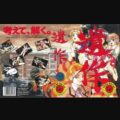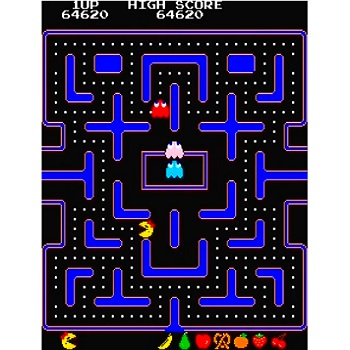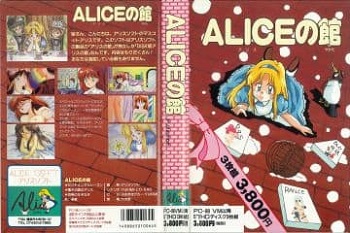ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..




 評価 5
評価 5【発売】:Active
【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS、Windows
【発売日】:1996年
【ジャンル】:アドベンチャーゲーム
■ 概要
作品の位置づけと基本情報
『Angel Halo(エンジェル・ハイロウ)』は、アダルトゲームブランドActiveが1996年にリリースした18禁恋愛アドベンチャーゲームで、PC-9801やFM TOWNS、Windows 95といった当時の主要PCプラットフォーム向けに展開されたタイトルです。同ブランドにとってはMS-DOSベースで動作する最後期の作品でもあり、フロッピーディスク時代からCD-ROM主流へと移り変わっていく過渡期の空気を色濃くまとっています。のちにMacintosh版が1998年に発売され、2000年にはWindows 95/98向けの廉価版も登場しており、一度出して終わりではなく、ハード環境の変化に合わせて何度か再パッケージされた経緯を持ちます。ジャンルとしてはテキスト主体の恋愛ADVでありながら、「人類の終末」「天使と悪魔の対立」「ルシファーの転生」といった宗教モチーフを全面に押し出したシナリオが特徴で、当時の美少女ゲームの中でもかなりシリアス寄りの世界観を持つ作品として語られることの多いタイトルです。
舞台となる時代と場所――終末目前の京都
物語の舞台は20世紀最後の年にあたる1999年12月の京都。プレイヤーは高校生の主人公・日下部真となり、静かな古都での学生生活を送っているかに見えて、その裏では世界の終わりがじわじわと近づいている、という構図で物語が進みます。ゲームが発売された1996年当時は、「ノストラダムスの大予言」が1999年の世紀末不安を象徴するキーワードとして世間を賑わせていましたが、本作では“その予言はすでに外れている”という前提から物語が始まり、プレイヤーに「じゃあ本当の終末はどんな形でやって来るのか?」という別種の不安と興味を抱かせる構成になっています。京都という土地柄も、ただの背景ではありません。重厚な寺社仏閣、古い町並み、水面に光が揺れる鴨川といったロケーションが、天使や悪魔が暗躍する物語に独特の陰影を与えています。日常シーンでは、ごく普通の学園ものらしい風景として描かれる一方、クライマックスが近づくにつれ、同じ街並みが「世界の終わりを迎えようとしている場所」として重たく感じられるようになる――このコントラストが『Angel Halo』の雰囲気作りに大きく貢献していると言えるでしょう。
天使と悪魔、そして“人類の鍵”である主人公
主人公の日下部真は、一見するとどこにでもいる普通の高校生です。真面目で責任感があり、クラス委員を任される程度には周囲から信頼されている青年ですが、本人すら知らない重大な秘密――「魔王ルシファーの生まれ変わり」であるという設定――を抱えています。この世界における終末とは、彼の内に眠るルシファーが覚醒し、世界の秩序を破壊してしまうこと。その引き金を引かせまいとする勢力が“天使”であり、逆に覚醒を促そうとする陣営が“悪魔”です。ドイツからの交換留学生としてやって来るソフィアは天界側の使者、同じく留学生として姿を現すリリスは魔界側のエージェントとして位置づけられており、二人のヒロインが真をそれぞれの陣営へと引き込もうとすることで、物語は大きく「天使ルート」と「悪魔ルート」に分岐していきます。この三者の関係性は単純な善悪対立にとどまらず、恋愛感情や人間関係、そして「自分の意志で世界をどうしたいのか」という哲学的な選択が絡み合っていきます。プレイヤーはテキストを読み進めつつ選択肢を選び、真がどのような心の結論に至るのかを見届けることになりますが、どのルートを辿っても“ルシファー復活”という大きな流れ自体は止められない――というハードな設定も、本作のトーンを象徴する要素です。
聖書モチーフと終末論が織り成す物語
『Angel Halo』の物語構造を語るうえで外せないのが、キリスト教的なイメージや聖書の引用が随所に用いられていることです。オープニングからして聖書の一節を想起させるようなフレーズが掲げられ、キャラクターの台詞やイベントの背景設定にも、天界・魔界・堕天使といった宗教用語や象徴が散りばめられています。とはいえ、本作は神学書のような難解さを狙った作品ではありません。プレイヤーにとっては、「天使はなぜここまで世界を守ろうとするのか」「悪魔たちは何をもって復活を望んでいるのか」という行動原理を理解するための、スタイリッシュな装飾として機能しています。特に、ソフィアが自らを「最初にして最後のもの、称えられ、同時に蔑まれるもの」と表現する印象的な自己紹介は、彼女がただのヒロインではなく、“終末にまつわる特別な役割”を持つ存在であることをプレイヤーに強く印象づけます。一方で、悪魔側のキーパーソンであるリリスの背景には、「神の最初の妻」という伝承をベースにした設定が盛り込まれており、単なる“悪役の誘惑者”にとどまらない重みが与えられています。こうした宗教的モチーフがあくまでエンターテインメントとして消化されつつも、プレイヤーに「善と悪」「救いと滅び」「神と人間の関係」といったテーマを自然に考えさせるよう作られている点は、本作ならではの特色と言えるでしょう。
ゲームシステムとプレイ感覚の概略
システム面では、テキストを読み進めながら要所で現れる選択肢を選び、ルートやエンディングが分岐していく、オーソドックスな恋愛アドベンチャースタイルを採用しています。FM音源によるBGM、CD-ROM版でのキャラクターボイス対応、CG閲覧モードや回想モード、メッセージスキップといった当時のADVとして欲しい機能は一通り押さえられており、「システムが足を引っ張って物語に集中できない」というストレスは少ない作りです。プレイのメインはあくまで長めのシナリオテキストであり、派手な戦闘シーンや複雑なパラメータ管理などは登場しません。その代わりに、天使ルート・悪魔ルートを中心とした複数の分岐と、個々のヒロインに焦点を当てたエピソードが用意されており、プレイヤーは周回プレイを通して少しずつ世界の全体像やキャラクターの裏側に触れていくことになります。ストーリーは基本的に一本道で進行しながらも、選択によって「誰の思惑に寄り添うのか」「真は自分の宿命をどう受け止めるのか」が変化していくため、同じシーンであってもルートによって印象が変わる作りになっているのがポイントです。
ビジュアルとブランド内での位置づけ
本作の原画を担当したのは、後年『Bible Black』や『DISCIPLINE』などで広く知られることになる聖少女で、彼女にとっても初期キャリアを彩る重要な一作に数えられます。当時のPC-98向け美少女ゲームならではの低解像度グラフィックながら、線の細さや陰影の付け方によって、天使や悪魔といった超常的存在の“人間離れした美しさ”が丁寧に描き出されており、終末を前にした不安定な空気感と相まって独特のビジュアルテイストを形作っています。Activeブランド全体で見ると、『Angel Halo』はクイズや麻雀、ライトな恋愛物が多かったラインナップの中で、宗教色と世界の破滅を真正面から扱った比較的重厚なシナリオ作品として位置づけられており、後の『HEARTWORK』や『Bible Black』へと続く“ダーク寄りシナリオ路線”の前兆と捉えることもできます。
18禁恋愛ADVとしての性格
『Angel Halo』は18禁指定の恋愛アドベンチャーであり、物語の中にはキャラクター同士の親密な描写や性的な表現を含んだシーンも挿入されていますが、ゲーム全体の印象としては「エッチシーンを見るための作品」というより、「重いテーマを持ったストーリーを読ませるタイプのADV」に近いバランスです。終末を前に揺れる人間関係、天使や悪魔が抱える葛藤、人類そのものの価値を問い直すような会話の積み重ねがメインであり、その延長線上に肉体的な関係が描かれていく、という構成になっているため、プレイ後はシナリオの印象が強く残るという感想もよく聞かれます。世界の終わりという大きなスケールの出来事を題材にしながら、その中心には一人の高校生と数人の少女たちの心情の変化がある――この“巨大なテーマと身近な青春ドラマの同居”こそが、『Angel Halo』という作品の概要を一言で要約するならふさわしい特徴だと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
終末と青春が同じキャンパスに同居する独特の世界観
『Angel Halo』の最大の魅力のひとつは、「人類の終末」という重苦しいテーマと、「高校生活」「恋愛」といったごく身近な青春ドラマが、違和感なく同じキャンパスの中で同居している世界観にあります。舞台は受験や部活動、人間関係の悩みなど、どこにでもある学生生活が繰り広げられている京都の高校ですが、その裏側では“世界が終わるかもしれないカウントダウン”が静かに進行している。このギャップがプレイヤーに強い印象を与えます。朝はいつものようにホームルームが始まり、昼休みにはクラスメイトと他愛もない会話を交わし、放課後にはヒロインと一緒に寄り道をする――そんな平凡な時間の合間に、天使や悪魔が意味深な言葉を残して去っていくことで、「今見ている日常はいつ崩れてもおかしくない」という緊張感がじわじわと蓄積していきます。完全な暗黒世界でもなければ、ただの萌え日常でもない、終末感と青春感が絶妙なバランスで同居した空気こそが、この作品ならではの魅力です。プレイヤーは、主人公の日常が愛おしく感じられるほど、「もし終わってしまったら」という喪失への恐怖も同時に強くなっていき、シナリオ終盤の選択肢がより重く心に響くよう設計されています。
天使と悪魔、善と悪の境界線をぼかすテーマ性
本作には天界と魔界という分かりやすい対立陣営が登場しますが、物語の中で描かれるのは単純な「正義vs悪」という構図ではありません。天使ソフィアは世界の滅びを防ぐために動いているものの、そのやり方や価値観が本当に人間にとっての“善”なのかどうかは、プレイヤーの視点によって揺らぎます。一方の悪魔リリスも、ルシファー復活を目指す存在として描かれながら、その根底にある感情や行動理由は決して一面的なものではなく、彼女なりの信念や優しさが垣間見える場面が多々あります。つまり、天使だから無条件に正しく、悪魔だから絶対的な悪、という描かれ方がされていないため、プレイヤーはルートを進めれば進めるほど「本当に責められるべき者は誰なのか」「救われるべきなのはどちらなのか」といった問いに直面することになります。なにより魅力的なのは、こうした哲学的なテーマが、難解な専門用語や説教臭い台詞で押しつけられるのではなく、キャラクター同士の会話や何気ない日常のワンシーンを通して少しずつ浮かび上がってくる点です。たとえば、何気ない雑談の最中にソフィアがふと漏らす言葉や、リリスが夜の校舎で見せる一瞬の寂しげな表情など、細かな描写が積み重なることで、プレイヤーはいつの間にか「天使と悪魔のどちらが正しいか」という単純図式ではなく、「どの選択なら自分は納得できるのか」を考えさせられてしまう。その“考えさせられる面白さ”が、本作に深みを与えています。
キャラクターたちの心理劇としての完成度
恋愛アドベンチャーとして見たとき、『Angel Halo』はキャラクター同士の関係性の描き方が非常に丹念で、そこが強い魅力になっています。主人公・真は、ただの受け身な転生者ではなく、クラス委員らしい責任感と、周囲を気にかける優しさを持ち合わせた人物として描かれ、その性格が選択肢や会話の端々に反映されています。ソフィアは、使命を帯びた天使でありながら、日常生活では不器用な一面も見せるため、神秘的な存在でありつつも「守ってあげたくなる」距離感を保っています。ドイツから来た留学生という設定により、文化や価値観の違いをめぐるやり取りも描かれ、単なる“天使ヒロイン”にとどまらない立体感が生まれています。リリスは奔放で積極的な性格が目立ちますが、悪魔としての役割と一人の少女としての感情の間で揺れ動いている様子が丁寧に描かれ、プレイヤーは“誘惑する悪魔”としてだけでなく、“報われにくい想いを抱える女の子”として彼女を見てしまうようになります。また、幼馴染の常盤まりもは、真との距離感が絶妙で、気安く毒づきながらも誰より彼を心配しているという関係性が、物語が進むごとにじわじわと効いてきます。どのキャラクターも“設定”だけでなく、“日々過ごす中での仕草や言葉の選び方”にまで性格が反映されているため、プレイしているうちにいつの間にかそれぞれの人物に対して感情移入が進み、終盤の選択やエンディングでの彼女たちの行動が、より強く心に刻まれる構造になっています。
ルート分岐によって別の角度から語られる世界の真相
『Angel Halo』はルート分岐型のシナリオ構造を採用しており、どのヒロインとどう関わり、天界・魔界のどちらに軸足を置くかによって、描かれるエピソードや真実の見え方が変わっていきます。単に「誰とくっつくかが変わる」レベルの分岐ではなく、ルシファー復活の意味、天界側の思惑、悪魔たちの本音など、重要な設定の断片がルートごとに別々に提示されるため、ゲーム全体を俯瞰するには複数回の周回プレイがほぼ必須です。この構造が、プレイヤーに「もう一度別の選択をしてみよう」という動機づけを強く与えています。また、周回を重ねるごとに、以前は意味がわからなかった台詞が別の意味を帯びて聞こえたり、「あのときの選択はこういう結果に繋がっていたのか」といった再発見が生まれる仕掛けが随所に盛り込まれているのも魅力です。さらに、“どのルートでもルシファー復活そのものは阻止できない”という共通の大枠があるため、プレイヤーは「どう終わるか」ではなく「終わりに向かう過程で誰とどんな想いを交わすか」「終末を前に何を選び取るか」という部分に注目するようになり、自然と物語の“経過”そのものを味わうプレイスタイルになっていきます。これは、ハッピーエンド一択の作品とは異なる、ビターでありながら味わい深い魅力と言えるでしょう。
ビジュアルと音楽が作り出す“静かな終末美”
グラフィック面では、当時のPC-98系作品らしい解像度と色数ながら、キャラクターの表情や衣装デザイン、背景の構図などにかなりのこだわりが見られ、特に夜のシーンや教会、神殿のような場所でのイベントは、陰影の強い配色によって“静かな終末”を感じさせるビジュアルに仕上がっています。天使ソフィアの神秘的な衣装や、リリスの妖しさを強調した立ち絵、そして主人公たちが通う学校や京都の街並みが、限られたドット数の中で丁寧に描かれており、ルートによっては同じ背景がまったく違う印象を与えるのもポイントです。音楽も世界観の形成に大きく貢献しており、荘厳さを感じさせるコーラス風の曲調や、緊張感のあるマイナーコードのBGMが、天界・魔界の対立や終末へのカウントダウンを演出します。一方で、学園生活の日常シーンには明るめでテンポのよいBGMが用意されており、その落差が物語の“陰”をより際立たせているのも巧みです。全体として、派手に盛り上がるテーマソングやアクションシーンで押し切るのではなく、じわじわと心に染み込んでくるような視覚・聴覚演出が中心になっているため、プレイ後しばらく経ってからふとメロディやワンカットのCGを思い出してしまう、そんな“後引く美しさ”が本作の魅力となっています。
18禁作品でありながらストーリー重視の手触り
18禁恋愛ADVというジャンルは、どうしても性的描写に注目が集まりがちですが、『Angel Halo』はあくまで「世界の終末と人間の選択」を中心に据えたストーリードリブンな作品として受け取られています。確かにヒロインとの関係が深まるにつれて、それを象徴するようなイベントシーンが用意されていますが、それらは単体で独立した“ご褒美”というよりも、ルート全体の感情の流れの中で意味を持たせるよう配置されています。たとえば、世界の命運を背負わされたソフィアが、“ただの少女”として主人公に寄りかかる瞬間に訪れる親密な描写は、彼女の弱さや人間味を感じさせると同時に、プレイヤーに「この幸せがいつまで続くのか」という不安を強く意識させます。また、リリスとの関係では、愛情と破滅がほとんど同義語のように近接しており、“甘い時間”であるはずのシーンが、どこか危うさと背徳感を同時に伴うような演出がなされています。こうした構成により、プレイヤーは単にシーンを“回収”するのではなく、それぞれのイベントが物語全体の中でどんな意味を持つのかを考えながら読み進めることになり、18禁作品としての側面と、ドラマ性の高いAVGとしての側面が高い次元で両立しています。
“世紀末感”を閉じ込めた当時ならではの空気
最後に、本作の魅力として見逃せないのが、“1990年代後半の空気感”そのものが作品に封じ込められている点です。まだインターネットが一般家庭に十分普及しきっていない時代、ポケベルや初期の携帯電話がようやく浸透し始めた頃の日本社会は、現代とは異なる静けさと閉塞感をあわせ持っていました。その世相と、「西暦2000年を目前にした世紀末不安」が重なり合い、『Angel Halo』の物語世界に独特のリアリティを与えています。作中で描かれる京都の街並みや学校生活には、90年代ならではのファッションや文化が垣間見え、プレイヤーにとっては懐かしさと共に、「あの頃、本気で1999年の世界の終わりを信じた人もいたかもしれない」という感覚を想起させます。今の視点からプレイすると、当時の技術や価値観がぎゅっと詰まった“タイムカプセル的な魅力”も加わり、単なるノスタルジー以上の味わいを持つことになるでしょう。世紀末という言葉が今ほど使われなくなった現在だからこそ、あの時代の“終末”への期待と恐怖をリアルタイムで描いた作品として、『Angel Halo』を再評価する価値があると言えます。
■■■■ ゲームの攻略など
プレイの基本方針と周回の考え方
『Angel Halo』は、選択肢によってルートとエンディングが分岐する恋愛アドベンチャーなので、「一周で全部を見よう」とするよりも、「まずは1ルートをクリアして全体の流れを掴み、2周目以降で細部を回収していく」というスタンスで遊ぶのが基本方針になります。最初のプレイでは、攻略情報を細かくチェックするよりも、自分の感性に従って選択肢を選び、「この世界に初めて触れるプレイヤーとしての驚き」を味わうのがおすすめです。物語の骨格――終末へ向かう世界、天使と悪魔が暗躍する構図、主人公の正体――を大づかみに理解してから、2周目・3周目で「今度はソフィアを優先しよう」「まりもに寄り添った選択をしてみよう」といった遊び方に切り替えると、同じイベントでも印象がガラリと変わって見えます。周回前提の構造なので、セーブデータは一つにまとめて上書きするのではなく、重要そうな分岐ポイントごとに複数スロットへ保存しておき、気になったらすぐ手前に戻って選択肢をやり直せるようにしておくと快適です。また、テキスト量が多い作品なので、長時間プレイすると細かい伏線や台詞を忘れがちです。気になる会話やキーワードが出てきたら、簡単にメモしておくと、後半で「あのときの台詞はこの伏線だったのか」と気づきやすくなり、物語をより深く楽しめます。
ルート分岐の大まかなイメージと選択のコツ
ルートの分かれ方をざっくり言えば、「誰と一緒に過ごす時間が長いか」「どのタイミングで誰の味方になる選択肢を選ぶか」という二点に集約されます。登場人物ごとに好感度のような隠しパラメータが存在するとイメージすると分かりやすく、イベント中に特定のキャラを優先したり、庇ったり、手を差し伸べたりする選択肢を選ぶことで、そのキャラのルートに乗りやすくなります。特にソフィアとリリスは、物語の根幹に関わる二大ヒロインなので、「天使寄りの選択肢」「悪魔寄りの選択肢」を意識しながら選ぶだけでも、どちらの陣営に物語の軸足を置くかが自然と決まっていくはずです。一方、幼馴染のまりもルートを狙う場合は、派手な選択肢で一気に好感度が上がるというより、“普段の小さなやり取りをどれだけ大事にするか”が重要になります。他のヒロインにばかり構っていると、いつの間にか距離が開いてしまうので、「放課後の誘いに乗るか」「悩んでいそうなときに声をかけるか」といった、さりげない分岐を丁寧に拾っていくのがポイントです。初回プレイでは「あえて誰のルートを狙うか決めず、自然体で選ぶ」ことで、自分の性格がどのヒロインに近いか、という“相性チェック”のような楽しみ方もできます。
日常パートで意識したい行動とイベントの拾い方
学園を舞台にした日常パートでは、どの場所へ行くか、誰と会話するかによって、発生するイベントが細かく変化します。教室、屋上、図書室、帰り道など、それぞれ出会いやすいキャラクターの“定位置”が何となく決まっているので、「この時間帯はここに行けばあの子に会える」というパターンを覚えておくと、狙ったヒロインのイベントを効率よく回収できます。また、一度見逃したイベントが後のフラグになっている場合もあり、「序盤に何となくスルーした選択肢が、終盤で大きな分岐に繋がっていた」といったことも起こり得ます。全イベントを一周で埋めようとするとどうしても作業感が出てしまうので、1周目は自然に気になった場所へ行き、2周目以降で「前は行かなかった場所」「前は選ばなかった会話」を重点的に回るのがコツです。特に、夜のシーンや放課後の校舎は、キャラクターたちの本音や核心に触れるイベントが発生しやすいポイントなので、「昼間は日常、夜は物語が動く時間帯」と意識して行動すると、ストーリーの密度を高く感じられるでしょう。
天使ルート・悪魔ルート攻略の心構え
天使側に寄り添うルート――一般にソフィアを中心とした展開――では、人類を守るという大義や自己犠牲、信仰や赦しといったテーマが前面に押し出されます。このルートを狙うときは、「世界をどうしたいか」という視点で選択肢を選ぶのがポイントです。たとえば、目の前の小さな幸せよりも、多くの人を救う可能性を優先するかどうか、といった場面では、短期的には辛い決断が“天界寄り”の選択になりがちです。一方、悪魔側に寄り添うルート――リリスを中心とした展開――では、運命に逆らう者、既存の秩序に対する反逆、個人の欲望や感情を肯定する姿勢が強く描かれます。このルートを進めたい場合は、「たとえ世界の終わりに繋がるとしても、自分の想いを貫くか?」といった問いに対して、迷わず感情を優先する選択肢を選ぶと、自然と悪魔側の物語へ深く踏み込んでいくことになります。それぞれのルートは、どちらが“正しい”かを示すものではなく、「もし自分がこの状況にいたら、どちらを選ぶだろう?」という疑似体験をさせてくれるルートなので、攻略というより“自分の価値観を試す選択肢集”として楽しむのが、この作品に最も合った心構えだと言えます。
難易度とバッドエンド回避のコツ
システム的な難易度で言えば、『Angel Halo』は極端にシビアな作品ではありませんが、“何となくプレイしていると気づけば望まない結末にたどり着いていた”というケースは少なくありません。特に、世界の終末を扱う作品だけあって、バッドエンドのバリエーションが豊富で、甘い空気から一転して容赦のない結末を突きつけられることもあります。バッドエンドを避けたいときには、以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。第一に、特定のヒロインへ一貫して好意的な態度を取り続けること。途中で別のヒロインに目移りしたり、決定的な場面で迷った行動をすると、“誰も救えない中途半端な結末”に流れやすくなります。第二に、重要なイベントらしき場面(教会や神社のような場所、終末に関する会話が出るシーン)では、安易にその場しのぎの選択肢を選ばないこと。たとえ一時的に関係が悪くなりそうでも、筋の通った答えを選ぶ方が、長い目で見れば良い結末に繋がることが多いです。また、クイックセーブ・クイックロード機能や、選択肢の直前にこまめにセーブしておく習慣をつけておけば、「この選択肢は危なそうだ」と感じたらすぐに別ルートを試すことができ、バッドエンドも“バリエーションのひとつ”として楽しめるようになります。
イベントコンプリート・CG回収を目指す場合の進め方
物語の全貌を把握したあと、やり込みとしてCGやイベントのコンプリートを目指す場合は、少し攻略的な視点が必要になります。まず、各ヒロインごとに「このルートでしか見られないイベント」「特定の条件下でのみ発生する隠しイベント」が存在するため、ルートごとに専用のセーブデータを用意し、細かな分岐を試せるようにしておきます。たとえば、ある日付の放課後にA地点へ行くかB地点へ行くかで、片方のヒロインの短いイベントが発生し、それがCG枚数に直結している――といったタイプの分岐です。一周目では気づきにくい“時刻限定”や“前の選択肢との組み合わせ”で開放されるものもあるため、攻略を詰める段階では、日付ごとに「どこへ行ったか」「誰と会話したか」を簡単にメモしておくと効率がぐっと上がります。また、全CG回収を目標にする場合は、どうしても細かい条件を満たす必要があるため、ゲーム内の回想モードやCG閲覧モードを定期的に確認し、「どのヒロインのどのシーンが抜けているのか」をチェックしながらプレイすると達成感を得やすくなります。最終的には、ソフィア・リリス・まりもたちメインヒロイン全員の個別エンディングと各派生エンド、そしてサブイベント的なシーンまで一通り見終えたとき、この作品の世界がようやく“完成したパズル”のように一枚の絵として見えてくるはずです。
裏技的な楽しみ方・自分なりのロールプレイ
『Angel Halo』は、派手な隠しコマンドやデバッグモードのような意味での“裏技”が売りのゲームではありませんが、遊び方の工夫次第でちょっとした“裏技的楽しみ方”が生まれます。たとえば、「徹底的に自己中心的な選択だけを選び続ける」「逆に、どのヒロインに対しても可能な限り誠実で優しい選択肢だけを選ぶ」といったロールプレイをしてみると、同じイベントでも印象がまったく変わって見えます。また、“天界にも魔界にもつかない、中立的なスタンス”を最後まで貫こうとすると、物語はどんな終末を迎えるのか――といった、自分なりの縛りプレイを試すのも面白いところです。さらに、世界観や宗教モチーフに興味があれば、作中で出てくる単語や聖書風の引用文を、プレイ後に自分で調べてみるのも一つの楽しみ方です。天使や悪魔の名前の由来、ルシファー伝承との関係などを知ることで、二周目以降のプレイが“設定を踏まえた再読”になり、キャラクターの台詞に込められた意味をより深く味わえるようになります。このように、『Angel Halo』の攻略とは単にエンディングに到達することにとどまらず、「自分がどんな価値観でこの世界を歩くか」を何度も試してみることそのものが、最大の攻略法であり、このゲームを長く楽しむコツだと言えるでしょう。
■■■■ 感想や評判
発売当時のプレイヤーが受けた“世紀末ドラマ”としての衝撃
『Angel Halo』が発売された90年代半ばの18禁PCゲーム市場では、学園ラブコメやライトなファンタジー色の強い作品が主流で、「世界の終末」や「天使と悪魔の宗教対立」を正面から扱うタイトルは、今ほど多くありませんでした。その中で本作は、PC-9801やFM TOWNSといった当時のPCユーザーが好むややマニアックな雰囲気も相まって、「ただヒロインといちゃつくだけのゲームとは明らかに違う」「プレイ後に妙に心に残る」といった感想を残した作品として語られています。プレイヤーの多くは、パッケージイラストや紹介記事から“天使と悪魔の三角関係ADV”程度のイメージで手に取ったものの、実際にプレイしてみると、物語の根底に流れる終末論や、主人公が負わされている“世界の鍵”としての重い宿命に驚かされた、という印象を抱きがちでした。特に、どのルートを辿ってもルシファー復活という大きな流れは避けられないという構造は、当時のプレイヤーにとってなかなかショッキングで、「必ずしもすべてが救われるわけではないビターなADV」として記憶に刻まれています。
ストーリーへの評価――王道と重さが同居した“読ませるADV”
ストーリーに関する評判でよく言及されるのは、「王道学園恋愛ものの定番要素と、終末ファンタジーとしての重厚さが同居している」という点です。序盤は、転校生の世話役を押しつけられた主人公が、ドイツから来た謎めいた少女や、奔放な留学生の女の子、そして幼馴染のヒロインたちとの距離を縮めていく、比較的ライトな学園ドラマとして進んでいきます。そのため、「最初は普通のギャルゲーだと思って気楽に遊んでいた」という声も多いのですが、終盤に近づくにつれて天界・魔界の対立やルシファーの正体が明かされ、物語のトーンは一気にシリアス寄りへシフトします。この“日常から非日常への落差”を、評価のポイントとして挙げるプレイヤーは多く、「読み進めるほど空気が重くなっていく感じがクセになる」「最後の方はテキスト送りの手が止まらなかった」といったポジティブな感想が散見されます。一方で、その重さゆえに「気軽に何周もするタイプのゲームではない」「読後感がずしんと残るので、すぐに別の作品に行きづらい」といった声もあり、良くも悪くも“感情を揺さぶるシナリオ”として受け止められていると言えるでしょう。
キャラクター描写に対する好意的な声
ヒロインたちのキャラクター性や関係性に関する評判は、総じて好意的なものが多く見られます。天使ソフィアは凛とした佇まいと使命感を持ちつつ、日常の中では不器用で人間味のある仕草を見せるため、「崇高さと庶民的な可愛さのバランスが絶妙」「守られる存在でありながら、こちらを導いてくれる感じがいい」と好感を持たれがちです。悪魔リリスは自由奔放な言動が目立つ一方、時折垣間見える寂しさや弱さに心を掴まれたプレイヤーも多く、「最初は軽薄に見えたけど、話が進むほど好きになっていった」という感想がよく挙げられます。幼馴染の常盤まりもについては、ツンデレの元祖的なポジションとまではいかないまでも、「素直になれないがゆえに遠回りしてしまう不器用さ」が評価され、「天使や悪魔という大きな存在に囲まれる中で、人間らしさの象徴のようなキャラ」「一番現実的で、一番共感できる」といった声もあります。こうしたキャラクターの好評は、“誰か一人に人気が集中する”というより、“それぞれに根強いファンがいる”タイプの作品であることをうかがわせます。
ビジュアル・ボイス・音楽面への評価
ビジュアル面に関しては、当時の解像度や色数の制約を踏まえたうえでも「キャラクターデザインが非常に印象的」「表情やポーズが心情をよく表している」と高く評価されることが多いです。特に、天使・悪魔というモチーフを活かした衣装やアクセサリーの描き込み、学園生活の何気ない一コマを切り取ったCGの構図など、プレイ後も頭の中に残り続けるカットがいくつもあるとの声が聞かれます。また、フルボイス作品ではないものの、要所を押さえたボイス演出や、イベントシーンでの声優の芝居が効果的に機能しており、「声が入ることでキャラの印象が一段深くなっている」「台詞そのものより声のトーンが胸に残る」といった意見もあります。音楽についても、荘厳なコーラス風BGMや切なさを帯びたピアノ曲などが、天使・悪魔・終末といったキーワードにうまくマッチしていて、「OPや特定シーンのBGMを今でも口ずさめる」「音楽があったからこそ重苦しいシーンに飲み込まれずに最後まで読めた」という好意的な感想がよく挙げられます。
テンポやボリュームに対する賛否両論
一方で、『Angel Halo』の評価は決して“褒め一色”ではなく、特にプレイテンポやボリューム感については賛否が分かれるポイントです。テキスト主体のADVであり、世界観の説明や心情描写にかなりの行数を割いているため、「じっくり読み込むタイプの人には向くが、軽快なノリを期待していた人にはやや重く、長く感じる」という意見があります。序盤から中盤にかけて、日常パートがやや長めに続く構成も、「その積み重ねが終盤の破局感に効いてくる」と評価する声がある一方で、「もう少し早く物語が動いてほしかった」「体験版の印象と比べると、本編はテンポがゆっくり」という不満に繋がることもありました。また、BADエンドのバリエーションや、ルート分岐の多さと比較して、ユーザーの中には「すべてのエンディングを見るには相当な時間がかかる」「CGコンプリートまで行く前に気力が尽きた」といった、ボリュームの多さをネガティブに捉える感想もあります。とはいえ、シナリオ重視派からは「これくらいの厚みがあるからこそ、世界の終末というテーマが説得力を持つ」と擁護する声も多く、プレイスタイルや好みによって評価が分かれるポイントだと言えるでしょう。
シナリオの“救いの少なさ”に対する複雑な反応
「どのルートを選んでも、ルシファーの復活そのものは避けられない」という作品構造は、本作を象徴する特徴であると同時に、プレイヤーの感想を大きく二分させた要素でもあります。終末を前にして、誰かを救うために別の誰かを犠牲にせざるを得ない展開や、“最善を尽くした結果が必ずしもハッピーエンドにならない”という結末は、「ゲームだからといって簡単に世界が救われるわけではない、という割り切りが良い」「苦いけれど、だからこそ印象に残る」と高く評価する声がある一方で、「頑張っても世界が救えないのはやるせない」「せめてどこかのルートだけでも完全な救いが欲しかった」と感じたプレイヤーも少なくありません。この“救いの少なさ”は、人によっては強烈な名作体験となり、人によっては「気軽におすすめしづらい」と感じさせる要因ともなっており、まさに本作の評価を語るうえで避けて通れない部分です。ただ、時間が経ってから振り返ると、「当時は受け止めきれなかったが、大人になってから思い返すと妙に心に残っている」「ハッピーエンド一辺倒の作品よりも、物語として印象が強い」と再評価する声も見られ、プレイ直後と数年後で印象が変わるタイプの作品だという捉え方もできます。
現在における“レトロPCゲーム”としての評価と存在感
PC-9801やFM TOWNS、初期Windows向けに展開された『Angel Halo』は、ハードウェア環境が大きく変わった現代では、現役でプレイするハードルが高くなっています。それでも、レトロPCゲームや90年代ADVに関心を持つユーザーの間では、「宗教モチーフ×学園恋愛×終末」という独自の組み合わせや、後に名を馳せるクリエイターの初期仕事としての価値などから、しばしば名前が挙がる一本です。入手難度の高さや動作環境の問題もあり、広く語られる“メジャー名作”というよりは、好きな人がじっくり語りたくなる“通好みの一本”という立場にありますが、その分、実際にプレイ済みの人からのコメントは熱量が高く、「今の基準で見ると古さはあるが、テーマと雰囲気は色あせていない」「終末ものADVの源流のひとつとして押さえておきたい」といった、作品の存在感を尊ぶ声が多く見られます。また、同時期の他タイトルと比べても、単なる“懐かしいエロゲー”ではなく、“90年代世紀末の空気を閉じ込めたシナリオADV”として記憶されている点は、本作特有の評価と言えるでしょう。
■■■■ 良かったところ
終末と青春を両立させた“空気感”の完成度
『Angel Halo』の良かった点としてまず挙げられるのは、「高校生のささやかな日常」と「世界の終末」という、スケールのまったく違う要素を破綻なくまとめ上げた空気感の完成度です。朝のホームルーム、昼休みの教室、放課後の寄り道といった何気ない時間の積み重ねが丁寧に描かれることで、プレイヤーは主人公たちの日常に自然と愛着を抱くようになります。その一方で、天使や悪魔が口にする不穏な言葉や、カレンダー上でじわじわ近づいてくる“破局の日”の存在が常に背景にあり、プレイを続けるほど「この穏やかな時間は永遠ではないのかもしれない」という感覚が強まっていく。このコントラストが非常に巧みで、単に重苦しいだけの終末物にも、ただ甘いだけの学園恋愛物にもならず、その中間にしか生まれない独特の味わいを実現しています。特に、日常シーンの細やかな描写が終盤の喪失感や切なさを何倍にも増幅させている点は、多くのプレイヤーが「ありふれた学園生活の描写が、ここまでラストで効いてくるとは思わなかった」と評価した部分でしょう。
キャラクターの“人間味”が生む感情移入のしやすさ
もうひとつの大きな長所は、登場キャラクター一人ひとりの“人間味”の描き方です。主人公・真は、特別な血筋や運命を背負っていながらも、それに胡坐をかくことなく、あくまで普通の高校生として悩み、迷い、時には逃げてしまう弱さも抱えた人物として描かれています。そのため、プレイヤーは彼を「選ばれし勇者」ではなく、「自分と同じように、ただ懸命に生きようとしている少年」として見やすく、世界の命運を左右する選択でも、“どこか他人事にできない”感覚で向き合うことになります。ソフィアやリリスといった天使・悪魔勢も、神話的な存在であると同時に、喜びや嫉妬、孤独といったごく人間的な感情を抱いているため、超然としたアイコンではなく、“たまたま天使/悪魔という役割を与えられた少女”として受け止められます。特に、使命と自分の想いの板挟みになって揺れ動くソフィア、軽口の裏に諦念や渇望を隠しているリリスの描写は、「善悪を超えて“ひとりのキャラクター”として好きになれる」と評されやすいポイントです。この“神話的存在の人間味”がしっかり描かれているからこそ、終盤の決断や別れがより胸に刺さり、「キャラゲーとしてもシナリオゲーとしても満足できた」という感想に繋がっています。
選択肢とルート構造がもたらす“自分の物語”感覚
良かった点として見逃せないのが、選択肢とルート構造の作り方です。多くのADVでありがちな「単に好感度を上げるための選択肢」ではなく、「この場面で自分ならどうするか」を問われているような選択が随所に盛り込まれているため、プレイヤーはルート分岐を“攻略のための分岐”ではなく、“自分の価値観を映す鏡”として体験できます。誰の誘いに乗るか、誰を守るために行動するか、世界と個人のどちらを優先するか――こうした問いに対する答えが、そのままエンディングの形になって返ってくる構造になっているため、クリア後には「これはゲームの物語であると同時に、自分が選んだ結末でもある」という手触りが残ります。また、ルートごとに提示される“真相の断片”が違っており、周回するたびに世界の成り立ちや天界・魔界の思惑が少しずつ明らかになっていくため、「次は別の選択を試してみたい」という意欲が自然に湧いてくるのも良いところです。単にエンディング数を増やしただけのマルチエンドではなく、“どの結末もそのルートなりの必然を感じさせる物語”として成立している点は、多くのADVファンから高く評価されるポイントでしょう。
ビジュアルと音楽が支えるドラマ性の高さ
グラフィックや音楽といった演出面も、本作の良さを語るうえで外せません。限られた解像度と色数の中で描かれたキャラクターCGは、目の描き方や表情の変化が非常に丁寧で、台詞そのものよりも“ワンカットの絵”が感情を雄弁に語っている場面が多くあります。特に、夕焼けに染まる校舎の廊下で立ち尽くすヒロインや、夜の教会での対話シーンなど、光と影のコントラストを活かした場面は、プレイ後も印象的なカットとして強く記憶に残ります。音楽面では、天使・悪魔・終末といったキーワードを支える荘厳なBGMから、日常パートを彩る軽やかな曲まで幅広く用意されており、場面転換のたびに“音”から空気が切り替わる感覚があります。重いテーマを扱っていながらも、メロディラインそのものはキャッチーで耳に残りやすく、「重苦しさだけが続かないよう、プレイヤーの心を支えるクッションの役割を果たしている」と感じられる点も、良い意味での配慮と言えるでしょう。ビジュアルと音の両面からキャラクターの感情や場面のトーンを補強しているため、テキストを読むスピードを自然にコントロールしてくれるのも、本作のドラマ性を支える重要な要素です。
終末を扱いながらも“説教臭くならない”バランス感覚
宗教モチーフや終末論を扱うと、どうしても説教臭くなったり、作者の思想を押しつけるような展開になってしまう危険がありますが、『Angel Halo』が上手いのは、そこを慎重に避けている点です。聖書を思わせる引用や、天界・魔界の価値観を語る台詞は存在するものの、あくまで“この世界観のルール”を説明するためのものであり、プレイヤーに特定の信仰や思想を強要するようなトーンにはなっていません。むしろ、「神に反逆した存在にだって理屈や信念がある」「世界を救おうとする行為が、必ずしも全員にとっての幸福とは限らない」といった、価値観の揺らぎや多面性を示すことで、「善悪を白黒つけようとせず、自分なりの答えを考えてほしい」というスタンスが感じられます。そのため、重いテーマながらも、「物語の中で提示される問いを、自分なりに受け止めながら遊べる」自由度があり、プレイヤーの数だけ解釈が生まれる余地を残しているのが良いところです。この“押しつけない姿勢”があるからこそ、本作は長い時間を経ても、「あのエンディングをどう受け止めるか」を語り合いたくなる作品であり続けているのでしょう。
18禁作品であることを逆手に取った“感情の深掘り”
18禁恋愛ADVとしての側面も、単なるお色気要素ではなく、キャラクターの内面を掘り下げるための装置として上手に機能しています。親密なシーンは、単に肉体的な関係を描くだけではなく、「世界が終わるかもしれない状況で、それでも相手を求めてしまう心情」「明日が来るか分からないからこそ、今日この瞬間にすべてを賭けたい想い」といった、極限状況下の感情を表現する場面として活用されています。ソフィアにとっては、使命と人間としての感情の折り合いをつけるための重要なターニングポイントとなり、リリスにとっては、破滅と快楽が表裏一体である自分の在り方を象徴する場面となるなど、シーンそのものがキャラクターのドラマと密接に結びついています。これにより、「18禁だから入っている要素」ではなく、「18禁だからこそ描ける心の奥底」が表現されており、感情の説得力や関係性の重みを増している点は、プレイヤーから“作品としての真剣さ”として好意的に受け止められています。
90年代PCゲームらしい“時代の匂い”が魅力として残っていること
最後に、“良かったところ”として特筆したいのが、作品全体に漂う90年代後半特有の雰囲気が、今となっては大きな魅力になっていることです。携帯電話もインターネットもまだ今ほど当たり前ではなかった時代の京都という舞台設定、学園生活の描写に流れ込むアナログな空気感、ノストラダムスの大予言に象徴される世紀末ムード――これらは当時のプレイヤーにとって“リアルタイムな現代”でしたが、現在の視点から見ると、レトロでどこかノスタルジックな魅力を帯びています。終末を恐れつつもどこかワクワクしていたあの時代の空気が、作中の細かな描写に刻み込まれているため、今プレイすると「当時の時代感覚まで含めて丸ごと味わえる」タイムカプセルのような作品になっているのです。テクノロジー的には古さを感じる部分もありますが、それすらも「この作品の魅力の一部」として愛でられる余地があり、単に“昔のゲーム”ではなく、“あの時代の空気を閉じ込めた一本の物語”として楽しめる点は、大きなプラス要素と言えるでしょう。
■■■■ 悪かったところ
テーマの重さと“救いの少なさ”が人を選ぶ
『Angel Halo』の短所としてよく挙げられるのが、扱っているテーマの重さと、物語全体に通底する“救いの少なさ”です。世界の終末、ルシファーの復活、人類の行く末といった題材は、それだけでプレイヤーの心に大きな負荷を与えますが、本作はその重みからあえて逃げず、どのルートに進んでも「すべてが丸く収まる完全ハッピーエンド」にはならない構造を取っています。この方針自体は作品の個性にもなっているものの、「一生懸命選択を重ねた結果が、どうにも報われない結末に繋がってしまう」「苦労した分だけ幸せなご褒美が欲しかった」というプレイヤーにとっては、大きなマイナスに感じられる部分でもあります。特に、恋愛ADVとして“好きなキャラクターのために頑張る”というスタンスでプレイしていた人ほど、「これだけ尽くしても、世界のルールそのものが変えられないのか」というやるせなさを感じやすく、プレイ後の疲労感や虚無感が強く残ってしまうことがあります。物語としては筋が通っていても、「ゲームとして癒やしやカタルシスを求めていた」層にはやや厳しい内容であり、その意味で“人を選ぶ作品”になっている点は、悪かったところとして挙げざるを得ないでしょう。
テキスト量とテンポの重さ――読み進める体力が必要
もうひとつの弱点は、テキスト量の多さに対して、展開のメリハリやテンポがやや重めであることです。終末論や宗教モチーフを自然に飲み込ませるために、世界観の説明や心情描写に相応の行数を割いているのは理解できるものの、プレイヤーによっては「もう少しコンパクトにまとめてほしかった」「同じようなやり取りが続く箇所が気になった」と感じる場面もあります。特に、序盤から中盤の学園生活パートでは、日常描写を積み重ねることが終盤の重さを支える重要な要素である反面、「いつ本筋が動き出すのか分かりにくい」「体験版で感じた盛り上がりに本編が追いつくまで時間がかかる」という印象を与えてしまうこともあります。さらに、ルート分岐が絡むため、別ヒロインのルートでも似たような日常イベントや説明が繰り返される箇所があり、周回プレイで全ルートを追おうとすると、「新しい情報を得たいのに、同じようなシーンを何度も読むことになる」という冗長感を覚える場合があります。シナリオ重視のADVとして考えれば、テキスト量の多さは強みでもありますが、「テンポ良くサクサクと進めたい」というプレイスタイルとは相性が悪く、読書に近い集中力と体力が求められる点は、悪い意味での敷居の高さに繋がっています。
分岐やフラグ管理が分かりにくく感じられる部分
マルチルートADVとしての作り込みは評価される一方、その複雑さが分かりにくさや遊びづらさにも繋がっています。どのヒロインのルートに入るか、どのエンディングに辿り着くかは、テキスト中の選択肢や日常パートでの行動に左右されますが、その条件がゲーム内で明示されているわけではなく、「気づかないうちに重要なフラグを取りこぼしていた」ということが起こりがちです。特定の日付に特定の場所へ行かなければ発生しないイベントや、あるヒロインのイベントを見ていないと別ヒロインの終盤シーンが変化しないといった“連鎖的な条件”も絡んでいるため、ノーヒントでプレイすると「なぜこの結末になったのか」「どこで道を誤ったのか」が把握しづらい構造になっています。その結果、「狙ったルートに入るまでが大変」「攻略本やネット情報を見ないとコンプリートは難しい」と感じるプレイヤーも少なくありません。もちろん、試行錯誤しながらルートの変化を楽しめる人にとってはやり込み要素になりますが、気軽に一通りのエンディングを見たいプレイヤーには、フラグ管理の不透明さがストレスになる場面もあり、この点はシステム面での弱点と言えるでしょう。
システム・UI面の古さとプレイ環境の制約
本作はPC-9801やFM TOWNS、初期のWindows 95環境向けに作られた作品であるため、現代の基準から見るとシステムやUI面でどうしても古さが目立ちます。メッセージスキップやロード機能など基本的な快適機能は備わっているものの、テキスト履歴の参照や細かな既読管理といった、最近のADVで当たり前になっている機能は期待できません。そのため、「うっかり早送りしすぎて重要な台詞を飛ばしてしまった」「少し前の会話を読み返したいのに、それができない」という不便さを感じる場面が出てきます。また、動作環境自体も現代のOSとは相性が悪く、実機やエミュレータの準備が必要になるなど、プレイを始めるまでのハードルが高い点も無視できません。これは発売当時の責任ではないものの、「遊びたいと思っても環境面で挫折してしまう」という意味では、作品へのアクセスを著しく制限している要因であり、“良い作品なのに触れられる人が限られている”というジレンマに繋がっています。システムまわりまで含めて快適に遊びたいプレイヤーにとっては、この古さは明確なマイナスポイントと言えるでしょう。
18禁要素とのバランスに違和感を覚えるケース
『Angel Halo』は18禁恋愛ADVとして制作されているため、物語の中には性的な描写を含むシーンがいくつか挿入されていますが、その扱い方については評価が分かれるところです。一部のプレイヤーからは、「終末と宗教を扱うシリアスな物語の中に、やや唐突に感じるシーンがある」「全体的なトーンに比べて、一部イベントの演出が浮いて見える」といった違和感が指摘されることがあります。シナリオ側は、キャラクターの心情や関係性の深化を表現する意図で描いているものの、プレイヤー側が“重厚なストーリーADV”として期待している場合、「ここでわざわざこの描写を挟まなくてもよかったのでは」と感じてしまうこともあるわけです。逆に、“18禁ゲームとしての実用性”を期待して購入したプレイヤーにとっては、物語比率が高く、そうしたシーンまでの道のりが長いため、「ストーリーは確かに良いが、抜きゲーとして見ると物足りない」という評価になることも少なくありません。どちらの層にとっても“あと半歩”ズレてしまっている印象があり、テーマの重さゆえに“18禁である必然性”の見せ方が難しかった部分が、悪い意味で表に出てしまったと言えるかもしれません。
情報量の多さによる“とっつきにくさ”
作品世界には、天使や悪魔に関する設定、聖書からの引用を思わせるフレーズ、人類の歴史観にまつわる考察など、さまざまな要素が詰め込まれていますが、その情報量の多さが、初見プレイヤーにとっての“とっつきにくさ”に繋がることがあります。終末ものや宗教モチーフに馴染みがない人にとっては、「固有名詞や概念が一気に出てきて頭に入りづらい」「世界観を理解する前に、ストーリーが進んでしまう」と感じる場面も少なくありません。一応、会話の流れや主人公の視点を通じて説明を補ってはいるものの、すべてを一回で消化するのはなかなか難しく、「気づいたらなんとなく雰囲気で読んでしまっていた」というプレイ体験にもなりがちです。こうした“情報の密度の高さ”は、ハマったときには大きな魅力となりますが、そこに至るまでのハードルとしては確実に存在しており、「シンプルな学園ラブコメを期待していた人には敷居が高い」「肩の力を抜いて遊べる作品ではない」と感じさせてしまう要因にもなっています。
総合的に見た“気軽に人に勧めにくい”性質
これらの短所を総合すると、『Angel Halo』は決して「誰にでも安心しておすすめできる」タイプのゲームではなく、「重いテーマと不完全な救いを受け止める覚悟がある人にこそ刺さる」作品だと言えます。ストーリーの質やキャラクターの魅力は高く評価されながらも、終末観の厳しさ、ルート分岐の分かりにくさ、システムの古さ、18禁要素とのバランスなど、プレイの敷居を引き上げる要素がいくつか重なってしまっているため、「良作だけれど人を選ぶ」「勧めるときに説明が必要」といった評価に落ち着きがちです。裏を返せば、これらのマイナス要素を理解したうえでプレイした人にとっては、他では得がたい体験を与えてくれる一本でもあるのですが、“ライト層からすると近寄りがたい”という事実は否めません。悪かったところをあえて一言でまとめるならば、「作品としての志は高いが、その高さゆえに間口が狭くなってしまっている」という点に尽きるでしょう。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
天使ソフィア――崇高さと不器用さが同居するヒロイン
『Angel Halo』を語るとき、多くのプレイヤーが真っ先に名前を挙げるのが、天使ソフィアでしょう。金髪碧眼の留学生という分かりやすい記号性を持ちながら、彼女の魅力は見た目の華やかさよりも、「崇高な使命を負った存在なのに、ふとした瞬間に覗く不器用さ」にあります。世界の終末を食い止めるために送り込まれた使者として、彼女は常に理性的であろうとし、人類全体の未来を俯瞰して見ようとしますが、日常生活の中では、日本の習慣に戸惑ったり、冗談が通じず周囲からクスっと笑われたり、感情をうまく表に出せずにぎくしゃくしてしまうことも多い。プレイヤーからすると、その“完璧ではない天使”っぷりが、とても人間らしく、守ってあげたくなるポイントになっています。また、主人公・真に対しても、最初は「世界の鍵として監視すべき対象」と距離を置きつつ接しているのに、物語が進むほど「ひとりの少年」として彼を見てしまい、使命と個人的な感情の間で揺れ動くようになる。その心の揺れが丁寧に描かれているため、「天使だから好き」ではなく、「葛藤しながらも前を向こうとするひとりの少女として好きになった」という声が多いのも頷けるところです。彼女のルートでは、世界の行く末と自分の想いのどちらを取るのかという、非常に重い選択が突きつけられますが、その結論がどんなものであっても、プレイヤーの中には「ソフィアならこう決断するだろう」という納得感と、「本当は別の未来もあったかもしれない」という切なさが同時に残り、それが彼女の人気を一段と高めています。
悪魔リリス――奔放さの裏に潜む孤独と一途さ
ソフィアと双璧をなす人気キャラが、魔界からの使者リリスです。初登場時から遠慮のないスキンシップを仕掛け、教室でいきなり真にキスをするなど派手な行動が目立つため、「軽薄で小悪魔的なお色気ヒロイン」という第一印象を持たれがちですが、物語を追うにつれて、その人物像はまったく違う姿を見せ始めます。彼女の奔放さは単なる遊びではなく、「どうせ世界も自分も長くはないのなら、欲しいものには手を伸ばす」という悟りにも似た諦念から来ており、真に向けられた好意もまた、ルシファーの器としての彼だけではなく、“彼自身”に対する強い執着が含まれていることが徐々に見えてきます。悪魔でありながら、真の前では妙に照れ臭い表情をしたり、ふざけた態度でごまかそうとして失敗したりする場面が多く、「本音を素直に言えないのは天使よりむしろリリスのほうでは?」と感じるプレイヤーも少なくありません。さらに、彼女の背景には“神によって拒まれた存在”としての影が落ちており、世界を壊そうとする動機の影には、「自分たちを切り捨てた秩序への反発」や「それでも認められたいという捻れた願望」が透けて見えます。その複雑さを理解したうえでプレイすると、彼女の一見わがままな言動の多くが、「自分の居場所がどこにもないと知っている者の精一杯の足掻き」に見えてきて、ラストに至るまでのすべてのシーンが一気に重みを増します。“悪魔だからこそ、ここまで一途になれる”という逆説的な魅力が、リリスを推しキャラに挙げるプレイヤーを多く生み出している理由でしょう。
常盤まりも――非日常の中に立つ“いちばん身近なヒロイン”
天使と悪魔という派手な存在に挟まれながらも、根強い人気を誇るのが幼馴染の常盤まりもです。彼女は真と同じクラス委員であり、小さい頃からずっと一緒に過ごしてきた相手ということもあって、遠慮のない口調やツッコミが多く、一見するとややきつめの性格に見えるかもしれません。しかし、その裏には「真のことを誰よりも理解している自負」と「それなのに、いつまで経っても“ただの幼馴染”のまま」というもどかしさがあり、ソフィアやリリスが現れたことで自分の立場が揺らぎ始めると、自分でも扱いきれない感情に振り回されてしまいます。プレイヤーからすると、そうした揺れや不安定さが、“いちばん人間らしいヒロイン”として共感を呼ぶポイントになっています。世界の終末だのルシファーの復活だのといった途方もない話が展開される中で、「明日もちゃんと学校があって、真がそこにいてくれるのか」という、極めて現実的で個人的な不安を抱いているのはまりもであり、そこに彼女だけのドラマがあります。また、どのルートを選んだとしても、彼女の存在が真にとっての“原点”として機能する構造になっているため、「エンディングがどうあれ、心のどこかでまりもに戻ってきてほしい」と感じるプレイヤーも多く、物語全体を支える土台のようなキャラクターと言えるでしょう。派手さでは天使や悪魔に一歩譲るものの、「最後に思い出してしまうのはまりもだった」という声が多いのも納得のいくところです。
主人公・日下部真――選ばれた存在でありながら“普通の少年”
恋愛ADVでは主人公が“空気”になりがちですが、『Angel Halo』の真は、その宿命からも性格からも、非常に印象深い主人公として受け止められています。彼はルシファーの生まれ変わりという途轍もない設定を背負っているものの、それを知らされるまでは、クラスメイトをまとめる委員長であり、友人と冗談を交わし、ときには教師に叱られる、ごく普通の高校生です。その普通さがあるからこそ、プレイヤーは真の視点を通じてこの世界を自然に受け入れ、天使や悪魔といった非日常の要素を“異物”としてではなく、“自分の日常に急に紛れ込んできた何か”として体験することができます。真の魅力は、決して完璧ではないけれど、逃げ続けるだけでもない、という中庸さにあります。ショックな真実を突きつけられたときに狼狽し、怒り、時に周囲に当たり散らしてしまう一方で、最終的には自分なりに答えを出そうと足を止めずに進もうとする。その姿勢が、プレイヤーに「この世界の運命は、他でもない“この少年”に託されるべきだ」と思わせてくれるのです。好きなキャラクターとして真を挙げるプレイヤーは、ヒロインたちに感情移入したあと、改めて周回プレイをしたときに「ああ、彼もまた被害者であり、主体でもあるんだ」と実感し、最終的に「この物語の主役はやっぱり真だ」と再評価することが多いようです。
サブキャラクターたちが醸し出す“世界の厚み”
『Angel Halo』の魅力はメインキャラクターだけに留まりません。真の親友ポジションのクラスメイトや、まりもの友人、教師陣など、いわゆるサブキャラクターたちにも、それぞれ小さなドラマが与えられており、その存在が“世界の厚み”を生み出しています。たとえば、真の親友的ポジションにいるクラスメイトは、深刻な悩みを抱える主人公にとってのガス抜き役であり、気取らない男子同士の会話が続くことで、「この世界には、天使や悪魔とはまったく関係ない“普通の高校生たち”もちゃんと生きている」という実感を与えてくれます。また、ドイツ語教師として登場するキャラや、学校外の大人たちも、それぞれの視点から終末に向かいゆく世界を映し出しており、「子どもたちの恋愛と選択」が決して彼らだけの問題ではないことを示しています。プレイヤーの中には、「とあるサブキャラがふと漏らした一言が妙に心に残った」「モブだと思っていたキャラが、あるルートでは重要な役割を担っていて驚いた」といった感想を持つ人も多く、こうした“脇役の光り方”も、好きなキャラクターの話題の中でしばしば語られるポイントです。メインヒロインだけが魅力的なのではなく、画面の端に映るキャラまで「その人なりの人生」を感じさせる描き方がされているからこそ、作品世界全体に愛着がわき、「この世界ごと好きだ」と感じられるのです。
ルートごとに輝き方が変わるキャラたち
プレイヤーによって「好きなキャラクター」が分かれる大きな理由のひとつは、ルートごとにキャラの見え方が劇的に変わる構造にあります。ソフィアルートでは彼女の崇高さと弱さが徹底的に掘り下げられ、リリスルートでは彼女の一途さと破滅的な魅力が前面に出てきますし、まりもルートでは“選ばれなかった側”としての不安や嫉妬が丁寧に描かれます。そのため、一周目で「正直あまりピンとこなかったキャラが、別ルートでは一気に推しになった」という体験がしばしば起こります。ある意味で、『Angel Halo』は“キャラクターカタログ”ではなく、“キャラクターの変化や揺らぎを読むためのADV”と言ってもよく、特定キャラを軸に何度もプレイすることで、「この子はここまでの情報がある状態でこの選択をしているんだな」といった細かな行動原理まで見えてきます。その過程で、プレイヤーは単に「見た目が好き」「性格が好み」という表面的な好きだけでなく、「このキャラのこういう生き方や価値観が、自分の心に響いた」といった、より深いレベルの“推しポイント”を見つけていきます。結果として、「好きなキャラをひとりに絞れない」「周回するたびに推しが増える」と悲鳴を上げつつも嬉しそうに語るプレイヤーが多いのも、本作らしい現象だと言えるでしょう。
プレイヤーの感性が映る“推し”の多様さ
総じて、『Angel Halo』はプレイヤーの価値観や人生経験によって、「誰を好きになるか」が大きく変わるタイプの作品です。世界を救おうと真剣に奔走するソフィアに共感する人もいれば、世界がどうなろうと自分の気持ちに正直であろうとするリリスに惹かれる人もいる。日常のささやかな幸せを守ろうとするまりもを推す人もいれば、物語の中心に立たされながら必死に答えを探す真そのものを、いちばん好きなキャラクターに挙げる人もいます。さらに、サブキャラの視点や台詞から世界を眺めることで、「もし自分がこの世界の住人だったら、どの立場の人間に近いだろうか」と考えたくなる余地もたっぷり用意されています。こうした“推しの多様さ”は、キャラクターひとりひとりにきちんと血が通っていることの証拠であり、プレイヤーが自分自身の感性を反射させながら物語を楽しめる器でもあります。好きなキャラクターを語ることは、そのまま自分がこの作品のどこに心を動かされたかを語ることでもあり、『Angel Halo』が長く語り継がれている理由のひとつは、まさにこの“自分ごととして語れるキャラの豊かさ”にあると言えるでしょう。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
マルチプラットフォーム展開された『Angel Halo』
『Angel Halo』は、当時としては珍しく、PC-9801・FM TOWNS・Windows 95(のちに98)・さらにはMacintoshと、複数のパソコン環境に向けて展開されたタイトルです。発売順で言うと、まず1996年10月17日にPC-98版・FM TOWNS版・Windows 95版がほぼ同時期に登場し、その後1998年2月27日にMacintosh版、2000年9月14日にWindows 95/98向けの廉価版がリリースされました。 同じ『Angel Halo』というタイトルではあるものの、ハードごとの性能・OS・表示解像度・サウンド環境の違いから、プレイ感覚には微妙な差異が生まれています。ここでは、それぞれの版を“同じ物語を別の器で味わう”という視点から、違いと特徴を掘り下げていきます。
PC-9801版――“DOS時代の匂い”を色濃く残した本家的存在
まず最初に語るべきは、PC-9801版です。Activeにとって最後のMS-DOSベース作品とされる本作は、「PC-98エロゲー」という言葉そのものを体現するような存在感を持っています。起動時には、DOS上でゲーム専用の実行ファイルを走らせる、いかにも“レトロPCゲーム”然とした手順が必要で、当時を知るユーザーには、この起動プロセス自体がすでにノスタルジーの一部と言えるでしょう。 表示解像度は一般的なPC-98美少女ゲームと同様の640×400ドット・16色(もしくは256色)相当で、背景や立ち絵は限られた色数のなかで陰影を工夫したドット絵として描かれています。そのため、FM TOWNS版やWindows版と比べると、色の情報量では一歩劣るものの、「線画の力」と「塗りの工夫」によって生まれる硬質な雰囲気が、終末ものADVの空気と非常に噛み合っています。 また、サウンドもFM音源を前提とした実装で、独特のチップチューン的響きが特徴です。シンセ感の強いストリングスやブラスが、天使・悪魔・終末というテーマを少し“無機質な神話”のように感じさせてくれます。CD-DAやPCM音源が主流になった後の世代と比べると、音の厚みはさすがに控えめですが、その分、BGMとテキストの距離が近く、プレイヤーは“音楽を聴く”というより“鳴っている音と一緒にテキストを読む”感覚に近いプレイ体験になります。 動作環境としては、当時のPC-98ユーザーにとっては標準的でしたが、現代から見るとフロッピーや古いHDD・CRTディスプレイ・FM音源ボードなど、すべてがレトロパーツの集合体であり、その環境ごとプレイ経験として記憶に残る版と言えます。「あの頃のPC-98文化の中で『Angel Halo』を味わった」という体験込みで作品を語りたいコアユーザーには、PC-98版こそ“本家”と感じられるでしょう。
FM TOWNS版――グラフィックとサウンドが一段リッチな“AV機寄り”の体験
同じく1996年にリリースされたFM TOWNS版は、マルチメディア指向のハードらしく、グラフィックやサウンド面でPC-98版より一段リッチな表現を楽しめるバージョンです。CD-ROMドライブを標準搭載し、256色表示やCD-DA再生能力を備えていたTOWNSのスペックを活かし、イベントCGの色数はPC-98版より豊かに、グラデーションも滑らかに表示されます。 キャラクターデザインや構図そのものは基本的に共通ですが、色合いのニュアンスが変わることで印象がかなり違って見え、“夜の教会”“夕焼けの校舎”など光と影のコントラストが重要なシーンでは、その差が特に強く感じられます。終末感を漂わせる空や、ステンドグラスを通した光の表現などが、TOWNSの表示能力によって少し“映画的”に感じられるのです。 サウンド面でも、CD-DAもしくはPCM音源によるBGMが採用されているため(作品によって実装の細部は異なりますが)、PC-98版のFM音源と比べると音の厚みや残響感が明らかに増しています。特に、荘厳な雰囲気を演出するBGMが多い本作において、リバーブの効いたコーラス風サウンドは天使・悪魔のモチーフと非常に相性が良く、「TOWNS版で遊ぶと音楽の印象がガラッと変わる」と語るプレイヤーも少なくありません。 システム面では、ベースになっているゲームエンジンはPC-98版と近いため、操作感覚自体は大きく変わりませんが、CD-ROMからの読み込みに伴う一瞬の待ち時間が挟まるシーンもあり、「音と絵が豪華になった代わりに、若干ロードが気になる」という感想もあり得ます。それでも、総じて「最も演出リッチなレトロ版」として、FM TOWNSユーザーにとっては誇りの一本と言えるでしょう。
Windows 95/98版――マウス操作と汎用性を備えた“実用派”
1996年の時点で同時に登場したWindows 95版、そして2000年の廉価版として再パッケージされたWindows 95/98版は、当時急速に普及しつつあったWindows環境向けの“主力版”と言ってよい存在です。従来のPC-98/TOWNSユーザーだけでなく、“DOSはわからないけどWindowsなら使っている”層にも手に取ってもらえるよう意識されたバージョンであり、インストーラを実行しておけばアイコンからすぐ起動できるという手軽さが、大きなポイントでした。 マウス主体の操作に最適化されており、テキスト送りや選択肢の選択、メニュー呼び出しなどもクリック一つで完結します。キーボードだけで遊ぶことも可能でしたが、「片手にマウス、もう一方の手は飲み物」といった現代ADVに近いプレイスタイルがとれるのは、Windows版ならではの利点でした。 グラフィック面では、PC-98・TOWNS版の素材をベースにWindows用に調整されており、環境によっては解像度や表示色数をOS側の設定に合わせて柔軟に扱えることから、「当時としてはかなり綺麗に見えた」という声も多く聞かれます。TOWNS版ほど“ハード専用チューン”ではないものの、可搬性と見やすさのバランスに優れた“標準版”と言えるでしょう。 サウンドは、環境のMIDI音源やPCM再生に依存する部分もあるため、ユーザーのサウンドカードやドライバ設定によって印象が変わることもありましたが、その分、自分のPCの音環境をチューニングする楽しみがあった時代でもあります。テキストスキップや既読制御など、当時としては標準的なADV機能を備えており、「今からレトロ環境を用意して遊ぶなら、最も手を出しやすいのはWindows版」と評されるゆえんになっています。
Macintosh版――当時としては貴重だった“Mac向け18禁ADV”
1998年に登場したMacintosh版は、当時としてはかなり貴重な存在でした。というのも、90年代の18禁PCゲーム市場はほぼWindowsとPC-98系列が中心で、Macユーザーが遊べるタイトルは非常に限られていたからです。Mac版『Angel Halo』は、そうした“取り残されがちだった”Macユーザーにとって、数少ない本格ADVの一つとして受け止められました。 基本的なシナリオやイベント構成は他機種版と同一ですが、UIはMac OSのインターフェースガイドラインに合わせて調整されており、ウィンドウの扱い方やメニューのレイアウトなどに“Macらしさ”が感じられる仕様になっています。操作系も、マウス主体かつ直感的で、Macユーザーが普段使っているアプリケーションに近い感覚でプレイできるよう意識されていました。 グラフィックやサウンドは、ハードの性能とOSの仕様に応じてWindows版から移植された形ですが、フォントレンダリングや色管理など、Mac側の特徴も相まって、同じCGでも微妙に色合いや雰囲気が違って見えるという声もあります。Windows環境に比べるとプレイヤー人口は少なかったものの、「Macで遊べた数少ない終末ADV」として印象深く記憶しているファンもおり、マルチプラットフォーム展開の幅広さを象徴するバージョンと言えるでしょう。
廉価版Windows 95/98版――“手に取りやすさ”を重視した再パッケージ
2000年9月14日に発売された廉価版Windows 95/98版は、内容的には従来のWindows版をベースとしつつ、価格を抑え、当時のPCゲームショップで手に取りやすいパッケージとして再登場したものでした。収録されているシナリオやイベント自体に大きな違いはありませんが、「名作ADVを改めて掘り起こす」という位置づけの再販であり、初回版を逃していたユーザーにとって、比較的安価に『Angel Halo』へアクセスできるチャンスとなりました。 この廉価版は、OS環境としてWindows 95/98を前提にしているため、当時の“ONU付きADSL普及期の標準的デスクトップPC”で問題なく動作することが想定されていました。CD-ROM一枚で完結し、インストール手順もより簡略化されていたため、「中古市場で比較的見つけやすく、プレイ環境さえ整えば今でも現実的な選択肢になり得る版」と見なされています。 もっとも、現在から見るとWindows 95/98そのものがすでにレトロOSとなってしまっており、互換モードや仮想環境を駆使しなければ動かしづらいのは他版と同様です。それでも、「最も後発で、比較的バグ修正や安定性の面でもこなれている可能性が高い」という意味で、“実用的に狙うなら廉価版を探す”というコレクター的な視点も存在します。
どの版で遊ぶか――ハードごとの“味”の違い
こうして見ていくと、『Angel Halo』は単に同じゲームを複数機種に移植しただけではなく、プラットフォームごとに微妙に異なる“味”が出ているタイトルであることが分かります。 – PC-9801版であれば、DOSベースの起動からFM音源BGM、16色ドット絵と、すべてが“レトロPCゲームらしさ”に直結しており、当時の空気を丸ごと味わいたい人向け。 – FM TOWNS版は、よりリッチなグラフィックとサウンドにより、“静かな終末映画”のような雰囲気を強めてくれる演出特化型。 – Windows 95/98版は、マウス操作と汎用性に優れ、実用的なプレイ環境と標準的な快適さを兼ね備えたバランス型。 – Macintosh版は、希少価値の高い“Macで遊べる終末ADV”として、当時のMacユーザーにとって特別な一本。 – 廉価版Windows 95/98は、後発ならではの入手性と安定性を期待できる、“再評価のための入り口”となる版。 同じシナリオであっても、音の鳴り方や画面の質感、インターフェースの癖が異なることで、プレイ時の記憶はかなり変化します。どのプラットフォームでプレイしても物語そのものの核は変わりませんが、「あのハードで遊んだ」という思い出込みで語られることが多いのは、マルチプラットフォーム展開された作品ならではの面白さだと言えるでしょう。
[game-10]
●同時期に発売されたゲームなど
★雫 ― ホラー路線へ踏み出したLeafの問題作
:★雫(しずく) 販売会社:Leaf 販売された年:1996年(PC-98版およびWindows 95版) 販売価格:Windows95版 定価6,380円(税込)/PC-98版 定価9,680円(税込) 具体的なゲーム内容: 「雫」は、学園を舞台にしたホラー・サスペンス色の強いビジュアルノベルで、後の美少女ゲーム史でもたびたび語られる“電波系”作品の源流のひとつとされます。プレイヤーは平凡な男子学生として、学園内で続発する不可解な事件や、人体実験の影を追いながら、複数のヒロインと関わっていきます。選択肢によって残酷な結末や精神的に追い詰められる展開に分岐し、単なる恋愛ADVの枠を超えた重いテーマ性が特徴です。テキスト量が多く、BGMと静かな画面演出でじわじわと恐怖を積み上げていくスタイルは、のちの「サウンドノベル」「ビジュアルノベル」の定番手法にも大きな影響を与えました。Angel Haloと同じ1996年に登場し、「恋愛ADVでここまでシリアスで救いの少ない物語を描ける」という可能性を示した点で、同時期の空気感を代表する一本と言えます。
★痕 ― 学園ホラーと恋愛ドラマを融合させた“後味の残る”名作
:★痕 -きずあと- 販売会社:Leaf 販売された年:1996年(PC-98/MS-DOS/Windows95) 販売価格:初回版 8,800円(税抜)ほか(Windows版) 具体的なゲーム内容: 「痕」は「雫」に続いてLeafが発売したホラーテイストのビジュアルノベルで、地方の旧家を舞台に、“血筋”“呪い”“宿命”といったキーワードが重くのしかかる作品です。主人公は父親の死をきっかけに親戚の家に身を寄せ、そこで暮らす四姉妹と奇妙な共同生活を始めますが、夜ごとに起こる怪異や残酷な事件に巻き込まれていきます。ゲームシステムはシンプルなテキストADVながら、選択肢の積み重ねによって姉妹たちの運命やエンディングが大きく変化し、どのヒロインを救えるか・救えないかがプレイヤーの心理に強く響きます。Angel Halo同様、人間ドラマと宗教・超自然要素を組み合わせた作風で、「重い設定+美少女キャラ」という90年代後半の美少女ゲームトレンドを象徴する一本です。
★Pia♥キャロットへようこそ!! ― ファミレスを舞台にした王道ラブコメSLG
:★Pia♥キャロットへようこそ!! 販売会社:カクテル・ソフト(F&C) 販売された年:1996年(PC-98/Windows95版) 販売価格:PC-98版 8,580円(税込)など 具体的なゲーム内容: 「Piaキャロ」は、ファミリーレストラン「Pia♥キャロット」でアルバイトをする主人公と、従業員の女の子たちとの恋模様を描いた恋愛シミュレーション+ADVです。シフト表を組み、接客の出来やイベント発生条件を意識しながら日々のスケジュールを管理する“バイトSLG”要素が盛り込まれており、どのヒロインと接する時間を増やすかによって物語が変化します。多彩な制服パターンや、夏らしいリゾート風の雰囲気、明るいBGMといった“ポップで楽しい”ビジュアルが支持され、シリアス路線が多かった当時の18禁ゲームの中で、「軽快なラブコメ」として強い存在感を放ちました。終末と宗教をテーマにしたAngel Haloと比べると、日常寄りで遊びやすい作品ですが、“アルバイト先での恋愛”というシチュエーションの定番化に大きく貢献したタイトルです。
★この世の果てで恋を唄う少女YU-NO ― マルチタイムトラベルADVの金字塔
:★この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 販売会社:elf(エルフ) 販売された年:1996年(PC-98版/のちにWindows版へ移植) 販売価格:PC-98版 定価10,780円(税込) 具体的なゲーム内容: 「YU-NO」は、並行世界と時間移動をテーマにしたアドベンチャーで、プレイヤーは主人公・有馬たくやとして、謎の装置「Reflector Device」を使いながら複数の時間軸とルートを行き来します。画面上の分岐マップと“宝玉”システムによって、いつでも任意の分岐地点に戻れる構造は当時としては画期的で、「時間を巻き戻し、別の選択肢を試す」プレイ感覚を強く印象づけました。物語的にも、家族の秘密や異世界の文明、世界の構造そのものに迫る壮大な展開が用意されており、恋愛要素とSF要素を高いレベルで両立させた作品です。Angel Haloが“終末の京都”を舞台に宗教的モチーフで世界の行く末を語るのに対し、YU-NOは“時間と世界の構造”から人間ドラマに迫っていくタイプで、どちらも「美少女ゲームでここまでスケールの大きな話ができる」とプレイヤーに強烈な印象を残しました。
★鬼畜王ランス ― 地域制圧シミュレーションで描くIF戦記
:★鬼畜王ランス 販売会社:ALICESOFT(アリスソフト) 販売された年:1996年(Windows95向け) 販売価格:初回版 8,500円(のちの普及版は定価9,350円など) 具体的なゲーム内容: 「鬼畜王ランス」は、RPGシリーズ「ランス」のIFストーリーを大規模な地域制圧型シミュレーションとして描いた外伝的作品です。プレイヤーは主人公ランスを中心に、人間や魔物、各国の勢力が入り乱れる大陸を舞台に、戦略マップ上で部隊を動かしながら領土を拡大していきます。イベントやルート分岐が膨大で、「どのキャラクターを仲間にするか」「どの勢力と敵対・同盟するか」によってエンディングが大きく変わるのが魅力です。ラフなギャグや過激な描写を含みつつも、世界観や歴史設定は非常に緻密で、“世界丸ごとを弄ぶ”ような遊び心が当時のPCユーザーから絶賛されました。シナリオ重視のAngel Haloとはジャンルが違いますが、“PCでしかできない大ボリュームの物語体験”という点では共通しており、同じ1996年の象徴的タイトルとして並び称されることも多い作品です。
★同級生2 ― 夏休みの三角関係を描く恋愛ADVの決定版
:★同級生2 販売会社:elf(エルフ) 販売された年:1995年(PC-98版)、1997年(Windows95版)など 販売価格:Windows95版 定価10,780円(税込) 具体的なゲーム内容: 「同級生2」は、オープンなマップと自由度の高いスケジュール管理が特徴の恋愛アドベンチャーです。夏休みの一定期間を舞台に、プレイヤーは街中を歩き回り、時刻や曜日、天候に応じて様々なヒロインとイベントを重ねていきます。前作「同級生」で確立した“期間限定・自由行動型恋愛ゲーム”をさらに磨き上げ、ヒロインごとの細かなフラグ管理や複雑な三角関係、切ないストーリーが話題を呼びました。Angel Haloと同時代に遊んでいたユーザーにとっては、「同級生2」で日常寄りの青春恋愛を味わい、「Angel Halo」で重い終末ドラマを堪能する、といった遊び分けができたのも印象的です。
★下級生 ― 学園+街歩きで“日常の恋愛”を丁寧に描く
:★下級生 販売会社:elf(エルフ) 販売された年:1996年(PC-98版)、1998年(Windows95版) 販売価格:Windows95版 定価10,780円(税込) 具体的なゲーム内容: 「下級生」は、主人公が“下級生のヒロインたち”と少し背伸びした恋を育んでいく恋愛ADVです。学校や街中を移動しながら、時間帯や場所ごとに異なるイベントを拾っていくシステムは「同級生」シリーズと共通ですが、より等身大の青春感や、まったりとした日常描写が重視されています。クラスメイトとしての悩みや家庭の事情など、ヒロインごとの背景が丁寧に掘り下げられており、シリアスなドラマから甘酸っぱいエピソードまで幅広いトーンを楽しめます。世界の終末と天使・悪魔の対立を描くAngel Haloとは対照的に、“ごく普通の学園生活の中での恋愛”にフォーカスした作品で、プレイヤーの気分によってシリアスと日常を行き来できる、同時代ならではのラインナップを形成していました。
★To Heart ― 日常系ラブコメ路線を決定づけた学園ビジュアルノベル
:★To Heart 販売会社:Leaf 販売された年:1997年(PC版) 販売価格:PC版 5,800円(税抜) 具体的なゲーム内容: 「To Heart」は、学園生活の中で少しずつ関係が深まっていく“日常系ラブコメ”路線を強く印象づけたビジュアルノベルです。主人公は高校生で、幼なじみのヒロインを中心に、ロボット少女や先輩・後輩など多彩なキャラクターたちと何気ない日常を過ごしていきます。派手な事件や惨劇はほとんど起こらず、日常のちょっとした会話や、季節の移ろいの中で少しずつ心の距離が縮まっていく過程が丁寧に描かれました。その“温度の低いドラマ”が逆に多くのプレイヤーの心を掴み、家庭用ゲーム機やアニメへのメディアミックス展開にも繋がります。終末や宗教観を正面から扱うAngel Haloと比べると非常に穏やかな作風ですが、「90年代後半の恋愛ゲームブーム」を語る上で欠かせない一本であり、同時期のPCゲーム文化の厚みを感じさせる存在です。
★WHITE ALBUM ― 冬の恋愛と三角関係を描く大人びたラブストーリー
:★WHITE ALBUM 販売会社:Leaf 販売された年:1998年(Windows95版) 販売価格:初回版 メーカー希望小売価格8,800円前後/定価表記9,680円(税込)など 具体的なゲーム内容: 「WHITE ALBUM」は、冬の街を舞台に人気アイドルとその恋人、そして周囲の人間関係が絡み合う恋愛ドラマです。主人公は、売れ始めたアイドル歌手の彼氏という立場であり、忙しさからすれ違っていく二人の関係や、そこに入り込んでくる別の女性たちとの微妙な距離感が描かれます。仕事とプライベートの両立、芸能界の厳しさ、嫉妬や孤独といった大人寄りのテーマが前面に出ており、「学生の日常ラブコメ」が中心だった当時の作品群の中でひときわ落ち着いたトーンを持つのが特徴です。Angel Haloもまた、若い登場人物たちが世界の終末と自分自身の運命の間で揺れる“重めのドラマ”を描いており、同じくLeaf作品である「WHITE ALBUM」と合わせてプレイすると、90年代終盤の恋愛ADVがどれだけ多彩な方向性を模索していたかがよく分かります。
★EVE burst error ― 二人の主人公で事件の真相に迫るサスペンスADV
:★EVE burst error(イヴ・バーストエラー) 販売会社:シーズウェア(PC-98版/Windows版) 販売された年:1995年(PC-98版)、のち各種PC・コンシューマに移植 販売価格:後年のWindows98/SE用DVD-ROM版 定価9,680円(税込)など 具体的なゲーム内容: 「EVE burst error」は、私立探偵・天城小次郎と、諜報機関に所属する女エージェント・法条まりな、2人の主人公の視点を切り替えながら巨大な陰謀に迫るサスペンスアドベンチャーです。プレイヤーは任意のタイミングで主人公を切り替えることができ、一方の行動がもう一方のルートに影響を与える“クロスオーバー構造”が高く評価されました。銃撃戦やテロ事件、国家レベルの陰謀が登場するハードボイルドな世界観と、ヒロインたちとの人間関係がバランスよく配されており、美少女ゲームファンと本格ミステリ・サスペンス好きの両方から支持を集めました。宗教と終末思想を軸にしたAngel Haloと同時代に、こちらは“現代の裏社会と国際的陰謀”を題材にしており、90年代PCゲームのバラエティ豊かなストーリーテリングを象徴する一本と言えるでしょう。
このように、「Angel Halo」と同じ時期には、ホラー寄りの「雫」「痕」、日常ラブコメの「To Heart」、壮大なSFの「YU-NO」、戦略SLGの「鬼畜王ランス」など、ジャンルもテーマもまったく異なる多くの作品がPC市場を賑わせていました。プレイヤーは、その日の気分や好みに応じて“終末の京都で天使と悪魔の戦いに巻き込まれるAngel Halo”を選んだり、“時間旅行SFのYU-NO”や“ファミレスバイトのPiaキャロ”を遊んだりと、非常に贅沢なラインナップの中から作品を選べたわけです。Angel Haloを語るとき、こうした同時期の代表作も合わせて眺めてみると、当時のPCゲーム文化の厚みや空気感がより立体的に浮かび上がってきます。
[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 英雄伝説IV 朱紅い雫[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004170m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチ/5インチソフト RPGツクール -Dante98-(ログインDISK&BOOKシリーズ)[3.5インチ/5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006306m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト カード型データベース アシストカード[アシストカルク体験版付][3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8922/155009819m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アンジェラス 〜悪魔の福音〜[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4538/155005895m.jpg?_ex=128x128)