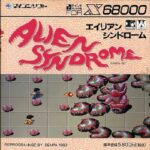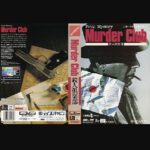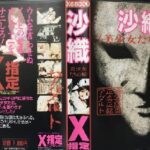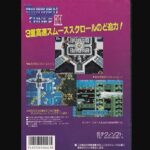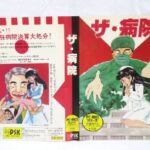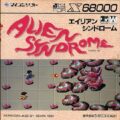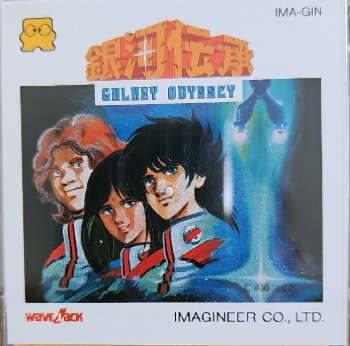瑞起 FZ戦記アクシス・グラナダ PACK [ZKSW-014-W1]
【発売】:ウルフ・チーム
【対応パソコン】:X68000、Windows
【発売日】:1990年10月10日
【ジャンル】:アクションシューティングゲーム
■ 概要
ウルフ・チームらしさが凝縮されたクォータービュー戦記アクション
『FZ戦記アクシス』は、1990年10月10日にウルフ・チームがシャープX68000向けに送り出したメカアクション・シューティングで、タイトルに付いた「FZ」は、同社の戦場アクションシリーズ『ファイナルゾーン』から続く系譜を示しています。プレイヤーは新型陸戦兵器「NAP(New Age Powered-Suits)」のパイロットとなり、要塞アクシスへの決死の侵攻作戦に身を投じることになります。画面は斜め上から戦場を見下ろす「クォータービュー」と呼ばれる疑似3D視点を採用しており、シューティングとアクションが高い密度で混ざり合った内容が特徴です。 本作は当時、X68000専用タイトルとして開発されましたが、ほぼ同時期にメガドライブ版も登場し、その後はWindows向けのダウンロード配信(プロジェクトEGG)や、現行機での復刻版など、長い年月をかけてさまざまなプラットフォームに姿を変えながら生き残ってきた作品です。
物語の舞台――NAPと要塞アクシスを巡る近未来戦争
物語の舞台は、巨大兵器や核戦争による大規模な力押しが成立しなくなった近未来。高性能な軍事衛星によって、大軍の動きは瞬時に監視・制御されるようになり、戦争は「少数精鋭の機動部隊が局地戦で要所を制圧する」というスタイルへ移行します。その新しい時代の象徴が、パワードスーツ型の陸戦兵器「NAP」です。 プレイヤーキャラクターであるハワード・ボウイは、外国人部隊「アンデッド」に所属する兵士で、彼に下された命令はほとんど“死刑宣告”にも等しい無謀な作戦。強固な防衛網に守られた巨大要塞アクシスへ単独に近い形で侵入し、要塞の中枢を破壊せよという内容です。物語自体はゲーム中のテキストやデモ演出で簡潔に語られるだけですが、凄惨な戦場に送り込まれた一兵士の視点を通して、寡黍な描写の中にもハードな戦争ドラマを感じさせます。
ジャンルとゲームデザインの骨格
『FZ戦記アクシス』は、ジャンルとしては「クォータービュー型のアクションシューティング」に分類されます。画面奥へ進む縦スクロールでも横スクロールでもなく、斜め上から見下ろした戦場を、NAPを操って8方向へ自由に移動しながら敵を撃破していくスタイルです。方向キーを連続入力することによって高速で滑るように移動できる「ローラーダッシュ」機能を備えており、単に撃つだけでなく、敵弾の雨をくぐり抜ける軽快なフットワークも求められるのが特徴です。 プレイヤーが扱える武器は非常に多彩で、全体としては20種類前後存在し、そのうち14個までを同時に装備可能という設計になっています。それぞれの武器には攻撃手段というだけでなく「シールド」のような役割も設定されており、装備している数だけ敵弾を防いでくれるという独特のシステムが導入されています。このため、単に火力の高い兵装を選ぶだけでなく、「どの武器をどれだけ積むか」という構成そのものが、防御力や生存率に直結する点が、本作ならではの戦術性になっています。
ステージ構成とミッションの流れ
ゲームは大きく分けて複数のミッション(ステージ)で構成されており、家庭用版の説明では「7つの個性豊かなステージ」と紹介されています。一つ一つのステージは、敵陣地への侵入、市街地での銃撃戦、要塞内部の突破など、シチュエーションが明確に分かれており、その最後には巨大なボスユニットが待ち構えています。 ステージの進行は基本的に一本道ですが、敵の配置やギミックはかなり密度が高く、油断していると一瞬で集中砲火を浴びて撃破されます。時には遮蔽物を利用し、時にはローラーダッシュで一気に距離を詰め、ボス戦では敵の攻撃パターンを見極めながら、装備している武器の特性を活かして攻め方を組み立てていく必要があります。単純に敵を全滅させるだけでなく、いかに被弾を抑えつつ優位なポジションを確保するかがステージ攻略のキモと言えるでしょう。
X68000が生み出すグラフィック表現
開発プラットフォームであるX68000は、当時のパソコンとしてはトップクラスのグラフィック性能を誇っており、本作もその能力を存分に活かしたビジュアルで話題となりました。キャラクターやNAPのスプライトは比較的大きく描かれており、クォータービューながらも“重厚なメカが戦場を駆ける”感覚がしっかりと伝わってきます。 背景には軍事基地や都市、要塞内部など、バリエーション豊かなマップが用意され、パネル状の床や装甲板のディテール、施設の陰影表現によって、平面のドット絵でありながらも立体感のある戦場が再現されています。X68000ならではの高解像度画面により、敵ユニットや爆発エフェクト、NAPのローラーダッシュ時の残像など、細かな描写までくっきりと表示されるため、アーケードゲームに迫る臨場感を家庭で味わえるという点も、本作の大きな魅力でした。
音楽とサウンド――初期・桜庭統サウンドの魅力
サウンド面では、ウルフ・チーム作品でおなじみの桜庭統を中心に、複数のコンポーザーが参加しています。海外向けの解説では、桜庭統に加えて、宇野正明や塩生康範、塩生康範の効果音制作などの名前が挙げられており、のちにゲーム音楽シーンで存在感を示す作曲家たちが、すでにここで実験的なサウンドを展開していたことが分かります。 X68000版では本体内蔵のFM音源だけでなく、外部MIDI音源にも対応しており、ローランドのMT-32やCM-32Lなどを接続することで、FM音源とは雰囲気の異なる、よりリッチなサウンドでプレイできるのもポイントです。さらにCM-64のPCM音源にも対応しており、当時としてはかなり贅沢な音響環境を実現していました。ゲーム音楽ファン向けにはサウンドトラックCDも発売されており、ゲーム中のBGMに加えバンドアレンジ版が収録されるなど、音楽単体でも評価の高いタイトルとなっています。
シリーズ内での位置づけと系譜
『FZ戦記アクシス』は、ウルフ・チームが手がけた戦場アクションシリーズ「ファイナルゾーン」の一作であり、『ファイナルゾーン ウルフ』『ファイナルゾーンII』に続く3作目にあたるとされています。シリーズ全体の共通点として、「少数精鋭の兵士が苛烈な戦場に投入される」というハードな世界観や、シビアな難易度設定が挙げられますが、本作では特にクォータービューとNAPという要素によって、“パイロット視点の戦記物”という色合いがより強く打ち出されています。 シリーズとしてのストーリー的な直接のつながりは薄く、各作品ごとに独立した物語を描いていますが、「FZ」の頭文字が示す通り、戦場の苛烈さや兵士の悲哀をテーマにした作品世界は一貫しており、『FZ戦記アクシス』もその流れの中で、また一つ異なるアプローチを提示した作品と言えるでしょう。
現代における復刻と評価
発売から長い年月が経った現在でも、『FZ戦記アクシス』はさまざまな形でプレイ可能な環境が整えられてきました。PC向けにはレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」でX68000版やメガドライブ版が配信されており、X68000タイトルの復刻を進める「X68000 Z」向けには、『グラナダ』との2本立てパッケージも登場しています。 さらに近年では、PS4/PS5やNintendo Switch、Xboxシリーズ、そしてPC(Steam)などの現行機向けに復刻版が配信され、巻き戻しやセーブ機能、画面フィルタやギャラリー、チート機能といった利便性の高い要素も追加されています。これにより、当時のハードを持っていなくても、オリジナル版の手触りを大きく損なうことなく遊べるようになり、往年のファンはもちろん、当時を知らない世代が本作に触れる機会も増えています。 このように、『FZ戦記アクシス』は単なる一時代のX68000用アクションにとどまらず、シリーズ作品として、そしてクォータービュー・メカアクションの佳作として、現在まで受け継がれているタイトルだと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの魅力とは?
クォータービューだからこそ味わえる「立体感のある戦場」
『FZ戦記アクシス』の魅力としてまず挙げたくなるのが、クォータービュー(斜め見下ろし視点)ならではの立体感です。真正面からの縦スクロールでも、横一直線のサイドビューでもなく、斜め上から戦場をのぞき込むような画面構成によって、戦車や歩兵、基地設備がすべて「空間の中に存在している」という感覚が強く伝わってきます。NAPがローラーダッシュで前進すると、床パネルの模様が斜め方向に流れ、敵弾は扇状の軌道を描きながらこちらに迫ってくる──こうした動きの一つ一つが、従来の平面的なシューティングとは異なる“奥行き”を感じさせてくれます。敵との距離感も「上下左右」だけではなく「斜め前方・斜め後方」といったニュアンスを含んでおり、わずか数マスの位置取りの違いが生死を分けることも多く、プレイヤーは自ずと戦場全体のレイアウトを立体的に把握しながら行動するようになります。この空間認識を駆使した立ち回りが、他の見下ろし型シューティングとはひと味違う“戦場を渡り歩いている感覚”を生み出しているのです。
ローラーダッシュが生むスピード感と緊張感
操作系の中でも特に印象に残るのが、方向キーを素早く二度倒すことで発動するローラーダッシュです。一歩ずつ歩くような通常移動に対し、ローラーダッシュは床の上を滑るように高速で移動できるため、敵の包囲網をかいくぐったり、一気に懐へ潜り込む攻撃的な動きが可能になります。しかし、速いということはそれだけ制御がシビアになるということでもあり、壁や障害物にぶつかれば一瞬の隙が生まれ、周囲から集中砲火を浴びかねません。リスクとリターンが表裏一体になっているため、プレイヤーは「ここは危険だがダッシュで抜けるべきか」「あえて歩いて慎重に進むか」という判断を常に迫られます。思い切ってローラーダッシュに踏み切り、敵の弾幕を紙一重で抜けた瞬間の「間一髪で生き延びた」という高揚感は、本作ならではの醍醐味と言えるでしょう。慣れてくると、ダッシュで敵の背後に回り込んでからショットを叩き込む、斜め方向へ滑り込みつつ弾を撃ち続けるなど、アクションゲーム寄りのダイナミックな立ち回りも楽しめるようになり、プレイスタイルそのものに“スピード感の美学”が宿っていきます。
武器=防御資源という独自システムの面白さ
『FZ戦記アクシス』の武器システムは、単なる攻撃手段の選択にとどまらず、防御力そのものを構成する要素として機能している点がユニークです。武装スロットには複数の特殊兵器を装備できますが、その数がそのまま「シールドの耐久力」に直結しており、敵弾を受けるたびにストックしている武器が一つずつ消費されていきます。つまり、火力重視で高威力の兵器ばかり詰め込めば、短期決戦には強くなるものの、被弾に対して非常に脆くなってしまいます。一方で、あえて扱いやすい汎用武器や補助的な兵装を多めに積んでおけば、防御層が厚くなり、多少のミスや囲まれた状況でも持ちこたえやすくなります。この「装備構成=ライフ管理」という設計は、単純に強い武器をかき集めれば良いという発想を否定し、「このステージ構成なら何を何個積むべきか」というビルドの工夫そのものを楽しみの一つに変えてくれます。ステージを進めるたびに、「さっきの構成ではここが弱かったから、次はこの武器の比率を増やしてみよう」と考えて試行錯誤を重ねる過程が、そのまま本作のリプレイ性・やり込み要素へとつながっていくのです。
ステージごとに変化する戦場演出とボス戦の迫力
クォータービューの画面構成を活かしたステージ演出も、本作の魅力を語る上で欠かせません。要塞外縁部の荒れ地から始まり、軍事施設を思わせる金属質なフロア、都市部を舞台にした市街戦、要塞内部の複雑な機械構造など、各ステージはテーマが明確に分かれており、進むたびに「次はどんな戦場が待っているのか」という期待感を煽ってくれます。障害物の配置や高低差を示唆する描写も巧妙で、ただ敵を倒すだけでなく、どのルートを選べば安全か、どこで一気に突破を図るかといった位置取りの選択も攻略の一部になっています。ステージの最後には大型のボスユニットが登場し、画面のかなりの面積を占めるサイズでNAPへ迫ってきます。大きくうねる砲塔、広範囲をなぎ払うビーム、画面端から端まで飛び交うミサイルなど、攻撃のバリエーションは豊富で、一つ一つのパターンを見切りながら隙を突いて反撃する戦いは緊迫感に満ちています。ボスの弱点位置や攻撃のタイミングに合わせて武器を切り替え、ローラーダッシュを駆使して死角に入り込むといった一連の流れが決まったときの達成感は、ステージクリアという単なる区切り以上のカタルシスをもたらしてくれるでしょう。
X68000のポテンシャルを活かしたグラフィックと演出
ハードウェアの性能を引き出したグラフィックも、プレイヤーを惹きつけるポイントです。高解像度の画面に描かれたNAPや敵兵器は、細かいラインや陰影によってメカとしての重量感が表現されており、「自分が今操っているのはただの人間キャラではなく、数トンはありそうな重装パワードスーツなのだ」という感覚を覚えさせてくれます。爆発エフェクトのスプライトや、被弾時に散る火花、地形の一部が破壊される演出なども、ドット絵でありながらきめ細かく作り込まれており、戦場全体が常に“動いている”ような印象を与えてくれます。オープニングデモにディスク1枚分をまるごと割り当てているというエピソードが象徴するように、ウルフ・チームは本作において演出面にも相当な力を注いでおり、ゲーム開始前からプレイヤーのテンションを高めてくれるのも魅力です。ストーリーや世界観の描写こそテキスト量は多くありませんが、そのぶんビジュアルとBGMが雰囲気作りを担っており、短い導入でも「これはただのロボットアクションではなく、一つの戦記ドラマなのだ」と感じさせてくれます。
重厚なBGMが紡ぐハードSF戦記の空気感
『FZ戦記アクシス』のサウンドは、ハードな近未来戦場を舞台にしたゲームの雰囲気を、音楽の力で一段と引き上げています。ステージ開始時には緊張を煽るイントロが流れ出し、戦闘が激しくなるにつれてリズムが強調され、シンセベースやドラムが前面に出てくる構成は、まるで戦場へ送り出される兵士の高鳴る鼓動を音にしたかのようです。一方で、ボス戦ではより攻撃的でスピード感のあるフレーズに切り替わり、「今まさに決戦の真っ只中にいる」という実感を強く与えてくれます。ステージごとの曲調もバラエティに富んでおり、冷たい金属で構成された基地内ではクールな雰囲気のナンバーが、荒涼とした地表では重々しい雰囲気の一曲が流れるなど、ビジュアルとサウンドがセットになって場面の空気感を演出してくれます。また、MIDI音源を使用した際には、FM音源とは異なる質感の音が鳴り響き、同じステージであってもまるで違うゲームのように感じられるのも贅沢なポイントです。「今日はFM音源で、明日はMIDIで」といった楽しみ方もでき、音楽好きのプレイヤーにとってはそれだけでも本作を遊ぶ理由になるほどの魅力を備えています。
高難度ゆえの達成感とリプレイ性
本作は決して易しいゲームではなく、むしろ当時の水準で見てもかなり手応えのある部類に入ります。しかし、その高めの難易度こそがクリアしたときの達成感を強くし、何度も遊びたくなる原動力にもなっています。序盤のステージから敵の攻撃は容赦なく、初見ではあっという間に武器ストックを削り切られることも珍しくありません。それでも少しずつ敵の出現パターンや地形のクセを覚え、どこでローラーダッシュを使うべきか、どのタイミングで火力を集中させるべきかが身体に染み込んでくると、以前は無理に思えた場所を滑るように突破できるようになり、「自分の腕前が確かに上がっている」という実感が得られます。また、装備構成の自由度が高いため、「前回は汎用武器多めだったけれど、今回は高威力兵器寄りで速攻を狙ってみよう」といった形でプレイスタイルを変えて再挑戦できるのも、リプレイ性を高める要因です。単にクリアするだけでなく、「いかに少ない被弾で進めるか」「どれだけ短い時間でボスを倒せるか」といった自己ベスト更新を目標に遊ぶことで、長く付き合える一本になっています。
メカアクションと戦記ドラマが同居する独特の世界観
最後に挙げたい魅力が、「メカアクションの爽快感」と「戦記物としてのハードさ」が同時に存在している独特の世界観です。プレイヤーは高性能NAPを操り、多彩な武器を駆使して敵をなぎ倒していきますが、物語の背景には政治的思惑や軍事力の均衡、兵士の命が軽く扱われる冷徹な現実がひっそりと横たわっています。ハワード・ボウイたち「アンデッド」は、どこか使い捨てのコマのような立場に置かれており、プレイヤーは彼らの視点で要塞アクシスの奥深くへ進むうち、「自分は何のために戦っているのか」「この戦いに勝った先に何があるのか」といった、言葉にはされない問いをふと感じ取ることになります。その一方で、ゲームプレイそのものはテンポが良く、メカアクションとしての爽快さがしっかり備わっているため、重苦しいだけの作品にはなっていません。ステージクリア時には「やった、ここまで来た」という素直な喜びがあり、その積み重ねがいつの間にか戦記ドラマ全体の盛り上がりにつながっていく──このバランス感覚こそが、『FZ戦記アクシス』が今もなお語り継がれる理由の一つだと言えるでしょう。
■■■■ ゲームの攻略など
まず押さえておきたい基本操作と視点のクセ
『FZ戦記アクシス』の攻略を語るうえで最初に意識したいのが、「クォータービュー視点に慣れる」という一点です。画面は斜め上からの見下ろしとなっており、コントローラーの上下左右の入力と、NAPの進行方向が直感と微妙にズレやすい構造になっています。例えば、画面右上へ進みたいときには「上+右」、左下へ退きたいときには「下+左」といった具合に、常に“斜め方向”を意識して操作する必要があります。序盤は敵の弾を避けようとして逆方向に飛び込んでしまうことも多いので、最初のステージではあえて敵を速攻で倒すことよりも、「障害物の周りを8方向移動+ローラーダッシュでぐるぐる回る」「敵弾を一発だけ撃たせて、それを斜め移動で避ける」といった練習を挟むと、後半ステージの生存率が大きく変わってきます。また、本作は敵に接近しすぎると一気に被弾が増えるタイプのゲームで、敵の出現位置を斜め方向から“なめる”ように攻撃するのが基本です。真正面から突っ込むのではなく、敵の攻撃ラインを少し外した位置からショットを流し込み、敵編隊の側面〜背後へ滑り込む感覚を体に覚えさせることが、全ステージ共通の立ち回りの土台になります。
ローラーダッシュの「加減」を覚える
方向キー2度押しで発動するローラーダッシュは、本作攻略の要ともいえるシステムです。高速移動によって敵弾の雨をまとめてかわしたり、敵の背後へ一気に回り込むことができる反面、勢いがつきすぎて障害物に突っ込み、動きが止まったところに集中砲火を浴びるという“自損事故”も起こしがちです。攻略のコツは、「常にダッシュで走り回る」のではなく、「敵弾が厚くなる局面だけ短く刻んで使う」ことです。具体的には①敵の弾幕が迫ってきたら、弾の隙間に向かって斜め方向へ短めのダッシュで滑り込む、②開けた場所に出た直後はダッシュを控え、敵の配置と弾の向きを一度確認する、③ダッシュ後は必ず通常歩行に戻して、次の回避に備える──といったサイクルを意識すると安定します。特に洞窟内や狭い通路のステージでは、ほんの少し角度を誤るだけで壁に当たり、その隙に敵の固定砲台から集中攻撃を受けてしまうため、「狭い場所では歩き中心、広い場所ではダッシュ多め」という切り替えを明確にするのが生存のポイントです。
武器構成は「火力・射程・安全性」の三本柱で考える
本作では多数の武器の中から一部を選んで装備しなければならず、その選択が攻撃力だけでなく防御力にも強く影響します。NAPは最大14個の武器を装着可能ですが、被弾するたびに装備している武器がシールドのように1つずつ消費されていくため、「強力な武器を少数精鋭で積む」か「扱いやすい武器を多めに積んで被弾に備える」かという大きな方針をまず決める必要があります。 具体的な構成を決める際には、①火力(ボスや装甲の厚い敵を短時間で削る力)、②射程と弾のばらけ方(画面のどの範囲をカバーできるか)、③安全性(弾速・連射性能・弾幕の厚さ)がバランスよく揃っているかをチェックするとよいでしょう。例えば、直進性の高い高威力武器はボス戦では非常に頼りになりますが、雑魚が大量に出るステージだと、狙いが少しずれただけで敵を取り逃し、接近を許してしまいます。そこで、雑魚処理用には広範囲に弾をばら撒ける武器や、前方を扇状にカバーできるタイプをメインに据え、対ボス用の高威力武器をサブとして温存しておく構成が無難です。弾速が遅い武器は、ローラーダッシュと組み合わせて“先回り射撃”を意識すると当てやすくなるので、「足の速さ」と「弾速の遅さ」を組み合わせて補う、という考え方も攻略の一助になります。
序盤ステージ:操作と視点に慣れることを最優先
最初のステージ群は、敵の攻撃パターンも比較的素直で、こちらのミスを修正する余裕がまだ残されています。この段階では「被弾しないこと」よりも、「どう動けば被弾を減らせるか」を体で理解することが重要です。具体的には、①敵出現位置の法則を覚える(画面のどの端から現れやすいか)、②遮蔽物の配置を頭に入れ、「ここは一度下がって敵を誘い込む」「ここはダッシュで一気に抜ける」といった“安全ポイント”を見つけておく、③敵の弾速や連射間隔に慣れ、どのくらいのタイミングでローラーダッシュを切れば抜けられるかを試す──といった練習を繰り返すと、後半の高難度ステージでの立ち回りが格段に楽になります。また、序盤のボス戦では意図的に被弾して武器ストックを減らし、「残り武器が少ないときの挙動」を体感しておくのも一つの手です。武器が減るほど失敗が許されない状況になるので、シールドが薄い状態での攻防を早い段階から経験しておくことで、後半の緊迫した局面にも落ち着いて対処できるようになります。
中盤ステージ:地形ギミックと敵編隊の組み合わせを読む
中盤以降のステージでは、洞窟内の暗いエリアで水たまりに隠れた砲台を探し出す場面や、狭い通路にセキュリティ装置が配置された基地内侵入ミッションなど、地形そのものが罠のように機能するシチュエーションが増えてきます。 ここでは、「敵がどこから来るか」だけでなく、「自分がどの方向へ退路を確保できるか」を常に意識するのがポイントです。洞窟ステージでは、水たまりの縁にゆっくり近づいていき、敵砲台が発射する瞬間に位置を微調整して弾道を見極めてから攻撃に転じると安全です。通路が入り組んだ基地内ステージでは、ローラーダッシュを多用すると壁への接触事故が増えるため、あえて歩き主体で進み、敵の隊列が固まったところで短いダッシュを挟んで背後に回る、といった“点で使うダッシュ”を心がけましょう。敵編隊が複数方向から迫ってくる場面では、あらかじめ「弾を消費してでも先に落とすべき優先ターゲット」を決めておくと判断がブレません。弾幕を張る固定砲台や、誘導弾をばら撒くユニットなど、放置すると回避に専念させられてしまう敵から先に排除し、残った敵を通常ショットで処理する、という順番を徹底することで、徐々に被弾を抑えられるようになります。
ボス戦攻略:パターン把握と「安全圏」の確保
各ステージ終盤に待ち構えるボス戦では、敵の攻撃パターンを見極めて“安全圏”を見つけることが最重要です。巨大列車型のボスであれば、車体のどの部分から砲撃が発せられるか、どのタイミングで車両ごとに動きが変化するかを観察しながら、「弾の飛んでこないライン」を探ります。 エリートメカとの一騎打ちのようなボスでは、相手の移動速度と攻撃方向を把握し、斜め後方に回り込んで攻撃できる位置をキープすることが重要です。NAPの武装はメイン・サブともに、ボス戦用に攻撃力重視の構成にしておくと、短期決戦を狙いやすくなりますが、その分被弾時に失う武器の価値も高くなるため、「回避優先でじわじわ削る」か「多少の被弾を覚悟して一気に削る」かを、自分の腕前と相談して決めるとよいでしょう。どのボスにも共通して言えるのは、「真正面に留まらない」「ローラーダッシュで敵の攻撃ラインの外側へ回り込み、攻撃後はすぐに離脱する」という基本の徹底です。ボスの動きをある程度覚えたら、「攻撃→1〜2歩さがる→斜め方向へダッシュ→再び攻撃」という自分なりのリズムを作り、そのリズムから外れないように戦うと、無駄な被弾が一気に減っていきます。
ステージ目標の把握と“無駄戦闘”を避けるコツ
メガドライブ版などの解説では、ステージごとに「特定の敵を規定数倒すとボス戦に進める」というルールが明記されており、X68000版でも基本的なゲームデザインは同系統です。 そのため、闇雲に出てくる敵を片っ端から倒すのではなく、「どの種類の敵を優先して狙うべきか」を早めに見極めることが重要になります。雑魚敵が無限湧きするエリアで延々と戦っていると、被弾を重ねて武器ストックが削られてしまい、肝心のボス戦で火力不足に陥る危険があります。ステージを何度かプレイしていると、「このタイプの敵を一定数倒すと、画面が切り替わってボス戦に突入する」といった感覚がつかめてくるので、それを踏まえて“必要な敵だけを効率よく倒すルート”を模索していくとよいでしょう。特定の大型ユニットや固定砲台が目標になっているステージでは、雑魚の相手を最小限にとどめ、目標ユニットの位置を常に意識した動き方を心がけることで、被弾を抑えつつ短時間でクリアできるようになります。この「無駄な戦闘を避ける」発想は、シビアな難易度の本作では特に重要で、結果として武器ストックの節約にもつながり、総合的なクリア率を大きく引き上げてくれます。
難易度とコンティニューの扱いを踏まえたプレイ計画
移植版や現行機向けの復刻版では難易度設定や巻き戻し機能などが追加されていますが、オリジナル版は基本的に“残機とコンティニューの使い方がすべて”というストイックな作りです。 攻略の際には、「今日はステージ○までの練習」「次はボス戦だけを重点的に」といった具合に、自分なりの目標を細かく区切ってプレイするのがおすすめです。コンティニューに頼って力押し気味に進めるのも一つの遊び方ですが、ある程度ステージ構成を覚えたら、一度コンティニュー回数を意図的に制限し、「残機が尽きるまでにどこまで行けるか」というチャレンジをしてみると、緊張感が増すと同時に自分の成長も感じやすくなります。現行機版ではセーブ機能や巻き戻しによって難所を細かく研究できるため、「まず復刻版でパターンを研究し、慣れてきたらオリジナル相当の設定で通しプレイに挑む」といったステップを踏むのもよいでしょう。
裏技・小ネタについてのスタンス
一部のレトロゲームでは、ボタン入力によるコンティニュー回数増加や、隠しコマンドによるステージセレクトなど、派手な裏技が定番となっていますが、『FZ戦記アクシス』に関しては、2025年時点でも決定的な裏技情報はあまり共有されておらず、攻略サイトでも「情報募集中」という記述が見られるほどです。 そのため、本作を攻略する際は「派手な裏技に頼るより、パターン構築と操作の習熟で突破するゲーム」と割り切ったほうが、結果的には楽しめるでしょう。とはいえ、現行機の復刻版では巻き戻しやセーブロードを駆使することで、事実上“練習用の裏技”のように難所を何度でも試せる環境が提供されています。これはオリジナルのゲームデザインを壊すものではなく、「本番に備えた訓練」として活用すれば、本来の難易度や手応えを維持したままゲームの奥深さを味わうことができます。つまり、『FZ戦記アクシス』の“攻略”とは、隠しコマンドを探すことではなく、自分の中に「戦場のパターン」と「操作のリズム」を作り上げていくプロセスそのものだと言えるでしょう。
まとめ:パターンとビルドを積み上げていくタイプの攻略ゲーム
総じて、『FZ戦記アクシス』は、1回のプレイで一気にクリアを狙うよりも、ステージごとの特徴や敵配置、ボスの挙動を少しずつ覚え、自分に合った武器構成と立ち回りを積み上げていくタイプのゲームです。クォータービューの独特な視点、ローラーダッシュによる高速移動、武器とシールドが一体化したシステムなど、どれも最初は取っつきにくく感じられるかもしれませんが、それらが噛み合ったときの爽快感は他作品にはなかなかないものがあります。初めて要塞アクシスの奥深くへ到達し、死地から生還したときの達成感は、このゲームならではのご褒美です。「難しいからこそ、攻略しがいがある」──そう感じるタイプのプレイヤーにとって、『FZ戦記アクシス』は何度も戦場へ戻りたくなる一本になるはずです。
■■■■ 感想や評判
遊んだ人がまず語りたくなる「硬派さ」と玄人向けな手応え
『FZ戦記アクシス』を実際にプレイした人の感想でよく見られるのは、「とにかく硬派」「渋い」「漢臭いシューティング」という言葉です。メカデザインや世界観がアニメ的でありながら、ゲーム内容はかなりストイックで、遊び手を甘やかさない難易度と戦場の雰囲気が強く印象に残るようです。X68000向けの紹介記事では、「数あるX68kシューティングの中でも特にお気に入り」と語るプレイヤーもおり、全方位からの攻撃に対応しなければならない緊張感や、武器構成を工夫する戦略性を高く評価する声が見られます。 一方で、「誰にでも薦められる分かりやすい爽快ゲーム」というよりは、「ある程度ゲーム慣れした人が真価を感じるタイプ」と受け止められている面もあり、レトロゲームの中でも「通好みの一本」という評価に落ち着いている印象です。
操作性への評価――クセはあるが慣れるとやみつきになる?
クォータービュー+ローラーダッシュという独特の操作感については、賛否両論ながらも強い印象を残しているポイントです。特にメガドライブ版のレビューでは、「細かく方向転換しようとすると意図せずダッシュが暴発する」「向きを変えたつもりがワンテンポ遅れて反応する」といった声があり、慣れるまでは思いどおりに操れずストレスを感じる人も少なくないようです。 ただし、同じプレイヤーが「ある程度慣れてくると、この重さやもたつきも“ロボットを動かしている感じ”として納得できる」と述べているケースもあり、単純に「操作性が悪い」の一言で片付けられているわけではありません。機体が少し重く反応することが、「パイロットが重量級メカを必死に制御している感覚」につながっていると肯定的に受け止める意見もあり、その“クセ”を楽しめるかどうかが評価の分かれ目になっているようです。
難易度とゲームバランスに対する声
難易度については、「高め」「容赦ない」といった評価が多数派です。コンティニュー自体は比較的多く許されているものの、一定ステージ以降はコンティニューしてもさかのぼった位置からやり直しになるなど、最後まで押し切るには相応のパターン構築が求められます。 一方で、「敵の配置や攻撃パターンは理不尽一歩手前に踏みとどまっている」「何度も挑むうちに上達を実感できるタイプ」と評するレビューもあり、歯ごたえのあるバランスを肯定的にとらえるプレイヤーも少なくありません。敵の出現タイミングやボスの行動パターンがある程度“覚えゲー”寄りであることから、「最初は厳しいが、慣れるとスムーズに進めるようになるタイプ」として支持されている側面もあります。総じて、「軽く遊んでクリアまで駆け抜ける」というライトな遊び方よりも、「じっくり腰を据えて攻略する」スタイルを好むユーザーに評価されているタイトルだと言えるでしょう。
グラフィック・演出面への感想――X68000版オープニングの衝撃
ビジュアル面、とくにX68000版のグラフィックとオープニング演出については、今なお強い支持が寄せられています。X68k向けのレビューや個人ブログでは、「高解像度の画面と精細なドットで描かれた戦場が圧巻」「X68000シューティングの中でも屈指の美しさ」といった誉め言葉が並んでおり、戦場のディテールやメカの描き込みに感心する声が多く見られます。 なかでも有名なのが、オープニングにディスク1枚分を割り当てた豪華な構成で、アニメーションと音楽がシンクロしながら物語の世界観を一気に提示してくるこの導入部は、「ゲーム本編以上に印象に残る」と語るプレイヤーもいるほどです。近年の感想記事でも、「ゲームとしての完成度は賛否があるが、オープニングと音楽だけでも触れてほしい」といったコメントがあり、ビジュアルと演出に関しては時代を超えて評価が続いていることがうかがえます。
サウンド・音楽への高い評価
音楽面の評価は総じて高く、「ウルフ・チーム作品らしい熱くドラマチックなBGM」「戦場の緊張感とヒロイックなムードを同時に感じさせる」といった声が散見されます。X68000のFM音源+MIDI対応という贅沢な仕様もあって、当時としてはかなりリッチなサウンド体験を提供していたことが、ゲーム音楽ファンの間で語り継がれているポイントです。サウンドトラックレビューでは、桜庭統の初期作品として、のちのRPGやアクションゲームで聴かれるダイナミックなフレーズの原型がうかがえると評価されることもあり、音楽単体で鑑賞しているファンも少なくありません。 一方で、メガドライブ版のみを遊んだプレイヤーからは「良い曲ではあるが、X68000版ほどの迫力には感じなかった」というやや控えめな評価もあり、ハードの違いによって受け止め方が変わる一面もあります。それでも、「全体としてBGMはかっこよく耳に残る」という点では、多くの人が意見を同じくしているようです。
X68000版とメガドライブ版、それぞれの評判の違い
X68000版とメガドライブ版の比較については、「X68k版は演出とサウンドを含めて完成度が高い」「メガドラ版は移植としてよく頑張っているが、どうしても劣化を感じる」というニュアンスの評判が見受けられます。X68000版はオリジナルとして開発されたこともあり、グラフィック・音楽ともにハードの性能を余すところなく引き出した“決定版”的な位置づけです。一方、メガドライブ版は家庭用ゲーム機としてより多くのユーザーに触れてもらうための移植という性格が強く、手軽に遊べる反面、「BGMの迫力がやや抑えめ」「操作感にクセが出ている」といった指摘もあります。 ただし、メガドライブ版のレビューの中には「ロボットを動かすゲームとしてはかなり楽しめる」「買ってよかった」といったポジティブな感想もあり、ハードごとの評価差はありつつも、「クォータービューのメカアクション」という体験そのものは一定の支持を得ていることがわかります。
ストーリーと世界観に惹かれるプレイヤーの声
ゲームとしてはアクションがメインでテキスト量は多くないにもかかわらず、ハワード・ボウイや外人部隊「アンデッド」、要塞アクシスといったキーワードが醸し出すハードな戦記SFの雰囲気に惹かれるプレイヤーも少なくありません。海外のレビューでは、「実在のアニメ原作があるわけではないのに、80年代末〜90年代初頭のOVA作品のゲーム化のような雰囲気」と評されることもあり、アニメファン的な文脈で楽しんでいる人もいるようです。 「戦争の中でしか生きられない男が、死地に送り込まれながらも戦い続ける」という設定は、ゲーム内で事細かく描写されているわけではありませんが、オープニングやステージ構成からプレイヤーが補完して楽しめる余地があり、その“想像の余白”を好意的にとらえる意見も見られます。
レトロゲームとしての再評価と現代の口コミ
現行機向けの復刻やダウンロード配信によって、最近になって初めて『FZ戦記アクシス』に触れたプレイヤーも増えており、そうした“新規勢”からの感想は、懐かしさよりも「新鮮なレトロ体験」というニュアンスを帯びています。Steamなどの配信ページでは、巻き戻しやセーブ機能、画面フィルタ、ギャラリーといったサポート要素が追加されていることから、「オリジナルの難しさはそのままに、遊びやすさが向上している」と評価する声があり、当時よりも間口の広いタイトルになりつつあります。 レトロゲーム愛好家のブログやレビューでは、「尖った部分が多く万人向けとは言い難いが、クォータービュー・メカアクションとして唯一無二の味わいがある」「BGMとオープニングだけでも価値がある」といった再評価も見られ、X68000を象徴する作品群の一角として語られることも増えています。
総評:強い個性がゆえに“刺さる人にはたまらない”一本
総合的に見ると、『FZ戦記アクシス』の評判は「粗も多いが、それ以上に個性と魅力が際立つタイトル」という位置づけに落ち着いています。操作のクセや高い難易度、ハードごとの差など、ネガティブに語られるポイントも確かに存在しますが、それらを上回る形で、クォータービュー戦場アクションの独特な手触り、重量感のあるNAPの挙動、ハードSF風の世界観、そして熱いBGMと豪華なオープニングがプレイヤーの記憶に刻まれています。メジャーな名作というよりは、「知る人ぞ知るカルト的な人気作」に近い立ち位置ですが、だからこそハマったプレイヤーからの愛情は深く、X68000やメガドライブの思い出を語る際に、必ずと言っていいほど名前が挙がる一本でもあります。今から触れる人にとっても、「少しクセの強い戦場SFアクションを体験してみたい」と思ったとき、真っ先に候補に入れてほしいレトロゲームだと言えるでしょう。
■■■■ 良かったところ
クォータービューならではの「戦場を駆け抜ける」感覚
『FZ戦記アクシス』の長所としてまず挙げられるのは、斜め見下ろし視点=クォータービューを活かしたアクション性です。画面奥へ真っすぐ進むだけの縦スクロールでもなく、左右だけを意識していればよい横スクロールとも違い、NAPは8方向へ自在に移動しながら前線と後方を行き来します。特にローラーダッシュを織り込んだ操作に慣れてくると、敵弾の隙間を縫うように斜め方向へ滑り込み、横からボスに襲いかかるようなダイナミックな動きが自然とできるようになり、「ただのシューティング」ではなく「戦場を駆ける兵器を操っている」という実感が強くなります。X68000 Z向けの紹介文などでも、NAPで戦場を高速で駆け回る感覚が推されており、この視点と操作性こそが本作を本シリーズや他のシューティングから一歩抜き出させているポイントだと言えます。
武器の積み方でプレイ感が変わる戦略性
多彩な特殊兵器を積み込める武装システムも、プレイヤーから好意的に語られる点です。多数の武器の中から一部を選び、さらにそれらがシールドの役目も兼ねるという仕組みのおかげで、「どの武器を何個積むか」という段階からすでに戦略ゲームが始まっています。火力重視で強力な兵器を少数積めば短期決戦に強くなり、広範囲をカバーできる武器や扱いやすいショットを多めに積めば、被弾に強く長期戦にも対応しやすくなる、といった具合です。海外の解説でも、本作の特徴として「武器のシステムの面白さ」が真っ先に挙げられており、単にボタンを押して敵を撃つだけでなく、自分のプレイスタイルに合わせて機体構成を組み替える楽しさが評価されています。
X68000版のグラフィックとオープニングのインパクト
X68000版を語るうえで外せない長所が、当時のPCとしてはトップクラスだったグラフィック能力をフルに活かした画面作りです。高解像度のドットで描かれた戦場は、金属板が敷き詰められた基地の床、都市部の建造物、要塞内部の機械構造などが細かく描き込まれており、クォータービューの視点と相まって、NAPが本当に立体的な空間を進んでいるような錯覚を覚えます。X68kゲームを特集した個人サイトでも、「美しい画面」「数あるX68kシューティングの中でも特にお気に入り」といった言葉で本作を挙げているものがあり、ビジュアル面は今なお高く評価されています。
さらに、ディスク1枚分を大胆に使用したオープニングデモも、多くのプレイヤーが「良かったところ」として真っ先に名前を挙げる要素です。ムービーと音楽が同期した演出で世界観を一気に提示するこの導入部は、「これから過酷な任務が始まる」という空気を一瞬で作り上げ、ゲーム本編への期待感を高めてくれます。「ゲームの内容に多少荒さがあっても、このオープニングを観られるだけで満足」という感想すらあるほどで、視覚的・演出的なインパクトは本作の大きな長所といえるでしょう。
熱いサウンドトラックとMIDI対応の豪華さ
サウンド面も、『FZ戦記アクシス』を語るときに必ず褒められる部分です。X68000用ゲーム音楽をまとめたサイトなどでは、本作のBGMについて「非常にかっこいい」「アニメーションと音楽の同期が見事」といったコメントが見られ、重厚な戦場を彩る楽曲群が高く評価されています。 さらに、FM音源だけでなくローランドのMIDI音源(MT-32やCM-32Lなど)に対応していることから、当時としては相当贅沢なサウンド体験が可能でした。MIDI環境を持つユーザーにとっては、「同じゲームなのにまるで別物のように豪華なサウンドになる」という驚きがあり、BGMを聴き比べるだけでも遊ぶ価値があると語られることもあります。後年リリースされたサントラCDも、ゲーム本編を知らない音楽ファンから注目されるほどで、「音楽が良いから印象に残っている」という声が多いのは、本作にとって大きな強みです。
遊び込むほど“化ける”高難度バランス
難易度の高さそのものは賛否の対象になりがちですが、ハードなゲームを好むプレイヤーにとってはこの「厳しさ」が大きな魅力になっています。X68000やメガドライブ版を遊んだ人の中には、「最初はすぐゲームオーバーになるが、少しずつ敵配置やボスパターンを覚えていくうちに、明らかに腕が上がるのを実感できる」と評価する声があり、覚えゲーとしての手応えを良しとする層から支持されています。 クリアまでの道のりは決して短くありませんが、そのぶん各ステージを突破したときの達成感は大きく、特に要塞アクシスの深部へ到達したときの満足感は格別です。最近の復刻版では巻き戻しやセーブなどのサポート機能が用意されているため、根性だけに頼らずパターン研究をじっくり行えるようになり、「本来の高難度を保ちつつ、挑戦しやすくなった」という点もポジティブなポイントといえるでしょう。
メカ×戦記ドラマの世界観が刺さる
細かなテキストで長々と語られる物語ではないものの、「外人部隊アンデッド」「巨大要塞アクシス」「NAPによる特攻作戦」といったキーワードだけで、80〜90年代らしいハードなSF戦記の香りが漂う世界観も、本作の良いところです。Evercade向けコレクションの解説などでも、主人公ハワード・ボウイが少数精鋭部隊の指揮官として、最後の大量破壊兵器を破壊する任務に挑むという筋立てが紹介されており、プレイヤーは「自分は消耗品の一兵士ではなく、部隊を背負って戦う一人のパイロットなのだ」という感覚を自然と抱きます。 アニメ原作があるわけではなく、ゲーム単体のオリジナル世界でありながら、どこかOVA的な雰囲気を感じるという声もあり、ハードSFやロボット物が好きな層にはそれだけで大きな魅力になっています。
今の環境でも遊びやすくなった“再評価しやすい”一本
近年はプロジェクトEGGでの配信やX68000 Z向けパック、さらに海外向けコレクションなどを通じて、本作に触れられる機会が増えています。現行ハード向けには、セーブ・巻き戻し・画面フィルタ・ギャラリーといったサポート機能つきの復刻版も登場しており、「昔から気になっていたけれど、当時の環境では手が出なかった」という人にとっては非常にありがたい環境になっています。 こうした復刻のおかげで、当時遊んでいたユーザーが懐かしさとともに再挑戦したり、新しい世代がレトロゲームとして“発掘”したりと、世代をまたいで良さを共有できるようになっているのも、本作の大きな長所です。「尖ってはいるが、独自の面白さを持ったメカアクション」として、いま改めて評価される土壌が整っていると言えるでしょう。
総合的に見た「良かったところ」
総じて、『FZ戦記アクシス』の良かったところは、クォータービュー視点の戦場表現、多彩な武器とビルドの試行錯誤、X68000らしい高精細グラフィックと豪華なオープニング、熱いBGMとMIDI対応、そして遊び込むほど光る高難度バランスとハードな世界観が、一本のゲームの中で強烈な個性としてまとまっている点にあります。スッキリ遊べるライトな作品とは方向性が異なりますが、「少しクセはあっても、独特の手触りを持つロボットアクションを遊びたい」というプレイヤーにとっては、何度も思い出しては戦場へ戻りたくなる、記憶に残るタイトルになっていると言えるでしょう。
■■■■ 悪かったところ
クォータービュー特有の操作の分かりづらさ
『FZ戦記アクシス』の短所としてまず挙げられるのが、クォータービュー特有の操作感に対して「分かりづらい」「直感的ではない」と感じるプレイヤーが少なくない点です。画面が斜め上から見下ろしの視点で構成されているため、コントローラーの上下左右とNAPの移動方向が素直に一致せず、「右に避けたつもりが斜め上へ進んでしまい、そのまま敵弾に突っ込んだ」というミスが起こりやすくなっています。特にアーケードの縦スクロールや、横シューティングに慣れているプレイヤーほど、この視点の違いによる違和感が強く出やすく、序盤から「思ったように動かない」とストレスを感じる要因になってしまうことがあります。メガドライブ版の評価の中にも、操作系のクセが理由でなかなか馴染めなかったという声があり、視点そのものは魅力的である一方で、「誰にでもすぐ楽しめる」タイプではないことが指摘されています。
ローラーダッシュ暴発問題と細かい操作のしづらさ
もう一つのネックは、ローラーダッシュ機能の扱いにくさです。方向キーを素早く二度倒すことで発動するこの高速移動は、本来なら本作の爽快感を支える重要なギミックですが、入力受付がシビアなため「ちょっと方向転換しようとしただけなのに勝手にダッシュしてしまった」という現象が頻発しがちです。狭い通路や障害物の多い場所でダッシュが暴発すると、そのまま壁に激突して行動不能になり、すぐに敵の集中砲火に晒されるという、プレイヤーにとってはかなり理不尽に感じられる状況が生まれやすくなります。結果として、「戦略的にダッシュを使う」というより「暴発を恐れて控えてしまう」という逆転現象が起こり、そのせいでゲーム本来のリズムを十分味わえないまま挫折してしまうケースも考えられます。アクションゲームにおいて“気持ちよく動かせる”ことは大きな魅力ですが、本作の場合、その一歩手前でつまずいてしまうプレイヤーが出やすいという意味で、操作系のチューニングは惜しい点だと言えるでしょう。
難易度の高さが人を選ぶバランス
本作は「歯ごたえがある」「慣れるまでが大変」といった評価がよく付くタイトルですが、その高難度ぶりは同時にマイナス点としても語られます。敵の攻撃は序盤から容赦なく、被弾すれば貴重な武器ストックがどんどん削られていくため、ちょっとしたミスがそのまま後半ステージでの戦力不足に直結します。コンティニューは用意されているものの、ステージ構成を知らない初見プレイではあっという間に残機と武器が尽きてしまい、「何が悪かったのかよく分からないままゲームオーバーになった」と感じてしまうこともあります。 こうした厳しさは、ハードなゲームを好むプレイヤーには大きな魅力になる一方で、「せっかく設定や演出に惹かれて遊び始めたのに、序盤の壁を越えられずにやめてしまった」という人も出やすい要因になっており、全体として“人を選ぶバランス”になっている点は、弱点といえるでしょう。
視認性の問題――敵弾や地形が見づらい場面も
クォータービューと高解像度のグラフィックは本作の美点である一方、戦闘の激しい場面では「どこから弾が飛んできているのか分かりにくい」「背景と敵弾のコントラストが弱くて見落としやすい」といった視認性の問題が顔を出します。特に、基地内部や都市部など背景の情報量が多いステージでは、床や壁の模様と敵のショットが重なり、慣れないうちは被弾原因が分からないままダメージを受けてしまうことが少なくありません。また、NAPや大型の敵ユニットのスプライトが比較的大きいため、画面内がキャラクターと弾で埋まり、結果的に足場や安全地帯の把握が難しくなる局面もあります。「美麗グラフィック」であるがゆえに、“ゲームとしての見やすさ”が一部で犠牲になっていると言える場面もあり、この点は当時から現在に至るまで賛否が分かれるポイントです。
ストーリー描写の薄さとキャラクターの掘り下げ不足
設定だけ切り取ってみれば、外人部隊「アンデッド」や主人公ハワード・ボウイ、要塞アクシスなど、アニメや小説にしても映えそうな要素が揃っていますが、ゲーム本編でのストーリー描写はそれほど厚くありません。オープニングデモや説明書で基本的な状況は提示されるものの、ステージ間でのドラマやキャラクターの心理描写は最小限にとどまり、「なぜハワードがこの戦いに身を投じているのか」「部隊の仲間たちはどんな人物なのか」といった部分はほとんど語られません。そのため、世界観に魅力を感じるプレイヤーほど、「もっとドラマが見たかった」「ミッションの合間に無線会話やイベントがあれば…」と物足りなさを覚えることもあるでしょう。 アクション重視の設計である以上、ストーリー量を増やしすぎればテンポを損なう懸念もありますが、せっかく強い設定が用意されているだけに、もう一歩踏み込んだ演出があったならという“惜しさ”が残る点は否めません。
メガドライブ版における劣化と評価差
X68000版と比べたときのメガドライブ版の立ち位置も、しばしば「悪かったところ」として話題になります。オリジナルであるX68000版はグラフィック・音楽ともにハードの性能を活かした作りで、オープニングを含め演出面が非常にリッチですが、メガドライブ版ではどうしても解像度・音源面での差が出てしまいます。レビューの中には、「移植としては健闘しているものの、X68k版の豪華さを知っていると物足りない」「BGMの迫力が落ちたように感じる」といった意見があり、両方を比較できる環境にある人ほどその差が気になってしまうようです。 また、メガドライブ版の操作性に関しては、前述の通りローラーダッシュの暴発や細かな制御のしづらさがより顕著に感じられるという指摘もあり、「家庭用ゲーム機向けに調整しきれていない」という印象を持たれる要因にもなっています。
テンポのムラ――盛り上がりにくい場面も存在
ステージ構成そのものはバリエーションに富んでいるものの、一部のエリアでは「敵出現のテンポが単調に感じる」「似たような配置が続きがち」といったテンポ面のムラも見られます。特に、目標撃破数を満たすまで似た敵編隊が繰り返し現れるシーンでは、「どこまで進めば変化があるのか分かりにくい」「同じような戦闘が長く続いてダレてしまう」と感じるプレイヤーもいるでしょう。 ボス戦や演出の派手な場面との落差が大きいため、余計に「地味な区間」が目立ってしまうという側面もあります。もちろん、パターンを構築してスムーズに進めるようになると、この“間”の時間は短縮され、リズムよく進行できるようになるのですが、初見ではその前に集中力が途切れてしまう危険もあり、ここもまた人を選ぶ要素になっています。
情報不足ゆえの取っ付きにくさ
発売当時から現在に至るまで、『FZ戦記アクシス』はメジャータイトルに比べると攻略情報や裏技が少なく、インターネット上でも詳しい解説ページは限られています。 そのため、現代のプレイヤーが初めて触れた際、「どの武器が有効なのか」「ステージごとの目標やルートが分かりにくい」といった“情報不足”に戸惑うことがあります。近年の復刻版で巻き戻しやセーブ機能が付いたことにより、自力でパターン研究をしやすくなったとはいえ、他作品のように詳しい攻略Wikiや動画が大量に存在するわけではないため、「自分で試行錯誤するのが楽しい」と感じるタイプでないとハードルが高いと受け止められがちです。情報が少ないこと自体が、“隠れた名作”らしさでもある一方で、新規プレイヤーには敷居の高さとして立ちはだかる点は否定できません。
総括:個性の強さゆえの「万人向けではなさ」
こうして悪かった点を振り返ると、『FZ戦記アクシス』は、クォータービューとローラーダッシュに代表される独特の操作性、高めの難易度、視認性やテンポのムラ、ストーリー描写の薄さ、バージョン間の差など、さまざまな“取っ付きにくさ”を抱えた作品であることがわかります。どれも決定的な欠点というより、「強い個性の裏返し」として現れている側面が強く、ハマる人にはたまらない要素である一方で、合わない人には最初の数時間で敬遠されてしまう要因にもなっています。総合的に見ると、「誰にでも安心して勧められるオールラウンダー」ではなく、「ある程度の覚悟と好みが合うプレイヤーに向けた尖った一作」といった位置づけになるでしょう。だからこそ、今なお“知る人ぞ知る一本”として語られ続けているのかもしれません。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
兵士として生きる男・ハワード・ボウイの魅力
『FZ戦記アクシス』で「好きなキャラクター」を挙げるとき、多くのプレイヤーが真っ先に思い浮かべるのが主人公ハワード・ボウイです。ゲーム内で長々と台詞が語られるタイプの主人公ではありませんが、外人部隊「アンデッド」の一員として極めて危険な任務に身を投じる姿からは、戦場に生きる兵士ならではの生き様がにじみ出ています。過去や私生活が丁寧に語られているわけではないからこそ、プレイヤーは彼の背後にある様々な事情を想像しながらプレイすることになり、その余白がキャラクターとしての魅力を深めています。「国家にとっては駒に過ぎないが、それでも自分の仕事を全うする」という無骨なプロ意識を感じさせる設定は、80~90年代のハードSF作品が好きな人ほど刺さりやすく、「多くを語らないからこそ印象に残る主人公」として記憶されることが多い存在です。戦場で何度撃破されても、コンティニューを重ねて黙々と再出撃していく様子は、プレイヤー自身の再挑戦意欲とも重なり、ゲームを進めるほど「この男を最後まで戦わせてやりたい」と感じるようになるでしょう。
使い捨て部隊「アンデッド」の無名の仲間たち
ハワード一人だけでなく、彼が所属する外人部隊「アンデッド」そのものも、プレイヤーにとっては印象的な“キャラクター集団”です。彼らの顔や名前が細かく描写されるわけではありませんが、「アンデッド」という部隊名が暗示するのは、生きて帰ることを前提としていない過酷な任務に専従させられている存在だという事実です。ゲーム中では、作戦説明やステージの雰囲気から、部隊としての立ち位置や扱いの冷酷さがさりげなく伝わってきます。プレイヤーは、画面の向こうで同じように戦っているはずの仲間たちを想像しながら要塞アクシスへと踏み込んでいくことになり、「名も知らぬ兵士たちの戦い」という戦記物ならではの感傷を覚える瞬間もあるでしょう。プレイヤーによっては、妄想設定として「自分のNAPはアンデッドの何番機か」「ハワード以外にどんなパイロットがいるのか」を想像して楽しむこともあり、公式設定ではないものの、部隊全員を含めて“好きなキャラクター”として捉えているファンも少なくありません。
相棒としてのNAP――無骨な人型兵器の存在感
本作では、人間キャラクター以上に強い存在感を放っているのが、プレイヤーが操る人型陸戦兵器NAPそのものです。ドット絵で描かれた機体は、派手な色使いや過剰な装飾を排した、いかにも軍事機械らしい無骨なシルエットをしており、重装甲でありながらローラーダッシュで戦場を駆け巡る姿は、多くのプレイヤーにとって“相棒”のような愛着の対象になっています。ゲームを進めるうちに、プレイヤーは自分なりの武器構成や立ち回りを確立していき、「この装備構成のNAPこそが自分の愛機だ」と感じるようになります。装備する兵器の種類によって性能や見た目の一部が変わるわけではありませんが、プレイヤーの頭の中では「重火力仕様」「高速機動仕様」といったイメージが自然と膨らみ、NAPが単なるゲーム上のアイコンではなく、戦場を共に生き抜くパートナーとして心に残るようになるのです。そうした意味で、「好きなキャラクターは誰か」と問われて「やっぱり自分のNAP」と答えるファンも少なくありません。
巨大ボスたちのキャラクター性――無機質だからこそ感じる恐怖
『FZ戦記アクシス』のボスキャラクターたちも、多くのプレイヤーにとって忘れがたい存在です。巨大列車型兵器、要塞の砲塔群、異形のメカなど、一体一体がステージのクライマックスを飾る“キャラクター”として強い印象を残します。彼らには人格や台詞があるわけではありませんが、画面の大半を占めるほどのサイズで迫りくる姿や、容赦なく弾幕を吐き出す攻撃パターンは、プレイヤーにとって明確な“宿敵”として記憶されます。特に初見では、その攻撃の激しさから「これは本当に倒せるのか」と不安にさせられるほどで、逆に攻略パターンをつかんで撃破したときには、単なる敵を越えた達成感を与えてくれます。見た目も、過剰なデザインではなく軍事機械としての説得力を意識したものが多く、「この世界に存在していそうな兵器」としてリアリティを感じさせてくれるのもポイントです。プレイヤーの中には、「一番好きなキャラクターは特定のボスだ」と語る人もおり、何度も戦ううちに“因縁の相手”のような愛着が湧いてくるボスも存在します。
上層部や作戦司令の“顔の見えないキャラクター”
物語上、ハワードたちに作戦を命じる上層部や司令官は、ほとんど姿を見せません。しかし、まさにその“顔の見えなさ”こそが、プレイヤーに強い印象を残す形でキャラクター性を与えています。無茶な作戦を冷静な口調で通達する電文や、要塞アクシスの危険性を知りながらも送り込む決断などからは、兵士たちを単なるコマとして見ている冷徹さが伝わってきます。ゲーム中で具体的な人物像こそ描かれないものの、プレイヤーは自然と「この命令を出しているのはどんな人物なのか」「本当にこの作戦に勝算があるのか」といった疑問を抱き、想像力の中で“見えない司令官”の人となりを形成していきます。こうした、画面の外側にいるキャラクターが存在しているかのように感じられる点も、戦争を題材とした作品ならではの味わいであり、「あの上層部こそ最大の敵だ」と冗談交じりに語るプレイヤーもいるほどです。
プレイヤー自身を投影しやすい“無口な主人公像”
ハワード・ボウイが多くを語らない主人公として描かれていることは、同時にプレイヤーが自分自身を投影しやすい余白にもなっています。強い個性や口調を持つキャラクターではなく、どちらかといえば寡黙な兵士として扱われているため、プレイヤーは自分の性格や価値観を重ねながら物語を進めることができます。「命令だから戦う」という冷めた視点で捉えることもできれば、「仲間や市民を守るために自ら死地へ向かう英雄」として解釈することもできるわけです。これによって、プレイヤーごとに“自分だけのハワード像”が生まれやすくなり、「自分にとってのハワード・ボウイ」という意味で好きなキャラクターとして挙げるファンも少なくありません。セリフ少なめの主人公だからこそ、それぞれのプレイヤーの心の中に別々の人物像が存在し、語る人の数だけ違うハワードの物語がある──そうしたキャラクターの在り方も、『FZ戦記アクシス』の魅力の一部といえるでしょう。
背景設定から生まれる“想像上のキャラクターたち”
『FZ戦記アクシス』は、キャラクター同士の掛け合いや日常会話などを前面に出した作品ではなく、その多くを背景設定とビジュアル、短いテキストに委ねています。そのため、プレイヤーは自然と「アンデッド隊にはどんなメンバーがいるのか」「ハワードの過去には何があったのか」「要塞アクシスの防衛側にはどんな司令官がいるのか」といった“見えないキャラクター”たちを心の中で描き出すようになります。ファンの中には、オリジナルの小説やイラストを描き、ゲーム中では語られない人間関係やドラマを補完して楽しんでいる人もおり、その二次的な想像力を刺激してくれる点も高く評価されています。キャラクターの情報量が少ないからこそ、プレイヤーは自分にとって理想的なドラマをそこに重ねることができ、「公式には存在しないが、自分の中では確かにいるお気に入りキャラクター」が生まれていくのです。この構造は、派手なキャラ立ちを前面に押し出した作品とは対照的ですが、ミリタリー色の濃いゲームとしては非常に相性が良く、静かな形でファンの創作意欲を掻き立てる要因になっています。
“好きなキャラクター”がプレイスタイルを形づくるゲーム
総じて、『FZ戦記アクシス』における「好きなキャラクター」とは、単に見た目や設定が好みかどうかだけでなく、自分のプレイスタイルやゲーム体験そのものと強く結びついた存在になっています。ハワードやアンデッドの無骨な兵士像に惹かれる人は、多少の被弾を恐れず前線に飛び込む攻撃的な立ち回りを選ぶかもしれませんし、NAPを大切な相棒と捉える人は、とにかく被弾を避けて慎重に一歩一歩進むスタイルを好むかもしれません。特定のボスを“宿敵”として愛するプレイヤーは、そのボス戦だけ異様に上手くなっていたりもします。このように、本作では「どのキャラクターが好きか」がそのままプレイ中の感情の動きや操作の選択に反映されやすく、ゲームシステムとキャラクターの魅力が密接に連動しています。派手なキャラデザインや大量のテキストがなくても、戦場での挙動や設定の断片だけで心に残るキャラクターを生み出している──それこそが、『FZ戦記アクシス』における“好きなキャラクター”の在り方だと言えるでしょう。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
X68000版:すべての基準になっているオリジナル
まず基準になるのが、1990年10月10日に発売されたシャープX68000シリーズ向けオリジナル版です。5インチ2HDフロッピー3枚組、定価8,800円(税別)という、いかにも当時の“ハイエンドPCゲーム”らしいパッケージでリリースされました。 画面解像度はX68000らしい高精細ドットで、31kHz(高解像度)と15kHz(通常TV相当)の両モードに対応しており、モニタ環境に合わせて切り替えが可能でした。 クォータービュー視点で描かれた戦場は、金属板が敷き詰められた床パターンや要塞内部の機械構造などが緻密に描かれており、「ロクハチらしい美麗グラフィックの代表例」として今でも名前が挙がるほどです。 サウンド面では、内蔵FM音源だけでも十分迫力がありますが、外部MIDI音源としてローランドMT-32やCM-64などに正式対応しており、対応リストにも名を連ねています。 当時高価だったMIDIモジュールを接続した時のサウンドは、まさに“家庭用とは別次元”のクオリティで、戦場の緊張感を音楽面から強烈に支えてくれました。オープニングデモもX68000版の大きな特徴で、ディスク1枚を丸ごと使ったアニメーションと音楽のコンビネーションは、「まずこれを見てほしい」と今も語られるほど強烈なインパクトを残しています。 ゲーム内容そのものについても、X68000版が最も“本来の姿”に近いと言えます。操作レスポンス、敵の出現パターン、地形の描き込みなど、後の移植版のベースはここにあり、後年のレビューでも「X68k版こそ完成形」という言い方をされることが少なくありません。
Windows版(プロジェクトEGG:X68000版エミュレーション)の特徴
2004年になると、プロジェクトEGGからWindows用ダウンロードソフトとしてX68000版の『FZ戦記アクシス』が配信開始されました。 これはいわゆる“完全なWindows移植”というより、X68000版をWindows上で動かすエミュレーション形式に近く、画面解像度やサウンドは可能な限りオリジナルの仕様を再現することを狙ったものです。プロジェクトEGG自体が、PC-8801・X1・X68000などの古いPCゲームをWindows上で遊べる環境として展開されているサービスであり、『FZ戦記アクシス』もその一ラインナップとして扱われています。 Windows版の利点は、何よりも“実機を用意しなくてよい”ことと、インストールさえ済ませれば現行のWindows環境で手軽に起動できることです。フロッピーディスクの読み込みや画面モードの切り替えを自前で調整する必要はなく、ランチャーから起動するだけでオリジナル版のプレイが可能になります。ゲーム内容そのものは基本的にX68000版準拠ですが、キーボード/ゲームパッド設定、ウィンドウ表示とフルスクリーン切り替えなど、PCアプリとしての最低限の快適さは備わっています。 一方で、MIDI音源環境を当時と同じ感覚で再現するには少し工夫が必要であったり、OSのバージョンによっては動作に相性が出るケースも報告されており、「完全に実機と同じ」とまではいかない点もあります。とはいえ、オープニングやBGMを含め“ロクハチ版の空気”を味わうには十分であり、「実機は持っていないが、X68000版を体験してみたい」という人にとって最も敷居の低い入り口になっているのは間違いありません。
Windows版(プロジェクトEGG:メガドライブ版)との違い
プロジェクトEGGでは、2013年にメガドライブ版『Final Zone(海外名)/FZ戦記アクシス』もWindows向けに配信されています。 こちらは“PC用ソフト”という形ではありますが、中身はメガドライブ版のエミュレーションであり、ゲーム内容やバランスは家庭用ゲーム機向けとして調整されたものです。 X68000版と比べると、メガドライブ版はハード性能の違いからグラフィック解像度や色数が抑えられており、全体的に画面がやや粗く、オブジェクトサイズや背景の描き込みも簡略化された箇所があります。また、操作感や難易度も家庭用寄りにチューニングされていると言われており、X68k版に比べて敵配置や攻撃の激しさが緩和されている代わりに、ローラーダッシュ暴発などの“癖”が強く感じられるケースもあります。 Windowsユーザーから見ると、「同じPCで遊ぶ“二つのFZ戦記アクシス”」という少し不思議な状況になりますが、どちらを選ぶかで体験はかなり変わってきます。X68000版EGGの方はオリジナル準拠で硬派な仕上がり、メガドライブ版EGGの方は家庭用らしい軽快さとアレンジ寄りのバランス、といったイメージです。両方購入して遊び比べると、同じ作品をPC-オリジナルとコンシューマー移植の両視点から楽しめるという、少しマニアックな遊び方もできます。
X68000 Z版と現代のWindows/コンソール向け移植
2020年代に入ると、『FZ戦記アクシス』は“懐かしのウルフ・チーム作品”として再び脚光を浴びるようになります。2024年には、X68000互換機「X68000 Z」専用ソフトとして『FZ戦記アクシス・グラナダ PACK』が発売され、オリジナル版をほぼそのままの形で最新ハードに移植した形で収録されました。 X68000 ZはPCというより専用機寄りの立ち位置ですが、中身はX68000アーキテクチャを再現しているため、実質的には“現代に蘇ったロクハチ実機版”という感覚で楽しめます。 さらに2025年には、Ratalaika Gamesによるマルチプラットフォーム版『Final Zone』として、PlayStation・Xbox・Nintendo Switch・Windows向けに配信が発表されており、現行機で気軽に遊べる環境が整いつつあります。 これらの現代版では、オリジナルのゲーム内容をベースにしつつ、画面フィルタやボタン配置のカスタマイズ、セーブ/ロードや巻き戻しといった“レトロゲーム向けお助け機能”が搭載されているのが一般的で、Windows版であってもX68000やプロジェクトEGGとはまた別の遊び心地になっているのが特徴です。
画面・サウンド・操作性の比較ポイント
対応PC(あるいはPC上のエミュレーション環境)ごとの違いを整理すると、主な比較ポイントは「画面」「サウンド」「操作性」「周辺機能」の4つになります。まず画面については、X68000実機版/X68000 Z版/EGGのX68000版がもっともオリジナルに近い描画で、クォータービューの高精細ドットがくっきりと再現されます。メガドライブ版EGGやコンソール向け移植は解像度や色数の制限がある分、若干ラフな印象になりますが、そのぶん画面の情報量が減って敵弾が見やすくなる場面もあり、一長一短といったところです。 サウンド面では、MIDI音源に対応しているX68000実機版・EGG版がもっともリッチで、MT-32やCM-64環境を用意できれば、重厚な戦場BGMをフルに堪能できます。 一方、メガドライブ版や現行機版はFM音源やPCMベースのアレンジになっており、同じ楽曲でも雰囲気がやや異なります。「どちらが好みか」は完全に個人差ですが、X68000版のMIDIサウンドは別格という声が多く、音楽重視なら一度は体験してみたいポイントです。 操作性に関しては、キーボード+ジョイパッド(X68000/EGG)か、家庭用コントローラー(メガドライブ/現行機)かの違いがあり、ローラーダッシュの入力しやすさなどが微妙に変わってきます。PC環境であればゲームパッドのボタン配置を細かく調整できるため、自分にとって最も扱いやすい設定を追い込めるのが利点です。
どの環境で遊ぶのがおすすめか
「対応パソコンによる違い」という視点で見ると、プレイヤーの好みや環境に応じて次のような選び方が考えられます。 ・とにかくオリジナルの空気を味わいたい人 → 実機X68000+オリジナル版、あるいはX68000 Z版が最有力候補です。画面・サウンド・操作感のすべてが当時のままに近く、「ロクハチで遊ぶ」という体験そのものを楽しめます。 ・手軽さ優先でPC(Windows)一台で完結させたい人 → プロジェクトEGGのX68000版がバランスの良い選択肢になります。インストールしてしまえばランチャーからすぐ起動でき、実機準拠の内容を比較的簡単に味わえます。 ・家庭用寄りのアレンジや難易度で遊びたい人 → 同じくEGGで配信されているメガドライブ版、あるいはコンソール向け現代移植版が向いています。多少の調整が入っているぶん、X68000版より“とっつきやすい”と感じるプレイヤーもいるでしょう。 ・サウンド重視のゲーム音楽ファン → X68000版+MIDI音源環境(あるいはそれをエミュレーションで再現した環境)がベストです。BGMの迫力と繊細さが一段階上がり、『FZ戦記アクシス』の魅力の大きな部分を占める音楽を存分に堪能できます。 このように、一口に「対応パソコン」といっても、実機ロクハチ・Windows上のEGG・X68000 Z・現行Windows/コンソール版と、いくつかの選択肢が存在し、それぞれに個性と利点があります。自分がどのポイントを重視するか──画面の美しさ、サウンドの豪華さ、手軽さ、あるいは当時の空気感──を考えたうえで環境を選ぶと、『FZ戦記アクシス』という作品をより深く味わうことができるでしょう。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
1990年前後は、『FZ戦記アクシス』が登場したX68000やPC-98を中心に、国産パソコンゲームが一気に成熟した“黄金期”でした。硬派なRPGやシミュレーション、洋ゲー移植、アニメ原作物などが次々に出ており、ハードの性能を限界まで使い切ろうという意欲作が目立ちます。ここでは、同じ頃に発売された代表的なPCゲームを10本取り上げ、発売年や価格とあわせて、その内容をざっくり振り返ってみます。
※「販売価格」は主にPC-98/PC-88版の定価がわかっているものを記載しています(一部は他機種版の価格を参考)。
★夢幻の心臓III
・販売会社:クリスタルソフト
・販売された年:1990年
・販売価格:定価9,700円前後(PC-8801版の定価:9,700円)
・具体的なゲーム内容:
国産RPG黎明期から続く『夢幻の心臓』シリーズの完結編にあたる作品で、クラシカルなウルティマ系RPGの集大成のような内容です。主人公は前作『II』のエンディング直後から物語に再び巻き込まれ、異世界での冒険をやり直すことになります。マップは見下ろし型の2Dフィールドで、街・ダンジョン・フィールドがシームレスにつながり、行動範囲が広がるにつれて世界の仕組みや歴史が解き明かされていきます。
戦闘はターン制で、コマンド入力によるオーソドックスなスタイルですが、自動戦闘や独特の“クラスチェンジ”要素があり、パーティ育成の自由度は高めです。グラフィックはシリーズの中でも格段に描き込みが増え、モンスターのデザインや街の風景もファンタジーらしい雰囲気に統一されています。シビアなバランスと、手探りで世界を歩き回る探索性が魅力で、当時のPCユーザーにとっては、まさに“古き良きRPGの完成形”として語られることが多い一本です。
★ミスティ・ブルー
・販売会社:エニックス
・販売された年:1990年(PC-9801版)
・販売価格:定価9,680円(PC-9801 5インチFD版)
・具体的なゲーム内容:
『ミスティ・ブルー』は、エニックスが手掛けたサスペンス色の強いアドベンチャーゲームです。謎の奇病やオカルト的事件を追う新聞記者が主人公で、現実世界と宗教的・神話的なモチーフが絡み合う重厚なストーリーが展開されます。プレイヤーは会話や調査を通じて情報を集め、徐々に巨大な陰謀と邪教的儀式の正体へと迫っていきます。
ゲームシステムはコマンド選択型で、画面いっぱいに描かれたグラフィックとテキストが最大の売りです。当時としてはかなり高密度なビジュアルとBGMが印象的で、ドラマ性の高い演出や、重いテーマを扱ったストーリーラインが評価されました。事件の真相が徐々に分かっていく構成や、続編を匂わせるエンディングなど、プレイヤーに強い余韻を残すタイプのAVGで、いまもコレクターアイテムとして人気が高い作品です。
★大航海時代
・販売会社:光栄(現コーエーテクモゲームス)
・販売された年:1990年(PC-88版5月、PC-98版7月 など)
・販売価格:PC-88版の価格9,800円(PC-98版もほぼ同水準)
・具体的なゲーム内容:
歴史シミュレーションで知られる光栄が手掛けた海洋冒険SLGで、「大航海時代シリーズ」の第1作です。プレイヤーはヨーロッパの港を拠点とする船乗りとなり、世界各地の港を巡って交易や冒険を行います。航路を自分で開拓しながら、香辛料や金銀財宝を売買して資金を増やし、より大型の船団を編成していくという“商人視点”のゲーム性が特徴です。
戦争一辺倒ではなく、地図の空白を埋めたり、未知の港を発見したりする探検要素が強く、プレイヤーごとに違う航海記録が生まれる「体験型シミュレーション」として人気を獲得しました。風向きや補給、嵐や海賊など、航海を妨げる要素も多く、計画性と運が試されるバランスになっています。後のシリーズ作品へとつながる“海洋交易+RPG的成長要素”の原点として、PCゲーム史の中でも重要な一本です。
★サークII(Xak II)
・販売会社:マイクロキャビン
・販売された年:1990年(PC-9801版は1990年11月2日発売)
・販売価格:定価9,680円(PC-9801 5インチ版)
・具体的なゲーム内容:
アクションRPG『サーク』シリーズの2作目で、前作の世界観とシステムを発展させた王道ファンタジー作品です。プレイヤーは若き剣士ラトクを操作し、広大なフィールドとダンジョンを探索しながら、世界に迫る災厄の謎に挑みます。視点はトップビューで、敵に体当たりして攻撃するスタイルを踏襲しつつも、前作よりアクション性が増し、ボス戦では位置取りや装備の選択が重要になります。
当時としてはキャラクター性の強いストーリーやアニメ調のイベントシーンが好評で、PCユーザーからコンシューマRPGに近い“ドラマ付きアクションRPG”として支持されました。音楽も評価が高く、シリーズ全体を通してサウンドトラックが愛好されているタイトルです。PC-98だけでなくMSX2、FM TOWNS、X68000など多数の機種に移植され、ハードを問わず長く遊ばれた一作でした。
★46億年物語 ―THE進化論―
・販売会社:エニックス
・販売された年:1990年(PC-9801版)
・販売価格:定価10,120円(PC-9801 3.5インチFD版)
・具体的なゲーム内容:
“進化”をテーマにした異色のRPGで、プレイヤーは原始の海に誕生した生命体となり、長い時間をかけてさまざまな環境に適応しながら姿を変えていきます。敵を倒して得たポイントを用いて、体のパーツ(頭・胴・足・尻尾など)を強化・変化させることで、プレイスタイルの異なる生物へと進化させられるのが大きな特徴です。
単なるレベルアップではなく、「どの器官をどう変えるか」で戦い方も移動能力も変わるため、試行錯誤しながら自分だけの“理想の生物”を目指す過程が非常にユニークです。太古の海から陸上、空中へとステージが移り変わる構成や、地球の歴史をモチーフにした世界観も魅力で、教養的な要素とゲーム性が上手く融合したタイトルとして記憶されています。後にスーパーファミコン版も登場し、そちらで知ったプレイヤーも多い名作です。
★ロードス島戦記 福神漬
・販売会社:ハミングバードソフト
・販売された年:1990年前後(PC-9801版など)
・販売価格:定価4,180円(PC-9801 5インチ版)
・具体的なゲーム内容:
人気ファンタジー小説『ロードス島戦記』のゲーム展開の一つで、本編RPGとは異なる“ファンディスク”的位置づけの作品です。原作やRPG版で使われたキャラクターデータや世界観を素材に、パズルやミニゲーム、ショートシナリオなどを詰め込んだバラエティソフトとなっています。
ヘビー級の長編RPGと比べればライトな内容ですが、原作ファンにとってはキャラクターや世界を“おまけ感覚”で楽しめる一作であり、当時のPCゲーム文化における「ファンディスク」という存在を象徴するタイトルでもあります。『FZ戦記アクシス』と同じくX68000/PC-98など複数機種向けに展開され、マニア層のコレクション対象としても人気が高いソフトです。
★ポピュラス(PC-98版)
・販売会社:イマジニア(PC-9801版)
・販売された年:1990年(PC-98版リリース)
・販売価格:定価10,780円(PC-9801 3.5インチ版)
・具体的なゲーム内容:
ピーター・モリニューが手掛けた“神様シミュレーション”の金字塔で、PC-98版は海外PCゲームのローカライズとして登場しました。プレイヤーは神となって自らの信者を導き、ライバルの神が率いる勢力との覇権争いに挑みます。地形を盛り上げたり削ったりして信者が住みやすい土地を整え、人口を増やしつつ奇跡を発動して敵の勢力を妨害するという、当時としては非常に斬新なゲーム性を持っていました。
戦闘はユニット同士の自動戦闘に任せ、プレイヤーはあくまで“環境”と“神の力”を通して間接的に世界に干渉するのがポイントで、プレイするたびに展開が変わる箱庭感覚も魅力です。『FZ戦記アクシス』がハードウェア性能を活かした国産アクションの到達点の一つだとすれば、こちらは海外生まれのシミュレーションが日本のPCユーザーに与えた強いインパクトを象徴する作品と言えるでしょう。
★三國志II
・販売会社:光栄
・販売された年:オリジナルは1989年、1990年前後に各PCへ移植(PC-98版もこの時期)
・販売価格:PC-9801復刻版 定価9,680円(オリジナルも近い価格帯)
・具体的なゲーム内容:
中国三国時代を題材にした歴史シミュレーション『三國志』シリーズの2作目で、武将ごとの個性やイベントを強化したことで人気を確立した作品です。プレイヤーは曹操・劉備・孫権などの群雄から一つを選び、中国統一を目指します。内政・外交・軍事をバランスよく行い、武将に指示を出していくゲーム構造は初代から踏襲しつつも、武将の能力値や忠誠度、登用・離反といった要素がよりドラマチックに表現されています。
後のシリーズと比べるとシステムはシンプルですが、その分テンポが良く、「あと1ターンだけ」とつい遊び続けてしまう中毒性があります。『FZ戦記アクシス』と同じ時期のPCゲーム雑誌をめくると、歴史SLGの代表格として必ず名前が挙がるタイトルで、当時のPCユーザーの多くが“歴史=光栄”というイメージを持つきっかけにもなりました。
★電脳学園III トップをねらえ!
・販売会社:ガイナックス
・販売された年:1990年(PC-98を含む各機種向け)
・販売価格:PC-9801版 定価9,680円(5インチ版/3.5インチ版とも)
・具体的なゲーム内容:
アニメ『トップをねらえ!』をモチーフにしたクイズ+アドベンチャーゲームで、ガイナックスが展開した「電脳学園」シリーズの一作です。ストーリー仕立てのシナリオ進行の中でクイズやミニゲームが挟まれる構成になっており、原作アニメのパロディやサービス満載のイベントが多数収録されています。
ゲームとしては、問題に答えて正解することでストーリーが進行し、特定の条件やスコアによって見られるシーンが変化するなど、リプレイ性を高める仕掛けもありました。アニメファン向けの作品でありながら、クイズゲームとしてのボリュームも十分で、当時のPC-98ユーザーの“アニメ+ゲーム”需要を象徴するようなタイトルです。『FZ戦記アクシス』と同じく、電波新聞社やパソコン誌でしばしば広告・記事が掲載されていたため、パッケージビジュアルだけ覚えているという人も多いでしょう。
★ロードス島戦記 福神漬(再掲扱い)と同時期のRPG群
・販売会社:ハミングバードソフト ほか
・販売された年:1990年前後
・具体的なゲーム内容の位置づけ:
厳密には1本のゲームではありませんが、『ロードス島戦記 福神漬』と同じ頃には、同じロードス島の世界を扱った本格RPG『ロードス島戦記 ~灰色の魔女~』『ロードス島戦記II ~五色の魔竜~』などもPC-98やX68000で展開されていました。これらは原作小説の物語をベースにしたストーリー重視のRPGで、パーティを組んでダンジョンを探索するオーソドックスなスタイルながら、原作ファンを満足させるイベントや世界観の再現度が高く評価されています。
『FZ戦記アクシス』がオリジナルロボットアクションとしてハードなゲームプレイを追求していたのに対し、ロードス島関連作や他のファンタジーRPG群は、物語とキャラクター性を前面に出した作品が多く、同時代のPCゲーム市場は“システム重視”と“ストーリー重視”の両方が共存していたことが分かります。
★まとめ:『FZ戦記アクシス』と1990年前後のPCゲーム
ここまで挙げた作品はいずれも、1990年前後という『FZ戦記アクシス』と同じ時代にPCユーザーを夢中にさせたタイトルばかりです。重厚なRPGや歴史シミュレーション、海外発のシミュレーション、アニメタイアップ作品など、ジャンルは多岐にわたりますが、「パソコンならではの表現」や「ハードの限界に挑戦する意欲」という点では共通しています。
『FZ戦記アクシス』はクォータービュー視点のロボットアクションとしてX68000の性能をフルに活かし、ハードなゲーム性とスタイリッシュな世界観で記憶に残る作品となりました。その周囲には、本稿で紹介したような多彩なPCゲームがひしめき合っており、プレイヤーはシューティングやRPG、SLGを気分に応じて遊び分けることができました。こうした“群像”の中に位置づけることで、『FZ戦記アクシス』という一本のゲームが持つ歴史的な意味合いも、より立体的に見えてくるはずです。
[game-8]![瑞起 FZ戦記アクシス・グラナダ PACK [ZKSW-014-W1]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0344/4562408250327.jpg?_ex=128x128)
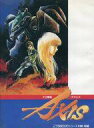

![【中古】 FZ戦記AXIS MD [メガドライブ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ajimura4861/cabinet/a/311-4/b000147ugw.jpg?_ex=128x128)