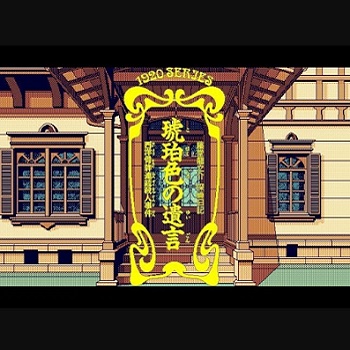【中古】「非常に良い」ウルティマ コンプリート
【発売】:ポニーキャニオン
【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM TOWNS
【発売日】:1988年
【ジャンル】:ロールプレイングゲーム
■ 概要
世界を形づくった伝説的RPGの原点
1980年代初頭、まだロールプレイングゲームという概念が一般的ではなかった時代に、後のRPG文化を決定づける一本が登場した。それがリチャード・ギャリオット(通称ロード・ブリティッシュ)によって生み出された『ウルティマI』である。本作は、のちに長く続くウルティマシリーズの起点であり、同時に『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』をはじめとする日本のRPGにも多大な影響を与えた作品として知られる。 ポニーキャニオンはこの名作を日本語化し、PC-8801・PC-9801・MSX2・X1・FM TOWNSといった当時の主要パソコンに移植して発売。海外で誕生した壮大な冒険世界を、日本のPCユーザーが自宅で味わえるようにしたのである。1980年代のパソコンRPG黎明期を象徴するタイトルであり、その存在感は今なお語り継がれている。
物語の舞台 ―― ファンタジーとSFが交錯する「ソーサリア」
本作の舞台となるのは、魔法と剣、そして文明の名残が混在する幻想世界ソーサリア。かつては平和に満ちたこの地も、今は邪悪な魔法使いモンデインによって支配されつつある。彼は太陽の力を封じた宝玉を奪い、その無限の力をもって怪物たちを生み出し、世界を恐怖で覆い尽くしていた。しかもモンデインは千年前の過去へと逃れ、時間すらも支配下に置くことで永遠の王国を築こうとしていた。 プレイヤーはロード・ブリティッシュによって異世界から召喚された勇者となり、この破滅の連鎖を断ち切るために旅立つ。だがこの旅は単なるファンタジー冒険に留まらない。ゲームを進めるにつれ、馬に乗って大地を駆け抜け、海を越え、ついには宇宙船を操縦して銀河へと飛び立つことになる。剣と魔法、そしてSF的テクノロジーがひとつの物語世界で融合している――それこそが『ウルティマI』最大の特徴だ。
キャラクターメイキングの自由度
冒険の始まりにおいて、プレイヤーは自らの分身となるキャラクターを作り上げる。種族は人間・エルフ・ドワーフ・ホビットの4種類、職業もファイター・ウィザード・シーフ・クレリックから選択可能。種族や職業によって初期能力が異なり、筋力や知性、体力などのパラメータを自由に振り分けることができる。 この仕組みによって、プレイヤーごとに異なる冒険スタイルが生まれる。正面から敵をなぎ倒す戦士タイプ、魔法で戦局を操る賢者、盗みや潜入で立ち回る盗賊など、選んだプレイスタイルがそのまま物語の味わいを変える。のちの多くのRPGが取り入れる「ロールプレイ」の概念を、すでにこの時点で完成させていたのだ。
三つの世界 ―― 地上・地下・宇宙の構成
『ウルティマI』の冒険は三層構造で展開される。まずは地上のフィールド。広大な平原、うねる山脈、湖や大海原が連なるマップを自由に移動し、城や町、洞窟を訪ねていく。トップビューで描かれたこのフィールドでは、モンスターの姿が遠くから見えるのが特徴で、敵との遭遇もプレイヤーの判断で回避できる。 次に、ダンジョン。ここでは3D視点が採用されており、通路の奥へと進む臨場感が味わえる。ウィザードリィのような一人称視点で、モンスターの姿が近づいてくるスリルがある。 そして第三の舞台が宇宙。宇宙船に乗り込み、星間を航行し、敵対するエイリアン艦隊との戦闘を繰り広げる。この「宇宙戦」では画面が一人称の3Dシューティング風に切り替わり、まったく異なるジャンルのゲームを体験しているかのような感覚を与える。これほど多層的な世界設計を1980年代初頭に実現していた点は驚異的であり、後のゲームデザインにも多大な影響を及ぼした。
ゲーム進行と目的
プレイヤーは各地の城を訪ね、王から与えられる依頼をこなしながら成長していく。クエストにはモンスター討伐や宝の探索などがあり、それを果たすごとに報酬が得られる。依頼の達成を通じてプレイヤーは少しずつ力をつけ、最終的にはモンデインの時空支配を打ち破る力を手に入れることが目標となる。 レベルを上げるには経験値を稼ぐよりも、戦利品や資金を集めてHPを購入するなど、独特のシステムが存在する。つまり、努力と資金運用が生存を左右する世界なのだ。また食糧(フード)の概念もあり、冒険中に食料が尽きると即座に命を落とす。このサバイバル感がプレイヤーに緊張感と没入感を与えた。
独特の経済と倫理観
『ウルティマI』には当時のRPGでは珍しく、「盗む」というコマンドが存在する。装備やアイテムを購入する金が足りなければ、店から盗みを働くこともできるのだ。ただし失敗すれば衛兵に追われ、命を落とす危険もある。このような自由度の高い行動システムは、プレイヤーに「善か悪か」の選択を迫るものであり、後のシリーズで展開される「徳のシステム」へとつながる布石でもあった。 プレイヤーの行動次第で世界が変化するという思想は、当時としては極めて先鋭的だった。
技術面 ―― パソコン移植の特徴
ポニーキャニオン版『ウルティマI』は、各機種の性能を最大限に活かして移植された。当時のPC-8801版では8色グラフィックによるシンプルながらも鮮やかな色彩が印象的で、PC-9801ではより高解像度で細かな地形が描かれた。MSX2版ではV9938チップによる滑らかなスクロールと、FM音源による重厚なサウンドが加わり、X1版はシャープ独自の発色特性で他機種とは異なるコントラストを楽しめた。 さらにFM TOWNS版では、当時としては珍しいCD-ROMによるBGMとアニメーション演出が導入され、ウルティマの壮大な世界観をよりドラマチックに演出した。 このように、同じ作品でありながらハードによってまったく異なる体験が味わえた点は、80年代パソコンゲーム文化の醍醐味のひとつであった。
シリーズへの影響と歴史的意義
『ウルティマI』は、後のウルティマシリーズすべての基礎を築いた。広大なオープンワールド、キャラクター育成、モラルと選択、そして「世界を冒険する喜び」というテーマ。そのすべてがこの第一作にすでに存在していた。 また、日本ではこの作品の流れを受けて『ハイドライド』や『ドラゴンスレイヤー』、そして『ドラゴンクエスト』といった国産RPGが次々に生まれた。特に「王からの依頼を受け、モンスターを倒すことで物語が進む」という構造は、JRPGの原型となったと言っても過言ではない。 ウルティマが提示した「冒険とは世界を変える行為である」という思想は、今日のオープンワールドRPGにも息づいている。
まとめ ―― 永遠の冒険の始まり
『ウルティマI』は、単なる古典RPGではない。限られた技術の中で「自由」と「壮大さ」を実現しようとした創造者たちの挑戦の記録である。剣と魔法、そして宇宙という異質な要素を統合しながらも、プレイヤーに「冒険することの意味」を問いかける。その精神こそが、40年以上経った今でも本作を語り継がせる理由だ。 プレイヤーがロード・ブリティッシュの世界に降り立つ瞬間、それは単なるゲームの開始ではなく、「RPGという文化」の始まりでもあったのである。
■■■■ ゲームの魅力とは?
プレイヤーを「本物の冒険者」に変える自由度
『ウルティマI』最大の魅力は、プレイヤー自身が「物語を動かす存在」であるという感覚を強烈に味わえることだ。1980年代のゲームは、ほとんどが固定されたルートを進むタイプだった。だが本作では、どこへ行くのも自由。最初にどの城へ訪れるか、どんな敵を狩るか、どの乗り物を買うか――そのすべてがプレイヤーの意志に委ねられている。 この自由さは、単なる「選択肢が多い」という話ではない。ゲームデザインの根底にあるのは、「プレイヤーが世界の法則を学び、考え、自ら行動することこそが冒険である」という思想だ。だからこそ、街や人々のセリフも最小限に抑えられ、ヒントも断片的。プレイヤーは自分の手で世界の仕組みを読み解いていく。結果として、本作は“疑似的な冒険者体験”を提供する稀有なゲームとなっている。
ファンタジーとSFの融合が生む異色の世界観
『ウルティマI』のもう一つの大きな魅力は、剣と魔法の世界に突如としてテクノロジーが顔を出す大胆な構成だ。 序盤は典型的な中世ファンタジー。プレイヤーは王の命を受けてモンスターを討伐し、宝を集める。だがゲームを進めていくうちに、店ではレーザー兵器や宇宙服が販売され、ついには宇宙船が登場する。この“ジャンルの壁を飛び越える感覚”こそがウルティマの真骨頂であり、当時のプレイヤーに衝撃を与えた。 ファンタジーの中にSFを自然に溶け込ませる構成は、単なる奇抜さではなく「時空を超える冒険」というテーマを体現している。モンデインが千年前へ逃れたこと、プレイヤーが異世界から召喚されたこと、そして宇宙を旅すること――それらすべてが“時間”と“次元”を越える旅のメタファーなのだ。
シンプルながら奥深いターン制バトル
本作の戦闘はターン制で、プレイヤーが行動を選ぶと敵も動く。この仕組みは一見地味だが、実際には高い戦略性を秘めている。敵との距離、装備、使用する魔法、逃走の判断――そのすべてが生死を分ける。特にダンジョン内では、敵が遠方から少しずつ近づいてくるため、早めに攻撃するか、逃げて態勢を整えるかといった判断が必要だ。 また、魔法はアイテム扱いであり、使うと消費される。つまり、戦闘は常にリソース管理とリスク判断の連続となる。プレイヤーがミスをすれば即座にゲームオーバー。だがこの厳しさこそが、1戦1戦の重みを生み、勝利した時の達成感をより強くしている。
「生きている世界」を感じさせる経済と生活
『ウルティマI』では、敵を倒して得た金で装備を整え、食料を補給し、乗り物を購入する。金がなければ盗むこともできる――まさに生きるための手段が多様に用意されている。この経済システムは、単に数値を増やすだけのものではなく、“世界がプレイヤーの行動に反応している”という感覚を与えてくれる。 たとえば、食料が尽きると即座に餓死するシステムは、プレイヤーに「冒険とは生存である」というリアルさを突きつけた。どんなに強力な魔法を持っていても、食糧がなければ終わり。現実と同じく、計画性とリソース管理が重要となる。この生々しさがウルティマの世界を単なる空想ではなく、“存在するもう一つの現実”に感じさせる。
プレイヤーの行動が世界を変える
初代『ウルティマ』では、プレイヤーの行動に対する反応がすでに実装されていた。盗みを働けば衛兵が追ってくるし、城の人々を攻撃すれば戦争状態になる。善悪の概念がまだ明確に数値化されていない時代に、プレイヤーの行動が世界のバランスを変えるという思想は革命的だった。 この「選択と結果」の構造は、シリーズ後半で登場する“徳のシステム”の前段階であり、プレイヤーに“道徳的責任”を考えさせる原点となった。単なる敵の殲滅ではなく、「なぜ戦うのか」「どう生きるのか」を問うRPGの哲学が、すでにこの時点で芽吹いていたのだ。
探求心を刺激する地形と発見の喜び
広大なマップには、城や町、洞窟、湖、山脈、そして未知の島々が散りばめられている。プレイヤーが方向を決めて歩き出せば、そこに確かな“旅”が存在する。マップ上に見える小さな点が、近づくと城だったり町だったりする――この「遠くに何かがある」感覚がプレイヤーの探求心をかき立てた。 さらに乗り物を手に入れることで移動範囲が飛躍的に広がる。馬に乗れば大陸を縦断でき、船を手に入れれば海を渡ることができる。そして宇宙船を得れば、ついに星々の彼方へと旅立てる。この段階的な解放感が、冒険のスケールを実感させる仕掛けになっている。
独自の成長システムが生む“自己強化”の感覚
『ウルティマI』では、経験値による自動的なパラメータ上昇は存在しない。レベルアップしても、強くなるとは限らない。能力を高めるには、イベントや王からの報酬、そして資金を使った訓練など、プレイヤーの“行動”が必要になる。このシステムは、単なる数値成長ではなく“自らの意志で強くなる”という実感を与えた。 この「行動=成長」という設計は、後のRPGにおけるスキル制や行動経験値の原型ともいえる。プレイヤーはただ戦うだけでなく、“どう生きるか”を通して強くなっていく――そこに深いロールプレイの魅力があった。
異世界での孤独と達成感
『ウルティマI』は非常に孤独なゲームでもある。頼れる仲間もいなければ、手取り足取り教えてくれるNPCも少ない。道を誤れば即死、食料を切らせば餓死。だが、だからこそ目的を達成した時の感動は計り知れない。 見知らぬ土地で知恵と勇気だけを頼りに生き抜き、ついにモンデインを打ち倒したとき、プレイヤーは本当に“自分が世界を救った”と感じられる。この没入感は、グラフィックや音楽が洗練された現代のゲームでも再現が難しい領域にある。
後世への影響と普遍的な魅力
『ウルティマI』が提示した冒険の形――自由度、自己決定、世界変化、善悪の選択――は、その後のRPGの骨格を形成した。『ドラゴンクエスト』の「王からの依頼」、『ゼルダの伝説』の「自由な探索」、そして『スカイリム』の「世界に干渉する行動」など、すべてにこの作品のDNAが流れている。 40年以上経った今でも、『ウルティマI』をプレイすると当時の開発者たちの情熱が伝わってくる。粗削りで不完全ではあるが、その未完成さこそが人間味にあふれており、まさに“創世記のRPG”と呼ぶにふさわしい。 本作は、ゲームという枠を越えて「冒険とは何か」「自由とは何か」を問いかける、永遠の古典なのである。
■■■■ ゲームの攻略など
序盤攻略 ―― 生存を最優先せよ
『ウルティマI』の序盤は、プレイヤーにとって最初の大きな試練だ。ゲーム開始直後、何の装備も持たずに広大なフィールドへ放り出されるため、行動を誤ると数分で命を落とす。最初の目的は「近くの城へたどり着くこと」だ。だが城の場所すら教えてもらえないため、方向感覚と運が試される。モンスターの動きを見ながら、安全そうな方向へ慎重に移動するのが基本となる。 城にたどり着いたら、まず王に話しかけて最初の依頼を受ける。この依頼をこなすことで経験を積み、報酬として資金を得ることができる。序盤は「金を集めて装備を整える」ことが何より重要だ。木の剣や皮の鎧では長く生き残れない。鉄製の武具を揃えるまでは、無理に遠出せず、城周辺の敵を倒して資金を蓄えるのが得策だ。
金策と装備 ―― 盗みも一つの戦略
このゲームでは、戦闘で得られる金額は少なく、強力な装備を購入するには膨大な資金が必要となる。だが、序盤から最強装備を手に入れる方法も存在する。それが「盗む」コマンドだ。成功すれば高価なアイテムをタダで入手できるが、失敗すると城の衛兵に追われ、瞬く間に命を落とす。まさにハイリスク・ハイリターンな選択肢だ。 安全に資金を稼ぐなら、王の依頼をこなすのが堅実だ。討伐対象を倒すと報酬が得られ、その額も少しずつ上昇していく。中盤以降は、より高額な装備を整えることで探索範囲が広がる。資金の使い方一つで冒険のテンポが大きく変わるのだ。
中盤攻略 ―― 乗り物を手に入れ、行動範囲を広げる
中盤の鍵は「移動手段の確保」だ。徒歩では移動速度が遅く、敵に囲まれて逃げ場を失うことも多い。まずは馬を購入して、陸地の移動をスムーズにしよう。これだけでも生存率が飛躍的に上がる。 次に目指すのは船。これを入手すれば海を渡って別の大陸に行けるようになる。そこには新たな城や町、ダンジョンが待っている。船の入手は資金面では厳しいが、冒険の自由度を大きく広げる投資となる。 また、船を手に入れた段階で食糧にも余裕ができる。乗り物に乗っている間は食料の消費が減るため、遠征が容易になるのだ。このバランス調整が非常に巧みで、「新たな移動手段を得ること=世界の広がり」を体感できる仕組みになっている。
ダンジョン攻略 ―― 3D空間での慎重な探索
ダンジョンは3D視点で構成されており、通路の奥にモンスターが現れる。マップはシンプルだが、敵の出現位置がランダムであるため油断は禁物。敵が見えなくても、別方向から攻撃を受けることがあるため、こまめに周囲を確認する必要がある。 ダンジョンでは、レベルを上げるよりも資金とHPを稼ぐのが主な目的だ。敵を倒すと一定確率で宝箱を落とし、それを持ち帰ることで大きな利益を得られる。敵の種類は階層ごとに変化し、下に行くほど強力になる。だが序盤は無理せず、浅い階層で戦うのが安全だ。 重要なのは、ダンジョンに入る前に食料を十分に用意し、HPを回復しておくこと。出発前の準備がそのまま生還率に直結する。冒険とは計画であり、勇気だけでは生き残れない――それを学ばせてくれるのがこのゲームの魅力でもある。
宇宙編 ―― 戦闘システムが一変する
中盤以降、宇宙船を手に入れることで、物語は大きく転換する。宇宙空間では操作方法がまったく異なり、トップビューで航行するフェーズと、3D視点で敵と戦うフェーズが存在する。 宇宙戦では、エイリアン艦をレーザーで撃墜するシューティング形式の戦闘が展開される。敵を倒すごとにスコアが上昇し、特定数を撃破することで「スペースエース」の称号が得られる。これを取得することが、エンディングへ進むための条件の一つでもある。 ただし、宇宙船には燃料と耐久値の概念があり、無計画な移動はすぐにエネルギー切れを招く。戦闘よりもまず、燃料管理が重要になる。宇宙空間で漂流する恐怖を味わうことも珍しくないが、これも『ウルティマI』がもたらす“本物の冒険”の一部だ。
終盤攻略 ―― モンデインとの最終決戦へ
終盤の目的は、悪の魔法使いモンデインを倒すこと。だが、彼は過去の世界に存在しており、通常の手段では到達できない。ここで必要になるのが「タイムマシン」だ。プレイヤーは時間を超えて過去へと旅立ち、モンデインの城に乗り込む。 最終戦では、モンデインが持つ“太陽の宝玉”を破壊することが勝利条件となる。直接攻撃だけでは勝てないため、宝玉を先に壊してから本体を倒すという戦略が必要だ。戦闘そのものは単純だが、ここまでにどれだけ準備してきたかが勝敗を決める。 全てを終えた後、ロード・ブリティッシュが勇者を称え、平和なソーサリアが戻る――だが、この結末もまた新たな冒険の始まりを予感させる。シリーズを通じて繰り返される「輪廻的な冒険構造」は、この初代ですでに確立されている。
小技・裏技 ―― 生き残るための知恵
本作には、当時のプレイヤーが発見したさまざまな小技が存在する。例えば、HPを上げたい場合は、ダンジョンで敵を倒した後に地上へ戻ると自動でHPが回復するという仕様を利用することで、回復アイテムを節約できる。また、衛兵を避けながら盗みを繰り返すと、短時間で高性能装備を手に入れられる。ただし、失敗すれば即死級の反撃を受けるため、実行には度胸が必要だ。 他にも、宇宙船戦闘では敵を画面端に誘い込み、一定の角度から連射することで安全に撃破できる“安地テクニック”が知られている。こうした裏技を駆使すれば、難易度の高い戦闘も安定して乗り越えられるだろう。
難易度と達成感
『ウルティマI』は非常に厳しいバランスで設計されている。レベルを上げても能力が直接上昇しないため、常に油断できない緊張感が続く。だが、プレイヤーが工夫を重ね、試行錯誤の末に生き延びたとき、その喜びは他のどんなRPGよりも大きい。 単純な勝利ではなく、「生き抜いた」という実感――それがこのゲームの真の報酬である。だからこそ本作は、現代のプレイヤーが遊んでも古びない。ゲームというより、“生存の物語”として心に残るのだ。
■■■■ 感想や評判
当時のプレイヤーが感じた衝撃
『ウルティマI』が日本のPC市場に登場した1980年代後半、当時のプレイヤーたちは一様に驚きを隠せなかったという。なにしろ、それまで日本で流通していたRPGの多くは、シンプルなダンジョン探索か、一本道のシナリオ型ゲームが主流だった。そこに現れたのが、自由に世界を歩き回り、城を訪ね、敵を倒し、さらには宇宙にまで飛び出すという“次元の違う冒険”だったのだ。 PC-8801版をプレイしたユーザーは、「ゲームの中で本当に旅をしているような感覚だった」「城から出た瞬間、目の前に広がる世界の広さに息をのんだ」と語っている。ゲームがまだ単なる娯楽ではなく“未知の体験”であった時代、ウルティマはまさに「もう一つの現実」を提供する作品として受け入れられた。
難しすぎるけど、やめられない
一方で、本作の難易度は非常に高く、多くのプレイヤーが序盤で命を落とした。地図もヒントも乏しく、誤った方向に進むと即座にモンスターに囲まれる。にもかかわらず、「もう一度挑戦したくなる」魅力があったという。 当時のプレイヤーの一人は雑誌インタビューでこう語っている。 「初めて遊んだときは、城にたどり着く前に3回死んだ。でも、ゲームオーバーになっても“次は行けるかも”と感じる不思議な吸引力があった。今思えば、あれは単なる死にゲーではなく、“世界を理解する学習ゲーム”だったんだ。」 この「失敗が経験になる」構造は、後のRPGデザインの基本となっていく。つまり、ウルティマはプレイヤーを突き放すのではなく、挑戦させ、学ばせ、成長させる作品だったのである。
PC誌やゲームメディアでの評価
当時のパソコン雑誌では、『ウルティマI』は技術的な側面でも高く評価された。1986年に『ログイン』誌上で紹介された際には、「海外RPGの真髄を日本語で体験できる貴重な作品」「冒険のスケールが国産タイトルとは別格」といったレビューが並んだ。 特にPC-9801版ではグラフィックの解像度と描画速度の両立が注目され、「これがパソコンで動くのか」と驚いた読者も多い。さらにFM音源対応によって、城や街のBGMがより荘厳に響く点も好評だった。 当時の日本市場では、英語圏のゲームを日本語化して販売する試みが始まったばかりであり、その第一線を走ったのがポニーキャニオンの『ウルティマ』シリーズだった。この取り組みが、海外RPG文化を日本に根づかせるきっかけとなったのは間違いない。
シリーズファンから見た初代の位置づけ
後年、ウルティマシリーズは「徳のシステム」を導入し、より深い哲学性を持つ作品群へと発展していった。その中で初代『ウルティマI』は、原始的で粗削りながらも“原点の輝き”を持つ特別な存在として評価されている。 シリーズの長年のファンたちは口を揃えて言う。「すべてはここから始まった」。善悪の区別がなく、ただ生き延びるために奮闘する自由な冒険――それは後のシリーズで失われていった“野生のウルティマ”とも呼ばれる。 ファンサイトやコミュニティでは、初代特有の混沌とした世界観を「ギャリオットの最も純粋な創作」として再評価する動きがある。特に、ファンタジーとSFを混在させた設定は、現代のゲームでも再現が難しいほどユニークだ。
開発者・関係者のコメント
リチャード・ギャリオット本人は、後年のインタビューで『ウルティマI』についてこう語っている。 「当時、私は“RPG”という言葉を知らなかった。ただ、自分が作りたい“冒険体験”を形にしたら、結果的にそれがRPGと呼ばれるようになったんだ。」 この言葉が示すように、『ウルティマI』はジャンルを狙って作られたのではなく、純粋な探究心と創造力から生まれた作品である。日本版の移植を担当したスタッフも、「あの時代に、あれほど広大な世界をパソコンで動かす発想は驚異的だった」と振り返っている。 つまり本作は、技術よりも理念――“冒険とは何か”という問いから生まれたタイトルだったのだ。
現代プレイヤーによる再評価
近年、レトロPCエミュレーターの普及により、『ウルティマI』を再び遊ぶファンが増えている。SNSやレビューサイトでは、「思ったより遊びやすい」「シンプルなのに世界が広い」「今のオープンワールドの原型」といった感想が見られる。 特に若い世代のプレイヤーが注目するのは、“自由度の高さ”と“発想の奇抜さ”だ。 「剣と魔法の世界で宇宙に行けるゲームなんて他にない」「この混沌が逆に新しい」と評する声もある。現代の整ったシステムとは違い、不親切さが逆に“発見の喜び”を際立たせるというのだ。 一方で、「説明不足で投げ出してしまった」「UIが分かりづらい」といった意見も見られるが、それすら“当時の雰囲気を味わう要素”として受け止めるユーザーが多いのが印象的だ。
日本文化への影響
『ウルティマI』は、単なる海外ゲームの移植にとどまらず、日本のゲームデザインにも多大な影響を与えた。堀井雄二は『ドラゴンクエスト』開発当時、「海外RPGの自由度を、日本人にも理解しやすい形で表現したかった」と語っているが、その“海外RPG”の代表格がまさに『ウルティマ』だった。 さらに、当時の同人誌やファン活動にも波及。プレイヤーが自作の地図を描き、攻略情報を交換する文化が形成された。これは後に“攻略本”や“ファンブック”といった出版文化へと発展していく。『ウルティマI』は、単に遊ばれたゲームではなく、プレイヤーコミュニティを育てたゲームでもあった。
ノスタルジーとしてのウルティマ
長年のファンにとって、『ウルティマI』は青春の象徴でもある。かつて深夜のCRTディスプレイの前で、コマンドを一つずつ入力しながら冒険した記憶――その原体験が、今も語り草になっている。 「現代のゲームは美しいけど、あの時代の想像力には敵わない」「画面の向こうに、本当に別世界があると思えた」。そんな声が多く寄せられている。 ゲームが未完成だからこそ、プレイヤーの想像力が介入する余地があった。『ウルティマI』は、その余白の中に“自分だけの物語”を見出す楽しさを教えてくれたのだ。
総合評価 ―― RPGの原点にして永遠の指針
現在に至るまで、『ウルティマI』は“RPGの原点”として語られ続けている。技術的な古さや操作の不便さは否定できないが、それ以上に“冒険する喜び”を純粋な形で体現している点が高く評価されている。 多くの評論家が指摘するように、「この作品にはまだ“ゲーム”と“物語”の境界が曖昧だった時代の息吹がある」。 プレイヤーが自ら考え、決断し、失敗し、再び挑む――その体験が今なお新鮮に感じられるのだ。『ウルティマI』は、時間を越えて冒険者たちに語りかける。 「世界は君の選択で変わる」と。
■■■■ 良かったところ
広大な世界を自由に旅できる開放感
『ウルティマI』の最も高く評価された点は、プレイヤーの自由な行動を許容する“開放感”にある。城の外へ一歩出れば、そこには何の制限もない。プレイヤーは自分の意志で方角を決め、町を探し、敵と戦い、未知の大陸を目指す。一本道の物語が常識だった時代に、「どこへ行ってもいい」という設計はまさに革命的だった。 フィールドの広さそのものも圧巻で、初めて海を越えた瞬間、多くのプレイヤーが「本当に別の世界に来た」と感じたという。視覚的にはドットで構成されたシンプルな画面だが、プレイヤーの想像力を刺激する余白があった。限られた技術の中で“心の中に広がる世界”を描き出した点が、今も支持される最大の理由だ。
ファンタジーとSFが同居する独自の世界観
本作の特筆すべき特徴として、剣と魔法の世界に突如として現れる科学文明の要素がある。ドラゴンと戦ったかと思えば、次の瞬間にはレーザーガンを持った敵が現れ、さらに宇宙空間に飛び立つ。これほどジャンルを越えた構成は、後のRPGでもほとんど見られない。 この“異質な融合”こそ、プレイヤーを惹きつけた魅力の一つだった。古代と未来、神話と科学――本来相反する要素を一つの世界で調和させ、しかもそれを自然に感じさせる。 このバランス感覚は、後のウルティマシリーズでも繰り返し取り上げられる“世界の多層性”の原点である。プレイヤーの多くは、「この奇妙な世界が本当に存在するかのように思えた」と語っている。
プレイヤーの行動に反応する“生きた世界”
『ウルティマI』では、プレイヤーの行動が世界の反応を引き起こす。たとえば、店で盗みを働けば衛兵が追ってくるし、人を襲えば町全体が敵に回る。逆に、依頼を果たして王から報酬を得れば、信頼を得て新たなクエストが発生する。 当時としては極めて画期的なシステムであり、「世界が自分の行動に反応している」という実感をプレイヤーに与えた。単に数値を動かすゲームではなく、“世界に存在している感覚”を味わえる作品だったのだ。 この「反応する世界」こそが、後のウルティマシリーズで洗練される「徳システム」の原型でもあり、RPGというジャンルに倫理と選択の概念を導入した最初期の事例として高く評価されている。
緊張感のある生存システム
多くのプレイヤーが好評を口にしたのが、食料システムと体力管理によるリアルな冒険感だ。歩けば食料が減り、尽きれば命を落とす。この単純な仕組みが、旅を一層緊張感あるものにしている。 また、敵との戦闘で体力を削られた際に、街へ戻って回復するか、無理を承知で進むかの判断も常にプレイヤーに委ねられる。まさに“生きるか死ぬか”の選択が連続するゲームデザインであり、そこには「生き延びること自体が目的」という原始的なRPGの精神が宿っている。 プレイヤーの一人はこう語る。「このゲームでは勝つことより、生き残ることのほうが価値がある」。まさに“冒険とはサバイバル”を体現した作品といえるだろう。
3Dダンジョンの先駆的な表現
本作のダンジョンは、一人称視点の3D描写で構築されている。通路の奥行きや曲がり角が視覚的に表現され、敵がじわじわと迫ってくる。これは1980年代初期としては革新的な技術だった。 この演出により、単なるテキスト探索では味わえない「空間を進んでいる感覚」が生まれ、プレイヤーは未知への恐怖と好奇心を同時に感じることになる。ダンジョン内で敵を発見したときのドキリとする緊張感、出口を見つけた瞬間の安堵――それらは現代の3Dゲームにも通じる原体験だ。 技術的制約の中で、ここまで臨場感を出せたこと自体が奇跡的であり、多くのプレイヤーが「当時のパソコンでここまでできるとは」と感嘆した。
成長の仕組みによる達成感
レベルを上げてもすぐに強くならないという本作の仕様は、一見理不尽に思えるが、プレイヤーからは「自分で努力して成長している実感がある」と好評だった。 能力値を上げるにはイベントをこなし、報酬として得るしかない。そのため、単に戦うだけでなく、“どう行動するか”を常に考える必要があった。 結果として、わずかな上昇や新しい装備を手に入れたときの喜びが非常に大きくなる。努力が報われる感覚がダイレクトに伝わるのだ。 これは現代ゲームのような派手なレベルアップ演出とは対照的だが、プレイヤーに「じっくり育てる楽しみ」を与えるものだった。
宇宙戦の斬新さ
中盤以降に突入する宇宙パートも、当時のプレイヤーにとっては忘れられない体験だった。RPGの途中で突如シューティングに変化するという展開は衝撃的で、しかもその完成度も高かった。 「RPGの中で宇宙船を操縦できるなんて夢のようだった」「あのレーザー音とエイリアンの影が迫る感じはいまだに覚えている」と、多くのファンが語る。 単なるミニゲームではなく、物語の核心に関わる要素として宇宙戦が組み込まれている点が秀逸であり、プレイヤーに「世界の広がり」を直感させた。RPGという枠を越えたゲームデザインの柔軟さが絶賛された理由である。
プレイヤーの想像力を刺激する設計
本作は決して派手ではないが、その“余白”がプレイヤーの想像力をかき立てた。モンスターの姿も簡素なグラフィックだが、プレイヤーの頭の中ではそれが壮大な存在として膨らんでいく。音楽も静かで、むしろプレイヤーが自分で“冒険のBGM”を感じ取るような構造になっていた。 この想像の余地こそ、ウルティマの魅力だ。現代の高解像度ゲームにはない「自分で世界を補完する楽しみ」があった。だからこそ、プレイヤーは長年この作品を語り継ぎ、頭の中で“自分のウルティマ”を持ち続けている。
日本版移植の完成度の高さ
ポニーキャニオンによる日本語移植版は、翻訳の丁寧さと操作性の調整で高く評価された。英語版特有の難解なコマンドを整理し、メニュー方式に近い形で再構築することで、日本のプレイヤーにも馴染みやすくなっていた。 特にFM TOWNS版では、音声とBGMが強化され、壮大な雰囲気を再現。マウス操作やCD-ROMの演出も当時としては革新的だった。 こうしたローカライズ努力があったからこそ、海外RPGという新しい文化が日本に根づいたとも言える。プレイヤーからは「ポニーキャニオン版でRPGの面白さを知った」という声が多数寄せられていた。
プレイヤーを“冒険者”にするゲーム
『ウルティマI』が他の作品と決定的に違うのは、プレイヤーを“キャラクター”ではなく“冒険者そのもの”にしてしまう点だ。 画面の中で起こることすべてが、自分の選択によって変化する。誰も助けてくれない世界で、自分の知恵と勇気だけを頼りに進む――その体験が、まるで現実の冒険をしているかのような感覚を与える。 多くのファンが「このゲームが人生で最初の“本当の冒険”だった」と語るのも、そのためだ。 『ウルティマI』は、単なるRPGではなく、“冒険という概念”をプレイヤーに教えた作品だった。
■■■■ 悪かったところ
序盤の理不尽な難易度バランス
多くのプレイヤーがまず挙げる不満点は、序盤のあまりにも過酷な難易度だ。ゲームが始まると、いきなり何の説明もなく広大な荒野に放り出される。最初の目的地がどこかも示されず、数歩歩くだけで敵に遭遇し、あっけなく倒されてしまうことも珍しくない。 「スタート地点から城までたどり着けない」「初回プレイで何をすればいいか全く分からない」といった声は、当時から非常に多かった。マニュアルを熟読しても答えが載っていないこともあり、手探りで理解するしかない。 これは、プレイヤーに「自分で世界を探索し、学ぶ喜び」を与えるための設計意図だったが、現代的な視点で見ると、導線の欠如として捉えられてしまう。初心者にとってはあまりにも冷たい導入だったのだ。
情報不足と不親切な設計
『ウルティマI』は、世界の説明が極端に少ない。王の依頼も「◯◯を倒せ」や「◯◯を探せ」といった簡潔な命令であり、その対象がどこにいるのか、どうやって辿り着くのかはプレイヤー自身が見つけるしかない。 マップには目印が少なく、どこに何があるのか覚えないと迷子になりやすい。町の住民もほとんど有用な情報を教えてくれず、同じ台詞を繰り返すだけの者も多い。 こうした不親切さは、リアリティを演出する意図もあったが、結果的に多くのプレイヤーを挫折させた。とくに「探索と試行錯誤を楽しむタイプ」でなければ、このゲームを最後まで進めるのは難しかっただろう。
戦闘の単調さとテンポの悪さ
戦闘システムはターン制で、攻撃や防御を繰り返すだけの非常にシンプルなものだった。そのため、長時間プレイしていると同じ展開の繰り返しになりやすく、戦略性に乏しいと感じるプレイヤーも多かった。 特に魔法の種類が少なく、強力な呪文も「消費アイテム扱い」なため、戦闘が単調になりがちだった。 敵AIも単純で、近づいて攻撃するか遠距離攻撃を行うかの二択しかなく、駆け引きの深さを求めるプレイヤーには物足りない内容だった。 また、戦闘アニメーションが存在しないため、視覚的な盛り上がりも乏しい。現代のRPGと比べると、どうしても「作業感」を覚えてしまう部分があった。
育成システムのわかりにくさ
レベルを上げても能力値が直接上昇しないという仕様は、当時から賛否が分かれた。多くのプレイヤーが「レベルアップしても強くならないのはおかしい」と感じたという。 実際には内部的な成長パラメータが存在し、戦闘を重ねることで少しずつ強くなっていく仕組みがあったが、ゲーム内でその説明が一切ない。結果として、「努力が報われない」と誤解されるケースが多かった。 また、パラメータを上げるイベントが限られているため、取り逃すと永久に能力が伸びないという理不尽さもあった。これはプレイヤーの自由度を高める一方で、バランスを崩す要因にもなっていた。
バグや挙動の不安定さ
当時のパソコンゲームとしては珍しくなかったが、『ウルティマI』の移植版にはいくつかのバグや不安定な挙動が報告されている。特にMSX2版では、長時間プレイするとデータが破損することがあり、セーブデータが読み込めなくなる事例もあった。 また、船や宇宙船の操作中に特定の入力をすると、画面がフリーズすることもある。これらの不具合は後の再販版で一部修正されたが、初期ロットでは致命的なバグとして知られていた。 当時のユーザーは「宇宙船で星を渡ろうとしたら宇宙の果てでフリーズした」と笑い話にしていたが、実際にはかなりのストレス要因であったのも事実だ。
テンポを損なう資金稼ぎ要素
資金を貯めるのに時間がかかりすぎる点も、プレイヤーの不満の的だった。強力な装備を手に入れるためには、何十体ものモンスターを倒さなければならず、その繰り返し作業が単調で退屈になりやすい。 さらに、敵のドロップ金額にランダム性があるため、運が悪いと何時間も同じ敵を倒し続けても目的の金額に届かないこともあった。 これにより、「冒険」というより「金稼ぎシミュレーション」と化してしまうこともあり、せっかくの自由度を活かしきれていないという声も多かった。 盗みコマンドによるショートカットも存在するが、失敗時のリスクが大きすぎるため、初心者には使いにくい選択肢となっていた。
プレイヤーへの説明不足と目的の曖昧さ
本作のメインストーリーである「モンデイン討伐」に至るまでの流れは、実はかなり分かりづらい。どのように時間を超えて過去へ行けるのか、どこでタイムマシンを入手できるのかなど、重要な要素がゲーム中で明確に示されていない。 そのため、多くのプレイヤーは雑誌や攻略記事を読んでようやく理解した。自力で全貌を把握するのはほぼ不可能に近い。 「何をすればいいのか分からないまま世界を彷徨う時間が長すぎる」という声は当時から多く、導線設計の粗さは批判の的だった。 とはいえ、逆に言えばその「不親切さ」が冒険のリアリティを高めていたともいえるが、万人受けしないことも確かだった。
音楽と演出の地味さ
『ウルティマI』は、雰囲気づくりのための音楽や演出がほとんど存在しない。街に入っても静かで、戦闘中も効果音がわずかに鳴る程度。プレイヤーの想像力を刺激する余白とも取れるが、「盛り上がりに欠ける」「寂しい」と感じた人も多かった。 FM音源対応のFM TOWNS版では多少改善されたものの、他機種版では基本的に静寂の中でのプレイが続く。 この「無音の世界」はウルティマ独自の美学でもあるが、初めて遊ぶ人にとっては物足りなさを感じさせたのも事実だ。現代の感覚でプレイすると、演出の淡白さが顕著に映る。
操作性の古さとテンポの悪化
キーボード操作中心のUIは、今の感覚ではかなり扱いづらい。コマンド入力が直感的ではなく、何をするにもキーを探して押す必要がある。 特に日本語版ではメニュー化されて多少改善されたとはいえ、依然として煩雑でテンポを損なう部分が多い。移動もターン制のため、1マス進むたびに敵や環境が動く仕様に慣れるまで時間がかかる。 「一歩進むごとに確認が必要」「入力ミスで命を落とす」など、操作の不自由さがストレスになる場面も多かった。
プレイヤー層を選ぶ硬派な作り
『ウルティマI』は決して万人向けではなかった。プレイヤーに理解力と忍耐を要求し、失敗を繰り返すことを前提としている。軽快な物語体験を求める人には敷居が高く、「何をしていいか分からないうちに終わる」という感想も少なくなかった。 その結果、熱狂的なファンを生み出す一方で、合わない人には全く響かないという極端な評価を受ける作品になった。 だが、この“硬派さ”こそがウルティマの魂でもある。挑戦的であるがゆえに、一部のプレイヤーには強烈な印象を残したのだ。
まとめ ―― 不完全ゆえの魅力と課題
こうした欠点の多くは、当時の技術的制約や設計思想の未熟さに由来している。しかし、その不完全さこそが『ウルティマI』の個性でもある。 確かに、理不尽で、説明不足で、不便なゲームではある。だが、だからこそプレイヤーは試行錯誤し、想像し、工夫する。 完璧なシステムの中で遊ぶよりも、自分で掴み取る楽しさがここにはあった。 つまり『ウルティマI』の“悪かったところ”は、そのまま“挑戦的な精神の証”でもあるのだ。
[game-6]■ 好きなキャラクター
ロード・ブリティッシュ ―― 世界の守護者であり創造主
『ウルティマI』に登場するキャラクターの中で最も印象的なのは、やはりロード・ブリティッシュだろう。彼はソーサリアの統治者としてプレイヤーを呼び寄せ、冒険の道を示す存在である。だが単なる“王”ではなく、この世界の根幹を理解している賢者でもあり、善と秩序の象徴として描かれている。 ロード・ブリティッシュは、実際の開発者リチャード・ギャリオットの alter ego(もう一人の自分)であり、プレイヤーにとっては“世界の創造主”でもある。彼の言葉には常に重みがあり、プレイヤーが絶望的な状況に陥ったときでも、「勇者よ、己の力を信じるのだ」という一言で再び立ち上がらせる不思議な力を持つ。 多くのプレイヤーが彼に敬意と親近感を抱いたのは、単なるNPCではなく“プレイヤーと対話する存在”として描かれていたからだ。『ウルティマI』のロード・ブリティッシュは、シリーズを通して最も“神聖でありながら人間味のある王”として愛されている。
モンデイン ―― 邪悪の象徴にして悲劇の魔術師
一方、プレイヤーが戦う宿敵・モンデインもまた、忘れがたい存在だ。彼は“太陽の宝玉”を手に入れ、不老不死の力を得て世界を支配しようとする大魔法使い。だがその背景には、野心だけではなく、知識への渇望と孤独があったとも解釈できる。 モンデインは典型的な悪役でありながら、その行動原理にはどこか人間的な弱さが見える。世界を支配したいという欲望も、究極的には「恐れ」や「失うことへの不安」から生じている。 プレイヤーの中には、彼を単なる悪として倒すのではなく、“もう一人の自分”として見る人も多かった。 特に、モンデインが過去に逃れ、時を操るという設定は、彼が“時間を超えてもなお恐怖から逃げられなかった男”としての悲哀を感じさせる。 このように、単純な勧善懲悪ではなく、“悪にも理由がある”という人間的なドラマを感じさせる点が、多くのプレイヤーを惹きつけた。
名もなき勇者 ―― プレイヤー自身の象徴
『ウルティマI』の主人公は、名前こそプレイヤーが自由に決められるが、実質的には“プレイヤーそのもの”である。この「自己投影型の主人公」こそ、本作が長く愛される最大の理由のひとつだ。 プレイヤーは地球から召喚され、異世界ソーサリアで試練を乗り越えていく。つまり、物語の主人公が“現実世界の自分”であるという設定が、没入感を何倍にも高めている。 自分がこの世界を救う――その実感は、ゲームの中に閉じたものではなく、プレイヤーの想像力と感情を通して“現実に影響する冒険”として心に残る。 「RPGとは、プレイヤーが役を演じること」だと定義されるが、『ウルティマI』ではそれがまさに体現されている。名もなき勇者は、単なるキャラクターではなく、プレイヤーの意志の結晶なのだ。
酒場の亭主 ―― 無骨な助言者
ソーサリア各地の酒場にいる亭主も、意外と印象深い存在だ。彼はいつも短い言葉で、しかし核心を突く助言をしてくれる。「宇宙の果てに答えがある」「乗り物が道を開く」など、物語のヒントをさりげなく口にする。 無表情なドット絵の中にも、どこか人間味があり、旅の疲れを癒してくれる存在として愛された。プレイヤーによっては「最初に会いに行くのは王ではなく酒場の親父だった」という人も少なくない。 彼の無骨な存在感は、“情報源”であると同時に“冒険者たちの心の拠り所”でもあった。会話内容はわずか数行だが、その一言がプレイヤーの行動方針を決定づけることもある。地味ながら欠かせないキャラクターだ。
商人たち ―― ソーサリアを支える名もなき庶民
武具屋、食料屋、馬屋――彼らは表舞台に立たないが、プレイヤーの冒険を支える重要な存在だ。特に序盤、食糧や装備を整えるために何度も通うことになるため、彼らの存在感は意外に強い。 セリフは短く単調だが、「この世界に生活がある」というリアリティを与えてくれる。買い物のたびに支払う金額の重みが、“生きるために働く庶民の現実”を感じさせるのだ。 中には、プレイヤーが“盗み”に手を染める対象にもなるが、それもまた世界の一部。善と悪の狭間で選択を迫られる瞬間、商人たちは“倫理の象徴”として機能している。
神官と僧侶 ―― 沈黙の守護者
町の神殿にいる神官や僧侶も、印象的な脇役として語られることが多い。彼らは常に穏やかで、時にプレイヤーの行いを戒め、時に癒しを与えてくれる。 「祈りは無駄ではない」「正しき心を忘れるな」という言葉には、後のウルティマシリーズに通じる“徳の思想”が芽生えている。 多くのプレイヤーが、旅の途中で何度も神殿に立ち寄り、彼らの言葉に救われたという。特に長い戦いの後で聞く僧侶の静かな言葉は、単なるゲーム上のメッセージを超えた“魂の安息”として心に残る。
盗賊と海賊 ―― 世界の裏側を生きる者たち
『ウルティマI』の世界は、決して善人だけで構成されていない。街の外には盗賊が徘徊し、海には海賊船が現れる。彼らはプレイヤーにとって脅威である一方で、“もう一つの生き方”を象徴している。 特に盗賊の存在は、プレイヤー自身の行動選択とリンクしている。店で盗みを働くと衛兵が現れるが、それはつまり“自分が盗賊と同じ立場に堕ちる”ことを意味する。 悪人であっても、その行動には生存の理由がある――そう感じさせるのがウルティマのリアリズムだ。敵でありながら、どこか人間味を感じさせる存在として、プレイヤーの記憶に残っている。
宇宙の敵 ―― 異なる次元の恐怖
宇宙に出ると、プレイヤーの前に現れるのがエイリアン艦隊だ。彼らは姿も行動も地上のモンスターとは異なり、まるで別の次元から来た侵略者のように振る舞う。 特に一人称視点で迫ってくる戦闘演出は、当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。 「RPGなのに、敵が本当にこちらに向かってくる感覚」「あの緊張感はいまだに忘れられない」と語る人も多い。 エイリアンたちは無言の敵だが、彼らの存在は“冒険の果てに未知が待つ”というウルティマのテーマを象徴している。ファンタジーの枠を飛び越え、宇宙という新しい神話を提示した存在でもある。
その他の脇役たち ―― 世界を彩る無数の存在
城の兵士、町の住民、道に迷った旅人――彼ら一人ひとりに特別な個性があるわけではないが、ウルティマの世界を支える背景として欠かせない。 ある者は意味深な言葉を残し、ある者はただ通り過ぎるだけ。それでも、彼らの存在があることでソーサリアの世界は“生きている”と感じられる。 この“匿名の群像”こそが、ウルティマの世界観を豊かにしている。プレイヤーが彼らを想像し、物語を補完していくことで、ゲームは完成する。 それは、誰もが自分だけの物語を紡げる自由なRPGであることの証明でもある。
まとめ ―― キャラクターが語らずして語る世界
『ウルティマI』の登場人物たちは、現代のように長い台詞やカットシーンで個性を表現することはない。しかし、短い言葉や存在そのものが、プレイヤーに深い印象を残した。 それは「想像力で補う余白の美学」だ。 ロード・ブリティッシュの威厳、モンデインの悲哀、酒場の親父の渋さ、無名の勇者の孤独――そのどれもが、プレイヤーの心の中で生き続けている。 『ウルティマI』のキャラクターは、単なるドットではなく、“世界そのものの声”として語りかけてくる存在なのだ。
[game-7]●対応パソコンによる違いなど
PC-8801版 ―― 国産RPGファンが初めて触れた“海外の風”
日本において『ウルティマI』を最初に体験したプレイヤーの多くは、NECのPC-8801版を通じてだった。当時のパソコンRPG市場を支えていた定番機種であり、8色グラフィックとFM音源による表現がウルティマの世界を再現するのに最も親しみやすい環境だった。 このバージョンでは、オリジナル版の英語メッセージを丁寧に日本語化し、操作性も若干調整されている。マップの配色や文字の読みやすさなど、限られたスペックながら視認性を重視した設計が特徴的だ。 ファンの間では「初めてRPGを冒険として感じたのはPC-88版だった」と語る人が多く、国産の『ハイドライド』や『ザナドゥ』と同じ文化圏にありながらも、“何か違う異国の香り”を漂わせていた。 ロード・ブリティッシュの城を訪れた時の荘厳なBGMや、ドットで描かれた広大な大地の印象は、当時のユーザーにとって強烈な記憶として残っている。
PC-9801版 ―― 高解像度で蘇ったソーサリア
PC-9801版『ウルティマI』は、当時すでに国内で主流となっていた16ビット環境を活かし、グラフィック解像度が大きく向上していた。 特に地形表現が緻密になり、山脈や森の境界がより自然に描かれている。ウルティマシリーズ特有の“俯瞰マップの広がり”がよりリアルに感じられるようになり、プレイヤーは「世界が一回り大きくなった」と感じたという。 また、PC-9801版ではサウンドボード対応によってBGMが強化され、城やダンジョン、フィールドで異なる音色が流れるようになった。 動作も軽快で、敵の出現やターン処理が速くなり、PC-8801版で感じられた“待ち時間”のストレスが大幅に軽減された。 多くのファンが「完成形に最も近いバージョン」と評価しており、長時間の冒険を快適に進められる安定性を持っていた。
MSX2版 ―― カラフルな表現と滑らかな動き
MSX2版『ウルティマI』は、V9938グラフィックチップによる256色モードの活用が特徴で、当時としては非常にカラフルな世界を実現していた。 フィールドの色彩が豊かになり、特に海や森の表現が鮮やかで、プレイヤーの探索意欲を刺激した。敵キャラクターのドット絵も少しデフォルメされ、PC-8801版よりもポップな印象を与えている。 また、MSX2特有のハードウェアスクロールを活かした滑らかな画面移動も評価が高く、「ウルティマの世界が生きているように感じられた」との声もあった。 ただし、メモリ制約のためにロード時間が長く、ディスクアクセス音が頻繁に鳴る点はプレイヤーから不満が出た部分でもある。 それでも、MSXユーザーにとっては“海外RPGへの入門編”として非常に価値が高く、ウルティマシリーズを通じてパソコンRPGの魅力を知るきっかけとなった人が多かった。
X1版 ―― 鮮やかな発色と硬派な仕上がり
シャープのX1版『ウルティマI』は、他機種と比べても特に発色が鮮烈で、独特のコントラストを持つ画面が印象的だ。 赤や青の発色が強く、ファンタジー世界の異世界感をより強調している。グラフィック描画は他機種に比べてやや遅めだが、その分落ち着いた色調と美しい表示バランスが評価された。 音源はPSGベースながら、独特の軽快なメロディが流れ、特に戦闘時の効果音が印象的で、ユーザーから「X1らしい硬派なウルティマ」と呼ばれていた。 当時のプレイヤーは、「まるで中世のタペストリーを見ているようだ」「音も控えめで、静かに冒険している気分になれる」と語っている。 派手さはないが、独特の雰囲気を持つ名移植として、今もレトロPCファンの間で評価が高い。
FM TOWNS版 ―― CD-ROMで進化した“豪華版ウルティマ”
FM TOWNS版『ウルティマI』は、シリーズの中でも特に完成度の高い豪華バージョンとして知られている。 CD-ROMメディアを採用し、BGMがリアルなオーケストラ調で再生されるほか、イントロや戦闘シーンにはアニメーション演出が追加されている。 プレイヤーは冒険の最初から“映画的な導入”を体験でき、ロード・ブリティッシュの登場シーンには声優によるナレーションも導入されていた。 グラフィックもフルカラー化され、空や海のグラデーションが美しく、当時のPCゲームとしては圧倒的な臨場感を誇った。 特筆すべきは操作系の改善で、マウス操作に対応し、アイテムやメニューを直感的に選べるようになった点だ。これにより初心者でも遊びやすくなり、シリーズ初体験のプレイヤーを取り込むことに成功した。 一方で、オリジナルの荒削りな雰囲気が薄まり、「綺麗すぎて冒険感が薄れた」との声もあったが、それも含めて“新世代ウルティマ”として評価された。
サウンドの違い ―― 機種ごとに異なる響き
サウンド面では、各機種の個性がはっきり表れている。PC-8801版はシンプルで静かな旋律が特徴的で、孤独な冒険の雰囲気を引き立てた。PC-9801版ではFM音源を活かした重厚なBGMが追加され、よりドラマチックな体験を提供した。 MSX2版は明るく軽快な音色で、ファンタジー要素を強調。X1版は音数こそ少ないが、効果音がクリアで、戦闘の臨場感が高い。 FM TOWNS版では、CDオーディオによるフル楽曲が流れ、オープニングや戦闘、エンディングごとに専用のテーマが用意されていた。 どの機種も方向性は異なるが、それぞれが「ウルティマの世界」を独自に表現しており、プレイヤーはハードの違いを超えて同じ物語を体験できた。
操作性・インターフェイスの違い
PC-8801版とX1版では、ほぼ同等のキーボード操作で構成されていた。一方で、PC-9801版以降はメニュー呼び出しのレスポンスが改善され、テンポが向上している。 MSX2版ではゲームパッドを使った操作も可能で、方向キーで移動、ボタンでコマンド選択という家庭用RPGに近い感覚が味わえた。 FM TOWNS版はマウス操作に完全対応し、ポイント&クリックでの移動や会話が可能だったため、ユーザー体験としては最も現代的だった。 このように、操作性の進化はシリーズの敷居を下げる重要な要素となり、日本でのウルティマ人気を広げる要因になった。
まとめ ―― どの機種にも宿る“冒険の魂”
こうして見ていくと、『ウルティマI』はどの機種でも独自の個性を発揮していた。グラフィックの表現力や音楽の質には差があったものの、プレイヤーに“未知の世界を旅する喜び”を与えるという本質は変わらない。 PC-8801版の素朴さ、PC-9801版の完成度、MSX2版の色彩美、X1版の静謐な発色、FM TOWNS版の豪華演出――それぞれが異なる魅力を持ちながら、同じ“冒険の鼓動”を響かせていた。 つまり『ウルティマI』は、どんなハードで遊んでもプレイヤーの想像力を解き放つ“装置”だったのだ。 当時のパソコン文化が多様であったことを象徴する作品として、いまも多くのレトロファンの心に生き続けている。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
★ハイドライド
(T&Eソフト・1984年・価格7,800円) 日本RPG史を語るうえで『ウルティマI』と並び称されるのが『ハイドライド』である。リアルタイムで動くキャラクターを操作し、敵に体当たりして戦うというアクションRPGスタイルは、当時としては非常に斬新だった。 善行・悪行によってエンディングが変化する徳の概念も導入されており、その後のRPGに強い影響を与えた。ウルティマが“異世界の冒険”を提示したのに対し、『ハイドライド』は“日本人が作ったRPG”の原点として評価されている。
★ザナドゥ
(日本ファルコム・1985年・価格8,800円) ファルコムが送り出した大ヒット作『ザナドゥ』は、ウルティマシリーズと同様に広大なフィールド探索とダンジョン攻略を両立させた本格派RPGである。 成長要素やショップシステム、パラメータ管理などは『ウルティマI』の影響を受けており、国産RPGが海外RPGを咀嚼して発展していった好例といえる。 その奥深いゲーム性と膨大なボリュームは“国産RPGの完成形”と呼ばれ、多くのユーザーがこの作品を通してRPGというジャンルの面白さを知った。
★ウィザードリィ
(アスキー/サーテック・1985年日本発売・価格8,800円) 『ウィザードリィ』は、当時のPCユーザーにとって“究極のダンジョン探索ゲーム”であった。3D表示された迷宮を進み、モンスターを倒し、宝を得る――そのシンプルな構造ながらも、奥深い戦略性と緊張感は他の追随を許さなかった。 『ウルティマI』と比較すると、より内省的・戦術的なゲーム体験であり、“心の迷宮”を探索するような感覚が味わえた。 この2作はしばしば“RPGの双璧”と称され、国産RPGデザインの基礎を築いた。
★ブラックオニキス
(BPS・1984年・価格7,800円) 日本初の本格RPGとして名高い『ブラックオニキス』は、ウルティマの影響を強く受けながらも、日本人向けに遊びやすく再構成された作品である。 操作性を簡略化し、ビジュアルを重視するなど、海外RPGの複雑さを排除して初心者にも入りやすくした。 「日本でRPGという言葉を広めた作品」と言われるほどのインパクトがあり、PC-8801を中心に大ヒット。『ウルティマI』と同時代に存在したことで、世界のRPG文化が日本に根付くきっかけとなった。
★ロードランナー
(ハドソン・1984年・価格6,800円) RPGではないが、同時期に人気を博したパズルアクションが『ロードランナー』である。シンプルなルールながら高い戦略性を持ち、知的ゲームとして多くのパソコンユーザーを虜にした。 『ウルティマI』が“想像力で遊ぶ”ゲームなら、『ロードランナー』は“反射神経と思考”の融合を楽しむゲーム。ジャンルは違えど、当時のPC文化を代表する存在である。
★ドラゴンスレイヤー
(日本ファルコム・1984年・価格7,800円) 『ドラゴンスレイヤー』は、“アクションRPG”という新しい潮流を築いた記念碑的作品。『ウルティマI』のようにコマンドを入力して戦うのではなく、リアルタイムで剣を振るい、敵を倒す。 これによりRPGが一気に一般層へと広がり、「動かして戦うRPG」という感覚を日本のプレイヤーに定着させた。 ウルティマの持つ自由度と、ファルコムの持つテンポの良さ――その融合が日本独自のRPG進化の源流となった。
★ザ・キャッスル
(セガ・1983年・価格6,800円) セガが手がけたアクションパズル『ザ・キャッスル』は、王女を救うために広大な城を探索するゲーム。ジャンルこそ違うが、アイテムを駆使して進む探索型の構造は『ウルティマI』にも通じるものがある。 多層構造のマップを自由に行き来できる設計は、後の“メトロイドヴァニア”にも影響を与えたとされている。ウルティマが“外の世界”を描いたのに対し、『ザ・キャッスル』は“閉じた世界”の探検を極めた。
★ポートピア連続殺人事件
(エニックス・1983年・価格8,800円) 堀井雄二が手がけた名作アドベンチャー。『ウルティマI』がファンタジーRPGであるのに対し、本作は現代日本を舞台とした推理ドラマである。 プレイヤーが入力した言葉に反応するコマンド式インターフェイスは、同時期のRPGとも共通しており、“プレイヤーが世界に語りかける”という構造を持っていた。 この作品の成功が、後の『ドラゴンクエスト』誕生へとつながる。そう考えると、『ウルティマI』と『ポートピア』は日本RPGの両輪と言っても過言ではない。
★リグラス
(アスキー・1984年・価格7,800円) 『リグラス』は、宇宙を舞台にした探索型RPGで、SF要素を前面に押し出した点が『ウルティマI』と共通している。 宇宙船を操縦し、惑星間を移動しながら謎を解いていくという内容で、プレイヤーは星々を旅しながら失われた文明の秘密を探る。 ウルティマの“ファンタジーとSFの融合”をさらに推し進めた実験的作品であり、ジャンルを越えたロマンを感じさせた。
★夢幻の心臓II
(クリスタルソフト・1985年・価格8,800円) 国産RPGの中でも『ウルティマI』の影響を最も色濃く受けているのが『夢幻の心臓II』である。広大なフィールド、ターン制の移動、ステータス成長、そして冒険者としての孤独感――そのすべてがウルティマへのオマージュといえる。 特に、前作よりも自由度を高め、プレイヤーが自ら行動目標を見出す設計は“日本版ウルティマ”と呼ばれるにふさわしい。 海外RPGを日本的感性で再構成したこの作品は、後のPC-RPG黄金期を支える礎となった。
時代背景と影響のまとめ
1983~1985年は、RPGという概念が世界的に形を成した黎明期であった。『ウルティマI』が海外で確立した“冒険と自由の形”を、日本のクリエイターたちが独自に解釈し、国産RPGの潮流を生み出していった。 この時期に登場した作品群は、いずれも「プレイヤーが世界を探検する喜び」を共有しており、互いに刺激し合いながら進化していった。 『ウルティマI』はその精神的支柱であり、“ゲームが物語を語る時代”の幕開けを告げた存在だった。 いま振り返れば、これらのゲームは単なるエンタメではなく、“プレイヤーの想像力を解放した文化運動”だったのかもしれない。
[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪
ファミコン ウルティマ 〜恐怖のエクソダス〜 セーブ可(ソフトのみ) FC【中古】
【中古】 ウルティマ2 聖者への道/ファミコン
ファミコン ウルティマ 聖者への道 セーブ可 (ソフトのみ) FC 【中古】
【ゆうメール2個まで200円】SFC スーパーファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ6 偽りの予言者 RPG スーファミ カセット 動作..
【ゆうメール2個まで200円】FC ファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ〜聖者への道ロールプレイングゲーム ファミリーコンピュ..
▲【ゆうメール2個まで200円】GB ゲームボーイソフト ウルティマ 失われたルーン RPG 動作確認済み 本体のみ 【中古】【箱説なし】【代..
FC ファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ 恐怖のエクソダス Ultimaロールプレイングゲーム ファミリーコンピュータカセット ..




 評価 5
評価 5







![【中古】【表紙説明書なし】[FC] Ultima(ウルティマ) 〜恐怖のエクソダス〜 ポニーキャニオン (19871009)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102320.jpg?_ex=128x128)