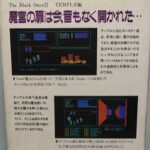キャノンボール2 [ バート・レイノルズ ]




 評価 4.73
評価 4.73【発売】:ポニカ
【対応パソコン】:PC-8801、X1、FM-7
【発売日】:1983年
【ジャンル】:レースゲーム
■ 概要
● 作品の立ち位置――映画の熱量を“走り”に変えたタイアップPCゲーム
『キャノンボール2』は、1983年にポニカが発売した、映画をモチーフにした横断レース系のPCゲームだ。映画側の“何でもアリ”な大陸横断レースの空気を、当時の国産8ビット/16ビット黎明期の表現に落とし込み、「とにかく早く、そして生き残れ」という一点にゲーム性を圧縮しているのが大きな特徴になる。発売時期も映画公開のタイミングに寄せたとされ、パッケージや導入演出の時点で「映画の看板を背負った作品」であることを強く打ち出していたらしい。つまり本作は、レースゲームとしての純粋な腕試しだけでなく、“話題作の世界へ参加する”という当時ならではの高揚感ごと提供するタイプのタイトルだと言える。
● 対応機種と発売時期――1983年末を軸に、資料上は表記ゆれも見える
ユーザーが挙げている通り、代表的にはPC-8801、X1、FM-7系で遊ばれた記録が残っており、特にFM-7側のデータベースでは「1983年12月」の市販タイトルとして整理されている。いっぽう、流通や媒体違い、あるいはデータベースの採録単位によっては1984年扱いで掲載されることもあり、同一タイトルでも“年表の置き場”が前後しやすいタイプだ。こうした表記の揺れは、当時のPCソフトがテープやディスクなど複数媒体で展開され、機種ごとに供給時期がズレやすかった事情とも相性がいい。本作を語るときは「1983年末ごろに登場し、機種や資料によっては翌年表記も見かける」くらいの捉え方が一番実態に近い。
● ゲームの目的――ロス→ニューヨークを最短時間で駆け抜ける“横断レース”の一点突破
本作のゴールは明快で、スタート地点からゴール地点まで、とにかく早く到達することに尽きる。映画のように多彩なチームの駆け引きを再現するというより、プレイヤーは一台の愛車を操り、道中で起きる妨害や事故のリスクをさばきながら距離を稼いでいく。画面は俯瞰視点のオーソドックスなカーアクション寄りで、細かな駆け引きより「危ないものを避け、危なくない範囲で攻める」という反射と判断が中心になる。横断レースという題材はスケールが大きいが、ゲーム側は“長距離を走り切るための事故回避と燃料管理”に焦点を当てており、その一点に映画の無茶さを凝縮しているのが面白い。
● 操作系と手触り――テンキー主体の直感操作で、当時の「キーボード運転」を体現
操作はテンキー中心で、左右の舵と加減速をキーで割り当てて走らせる方式が基本になる。いまの感覚だと単純に見えるが、当時はこの“キーで車を操る”感覚自体がPCゲームらしさの象徴でもあり、慣れてくると一定のリズムで車体を滑らせるように扱えるのが気持ちいいポイントだ。資料では、加速とブレーキをテンキー(または別キー)に割り振る記述があり、キーボードだけで完結する設計を意識しているのが分かる。反面、機種によってキー入力の癖が難度に直結する場合もあり、同じルールでも「やけに厳しい」「意外といける」と体感差が出やすいタイトルでもある。
● 危険の種類――ライバル車の体当たり+上空からの攻撃で、事故が“時間”を削る
道中の脅威は、単にコースアウトしないよう走るだけでは終わらない。ライバル車がぶつけてきたり、上空から落下物が投下されたりと、“走行そのものを止めに来る要素”が混じっている。ここが本作をただのタイムアタックではなく、アクション性の強いレースゲームにしている部分だ。さらに重要なのは、事故のペナルティが「車両を失う」だけでなく、結果として順位や到達ペースにも響く作りになっている点で、単発ミスの痛さが非常に分かりやすい。つまり本作では、爆発=残機減少という古典的な罰に加え、“横断レースの時間が削られる”感覚を強めることで、長距離題材に説得力を持たせている。
● ストック制――5台を使い切ると終幕、無茶の代償がそのまま難易度になる
本作は、いわゆる残機(ストック)を持つタイプで、危険に当たって爆発するとストックを1台消費する。資料上は、ストックを全て失うとゲームオーバーという整理で、横断の長さに対して“ミスの許容量”がはっきり設定されているのが分かる。ここで面白いのは、ストックがあるせいでプレイヤーは一瞬だけ強気になれるのに、横断の終盤に近づくほど「残り台数=精神的余裕」が目に見えて減っていく点だ。序盤は攻めても取り返せるが、終盤は一回の爆発がそのまま詰みに近づく。横断レースを一本の長いドラマとして成立させるために、ストック制が“緊張の設計図”として機能していると言える。
● 燃料と補給――“ぶつかる”のに“優しさ”が要る、独特のリスク管理ギミック
長距離を走る以上、燃料の概念が入ってくるのは自然だが、本作の補給がひと癖ある。補給対象に勢いよく接触すると自滅につながり、適切な加減で寄せていく必要があるため、「補給=安全地帯」ではなく「補給=新しい綱渡り」になる。つまり、燃料は時間経過で減る単なるメーターではなく、プレイヤーに“危険な作業をやり切る勇気と繊細さ”を要求する第二の難所だ。さらにコース上には賞金車のような要素もあり、うまく接触できれば有利さが生まれる可能性が示唆されている。速さを求めるほど補給が増え、補給が増えるほど事故が増えやすい――この循環が、横断レースという題材をゲームの緊張感へ変換するコアになっている。
● 画面・演出・技術的プロフィール――FM-7側の記録から見える“当時の作り”
FM-7系での記録を見ると、表示は640×200の8色モードが挙げられ、音源はPSGとして整理されている。さらに作者名(クレジット相当)として個人名が登録されており、当時のPCゲームらしい“作り手の顔が見える距離感”も感じられる。こうした仕様は、現代の派手な演出とは別方向の魅力を支える要素で、限られた色数・解像度の中で「昼夜や時間帯の雰囲気差」を出して旅の長さを演出する、といった工夫につながっていく。横断という題材は画面上の情報量を要求しがちだが、本作は“それっぽさ”を成立させる優先順位を心得ていて、最低限の視覚変化と危険演出で、走り続ける物語を成立させている。
■■■■ ゲームの魅力とは?
● “大陸横断”をゲームの手触りにしたスケール感――長距離レースの気分を短い操作で味わえる
『キャノンボール2』の面白さは、まず題材の大きさを「プレイヤーの焦り」として体感させるところにある。ロスからニューヨークへ――という設定をそのまま地図やイベントで細かく再現するのではなく、走り続けるほど緊張が増す仕組み(燃料、事故、残り台数)を積み重ねて“横断している気分”を作る。画面の中で起きているのは短い判断の連続なのに、気持ちはずっと先のゴールを意識したままになる。だからプレイ後の印象が、単なるステージ制レースよりも「一気に走り切った」感覚に寄りやすい。これは題材の派手さを、ルール設計で実感へ変換できている証拠だと言える。
● 速さだけでは勝てない“生存型”レース――アクションゲームの緊張が乗ったスピード勝負
当時のレースゲームというと、ライン取りや速度管理の比重が高い作品も多いが、本作はそこへ分かりやすい危険を混ぜてくる。ライバル車の接触や上空からの妨害など、走行そのものを止めに来る要素が入ることで、単純なタイムアタックにならない。速く走りたいのに、危ない瞬間には“ため”が必要で、攻めすぎると爆発して台数が減る。つまり本作は、アクセル全開の爽快感と、事故を避ける神経戦を同じレーンに並べたタイプの作品だ。スピード感を持ちながら、アクションゲームらしい緊張で手が汗ばむ――この二重構造が、当時としては強い引きになっている。
● 燃料補給が“イベント”になる設計――寄せる操作が生む、独特の駆け引き
魅力として語られやすいのが燃料まわりだ。燃料が減るだけなら普通だが、本作では補給の取り方がいかにも危うい。補給対象に勢いよく当たると大事故になり、慎重に“寄せて”成功させる必要があるため、補給行為そのものが一種のミニゲームになる。ここが良いのは、燃料が単なる制限ではなく「危険を伴う選択肢」に変わる点だ。まだ粘れると思って走り続ければ燃料が尽きるし、早めに補給を狙えば事故のリスクが上がる。どちらを選んでも神経を使うので、長距離レースのリアリティというより“横断レースを最後まで成立させるためのドラマ”が生まれる。さらに、賞金を載せた車の扱いなど、欲張り心を刺激する要素もあり、無茶をするほど面白く、無茶をすると痛い目を見るという、ゲームらしい誘惑が用意されている。
● ルールが理解しやすいのに奥が深い――テンキー操作で“自分の運転癖”が出る
操作体系が比較的シンプルな点も、魅力として大きい。左右と加減速をキーに割り当てる方式は、慣れれば直感的で、複雑なコマンドを覚えずに走りへ集中できる。いっぽうで、事故回避や補給の寄せ方には「丁寧に入力する感覚」が必要になるため、同じ操作でも人によって運転の癖が強く出る。雑に入力して強引に進むタイプは序盤の勢いは出るが事故が増えやすく、慎重派は安定するがタイムが伸びにくい。ここに燃料と台数が絡むことで、プレイスタイルそのものが戦略になっていく。単純なのに、結果が単純にならない――このバランスが、繰り返し遊びたくなる理由だ。
● 機種ごとの体感差が“思い出”を濃くする――同じゲームでも印象が変わる面白さ
レトロPCゲームらしい魅力として、同タイトルでも機種や環境によって難度や手触りが変わりやすい点が挙げられる。たとえばFM-7版については、キー入力特性の影響で難しく感じやすいという指摘があり、同じルールでも「簡単だと思った」「異常に厳しい」と評価が割れやすい。だからこそ、友人の家で触れた版、店頭デモで見た版、自宅でやり込んだ版――それぞれの記憶が別々の色で残る。これは現代の統一環境では得にくい、当時のマルチプラットフォーム展開ならではの旨味だ。遊ぶ版が変わると攻略の優先順位(入力の丁寧さ、危険回避の余裕、補給のタイミング)が変わることもあり、“同じゲームを別の競技として楽しめる”感覚すらある。
● タイアップ作品としての価値――映画の勢いを家庭に持ち込み、語れるネタになる
映画由来のゲームは、原作再現の完成度で語られがちだが、本作の強みは“勢いの翻訳”にある。映画の無茶な大会感を、爆発や妨害、横断という大目標に凝縮し、プレイヤー自身の失敗談として語れるようにしている。補給でしくじって自滅した、欲張って賞金に手を出して台数を溶かした、終盤で焦って連続爆発した――こうしたエピソードが出やすい設計は、タイアップ作品としてとても相性がいい。遊んだ人同士で「どこでやられた」「どのくらい進めた」と会話が成立するので、単なる一本のソフト以上に“話題の核”になりやすい。レースゲームでありながら、バラエティ番組的な盛り上がりが出るのは、題材とルールのかみ合わせが良いからだろう。
● まとめとしての魅力――短い理解、長い緊張、そして一発のドラマ
総合すると『キャノンボール2』の魅力は、理解しやすいルールでプレイヤーを走らせ続け、燃料と危険で心拍数を上げ、最後は“生き残った者だけがゴールに届く”ドラマを作るところにある。走っている間は単純な入力でも、頭の中はずっと計算している。補給を今やるか、まだ粘るか。攻めるか、残機を守るか。レトロPCゲームらしい粗さや割り切りがある一方で、その割り切りがむしろ尖りになって、横断レースの醍醐味を濃縮している。だから本作は、映画の名前を借りた一発ネタで終わらず、「怖いのにもう一回」と言わせる中毒性を持った“生存型カーゲーム”として印象に残り続ける。
■■■■ ゲームの攻略など
● まず押さえるべき勝ち筋――「速さ」より先に「完走力」を作る
『キャノンボール2』は大陸横断という題材の通り、短距離のスプリントで上手さが決まるタイプではなく、最後まで走り切る設計が土台になっている。最短到達を目指すのは当然としても、序盤から無理にタイムだけを追うと、事故の連鎖でストックが溶け、燃料の都合で補給回数が増え、さらに危険が増えるという悪循環に入りやすい。攻略の第一歩は、思い切って「最初の数回は記録を捨てる」つもりで、危険の種類と出現の癖、事故が起きた時の立て直し方、補給の感覚を身体に覚え込ませることだ。完走力が上がるほど、自然と“攻められる時間帯”が見えてくるので、最終的にタイムも伸びる。
● 操作の基本――テンキー運転は「長押し」より「細かい刻み」が強い
テンキーで左右・加減速を行うタイプのレースは、入力を荒くすると車体が暴れやすい。攻略で意識したいのは、ハンドル操作を長押しで曲げ続けるのではなく、短い入力を連続させて微調整すること。直線では“真ん中に戻す”操作が遅れるだけで被弾や接触が増えるので、曲げたら戻すをセットで覚えると安定する。加速も同じで、常に全開にするより、危険が近い場面では一段落とすように調整した方が、結果的に事故が減って平均速度が上がる。キー入力の癖が出る作品ほど、「乱暴に押して速い」ではなく「丁寧に押して結果が速い」形に落ち着きやすい。
● コース取りの考え方――画面の先を読む“安全な線”を先に固定する
走行画面に慣れていないうちは、目の前の障害物に反応して左右へ逃げるだけになりがちだが、それだと逃げた先で別の危険に触れやすい。おすすめは、自分の中で「基本はこの位置」という安全ラインを先に決めてしまうこと。たとえば画面中央寄りを基準にして、危険が来たときだけ最小限ずらす、ずらしたらすぐ戻す、という流れを癖にする。これだけで走りが“蛇行”から“回避”に変わり、接触事故や被弾が減って残機も燃料も守りやすくなる。つまり攻略のコツは、派手に避けることではなく、避けた後に素早く元の線へ帰還することだ。
● ライバル車の処理――ぶつけ合いに付き合わず「先に位置で勝つ」
他車が衝突してくる場面では、反射的に左右へ避けるより、「当たりに来る車の軌道」を観察して先回りする発想が有効になる。こちらが大きく逃げるほど相手の接触範囲に入りやすく、さらに別の車体や危険物を呼び込む。したがって、相手が寄ってくる側とは逆方向へ“半歩だけ”ずらし、速度を少し落として接触タイミングをずらす、という処理が安定しやすい。体感としては、相手を避けるのではなく、相手の衝突タイミングを外すイメージだ。慣れてくると、無駄な左右移動が減り、平均速度が勝手に上がっていく。
● 上空からの妨害対策――「見えたら避ける」ではなく「見える前から備える」
上から落ちてくるタイプの危険は、出現してから反応すると間に合わない局面が出やすい。攻略で大事なのは、危険が来そうな区間では、あらかじめ車体の位置と速度を整えておくこと。具体的には、画面の端ギリギリを走らない、蛇行を抑える、直線は直線のまま保つ、といった“自分のブレを消す”準備が効く。自分が安定していれば、落下物の気配が見えた瞬間に最小入力で回避でき、余計な動きをしなくなる。結果として被弾率が下がるだけでなく、避けた後の立て直しも早くなる。
● 残機(ストック)の使い方――「温存」ではなく「配分」で考える
ストック制のゲームは、残機が多いと雑になり、少なくなると縮こまりすぎる、という両極端になりやすい。攻略的には、残機を“保険”ではなく“旅の資源”として扱うのがコツだ。序盤は学習のために多少のミスが出ても良いが、同じ原因で連続して失うのは損なので、爆発したら直後の数分は意識して運転を丁寧にする。中盤以降は、残機が減った分だけリスクを減らす走りへ切り替え、補給と回避の成功率を優先する。終盤は、タイムを縮めたい誘惑が強いが、残機が少ないほど一発が致命傷になるため、攻めるのは“安全ラインを保ったまま速度を上げられる場面”だけに限定する。この切り替えができると、完走率が一気に上がる。
● 燃料管理の基本――減ってから焦るより「補給計画」を先に作る
燃料があるゲームは、無意識に走ると補給がいつもギリギリになり、補給の難しい局面で無理をして事故を招きやすい。そこで有効なのが、燃料計が半分を切ったら“次に見かけた補給対象で狙う”と決めておくこと。補給は成功するほど安心だが、成功させるには落ち着いた速度と姿勢が要るので、余裕のあるうちに済ませるのが正しい。逆に、燃料が少ない状態で補給対象を逃すと心理的に焦り、入力が荒くなって事故率が上がる。燃料は数字ではなくメンタルを守るための指標として扱うと、運転が急に安定してくる。
● 補給の実践テクニック――“そっと触る”を具体化するコツ
補給が苦手な人ほど、「近づく」まではできるが「触れる瞬間」に力が入り、勢いが残ったまま当たって爆発する、というパターンになりやすい。成功率を上げるための手順は、①補給対象の横へ無理に突っ込まず、まずは同じ進行方向で並走できる位置に入る、②速度差を小さくするために一度アクセルを緩め、必要なら短くブレーキを刻む、③車体の角度をなるべく平行に保ち、斜めから突かない、④最後の“寄せ”はハンドル長押しではなく短い入力で少しずつ詰める、の順が安定しやすい。要するに、接触を一回で決めようとせず、並走→速度合わせ→平行→微寄せ、という段階を踏むのがコツだ。慣れてくると、補給は怖いイベントから、計画的に踏める作業へ変わっていく。
● 難易度の捉え方――理不尽に見える部分は「慣れ」で吸収できる
本作は、妨害や衝突の要素があるため、初見では運に左右されるように感じやすい。しかし実際は、運に見える瞬間の多くが「姿勢が不安定なまま危険地帯へ入った」ことから生まれる。つまり、危険の種類を覚え、回避の型を作り、補給を計画的にこなし、無駄な蛇行を減らすほど、“理不尽さ”は薄れていく。難易度は高いが、攻略の方向性がはっきりしているタイプで、上達の手応えが出やすいのが救いだ。特に、爆発の原因を「運が悪い」で片付けず、「接触角度」「速度差」「避けた後の戻し」「焦りによる入力の荒さ」のどれだったかに分解できると、次のプレイで改善点が明確になる。
● 裏技というより“当時流の工夫”――環境を整えると成功率が上がる
派手な隠しコマンドよりも、当時のPCゲームは“遊びやすい環境づくり”が実質的な裏技になることが多い。テンキー入力が命の作品では、キーの押しやすさ、キーリピート設定、キーボードの反応の癖が体感難度に直結する場合がある。もし環境側で調整できるなら、入力が暴れないようにし、誤入力を減らす工夫をするだけで、補給の成功率や回避の精度が上がる。さらに、短時間の集中プレイを繰り返して“補給だけ練習する”“妨害対策だけ試す”といった目的別練習をすると、いきなり通しで走るより上達が速い。裏技がなくても、攻略のための近道は作れるタイプのゲームだ。
● 上級者向け――タイム短縮は「危険を減らして速くなる」発想で詰める
タイムを詰める段階になると、単純にアクセルを踏むより、事故と補給のロスを減らす方が伸びる。具体的には、①回避後の復帰を早くして蛇行時間を減らす、②補給を“焦って狙う回数”を減らし、成功率の高い条件で決める、③危険地帯では速度を落としてでも確実に抜け、次の安全地帯で取り戻す、④接触のリスクが高い場面では順位より生存を優先し、結果として通しの到達が速くなる、という考え方が効く。横断レースの攻略とは、最速を出すことではなく、最速でゴールに到達するための“安定した最短ルート”を作ることだ。ここまで来ると、本作はアクションレースでありながら、意外と戦略ゲームのような顔を見せてくる。
■■■■ 感想や評判
● 当時の受け止められ方――“映画の勢い”を家庭に持ち込める話題性が強かった
『キャノンボール2』の評判を語るとき、まず大きいのは「映画と同名の大陸横断レースを、家のパソコンで遊べる」という一点が持っていた吸引力だ。1983年前後の国産PCゲームは、題材そのものが新鮮さの一部になりやすく、映画の看板があるだけで友人同士の会話のタネになった。実際の内容も、横断という大目標、妨害、爆発、燃料と補給といった分かりやすい要素で構成されていて、初見の数分で「このゲームは何をさせたいのか」が伝わる。ここが、難しいルールや長い説明書が前提になりがちなPCゲームの中では、入り口の広さとして評価されやすいポイントだったと思われる。
● プレイヤーの反応で目立つ長所――遊ぶほど“横断レースのドラマ”が濃くなる
遊んだ人の感想で目につくのは、単なるタイムアタックよりも「事故を避けて生き残る」緊張感が記憶に残りやすい点だ。爆発=ストック消費という分かりやすい罰があるため、上達の指標が明確で、最初はすぐ終わっても「次はもう少し長く走る」「補給を一回は成功させる」といった小目標が立てやすい。燃料補給も、成功すると一気に気持ちが軽くなる反面、失敗するとあっけなく爆発するため、うまくいった時の達成感が強い。短い操作の積み重ねで長距離の旅を作る設計が、当時のプレイヤーの“体験談”として残りやすく、結果として語られ続けるタイプの作品になった。
● 逆に割れやすい評価――難しさの原因が「自分の腕」だけではないと感じる瞬間
一方で、評価が割れやすいのも本作の特徴だ。とくにFM-7版については、操作自体は単純なのに、キー入力の特性が影響して難易度が跳ね上がって感じられる、という指摘がはっきり出ている。そのため「ゲームの仕様が厳しい」というより「環境が厳しい」と受け取られ、機種を変えると印象が変わるタイトルとして語られることが多い。攻略以前に“操作の通りに車が動いてくれない”と感じると、面白さへ到達する前に疲れてしまう人も出る。逆に、入力に慣れた人や別機種版を触れた人は「分かりやすいのに手強くて燃える」と捉えやすく、ここが評判の分岐点になりやすい。
● テープ媒体ならではの声――ロードの長さが“儀式”になり、評価に影響する
当時の空気を含めた感想として、カセットテープ運用の待ち時間は外せない。資料や実測系のプレイ記録では、起動から遊べる状態になるまでかなり時間がかかる例が語られており、ここを「懐かしい儀式」として笑えるか、「テンポを削がれるストレス」として受け取るかで印象が変わる。ロード中に説明書を読み込む、家族に茶を入れてくる、雑談しながら待つ――そういう生活の中の遊び方ができる人にとっては、待ち時間すら当時のPCゲームらしさになるが、ゲームのテンポを重視する人には明確なマイナスに映る。特に“何度も挑戦して上達する”タイプの設計なので、再挑戦までの手間が大きいほど、難しさが余計に刺さる構造になりやすい。
● 良い意味での雑味――妨害と事故が生む“バラエティ感”をどう受け取るか
妨害要素が強いレースゲームは、爽快感と理不尽感が表裏一体になる。本作も例外ではなく、「爆弾や接触があるからこそ映画っぽい」「レースなのに突然終わるのが納得いかない」と感じ方が分かれる。とりわけ、補給や賞金要素など“欲をかくと危険が増える”仕組みは、バラエティ番組的な面白さとしてハマる人がいる一方で、純粋なドライビングを楽しみたい人にはノイズになることもある。ただ、どちらに転ぶにせよ、本作が単調な周回型ではなく、毎回ちょっとした事件が起きるよう設計されているのは確かで、「同じ道を走っているのに、毎回違う顔になる」点を評価する声は根強い。
● コレクター視点の評判――資料性と“当時の一本”としての存在感
近年のレトロPC界隈では、当時の映画タイアップ作品としての資料性、そしてメーカー・タイトルの珍しさから、コレクション対象として語られることも多い。データベース上では価格や発売月などが整理されており、同時代ソフトの中で比較しやすい位置づけになっている。こうした“情報として残っている”こと自体が、後年の評価を底上げしている面もある。ゲームとしての出来だけでなく、時代を象徴するパッケージ、マニュアルの語り口、媒体の運用、機種ごとの差――それらをひっくるめて「1980年代PCゲームの肌触りを思い出せる一本」として扱われやすい。
● 総評――刺さる人には強烈、合わない人には厳しい、それでも語り継がれるタイプ
まとめると、『キャノンボール2』の評判は、派手な題材と分かりやすいルールが入口を広げる一方で、事故と補給の厳しさ、機種・入力特性、媒体都合によるテンポの問題が、好みを強く分ける方向に働いた――という形に落ち着く。だからこそ「大味で楽しい」「とにかく難しい」「当時はこれが熱かった」といった多層の語られ方が残りやすい。レースゲームとしての純粋さより、“横断レースを最後まで成立させるためのドラマ”に魅力を感じる人ほど評価が上がる作品で、レトロPCらしい尖りを味として楽しめるかが、最終的な満足度を決める。
■■■■ 良かったところ
● “横断している感”がちゃんと残る――長距離レースの物語を、少ない要素で成立させた
本作のいちばん大きな長所は、画面の中でやっていること自体はシンプルなのに、「遠くまで来た」「やっと中盤を越えた」「ゴールが見えてきた」という旅の手触りが残りやすい点だ。地名や景色を細かく見せなくても、燃料・残機・妨害という三点があるだけで、プレイヤーは自然に“長い道のり”を意識する。これは横断レースという題材に対して、必要な緊張の骨格をちゃんと掴んでいるということでもある。とくに終盤、残機が減った状態で危険をさばき切ったときの達成感は、周回型レースでは得にくい種類のものだ。「速かった」より「走り切った」が先に来る――ここが、良い意味での独自性になっている。
● 事故と生存のバランスが“語れる体験”を作る――一回のミスがドラマになる
爆発してストックが減る、燃料が尽きそうで焦る、補給に失敗して自滅する。こうした出来事は、ゲームとして見ると厳しい要素なのに、体験としては強烈に記憶へ残る。良かった点として挙げられやすいのは、「成功と失敗が分かりやすく、話のネタになる」ところだ。友人に「補給でやられた」「爆弾に当たって終わった」と言うだけで状況が伝わり、遊んだ人同士の会話がすぐ成立する。つまり本作は、プレイ体験が“エピソード”として切り出しやすい設計になっていて、そこがタイアップ作品の空気とも噛み合っている。
● 補給ギミックが面白い――“危険な作業”として成立していて、成功したときの快感が強い
燃料補給が単なる回復ではなく、慎重に寄せる操作を要求する点は、本作の良さとして語られやすい。普通なら「補給ポイント=安心」になりがちだが、本作は逆に「補給の瞬間が一番怖い」と言えるほど緊張する。だからこそ、成功したときの気持ちよさが大きい。しかも、補給をうまくこなせるようになると、走り全体が安定し、到達距離も伸びていく。上達の実感が“補給の成功率”として目に見えるため、プレイヤーは自然と練習したくなる。ゲーム側が用意した難所が、そのまま成長の指標になるのは、設計としてかなり美味しい。
● ルールの理解が速い――すぐ遊べて、すぐ悔しくなって、すぐ次をやりたくなる
当時のPCゲームには、説明が長くて導入が硬い作品も多かったが、本作は目標が単純で、触ってすぐ理解できる。走る、避ける、爆発したら減る、燃料が減る、補給する。これだけで“横断レースのゲーム”として成立している。だから初見でも「何が悪かったか」が分かりやすく、やられた直後に「次はこうしよう」と改善案が出る。悔しさがそのまま次の挑戦へ繋がりやすい作りで、短時間でも“もう一回”が起きやすい。ゲーム体験の回転が速いのは、良かったところとして素直に挙げられる。
● レトロPCらしい手触り――キー操作の癖まで含めて“当時の運転”になる
テンキー中心の運転は、いま見ると原始的だが、当時のパソコンゲームとしてはむしろ王道の魅力だ。キーの押し方、刻み入力、曲げた後の戻し――そういう操作の癖がそのまま腕前になり、プレイヤーの性格までにじみ出る。良い点としては、パッドやハンドルがなくても「自分で操っている」感覚が強いところだ。慣れてくると車体の挙動が手の中に入ってきて、危険を抜けるたびに“運転が上手くなった”実感が積み上がる。レトロPCのゲームは、ゲーム内容だけでなく、入力の儀式や環境も含めて味わうものだが、本作はその味が濃い。
● リプレイ性が高い――同じ内容でも展開がズレるので、単調になりにくい
妨害や接触が絡む作品は、毎回同じ走りになりにくい。ここは人によって好みが分かれる部分でもあるが、“良かった点”としては、単調なタイムアタックよりも展開に揺らぎが生まれ、同じ区間でも違う緊張が味わえることが挙げられる。補給の成功・失敗、接触の有無、危険回避の精度――それらが噛み合うと、一気に伸びる回が出てくる。その瞬間が強い快感になり、「次はもっと伸ばせるかもしれない」と思わせる。上達の結果が数字だけでなく体感として分かるのは、繰り返し遊ぶ理由になる。
● “時代の空気”を背負った一本――映画タイアップPCゲームとしての存在感
ゲーム単体の完成度だけでなく、映画が話題になっていた時期に“家庭のPCで遊べる形”として現れたことも、良かったところとして語れる。レースの無茶さ、爆発の派手さ、何でもあり感――そういった勢いを、当時の表現で切り取って持ち帰った。後年に振り返ると、これは単なるレースゲームではなく、「80年代のPC文化が、映画の流行をこう受け止めた」という記録にも見える。だから、遊んだ体験自体が思い出と結びつきやすく、レトロとしての味わいが増していく。
● 総まとめ――“荒いのに忘れられない”良さがある
『キャノンボール2』の良かったところをまとめると、横断レースのスケール感を、燃料・残機・妨害という分かりやすい仕組みで体感に変え、補給という難所で緊張と達成感を作り、短い理解で何度も挑戦させる回転の良さを持っている点に集約される。整いすぎた快適さではなく、尖った厳しさが面白さに直結しているタイプで、その荒々しさが“語れるゲーム体験”を作っている。だからこそ、上手くいった一回が強烈に残り、「また挑戦したい」という気持ちが続きやすい。
■■■■ 悪かったところ
● 事故の重さがストレートすぎる――“一発アウト感”が強く、上達前に心が折れやすい
本作は、ぶつかったり被弾したりすると爆発してストックを失う作りが分かりやすい反面、そのペナルティがあまりに直線的で、初心者ほど「何が起きたのか分からないまま台数だけ減る」体験になりやすい。横断レースの緊張を作るために厳しさが必要なのは理解できるが、序盤で連続事故が起きると学習が進む前にゲームオーバーが近づき、やる気が削がれる。せめて“軽い接触”と“致命傷”の段階がもう少し分かれていれば、失敗から立て直す余地が増えたはずだ。結果として、面白さに到達する前に「とにかく怖い」「難しすぎる」という印象だけ残ってしまう人が出やすい。
● 妨害の納得感が揺れやすい――アクション性の魅力が、理不尽さにも化ける
上空からの攻撃や、他車の衝突など、レースにアクション性を足す要素は刺激的だが、タイミングや回避余地が読みにくい場面があると、プレイヤー側は“運でやられた”と感じやすい。特に、回避しようとして蛇行した結果、別の危険に当たるような連鎖が起きると、原因が自分の操作なのか、配置の意地悪さなのかが曖昧になり、納得しにくい。ゲームとしては「落ち着いて走れ」というメッセージなのだが、初見のうちは落ち着くための経験値が足りないので、理不尽感が先に立つ。映画タイアップ的な“無茶さ”を再現したとも言えるが、遊びとしての公平感を重視する人にはマイナスに映りやすい。
● 補給の難しさが“詰み”になりうる――燃料システムが逆に窮屈に感じる瞬間
補給は本作の名物要素だが、裏返すと最大のストレス源にもなりやすい。燃料が減っているのに補給に失敗すると、事故で台数を失うだけでなく、補給に再挑戦する機会まで含めて流れが崩れ、心理的に一気に追い詰められる。しかも、補給は成功させるために速度と姿勢を整える必要があるため、焦っている状態ほど成功率が下がる。つまり燃料が少ないほど、気持ちが焦って操作が荒れ、失敗しやすくなるという負のループが生まれる。ここはゲームとして“上達の壁”になるが、壁が高すぎると窮屈さの方が目立ってしまう。
● 機種差・環境差が評価を割る――同じゲームなのに“別物”に感じる可能性
マルチ機種展開の利点は広い層が遊べることだが、欠点は体感が揃わないことだ。本作はキー入力の癖や反応によって難易度が変わりやすいタイプで、遊ぶ環境によって「思った通りに動かない」「急に厳しく感じる」といった不満が出やすい。ゲーム内容そのものの良し悪しとは別に、ハード側の個性が評価に混ざってしまうため、作品としての“公平な評判”が形成されにくい。これは当時のPCゲーム全般に言えるが、特に繊細な補給や回避を求める作品では問題が目立ちやすい。
● テンポの問題――再挑戦までの手間が、難しさと組み合わさって負担になる
本作は挑戦回数を重ねて上達するタイプなのに、当時の媒体・環境では起動やロードに時間がかかることがある。失敗してすぐ再挑戦したいのに、そこまでの手間が大きいと、学習のサイクルが鈍ってしまう。特に“補給で失敗→すぐやり直して感覚を掴む”という練習がやりにくく、上達を阻害する方向に働く。もちろん、当時はそれが普通だったとはいえ、ゲームデザイン側が要求するリトライ性と、環境側のテンポが噛み合っていない点は、悪かったところとして挙げられやすい。
● 情報の提示が不親切に感じる可能性――危険の予兆や判定が分かりにくい
レトロPCゲームでは、判定や予兆が今ほど親切でないのは当然だが、本作は特に「なぜ爆発したのか」が分かりにくい局面が起きやすい。補給での接触角度、速度差、危険物の当たり判定など、結果だけが派手に出て原因が見えにくいと、改善点を掴む前に疲れる。プレイヤーが上達できるように、危険の直前にもう一段階のサインがある、補給成功時の位置関係が分かりやすい、接触の“軽重”が見た目で伝わる、といった配慮があれば、理不尽さの印象は減ったかもしれない。
● “映画の雰囲気”の再現が薄く感じる人もいる――レースの外側が割り切られている
タイアップ作品として見ると、映画のキャラクター性やチームの個性、イベント性などを期待する人もいる。しかし本作は、基本的に一台の車で走り切ることに焦点を絞っており、世界観の賑やかさはゲーム性の割り切りの中に吸収されている。そのため、映画のファンほど「もっとネタが欲しい」「登場人物らしさが薄い」と感じる可能性がある。逆に、レースゲームとしての筋肉質な設計を評価する人には長所だが、タイアップの期待値が高い人には物足りなく映る点は否めない。
● 総まとめ――尖りが魅力でもあり、欠点でもある
『キャノンボール2』の悪かったところをまとめると、事故の重さと妨害の苛烈さが“理不尽”に転びやすいこと、補給が上達前には詰みの圧力になりやすいこと、そして機種・環境差やテンポの問題が難しさを増幅させることに集約される。面白さの核が「厳しさ」から生まれているぶん、その厳しさを楽しめるところまで到達できない人も出やすい。結果として、刺さる人には忘れられないが、合わない人にはとことん厳しい――そんな評価の割れ方を生みやすい作品になっている。
[game-6]
■ 好きなキャラクター
● “キャラクター”の考え方――本作は人物より「マシンとチーム像」を愛でるタイプ
『キャノンボール2』は、RPGのように台詞や掛け合いで人物像を深掘りする作品ではなく、基本的に走行とサバイバルを主軸に据えたレースゲームだ。そのため、プレイヤーが惹かれる対象は、物語の登場人物というより「参戦しているチームの雰囲気」や「マシンのイメージ」に寄りやすい。映画由来の“何でもあり”の大陸横断レースという舞台設定があるぶん、プレイヤーの想像力が働き、画面上の限られた表現から「この車はこういう勝ち方を狙っているはずだ」と勝手にキャラ付けして楽しめる余地がある。つまり本章でいう“好きなキャラクター”は、厳密には人物名ではなく、走りの個性を感じさせる存在(自車や他車、補給車、さらには妨害を仕掛ける存在)を含めた“ゲーム内の役者”として捉えるのが本作らしい。
● 主役:自車スタリオン・ターボ――プレイヤーの分身として愛着が積み上がる
好きな存在としてまず挙がりやすいのは、やはりプレイヤーが操る自車だ。資料上ではスタリオン・ターボが愛車として扱われ、プレイヤーはこの一台で横断レースを戦い抜く。ここで面白いのは、同じ車なのにプレイヤーの操作が変わるほど“性格”が変わって見える点だ。慎重派のスタリオンは堅実で、補給も丁寧にこなす相棒になるし、攻め派のスタリオンは危険をかいくぐって突っ走る暴れ馬にもなる。爆発してストックを失うと、単なるペナルティ以上に「相棒を落とした」感覚が残りやすく、次の一台に乗り換えた瞬間、気持ちが引き締まる。この“分身の積み重ね”が、キャラクター性の薄いゲームなのに愛着が生まれる理由で、自車そのものが最強の主役として成立している。
● ライバル車たち――顔が見えないからこそ、走り方でキャラが立つ
本作のライバル車は、細かな設定説明がなくても「ぶつけてくる」「道を塞ぐ」「こちらのラインに入ってくる」といった行動で印象が決まる。プレイヤー側から見ると、丁寧に走っている時ほど“理不尽な乱入者”に感じられ、攻めている時ほど“同じ土俵で殴り合う相手”に見える。つまりライバル車は、ただの障害物ではなく、プレイヤーの心理状態を映す鏡のような役割も持つ。好きになり方としては、「あの厄介な車が来たらこう捌く」と自分の攻略メモの中で存在感が強くなり、気づけば“宿敵”として記憶に残る。顔や名前がないのに、プレイヤーの中で勝手にキャラが育つ――これも、レトロレースゲームの美味しい部分だ。
● 補給車(タンクローリー)――助け舟なのに一番怖い、だからこそ忘れられない存在
好き嫌いが分かれるが、“キャラクター”として強烈なのが補給車だ。燃料をくれる存在なのに、接触の仕方を間違えると自滅につながるため、プレイヤーにとっては救世主と死神が同居している。特に燃料が尽きかけている状況では、補給車が見えた瞬間に安心と恐怖が同時に湧き上がる。この感情の揺れが大きいほど、補給車は単なるオブジェクトではなく、物語装置として記憶に焼き付く。成功したときは「助かった!」と叫びたくなり、失敗したときは「なんで今なんだ」と恨み言が出る。プレイヤーの感情をここまで動かす存在は、ある意味で主人公級で、好きなキャラクターとして挙げたくなる理由が十分にある。
● 賞金車の誘惑――“欲”を刺激するトリックスター的存在
資料では賞金を積んだ車の存在が語られ、触れることで何らかの利益が得られる可能性が示唆されている。この手の要素は、横断レースの本筋からすると寄り道だが、ゲームとしては強烈なスパイスになる。なぜなら、プレイヤーの中に「今は危ないけど、取れたら得だ」という欲が芽生え、判断がぶれるからだ。つまり賞金車は、敵でも味方でもない、プレイヤーの心を乱すトリックスターとして機能する。好きなキャラクターとして語るなら、「あいつが現れると走りが崩れる」「でも取れた時は気持ちいい」という二面性が魅力になる。ゲーム内の“誘惑役”として、存在そのものがドラマを生み、記憶に残りやすい。
● 上空の妨害者(ジェット機など)――理不尽の象徴であり、克服の達成感の源
上空から危険を落としてくる存在は、プレイヤーにとっては理不尽さの象徴になりやすい。しかし、だからこそ攻略しがいのある“ボス”としても成立する。最初は「見えないところからやられる」と感じても、慣れてくると「来そうな気配の区間では姿勢を整える」「蛇行しない」「回避後の戻しを早くする」といった対処法が身につき、被弾が減っていく。この変化が気持ちよく、妨害者は“憎まれ役”でありながら、上達の指標を提供する存在にもなる。好きなキャラクターというより、好きな因縁相手、好きな悪役として記憶に残るタイプだ。
● プレイヤー自身が最大のキャラクター――運転の癖がそのまま物語になる
本作の面白いところは、結局のところ最もキャラが立つのがプレイヤー自身だという点にある。慎重すぎて補給を先延ばしにして燃料切れになる人、欲張って賞金車に突っ込み自爆する人、終盤で焦って蛇行し連続事故を起こす人。これらはすべて、操作の癖と判断の癖が生み出す“自分の物語”だ。だから「好きなキャラクター」を語るとき、本作では「自分のスタイル」がそのまま答えになることも多い。プレイヤーの性格が露骨に出るレースゲームは意外と貴重で、ここが本作を思い出深くする要因になっている。
● まとめ――名前がなくても、役割が濃ければキャラは立つ
『キャノンボール2』の“キャラクター”は、人物の顔や台詞で成立しているのではなく、役割と感情の動きで成立している。主役の自車は分身として愛着が積み上がり、ライバル車は行動で宿敵になる。補給車は救世主であり恐怖の象徴、賞金車は誘惑のトリックスター、上空の妨害者は憎まれ役であり攻略の目標になる。こうして見ると、本作はシンプルなレースゲームに見えながら、登場する“役者”がそれぞれ濃い仕事をしていて、だからこそプレイ体験がエピソードとして残る。キャラゲーではないのに「好きな存在」を語れる――それ自体が、本作の味わい深さだ。
[game-7]
●対応パソコンによる違いなど
● まず前提――同じタイトルでも「遊び味」は機種と媒体で変わりやすい世代
『キャノンボール2』は、当時らしく複数機種に向けて展開された“マルチプラットフォーム型”のPCゲームで、FM-7・PC-8801・X1(資料によってはPC-8001も)に向けた版が確認できる。 ここで大事なのは、ルールが同じでも「入力の癖」「表示モード」「音の鳴り方」「媒体(テープ/カセット等)によるテンポ」が違うと、体感難易度や気持ちよさが別物になりやすい点だ。つまり“どの版で遊んだか”が、そのまま作品評価の色になるタイプで、対応機種ごとの差を語る価値が大きい。
● FM-7版――見た目の素直さと引き換えに、キー入力の特性が難易度に直結しやすい
FM-7向けの情報としては、同名映画の公開に合わせた発売で、アメリカ大陸横断のレースゲームであることが明記されている。 また、レトロPC系のプレイレポートでは「操作自体は難解ではないが、FM-7のキー入力特性の影響でかなり難しく感じやすい」旨が語られており、可能ならジョイスティック利用や他機種版を勧めるニュアンスまで出ている。 この“入力のクセ”は、単に操作が重いというより、回避や補給のような繊細な調整を要求される場面で露骨に響く。『キャノンボール2』は、燃料補給を「そっと寄せる」タイプの判定にして緊張感を作っているので、入力が思った通りに収束しない環境ほど、補給=運試しのように感じられてしまう。FM-7版の評価が割れやすいのは、ゲーム性そのもの以上に、この“機種側の手触り”が攻略の土台を揺らすからだと言える。
● PC-8801版――データ上は「コンパクトカセット」表記があり、版管理の揺れが出やすい
メディア芸術データベースでは、PC-8801向けに「コンパクトカセット」表記の個体が登録され、出版日(発売月相当)として1984年2月の情報が載っている。 さらに、別系統のデータベースではPC-8801版がテープで価格3,500円と整理されている例も見える。 ここから読み取れるのは、当時の流通・媒体事情として「カセット/テープ系での展開が中心で、資料によって表記単位(発売月・版・媒体)がズレやすい」ことだ。つまりPC-88版は、遊びやすさ以前に“どの媒体・どの時期の個体を指すか”で話が揺れやすい。とはいえPC-88はキーボードの扱いやすさや周辺機器の選択肢も含めて、遊びの安定度が確保されやすい環境でもあるので、FM-7版で苦戦した人が「他機種版で試すならまずPC-88」と考えるのは自然な流れになる。
● X1版――カセットテープ系として流通し、価格情報が比較的まとまりやすい
X1向けについては、ショップの買取ページなどから「X1/turboのカセットテープソフト」として扱われ、定価3,850円といった情報が見える。 もちろん価格は資料の種類で動くが、少なくとも“X1版=テープ系”として認識されている例がはっきりあるのは大きい。 遊び味の面では、X1は表示やスクロール表現の印象が作品によって差が出やすいプラットフォームでもあるため、同じ『キャノンボール2』でも「画面の見やすさ」「速度感」「入力の追従」が体感として変わる可能性がある。さらに、テープ運用の場合はロードやリトライのテンポがプレイ体験を左右しやすく、短い試行錯誤で上達していく本作とは相性が難しい面も出る。X1版を評価するときは、純粋なゲーム内容だけでなく“テープ運用のテンポ”を含めた体験として語られがちになる。
● 「FM-7/PC-88/X1」で一番差が出るポイント――入力・補給・危険回避の三点セット
このタイトルは、①他車や落下物などの危険を避ける、②燃料を補給する(しかも繊細に寄せる)、③それらを長距離の通しプレイで繰り返す、という性格を持つ。だから機種差として効きやすいのは、グラフィック差よりも「入力が気持ちよく決まるか」「補給の寄せが狙った通りにできるか」「回避後にスッとライン復帰できるか」の方になる。実際、FM-7版はキー入力特性が難度を押し上げる、という言及があるため、ここが最も象徴的な差として語られやすい。 逆に言えば、入力が安定する環境(ジョイスティック利用を含む)へ寄せられるほど、本作の面白さは「理不尽」より「緊張と達成感」に寄っていく。同じソフト名でも評価が割れる理由は、だいたいこの軸に集約される。
● “同タイトルで機種版を渡り歩く”楽しみ――レトロPCならではの二度おいしい遊び方
近年の紹介記事でも、FM-7以外にPC-8801版やX1版(さらにPC-8001版)へ触れる導線が示されており、「版を変えて体験する」こと自体が楽しみ方として成立している。 たとえば、FM-7版で“難しさの正体”を体感したうえでPC-88版に移ると、同じ難所(補給・回避)が「自分の腕」で解ける感覚が強まり、ゲームの評価がガラッと変わることがある。逆に、先に安定版で慣れてからFM-7版へ行くと、“移植差の研究”として面白くなる。レトロPCゲームの醍醐味として、こうした渡り歩きができるのは本作の良い側面だ。
[game-10]●同時期に発売されたゲームなど
★ドアドア
・販売会社:エニックス ・販売された年:1983年(2月) ・販売価格:3,800円 ・具体的なゲーム内容:当時の国産PCで「アーケードっぽさ」を強く打ち出した、テンポ重視のアクション寄りパズル。画面内の敵を“倒す”よりも、仕掛け(ドア)を利用して閉じ込めていく発想が軸で、プレイヤーは短い手数の中で「次にどの敵を誘導し、どのタイミングで閉めるか」を組み立てていく。敵ごとに動きのクセが違うため、同じ面でも“追い込み方”が変化し、反射神経だけでなく観察→仮説→実行の循環が楽しさになるタイプ。ステージ設計も「失敗の学習」が効く作りで、数回やられても“次はこうする”が浮かぶのが良さ。スピード感と分かりやすさで、当時の88ユーザーに「家で遊べる本格アクション」を印象づけた代表格。
★森田のバトルフィールド
・販売会社:エニックス ・販売された年:1983年(2月) ・販売価格:3,800円 ・具体的なゲーム内容:後年のウォーシミュレーションにも通じる“戦場の読み合い”を、当時のPC性能に合わせて筋の通ったルールでまとめた戦略SLG。ユニットの性能差、補給や移動の考え方、地形を踏まえた布陣など、派手さよりも「一手の価値」を積み上げる設計が魅力。敵味方の衝突は数字や確率だけで終わらず、どこを取ってどこを捨てるか、占領の順序をどう最適化するかが勝敗に直結する。アクションゲームと違い、操作速度より“意思決定の質”が問われるので、時間をかけて考えたい層に刺さった一本。忙しないゲームが苦手でも、盤面を眺めて戦況を作る楽しさがある。
★アルフォス
・販売会社:エニックス ・販売された年:1983年(6月) ・販売価格:6,800円 ・具体的なゲーム内容:アーケードの大型人気STGに影響を受けた時代に、“それっぽい”だけで終わらせず、遊びの芯を太く作った縦(または縦基調)のシューティング。敵弾や編隊の圧、地上物の存在感などを、当時の表現でどう成立させるかに工夫があり、単なる模倣ではなく「自宅で遊ぶための設計」に落とし込まれている。プレイヤーは撃つだけでは押し切れず、危険地帯をどの角度で抜けるか、弾の密度が上がる局面で安全地帯をどう作るかが重要になる。見た目の“憧れ”と、攻略の“手応え”が両立していたからこそ、当時の88ゲームの象徴として語られやすい。
★ポートピア連続殺人事件
・販売会社:エニックス ・販売された年:1983年(6月) ・販売価格:3,600円 ・具体的なゲーム内容:事件の全体像を“推理で組み立てる”面白さを、コマンド選択型AVGとして分かりやすく提示した代表作。移動・聞き込み・調査といった基本動作を積み重ねて、情報の欠けている部分を埋めていく流れが主で、プレイヤーは「今の自分に足りない手がかりは何か」を意識するほど進行が安定する。会話や現場の観察から、次の行き先が自然に浮かぶ導線があり、当時の“アドベンチャーゲーム”というジャンル感を広めた一本でもある。アクションのような瞬間操作ではなく、メモを取りながら整理する楽しさが強いので、同時期のリアルタイム系と好対照。
★倉庫番
・販売会社:シンキングラビット ・販売された年:1983年(8月) ・販売価格:3,400円 ・具体的なゲーム内容:見た目はシンプルでも、手順の最適化がそのまま腕前になる“押し出しパズル”の金字塔。荷物(箱)を押して所定位置へ運ぶだけなのに、押した箱は基本的に引けないため、数手先の詰みを避ける読みが必須になる。上達すると、闇雲に動かすのではなく、盤面を“区画”として捉えて流れを作れるようになり、解けた瞬間に「頭の中の地図がつながる」快感が生まれる。短時間で1面に集中できる反面、難所は何日も悩める密度もあって、遊ぶ時間の長短を選ばないのが強み。
★ドリームランド
・販売会社:マイクロキャビン ・販売された年:1983年(8月) ・販売価格:6,500円(PC-8801/SR表記例)/4,800円(別版の価格表記例) ・具体的なゲーム内容:当時の“絵で見せるアドベンチャー”の魅力を前面に出した、夢の世界を巡るファンタジーAVG。プレイヤーは現実の論理だけで突っ切れない場面に出会い、手に入れたアイテムやヒントをつなぎ替えながら“夢らしい筋道”を探すことになる。場面ごとに雰囲気が切り替わり、目的は明快でも手段が一筋縄ではいかない構成が、探索のモチベーションを保つ。グラフィック重視ゆえにテンポが厳しいと感じる人もいるが、逆に“画面を眺めて世界に浸る”遊び方と相性が良かった。
★デゼニランド
・販売会社:ハドソン ・販売された年:1983年(PC-8801向けの掲載例:12月/他機種含む発売月表記例:9月) ・販売価格:6,800円(PC-8801向け定価例)/カセットテープ4,800円・FD6,800円(媒体別表記例) ・具体的なゲーム内容:巨大なテーマパーク風の舞台を歩き回り、アトラクション(=区画)ごとの謎や入手物を積み上げて進めるコマンド型AVG。進行は一本道というより“園内を回って条件を満たす”感触が強く、どこで何を拾ったかが後で効いてくる。パロディ色の強い雰囲気と、当時のAVGらしい英単語入力やコマンド選択のクセが混ざり、笑える場面と理不尽に悩む場面が同居するのが特徴。結果として、友人同士で情報交換しながら解く楽しみが生まれやすく、話題性のある一本になった。
★ウィザード・アンド・ザ・プリンセス
・販売会社:スタークラフト ・販売された年:1983年(5月) ・販売価格:12,300円 ・具体的なゲーム内容:海外発の物語型AVGを日本語化・移植した系譜の中でも、“絵本のようなファンタジー”を前に押し出した作品。プレイヤーは童話的な世界観の中で、目に入るものを調べ、試し、失敗しながら道を切り開く。後年の国産AVGの感覚に比べると不親切な部分もあるが、逆に「自分が主人公として迷い込んだ」感触が濃い。画面の美しさや異世界の空気を味わうことが中心なので、スコアやタイムで競うゲームとは別の価値で人気を集めた。
★ウルトラ四人麻雀
・販売会社:ツクモ ・販売された年:1983年 ・販売価格:5,800円(FD)/3,800円(TAPE) ・具体的なゲーム内容:当時のPC麻雀として“打ち味”を重視した四人打ち。麻雀ゲームは速度と手応えがそのまま評価に直結しやすく、演出よりも手牌処理や進行のキビキビ感が重要になるが、本作はそこを狙っていたタイプ。対局の流れが止まりにくいだけで、「自分の判断で局が動く」感覚が出やすくなる。細かな表現は機種差が出るものの、麻雀という題材自体がリプレイ性の塊なので、長く遊ばれやすいジャンルの強みも追い風になった。
★爆弾男(ボンバーマン)
・販売会社:ハドソン ・販売された年:1983年(7月) ・販売価格:3,200円 ・具体的なゲーム内容:後年のシリーズ像とは手触りが異なる時代の“原型”として、短い判断の連続で局面をこじ開けるアクション。爆弾というギミックは、置いた瞬間に勝ちではなく、爆風の届き方・障害物・自分の逃げ道を同時に考えないと自滅する。つまり「攻撃=制圧」ではなく「攻撃=盤面制御」になっていて、狭い空間ほど読みが濃くなる。ステージを覚えるだけでも上達し、そこから“爆破の角度”や“敵誘導”を覚えると一気に攻略が安定するタイプで、当時の家庭PCでも遊び応えのある一本だった。
★(補足)当時の“同時期”感と『キャノンボール2』との並び
・販売会社:— ・販売された年:— ・販売価格:— ・具体的なゲーム内容:1983年前後のPCゲームは、アクションの“瞬間の面白さ”を追う作品(ドアドア、爆弾男、アルフォス)と、時間をかけて考える作品(森田のバトルフィールド、倉庫番、AVG群)が同じ市場で競い合っていた時期でもある。『キャノンボール2』のような“走り続ける”系は、操作ミスが即リスクになりやすく、テンポと緊張感で勝負する側に近い。一方で、AVGやパズルが伸びた背景には、ハード性能やプレイ環境(家庭での遊び方)に合わせて“思考の面白さ”が磨かれた流れがある。つまり同時期の名作を並べてみると、当時のPCゲームが「何を強みにして家庭へ届いたのか」が立体的に見えてくる。
[game-8]![キャノンボール2 [ バート・レイノルズ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6079/4988135806079.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004982m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アマランス[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005195m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト LUNATIC DAWN[HDD専用/3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004234m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801UX 3.5インチソフト 妖撃隊 -邪神降魔録-[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005386m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト WINGS ウィングス[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006462m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 機甲装神ヴァルカイザー[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004140m.jpg?_ex=128x128)